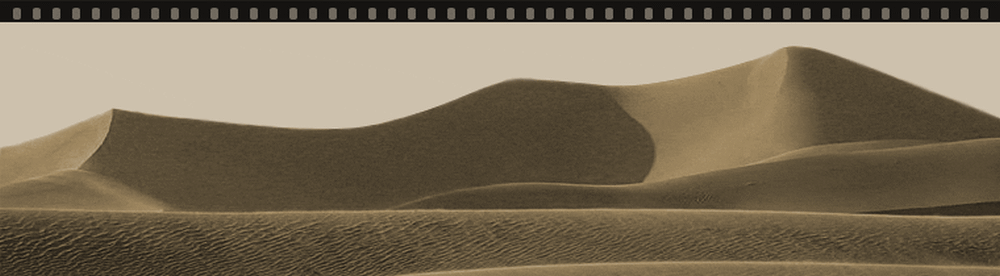2007年03月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-

きょう(3/28)も、上野・鈴本演芸場の六代目柳朝襲名披露興業に夫婦で行ってきました。
前回(3/24)は、最後まで立ち見で疲れたので、きょうは「絶対に座りたい!」と、まず私一人で先に開演2時間前に行ってみましたが、すでにもう20人ほど並んでいました。この並んでいる間は立っているのですから疲れるのは同じなのですが、それでも「この位置なら確実に座れる」と判ると、立ちっぱなしも苦にはなりません。開場30分前にはかなりの列になっていました。↓がその光景です。開場直前に、当日券を買う列と、前売り券を持っている人の列を分けたので、かなり早い順番の入場になり、そのでおかげで最前列に着席できました。開演直前に入場する奥さんには携帯メールで座席に位置を伝えられます。きょうの披露口上は、前回(3/24)並んでいた三遊亭円歌さん、林家正蔵さんはいませんでしたが、替わりに春風亭小朝さんが出ていました。きょうは、高座で不思議な「光景」を3、4回目にしました。いつもは出演者が交代する都度、前座さんが出てきてメクリを替えて、座布団を裏返しにしたら、すぐ舞台の袖に引っ込んで次の出演者が出てきます。しかし、きょうは座布団の前に腰を下ろした前座さんが、客席の奥のほうを見ながら、座布団返しをしないで動きを止めてじっとしているのです。(何だろう?)と体をひねって後方の客席を見たら、何人かの団体客が着席しようと、狭い列の間を移動しているところでした。どうやら、そのお客さんたちが着席するを待っているようでした。開演後に来場したお客さんが着席する場合、高座で噺家さんが演じている最中は避けて、出演者が交代する「間」を利用するのですが、それに時間がかかる場合は、座布団返しの前座さんは、舞台に上がったまま客が着席するのを待っているのです。私は何十回も寄席に来ていますが、きょう、初めてそういうことに気づきました。きょうも立ち見は30人ほど。私の知人のSさん夫婦も立ち見になったらしく、「披露口上」の後、「立っているのが辛くなったから」と私に声をかけて帰られました。確かに、年配者には長時間の立ち見は辛いですね。 春風亭柳朝さんの演目は、前回(3/24)は「明け烏」で、きょうは「井戸の茶碗」でした。すぐ後ろの席が若い女性4人のグループでしたが、よく笑っていました。、寄席はきょうが初めてっだったようで「寄席がこんなに面白いとは思わなかった」とお互いに興奮した口調で話していたのが、耳に入ってきました。「次はいつにしようか」というような相談をしていたようですが、こうやって寄席に若い女性客が増えてきたんですね。
2007.03.28
コメント(0)
-

きょう(3/25)は、三遊亭好二郎・飯能独演会第4回目でした。
好二郎さんの第3回(12/17)の時は、夜間の会場が初めて来る人に目立つように神社の鳥居前の柵に沿って、グラスに入れたロウソクを30本ほど並べて灯してみました。ずらりと並んだロウソクの灯りで連想されたのか、そのとき好二郎さんが話したのは「死神」でした。きょう(3/25)は、あいにくの雨だったので前回のようにはロウソクを並べられませんでした。出し物は「うどん屋」と「崇徳院」の二席。来場者はスタッフも含めて計65人でした。↑会場風景です↓きょうも感じたのですが、好二郎さんは「枕」が上手いと思います。きょうは「西武ライオンズの裏金問題」や「不二家の営業再開」でさりげなくタイミングの良い笑いをとっていました。私の独断かもしれませんが、人気の出る噺家さんと人気の出ない噺家さんの違いの一つに、この「枕」があると思っています。面白い新鮮な「枕」であれば、本来の落語の演目より長くても構わない、とさえ思っています。それには、他の人も使っている「新鮮味の無い話」ではなく、自分独自のオリジナルの「枕」が重要なのですが、好二郎さんの「枕」にはそのオリジナリティが有ります。次回の好二郎飯能独演会・第5回は8月19日(日)18:30からです。
2007.03.25
コメント(0)
-
きょう(3/24)は、上野・鈴本演芸場の六代目柳朝襲名披露興業初日に夫婦で行ってきました。
昼間、地元のイベントに参加していたので自宅を出たのが遅くなり、鈴本に着いたのは開場20分前。すでに入場が始まっていましたが、まだ残っていた行列の最後尾に並びました。ところが無情にも、行列整理の係員に、私の3人前で「ここで満員札止めです」と言われてしまいました。せっかく埼玉県飯能から片道700円と約2時間かけて来たのですから、諦められません。「前売り券を持っているのですが」と言うと、「お立ち見ですがそれで宜しければ」と入場させてもらいました。入り口で、一朝師匠の原稿が掲載されているタウン誌『うえの』を来場者に手渡ししていた一之輔さんに「立ち見で済みません」と挨拶されました。客席は本当にすでに超満員。後方で立っていたお客は50人を超えていたのではないでしょうか。奥さんは通路に座り込みましたが、私はずっと壁に寄りかかっていました。中入りの時に、ロビーでオニギリを食べたときだけ座れましたが、とうとう最後まで3時間半立ち続けでした。真打ち披露興業は、ここ数年では、たい平、喬太郎、扇辰、菊之丞、三三と経験して今回で6回目ですが、「初めて」のことが有りました。いままでの「口上」は、居並んだ師匠方が話すだけで、新真打ち当人はただ列の中央に居て顔を見せているだけでしたが、今回は、なんと「口上の最後」に当人の挨拶があったのです。司会の柳家権太楼師匠が「今回の披露興業から当人にも挨拶させることに改めました」と言っていましたが、私もこの方法のほうが良いと思います。さぁ、次回の3/28(水)は、開場の1時間前には並んでいよう!
2007.03.24
コメント(2)
-
その5・「使用する会場」を決める(上)
地域寄席の「目的」「開催頻度」「公演時間」「出演者の人数」を決めたら、次は、5.「使用する会場」を決める ことです。地域寄席を定着させるためには「会場」はとても重要な要素です。【地域寄席って何?】という項目で2007/01/18付け にも書きましたが、地域寄席の会場には、よく近所の集会場や飲食店、事業所内のスペース、お寺、神社、個人宅などが使われます。市民会館の大ホールや、ホテルの宴会場で開催される落語会もありますが、300人も400人も入場できるような大きな会場は、「地域寄席」には適さないと思います。「会場を決める」ときに、多くの主催者が迷うのは「毎回、同じ会場に定めてしまう」か、それとも「毎回、会場を変えて行うか」ということでしょう。主催者グループの中に「うちのお店を使って欲しい」とか「我が家を会場にして欲しい」と要望する人が多い場合、1ヵ所に決められないこともあります。実は、<有望若手応援寄席>も、スタート当初は、毎回、会場を変えていましたが、その理由は下記のようなものでした。A.市内の飲食店を会場にすれば、そのお店の外にポスターが貼れるし、店内に案内チラシを常備しておけるのでPRに有利だB.その会場の持ち主(オーナーや店長)も、世話人に加わってもらえるので発起人の負担が軽くなる。C.だから、会場として使用する場所は多いほうが得策だしかし、結論から言うと、「毎回、同じ会場」のほうが得策です。それは下記の理由からです。1.会場が毎回違うと、お客さんの中には間違える人も出てくる2.主催者でも勘違いで会場を間違えてしまうこともある3.さらに、出演者まで会場を間違えたら「冷や汗」ものである4.ポスターやチラシに書く「会場」に記載ミスが生じることもある5.場内で使用するモノを毎回移動させなければならない6.会場案内図も会場の数だけ作成しなければならない7.会場毎に大きさが異なると「来場者の予測」がしにくい<有望若手応援寄席>も、会場は全部で5ヵ所使用しましたが、2004年1月の第38回から、1ヵ所に定めました。もし、次に会場を変えることがあるとしたら、いまの所ではお客さんが入りきれなくなったときです。いまの会場は150人くらいまでは大丈夫です。(そんな事態になることを待ち望んでいますが・・・・・)
2007.03.22
コメント(0)
-

きょう(3/18)は、春風亭朝之助さんの真打昇進・六代目柳朝襲名披露宴に夫婦で行ってきました。
落語が好きでCDやカセットで聴いていても、噺家さんとの直接の交流がないと、真打ち披露パーティーに出席できる機会は得られません。若手の噺家さんを応援する地域寄席を主催する楽しみに一つに、この真打昇進披露パーティーへの出席があります。私は、2000年の秋から「有望若手応援寄席飯能」を始めたので、入船亭扇辰さん、古今亭菊之丞さんに次いで3回目の真打ち披露パーティー出席です。(昨年真打ちになった柳家三三さんは披露パーティーの替わりに披露公演だったので)でも私の奥さんにとっては初めて体験。会場は、皇居前の東京會舘。12:00開宴なので11:30頃会場に着きましたが、もう受付は混んでいました。大変な盛況で、出席者は500人だそうです。10人~11人が着席した円卓が、数えたら43くらいありました。経験したことのない方へ、一言で真打ち披露パーティーを説明すると「一般の結婚披露宴と会場のスタイルも式次第も雰囲気もかなり似ている」と思って下さい。来賓祝辞→乾杯→食事(この間に主役は各テーブルに挨拶回り)→余興→最後の挨拶と続きます。ですから、出すお祝儀も、「友人の結婚披露宴」や「友人の子供の結婚披露宴」に出席した時に包む金額と同じで良いのでしょう(たぶん)余興の名物「市馬師匠・俵星玄蕃の熱唱」「喬太郎師匠・裸の腹芸」の写真は「部外秘」なので載せられません。 写真は宴の最後に壇上で五代目柳朝一門の師匠方と並んで挨拶する6代目柳朝師匠。左端の背広姿の人は小朝師匠です。下旬からは鈴本演芸場を皮切りに各寄席での披露興業。私は4つの寄席とも聴きに行く予定です。
2007.03.18
コメント(0)
-
きょう(3/14)は、八王子で柳家小三治師匠を聴いてきました。
きょう(3/14)は、一人で「八王子寄席名人会」に行ってきました。主催者は、八王子市内2ヶ所で若手噺家中心の地域寄席を毎月開催しているSさん(日本文化情報会)です。なぜ「名人会」と名付けたかというと、柳家小三治さんが出演するからです。私は、有望若手応援寄席飯能のチラシを600枚持参して、12:00から行われた「チラシ挟み込み作業」に参加し、その後、会場の入口で「入場券のもぎり」の手伝いをしました。会場は800席の八王子いちょうホール。平日の14時開演ですから来場者は500人前後。そのため会場は「やや寂しいなぁ」と感じは否めませんでした。(かなりの赤字になったのではないかと案じています)会場の規模と入場料の設定は、主催者として一番悩むところです。出演料で赤字が出ないようにするには、できるだけ大きな会場が望ましいのですが、それなりの「集客」を必要とします。「落語は小さい会場で、噺家さんを身近に感じて聴きたい」とお客さんは思いますが、少人数の来場者数で赤字にならないようにするには、入場料を高額に設定しなければなりません。「大会場で低料金」でも、「小会場で高額の入場料」でも、どちらにも「集客が難しい」という困難な課題がつきものなのです。プロの興業主が小三治師匠の落語会を主催すれば、どんな大会場でも「完売」にすることができるのでしょうが、興業能力としては素人の地域寄席には、「赤字にならない集客」がいつも大きな課題なのです。 <今日の演目> 柳家小きち「牛誉め」 柳亭こみち「宮戸川」 柳家小三治「天災」 -中入り- 古今亭菊之丞「酔っぱらい」 柳家小三治「あくび指南」
2007.03.14
コメント(0)
-
学校の体育館ではなく、和室や舞台設備の有る公民館での「落語入門教室」を定着させたい
学校寄席ではないスタイルで、「中高生に生の落語に触れて欲しい」「落語を聴く楽しさを体験して欲しい」と思っている落語フアンは多いと思います。私もその一人なので、先日(3/10)の「中高生のための落語入門教室」を企画したのですが、集客結果は「無惨」でした。しかし、ここでめげてはいられません。諦めずに「次の企画」に着手していきましょう。私は、7年前に有望若手応援寄席飯能を始める時から、「地道に続けていれば、地元の小中高校から学校寄席の要請が来るようになる」ということを期待していました。結果は、おかげで市立中学校と県立高校で1校ずつ声がかかりました。いずれも会場は体育館。両方とも「落語には広すぎる会場」でした。この時、学校寄席といっても、地域の市民会館や公民館のホールや和室でやるならともかく、「広すぎる体育館は落語に向かないな」ということを痛感したのです。「まったく落語に関心の無い生徒に、授業の一環だからと強制的に聴かせるのは、どうかなぁ・・・・とも感じたのです。(もっとも、私が昔落語好き少年だった中2の時、学校の体育館に600人の同学年を集めて無理に聴かせたことがありましたが・・・)小学生や中高生に「生の落語」に触れてもらって喜ばれるのは、多少なりとも、「落語ってなんだろう?」「ちょっと聴いてみよかな」と興味を抱いた生徒だけを集めて落語教室をやったら、面白いのではないか・・・と思ってしまったのが、今回の「公民館での落語入門教室」だったのです。どの地域にも「落語会に相応しい雰囲気と規模の会場」は幾つかあると思います。公民館以外にも、町内会の集会所、神社仏閣、セレモニーホールなどです。飯能市でも、ちょっと離れた町内会の「子供会+敬老会」から要請があった時は、中高生はいませんでしたが、小学生がかなり来ていました。(自分の体験でも判るように、中高生にもなれば、地元のイベントなんかに行きませんね・・・)会場に来た子供たちは、親や祖母や祖父と一緒に来たとは言っても、やはり「聴きに行ってみたい」という自分の意志もそこにはありましたから、かなり喜んでもらえました。(この時は古今亭菊之丞師匠でした)けっして、主催者から配られたお菓子が目的ではなかったと思います?(そう思いたいですね)
2007.03.12
コメント(2)
-

第1回は「集客」は最悪最低、しかし、「内容」は秀逸最高!
2/16の書込でお知らせした「中学生・高校生のための落語入門教室」がきょうでした。会場の飯能市中央公民館の主催事業ですから、「広報はんのう」にお知らせが載り、さらに地区内の6つの中学校と4つの高校にチラシを配布してもらいましたが、事前の申込は6名だけしかありませんでした。 忙しいスケジュールを割いて来てくれる柳家三三師匠には「少な過ぎて申し訳ない」気持ちで一杯です。11:00開演。結局、来場者は、小学生2人、中学生1人、高校生1人、大人3人が「本当」のお客さん。他には、有望若手応援寄席の世話人仲間のKさん、公民館の担当者Yさん、それと私。集客は大失敗、最悪最低でしたが、「落語教室」の内容は、最高!私は、噺家さんによる「落語解説」のような場を20回以上は経験していますが、三三の「落語教室」は秀逸でした。とくに「一人芝居」と「落語」の相違点を、初めての子供でも理解できるように、実演で判らせてくれました。蕎麦やうどんを食べる仕草や、麺をすする音は、希望した子供を高座に上げて、実地指導です。(その写真)この高座に上がった子は小5ですが、昨年、市内の山間部で開催された屋外イベントで、「辻落語」をやっていた子供です。地べたに置かれていた「投げ銭用の缶」には100円玉がぎっしりでした。その時に私が声をかけて、有望若手応援寄席飯能のチラシを渡し、「いつでも無料にしてあげるからおいで」と誘い、以来、おとうさんと時々会場に聴きにきています。<今回の反省> やはり中高生相手の落語教室は「学校単位」でやったほうが「大勢に聞かせられる」ことが改めてわかりました。<今回の収穫>「落語入門教室」は20代の若い人たちにも「必要かつ有効」ということがわかりました。<新たに生じた希望>どなたか、柳家三三師匠を講師にした「落語入門教室DVD」を制作して販売しませんか?
2007.03.10
コメント(0)
-
その4・毎回の「出演者の人数」を決める
地域寄席の「開催頻度」や「公演時間」を決めたら、次は、4.毎回の「出演者の人数」を決める ことです。地域寄席を開催し、定着させるためには、出演者を決める前に、「毎回の出演者の人数」を決めることが重要です。本来「寄席」とは、何人もの芸人さんが出演するものです。出し物も、落語だけでなく、講談、曲芸、俗曲、漫才、手品、紙切り、踊り、演奏・・・・・・と多種多様な芸人さんが寄り集まって舞台を構成するから「寄席」なのです。しかし、最大の開催経費である「総額の出演料」は、当然、出演者の人数に比例します。私が主催している<有望若手応援寄席・飯能>は、出演者をいつも「一人」に限定しています。出演者が一人なので、「寄席」という雰囲気は乏しいのですが、その代わり、文字通り本当の「独演会」です。地域寄席の多くは、三人から五人の出演者ではないでしょうか。「出演者が二人」という地域寄席も少ないほうだと思います。なんと言っても、この「出演者の人数」で、公演時間も定まってきます。有望若手応援寄席の公演時間は、出演者が一人なので、休憩を入れて80~120分です。出演者が3人以上であれば、公演時間は120分~180分になるでしょう。毎回、休憩無しで60分~90分にしたいと思ったら、出演者の人数は一人か、せいぜい二人までにしておいたほうが良いでしょう。
2007.03.09
コメント(0)
-
その3・「公演時間」を決める
地域寄席の「開催頻度」を決めたら、次は、3.お客さんに楽しんで頂く「公演時間」を決めることです。公演時間は、地域寄席なら、最低で1時間、最長でも3時間くらいではないでしょうか。たとえ入場料が無料であっても、地域寄席が30分程度では、わざわざやってきてくれたお客さんにしてみれば、「なんだ、こんな程度かよ!」という不満が出るでしょう。しかし、途中の中入りを挟んでも、3時間以上では「長すぎる」「飽きる」「うんざりする」という気持ちが生じてきます。その点、鈴本演芸場や浅草演芸場などの定席は、私は「少し長い」のではないか、と思っています。「有望若手応援寄席飯能」でも、出演者によっては、休憩を含んでも70分以下の時が有ったのですが、その時は、お客さんから「何だよ、これだけかよ」と不満を言われないかと、ひやひやしたものです。(言われませんでしたが・・・・・)
2007.03.07
コメント(0)
-
その2・毎月か?隔月か?「開催の頻度」を決める
地域寄席を始める目的を明確にしたら、次は、2.毎月か?隔月か?「開催の頻度」を決めることです。毎月開催するのか? それとも隔月開催なのか?三ヶ月毎に春夏秋冬の開催もいいでしょう。しかし、「年一度の開催」では、地域寄席とは言えません。(私の独断ですが・・・・・)とにかく、「定期的に開催される」のが地域寄席なのです。私が、「有望若手応援寄席・飯能」を始める時は、最初から「毎月開催」と決めていました。そのほうが「楽だ」と思ったからです。なぜなら、1月に来場してくれたお客さんに、その会場で、次の2月や3月の前売り券を買って貰えるからです。中には3ヶ月先の前売り券を買ってくれる人もいたりするからです。「前売り券が捌ける」というのは、地域寄席を継続させるためには重要な要素なのです。地域寄席を始めたい人の中には、「毎月開催は大変だから隔月か年4回程度で」と考える人が少なくありません。しかし、1月に来場してくれたお客さんが、4月の前売り券を買ってくれることはあっても、さらにその先の7月の前売り券を買ってくれることはありません。毎回、ゼロから前売り券を売り捌かなくてはならないのは、かなり精神的な負担感が大きいものです。私の偏った見解かもしれませんが、隔月開催や年4回開催の地域寄席よりは、毎月開催の地域寄席のほうが長続きしていると思っています。しかし、開催頻度は主催者が、それぞれの「事情」で決めていいのです。私は、全ての仕事を引退して、時間的な余裕が持てるようになったら「毎週開催」に挑戦してみたいと思っています。
2007.03.05
コメント(0)
-
その1・発起人である自分の「目的」を明確にする
地域寄席を自分でも主催してみたい!そう思っている人もいるでしょう。【地域寄席の始め方】というカテゴリーでは、そんな人たちに向けて、「始めるための準備」を時間軸に沿って書いてみました。まず、最初にやることは1.発起人である自分自身の「目的」を明確にすることです。落語フアンが地域寄席を始める目的には、先日(2/27)書いたように、<建て前の目的>と<本音の目的>があります。実は、せっかく始めた地域寄席が「続く」か「続かない」かは、<建て前の目的>ではなく、<本音の目的>が大きな要因になるのです。例えば、「自分の好きな噺家さんの落語だけを聴きたい」という目的で、地域寄席を始める人が少なくありません。(私もそうでした)これは本音の目的なので、「始める」ことは簡単にできますが、「続ける」ことが負担になると、「こんな苦労をするくらいなら、思い切って止めてしまって、情報誌やwebサイトで好きな噺家さんの日程を調べて、追っかけをしていたほうが楽だ」とばかり思うようになって、せっかく始めた地域寄席をすぐに止めてしまうことになってしまうのです。あるいは、 「噺家さんと個人的に親しくなるキッカケにしたい」という目的で始める人もいます。(私もその一人でした)こういう人は、その噺家さんと、何かをキッカケに気まずくなったり、その噺家さん自体に飽きてしまうと、もう「続けていこう!」という気持ちが無くなってしまいます。しかし、「地域の人たちに認知されるイベント主催者になりたい」という目的で始める人もいます。(私にはそういう目的もありました)そういう人は、「世間の目」とか、「地域の人たちの評判」を気にしますから、ちょっとやそっとのことでは止めないものです。時間的に、金銭的に苦しくなっても、意地と見栄のためにも、始めてしまった地域寄席は続けていくものです。(いまの私がちょっと該当します)とにかく、地域寄席を始めようと思ったら、現時点での、あなたの「目的」を正直に見詰めてみて下さい。
2007.03.03
コメント(0)
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
-

- 避難所
- 【大人気】「エアーソファー」 で、…
- (2025-10-30 22:24:38)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- Lindt 50%OFF★OUTLET SALEでお買得♪
- (2025-11-21 14:38:36)
-