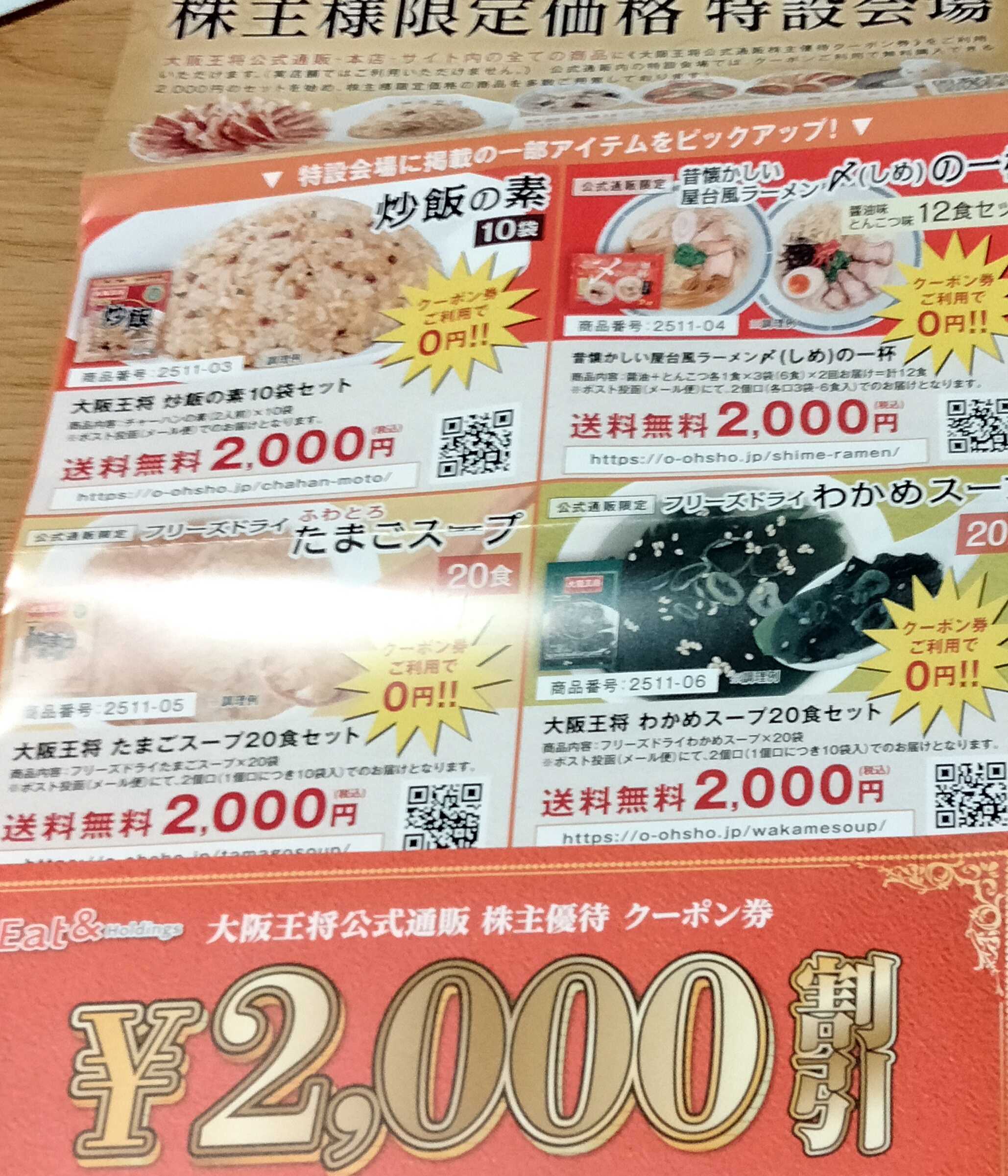2009年01月の記事
全39件 (39件中 1-39件目)
1
-
笑い方、泣き方
ちゃんと笑ってますか?大きい声で、「わあーっ、すごい。面白い~っ!!」と叫んだことがありますか?最近、ちゃんと泣いたことありますか?何かのニュースを読んで泣きますか。感情移入します?それより、悲しいことにすら遭遇してなかったりして?「一緒にご飯を食べなさいねと、 神様が言ったから、僕たちは家族になった」これは私の好きな家族に関する誰かさんのセリフ。家族に限らず、笑ったり、怒ったり、泣いたり、、、そういうことをしてこそ、人間らしいと思います。誰かと何かをして、感情の積み重ねが、情操を育んでいく。感情とは、たぶん人間のスイッチなんです。感情のスイッチが入らないと、種々の内分泌ホルモンは、出てこないような気がします。スイッチoffのままなら、マジンガーZもただの鉄の塊り。もし、俺か!!と思った人は、とりあえず、走ってみましょう。走ることでも、何か気持ちいいスイッチが入ります。小生も走ってます。メタボ対策ですが。。。記:とらのこどもps 笑い方、泣き方を知ってても、使わないと忘れちゃう。 せっせと使うのがいいみたいです。 スイッチ~ON!、ワン、トゥー、スリー!!
2009.01.31
-
小さなけんちゃん
作家 林真理子さんのファンで、小説も読むのですが、いろいろな雑誌に掲載のエッセイがいい。なんとも、好きな文章なんです。温かく、円くなった。ファンサイト:http://hayashimariko.web.fc2.com/book/58.htmlそれで、彼女のエッセイ等をスクラップしています。雑誌、新聞などをビリビリと破って、ノートポケットに入れるだけ。最近のもので、「小さなけんちゃん」というのがある。短文なので、ご紹介したいと思います。agora誌より。けんちゃんがわが家にはじめてやってきたのはたった二歳、お誕生日が過ぎたときだった。すでに、「お泊り」で馴染んでいる小学生三年生のとも君、五歳のゆうちゃんのお兄ちゃんたちに挟まれてやってきたけんちゃんの手には、着替えが入った、大きなデパートの紙袋がしっかりと握られていた。お兄ちゃんたちにしても、着替え勉強道具入りの紙袋だけど、赤ちゃんを脱したばかりの、背丈だってテーブルの下へすっぽり入りそうに小さな子が紙袋をぶら提げる姿には、憐憫を覚えないわけにはいかず、袋の底を引きずりながら部屋に入ってきた。そのいたいけなさ、そのことだけで私の胸は痛んだ。いまの時代、わが子がお泊りするといったら、親たちはカバンなりリュックなりを用意してやるだろう。そうしてもらえない事情を、けんちゃんは背負っている。けんちゃんたちは、児童保護施設で暮らす子どもたちである。交通事故とかで親を亡くしたとか、親が養育放棄したとか、さまざまな理由で保護されたのだ。家庭と言う者を知らずに育つので、自分が結婚して家庭を持った際に途方に暮れて、ギブアップ。子がさずかっても、育て方がわからず施設に送るというケースもある。こうした悪循環を防ごう、家庭を学ぶ機会をあたえようという制度が、私の住む地域での「三日里親」。学校の長期休暇の時期に子どもたちを二週間ほど、応募の中から認可した里親家庭へ預け、普通の家庭生活のありようを体験させるのだ。とも君たちはわが家に来るようになって三年目なので勝手知ったるもの、私を「おかあさん」とわだかまりなく呼び、台所に立つ私の傍らで魚を捌くところをじっと見る。彼らは決して部屋中を飛び回ったりしない。お行儀の良さは、わが息子以上である。小さいけんちゃんはお兄ちゃんたちの後ろにくっついていたが、二日もすれば、私にべったりの腰ぎんちゃく。近所の八百屋さん、肉屋さんへの買い物も全員がついてきて、けんちゃんは私に負ぶわれて帰る。ある夜のことだ。「家族全員一部屋で、いっしょくたに寝よう」という相談がまとまり、和室に布団を敷き、合宿状態で就寝した。私の布団にはけんちゃんがいて、眠りにつくかどうかというときだった。向こう向きに寝るけんちゃんが、どういうことか、小さな手で壁をひっかいているのだ。「どうしたの」と聞いても返事がない。顔を覗くと何かを我慢するように口元をぎゅっと結ぶ。その頬に赤みがさしている。驚いておでこに手を当てると熱い。急ぎ体温計で熱を測ると三十八度。たいがいの二歳ならぐずるところだが、けんちゃんは泣きもせず、黙って我慢した。きっと我慢の限界がきたので、でも私は本当の母ではないと二歳にして承知しているから、壁に助けを求めたのだ。応急手当に小児用熱さまし、そして久方ぶりに忘れずに仕舞っておいた氷まくらを取り出した。少しゴムの臭いのする口に製氷室の氷を入れながら、私はなんだか無性に悲しくて、涙がこぼれてしかたなかった。 林真理子さんの温かさが、文章からほのかにかおり立つ。 そんな気がします。私も読みつつ、涙がこぼれてしかたが なかった。また彼女のエッセイ集を買いたい、そう思った。 記:とらのこども
2009.01.31
-
光あふれる言葉を伝えたい
闇に閉ざされた心からはマモノが生まれ堕ち、光に満ちた心からは天使の翼が羽をひろげる。運命に立ち向かうのも、未来を変えるのも、ひとりひとりの心から始まる。光に満ちた心は、光あふれる言葉となり、まばゆい行為となって伝わってゆく。ひとりひとりの輝きが世界に満ちるとき、運命はその姿を変える。国際戦略サイトにそうあった。http://fuku41.hp.infoseek.co.jp/ であるならば、ボクは光に満ちたココロを持ちたいと思う。 キミのココロにも、その気持ちをとどけたい。 誰もひとりきりでは生きていけない。 だから、できることをしたい。キミのために。ボクのために。 そして、こどもたちのために。。。 記:とらのこども@再掲シリーズ
2009.01.31
-
"やまとことば"が伝えるもの
言葉というものは、お母さんから話しかけられて、いっぱい聞いて、しみ込んでしみ込んで、自分のものになる。そのときの言葉はやさしく、あたたかく聞こえる。だから、こころにまで響いてくる。もちろん、おかあさんの愛情たっぷりの言葉だからだ。酔って帰宅したお父さんの言葉は、泣いて拒絶!?また、あかちゃんに「現代社会の問題は云々」などという漢字いっぱいの言葉はしゃべらない。当然、やまとことばになる。だから、ポエムも、歌も、演説すらも、大和言葉こそ心に響き、しみ透る。「我は海の子~」という唱歌がありますが、あれは全ての歌詞が大和言葉なんですね。であればこそ子どもらの心にしみとおる。わたしが好きなブログのなかに、そんな香りがあるブログがあって、訪問すると、なんともやさしい、話しかける雰囲気があります。わたしはそういうブログが大好きです。皆さんにも教えたいんだけど、ヒ・ミ・ツです!!ごめんなさい♪記:とらのこども@休日再掲シリーズ われは海の子(われはうみのこ) 1 われはうみのこ しらなみの さわぐいそべの まつばらに けむりたなびく とまやこそ わがなつかしき すみかなれ 2 うまれてしおに ゆあみして なみをこもりの うたときき せんりよせくる うみのきを すいてわらべと なりにけり 3 たかくはなつく いそのかに ふだんのはなの かおりあり なぎさのまつに ふくかぜを いみじきがくと われはきく なつかしの童謡:http://www.toshiba.co.jp/care/benri/douyou/2ware.htm
2009.01.31
-
学び
学ぶと言うが、自働的に学ぶのではない。学び(気付き)があるのだ。それは天啓である。導きなのだと思う。例えば、山からは、山から学ぶものがある。文字どおり、山ほどある。その険しさ、その厳しさ、その豊かさは、直にふれもせで分からない。ところが、5年・10年 山と関わっても、天啓が無ければ、学び(気付き)は無い。ある時、あっと驚くような真理に気付く。そのときに、すとんと腑に落ちる。それが「学び」だ。まさに気付きである。それを知恵という。知識と知恵とは似ているが別物だろう。学びは、受ける備えのある人に降ってくる。記:とらのこども
2009.01.31
-
大いなるもの
大都会、ネットワーク、情報、あるれる知識によって、知らず知らず、頭でっかちになっている私たち。深海の深みも、極寒の極地も、悠久なる太古のことも、遠く遠く離れた宇宙のことも、知っている。(つもり)本当は、何も知らない。本当は、見たことも触れたこともない。野球のビデオを100回見て、野球の歴史を深く知り、バットの構造も、ルールブックも知悉した若者がいた。ところで、彼は野球をやったことがない。彼は、野球を知っていると言うべき存在だろうか??海を見ろ、海に潜れ、海に漕ぎ出せ。カラダに染み入るほど、触れて、見つめてこそ、やっと何かがほんの少しだけ、あなたに気付きをくれるだろう。学校の勉強は、ただの準備運動に過ぎない。あれは、「本物の学び」の第一序章なのだろう。かごの中の鳥は、どんなに上手に飛べたとしても、かごの中の鳥に賞賛されたとしても、所詮は、かごの中。都会とは、巨大な鳥かごかも知れぬ。今ふと、そう思った。本物の大いなるもの。海や、山や、冬の雪に触れて欲しい。記:とらのこどもps いつの世も、大いなる変革は地方から起こる。 それは自然の大いなるものに触れているから。 都会の人は、生きているが死んでいるのかも。
2009.01.31
-
ちょっぴり早いバレンタイン
ちょっぴり早いんですけど、とある方からチョコをいただきました。宅配便の不在通知を受け取って、配達のお願いを電話して、なかなか通じない郵便局のその電話を、何回も、何十回も電話して、やっとつながって、やっと配達してもらって、やっと受け取った「チョコの詰め合わせ」。その必死さが、我ながら恥ずかしく思うほど、うれしかったなあ。ほんとありがとうございます!!この高揚感、久しぶり。記:とらのこどもps そういうプレゼント。 今度はわたしが誰かにしたいと思います。
2009.01.30
-
冬の旅
冬は寒い。こころまでかじかむときがある。そういうときは、あったかい温泉がいい。こどもの希望のスキー旅行にかこつけて、妻とこっそり、夜の密談。行きたい温泉と、近所のスキー場を探す。「キミのためだよ」と、リップサービス。このときこそ、へそくり登場。部屋も、食事も、ぜいたくざんまいOKだ。家族のこころがあたたまれば、不思議と自分も温まる。こころがほっとする。旅は、ほっとステーション。。。寒い冬は、人肌のあたたかさに限る。記:とらのこども
2009.01.27
-
幸せのホームページ
幸せにしてくれる人 幸せにしたい人幸せになるために、自分を幸せにしてくれる人を探す、というのも1つの幸せになる方法だと思います。でも自分を幸せにしてくれる人はなかなか見つからないという人が多いのではないでしょうか。自分を幸せにしてくれる人がいる人は幸せだと思います。幸せにしたい人・大切にしたい人がいる人は多いと思います。幸せアンケートで、幸せにしたい人が「いる」人は現在72%です。幸せにしたい人がいることも幸せなことの1つだと思います。その人を幸せにすることを考え実践すれば幸せになれるのですから。では幸せにしてくれる人を探すのと、幸せにしたい人を探すのでは、どちらが容易でしょうか?つぎに、幸せにしてくれる人を求めている人と、幸せにしたい人を求めている人とどちらが多いでしょうか?これは前者のほうが圧倒的に多いのではないでしょうか。とすれば需要と供給の関係から考えれば、幸せにしたい人を探せばすぐに見つかりそうです。と言っても、どういう人を幸せにしたいかはこころ(気もち?)が決めることですから、人を幸せにしたいと思えない人には、どこを探しても幸せにしたい人は見つからないし、幸せにしたい人の条件がすごくきびしい人は、なかなか見つけられないでしょう。人を幸せにしたいという思いが強い人は、幸せにしたい人がすぐ見つかるんじゃないかと思います。人を幸せにすることを喜んでできる人は、幸せにしたい人がたくさん見つかるような気がします。以上は、「幸せのホームページ」よりhttp://www.din.or.jp/~honda/とらのこどものお勧めです。ぜひぜひ、ご覧ください。きっとほっとしますから。
2009.01.26
-
坂道
二十歳の頃にはいっきに駆け上った坂道は、途中で大きく二度曲がる。最初の角は、果樹園や墓地の横を抜ける細い道。夜などは暗い恐い道だが、バス停までの近道だ。次の角は、高台の公務員宿舎へと続く道。この先は、コンクリート舗装へと変る。坂道の左。ちょうど中ほどの横っ腹に、下の学校から一気に上がる階段がある。駆け上がれば数分。ベロベロに酔っ払っていたとき2時間かかった。坂の上の私の家は、白地にブルーの塗装が映え、入居したときは、それは光り輝いてみえた。青雲寮という学寮が、丘の上、空に突き出て立っていた。200余名が住んでいた。ぼくたちは、その坂を寮坂(りょうざか)といった。坂道の両側には、大きな桜がいっぱいあって、毎年、入学式に彩りを添える。その頃には、まだあどけない顔の新入生だとか、晴着のご両親も一緒に坂を上る姿を見たものだ。今頃、桜のつぼみは未だ堅かろうが、春のときを、じっと待っているに違いないのだ。若かったあの頃、登る坂の先が見えなくてもまったく頓着しなかった。今また、今度は人生のゴールが近づいている。坂の先が見える。(ような気がする)人生の坂の途中にも曲がり角がいくつもあった。今頃になって、ふと振り返る。寮坂のふもとには住宅地。やがて国道に至る。寮坂の向こうには、ただ空が広がっていた。あの頃、ボクはどっちを見ていたんだろう。そして、今は。。。記:とらのこども
2009.01.25
-
日本国憲法第9条
現行憲法を作るとき、日本から軍をいっさいなくそうとしたのは、GHQのマッカーサー元帥ですが、それを受け入れたのは、首相幣原喜重郎(しではらきじゅうろう)です。ところが、それはマッカーサーを欺くトリックだったという説があります。マッカーサーを引っ掛けて、日本がアメリカの尖兵になるのを避けようとしたというのです。 「昭和の三傑」著者:堤堯/集英社インターナショナル 著者の堤堯さんは、元文芸春秋編集長です。幣原喜重郎は戦前、国際協調路線を取り「軟弱外交」と言われたオールドリベラリストですが、終戦の年の10月に、首相の座に就いています。堤さんの説によれば、この幣原喜重郎が憲法第9条、いわゆる「戦争放棄」条項をマッカーサーに提案して、それとの交換条件で天皇制を存続させたといいます。だから、第9条を含む現行憲法は、押付けではない。むしろ幣原喜重郎がそのアイデアを出したのだと書いています。そこでこの本のサブタイトルが、「憲法9条は「救国のトリック」だったとなっている。究極のトリックではなく、救国のトリックだというわけです。堤さんの仮説の当否はともかく、第9条は日本国憲法のなかでもいちばん重要なポイントです。正当防衛まで否定しているわけで、普通の国ではありえない条文です。憲法の草案が発表されると、かの共産党も反対しているほどです。共産党の幹部・野坂参三なども、「武力を完全放棄してどうして国の安全を保てるのだ」と、国会で幣原首相に詰め寄っています。さて、真実はどうだったのでしょう。残念ながらその関係者は、もういません。そろそろ普通の国になるために、真剣に努力すべき時期でしょう。それを歴史の大先輩たちも望んでいると思えてなりません。考えろ、考えろ、考えろです。現状維持だけで良いというのは、思考放棄に他なりません。記:とらのこども
2009.01.24
-
自分のやるべきこと
人は自由である。歩いてどこまでも行けるし、思考は宇宙を越えることができる。人は不自由である。何でもできるから、何をしてよいか分からない。やかんはやかん。松の植木は、庭木の松でいい。番犬は、家の番犬であることに満足しているように見える。能動的なようでいて、受動的なわたしたち。どこで何をすべきか、本当は環境が求めている声を聞くべきだ。家族がお腹をすかせていれば、食事を作ろう。もし、地面に穴が必要ならば、穴を掘ろう。謙虚に耳を傾ければ、やるべきことが見えてくる。この頃、そう思うのである。記:とらのこども@再掲シリーズPS こどもを見てあげましょう。こどもに耳を傾けましょう。 家族ひとりひとりに、同じようにしてみましょう。 知らず知らず、無くてはならぬ自分になっていく。 今日、妻は風邪。私が買い物&晩御飯の準備です。
2009.01.24
-
希望をもって生きる
『努力する人は希望を語り、 怠ける人は不満を語る』 井上靖 希望を語る(想う)と、少し幸せな気もちになれる 不満を語る(想う)と、少し不幸な気もちになる 希望を語る人と不満を語る人、どちらになりたいでしょうか? 『愚かな人はただ願い、不平をいい続けるが、 賢い人はよく働き、おだやかに結果を待っている』 ジェームズ・アレン 『夢が実現する可能性があるからこそ、 人生はおもしろいのだ』 パウロ・コエーリョ http://meigen.shiawasehp.net/k/p-coelho02.html 1月はもう過ぎようとしているが、今からでも遅くない。 春はもうすぐだ。雪の下の草は春の準備をしている。 負けてはならないと思う。 素晴らしい今年にしたい。 記:とらのこども@再掲シリーズ
2009.01.24
-
西郷隆盛と征韓論
1868年に維新がなり、明治新政府は「政権が朝廷に戻った」旨を、当時の韓国(李氏朝鮮王朝)に国書を出します。その文面の中に、「本邦、頃、時勢一変、政権一ニ皇室に帰ス。帰国との隣誼、固厚シ。」(ほんぽう、このごろ) (りんぎ、もとよりあつし)といった文言があったため、韓国は国書を受け取りませんでした。「皇」という字は、シナの皇帝のみが使うべき文字だからという理由で、拒絶したのです。自国「皇室」という文字を使う「倭奴(ウエノム)」は、無教養、無礼極まりないと、怒りに打ち震えたのです。これに対して、当然わが国では韓国はなんと無礼な国だといって、一気に征韓論が沸き起こりました。しかし、西郷は、、、「いくら無礼な国だからといって、ただちにそれを軍隊で攻めるというはムチャである。それよりも自分が一兵も連れずに行く。」と言いました。「行けば、必ず殺される。攻めるのはそれからでいいではないか。」と言ったわけです。だから、西郷隆盛は武断派ではありません。西郷は征韓論を抑えた側です。現に、西郷が閣議などの公式な場で、征韓論を主張した史料はありません。それどころか、閣議では出兵に反対し、平和的交渉による日韓国交正常化を力説しています。西郷隆盛の征韓論というのは全くの俗説に過ぎません。ところが、そういう基本的なことさえ、ノムヒョンは知らなかった。日韓首脳会談が鹿児島で開催されるとき、「鹿児島は西郷隆盛の生まれた国(薩摩藩)だから嫌だ。」ゴネたのです。しかも、そのときの首脳会談で「今後、歴史問題は持ち出しません」との発言が記録されいるのも関わらず、その後の対日バッシングは、ご存知の通りだと思います。しかし、昭和40年(1965年)の日韓基本条約が成立したとき、その条約のなかに明文で、今後、過去のことは持ち出さないことが規定されていて、お互いの国会で批准されているのです。にも関わらず、いつも歴史問題を持ち出す韓国大統領はどうしようもありません。公の場で「出さない」といったら出すべきではありません。それが一国の大統領の重みというものでしょう。でなければ、隣国との交誼を厚くしたいという友人の国を無くすだけです。韓国が自主独立し、健全に発展して欲しいと念願しています。記:とらのこども参考文献:「中国・韓国人に教えてあげたい本当の近現代史」渡辺昇一この本は簡潔、且つ秀逸です。とらのこどものお勧めです。
2009.01.24
-
円高
円が高い。どこまで行くのと聞きたくなる。もっと高くなりそうな雰囲気だ。円が高いと、海外旅行はお得だし、海外から購入する原油や、原材料も安くなる。とはいえ、おおかたの製造業は苦しい。円高で、現地価格では売り上げが目減りする。ドルにも、ユーロにも、ポンドにも、ウォンにも、どこの通貨に対しても、すごく高い。日本の政府、金融、会社、個人にいたるまで、円を外国通貨へ換える活動が望まれる。どんどん外国通貨から円に換わっているから、円が高い。誰がそんなに円を買っているんだろう。。。本当に不思議なくらい円が強い。喜ぶべきか、悲しむべきか。それが問題だ。円高で儲かっているところは、速やかに社会へ還元して欲しいものだ。記:とらのこども
2009.01.23
-
どないでっか?
どないでっか?儲かってまっか?これは関西で代表的と言われた挨拶のせりふ。もっとも、本当に使う人はまれである。 どやねん、元気してんのんか? 頑張れよ、きっと大丈夫だから。 もう少しだけや。我慢、我慢。我慢しいや。 いけんで、絶対。かめへんからいてまえ!! よっしゃ、それでいこ! 時間取るよってに、話し聞かせてや。。。いろんな言葉、いろんな労り、励まし。言葉とは、こんなにも優しい、温かいものかと思うときがある。基本は、自分がかけられたい言葉を、誰かにかけることだ。ほんのちょっぴり勇気を出せば、声を掛けられる。声を掛ければ、何かがはじける。気持ちが通じる。ほんなら、明日からそないしまひょか?気分よう気張んのが、よろしいようで。記:とらのこども
2009.01.21
-
為せば成る
仕事を頼むと、「難しそうですね」「無理かもしれません」「私には荷が重過ぎる」「時間が足りない」などと消極的、否定的な言葉を並べる人がいます。こういう言葉は禁句にしたほうがいい。「できない」「難しい」と口にした瞬間から、それは本当にそうなります。「やってみます」「できると思います」と言えば、そのとおりになるのです。(中略)「できる」と思って取り組めば、脳細胞が活性化して「どうしたらできるか」を真剣に考えます。「できない」と思ったら、そこから先は考えないし、努力もしません。だから本当にできなくなるのです。赤ちゃんは一生懸命立ち上がろうとします。なかなか立てないけれど、何度も何度も立ち上がろうとします。すると少しずつ立てるようになっていく。なぜたくさんの失敗をしながらあきらめずに立とうとするのでしょうか。それは、赤ちゃんの頭の中には、「立てない」「難しい」「ダメだ」といった言葉がまったくないからです。立てないのではないか、歩けないのではないかとは微塵も考えません。だから何度失敗しても楽しそうに努力するのです。以上は、「メルマガるい」から。とらのこどものお勧めです。
2009.01.20
-
正しい作法
カラリッと氷が音を立てる。ガラスのコップのなかを、何故かしら反時計回りに氷が崩れて、回って、落ちる。スコッチの琥珀色。光を透かしてテーブルの木目が光る。氷だけが、白く浮かび上がる。まるで、暗いベットで白く胸が浮かび上がるように。ひとくち、ゴクリと飲む。傾けたグラスのなかで、カラコロッと氷が泣く。またひとくち飲む。今度は、グログロッと泣く。手に持ったグラスを振ってみる。グシャグシャグシャと、氷が身を震わせる。両手を胸に引き寄せて、わななく表情と同じよう。ラスト。一息に飲む。氷が崩れて落ちる。後は氷だけ。すすると、甘い琥珀の蜜の味がした。記:とらのこどもps 忘れた頃に、”クリッ”と氷がボクを呼んだ。 グラスに舌をのばして、最期の甘露を舐めとる。
2009.01.19
-

もっともっともっと!
もう少し、遊びたい。もう少し、いい生活がしたい。もう少し、楽をしたい。もう少し、素敵な恋をしてみたい。みんな、そう思っている。もう少し、もう少し。もっともっともっとって。そのために、どうすればいいかは本当はわかってる。だから、明日からそうしよう。きっと、手が届くはず。記:とらのこども
2009.01.18
-
噂の地酒を探る会
「噂の地酒を探る会」というお店?(個人の家)があった。今はもうない。そこの親父殿は著名な書家で、特に日本酒のラベル書きにおいて、最高峰と言われていた。「日本国内のラベルは、ほとんど全部、わしが書いた!」と豪語するごとく、全国の銘酒がそれこそ何でも飲めた。それも限定数百、数千本というような凄い酒がゴロゴロ。ラベルを書いた蔵元から贈られるのだが、到底、一人では飲めるはずもない。というわけで、「噂の地酒を探る会」というお店となった。とはいえ、普通のお店ではないので友人、知人限定。または、友人の紹介(同行に限る)という厳しさ。元近鉄の今は故人となった仰木彬監督がよくいらしてました。お客さんには、有名人も少なくなかったようです。残念ながら芸能界に疎い私はよく分かりませんでしたが。。。このお題。人は人を求めるのだ。ということを書きたかったのです。親父殿は、普段は兵庫県の山奥にいたはずで、ときどき山から下りてきて、天王寺にある自宅へ客を呼ぶ。私たちのような若い客は少なかったようで、ずいぶん可愛がってもらいました。(⇒いっぱい飲まされた!)とにかく、倒れるほど飲んで、ふらふらと仲間と歩いた路地裏の街灯、ガード下の自転車。支えて支えられて、いつもどうやって帰ったのか。。。実に懐かしい。私の青春は、なぜかいつも日本酒の香りでした。そういうお店、そういう仲間。うまい酒。いつまでも続く長い長い夜の時間。いろんな人に迷惑をかけて生きていたんだなあ。少しでも、人の役に立ちたいと思います。記:とらのこどもps そのお店。お品書きは何も無し。 これが飲みたい!と言ってもダメ。まずこれを飲めからの スタート。どうだ、うまいか?じゃあ、次はこれだ!! そして、次から次へと飲まされる。 お会計も、大将が「う~ん、5万円!!」とかって感じで きわめてテキトーな感じ。でもきっとめっちゃ安かった。
2009.01.18
-
「みる」
見る、診る、看る、視る、観る。これらは全て「みる」を読む。意味は漢字のとおりだ。最近、言葉とともに人間も薄っぺらくなってきていて、他人様は分からないが、自分の薄っぺらさに嫌気さえ。刹那的、衝動的、受動的になっている感じ。だから、つい、いらいら感も。そういうときは、自分をじっと観るようにしている。何を感じて、何を考えて、何にあせっているのか。。。第三者的に見つめていると、見えてくる。そのとき、こうしたらいいのに!という部分も見える。衝動という(自動回路)で、動いているうちは、そいつが見えない。だんだん焦ってくる。燃えそう!!自分の消火は、自分でやるものだ。それであればこそ、小火(ぼや)で済む。記:とらのこども
2009.01.18
-
迷惑をかけないようにする
迷惑をかけながら生きているこれは友人から聞いた話。ある日本人がインド人の記者に、「日本では他人に迷惑をかけるなと教育しています」と言ったところ、そのインド人は、「私の国では、人は他人に迷惑をかけながら生きているのだと教えます」と答えたそうである。インドの人が言うように、「人は他人に迷惑をかけずに生きることは出来ない」というのが真実だと思う。まずそのことをふまえた上で、「これ以上迷惑をかけてはいけない」と教えるべきなのだろう。よく似た話に、「自立」ということがある。私も安易にこの言葉を使う。しかし考えてみるとそもそも人間は自立してなど生きれない。食物一つとっても、いろいろな生物のお世話になっているのである。そうした基本的な認識を忘れて、偉そうに「自立」などという言葉を口にすべきではないのだろう。さて、今日は楽しい土曜日である。友人から映画DVDを借りたので、今夜はこれを鑑賞するつもりだ。これ以上家人に迷惑をかけないよう、夜中にひっそりヘッドホーンで見ようと思う。
2009.01.17
-
人類破滅のワナ
愛人エバとレニへ……子どもを生まない民族は滅びる ヒトラーの言葉の中で、 「人類破滅の罠」として子どもを産まない女性の話しがある。 それは、有名な愛人のエバ・ブラウンと、もう一人のレニ・ リーフェンシュタールへ語った言葉だ。これはまさにその通り だろうと思うのだ。「レニ、こんな時期にこんな所へよく来てくれた。でも、きみはここを去って、二度と戻っては来ないよ。そして、それでいい。きみは長生きして名声を得るだろう。また、死ぬまで映像の美とともにあるだろう。将来の……今世紀末から来世紀はじめの文明国では、きみのように結婚もせず、子どもも生まず、一生、男以上の働きをする女性が増えるよ。しかし、それは当然、女性の見かけの地位の向上とともに、その民族の衰亡──ひいては人類の破滅につながるワナなんだけどね。」また、ヒトラーは人間を弱らせるものとして、「酒と、タバコと、肉食」をあげていたそうです。そして事実、彼は酒とタバコはやりませんでした。自分の健康を保持するため、なんでしょう。その意思は真似たいものです。
2009.01.17
-
貝や「山吹」
貝や:貝屋は、貝焼きの専門店。中座の西の南北の筋の法善寺横丁の看板の角から二軒目にその店はあります。 大阪には、貝焼きのお店が何軒もあるんです。そのなかの知る人ぞ知る店が、法善寺の貝や。屋号は「山吹」。屋台の香りがほのかに匂うカウンターのみの店構えでキャパは六名。無理してもうひとり座ることができるこじんまりしたお店です。それゆえお互いの顔が十分に見え、美味しい料理、お酒を堪能できるんです。 もちろん料理は「貝や」という屋号通り、貝料理のみ。メニューは黒板に解説つきのものと主人、お母さんのお二人でいっぱいの調理スペースに貼られている暗号のような二文字で書いている札があります。 普通は、ホタテの貝ひもの焼き。熱々の日本酒をすする。私の好きだったのは、まて貝。でかいまて貝をじっくり焼き上げる、絶品!!大好きだった彼女を誘って行ったことがあります。飲んで、話し込んで、また飲んで。。。べろべろになって、その後、どうしたかは覚えていません。とにもかくにも、飲んべいにはたまらない店でした。小さい店のために初めての方はおそらくはたどりつけないと思います。ひとたび入れば居心地のよさに驚くと思います。 懐かしい。。。私の三十代は、大阪の赤提灯の匂いがする。記:とらのこどもps せっかくベロベロになったのに、彼女とは何もなかったんです。 ほんとに大好きでした。そういう人とは何もないものかも。。。 甘酸っぱいというよりも、日本酒の匂いのする思い出です。
2009.01.17
-

三島由紀夫と、ヒトラーの予言
三島由紀夫がヒトラーについて語った言葉「ところでヒトラーね。彼がやったことは世界中の人が知ってる。だけど、彼がほんとは何者だったのか誰も知っちゃいない。ナチの独裁者、第二次世界大戦の最大戦犯、アウシュヴィッツの虐殺者、悪魔……。これが今までのヒトラー観だけど、ほんとはそれどころじゃない。彼のほんとの恐ろしさは別のところにある。それは彼が、ある途方もない秘密を知っていたってことだ。人類が結局どうなるかっていう秘密だ。彼は未来を見通す目を持っていて、それを通じて、その途方もない未来の秘密に到達しちゃった。」「だから五島君。もしきみが10年後でも20年後でも、ヒトラーのことをやる機会があったら、そこんところをよく掘り下げてみることだ。もしきみにいくらかでも追求能力があれば、とんでもないことが見つかるぜ。ほんとの人類の未来が見つかる。やつの見通していた世界の未来、地球と宇宙の未来、愛や死や生命の未来、生活や産業の未来、日本と日本の周辺の未来……。なにしろ『我が闘争』の中にさえ、やつは未来の日本や東アジアのことを、ずばり見通して書いてるくらいだから。まだ30代かそこらで、やつは、それほど鋭い洞察力を持ってたってことになるよな。」 ※ 約1時間のインタビューの間に、三島由紀夫は、これ以外にも五島氏に強烈なインパクトを与えた“ヒント”を2つ授けたという。1つは太古の日本民族と古代インドを結ぶ妖しい関係で、また、そこから発展してくる人類の超古代文明全体への、目くるめくような壮大なヒントだったという。そしてもう1つが、「人間の死後と転生」についての画期的なものだったという。 そしてヒトラーの予言は、ドイツ第3帝国の崩壊とともに、戦勝国となった いくつかの重要な国だけに引き継がれた。 その預言書は、極めて厳重に管理、秘密保持されていると言う。 アメリカも、イギリスも、その秘密を知っている。 戦後の60年の平和。しかしながら、今、まさに大動乱の時期を迎えつつ あるけれども、これも予言されていたに違いない。 日本は、未だその秘密を知らない。 知らないけれども、漏れつつあるその秘密を求め、解き明かしつつある。 それは、知らないほうが良いのかもしれぬ。 ただ良く生き、ただ日本らしく行くのみだ。 恐れるよりも、生きることが重要だ。 とらのこども
2009.01.17
-
笑って泣いて、生きるのみ(再掲)
散るさくら 残るさくらも 散るさくら 弘兼憲史遅かれ早かれ、ひとは皆死んでいくのだと思えば、ともに過ごしてくれる人は、なみだが出るほどありがたい。とにもかくにも、あれもこれも、できるかぎりに、取り組みたい。笑って、泣いて、生きていくよりほかないのだから。 昨日 また かくてありけり 今日もまた かくてありなむ この命 なにをあくせく 明日をのみ 思いわづらふ 島崎藤村帰宅したら、山ノ神と相談してうまいものを食いに出かけたい。日帰り温泉に行こうと思う。記:とらのこども@休日再掲シリーズ
2009.01.17
-
アドルフ・ヒトラーの予言(再掲)
アドルフ・ヒトラーは、言わずと知れたドイツ第3帝国の総統だった。第2次世界大戦を引き起こし、世界、特に欧州全部をを恐怖の淵に誘った。このヒトラーが大予言者だったことは、一般的ではないが、いくつかの本が出ている。その中に、ロケットや原爆のことも、インターネットの実なども予言されている。彼が生まれて50年後に大戦が終結し、100年後にはベルリンの壁が崩壊した。日本に関係ある部分ではないか、、、と言われている部分として、「東のほうに大人になっても、皆、子どものままという不思議な国が出現する」というものがある。そんなことは通常、有り得ない国の状況だが、日本の状況を考えると、ずばりその通りではないか?という気もする。また、神人(超新人類)の出現も予言している。それは、生まれてまもない時期に、すでに大人の思考を持ち、世界の全てを見通す能力を持つという。世界は、その超新人類に完全に支配され、人々は農耕の牛馬のようになる。ヒトラーの死後、100年後にそういう時代が来るという。それは、2039年だ。また、それを阻止する可能性も示唆している。それもまた日本であり、日本から世界を救う何かが出てくると。。。そは弥勒菩薩の登場か!?(弥勒菩薩とは、景教(日本に来たユダヤ人がもたらしたという)の影響)(という説もある。)興味のある方は、本を求めてご覧ください。なかなか興味深く面白いです。記:とらのこども@休日再掲シリーズヒトラーの予言http://inri.client.jp/hexagon/floorB1F_hss/b1fha400.html(ヒトラーの予言より、一部抜粋)「よろしい、では解説してやろうハンス。私が言った未来に現われる「永遠の未成年者集団」というのは、もちろん、死ぬまで大人になりきれない人間たち、ということだ。そんなことは、厳しい正常な社会ではありえない。だからそうなる背景には、甘やかされた異常な社会が当然ある。その中で同じように大人になりきれない親に、愛玩動物のように育てられるため、子供も成人しても真の大人になれないのだ。 しかしハンス、実はそれだけじゃない。私が本当に言いたかったのは、そのことではない。未来社会には、そういう「永遠の未成年者集団」が現われる一方で、幼いときから大人の思考と感情を持った人間達も現われるのだ。信じられないだろうが、彼らは胎児のときからさえ、そのように教育される。5つか6つで一人前の理屈と判断力を備え、13,4歳にもなれば、並の大人を指揮するほどの力を持つようになる。つまり両極端ということだ。肉体が大人で感情が幼児のようなグループと、肉体はまだ青春期にまでいかないのに、思考と感情が大人を超えるグループ・・・」 「しかもハンス、それは人間の発育状況だけじゃないのだ。人類と社会のあらゆることが、未来には、そのように両極端に分かれてしまうのだ。たとえばカネだ。一方には腐るほど大量のカネを持ち、広く高価な土地を持ち、労せずして限りなく肥っていく階級が現われる。貴族とか新しい中産階級とか言ったのはその意味だ。 だが少数の彼らが現われる一方で、他方の極には、何をどうやっても絶対に浮かび上がれない連中も現われるのだ。それはカネだけの問題でもない。より正確にいえば、精神の問題だ。限りなく心が豊かになっていく精神の貴族、精神の新しい中産階級が現われる半面、支配者が笑えと言えば笑い、戦えといえば戦う「無知の大衆」「新しい奴隷」も増えていくのだ。」
2009.01.17
-
冬ですねえ。。。
冬ですねえ。毎日、とっても寒いです。今日は、雪のところも多かったようです。テレビでやってました。でも、とらのこどもは、冬も大好きです。厳しい寒さが、身体をぴしっとさせてくれる感じが好きです。冷たい水で、顔を洗うのも、引き締まる感じで好きです。こどものころを、なぜか思い出します。こどものころは、もっともっと寒かった。かじかんだ手を、はあー、はあーっと、息で温めました。手にはしもやけ、あかぎれがありました。そして思い出す歌と言えば。。。「北風小僧の寒太郎」井出隆夫作詞・福田和禾子作曲-------------------------------------------------北風小僧(きたかぜこぞう)の寒太郎(かんたろう)今年も町までやってきたヒューン ヒューンヒュルルンルンルンルン冬でござんすヒュルルルルルルン北風小僧の寒太郎口笛(くちぶえ)吹き吹き一人旅(ひとりたび)ヒューン ヒューンヒュルルンルンルンルン寒(さむ)うござんすヒュルルルルルルン北風小僧の寒太郎電信柱(でんしんばしら)も泣いているヒューン ヒューンヒュルルンルンルンルン雪(ゆき)でござんすヒュルルルルルルンhttp://www.mahoroba.ne.jp/~gonbe007/hog/shouka/kitakazekozo.html
2009.01.17
-
公務員もリストラの予感
88自治体が赤字地方債 07年度、愛知県最多の359億円 2008年3月8日03:11 中日新聞 建設事業でなく税収減の補てんを目的とした地方債の発行を認めるのは、オイルショック後の1975年度(約3400億円)不況感が強かった2002年度(約1200...道路財源支出50法人を半減 国交省方針、駐車場機構は解散 以下、省略。(注意 昨年の記事です)2009年の春には、いったいどうなることやら。来年度予算の財源不足の見込みは、5000億円弱の試算が出ている。愛知県の赤字地方債の発行額は、おそらく巨額となることだろう。そうした中で、来年度一般職員給与の6%(年収平均で47万円カット)する案を、県職員組合に提示した。総額で320億円の削減となる。背に腹は代えられない。おそらく、この風潮は全国的な流れになりそう。公務員の皆様、気合いを入れて経費削減、財政再建をお願いします。組合員平均で約800万円の年収は、民間と較べてどうなのか。このへんも議論に上がってきそうな予感である。小生は、河村氏が名古屋市長選に出れば、投票しようと思っている。落ちるところまで落ちた、腐ったところは、ブチ壊すほかは無い。その時期は、もう間近いのではないか。なんとなく、そんな気がするのである。記:とらのこども
2009.01.17
-
冬の夜に欲しいもの
秋の夜長というけれど、冬はもっと夜が長い。というより、夜の始まりが早いから長い感覚があるのだろう。北海道なら冬のこの時期。昼の長さは8時間から9時間ほど。沖縄へ行けば、1時間くらいは長くなる。日本は広い。そんな冬に欲しいもの。あったかい温泉。冷たいみかん。敷布団の厚いこたつ。朝の5分、10分。暖機運転の5分間。暖房がすぐに入る自動車。休日の朝の雪景色。庭の赤い花。プランターの花卉の新芽。うまい酒。おでん鍋。そして楽しい夢。いい夢、見てくださいね。明日の朝は、ゆっくりなんでしょ???記:とらのこども
2009.01.16
-
寒い夜には。。。
寒い夜には、人肌が恋しい。あたたかくやわらかく包むこむような、温もりが欲しい。でも、ほんとに欲しいのは、温かい気持ち。やさしく微笑んで、話しを聞いて欲しい。そう思う。いろりの焔がゆらめいて、しんと静まる夜なべのころに、物語りこそ似合うもの。こたつに蜜柑。暖房はデロンギだけ。くっくっと頑張る。テレビはいらない。足先がつっついて、漫画を読んでねっころがる。そのうち、学校の話しなど、そのうち、スキーの話しなど、少しずつ話し出す。誰かが話して、誰かが囃して、誰かがちゃあんと聞いていて、誰かが願いを叶える。そんな炬燵。欲しくはありませんか?そういうとき、テレビはいらないんです。寒い夜には、人肌が恋しい。あたたかくやわらかく包むこむような、温もりが欲しい。大好きなあの人を、ボクが温めてあげようと思うけれど、湯たんぽ君に、今夜は譲るとしよう。記:とらのこども
2009.01.16
-
好きな人
好きな人が笑うと、自分もうれしい。自分も一緒に笑いたくなる。好きな人が怒ると、おろおろする。どうしたらいいんだろうって、いっぱい考える。好きな人が泣くと、抱きしめたくなる。とにかく、受け止めたいと思う。好きな人がいるっていいですね。すごく幸せなことだと思います。記:とらのこども
2009.01.15
-
良いニュースを聞きたい。
スキー旅行やイベントの話し、スイミングの進級試験の合格とか、結婚の話し、出産の話し、その他もろもろ良いニュースはあるものだ。世間にあっても、円高で良いことがあった企業もあるだろうし、原価を下げるため、海外へ出て行く企業もあるだろう。日本にあるべきものが残り、海外へ出るべきものが出て行くことになるだけ。季節の移り変わりとともに、自然とそうなるべきことが、人間の世界では、なかなかそうならない。スムーズに進むよう、政府、行政の支援があるべきだと思うけれど、多くの場合は、阻害要因の話しをよく聞く気がする。話し合えば、わかるはず。話し合えば、できるはず。ホントは、めっちゃ儲かっているんでしょ?そう聞きたい業種は、いくつもある。円安のときに高くなった品物は、そう簡単に下がりはしない。かくして、差益で儲かる業種もあるのは当然だ。それはそれでいいとして、良いニュースを作りたいものだし、良いニュースを伝えて欲しい。トヨタやソニーだけが、日本の会社ではない。これからの主役は、円高を背景とする企業であるはずだ。視点を変えてみよう。きっと良いことがいっぱい転がっていると思う。記:とらのこども
2009.01.13
-
時代の空気に流されるな
今年の年始のあいさつは、「いけませんね~、えらい不景気でさっぱりですわあ。。。」という挨拶が飛び交っている。むこうもこっちも不景気であれば、安心するし、なぜかしら、うれしくも感じる。どうして、気張らないのか?どうして、打破しようと思わないのか?時代の空気に流されてはならぬと思う。それは、自分のなかの弱気に負けているだけなのだ。考えて、考えて、考えて、できることを、一生懸命にやるだけなのだ。それは特別なことだろうか?否、それこそ当たり前のこと。安易に時代の空気に流されてはいけない。それは、自分自身のためである。それは、子どもたちの世代のためである。記:とらのこどもps うれしいことは、努力して成功することだ。 他人の窮状を喜んでいては、お天道様に顔向けできない。
2009.01.08
-
夢をつかむ、そのために。
地球上の動植物のたんぱく質は、20種類のアミノ酸から構成されており、 人間の場合、そのうちの9種類はカラダで合成されず、食事からとる必要があるので「必須アミノ酸」と呼ばれている。 ところが、原始的な生物は、それら全てのアミノ酸を体内で合成することができる。高等と言われる動植物になるほど、体内で合成できないアミノ酸が増える。なんとなく不思議だが、これには理由がある。 当然、物質合成には、手間ひまがかかる。大きいエネルギーも必要になる。いつか、なにかの突然変異で、必須アミノ酸のひとつが合成できない個体ができた。その個体は、その合成できない不備のために、自身で合成する以外の方法で、そのアミノ酸を獲得しなくてはならない。でなければ、死ぬ。具体的には食物から取得することになり、これが恒常的に満足できれば死ぬことが無い。となったとき、当該物質合成の手間ひまから解放されることになる。他の用途にエネルギーを振り向けることができる。そしてようやく生物は大型化、高等化することができたのである。何かをしないことは、他の有意義な何かにエネルギーを振り向けられる、ということだ。夢をつかむためにも、同じプロセスをたどれば有利なのは、容易に想像できる。仕事や、生活や、全てのことを自分だけでするのは不利であり、できれば避けたい。素直な気持ちで、「人に頼る姿勢」が成功を招く。優秀な技術者、研究者は、自らのプロジェクトのために、全てのエネルギーを投入する。髪はぼさぼさで、机や、研究室はごみが散乱している人は少なくない。話す言葉さえ、特異な言葉になっていくこともまれではない。そして目立たないけれども、支えてくれる人が陰にいる。かつてバンカラと言われた学生たちも、同じ様相を呈していたのではないか。学問を追いかけて、原典にあたり、議論して、また高みににじり入る。学寮や下宿のおかみさん、本屋や飲み屋の大将もやさしかった。家庭人であれば、仕事以外まったくダメね、と言われるお父さんこそが、会社ではきわめて有能だったに違いない、と思うのである。いかがであろう。昼間のパパはちょっと違うのだ。昼間のパパは光ってるのだ。そしていい汗をかいている。昼間のパパは男なのだ。(韓国語の”サナイ”の意味で)スーツもネクタイも、パンツもシャツも、妻に任せてこそ、良い仕事に注力できた。であるので、家にあっては縦のものを横にもしなかったりする。そういう、「ちゃんとだらしないパパ」は悪くない。地下鉄で、髪さらさらの高校生を見るたびに、掃除、洗濯、あまつさえ夕食の支度さえ如才なくこなすお父さんの話しを聞くたびに、どうしても違和感を憶える。何のために生まれてきたのかと聞きたくなる。夢のある、夢を追いかける男性こそが、好きだ。夢のある、夢を追いかける男性を好きになる女性こそが、大好きだ。(今の世の中であるから、逆でも良いと思います。)とりあえず、独身の20代、30代が増えている理由のひとつに、「この人がいい、この人は生きている」と感じさせる何かが、世の男性に無くなっているんじゃないか、女性たちはそれを無意識で感じているんじゃないか、などと思う。とりあえず、私は、私の家で、「ほんとダメねえ。役立たずね。」と言われるのがうれしい。名誉にかけて言い訳するが、ときどきは役に立つし、いざというときは、「やっぱりお父さん!!さすがだわあ。」と言われるときもある。記:とらのこども@ネタ切れ再掲シリーズ参考 : 忌野清志郎さん 「パパの歌」http://moocs.com/cs/catalog/moocs_song/detail/sid_498800615509100002/1.htm
2009.01.07
-
人事を尽くして。。。
なるようになる。なさねばならじ。皆様は、どちらがお好みでしょう? 何もしない。無為自然。 何かをする。有為泰然。 叫び、喚く。混乱騒然。為すべきことを為し、来るものを受け止め、どのようになろうと、生きるのみ。とはいえ、よく考えて、為すべきことをし、結果は黙って受容したい。せめて、慌てふためくのだけは、避けたい。不安をあおる言動は、ミットモナイ。記:とらのこども
2009.01.06
-
ふるさとと、ちちはは
お正月。テレビが帰省ラッシュのニュースを伝えている。「安・近・短」などと、解説者が言うけれど、帰省するというのは、そうした背景とは別だろうと思う。鮭が故郷の川を遡るのと同じ香りがする。鮭と違うのは、帰省した後に、再び都会に戻ることだ。帰省したときに、同級生に会うこともあるだろう。兄弟、親戚が集まって、宴席もあろう。ただただ、故郷の山川を仰ぎ見る人もいるだろう。恩師に会う人もあり、寺社仏閣へ参る人もあろう。そして何よりも、両親との久しぶりの再会。話題は、月並みでもいい。小遣いの多寡などどうでもいい。父母は、自分の原点である。お正月。自分の原点の再確認こそが貴重だ。きっと、また、頑張ろうと思うだろう。そんな私が思い浮かべた歌は、「かあさんのうた」皆様のお正月は、いかがだったでしょうか。素敵な今年になるようお祈り申し上げます。記:とらのこども かあさんの歌 窪田聡 作詞・作曲 http://fps01.plala.or.jp/~hojo4532/new_page_49.htm 母さんが夜なべをして 手袋編んでくれた 木枯し吹いちゃ 冷たかろうて せっせと編んだだよ 故郷の便りはとどく いろりの匂いがした 母さんが麻糸つむぐ 一日つむぐ お父は土間でわら打ち仕事 お前もがんばれよ 故郷の冬はさびしい せめてラジオ聞かせたい 母さんのあかぎれ痛い 生みそをすりこむ 根雪もとけりゃ もうすぐ春だぞ 畠も待ってるよ 小川のせせらぎが聞える 懐しさか泌み通る
2009.01.04
-
心の共鳴菅
こころのなかには、共鳴する器官があるにちがいない。ときおり、ピッと感じるセンサ部分と、「ドーン」と大きく知らせるための衝撃警報の部分と、共鳴するかどうか、検討する部分、そしてそれは、軽く素早く担当くん、ゆっくりじっくり担当さんのふたり。最期に、共鳴するための大きい「音さ」が、真ん中にすえられている。でも、共鳴stopのための部分もあるに違いない。わたしは、どうしたわけか、このこころのなかの共鳴する器官の働きを、愉しみつつ、眺めるくせ(楽しみ)ができた。自分のことなのだけれど、じっと眺めていると実に面白い。ほおー、そうきたか。ほー、やっぱりな。ほおー、我慢しちゃうんだ。共鳴したい。そういう欲求がたしかにある。本や映画だけでは、少しはできても、大きくは、ずっとは共鳴できない。ひとりでは、共鳴できないんです。だから、誰かと一緒に、共鳴させて欲しいと願う。ぐわああんと鳴り響き、トドロカセタイ。記:とらのこども@休日再掲シリーズ
2009.01.04
-
謹賀新年
皆様、健やかに初春をお迎えのこととお慶び申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。ブログの世界は、「往来」のようなものかもしれませんね。行き交う人や車のごとく、多くの文章が通り過ぎる。ニアミスもあれば、事故もある。温かい励ましもあれば、示唆もある。そしてまた、記憶に残る記事もある。皆様から、多くのご指導、ご支援をいただいた昨年でした。本当にありがとうございます。というわけで、本年も相変わらずよろしくお願い申し上げます。小生も、相変わらず、思うまま、徒然のブログをお届けします。とらのこども拝 今年の抱負 「考えろ、考えろ、考えろ!」です。
2009.01.04
全39件 (39件中 1-39件目)
1