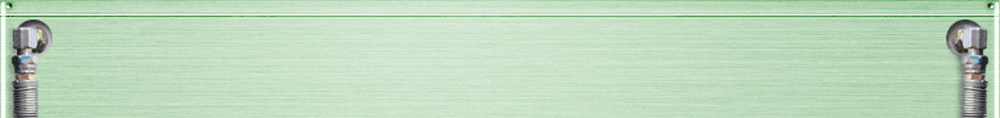全て
| カテゴリ未分類
| プレスリリース
| ドライアイ
| 文献発表
| 厚生労働省通知
| 妄想
| 新聞報道
| お勉強
| 前立腺がん
| 医療費
| 原発
| 制がん剤
| 政治
| 自閉症
| 子宮頸がんワクチン
| 哲学
| 宣伝
| 憲法
| 医療用医薬品
カテゴリ: カテゴリ未分類
腸内細菌叢の乱れはさまざまな病気を引き起こすことが知られていますが、命にかかわる問題としては骨移植後に腸内細菌叢が乱れ、移植の成功率が減ることです。
プロバイオティクスや糞便移植は“「有益な菌を投与することによる治療」であり、どちらも腸内の環境の変化をともなわなければ、効果の持続性は見られず、プロバイオティクスでは飲むのを止めるとすぐに腸内細菌叢は元に戻っていることが多くの文献で明らかになっています。(実際にどれぐらいで元に戻るのかは実験条件:中止後の腸内細菌叢を計った日数に影響されるので、詳しくは分かりませんが、大抵は6週間後が測定日でその効果は投与前と同様になっています。
2017年10月25日の北海道大学の プレスリリース によれば
α-ディフェンシンは経口投与でも効果がある事がマウスによって確かめられています。
パネト細胞増殖因子の投与やα-ディフェンシンの投与が腸内細菌叢の正常化に役たつことが分かりました。
今後は人でも同様の機能が働いているかの確認が必要ですが、まずは骨髄移植時の腸内細菌叢の乱れを予防するということに限って臨床に持って行ける可能性を追求してもらいたいものです。
プロバイオティクスや糞便移植は“「有益な菌を投与することによる治療」であり、どちらも腸内の環境の変化をともなわなければ、効果の持続性は見られず、プロバイオティクスでは飲むのを止めるとすぐに腸内細菌叢は元に戻っていることが多くの文献で明らかになっています。(実際にどれぐらいで元に戻るのかは実験条件:中止後の腸内細菌叢を計った日数に影響されるので、詳しくは分かりませんが、大抵は6週間後が測定日でその効果は投与前と同様になっています。
2017年10月25日の北海道大学の プレスリリース によれば
R-Spondin11と呼ばれる腸の粘膜の細胞を増殖させるタンパク質が,腸内で高い殺菌作用をもつα-ディフェンシンを分泌するパネト細胞を増殖させ,α-ディフェンシンの分泌量を増加させることを発見。つまり、腸内細菌叢を調節するタンパク質が腸内細菌叢を正常化させるような(必要な菌は殺さず、不要な菌には殺菌的に働く。)と言うことです。
α-ディフェンシンは経口投与でも効果がある事がマウスによって確かめられています。
パネト細胞増殖因子の投与やα-ディフェンシンの投与が腸内細菌叢の正常化に役たつことが分かりました。
今後は人でも同様の機能が働いているかの確認が必要ですが、まずは骨髄移植時の腸内細菌叢の乱れを予防するということに限って臨床に持って行ける可能性を追求してもらいたいものです。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.