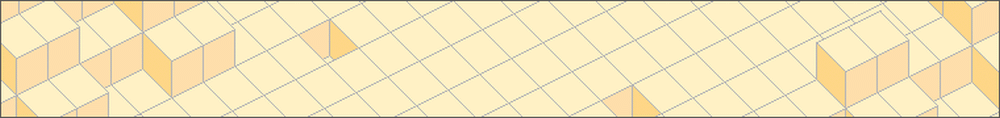2010年01月の記事
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-

佐藤由規、速球で抑え込む
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■8回表、プロ選抜のマウンドにヤクルト・佐藤由規(仙台育英高)が立った。そして高校時代と同様、全11球の内10球を速球で勝負し、3人の打者を打ち取った。9番・途中出場の小野紘明(亜細亜大3年、中京高)に対しては、初球を150kmの速球でど真ん中に放り込んだ。2球目は149kmの速球、これを小野は振り遅れて空振り。3球目は速球を内角に投げ込み(147km)、どん詰まりの二ゴロに抑えた。1番・伊志嶺翔大(東海大3年、沖縄尚学高)にはコントロールが乱れ気味だったが、フルカウントから6球目に149kmの速球を投げ、これもどん詰まりの二ゴロに抑えた。■佐藤由規。仙台育英高時代は、3度甲子園に出場している。2006年夏、そして翌07年のセンバツと夏。ボクが最も印象に残っているのは、07年夏に行われた対智弁学園高戦だ。この試合の序盤、スピードを抑えて制球を重視した投球だった佐藤由規。だが4回になってスピードが急上昇。そしてついに155kmを計測し、スタンドからは「うぉっー」と、大歓声が起きた。※155kmは、日南学園高・寺原隼人(現・横浜)が記録した最高記録154kmを上回る記録だった。これでスピードへの欲が目覚めたのか、由規には次第に「力み」が見られるようになり、味方野手の失策や不味い連携プレーも重なって、5回の大量失点につながった。結局智弁学園に敗れてしまったが、ヘタに155kmの速球を投げてしまったことが、由規が自らリズムを狂わせてしまったように、ボクには思えたのだ。(2回戦、2007年8月15日)育 000 000 002 =2智 000 050 00X =5(育)佐藤由、(智)内之倉-阪口今日も1クリックお願いします
2010.01.30
コメント(2)
-

大学野球と観客数
早大の第100代主将に就任した今秋ドラフトの超目玉・斎藤佑樹投手(3年)が28日、都内で行われた東京六大学野球連盟の理事会に初出席。学生服姿で新理事として初仕事をこなし、学生の観客動員増を呼びかけた。新年度初の理事会で、観客動員対策活性化委員会の設置が決定。4月の春季リーグでは前年(全35試合で30万1000人)比10パーセント増を目指す。近年、学生の来場者数が減っており、「もっと来てもらえるような対策を考えなきゃいけない」と斎藤。同連盟は800円の学生割引席の新設を決定、広報紙も作り、来場者などに配る方針も固めた。 (スポーツ報知)■早稲田大・斎藤佑樹(3年、早稲田実)のコメントに対し思うのは、「現役の一選手が集客のことまで考えなければならないのか?」ということ。ただ連盟にとって観客増に向け、人気・知名度で群を抜く斎藤がどうしても必要という事情もあるんだろうけど。今年は斎藤にとってのラストイヤー。今年の観客動員数も大事だけれど、来年以降はもっと深刻なのだ。詳しい観客動員数の推移を調べてコメントを書きたかったけれど、残念ながらそのデータが見つからなかった。仕方がないので断片的な情報(『スポーツ報知』『TOKYOHEADLINE』より引用)に、推測を加えざっくりまとめると、次のようになりそうだ。「戦後、次第に人気が盛り上がった東京六大学リーグは、1954年および74年頃は50万人(1シーズンあたり)を動員したことがあった。だが次第に低迷し、2000年~2006年頃までは20万人前後(同)に。そして斎藤ら88年組が大学に入学した2007年以降は30万人(同)に若干上昇している。ただ盛り返しているといっても、絶頂期の6割程度でしかないが・・・」■以下、『TOKYO HEADLINE』より引用。1925年(大正14年)に発足した東京六大学リーグが発足、学生野球の最高峰として人気が高まった。戦後は、試合前日から徹夜で並ぶ観客もいるほどで1シーズンの観客動員数が50万人に達したこともあった。例えば立教大に長嶋茂雄さんが入学した54年(昭和29年)や、昭和の怪物・江川卓さんが作新学院高から法政大に進学した74年(昭和49年)などが人気の絶頂だったとされている。だが、ここ数年は1シーズン20万人前後で推移。06年春のリーグ戦では"ドル箱"の早慶戦が、3試合計で4万9000人。うち2試合が平日開催という点を考慮に入れても、01年春には2試合で6万8000人を集めていた。低迷は続いている。 (以上、『TOKYO HEADLINE WEB』2006年9月24日)■凋落ぶりの大きい東京六大学リーグだけど、先日、絶頂だった頃の映像を見た。それはNHKのテレビ番組(※)でのこと。立教大・長嶋茂雄さんがレフトスタンドに本塁打を打つシーンが白黒映像で映っていてた。その場面を見てボクが驚いたのは、長嶋の豪快な打球よりも観客数の多さ。たぶん映像は58年(昭和33年)頃のものだと思うけど、外野席にまで人・人・人・・・。観客でギッシリと埋まっていたのだ。まさに人気絶頂の頃の映像。今では早慶戦だってお目にかかれない光景だった。(※)テレビ番組『ONの時代 スーパーヒーロー50年目の告白』(NHK、2009年9月21日放送)。■東都大学リーグも同じ。今は閑古鳥が鳴いている状態だけど、以前は違った。観客席が人・人・人で埋まっていたことがあったようだ。ボクはそのことをブログ「応援します 東洋大野球部」で知った。このブログでは、東洋大が初優勝した時の新聞(昭和51年秋)が紹介されていた。掲載された写真に写っているのは、内・外野席をギッシリと埋めた人・人・人・・・。東京六大学リーグ同様、この観客の多さは、現在と比較すると感動的ですらあるのだ。「応援します 東洋大野球部」はこちらです。今日も1クリックお願いします
2010.01.30
コメント(4)
-

岩崎恭平、東海大時代のこと
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■両チームを通じ、この試合には計48人の選手たちが登場した。そして最後の48番目に出場した選手は中日・岩崎恭平(東海大相模高-東海大)だった。出番が訪れたのは9回裏二死の場面。粘りに粘って右前安打を放った嶋基宏(楽天、中京大中京高-國學院大)の代走として岩崎が登場した。だが次打者の坂本勇人(読売、光星学院高)が菅野智之(東海大3年、東海大相模高)の2球目を打ち、あっさり三ゴロに倒れて万事休す。岩崎は見せ場を作ることなく試合は終わってしまった。■岩崎恭平にとって、大学日本代表の1番を務める伊志嶺翔大(3年、沖縄尚学高)は東海大の2年後輩に当たる。また菅野は東海大の3年後輩だ。また大学代表の各選手たちとの関係も深い。08年の全日本大学野球選手権・準決勝では、野村祐輔(当時・1年、広陵高)や荒木郁也(当時・2年、日大三高)のいた明治大との対戦を経験。また決勝では乾真大(当時・2年、東洋大姫路高)や林崎遼(同)のいた東洋大とも対戦をした。結局この大会では、岩崎のいた東海大は東洋大に敗れ、前年に続く準優勝に終わった。だが準決勝の対明治大戦の「大逆転劇」は、記録にも記憶にも残る「迷」試合。明治大が6点をリードした後、東海大が5回に一挙16点を奪って逆転勝利したとんでもない試合だった。スコアは次のとおり。(準決勝、東海大vs明治大 2008年6月14日)明 303 0 0 0 001 =7海 000 016 0 10× =17 (明)江柄子-岩田-野村-近藤-門田、(海)杉本-中西-小松崎■また、2008年7月に開催された第4回世界大学野球選手権(於:チェコ)に、岩崎は日本代表選手として選出されている。この時のチームメイトには斎藤佑樹(当時・早稲田大2年、早稲田実)らがいた。 ※本日(2010年1月27日)、このブログのアクセス数が100万件を突破いたしました。これまで訪問していただいた皆様に深く感謝申し上げます。今日も1クリックお願いします
2010.01.27
コメント(2)
-

田中浩康の高校・大学時代
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■東京六大学リーグで100本安打を放った実績を持つ田中浩康(現・ヤクルト、尽誠学園高-早稲田大)は、プロ選抜のスタメン・6番(セカンド)に名を連ねた。1打席目は2回裏。この回の先頭打者として東洋大・乾真大(3年、東洋大姫路高)と対戦した。乾は(緊張感が解けなかったためか)制球が定まらず田中は四球を選んで出塁。その後に「足」を見せて二盗に成功した。(大学代表の捕手は青山学院大の小池翔大)2打席目は4回裏。一死一塁の場面で登場し亜細亜大・東浜巨(1年、沖縄尚学高)と対戦した。カウント1-1からの3球目に一塁走者(代走)の小窪哲也(現・広島、PL学園高-青山学院大)が二盗に失敗。二死走者なしになった場面で、東浜の外角への速球(143km)に空振りの三振を喫した。■田中浩康。京都出身だが、高校は「野球どころ」香川県にある尽誠学園高に進学。1998年夏(1年時)と翌99年夏(2年時)の2度、甲子園に出場した。98年夏は初戦に市立船橋高と対戦。田中のスクイズで勝ち越した後は猛打炸裂、結局12-3で大勝した。だが2回戦は関大一高と対戦、延長10回に関大一高のサヨナラ・スクイズで惜しくも敗退した(スコア3-4)。この時、関大一の投手は現・阪神の久保康友。99年夏は初戦に古豪・松商学園高に6-3で勝利したが、2回戦で智弁和歌山高にスコア0-2で惜敗した。■大学は早稲田大。青木宣親(現・ヤクルト、日向高)や鳥谷敬(現・阪神、聖望学園高)、武内晋一(現・ヤクルト、智弁和歌山高)とはチームメイトだった。そして記念すべき100本安打を記録した打者のひとりでもある。田中の記録は102本。これは東京六大学リーグの通算最多安打22位(09年末現在)に位置する。ちなみに同じ102安打の記録を持つ選手は3人いる。田中のほかには慶応義塾大の山下大輔(現・ドジャースのルーキーチーム守備コーチ、清水東高)と早稲田大のチームメイトだった武内。また02年には第1回世界大学野球選手権の日本代表チーム・メンバーに選出され、銅メダルを獲得した。この時のチームメイトには立教大の多田野数人(現・日本ハム、八千代松陰高)、早稲田大の和田毅(現・ホークス、浜田高)や鳥谷、そして日本大の村田修一(現・横浜、東福岡高)らがいた。あっ、そうそう・・・。J-SPORTSでこの試合を解説していた山中正竹さんが、この時の日本代表チームの監督だった。 今日も1クリックお願いします
2010.01.26
コメント(0)
-

亀井義行の高校・大学時代
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■オーバーエイジ枠に27歳で出場した亀井義行(読売、上宮太子高ー中央大)は、プロ選抜の中軸・5番に座った。1打席目(1回)は、早稲田大の斎藤佑樹(3年、早稲田実)と対戦して一ゴロ。2打席目(4回)は亜細亜大・東浜巨(1年、沖縄尚学高)から左飛。3打席目(6回)は早稲田大・大石達也(3年、福岡大大濠高)からは3球三振と、軽く捻られた格好(?)。そして4打席目(8回)は東海大の菅野智之(2年、東海大相模高)と対戦し三邪飛に倒れた。(あぁ、4タコ・・・)■亀井義行。松本哲也(読売、山梨学院大付高ー専修大)や嶋基宏(楽天、中京大中京高ー國學院大)と同じ東都大学リーグ出身だが、彼らとは違い神宮第二球場(2部リーグ)の経験はない。1年春から4番を打ち、幸運にも常に1部リーグで試合をすることができた。そして4年時には通算100安打を放ち、25年ぶりのリーグ優勝(2004年秋)に貢献。また同年、日米大学野球に代表選手(東京地域代表枠)として選出されているが、その時のチームメイトには東北福祉大の3年生だった根元俊一(現・ロッテ、花咲徳栄高)がいた。■上宮太子高時代は一度だけ甲子園に出場している。それは2000年センバツのこと。だが初戦で明徳義塾高に3-9で大敗している。この時、亀井はチームのエース。だが完投したものの被安打15(本塁打1、三塁打2、二塁打3)と散々な出来だった。中央大に入学後、野手に転向した(大学入学直後は遊撃手、その後外野手に)。今日も1クリックお願いします
2010.01.25
コメント(0)
-

根元俊一と日大三高勢
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■8回裏、二死一・三塁のチャンスの場面にロッテ・根元俊一(花咲徳栄高-東北福祉大)が代打で登場した。大学日本代表の投手は、この回途中から登板した菅野智之(東海大2年、東海大相模高)。カウント1-1となった2球目、一塁走者の天谷宗一郎(広島、福井商高)が二盗に成功し、走者が二・三塁に。根元にとってオイシイお膳立てが出来上がったが、3球目(143kmの速球)、そして4球目(95kmの変化球)をいずれも空振り。結局、三振に終わってしまった。■根元俊一。花咲徳栄高の3年時(2001年)、主将としてチームを夏の甲子園に導いた。埼玉県大会の準決勝は、春日部共栄高戦に4-0のシャットアウト勝ち。続く決勝は春日部東高に1-0で辛勝し、甲子園切符をGETした。※この大会、優勝候補はエース大竹寛(現・広島)を擁した浦和学院高だったが、準々決勝で春日部共栄高に逆転負けし、早々に姿を消していた。■根元のいた花咲徳栄高の甲子園の成績。初戦は宇部商高に12-0で大勝したが、2回戦はこの大会で優勝した日大三高に4-11で大敗。この時、日大三高には後にドラフトで同時指名される選手が4人もいた(史上最多タイ記録)。その4選手とは、投手の近藤一樹(現・オリックス)、3番・中堅手の内田和也(元・ロッテ)、1番・二塁手の都築克幸(元・中日)、そして控えだった千葉英貴(元・横浜)のこと。■ちなみに大学日本代表のメンバー・阿部俊人は、根元の高校、大学を通じての後輩である。 今日も1クリックお願いします
2010.01.24
コメント(0)
-

天谷宗一郎と内海哲也、過去の対戦
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■天谷宗一郎(広島、福井商高)は、プロ選抜の3番・レフトで出場した。第1打席は初回、無死一・二塁のチャンスにまわってきた。だが、斎藤佑樹(早稲田大3年、早稲田実)の速球を叩いて平凡な二ゴロ。4-6-3と転送される併殺に終わった。ただ2打席目は中央大・澤村拓一(3年、佐野日大高)から内野安打。4打席目は明治大・西嶋一記(3年、横浜高)から中前に安打を放ち存在感を見せつけて、1打席目の汚名返上を果たした。さらに天谷、5回は守備でも魅せた。越前一樹(立正大3年、横浜高)の左中間への飛球を好捕するファインプレー。グラブをはめた右手を思い切り伸ばし、逆シングルで捕球する姿は間違いなく格好よかった。■天谷宗一郎。福井商高時代は3度、甲子園に出場している(2000年夏、2001年春と夏)。00年夏、福井県大会・決勝は不祥事でセンバツ大会の出場を辞退していた敦賀気比高と戦った。そして延長の末に勝利し、甲子園出場を決めた。この時、敦賀気比高には内海哲也(現・読売)がいた。(福井県大会決勝、2000年7月31日)福井 010 010 000 1 =3敦賀 002 000 000 0 =2(福)吉田-山岸、(敦)内海?01年のセンバツは、初戦で桜美林高に11-9で勝利したものの、2回戦で浪速高にスコア6-7で敗退した。この時、浪速高には現・オリックスの大引啓次(法政大)がいた。 今日も1クリックお願いします
2010.01.24
コメント(0)
-

前田健太、プロの貫禄
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■プロ選抜の先発は広島・前田健太(PL学園高)だった。大学日本代表の先頭打者は伊志嶺翔大(東海大3年、沖縄尚学高)。その伊志嶺は試合前に話していた。「(前田の初球は)速球に違いない。その初球を狙いたい」。前田はその要求どおりに速球を投げる。球速は143km。待ち構えたように伊志嶺がフルスイングをしたが、打球はどん詰まり。ファーストへのフライになり、前田vs伊志嶺の同級生対決は前田の貫禄勝ちで終わった。次打者の法政大1年の多木裕史(坂出高)に対しては、初球は141kmの速球(ストライク)、次に落ちる変化球(空振り)でカウントを整えると、フィニッシュは内角ぎりぎりに144kmの速球。多木を中途半端なスイングの空振り三振に仕留めた。前田、背中につけた「18」がやけに大きく見えた。■前田健太。 高校時代は甲子園に2度出場しそれなりに話題を集めた選手だった。1年時の夏(04年)は中山怜大(現・立教大4年)や荒木郁也(現・明治大3年)らがいた日大三高と対戦し初戦敗退。3年時はセンバツ(06年)ではベスト4に進出したものの、準決勝で清峰高にスコア0-6で敗退した。※3年時のチームメイトには岡崎啓介(現・立教大3年)らがいた。ボクにとって印象的だった前田のプレーは投球ではなく「走塁」。それは準々決勝の秋田商高戦(06年4月1日)のことだった。この試合の2回表、二塁打で出塁した前田が犠打で三進した直後にホームスチールを試みた。秋田商のバッテリーはまったく無警戒だったため生還に成功し、この走塁でチームを勢いに乗せて結局スコア4-1で完勝した。PLのエースで4番だった前田は、「投」と「打」だけでなく「走」にも優れた野球センス溢れる球児だった。■また高校時代、大阪府大会でライバルだったのは辻内崇伸(現・読売)や中田翔(現・日本ハム)らがいた大阪桐蔭高。前田が2年時(05年)に甲子園出場を逃したのは、この大阪桐蔭に敗れたため。 今日も1クリックお願いします
2010.01.23
コメント(4)
-

秦真司さんのこと
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■この試合を中継していたJ-SPORTS、山中正竹さん(佐伯鶴城高-法政大)とともに解説を務めていたのは秦真司さん(鳴門高-法政大)だった。今日は、その秦真司さんのこと。ボクは秦さんの野球解説を初めて聞いた。山中さんは実況の島村俊治さんや同じ解説者の秦さんに気を使い、注意深そうにコメントを言っていたのに比して、秦さんのコメントは奔放。法政大の大先輩・山中さんのコメントに口をはさむシーンもあった。投手出身の山中さん、捕手出身の秦さん。出身のポジションからは、2人はまるで逆の性格のようにボクには思えた。(以下、敬称略)■秦の法政大時代。それまで正捕手だった木戸克彦(現・阪神ヘッドコーチ、PL学園高-法政大)の卒業後、その座を掴んだのが(たしか)この秦だった。ボクは残念ながら、彼の大学時代のプレーを詳しくは憶えていないが、ひとつだけ記憶しているシーンがある。それは、リーグ戦のある試合であったホームベース上のクロスプレー。本塁を目がけて突進する相手チームの走者。一方、外野からの返球をミットに収めて待ち構える秦捕手。タイミングは完全にアウトだったが、走者は体当たりを試みて、秦はその力に負けて突き飛ばされてしまったのだ。怒り心頭の秦、起き上がりざまその走者を睨みつけ、一触即発の空気がグラウンドに漂った。結局、何事も起きなかったものの、その時の鼻っ柱の強そうな秦の表情が妙にボクの記憶に残っている。■法政大卒業後はヤクルトに入団(1984年)、そして87年からは正捕手の座を獲得した。そして91年からは得意の打撃を活かすため外野手に転向。その後、日本ハムやロッテを主に「代打屋」として渡り歩いた。90年、正捕手から外野手に転向せざるを得なかった原因は、この年ヤクルトの監督に就任した野村克也(楽天・前監督)にあった。そのエピソードが書籍『プロ野球の一流たち』(二宮清純著、講談社現代新書)に書かれていたので、以下にその一部(3頁)を引用します。(※秦さん自身は思い出したくないことかもしれないし、別に悪く言う意図もないのだけど秦さんの転機について書かれており、また野村元監督の「根拠を重視する」考え方がはっきり出た内容だったので、引用します)当時ヤクルトには秦真司というレギュラー捕手がいた。守りはそこそこだったが、バッティングには光るものがあった。我慢強く使っていた野村だったが、ある日、ついに堪忍袋の緒が切れた。ノースリーのカウントで秦はピッチャーに変化球を要求したのだ。野村の回想---。「これはもうダメだと思いましたね。なぜ、ど真ん中にストレートを投げさせないのか。それでベンチに帰ってきた秦に『あんなもん、ど真ん中のまっすぐに決まっとるやないか。なんで変化球なんだ?』と聞いた。百歩譲ってバッターが4番ならわかりますよ。しかし下位打線なんだから。相手からしたら、一人でもランナーをためたい場面。何をどう考えても変化球のサインはありえないんです。すると秦、シラーッとした表情で『いやぁ、ひょっとしたら振ってくるかもしれませんから』と言った。(中略)振ってくると判断したらしたで、その根拠を示さなくちゃいけない。ひょっとしたら、というのはサインを出す根拠にはならないんです。この時点で僕は秦を見限った。それでルーキーの古田を使うことに決めたんです」(以上、『プロ野球の一流たち』)今日も1クリックお願いします
2010.01.20
コメント(3)
-

「あの時」の小林繁さん
■以下、サンケイスポーツより。「江川卓投手との交換トレードで阪神に移籍したことで知られる、巨人や阪神で投手として活躍した現日本ハム1軍投手コーチの小林繁氏(57)が17日、心不全のため亡くなった。57歳だった」「引退後はテレビ、ラジオ解説者を経て97から01年までは近鉄で、07年には韓国のSKワイバーンズで、08年からは日本ハムでコーチを務めていた。通算成績は374試合に登板、139勝95敗17セーブ、防御率は3.18。最多勝利に1度、最優秀投手に2度輝いている。沢村賞、ベストナインも2度選ばれている」(以上、サンケイスポーツ)■小林繁さんが亡くなった。昨日(1月17日)、ボクはテレビを見ていなかったので、このニュースを今日の朝刊で知った。小林繁さんといえば、まず思い出すのは「空白の一日」(1978年11月21日)のこと。当時クラウンライターライオンズの代表だった坂井保之氏の著書『深層「空白の一日」』(ベースボールマガジン社新書)で、小林さんの阪神へのトレードが決まった直後の経緯を次のように記している。以下、同著(86頁)より引用。小林投手はキャンプイン前日、羽田空港から巨人職員に連れ戻され、阪神へのトレードを通告された。この突然の変化にファンは驚き小林に同情を寄せたが、「同情していただかなくても結構です。ぼくは野球をやるだけです」と言って、この健気な態度で男をあげた。ちなみにその年(79年)小林は対巨人戦8勝0敗の好成績を挙げ、自分を売った古巣に一矢を報いた・・・。(以上『深層・・・』)■つい先ほど、ボクは近鉄バファローズが最後の優勝を決めた試合のビデオ(2001年9月26日)を見ていた。北川博敏(現・オリックス、大宮東高-日本大)の逆転サヨナラ満塁本塁打で逆転勝利を決めた試合だ。この年、小林繁さんは近鉄の投手コーチを務めていた。梨田昌孝監督(現・日本ハム監督)が表彰式でチャンピオンフラッグを受け取った後、近鉄の首脳陣や選手たちは大阪ドーム(旧称)をグラウンドパレードが始まった。(ボクは小林コーチの姿をテレビ画面から追ってみた)先頭に梨田さんが立ち、そして中村紀洋(現・楽天、渋谷高)、水口栄二(現・オリックスコーチ、松山商高-早稲田大)、吉岡雄二(現・メキシカンリーグ・ヌエボラレドオウルズ、帝京高)、盛田幸妃(函館有斗高)らがチャンピオンフラッグを握りしめてグラウンドを一周していた。その脇ではタフィ・ローズ(現・オリックス)がひとり離れてスタンドに向かって万歳!を繰り返し、少し遅れて門倉健(現・韓国SKワイバーンズ、聖望学園高-東北福祉大)や三沢興一(現・米独立Lロングビーチアーマダ、帝京高-早稲田大)らがジャレあって歩いている。(まだ小林コーチの姿が見えない・・・)少し遅れて見えたのは、ジェレミー・パウエル(現・米3Aインディアナポリス・インディアンス)。そして高村祐(現・楽天コーチ、宇都宮南高-法政大)、益田大介(現・楽天ジュニアコーチ、滝川二高-龍谷大)、柴田佳主也(明石高)、大塚晶則(元・レンジャーズ、千葉敬愛高-東海大)、香田勲男(現・読売コーチ、佐世保工高)、前田忠節(現・四国九州IL香川オリーブガイナーズコーチ、PL学園高-東洋大)らが続く。髪をハデな金色に染めた前川勝彦(元・米3Aメンフィスレッドバーズ、PL学園高)も見える。■そして最後の集団を正田耕三コーチ(現・オリックスコーチ)らとともに歩く小林コーチの姿を、やっと見つけることができた。付けていた背番号は「70」。表情は特に嬉しいというのでもなく、どちらかというと無表情・・・。この直後に(優勝したものの)投手陣の不成績(防御率5点台)の責任をとって退団したのだから、この優勝が決定した瞬間には、すでにその意思を固めていたのかも知れない。合掌。 今日も1クリックお願いします
2010.01.18
コメント(2)
-

危なかった・・久米勇紀
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■「まるで手投げですね」。テレビ解説(J-SPORTS)をしていた秦真司さん(群馬ダイヤモンドペガサス監督、鳴門高-法政大)は、5回表に登板したプロ選抜の久米勇紀(ホークス、桐生一高-明治大)の投球を見て苦言を呈した。久米は昨年6月、故障で戦列を離れて以来、久々の投球だった。実戦感覚がまだ戻っていなかったかもしれないが、対戦した大学日本代表の3人の打者すべてにバットの芯で捕らえられた。■5番・越前一樹(立正大3年、横浜高)には146kmの速球を左中間に運ばれた。レフト・天谷宗一郎(広島、福井商高)の逆シングルの好捕で救われたが、通常なら二塁打コースの当たりだった。明治大の後輩、6番・荒木郁也(明治大3年、日大三高)にはピッチャー強襲な当たりを浴び(記録は投ゴロ)、7番・萩原圭悟(関西学院大1年、大阪桐蔭高)にも強い打球を打たれた(記録は一ゴロ)。■久米勇紀。桐生一高3年の時に甲子園に出場し、主将として桐生一高をベスト4に導いた(03年)。そして準決勝では常総学院高と対戦し逆転負けをしたが、その時常総学院高には大崎雄太朗(現・西武、青山学院大)がいた。今日も1クリックお願いします
2010.01.16
コメント(0)
-

新井貴浩、歴史的試合の初打点
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■「この歴史的な試合に出場できて嬉しい。若い気持ちに戻って、いま自分が持っているすべてを出したい」 今季(09年)の成績が思わしくなかった新井貴浩(阪神、広島工高-駒澤大)は、32歳ながらオーバーエイジ枠(27歳以上)に自ら志願。そして、「お世話になった大学野球に恩返しをしたい」と、意気込みを話していた。■新井はプロ選抜の4番に座った。初打席は初回、二死三塁の場面でまわってきた。相手投手は、大学日本代表の先発・斎藤佑樹(早稲田大3年、早稲田実)。初球 147kmの速球が外角へ。ボール2球目 速球が今度は内角へ。ボール3球目 138kmの変化球が内角へ。ファール4球目 内角低めに落ちる変化球。これもファール。試合前、大学日本代表の榎本保監督(近畿大)は、「プロの打者は外のコースを巧く捌(さば)くから、内側を攻めろ」と斎藤に指示を出し、その指示通りに内角を上手に攻めていた斎藤。そして5球目。バッテリーのサインが合わず一拍の間をおいた後、捕手の小池翔大(青山学院大3年、常総学院高)は外側にミットを構えた。だが、斎藤の投げた球は「逆球」となって、なぜかド真ん中へ。新井はその絶好球を右に弾き返す。打球は一・二塁間をゴロで抜けていき、ライト前に達した。この新井の適時打がプロ選抜の先制点になった。※(ボクの記憶に間違いがなければ)プロと大学生の現役選手どうしが戦う、戦後初めての試合で、新井は記念すべき最初の打点を挙げた打者ということになる。※上記の青い文字はJ-SPORTSの実況から引用。■新井貴浩。駒澤大在学時の監督は、太田誠さんだった。太田さんの座右の銘は「姿即心、心即姿」。姿すなわち心を表し、心すなわち姿を表す・・・。新井の駒澤大時代、太田監督に怒られたエピソードを。以下、ブログ「とよのひとりごと・・・」より引用。ある打席で新井選手、甘い球を見逃し、「しまった」という顔をしたそうです。結局、その打席は凡退してしまうのですが、太田監督は凡退したことではなく、「しまった」という表情に関して注意します。そのココロは・・・「あの表情に、お前の弱さが出ている。敵に隙を見せるな」ここに「姿即心」の真意が見えるのではないでしょうか。確かに、甘い球を見逃したら、「しまった」となるのも無理はありません。しかし、そこで勝負あったも同然なんですよね。投手側としては、優位な気持ちで勝負を進めることができますから。今日も1クリックお願いします
2010.01.16
コメント(4)
-

和製長距離砲・岡田貴弘
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■2回裏、”なにわのゴジラ”ことオリックスの岡田貴弘(履正社高)は、大学日本代表の乾真大(東洋大3年、東洋大姫路高)と対戦した。岡田は今後大いに期待される”和製長距離砲”である。ただこの打席はちょいとガッカリさせられた。1球目 119kmの変化球、ストライク2球目 133kmの高めの球を叩いてファールそして3球目、タイミングを外す変化球に、岡田の力のないスイングでバットは空を斬った(空振り三振)。すぐさま、すたこらとベンチに向かって駆けた。J-SPORTSの解説者・山中正竹さんは、「速球には対応できますが、このへん(変化球への対応?)がまだ甘いですね」と岡田についてコメントした。■岡田貴弘。履正社高時代に甲子園の出場経験はないが、通算55本塁打を放つスラッガーだった。3年生の夏には、大阪大会準決勝で中田翔らを擁する大阪桐蔭高と対戦したこともある。その試合では、中田翔からバックスクリーンへの3ラン本塁打を放ったものの、敗れてしまい、甲子園切符をゲットすることはできなかった。 (wikipediaより引用)この時の大阪桐蔭高には中田翔のほかに現・中日の平田良介、現・読売の辻内崇伸、そして現・関西学院大の萩原圭悟(1年)がいた。■09年10月、一般に公募して決まったニックネームは”T-岡田”(ティー・おかだ)。今日も1クリックお願いします
2010.01.14
コメント(0)
-

阿波野秀幸。
■昨日付の日刊ゲンダイが自主トレに励む西武・菊池雄星のコメントを報じていた。「フォームを固める時に気をつけるのは小さくまとまらないこと。今はスピードを気にせず、一番大きなフォームで、(自分の)いいところを探しています。この時期しかフォームをいじられませんから」 (以上、日刊ゲンダイ)■この「この時期しかフォームをいじられませんから」という菊池のコメントを読んで、ボクは元近鉄のエース・阿波野秀幸(横浜市立桜丘高-亜細亜大)のことを思い出した。あの時、阿波野も「開幕前の時期しかフォームを変えることはできないんだぞ!」と、胸の内で叫んでいた投手の一人だった。■あの時とは、1990年(平成2年)のこと。そして、きっかけになったのはボークのルール変更だった。阿波野秀幸。近鉄に入団後、驚異的なペースで勝ち星を挙げた。87年から89年の3年間に48勝(32敗)。持ち球のスクリューボールは有名だけど、それだけでなく牽制も得意とした投手だった。ところが90年、ボークのルールが急きょ変更になり、阿波野は投球フォームの改造を余儀なくされた。それでも自分の得意な牽制技術をその後も活かすため、キャンプでは何度も何度もフォームの確認を審判に依頼し、お墨付きをもらった上でシーズンに臨んだ。■しかし、いざシーズンが始まると、一塁に牽制するたび審判は「ボーク」と判定した。以下、『野球狂列伝』(澤宮優著、河出書房新社刊)より71頁を引用。 牽制ができなくなれば、盗塁されないためにクイックモーションで投げるしかなくなる。シーズン中にフォームの矯正をしなければならないため、当然無理が生じた。シーズン前に指摘されれば、準備を十分にして公式戦に臨めたが、さすがにシーズン中に指摘されたのは痛かった。阿波野はこのときの驚きを語る。「一番つらかったのはシーズン途中でボークになったことです。正直『泡食った』というか、それなりに自分で絶対的な自信のある技術だったので、それができないことで精神的にハンディを背負ってしまった。それに伴って盗塁されない技術練習を今以上にしなければならなくなった。シーズン中にそういう対策をする練習が続いたんですね。今から考えると異常なことで、登板と登板の間にその練習をずっとやりました。結果は疲れたまま次の登板を迎えるということで、肘を壊していしまいました。でも痛いですから投げられませんと簡単に言える時代でもなかったですから、我慢して投げました。今だったら言えるでしょうけどね」 (以上、『野球狂列伝』)■愚痴など言わず阿波野は頑張った。なんとか新しいルールに対応した投球術を身につけようと踏ん張り続けた。でもその後、無情にも勝ち星は激減した。90年に10勝を挙げた以降は読売、横浜を渡り歩き、90年から引退するまでの11年間の勝利数は27(36敗)。最後まで実力どおりの活躍をすることなく、阿波野の14年間の現役生活は2000年に幕を閉じた。阿波野の通算成績。305試合、1260イニング、75勝68敗5セーブ、防御率3.71。 今日も1クリックお願いします
2010.01.13
コメント(8)
-

大崎雄太朗の高・大学時代
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■7回裏、無死一塁のチャンスに、途中からレフトの守備についていた大崎雄太朗(西武、常総学院高-青山学院大)が左打席に立った。大学日本代表の投手は、明治大の野村祐輔(2年、広陵高)。初球 117kmの変化球が外角に外れてボール2球目 121kmの変化球、これもボール3球目 127kmの落ちる変化球を空振り(ストライク)4球目 111kmのカーブ、ストライクそして5球目は127kmのチェンジアップ。これを大崎は空振りし、三振を喫した。コースこそ甘かったものの、動くボールで大崎は完全にタイミングを外されてしまった。■大崎雄太朗。昨日このブログに書いた嶋基宏(現・楽天、中京大中京高-國學院大)や松本哲也(現・読売、山梨学院大付高-専修大)と同じ東都大学リーグの出身だが、2部リーグの経験はない。常に「陽のあたる」東都の王道を歩んできた選手と言える。また青山学院大時代のチームメイトには、この記念試合に一緒に出場していた小窪哲也(広島、PL学園高)らがいた。2005年(大崎が3年生の時)は実力が認められ、日米大学野球の代表選手に選出された経験をもつ。そして全試合にトップバッターで出場し、日本の優勝に貢献した。この時、代表チームのチームメイトだったのは、前出の小窪のほかに大隣憲司(現・ホークス、京都学園高-近畿大)、根元俊一(現・ロッテ、花崎徳栄高-東北福祉大)や平野将光(現・西武、浦和実高-平成国際大)。■常総学院高時代には甲子園に3度も出場している。01年のセンバツでは、大崎は背番号「4」をつけて出場し、全国制覇を果たした。初戦(2回戦)は南部高にスコア8-7で逆転勝ちし、3回戦は金沢高に4-1で勝利。さらに準々決勝は東福岡高に4-2、準決勝は関西創価高に延長10回サヨナラ勝ち。そして決勝は仙台育英高に7-6で勝利し、優勝を決めた。このセンバツ大会、準々決勝で対戦した東福岡高には現・横浜の吉村裕基や、現・阪神の上園啓史(武蔵大)がいたし、準決勝・関西創価高のエースは野間口貴彦(現・読売、創価大中退)だった。今日も1クリックお願いします
2010.01.12
コメント(0)
-

再戦!松本哲也対長野久義
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■プロ選抜の2番・センターでスタメン出場したのは松本哲也(読売、山梨学院大付高-専修大)だった。独特の”天びん打法”で大学日本代表の各投手と対戦した。1打席目は早稲田大・斎藤佑樹(3年、早稲田実)と対戦、フルカウントまで粘って四球を選んだ。2打席目は澤村拓一(中央大3年、佐野日大高)と対戦し遊ゴロ。3打席目は大石達也(早稲田大3年、福岡大大濠高)から中飛。そして最後の打席は西嶋一記(明治大3年、横浜高)からストレートで四球を選んで出塁した。■松本哲也。専修大時代はずっと東都大学リーグの2部暮らしが続いた。1部に昇格できたのは4年生の秋季(06年)だから、松本自身が神宮球場でプレーをしたことはない。松本にとって大学野球のステージは、いつも神宮第二球場だった。06年秋季の1・2部入替戦は11月5日と6日、2部優勝の専修大と1部最下位だった日本大が対戦した。(1回戦、11月5日)日大 100 000 000 000 =1 専大 000 010 000 001x=2 (日)篠田-十亀-服部-●山口、(専)山田章-長谷川俊-土本-○湯本(2回戦、11月6日)専大 110 201 002 =7 日大 001 001 000 =2 (専)橋本-長谷川俊-土本-○長谷川樹、(日)●篠田-服部-十亀この2戦、主将だった松本は3番・センターで出場している。残念ながら8打数1安打とパッとしなかったが、後輩たちに1部昇格をプレゼントすることができた。一方、この時対戦した日本大の主将で、松本と同じ3番・センターだったのは長野久義(4年、筑陽学園高)。長野は松本とは逆に、チームを2部に転落させてしまった。今年から2人は読売のチームメイトになって外野のポジションを争うことになった。なんだか因縁めいたものを感じてしまう。■松本は山梨学院大付高1年生の時(2000年夏)、一度だけ甲子園に出場したことがある。しかし初戦で樟南高と当たり、スコア1-4で敗退した。この時、樟南高のエースは青野毅(現・ロッテ)だった。今日も1クリックお願いします
2010.01.11
コメント(0)
-

なぜか笑顔だった、嶋基宏
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■スコア1-1の同点で迎えた9回裏、二死走者なしの場面で嶋基宏(楽天、中京大中京高-國學院大)が打席に立った。大学日本代表の投手は東海大の菅野智之(2年、東海大相模高)。初球 直球(147km) 外角ぎりぎりに決まりストライク2球目 直球(141km) 初球とほぼ同様のコースだったがボール3球目 カーブ(115km) 内角でストンと落ちた4球目 スライダー(140km) ファール5球目 スライダー(138km) これもファール6球目 直球(141km) 高めの球をこれもファールそして7球目。高めのボール球(直球)を、振り遅れながらもライトの右に弾き返した。この日の嶋、打席では常に笑顔だった。その笑顔の意味は、菅野の投げる球への驚き(苦笑い)だったのか。それとも、プロとしての余裕を示すものだったか? いずれにせよ結果はヒット。一塁ベース上の嶋は安堵の表情を浮かべていた。■嶋基宏。ボクが初めて彼を観たのは、2006年6月3日に行われた東都大学リーグ1部・2部入替戦の第1戦だった。この頃、嶋はすでにドラフト候補捕手として注目を集めていて、ボクのお目当ても嶋だった。立正大(1部6位) 000 210 010 =4 國學大(2部1位) 120 410 00×=8 (立)高田-武部-高橋、(國)佐藤-相原2部リーグ戦に優勝した國學院大が出場したこの入替戦。ボクが観たこの試合(1回戦)で勝利後、2回戦で星を落としたものの3戦目で勝利。見事に1部昇格を果たした。嶋は4番を打つ中心打者だったし、嶋に続く5番打者は聖沢諒(現・楽天、松代高)だった。■嶋の中京大中京高時代のポジションはセカンド(大学2年時に捕手に転向した)。甲子園は2002年のセンバツに一度だけ出場した。チームメイトには、投手の中根慎一郎(現・三菱重工名古屋、慶應義塾大)や、捕手のは渡辺哲郎(現・トヨタ、法政大)がいたが、甲子園の初戦で西村健太朗(現・読売)を擁する広陵高と対戦し、スコア0-4で完封負けを喫した。 今日も1クリックお願いします
2010.01.11
コメント(1)
-

亜細亜大・小野紘明
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■亜細亜大・小野紘明(3年、岐阜・中京高)は8回表、この試合初めて打席に立った。そしてプロ選抜・佐藤由規(ヤクルト、仙台育英高)の速球を打ち、セカンドゴロに終わった。小野紘明。本間篤史(3年、駒大苫小牧高)とともに、4月から亜細亜大の副主将を務めることになった。自チームでは主に1番か2番を打ち、3番の中田亮二(4年、明徳義塾高。09年ドラフトで中日が3位指名)や4番・中原恵司(4年、武蔵工大二高。09年ドラフトでホークスが4位指名)の主軸打者につなげることが役割だった。ただ昨秋のシーズン、亜細亜大はこれだけの打者を擁しながらも、伏兵の立正大や國學院大に勝ち点を奪われるなど、成績は決して芳しくはなかった。立正大の優勝と青山学院大の2部転落ばかりが話題になったが、(6連覇を狙ったはずの)東洋大とともに亜細亜大も後悔の残るシーズンとなった。■小野、中京高時代に甲子園出場経験はない。高校3年生だった2006年夏は岐阜県大会の準々決勝で、エース・金森亮太を擁する県岐阜商高に4-7で敗退した。県岐阜商高はその後、県大会で優勝し甲子園に出場したが、1回戦で智弁和歌山高に敗れた。金森はその後明治大に進学(3年、投手)。また県岐阜商高の控え投手には三上朋也(現・法政大2年)がいた。今日も1クリックお願いします
2010.01.11
コメント(0)
-

立教大・田中宗一郎
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■途中出場した立教大の田中宗一郎(3年、佐賀西高)は9回表、初めて打席に立った。独特の前足(右足)を上げる一本足打法で、プロ選抜の山口俊(横浜、柳ヶ浦高)と対戦した。そして田中は山口の2球目を叩いたが平凡なショートゴロ。唯一の打席がたった2球で終わってしまった・・・。■田中宗一郎。昨年7月の日米大学野球にも代表選手として選出されたが、出番は少なかった。ただ東京六大学リーグ戦では、「何かをやってくれそうな」雰囲気をもつ数少ない打者の一人だった(立教大の打線においては)。※田中の他に期待できる打者は、岡崎啓介(2年、PL学園高)や五十嵐大典(4年、新潟明訓高)ぐらい。大林賢哉(2年、大垣日大高)もなぁ・・・ボクが思い出すのは昨年の秋季リーグ戦、10月10日の対早稲田大1回戦のこと。この試合で1番打者だった田中は4回表、早稲田大のエース・斎藤佑樹(3年、早稲田実)から打った本塁打。135~139kmの直球が3球続いた、その3球目をライトスタンドに運んだものだった。■田中は一年間の浪人後に立教大に入学した。出身校の佐賀西高は佐賀県NO1の進学校らしい。ボクの友人に佐賀西のOBがいて、たしかそういって自慢していたことがある。進学校ならば県大会の成績も芳しくなかろう・・・と思っていたが、さにあらず。なんと、田中が高校3年生だった05年、春季佐賀県大会では佐賀西高が優勝していることがわかった。もちろん田中は主軸を打っていた。 今日も1クリックお願いします
2010.01.09
コメント(2)
-

東北福祉大・阿部俊人
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■途中出場の阿部俊人(東北福祉大3年、花咲徳栄高)は8回表、二死走者なしの場面で左打席に立った。対するプロ選抜の投手は、ヤクルト・佐藤由規(仙台育英高)。初球、由規の投げた変化球は大きくすっぽ抜けてボール。そして2球目は145kmの直球。これを阿部が振りぬくと打球はレフト後方へ伸びた。だがフェンス手前で失速。この試合唯一の阿部の打席は、レフトへのファールフライで終わった。■阿部俊人。昨年7月に行われた全日本大学選手権、東北福祉大は初戦を創価大と戦った。創価大の投手はエース・大塚豊(創価大4年)。阿部は1番打者で出場し4打数1安打。大塚から1安打を放ったものの、スコア1-4で敗退した。そして11月の明治神宮大会では、2回戦で後にこの大会に優勝する立正大と対戦した。この時も阿部は1番打者で出場したが、阿部の成績は4打数1安打。結局スコア1-2でサヨナラ負けを喫した。09年、常に優勝候補の一角を占める東北福祉大にとってパッとしない一年だった。阿部は一昨年(07年)の全日本大学野球選手権でサヨナラ安打を放ち、ヒーローになった経験がある(奈良産大戦)。でもチームの成績同様、阿部にも後悔の残る年だったかもしれない。■この阿部、高校、大学を通じてロッテ・根元俊一の後輩である。埼玉の花咲徳栄高出身だから、ボクも県大会で見たことがあるはずだけど、まるで記憶にない(最近、物忘れが激しい・・・) 阿部が高校3年生だった06年夏の埼玉県大会を調べてみた。すると花咲徳栄高は準々決勝で、後にこの大会で優勝した浦和学院高にスコア5-6で敗退していたことがわかった。浦和学院高には赤坂和幸(現・中日)や内山拓哉(現・東洋大2年)がいたし、この大会でもっとも注目を浴びていたのは、鷲宮高の増渕竜義(現・ヤクルト)だった。今日も1クリックお願いします
2010.01.09
コメント(2)
-

土生翔平、ボクの記憶から
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■早稲田大・土生翔平(2年、広陵高)は、大学日本代表の3番打者としてスタメンに名を連ねた。ポジションはレフト。1打席目は前田健太(広島、PL学園高)と対戦して左飛。2打席目は金刃憲人(読売、市立尼崎高-立命館大)の132kmの変化球にあえなく空振り三振。そして最後の打席になった3打席目は、前の打者・多木裕史(法政大2年、坂出高)の適時打で1-1の同点に追いついた直後にやってきた。なおも一死一・二塁の”おいしい”場面。だが大隣憲司(ホークス、京都学園高-近畿大)に死球を喰らい、見せ場を作ることなくベンチに引っ込んだ。■早稲田大でも3番を打っている土生、今秋のリーグ戦の成績は素晴らしかった。打率は4割ちょうどで打撃十傑の堂々2位。そして今春のリーグ戦の成績も打率.318で10位にランクインしていた。ただ、それでいて、ボクにとって土生の印象はあまりない。スコアブックをめくりながら思い出すのは次の2つのシーン。(1)昨年4月28日の対法政大3回戦。5回裏に、この時点では法政のエースだった加賀美希昇(3年、桐蔭学園高)からライトのポールに当たるソロ本塁打を放った場面。(2)そして、昨年10月10日の対立教大1回戦。3回表に立教のエース・戸村健次(4年、立教新座高)から放ったセンター左への適時三塁打。この土生の適時打が戸村KO!の引き金になった。■広陵高時代は明治大・野村祐輔(2年)らとチームメイトだった。今日も1クリックお願いします
2010.01.05
コメント(4)
-

荒木郁也のHRと松下建太
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■明治大の荒木郁也(3年、日大三高)は、大学日本代表の6番・サードでスタメン出場した。 (荒木のサードというポジションは、あまり記憶にないが・・・)1打席目は大嶺祐太(ロッテ、八重山商工高)に3球三振。2打席目は、明治大の先輩・久米勇紀(ホークス、桐生一高-明治大)の初球を叩いて投ゴロ。そして3打席目は唐川侑己(ロッテ、成田高)からラッキーなショートへの内野安打を放った。一方、守備機会は2度あった。8回に亀井義行(読売、上宮太子高-中央大)の三邪飛と、5回に中田翔(日本ハム、大阪桐蔭高)が見せた三塁への凡走を、タッチアウトにしたプレー。テレビや新聞で何度も報じられたから、荒木にとってはおいしいプレーだったかもしれない。■荒木郁也。ボクが最も憶えているのは2008年5月17日の対早稲田大1回戦。早 010 100 010 =3明 000 010 003X=4この試合、完全に早稲田ペースで進んでいた。9回裏、ボクはそろそろ家に帰ろうと思い席を立ち上がったところ、その途端に明治大の反撃が始まった。それは一死後のこと。小道順平(当時3年、二松学舎大附高)が二塁打で出塁し続く千田隆之(当時3年、日大三高)の適時打で、あっという間に1点差となった。そして荒木郁也(当時2年)がフルカウントからの7球目を叩き、ライトスタンドへ逆転サヨナラ本塁打を放ったのだ。荒木が本塁打を打った瞬間、ボクは早稲田大の松下建太投手(当時3年、明徳義塾高)の姿をずっと見ていた。マウンドから本塁打を見届けた松下は帽子を剥ぎ取って、だれにともなくベコリと頭を下げた。そして、うつろな表情で頭をかきむしっていた。その姿は「こういった緊急事態に、自分がとるべき態度」を懸命に考えているように見えた。その松下建太、昨秋(2009年)のドラフトで西武から5位指名を受け入団した。今日も1クリックお願いします
2010.01.03
コメント(0)
-

越前一樹vs大嶺祐太
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■2回表、大学日本代表の攻撃。一死走者なしの場面で、この試合の2日前に明治神宮大会で優勝した立正大の主軸打者・越前一樹(3年、横浜高)が右打席に入った。対するプロ選抜の投手は、この回から2番手投手として登板した大嶺祐太(ロッテ、八重山商工高)。1球目 119kmの変化球(内角に外れてボール)2球目 139kmの直球(外角ぎりぎり、ストライク)3球目 136kmの直球(2球目と同じコースでストライク)そして4球目は、外角低めに落ちる112kmのカーブ。これを越前は空振りして三振を喫した。走ってベンチに帰る越前。その越前の姿を表情を変えずに見つめる大嶺。とても堂々としていて相手打者を見下ろすような表情。大嶺の心の内に秘めたプロのプライド(?)らしきものをボクは感じた。■越前一樹vs大嶺祐太。実はこの2人、高校時代に甲子園で対戦したことがある。2006年センバツのこと。この大会で優勝する越前のいた横浜高は2回戦で八重山商工と対戦、金城長靖(現・沖縄電力)と大嶺を打ち崩して勝ち星を挙げている。(2006年3月29日)横浜 001 600 000 =7八重 000 001 050 =6(横)川角-浦川、(八)金城-大嶺この試合、越前は7番・レフトで先発出場していた。そして4回途中から急きょ登板した大嶺と、計2度対戦している。対戦結果は次のとおり。1度目 レフト前安打(5回表)2度目 ショートゴロ(7回表)3年半前の対戦、2人は憶えていたろうか?■越前一樹、06年はセンバツ・夏ともに甲子園に出場している。前述のとおりセンバツで優勝しているが、八重山商工高と対戦後、準々決勝では斎藤佑樹(現・早稲田大3年)を打って早稲田実にスコア13-3で圧勝。準決勝は尾藤竜一(現・読売育成選手、早稲田大中退)を擁する岐阜城北高に、12-4でこれも圧勝した。そして夏。初戦で中田翔(現・日本ハム)や謝敷正吾(現・明治大3年)らのいた大阪桐蔭高に6-11で大敗した。だが、越前はこの試合で本塁打を打って一矢を報いている。また、横浜高のチームメイトだった西嶋一記(現・明治大3年)は2番手の投手として大阪桐蔭高戦に出場していた。今日も1クリックお願いします
2010.01.02
コメント(6)
全23件 (23件中 1-23件目)
1