2009年11月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
フィンランド語の絵本はどこ?
自分のブログでこんな事を書いてもしょうがないかもしれませんが、、フィンランド語の「勉強」かなりストレスになって来ています。文法が大変な言語だとは聞いていましたが、覚える規則が膨大です。格変化というのがいっぱいあって,その規則をおぼえなくてはだめなんだそうです。昔から暗記学習が大の苦手だった私は教科書読むだけ学習が主だったので、それで切り抜けようかと思っているのですが,それでは手に負えない状況です。教科書がそういうふうにできていないのです。そこで私のへそ曲がり根性がでてきてしまいます。フィンランドの子どもたちもしゃべっているんだし、後から文法っていう方法もあるんではないのかな~、と。ORTみたいな本を探してそれを読んだらどうなるんだろう,って思います。全くの未知の言語を多読するいい実験になると思うんですが。絵本どこかになかな~、と思案しています。
2009.11.30
-
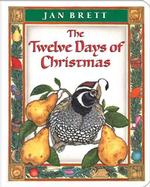
クリスマスの歌と絵本
今週からクリスマスの歌を歌い始めました。毎年歌っているのは「Twelve Days of Christmas」です。これは超がつくほど有名な歌ですから、どこかでみんな聞いた事がある歌ですが、歌詞がとっても長くてめんどうくさい!、と思われるのですが,意外とみんな覚えてくれます。低学年はカードゲームをして序数とそれぞれの数の絵の組み合わせてしながら歌っていくとあら不思議、みんな簡単に歌えてしまいます。高学年はもう飽きるほど歌ってますが、安心して歌えるのでこの歌は欠かせません。この歌の絵本はいっぱいでていますが、うちにあるのはこの絵本(昨年も紹介してましたね。) これは期末テストの終わった中学生に歌ってもらおうと思っているおなじみの歌です。「Jingle Bells」この絵本はIza Trapaniさんが歌からヒントを得て物語にして長い歌詞をつけて歌っています。物語として読むととても楽しいです。世界中のいろいろな国のクリスマスの様子が描かれています。本の最後の方のページには各国のクリスマスの習慣の説明がのっていますので,歌った後で,読んでみるのもいいかと思います。
2009.11.26
-
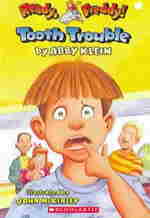
児童書 Ready, Freddy
数年前に4冊買ってみたもののほとんど読まれなかった"Ready, Freddy"シリーズですが、大人の会員さんが読んでくれて、おもしろい、他にないんですか,と言われて、買い足しました。Audible.comには6冊分の音源がありましたので音源も買いました。主人公のFreddyはSharkが大好きな小学生です。1巻目は乳歯から永久歯に生え変わるころの子どもの気持ちがよくわかります。クラスのみんながどんどん歯が抜けて行くのに自分だけまだ抜けないのでなんだか嫌に気分のFreddy。なんとかして歯を抜こうとがんばります。歯が抜けるって不安だけど大人になって行く証拠のようでもあるんですね。子どもの日常をユーモアたっぷりに描いていて、学校の様子、家庭の様子などもかいま見られてなかなか面白いシリーズです。朗読も大人の男性の声ですが、気持ちのこもった、さすが本職の声優さんと思われます。聞いているだけでも笑ってしまう場面がいっぱいです。
2009.11.25
-
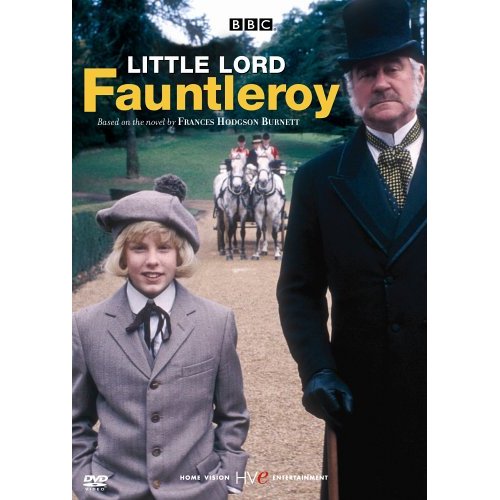
字幕なしドラマ、DVD Little Lord Fauntleroy
字幕なしでドラマやDVDを見る!と宣言してから今までに76時間になりました。今日は小公子"Little Lord Fauntleroy"を見ました。日本のアマゾンから955円で買ったのですが、リージョン1ですので,普通のテレビ用のDVDプレーヤーでは見られません。パソコンをリージョンを1に変えてみています。日本語字幕も音声もないので英語でみるしかないのがこいうDVDのいいところです。字幕なしで見るのは子ども向けがいいですね。ストーリーがわかりやすいです。小さい子はテレビの教育テレビやアニメを言葉がわからなくても楽しそうに見ていますから、子ども向けはわかりやすくできているという事でしょうか。このお話しは日本でもアニメになっているようですが、私は昔々に少年少女文学全集で読んだ記憶はありますが,細かい筋は忘れていました。アメリカ人と結婚したためにイギリスのおじいさんから絶縁されていたお父さんが亡くなってお母さんと2人つましくニューヨークで暮らしていたセドリックに突然イギリスにおじいさんがいるという知らせ。息子のためにとイギリスに渡ったお母さんとセドリックですが、一緒にはくらせません。でもセドリックのやさしさが頑固なおじいさんを変えていきます。冬のように暗く冷たいおじいさんの心を溶かし、お城の召使いや執事や家政婦もみんな変わって行きます。英語はおかあさんとセドリックは聞きやすく,おじいさんの英語は聞きにくい、イギリス英語になるととたんに私の耳が機能しなくなるようです。
2009.11.22
-
QA-100
小学生6年生クラスではそろそろ中学校を意識してQA-100をを取り入得れています。松香フォニックス研究所の一番と言ってもいいくらいに古い教材です。100のの質問と答えからなっている本です。超シンプルな本なのですが、結構役に立ちます。小学生クラスでは気がつくとAre you~~?や、Do you ~~?の質問はしょっちゅうしていますが、意外と第3者についての質問は少なくなってしまいます。中学生になって2学期いきなりDoes~~~となると混乱が生じます。この第3者の感覚、三人称の感覚がいまいちつかめないないようなのです。中学生の一番最初につまづく文法と言ってもいいでしょうか。このQA-100はコンパクトながら、身近な質問がどんどん出て来て、反射的に答えられるものばかりなのです。Does your mother drive a car?というと,反射的にYes, I do.と答えてしまう子がほとんどなのですが、そこで、Iってだれのこと?、お母さんは自分じゃないから言えないから、sheだねと言うと,女の人はsheなんだと気づいてくれます。中学になって問題集の単語の欄に、she---女の人,と書く子が出てきますが、それはちゃんとわかっていた証拠、その時に学校英語的に彼女って言う言葉を教えればいい事です。こんなふうにDoesやdoesn'tを使う経験から入ってから覚えた方がずっとわかりやすいようです。中学になっていきなり教科書からではわかりにくいと思います。Did you~~の質問やHave you~~の質問なども入っていて感覚がつかみやすく、なかなか役に立つ教材です。
2009.11.22
-
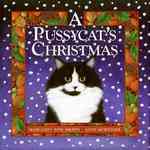
クリスマス絵本 A Pussycat's Christmas
クリスマスの絵本をいろいろ探していて見つけた絵本です。まずは表紙の絵に惹かれました。作者がMargaret Wise Brownであることもきっといい絵本だろうと予想して買ったのですが、ほんとにすばらしい絵本です。この黒と白の猫の毛のふさふさ感、ついつい触ってもしかして本物?って触りたくなります。眺めているだけでクリスマス気分に浸れます。Pussycatにはクリスマスのにおいがわかります。クリスマスの音がわかります。氷のサクサクした音やクリスマスツリーのにおいがわかるのです。普通、猫はこたつで丸くなる,というくらいですから,外へ行くのは嫌いなはずですが、この猫は違います。ふわふわの雪が大好きです。猫の五感が自分にも伝わってきそうな絵本です。私が子どもの頃は私の田舎にももっとたくさん雪が降って寒かったのですが、なぜか,ぬくぬくした暖かい思い出ばかりです。クリスマスを待つワクワク感がこの絵本を読んでよみがえってきました。もちろんこんなに豪華のツリーはなかったけれど、、
2009.11.17
-
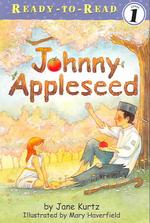
Johnny Appleseed2冊
秋にふさわしい本と思って注文した本が今頃届きました。Johnny Appleseedです。開拓時代のアメリカでリンゴの果樹園を作って、ぼろぼろの洋服を着て、いつも裸足でいろいろな所を旅しながら、自分が育てたリンゴの苗や種を物々交換したり,貧しい人にはただであげたりして、リンゴをを広めた人のお話です。アメリカの開拓時代のお話は夢があっていいですね。Ready-to-Readシリーズのレベル1です。とってもシンプルな英語でわかりやすく書かれています。Step into Reading シリーズのレベル3です。My Storyという事でJohnny 自身が語っている形です。前にも紹介した事がある,この絵本もリンゴのおいしそうな香りがただよってくるようです。
2009.11.14
-
お母さんと子どもの英語
うちの多読クラブの会員さんは中学生から一般人までいろいろですが、中学生の次に多いのはお母さんたちです。多読を始めようと思ったきっかけはお子さんに英語をやらせようかなと思って,と言って来た方も何人かいますが、なぜか,今はほとんどの方がご自分の多読の方に一生懸命です。私から見たらまだまだ若いお母さんたちです。子どもの英語はまだまだ焦る必要なんかないんですから、ご自分が楽しく英語をやっていたらきっとお子さんもやる気がでるかもしれませんよ、とお話しています。あるお母さん、英語の絵本をお家に持って帰って見せても敏感にお母さんの期待を感じてしまったのか、日本語の本でなきゃいやっと拒絶されたそうです。それ以後お母さん一人、どんどん多読がすすんでいたのですが、数ヶ月たったある時,お子さんがORTを見て自分から読みたいと言い出したという事です。お母さんが楽しそうに読んでいるキッパーたちの絵本を覗いてきっと興味をもったのでしょう。でも、このおかあさん、偉いのです。でも,焦って見せるとすぐ拒絶されそうだから、じっくりやります,との事。このお母さんとお子さん,とってもいいなあ,て思いました。世間では英語育児がさかんなようですが、英語なんていつからでも大丈夫だと思います。焦る必要はまったくないと思います。せめて幼児期はもっとのんびりでいいんではないでしょうか。児童英語教室をやっている私がこんなことを言うのも変かもしれませんが、、、
2009.11.13
-
NHKドラマ 「ホテルバビロン」がおもしろい!
この秋スタートのNHKの海外ドラマにはまっています。仕事が終わって家族もまだ帰っていないという時、録画しているドラマに手がでます。なかなかおもしろいのです。「刑事コロンボ」と「突然サバイバル」と「ステート・オブ・プレイ」と「ホテルバビロン」を録画して見ていたのですが、まず、ステート・オブ・プレイ」からは撤退しました。全然わかりません。日本語でも見てみましが、それでも理解できません。言葉もわかりにくいし、筋もついて行けなくて、やっぱりもっと単純なのがよさそうです。一番気楽に見られるのは高校生の冒険もの「サバイバル」です。今一番気に入っているのは「ホテルバビロン」。今日見たのは特に面白かった!高級ホテルの現実にはいろいろ驚かされます。あくまでドラマですからどこまでが真実かわかりませんが、今日はホテルで働く不法滞在者の話でした。ロンドンにもアフリカやアラブ系などの不法滞在者がいて,それが公然の事実でとしてある程度当局も目をつぶっている部分があるという感じがしました。時々手入れをして捕まる人もいますが、ホテル側も不法滞在者の安い労働に頼って利益を上げているという現実があります。こんな深刻な内容と,同時進行でちょっとコミカルなゲイの話が入っていたり、2つ3つのドラマが同時進行するというほんとによくできたドラマだと思います。華やかなロンドンの高級ホテルが社会の縮図にも見えます。
2009.11.11
-
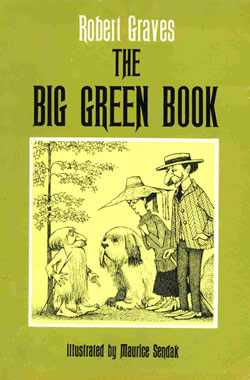
Maurice Sendakの絵本 The Big Green Book
The Big Green Bookずっと本箱に入れてなかったのですが、出してみたらなかなかいいのでご紹介します。特に大人の方には気に入ってもらえると思います。5年ほど前にニューヨークに行った時に古本屋でたったの1ドルで買った絵本です。なぜか絶版になっているようです。アメリカのアマゾンでも再販を望む声がたくさん書かれています。両親が亡くなってしまったジャックはおじさんとおばさんの家に引き取られました。ある日、屋根裏部屋で魔法の本を見つけます,何でもかなえてくれるthe big green bookでした。早速ジャックは魔法をかけて自分をぼろぼろの洋服を着た老人に変身します。ジャックを探しに来たおじさんとおばさんを老人に化けたジャックは賭け事して負かしてしまします。まんまとだまされるおじさんとおばさん、大人と子どもの立場が逆転します。何でも思いのままに操れるジャックは心の中でクスクス笑っています。痛快なお話、Maurice Sendakの白黒のちょっととぼけた絵がなかなかいい味です。アメリカのアマゾンだったら古書で買えるようですす。
2009.11.11
-
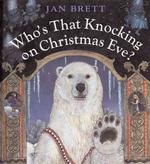
クリスマス絵本をかごに入れました。
ハロウィーンの絵本を本箱にもどし、クリスマス絵本をかごに入れました。もうすぐクリスマスなんて今年は時の経つのが早く感じます。いくつか篭の中の本をご紹介します。Who's That Knocking on Christmas Eve by Jan Brett不思議なトロルが出てきます。トロルもJan Brettの絵ではちょっと怖いけれどかわいらしく、幻想的です。ところで、クリスマス絵本のかごを見ていて、圧倒的に熊が出てくる絵本が多い事に気づきました。冬のクリスマスのころには熊は冬眠しているはずなのに熊がいっぱいなのです。熊のふわふわした雰囲気がクリスマスの温かい雰囲気に合っているのでしょうか。この絵本もとってもあったかい雰囲気の絵本です。クリスマスが待ちきれないLittle BearとGrandbearのお話です。Is It Christmas? by John Prater
2009.11.10
-

京都へ行ってきました
教室の平日休みはめったにないことなので、この機会とこの季節にと、思い立って京都へ行ってきました。5~7日までの2泊しました。急に寒くなったので、きっと紅葉真っ盛りかと思ったのですが、残念、まだまだ3分といったところでした。1枚目は御室仁和寺、2枚目は哲学の道です。 詳しい事はもう一つのブログの方に書く予定です。今回の旅行の教訓、京都も外国と同じ位たくさん歩く、絶対ブーツで行ってはいけない!ということです。低いヒールのブーツで行ったのですが、靴の底が平でないという事がこんなにも歩きにくいということを再確認しました。外国旅行の時は一番歩きやすい普段はいているウォーキングシューズで行ったのですが、色が秋っぽくないし、京都はちょっとはおしゃれっぽい方がいい、、なんて思ったのが良くなった!とたんにひざ、太ももが痛くなって後悔しました。これ以上は無理、と思い、しかたなく駅ビルの中にある伊勢丹でウォーキングシューズを買ってしまいました。宿代より高くついてしまいました。でもこれは10年ははくつもりですから、、、と、言い訳してます。
2009.11.08
全12件 (12件中 1-12件目)
1










