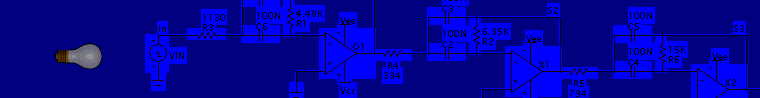2009年04月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-

VusualC#を使ってみた。
Visual C#を使ってみました。以前、Visual C++にトライしようとしたことがあったんですが、あまりにもプログラミングが面倒だったので、諦めていました。そのためパソコンのプログラムといえば、もっぱらVisual Basicでした。ある人から、Visual C#は、Visual Basicと同感覚だよ!という助言をもとに、マイクロソフトのWebサイトからExpress Edition (2005)をダウンロードしました。使ってみると、その通りですね、プログラムの開発環境はVisual Basicと殆んど変わりませんし、ボタンなどのコントロールをFormに貼り付けていけば画面が出来上がります。それからPICマイコンなどと通信するためのシリアル通信機能が、標準で用意されています。旧バージョンの.NETだとこの機能が使えないため、わざわざVB6のコントロールを流用した記憶がありましたので、これは助かります。PICマイコンのプログラミングが殆んどC言語で行われていることもあり、C#の ”C言語ライクな記述 { で始まり } で終わる。”は、PICマイコンと、パソコン側プログラミングを並行して行う場合に、混同することが少なくて、より好ましいと思いました。ついでに、写真の本も買いました。1500円+税は専門書としては、結構安いと思います。
2009.04.25
コメント(2)
-
フォノ・イコライザアンプ改造
自作のフォノ・イコライザアンプを改造しました。今回の改造は、商用電源を止め単三電池式のバッテリー駆動にしたものです。改造ですが、単三電池(1.5V)が正負電源毎に10本です。つまり20本でアンプを駆動するようにしました。とりあえず安価なマンガン電池、20本で試してみましたが、音質は確実にグレードアップしたと思います。繊細感がアップし、低音も、力強く感じられます。音は結構良くなったと思うのですが、ちょっとそっけない感じもします。おそらくオペアンプが超低歪率、広帯域なLME49720(ナショセミ)だったせいかも知れません。NJM2114DかNJM5532あたりで、試してみたいと思います。それから、カップリングコンデンサやイコライジング・ネットワークコンデンサが汎用のフィルムコンデンサだったせいもあるので、こちらも交換してみたいです。
2009.04.18
コメント(0)
-
KT66シングルアンプの測定
KT66真空管アンプの周波数特性と歪特性を測定しました。周波数特性については、10Kz方形波から高域の伸びが期待されましたが、予想通りの結果となりました。100KHz(-6dB)程度これは、真空管アンプとしては、かなり良い特性だと思います。次に歪特性ですが、0.001Wからプロットしました。出力とともに歪が増えるかと思いきや0.6W付近で下がって、その後出力ととも増えていきます。このようなカーブを描いた理由ですが、このアンプは、P-G帰還やオーバーオールNFBをかけていません。そのため、初段にμSGの低いFE83EF83使用し、2次歪の打ち消しを狙っています。歪特性のグラフから丁度0.6W付近で歪を打ち消しあっているためだと思われます。FE83EF83のカソード抵抗を調整することにより、さらに歪の打消しを追い込めるようですが、この位であれば充分と思います。残留ノイズも良好で、左右とも0.5mV位でした。FE83→EF83でした。訂正します。
2009.04.12
コメント(4)
-
ペン型USBオシロ
秋月電子通商で販売しているペン型USBオシロスコープ PicoScope2104です。安価ですが、使ってみると(1)オシロ(2)FFT(3)周波数測定(4)電圧が一度に見れるし、データをファイルに保存できて便利です。但し、先端がデリケートなので、アタッチメントを取り付けるときは慎重に....私の場合、付属のオシロ用のプローブを差し込もうとしたんですが、硬くて入りませんでした。アナログオシロで使っていたプローブに交換したら問題なく入りました。
2009.04.05
コメント(2)
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-

- 気になる売れ筋おもちゃ・ホビー・ゲ…
- LEGO ‐ Star Wars ‐ | レゴブロック…
- (2025-11-15 21:55:46)
-
-
-

- 戦闘機の写真を撮るのが好き!
- 三沢基地航空祭2025.09.21
- (2025-11-19 06:30:06)
-
-
-

- フォトライフ
- 源氏物語〔34帖 若菜 50〕
- (2025-11-19 11:30:04)
-