2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2013年03月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-

腰痛
腰痛:日本人の健康に脅威 長寿でも、病気に苦しむ期間長く腰いた 家で我慢すれば ただの腰いた 病院行けば 腰痛症腰痛が健康寿命に大きな影響を与えているようです。1.腹筋・背筋・脚筋を強く、全身の特に体幹の筋肉をしなやかに。2. そして、物を持つ時は脚で持つ。3. 最後に、風呂上がりに、その日の疲れをとるストレッチをしっかりと。 腰痛予防の原則です。腰は身体の動きの要(カナメ)で、 痛みがあると動きづらくなり、動かないでいると動けなくなり、ロコモとなり、介護状態に近づきますので、ご用心! 以下、毎日新聞 3月28日(木) より配信です。 日本人にとって「健康で長生き」の脅威となる病気や障害のトップは腰痛との分析結果を、米ワシントン大、東京大などの研究チームがまとめ、英医学誌ランセット(電子版)に発表した。自殺も上位に入っている。チームは「世界一長寿の日本人の健康が揺らぎ始めている。長く生きても病気などに苦しむ期間が延びていることを示している」と説明する。 日本の分析は、厚生労働省の人口動態調査などを基にした。平均寿命より早く死亡することで失った年数、障害を抱えて生きる年数を考慮し、病気などが健康に与える負担の程度を分析した。この手法は、死に直結しないが日常生活に支障をきたし、健康寿命を縮める病気や障害を明らかにできる。 その結果、2010年で最も負担度が重かったのは「腰痛」で、脳卒中、虚血性心疾患(心筋梗塞(こうそく)など)、肺炎、関節症などの筋骨格系障害、肺がん、自殺――と続く。1990年の分析ではトップ3は脳卒中、腰痛、虚血性心疾患の順だった。また、自殺は若年層(15~49歳)の死因の27%を占め、90年の16・5%から急伸、世界でも飛び抜けて高かった。 さらに、こうした脅威の背景にある最も重要な要因として「食生活」を指摘した。和食は低カロリーだが塩分が強く、果物やナッツ類が不足するなど栄養素の偏りが問題だという。2位以下は高血圧、喫煙(副流煙を含む)、運動不足、肥満だった。 チームによると、2010年の日本人の平均寿命は82・6歳だが、健康寿命は73・1歳(男女平均)。分析にあたった渋谷健司・東京大教授(国際保健政策学)は「政府は国民の健康課題に効果的に取り組んでいるように見えない。食事の改善、禁煙、腰痛対策など高齢化に伴う問題とともに、自殺予防に向けた精神疾患対策などを進めなければ、健康長寿世界一の座を維持できないだろう」と話す
2013/03/28
コメント(0)
-

脳卒中になる確率
脳卒中になる確を簡単に予測できる算定表が開発されました。 読売新聞からです。 40~60歳代の日本人が今後10年間に脳卒中になる確率を自分で簡単に予測できる算定表を、藤田保健衛生大学の八谷(やつや)寛教授(公衆衛生学)らの研究チームが開発した。 年齢や血圧などの数値を点数化し、合計点数を求めると確率がわかる。健康への関心を高めることにも役立ちそうだ。 算定表は、茨城、新潟、高知、長崎、沖縄の5県で1993年に40~69歳だった男女計1万5672人を平均14年間追跡した大規模調査に基づくもので、実際に脳卒中になった人(790人)の危険因子を調べ、発症確率を求めた。年齢、性別、喫煙、肥満度、糖尿病の有無、血圧と降圧薬を内服しているかを自分でチェックし、点数を合計して表と照らし合わせる。同時に血管年齢もわかる。
2013/03/23
コメント(0)
-
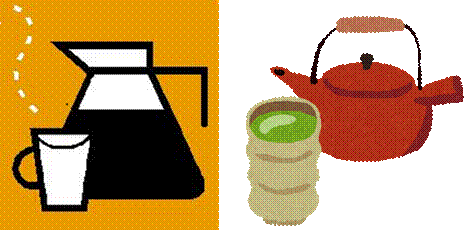
緑茶で脳卒中リスク低減 コーヒーでも
緑茶で脳卒中リスク低減 コーヒーでも、8万人調査共同通信社 3月15日(金) 配信 緑茶、コーヒーを毎日1杯以上飲む人は、脳卒中のリスクが減るとの研究結果です。でも、飲みすぎはマイナスの影響があることかと思いますので、飲みすぎにはご注意を。 緑茶やコーヒーをよく飲む人は、飲まない人に比べて脳卒中になるリスクが2割程度低かったとの研究結果を、国立がん研究センター(東京)と国立循環器病研究センター(大阪)のチームが15日、発表した。 緑茶の血管保護効果やコーヒーの血糖値改善効果が影響している可能性があるという。 チームは、1990年代後半に東北から沖縄の9保健所管内に住んでいた45~74歳の男女計約8万2千人を平均13年間追跡した。この間に3425人が脳出血、脳梗塞、くも膜下出血といった脳卒中を発症した。 追跡開始時点で、緑茶を「全く飲まない」「週1~2回飲む」「週3~6回」「毎日1杯」「毎日2~3杯」「毎日4杯以上」のグループに分けて解析すると、飲まないグループに比べ、毎日1杯以上のグループは脳出血のリスクが22~35%低かった。脳卒中全体では毎日2~3杯以上で14~20%低かった。 コーヒーについては、飲まないグループに比べ、週1~2回以上のグループは脳梗塞のリスクが13~22%低かった。脳卒中全体では週3~6回以上で11~20%低かった。
2013/03/15
コメント(0)
-
座りっぱなしの生活は・・・?
>座りっぱなしの生活で高まる慢性疾患リスク座位での時間が長くなればなるほど、癌、糖尿病、心疾患などの慢性的な健康問題のリスクが高まることが実証されました。ヒトは動くことを忘れると、様々な健康問題が生じるようです。以下、CARE NET からです。 立ち上がって歩き回ることなく毎日数時間を過ごしている人は要注意だ。一日に座っている時間が長いほど、癌、糖尿病、心疾患などの慢性的な健康問題のリスクが高まることが新たに示唆された。 オーストラリアおよび米カンザス州立大学の研究グループは、オフィスワーカー、トラック運転手など、日常的に長時間座って過ごす人にとってこの知見は重要なものだと述べ、慢性疾患リスクを低減するためには、座る時間を減らして運動量を増やす必要があると結論付けている。研究著者であるカンザス州立大学助教授のRichard Rosenkranz氏は、「慢性疾患に関しては、運動量が少ないよりも多いほうがよいということは確信をもっていえるが、座っている時間を減らすことにも注目する必要がある。多量の事務作業によって長時間の座業を要求されると、運動不足とエネルギー消費量の低さから健康に害が及ぶ可能性がある」と述べている。 今回の研究では、オーストラリアのニューサウスウェールズ州に在住する45~65歳の男性6万3,000人強を対象に、慢性疾患の有無、および一日に座って過ごす時間を調査。その結果、座っている時間が1日4時間以下の人は、毎日4時間以上座って過ごす人に比べて癌、糖尿病、心疾患、高血圧などの慢性疾患を有する率が大幅に低かった。また、1日6時間以上座って過ごす人は、糖尿病リスクが有意に高かったという。 座っている時間が長いほど、慢性疾患数も多く、被験者の運動レベル、年齢、所得、教育、身長、体重を考慮してもこの結果は変わらなかった。Rosenkranz氏は、「座っている時間が長いほど、慢性疾患リスクが着実に段階的に増大した。8時間以上座って過ごす群は明らかにリスクが最も高かった」と述べ、「単に運動が十分でないということではなく、長時間座っていること自体が問題。それに加えて、座っている時間が多いほど運動する時間が少なくなる」と付け加えている。 座っている時間が慢性疾患の発症につながるのか、またはその逆なのかは完全にわかっていないという。今回の研究は、オンライン医学誌「International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity(IJBNPA)」に2月8日掲載された。
2013/03/08
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-

- ウォーキングダイエット日記
- ばんぶーさんの朝散記録 〜2025秋本…
- (2025-11-16 06:30:06)
-
-
-

- 喘息・橋本病・胃潰瘍・筋緊張型頭痛…
- 治らないと諦めていた症状が完治した…
- (2025-05-21 00:28:42)
-
-
-

- 介護・看護・喪失
- 書いてないだけ、毎日想っている
- (2025-11-22 22:10:15)
-






