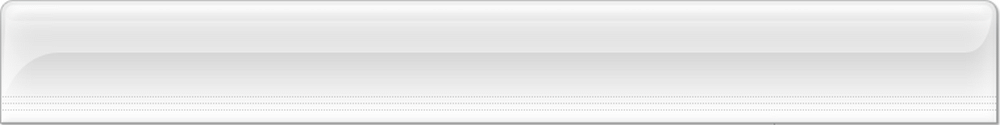ただでさえ歴史が好きな上に、その大転換点だったら、とてつもなく胸が沸く。
しかも、それが、自分が生きている、今、このとき、本日、8月17日金曜日、日本時間午後9時だったら?
多くの人が想像している通り、わたしは血沸き肉踊る興奮の中にある。
ロイターのWebページは世界中の大激動を伝えていて、世界中の専門家たちがいっせいにブログで生の声を聞かせてくれ、ボタンを押すたびに新たなRSSがわたしに更新を告げる。
日本の、クーラーの効いた、暗くした部屋で、ジュリー・アンド・マリーを聞きながら、これを書いている。
わたしが見ているのは、劇的なクレジット危機。
7月の末のサブプライム問題より始まった、マネーの大激流である。
第二次世界大戦以前の大転換は戦争や革命によって起こったが、21世紀の大転換はグローバル市場において、全くの無血で起こるようだ。
実は、わたしは分家の方で、サブプライム問題を書いている。
■夏休みのサブプライム観察日誌
ここでの結論は、
まあ、良くも悪くも、一生に一度みれるかどうかの大破綻をおそらくわたしは見ているのだろう。わたしにはできることはないし、プレイヤーたちがなんとかどうにかしてくれることを祈るしかない。
これを教訓にどう生きるかを、考えるしかない。
サブプライム問題は米国の経済の崩壊であり、致命的なモラルハザードによってそれは起こった。
あ、そうそう、念のために言っておくと、わたしの資産(ほとんどないに等しい額だが)は全額ポンドの外貨貯金となっており(単純に英国好きなだけだったりするのだが)、たぶん最高値から20%ぐらい円換算で価値が下がるはずだ。
なので、わたしも被害を受けているといってもよいかも知れないし、もし利害があるのだとすれば、急激な円高が進んでいる現在を喜んでいるはずはない。
しかし、この激動を嬉々と見つめずにいられようか。
たった今、全世界の金融商品からマネーが逃げ出し、安全な債権に向かっている。
全世界的に株式は下落し、日本でロイターを見ている限りは、全通貨が下落しているように見える。エコノミストの指摘では円キャリー取引の手仕舞いで急激な円高が進んでいるのが原因で、円は一日に2円というすさまじい勢いで高くなっている。
わたしは、しばらく、この状況でどこにマネーは流れているのだろうか、とぴんぼけした感想を抱いていた。
円とスイスフラン以外がすべて下落しているのであれば流れているところは1つしかない。円に流れているのである。急激な勢いで、すさまじい勢いで円に資金が流入しており、円でしばらく投資先を見つける間、休息して、またどこかに流れていくのである。
7月末からの資金の流れを見ていると、次の二件のロイターが象徴しているような気がしている。
■将来的に欧米で商業銀行の買収も検討=三菱東京UFJ銀
これは8月16日の記事。つまり昨日。この金融危機において、三菱東京UFJは大打撃を受けた欧米の銀行の物色を始めており、アジアを主戦場とする意思を固めている。これは非常に簡単で、顧客=欧米、投資先=アジアという方針を固めたということだ。
■米ブラックストーン、インドや日本での投資に関心
ちなみに、ブラックストーンは、つい最近IPOしたばかりのファンドであり、中国政府から30億ドルの投資を受けていたりする。
四半期決算は絶好調。
■米ブラックストーンの第2四半期は増益、買収や不動産売却が寄与
崩壊寸前の米国市場からかなりぎりぎりで逃げることに成功した。
■米ブラックストーン、エクイティ・オフィスの不動産大半売却か (ロイター)
ブラックストーンは、インドの急成長小規模企業に投資するらしく、日本ではたしか不動産に投資する予定だった気がする(未確認情報)。
それ以外の多数の有力(察しのいい)資本が、米国から資金を引き上げ、アジアに資金を投入しようとしている。リスク債に投じられていた資金が、いますさまじい勢いで円に逃避し、休息し、アジアへ向かおうとしている。
なぜ、今、円に逃避しているのであろうか?
それは、少し考えればよく分かる。
今、もっとも安全な通貨が円だからだ。
円キャリーの巻き戻しなどと、ぴんぼけした感想を抱いていたわたしは頭をハンマーで殴られた気分になった。
円建てで借りていたのは、円の金利が低かったからではない。
円がもっとも安全だったからだ。そして、その円の資産を生かす投資先が円建てでは見つからなかったので、キャリーされて外国の高利債に投資されていたのだ。
そして、全世界的な金融不安とともに、円の元にマネーが戻ってきた。
それに気づかせてくれたのはこのエントリー。
■[経済] 株価はフラクタルだ
いつの間にか「暫定」基軸通貨は円になっていたのだ。
しかし、日本は米国と、なんと言うか「べったりな」同盟関係にあり、為替政策はドルペッグと言ってよいほど二人三脚状況だったので、ドル=円同盟が基軸通貨として機能していたのだと思う。
しかし、米国経済の崩壊の兆しが見え始め、新興国市場が急速に立ち上がり、アジア金融危機などを経て、ユーラシアがドルを嫌い始めた。その経緯は、次の2エントリーに詳しい。
■ドルの基軸通貨からの転落への準備を怠るな
■円・元・ドル・ユーロの同時代史 最終回~基軸通貨の危機
特に、後者はこれまでの通貨の流れを詳細に追っているので非常に参考になると思う。 この2つのエントリーが告げているのは、日米同盟にアジア通貨を組み込んだアジア共通通貨単位に基軸通貨は移るということである。ストーリーはこうだ。
アジアはアジア金融危機によりドルを膨大に積み上げた。
だから、アジアはドルを投売りすることはない。
ただ、ドルの政策に強権を振るわれ、揺さぶられ続けるのは我慢しがたい。
なので、製造業で結びつきが強くなったアジア経済圏にアメリカを組み込んで、ゆるい金融同盟を作ろう。
基軸通貨は歴史のいたずらなのかそうでないのか、ポンド→ドル→円と移り、旧宗主国からその植民地へと移動し、英米日同盟にアジアを含めようとしている。
もし、歴史に法則があるのであれば、ロンドン・ニューヨーク・東京市場はその後も主要マーケットであり続け、次の主役はアジアであるが、それによって主役を譲った者が一方的な衰退をするわけではない、と読むことも出来る。
直近では、激しい乱高下でなかなか先を見通すことは難しくなっている。
しかし、確実にやってくるのはドルの一極支配の緩やかな崩壊であり、強烈な同盟国である日本の円を媒介としたアジア経済圏の勃興であり、世界の多極化である。
ドルの崩壊は免れない。
■綻目前、サブプライムの猶予は3カ月 / SAFETY JAPAN [大前 研一氏] / 日経BP社
しかし、致命的な崩壊が起こるはるか以前に、暫定的な経済同盟がすでに日本を媒介として出来上がってしまっており、運命共同体である以上、米国が切り捨てられるという事態には陥らないという歴史のようだ。
緩やかな調整が行われ、主役がアジアにシフトしていくのだろう。
それが、はからずも90年代初頭の日米の経済戦争に端を発しているようで面白い。
■円・元・ドル・ユーロの同時代史 第38回~為替を武器にしたクリントン政権
90年春に始まったいわゆるバブルの崩壊を受け、当時は日本経済が「失われた10年」へ向け下降を続けていた時期だ。円高にならなければならない経済ファンダメンタルズはなかった。
にもかかわらず、市場参加者の総意によって作り出された円高環境は、マサチューセッツアベニュー・モデルが説いていたように、日本経済の構造を変えてしまった。輸出採算を悪化させた企業が挙って(こぞって)東南アジア諸国へ、次いで中国へ盛んな直接投資を始め、製造拠点を移動させ始めたからである。
このようにクリントン政権に徹底的な攻撃を浴びせられた後、「円の国際化」、「円の自立」、「円圏の確立」といった方向が日本国内で盛んに論じられ始めたのは当然の成り行きだったと言わねばならない。ただし威勢のよかったこれら議論は、結論を先に言えば、ただの議論で終わってしまった。
ブッシュがどんなに致命的な失敗を繰り返しても、クリントンの勝ちは馬鹿でかかった。
米国をぶっ壊れない国にしてしまった。
たぶん、そういうことだ。
追記:
このドルの一極体制の崩壊は、かなり多くの識者が予測していたようである。
■基軸通貨でなくなるドル 2005年3月15日 田中 宇
http://tanakanews.com/f0315dollar.htm
ただ、そこへソフトランディングする方法を模索していて、結局、サブプライムを震源としたハードランディングで、決着がつくということになる。
この記事を読んだときは、そんなばかなと思ったのだけど・・・。
PR
Calendar
October , 2025
September , 2025
July , 2025
Comments
Keyword Search