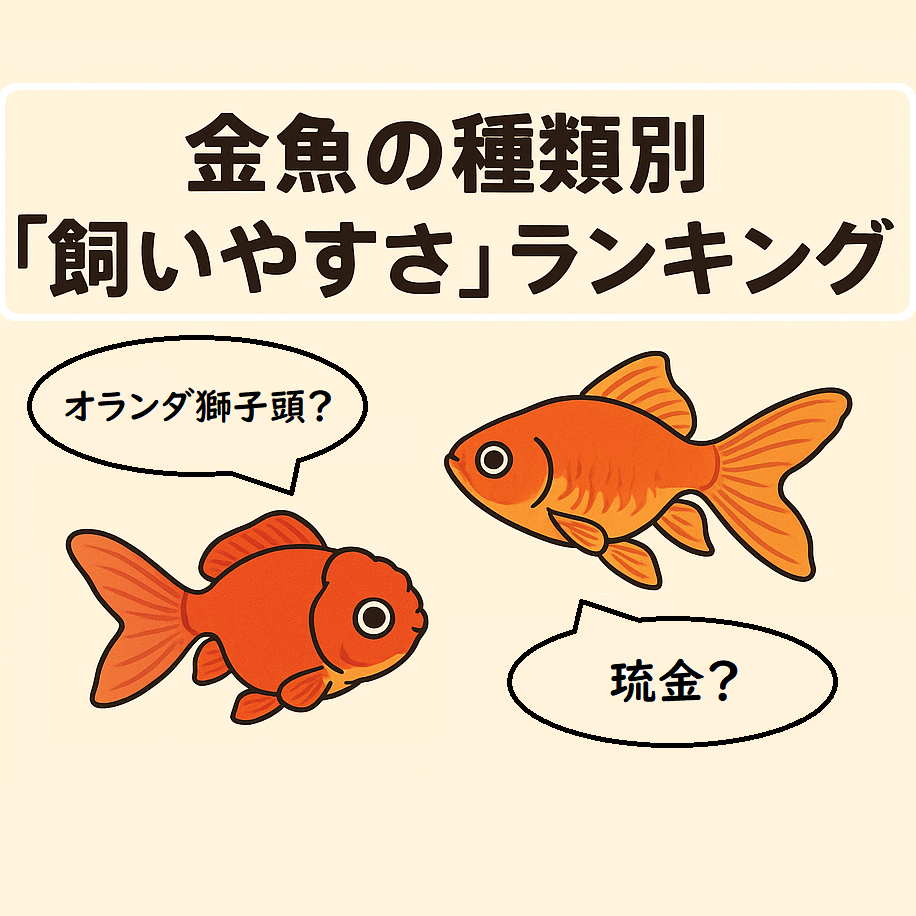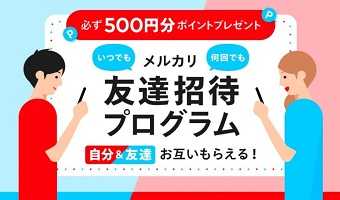2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年02月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-

金メダル
やりましたねぇ荒川選手。日本で初めての女子フィギアスケートでのゴールドメダル。朝テレビを見ながら感動してしまいました。点数にならないイナバウアーをあえて取り入れる勇気、どの選手よりも綺麗でした。イナバウアーっていうわざは1955年に西ドイツのIna Bauerという選手が初めて披露したわざなんだそうです。荒川選手のイナバウアーほど反り返ることはなかったみたいです。荒川選手が完成させたわざとなるのでしょうね。スタンディングオベーションが出たときには感無量でした。4年に一度のオリンピックで最高の演技を行う。大変な努力の成果だと思います。おめでとうございます。
2006/02/25
コメント(0)
-
杏仁
最近流行の杏仁豆腐(´ー`)僕も非常に大好きでよく買って食べています。昔は中華料理屋さんでしか食べることができなかったですが今ではコンビニでも売ってるいる定番デザートですね。実は杏仁というのは漢方医学で利用されている漢方薬でもあるのです。漢方では杏仁(きょうにん)と呼びます。バラ科のホンアンズまたはアンズの種子のことで「胸膈の気滞を利し、大腸気秘を通ず」といわれています。胸の気のうったいを去って停水を除き、呼吸困難や咳、心痛を和らげる作用があり、緩下作用があり便秘にも利用できます。また組織の酸素利用を高め、肝機能の改善、脳内の酸素消費量の増大が期待できます。普段何気なく食べている食材にも漢方は存在するのですね。
2006/02/21
コメント(0)
-

葛根湯
いや~、先週は大風邪ひいて大変でした。熱は上がるわ、咳は出るわ!結局週の後半はボロボロの状態でのお仕事でした。うちのスタッフも全員に移って全滅。長い1週間となりました。風邪を引いたときには漢方ではいったい何の薬を使うのかと考えた場合やはり一番に思いつくのが葛根湯(かっこんとう)ですね。葛根湯とは葛根(かっこん)麻黄(まおう)桂枝(けいし)生姜(しょうきょう)甘草(かんぞう)芍薬(しゃくやく)大棗(たいそう)の7種類の薬草を調合した漢方薬で風邪薬として今では薬局で比較的簡単に手に入ります。この中の葛根というのはマメのくず(澱粉)のことで身体上部の血行を良くするといわれています。そこに麻黄、桂枝が加わることにより発汗作用が強くなります。葛根湯は風邪だけの薬ではなく、胃炎なんかでもよく効いてくれるお薬です。葛根湯は確かに風邪には非常によいお薬と思いますがもっと簡単なお薬があります。葛根湯の中にも含まれていますがそれは生姜(しょうが)です。漢方では生姜(しょうきょう)と呼びます。漢方では生姜は諸毒を解し、寒を散じ、嘔を止め、咳を治し、気・血の滞りを循(めぐ)らすといわれています。咳がひどいとき、胃腸の弱っているとき、身体が冷え込んでいるときあと便秘なんかにも生姜はすばらしいお薬となるでしょう。生姜湯なんていうのがかなりいいんじゃないでしょうか。
2006/02/20
コメント(0)
-

漢方医学
東洋医学と西洋医学の違いは生薬を中心とした漢方薬や鍼灸治療などに目が行きがちですが一番の大きな違いは診察の深さにあると思っています。漢方医学の診察は四診といわれる独特な4つの診察方法に大別されます。四診とは望診・聞診・問診・切診の4つです。望診とは目で見て診察するという意味で栄養状態、皮膚の色や艶、顔の表情、特に舌の状態などを診察します。聞診とは耳で聞くという意味の診察方法で声、咳などの音、胃の音などのほか臭いも聞診に含まれます。体臭、口臭、排泄物の臭気などです。問診とは患者さんの話を聞くことから病気の原因を推察します。ただ単に患者さんだけではなく、家族などからも話を聞きます。病状も自覚症状だけではなく、生活環境や概応歴など細かく聞くことで治療方針を決定します。切診とは接触して診察する方法です。脈診、腹診、背診、切経(経絡の切診)などがあります。これらの診察方法は西洋医学となんら変わらないように思えますが、実際は一つ一つの診察が非常に深いということです。例えば脈診ひとつをとっても脈の種類は20種類以上あります。それらのすべてを判断することで病気の決定、治療法の確定、薬の選択を行っていきます。現在の医療は獣医医療もしかり、検査検査で病気の診断を行う傾向がありますが漢方医学のような診察方法も十分取り入れていくことが大事ではないかと思います。
2006/02/13
コメント(0)
-

漢方医学
今日ももう少し漢方医学について書いてみたいと思います。「気・水・血」の流れを見極め「汗・吐・下」を利用して正常に戻す今日はこのあたりを詳しく。ここにある「汗・吐・下」これが基本的な漢方の治療法になります。「汗」とは汗をかかせること汗と一緒に身体の中の毒を出させることです。「吐」とは吐かせること身体の上部の毒を出させるときに有効です。「下」とは下らせること排便、排尿と共に毒を排泄します。身体の状態をしっかり見極めて「汗・吐・下」の治療を行うということです。病気の状態を判断するのが「気・水・血」の流れです。なんとなくニュアンス的には解りそうですが実際はちょっと違うので説明しますね。「気」とはこんな感じです。生態は陰と陽の気が結合されている状態でこの気が離れると死に至ると考えられています。古代中国の学問、陰陽道が元になっていると思われます。この陰と陽の気のバランスを把握すことが気を診るということです。こんな言葉があります。「先天の元気」は腎に宿り、「後天の気」は三焦にうける生まれてより持っている気を先天の元気食べ物や生きることによって得られる気を後天の気といいます。三焦とは五臓六腑三焦の三焦です。これらの気が少なくなったり多くなったりすることにより病気になると考えられています。「水」とは身体の水分の状態皮膚のつや、むくみ、そして脈などを指します。特に脈は非常に重要で脈の打ち方にはいくつもの分類があります。「血」とは血液ではなく、顔色、粘膜の色などを指す言葉です。漢方医療は「気・水・血」これらの状態を把握することにより身体の状態が陰に傾いているのか、それとも陽に傾いているのかを判断しそれにあわせて、「汗・吐・下」を利用して身体のバランスを正常に戻していくこれが基本的な考え方となるのです。
2006/02/07
コメント(0)
-

漢方医学
漢方医学という言葉は 非常に良く使われます。しかし、漢方ってなんだろうと問われるとどういうものかと答えられる方は少ないんじゃないでしょうか?そこで今日は漢方医学の定義?原理?考え方みたいなところを簡単に書いてみようと思います。まず、病気の原因というのを漢方ではどう考えているかというと「外邪(がいじゃ)」「外傷」「内傷」の3つの要因重なり合ってが病気が起きると考えられています。「外邪」とは細菌やウィルスなどの外的要因ということになりますが実際は昔はそれらの存在自体がわからなかったので漠然とした要因としてとられられていたようです。「外傷」とは傷のことではなく風・寒・暑・燥・火などの気象現象のことで環境要因といえるでしょう。「内傷」とは喜・怒・思・憂・恐・悲・驚などの感情や飲・食・労・倦・などの身体の中で生まれてくる要因をさします。これらの3要素が漢方でおける病気の要因となります。漢方では「気・水・血」の3要素で生態は成り立っていると考えられています。この「気・水・血」の機能が崩れると病気になると考えられていました。「気・水・血」の流れを見極め「汗・吐・下」を利用して正常に戻すこれが漢方医学になります。ちょっと難しいですね。゜(゚´Д`゚)゜。
2006/02/06
コメント(0)
全6件 (6件中 1-6件目)
1