PR
カレンダー
コメント新着
キーワードサーチ
中学受験の国語は、親子のすれ違いが起きやすい科目。「読んだけどわからない」「記述が書けない」など、よくある悩みに共感しながら、原因と解決策をわかりやすく紹介します。親ができる声かけや考え方の整理法も掲載。親子で“考える国語”に一歩踏み出すヒントをお届けします。
はじめに:親子でぶつかる国語の“壁”
「この記述、何を書けばいいの?」「ちゃんと読んだの?」「読んだけど、わかんない…」 中学受験の国語では、親子の会話がすれ違う場面が少なくありません。特に記述問題や読解のズレは、親が教えようとしても子どもがピンとこないことが多いものです。今回は、そんな“あるある”を通して、親ができるサポートのヒントを探っていきます。過去の保護者の実例から原因と対策を記していますので、参考になれば幸いです。
あるある①:「記述問題で固まる」
【原因】設問の意図がつかめていない/答えの型が身についていない
【対策】とにかく書く
設問のキーワードに注目する練習
「理由+気持ち」の型で答える習慣
親の声かけ:「この設問は“なぜ?”って聞いてるね。理由を探してみよう」
あるある②:「親の説明が伝わらない」
【原因】抽象的な説明/子どもの読解レベルとのギャップ
【対策】最悪の場合は、模範解答を写させて、それに近い形に仕上げる
具体例を使って説明する
一緒に本文を読んで「どこにヒントがある?」と問いかける
親の工夫:「この場面、○○だったらどう思う?」と感情に寄せて考えさせる
あるある③:「読んだのに答えがズレる」
【原因】読解の視点がズレている/設問との接続が弱い
【対策】まずは設問に線を引く
本文と設問をつなぐ“根拠探し”の習慣
答えの根拠を言語化する練習
親の声かけ:「この答えの根拠、どこに書いてあった?」
国語は“わかる”より“考える”が大事です。親子で一緒に「どう考えたか」を言葉にする時間が、受験力を育てます。時間があれば書けたのか、時間があっても書けないのか、限界点をテストとテスト直しで見極め改善を積み重ねることが重要です。
あるある➂のケースが多いので改善の積み重ねが必要です。自分が書いた答えを先生に見てもらうことです。模範解答をそのまま教えてもらってきていたら「どう書けばそうなるか」を質問させましょう。個人的には模範解答はあくまでも模範であり、そのとおりになることはないとして指導しています。
まとめ
国語は“感覚”ではなく“考え方”で伸ばせる科目です。親子で「どう考えたか」を言葉にする時間が、受験力を育てる第一歩になります。すれ違いが起きたときこそ、対話のチャンス。親が“問いかける力”を持つことで、子どもの読解力は自然と育っていきます。
お困りごとがあるならば、早めに対策を。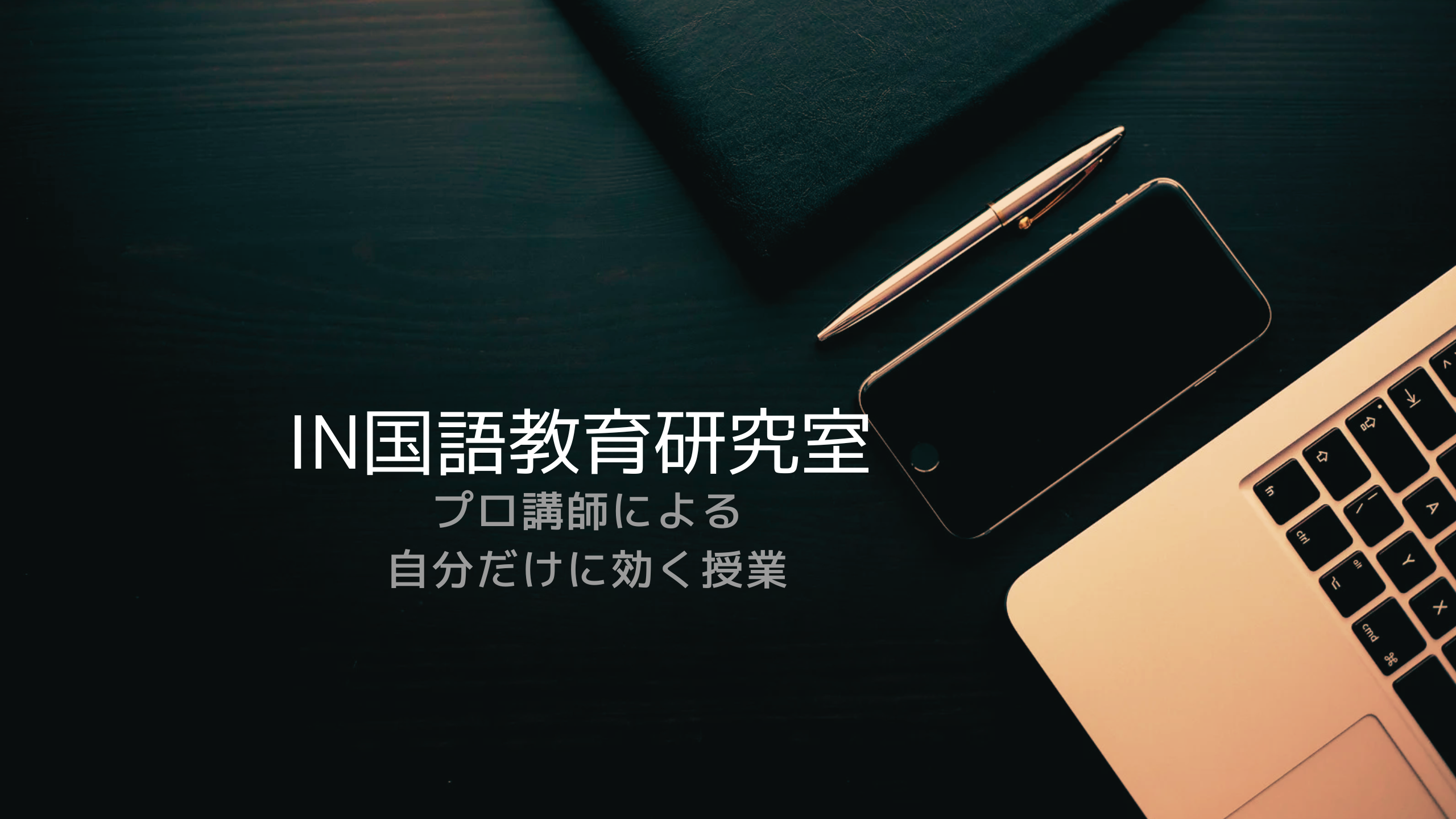
ご相談は IN国語教育研究室
まで。
頑張れ!受験生!
-
短所は認めたところから始まる 2025.11.21
-
見ていないふりをしながら、しっかり見る 2025.11.20
-
【ブログ更新しました】「安心して話せる… 2025.11.20









