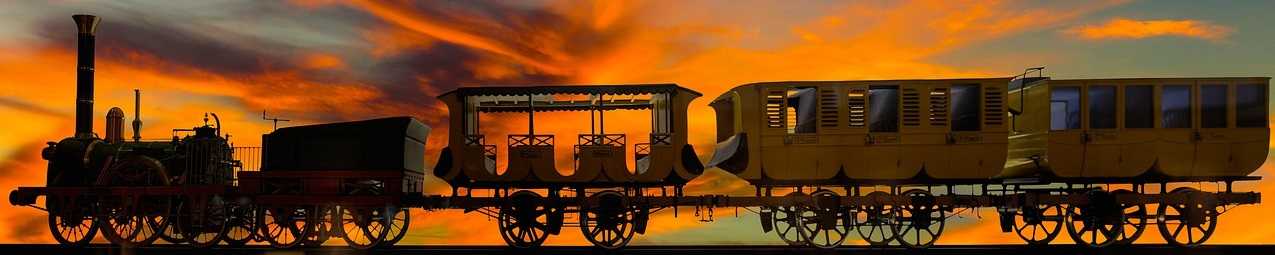2025年10月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-

【新発見・現地確認済】 観音院の座像(リンク集3 No.9)
にほんブログ村 観音院のもう一体の新発見の報告。在銘の高見観音の向かって右にある坐像です。発見者は「FDG公式さん」です。【FDG公式さん】 「FDG公式さんのH.P.」植木の陰にあり、坐像を見るアングルは限定されます。横から見ても前後の接合部が不明瞭です。胸厚の薄さは高見彰七作品の特徴です。頭部のワレは痛々しい。鉄筋も露出しています。背面はシンプル。表情も含めて、高見彰七作品と考えて良いでしょう。現地確認も完了しましたので、リンク集登録させていただきます。【 リンク集3 (No.9) 坐像 】 ・所在地: 愛知県豊田市千足町 観音院 ・製作年月: 不明 ・作家銘: なし ・寸法: 高さ67cm, 胸部幅35cm, 胸部厚15cm 台座 30×30cm ・発見者: FDG公式さん●この坐像は誰か?この坐像は仏像とも、人物像とも捉えられます。そのヒントは、観音像と坐像の中間位置手前にある石板にあります。石板には「仏縁 〇〇〇〇〇(個人名)」とあります。観音像の向かって左隣の大黒天にも同じ個人名が施主としてあり、「平成11年」の年号もあります。高見彰七作品と少し年数が離れますが、「仏縁」の名のとおり、この石板の方が、坐像に所縁がある可能性がありそうです。観音院の住職の可能性もありますが。興味深い高見彰七作品でした。【 ショコラドゥショコラ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.10.29
コメント(38)
-

【新発見・現地確認済】 観音院の観音菩薩像(リンク集2 No.36)
にほんブログ村 「高見彰七」在銘の観音像、新発見の報告。発見者は「FDG公式さん」です。【FDG公式さん】 「FDG公式さんのH.P.」今回は在銘の作品、疑いなく高見彰七です。現地確認も完了していますので、リンク集登録させていただきます。【 リンク集2 (No.36) 観音菩薩像 】 ・所在地: 愛知県豊田市千足町 観音院 ・製作年月: 不明 ・作家銘: あり。「高見彰七」 ・その他: 台座に家紋 ・寸法: 観音像 高さ160cm, 胸部幅43cm, 胸部厚30cm 台座 上部幅73cm, 奥行60cm, 高さ110cm ・発見者: FDG公式さん高さ160cmの観音像が高さ110cmの台座に乗った大きな作品です。台座には家紋があり、特定の人物のために制作された観音像だと推定されます。穏やかな表情が多い高見観音ですが、こちらの高見観音は凛々しいお顔です。高見観音の特徴、側面の前後接合部(ヒビ割れ)もあります。台座背面には「高見彰七作」と縦書きされた銘があります。数少ない在銘作品は、いずれも特定の奉納先に向けて作られた作品。「特定の奉納先」ということが、作品が在銘になる必要条件なのかもしれません。「FDG公式」さん、新発見おめでとうございます。そして、いつもながら、ありがとうございます。以前のこのエリア付近も探索していましたが、観音院は見落としていました。あらためて、見落としがちな場所にこそ、高見彰七作品はあるものだと思いました。観音院の別の高見彰七作品については、別記事にて検討いたします。【 フルーツロールケーキ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.10.27
コメント(27)
-

高見彰七作品をAIでぬいぐるみ化
にほんブログ村 多忙なのにAIで遊んでしまいました。◇高見観音をぬいぐるみ化ちょっとやりすぎ感があります。これが元画像。別の高見観音でトライ。これは良い感じ!◇高見彰七のお狐様キバも、妙にかわいい。◇高見彰七の神馬予想通りです。◇高見彰七の地蔵菩薩ちょっとかわい過ぎ?◇茶々丸ちゃんmarnon1104さんの茶々丸ちゃんでトライ。画像の無断借用すみません。変換されなかった尻尾が残念。別の画像が良さそうです。とりあえず楽しめました。以下に使い方をご紹介します。●AI Google Geminiの使い方1)下記にアクセス【Google Gemini】 「Google Gemini」2)「ツール」を左クリック。「Imagenで画像生成」を選択3)「画像の説明を入力」欄に画像をドロップ4)続けて下記のコマンドを入力 (動物の画像の場合) Generate an image showing this animal as a simplified and deformed as an anime-like plush toy (made of short-pile, soft-touch polyester knit fabric).動物以外の画像では、コマンド中の”animal”を変更ください皆さん、お楽しみください。【 抹茶スイーツケーキ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.10.21
コメント(30)
-

【新発見・速報】 観音菩薩像と坐像
にほんブログ村 高見彰七作品候補・新発見の連絡を受け、現地確認しました。今回はその速報です。発見者は、皆さんもよくご存じの「FDG公式さん」。【FDG公式さん】 「FDG公式さんのH.P.」しかも今回は観音像と坐像の2体。像の高さだけで160cm、台座を含めると高さ270cmの大きな観音像。さらに珍しい在銘の高見観音です。もうひとつは坐像。これも現地確認で高見彰七作品と判断しました。詳細は次回以降でご紹介します。リスト登録上、観音像と坐像は各々別の紹介となります。都合により詳細のご報告が遅れそうですので、まずは速報でご紹介させて頂きました。【 抹茶スイーツケーキ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.10.19
コメント(32)
-

力石の重さは?
にほんブログ村 矢作橋近くの小さな八幡社。その境内には力石(ちからいし)があります。大人が抱え持てそうな力石。この力石の重さはいくらでしょうか?ヒントは力石をよくご覧ください。答えは最後に。答えを検討中、八幡社の狛犬をご覧ください。小さく、憎めないお顔の狛犬。阿吽ともにかわいらしい。しっかり和ませて頂きました。さて、力石の重さはおわかりでしょうか。では、答えです。力石の表面には「四十メ目」と書かれています。「メ目」とは「貫目」。つまり、この力石は「40貫」の重さがあります。1貫は3.75kgですので、40貫は150kg。この力石は重さ150kgあります。よく境内で見る力石。気軽に持ち運ぶには、ちょっと重いですね。【 防犯 窓ロック 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.10.17
コメント(26)
-

【訂正版】 矢作川橋近傍の観音菩薩像(リンク集2 No.35)
にほんブログ村 矢作橋近くの高見彰七作品、新発見の報告。現地確認での訂正箇所を反映した、リンク用まとめを掲載します。発見者は「FDG公式さん」です。【FDG公式さん】 「FDG公式さんのH.P.」観音像は特に発見が困難な場所にありました。矢作川沿いの小道、名鉄鉄橋近くに観音像はあります。少し小柄な観音像ですが、綺麗な造りです。高さ1m以下の小振りな観音像ですので、前後接合面での割れはありません。小振りな観音像では、前後側面のワレがない高見観音が多くなります。高さ1m付近を境に、高見観音の製作方法が異なるのかもしれません。像の後頭部付近では大きな骨材(砂利)が露出しています。モルタル像でこれほど粗く大きな骨材は通常は使いません。骨材が表面に露出して、繊細な細工を損なう恐れがあるためです。高見彰七作品では、像後部には粗い骨材を含むモルタルがしばしば使われます。これには粗い骨材を配合し、像の強度を高めようとした意図があったと思われます。「背面のモルタルに粗い骨材を配合している」今回の観音像にも、この高見彰七作品の特徴があります。観音像は台座から外れてしまっています。台座には「交通安全 南無阿弥陀仏」(推定)の文字があります。文字のある面が前面の様です。本来この観音像は、交通量の多い国道1号線(旧東海道)、矢作橋付近にあったと考えられます。移設時に、観音像は台座から外れたと思われます。隣には弘化2年と書かれた石柱があります。この弘化2年の石柱は、同じ矢作川支流、足助町ににある弘化2年の石柱との関連が推定されます。「足助町の弘化2年の道標」【画像出典】 「足助町 弘化2年の道標」この石柱や台座と観音像の間には、瓦片や小石が詰められています。また観音像は両者側に傾いています。石柱と台座は観音像転倒防止の支えとなっています。現地確認の結果、高見彰七作品と判断しました。リンク集登録させていただきます。【 リンク集2 (No.35) 観音菩薩像 】 ・所在地: 愛知県岡崎市矢作町 名鉄本線矢作川橋近傍 ・製作年月: 不明 ・作家銘: なし ・その他: 台座に「交通安全 南無阿弥陀仏」(一部地中埋没) ・寸法: 観音像 高さ65cm, 胸部幅25cm, 胸部厚22cm 台座 幅25cm, 奥行25cm 石柱 幅7寸, 奥行8寸, 地上露出高約30cm ・発見者: FDG公式さんこれで、高見彰七作品は117体確認済みとなりました。消失作品7体や検討中の作品1体もあります。自力では発見は困難な今回の新発見。引き続き情報をお待ちします。いつもながら、FDG(フィールド・ティスカバリー・ゲーム)の探索力には驚きます。「FDG公式」さん、新発見おめでとうございます。【 ホテルオークラ クリスマスケーキ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.10.13
コメント(46)
-

日本武尊の陶像(矢作神社)
にほんブログ村 矢作橋から川沿いに歩くと、矢作神社があります。川沿いの道からやや急な坂道を、雨に濡れた落ち葉で滑らないように注意しながら下ると矢作神社です。この神社には、日本武尊の陶像があります。反乱を起こした賊を、日本武尊がこの地で撃破したという伝説にちなみます。その際には矢作川に生えていた竹で作られた矢が使われたそうです。この日本武尊像の作者は、杉浦庄之助。昭和18年(1943年)に製作されました。杉浦庄之助は愛知県高浜市の鬼瓦師。鬼瓦だけではなく、陶製の塑像も作られています。調べると、杉浦庄之助は明治33年生まれ、没年は昭和41年。この大きな日本武尊像は3分割して、五郎作土管窯で焼かれたそうです。杉浦庄之助氏は、知名度のある作家の様です。以前を私が紹介した高浜市の大山緑地。ここの2体の仔狸も杉浦氏の作品です。【関連記事】 「たぬきさん、どうして驚いているの?」鬼瓦師でありながら、陶製の作品も残した杉浦氏。愛知には興味深い作家が多くいるものです。【 ソーラー防犯灯 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.10.11
コメント(30)
-

青銅の馬頭観音は雨の中
にほんブログ村 名鉄矢作橋駅から矢作橋への経路の途中、光明寺がありました。お寺を外から眺めると、次の方のお姿が。大きな馬頭観音像。珍しく青銅製です。近代に造られた新しい馬頭観音とは思いますが、なかなか良いお姿です。折悪く激しい雨。この雨がなければ落ち着いてご挨拶できたのに。とても残念な雨でした。【 防犯 防草 ジャリ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.10.09
コメント(33)
-

矢作橋のふたりの出会い
にほんブログ村 先日の推定・高見観音のすぐ近くには矢作橋があります。そこには次の「出会いの像」があります。これは日吉丸(後の豊臣秀吉)と蜂須賀小六の出会いに関する伝説を示しています。私はこの出会いの像の付近に、推定・高見観音はあったのではと考えています。その根拠は下記の通り。1)国道1号線沿いであること 矢作橋は国道1号線が矢作川を越える橋。 交通安全を祈願して建てられた高見観音に相応しい設置場所です。2)弘化2年の石碑と共にあること 足助(あすけ)町の弘化2年の石碑が街道の道標であったように、 観音像の横の石碑も街道沿いにあったと推定されます。 足助町の石碑は矢作川近くにありますので、 今回の石碑も、旧東海道(国道1号線), 矢作川付近にあったと推定されます。3)五色園での浅野祥雲作品の存在 五色園の浅野祥雲のコンクリート像は、大半が宗教に関わる作品です。 しかし宗教とは無縁の異彩を放つ作品があります。 それが次の「矢作橋の出会いの像」です。 矢作橋で寝ていた日吉丸。 そこを通りかかった蜂須賀小六一行が、日吉丸の頭を蹴りました。 日吉丸は一行に「詫びろ」と詰め寄りました。 日吉丸の勇敢さを示す逸話ですが、 実際にはふたりの生きた時代は異なり、出会いは伝説にすぎません。 浅野祥雲は高見彰七より、1歳年下。 しかし、浅野祥雲はプロ作家、高見彰七はアマチュアです。 高見彰七が観音像を建てる場を選ぶ時、 同世代のコンクリート像作家・浅野祥雲を意識して、 矢作橋付近を選んだとしても不思議ではないでしょう。以上は私の空想に過ぎません。しかし、高見彰七と浅野祥雲が同世代であったのは事実です。もし高見彰七が矢作橋に浅野祥雲の影を見ていたとしたら、ふたりの作品の類似性を見るという、新たな見方が必要になるのかもしれません。【 太閤秀吉献上ようかん 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.10.07
コメント(29)
-

【現地確認】 矢作川橋近傍の観音菩薩像 その4
にほんブログ村 矢作川橋近傍の推定・高見観音、現地確認の最終回です。今回は弘化2年の石碑についての確認です。結論としては、やはりこの石碑は観音像の転倒防止に使われていました。1)観音像が石碑と台座側に傾いて置かれている 次の写真を御覧ください。 観音像は台座に支えられるとともに、石碑側に傾いています。 石碑が観音像の転倒防止に役立っているのがわかります。2)石碑が前向きに傾いている 観音像手前の弘化2年の石碑は、大きく前傾しています。 観音像の支えとしての意図がうかがわれます。3)石碑,台座と観音像の間に詰め物がある 次の写真でおわかりでしょうか。 台座と観音像の間に瓦の破片が詰められています また石碑と観音像の間にも数個の石が詰められていました。 観音像を固定しようとする意図がみられます。4)詰め物の瓦は小石は固定があまく、実際は機能していない 詰め物には隙間があり、固定されていません。 実際には観音像の固定には役立っておらず、 プロの業者の仕事ではありません。 最終的な観音像の設置は、地元の素人が行ったと推定できます。以上から、弘化2年の石碑は、観音像の転倒防止に使われていると確認できました。また詰め物の緩さなどから、最終的には地元住人が設置に関わったと思われます。幾つもの項目が判明し、有意義な現地確認でした。それにしてもこの場所は、意外に電車からは目立つ場所です。私の現地確認中でも、往復5~6本の電車が鉄橋を通過しました。さすが運行本数の多い名古屋鉄道本線です。電車の車窓から見ていた人からは、雨に濡れながら、草むらに埋もれて、巻き尺を手にした不審者が見えたことでしょう。【 防災対策: 非常食 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.10.04
コメント(40)
-

【現地確認】 矢作川橋近傍の観音菩薩像 その3
にほんブログ村 矢作川橋近傍の推定・高見観音、現地確認の続きです。前に観音像の高さが65cmだったのが予想外だったと書きました。観音像の高さは高見彰七作品を考えるうえで重要です。以前に、高さ70cm程度以下の観音像と、120cm前後以上の観音像には違いがあると書きました。それはおそらく製法の違いです。120cm前後以上の観音像では、像の前面と背面の接合部でヒビ割れが確認できます。これは、前面と背面を接合して製作したためと思われます。前面と背面をセメントやノロで接合した場合、接合面が弱くなり剥離しやすくなります。一方で、70cmクラス以下の観音像では、接合面の割れがない像が多くなります。単純に接合面にかかる負荷が大型像の方が大きいためかもしれませんが、私は観音像の大小で製作方法が異なるためと考えています。今回の観音像も、明確な接合面のヒビ割れは確認できませんでした。私が接合面からの剥離と考えていた像の足元の段差も、観音像前面の着物のたもとの表現と確認できました。つまり今回の観音像には前後間のヒビ割れは確認できず、像の足元付近での剥離は見つかりまでんでした。やや異例ではありますが、この観音像は下半身背面で段差のある造形をしています。ヒビ割れは確認できず、高見観音としての特徴はひとつ減ります。ただし頭部背面の粗いモルタルの使用や鉄筋の使い方などの特徴はあります。やや根拠は薄くなりましたが、現地確認でも高見観音だという印象は変わらず、高見観音としてのリスト登録は変わらずリンク予定です。また台座のどちらが前かという疑問はありましたが、交通安全などの文字がある反対面は粗い仕上げでした。文字のある面が観音像の前側で、台座に残る観音像の一部は、観音像の前面の裾部分と推定されました。ところで、弘花2年の石碑がなぜあるのか。これも現地確認でわかりましたので、次回ご報告します【 防災対策: 寝袋 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.10.02
コメント(32)
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
-

- 私なりのインテリア/節約/収納術
- 複利の効果ってすごい!のお話
- (2025-11-15 00:31:49)
-
-
-

- 素敵なデザインインテリア・雑貨♪
- [送料無料] ダーツ & はんこ & …
- (2025-11-13 21:04:35)
-