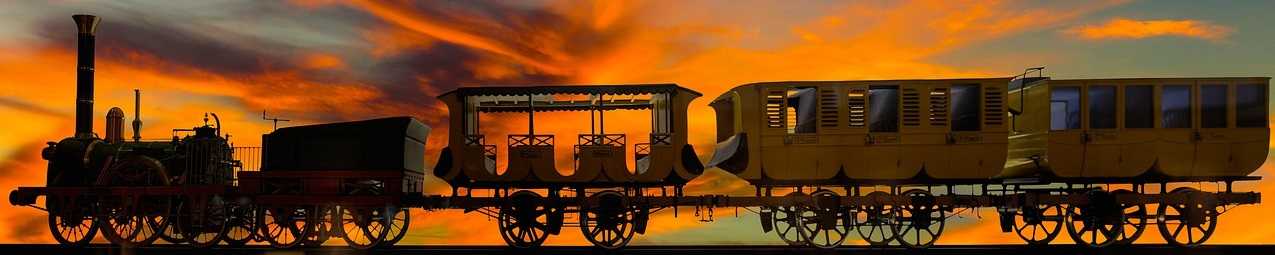2025年02月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-

巨大マヨネーズの中身は?
にほんブログ村 久しぶりに名古屋駅前を歩きました。名古屋駅前に置かれたマヨネーズ、容器から中身がはみ出していました。中身はナナちゃんによく似ています。どうやら、100周年が嬉しかったようですね。さて、その後、地下街を歩いていて、ヒヤリとすることがありました。以前に化石をご紹介したように、名古屋の地下街の床は、大理石などが多用されています。その地下街の曲り角。死角から来る人に注意して、視線は上の方にあります。対向者がいないことを確認して、曲がり角で方向転換。その途端、ズルっと足が滑ってよろめきました。なぜ?と思い確認すると、写真のような鎖が落ちていました。(アフィリエイトリンクで、似た商品を探しました)もともと足元がおぼつかない私。しかも革靴で、大理石の上の鎖を踏めば当然滑ります。特に曲がり角で方向転換中では……。とりあえす、通路の隅に鎖を避けて立ち去りましたが、完全に撤去すれば良かったと反省しています。あの後、誰も踏まなかったことを願います。< ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.02.28
コメント(30)
-

一畑山薬師寺の涅槃像
にほんブログ村 先日ご紹介した蛇ヶ谷龍神の小さな高見観音。この観音像は一畑山薬師寺の駐車場脇にあります。一畑山薬師寺はテレビCMなどで有名。2月23日の朝刊にも大きな広告が掲載されていました。それでも私は一畑山薬師寺を参拝したことがありませんでした。なぜならこの寺院の口コミ情報があまり良くなかったからです。結論から申しますと、評判ほど悪い感じはありませんでした。食事はしませんでしたが、境内にある食堂も良心的な価格。祈祷を受けると入浴できる温泉(御霊泉)もありますが、価格1,500円以上というのも妥当でしょう。なにより参拝者が非常に多く、1,500台駐車可能な駐車場に、次々と列をなして参拝者の車がやってきます。私は歩きましたが、藤川駅から送迎バスもあるそうです。近くの道の駅にもタクシー乗り場はありませんが、電話してタクシーを呼ぶこともできたそうです。私も登りは足場の悪い登山道を登りましたが、下りは舗装され路側には完備された歩道や階段を利用しました。一畑山薬師寺は臨済宗妙心寺派のお寺。この寺院で有名なのは、全長8.9メートルの涅槃像。ただ全身純金貼りという装飾は、好みが別れるでしょう。多宝塔にみえるのは、水子地蔵を祀った建物。鉄筋コンクリート造り。昭和34年にできた本堂はコンクリート造り。巨大な建屋から警戒心を持つ方もおられるでしょう。以上のような点は、私は気になりません。これ以上に警戒心を持たざるを得なかった寺院はいくらもあります。ただ、やめて欲しいと思ったのは、たえず境内に流れている女性の声でのメッセージ。日本語ですが頻繁に英語が織り込まれ、参拝者にメッセージを伝えています。よく覚えていませんが、”Blieve your heart.”などと言っていました。境内に流れる大音量のメッセージは不要だと思います。参拝は静かにしたいものです。あと、高見観音の扱いをもう少し良くして頂ければ、少なくとも私は喜びます。【 食用金箔 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.02.25
コメント(48)
-

冷たく強い風が吹く日は 頬を紅く染めて
にほんブログ村 桜より梅の方が日本らしい、そう思うのはなぜだろうか。一斉に咲き、舞い散る桜は美しい。とても美しいが、華やかすぎる。それに比べ、梅の花はとても静かだ。まだ寒い日も、強い風が吹く日も、梅の花は細い枝にしがみつき、咲き続ける。また今日も、冷たく強い風が梅をたたく。それでも梅は風に耐える、頬を紅く染めながら。せめてあの風が、春を招く風であったなら。梅を見守ることしかできない非力さに、ただ、そう願うことしかできない。【 のし梅 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.02.23
コメント(38)
-

備前焼 木南知加選の狛犬
にほんブログ村 中断していた村社 灰寶神社の続きです。二宮尊徳像の他にマニアックな発見もあったとお話しました。それはこちらの狛犬です。愛知県ですから常滑焼?そう思いましたが、よく見ると備前焼です。しかも私が好きな作家、木南知加選の作品でした。作家銘もあります。備前焼の狛犬は、木村家の作家の作品が多くあります。木南知加選の狛犬は多くはなく、愛知県で出会えるとは思いませんでした。備前焼 泰山窯の作家、木南知加選。その造形は、ブロンズの技法を活かした独特なものです。好き嫌いが別れる作品だと思います。みなさんは如何でしょうか。マニアックですが、陶器のブログらしいご紹介でした。【 備前焼 木南知加選 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.02.21
コメント(34)
-

高見彰七のコンクリート像 リンク集 更新
にほんブログ村 高見彰七のコンクリート像 リンク集を更新しました。全115体となりました。●【リンク集 トップ】 「高見彰七リンク集」高見彰七リンク集2「観世音菩薩像」に次の2体を追加しました。(No.33)【豊田市 阿弥陀院】(No.34)【豊田市 蛇ヶ谷龍神】引き続き、新発見の情報をお待ちしています。【 桜餅だんご 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.02.19
コメント(38)
-

【新発見】 高見彰七作品リンク集2 No.34 蛇ヶ谷龍神
にほんブログ村 岡崎市の名鉄 藤川駅。この駅の周辺は、東海道五十三次の藤川宿の遺構が点在します。寺院や神社も多く点在するので、藤川駅周辺を散策しました。ただ散策には、ひとつ課題がありました。多くの文化財は旧東海道沿いにありますが、一畑山薬師寺だけが山の上にあります。一畑山薬師寺はテレビCMもよく流れている寺院。藤川駅にはタクシー乗り場もなく、仕方なく山歩きを決行しました。まずは関山神社に行きます。その境内から関山神社奥の院を経由して、一畑山薬師寺に向かいます。こちらがその参道(登山道)です。石に足を取られやすい、かなり急勾配の参道。この岩場は波蝕巨礫群という地層によるものと説明書きがありました。この様な道を、駅から2km、標高差200m……。どうにか到着した一畑山薬師寺には、広い駐車場がありました。その駐車場の片隅に、蛇ヶ谷龍神の小さな祠があります。蛇ヶ谷龍神はこの地に一畑山薬師寺を開けとお告げした蛇神様を祀っているそうです。祠の説明板の下に見慣れたものがあります。一目でわかる、高見観音です。高見観音では最も小さいクラスです。前後の接合面は不明瞭です。小型の像は一体で製作しているのかもしれません。後から見ると、鳥の糞の汚れが痛々しい。それにしても置かれ方が適当です。固定されていない様子で、周囲の石で補強しています。祀る場所に困り、誰かが置いたものでしょうか。岡崎市の南東部では、高見観音の発見例はありませんでした。珍しい地域での発見例として、高見彰七作品リストに登録です。リンク集2 (No.34) ・所在地: 岡崎市藤川町王子ヶ入 蛇ヶ谷龍神 ・製作年月: 不明 ・作家銘: なし ・特徴: 高さ45cm, 胸部幅 12cm, 胸部厚 9cm, 裾幅 15cm【 置時計 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.02.16
コメント(48)
-

大きな二宮尊徳像にご挨拶
にほんブログ村 名鉄 平戸橋駅から越戸駅までの間にある神社をもう1社ご紹介します。村社 灰寶神社です。村社ですが、境内の広い神社。ここに私の目を惹くものが2点ありました。まずは大きな二宮尊徳像。私は見上げて撮影していますが、2m程度の大きな像です。高さは計っていません(笑)。この大きさ、少年ではありませんね。二宮尊徳を児童虐待と批判する声もある今日、新しい二宮尊徳像自体、珍しいと思います。もうひとつの注目は、とてもマニアック。マニアック過ぎて伝わらないと思いますので、若干の説明も含めて、次回にご紹介します。【 おやすみライト 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.02.14
コメント(40)
-

冬に咲くロウバイは やさしくうつむく
にほんブログ村 凍てつく冬の寒さに耐えるかのようにロウバイはうつむいて咲く。風雪からシベを守るためだろうか。うつむき、それでもなお冬にあがらうその姿は私たちに生きるものとしての共感と励ましを与えてくれる。冬に咲くにも関わらずロウバイは虫たちに受粉を助けられる虫媒花だ。数少ない冬の虫。ロウバイと虫たちの一期一会の出会いがそこにある。ロウバイはうつむくことで虫たちを守る傘になろうとしているのかもしれない。凍てつく冬の日に、温かい出会いがある。そんなやさしいロウバイが美しい。【 陶器の浮き玉 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.02.11
コメント(51)
-

身掛山 観音院は石仏だらけ
にほんブログ村 豐田市の身掛山 観音院。前鬼・後鬼を従えた役小角の他にも、非常に多くの石仏があります。その一部をご紹介しましょう。新しいけど、大きな馬頭観音様。頭部には、馬と牛の双方が刻まれた、やや珍しい石仏です。観音院の入り口付近の観音様。不動明王様。外に置かれた役小角様。烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)。案内板の表記では「沙」が抜けています。六地蔵。童観音(わらべかんのん)とのこと。むしろ、童地蔵か、童道祖神(双体仏)と呼びたくなりますが。塀沿いにあるのは、千体仏でしょうか。小さな石仏は観音像です。ほんの一部をご紹介しました。ご紹介は新しい石仏ばかりになりましたが、古い石仏も多くあります。古い石仏は各地から引き取って保存されたのでしょうか。ありがたいことです。【 おやすみライト 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.02.09
コメント(40)
-

愛らしい前鬼と後鬼
にほんブログ村 名鉄 平戸橋駅から越戸駅までの間にある寺院や神社。ここにも面白いものが幾つもありました。その一部をご紹介します。ますは、身掛山 観音院。この寺院には、新旧、数多くの仏像などがあります。私が惹かれたのはこちらです。前鬼・後鬼を従えた役小角(えんのおづぬ)がおられます。前鬼・後鬼は瓦製ですが、愛らしいお顔をされています。アップでもご覧ください。鬼ですが憎めません。役小角もこの鬼ならば、従えるというより、癒してくれるペットと思っているかもしれません。【 ミッフィー雛人形 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.02.06
コメント(52)
-

リンク集2 No.33 阿弥陀院の高見観音 続き
にほんブログ村 阿弥陀院の観音像が、高見彰七作品とする理由を紹介します。1)観音像の姿勢が体をくねらせた「流れ形」 これは皆さんも同意かと思います。 衣装の造形にも高見観音の特徴があります。2)像の前後に接合部がある 像の前後を別に作成して接合する高見彰七の製造法の特徴。 比較的綺麗ですが、接合面に沿ってヒビ割れもあります。3)手を体と一体化させている これも高見観音の特徴。 腕の破損を防ぐためでしょう。4)寸法比が高見観音の中型サイズ 中型の高見観音像は、 高さ:胸幅:胸厚=120~160:30~50:20~30。5)顔に明るい褐色の着色が残っている 高見観音で使われる着色が残っています6)顔のモルタルはきめ細かく、体のモルタルは粗い お顔は滑らかに仕上げられている7)お顔がご親族に似ている お顔に見覚えがあると思っていましたが、 前回の記事掲載後に気づきました。 ゆるいなどと書いてしまい、すみませんでした。ところで、阿弥陀院のお堂内は綺麗で、御住職もおられるようです。ただ、御堂の外装は修繕が必要にみえます。維持管理は大変とは思いますが、お寺も観音像も永く守っていかれますようお願いしたいと思います。【 孫が描いた似顔絵のハンカチ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.02.04
コメント(37)
-

【新発見】 高見彰七作品リンク集2 No.33 阿弥陀院
にほんブログ村 豊田市の名鉄 平戸橋駅で下車。隣の名鉄 越戸駅までの一駅間を国道153号線に沿って歩きました。この道沿いのわずかな区間に、5か所も寺院や神社があります。それらをのんびりと散策しました。新発見は、平戸橋駅から最も近い阿弥陀院でありました。入り口がわからず、阿弥陀院の墓地から入りました。すると墓地の中に、見慣れた後ろ姿が。高見観音と確信、あわてて近寄ります。前に回り込んで、こんにちは!えっ!!え、えっ!!なんてゆるい表情なのでしょう。今までにないゆるさです。ひとめぼれしてしまいました。それにしても、実寸以上に厚みが薄く感じます。しばらく観察したり、寸法を計ったり。角度を変えて散々ながめ、思案して、高見彰七作品と判定しました。リンク集2 (No.33) ・所在地: 豊田市平戸橋町太戸 阿弥陀院 ・製作年月: 不明 ・作家銘: なし ・特徴: 高さ155cm, 胸部幅 33cm, 胸部厚 19cm,裾幅 60cm本作品、コンクリート像好きであれば、一見の価値があります。ぜひ現地でご覧ください。本当に高見観音?そういう声も多いと思います。次回は、私が阿弥陀院の観音像を高見彰七作品と判定した理由をご説明します。【 ゆるかわ 似顔絵 名入れ マグ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.02.01
コメント(44)
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
-

- 家を建てたい!
- 30年以上経てば、全て交換です
- (2025-11-29 20:20:02)
-
-
-

- 手芸・ハンドメイド好きなヒト、大集…
- 22cmドールスタンドカラーブラウス製…
- (2025-11-29 13:17:55)
-
-
-
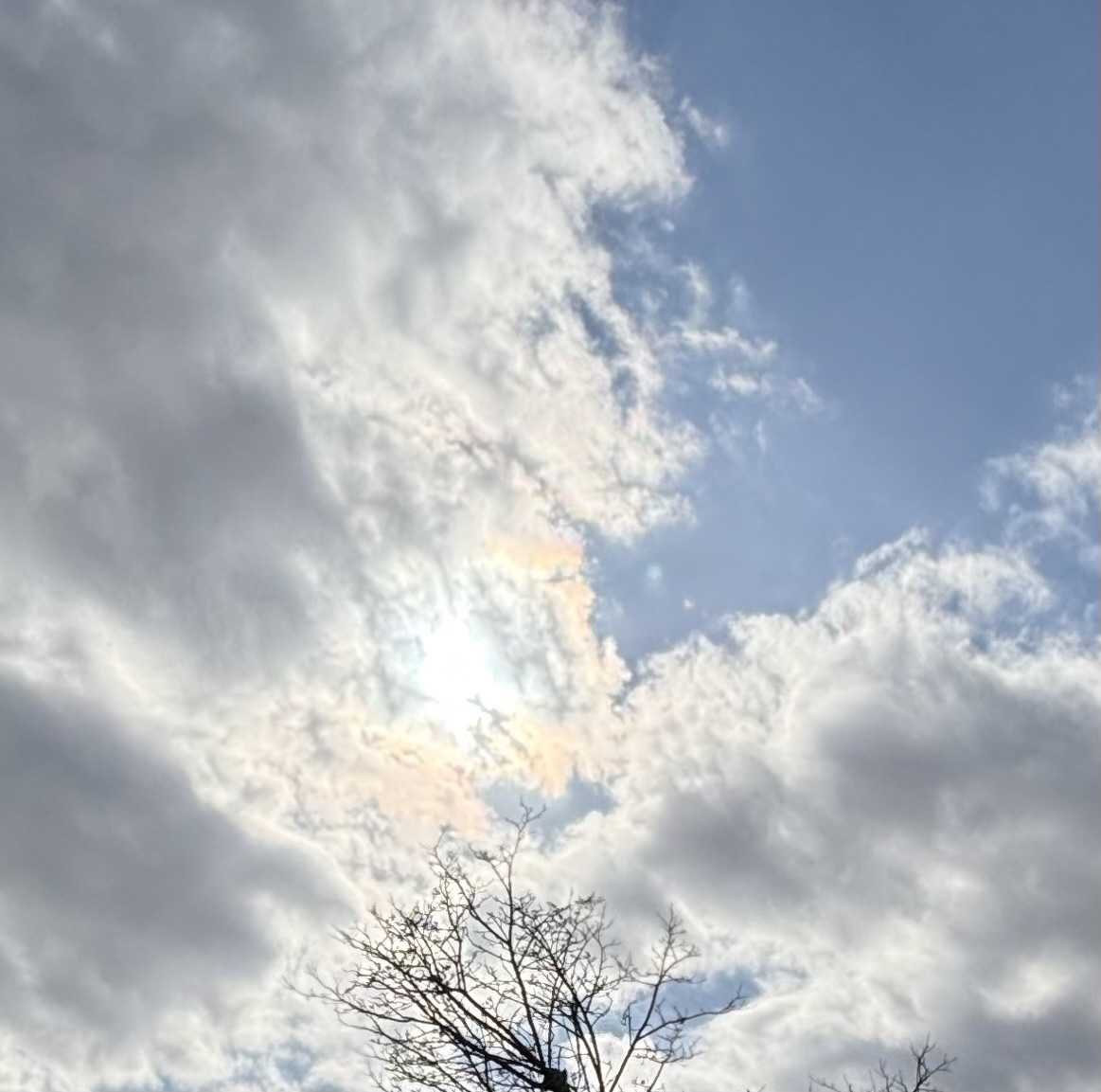
- 日常の生活を・・
- 娘の送迎でトータル3時間も運転して…
- (2025-11-28 21:31:25)
-