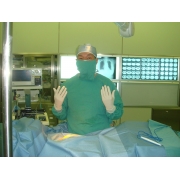![]() 昔、キノコはすべて天然物であった。天然物のキノコは発生する条件が整わないと発生しない。すなわち、寄生する植物があることと温度と湿度である。寄生する植物はそのキノコによって相性がある。そして適当な湿度と温度のもとで、菌糸がその植物の主に樹皮の下をはびこり、キノコの発生に適した条件になるとキノコが出てくるというわけである。
昔、キノコはすべて天然物であった。天然物のキノコは発生する条件が整わないと発生しない。すなわち、寄生する植物があることと温度と湿度である。寄生する植物はそのキノコによって相性がある。そして適当な湿度と温度のもとで、菌糸がその植物の主に樹皮の下をはびこり、キノコの発生に適した条件になるとキノコが出てくるというわけである。
![]() その条件とは、適当な湿度と1日の温度差が重要であると言われる。秋に朝晩冷え込むようになり、1日の温度差が一定以上に大きくなると発生する。
その条件とは、適当な湿度と1日の温度差が重要であると言われる。秋に朝晩冷え込むようになり、1日の温度差が一定以上に大きくなると発生する。
![]() キノコは菌類の繁殖のための形態、子実体と言われる。開いたキノコを採ってきて、黒い紙の上に置いておくとキノコの胞子が落ちて胞子紋ができる。キノコの繁殖は菌糸がはびこることとこの胞子によるものとある。菌糸がはびこる方法ではその樹が完全にキノコの利用する養分が吸い付くされてしまうと、それ以上続かない。するとキノコは胞子の状態で空中をただよい、次に寄生できる樹をさがすわけである。
キノコは菌類の繁殖のための形態、子実体と言われる。開いたキノコを採ってきて、黒い紙の上に置いておくとキノコの胞子が落ちて胞子紋ができる。キノコの繁殖は菌糸がはびこることとこの胞子によるものとある。菌糸がはびこる方法ではその樹が完全にキノコの利用する養分が吸い付くされてしまうと、それ以上続かない。するとキノコは胞子の状態で空中をただよい、次に寄生できる樹をさがすわけである。
![]() マツタケとかホンシメジといった、生きた樹の根と絡み合った菌根形成をして寄生するキノコでは生きたその樹がなければ栽培はできない。ホンシメジといって売られているのはよく似た木材腐朽菌のブナシメジである。一番最初に栽培が可能になったのはシイタケである。マイタケなどは昔天然物しかなくて、ミズナラの根元に出る珍しいキノコで、見つけると嬉しくて舞いたくなるので舞茸と呼ばれるようになった。
マツタケとかホンシメジといった、生きた樹の根と絡み合った菌根形成をして寄生するキノコでは生きたその樹がなければ栽培はできない。ホンシメジといって売られているのはよく似た木材腐朽菌のブナシメジである。一番最初に栽培が可能になったのはシイタケである。マイタケなどは昔天然物しかなくて、ミズナラの根元に出る珍しいキノコで、見つけると嬉しくて舞いたくなるので舞茸と呼ばれるようになった。
![]() 今では、大抵の木材腐朽菌が栽培品ができるようになった。雪国まいたけ、ホクト産業などの会社は天然の優秀な菌株を見つけてはその栽培品を養殖するラインを作り、巨額の利益を上げている。しかし、現在でも養殖品と天然物を比べると、美味しさという点では天然物の方が数段優っている。よく、山の方の産直の店によると、栽培品と天然物が並べて売っていて、栽培品の方が揃っていてミテクレはよいが、値段は天然物の方が数倍~10倍くらいしている。
今では、大抵の木材腐朽菌が栽培品ができるようになった。雪国まいたけ、ホクト産業などの会社は天然の優秀な菌株を見つけてはその栽培品を養殖するラインを作り、巨額の利益を上げている。しかし、現在でも養殖品と天然物を比べると、美味しさという点では天然物の方が数段優っている。よく、山の方の産直の店によると、栽培品と天然物が並べて売っていて、栽培品の方が揃っていてミテクレはよいが、値段は天然物の方が数倍~10倍くらいしている。
![]() 栽培品と天然物ではかなり形が変わっているものもある。代表的なものではエノキタケがある。エノキタケはどこのスーパーでも売っているが、オガクズ栽培のあのモヤシのような薄黄色のキノコである。天然のエノキタケは笠も大きく開き、柄が黒くなるのが特徴である。黒くなった柄まで食べられる。汁物にしても、天麩羅にしても美味しいキノコである。
栽培品と天然物ではかなり形が変わっているものもある。代表的なものではエノキタケがある。エノキタケはどこのスーパーでも売っているが、オガクズ栽培のあのモヤシのような薄黄色のキノコである。天然のエノキタケは笠も大きく開き、柄が黒くなるのが特徴である。黒くなった柄まで食べられる。汁物にしても、天麩羅にしても美味しいキノコである。

![]() 晩秋に長谷村で。
晩秋に長谷村で。
![]() このキノコは晩秋から翌春まで採ることができる。春先に山菜採りに行って雪の中から顔を出していることもある。
このキノコは晩秋から翌春まで採ることができる。春先に山菜採りに行って雪の中から顔を出していることもある。

![]() 春、山菜採りに坂内村に行って、河原の柳の倒木に出てました。
春、山菜採りに坂内村に行って、河原の柳の倒木に出てました。

![]() 同じく坂内村で雪の中から顔を出してました。
同じく坂内村で雪の中から顔を出してました。
-
発見!( ^)o(^ ) 2020年11月10日 コメント(4)
-
初物( ^)o(^ ) 2020年10月05日
-
今年のマツタケは不作?"(-""-)" 2020年09月23日 コメント(4)
PR
フリーページ

日本の蝶(270種)

アゲハチョウ科(23種)

1.ギフチョウ☆

2.ヒメギフチョウ

3.ウスバシロチョウ☆

4.ヒメウスバシロチョウ☆

5.ウスバキチョウ

6.クロアゲハ☆

7.ナガサキアゲハ☆

8.モンキアゲハ☆

9.オナガアゲハ☆

10.ジャコウアゲハ☆

11.シロオビアゲハ☆

12.ベニモンアゲハ☆

13.アゲハ☆

14.キアゲハ☆

15.カラスアゲハ☆

16.ミヤマカラスアゲハ☆

17.オキナワカラスアゲハ☆

18.ヤエヤマカラスアゲハ☆

19.アオスジアゲハ☆

20.ミカドアゲハ☆

21.ホソオチョウ☆

22.オナシアゲハ☆

23.コモンタイマイ☆

シロチョウ科(28種)

24.ヒメシロチョウ☆

25.エゾヒメシロチョウ☆

26.キタキチョウ☆

27.ツマグロキチョウ☆

28.ミナミキチョウ☆

29.タイワンキチョウ☆

30.ホシボシキチョウ☆(T_T)/~~~

31.ヤマキチョウ

32.スジボソヤマキチョウ☆

33.モンキチョウ☆

34.ミヤマモンキチョウ☆

35.ウスキシロチョウ☆

36.ウラナミシロチョウ☆

37.ツマキチョウ☆

38.クモマツマキチョウ☆

39.ツマベニチョウ☆

40.タイワンシロチョウ

41.ナミエシロチョウ☆

42.カワカミシロチョウ

43.モンシロチョウ☆

44.スジグロシロチョウ☆

45.ヤマトスジグロシロチョウ☆

46.エゾスジグロチョウ☆

47.タイワンモンシロチョウ☆

48.オオモンシロチョウ☆

49.エゾシロチョウ☆

50.ミヤマシロチョウ

51.クロテンシロチョウ☆

シジミチョウ科(81種)

52.ウラギンシジミ☆

53.ゴイシシジミ☆

54.シロモンクロシジミ☆

55.ムラサキシジミ☆

56.ムラサキツバメ☆

57.ルーミスシジミ☆

58.ウラゴマダラシジミ☆

59.ウラキンシジミ☆

60.チョウセンアカシジミ☆

61.オナガシジミ☆

62.ウスイロオナガシジミ☆

63.ミズイロオナガシジミ☆

64.ウラミスジシジミ☆

65.アカシジミ☆

66.カシワアカシジミ☆

67.ウラナミアカシジミ☆

68.ムモンアカシジミ☆

69.アイノミドリシジミ☆

70.メスアカミドリシジミ☆

71.ミドリシジミ☆

72.クロミドリシジミ☆

73.ヒサマツミドリシジミ☆

74.キリシマミドリシジミ☆

75.オオミドリシジミ☆

76.ジョウザンミドリシジミ☆

77.エゾミドリシジミ☆

78.ハヤシミドリシジミ☆

79.ヒロオビミドリシジミ☆

80.ウラジロミドリシジミ☆

81.フジミドリシジミ☆

82.ウラクロシジミ☆

83.イワカワシジミ☆

84.トラフシジミ☆

85.カラスシジミ☆

86.ミヤマカラスシジミ☆

87.ベニモンカラスシジミ☆

88.リンゴシジミ☆

89.コツバメ☆

90.キマダラルリツバメ☆

91.ベニシジミ☆

92.クロシジミ☆

93.ウラナミシジミ☆

94.オジロシジミ☆

95.アマミウラナミシジミ☆

96.ルリウラナミシジミ☆

97.ヒメウラナミシジミ☆

98.マルバネウラナミシジミ(T_T)/~~~

99.シロウラナミシジミ☆

100.ウスアオオナガウラナミシジミ

101.ヤマトシジミ☆

102.シルビアシジミ☆

103.ヒメシルビアシジミ☆

104.ハマヤマトシジミ☆

105.ホリイコシジミ☆

106.オガサワラシジミ

107.ルリシジミ☆

108.スギタニルリシジミ☆

109.ヤクシマルリシジミ☆

110.サツマシジミ☆

111.タイワンクロボシシジミ☆

112.ヒメウラボシシジミ(T_T)/~~~

113.ツシマウラボシシジミ

114.リュウキュウウラボシシジミ☆

115.ツバメシジミ☆

116.タイワンツバメシジミ

117.クロツバメシジミ☆

118.ムシャクロツバメシジミ☆

119.ゴイシツバメシジミ

120.ゴマシジミ☆

121.オオゴマシジミ

122.カバイロシジミ☆

123.オオルリシジミ

124.ジョウザンシジミ☆

125.カラフトルリシジミ

126.ヒメシジミ☆

127.ミヤマシジミ☆

128.アサマシジミ☆

129.クロマダラソテツシジミ☆

130.タイワンヒメシジミ☆

131.ホリシャルリシジミ☆

132.タッパンルリシジミ(T_T)/~~~

タテハチョウ科(101種)

133.テングチョウ☆

134.アサギマダラ☆

135.タイワンアサギマダラ☆

136.ヒメアサギマダラ☆

137.リュウキュウアサギマダラ☆

138.ウスコモンマダラ

139.ミナミコモンマダラ(T_T)/~~~

140.カバマダラ☆

141.スジグロカバマダラ☆

142.ツマムラサキマダラ☆

143.マルバネルリマダラ☆

144.シロオビマダラ(T_T)/~~~

145.オオゴマダラ☆

146.ホソバヒョウモン☆

147.カラフトヒョウモン☆

148.ヒョウモンチョウ☆

149.コヒョウモン☆

150.アサヒヒョウモン

151.クモガタヒョウモン☆

152.ミドリヒョウモン☆

153.メスグロヒョウモン☆

154.ウラギンスジヒョウモン☆

155.オオウラギンスジヒョウモン☆

156.ギンボシヒョウモン☆

157.ウラギンヒョウモン☆

158.オオウラギンヒョウモン☆

159.ツマグロヒョウモン☆

160.ウラベニヒョウモン(T_T)/~~~

161.タイワンキマダラ☆

162.カバタテハ

163.オオイチモンジ☆

164.イチモンジチョウ☆

165.アサマイチモンジ☆

166.ヤエヤマイチモンジ☆

167.シロミスジ☆

168.コミスジ☆

169.ホシミスジ☆

170.ミスジチョウ☆

171.オオミスジ☆

172.フタスジチョウ☆

173.リュウキュウミスジ☆

174.イシガケチョウ☆

175.ヒョウモンモドキ☆

176.コヒョウモンモドキ☆

177.ウスイロヒョウモンモドキ

178.サカハチチョウ☆

179.アカマダラ☆

180.キタテハ☆

181.シータテハ☆

182.ヒオドシチョウ☆

183.エルタテハ☆

184.キベリタテハ☆

185.ルリタテハ☆

186.クジャクチョウ☆

187.コヒオドシ☆

188.アカタテハ☆

189.ヒメアカタテハ☆

190.キミスジ☆

191.イワサキタテハモドキ☆

192.タテハモドキ☆

193.アオタテハモドキ☆

194.コノハチョウ☆

195.イワサキコノハ(T_T)/~~~

196.リュウキュウムラサキ☆

197.メスアカムラサキ☆

198.ヤエヤマムラサキ☆

199.スミナガシ☆

200.コムラサキ☆

201.オオムラサキ☆

202.ゴマダラチョウ☆

203.アカボシゴマダラ☆

204.フタオチョウ

205.ジャノメチョウ☆

206.キマダラモドキ☆

207.オオヒカゲ☆

208.ツマジロウラジャノメ☆

209.ウラジャノメ☆

210.ヒカゲチョウ☆

211.クロヒカゲ☆

212.クロヒカゲモドキ☆

213.シロオビヒカゲ☆

214.サトキマダラヒカゲ☆

215.ヤマキマダラヒカゲ☆

216.ヒメキマダラヒカゲ☆

217.リュウキュウヒメジャノメ☆

218.ヒメジャノメ☆

219.コジャノメ☆

220.クロコノマチョウ☆

221.ウスイロコノマチョウ☆

222.ヒメヒカゲ☆

223.シロオビヒメヒカゲ☆

224.ベニヒカゲ☆

225.クモマベニヒカゲ

226.タカネヒカゲ

227.ダイセツタカネヒカゲ

228.ヒメウラナミジャノメ☆

229.ウラナミジャノメ☆

230.マサキウラナミジャノメ☆

231.ヤエヤマウラナミジャノメ

232.リュウキュウウラナミジャノメ☆

233.ルソンアサギマダラ☆

セセリチョウ科(37種)

234.キバネセセリ☆

235.オキナワビロウドセセリ☆

236.テツイロビロウドセセリ☆

237.アオバセセリ☆

238.タイワンアオバセセリ☆

239.ダイミョウセセリ☆

240.コウトウシロシタセセリ☆

241.チャマダラセセリ☆

242.ヒメチャマダラセセリ

243.ミヤマセセリ☆

244.ギンイチモンジセセリ☆

245.タカネキマダラセセリ

246.カラフトタカネキマダラセセリ

247.ホソバセセリ☆

248.ホシチャバネセセリ

249.クロセセリ☆

250.オオシロモンセセリ☆

251.クロボシセセリ☆

252.コチャバネセセリ☆

253.ヒメキマダラセセリ☆

254.コキマダラセセリ☆

255.アカセセリ☆

256.キマダラセセリ☆

257.アサヒナキマダラセセリ

258.ネッタイアカセセリ☆

259.スジグロチャバネセセリ

260.ヘリグロチャバネセセリ

261.ユウレイセセリ☆

262.ヒメイチモンジセセリ

263.イチモンジセセリ☆

264.オオチャバネセセリ☆

265.ミヤマチャバネセセリ☆

266.チャバネセセリ☆

267.トガリチャバネセセリ

268.オガサワラセセリ

269.バナナセセリ☆

270.カラフトセセリ☆

Nature Watching Race

エッセー

師匠からの贈り物

束の間の夢

ある少女の死と飼い犬の家出

ジャコウアゲハのミーちゃん

トライアスロン

崩れた安全神話

大会中の事故と自己管理

大会中の事故と自己管理(英文)

トライアスロン事故史から見たルールの変遷

泳げる人の溺死
コメント新着
チョウの印象が強く… New! MIYA KOUTAさん
今日は晴れから
 New!
mogurax000さん
New!
mogurax000さん軍手でペンキ塗り New! kororin912さん
2025年5月 花のカナ…
 New!
隠居人はせじぃさん
New!
隠居人はせじぃさん東山散策【2025…
 New!
yamagasukiさん
New!
yamagasukiさんキーワードサーチ
カテゴリ
カテゴリ未分類
(192)不明の花
(8)キノコ
(278)山芋
(10)花
(389)山菜
(392)海産物
(199)樹木
(66)医療
(121)レシピ
(81)トライアスロン
(279)昆虫
(2906)果実酒
(8)競艇
(140)監察医
(67)オートバイ
(3)動物
(1233)紹介
(271)囲碁
(23)蒲郡の紹介
(66)本の紹介
(12)人物紹介
(42)植物
(88)道具
(94)野菜
(46)酒
(87)季節
(80)湿原・湿地
(30)写真
(41)旅行
(116)ライオンズクラブ
(92)間違い
(0)ノスタルジー
(31)狩猟
(1)カレンダー
2025年10月
2025年09月
2025年07月