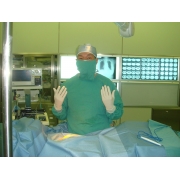![]() アサギマダラは渡りをする蝶の代表とされています。秋には南下の旅をし、春には北上の旅をします。もちろん、寿命は5か月~長くても7か月ですので、その間に世代交代が起こります。
アサギマダラは渡りをする蝶の代表とされています。秋には南下の旅をし、春には北上の旅をします。もちろん、寿命は5か月~長くても7か月ですので、その間に世代交代が起こります。
![]() 一方で愛知県でもアサギマダラは越冬をしています。豊橋には食草のひとつ、キジョランが冬でも枯れずにあり、そこでは全てのステージを見ることが出来ます。
一方で愛知県でもアサギマダラは越冬をしています。豊橋には食草のひとつ、キジョランが冬でも枯れずにあり、そこでは全てのステージを見ることが出来ます。

アサギマダラの卵(豊橋市)
posted by
(C)ドクターT

アサギマダラ1齢幼虫 (4)
posted by
(C)ドクターT

アサギマダラ2齢幼虫-001
posted by
(C)ドクターT

アサギマダラ3齢幼虫
posted by
(C)ドクターT

アサギマダラ終齢幼虫
posted by
(C)ドクターT
![]() これらは、今の時期、愛知県でも見ることが出来ます。ならば、何故渡りをする必要があるのでしょうか?
これらは、今の時期、愛知県でも見ることが出来ます。ならば、何故渡りをする必要があるのでしょうか?
![]() それはやはり温度に敏感なためと、食草の量であると思われます。
それはやはり温度に敏感なためと、食草の量であると思われます。
![]() アサギマダラの活動に適した気温は22℃から26℃と言われています。特に、暑さには弱いようです。活動は出来なくなりますが、冬の低温には比較的強く、雪が積もらないところでは越冬することが出来ます。
アサギマダラの活動に適した気温は22℃から26℃と言われています。特に、暑さには弱いようです。活動は出来なくなりますが、冬の低温には比較的強く、雪が積もらないところでは越冬することが出来ます。
![]() 食草はガガイモ科のつる性植物で、ガガイモ、イケマ、オオカモメヅル、キジョラン、サクララン、ツルモウリンカなどで南西諸島ではツルモウリンカが主な食草となっており、本州では高原地帯に多いイケマが主な食草と考えられますがこれも冬には枯れてしまいます。そして、愛知県ではガガイモが食草になりますが、それほど多くはなく、冬は枯れてしまいます。キジョランは常緑で冬でも枯れませんので、冬の間の食草とすることが出来ますが、そんなに多くはなく、私は愛知県では2か所しか自生地を知りません。
食草はガガイモ科のつる性植物で、ガガイモ、イケマ、オオカモメヅル、キジョラン、サクララン、ツルモウリンカなどで南西諸島ではツルモウリンカが主な食草となっており、本州では高原地帯に多いイケマが主な食草と考えられますがこれも冬には枯れてしまいます。そして、愛知県ではガガイモが食草になりますが、それほど多くはなく、冬は枯れてしまいます。キジョランは常緑で冬でも枯れませんので、冬の間の食草とすることが出来ますが、そんなに多くはなく、私は愛知県では2か所しか自生地を知りません。
![]() 南西諸島では秋に北から渡ってきた個体と春に発生した新鮮個体が多くなりますが、気温が30℃を超える日が続く夏には激減し、北へ渡って行くようです。その時期には、食草のツルモウリンカもアフリカマイマイやモンクロキシタアツバと言う蛾の幼虫の食害で少なくなってしまいます。
南西諸島では秋に北から渡ってきた個体と春に発生した新鮮個体が多くなりますが、気温が30℃を超える日が続く夏には激減し、北へ渡って行くようです。その時期には、食草のツルモウリンカもアフリカマイマイやモンクロキシタアツバと言う蛾の幼虫の食害で少なくなってしまいます。
![]() 渡りをする動機はやはり、気温と食草の量であろうと思いますが、それでは愛知県で越冬しているのは渡りをしないアサギマダラなのでしょうか
渡りをする動機はやはり、気温と食草の量であろうと思いますが、それでは愛知県で越冬しているのは渡りをしないアサギマダラなのでしょうか
![]() 私はアサギマダラに渡りをするグループと渡りをしないグループがいると考えるよりも、渡りをするという性質はアサギマダラに共通の性質と考える方が自然だと思います。と言うことは、愛知県で越冬するアサギマダラはもっと北の東北や北海道で生まれた個体が南下して愛知県に来たところで、食草のキジョランを見つけてそこに産卵したものではないかと思います。
私はアサギマダラに渡りをするグループと渡りをしないグループがいると考えるよりも、渡りをするという性質はアサギマダラに共通の性質と考える方が自然だと思います。と言うことは、愛知県で越冬するアサギマダラはもっと北の東北や北海道で生まれた個体が南下して愛知県に来たところで、食草のキジョランを見つけてそこに産卵したものではないかと思います。
![]() そのことを実証するには、マーキング調査をする必要があると思います。すなわち、春に羽化した個体にマーキングをして放して、それが東北や北海道で再捕獲されれば、愛知県で越冬したアサギマダラも同じように渡りをしているということになります。
そのことを実証するには、マーキング調査をする必要があると思います。すなわち、春に羽化した個体にマーキングをして放して、それが東北や北海道で再捕獲されれば、愛知県で越冬したアサギマダラも同じように渡りをしているということになります。
-
レジン包埋標本作製( ^)o(^ ) 2020年12月20日
-
後天性サバン症候群になって、・・・。( ^… 2020年12月14日
-
越冬集団その2( ^)o(^ ) 2020年12月13日
PR
フリーページ

日本の蝶(270種)

アゲハチョウ科(23種)

1.ギフチョウ☆

2.ヒメギフチョウ

3.ウスバシロチョウ☆

4.ヒメウスバシロチョウ☆

5.ウスバキチョウ

6.クロアゲハ☆

7.ナガサキアゲハ☆

8.モンキアゲハ☆

9.オナガアゲハ☆

10.ジャコウアゲハ☆

11.シロオビアゲハ☆

12.ベニモンアゲハ☆

13.アゲハ☆

14.キアゲハ☆

15.カラスアゲハ☆

16.ミヤマカラスアゲハ☆

17.オキナワカラスアゲハ☆

18.ヤエヤマカラスアゲハ☆

19.アオスジアゲハ☆

20.ミカドアゲハ☆

21.ホソオチョウ☆

22.オナシアゲハ☆

23.コモンタイマイ☆

シロチョウ科(28種)

24.ヒメシロチョウ☆

25.エゾヒメシロチョウ☆

26.キタキチョウ☆

27.ツマグロキチョウ☆

28.ミナミキチョウ☆

29.タイワンキチョウ☆

30.ホシボシキチョウ☆(T_T)/~~~

31.ヤマキチョウ

32.スジボソヤマキチョウ☆

33.モンキチョウ☆

34.ミヤマモンキチョウ☆

35.ウスキシロチョウ☆

36.ウラナミシロチョウ☆

37.ツマキチョウ☆

38.クモマツマキチョウ☆

39.ツマベニチョウ☆

40.タイワンシロチョウ

41.ナミエシロチョウ☆

42.カワカミシロチョウ

43.モンシロチョウ☆

44.スジグロシロチョウ☆

45.ヤマトスジグロシロチョウ☆

46.エゾスジグロチョウ☆

47.タイワンモンシロチョウ☆

48.オオモンシロチョウ☆

49.エゾシロチョウ☆

50.ミヤマシロチョウ

51.クロテンシロチョウ☆

シジミチョウ科(81種)

52.ウラギンシジミ☆

53.ゴイシシジミ☆

54.シロモンクロシジミ☆

55.ムラサキシジミ☆

56.ムラサキツバメ☆

57.ルーミスシジミ☆

58.ウラゴマダラシジミ☆

59.ウラキンシジミ☆

60.チョウセンアカシジミ☆

61.オナガシジミ☆

62.ウスイロオナガシジミ☆

63.ミズイロオナガシジミ☆

64.ウラミスジシジミ☆

65.アカシジミ☆

66.カシワアカシジミ☆

67.ウラナミアカシジミ☆

68.ムモンアカシジミ☆

69.アイノミドリシジミ☆

70.メスアカミドリシジミ☆

71.ミドリシジミ☆

72.クロミドリシジミ☆

73.ヒサマツミドリシジミ☆

74.キリシマミドリシジミ☆

75.オオミドリシジミ☆

76.ジョウザンミドリシジミ☆

77.エゾミドリシジミ☆

78.ハヤシミドリシジミ☆

79.ヒロオビミドリシジミ☆

80.ウラジロミドリシジミ☆

81.フジミドリシジミ☆

82.ウラクロシジミ☆

83.イワカワシジミ☆

84.トラフシジミ☆

85.カラスシジミ☆

86.ミヤマカラスシジミ☆

87.ベニモンカラスシジミ☆

88.リンゴシジミ☆

89.コツバメ☆

90.キマダラルリツバメ☆

91.ベニシジミ☆

92.クロシジミ☆

93.ウラナミシジミ☆

94.オジロシジミ☆

95.アマミウラナミシジミ☆

96.ルリウラナミシジミ☆

97.ヒメウラナミシジミ☆

98.マルバネウラナミシジミ(T_T)/~~~

99.シロウラナミシジミ☆

100.ウスアオオナガウラナミシジミ

101.ヤマトシジミ☆

102.シルビアシジミ☆

103.ヒメシルビアシジミ☆

104.ハマヤマトシジミ☆

105.ホリイコシジミ☆

106.オガサワラシジミ

107.ルリシジミ☆

108.スギタニルリシジミ☆

109.ヤクシマルリシジミ☆

110.サツマシジミ☆

111.タイワンクロボシシジミ☆

112.ヒメウラボシシジミ(T_T)/~~~

113.ツシマウラボシシジミ

114.リュウキュウウラボシシジミ☆

115.ツバメシジミ☆

116.タイワンツバメシジミ

117.クロツバメシジミ☆

118.ムシャクロツバメシジミ☆

119.ゴイシツバメシジミ

120.ゴマシジミ☆

121.オオゴマシジミ

122.カバイロシジミ☆

123.オオルリシジミ

124.ジョウザンシジミ☆

125.カラフトルリシジミ

126.ヒメシジミ☆

127.ミヤマシジミ☆

128.アサマシジミ☆

129.クロマダラソテツシジミ☆

130.タイワンヒメシジミ☆

131.ホリシャルリシジミ☆

132.タッパンルリシジミ(T_T)/~~~

タテハチョウ科(101種)

133.テングチョウ☆

134.アサギマダラ☆

135.タイワンアサギマダラ☆

136.ヒメアサギマダラ☆

137.リュウキュウアサギマダラ☆

138.ウスコモンマダラ

139.ミナミコモンマダラ(T_T)/~~~

140.カバマダラ☆

141.スジグロカバマダラ☆

142.ツマムラサキマダラ☆

143.マルバネルリマダラ☆

144.シロオビマダラ(T_T)/~~~

145.オオゴマダラ☆

146.ホソバヒョウモン☆

147.カラフトヒョウモン☆

148.ヒョウモンチョウ☆

149.コヒョウモン☆

150.アサヒヒョウモン

151.クモガタヒョウモン☆

152.ミドリヒョウモン☆

153.メスグロヒョウモン☆

154.ウラギンスジヒョウモン☆

155.オオウラギンスジヒョウモン☆

156.ギンボシヒョウモン☆

157.ウラギンヒョウモン☆

158.オオウラギンヒョウモン☆

159.ツマグロヒョウモン☆

160.ウラベニヒョウモン(T_T)/~~~

161.タイワンキマダラ☆

162.カバタテハ

163.オオイチモンジ☆

164.イチモンジチョウ☆

165.アサマイチモンジ☆

166.ヤエヤマイチモンジ☆

167.シロミスジ☆

168.コミスジ☆

169.ホシミスジ☆

170.ミスジチョウ☆

171.オオミスジ☆

172.フタスジチョウ☆

173.リュウキュウミスジ☆

174.イシガケチョウ☆

175.ヒョウモンモドキ☆

176.コヒョウモンモドキ☆

177.ウスイロヒョウモンモドキ

178.サカハチチョウ☆

179.アカマダラ☆

180.キタテハ☆

181.シータテハ☆

182.ヒオドシチョウ☆

183.エルタテハ☆

184.キベリタテハ☆

185.ルリタテハ☆

186.クジャクチョウ☆

187.コヒオドシ☆

188.アカタテハ☆

189.ヒメアカタテハ☆

190.キミスジ☆

191.イワサキタテハモドキ☆

192.タテハモドキ☆

193.アオタテハモドキ☆

194.コノハチョウ☆

195.イワサキコノハ(T_T)/~~~

196.リュウキュウムラサキ☆

197.メスアカムラサキ☆

198.ヤエヤマムラサキ☆

199.スミナガシ☆

200.コムラサキ☆

201.オオムラサキ☆

202.ゴマダラチョウ☆

203.アカボシゴマダラ☆

204.フタオチョウ

205.ジャノメチョウ☆

206.キマダラモドキ☆

207.オオヒカゲ☆

208.ツマジロウラジャノメ☆

209.ウラジャノメ☆

210.ヒカゲチョウ☆

211.クロヒカゲ☆

212.クロヒカゲモドキ☆

213.シロオビヒカゲ☆

214.サトキマダラヒカゲ☆

215.ヤマキマダラヒカゲ☆

216.ヒメキマダラヒカゲ☆

217.リュウキュウヒメジャノメ☆

218.ヒメジャノメ☆

219.コジャノメ☆

220.クロコノマチョウ☆

221.ウスイロコノマチョウ☆

222.ヒメヒカゲ☆

223.シロオビヒメヒカゲ☆

224.ベニヒカゲ☆

225.クモマベニヒカゲ

226.タカネヒカゲ

227.ダイセツタカネヒカゲ

228.ヒメウラナミジャノメ☆

229.ウラナミジャノメ☆

230.マサキウラナミジャノメ☆

231.ヤエヤマウラナミジャノメ

232.リュウキュウウラナミジャノメ☆

233.ルソンアサギマダラ☆

セセリチョウ科(37種)

234.キバネセセリ☆

235.オキナワビロウドセセリ☆

236.テツイロビロウドセセリ☆

237.アオバセセリ☆

238.タイワンアオバセセリ☆

239.ダイミョウセセリ☆

240.コウトウシロシタセセリ☆

241.チャマダラセセリ☆

242.ヒメチャマダラセセリ

243.ミヤマセセリ☆

244.ギンイチモンジセセリ☆

245.タカネキマダラセセリ

246.カラフトタカネキマダラセセリ

247.ホソバセセリ☆

248.ホシチャバネセセリ

249.クロセセリ☆

250.オオシロモンセセリ☆

251.クロボシセセリ☆

252.コチャバネセセリ☆

253.ヒメキマダラセセリ☆

254.コキマダラセセリ☆

255.アカセセリ☆

256.キマダラセセリ☆

257.アサヒナキマダラセセリ

258.ネッタイアカセセリ☆

259.スジグロチャバネセセリ

260.ヘリグロチャバネセセリ

261.ユウレイセセリ☆

262.ヒメイチモンジセセリ

263.イチモンジセセリ☆

264.オオチャバネセセリ☆

265.ミヤマチャバネセセリ☆

266.チャバネセセリ☆

267.トガリチャバネセセリ

268.オガサワラセセリ

269.バナナセセリ☆

270.カラフトセセリ☆

Nature Watching Race

エッセー

師匠からの贈り物

束の間の夢

ある少女の死と飼い犬の家出

ジャコウアゲハのミーちゃん

トライアスロン

崩れた安全神話

大会中の事故と自己管理

大会中の事故と自己管理(英文)

トライアスロン事故史から見たルールの変遷

泳げる人の溺死
コメント新着
 New!
隠居人はせじぃさん
New!
隠居人はせじぃさん2025 霜月 中… New! 小芋さんさん
久米島最高齢バスガ… New! G. babaさん
今季一番の冷え込みで
 New!
mogurax000さん
New!
mogurax000さんあと、一週間! New! kororin912さん
富士での紅葉と、冠…
 putimimiyaさん
putimimiyaさんキーワードサーチ
カテゴリ
カテゴリ未分類
(192)不明の花
(8)キノコ
(278)山芋
(10)花
(389)山菜
(392)海産物
(199)樹木
(66)医療
(121)レシピ
(81)トライアスロン
(279)昆虫
(2906)果実酒
(8)競艇
(140)監察医
(67)オートバイ
(3)動物
(1233)紹介
(271)囲碁
(23)蒲郡の紹介
(66)本の紹介
(12)人物紹介
(42)植物
(88)道具
(94)野菜
(46)酒
(87)季節
(80)湿原・湿地
(30)写真
(41)旅行
(116)ライオンズクラブ
(92)間違い
(0)ノスタルジー
(31)狩猟
(1)カレンダー
2025年10月
2025年09月
2025年07月