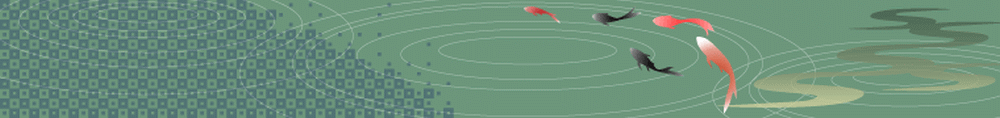全39件 (39件中 1-39件目)
1
-
うむうむネット通信 「あの人に会いたい 」中村奈美さん
第11回 うむうむネット通信 「あの人に会いたい」~世界に一つだけの美とキレイ~ ナナカラー カラーアナリスト 中村奈美さん 千曲市在住の中村奈美さんは、人と「色」との出会いを通し、一人ひとりが自分らしく輝いて生きるお手伝いをするカラーアナリスト。また、知る人ぞ知る「ママイキ」を長野県で初めて主催したり、特技や専門を持つママ同士が活躍できる場として「ステキに花咲くママの会」を結成したりと、自然体ながらとてもアクティブなママでもあります。お仕事柄とはいえ、いつお会いしてもオシャレ。しかも内面から輝くステキのヒミツを知りたくて、千曲市までお話を伺いにいってきました。色のない時代 ~カラーの仕事に出会うまで~ 空に虹を見つけると、それだけでなんだか幸せな気持ちになりませんか?キレイな色を見るとウキウキしたり、好きな色は自然と目に入ってきたり、生活に「色」の視点を取り入れると、多くの可能性が広がっていくことをご存知ですか? 私は、カラーアナリストとして、一人ひとりが本来持っている魅力(素質)を一番に輝かせる「色」をお伝えする仕事をしています。自分にしっくり馴染む色は、どれだけ人に自信を与え、前向きな生き方に変えていくのか、数多くのお客様の喜びの声から実感しています。そんな私も15年前の新婚当時は、色のない生活を送っていました。東京生まれの東京育ちの私にとって、夫以外だれも知り合いのいない長野での暮らしはただ不安ばかり。折りしも季節は、寒くて暗いグレーの季節「信州の冬」が始まろうとしていました。同居している義母さんが病を患っていたこともあり、義母さんのお世話をしながら、遅く帰ってくる夫をじっと待っているだけの毎日は本当に辛く、千曲川の河川敷で泣いていたこともあったんですよ。今思い出しても、その頃の記憶には色がないんです。そういえば洋服も、黒が多くモノトーンばかり着ていましたね。しかし、「このままではいられない」という気持ちから、まずは自動車教習所に通い、ペーパードライバーを返上。長野での生活に欠かせない車の運転ができるようになりました。また、大学で建築を学び、独身時代も建築業界で働いていた私は、一級建築士を目指すことを決意し、猛勉強もスタートさせました。インテリア関連のお店で仕事も始めました。とにかく、自信をつけたかったんでしょうね。 先が見えないトンネル ~頑張っても、苦しくて、前に進めない~その後、ハウジングメーカーでCADを使った仕事に転職。自分の希望する建築の仕事をしていても、やはり建築業界は男世界。頑張っていても楽しいどころか、苦しかったですね。建築士一級の試験は、一次を合格したものの、二次試験ではありえないミスを犯し、失敗。「自分は、この道ではないのかも・・・」と思い始め、少しずつ「子どもができても続けられる仕事、心から楽しいと思える好きなことを仕事にしよう」と考えるようになりました。「建築にこだわらなくていい」と自分にGOサインをだしてあげたら、気持ちがすっと楽になったことを覚えています。あれだけ頑張って目指していた建築士一級の取得は、親への恩返しの気持ちが強く、自らが本当に望んでいることではなかったのかもしれません。自分の好きを再発見 ~色の世界は希望の光~ 「自分の好きって何だろう?」を確認するために、リフレクソロジーやウェブデザインなどいろいろなことを体験しました。カルチャーセンターの「カラー講座」もその一つでした。「こういう仕事もあるんだ~」と、驚いたことを覚えています。思い返せば、建築学科時代もカラーに興味を持っていたこと、パステル画の演習は、特に意欲的に取り組めた記憶もよみがえってきました。そこで、早速はじめた通信教育の「カラー講座」。6ヶ月課程の内容を、気がつけば1ヶ月で終わらせてしまったほど、ワクワクしましたね。「色」の知識や「色」の意味を学ぶことは、自分にとって楽しい時間で、色彩検定の2級、3級も独学で取得しました。建築士の勉強では、必死に頑張ってもなかなか前に進めませんでしたが、カラーの道は、自分でもわかるほど、どんどん前に進んでいくのです。 ちょうどその頃、長男を妊娠。ハウジングメーカーでの仕事を続けていたので、体力的にはキツイときもありましたが、「パーソナルカラー診断」という仕事に焦点を定めていたので、とても充実していました。あちこちから学校資料を取り寄せるなか、「カラーミーアシーズン」との出会いは、まさにビビビ。心理的要素や科学的な根拠も学べる内容に「私の目指すものはこれだ!」と確信したのです。その興奮のせいか!?グットタイミングで、長男の出産を告げるおしるしも来たんですよ。 自分らしく輝く ~自分だけの「色」を見つけたら、世界が虹色になった~ 長男出産後は、しばらく赤ちゃん最優先の生活を送りました。「カラーの道を進む」という光が見えていたので、あせりや不安はほとんどなかったですね。元気になってきた義母の心強い言葉もあり、家族の協力体制も整い、長男が生後10ヶ月から、半年間「カラーミーアシーズン」のカラーアナリスト養成講座のために、東京まで通学しました。毎回、課題も多く、子どもを寝かしつけてから、時には徹夜しないと終わらないこともよくありましたが「辛い」とは思いませんでした。この時に、徹底的に学んだ深い内容があるからこそ、カラーアナリストとして独立するときの自信にもつながっています。 私は「色」と出会い、自分の色、自分の個性を知ることで、「自分らしさ」をとても大切なものと考えるようになりました。同じように、他の人の個性、他者との違いを認めることができるようになり、人間関係も大きく変わったように思います。カラーの世界に限らず、自分の好きなことをしているときは、とてもハッピーな時間です。かけがえのない家族を大事にしながら、もっと自分らしく輝くために、自分のやりたいこと、知りたいこと、学びたいことはどんどんチャレンジしていきます。赤ちゃん・小さなお子さんと暮らすママへ 子育て中は、本当に忙しく、しかも単調な生活になりがちです。子どものためにすることはいくらでもあって、自分の時間はなかなか持てません。ママになると、自分のことをすることに罪悪感を抱く人も多いでしょう。しかし、自分らしく過ごせるときは、穏やかで、前向きな自分でいられるはず。だから、毎日の暮らしの中で、ほんの5%でも1%でも、ママとしてではなく、自分らしい時間を持つことは、とても重要なことなんですよ。 制限ある生活の中で「ママ」であること、「自分らしさ」のどちらかだけを選ぶのではなく、「両方を選択」できる自分なりの方法を見つけて欲しいですね。いつか子育ては終わり、100%自分のための時間はやってくるのですから・・・。お話を終えて・・・ ご自身の魅力を輝かせる奈美ブルー(ワタシが勝手に命名)をはじめ、自分らしい色をまとう奈美さんと話していると、こちらまで前向きになってくるから不思議です。 穏やかな雰囲気の奈美さんですが、「まずはやってみよう」という好奇心の強さとスピーディな行動力、そして人への優しさが、彼女の内面から溢れる輝きの源なのだと思いました。(大日方)NANA CORLAR のご案内 ママだって、自分らしく輝きましょう。まずは新しい自分色の発見から、新たな可能性の扉を開いてみませんか? 中村さんは、ご自宅を中心にお子さん連れでも受講できる講座なども開講しています。MENUパーソナルカラー診断 パステル和みアート講座・パステル和みアート準インストラクター養成講座TCカラーセラピー・TCカラーセラピスト養成講座数秘&カラーセラピー などなどお問い合わせ先:NANA.COLOR (ナナカラー) E-mail:nanacolor7@yahoo.co.jp URL:http://www.nana-color.com
2013年03月02日
コメント(0)
-
永遠の永遠の永遠 愛はとこしえに~ その1
「無限の網」というあなたの自伝を夢中で拝読いたしました。芸術という武器で戦ってこられたあなたの半生、生き様を詠ませていただきながら、ページを行きつ戻りつしながら、何度、心がどよめき、カラダが振るえ、涙がにじんだでしょう。私のちっぽけな想像力ではたちうちできないほどの苦難と、孤独と、恐怖の中で、あなたがここまで立ち止まることなく、歩み続け、進んでこられたことを、ただ、ただ、尊敬と畏敬の念を抱き、同時代に生きている人間として感謝の気持ちをもって、あなたの芸術を私なりに精一杯にうけとめたい。全国各地で巡回されてきた「永遠の永遠の永遠」が、松本で開催されるのを心から楽しみにしていました。本当は、先日のNHKテレビ番組「スーパーウーマン」でユーミンとの共演を見ていた母も連れて行きたいしオヤバカとはいえ、アーティストの根が見え隠れする10歳のムスメも連れて行きたい。気軽にアート談義ができそうな女友達とも出かけたい。でも、まずは、1人でわたしという単体が、どう受け止めるのか、誰よりも、自分自身が私に興味があったのです。どうしても草間さんのドキュメンタリー映画「わたし大好き」も観たかったので松本市立美術館で上映される10月6日整理券が配られる10時までに到着するように車を飛ばして、単身、松本市へ向かいました。整理券は先着100名。到着予定時間の10時には、きっと、行列ができているだろう・・・と高速道路を、飛ばしに飛ばした私ですが私の車は、すんなりと美術館の駐車場には入れたし整理券番号も、56番。ホッとしたけれど、16時までに長野に戻らなくてはいけない私には時間がありません。すぐに、巨大なヤヨイちゃん人形をみあげながら、いよいよ、ヤヨイワールドへ。展示コーナーを曲がって、作品が、私たちのを目の前に現れるたびに「キョーレツ」という声や反応も聞こえてきました。そうです。生きているということは、それだけで、キョーレツなこと。クサマヤヨイの作品を見てると皮膚がザワザワしてくる落ち着かない気持ちになる・・・と、どなたかが、話していたことがあります。それこそが、草間ヤヨイの日常 なのでしょう。そう想像しただけで作品のすべては、孤独な戦いの戦利品なのだと思いました。つづく
2012年10月12日
コメント(0)
-
手相は人生の地図
幼少より、気がついたら、手相にはずっと興味をもっていて、石川啄木の気分で「じっと手を見る」ことを、ことあるごとによくしてきたワタシ。しかも手相の線が変わっていることに、たびたび気がついたことも。それなのに本格的に手相をみてもらう、というチャンスはこれまでなかったんです。それが縁あって、本日「開運未来流 手相リーディング入門講座」なるものに参加してきました。手相とは、「生まれる前に神様と相談して決めた人生の地図」だそうでだから、自分を幸せにするための、道しるべのようなもの、というお話からスタート。 そう思うと、手のひらを眺めながら、どの線も、しわも、ふくらみも、みんな愛おしいんだなあ。それにしても、ご一緒のテーブルにはヒーリングカウンセラーの方やら一万人に1人・おしゃか様の手相と同じと言われる方ジャンジャンバリバリのバイタリティーある三重生命線があり、 しかも、ちょっと変わった一芸に秀でたマスカケ線の方芸術線がばっちりくっきり、しかも、ずっと願いがかなっちゃうソロモンの輪がある方と、キョーレツ(もとい)個性的な方々ばかり。しかも、他のテーブルでも、「ア、珍しい」「めったにないんですよ」と講師である堀向さんの声が、何度も。どんだけ、個性的な方々が参加している講座なんだ・・・・しかも 単なる手相の鑑定法というだけでなく、それぞれ線の特徴を伝えるにも、どう伝えたら、うれしいか、 うまく受取れるか・・・そういう部分での配慮を感じ、そういう気配りが、自然と会話の中で、できる人は、「人」をイキイキと活かせる人なんだろうな・・・・とも感じました。ちなみに、手相に興味のない人もみんな知ってる生命線。その長さは、寿命の長さとは関係ないそうですよ。かの泉重千代さんは、決して長い生命線ではなく、どちらかというと短かったようです。また、手相鑑定をする人が、もし、あまりにも「寿命」に関して、はっきりと年齢まで言うような人ならば、ちょっと???怪しいかも・・・・ツボとか買わせたいのかも・・・・寿命に関しては、やはり知らなくて良いこと、伝えることではないこと・・・というお話も、思わずうなづきました。堀向先生のお話はとても楽しく、、自分も人も、心に灯が灯るような、思わず、うれしくなってしまうような、手相のヒミツ、手相の見方をギュって、教えていただいて、今は、だれかれかまわず、皆さんの手相をそっと、のぞいてみたいワタシ。ちなみに、ワタシの手相もそれなりに、神秘十字があったり、仏眼があったり、貢がれ線(経験はなしぞ!)!!などあれこれ特徴的な線があるにはあったのですが、一番は、「面食い線」が かなり、くっきり・・
2012年09月20日
コメント(0)
-
泣き虫上等!
ボクは泣き虫でともだちに、ちょっと押されては泣き、つまづいては泣き、給食を残しては泣き、お着替えが最後になったって泣き毎日、泣いてばっかり。すると、大人は ボクの顔を覗き込みながらいけない、いけない、泣いちゃいけない、泣かない、泣かない 男の子は泣かないって、かならず、言うけどボクは、余計に、悲しくなってどんどん、涙はでてくるし、エンエン、泣き声とまらないしズーズー鼻水だって、たれちゃう。でもね、ボクが泣いているとき母さんは、いつだって、泣いていいのよ、泣きなさい。泣き虫上等!泣いて、泣いて、いっぱい泣いたらすっきりするからそしたら、きっと、笑えるよ。って。だから、ボクは母さんと一緒だと、いっぱい泣く。エンエン泣く。オイオイ泣く。ピーピー泣く。いっぱい泣いたら、ちょっと疲れておなかが減って、ボクのおなかがグーって鳴って、母さんが笑い出して、ボクも笑って、ハイ、オシマイ。ボク、今日、初めて母さんの涙を見た。ボクはびっくりして、あわてて、母さんのそばに走ったんだ。「どうしたの?」って、聞いたら「嬉しいのよ」って母さん、また泣くんだ。それは、母さんのお誕生日に届いた海の上にいる父さんからの、ラブレター。ボク、いつもの母さんみたいに言ったんだ。泣いていいよ。いっぱい、泣いて、いっぱい泣いて、そしたら、二人で笑って、父さんに、電話しようよって。泣き虫ボクは今日、初めてうれしいときも、幸せなときも、泣くんだってこと、知った。、ボクは、幸せなときもうれしときも、きっと、いっぱい泣いちゃうんだろうな。泣き虫バンザイ!泣き虫上等!
2010年08月13日
コメント(0)
-
卯の花忌のご案内
先日、エディーターズミュージアムの荒井さんから おはがきで、案内をいただきましたので情報のおすそわけ 6月5日土曜日 17:00~19:00 場所:上田駅前 若菜館ビル3階・エディターズミュージアム 参加費:1200円 高校生以下500円 定員:120名 (定員になり次第締め切り・なのでもう遅かったらごめんなさい。) 児童文学者の灰谷さんをしのんで、集まる会です。 ゲストは、報道者写真家の石川分洋さん。 もちろん、小宮山量平さんも。 お問い合わせ:お申し込み 0268-25-0826(11:00~17:00)
2010年06月02日
コメント(0)
-
うむうむネット通信 第4回「あの人に会いたい」 荒井きぬ枝さん
うむうむネット通信 第4回「あの人に会いたい」 エディターズミュージアム「小宮山量平の編集室」代表 荒井きぬ枝さん以前、上田市にあるエディターズミュージアム(小宮山量平さんの編集室)を訪れた時のこと。突然の訪問にもかかわらず、小宮山さんの長女である代表の荒井きぬ枝さんは、一見の若造である筆者を温かく迎えてくださいました。「兔の眼」の作者である灰谷さんの思い出を聴かせて下さったり、児童文学について、子供について、教育について、平和について、小数派についてなどなど、時間を忘れてしまうほど、自由に楽しく、熱く、いろいろなお話をさせていただきました。とても貴重な時間でした。先日、筆者はテレビで山田監督の「母べえ」を観たとき、同じ母として、いてもたってもいられない気持ちになりました。今も世界中のあちこちでは、戦争で親を失う子供があふれ、傷だらけで戦う兵士たちは、それぞれの「正義」の名の下に、誰かを殺し、街を焼き尽くし 戦争が続いています。 一方で、今自分が、こうして静かな朝を迎えられるシアワセは、温かい夕食を家族で囲めるシアワセは、すべて「平和」であるという大前提のもとに成り立っていることを今更ながらに、強く強く感じたとき、言いようもない焦燥感に襲われました。そして、「命を大事にするという哲学を日本人はもう一度取り戻さなくてはいけない」という小宮山量平さんの言葉と出会った、エディターズミュージアム代表の荒井きぬ枝さんから、「平和を守るということについて」のお話を聴きたくなったのでした。 IMAGEIN ~想像してみよう~「平和を守る」とは、何も、声高に「戦争はんたーい!」と大声で訴えることではないと思うの。それは、「想像する」ことから始まるのです。「もし、あなたの愛する人が戦場にいかなくてはならなくなったら・・・もし、あなたの大事な子供が、爆撃を受けたとしたら・・・・・」愛する人がいる人なら、お母さんになった人なら、想像しただけで、とても耐えられないわよね。そんな親としての当たり前の気持ちを書いた父の文を紹介するわね。」 荒井さんは、一冊の本を静かに開き、朗読を始めました。****************************************私はお前をえたとうとうお前は生まれてきた。(中略)生れるとすぐ眼をひらいた。きれいな体。あらゆるものを祝ってあげたいような、祝福、祝福!1947・11・11お前のお七夜ということで、十何人のお客様だ。お前を抱いて、仏前。神前におじぎ。そうしながら、私はふっと、涙ぐむ。ひとりの人間が生長する過程には、こんな素朴な祝福が、やはり何度となく積み重ねられているのだ。私たちは、1人1人の人間を、そういう祝福の累積として見ることを忘れがちだ。人のいのちが大切だ・・・・・ということの内容は、ひとりの人間の中にも、実にたくさんのひとびとの祝福が積み重ねられているからだ、ということになるかもしれない。お前によって、今更のように、命の尊さ、温かさを知る。1950・7・13昨日、おもいがけなく、お前にけがをさせてしまった。表てを通るジープを珍しがってはしりでたようとしたとたんにころんで額を割ってしまったのだ。血がふきでるのをおさえて、お母さんが医者へかけていったあと、私は寝台にひっくりかえって、どきどきしながら、ただ泣いていた。ふた針ぬったあと、お前も自分から醒めるのをおそれるように、こんこんと眠り続け、夜じゅうまんじりともしないで見まもった私たちの心配の中に、今朝はもう、すっかり元気な目醒めだった。その笑顔を見て、ああよかった、と思ったとたん、何だか力が抜けて、こんどは私の方がぐったりと眠ってしまったのだ。 それにしても、これからのお前の成長過程を通じて、こんなつらい思いを何度も味わねばならぬことを思うと、今更のように、人の生きることの深さをかんがえさせられる。そして、「子供は可愛い」という月並みなことばを持つ意味深さが、新たな深みを加えて私に迫ってくるのだ。ああ、その辺にさりげなく凡々とうごめいている無数の父や母の心に、こんなに痛みやすい心が秘められているのだとは!うかつにも、これは、お前の傷によってえたわたしの新しい体験だ。 毎日の新聞が、大きく朝鮮の戦争を報じている。「爆撃」とか「占領」とかいう文字をよむ私たちの心には、二つの勢力の進退を測る、将棋見物の心情が先に立ち易い。しかし、私の心は、こういう痛みやすい父や母の心を、先ず感ずべきなのだ。私は、もう白い包帯をしていることさえ忘れたように、私の膝で歌うお前を抱きながら、何トンの爆弾、何機の飛行機という文字に注目をする。すると、その一トン、その一機が、ぴくん、ぴくんと、私の心に痛い。どうか世界の皆さん、一発の弾丸でも、どんなに父や母の心が痛むか、そういう数えきれない累積として、戦争を思い、新聞をよんで下さい―私は今更のような反省で、遠いところを見つめるような気持ちになり、無意識にもお前の頭を撫でてしまう。1950・8・1どうして?―という問いをお前のまわらぬ舌は、どおって?と発音する。この数日、急にお前は、そういう問いを発するようになった。あの、質問によって知識を得ようとする成長期がお前の中で始まったのだ。【中略】「どおって?」この幼なことばに、わたしは生涯をかけて答えねばならない。じつに無数の問いにたいして、正しく答えることのできる父でありたい。【中略】愛とか苦しみとか喜びとかの人の心の彩りについて、更に、死や戦争や貧乏について・・・・・水々しい(原文ママ)お前の問いに答えることにより、私も新しくすべてをみつめなおすことだろう。お前と共に、また勉強だ。*****************************************荒井さんは、すでに茶色に変色し、ところどころページがほつれかかっているその本をいとおしそうに触れながら、話を続けた。「これは、私が生れた時から2歳半ごろに書かれた父の日記なの。公の場でお話をする機会があるときに、私はこの文を引用することがよくあるの。それは、自分がいかに愛されて育ったかということではなく、親の子への愛、親としての責任、平和に寄せる思いを強く伝えてくれる文章だからなんです。」 筆者は、荒井さんの朗読を聴きながら、涙があふれてくるのを止められなかった。以前、夫の不注意で、娘が腕に大やけどをおった時のことを思い出していたのだ。その時の、夫が泣きながら、壊れてしまうのではと思うほど娘を強く抱く姿を。抱かれながら、懸命に痛みをこらえる娘の姿を。その二つの愛おしい存在を眼前に、何もできずに立ちすくむ自分を。また、本文中にある「爆撃」という言葉を聴いたとき、筆者は終戦の日を目前に長野空襲で47人の死者がでたという事実のことを考えていた。たった数十年前、今私たちが暮らすこの街で、47人もの民間人が戦争で亡くなったという事実。47という数字は、単なる一塊の数字ではない。その先にはひとり、ひとりの命があり、わが子の死を悲しむ47人の親たちの姿を想像すると、怖くて、辛くて、涙が止まらなかったのだ。――荒井さんは、続ける。眼に見えない大切なものを見抜く力「平和って、決して軍隊や兵器で守られているものではないと思うの。私たちの、ほんの少しの想像力で、世界中のあちこちの痛みを自分の痛みのように感じることができる人がふえれば、その気持ちの延長線上に、「平和」を守ることはできるはず。そのためにも、大人たちが、想像力と創造力を使って、眼には見えない大切なものがわかる心。そして、おかしいことは、おかしいと言える強さ。本質が何かをわかる大人として、成長していきましょうね。」「この文は、この本で読んでほしいから、お貸しするわ。」と荒井さんは、1950年に理論者より出版された大事な大事な初版本「愛になやみ、死をおそれるもの」を、筆者に貸してくださった。筆者は、まだまだ話し足りない気持ちを抱えたまま、エディターズミュージアムを後にした。:****************************************荒井さんとお話を終えて・・・母だからこその使命戦争やテロのニュースを見たとき、遠い国のどこかの話ではなく、私たちは、わが子の「いのち」はもちろんのこと、すべての「いのち」について、もっと敏感に、もっと真剣にならなくてはいけないのではないか・・・それこそが、母としての使命ではないか・・・と思うのです。ひとりひとりの「愛するものを守りたい」という強い思いの累積が、怒りや欲望や恐れや怨みで、複雑にからみあうマイナスのエネルギーの集大成としての「戦争」を食い止めることができると、信じたいのです。そんなこと言うのは、おろかなドリーマーだと政治家やオトコたちは笑うかもしれません。でも、母たちは、本気で平和を望みましょう。本気で、わが子を、自分たちの暮らしを、世界の平和を守りましょう。 それぞれの出産。それぞれの子育て。それぞれの家族があっていい。でも、どんなときも「平和」でなければ・・・そんな思いを少しでも皆さんと共有したくて、書かせていただきました。文責 大日方 雅美★エディターズ・ミュージアムEditor's Museum 「小宮山量平の編集室」上田駅下車お城口徒歩2分 若菜館ビル3階 ?0268(25)0826開館時間:AM11:00~17:00 休館日:火曜日入館料:一般300円・中学生以下無料 http://www.editorsmuseum.com/今回、私が訪れたのは、上田市にあるエディターズミュージアム~小宮山量平さんの編集室~そこは、数々の良質な児童文学作品を送り出して下った理論者の創設者であり編集人であり、96歳にして現役の作家である小宮山量平さんの15000冊からなる蔵書が納められているスペースだ。その空間に入って一瞬にして私は、図書館が大好きだった小学生の私になった。かつての私が夢中になって読んだ本、繰り返し読んだ、懐かしい本に出あえたのだ。ちなみに、このビルの中にある若菜館は、創業110年の老舗のうなぎやさん。残念ながら私もまだ味わっていないので、今度行く時は、ぜひうなぎも食べたいと思っています。
2010年05月24日
コメント(0)
-
平和について
うむうむネット通信 第4回「あの人に会いたい」 エディターズミュージアム「小宮山量平の編集室」代表 荒井きぬ枝さん以前、上田市にあるエディターズミュージアム(小宮山量平さんの編集室)を訪れた時のこと。突然の訪問にもかかわらず、小宮山さんの長女である代表の荒井きぬ枝さんは、一見の若造である筆者を温かく迎えてくださいました。「兔の眼」の作者である灰谷さんの思い出を聴かせて下さったり、児童文学について、子供について、教育について、平和について、小数派についてなどなど、時間を忘れてしまうほど、自由に楽しく、熱く、いろいろなお話をさせていただきました。とても貴重な時間でした。先日、筆者はテレビで山田監督の「母べえ」を観たとき、同じ母として、いてもたってもいられない気持ちになりました。今も世界中のあちこちでは、戦争で親を失う子供があふれ、傷だらけで戦う兵士たちは、それぞれの「正義」の名の下に、誰かを殺し、街を焼き尽くし 戦争が続いています。 一方で、今自分が、こうして静かな朝を迎えられるシアワセは、温かい夕食を家族で囲めるシアワセは、すべて「平和」であるという大前提のもとに成り立っていることを今更ながらに、強く強く感じたとき、言いようもない焦燥感に襲われました。そして、「命を大事にするという哲学を日本人はもう一度取り戻さなくてはいけない」という小宮山量平さんの言葉と出会った、エディターズミュージアム代表の荒井きぬ枝さんから、「平和を守るということについて」のお話を聴きたくなったのでした。 IMAGEIN ~想像してみよう~「平和を守る」とは、何も、声高に「戦争はんたーい!」と大声で訴えることではないと思うの。それは、「想像する」ことから始まるのです。「もし、あなたの愛する人が戦場にいかなくてはならなくなったら・・・もし、あなたの大事な子供が、爆撃を受けたとしたら・・・・・」愛する人がいる人なら、お母さんになった人なら、想像しただけで、とても耐えられないわよね。そんな親としての当たり前の気持ちを書いた父の文を紹介するわね。」 荒井さんは、一冊の本を静かに開き、朗読を始めました。****************************************私はお前をえたとうとうお前は生まれてきた。(中略)生れるとすぐ眼をひらいた。きれいな体。あらゆるものを祝ってあげたいような、祝福、祝福!1947・11・11お前のお七夜ということで、十何人のお客様だ。お前を抱いて、仏前。神前におじぎ。 そうしながら、私はふっと、涙ぐむ。ひとりの人間が生長する過程には、こんな素朴な祝福が、やはり何度となく積み重ねられているのだ。私たちは、1人1人の人間を、そういう祝福の累積として見ることを忘れがちだ。人のいのちが大切だ・・・・・ということの内容は、ひとりの人間の中にも、実にたくさんのひとびとの祝福が積み重ねられているからだ、ということになるかもしれない。お前によって、今更のように、命の尊さ、温かさを知る。1950・7・13昨日、おもいがけなく、お前にけがをさせてしまった。表てを通るジープを珍しがってはしりでたようとしたとたんにころんで額を割ってしまったのだ。血がふきでるのをおさえて、お母さんが医者へかけていったあと、私は寝台にひっくりかえって、どきどきしながら、ただ泣いていた。ふた針ぬったあと、お前も自分から醒めるのをおそれるように、こんこんと眠り続け、夜じゅうまんじりともしないで見まもった私たちの心配の中に、今朝はもう、すっかり元気な目醒めだった。その笑顔を見て、ああよかった、と思ったとたん、何だか力が抜けて、こんどは私の方がぐったりと眠ってしまったのだ。 それにしても、これからのお前の成長過程を通じて、こんなつらい思いを何度も味わねばならぬことを思うと、今更のように、人の生きることの深さをかんがえさせられる。そして、「子供は可愛い」という月並みなことばを持つ意味深さが、新たな深みを加えて私に迫ってくるのだ。ああ、その辺にさりげなく凡々とうごめいている無数の父や母の心に、こんなに痛みやすい心が秘められているのだとは!うかつにも、これは、お前の傷によってえたわたしの新しい体験だ。 毎日の新聞が、大きく朝鮮の戦争を報じている。「爆撃」とか「占領」とかいう文字をよむ私たちの心には、二つの勢力の進退を測る、将棋見物の心情が先に立ち易い。しかし、私の心は、こういう痛みやすい父や母の心を、先ず感ずべきなのだ。私は、もう白い包帯をしていることさえ忘れたように、私の膝で歌うお前を抱きながら、何トンの爆弾、何機の飛行機という文字に注目をする。すると、その一トン、その一機が、ぴくん、ぴくんと、私の心に痛い。どうか世界の皆さん、一発の弾丸でも、どんなに父や母の心が痛むか、そういう数えきれない累積として、戦争を思い、新聞をよんで下さい―私は今更のような反省で、遠いところを見つめるような気持ちになり、無意識にもお前の頭を撫でてしまう。1950・8・1どうして?―という問いをお前のまわらぬ舌は、どおって?と発音する。この数日、急にお前は、そういう問いを発するようになった。あの、質問によって知識を得ようとする成長期がお前の中で始まったのだ。【中略】「どおって?」この幼なことばに、わたしは生涯をかけて答えねばならない。じつに無数の問いにたいして、正しく答えることのできる父でありたい。【中略】愛とか苦しみとか喜びとかの人の心の彩りについて、更に、死や戦争や貧乏について・・・・・水々しい(原文ママ)お前の問いに答えることにより、私も新しくすべてをみつめなおすことだろう。お前と共に、また勉強だ。*****************************************荒井さんは、すでに茶色に変色し、ところどころページがほつれかかっているその本をいとおしそうに触れながら、話を続けた。「これは、私が生れた時から2歳半ごろに書かれた父の日記なの。公の場でお話をする機会があるときに、私はこの文を引用することがよくあるの。それは、自分がいかに愛されて育ったかということではなく、親の子への愛、親としての責任、平和に寄せる思いを強く伝えてくれる文章だからなんです。」 筆者は、荒井さんの朗読を聴きながら、涙があふれてくるのを止められなかった。以前、夫の不注意で、娘が腕に大やけどをおった時のことを思い出していたのだ。その時の、夫が泣きながら、壊れてしまうのではと思うほど娘を強く抱く姿を。抱かれながら、懸命に痛みをこらえる娘の姿を。その二つの愛おしい存在を眼前に、何もできずに立ちすくむ自分を。また、本文中にある「爆撃」という言葉を聴いたとき、筆者は終戦の日を目前に長野空襲で47人の死者がでたという事実のことを考えていた。たった数十年前、今私たちが暮らすこの街で、47人もの民間人が戦争で亡くなったという事実。47という数字は、単なる一塊の数字ではない。その先にはひとり、ひとりの命があり、わが子の死を悲しむ47人の親たちの姿を想像すると、怖くて、辛くて、涙が止まらなかったのだ。――荒井さんは、続ける。眼に見えない大切なものを見抜く力「平和って、決して軍隊や兵器で守られているものではないと思うの。私たちの、ほんの少しの想像力で、世界中のあちこちの痛みを自分の痛みのように感じることができる人がふえれば、その気持ちの延長線上に、「平和」を守ることはできるはず。そのためにも、大人たちが、想像力と創造力を使って、眼には見えない大切なものがわかる心。そして、おかしいことは、おかしいと言える強さ。本質が何かをわかる大人として、成長していきましょうね。」「この文は、この本で読んでほしいから、お貸しするわ。」と荒井さんは、1950年に理論社より出版された大事な大事な初版本「愛になやみ、死をおそれるもの」を、筆者に貸してくださった。筆者は、まだまだ話し足りない気持ちを抱えたまま、エディターズミュージアムを後にした。:****************************************荒井さんとお話を終えて・・・母だからこその使命戦争やテロのニュースを見たとき、遠い国のどこかの話ではなく、私たちは、わが子の「いのち」はもちろんのこと、すべての「いのち」について、もっと敏感に、もっと真剣にならなくてはいけないのではないか・・・それこそが、母としての使命ではないか・・・と思うのです。ひとりひとりの「愛するものを守りたい」という強い思いの累積が、怒りや欲望や恐れや怨みで、複雑にからみあうマイナスのエネルギーの集大成としての「戦争」を食い止めることができると、信じたいのです。そんなこと言うのは、おろかなドリーマーだと政治家やオトコたちは笑うかもしれません。でも、母たちは、本気で平和を望みましょう。本気で、わが子を、自分たちの暮らしを、世界の平和を守りましょう。 それぞれの出産。それぞれの子育て。それぞれの家族があっていい。でも、どんなときも「平和」でなければ・・・そんな思いを少しでも皆さんと共有したくて、書かせていただきました。文責 大日方 雅美★エディターズ・ミュージアムEditor's Museum 「小宮山量平の編集室」上田駅下車お城口徒歩2分 若菜館ビル3階 ?0268(25)0826開館時間:AM11:00~17:00 休館日:火曜日入館料:一般300円・中学生以下無料 http://www.editorsmuseum.com/今回、私が訪れたのは、上田市にあるエディターズミュージアム~小宮山量平さんの編集室~そこは、数々の良質な児童文学作品を送り出して下った理論社の創設者であり編集人であり、96歳にして現役の作家である小宮山量平さんの15000冊からなる蔵書が納められているスペースだ。その空間に入って一瞬にして私は、図書館が大好きだった小学生の私になった。かつての私が夢中になって読んだ本、繰り返し読んだ、懐かしい本に出あえたのだ。ちなみに、このビルの中にある若菜館は、創業110年の老舗のうなぎやさん。残念ながら私もまだ味わっていないので、今度行く時は、ぜひうなぎも食べたいと思っています。 皆さんも、少し足を伸ばして ご家族で訪れてみてはいかがですか?
2010年05月05日
コメント(0)
-
うむうむネット通信 「あの人に会いたい」より、内田幸一さん
うむうむネット通信 第3回 「あの人に会いたい」冒険あそびの森 代表 内田幸一さん 大人からもこどもからも“うっちゃん”の愛称で親しみを込めて呼ばれている内田幸一さんは、およそ30年前に飯綱高原に移住し「子どもの森幼児教室」飯縄高原ネイチャーセンターを設立。 現在、飯綱にあるネイチャーセンターを拠点に、幼児、児童の自然体験の推進や、親子関係に関する講演など自然教育や環境教育を軸とした活動をされています。 2009年度オープンした「冒険あそびの森」の一角にある木遊び館でお話をお伺いしました。 なぜ、自然教育なのか・・自然は、人を育てる 学生時代、自然が好きな自分は、飯綱をはじめ長野や山梨、関東近郊の自然豊かな場所を何度も訪れ、登山など通じて自然の中でかけがえのない体験をしました。自然の一員である人間は自然を通じて成長しますし、進化をしてきた生き物でした。自然の中で沢山の活動をしてきたことと専門である幼児教育を結びつけたのは、はじめはチョットした思い付きだったのかもしれません。この30年間の様々な活動は、その直感を検証するためだったようにも思っています。自然体験というと特別なことを考えがちですが、ただ、じっと花を観察したり、虫の様子に見とれたり、木に登ったりといった誰でもがごく当たり前にすることから始まります。自然の中で遊ぶことで坂を登ったり、木にぶらさがってみたり、飛んだり、ころげまわるうちに身のこなしが良くなります。手や足の先まで意識が届いて動くと自分の身体はことのほか心地よいものとして感じられます。そんな一瞬に達成感や充実感を感じるものです。それはある種の喜びの感情であり、その喜びは必ず次の行動を呼び起こします。自然の中で多くの子どもたちと過ごしてきた私は、子どもたちの自然の中で見せる様子を数多く見る機会に恵まれました。天候の変化や人の力の及ばない自然の中で、子どもたちは時にドラマチックな目覚しい成長を見せる時があります。自分を柔軟に変化させ自然の力に逆らうこと無く適応するその姿は素晴らしいものです。子どもたち自身に成長の可能性があるのはもちろんですが、自然環境がそのきっかけを作っていることは明らかです。自然には人が用意するものとは違った、子どもたちを成長させる教育的な可能性があると私は確信しています。 自立とは、自分の人生を幸せに生きる力を持つこと 子どもは成長します。成長とは、子どもの年齢、時間軸によってそのとらえ方は変わっていきます。しかし、成長のゴールは自立への道筋をたどることだと考えています。そして、親の役割は、子どもが自立できる力をつけるための援助者といったところでしょうか。では、自立とはどんな力でしょう。私は、自分の人生をより良く生きるための力だと考えています。自己を肯定し、卑屈にもならず、過大評価でもなく、自分の裁量や能力を正しく把握し、自ら望む方向へ進んでいける力。積極的に人とのコミュニケーションをとりながら人との関係、物事との関係を自分の意思や考えで判断し、向き合い方や自分の生き方を自分で決断できる力。問題が生じても、どうしたらその問題を解決できるかを判断し、対応していくそんな力を身につけることではないでしょうか?過去においては、日常生活の中で知らず知らずのうちに身につけることができた人として必要な技能や知恵は、現代社会ではなかなか育むことが難しくなっています。そうしたものは実体験の中で多くは育まれてきました。人としての基礎が築かれることなく、更にその上を築くことは難しいでしょう。自立した一人の人間を育てるためにはその基礎となるところを育てることを意識しなければなりません。自然の中での活動や多くの子どもたちが交流し様々な関わりをもつ活動は、子どもたちのそうした人としての基礎を育てる機会になるでしょう。心も身体も実体験の中で成長していくことをどうぞ知っていただきたいと思っています。 子どもの自立のために大人が、できること、心がけること~安心感が成長を引き出す~ まずは、子どもを信じましょう。もちろん成長に即した対応や付き合い方は必要です。基本的に大人は子どものやること、選ぶことを穏やかに見守ります。危険からは守らなければなりませんが、出来るだけ子どもの自由にまかせます。親が理解できること、大人のものさしに合うことだけを褒めるのではなく、その子のそのままを受けとめることが大切です。お子さんはいつも親が大好きでどんな親でも認めているのに、大人の方は条件を出して子どもに様々なことを一方的に要求してしまいます。子どもと大人の信頼関係を崩しているのは大人の方からという事になるかもしれません。大人が自分を認めているという安心感をもったとき、子どもは自分から動き出します。自分が決めたことを行動に移し認めてもらえる経験を積み重ねた子は、自分を肯定でき自己に対する信頼を増すことが出来ます。自分を肯定的にとらえる子は、他者に対しても積極的に働きかけ新しい人間関係を構築していくことが出来ます。また、自分との違いについても寛容であり対応もできます。こうした子どもを肯定した信じる形の大人の子どもに対する向き合い方により、子どもはその子自身の持つ力を最大限に活かし、自分の可能性にチャレンジする力を発揮するものです。 「子どもの自立」をサポートするためには、 まず大人が自立する 子どもの自立を見守る大人が、まずは自立していなければと思います。大人の自立とは、親として大人としての自分の立ち位置を明確にすること。自分の考え、生き方をはっきり示すことが出来るか、相手を理解できない、意見が違う時も、怒りといった感情ではなく、相手の意見や話を聞き入れる余裕があるか、自分の言った言葉に責任を取れるか、約束を守れるか、一人の人としての在り方、その姿勢を持つことだと思っています。その場しのぎの子どもだましではなく、ぶれない大人の生き方や感性が大人に求められているのだと思います。子どもは大人の嘘を見抜く力を持っています。子どもからはその事は言ってきませんが、感覚的本能的に受け入れられないものとして、大人の本性を見ぬくものです。ですからことのほかこのことは私たち大人側が、意識して正していかねばならないでしょう。そうでなければ、この悪しきことを子どもたちは学んでしまうことになります。 ☆ご案内今回、お話を伺った内田さんの活動拠点を紹介します。私たちの街、ナガノにはこんな豊かな財産『自然』がある。親子でイイヅナを遊びつくそう! ☆冒険あそびの森 ~自然は子どものミュージアム~街中や自宅ではなかなかできない遊びや活動が一年中行える野外体験施設です。ツリーハウスや、ダイナミックなロープでの遊び場のほか、キャンプ施設・幼児用トイレ・オムツ交換台もあります。●入場料:小学生~大人:500円・幼児・300円・2歳以下は無料問合せ先:飯綱高原 ネイチャーセンター 電話 026-239-3301 ☆ ツボミ子育てサロン~よちよち自分の足で歩き出したら、イイヅナの自然が両手を広げて待ってるよ~ 1歳6ヶ月からの未就園児とその保護者対象。懐の大きいあったかいスタッフたちが、親子ともに受け止めてくれ、親子で一緒に、自然を”感じる”体験ができます。今回、”うっちゃん“の話を伺った大日方も、当時1歳10ヶ月の娘と2年間、お山(ツボミ子育てサロン)へ通いました。長靴姿で思い切り笑って、遊んだ親子の時間は、私たち親子の原点です。
2010年04月05日
コメント(2)
-
ラリマー
ラリマー静かに握る指の隙間から ラリマーのこぼれた光が 語りかけてくる。昔、昔、ずっと昔 私は、月だった。月に「虹の入り江」という場所があることを知っているかい?そこは、月の光の源で、私は、そこから長い間、この星(地球)を観ていたよ。いつか、きっと、ここに来ることになると想いながら。どれくらい、時を重ねただろう。十六夜の晩は、この入り江に 月の光を注ぐと、小さく揺れるさざ波は、光のかけらを水面に集めていたよ。何百回、何千回、何万回と十六夜の晩を迎えるたびにさざ波は、月の光のかけらを あの岸辺に運びつづけ永い、永い時間の中で、かけらは私になっていった。繰り返される悲しいデキゴトが、この星で続くたびに遠い月から 地球の芯から私を呼ぶ 誰かの声が聴こえ私は、いろんなところへ旅をしてそうしていま、あなたにたどり着いたんだ
2010年03月13日
コメント(1)
-
味覚が引き寄せるインスピレーション
おいしいモノがすきだ 食いしん坊だ。 腹八分目でなんて、やめられない。 いつものアレを食べる 安心感も大事だが ときどき、ほんの時々、 想像できない、したこともない 思いがけない 食・味との出会いが ワタシを刺激する。 見た目、というよりも 舌で感じた印象がムクムクと 動き出し、 思わず言葉にしてしまうことがある。 デコレッドルームズの大豆ブラウニーを 食したときのこと、 当初イメージしていた味よりも 数段、オトナな味だったので おもわず、「プラダを着た悪魔」みたい・・・と、漏らすと そばにいたゆっぴーさん、なないろさんオオウケ。 先日、言の葉さんと、なないろさんと 隠れ家で、食べた中華料理にも、やられちまった! あのピリリと山椒を効かせたマーボードーフは、 明日のジョーの「丹下のおっさん」みたいだった。 、 また言の葉さんと、なないろさん、大わらい。 これって、 こういう日記で読んでも なんのことやら、わからんだろうな= ライブで、 同じものを食べた人たちにしか 伝わらないのだろうか・・・・・ なんて、えらそうだが オイシ~ウマイ~ しか、出ないときも もちろん多数。 言葉すら、出せない味もある。 おいしいモノは、五感を刺激する。クリエティブな食べ物は、人もクリエティブにする。
2010年03月13日
コメント(0)
-
スピリチュアルエレメント
すぐそこに山肌がみえ、 とうとうと流れる河音の中、 言の葉さんの スピリチュアルエレメントは始まった。 仰向けになったことまでは 確かな記憶 そのあとは、もう 言の葉さんの、手・指から届くあったかいものを 皮膚の奥のほうで感じていたとしか、言いようがない。 何をどうしたのかは、思い出せないけれど 眼を開けるまでの間、 ずっと、眠っていたのかといえば、 言の葉さんの気配は感じていたし、 ときおり、ポコポコと地中から湧き出す温泉のように レイキを感じたときみたいに カラダの中で、あったかい動きがあったことも感じていた。 ひとつひとつは思い出せないけれど 人や、できごとが脳内に 映画のスクリーンのように、 映し出されては、一瞬で消えていった。 時計にすれば、1時間とちょっとの間 早いとか、長いとかという時間の概念はなく、 ワタシの意識は、別の場所にいた気がする。 およそ20年前に、ひどい鞭打ちをしてから 四度の鞭打ちをし、 そのために、長い間 首の運動(後ろに傾けること)ができなくなっていた私の首が そのために、美容院でのシャンプーを諦めているワタシの首が 前に、横にと、言の葉さんの言葉にあわせて ゆっくり動いたあと、 恐る恐る、後ろに傾いていったときのこと、 首と鎖骨のあたりが ローリングストーンズのタラコクチビルのように裂け そこから、ナイアガラの滝があふれ出す映像が 見えた。 その映像だけは、それまでの すぐに消えてしまう曖昧な記憶ではなく かなり、はっきりと感じた、見えた映像だった。 そこから、 言の葉さんからの質問が始まった。 水しぶきを感じながら、滝のような中を通っていく自分と そういう私達を、かなり斜め上の場所から、眺めている自分がいた。 その時の、私は自分そのもの。 それ以上でも、それ以下でもない、ちょうどいい ワタシ。 月と眼があった!と感じるときの 雪上で、寝転んで 自分の背中と雪と地面と空が つながっていくと 感じる その心地よさ と同じ種類。 あ~ そうか~ そうだったんだ~ インドアで、軟弱なワタシだけれど 自分が思っている以上に 月や、森や、川や、風、山・雪に インスパイアされるんだ、ということを 気づいたというか 思い出したというか。
2010年03月13日
コメント(0)
-
リフレーム~人生で大切にしたいこと~
別名「上質な井戸端会議」に参加したときのこと。いくつか出されたのお題の中で、一番ココロに残ってるモノ「あなたにとって人生で大切にしたいことを3つあげてください。」ワタシの大切にしたい3つのこと。☆自分にも、他人にも誠実に生きること。☆愛し合うことそして、☆楽しむことそれから、3人一組でグループを作り、自分の書いたものを、シャッフルして他の人に渡す。他の人は、人の書いた 「人生で大事なこと3つ」を自分のこととして、説明をする。それを、書いた本人ともう1人が聴いて感想や、実際にはどういう気持ちで書いたのかをシェアする。という リフレームという ワークをした。自分では書かない、選ばない 他の人の大事なことをあえて言葉にすることで他の人はどう捉えるのか、どう考えるのかを知ることはとっても新鮮であり、自分自身の考えを深めるためにもよいワークだったと思う。そして、人の大事にしていることを、自分の言葉で語りだすことも。今回の場合、こどもの年齢も、職業も、バックボーンも、まったく違う偶然集まった3人が、人生において「楽しむ」ことを大事にしたいという共通項で、つながっていた。これも、また、何かの縁なんだろう。大事なこと、好きなこと、わかっているようで、知っているようで知らない自分のことあらためて、人の言葉を借りて、気づく、感じることができる「リフレーム」というワークに、表現のセッションという、可能性も感じた。
2010年01月31日
コメント(0)
-
「心の専門家」とは?
心が弱ってる人、病んでる人が増えているという。数字的には、そうなのかもしれないが、実際には、昔と単純に比較できないとおもっている。精神科・心療内科という病院に通院するということが以前よりは、ひろく理解されるようになったからかもしれない。だからといって、偏った知識で、心の病に対する差別や、偏見が 少しは減ってるのかどうかはわからないしかし『病』という診断を受けた人も、受けていない人も、苦しんでる人、辛い人、不安な人という人も含めれば、『心が弱っている』人はかなり多いように思える。そして、そういう人が増えれば増えるほど『心の専門家』という商売もあちこちに、増えているように感じる。この時代に、あまりにも安易な「カウンセラー」やら、「セラピスト」が増殖してはいまいか?もちろん、きっと多くの『心の専門家』は、真摯な想いを持ってるはずだと思いたい。ただ、彼等に問いかけてみたい。話しを聞いてもらって、すっきり、ドコロですまない、闇夜をさまようような人たちの一生と付き合う覚悟はあるのだろうか・・当事者にとってみれば、どうなのだろう・初めて会った「心の専門家」という職業人ではなく、必要なのは、一生を通して、人生をかけてその人をそのまんま、受け止めてくれる存在なのではないだろうか・
2009年09月05日
コメント(0)
-
夏休みが終わり
信州の夏休みは、短い。夏休み最終日の夜『人生サイアクの日だ~』とハナゾー。いつの間に、人生サイアクの日なんて表現をおぼえたのかと驚いたがすかさず、「今日が、サイアクなら、明日から楽しいこと増えていくばっかりじゃん」と返すと、『明日も、サイアクだもん』だと。「サイアクって? わかってる?」と訊くと、モゴモゴしつつも、「だって、ずーと学校でしょ!」夏休みが終わって 2学期が始まり4日めの今朝、玄関で、動けないハナゾー。緊張していた4月もどんなに眠い朝も、今日はちょっとゲンキないな~という日もランドセルを背負って、玄関に行けばもう、心決めて、それなりにゲンキよく『行ってキマース』」と出発していたけど、夏休み明けの19日は、家から出て、しばらく立ちすくんでたのを夫が、窓から見かけてた。そして今朝、ハナゾーのココロが、本当にイヤって言ってるの、伝わってきて、ドアのところまで、出て行きもう一度抱きしめる。ゲンキの元、ハナゾーに入っていくように、と祈りながら小さく、がんばって、と、声かけた。ワタシがカラダを放し、一歩踏み出た後振りかえった顔が、 あんまり切なくてもういちど『がんばって』とは、言えなかった。それでも、ハナゾーは、何かを振り切るように出かけていった。さっき、手渡したランドセルの重さがワタシの手に残ってた。緊張と興奮の4月が終わり、かなり学校に慣れるまでには時間がかかることを覚悟していた割りに早く慣れて良かったと思い始めた5月連休明けだろうか一方で、ハナゾーのコトバの中にどうやら、小学校とは自分が想像していたような場所ではなく、なんで?と腑に落ちないことばかりなんだろうな。と学校や先生に対する疑問や不信が少しずつ、ほんの少しずつ見え隠れしてるのを感じてはいた。私自身も、ハナゾーの疑問の声がわかるだけにそのつど、親として最良の対応ができたかというと自信がない。ある先輩お母さんは、そういう疑問やズレ、このままでいいのか?という思いを親も子も抱えながら、3年生くらいまではいくの。でもその頃に、なると、あきらめの気持で慣れていくんだよ・・」と。その話しをきいて、そうなのか、そうなのか・・と深いため息をついたことを思い出した。夏休み帳の中に6種類ほどの自由勉強があった。自由といいながら、ハナゾーの学校では、押し花やたたき染め と指定されていたのでもちろんそれをやっていったのだが夏休み帳の中にも「色水あそび」があったのでハナゾーが、キャンプで体験したたまねぎの皮で染めたTシャツを持たせた。オトナが見てもステキにできたのでハナゾーの意思ではなく、勝手にワタシがランドセルにいれておいたのだが、その夜、私が『センセイ、なんて言ってた?」と訊くと「洋服の(染め)なんて、宿題になっていません・・・・て。」呆然とした。呆然としすぎて、すぐに言葉が見つからなかった。言葉が見つからないので、怒りとあきれの感情が 飛び出た。「おかーさん、センセイにアタマに来た!お手紙、書く!」とぷんぷんしながら言うと、 ハナゾー『ヤメテー! ハナゾー、なんとも思ってないから。おかーさん、お手紙書かないで。」と、冷静に言う。その表情を見たら、親ばかかもしれませんが、ハナゾーは、もうセンセイのこと、ザンネンな人だってわかっちゃってるんだな、と感じた。まだ、悲鳴という音にならずに バイブレーションのような形で外へ発信しているハナゾー。それは、緊急ではないかもしれない。それでも、この世で一番愛する我が子から聴こえてきたのだから気にしない、なんて、できない。今の私にできることは何だろう。どうすることが、ハナゾーにとってベストなことなんだろう。ガッコウやセンセイばかりに問題があるとは思っていない。やはりワタシに余裕がなく、幼稚園時代に比べると 何かをするわけでなもない、 なんとなく二人でいる時間というものが、ものすごく減ってしまっていることも影響していると思う。今の私がすぐできることといえば、できるかぎり日々の生活の中で、ハナゾーと過ごす時間をもうちょっとだけ丁寧に、と心がける。ハナゾーには笑っていて欲しい。自分も、人生も好きでいて欲しいから。
2009年08月24日
コメント(0)
-
戦争とは あなたの愛する人が死ぬということです
戦争とは あなたの愛する人が死ぬということです。もう二度と会えなくなるということです。美輪明宏さんはナガサキで被爆しています。9日は、ナガサキに原爆が落とされた日です。平成21年の8月9日の11時2分私は、雨の中、家族で海に行く車の中ナガサキの平和式典の中継をラジオで聞きました。ムスメはすやすやと車で眠っていました。私は安心して夫の運転に身を任せていました。何もかもが平和な時間でした。その中で話された被爆者代表の方の言葉が耳から離れません。64年前の8月9日、8歳の彼女は家族9人新築したばかりの家で 元気に暮らしていたそうです。その日の朝も楽しく朝食をとっていたそうです。それなのに11時2分、アメリカが落とした原爆がすべてのものを彼女から奪っていきました。たった8歳の少女と全身ヤケドを負った4歳の弟だけが生き残りどうにか逃げたもののその弟も、戦争が終わって2ヵ月後に亡くなり、彼女は、1人ぼっちになりました。原爆体験そのものも地獄絵のようですが、その後の家族がいない生活は苦しくて悲しくて地獄のようだったとこの苦しみを、もう誰にも味あわせたくないと思ったから46年間誰にも話せなかった辛く、悲しい原爆の体験を次世代に語り継ごうと決めたそうです。ラジオから聴こえる被爆者の方の話しを聞きながら7歳のムスメが1人になったことを想像しただけで私は、いてもたってもいられませんでした。何も語らずとも今の70代以上の人には 少なからず戦争の犠牲者だと思います。再び、美輪さんの本からの抜粋です。戦争とは、自分が好きな音楽も聴けない。好きなファッションもできない。命令に従わなければ、ぶん殴られ、蹴られ、そして殴り殺されても だまって、受け入れるしかない。戦争とは、理不尽で悲惨なことばかりでした、正義の戦争なんてありません。硫黄島で戦った高齢の元アメリカ人兵士が話していました。戦争に勝ち負けもない。みんな、負けなのです。戦争は、すべての人が、バラバラになり、ぼろぼろになるだけだ、と。平和を望むという言葉を聴いたとき皆さんは、何を思い浮かべますか?私は、日本国憲法9条とジョンレノンの「イマジン」です。私は、憲法9条改正に反対です。ぜったいに反対です。9条は、現実的でないという人がいますがそれなら、どうして日本は戦後いちども戦争をしないですんだのでしょうか?北朝鮮のような危ない国から、国を守るためには軍隊が必要だ、9条を変えよう!という人がいます。そういう考えを持つ人は残念ながら、今の日本で結構、おおぜいいるようです。平和を望むからこそ、武器が必要だ、という表現をする人もいます。自分から攻めに行くのではないやられた時だけ、やり返すのだからいいのだ、という言い方をする人もいます。でも、それって、戦う意思を公にしていることだと思いませんか?国を守ると言われても、国って、なんでしょう?国はどこ?国は誰?自己中心といわれてもいい、私は国を守るかどうかよりも大事な家族を守りたい自分の人生を守りたい大切な友人たちといい人生を送りたい家族と幸せに暮らしたいそう願うちっぽけな1人の人間です。そしてなんの力も、知恵もない私のような一市民が一番犠牲になるのが戦争だと思うのですだから、どうしてもどんな正義があろうとも戦争はイヤなのです。韓国のスターにも徴兵制があることを知り日本にはなくてよかった・・・だけでいいのでしょうか?私たちが一生懸命に働いて納めてる税金が、どんな使われ方をしているかを知らないでいいのでしょうか?不景気対策という名目でばら撒かれた還付金が結果として、生まれたばかりの赤ちゃんにいたるまで一人4万円強の借金を背負わされたことになっていることも・自衛隊の国家予算がどのくらいかも。皆さん知っていますか?そう書いている私もわからないこと、知らないことばかり。私たちは、だいじなことをしらなすぎです。どうして日本はあの悲惨な戦争を始めてしまったのか、どうして負け続ける状況で 戦争をやめれなかったのか、私も答えられません。でも、そんな私にもいえる事はあの戦争は間違いだったということです。美輪さんは言います。大切なのは、真の教養・考える力 判断する力だと。そのための教育が必要なのだと。戦前に暗殺された原敬首相は、こう言っていたそうです。食料に限らず、石油ももちろん、鉄もニッケルも、日本には資源がない。その日本が世界で認められるとしたらそれは人的資源である、と。一握りのエリートたちの数学オリンピックの成績がいいか悪いかも大事ですが、もっと、大事なこととして自分の頭で考えて、判断し、行動できる小市民を育てることが、親であり、私たちオトナの責任だと思うのです今の平和な日本に暮らすひとりひとりが本気で64年前に起こった戦争を知ること平和を望み、戦争を拒むことが自分の人生を愛し、すべての命を尊ぶことにつながることだと信じています。たとえ ドリーマーだと笑われても。最後に想像してみてください。夏休みを利用して自由に旅行に行くこともなくお気に入りのアロマでお風呂にはいることも満足な食事をとることもできずあなたの愛する人が今日、あなたを守るといいながら、戦争に行く日を。
2009年08月10日
コメント(0)
-
修繕するものとされるものの力関係に差があってはならない
「修繕するものと されるものの力関係に差があってはならない」 人を助けに行く人は使命感に燃えた強い人が多い.けれどそうすると助けられる方がたまったもんじゃないそういうときにスッと同じ力、同じ強さになれる・ことが大事。と、臨床心理学者の河合ハヤオさんは書いています。それって、同じ弱さやナイーブさ、寂しさを感じることができることが大事言い換えることができるのでは、ないのでしょうか?。私、「癒し」って言葉も あんまり好きじゃなくなってきました。 人に癒しを与えるなんて、なんて、おこがましいんだろう・・て感じちゃうんです。だが、毎日、7歳になるムスメとの暮らしの中で圧倒的な 強さの象徴のような 母 が、一方的に、自分の経験と価値観と、母の都合で、「しつけ」とかいう名目で何かをムスメにおしつけていないだろうかそしてもうひとつ。「やさしさの根本は、死ぬ自覚 」by河合はやお魂と魂を触れ合わせるような人間関係をつくろうというとき大事なのは、お互い限りある人生なんだ、必ず死ぬものなんだと言う一点を共有しあっているということ。 あなたも死ぬ、私も、死ぬ、お互い死ぬんだということを日々共有していけばお互いが尊重しあえる。と書いています。「やさしさ」の意味も変わってくる気がします。相手のマイナス面も受け入れられる。そんな関係だからこそ永遠を感じる至福のひとときが、永遠につながる。 のでしょうね。
2009年07月19日
コメント(3)
-
星野道夫さんの言葉
原野で出会うクマの命と自分の短い一生とどこかで絡まっている。 自然という同じタペストリーの中に織られたそれぞれの糸のような気がしてきた。 この世に生きるすべてのものはいつか土に帰り、また旅が始まる。 かけがえのないものの死は多くの場合、残された者にあるパワーを与えてゆく。 19歳の時に一冊の本を手に取ったことで導かれるように訪れたアラスカの魅力を生涯かけて、確認していった星野さん・ 圧倒的なアラスカの自然の中で、あらゆる命が「生きている」ことの奇跡に対する畏怖の念を写真と、コトバで私たちに伝えてくれた星野道夫さん。星野さんの文章を読めばよむほど、自分の短い人生を知っていたとしか思えないようなコトバにであう。全ての命は無窮のかなたへ、旅を続けている。そして、星さえも同じ場所にとどまってはいない。 この世に生きるすべてのものはいつか土に帰り、また旅が始まる。 人はいつも、それそれの光を捜し求める長い旅の途上なのだ 人はいつも、それそれの光を捜し求める長い旅の途上なのだ
2009年07月15日
コメント(0)
-
うむうむネット通信・インタビューより「助産師 保谷ハルエさん」
お産を語る会が二ヶ月に1度発行している 「うむうむネット通信 」の「あの人に会いたい!」というインタビューコーナーを隔月で 担当することになりました。その第一弾の方のインタビューをまとめたものです。 新企画「あの人に会いたい!」記念すべき第一回目は、うむむネットのアドバイザーでもある助産所ほやほやの「保谷ハルエ」さんです。連休明けのある日、お忙しい保谷先生にお時間をいただき、代表のUと、T、Oの3名がお話を伺いました。~助産所ほやほやが生まれるまで~Q なぜ、助産師になろうと思ったのですか?「助産所ほやほや」を作った経緯を教えてください。A 看護士として最初の配属先が産科だったことが、きっかけですね。産看護士よりも、輝いていたのが助産師だったんです。産科では、助産師が主体的に動けることが多く、その仕事の奥深さ、可能性に心惹かれ、助産師になることを決めました。助産師として病院に勤務していたときも、新しい命を迎える喜びや感動を感じてはいました。でもどこかで、「お産」の主役はお母さんと赤ちゃんなのではないか、助産師がもっと寄り添う「お産」があってもいいのではないか、という思いを感じていました。その気持ちが「助産所ほやほや」につながっています。そうはいっても、開業当時は分娩を扱う助産所はほとんどなく、おっぱいマッサージなどが中心でした。しかし、ある熱心な妊婦さんから「どうしても助産所で産みたい」という相談があり、その方の主治医からも「何かあったら待機しているから」という力強い励ましをいただいたことで、最初の分娩を受け入れる決意をしたのです。その後、あちこちから問い合わせがあり「助産院で産みたい」「自分らしく産みたい」と多くの妊婦さんが望んでいることを実感。「自分らしいお産」「自然なお産」を支える助産師として「助産所ほやほや」を整えていったのです。 ~赤ちゃんの誕生!その感動がパワーの源~Q,お産は365日、24時間体制でハードなお仕事だと思いますが、とてもパワフルな保谷先生。その原動力はなんですか?A やはり、かわいい赤ちゃんでしょうね。お腹の中から見守ってきた赤ちゃんを、自分の手で取り上げるという感動は、何物にもかえられません。また、妊婦さんとそのご家族、みんなで「お産」をしたという一体感ですね。赤ちゃんが無事に生まれたという安堵感、新しい命を迎えるという喜びを共に味わう中で、大きなエネルギーが蓄えられていく気がします。「妊娠」「出産」という人生の特別な機会に、自然な力の素晴らしさ、感動を1人でも多くの方に味わってほしいと思いますね。~ 自分らしいお産は、自分らしい子育て、自分らしい人生につながっている~Q どうしたら「自分らしいいいお産」ができるのでしょうか?A 忙しすぎる現代では、気力、体力、体型的にも自然なお産が難しくなっています。理想論だけでは、いいお産はできません。まずは自分の体を信じて!食事も生活習慣も含め、自分のしたいお産ができるカラダ作りから始めてください。自分を信じるために、自分自身をコントロールする必要もあります。妊娠から出産までの間には、体調不良に加えて不安や葛藤も乗り越え、自分の状態を受け入れることができたときに、女性は、1人の子供の命を育てるという母としての責任や覚悟が生まれるのだと思います。Q 保谷先生が考える「いいお産」「自然なお産」とはどんなお産ですか?A 自然なお産とは、自分の力を最大限に発揮できるお産ですね。そのためには、妊婦さんも赤ちゃんも、リラックスした状態が一番いい。私たちはできる限り、ご自宅で過ごすようにリラックスできる環境を用意しています。女性が本来備わっているはずの「産む力」を発揮できるように、妊婦さんの気持ちに寄り添い、いろいろな面でサポートできるのが助産師ですから。現実には、全ての妊娠、全ての出産が安産ではありません。多くの病院では、分娩台の上で妊婦さん自身も何が起こっているのかわからないまま医療行為が進んでいく、ことがあるのです。だからこそ「いいお産」をするためには、他人任せ、病院任せにせず、「自分のお産は、自分でコーディネートする」という主体的な意思が必要です。どこで産むか、どんな方法で産むかだけが問題なのではなく、結果として自然分娩でなかったとしても、「お母さんになる」という喜びと自覚をもって、主体的な「お産」、自分なりの「納得できるお産」ができたら、それが「いいお産」だと思いますね。自分らしいお産ができた人は、自分らしさを大切にし、自分の存在を肯定できるでしょう。そして、きっとその子らしさを大切にするいい子育てをするでしょう。自分らしいお産をするということは、自分の人生を自分で生きることにつながるのです。だからこそ、私は、そうした女性たちを全力でサポートしていきたいのです。お話を伺った後、保谷先生が「助産所ほやほやさん」を案内してくださいました。どの部屋にも畳があり、家庭的な落ち着ける雰囲気でした♪ ちょうどお昼時だったこともあり、助産所内のキッチンから、美味しそうな家庭料理の匂いが漂ってきました。 帰り際、「お母さんたちのパワーは頼もしい。応援しているよ。」とステキな笑顔で声をかけていただきました。
2009年07月07日
コメント(2)
-
「粗にして 野だが 卑ではない」
「粗にして 野だが 卑ではない」 城山三郎 ~石田 禮助の生涯~ 城山三郎さん原作のテレビドラマが 渡辺謙主演で 制作されているらしい。 先が見えない不安と混迷の今、時代が、 多分、オトナの男たちが、城山三郎さんを 求めているのだろう。 城山 三郎さんといえば、経済小説・伝記小説の第一人者である。 正直、そう多くの氏の著作を読んだわけではないが、 20代前半の私は、このタイトルに惹かれて、文庫本を手にした。 それまで、自分が読んできた分野とは明らかに違っていたのが、 面白くて一気に読んだ覚えがある・ というのも、この本に描かれた第五代国鉄総裁 石田 禮助の生き方が、その言葉に集約 されていたからだ。 実際に、石田氏が国鉄総裁として、国会に登院した際、代議士たちを前に自らのことを、 「生来、粗にして野だが、卑ではないつもり。」と、話したそうだ。 人として、こう在りたい、と、おもった。 そして今も、この言葉に惹かれ続けている私がいる。 この言葉を眼にするたびに、自省する私がいる。 自分は、 どうだろう?卑しくないだろうか? と。
2009年07月05日
コメント(0)
-
言の葉ノート
毎日の暮らしの中で、いろんな「ことば」と出会う。人とつながる 話し言葉も、 1人自分と向き合う 活字も。言葉と仕事をしてきて人と、ことばを、話してきてことばは、難しい、つくづくと思う。それでも、私は 「ことば」が好きなんだ、な、とも。ことばに、たすけられたり 微笑んだり、うなづいたり、涙ぐんだり、傷つけられたりしながら、生きている。これからも、できるかぎり、自分の真ん中と、ずれない言葉で 生きていきたい。 言葉にすることが、思考である。 by 勝間和代今をときめく 勝間和代さんが、朝日新聞のコラムで書いていたことをおおまかに、まとめると、自分の経験や感覚を、何らかの言葉に変換していくプロセスそのものが私にとっての思考なのです。優れた思考や体験を聞き、良書を読み、それを、ブログや人に話すその一連の流れが言葉を受け取って考え、その考えを、再び言葉にする活動それこそが、思考するということ。 言葉が、わたしたちの思考をつかさどっている。 だからこそ、言葉は、人生を変えると。おそれおおいですが、私もまた、同じようなことを感じ、考えていたのでこのノートの最初の言葉に、選びました。 ずっと、おろそかにしてきたこちらのブログですができる限り、書いていきたい と、思っています。
2009年06月17日
コメント(0)
-
シンプル イズ 美味い!
家人が 知人から 北海道直送の カラ付牡蠣を、もらってきた。 我が家の一番大きななべ、いっぱいに、牡蠣を並べ 料理酒をふりかけまくり 蒸す。 ナイフで殻をこじ開けて プリプリの牡蠣に柚子をしぼり 食す。 潮味が効いていて、ウマイ! 殻に残っている、やや白みかかった汁も ウマイ! 素材がうまいと、料理はいらない。 シンプル is best を痛感。 しかし、こんなうまいもの、今から味わっている ハナゾーの味覚が、末恐ろしい。
2008年11月28日
コメント(2)
-
不思議な出会い
冷たい雨が 朝から降る日だった。 目の前で、バスが行ってしまい、 次のバスまでの時間を確かめると 結構、あった。 うんざりしながら、歩道もない道を ワタシは歩き始めた。 カサは、折りたたみだったので 弱弱しかった。 そのときの自分みたいに すぐ折れちゃいそうなほど。 結局、次の次の次のバス停まで 雨のなかを歩いた。 もどるにもどれない道を歩きながら、 強力な相棒、パタゴニアのウィンドブレーカーさえも へなちょこに成り下がっていった。 カラダはどんどん冷え切っていったし、 ワタシは、ここで何をしているんだろう。 と思うと、こころにも 冷たい雨が、どんどんたまって 水溜りのように どんよりしていた。 ようやくバスがきた。 ワタシは、かなり情けない顔で、 あたたかいバスに乗り込んだ。 空席はいくつかあったが なぜだか、ワタシは吸い込まれるように ある老人の横に座った。 カラダがあたたまる間での間 ワタシは目に入ってくる外の景色も見えず 車内のおしゃべりも、聴こなかった。 ちょうど、ワタシの心も体も 「バスに乗っているいまの自分」 に追いついたときワタシの心が 落ち着きを取り戻した状態になったことを知っていたかのように 隣の席のおじいさんが、抜群のタイミングで 静かに話し始めた。 ずいぶん昔、この島(イギリスのワイト島)を恋人と一緒に離れ、アメリカに向かったこと その恋人と一緒にとても苦労したこと しかし、その恋人は死んでしまったこと それからしばらくして、 今の奥さんとであったこと。 その奥さんととても幸せに アメリカの西海岸で暮らしていること 今日は (確か50年ぶりといっていたような気がする、 とにかく、彼女と島を離れて以来、)久しぶりに 故郷のワイト島に帰ってきて、過ごしたんだ。 というような、身の上話をしてくれた。 そういわれれば、ここで暮らす高齢者のファッションとは 明らかに違う装い。 そして、 自分は、二人も、人生で最高のパートナーといえる 人と出会えたのだから、とても幸せものだとおもえること そんな言葉に ワタシはただ、熱心に耳を傾け、その穏やかな雰囲気の紳士の前でとてもリラックスした気持ちになっていた。 さっきまでのびしょぬれな気持ちは、 ほとんど乾き始めていた。 ごらん、窓の外の木々を 美しいだろう? とても生命力を感じる、美しさだ! 僕はね その辺に座っている彼女たち(地元に住むおばあちゃんたち)のことはわからないんだけど、 あの木々や、 それから、そう君の事 わかるよ。 君の人生はとても素晴らしいものになるよ! 僕には、わかるんだ。 そういわれて ワタシはとても嬉しかった。 握手をして御礼を言ったような気がするが 実際のところ、私はいつバス停を降りたのか、 どう別れたのかは、思い出せない。 そのおじいさんは、 ただ、異国にひとりでいる、びしょぬれで、 しょぼくれていた いかにも惨めな東洋人のワタシを 励ますために そんなことを言ってくれたのかもしれないけれど ワタシの心は、とても暖かくて ふんわりふくらんでいた。 心地よい気持ちだけが いつまでも残っていた。
2008年11月28日
コメント(0)
-
五感で味わうことの難しさ
納期すれすれの仕事を抱えつつ、 生誕100年東山魁夷展に ハナゾーと行ってきた。 雨の平日午後なので、すいていることを祈っていたが さすが、国民的画家と呼ばれる画伯の大規模な展示なので 駐車場には、県外からの車も多く、そこそこ混雑していた。 入館料は、ありがたいことに園児は無料。 今まで、ほぼ何でもそうだったけど、 ハナゾーが、小学生デビューと同時に、 いろんなことにお金がかかるようになることをあらためて、認識。 美術館などには、気軽に連れて行きたいのにな~と思う。 入り口には、音声ガイドが並んでいた。 いつも、音声ガイドを借りようか迷うのだが、 これまでの私は、そのまんま、観たまんまを感じたいので 借りたことがなかった。 今回も、最初は借りるつもりはなかったのだが、 いくつかの作品に関して、東山画伯本人の肉声で 作品のポイントを説明しているということから 音声ガイドというものを借りてみた。 しかし、音声ガイド機は、すぐにハナゾーにとられ ハナゾーは、目の前にある『作品』よりも、その操作に夢中である。 私は、体をかがめて、ハナゾーの耳に近づき、 2人でガイドを聞こうとする。 でも、その中腰は、腰痛持ちには耐え難い姿勢だった。 画伯本人の声で話されるからこその、説得力ある言葉が 耳に入ってから、作品を見直すと、「なるほど」という発見も もちろんある。 しかし、不器用な私は、耳がコトバに意識を集中すると 目は確かに作品を見ているのに、アタマのなかに言葉が先走りをし、 作品そのものの持つパワーのようなものを、 あまり掴めなかった気が・・・・五感全部で味わうなんて、 仕事で割と気楽に書いてしまうこと、あるけれど そんなこと、そうカンタンにはできないことを体感。 途中から、ハナゾーに音声ガイドを自由に持たせ、 私は私のペースで作品と向かいあうことにした。 東山魁夷の作品は 林を描いても、紅葉を描いても、京都の雪を描いても、山を描いても、ヨーロッパの家並みを描いても、そこに『気』がある。『気配』があるのだ。手を伸ばせば、絵画の中の「気」を手ですくえそうなほど。それは、深い森の中を歩いたとき、なんとなく感じる『気』 川面を眺め続けている時、なんとなく感じる『気』に 近いような気がする。 後半、音声ガイドを手放したことで 私は、自分なりの鑑賞を取り戻した。 しかし、 ポーラコレクションのとき、ローランサンやルノワールの作品の前で、動かず見入っていたハナゾーを知る母としては 残念ながら「東山画伯、完全に音声ガイドに完敗の状態です」 と、言わざるを得ない。
2008年11月28日
コメント(1)
-
贅沢な信州の秋
朝4時 家をでた我が家の狩人 雨の中、びしょぬれになりながら 大物を見つけて、大満足でご帰還。 なんと、天然マツタケ、直径15センチはあったでしょう。 あんな大きな国産、というか 山で採ったマツタケ、見たことない しかも、幻の・・といいながらここ3年、毎年 味わっている 舞茸さんまで ご同伴で。大物二種のキノコ、写真に収めようとしたら 「そういう無粋なことはしないの!」と家人に一喝されたので 画像でお見せできないのが、残念。 マツタケご飯にしようかな~と思っていたら 「今夜はすき焼き」の一言で 決まり。 信州牛だけを買いに、夏にイベリコ豚を購入した肉専門店に向かう。 最初、牛肉を300グラム買ったのだが、「お野菜大目なら、300でじゅうぶんですよ。」という言葉に反応し、プラス100グラム追加する。 キノコを味わうために、他の具を少なめにしたい、我が家の料理人の意図から、糸こんにゃくは水っぽくなるから不要とのこと。 具は、マツタケ・舞茸、焼き豆腐ちょっととネギ、そして牛肉 のみ。 割り下のバランスも、料理人にお任せ。 マツタケ、舞茸の処理も、ぜ~んぶ、採ってきた方がやってくださる。 私は、ネギと焼き豆腐を切っただけ。 ウチの人は釣ったサカナもそうなのだが、自分で採ったものは、その瞬間から こうやって、食べる・・というようなイメージが できているらしい。 そういう意味でも、主婦にとっては、贅沢な夕食でした。 味は、そりゃ、もう、オイシカッタ。 マツタケは、そのままではハナゾーが失神シソウナホド(ウソ) キツイにおいだったので、かなり時間をかけて味がしみてから 食べても、なお「マツタケ」を主張する強い味。 味は、断然舞茸のほうがウマイ。 ハナゾーお肉しか食べていないんじゃ? 次の日も、ハタケシメジを採ってきた家人 オリーブオイルにガーリックで炒めて、最後にちょっとだけ お醤油でパスタと食べました。 これまた、うまかった~ 昨日の大物二種類のキノコに比べるとクセがないので ハナゾーも、食べる食べる。 信州の秋は、ほんと幸せです。 果物もおいしいしね~
2008年11月28日
コメント(0)
-
終わりは 始まり
まだ夏の太陽が照りつける9月初旬普段の生活ではまったく縁のない『広尾』に上陸した。その日から、心の余震は続いている。あれから、二ヶ月。長野の朝の最低気温は3度。フリース着込み、110デニールのタイツをはき最後のハピチアに参加するために発車ギリギリの新幹線に飛び乗った。ママイキ@長野受講中の初夏、主催者ちいちいさんから、ハピチアを勧められた私。ハピチアをよくわかっていないまま、 直感で申し込むことを決めた。 すでに定員オーバーのところ、コーチにお願いしなんとか、16期に滑り込むことができたのだ。そして・・・ハピチア16期の多くの方は、すでに自分のツールを手にし、明確なビジョンを見据えてさらに高みに登ろうという意欲ある面々。それにくらべて、自分はといえば恥ずかしながら相変わらずのモラトリアムを、どうにかしたくて。仕事を説明すれば『商業ライター」というものの完全受身の受注体制で、忙しさも、仕事の内容も、そしてもちろん、報酬も自分ではコントロールできない今の状態から、一歩前に進むべき道・方向を見極めたくて、確かめたくて、挑みたくて、受講を決めたのだ。初回、二回目のハピチアの凝縮された2時間半は、興奮にも似た状態で、ひろっしゅコーチから心地よいほど熱くて、速いボールをバシバシ投げられた。しかし、日常に戻れば、9月、10月は短納期連続の仕事をなんとかこなすことだけで精一杯で宿題も、投げられたいくつものボールもどう受け取めているかの振り返りが十分でないまま過ぎていった。そして最終回の11月・三回目を迎えてしまった。初回、二回目の前日や朝に感じたワクワク感よりもどよ~んな気持。あせりや苛立ち。『ハピチアは終わってしまうのに、自分って」という自己嫌悪感にも近い気持でハピチア3回目を迎えた。三回目は、初回、二回目に比べ、圧倒的にシェアの時間が多く強い志をもって、自分の目指す方向へ進もうとしている人たちののコトバは、リアルに響いた。いろんなことに気づき、チャレンジをしている16期メンバーの存在はワタシにとって、これまでにない大きな刺激だと感謝したい。この縁を大切に、互いに高めあう関係を、大切に、していきたいと思っている。しかし、自分は、霧の中にいる。今、立っている場所さえ、ぐらつく岩場なのか、砂場なのか、土なのかそれさえも、わかっていないまま ハピチアは終わってしまった。終わってしまったのだが、これは『始まり』なのだと今は思える。受講前、消化不良気味だったココロに、小さく弱くとも、確かな火種がともっている。レジュメ表紙の言葉『自分ひとりのビジネスとは、ライフスタイルそのものであり、自分と言う人間がどういう人間か、自分は何を大切にしているかを表明するものである」~『自分ひとりのビジネス」より自分の強みを活かせるツール(ビジネス)を探し出そうとばかりしていたけれど、それだけではスタートできない、ダメなんだ、ということだけは確信した。自分が求めていた劇的な答えなんかなくてどんなに苛立ちやあせりや自己嫌悪感がくすぶっていたとしても目をそらさずに、今まで以上に、もっと深く広く、冷静に、「自分がどういう人間なのか」を、見据えていくことが必要だという『始まりの始まり』に、行き着いたのだ。
2008年11月11日
コメント(6)
-
私版・シャルルドゴール空港にて
ロンドンから私がシャルルドゴール空港に到着したときのことだ。どれくらい前になるのだろう?今ならユーロスターを利用しただろうが、その当時はまだドーバー海峡を通っていなかったのだ。 残念ながらシャルルドゴール空港では、運命の出会いも、心を待つような爺さんにも会えなかったが、日本人の良心!?には出あえた。 入管後、荷物を無事に見つけほっとしたら、私は急にトイレに行きたくなった。 バックパックなのでそのまま背負ってトイレ近くまで行ったが、ひとつしかない小さなトイレ入り口には、ツアー客らしい関西系女子大生軍団がところ狭しと並んでいる。狭いトイレに大きなバックパックが邪魔になることは間違いなかった。そうかといってそのあたりに置いていくわけにもいかない。 それなら!と、私はトイレを済ました女の子たちの後をついて行った。そして、ツアーの集合場所らしき周辺にいる彼女たちに 「すみません、ちょっとこの荷物みてていただいていいですか?」と、私のバックパックを頼んだ。ツアーの人が全員戻ってこなければ、彼女らはここから動かないはず、という私の読みで私はそれで安気にトイレに行くことができ、すっきりした。それから、彼女たちのツアー集合場所へ戻り、無事に見張ってもらっていた我がバックパックを受け取った。 「ありがとうございました」と立ち去ろうとすると、荷物を見てくれていた人は『え?同じツアーの人 ちゃうの?』と驚く。 「すみません、違いま~す。一人旅なんでお願いしちゃいました!」と私。彼女たちは、あっけにとられていた。 今は「日本人」というだけでは、信用できなくなってしまったなあ
2008年11月04日
コメント(5)
-
シャルルドゴール空港にて
シャルルドゴール空港と言えば、人気作家と女優が運命的な出会いをした場所、ということで話題になったことがあるが私にとっては、もっと印象深い話がある。 シャルルドゴール空港に作家の開高健が到着したとき、ベンチに御爺さんがひとりで座っていた。ひどく沈んでいるように見えたので『大丈夫か?』と声をかけると 「心が、ここに追いつくのを待っているのだ」と答えたそうだ。 この話は、残念ながら、シャルルドゴール空港で、ではなかったけれど。 同じ家に住むようになる前、旅の途中で、釣り人が私に話してくれた。 人類は飛行機などという、考えてみると空恐ろしい文明の力を発明し、駆使するようになったおかげで、世界は本当に狭くなり、移動時間も驚くほど短くなった。けれど、そのことを便利になったと言うだけで、片付けられない人もいる。 寄り道、回り道が好きな私も、「早く!」が、苦手だ。 そうはいっても、飛行機には、乗りたいですがね。
2008年11月04日
コメント(2)
-
官能的なステーキ
実家から「りんごで育った信州牛」のステーキ肉をもらった。我が家では、うまいものの料理は棟梁にまかせる・・がルールになりつつあるので、今夜も任せた。塩、ブラックペッパーで下味をつけ、にんにくと焼く。ほとんどレア。結構な厚みもあったのだが、やわらかい、肉に甘みがある。ハナゾーもぺろりと食べた。 棟梁は、にんにく、しょうが、りんごを摩り下ろし、そこに酒、しょうゆを混ぜた特製ソースも作ってくれたが、パワーある肉本来の味には、日本の宝「しょうゆ」だけが一番美味しかった!ああ、本当に美味しかった。 ここだけの話 さっき食器洗いを済ませた後、こっそり一人でもうちょっとだけ焼いて、また食べてしまった!この肉のうまさは、官能的だ。 本当は、マクロビオティックとかも気になっていて、最近は「美味しい精進料理」なんて本まで買っちゃったのに この誘惑には勝てなんだ。
2008年11月04日
コメント(0)
-
ワクワクその後
ワクワクした気分で書いた日記が9月25日だったのだから、 どれくらい、時間が経っていたのかを考えると 悲しい。 そして、やるせない気持ちになる。 世の中、誰もが忙しいんでしょうが 私もそれなりに、忙しい中、急いで書いたコピーを、 3週間以上も、担当者にほっておかれていた。 何のために2時間半も打ち合わせをしたのだというのだろう。 それを元に書いたコピーも+新しいアイディアも ほって置かれたあげく 違う担当者になって、ゼロからの打ち合わせだと。 書いたコピーの中味をどうこう言われるのも確かにイヤだけど これって、それ以前だろう~ ワクワクが大きかっただけに 沈むよな~。 しかも、その担当者、私の中では信頼できる人だったから余計に 不信感も加わって・・・ マイナスな感情があふれて、ドよーんとしてしまった時には これって、何かの修行? どんなをメッセージを受け取ればいいの?と 自分に訊いてみる。 そのとき、自分なりの答えが見つかれば 結構、早く浮かびあがれるんだけど。 参ったな~。 こんなことがあっても、進行中の他の仕事もあり・・・ トンネル中の 落とし穴の一つを紹介しました。
2008年10月29日
コメント(8)
-
ピカソに打ち抜かれて
10月6日 雨13時までは、自分力を高めたい女性たちのセミナー「ハピチア」に参加。そこで、眠気も吹き飛ぶ濃い時間を過ごしたあとは、ひろっしゅコーチをはじめ、同メンバーでランチにいく。その後、ワタシは、1人「六本木」に向かった。広尾から地下鉄で一本、ミッドタウンのサントリー美術館で、ピカソ展が始まったばかりのことをチェックしていたからだホントは、新国立美術館と同時開催なので、両方観たかったけど、次の日も朝から仕事で遠くに行く予定があったし、短時間で観るには新国立美術館では広すぎると思ったので、サントリー美術館だけにした。小学3年生だった。地元の県立美術館に、ピカソ展が来て両親と姉と観にいったのは・・その時は、作品よりも、会場に大きく飾られていたピカソの写真が印象的で今でもはっきりと覚えている。写真のピカソの目にビビビと打ち抜かれたのがワタシのアート初体験だったと思う。それから、時が過ぎ気がつけば、美術館に行くことが好きなオトナになった。そして、今もピカソが好きだ。ワタシがその昔、ヨーロッパへ旅したのもパリとバルセロナのピカソ美術館に行きたかったから。この美術界の巨人はいまだに誰にも、犯されない。むしろ、ますます他を寄せ付けない圧倒力をもつ。サントリー美術館では「魂のポートレート」というタイトルで 自画像、人物像を中心に約60点を展示。「青の時代」以前の作品から最晩年のものまで。その変幻自在な作風の変化が年代ごとに展示されているのでピカソの人生と重なって わかりやすかった。それにしても ピカソの作品たちは絵にせよ、彫刻にせよどれも、なんと「生なましい」ことだろう。作者から離れ、作者は死に、残された作品らが、いまだにピカソのエネルギーの塊を内側から放ってくる。恋に破れて10代で自殺した親友のデスマスクを描いたピカソもすでに美術界での地位を確立したピカソもどの作品を見ても、感じるのは苦しくても、しんどくても「自分」から目をそらさなかった、ということ。やはり、今回もピカソに打ち抜かれた私。帰る前にハピチアの宿題、小さなサプライズを一つ。アートサロンで売っていたピカソのポストカードにこのときのワタシの感動やら興奮やらを走り書きし 大好きな友人あてに送る。
2008年10月09日
コメント(13)
-
忙しさにも、感謝
仕事で忙しいことを愚痴らないようにしよう。 特に、疲れてきたり、数が膨大だったり 先が見えなくなったりしてくると つい、つい 勝ってになんだか 被害者みたいな気持ちに なって、 見えている担当者 見えないその先の、担当者 そして、ワタシの大事な家族にさえ すさんだ気持ちをむけそうになる。 でも、だけど、 ワタシはこういう仕事をしています、と 手を上げている以上、 そして、引き受けた以上 どんなに、単価が安くても どんなに、納期が短くても どんなに、内容がわからんちんでも。 「仕事」で忙しいことは 愚痴ることではないだろう? 毎回、納期と質のバランスをとりながら その中で、ベストを尽くして仕事をしているつもりだ。 それは、当然のことだ。 単に、使い勝手がいいからかも、しれない。 適当に、お願いしやすかっただけかも、しれない。 それでも、これだけいろんな人がいる中で ワタシを選んでくれたこと、指名してくれたことに 感謝しよう。 そして、ワタシとその仕事がであった意味や ワタシが、その仕事を通して得ることが きっと、あると思えば やはり、仕事をいただけるということは なんと、ありがたいことでは、ないか。 1日を無駄なく、過ごしているか? もっと、メリハリつけることはできないか? 優先順位は間違っていないか? そういうこと、全部、見直して、 それでも工夫の仕様がないほど「忙しい」時に、 はじめて 忙しさを口にしてもいいのかもしれない。。。
2008年10月09日
コメント(2)
-
風林火山編
稀代の軍師・山本勘助が主役だった昨年のNHK大河ドラマ「風林火山」 長野県内には数多くの「風林火山ゆかりの地」がありますが、その中でも今回は上田市周辺に絞り、いくつかをご紹介します。まずは、上田市内にある上田原古戦場を紹介しましょう。ここは、諏訪を落とした甲斐の武田晴信・後の信玄(市川亀次郎)が、本格的な信濃侵略の足掛かりとして、坂城を本拠とする村上義清と対決した場所です。戦死者は約4千人あるいは6千人ともいわれ、晴信も傷を負う激戦となった一帯は、現在、県営球場を中心に古戦場公園として整備されています。 近隣には、山本勘助(内野聖陽)を庇護しこの地で討死した武田家の重臣、板垣信方(千葉真一)の墓があります。信方が愛煙家だったとの言い伝えから、タバコを供えると願い事がかなうともいわれています。上田原の戦いで手痛い敗戦をした信玄は雪辱を果たすべく、村上勢の要衝砥石(戸石)城に兵を進めます。その戦いが有名な「信玄の砥石城くずれ」です。上田市北東部にある砥石城跡地は、まさに山城そのもので、信玄を苦しめたであろう山道を登りきると、上田市街と真田の町並みが一望できます。無敵の武田勢が落とせなかったこの砥石城を攻略したのは、信玄の懐刀・名将真田幸隆(佐々木蔵之介)でした。真田幸隆は、山本勘助との出会いから、仇敵武田家に仕えることになったといわれています。大河ドラマのなかでは、勘助にとって数少ない心を許せる友であり、ともに軍略を語り合えるよきライバルとして描かれています。 旧真田町にある真田氏歴史館には、真田三代に関する各種の資料が展示されています。また、幸隆夫妻、昌幸のお墓がある真田氏の菩提寺長谷寺は、シダレザクラが有名なので、ぜひとも春に訪れたい場所です。 砥石城を真田幸隆に預け、本格的に北信濃への侵攻が可能になった信玄は、越後の上杉謙信(Gakt)との決戦に備え、まず生島足島神社に願文をささげ、次に塩野神社に朱印状を奉って武運長久を祈りました。 生島足島神社には、信玄が配下の武将に忠誠を誓わせたとされる「武田信玄武将の起請文」83通と、勝利を祈願した「願文等」11通(ともに国重要文化財)が残されており、境内の歌舞伎舞台に、常設展示されています。現代口語訳も併設されているので、解り易く読むことができます。 また塩田平にある塩野神社は、約1100年前の書物『延喜式』にも記されている古く格式神社です。ここでも「武田信玄朱印状」が残されています。上田市指定文化財である塩野神社の拝殿および本殿は江戸時代に造立されたものですが、「楼閣づくり」と呼ばれる珍しい二階建ての拝殿は、特に必見です。 最後は、川中島の合戦の折に、信玄が負傷兵の湯治場に使ったと伝えられる大塩温泉を紹介しましょう。のどかな田園地帯にあり、数軒の宿がひっそりとたたずむ鄙びた温泉です。武田信玄(市川亀治郎)の家臣大塩氏によって発見された大塩温泉は、信玄の隠し湯と言われています。格安で気軽に入れる共同浴場でのんびりと、山間の静けさを味わいながら、歴史散策の疲れを癒せます。 ご紹介した各史跡は、交通の便は良くありませんが、クルマさえあれば、比較的近距離ですので、半日程度の時間で、ゆっくり回ることができるでしょう。 機会があれば、ぜひ訪れてみてください。きっと、歴史上の人物達が身近な存在に思えてくることでしょう。
2008年10月08日
コメント(0)
-
インプットその1
エレベーターを降りると、ハピチアメンバーのテーブルから白い光が出ていた・・・ように、見えた。これも、ハッピー勘違い?空席に座る。まだ、軽く息があがっている。着席したのに、即はその場に入れないワタシ。湿った服がカラダに張り付いてきた。そのとき、カラカラ空っぽ頭のルーレットがとまった。そこへ、ココ一ヶ月の自分の動きを振り返り、話している方の言葉が ス~っと入ってきた。言葉が耳に、心に届いた時すでにカラダは着席しながらも、入りきれなかったワタシの意識全体が、透明人間になって「ハピチア」に、入っていった。おおお、滑り込みセーフ。もはや、雨に濡れたことも、道をまちがえたことも、朝方まで、やっていた仕事のかけらも残っていない。スイッチの入ったワタシのインナースペースにはハピチアメンバーの話やひろっしゅコーチのエネルギーあふれる言葉がどんどんと、インプットされていく。気持ちいい~行動量の人は、確実に、いろんなことが見えている。気づけている。自分はどう?どう?どう?メールでも、ブログでも、心が動いた時には即レスしよう。伝えなければ、伝わらない。伝えてもらって嬉しかった、与えてもらえて嬉しかったことは、ちゃんと 嬉しさのお返しをしよう。自分の都合、自分の判断だけで「そのまんま、・・・ぱなし」の人、いるんじゃないの? どう?どう?どう?熱っぽい言葉、思いのある言葉を集中して聴き拾いながら自らへの問いかけも、バンバンバン矢を放つ。いまだに、突き刺さった「矢」はどんな人を応援したくなるか?の答えたち。それは、そのまま、自分はどうかの問いかけでもある。○一生懸命な人○謙虚な人○人のために動いている人○ポジティブな人○共感できる人○切磋琢磨している人○本心で話をしている人○自分とちゃんと向き合っている人○素直に頼ってくれる人○自分にとって魅力的な人○同じ経験をしている人○信用をしている人ナドナドなど・・・人と人の関係を大切に。もちろん、今だって、今までだって、そうしてきたつもり。でも、これまでは、自分なりの、自分だけの判断や対応だったのでは?相手を「承認」していたか?「評価は相手が決める」この言葉もまた、いまだに 抜けない矢の一つ。刺さった矢は、ワタシ内へとインプットをし続ける 小さな見えない注射針だ。数週間、擦り切れ削られていた、ワタシに効いている。
2008年10月08日
コメント(8)
-
インプット前
納期が重なり、半径1メートル以内の世界で、1人、パソコンとのニラメッコ生活が続いてる。家事は、できる限り、見て見ぬふり。お昼は食べずに、何かかじるものを口にいれて、手を動かし続ける。友人からのランチのお誘いも二度 三度とお断りしている。体重はいっこうに減らないが、 それでも確実に、自分の何かが削られている。 6日朝納期の仕事を、無事に6日朝3時ごろメールして、ほっとして、ようやく第一回目のハピチアのレジュメを、手に取る。初夏、意気込んで申し込んだハピチアだが、第一回目からの一ヶ月、まともに宿題もできず「あ~と~で~」とアタマの片隅にある押入れに押し込んだまま、二回目の10月6日がやってきてしまった。新幹線に飛び乗った時には、眠気を通り越し、アタマグルグルグルグルルーレット。ムスメを実家にお願いしたとき、お気に入りの黄色のかさを忘れたために広尾駅からしばらく、秋雨の中を歩いた。目で見ているよりもずっと降っている雨で濡れたワタシは、タクシーを捕まえようとおもったのだが会場の正式名称を思い出せずに断念。髪が濡れる。帽子も濡れ始める。それでもしかたなく、しばらく濡れたまま歩き続けたワタシの中で、小さな元春が「情けない週末♪」を歌ってくれた。大好きな歌だがテンションがさがる。アタマのルーレットは回るだけで、役に立たない。こういうときこそ「私って、運がいい!」と声に出そう。目の前に、「コンビにより安いビニ傘」のポップ発見。ほら、ワタシはやっぱり、運がいい。と ハッピー勘違い。そう思ったのもつかの間、道を間違える。どんどん、ハピチアが遠のいていく。もう300円のビニ傘のおかげで、雨に打たれてはいないんだけど「アカシアの雨に打たれて」ならぬ♪金木犀の雨に打たれて、このまま、溶けてしまいたい~と、1人、懐メロの替え歌を小声で歌ってみる。いかん、余計に、遠のく。こういうときは、「私って、運がいい!」と、声に出そう。ほうら、やっぱりワタシは運がいい。だって、こうして溶けないで、ちゃんと、見覚えのあるオシャレな入り口に到着できたのだから。つづく。。
2008年10月07日
コメント(0)
-
北白樺高原 長門牧場
以前、仕事で書いた信州の観光案内を思い出したように、いくつか載せていきます。 今回は、「長門牧場」 蓼科山のふもと、標高1,400メートルの北白樺高原に位置する長門牧場は、本州一広く酪農を中心に、生産・製造・販売を一貫して行なう国内では新しいスタイルの牧場です。 東部湯の丸インターより車で45分、県道40号からの入り口には二頭のかわいい牛が訪れる人々を出迎えてくれます。広い駐車場から花壇を抜けて進んでいくと、そこは見渡す限りの牧草地。目の前を遮るものが何もない敷地は、東京ドームの45倍、216ヘクタールという本州一の広さを誇ります。 お天気が良い日は、浅間山、※北信五岳、美ヶ原高原、北アルプスといった長野県の代表的な山々が一同に見え、素晴らしい眺めを楽しむことができます。長野県内でもこんな贅沢な景色を眺めることができるのは、ここ長門牧場だけでしょう。この素晴らしいロケーションは、映像関係者にも注目されており、NHK大河ドラマ「義経」のオープニングシーンも、ここで撮影されたそうです。また、牧草地には石がほとんどないのでヨチヨチ歩きの赤ちゃんや子供たちが元気に走り回っても安心です。マナーをしっかり守れば牧草地内で愛犬と一緒に遊ぶこともOKなので、首都圏からも多くの愛犬家たちがペットと共に訪れています。長門牧場では、牧場ならではの楽しい体験ができます。どなたでも気軽にできるバター作りやアイスクリーム作りは、家族連れに人気です。4名から体験できる手作りバターは、絞りたての牛乳50ccと小さじ3杯の生クリームが入ったフラスコを上下に振り続けること約15分、小さな球状のバターが出来上がります。その場で自家製パンにつけて試食できるのも嬉しいですね。手作りアイスクリームは、2名以上25名程度までの人数で行なわれ、グループ単位での体験となります。どちらも前日までに予約が必要です。また予約をしなくても、オリジナル乳製品の製造過程を見学できるプラントもあります。レストハウスから、丘を下って約10分ほど歩くと乗馬体験のスペースがあります。スタッフの丁寧な指導と賢い馬のおかげで、初めての人も、安全に楽しく、草原や林道の中を乗馬することができます。4,5歳位のお子さんから楽しめるひき馬体験もあります。レストハウス内のレストラン『コリーヌ』では、自家製の新鮮な乳製品をふんだんに使った牧歌的家庭料理がいただけます。 店内は、とても明るく開放的な雰囲気、大きな窓からは、北アルプスが見えます。夏になると、テラス席やレストラン前広場に設置されるテーブルでも食事を楽しめます。レストハウスのショップは、自家製乳製品はもちろん、蓼科山麓の地下水で作る自家製天然酵母のパンなど、安全で新鮮なもの、ここでしか手に入らない個性的なものにこだわった品揃えです。レストハウスでは、長門牧場一番人気のソフトクリームを味わうこともお忘れなく。真夏になると1日3,000個は売れてしまうというウワサの一品は、その日の朝に絞った新鮮なミルクで作られているので、濃厚な味わいながらしつこさをまったく感じさせない美味しさが人気の秘密のようです。入場料、駐車料が無料の長門牧場は、あまりお金をかけずに一日中楽しめる魅力的な場所です。皆さんもぜひ、眼前に妨げるものが何もないという贅沢、ここにしかない美味しさを味わう贅沢を体感しに、長門牧場を訪れてみてはいかがでしょうか?※北信五岳・・・・・・長野と新潟の県境にある斑尾山、妙高山、黒姫山、戸隠山、飯綱山を、総称して、北信五岳(ほくしんごがく)と言います。
2008年10月01日
コメント(2)
-
手紙
先日 NHK特集で、初めてアンジェラアキの「手紙」を知った。「手紙」は、今年の中学生合唱コンクルールの課題曲だという。その番組では、作詞作曲を手がけたアンジェラアキの想いと、全国各地のいろんな中学生たちが、どんな想いでこの曲を歌っているかを丁寧に追っていた。この曲は、アンジェラアキが、実際に15の時未来の自分にあてた手紙を、見つけたことから書かれたのだという。この曲を聴いていたら、すでに、もうずいぶん遠くなってしまったはずの自分の中学時代を思い出した。ワタシの中で、まだ密かに?生き残っているあの頃の声にならない自分の言葉がリアルに浮かび上がり気がつけば、番組の中で涙ぐむ中学生のように、泣いていた。でも、当然だが、中学生の彼等と私が大きく違うのは、先のことが見えない不安やあせりは、何も、中学生の専売特許ではないことを、知っていること。どんなに大人になったって、歳を重ねても、人生に「不安」がなくなることはない。そんなことは、ありえないことも。だけど、それでも大丈夫だよって、言えること。あの時代の息苦しさも痛みも、人との出会いも、その後の出来事もすべて、今の自分につながっていると、私もいえるから。番組の中の中学生達が、とても愛おしく感じられた。この時代に生きているすべての「中学生」に、私もエールを送りたくなった。そして、自分にも。未来は「今」の延長線上にある。だからこそ、今の自分を信じて、未来の自分へ、わたしも手紙を書いてみようと思う。
2008年09月30日
コメント(0)
-
バランス感覚
明日27日は、ムスメの運動会だというのに、夕方16時~18時過ぎまで、取材でした。初めてのお取引先と昨晩8時半過ぎに電話でご挨拶。そこで場所を説明され、現地集合です。取材のお相手は、地元ではかなり大手の某メーカーの開発部長さん。あらかじめ決められた質問があり、それに沿っての取材だったのでさすが、開発部長さま、お答えを万全に準備されていました。こちらは、ICレコーダーに録音はしてありますがペンを走らせながら、一方的に伺うばかり。メーカーさんの事業内容をご説明いただいたのだが理系さっぱりわからんちんの私にも、なんとなく・・・は、伝わってきた。難しいことを、専門用語を使わずに、説明できる・・それって、スゴイコトです。噛み砕き方が、スバラシイ・・・・いろんなお話を聴いているううちに長年、この大きな組織の中で、エンジニアとして、管理職としていろんな経験をされてきた方の「バランス力」が、伝わってきた。わたしの場合、今は・・・たぶん、これからも、よっぽどのことがない限りどこかの組織に就職をすることはないかもしれない。(望んでも厳しいだろうが)そのせいか、今日の仕事に限らず、仕事を通して知る「組織人」の良い面が、自分には痛くて、眩しいときがある。だけど、同じようなことは絶対できないが、かなりアンバランスなわたしなりの「バランス感」を養っていくことはできるはず。そう思いたい、取材だった。取材は、たいていの場合、どんな取材も楽しい。人の話をしっかり聴くことができるから。でも、大変なのは、これから・・。開発部長さんのいっぱいの想いが詰まったお話のエッセンスを、かなり少ない文字量に、どうつめていくことができるか・・それが、ワタシの仕事。今、29日納期の仕事が二つ。この仕事は1日まで。その後、3日納期のもある。どうする~オレ~(オダジョー風)明日、運動会、どころじゃないんだけどな~でも、延期されても、困るしな~。
2008年09月26日
コメント(2)
-
久しぶりのワクワクを逃すな
仕事をしていて「楽しい」と感じていますか? 今、仕事を持っていない方も、どんな時、ワクワクしますか? 私の場合、遊ぶ計画を立てるときは、「楽しむ」ために、ワクワクしながら すぐにあちこちへの段取りをします。 ここずっと、仕事をしていても ワクワクしながら取り組めるようなものとは、縁遠かった。 フリーというと聞こえはいいが、所詮、下請けだし 母業を優先しなければいけないことが多い今の状況では 「分業」的な仕事は、仕方ないし、むしろ、ありがたいこと と、割り切ってもいました。 だから、仕事となると「重い腰」をやっとあげて、 「納期」と「質」のバランスに注意を払ってばかり。 それが、昨日の打ち合わせでは、違ったのだ。 ある食品メーカーの販売促進用グッズを、リニューアルする仕事。 一つは、今ある写真を使ったリニューアルで、先方支給の文章をリライトするもの。 そこにもうひとつ まったくゼロからの提案もしようと、いう話になった。 (ていうか、自分がそうしようと、営業担当に働きかけたんだけど) まだ、正式に発注されたわけでなく、 プレゼンした結果で、どうなるかわからない仕事・・だから、ギャラもでるかでないか、わからない仕事である。 だけど、今、私は、久しぶりに「仕事」で、ワクワクしている。 お米を研ぎながらも、 洗い物をしながらでも、 即・使えるかどうかは別として どんどん、アイディアが沸いてくる。 明日は、違う縁からいただいた、新しい仕事だ。 それに関しては、めんどくさそう・・という印象だったけど、 このワクワクのおかげで、 そっちも楽しんで、がんばろうという 意欲に変わってきた。 この、ワクワクの感覚を大事に逃さずに「きっちり仕事」をして、先を見ていこう。 そうだこれまで関わった「works]も、このノートに載せていこう!
2008年09月25日
コメント(2)
-
はじめまして
はじめまして!オビオビオです。この数年間、ほぼ毎日パソコンに座りながら、ヒトサマのブログを拝見しながら納期に追われていることを言い訳に、日常プラス@の新しいことを始めることができませんでした。一方で、自分が直感的に「面白そう」と判断したときの私は、即断即決で動きます。話題の ひろっしゅコーチって何者?どうして、ボランティアで「ママイキ」を主催するの?という好奇心から「ママイキ@長野」の主催メンバーになり、気がつけば「ハピチア」にたどり着きました。そして本日、ハピチア16期最後尾ながら、ブログデビューです。 ひろっしゅコーチと出会わなければ、いつまでたっても、何も始まらなかったかもしれない。そう思うと、改めてひろっしゅコーチに感謝です。そんな、話題のひろっしゅコーチの講演会が、11月にあります。ひろっしゅコーチは、ただのコーチングのコーチではありません。類稀なるエンターテナーにして、迷える母達のチアリーダーなのです。聴けば、必ず、笑えて、泣けて、自分が好きになり、そしてなんだか、ムズムズ 動き出したくなるはず。私も、ゆっくりとカメのペースでですが、ようやく動き出しました。きっとあなたも。
2008年09月23日
コメント(2)
全39件 (39件中 1-39件目)
1