2007年11月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-

ブログ開設3周年です/11月28日(水)
ブログをしばらく小休止しているので、少々お恥ずかしいのですが、きょう28日でうらんかんろのブログ「酒とピアノとエトセトラ」はめでたく(?)開設3周年を迎えることができました。 きょうまで書き綴ってきた日記は410件。アクセス数も14万5千を超えて、もうすぐ15万の大台も現実のものとなってきました(もっとも、アクセス数を増やすことが目標でもないので、アクセスの多い少ないはほとんど気にしないのですが…)。 とにもかくにも、生来ずぼらな僕がここまで続けて来られたのは、ブログを訪れてくださり、感想や温かい励ましなどのコメントをしてくださる皆様方のおかげだだと思っています。改めて厚く、厚く御礼申し上げます。 最近は、ネタ枯れに加えて、プライベートな事情で多忙を極めていたこともあって、日記をずっとさぼって参りました(更新しなければというプレッシャーがないことがこんなに楽だとは…(笑))。 酒やBARや音楽などのネタの仕込みが一段落いたしましたら、再びぼちぼちと日記を記していきたいと思っております。今後とも、末永くどうか宜しくお願いいたしまーす。 末筆ながら、日ごと寒さも募るこの頃です。皆様、風邪などひかれぬようにお身体を大切にされ、元気でクリスマスと新年を迎えられるように、心よりお祈りいたします。
2007/11/28
コメント(21)
-

英国への旅(完)番外編/11月15日(木)
さーて、これでほんとにほんと、最後の「英国への旅日記」。番外編をお送りいたします。旅の中で気づいたこと、教訓、反省、こぼれ話などをあれこれと…。 ◆機内持ち込みのバッグは大きめで ご存じのように、あの「9.11同時テロ」以降、機内持ち込み物のルールは格段と厳しくなった。機内持ち込み用のバッグは1人1個に制限され、液体類の持ち込み量にも細かい規定が設けられている(1本は最大100cc以内。しかも20×20cmの透明な袋に入るだけしか入れられない)。 しかし機内持ち込みのバッグは、個数制限はあっても、大きさ(容量)の制限は緩やかだ。だから小さい機内持ち込み用バッグ1個だけだと、土産物などで荷物が増える帰国時などには困ることになる。 機内持ち込み用カバンは、可能な限り大きめのものを出発時にトランクに入れておき、帰国時には大いに活用しよう(なお、機内持ち込みカバンは1人1個までだが、セキュリティ・チェックを終えた後に免税店で購入した品だけは例外的に持ち込めます)。 ◆快適な機内、退屈せず 長距離便の機内は乗るたびに飛躍的に進歩している。エコノミー・クラスの座席の広さにさほど変化はないが、退屈を紛らわせるエンターテイメントの選択肢は格段に広がっている。前の座席の背に設置されているモニターテレビは、2年前のイタリアへの機内にも備わっていたように記憶しているが、映画はせいぜい7、8本くらいの中からでしか選べなかった。 それが今回のKLMのエアバスでは、なんと約100作品くらいの中から好きな映画が選べて、好きなだけ観ることができた。日本では劇場公開中の最新作も結構あった。ただし残念ながら、日本語吹き替えや日本語字幕がついているのはほとんどない。セリフが英語の映画でも字幕はオランダ語、ドイツ語、フランス語など欧州の言葉ばかり(アラビア語字幕付きも結構あったのに…)。 従って、ある程度ストーリーを知っている映画(「ビバリーヒルズ・コップ」「ダイハード4」「めぐり逢えたら」などや、言葉が分からなくても分かる映画(「ミスター・ビーン」など)を中心に選んだが、10時間半のアムステルダムへの飛行中、(飛ばし飛ばし観たのも含めて)6本も観ることができ、まったく退屈しなかった。 ◆携帯電話の進歩に驚く 一昨年のイタリアへは携帯は持っていっても電源は入れなかった(海外対応の機種じゃなかったことが最大の理由)。しかし、今回は海外対応の携帯を持参し、あらかじめ現地では携帯電話会社を自動的に選択するような設定にしておいた。その結果、日本国内で使うと同様、普通に使えた。メールも難なく日本へ送れた。 海外でも公衆電話の数は減っている。だからレストランを電話で予約せざるを得ないような場合、やはり携帯があると便利だ(とは言っても、昼間、店の近くに行ったついでに夜の予約を入れたというケースや、予約なしでというケースが多かったので、携帯を使った回数は少なかったが…)。 こちらから電話をかけるのは少なかったが、日本からかかってきたことが一度だけあった。ロンドンからストラットフォード・アポン・エイボンへ向かう朝の車内で、会社の部下から電話を受けた。 音質は驚くほどよく、まるで日本国内でしゃべっているのと変わらない。かけた方の部下も声が明瞭なのにびっくりしていた。通信機器の進歩はほんとに驚くばかりだ。今後どこまで進歩するのか、技術革新はどういう方向へ向かうのか興味は尽きない。 ◆海外旅行の“ゼヒもの”は 海外旅行に必ず持っていって方がよい“ぜひもの”は、人によっていろいろあるだろう。機内マクラ、室内用の携帯スリッパ、日本茶のティーバック、常備薬、カメラの予備電池、辞書や地図等々。しかし、僕がまず一番に挙げたいのは、やはり電圧変換用コンセント。 デジカメも携帯電話も、今では充電式電池であることが常識。そのバッテリー残量が少なくなってきた場合、ホテルの部屋のコンセントから充電するしかないが、当然、日本のコンセントは国外ではほとんど使えない。英国内も然り。だから、英国内での変換用コンセントを日本で1個買って持って行った。 ところが、情けないことに、エジンバラからアイラ島への1泊旅行に行く際、小型ドライヤーの袋に一緒に入れて、トランクにしまったままにしていたことを忘れたまま、出発してしまった(アイラ島へはショルダー・バッグ1個の軽装で行った)。 グラスゴー空港内の旅行用品ショップならひょっとしてあるかもと思い、探すと確かに売っていた。早速1個を購入したが、差し込み口の周りに、ご丁寧にも、固定式保護カバーが付いている。 この形状がゆえ、携帯電話やデジカメの折りたたむタイプのコンセントは、このカバーが邪魔になって入らない。日本で買った変換コンセントの形はまったく問題なかったが、後の祭り。英国人はほんとに「余計なもの(保護カバー)」を付けてくれる。 幸い結果的に、アイラ島にいる間にバッテリーがダウンすることはなかったが、常に不安を感じながらの2日間だった。教訓としては、「変換用コンセントは複数個を買い、1泊旅行用のバッグにもあらかじめ入れておくこと」か。 ◆両替はやはり信頼できる所で 海外旅行では現地で両替をする機会が多いと思うが、現地のガイドさんらにレートの良い、良心的な両替所を教えてもらうのが一番。くれぐれもホテルのフロントで両替するのは、レートが悪いし、法外な手数料を取られたりするので避けた方がいい。 エジンバラのホテルで日本円の4万円を両替した時と、ロンドン・ピカデリーサーカスのアメリカン・エキスプレスで同じ4万円を両替した時を比べたら、ポンド換算で1万円近くも差が出た。現地通貨への両替は街の、信頼できる場所でしよう。 ちなみに、英ポンド紙幣にはイングランド銀行発行のものと、スコットランド銀行発行のものとがある。前者はスコットランドでも使えるが、後者はイングランドではまず使えない(イングランドとスコットランドの仲の悪さは今もこういう所に残る)。スコットランド→イングランドと移動する場合は、スコットランド出発時の空港でイングランド紙幣に両替しておくことが大切だ。 ◆チップは柔軟に考えよう 欧米への旅で迷うのがチップの金額。レストランやタクシーでの相場は料金の10~15%くらいだが、ホテルのメイドさんへあげるピロウ・チップはどうか。ガイドブックには英国の場合、1人50ペンス~1ポンドと書いてあった。 4泊したエジンバラのホテルでは僕らは毎朝、二人それぞれの枕の下に1ポンド(計2ポンド=約500円)を置いたのだが、最終日には、なぜか逆に1ポンド硬貨2枚が返してあった。想像するに、毎日多くもらいすぎたと思ったメイドが返してくれたのかもしれない。 こんな異例とも言える良心的なメイドと出会えて、エジンバラの印象はさらには素晴らしいものになった。ガイドブックにあるピロウ・チップの相場はあくまで目安ということで、サービスの程度に応じて、柔軟に対応していけばいいのだろうと思う。 ◆シャッターチャンスに2度目はない 当たり前の話だが、海外旅行のシャッターチャンスに2度目はない。撮れるその時には無理してでも撮っておかなければ、後で後悔することになる。とくに風景ではなく、人と一緒に撮る場合、2度目はまずないと思わなければならない。 今回の旅でも、訪れた場所や店や食べた料理で、写真をいくつか撮り忘れたものがあり、この「2度目はない」という教訓を痛感した。何よりも残念だったのは、エジンバラのレストラン「マッスル&ステーキ」のオーナー夫人・ユイさんとの2ショットを撮りそこねたこと。これは今なお非常に後悔している。 店が忙しくなり、超満員になって気を遣って、撮るタイミングを逸したこともあった。店が混み始める前に先に撮ればよかった。「撮れる時に先に撮れ。どうしても撮りたい時は無理してでも撮れ」。今後はそうしようと心に誓った。 ◆早朝出発は前夜のうちに食料調達を 今回の英国旅行では早朝に出発することが多かった。ホテルの朝食時間帯に食べられない時は、前日のうちに「持ち歩き用の朝食(袋などに入れたもの)」をホテルに頼んだが、指定の時間通りに用意されていないことが多かった。 中身も例えば、「何も入っていないクロワッサンに生リンゴ、瓶入りのリンゴジュース」を紙袋に放り込んだだけというひどい内容(そんな朝食なら、10分もあれば準備できるだろう。「サンドイッチをつくるという約束」はどうなった!と怒る気も萎える)。 時間や約束にルーズなのは欧米人の習性なのか(日本の一流ホテルではこういうルーズさはまずないだろう)。早朝に出発する際は、前夜のうちにスーパーなどで食料や飲み物を調達して用意しておくこと。「ホテルを信用せず、自力で備えること」。これも貴重な教訓となった。※以上で、今回の「英国の旅日記」はおしまい。1ヶ月以上の長い間、ご愛読ほんとうに有難うございました!こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2007/11/15
コメント(4)
-

夢にまで見た生キャロル!/11月10日(土)
大人になってから、僕が独学でピアノを始めるようになったきっかけは、ジャンルは違うが、5人のアーチストによる影響が大きい。 ビル・エバンス、エルトン・ジョン、ビリー・ジョエル、ポール・マッカートニー、そしてキャロル・キングの5人である。エバンスは僕がピアノに興味を持ち本格的に練習し始めた頃にはもう亡くなっていたので、悔しいけれど生の演奏は聴いたことはない。 エルトン、ビリー、ポールの3人はライブに行ったので生の演奏に接することができた。長年あこがれ続けながら、いまだ一度も生の歌声、ピアノに触れたことがないのがキャロル・キングだった(写真左=真ん中がキャロル・キング) シンガー・ソングライターとして60年代から活躍を続けるキャロルは、90年に来日公演をしたのを最後に日本には来ていない。ことし65歳。もう日本には来ないのかもしれないなぁと半ばあきらめていた僕だった。 そのキャロルが嬉しいことに日本にやってきた! 残念ながら単独公演という形ではなかったが、ヒップホップ・ソウルのメアリー・J・ブライジ、ヒップホップ&ラップのファーギーという若手ともに、「3 Great American Voices」と銘打ったコンサートで来日した(なぜこの3人の組み合わせなのかという疑問も残るが…)。 僕は日本ツアー初日の11月5日(月)に行ってきた。場所は大阪城ホール。残念ながら客席は7割程度の入りだったが、僕にはそんなことはどうでもいい。30年近くあこがれ続け、切望し続けた生キャロルが見られる(聴ける)のだから。 どういう構成でやるのかなのか思っていたら、いきなり、キャロルが一人でステージに現れた。「コンバンワー、オオサカ!」と言って、いきなり1曲目を弾き始めた。曲はあの偉大なアルバム「タペストリー(つづれおり)」(写真右下=全世界で6000万枚も売れ、今なお人気のロングセラー)から「Beautiful」。 そして、第一部はすべてキャロル・オンリー。演奏は途中からバックに、アコースティック・ギター2人が入るだけというシンプルなもの。でもバックがシンプルでも、キャロルの歌声の存在感があれば、そんなことは全然問題にならない。 キャロルは約1時間、11曲も歌った。僕はただただ彼女の歌声とピアノに聴き惚れた。この後出てきたファーギー、メアリー・J・ブライジを挟んで、最後のアンコールでは、キャロルが再び大きな拍手に迎えられて登場した。 キャロルら3人は、「Dancing In The Street」(ミック・ジャガーとデヴィッド・ボーイのデュエットで知られる)、「Natural Woman」(これもタペストリー収録の彼女の代表曲)の2曲を歌った(ただし、日本ツアー初日とあって、3人の歌はバラバラ。いかにもリハーサル不足という印象だった)。 ファーギーもメアリー・J・ブライジも歌は文句なしに上手い。しかし、存在感という点では、やはり50年近い芸歴を持つキャロルには勝てない。何度聴いても「タペストリー」というアルバムは偉大だと思う。もし無人島へ3枚だけアルバムを持っていってよいと言われたら、僕は間違いなく「タペストリー」をその1枚に選ぶ。 キャロルは、僕がまだ観ていないビッグ・ネームの最後の一人だった。コンサートを観終えて、僕は満足感と虚脱感が入り交じった複雑な気持ちに襲われた。生キャロルを観た幸せは、とても言葉ではうまく言い表せない。キャロル、本当に有難う。僕はあなたが大好きです。You make me feel like a natural man!【11.5.のセットリスト】=キャロル分のみ →Beautiful、Welcom to my living room、Where you lead、So far away、Up on the roof、Smackwater Jack、Will you love me tomorrow? Love makes the world、Sweet seasons、You've got a friend、I feel the earth move、アンコール=Dancing in the street、A natural woman【追記】まだ生キャロルを聴いていない方で、ぜひ観たいという方は「3 Great American Voices」の日本公演はまだ12日(月)、13日(火)=いずれも日本武道館=もあります。当日券もきっとあると思うので、万難を排して急いでください!こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2007/11/10
コメント(3)
-

英国への旅:ロンドン編(2)/11月7日(水)
ストラットフォード・エイボンへの半日旅行からロンドンへ帰ってきた僕ら。最後の一日はどこで過ごそうかと考えたが、結局、ピカデリー・サーカス付近に戻ってきた。 ソーホーにもオックフォード・ストリートにも近いし、なによりも街に活気がある。買い物にも食事にも好都合なロケーションだ。パブも多いので歩き疲れて喉が乾いたら、ビールを一杯やれる(写真右=ソーホー界隈)。 天気は少し雨模様。今回の旅では、ずっと不安定な天気だったような気がするが、かと言って、大荒れという日もなかったので、まずはめでたしかもしれない。 昨日に続き百貨店を覗いたほか、土産物屋や酒屋さん(写真右下=「ミルロイ」という名前でした)にもお邪魔した。ただし、酒屋には、「ほしいウイスキーは数あれどお値段が…」状態。 はっきり言って、英国でのウイスキーの値段はそう安くはない。ポンドのレートを考えたら、日本の方が安いかも(写真左=ソーホーのパブ。店先でのビールのラッパ飲みも楽しい)。 ウイスキーボトルは持ち歩くには重いし、街場の酒屋で買うのは断念し、唯一、珍しいウェールズ産のモルト・ウイスキーのミニチュア瓶やスコットランドのモルト蒸留所マップなどを記念に買った。 さて、最後の夜の晩飯は、前回のロンドン編でも触れたが、インド料理。ガイドブック等を参考にして、ソーホー界隈に数多くあるインド料理店のなかから「デリー・ブラッセリー」(写真左下)という店を選んだ。 店は、ソーホー地区のほぼど真ん中。「ロンドンっ子にも人気の店」というから、味の方はまず大丈夫だろう。1階フロアもあったが、僕らは地下のフロアに案内された。 とりあえずビールで乾杯。もちろん、せっかくだからインドの地ビール「キング・フィッシャー」(写真右下)を選ぶ。軽くてフルーティ。味わいもまずまず(でも、やはり日本のビールが世界で一番クオリティが高いと思うのだが…ね)。 料理は、前菜(写真左下=固くて薄いナンに4種類の具を乗せて食べる)のほか、小エビのカレー、オリジナルな味付けのタンドリー・チキン、これにサフラン・ライスが2人前付く。ボリュームは十分だ。 地下のフロアにはテーブルが4つほど。しかし1時間経っても、僕ら以外には客はなく、ヒマそうにした男性従業員が「日本から来たのか? 日本人はよくうちの店に来てくれるよ」などと話しかけてくる。 連れ合いが「ナマステ(こんにちは)」とヒンディー語で話しかけると、「僕はインド人じゃなく、バングラデシュ人なんだ。だからナマステじゃないよ」と応じられる。 バングラデシュでの公用語はベンガル語だ。インド料理店だから従業員が必ずインド系とは限らない。ステレオタイプの思考は要注意だ。 ちなみに彼によれば、ベンガル語の「こんにちは」は「ノモシュカール」または「アッサラーム・アライコム」。ついでに教えてもらった「ありがとう」は「ドンノバード」という。 帰り際、僕は彼に「ドンノバード」と言い、ドアを開けてくれた別の男性従業員にも(彼とベンガル語で話していたようなので)同じ言葉を口にした。すると満面の笑みで、彼も「ドンノバード」と応えてくれた。 何度も同じことを書くけれど、現地の人たちとの生のふれ合いこそ、旅の最大の喜び。今回スコットランドやロンドンでふれ合った素晴らしい人たち。その人たちのホスピタリティは旅先の風景とともに、終生忘れることはないだろう。 かくして7泊9日の英国の旅は終わった。日本の現実に再び引き戻された僕。まるで夢のような旅の記憶が、1カ月以上経っても、なお夢に出る。興奮はまだ続いているが、次回の訪問はいつ実現するかは分からない。 しかし必ずもう一度、僕はスコットランドの地を踏みたい。いやきっと踏むつもりだ(もちろんアイラ島も!)。その日まで、美味しいスコッチ・モルトを愛し続け、素晴らしきスコットランドの人たちにささやかな経済的貢献をしていきたい。 ◆英国の旅(完):番外編へ続く。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2007/11/07
コメント(4)
-
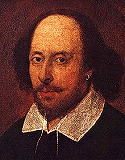
英国への旅:ストラットフォード・アポン・エイボン編/11月3日(土)
イギリスの有名な作家と言えば、皆さんは誰を思い浮かべるだろうか。ウィリアム・シェイクスピア、エミリー&シャーロットのブロンテ姉妹、サマセット・モーム、チャールズ・ディケンズ、コナン・ドイル、アガサ・クリスティ、ジェイン・オースチン…。 僕にとっては、やはり最初に名を挙げたシェイクスピア(1564~1616)=写真左は肖像画=である。「ハムレット」「マクベス」「オセロ」「リア王」の四大悲劇で名高い劇作家にして、詩人。 死後約400年を経て今なお世界中で読まれ、愛され、その作品が上演され続ける。僕には中学生の時の英文購読で出合って以来、ずっと忘れられない偉大な存在だった。謎の多いその生涯も魅力的だった。 なんと言っても、16~17世紀という時代(日本ではまだ戦国時代末期~江戸時代初めだった)において、人生の真理の数々をあのような見事なドラマ(戯曲)に仕立てた才能は、源氏物語を書いた紫式部同様、文学史上の奇跡と言ってもいいかもしれない。 彼の生まれ故郷は、ロンドンから電車で2時間余かかる「ストラットフォード・アポン・エイボン」という長い名前の街である。その名も中学生の時に聞いて、忘れられないでいた。 そして、生家が今も残るというその街をいつか訪れるのがずっと夢だった(今でこそ2時間余だが、当時はロンドンまで何日かかったのだろうか)。 9月28日。そんな長年の夢を実現させる日がついにやって来た。スラットフォード・アポン・エイボン行きの電車は、ロンドン市内のメリルボン駅(写真右上)という駅から出ている。朝イチの電車に乗るために、僕らは朝食後すぐホテルからタクシーに乗った。 電車は7時20分発。僕らは10分前に着いた。しかし駅の行き先表示に「ストラット…」は見あたらない。おかしい。出発前にこの鉄道会社のHPでチェックした時は確かにあったはずなのに…。 駅員に聞いても、乗り込む乗客に聞いても、「この(7時20分発の)電車はストラット…へは行かない」という答え。う~ん困った(写真左上=こちらは僕らが乗った方の電車の表示)。 乗るか次の電車にするか…。迷った末に乗車は断念し、次の8時54分発まで、仕方なく駅構内や駅周辺で時間をつぶすことにした。 後で調べたら、「7時20分発」は途中の駅で別の電車に乗り継ぐ形で「ストラット…」まで行くのだった。ならば駅員はそう教えてくれるべきだった。不親切な駅員に腹が立つ。 しかし、こういうハプニングもまた楽し。プラス志向で考えて、構内のお店をあちこち覗いたりして時間を有効に使う。メリルボン駅はロンドン市内の駅では一番古く、130年以上昔の建物を今も使っている。 歳月を経ても赤レンガの駅舎はとても美しい。アガサ・クリスティやチャーチルもこのホームに降り立ったんだろうなぁと思うと感慨深い(ただしシェイクスピアが生きていた頃は、当然まだ鉄道はなかった。彼は馬車でロンドンまでやって来たのだろうか)。 遅れること約1時間半、8時54分発の急行に乗った僕らは、一路ストラットフォード・アポン・エイボンへ向かう。乗客は半分くらい。僕ら同様、シェイクスピアの故郷を訪ねる観光客らしき人たちが目立つ。 列車が動き出してまもなく、あの有名な「ウェンブリー・スタジアム」も見えたが、20分も走ると、途中の車窓は駅周辺の小さな街並み以外、のどかな田園風景がほとんど。ロンドンのすぐ近郊とはとても思えない。 午前11時すぎ、ほぼ定刻通り無事にストラットフォード・アポン・エイボンに到着。 超有名な街にしては駅舎(写真右上)は小さく、平屋で改札口も1カ所だけ。日本の田舎町によくあるような駅に近い。 切符は往復で買っているから、早速僕らは生家のある街の中心部の方へ歩き出す。観光客は皆同じ方向へ向かうので道に迷う心配はない。 駅から街の中心までは約15分ほど。途中、通り沿いには観光客目当ての土産物屋や飲食店などが数多くある(写真左上)。 建物は街の景観を壊さないように、できるだけ昔の雰囲気を残している(おそらく法律的な規制もあるのだろう)。通りには、世界中からやって来たシェイクスピア・ファンらがあふれて、さながら夏場の軽井沢のような雰囲気。 目指す生家は50年ほど前までは荒れ果てていたのを地元の人たちが修復し、さらに内部はシェイクスピアが生きていた頃の内装に復元されている(図面が残っていたため、可能だったとか)。 室内は現代の感覚では質素な造りだが、シェイクスピアは裕福な農家の生まれだったといい、そのせいか広くて部屋数も多い。 街には、ほかに娘夫婦の住んだ家(写真左)や孫娘夫婦の住んだ家というのも保存・公開されている。 生家と合わせて3カ所を見学できる割安(11ポンド)の共通チケットも販売されていたので、僕らはこの共通チケットで見て回ることに。 生家周辺にはソーセージやチーズ、ドライフルーツ、野菜、お菓子などを売る露店もたくさん出て、まるでお祭りのように賑やか(写真右=燻製したものなど様々なニンニクを売る店も)。時間があれば1軒、1軒ひやかして回りたいところだが、時間がないのであきらめる。 それにしても生家周辺まで来ると、周りの古い建物はとてもよく管理が行き届いている。軒先をフラワー・バスケットを飾っている家も数多くあって、歩いているだけでも気持ちがいい。 住民たちが、祖先の大切な遺産であるこの街を愛して、いかに大切にしているかが伝わってくる(写真左=美しく手入れされたシェイクスピアの娘夫婦の家の庭)。 再開発や老朽化を理由に、歴史的建造物をすぐに取り壊してしまう日本の馬鹿な建築家や役人たちは、こうした人たちに学ぶがいい。 さて、生家など3カ所の見学を終えた僕らは、ロンドンに引き返す前に、昼ご飯。「ストラット…」で一番古いパブとして、ガイドブックにも出ていた「ギャリック・イン」(写真右)という店に入る。 お昼時の店はほぼ満員。ここはずうずうしくも空いているテーブルに座り、時間もないので、適当にエール・ビールとサンドイッチを頼む。 1594年に建てられたパブは、昔の酒場の雰囲気をとてもよく伝えていて、タイムスリップしたような気分(シェイクスピアもひょっとしてここでビールを飲んだのかな?)。 しかし、店内は込んでいるのに従業員の数も少ない。料理が出てくるまで30分近く待たされる(そのとばっちりで、帰りの電車へは駅まで走って、滑り込み)。 ストラットフォード・アポン・エイボンにはわすが3時間余という短い滞在だったが、憧れのシェイクスピアの故郷を訪れ、彼の素晴らしい戯曲を生む舞台となった街とその空気に触れることができた。僕らは心から満足感を味わい、ロンドンへの帰途へついた。 ◆英国への旅:「ロンドン編(2)」へ続く。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2007/11/03
コメント(2)
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
-

- 缶チューハイ大好き!
- KIRIN 氷結® mottainai …
- (2025-11-21 19:56:45)
-
-
-

- モルトウイスキーの話題
- 限定企画A113回 12650円で当たる 山…
- (2025-11-27 19:50:04)
-
-
-

- BAR大好き!!
- ボジョレー ヌーボー
- (2025-11-20 17:44:27)
-







