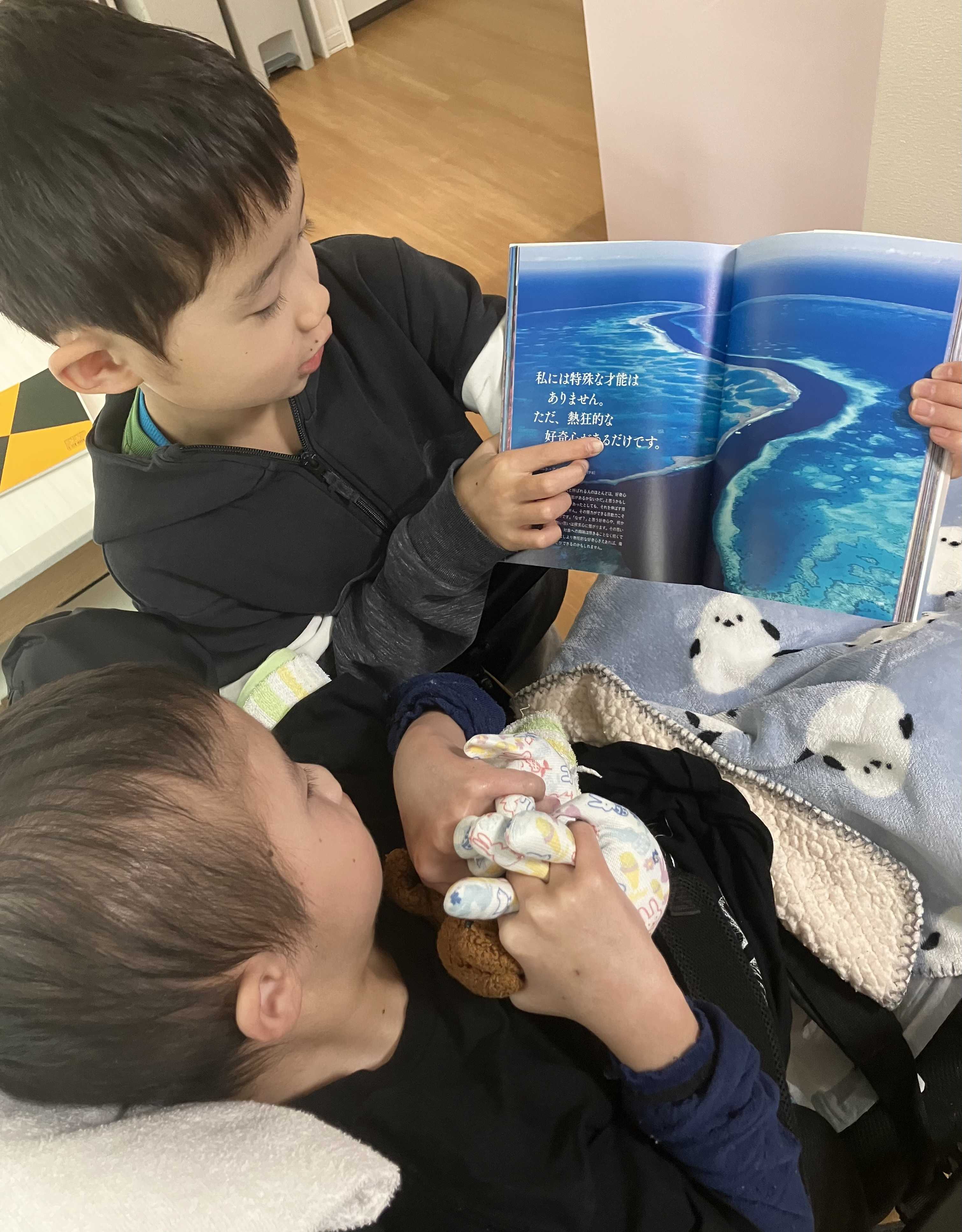2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007年12月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
メールチェックは不眠のもと=エスプレッソ2杯の効果!!
みなさん、こんにちは。年末は帰省のためうちのラブちゃんを訓練所に預けました。いつまでも車の方を見ている姿を見ると涙がでました・・・・ (転載開始)メールチェックは不眠のもと=エスプレッソ2杯の効果ベッドに入る1時間前に電子メールをチェックすると不眠の原因に-。28日付英紙デーリー・テレグラフは、英専門家のこうした研究結果を報じた。 英エディンバラ睡眠センターのクリス・イジコフスキ博士によると、就寝前に電子メールの有無を確認すると、脳が行う眠るための準備作業を中断させるという。電子機器からの光が脳への信号となり、自然な眠りを誘うホルモン「メラトニン」の分泌を妨げるためだ。 また、睡眠を妨げる最大の要因の一つは仕事のストレスで、ベッドに入る前に仕事の電子メールを見ることは、エスプレッソコーヒー2杯分と同じ不眠効果があるという(時事通信)。(転載終了) やはり、就寝前のテレビやインターネットは問題だったのですね。そうはいっても仕事が・・・・・電磁波の影響だけではなく、光そのものが脳の松果体や体内時計の視床下部に作用するのですね。就寝前は読書に切り替えましょう。
December 30, 2007
コメント(1)
-

医療崩壊と司法の論理!!
みなさん、こんにちは。今年ももうあと少しになりましたが、実感としては何も変わりませんね。 年のせいでしょうか?子供のときは嬉しかったですが・・・・・・ (転載開始) 虎の門病院・小松秀樹氏 「保険医療と賠償金」本気で議論を シンポジウム「医療崩壊と司法の論理」 虎の門病院泌尿器科部長の小松秀樹氏は23日に早稲田大で開かれたシンポジウム「医療崩壊と司法の論理」の中で、「多額の賠償金が、保険医療の中で支払われていることについて、本気で議論すべき」と被害者救済の在り方に問題を提起した。シンポジウムは、早稲田大紛争交渉研究所と大阪大コミュニケーションデザイン・センターが主催する「対話が拓く医療IV」として開催された。 シンポジウムでは、医療側と司法側のそれぞれからシンポジストが登壇し、「法律や判例がそうなっているから」という法律家の常識と、刻々と変化する患者の容態に対応する医療者の思考との間に大きな隔たりがあることが示された。 小松氏は、法律家と医療者の論理体系のギャップについての議論の中で「日本の法律家の思考は狭すぎる。法律家が経済をはじめ法律以外のことには疎いために、実情に合わせて法律が変わっていかない」と指摘した。 また、ヒューマンエラーは処罰すべきではないとした上で、厚生労働省がまとめた死因究明制度(第2次試案)の通りに院内の事故調査委員会の報告が司法に活用されるようになると、善意の報告が証言となって処罰されることになりかねず、さらなる対立やあつれきを生むと指摘した。 医師・患者間の対立は、医学へも影響を及ぼしている。小松氏は「医学に対する弊害はすでに出ている。学会で合併症・副作用報告を行った発表者が訴えられるケースも出てきており、現実に合併症・副作用に関する学会報告が少なくなっている」と述べた。 シンポジウムでは説明義務違反によって大学病院が敗訴し、6000万円の賠償金を支払った医療事故判例が紹介された。これについて小松氏は、「多額の賠償金を家族に支払うことが、本当に被害者救済になっているのかは疑問だ」とし、被害者に扶養家族がある場合には賠償が必要だが、現在の賠償方法は医療の継続にとって弊害になるとの懸念を示した。 さらに「これまで議論されてこなかったが、こうした賠償金の支払いが保険医療のなかで行われていることについて、本気で議論すべきだ」と問題を提起した(Japan Medicine)。(転載終了)医療はサービスとリスクが一体となった特殊なビジネスといえると思います。医師の故意の事故であれば、糾弾すべきでしょう。日本のオンボロ保険医療の問題は、医師を含めスタッフの慢性的なマンパワー不足、コメディカルの少なさ、医療施設の貧弱さなどヒューマンエラーではすまされない複合的な構造問題があります。ただ、一般の人には世界の医療事情を知っているわけではありませんので、このところが理解しにくい。おりしも不景気で格差が拡大している中で、病院や医師はターゲットにしやすいという要因もありますね。何の権力もありませんから。 厚生労働省をはじめ官僚が全ての権力を握る日本では、このまま医療崩壊していくしかないでしょう。私も日本の医療には見切りをつけていますが、自分が今できることを一生懸命やるしかないという境地です。来年はアメリカと日本は世界でも落ちぶれ国家として沈んでいくでしょう。来年の大不況を乗り越えたら、私たちはようやく戦後の区切りをつけられるチャンス(アメリカの支配からの脱却)を得るのではないでしょうか?
December 29, 2007
コメント(0)
-

アレルギーの「元」引き込む細胞内たんぱく質特定 !!
みなさん、こんにちは。久しぶりに8時間臥床できました。短時間睡眠が続いていましたので、夜中に何度も目が醒めましたが、朝まで横になりました。これで年末までまたバリバリ動けるでしょう・・・・・ (転載開始) アレルギーの「元」引き込む細胞内たんぱく質特定 生体がアレルギー反応を起こすのに不可欠な細胞内たんぱく質を理化学研究所の研究チームが特定した。新しい抗アレルギー薬の開発につながると期待され、米科学誌「ネイチャー・イミュノロジー」に掲載された。 アレルギーは、鼻や腸などの粘膜にある肥満細胞からヒスタミンなどの化学物質が放出されることで起こる。この放出にカルシウムが関与していることは分かっていたが、細胞の外から中へどのように流入するかは不明だった。 理研免疫・アレルギー科学総合研究センターの黒崎知博グループディレクター(分子免疫学)らは、細胞内でカルシウム濃度を感知する働きのある「STIM1」というたんぱく質に着目。STIM1を作る遺伝子を欠損させたマウスの肥満細胞では、外部からのカルシウム流入が抑制されることを発見した。さらに、典型的なアレルギー反応である血管の透過性上昇が、STIM1の量が半分程度のマウスでは抑えられることも確認。STIM1には細胞の外から中へカルシウムを流入させる働きがあり、アレルギー反応に不可欠な物質だと特定した。黒崎さんは「アレルギー以外の重要な役割に影響を与えずにSTIM1の働きを制御できれば、従来の抗アレルギー薬より有効な薬が開発できる可能性がある」と話している(毎日新聞社)(転載終了)この時期は、鼻閉が続き、鼻から息が吸えませんので不快です。3時間ごとに点鼻薬をスプレーしていますが、そのうち鼻粘膜が死んでしまうのではと危惧しています。STIM1は、アレルギーと直接は関係のないカルシウムの働きを調整しているものですから、アレルギー以外の働きに対する影響が危惧されますね。私たちは鼻が詰まっても、口で呼吸することができますが、他の動物は口で呼吸できません。動物は鼻が詰まることはないのでしょうか? ちなみにサルは花粉症がありますが・・・・・
December 27, 2007
コメント(0)
-
iPS細胞なお未知数 再生医療実現へ、世界が期待!!
みなさん、こんにちは。今日もかなり温かいですね。クリスマスがこんなに温かいのは、生まれて初めてです。数年これが続けば、温暖化も信じられるかもしれません・・・・・(転載開始) iPS細胞なお未知数 再生医療実現へ、世界が期待 ◇研究競争、米猛追 さまざまな細胞に育つ能力を持つ万能細胞「人工多能性幹細胞(iPS細胞)」。京都大と米ウィスコンシン大などのチームがそれぞれ、ヒトの皮膚細胞からの作成に成功したことを発表してから1カ月が過ぎた。再生医療の実現へ道を開く可能性があり、各国政府が注目、文部科学省も5年間で総額100億円を投入する総合戦略をまとめた。しかし多くの課題もあり、「胚(はい)性幹細胞(ES細胞)」や「体性幹細胞」の研究の進展を求める声も出ている。【須田桃子、永山悦子、西川拓】 「日本の独り勝ちは100%あり得ない。このままいったら日本は銅メダルがいいところ」。ヒトiPS細胞を作成した山中伸弥・京都大教授は、臨床応用の見通しを語る。 世界の競争は激しさを増す一方だ。京都大などが11月に作成に成功と発表した直後、別の米チームがiPS細胞で貧血症マウスの治療に成功と発表するなど、新たな成果が次々に発表されている。山中教授は「治療への応用は我々も計画していたが、他のチームがすごいスピードでやってしまった」と話す。 再生医療の柱は、ヒトの受精卵を壊して作るES細胞や卵子にヒトの体細胞の核を入れて作るクローン胚由来のES細胞とされてきた。だが、受精卵を壊す点やクローン人間誕生につながるクローン胚を作る倫理的問題が指摘されていた。iPS細胞は受精卵を使わず、クローン胚を作る必要もない。患者の細胞から作れ、拒絶反応の心配もない。このため各国はこぞって研究に力を入れ始めた。 22日には、08年度予算財務省原案の復活折衝で10億円増額が認められ、初年度に約22億円を確保。京都大の研究センターを中核に、全国の研究者で「iPS細胞研究コンソーシアム」を組織する。 だが、山中教授は「韓国、シンガポールなどは02年ごろから幹細胞研究に力を注ぎ、ヒトES細胞研究での実績もある。特に米国の追い上げがすごい」と危機感を募らせる。ある研究者は「日本は川の上流の泉を見付けたが、下流(臨床応用)へ行く船(技術や特許)は既に米国の手中にある」と指摘する。 ◇ESすら臨床計画段階 再生医療実現への期待は、98年に米国のチームがヒトES細胞の作成に成功した時にも高まった。しかし、ヒトES細胞による治療は依然として実現していない。目的の細胞に自在に分化させたり、治療に使える質や量の細胞を作り出す技術の開発に手間取ったためだ。米国でようやく、ヒトES細胞から作った細胞を脊髄(せきずい)損傷患者に移植する臨床研究の計画ができた段階にある。 iPS細胞もES細胞と同様、目的の細胞への分化や培養の技術が必要になる。岡野栄之・慶応大教授(再生医学)は「iPS細胞は分化能力やがん化の恐れなど、不確定な要素が多い。まずES細胞による臨床研究を前進させ、ノウハウを蓄積すべきだ」と指摘する。 iPS細胞は分化した細胞を元に戻して作るため、ES細胞以上に人工的な細胞となる。基礎生物学研究所の勝木元也名誉教授は「体細胞を人工的に若返らせ受精卵のような万能状態に戻しても、体細胞だった時の履歴が残っている可能性がある。治療に使った場合にどんな影響があるか不明だ」と警鐘を鳴らす。 過剰な期待の悪影響を懸念する声もある。韓国で05年に発覚したES細胞研究論文の捏造(ねつぞう)事件を例に、理化学研究所発生・再生科学総合研究センターの西川伸一ディレクターは「一つの技術を巡り、国内の利益だけを考えて騒いでいては、同じ過ちを繰り返す恐れがある。アジア各国との連携も視野に入れた研究振興策のような幅広い政策が求められる」と指摘する。 ◇実用化近づく体性幹細胞、今後10年の「主役」--研究者、低予算を懸念 現状は、iPS細胞やES細胞より、ヒトの体内にある体性幹細胞を使う方法の方が再生医療の実用化に近づいている。 名古屋大は今月6日、乳歯に含まれる体性幹細胞(歯髄幹細胞)を使い、歯の象牙質や骨、血管などの再生医療の実現を目指す「乳歯幹細胞研究バンク」の設立を発表した。上田実教授は「骨髄や乳歯の体性幹細胞は、人工的な操作を加えておらず、ES細胞やiPS細胞ほどの爆発的な分化・増殖能力がない分、逆に移植したときの安全性は高い。少なくとも今後10年間は体性幹細胞が再生医療の主役だろう」と話す。 産業技術総合研究所は骨髄にある間葉(かんよう)系幹細胞に注目する。筋肉や骨だけでなく、心筋や神経の細胞に分化する能力もあり、既に心臓病患者などへの臨床試験が進む。 しかし、体性幹細胞の臨床応用には、必要な量まで増殖させることが困難などの課題が残る。ある体性幹細胞研究者は「iPS細胞ばかりに予算や人員が集中し、体性幹細胞の研究が遅れるようなことがあれば、患者のためにならない」と懸念を示す。..................................................................................................................... (転載終了)次世代の西洋医学の治療の柱となりそうな再生医療。皮膚細胞から万能細胞を作る試みがヒートアップしています。おそらく中国か米国が臨床応用を始めるでしょう。日本は全て特許をアメリカにおさえられ、いつものごとくライセンス料をとられて、良質なものを作る技術屋のままでしょう。官僚さえいなければ、日本も立派な世界を牽引する国になるのでしょうが・・・・・
December 25, 2007
コメント(1)
-
日本の医療は遅れている!
みなさん、こんにちは。今日は東京でアメリカ医師国家試験の説明会に出席しました。やはり厚生労働省も日本の医療がアメリカの10年遅れていることを認めているようです。やがて日本の医療も野球と同じように空洞化していくのかも知れませんね。 (転載開始)APAが認知症治療の最新ガイドラインを発表 米国精神医学会(APA)は、アルツハイマー病などの認知症治療に役立つ診療ガイドラインの第2版を発表した。これは1997年に発行された第1版を更新したもの。臨床的根拠が強化され、有用なヒントを盛り込んだ内容となっている。 同ガイドラインは『American Journal of Psychiatry』12月号の補冊として発行される。 「強化された根拠は一読の価値あり」 「追認試験が数多くあったので、作成した勧告のほとんどを強化することができたと思う」とジョンズ・ホプキンス大学医学部(メリーランド州ボルチモア)のPeter V. Rabins, MDとガイドライン作成グループ代表はMedscape Psychiatryに話した。「実際のところ真新しい内容はない。根拠の強化が中心となった」。 「結局、内容は実際それほど新しくなっていない」とメイヨー・クリニック(ミネソタ州ロチェスター)のDavid Knopman, MDと米国神経医学会のあるメンバーはMedscape Psychiatryへのコメントで繰り返した。「あっと驚くような診療上の変更はなかったし、あるとも思っていなかった」。Knopman博士は、文書としてよく書けているとも言う。「診断と治療に関する多くの問題についてよく練られた文章で書かれているので、一読する価値は十分にある」。 最近の10年の発展 最初のガイドラインが発表されてから10年、新薬が使えるようになり、当時の勧告を裏付ける根拠がさらに強化された、とRabins博士は話した。 「良かった点としては、第一に新しいクラスの薬剤、memantine(商品名Namenda、Forest Pharmaceuticals社)のほかに、アルツハイマー病治療に用いる3つのコリンエステラーゼ阻害薬がFDAに承認された」と説明した。 また、第二に患者の情緒的健康を標的にした非薬物治療の有効性を示す良い根拠が出てきた。第三に、アルツハイマー病患者のうつ病治療で、薬物療法は明らかにプラセボより有効であることを示す強い根拠が出てきた。第四に、介護人に知識と心理的サポートを与えることが、介護人と患者にとってプラスになるという新たな根拠が得られた、という。 「あまり良くなかった点としては、アルツハイマー病治療でビタミンEの投与勧告を削除したことである。ビタミンEの効果を支持する新しい研究がなかったことと、高用量の場合健康上のリスクがあることが主な理由である」とRabins博士は続けた。 また、この2年では、定型および非定型にかかわらず抗精神病薬が認知症の人の死亡リスクを増加させることが明らかになった。 重要な変更点:抗精神病薬の制限 激越、妄想、幻覚、攻撃などの神経精神症状がある患者に関しては、非薬物療法をまず試してみるべきという強い根拠が出てきた。そして、家庭や長期療養施設などあらゆる環境で抗精神病薬の使用を制限する現実的努力をすべきである。「これは今回のガイドラインにおいて最も重要な診療上の変更点である」とRabins博士は付け加えた。 「抗精神病薬を処方する場合、確実に効果がある薬が必要に応じて処方されるように現実的努力をしていく必要があると思う。薬が無効だった場合は、中止すべき」とも話す。 治療計画の作成と実行 この55ページに及ぶガイドラインの要旨では、臨床的根拠に基づいて勧告に3段階評価が付けられている。このセクションは認知症状、精神病、激越、うつ病、睡眠障害の治療勧告をまとめ、心理療法、精神科治療、高齢患者の治療、長期ケア時の特殊な問題を考察している。 次のセクションは、個々の患者の段階的治療計画を作成し、実行するための案内である。最後のセクションでは、治療計画に影響する特殊な臨床的特徴について詳しく述べられている。 2003年1月から2006年12月まで、Rabins博士はAstraZeneca、Janssen、Eli Lilly and Company、 Forest Pharmaceuticals、Wyeth Pharmaceuticalsの各社から講演料を受け取った。その他のガイドライン作成グループメンバーの利害関係情報は、診療ガイドラインに記載されている。診療ガイドライン作成実行委員会が同ガイドラインを審査した結果、上記利害関係の影響は見当たらなかった(Medscape)。 (転載終了)やはり製薬会社からお金の出ているレヴューは、第一にその会社の薬を売り込みますね。この報告書で大切なのは、アルツハイマーの患者さんの介護者や家族へのサポートがアメリカではしっかりしていることですね。臨床心理士が重要な役割をしていますが、日本では心理学は医療よりも遅れています。病院には必ず必要な存在ですが、精神科以外はほとんど臨床心理士がいません。医療に対する考え方も相当遅れているのですね・・・・・
December 22, 2007
コメント(0)
-

緑茶が前立腺がん抑制か 5杯超で進行のリスク半減!!
みなさん、こんにちは。朝が冷え込んだ日は、お昼の天気がいいですね。これはどういった理由なのでしょうか?(転載開始)緑茶が前立腺がん抑制か 5杯超で進行のリスク半減 緑茶を1日平均5杯以上飲む男性は、1杯未満の人に比べ、進行性の前立腺がんになるリスクが約半分になるとの疫学調査結果を、厚生労働省研究班(主任研究者・津金昌一郎(つがね・しょういちろう)国立がんセンター予防研究部長)が19日発表した。1杯は約150ccという。 がんが前立腺内にとどまる「限局がん」については、緑茶飲用との関連はみられなかった。進行がんだけに影響した理由は不明だが、緑茶に含まれるカテキンという物質に、がんが広がるのに関係する物質を抑える効果があることも関係しているらしい。 調査は岩手、大阪など全国9府県の40-69歳の男性約5万人が対象。平均12年の追跡期間中に404人が前立腺がんになり、うち114人が前立腺を超えて広がる進行性がんだった。 進行性前立腺がんになるリスクは、緑茶を飲む量が多い人ほど小さいという結果で、1日平均1杯未満の人のリスクを1とすると、5杯以上の人は0.52だった。 研究班はこのほか、男女約13万人を対象に実施した、胆石と胆道がんに関する疫学調査結果も発表。それによると、胆石を患ったことがある人はない人と比べ、胆道がんになる危険度が2.5倍高く、特に女性では3.2倍になることが分かった(共同通信社)。(転載終了)やはり緑茶は、一度できたガンの進行を抑えるのに寄与しているのですね。ただ、疑問に思うのは、緑茶の質です。無農薬のものもあれば、有機栽培のものもあります。こういった緑茶の質の違いは考慮されているのでしょうか?医薬品と違うのは、質もバラツキですね。しかし、全体で結果は出ているので、カテキンの威力は証明されていますね。
December 20, 2007
コメント(0)
-
タミフルが直接、異常行動を起こしている可能性は低い??
みなさん、こんにちは。朝に霜が降りるようになりました。青空駐車の車は困る季節ですね・・・・ (転載開始) タミフルが直接、異常行動を起こしている可能性は低いリン酸オセルタミビル(商品名:タミフル)服用と異常行動発現との因果関係を確認するために国が実施した調査の1つ、「インフルエンザ罹患に伴う異常行動研究」(主任研究者:国立感染症研究所感染症情報センター長・岡部信彦氏)の結果が16日に発表された。「リン酸オセルタミビルの臨床的調査検討のためのワーキンググループ」(臨床WG)の中心メンバーの1人、日大精神医学系教授の内山真氏は、この研究結果について、「タミフルを服用したかどうかによらず、インフルエンザ罹患時に異常行動が発現することが明らかになった」などとまとめた。 今回発表されたのは、2006/07シーズンに臨床医が経験したインフルエンザ患者の重度の異常行動137例についての解析結果。全国の医療機関から報告された164例のうち、日時が不明なものや、31歳以上の症例を除外した。なお、2007/08シーズンの調査は現在、実施されているところで、来春以降に結果が発表される予定だ。(関連記事:2007.12.6 症例報告求む!「インフルエンザと異常行動」) 調査では、重度の異常行動を、(1)突然走り出した、(2)飛び降りた (3)その他、予期できない行動であって、制止しなければ生命に影響が及ぶ可能性のある行動―――と定義した。解析対象となった137例で調べたところ、82人(60%)がタミフルを使用していたが、52人(38%)は使用していなかった。不明は3人(2%)だった。ザナミビル(商品名:リレンザ)、アセトアミノフェンの使用状況は以下の通り。表1 2006-07シーズンに異常行動を起こしたインフルエンザ患者137人の服薬状況使用していた 使用していない 不明 タミフル 82人(60%) 52人(38%) 3人(2%) リレンザ 9人(7%) 105人(76%) 23人(17%) アセトアミノフェン 51人(37%) 53人(39%) 33人(24%) つまり、異常行動を起こしたインフルエンザ患者の6割がタミフルを使用していたことが分かった一方で、4割は、タミフル不使用でも重度の異常行動を起こしていることが分かったことになる。 137人の患者の性別は、101人(74%)が男性で、36人(26%)が女性。男性に重度の異常行動が出やすいことが示唆された。 さらに、137人のうちから10歳未満(56人)と10歳代(69人)を抽出して、厚労省から「タミフル服用後の異常行動について」(緊急安全性情報の発出の指示)が発せられた3月20日を境に(2007.3.21 タミフル、一転して「10代は原則使用禁止」に)、異常行動の発生率に大きな変化があったかどうかを見たのが表2だ。 3月20日の前後で全報告数に対する比率を見ると、10歳未満と10歳代で有意な差は認められなかった。正確な数字は不明だが、3月20日を境に、10歳代インフルエンザ患者へのタミフル処方は大幅に減少しているはず。にもかかわらず、10歳代の異常行動の報告数は、3月21日以降も特別減った様子がなかった、と解釈できる。表2 年齢別に見た3月20日以前と3月21日以降の患者数3月20日以前(90人) 3月21日以降(35人) 10歳未満(56人) 39人 17人 10歳代(69人) 51人 18人 内山氏は、「インフルエンザ罹患時に、インフルエンザ脳症の定義には当てはまらない脳の異常が起こり、重大な事故につながる可能性があることが分かった。このことは事故を防ぐ上でも重要だ。タミフルが直接、異常行動を起こしている可能性は低くなったと考えるが、異常行動が起こるリスクを高める可能性は残されている。今後は、その点の解明が焦点になる」などと述べた。 (転載終了)インフルエンザはウイルスであり、扁桃リンパから吸収されると理論的には、全身のどこに感染しておかしくありません。ウイルスは接着するときに相性のよい細胞があるために、だいたい感染する組織は決まっています。今回の調査では、インフルエンザでも軽い脳炎が起こっているという貴重な結果が報告されました。タミフルは感染に関係なく、脳炎を起こすことを証明するには、健常人に服用してもらうしかありませんね。異常行動を高める可能性は否定できていませんので、本当に必要な薬かどうかはまだ?のままだということです。
December 18, 2007
コメント(0)
-

抗癌効果のある食事はあるのだろうか?
みなさん、こんにちは。1ヶ月ぶりに東京に来ましたが、空気の悪さは相変わらずですね。たくさん人がいるのですが、なにか田舎よりも寂しさを感じるのは、私だけでしょうか? (転載開始) 抗癌効果のある食事はあるのだろうか? ある種の果物と野菜を食べると癌のリスクが低下しその増殖が止まる可能性すらある Kathleen Doheny【12月6日】ある種の果物と野菜が癌のリスクを低下させ、その通過路に発生する癌を抑制するのに役立つ可能性があると、新規研究は示唆する。 「抗癌作用をもつ食事」が現実に存在するわけではないが、ある種の果物と野菜を多量に摂取することは、発癌リスクを低下させるのに役立つと、研究者らは米国癌研究学会の第6回国際癌予防研究フロンティア年次会議(フィラデルフィア)で報告した(12月6日)。 その知見は、果物と野菜の摂取量が多いことが癌リスクの低下と関連することを明らかにした、以前の研究を確認および補強するものである。 最新の「A」リストには、ブラックラズベリーが食道癌の予防、およびブロッコリーのようなアブラナ科の生野菜が膀胱癌の予防に推奨されている。 新しい知見にもかかわらず、「魔法のような効果のある」食物はないと、オハイオ州立大学総合癌センター(コロンブス)の栄養学の准教授であり、演者のひとりであったLaura Kresty, PhDは述べている。「この研究から学ぶべき重要なことは、多様な[果物と野菜]を食べよ、旬のものを食べよということである。本当に目指すべきことは、果物と野菜の総摂取量を増やし、野菜中心の食事を摂るように努めることである」。 ブラックラズベリーが食道癌のリスクを低下させる可能性がある ブラックラズベリーを食べることが、食道癌になるリスクの高い人々を保護する可能性があることを、Kresty博士らは見出した。博士らは以前に動物実験において、ブラックラズベリーが口腔、食道、および結腸の癌を抑制することを見出していた。 果物はおそらく、酸化ストレス、すなわちフリーラジカルによる細胞破壊を減らすこと、およびDNA損傷と細胞増殖速度を軽減することによって、そのような作用をするのであろうと、博士は述べている。 博士らは、バレット食道と呼ばれる食道の前癌病変を有する高リスク患者に研究対象を拡大することにした。バレット食道患者は食道癌のリスクが30 - 40倍高いと、Kresty博士は述べている。食道癌は致死的であり、5年生存率は15%しかない。 研究では、20例の患者が、凍結乾燥したブラックラズベリーを1日に1オンス(28.3g)または1.5オンス(42.5g)(男性はより多く)、26週間摂取した。「我々は酸化ストレスのマーカーを測定した」とKresty博士は述べている。そのひとつが、尿中に排出される8-イソプラスタンという物質である。 「研究終了時に、58%の患者は8-イソプラスタンが顕著に減少しており」、これは酸化ストレスの減少を反映していた。 研究者らは、発癌物質の無毒化を促進するGSTpiという酵素の組織内レベルも検討した。37%の患者においてはこの保護作用を有する酵素が増加していたことが明らかになった。 研究では実際に癌が発生した人々が減少したかどうかを調べる長期追跡調査は行われなかったが、Kresty博士は、果物には「保護作用があるように思われる」とWebMDに語っている。 ブラックラズベリーは食料品店で売っていると博士は述べる。「通常、少しずつ食べるような種類のものである」と博士は述べている。 膀胱癌の予防のための野菜 ブロッコリー、ブロッコリースプラウト、キャベツ、およびカリフラワーのようなアブラナ科の生野菜は、膀胱癌のリスクを約40%低下させるようであると、Roswell Park癌研究所(ニューヨーク州バッファロー)の研究者らは学会で報告した。それは、それらの野菜に含まれている、膀胱癌に対する保護効果を有すると考えられるイソチオシアン酸塩すなわちITCという化合物によるものである。 「生のアブラナ科の野菜は加熱調理した野菜よりも良い。なぜなら調理中にイソチオシアン酸塩の量が60% - 90%減少するからである」と、研究のひとつを率いたRoswell Park研究所の博士研究員であるLi Tang, MD, PhDは述べている。 博士のチームは膀胱癌と診断された275例の被験者および825例の健康な被験者の食習慣を調査した。診断前の生および加熱調理済みの野菜の摂取、喫煙習慣、ならびに他のリスクファクターについて質問した。 1カ月にそれらの野菜を3食分以上摂取した非喫煙者は、1カ月に3食分未満しか摂取しなかった喫煙者と比較して、膀胱癌になる可能性が約73%低かった。(3食未満しか摂取していない非喫煙者のデータが示されておらず比較できない。) ブロッコリースプラウトは膀胱癌の予防に、より優れている可能性があると、動物におけるブロッコリースプラウトの効果を研究したRoswell Park癌研究所の腫瘍学の教授Yuesheng Zhang, MD, PhDは述べた。博士のチームは4群の動物を用いて検討を行った。1つの群には膀胱癌を誘発することが知られている溶液を飲ませブロッコリースプラウトの凍結乾燥抽出物を摂取させた;その他の群には、ブロッコリー抽出物のみか、または発癌物質のみを摂取させた。もう1つの群は対照群とし、何もしなかった。 10カ月後の時点で「発癌物質[のみ]を摂取した動物の96%に腫瘍が発生した」と博士は述べている。発癌物質とブロッコリー抽出物の両方を摂取した動物のうち、癌が発生したのは37匹のみであった。(曝露した動物数が示されておらず比較できない。) この場合も、保護効果を示すと考えられるのはITCである。ブロッコリースプラウトは発癌物質を無毒化する上で重要な2つの酵素を活性化することによって効果を発揮するようであると博士は述べている(Medscape)。(転載終了)何かパッとしない結果ですが、これも当たり前ですよね。ガンは複合的要因で発生・進展するものですので、単一の食物や治療法で治癒させるという発想がどうかしていると思います。治療もやはり組み合わせでやっていくのがよいでしょう。何の食べ物がガンの発生を抑えるといった短絡的な発想のもとの研究はもうそろそろ終わりにしてほしいものです。
December 16, 2007
コメント(0)
-
夫の喫煙、妻の肺腺がん危険2倍に !
みなさん、こんにちは。このシーズン宴会に行くと、タバコの煙にやられてしまいます。宴会や食事階でも分煙してほしいですね。 (転載開始)「家庭でも分煙を」厚労省研究班 夫の喫煙、妻の肺腺がん危険2倍に 夫が喫煙者だと、非喫煙者の妻が肺腺がんになる危険が2倍になることが厚生労働省研究班(主任研究者、津金昌一郎・国立がんセンター予防研究部長)の大規模疫学調査で分かった。夫の喫煙本数が多いほど妻が肺腺がんになりやすく、研究班は「家庭や職場で分煙を工夫すべきだ」としている。がんの国際専門誌に発表した。 肺腺がんは主に肺の奥にできるがんで、女性の肺がんでは最も多い。研究班は妻(40-69歳)がたばこを吸わない夫婦約2万8000組を対象に、平均13年間追跡調査した。 追跡調査期間中に肺がんと診断された妻は109人で、うち82人が肺腺がんだった。夫が喫煙者の場合に妻が肺腺がんになる危険は、夫が非喫煙者の場合の2倍、夫がかつて喫煙者だった場合も同1・5倍になっていた。 夫の喫煙本数別でみると、1日に20本未満の場合は吸わない場合に比べ1・7倍、20本以上は同2・2倍と、本数が多いほど妻が肺腺がんになる危険が高まった。82人の約4割は夫からの受動喫煙が原因と推定された(毎日新聞社)。(転載終了) 喫煙は明らかにガンの確立を上げます。喫煙がベースにあり、あとはストレスが加われば、ほとんどの人は間違いなく肺がんなどにかかるでしょう。喫煙してもガンにならない人は、ストレスに対する耐性があるのかもしれませんね。
December 13, 2007
コメント(0)
-
荒れる病院で暴力対策進む 医師ら疲弊!!
みなさん、こんにちは。最近は雨が降ったりして、さほど冷え込みはありません。これくらいの気候で冬が終わってくれたらいいのですが・・・・ (転載開始)荒れる病院で暴力対策進む 医師ら疲弊、人中心医療を 病院も荒れだした。「暴言・暴力お断り」。こう訴えるカラーポスターが千葉県の船橋市立医療センター救急外来のロビーに張り出されている。医療安全にいち早く取り組んできた同病院は、患者や家族からの暴力への対策として4月からポスター掲示に踏み切った。 「救急外来で患者や家族と個室で話し合うとき暴力行為を受けやすい」と同病院救命救急センターの池田勝紀(いけだ・かつき)医長。看護師らが患者から怒鳴られることは日常茶飯事だ。看護師や医師が理不尽な要求で精神的ストレスを受けて仕事を辞めていく誘因になっている。 同病院では、事件トラブル対応が徐々に増え、2006年度は暴言・暴行・威圧・恐喝が9件、盗難が5件、不審者侵入が3件あった。うち5件は110番通報した。 患者や家族が激高しても医師らは「苦しんでいるのは患者だから仕方ない」と我慢してきた。しかし、犯罪が増える社会の中で病院でも暴力が横行、スタッフを守らなければ、質の高い療養環境を維持できなくなった。 病院は攻撃に弱い。池田医長は「医師や看護師は、病気の人を助ける訓練を受けているが、暴力への対処法は教えられていない」と話す。このため、警察の防犯セミナーで簡単な護身術を学んだり、暴力行為には院内放送で「コードホワイト」と緊急事態を通報して職員が駆けつける仕組みをつくったりした。 激務で医師や看護師が大量に辞めて医療崩壊の危機にある。どの病院も残った医師らに過重な負担がかかり疲弊してヘトヘト。「患者さんに『体に気を付けてください』とかえって励まされるぐらい」と苦笑が漏れる。 東京や大阪では警察OBを雇って暴力対策に乗り出す大病院が増え始めた。聖路加国際病院(東京)の福井次矢(ふくい・つぐや)院長は11月の「医療の質・安全学会」で「採血を1回失敗したら、業務上過失傷害罪だと言われてショックを受けた」と語った。「患者さま」という表現も患者の節度を弱めたようだ。 世界保健機関(WHO)と同学会が主催する国際シンポジウムが11月25日東京で開かれ、「"人"中心の医療」で改革を訴える東京宣言を採択した。提唱者の尾身茂(おみ・しげる)WHO西太平洋地域事務局長によると、患者中心の医療を発展させたもので、医療者も人であり、疲弊させないようにするのは必要だとする視点も組み込んだという。 × × 医療機関の安全管理 院内暴力や犯罪について厚生労働省は昨年、都道府県に通達を出し、医療機関に安全管理体制明確化を示した。その中で暴力を容認しない掲示や対策マニュアル、防犯設備拡充、警察との連携などを提案している(共同通信社)。(転載終了)今、病院では国家官僚のしめつけに対する八つ当たりのように、クレームが続出してます。本当の暴力だけでなく、言葉の暴力も人を疲労させますね。日本での医療の仕事は非常に質が低く、できる医師はアメリカやヨーロッパに流出しています。日本の野球と同じように、やがて日本の医療も空洞化が進むでしょう。私もこの年からアメリカ医師試験に挑戦しようと思っております・・・・
December 11, 2007
コメント(0)
-
陣痛女性に非情の銃弾 米軍!!
みなさん、こんにちは。うちのラブラドールの首にまた500円玉大の皮膚感染が悪化しています。先日、体を綺麗に洗ったのですが、ダニが6匹も見つかりました。ひょっとしたら、このダニが媒介しているウイルスやバイ菌が原因ではないかと思いました。山で放して散歩するのは、控えたほうがよいかもしれませんね。 (転載開始)陣痛女性に非情の銃弾 米軍、病院急行の途中で 夜間外出禁止のバグダッド 「緊急ルポ」 夜間外出禁止令下のイラクの首都バグダッド。日没後、陣痛の女性を乗せ、病院に急ぐ車両に米軍から非情の銃弾が浴びせられる。イラクでは米軍の増派などのため、首都など一部でテロや攻撃が減少、治安が改善傾向にあるとされる。しかし女性たちは喜びに満ちたはずの出産ですら、命懸けで臨まざるを得ない。 ▽警告なしの発砲 バグダッド東部、新バグダッド地区。妊娠8カ月だった主婦シーナ・ハミドさん(24)は昨年1月の深夜、突然陣痛を訴えた。しかし夜の病院行きは極めて危険。夜間外出禁止令下のバグダッドでの車の運転は、米兵やイラク警察の拘束や攻撃を受ける恐れがあるだけでなく、民兵が設けた"死の検問所"さえある。 しかし娘の窮状を見かねたシーナさんの父親ハミドさん(62)はハンドルを握ることにした。助手席に母親ファウザヤさん(57)、後部座席のシーナさんには夫のヒクマトさん(32)が付き添う。最初の警察検問所は無事通過したが、悲劇はその直後に起きた。右側通行の道路を逆走してきた米軍車列が警告なしに発砲してきたのだ。 「撃たないでくれ」。必死に手を振るヒクマトさんは肩に被弾した。悲鳴を上げるシーナさん。近づいた米兵にヒクマトさんは「助けて」と叫んだが、米兵は何もせずに立ち去ったという。 両親はほぼ即死だった。シーナさんらは警察に救助され病院に搬送されたが、男女双子の赤ちゃんは死亡していた。 ▽転院の途中で イスラム教シーア派が多数を占めるバグダッド北部のカドミヤ病院。産婦人科医で、自らも10月4日に男児を出産したばかりのワフワ・サレハ医師(35)は「夜間陣痛を迎えた女性が病院に急行する途中、米兵に銃撃される例は枚挙にいとまがない」と話す。 バグダッド西部タジの主婦イブティサンさん(32)は今年4月の深夜、産気づいた。しかし夫の運転で病院に向かう途中、パトロール中の米軍の激しい銃撃を受け死亡、夫も重傷を負った。 今年5月に陣痛を訴えた別の主婦アマルさん(27)は夫とともに何とか病院にたどり着いたが、帝王切開をする手術室が自爆テロによる負傷者で満杯のためカドミヤ病院へ向かうことに。2人の車は途中いくつもある検問所の1つで銃撃を受け、夫が死亡。病院にたどり着いた時には手遅れで流産だった。 同医師によると、銃撃を避けるため、前照灯を消したまま走行し、米軍戦車に衝突、帝王切開で出産したものの、夫婦ともに重傷を負った例も。 ▽「ハミド」 「身ごもった私が悪かった」。一度に両親と赤ちゃん2人を失い、シーナさんは一時、妊娠した自分自身をのろった。 「どんな将来が待っているのか分からない。それでもぼくたちには新しい命が必要だ。これは神がわれわれに授けた試練なのだから」という夫の言葉を受け入れる気持ちになったシーナさんは、いま妊娠9カ月だ。 おなかの子は男の子と分かった。名前は「ハミド」と決めている。自分のために命をかけた父親ハミド、そして母親の命を受け継いだ子どもと信じているから。▽バグダッドの出産事情 バグダッドの出産事情 イラク首都バグダッドの産婦人科医らによると、旧フセイン政権時代、10カ所の主要産婦人科医療施設でそれぞれ1日平均40人の赤ちゃんが生まれたが、政権崩壊直後は60人に増えた。独裁政権崩壊で経済制裁が解除されたことによる経済、社会状況に対する期待を反映したものとみられる。しかし、極度の治安悪化で昨年は30人に減少。医師は拉致、殺害などテロの標的となっており、国外脱出者が急増、医師不足も深刻になっている(共同通信社)(転載終了)これでは、イラクの人は自爆テロでもなんでもするでしょう。今世紀アメリカに殺戮された原住民(つまり日本人も含めた非欧米人)はおびただしい数になるでしょう。今だにこのように非欧米人の命は粗末に扱われているのです。何が米軍への給油再開だ。日本人は頭がどうかしてますね。身のまわりの小さな不正には口うるさいくせに、アメリカという巨悪には黙り込みを決め込む。官僚がその情けない日本人の最たるものです。日本という誇りを持てないという屈折した感情はないでしょうか?いくらアメリカにはいつくばっても、日本人は所詮は原住民なのだから、いいように利用されるだけなのです。欧米人の支配する世界にノーといえる国民になりたいものです。
December 5, 2007
コメント(0)
-
がんの約2%、CTが原因 医療被ばくで米チーム!
みなさん、こんにちは。最近また鼻づまりがひどいです。点鼻薬の効果も数時間に短縮されてきました。酸素濃度が低いと、全てのパフォーマンスが低下するので困ったものです。 (転載開始)がんの約2%、CTが原因 医療被ばくで米チーム 放射線を利用するCTスキャンの使用頻度が米国で急増、将来のがん患者のうち約2%をこれらのCT検査による被ばくが引き起こす恐れがあると、米コロンビア大の研究チームが米医学誌に29日発表した。 CT検査の3分の1は医学的に不要との統計もあるとして、不必要な使用を避けるよう警告している。 チームによると、米国の医療現場でCTスキャンの使用回数は1980年の約300万回から2006年には約6200万回へと急増。断層画像を取得するのに何度もエックス線を照射するため、撮影1回当たり15-30ミリシーベルトを被ばく。一連の検査でこれを2、3回繰り返し、計30-90ミリシーベルト被ばくするという。 通常の胸部エックス線撮影では0.01-0.15ミリシーベルト、乳がん検診では3ミリシーベルトを被ばくするとされる。 チームは広島や長崎の原爆被爆者の疫学データと比較するなどした結果、現在のCT検査による発がんリスクが将来、全米のがん患者の1・5-2・0%に達すると推計した。 チームは「CT検査の利益とリスクを比較することが大切だが、不要不急の検査や、放射線の影響を受けやすい子どもへの使用は控えるべきだ」としている(共同通信社)。(転載終了)CT検査は、人間の体を輪切りにして見れるので、非常に診断には有難い検査です。問題は被爆量が半端ではないことですね。健診レベルで使用するのは不要な部類に入るのでしょう。被爆のことを考えると、MRIの方がいいと思いますが、CTほど気軽にできる環境にはまだないことと、磁気の副作用がまだはっきり分かっていないことが難点です。将来は「あのときにとったCTが原因でガンになった」なんて訴訟する人がアメリカあたりでは現れるかもしれませんね。
December 3, 2007
コメント(1)
全12件 (12件中 1-12件目)
1