2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年01月の記事
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-
レスリングの壁
レスリングの壁KIDが2回戦で負けたらしい。 単に負けただけならそれほど興味もわかないのだが,怪我をしたというのが気になった。KIDほどの格闘家が怪我をするなんてことは,余程のことがないとありえない。ってことでみてみた。 http://www.youtube.com/watch?v=FjtGKI4Q__U http://www.youtube.com/watch?v=eGiJzpltBFE 素人ながらに井上選手の巻き投げが見事だなあと思った。柔道の一本背負いのように踏ん張るのではなく,むしろ膝を抜く(とは違うな、足を逃がすというか)ように全身を空中に放り出して重力を使って投げている(ようにみえる)。 KIDはまったくこの投げを予測できていなかったから怪我をしてしまったのだろう。甲野善紀先生の古武術に通じるものがありそうだ(甲野先生のコメントを聞いてみたい気もする)。 しかしその井上選手が優勝したのかと思えば準優勝という。壁は厚いなあと他人事ながら思った(スポーツならどこでも壁は厚いのだが)。 予測できない攻撃を受けるというのは,どうだろう。レベル(動きの質)が違うということなのかもしれないし,井上選手も決勝で負けていることを勘案すると頭に入っていればある程度対応可能になるってことかもしれない。 KIDが悪いわけじゃないんだろうけど,そもそも「神の子」という名称はいかがなものかなと思っていた。「神の子」が「人の子」に負けるってのもおかしな話だ。まあその名称がウケてるわけで,観客がたくさんきてレスリング協会も喜んでいることだし,いいのかもしれないが,バスケの神様がベースボールでは通用しなかったようなことにならなきゃいいんだけどね(ちなみにマイケル・ジョーダンは凄く好き)。 とはいえ,ふつうに考えると復帰してすぐに1回戦勝っただけもやはりすごいことだ(国内ベスト8)。
2007/01/29
-
次世代人間科学研究会(最終回)のお知らせ
2007年2月11日に,長年(というほどでもないけど)にわたって主催してきた次世代人間科学研究会の最終回を行うこととなりました。次世代研の志を継承する場,そして志を共有する人たちの良き出会いの場として最後の役割を果たせたらと思っています。この研究会はわりとこじんまりと開きたいと思っています(現在予約参加者50名ほどです)ので,構造構成主義シンポジウムよりも密度の濃い議論ができるのではないかと思っています。学問の発展に関心のある方は,どなたでも参加できますので,お誘い合わせの上奮ってご参加頂ければと思います。ーーーーー以下転載可ですーーーーーー次世代人間科学研究会(最終回)「次世代の学知構築システムを考える」 日付 2007年2月11日(日)場所 早稲田大学西早稲田キャンパス19号館3階311教室http://www.waseda.jp/jp/campus/index.html第一部 学会の現状と展望(13:00~14:30) 司会 松嶋秀明(滋賀県立大学) 話題提供 無藤隆(白梅学園大学) 話題提供 菅村玄二(日本学術振興会)第二部 次世代型学術媒体モデルの提示(15:00~16:30) 司会 荒川歩(名古屋大学大学院) 話題提供 京極真(江戸川医療専門学校) 話題提供 西條剛央(日本学術振興会)第三部 さらなる議論に向けて(17:00~18:10) 司会 荘島宏二郎(大学入試センター) 総論 池田清彦(早稲田大学) 総合ディスカッション【企画趣旨】 もともと研究は個人的な営みである。研究によって個人の疑問を解決できればよかった。しかし,研究に公共性が求められ,何らかの学界システムが必要となった。それゆえ,現在は,各種学会や学術雑誌が学界の発展を担っているのは疑いようがない。そしてこれからもそうした役割を果たし続けるであろう。 しかし、改善すべき点は多く指摘されているのも事実である。さらに、業績重視の傾向やインターネットなどの急速な発展によって時代は大きく変化している中で、学会や学会誌,学術誌も新たなあり方が求められている。それゆえ,次世代の創造を志した次世代人間科学研究会の最終回では、次世代の学知構築システムを建設的に考えてみたい。 現実を踏まえない理念は虚妄に過ぎないが,理念なき現状肯定しているだけではシステムは硬直化していく。システムを維持すればいいというものでもないが,変えれば良いというものでもない。現実を踏まえ,変えるべきではない点,変えるべき点などを精査しつつ、斬新なアイディアを取り入れることによって,学知発展の基盤を支える新たなシステムについて皆さんと一緒に考えていきたい。 第一部では、数多くの学会の運営に携わってきた無藤隆氏に、これまでの学会の長所と限界、そして現実的制約を踏まえながら,これからの学会システムに求められることを語って頂く。次に,世界40ヶ国以上が参加している国際学会である"Society for Constructivism in the Human Sciences"の編集委員を務め,現在,ケネス・ガーゲン氏らと共に,新しい学会の構想に取り組んでいる菅村玄二氏には,国際的な学会や学術誌の動向を報告してもらう。 第二部では,蛸壺化した学界に一石を投じるため,著者に印税を支払うなどの画期的システムを備えた新たな学術媒体『構造構成主義研究』の創刊に編集者の一人として関わり,現在もなおその発展に尽力する京極真氏には,『構造構成主義研究』を創刊するまでの経緯や,そのモチーフ,システム上の工夫点などを語ってもらう。西條剛央氏には、次世代人間科学研究会の中核メンバー等によって,斬新なアイディアをいくつも組み込んで編纂した『エマージェンス人間科学』の魅力と語ってもらい,さらなる学知構築システムの構想を語ってもらう。 第三部では、第一部、二部を踏まえ池田清彦氏に指定討論的に総論を行っていただく。その上で,会場のみなさんと一緒に次世代の学会や学術媒体のあり方についてディスカッションしていく予定である。[参加費] 無料[懇親会] 18:30ー20:30 (2500~3000円程度を予定)[締め切り] 2007年2月5日(月)[申し込み先] 西條剛央: saijo@akane.waseda.jp参加者数を把握する必要があるので2007年2月5日(月)までに,件名を【次世代研参加】として下記の情報を記入してお送りください。みなさんお誘いあわせの上ご参加ください。●参加者氏名(複数可):●懇親会参加:有・無(該当する方を明記)ーーーーーーーーーーーーーーーーー
2007/01/26
-

叔父さん的思考
先日は親友の誕生日だった。 親友の誕生日でわざわざ祝いに行ったりするマメさはないのだが,それが妹の旦那,姪のお父さんともなると話は別。 妹の作った料理や,ケーキを食べ,ビールやワインを飲んで愉しい時間を過ごす。 姪のゆらちゃんは,前よりも言葉っぽいことを話すようになった。 それと気がむくとミスチルの「しるし」を歌い出す。 「じゃーりんじゃーりー」(ダーリンダーリーン)とか,なんとか。それがなんともかわいい。 抱っこしながらそのまま続きを歌ってあげるとスヤスヤと寝てしまった。 かわいい姪を生んでくれてありがとう。と叔父は思うのでした。
2007/01/24
-
科学リテラシーの健全は発達段階か
例の納豆騒動で苦情は止まらず,「信用できなくなった」などの内容のメールが送られてきているとのこと。これは市民科学教育的に良いことだと思う。科学番組を「利用」するための科学リテラシーとして健全な発達段階ともいえる。テレビの言う「科学的に実証されました」系の「物語」をーー特に深夜の通販番組では軒並みみられるがーー「信用できなくなる」のはいたって健全なこと。 だから,この場合「信用できなくなった」という言明は,「一つ科学リテラシーが身に付きました」ということと同義であり,苦情としてではなく,「おかげさまで」というコンテクストで使うこともできるはずなのだ。 科学的知見も,番組も「人間によって作られた」もので,特にテレビ番組が「視聴率」という「至上命題」がある以上,どうしても一般人にウケる内容に偏らざるを得ない。これはある程度仕方が無い。 みのもんたの番組だって,ねつ造までとはいなくとも,実質的にほとんど意味がないような知見はおそらくいくらでも垂れ流してきただろうしね。 だからといってすべてを疑うというのもまた難しいことだし,その必要も無い。 ただ,テレビでいう科学的なんチャラなんてものは,客観的事実でも,ましてや「信じるべき真実」なんかじゃなく,その程度の物語だということを踏まえた上で,「活用」すればいいのだと思う。 なんだったら過去のあるあるや,みのもんたの番組などを含めて,すべての科学的情報番組を厳密に「検証する」番組でもやったらいいんじゃないかと思う。 「情報源」や「ローデータ」にアクセスできなければ,大学院などで科学的な教育を受けてきた人でも実際に検証することはできないが,「考え方」を学ぶだけで判断する際にはだいぶ違ってくる。 どのように科学的知見というものが「作られて」いて,それを検証するにはどうしたらいいのか。そういうメタ番組があったらけっこうおもしろいし,それこそ役立つと思うのだけど。 (まあ,テレビに振り回されない最大の方法は,テレビをみないことでもあるのだが,身も蓋もないか) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=149215&media_id=2 <番組ねつ造>視聴者からの苦情止まらず 9200件超える (毎日新聞 - 01月24日 20:00) 関西テレビ(大阪市北区)制作のテレビ番組「発掘!あるある大事典2」で、データやコメントがねつ造されていた問題で、同テレビは千草宗一郎社長の減俸などの処分と番組打ち切りを発表したが、視聴者からの抗議や苦情、問い合わせが止まらない。同テレビとキー局のフジテレビ(東京都港区)など系列各社に届いた声はこれまでに計9200件を超え、23日の処分発表後は「処分が甘い」の声も寄せられ始めている。 NHKと民放が設立した第三者機関、放送倫理・番組向上機構(BPO)にも、視聴者から抗議のメールが寄せられている。「信用できなくなった」などの内容で、24日までに約50件にのぼった。BPOは「(今回の問題に限らず)総務省から厳重注意を受ける番組が最近、複数あった。早急に対応を検討する」としている。【北林靖彦、濱田元子】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007/01/24
-
納豆騒動,振り回され過ぎ
世には納豆騒動なるものが起きているらしいが,テレビをみない僕にはあまり関係がない。そもそもテレビでやっている「科学的なんチャラ」というものは信用していない。心理学をやってきて,いくらでもなんとでもいえる,ということはよくわかっているし,ましてやテレビのやることである。ふーん,ぐらいにしか思わない(ダイエットなど,家に食べ物がなければ自然とできる)。 自分にとって本当に大切なことなら,いろいろなリソース(書籍,ネット)を駆使して信憑性のある知見を自分で見つけると思う。 突然納豆を買うといったことはよくあることでさほど驚きもしなかったが,報道がねつ造だと分かった途端に買うのを止める消費者には何だかなあと思った。 ここまでくると振り回され過ぎで,もはやギャグである。 これでねつ造はねつ造で本当でしたなんてなったら,また突然買い込むのだろうか。 振り回されたのは自分の責任でもあるんだから,突然買うのを止めたりしないで,身体にもいいし,おいしいんだからと強がってとりあえずしばらくは食っといたらいいんじゃないかと思った。 納豆業者がかわいそうだろう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=147664&media_id=2 <番組ねつ造>納豆発注ストップ…業者悲鳴 (毎日新聞 - 01月22日 03:21) テレビ番組「発掘!あるある大事典2」が放送した「納豆ダイエット」の内容ねつ造を、制作した関西テレビ(大阪市北区)が認めて一夜明けた21日、大生産地の茨城県の納豆製造業者には早速発注取り消しの電話が入り、業者が頭を抱えている。増産態勢をとっていた業者は「このままでは廃棄処分が出るかもしれない」と話す。 同県日立市の小規模業者は「7日の番組放映後、スーパーの注文が通常の1.5倍以上に増えたが、今日から注文がぱたっと止まった」と話す。発酵で作る納豆は出荷2~3日前に、発注量を予測して製造を始める。業者は「22~23日出荷分は既に作ったが、賞味期限は1週間。注文が来なければ廃棄するしかない。数十万円の損失になる」とため息をつく。 同県土浦市の小規模業者も、スーパーから注文を取りやめる電話がかかってきた。「納豆の容器や出荷用段ボールも大量に発注してしまった。倉庫に入らないかもしれない。テレビ局はスーパー、業者、消費者ら大勢の人に迷惑をかけた。影響力が大きいことを認識してほしい」と憤る。 水戸市のスーパーの男性従業員(36)は「番組で売り上げが倍になったが、今日の売れ行きは以前に戻り、かなりの納豆が売れ残った。大量仕入れで在庫もあり、消費期限内にさばききれるか心配。発注はしばらく見合わせる」と話した。【三木幸治、原田啓之】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007/01/22
-
教育思想研究と原理的思考
先日は,池田清彦先生主催の勉強会だった。 3名の院生に発表してもらった。 一人目はS君。ブルーナー研究で,非常に勉強になった。ブルーナー研究を教育思想として研究しているひとはあまりいないので,オリジナリティは出しやすいが,他方(デューイなどと比べれば)希代の大学者というわけでもないので,思想研究するにあたって独自の難しさがあるようだった。 思えば彼との出会いは印象的だった。 前期中にこの勉強会のあと近くの居酒屋に行った。池田先生と僕が先頭で店に入ると,近くの席で飲んでいる学生の一人が池田先生の顔,僕の顔をみて言葉を失っている。 ん,なんだろうと池田先生と顔を見合わせる。彼は「あの,池田先生と西條さんですよね」といった。 話を聞いてみると,どうもちょうど池田先生と僕との対談本『科学の剣 哲学の魔法』を読んだばかりだったらしく,あの本にはけっこう写真が入っていることもあって,気づいたということだった(その後,飲み会中に写真を取って欲しいとやってきた)。 前日に竹田先生との勉強会後に飲んでいたときに、後で出てくるI君がやってきて「後輩で是非、西條さんに会いたいといっている人がいるんです」といっていたのを思い出して、いってみたら、やはりその後輩がこのS君だった。それが契機となって池田先生の授業に潜らせてもらうようになり、時々研究室に遊びにくるようになった。そんなこんなで勉強会にきてもらうことになって,今回の発表につながる。 縁があったということなのだろう。 2人目の発表はU君。デューイの「経験」についての発表だった。この概念はかなり誤解されているようで,僕も気になっていたところだったので(どちらにも読めるところがあっていろいろ読まないと判断が難しい)とても勉強になった。デューイ研究は膨大な資料,研究論文があるため,もはややられ尽くされており,なかなかオリジナルな研究をすることは困難なようであった。S君とは悩みの構造が反対だったのが興味深い。 今後より広い視座から研究を進めることに関心があったようだったので,愉しみだ。 彼は大人しいのだが,熱い思いを秘めている。一度口を開くと流暢に語り出し,話を聞いているのは愉しい。 3人目の発表はI君(このI君は『現代のエスプリ』の僕の論考にも出てくる)U君を紹介してくれたのがこのI君である。彼の発表はエマソンとデューイ思想のエッセンスを掴みながら,教育における「個」と「公」のアポリアを解明するという画期的な論考。 まず非常に文章がうまい。相当書き慣れている,という感じがする。論文の構成(流れ)もよくできており,論文の完成度は相当なものだ。 論文としてはほぼ完璧だったのだが,アポリアを解明する理路としては,原理性に欠ける箇所があったのでいくつか指摘した。 まず,彼の論文の随所にみられる「条件さえ整えば,人は必ず○○にめがけて○○する」という語法が気になった。 これは竹田青嗣先生の著作に時折見られる語法だ。 「これ竹田節だね」というと,彼は「あ,わかりました?(笑)」と言っていた。 彼は竹田青嗣先生の著作に強い影響を受けており,現在も直接指導を受けている(この論文もみて頂いたらしい)とのことだったので,これは自然なことだ。 自分にとって説得的と感じられる語法をマネていくことは,とても大切なことだと思う。 僕も竹田先生の著作からは,多くの大事なことを学んだ。 だが,この語法に関しては、使用の際には注意が必要だとも思う(うまく使えばいいのだが)。 というのも,「条件さえ整えば,人は必ず○○にめがけて○○する」などということは,人間の同質性,人間の本質は単一性を前提としなければ成立しないからだ。 人間の本質は単一である,ということはある種の真理主義を前提としているとまではいかなくとも,それは可疑性が高い言明だ。 そうした前提を了解してくれる人には説得的な理路足りうるが,「人間の本質は多様である」という信念をもっているひとに了解されることはない。 『現代のエスプリ』の論考では「原理性の深度はその理路が基礎づける射程に比例する」というテーゼを提起したが,まさにこの「条件さえ整えば,人は必ず○○にめがけて○○する」という語法は,「人間本質の単一性」という前提の上にしか成立しないため,その基礎づけられる射程は限られてしまうのだ。 したがって、こういう語法を絶対に使ってはならない,ということではないが,少なくとも原理的な理路を構築する際には「使用上の注意をよくお読みの上ご使用下さい」ワードにして捉えておいた方がよいだろう。 じゃあ,どう書けば良いのかといえば,僕なら 「特定の条件が整えば,○○にめがけて○○しやすくなる」 あるいは 「多くの人が○○にめがけて○○するためには~という条件が必要となる」 ぐらいにしておくだろう。 え,違いがわからないですって? 「条件さえ整えば,人は必ず○○にめがけて○○する」っていうのは,ほとんど刺激と反応(S→R)で説明する行動主義の亜系みたいなもので,機会論的人間像が前提となっているともいえなくもない。なにせ「条件」→「行動」というのだから。 それは「経済力と社会的地位という条件さえ整えば,人は必ず結婚する」といっているようなもので,こう考えてみると,そんなわけはないとすぐにわかる。 僕の提示した修正版は, 「経済力と社会的地位といった条件が整えば,結婚しやすくなる」 といったぐらいのもので,これはそんなに無理がない(根本仮説性は排除できないにせよ)。 とはいえ、竹田先生がこの語法を使うときは、社会システム全体について言及していることが多いようにも思う(印象だけで確認していないのでこれはかなり不正確)。その文脈で、この語法を使う時は,括弧付きで「社会全体の傾向として」ということが含意されるため、結果としては「多くの人が○○にめがけて○○するためには~という条件が必要となる」 というニュアンスを帯びるため、それほどマズイことにはならないのだ。しかし、この語法だけ取り出して,安易に自分の理路に組み込むと、原理的な破綻を呼び寄せることにもなりかねないので注意が必要ということなのだと思う。これと関連するのだが,何かを基礎づける原理的な理路を提示する場合,あるいはメタ理論を構築する場合,「原理」と「根本仮説性の高い理路」を意識的に分けて書く必要がある(こんなことを指摘するのは僕ぐらいのものだろうけど)。 原理は特定の方向性や価値観を含まない方がより原理性の高い理路となる。 池田先生が『構造主義科学論の冒険』にふつう「形式主義」というと悪口だが,自分はそう言われたら喜ぶ書かれていて,なるほどと思った。つまり,形式(構造)は中身がないため,あらゆるものに妥当するというのだ。 それと同じで,原理(これも構造の一種だが)もコンテンツ(内容)はない方が,その射程は広がるのである。 内容があると,その理路の基礎づけられる射程はその内容下に限定されるからだ。 原理的な基礎付けをした上に,現代社会の難問を解明するために何らかの方向性を打ち出すのは良い。そしてその部分は多少根本仮説性の高い(疑う余地のある)ものであってもよい(というか,ある程度そうならざるをえない)。 大事なことは,この二つの構造(原理と内容)を分けて考える(書く)ということだ。 そうすれば,根本仮説性の高い理路(ソフト)を修正する必要が出てきたとしても,原理の部分(ハード)はそのままで,ソフトだけ修正すればよくなる。そしてソフトを入れ替えれば,他のテーマにも導入可能になるのだ。 無論,これは彼の実力不足ということではない。むしろ逆で,こうした指摘を呼び起こすということが彼の実力が相当なものだということを物語っている。こういうことは自分で原理(メタ理論)を作ってみたことがないとわからないのだ。逆にいえば,彼は相当イイ線いってるということだ(優れた原理を構築し始めているということだ)。 彼にはいずれ1冊本を書いてもらおうと思った(なぜそうしたことが可能かといえば、ナカニシヤの編集長さんから「西條さんが監修で書かせたい人に1人1冊,1年で4冊,10年で40冊のシリーズ本を出したい」というオファーを頂いているため)。意図したわけではないのだが今回3名とも全員教育学を専攻しているということで教育思想特集となった。 一連の発表を通して,教育思想研究にとって研究対象となる「デューイ」や「ブルーナー」といった人物(のテクスト)は,心理学でいうところの「データ」に該当するものなんだな,ということがわかった。 だから教育思想において,人物研究を行わないということは,心理学でいえばデータを使わないようなもので,教育思想研究としては認められないのだ。 「デューイ」といった膨大だが,分析し尽くされている「データ」を選ぶか,「ブルーナー」といったそれほど豊かといはいえないが稀少な「データ」を選ぶかといった選択が,教育思想の出発点となるのだろう。 いずれにしても,心理学が「データ」分析に終始して,「で,だからなに?」という研究で終わってしまうことが虚しいように,教育思想が「人物研究」に終始して,「で,だからなに?」となってしまうことは虚しいと,3者とも思っているようだった。 それは健全な感覚だと思う。 データを通して,教育思想について何を語れるかが勝負なのだろう。心理学におけるデータが,心を説明するためのツールであるように,人物研究はあくまでもそのためのツールとして捉えつつも,同時に院生としてはその分野で認められるためにもその作法や技術を身に付けていくことが大事なんだろうと思う。 また今回の議論を通して,デューイ・プラグマティズムと構造構成主義の異同もよりはっきりした形で掴めたので、これも収穫だった(内容は誰かが論文化するだろうからここには書かない)。以上のような、原理と根本仮説を分けて理路を構築するといった話は、彼らにとって目から鱗だったらしく、飛躍的な知的成長期を迎えるためのエッセンスを掴んでもらえたようだ。今後の展開が愉しみ。その後,みんなで飲み会に行き,結局朝までいろいろ話し込んで愉しかった(最近若いな自分)。
2007/01/22
-

『ナラティブと医療』
斎藤清二先生等編の『ナラティブと医療』が出ました。医療関係者はもとより,物語論に関心のある方は必読の書です。 http://www.amazon.co.jp/ナラティヴと医療-江口-重幸/dp/4772409440/sr=8-1/qid=1171090472/ref=sr_1_1/250-0908101-9171453?ie=UTF8&s=books(その斎藤先生が,「物語と対話に基づく医療(NBM)と構造構成主義」という題で論考を書いてくださっていて、これは非常に興味深いのでいずれまた)また,阪大の院生が,メッセージをくださいました。構造構成主義に深く共感してくださった(知らずに構造構成主義者でした)という嬉しい内容でした。 そういうメッセージをもらえると,がんばろうっていう気持ちになるのでありがたいなあと思います。
2007/01/21
-
「わかりあうための思想をわかちあうためのシンポジウム(第一回構造構成主義シンポジウム) 」
3月11日に養老孟司先生,竹田青嗣先生,池田清彦先生などと一緒にシンポジウムを行います。参加費無料で,内容も一般向けでわかりやすく,また途中参加・中途退出等も可能ですので,一般の方もお気軽にご参加ください☆すでに予約参加者が300名以上になっているようですので,お早めの予約をお勧め致します。 ━━━━━━━以下転載可━━━━━━━「わかりあうための思想をわかちあうためのシンポジウム(第一回構造構成主義シンポジウム) 」 <日付> 2007年3月11日(日) <場所> 早稲田大学西早稲田キャンパス14号館201教室 http://www.waseda.jp/jp/campus/index.html <コンセプト> 世の中「信念対立」が満ち溢れている。政治,教育,医療といった世の中で議論が紛糾している論件の多くが、終わりのない信念対立の様相を呈している。構造構成主義は,こうした信念対立を巧みに解消しつつ、新たな道筋を見出していくための思想的体系である。今回のシンポジウムは,構造構成主義という「わかりあうための思想」を参加された皆様と「わかちあう」というコンセプトのもとで開催される。 第一部では、養老孟司氏をお招きして、我々日本人の多くが「無思想という思想」をもっているということを自覚することが無用な信念対立を回避するためにいかに役立ちうるのか、またそれを深く自覚するための考え方について講演して頂く。 第二部では、生物学から科学論、教育,社会システムまで幅広いテーマの著書を出されている池田清彦氏,現象学を中心として多様な哲学的思考に精通する竹田青嗣氏、また二人の思想的エッセンスも組み込みつつ構造構成主義を創始した西條剛央氏をお招きし、身近な信念対立の問題がなぜ起こるのか,そしてそうした信念対立を解き明かすための考え方,対処法までをわかりやすくお話していただく。 第三部は、信念対立に悩まされることの多い医療現場における問題に焦点化する。京極真氏はチーム医療と異職種間連携について、斎藤清二氏は医学と臨床実践、高木廣文氏には看護学に、構造構成主義を導入した新たな枠組みについてそれぞれ論じていただく。それを踏まえて指定討論の先生方に議論をしていただき、また会場の皆さんの意見も拝聴しながら、建設的に議論を展開していきたい。 皆様の参加を心よりお待ちしております。 <タイムスケジュール> 10:00 開場 10:20 開会の言葉 池田清彦 第一部 (10:30~11:50) 無思想の意識化 10:30 特別講演 養老孟司 11:30 質疑応答 11:50 昼休み(60分) 第二部 (12:50~15:10) 現代社会の信念対立を解き明かす 12:50 鼎談 池田清彦・竹田青嗣・西條剛央 14:50 質疑応答 15:10 休憩(30分) 第三部 (15:40~17:50) 構造構成主義の医療領域への展開 司会 川野健治 15:40~16:40 話題提供 京極 真・斎藤清二・高木廣文 16:40~17:10 指定討論 池田清彦・井原成男 17:10~17:50 ディスカッション 17:50 閉会の言葉 西條剛央 懇親会 18:30~20:30 <シンポジウム参加費> 無 料 <懇親会参加費> ・予約参加3000円 / 当日参加4000円 <申し込みについて> 当日は混雑が見込まれますので,参加される方はメールによる事前予約をお願いいたします。また,定員をオーバーした場合には,先着順で予約参加者を優先させていただきますので,お早めに予約されることをお勧め致します。 【申し込み先】 structuralconstructivism@gmail.com 上のアドレスに,件名を「第一回構造構成主義シンポジウム」とし,下記の情報を記入してお送りください。 ●参加者氏名(ふりがな): ●メールアドレス: ●懇親会参加:有・無(該当する方を明記) ●メールマガジンへの登録:有・無(該当する方を明記) (メールマガジンでは,今回のシンポジウムの追加情報,ならびに年に数回,構造構成主義に関連する最新情報が発信されます。) <構造構成主義公式ホームページ> http://structuralconstructivism.googlepages.com/ 構造構成主義の最新情報については公式ホームページにアクセスしてください。 ━━━━━━━━━━━━━━
2007/01/20
-
仕事の質によって戦略的に仕事場を変える
今日も一日中,いろいろ細かい仕事を延々とやっていた。 つかれた。なんか、研究しているときとは質の違う疲れだなあ。 でも、今日必ず終わらせようと思っていたことの4つは終わらせた(←あと2つは終わってない!)。 ちくしょー、自分,もしかして仕事が遅いのでは、という思いがよぎる。 しかし、今さらそんなこと考えても意味はない。 まあ自分にしては頑張ったかな。以前よりは速くなってるよな。そういうことにしておこう。そういや、明日は半日池田先生主催の勉強会がある。その発表論文3本も読み込まなきゃだな。 月曜から土曜までぶっ通しで研究室にいくのは、記録的なことと思われる。 しかし考えてみると,何かを深めるときは家にこもって考え続けるのはいいのだが、事務的な仕事をこなすときは、家にいてもはかどらないので、外に出てパリッとこなした方が効率があがるように感じる。 仕事の性質によって、場を戦略的に変えるという視点は案外有効かもしれない。
2007/01/19
-
『現代のエスプリ』(特集 構造構成主義の展開~21世紀の思想のあり方~」
エスプリ発売開始「現代のエスプリ」の最新号「構造構成主義の展開,21世紀の思想のあり方」が発売開始となりました! http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4784354751/ref=s9_asin_image_1/250-0908101-9171453 この本は以下の目次をみればお分かりのように現代思想を代表する論客と、新進気鋭の研究者が集結しており、これ以上ないというぐらいすごいメンツです。 <この巻に向けて>ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー構造構成主義とは最新の認識論であり,科学論であり,思想的枠組みでもある。その特長は,信念対立を巧みに回避しながら,多様な枠組みを十全に機能させるメタ性にあり,そうした特性から「使えるメタ理論」として様々な領域に普及しつつある。構造構成主義という新たな思想的動向をその目で見定めてみて欲しい。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『構造構成主義の展開 ー21世紀の思想のあり方』 編集 西條剛央・京極真・池田清彦 巻頭言 構造構成主義パラダイムの展開(西條剛央) 座談会 21世紀思想のあり方(池田清彦・西條剛央・京極真・上田修司) 第一部 構造構成主義と関連思想 構造主義科学論余話(池田清彦) 構造主義の思想史的意義(内田 樹) ポストモダン思想(高田明典) 理論体育学の提唱(甲野善紀) 20世紀の三大思想と構造構成主義(やすいゆたか) 構成主義とは何でないのか?(菅村玄二) 哲学の再生(竹田青嗣) 無思想の意識化(養老孟司) 第二部 構造構成主義の展開 構造構成的障害論の提唱(京極 真) 歴史学の信念対立を読み解く(多田羅健志) 構造構成主義的臨床心理学(高橋 史) 認知運動療法の新展開(村上仁之) 構造構成的英語教育学研究法(田中博晃) 人間科学的医学(斎藤清二) 構造構成的認知症アプローチ(田中義行) 構造構成主義的国家(上田修司) 構造構成主義的看護学(高木廣文) 構造構成主義とはどのような理論か(西條剛央) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ちなみに僕の論考の冒頭は,僕が昨年ここに書いた夢の話から始まります(続きは本誌にて)。 短い論考の中では,最も質の高い(そしてわかりやすい)論考になっていると思うので,関心のある方はどうぞ(構造構成主義とはどのような理論かわかると思います)。
2007/01/18
-
対談 甲野善紀×岡田慎一郎(2007年1月21日 新宿・紀伊國屋ホール(紀伊國屋書店新宿本店4F) )
甲野善紀先生と,その原理を介護に応用されている岡田慎一郎氏の対談が行われます。実技なども直接見れるとのことですので,古武術や介護に関心のある方は是非ご参加してみてください。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●第56回新宿セミナー@kinokuniya「対談 甲野善紀×岡田慎一郎」 (『古武術介護入門』(医学書院)刊行記念) 〔開催日〕 2007年1月21日 13:00~15:00(12:30開場) 〔講師〕 甲野善紀(武術研究者) 岡田慎一郎(介護支援専門員・介護福祉士) 〔開催地〕 新宿・紀伊國屋ホール(紀伊國屋書店新宿本店4F) 〔定員〕 400名(全席指定) 〔主なプログラム〕 「古武術+介護」という意外な組み合わせが、身体介助を「つらい」から「楽しい」に変えました。古伝の武術を参考に、独自の術理を探求する武術研究者・甲野善紀氏と、『古武術介護入門』著者である介護福祉士・岡田慎一郎氏による、初の公開対談。その実技を間近で体感できる機会をお見逃しなく! 〔参加費〕 1,000円 ※前売り券は2006年12月21日(木)より、紀伊國屋書店新宿本店5F「キノチケットカウンター」にて販売開始予定。 〔連絡先〕 紀伊國屋ホール 〒163-8636 新宿区新宿3-17-7 TEL (03)3354-0141(10:00-18:30受付) http://www.kinokuniya.co.jp/01f/event/shinjukuseminar.htm#seminar_56
2007/01/17
-

ポップ完成
ポップ,ひとまず完成した。 字が綺麗だったらいいのに,と本気で思った。 完成品をここにアップするのも憚られるのだが,書店に置かれるのだから,ここにアップできないようでは話にならない(観念するほかない)。 おまけ(京極真さんとのスカイプでのやり取りの一部) 京 「最先端から加速します!」ってのはどう? 西 意味わからんし(笑)「構造構成主義は未来からやってきた思想です」っていうのはどう?・・・なんかトンデモみたいになっちゃうか(笑) 京 最後に「西條@金星人」とか付けたら余計台無しやね(笑) 西 「ぶーんぶーん」とか吹き出しつけたりして(笑) 京 完璧台無しやね(笑)
2007/01/13
-

本のポップを書くことに
至文堂から『現代のエスプリ』のポップを手書きで欲しいと連絡がきて,ただ今どんなことを書くか思案中。ジュンク堂に平積みにしてもらえるみたい(そこに立てられるのだろう)。 もちろん平積みにして頂けるのはとても有り難いし、書いたことがないので,何を書けばいいのかよくわからない。 「現代思想の最先端がここにあります。 是非お手に取ってその動向を見定めて頂ければ幸いです」 ってな感じかなあ(感想や提案求む!)。 そもそもクロペンでいいのか,カラーの方がいいのか。。。綺麗な字かかなきゃだし。 はー。やったことないことにチャレンジするのは気が重いが,今年の抱負もあることだし,チャレンジしてみよう。
2007/01/13
-
今年の抱負
臥薪嘗胆,四面楚歌,五里霧中,五十歩百歩,初志貫徹,福利厚生,文明社会,形而上学,仮説検証,誤字脱字・・・いろいろ思い付くが、 今年の第一コンセプトは【チャレンジ】とすることにした。 日常生活においては安定志向なのだが、今年は意識的にチャレンジ精神を発揮したいと思う。 変化を恐れない。必要なことであれば苦手なことにもチャレンジする。そういうものの中に愉しさを見出すようにする。 第二コンセプトは【継続】。 「継続は力なり」ってやつだ。 この根本仮説を信じるのだ。 実は「毎日欠かさず継続する」というのは、相当苦手なことの一つ。 ゆえに、これを抱負に掲げるということは、今年の抱負は達成できない確率が飛躍的に高まることを意味する。 だから正直,掲げたくない。 が、今年の第一コンセプトは【チャレンジ】だから、この第二コンセプトにもチャレンジすることにした。 中学1年生のとき、唯一1年間365日欠かさず腕立て伏せをしたことがあった(50回ぐらいだけど)。 しかし、それが最初で最後で、僕は何かを意思の力で毎日欠かさず続けるということをしたことがない(今のところ)。 でも、僕のことだからうっかり忘れてしまうということはありそうだ。 その場合は、次の日にうっかり分もしっかりやればオッケーということにしておきたいと思う(←甘い)。 ということで、今年は、行動面では【チャレンジ&継続】を標語にがんばっていきます。 メンタル面では、8日の新聞記事で桑田投手が,斎藤に「応援してあげたい。純粋で謙虚な気持ちでやってもらいたい」とエールを送ったというのを読んで,自分も【純粋で謙虚な気持ち】を忘れないようにしようと(勝手に)思った次第です。
2007/01/12
-

「トレーニング・デイ」
年末年始はのんびりした実家ライフを送った。出かけたのは祖母の家(車で3分)にいったぐらい。 茶の間で、姪のゆらちゃんと遊び(遊んでもらい)、新年早々文字起こしをしつつ、めったに見ないテレビを見まくった。 で、夜中にテレビに流れている映画をみた。 全部観終わってから分かったのだが,『トレーニング・デイ』という映画だった(さっき調べてみたらなかなか評価の高い作品のようだ)。 http://www7a.biglobe.ne.jp/~pinery/movie/training.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 念願だったロス市警麻薬捜査課に配属された新人刑事ジェイクにとって、今日は勤務初日。彼のパートナーは数々の大物摘発で伝説となり、憧れの存在でもあるベテラン刑事アロンゾだ。やや緊張の面持ちでアロンゾと待ち合わせたジェイク。だが、のっけから唖然とさせられる。「か弱い子羊でいるか、獰猛な狼になるのか、それを選べ」。そう言うと、アロンゾは押収した麻薬をジェイクに吸わせる。意識を朦朧とさせながらアロンゾの捜査に同行するジェイク。そこで彼が見たものは職権乱用による過剰暴力、脅迫、証拠のでっちあげ、どんなモラルも通用しない犯罪捜査の最前線だった。翻弄するジェイクをよそにアロンゾの行動はエスカレートしていく。そんななか、アロンゾの昔なじみの情報屋から、ロシア人によるアロンゾ報復計画を聞き・・・。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 麻薬捜査官になったばかりの新米警官を、ベテラン刑事がいろいろと諭している。汚いことをやるのも仕事のうちだとかなんとか。 新米警官は完全な犯罪行為(殺人)を目の当たりにし、上に報告するという。ベテラン麻薬捜査官は巧妙に策略を巡らしていたため、そんな証言をしても、状況的に自分が不利になるだけだとして、次のようなセリフを言った。 「問題は事実じゃない、何を証明できるかだ!」 これは非常にアメリカ的だなあ、と僕は思った。そして一見説得力があり、これにまっとうに反論することは難しい。 じゃあ事実はどうでもいいのか? そうじゃないだろう(と思うのがまっとうな人の感覚のはず)。 しかし、論理的な形で反論することは容易ではない。確かに事実がどうであれ、証明できなければどうにもならないからだ(そもそも“事実”とは何かという難問でもある)。映画の主人公も、逆らったものの、論理的に反論することはできなかった。 僕も,以前から違和感はあったし、何か言い当てられそうな感じはあるけど、はっきりとはわかっていなかった(そのうち考えようと思っていたけども、考える機会がなかった)。 で、この映画を通して,その違和感を解消する理路をみつけた。そういう論難にはこう答えれば論理的に論駁できる(解消できる)んだなということがわかった。分かってしまえばどうということもないのだけど、今回明示的に認識できたことは、哲学的・認識論的には意義ある進展だと思う(内容についてはいずれどこかに書きたいと思います)。
2007/01/09
-
あけましておめでとうございます。
昨年は大変お世話になりました。今年もどうぞよろしくお願いします。 さて、実家に帰ってきて、姪と遊びながら久しぶりに皆でテレビをみていました。 大晦日はとりあえず、K-1をみてみましたが、あの引っ張り方というか、過去の映像と今日やった試合がわざとわからなくしているのはどうかと思いました。それだけならまだしも、今日ちょっと前にやった試合も、さぞかし今ライブでやっているかのように再度流す商業主義にはうんざり。みんなで「こりゃ反則だ」ということでチャンネルを変えました。なんか「視聴者をバカにしてんのか」と感じさせる番組はサイアクですね(谷川さんとか変わらないとダメなんでしょうね)。 で、以下は妹とCDTVをみながら、特にモーニング娘の過去の映像みていて思ったこと。 モーニング娘。は、流行に流されやすい日本の浅はかな部分が最も反映されているようであまり好きじゃなかったのだけど、登場した頃からのVTRを俯瞰してみてみると、ああ,これは「諸行無常」を尤も体現しているなあと思ったのでした。 あるいは、方丈記の一節「ゆく河の流れは絶えずして,しかももとの水にあらず」を彷彿させるとでも申しますか。 まあそれはどうでもいいんですけど(←いいのかよ)、やっぱりあれですね、芸能界や音楽業界も、企画モノとか勢いだけで出てきた一発屋は、消えますね。 どこの業界も実力がないと生き残れないんだなあと思った次第です。 とはいえ、実力が妥当に評価されるとは限らないのだけども、それでも大きな流れでみれば、卓越した実力のあるひとはひとたび誰かに見出されれば,残っていくものなのかもしれないと。 そういう意味ではこの移ろいやすい人の世も,ある程度信じていいのかもしれない、とあらためて思った次第です(まあもとより信じてはいるけども)。 話は変わって,2006年最後に読んだ本を発表したいと思います。 最後に読んだ著書は、『現代のエスプリ(特集 構造構成主義の展開ーー21世紀の思想のあり方』でした。って、手前味噌ですいません。ちょうど出版社から届いたから読んだというだけのことなんですが。 しかし、この本はやっぱおもしろいです。池田先生と電話で話したら、池田先生もすぐにほとんど読んでお面白かったとおっしゃっていまして、「あの論考はあれはあれだけどあれだよね」「そうなんですよねああいう意味ではあれはあれはあれなんですが意外にあれですよね」とか話していました(なお、2006年の最後に電話で話した人は池田清彦先生でした。ラス2が甲野善紀先生でした。ラストメールをしたのは大学院の後輩のHさんでした)。 さて、最後に読んだ漫画本は『PLUTO』(1~4巻)でした。そうあの手塚治虫の作品を浦沢直樹が独自の視点から新しい作品にしてしまったあれです。 http://www.amazon.co.jp/PLUTO-1-浦沢-直樹/dp/4091874312 ほんとウカツでした。昨年最もウカツだったなあと思ったことはこの作品のことを知らなかったことといっても過言ではないでしょう(いや噂はどこかで聞いていたけどもどうせあれだとと思って読んでなかった)。 これは1巻で涙が出てきましたね(新幹線の中で)。浦沢直樹の作品は、『パイナップルアーミー』とかちょっと前の作品も好きなのですが,これは最高傑作かもしれません。 ちなみに『21世紀少年』などは売れているみたいですが、僕にいわせれば、「おいおい、いつまでも謎めかせればいいってもんじゃねーぞ」というべき駄作だと思います(言い過ぎ:ファンのひとスイマセン)。 ともあれ『PLUTO(プルートウ)』は、まだ読んでいない方は本年初のオススメ本です。 では、そういうわけで?今年もよろしくお願いします。 (ほろ酔い日記でスイマセン)
2007/01/01
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- 韓国での食事(11月 12日)
- (2025-11-15 02:35:31)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 立花孝志容疑者を名誉毀損罪で起訴……
- (2025-11-28 17:00:05)
-
-
-
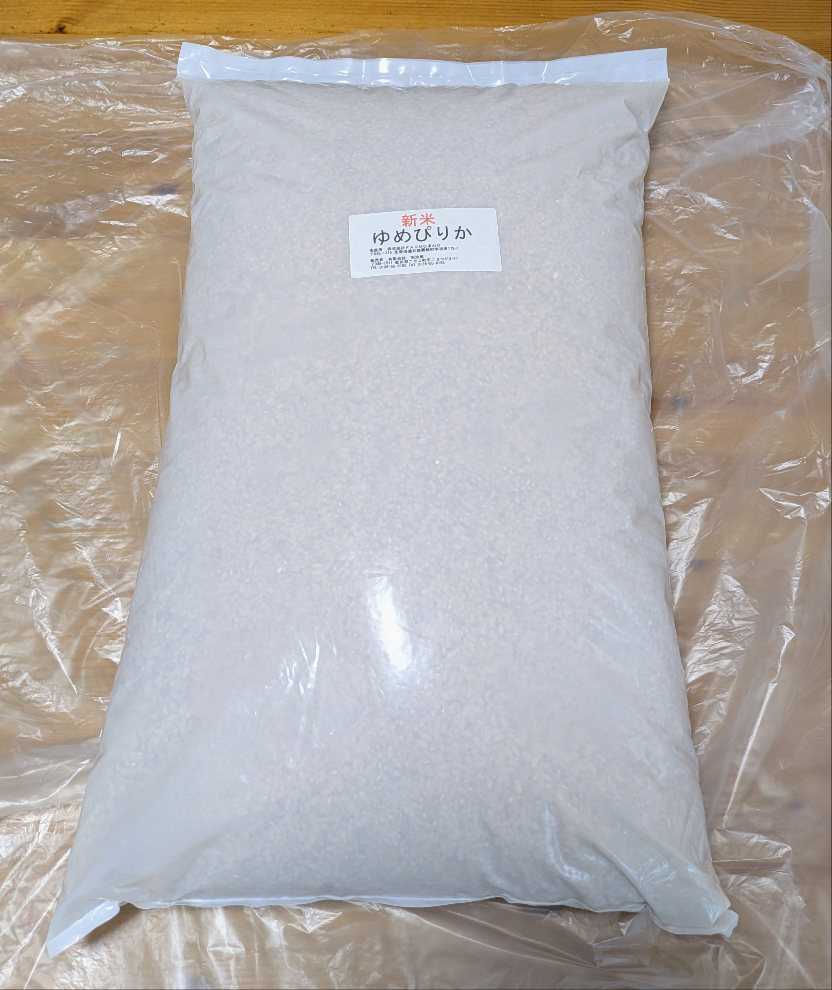
- みんなのレビュー
- 【レポ】コイン精米初挑戦 ゆめぴり…
- (2025-11-28 14:30:04)
-







