PR
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(1)読書案内「日本語・教育」
(21)週刊マンガ便「コミック」
(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝
(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」
(58)演劇「劇場」でお昼寝
(2)映画「元町映画館」でお昼寝
(103)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝
(13)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝
(107)読書案内「映画館で出会った本」
(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」
(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」
(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり
(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」
(24)読書案内「現代の作家」
(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」
(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり
(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ
(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」
(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」
(30)読書案内「近・現代詩歌」
(50)徘徊「港めぐり」
(4)バカ猫 百態
(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」
(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」
(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」
(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝
(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝
(14)映画「パルシネマ」でお昼寝
(41)読書案内「昭和の文学」
(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05
(16)読書案内「くいしんぼう」
(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝
(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」
(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」
(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」
(32)ベランダだより
(130)徘徊日記 団地界隈
(108)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり
(24)徘徊日記 須磨区あたり
(26)徘徊日記 西区・北区あたり
(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり
(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc
(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」
(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり
(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」
(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」
(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」
(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」
(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」
(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」
(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」
(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて
(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」
(13)映画 パレスチナ・中東の監督
(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」
(7)映画 韓国の監督
(22)映画 香港・中国・台湾の監督
(29)映画 アニメーション
(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢
(47)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭
(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行
(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督
(36)映画 イタリアの監督
(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督
(14)映画 ソビエト・ロシアの監督
(6)映画 アメリカの監督
(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発
(5)読書案内「旅行・冒険」
(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」
(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督
(4)映画 フランスの監督
(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督
(10)映画 カナダの監督
(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督
(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督
(6)映画 イスラエルの監督
(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督
(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督
(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督
(5)映画 トルコ・イランの映画監督
(8)映画 ギリシアの監督
(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督
(2)映画 ハンガリーの監督
(4)映画 セネガルの監督
(1)映画 スイス・オーストリアの監督
(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家
(1)読書案内 ジブリの本とマンガ
(5)週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)
徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり
徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」
ロディ・ボガワ ストーム・トーガソン「シド・バレット 独りぼっちの狂気」シネリーブル神戸no244
NTLive サム・イェーツ「ワーニャ」シネリーブル神戸no245
週刊 読書案内 村上春樹「村上春樹 翻訳 ほとんど全仕事」(中央公論新社)
フリーヌル・パルマソン「ゴッドランド GODLAND」シネリーブル神戸no238・SCCno21
アグニエシュカ・ホランド「人間の境界」シネリーブル神戸no243
週刊 読書案内 村上春樹 柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」(文春新書)
コメント新着
キーワードサーチ
小西甚一「古文研究法」(ちくま学芸文庫)
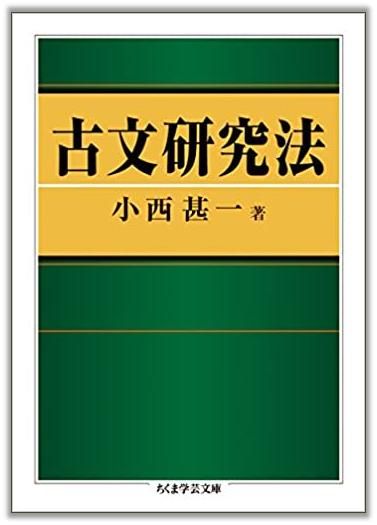 ちくま学芸文庫
で復刊されるずっと前、こんなことを高校生相手に書いていました。とてもさっこうんの高校生の手におえる参考書とは思えなかったのですが、ハッタリ気分で書いていたら復刊されて驚きました。
ちくま学芸文庫
で復刊されるずっと前、こんなことを高校生相手に書いていました。とてもさっこうんの高校生の手におえる参考書とは思えなかったのですが、ハッタリ気分で書いていたら復刊されて驚きました。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
古典の授業をしていて、自分が物を知らない事をつくづく感じています。勉強するべきときに勉強せんとこういうオトナになる、なんて説教をたれる気はありません。しかし、授業中に困っても、まめに調べる気力も最近は失われていて、これは、正直ヤバイのですが、高校生諸君に対しては、せめて参考文献ぐらいは紹介しようという次第です。
そう思いついたのは、なかなか殊勝な態度なのですが、残念ながら受験参考書の類は自分自身が30数年前、必要に30迫られて読んだ、「ある参考書」以来まじめに見たことがないからよく知らないのです。
皆さんが「そんないい加減なことでいいのか!」と怒るのももっともです。しかしね、時々本屋さんが「見本に」といって持ってくる最近の参考書の類はみんな、あの頃読んだ「ある本」の換骨奪胎に見えるのですよ、ぼくには。
「肝」になる文学思想は捨て、外観は似せているが、全体を支える「骨」はありません。やればとりあえず点は取れるようになりますが、古典に対する教養はせいぜい枝葉しか身につきません。クイズに強くなる豆本化しいて、パターンと頻出例を繰り返すだけで味も素っ気もありません。結局、面白いのは、面白くもないゴロ合わせだけという始末です。みんな「当てもん」に強くなるためのテクニックなのですね。
皆さんを試そうと待ち構えている「センター試験」や「模擬テスト」が、要するに「当てもん」なので、そうなるのはよくわかります。世間のパターンもそうなっているようですから、ある意味「合理的」なのでしょうね。でも、それって 「バカじゃない?!」
ってことじゃないでしょうか。
極論かもしれませんが、センター試験の古典で点を取るのは、実は簡単です。一年生で使った教科書がありますね。あれで、漢文はすらすら書き下せること。だから、読めればいいわけですね。古文はすらすら訳せること。それだけ八割は大丈夫です。あの薄い教科書一冊、本文だけでいいです、すべて暗唱できれば、センターなら満点は確実です。
ウソだとは思うが、一度だけ シマクマ を信じてやろうという人は、この夏休みがチャンスです。せっかくですから、課題の問題集で試してください。
古文、漢文それぞれ 15
題ありますね。一日、一題づつ、計二題、ノートに本文を写してください。訳や解説は、適当に読んで、線でも引きながらで結構です。これを二往復してください。
狙いは古典の本文を丸ごと頭に入れることです。二度目に口語訳がつっかえるようならもう一度やってください。その結果 10
月のマーク模試で、あなたの古典の偏差値は 10
点アップしています。もとが30点台の方は15点から20点上がります。すると文法で説明したくなります。
でもね、点数が上がって勘違いしてはいけないことがあります。模試の数値は古典文学読解の実力を保証しているわけではないということです。それは忘れないでください。放ったらかしてしまうと、すぐに下がります。
で、話を戻します。読む練習ができて、さあ、ここから必要になる本を参考書と呼ぶのです。ぼくが受験生の時に出会ったある本とは 小西甚一 という人の 「古文研究法」 という本ですが、本物の参考書でした。
小西さん
のその参考書は 「古文とは何か」
という大胆な問を設定して受験生に説明しようとしていました。ぼくは読んでいて眠くてしようがなかった記憶があります。アホバカ高校生が 「古文とは何か」
なんて考えるはずがないわけで、考えたとしても 「退屈である」
という答えしかなかったはずですから、眠いのも当然でした。しかし、ずっと後になって、この参考書のすごさに納得するのです。
ぼくの場合は大学生になって、この人の 「日本文学史」(講談社学術文庫)
を読んアレっ?と感じた時でした。
「古文研究法」
は受験参考書の面(つら)はしていますが、実は日本古典文学概論だったんです。気付いた結果、この人の 「俳句の世界」(講談社学術文庫)
とか、その他の著作を探したりしましたが、要するに、お弟子さんにしてしまうん本だったんです。
実をいえば、 小西甚一
という人は中世文学のエライ学者で、なぜか受験参考書もたくさん書いていますが、例えば 「俳句の世界」
なんて、素人にもとても面白い本です。受験参考書で。そういう参考書もあるということを忘れないでください。
とか言いながら、この本は手に入らないでしょう。古すぎます。学術文庫の方でも読んでみてください。
いつものように 「なんのこっちゃ」
という話でした。

ボタン押してね!
ボタン押してね!


-
週刊 読書案内『高等学校における外国に… 2022.02.02
-
週刊 読書案内 荘魯迅「声に出してよむ… 2021.07.11
-
週刊 読書案内 山田史生「孔子はこう考… 2021.04.17










