読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」 20
読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」 15
読書案内「BookCoverChallenge」2020・05 16
読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて 5
映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督 6
[読書案内「現代の作家」] カテゴリの記事
全100件 (100件中 1-50件目)
-

週刊 読書案内 いしいしんじ「いしいしんじの本」(白水社)
いしいしんじ「いしいしんじの本」(白水社) いしいしんじの文章が好きなのですね。 で、市民図書館とかの新入荷とかの棚で見つけるとかならず借りるんです。横着なので日本の作家の「イ」の棚に行ったりはしないんです。 で、今回も新入荷の棚で見つけたのですが、ほぼ10年前、2013年の一刷の本で、???だったのですが、やっぱり楽しく読みました。 書評とか、まあ、流行の言葉でいえばブックレビューとか、文庫本の解説とか、新聞の文芸欄の記事とかを集めたエッセイ集でした。 いしいしんじのなにがどう好きなのかと問われると返答に困るんですね。好きだから好きだというしかないところが、多分、彼の文章の特徴だと、まあ、ボクは思っているわけで、たとえばこんな本の紹介があって、よしよしなのです。『ペルソナ』鬼海弘雄鬼海弘雄が今日も写真を撮りつづけているというのは、おおげさでなく、人類の希望だと思う。このように人間を見、人間の姿をこの世に残すことが、ひとりの人間にできるというのは、この現代においてほとんど奇跡。『ペルソナ』は、写真集はもうこれ一冊でいいという本。ときどき、本はこれ一冊あれば、という気持ちにもなる。(P201ふたば書店選書リスト2011「おすすめの30冊」) で、そのとなりに斎藤道雄の「悩む力」、もうちょっと先に「海街dairy」だったりします。「海街dairy」吉田秋生よくいわれていることかも知れませんが、小津安二郎の作品を想起させます。けれども、ある意味小津を超えている。日本漫画にしかできないことが、ここでは易々と、あらゆるページ、あらゆるコマのなかで魔法みたいに達成されている。鞄に入れて持ち運べル、ポータブル鎌倉。波音や蝉時雨、谷をわたってくる風音つき。(P204) まあ、書きかたもですが、ラインアップがいいですね。手元に置きたい本ですが、やたら買いの結果の積読の山の再来に陥るのが怖いので、市民図書館です。 とりあえず、目次を載せておきます。一つ一つの文章が短いので、ちょっと、大変な量ですが、後ろに、そこで話題になっている作品名、書名、をつけました。作家の名前も付ければいいのですが・・・、一応クイズということで(笑)。 まあ、ボンヤリ眺めていただければいいかなと。ボクは新しい本と出合うのが嬉しくて、こういう本を読むことが多いですね。目次はじめに ティーンエイジャーのいしいしんじ 「婦人画報」韓国のひとたちへ 「トリツカレ男」本を読んで大きくなる 「漱石・太宰・賢治」みさきのすきま 「エクソフォニー他」浮遊する世界 「パンク侍」アメリカの幸福 「世界のすべての八月」林芙美子の庭 背中のなかの巨大な手 「もうおうちへかえりましょう」問いかける言葉 「自分と自分以外」ケストナーさんへ 軽々と歩くひと 「恋するように旅をして」サイン本の絵柄 旧制高校の必読書 「愛と認識との出発 他」詩の起源 「おわりの雪」舞い降りる物語の断片 「おわりの雪」「わからないもの」のかたち 「ハミザベス」主人公の気持ち 「梶井 他」うみうしのあわい 「ポーの話」ふたりの旅人 「200X年文学の旅」本が置かれる棚 「アメリカの鱒釣り」仕事をしていない人間はひとりもいない 「流刑地にて」他円、矢印、方形 「残光」わからなさの楽しみ 「こどもの一生」本は向うからやって来る 「ジャコメッティ」収縮する距離 「海」ことばをドリブルする 「聖女チェレステ団の悪童」イリノイの夏 「レイ・ブラッドベリ大全集」「もの」にまつわる「ものがたり」 「古いものに恋して」寄席に入ってきいてみる 「圓太郎馬車」巡礼路の光景 「たいようオルガン」「めくり終える式」読書 「天才バカボン」他洞窟ツアー 「たいようオルガン」中原中也の詩を読む、という出来事流れていくに委せる 「ノルゲ」自分でハワイをやる 「金毘羅」他多数文章が「揺れ動く」 「土星の環 イギリス行脚」闇の中の物語 「灯台守の話」書くということ 「大竹伸朗」霧のなかの本 「きりのなかのサーカス」透明な穴に飛び込む 「中島らも」動物ばかり 「白痴」(ドストエフスキー)中国という感覚にのみこまれる 「転生夢現」時間に遅れる子ども 「走れメロス」他ページのむこうの特別な時間 「原っぱと遊園地2」笑える本 「吾輩は猫である」他開かれた小説 「ボディ・アンド・ソウル」とっておきの秘密の沼で 「四人の兵士」ボロボロになった背表紙 「デカルトからベイトソンへ」多次元のスポロガム 「大洪水」広大な宇宙の暗み 「見えない音、聴こえない絵」ふたつの北極 「極北で」大正時代の聖書 ハマチとの子 「夏の水の半魚人」金木町のブルース 「津軽」他厚い本に手が伸びる 「魔の山」他西脇順三郎という水を飲む 「葦」見えないけどそこにある 「冥途」他鬼海村と戌井村 「まずいスープ」「夢」と「ロマン」 「真鶴」他小説を「生きる」時間 「坊っちゃん」他様変わりする風景 「がらくた」本はSP盤のように 「メイスン&ディクソン」他乱反射するいのち 「馬鹿たちの学校」トーマス・マンの菩提樹 「魔の山」おすすめの三十冊 「灯台へ」他目がさめるまでの時間 「火山の下」他寝ているあいだに小説は育つ 「ジュージュー」名指ししたことのない光 「星へ落ちる」たちのぼり、流し去る 「ウォーターランド」大坂で笑い、のたくることば 「あめりかむら」人間を拡げる心地よい違和感 「野生の探偵たち」他まどろみの読書 「失われた時を求めて」ともに歩いていく仲間 「野蛮な読書」妄想の花 「円朝芝居噺 夫婦幽霊」猫の卵 「ふしぎなたまご」たくらみと、自然なふくらみ 「持ち重りする薔薇の花」まわりつづけるノイズ 「一一一一一」戦うボニー 「ぶらんこ乗り」みんなと「ともだち」 「サブ・ローザ」目で読む音楽 「注文の多い料理店」他ブラジルから響く、遠い新しい声 「遠い声」(松井太郎)「はじめて」の作家 「ブラッドベリ」ふくらみの物語 「許されざる者」恋愛の幾何学模様に風が吹いて 「ひらいて」小説を書いているあいだ 長新太の海 塗師のうつわ 「名前のない道」 いや、ホンマに膨大になりました。ここまでお付き合いご苦労様でしたね(笑) 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)
2024.11.05
コメント(0)
-

週刊 読書案内 岩井圭也「われは熊楠」(文藝春秋社)
岩井圭也「われは熊楠」(文藝春秋社) 岩井圭也という人の「われは熊楠」(文藝春秋社)という、南方熊楠という人物の生涯を描いた伝記小説を読みました。 岩井圭也という人の作品を読むのは初めてですが、直木賞の候補に選ばれた作品のようです。南方熊楠という、明治から昭和にかけて生きた人物の生涯を追った作品でした。南方熊楠って誰?なんて読むの? 若い人たちには、まあ、そういう感じで受け取られる人物であり、名前なんじゃないかと思いますが、実は、かなり有名な方で、伝記を小説化した作品では、ボクが読んだことのある作品だけでも、かなり古いのですが、1980年代の終わりころの作品で、神坂次郎の「縛られた巨人 南方熊楠の生涯」(新潮文庫)、津本陽の「巨人伝」(文春文庫上・下)という、それぞれかなりな大作(内容は覚えていませんが)がすでにあります。 それから、たとえば、1990年ころですが、当時、ニューアカの旗手の一人だった中沢新一というような人も「森のバロック」(せりか書房・講談社学術文庫)とか、「熊楠の星の時間」(講談社メチエ)とかで繰り返し話題にしていて、多分、ある種の熊楠ブームだったんでしょうね。 ボク自身は興味を持っていて、結構、読んだ人ですが、ああ、そうそう、坪内祐三という方に「慶応三年生まれ 七人の旋毛曲り 漱石・外骨・熊楠・露伴・子規・紅葉・緑雨とその時代」(講談社文芸文庫)という面白い評論?エッセイ?にも名前が出てきますね。 ちょっと話がそれますが坪内祐三のこの本は「明治」という時代に興味をお持ちの方にはおススメですね。司馬遼太郎の「坂の上の雲」(文春文庫・全8巻)が、到達点からの振り返りだとすれば、こっちは、慶応三年というのは、翌年が明治元年ですからね、明治と同い年の人物たちの生きざまを始まりからの視点で追ったという意味で面白いですね。 というわけで、南方熊楠、みなみかたくまぐす、くまくすと読む場合もあるようですが、慶応3年生まれの一人である彼が何者だったのか? というわけですが、慶応3年、1867年5月18日に生を受け、昭和16年、1841年12月29日に亡くなるまでの74年間、坪内風にいうならつむじを曲げ続けて、学問だけを生きた人です。天才とか、奇人とか、孤高の巨人とか、大博物学者とか、まあ、いろいろの呼び名がありますが、ボクには、その正体を一言でいう根性も知識もありません。だって、粘菌とか、曼荼羅とか、大英博物館とか。だいたい、粘菌って、わかります?(笑) でも、やっぱり気になるんですよね。で、まあ、目の前にこういう本があると読んでしまうわけです。 もし、ウキペディアとかで調べてみて興味がわくようなら、この「われは熊楠」を読むと、熊楠の生涯のあれこれが、まあ、年齢に沿ってとても分かりよく描かれていて、ああ、そうか、面白い人だな! と腑に落ちます(笑)。 本書は、それぞれ、第1章「緑樹」から第2章「星花」、第3章「幽谷」、第4章「閑夜」、第5章「風雪」、そして第6章「紫花」と題し、6章立てで、南方熊楠の生涯を追っています。 和歌浦には爽やかな風が吹いていた。 梅雨の名残りを一掃するような快晴であった。片男波の砂浜には漁網が拡げられ、その網で壮年の漁師が煙管を使っている。和歌川河口に浮かぶ妹背山には夕刻の日差しが降りそそぎ、多宝塔を眩く照らしていた。 妹背山から二町ほどの距離に、不老橋という橋が架かっている。紀州徳川家の御成道として、三十数年前に建造されたものであった。弓なりに反った石橋で、勾欄には湯浅の名工の手によって見事な雲が彫られている。 その雲に、南方熊楠はまたがっていた。(P5) これが書きだしです。で、ネタバレみたいですが下が結句です。 人魂となった熊楠は、夏野原を駆けていく。熊楠は世界であり、世界は熊楠だった。沖の方角から、爽やかな海風がふわりと吹いた。 それは、熊楠がこの世に生を受けた日の風であった。(P128) 生まれたときから、魂となって飛び去って行くまで「爽やかな風」に吹かれて生きた男というのが、この作家の南方熊楠です。だからでしょうね、希代の奇人の生涯を気持ちよく読み通すことが出来ます。 まあ、そこがこの作品のよさでもあり、物足りなさでもあるのでしょうが、ボクは、この若い作家が、今時、南方熊楠なんぞに挑んで「こんな人がいた!」 と世にさしだしている姿勢というか、態度に好感を持ちました。なんとなく、一つの時代が終わりつつあることをボクは、実感というか、肌合いというかでは、かなり、リアルに感じています。新しい時代が、新しいはじまりの時代なのか、破滅の時代なのかはともかくとして、とりあえず、南方熊楠なんていう、変人に関心を持つ人がいることに、何となくな期待と希望を感じます。若い人に読んでほしい作品ですね。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)
2024.11.03
コメント(0)
-

週刊 読書案内 山下澄人「月の客」(集英社)
山下澄人「月の客」(集英社) 山下澄人の「月の客」(集英社)を読みました。2020年に出たときに買って、もう、何度目かです。 最初に読むときに「月の客」やし! とか思って、米くるる友を今宵の月の客 芭蕉此の秋は膝に子のない月見かな 鬼貫岩鼻やここにもひとり月の客 去来 こんな句を思い浮かべました。まあ、それぞれ江戸時代の有名な句ですが、今更でボクがいうまでもありません。どれも、イイ句ですね(笑)。ことばが描いている世界を月の光がほのかに照らしていて、ほんのり明るい、さすがです。 で、山下さんの「月の客」ですが、何度読んでも、まあ、これらの句が関係あるような、ないような、でも、作品世界を月の光が照らしていることは、確かなのですが、だからどうだといわれれば困りますが、まあ、そういう小説です。 ネットでよめる集英社の作品紹介に「小説の自由」を求める山下澄人による、「通読」の呪いを解く書。とあって、まあ、大変なのですが、続けて登場人物と物語の展開につて 父はおらず、口のきけない母に育てられたトシは、5歳で親戚にもらい子にやられた。だがその養親に放置され、実家に戻ってきたのちトシは、10歳で犬と共にほら穴住まいを始める。 そこにやってきたのは、足が少し不自由な同じ歳の少女サナ。サナも、親の元を飛び出した子どもだった―。 親からも社会からも助けの手を差し伸べられず、暴力と死に取り囲まれ、しかし犬にはつねに寄り添われ、未曽有の災害を生き抜いたすえに、老い、やがていのちの外に出た<犬少年>が体験した、生の時間とは。 という、エライ詳しい紹介までついています。なんで、こういう、ネタバレともいえる紹介が? ですが、お読みになればすぐにわかります。読み終えて、この紹介を読みなおして、問題は、それで、わかったのかどうかということなのですが、ああ、そうだったのか !? と、ようやくわかる作品だからです(笑)。 土手へ出て、下りる、草がはえている、草を踏んで下りる、砂利の道を横切り、再び草地、そしてかたい土、これは確かグラウンド、子どもが野球をする、子どもの声が聞こえて来る、聞こえてくるようだ、聞こえてはいない、足跡がいくつも、小さい足跡、いぬがにいをかいでいる、空は晴れて相変わらず大きな月が出ていて 月はな十五夜かけて満月になんねん その反対は真っ暗、新月、真っ暗 かぐや姫も、手ぇ伸ばして、見えへん見えへん、言うて み、み、水―、や、 ヘレンケラーやん 知らんの? あんた何にも知らんな (P4~P5) 最初に、空に月が出ているシーンです。 穴の前でトシが寝ている、死んでいる、横にいぬがいる、いぬはトシのにおいをかいで、横になる。腹が減ればいぬはトシを食べる大きな月 月から見えている星は、止まったりしない、音もない、時々何かが白く走っては消える、生きものは、もう見えない、見えないが、いる、たくさんの、しかし、それは、いつまで、続く、 もうしばらくは このまま、続く(P189) 最後の最後、実は、月は作品の中でくりかえし描写されますが、これが最後の最後の月です。解説によれば、主人公で、ひょっとしたら語り手だったかもしれないトシと呼ばれる少年、ひょっとしたら、最後はオジサンは、このシーンでは、もう、死んでいて、隣にいぬ、ひょっとしたら主人公だったかもしれない、いぬ、がいて、月が出ています。 ここまでやってきた小説世界のこのシーンには、ここまで、どのシーンにも、ずっと、あったのに、なくなっているものがあります。「声の響き」ですね。み、み、水―、や、ヘレンケラーやん知らんの?あんた何にも知らんな 最初の引用のシーンで、誰が誰に語りかけているのかは定かでないのですが、神戸暮らしのボクには異様にリアルな、そう、神戸弁なんですね、声が響き始めて、180ページの作品中、ずっと、響き続けています。 紹介に「犬少年」とありますが、最後まで、主人公であるらしいトシが犬少年と呼ばれていたことに、ボクは気付きませんでした。 あるのは、誰かが、作品中の誰かになのか、読み手のボクになのか、「知らんの?あんた何にも知らんな」 という声だけでした。 で、最後は、月は空にあるようで、誰の声なのか、もちろん、わからない、静かな声が響きます。もうしばらくはこのまま、続く 文字で書きつけるほかに方法がない小説に「声」を響かせん! とする荒業です。大したものです。 山下澄人が、お芝居の演出家であることは知っていましたが、どんなお芝居をやっていらっしゃるのか?ちょっと見てみたいものですね。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)
2024.10.18
コメント(0)
-

週刊 読書案内 町田康歌集「くるぶし」(COTOGOTOBOOKS)
町田康 歌集「くるぶし」(COTOGOTOBOOKS) えーっと、今日の案内は、あの町田康の歌集です。歌詞集ではなくて。ミソヒトモジ(三十一文字)の短歌集です。町田康歌集「くるぶし」.COTOGOTOBOOKSという出版社です。 市民図書館の新刊の棚にありました。まいりました!(笑) 町田康でした。意味不明でした。「ボンジョビ」、「モカシン」、「中目黒」、「生肉」、「尻子玉」、全部で五章、歌の数は三百五十首あまり、率直にいいますとなめとんかチュッパチャプスなめとんかしばきあげんど人らしくしろ という気持ちです。 まあ、本書の中にあった彼自身の歌ですが、とか何とかいいながら、ポストイットとか貼りながら最後のページまで読んだボクも暇ですね。 開巻第一首から、最後の「天の原」まで、別に分かったわけじゃありませんが、章の題になっているとか、そういういい加減な理由ですが、選んでみました。上の歌と合計二十首です。ボンジョビあの時の愛と勇気と感動が今は呪いとなりにけるかも春山も破損しまくるボンジョビの予想もしない尻の入口くるぶしは俺の心の一里塚夜の心はみなの禿山共感の乞食となりて広野原彷徨いありく豚のさもしさモカシン軍服で歩んでいけよ遠い道ユニセックスの裾もからげて花柄は今も巷に流行れども俺は鉄無地行きて帰らずモカシンで歩んでいけばチンチラも笑ひ転げる山の細道葛餅に栗揉み込んでしたり顔千林から変わる人柄中目黒百圓がシートの下に落ちてもて二度と取れない夏の暑い日もはやもうなにもしないでただ単に猫を眺めて死んでいきたい五分ほど迷うて買う柏餅みんな悲しく自分なんだよ阿保ン陀羅しばきあげんど歌詠むなおどれは家でうどん食うとけ生肉ブラジルの生肉だけを食べ続けあの日のサンバ鳴りて止まらず筋力を全部なくして鬱勃と漲るパトス行くえ知らずもその道は通行止めだ諦めろ海の底から呼ばう霊魂ボコボコにどつき回したヘゲタレが上司になってもうて半泣き尻子玉作るなよ自在自由に作られろ豚に生まれろそれが歌やぞおのこらが何も言わずに尻子玉ズバズバ出して歩む細道天の原ふりさけみれば春日なるアンガス牛に出し月かも いかがでしょうか。ちょっと、この歌集探してみようかな? とか、まあ、思いませんよね(笑) でもまあ、町田康ですよね、やっぱり(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)
2024.09.17
コメント(0)
-

週刊 読書案内 村田喜代子「龍秘御天歌」(文藝春秋社)
村田喜代子「龍秘御天歌」(文藝春秋社) 2024年、まあ、今年の夏のはじめに「ちゃわんやのはなし」という、十五代沈壽官さんという、薩摩焼の当主を追った、実に味わい深いドキュメンタリー映画を見たときに、思い出した本が三冊あったのですが、その一冊が、今日案内するこの小説です。 村田喜代子の「龍秘御天歌」(文藝春秋社)ですね。1998年、ですから、25年も前に「文学界」に発表され、その後、単行本として出版され、今では文庫で読むことができる作品ですが、映画で、歴史事実の解説として、アニメーションで描かれていた薩摩焼の初代と同じく、まあ、「ちゃわんやのはなし」の登場人物たちは500年の歴史の中を生きていらっしゃった! わけですが、本作は、同じ、慶長の役で拉致されて、日本で窯を開いた朝鮮の陶工の初代の葬式を、慶長の役、丁酉(ていゆう・ひのととり)倭乱から、ほぼ、50年後の江戸時代初期という時代と、黒川藩という、多分、有田あたりに架空の藩を設定することで、小説的想像力を奔放にふるって描いた作品! です。 初七日を迎えると、忌中の家はいちおう普段の暮らしにもどる。龍窯で知られた辛島家にも精進落としの日がやってきた。朝の内に檀那寺の願正寺で内輪だけの法要をすませた。その後に精進落としの酒肴を弔問客に出すのだが、これは皿山の土地柄で一日の窯仕事が終わった夕方から席を設ける。 これが書きだしですが、すでに、日本名を名乗っている龍窯という窯の窯元、辛島家の初代、当主、十兵衛が亡くなり、通夜、葬儀、埋葬が滞りなく終わったかの初七日の法要のシーンから始まりますが、ここから250ページ、小説が描いているのは一人の人間の死と魂のゆくへをめぐる、夫婦、親子、一族のドラマ でした。 引用個所から、亡くなった十兵衛の跡取り、長男の十蔵が、参会者に向かって挨拶を始めますが、描かれるのは屋敷の客間、中の間、下の間に集う50人を越える人間たちの、一人一人の身分、年齢一覧でした。 上の八畳間は外からの客で、顔ぶれはこうだ。 皿山代官所からは、下目付の柳番太郎。取り締まり方の市田佐内。町役からは、赤絵付庄屋の団六。大散使の問屋おこない屋喜平。村役の俵山窯焼き宗八。別当の河原山窯焼き藤次郎。散使の窯焼き亀平。被官の豊田常臣。 中の間は窯の働き手たちで占められていた。ざっとこうである。 喪主十蔵は四十四歳。故十兵衛の妻の百婆、七十歳。故国朝鮮の習慣で女隠居は通り名で呼ぶ。百婆とは窯の者がつけた尊称だ。次男、ロクロのの以蔵、三十三歳。四男で同じく窯焚き兼良、三十三歳。十蔵の長男でロクロの兵太、二十歳。次男でロクロの参平、十七歳。以蔵の長男で窯焚きの以助、十九歳。次男で窯焚きの以作、十七歳。雇い人でロクロの権十、七十歳。権十の長男で同じくロクロの清助、四十歳。次男で同じくロクロの市次、三十七歳。故万治の長男で窯焚きの寅吉、四十七歳。次男で同じく窯焚きの熊吉、四十五歳。万治の女房で呉須すりのアカ、六十八歳。釉かけの伊十、七十二歳。 下の八畳には十蔵の嫁で型打ちのコシホ、三十八歳。以蔵の嫁で同じく型打ちのオクウ、三十七歳。元良の嫁でだみ手のアカイ、三十一歳。兼良の嫁でだみ手のイヌ、二十五歳。他に雑役の荒仕子、薪の皮はぎなど住み込みの者たちと、辛島家の子供たち十数人で、締めて五十余名。 ここまで、この初七日の席に座っている人の名前を真面目に読んできた人はえらいと思います。写しているボクも、ちょっとエライ。で、何で、この個所を引用したのかといいますと、一つは葬式とはこういうものである! という作家の視線というかを、とりあえず紹介したかったわけです。ここではまとめて引用しましたが、作品では、一人一人、行分けして描かれています。 で、二つ目は、今、この席に座っている伊十という、辛島十兵衛と流浪を共に生きてきた老人がどんな気持ちでここにいるかというところから、この七日間に、辛島家の葬儀の現場でおこったドラマ、つまりは作品全体の二重構造が見え始めるという、とっかかりを、案内しないわけにいかないと思ったからですね(笑)。 七日目に行う日本の精進落としじたい、伊十には納得がいかない。坊主がきて経をあげた後は飲み食いだけで忌み明けとなる。伊十の故国では死者を出した家は、三年間も忌み明けはできない。葬式後七日目といえば、喪主は故人を埋めた墓地に仮小屋を建てて寝泊まりし、仕事もなげうって朝に晩に膳を差し上げ、地へ頭をすりつけて礼拝に励んでいる頃だ。国が異なると弔い方も違うのは仕方がないが、何と想いの薄いことだろう。 目脂にかすむ目で伊十はもう一度、座敷中を眺めた。すると賑や耀かな人々の背後に、白麻の喪帽に喪服をつけた影法師のような一群がぼーっと居並ぶのが見えた。異相の彼等は動かず塑像のようでもある。しかし顔を見ればそれは伊十の仲間たちばかりだ。 故辛島十兵衛こと張成徹(チャンソンチョル)。百婆こと朴貞玉(パクジョンオク)。長男十蔵こと張正浩(チャンジョンホ)。十蔵女房コシホこと権麗喜(クォンコヒ)。次男以蔵こと張太浩(チャンテホ)。以蔵女房こと韓青玉(ハンチョンオク)。三男元良こと張永浩(チャンヨンホ)。四男兼良こと張秀浩(チャンスホ)。十蔵長男兵太こと張衛善(チャンウィソン)。次男参平こと張明善(チャンミョンソン)。以蔵の長男以助こと張光善(チャングワンソン)。次男以作こと張順善(チャンスンソン)。ロクロの権十こと韓大中(ハンデジュン)。長男清助こと韓植元(ハンシグオン)。次男市次こと韓植耀(ハンシギョ)。故万治こと李則一(イチギル)。女房アカこと金明順(キムミョンスン)。長男寅吉こと李延吉(イヨンギル)。次男熊吉こと李延泰(イヨンテ)。藤次郎こと権会雄(クォンフェヨン)。亀平こと張日徹(チャンイルチョル)。 故郷全羅道(チョルラド)の田舎では秋になると胡桃がいっぱい熟れた。わし達は実を厚い殻の中に閉じこめた、あの胡桃そっくりだなあ、と伊十こと韓則陽(ハンチギャン)は思った。 それぞれ、座敷に座っている人たちが、もう一度眺め直されていることがお分かりになるだろうと思いますが、この作品の面白さは、こうして作家が描き始めた目の前の世界を朝鮮の魂が底流する二重構造とあつらえたところにあると思いますが、この後のワクワクするような展開の主人公は、百婆こと朴貞玉(パクジョンオク)ですね。 龍窯という窯を夫十兵衛を支え、伊十や権十を励ましてつくりあげ、子を産み、子供たちの妻子を教育してきた、百婆という女性の、自由でおおらかで気骨に満ちた振舞いのすばらしさは、ちょっと言葉では言えませんね。まあ、お読みになって、お確かめください(笑)。 映画「ちゃわんやのはなし」で、たしか、十四代沈壽官を支えたお母さんだったか、十五代の奥さんだったが、蝶になって登場するシーンがありましたが、「あっ、百婆だ!」 でしたね。 これで、「ちゃわんやのはなし」で思い出した二冊目の案内終了です。あと一冊ですね。残すは「パッチギ・対談編」です。ガンバリマス!追記2024・08・03 この小説の題名の「龍秘御天歌」についてですが、「龍飛御天歌」という、15世紀、朝鮮の李王朝の頃編集された、王朝礼賛歌集があるそうです。ボクは読んだことはありませんが、村田喜代子さんが、その歌集を意識において大目をお付けになったことは確かでしょうね。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)
2024.08.02
コメント(0)
-
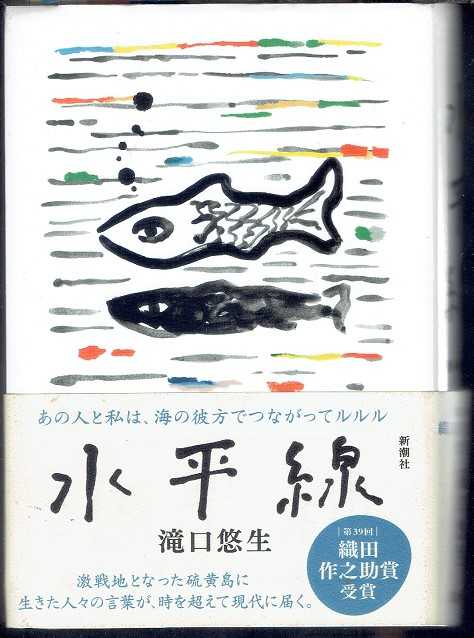
週刊 読書案内 滝口悠生「水平線」(新潮社)
滝口悠生「水平線」(新潮社) 今回、案内するのは滝口悠生の新しい作品で「水平線」(新潮社)です。 昨年(2023年)一番記憶に残ったのがこの作品でした。昨年の夏ごろだったかに読み終えて、傑作だと思いましたが、うまくいえないので、放ったらかしになっていました(笑)。 滝口悠生という人は「死んでいないもの」(文春文庫)という、「死んでいなくなった」のか、「死んではいない」のか、わからないという、まあ、人をくった題で、葬式に集まった人間たちを描いて2016年だかに芥川賞をかっさらった作品で気に入ってから、何となく読み継いでできた作家です。 1982年生まれで、2003年には41歳。若い作家ですね。同世代の作家たちと、ちょっと味わいの違う中編小説の人だと思っていましたが、今回の「水平線」は26章、503ページの大作でした。 書き出しはこんな感じです。 屋上のデッキからは、洋上に快晴が広がりつつあるのが見えた。風は穏やかだったが、航行する船上では向かい風が生じ、風を受けた耳元からがぼうぼう鳴った。風は海から来て、船を抜け、また海に吹き去る。ときどき、そこに誰かの酔いが紛れているような気がしたが、それがゆうべの酒の残りなのか船酔いなのかわからない。どの方向に目をやっても、島影は全然見えない。いまデッキ上には誰もいない。(P3)船はいまも確かに一つの時間を前に進んでいる。昨日の昼前に東京の竹芝桟橋の港を出て、一晩を越えた。貨物船おがさわら丸の行き先はその名の通り小笠原諸島父島である。夜の明けた太平洋を南進している。(P4) ここでの語り手は横多平(よこたたいら)という登場人物自身のようですが、38歳、フリーの編集者だそうです。今、小笠原諸島の父島行きのおがさわら丸に乗っています。 彼が、なぜ、この船に乗っているのか。広大な「水平線」を越えて、彼はどこに向かっていて、そこで何が起きるのか。まあ、そんなムードで小説は始まりました。 しばらく読むと語り手が、三森来未(みつもりくるみ)というパン屋さんで働いている36歳の女性に替わって、今度は自衛隊入間基地の飛行場で出発を待っているこんな描写になります。 私の胸には、三森来未(みつもりくるみ)、と名前の書かれた札がついている。今日輸送されるのは私たち、つまり人間で、一瞬なにか物のように扱われているような気になるが、考えてみれば輸送機と言っても運ぶのは物資や資材に限った話ではなく、ふだんから人材つまり自衛隊員の輸送を担うものであるわけだった。自衛隊員にはそもそも旅客機なんかないだろうし。いや、もしかしたらあるのかな。いや、ないか。中略 私たちは戦場に派遣されないし、イラクにもクウェートにも派遣されない。輸送機の行き先は小笠原にある硫黄島という島である。東京都が春のお彼岸に行ってくる、硫黄島の元住民に向けた墓参事業は、かつて島に暮らしていたひとだけでなく、その親族も対象とされていて、ここに集まっているのはその参加者だ。(P15 ~P16) 小説は東京都の南の果て小笠原諸島の、そのまた南の果ての硫黄島に向かう二人の男女の姿を描くことから始まっているのですが、この三森来未さんの語りに続いて、硫黄島というのは、クリント・イーストウッドが映画で描いた、あの硫黄島のことで、1960年代の終わりにアメリカから返還されて以来、2010年現在、自衛隊の基地があるだけで、一般住民は一人も生活していない島だということ、太平洋戦争の末期、1944年に強制された全島疎開以前は1000人を超える島民が暮らしていらしいのですが、その後、硫黄島の争奪をめぐる激戦で日本陸軍の軍人20129人、100人近くの現地徴用の島民、6821人のアメリカ兵が亡くなり、今でも、10000人以上の遺骨が眠っているということを記したうえで、展開していきます。 もう少し登場人物と、この小説が描く物語の発端を説明すると、船に乗っている横多平と、自衛隊の輸送機を待っている三森来未は、来未さんが、離婚した母の旧姓を名乗っているだけで、それぞれ独身の実の兄妹です。その兄妹が、なぜ、今、硫黄島か? まあ、そういう疑問で読み進めたわけですが、その二人の携帯電話にフイにかかってくる電話がすべての始まりでした。 二人が生まれる40年以上も昔に、現地徴用されて硫黄島で亡くなったり、疎開した伊豆の町から蒸発したはずの祖父の弟や祖母の妹から電話がかかってくるという奇想的現実を発端に兄、妹を動かし始めるのです。 そこから、若い二人の現在の生活が描かれるのですが、その、「今」そのものの生活にケータイ電話から、いたずら電話を思わせる明るさで「過去」が響いてくる中で、語り手を変幻に替えていくことで、故郷を知らない二人とその家族、戦中、戦後を生きた祖父母の人生、1940年代の島の暮らしが重層的に重ねられていく書きぶりで、忘れられつつある戦後を背景に「現代」を描くという、久々の本格小説だと思いました。 まあ、ボクの感想ではさっぱり要領を得ないのですが、新潮社のホームページで作家の松家仁之さんが「死者から届く親しげな挨拶」と題して書評していらっしゃるので、関心のある方はそちらをどうぞ。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)
2024.05.11
コメント(0)
-
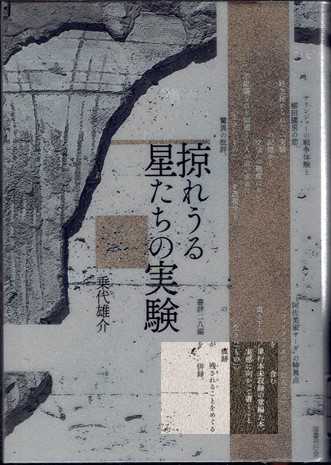
週刊 読書案内 乗代雄介「掠れうる星たちの実験」(国書刊行会)
乗代雄介「掠れうる星たちの実験」(国書刊行会) 乗代雄介という作家にはまっています。まあ、何が面白いのかよくわからないままなのですが、とりあえずみんな読んでみようか!? というはまり方です。 というわけで、今回の読書案内は「掠れうる星たちの実験」(国書刊行会)という評論集です。少し長めの評論が一つ、書評、創作をまとめた本です。具体的な内容は後ろに目次を貼りましたからそれをご覧ください。 案内するのは(まあ、案内になっていない木もしますが)表題の評論「掠れうる星たちの実験」です。 読む作品、読む作品、語り手や登場人物の配置について、かなり意識的な方法論に基づいて書いているんじゃないかと、まあ、読み手のボクに思わせる乗代雄介という作家の「小説」に対する、自分では「考え事」といっていますが、まあ、小説論というのは少し大げさかもしれませんが、ようするに「考え事」が書かれている50ページほどの論考です。 で、手に取って、まあ、最近は評論とか面倒なのですが、ついつい、読み続けたきっかけは、チョット、ボクには並べて考えるなんて、とても思いつきそうもない二人の人物を引っ張り出してきて「考え事」を始めていたからです。 二人とは、「ライ麦畑でつかまえて」のサリンジャーと「遠野物語」の柳田國男でした。まず、この取り合わせが面白いと思いませんか? このお二人が、乗代雄介の「考え事」に呼び出されていると聞いて、「語り」と「記述」、「書きことば」と「話ことば」、まあ、そのあたりを思い浮かべられた方は、なかなか、鋭いと思います。 で、書き出しあたりに、乗代雄介はこんなことをいっています まずは「ライ麦畑でつかまえて」のホールデンが、子供の頃エイグルティンガー先生に土曜日ごとに連れていかれた自然科学博物館について述懐する場面を見てみたい。ペアを組んだ女の子の汗ばんだ手、守衛の注意から、インディアンやエスキモー、鹿や南に渡っていく鳥の剥製を並べたジオラマ展示について詳述された後で「でも、この博物館で、一番よかったのは、すべての物がいつも同じとこに置いてあったことだ」とホールデンは語る。「何一つ変わらないんだ。変わるのはただこっちのほうさ」と続け、さらに変わるとは厳密にいえば「こっちが年をとる」ようなことではないと注釈をくわえている。(P11) 作家の考え事は、「変わること」と「変わらないこと」に焦点をあてて進みそうなのですが、続けて作家が引用したのは、下のような二つの文章でした。 こっちがいつも同じではないという、それだけのことなんだ。オーバーを着てるときがあったり、あるいはこのまえ組になった子が猩紅熱になって、今度は別な子と組になってたり、あるいはまた、エイグルティンガー先生に故障があって代わりの先生に引率されてたり、両親がバスルームですごい夫婦喧嘩をやったのを聞かされた後だったり、道路の水たまりにガソリンの虹が浮かんでくるとこを通ってきたばかりであったり。要するにどこか違ってるんだ―うまく説明できないけどさ。いや、かりにできるとしても、説明する気になるかどうかわかんないな。(「ライ麦畑でつかまえて」サリンジャー) 誰にでもいつ行ってもきっと好い景色などというものは、ないとさえ思っている。季節にもよろうしお天気都合や時刻のいかんもあろうし、はなはだしきはこちらの頭のぐあい胃腸の加減によっても、風景はよく見えたり悪く見えたりするものだと思っている。(「豆の葉と太陽」柳田國男) 乗代雄介はサリンジャーがホールデン少年に「説明する気になるかどうかわかんないな。」 と言わせていることの、小説の書き手にとっての問題について考えてみようとしているわけですが、それがどういう結論にたどりつくのか、あるいは、たどり着かないのか、そのあたりは、この論考をお読みいただくほかはないわけですが、この「考え事」の題としている「掠れうる星たち」を暗示する二つの引用で論をとじています。「自分だけで心の中に、星は何かの機会さえあれば、白昼でも見えるものと考えていた。」(柳田國男「幻覚の実験」)「おまえの星たちはほどんそ出そろったか?おまえは心情を書きつくすことにはげんだか?」(サリンジャー「シーモア序章」) 最近、ボクが、小説とか読んだり、映画とかを見ながら、引っかかっているのは、読んだり見たりしているボクが、それぞれの作品のどこに「ホントウノコト」を感じているのか、わけがわからないと思いながら、そのわけのわからなさに惹かれるのは何故か、そこにぼく自身が何を見たり、読んだりしているのか、まあ、そういうことで、できれば、それをちょっと言葉に出来ればいいのですが、「涙がとまりません」とか、「笑えました」とかいういい方でしか言葉にできないことを訝しく思っているのですが、乗代雄介という作家が、どうも、そのあたりのことにこだわって小説を書こうとしているようだと思わせる「考え事」でした。 要をえない案内ですが、ボクには、かなり面白い考え事でしたよ。で、本書の目次を貼っていきます。興味がわいたら、図書館へどうぞ(笑)。 目次評論掠れうる星たちの実験 P5書評 P61『職業としての小説家』村上春樹 『このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる/ハプワース16、1924年』J・D・サリンジャー(金原瑞人訳) 『アナーキストの銀行家 フェルナンド・ペソア短編集』フェルナンド・ペソア(近藤紀子訳) 『ペンギン・ブックスが選んだ日本の名短編29』ジェイ・ルービン編『ののの』太田靖久 『大工よ、屋根の梁を高く上げよ/シーモア―序章―』J・D・サリンジャー(野崎孝、井上謙治訳) 『サピエンス前戯』木下古栗 『謎ときサリンジャー 「自殺」したのは誰なのか』竹内康浩、朴 舜起 『柳田國男全集31』柳田國男 『ナチを欺いた死体 英国の奇策・ミンスミート作戦の真実』ベン・マッキンタイアー(小林朋則訳) 『揺れうごく鳥と樹々のつながり 裏庭と書庫からはじめる生態学』吉川徹朗 『サガレン 樺太/サハリン 境界を旅する』梯久美子 『いまだ、おしまいの地』こだま 『契れないひと』たかたけし 『自然な構造体 自然と技術における形と構造、そしてその発生プロセス』フライス・オットー 他(岩村和夫訳) 『記憶よ、語れ 自伝再訪』ウラジーミル・ナボコフ(若島正訳) 『鷗外随筆集』森鷗外(千葉俊二編) 『佐倉牧野馬土手は泣いている(続)』青木更吉 『松本隆対談集KAZEMACHI CAFE』松本隆 他 『現代児童文学作家対談5 那須正幹・舟崎克彦・三田村信行』神宮輝夫 『ウォークス 歩くことの精神史』レベッカ・ソルニット(東辻賢治郎訳) 『トンネル』ベルンハルト・ケラーマン(秦豊吉訳) 『今日を歩く』いがらしみきお 『手賀沼周辺の水害 ―水と人とのたたかい400年―』中尾正己 『海とサルデーニャ 紀行・イタリアの島』D・H・ロレンス(武藤浩史訳) 『声と日本人』米山文明 『ライ麦畑でつかまえて』J・D・サリンジャー(野崎孝訳) 『案内係 ほか』フェリスベルト・エルナンデス(浜田和範訳) 創作 P217八月七日のポップコーン センリュウ・イッパツ 水戸ひとりの記 両さん像とツバメたち 鎌とドライバー 本当は怖い職業体験 This Time Tomorrow 六回裏、東北楽天イーグルスの攻撃は フィリフヨンカのべっぴんさん 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)
2024.05.09
コメント(0)
-

週刊 読書案内 井戸川射子「この世の喜びよ」(講談社)
井戸川射子「この世の喜びよ」(講談社) 井戸川射子という人の「この世の喜びよ」(講談社)という作品集を読みました。書名になっている「この世の喜びよ」は、ちょうど1年前、2023年1月に発表された芥川賞の受賞作ですが、ほかに「マイホーム」・「キャンプ」という短編が入っています。 西宮あたりで、公立高校の教員をなさっている方だと聞いて、2021年に野間文芸新人賞を受賞されたという「ここはとても速い川」(講談社文庫)という作品を読んで「あっ、この人は、ちょっとちがう!」 まあ、そんな、感想を持って注目していた人でしたが、最近気に入っている乗代雄介とは、まあ、好対象(笑)というか、2作目で芥川賞でした。 あなたは積まれた山の中から、片手に握っているものとちょうど同じようなのを探した。豊作でしたのでどうぞ、という文字と、柚子に顔を描いたようなイラストが添えられた紙が貼ってある。そのまえの机に積まれた大量の柚子が、マスク越しでも目が開かれるようなにおいを放ち続ける。あなたは努めて、左右均等の力を両足にかけて立つ。片方に重心をかけると体が歪んでしまうと知ってからは、脚を組んで座ることもしない。腕時計も毎日左右交互につける。あなたは人が見ていないことを確認しつつ片手に一つずつ握っていき、大きさ重さを感じながら微調整し、ちょうどいい二つをようやく揃えた。喪服の生地は伸びにくいので、スカートの両側についたポケットにそれぞれ滑り込ませると、柚子の大きさで布は張り膨らむ。この柚子は娘たちに、風呂の時に一つずつ持たせてやろう、とあなたは手の中のを握りしめた。従業員休憩室に、おすそ分けがこうして取りやすく置いてあるのは珍しい。大きなショッピングセンターなので休憩室は広く、売り場のコーナーごとに仲良くまとまっている。仲間内でお土産が配られたりして、普段は分け合っているのを横目で眺めるだけだ、お菓子などは、あなたにはいつも回ってこない。(P7~P8) 書き出しの、最初のパラグラフです。「あなた」という2人称の代名詞で語られる「誰か」の行為(外面)から意識(内面)までが、この作品で、その「誰か」のことを「あなた」と呼んでいる書き手によって描かれていました。 誰かは、引用部で分かるように、どこかのショッピングセンターの喪服売り場で「仲間内でお土産が配られたりして、普段は分け合っているのを横目で眺めるだけ」 だと感じながら働いていて、もう少し読めば、ポケットに入れた柚子を「風呂の時に一つずつ持たせてやろう」 と思う二人の娘が、すでに就職したり、大学生になっていたりしている、おそらく40歳をこえる女性だということもわかってきますが、問題は、その女性を「あなた」と呼んで、この文章を書いているのは誰なのかということですね。 例えば、よく知られたこんな書き出しの小説があります。「或日の暮方の事である。一人の下人が、羅生門の下で雨やみを待つてゐた。」 教科書でご存知でしょう、芥川龍之介の「羅生門」の冒頭ですが、この一文の「一人の下人」を「あなた」に置き替えてみると、読者はこの小説の「書き手」と「あなた」の関係は何か? から目を離せなくなると思いませんか。小説が説話物語的な構造を捨てて、書き手と、登場人物である「あなた」との「関係」を描かずに終えることはできないだろうという、まあ、ある種の緊張感 を内包する現代小説化していくと思うのですね。この作品は、そこに着目して現代を生きる人間を描こうとしているのではないか? まあ、そういうことを期待して、2ページ、3ページと、ほとんど何も起こらないこの作品のページを繰って読み続けながら、ボクの頭から離れないもう一つの疑問は「この世の喜びよ」と、作品名によって明示されている、「この世の喜び」とは何か? ですね。 で、この本の7ページから96ページまで、全部で89ページある、この作品の87ページまでたどり着いたのですが、語り方に変化はありませんし、題名理解への暗示もありません。 ところが、最後の2ページです。突如、もう一人の「あなた」が登場し、初めて、他者に2人称で呼び掛ける、1人称の「私」も登場します。「私は炎みたいな形の木とか、太い幹の根もとから色の薄い若木が取り囲むように生えてて、これから競い合うように、枝はどう伸びていくんだろうとか、そういうのを眺めてた。」 初めて、この小説に、一人称の「私」が出てきた一文の後半です。 で、作品は指示対象が異なるらしい二つの、同じ二人称代名詞「あなた」の出てくるこの一文でとじられます。「あなたに何かを伝えられる喜びよ、あなたの胸に体いっぱいの水が圧する。」 ここまで読んできて浮かんできた、あれこれの疑問が、この一文ですべて氷解したりはしませんでしたが、読み終えたとき、なんだか深くため息をつきながら、「胸に体いっぱいの水が圧」している「あなた」の姿を思い浮かべました。 わからないところは残っていますが、確かに、今という時代の、社会の片隅で、ひっそりと生きている人間の「希望」 を描こうとしている作品であることは間違いないと思います。 納得です。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)
2024.04.15
コメント(0)
-

週刊 読書案内 小谷野敦「文学賞の光と影」(青土社)
小谷野敦「文学賞の光と影」(青土社) その昔「もてない男」(ちくま新書)という、まあ、衝撃的な(笑)書名の所為でベストセラーになった本を書いた小谷野敦という、多分、比較文学の研究が本業だったはずの方の「文学賞の光と影」(青土社)を市民図書館の返却の棚に見つけたので読みました。 一応、「読書案内」と看板を上げているわけですから、どうぞお読みください! というのが基本ですが、今回のように「まあ、こういう本もありますよ、別にすすめませんが」という時も、まあ、ないわけではないので、悪しからずです。 はじめにの終わりに、まあ、執筆意図についてでしょうね、こう書かれています。 芥川賞のように有名になると、ふだん文学を知らない人も関心を持つから、公募の賞だと思い込んでいるいつ人や、純文学って何?え?こういうのが「ジュンブン」なの?といった疑問を持つ人も多い。そこで本書では、内外の文学賞について、よもやま話を書いて、いろいろ疑問に答えておきたいと思う。まあ、この本自体がベストセラーにならないと、誤解を解くというわけにはいかないのではるが。 文学の素人の方には、まあ、様々な疑問や誤解があるようですが、疑問にお答えして、誤解を解きますということですが、要するにこの本が売れれば、いろいろ解決しますよという、まあ、読み終えて見ると、ちょっと誇大広告(笑)で、いや、儲かるのはあんたやろということらしいですが、目次はこんな感じです。目次第1章 芥川賞と直木賞の栄光と死屍累々第2章 ノーベル文学賞第3章 貰えなかった恨み第4章 新潮社の栄光と文学賞第5章 作家と学歴第6章 文学賞の女と男怨念の書―あとがき 目次を、まあ、索引がわりにして、あっちこっちのページを覗いているうちに、読み終えました。何が、どう書いてあるのかというと、今度はあとがきですが、 私は学者の道を歩み、博士号までとった。そうである以上、別に東大とは言わないが、しかるべき大学の教授になりたかった。というか、当然なるものと思っていた。ところが、時代が悪いのか自分が悪いのか、いや、時代が悪いに決まっているのだが、それはどうもないようである。そこで、大学教授より格が上である××賞をとってやろうと、邪念を抱いたのである。いや、本気で邪念だと思っているわけではない。 ぞんな時、たまさか、本書を執筆することになった。かなりの分量、文学賞をめぐる人々のやっさもっさについて書いていくうちに、私の中から、つきもののが落ちたように「賞などどうでもいいではないか」という悟りのようなものが生まれたのである。 ご本人がおっしゃっている通り、様々な賞をもらったり、あげたりする、あれこれの作家や評論家について、まあ、スキャンダルと云う程の毒があるわけでもない、「やっさ、もっさ」が書かれていて、こういう話が好きな人には面白いでしょうね。 多分、文芸雑誌や、ゴシップ雑誌のバックナンバーを、かなり丹念に調べた(根が学者なのでしょうね)その結果を、しかし、だから、憶測かうわさに過ぎないかもしれないゴシップ記事として書き連ねていらっしゃって、まあ、結果的に、ご本人の賞が欲しいという妄執 からは、解脱というか、悟るというかのメデタイ結果なのかと思うと、最後のページにのせられていた戯れ句がこうでした。 賞とれず 根岸の里の詫び住居 笑えませんね。 焼いても治らんといういい方がありますが、まあ、「もてない男」でもそうだったような気がしますが、ちょっと引きながらの上から目線というスタイルが彼のウケ狙いなのでしょうが、芸のないことですね。 ただ、何とか賞をめぐるゴシップは、ほんと、山盛りで、知ったからどうだという気もしますが、「読みごたえ」ありますよ。ボクの場合、こうして案内していて、すでに忘れてますから、まあ、こんな本もありますヨ! でした。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)
2024.04.10
コメント(0)
-

週刊 読書案内 乗代雄介「皆のあらばしり」(新潮社)
乗代雄介「皆のあらばしり」(新潮社) 2021年の「新潮」10月号に掲載された作品の単行本化ですが、文庫はまだありません。その年の芥川賞の候補作らしいですが、これで3回目の落選です。 「十七八より」(講談社文庫)で群像新人文学賞でデビューして以来、「本物の読書家」(講談社文庫)で野間文芸新人賞、「旅する練習」で三島由紀夫賞と坪田譲治文学賞のダブル受賞、で、「最高の任務」(講談社文庫)が2019年、「旅する練習」(講談社)が2020年の芥川賞の候補作になって、今回案内している「皆のあらばしり」で3回目、ちなみに、2023年には「それは誠」(文藝春秋社)で4回目の候補になりましたが、やっぱり落選でした(笑)。 というわけで、「皆のあらばしり」ですが、今回は書き出しではなくて50ページあたりからの引用です。「青年は小津安二郎は知っとるか?」「映画監督だろ。」男が黙って指さしたところには小津久足という名前があった。「小津久足は、伊勢の松坂の豪商、干鰯問屋湯浅屋の六代目当主や。家業の傍ら、歌に国学、紀行文と文事を重ね、歌は約七万首、蔵書は西荘文庫として残っとる。あの滝沢馬琴にも、その博識と文才を認められた友人として知られる江戸の文人や。『南総里見八犬伝』ぐらい読んだことあるやろ。」「ない」「そうかいな」男はそんなことは織り込み済みだとばかりに言った。「しかし、自分を偽らんのが青年の見込みあるところやがな。下に偽るならまだしも、上に偽って背伸びされたら話が一向通じんから困ったもんやで」「あんたはいつ読んだんだよ」「いつやったかな。青年が今、高二やろ。高一ぐらいで読んだんとちゃうか」学年を教えた覚えはなかったけれど、後輩にも会ったし、どこかで察したのだろう。「ほんとかよ」とぼくは言った。「下に偽ってるんだろ」「そう思わせたらこっちのもんやけど、まあええわ。話を戻そうやないか。その小津久足の、母違いの弟の孫が小津安二郎なんや」「その人がどうしたんだ」「その小津久足の著作として」と指をすべらせ「ここに「陸奥日記」と「皆のあらばしり」が一点ずつあると書いとるわな。このほんまにしょーもない蔵書目録、何を大層に目録やっちゅう漢字やけど、唯一おもろい、掃き溜めに鶴はこいつや」 とまあ、こういう感じなのですが、小説の登場人物は、ここにいる「男」と「ぼく」、舞台は栃木県にある皆川城という、室町時代の山城の城跡の公園です。二人は、ある日、偶然、その公園で出会います。「男」の名前は不明ですが、やたら、歴史に詳しい、単身赴任のサラリーマンで、「ぼく」は地元の高校2年生で、歴史研究会のメンバーです。 で、「ぼく」の一人称で書かれているわけですから、「ぼく」がこの文章の書き手ということになりますね。ただ、他の作品のように日記であるとか、手紙であるとかいう形式が選ばれていないところが、この作品の特徴ですが、実はここでは、もう少し違う形式が導入されているのですが、気になる方は、まあ、読んでみてください(笑)。 そのほかの登場人物は、同じ歴史研究会の後輩の竹沢さんだけです。古くからの造り酒屋だった竹沢酒店の娘です。彼女が登場して「ぼく」に呼びかけるシーンで。初めて、ぼくの姓が浮田君であることがわかりますが、名前はわからなかったと思います。 で、小説の不思議な題名である「皆のあらばしり」は、引用でおわかりのように、小津久足という江戸時代末期の文人が残した草紙ということなのですが、今、男が見ている蔵書目録は竹沢酒店にあったものです。ちなみに、お調べになればわかりますが「あらばしり」は、新酒を絞る時に、絞らなくても出てくる最初の酒のことだそうです。 で、最初の謎が、「皆のあらばしり」などという草紙が果たして実在するのかどうかでした。「偽書」といういい方がありますが、この「皆のあらばしり」は真書なのか、偽書なのか、男と浮田君の二人が、まあ、そのあたりをめぐっての会話劇で読み手を引っ張るわけですが、この作家得意の「オチ」まで来ると、小説の「語り手」も含めた手の込み方というか、実に技巧に徹した工夫が凝らされていたことが分かって、チョット啞然とします。 まあ、おすきなかたは膝を叩いて、という所でしょうが、ボクは「書く」という行為の信憑にこだわり続けているらしいこの作家の実験作の一つというふうに感じました。 サリンジャーの最後の小説ですが、「ハプワース16、1924年」(新潮社)という作品があります。シーモアという、すでに、死んでいる兄が、まだ7歳だった時に両親に向けて書いた手紙を、大人になって作家になった弟のバディが、そのまま写して小説作品にしたという不思議な作品ですが、あの、方法に少し似ていますね。「書く」行為から「書き手」を消す にはどうしたらいいかということが、乗代雄介の実験のようですが、さて、うまくいっているのでしょうか。まあ、それにしても、あれこれ頑張っていますね(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)
2024.04.08
コメント(0)
-

週刊 読書案内 乗代雄介「パパイヤ・ママイヤ」(小学館)
乗代雄介「パパイヤ・ママイヤ」(小学館) 乗代雄介の作品にはまっています。図書館の棚から、適当に借りてきたこの作品は、昨夏だったか芥川賞を逃した「それは誠」(文藝春秋社)という、高校生の群像を描いた作品の一つ前の単行本で、かなり新しい作品です。 何に興味があってハマっているのかということですが、作家の「方法意識」ですね。どんな登場人物に、何を書かせようとしているのかな? というあたりですね。彼の小説は、全体としてはもちろん小説なのですが、手紙、日記、語り、記録、というふうに、ある特定の文体を採用することによって、「出来事の時間」と「書くという行為の時間」をずらすことによって生まれてくる、記述としては描かない「何か」 を狙っているんじゃあないか、で、その狙いは何だ、というふうな興味ですね。ボクが、ここで「何か」と考えているのは、所謂、「テーマ」とか「主題」とかと呼ばれているものとは少し違うものですね。 それがわかったらどうだというんだ!? と問い返されると困るのですが、まあ、そのあたりの作家の姿が見えてくると面白いんじゃないかという気分にすぎません(笑)。 で、「パパイヤ・ママイヤ」(小学館)ですね。ガール・ミーツ・ガール! 一読、こてこての青春小説です。すぐ読めます(笑)。で、 とりあえず、書き出しはこんな感じです。 これは、わたしたちの一夏の物語。 他の誰にも味わうことのできない、わたしたちの秘密。 もしもあなたが私の撮った写真を持っているなら話はちょっと変わってくるけど、そのほとんどんは世界に一枚しか存在しないものだし、そもそも、誰かさんを差しおいてあなたがそれを手に入れるなんて絶対にありえない。 わたしにしたって、この夏の写真のことは、もう言葉で説明するのがやっと。例えば、あの日あの時、わたしたちの物語の入口を写した一枚。 笹藪の間に空いた砂利道をふさぐように建っている灰色のフェンス。網目にはいくつかの案内板が備えつけてある。南京錠を付けた閂が通されているけれど、フェンスと藪の間には人が通れるぐらいの隙間があって、そばには「歩行者通路」と書かれた赤いコーンが置いてある。(P001) この文章の書き手である「わたし」はママイヤちゃんです。高校生くらいの女の子です。「わたしたち」といっていますが、もう一人がパパイヤちゃん。高校2年生の女の子です。「わたしたち」の二人は今日、初めて会います。 知り合った経緯とか、ママイヤ、パパイヤというネームの経緯は、そこら中にあるレヴューか、本があれば、このあと数ページも読めばわかりますから、まあ、お読みください(笑)。 で、この作品で乗代雄介が持ち出してきたのが「写真」です。ちょうど、この作品を読んでいた時に、ボクの知り合いの中学生、我が家の愉快な仲間のオチビさんの一人ですが、彼女がデジタルとかスマホとかではない、フィルム使用のポケットカメラで写真を撮りたいのだけれど、ジージは持っているかといってきたので、事情を聴くと「流行ってるねん!」 ということで、この小説の設定に納得したのですが、引用にあるとおり、写真の画像の描写が文章にしてあるところが、ひょっとして、作家のたくらみなのでは? というのがボクの興味です。 写真を撮っているママイヤちゃんと、それを、横とかで見ているパパイヤちゃんが、作中での写真の意味について、青春ドラマのハイティーンの少女らしい会話をします。「なんで好きなの、写真」「わたしだけが気付いているって思えるから」「何に?」「この世界の」言ってから「なんだろ」と考える。「その美しさに?」「えー」声はいつもにも増して長く伸びた。「いいじゃん」力なく笑って手すりに両肘をついて、顔を隠そうとしている自分に気付いた。「写真やるには弱すぎるよ、わたしは」そう言って遠くではなくすぐ下の海を見下ろす。「変わっちゃうのに耐えられないから」「でも写真って、撮る方が気付いてなくても写るじゃん。それならよくない?」私がそれについて答えられないでいるうちに、パパイヤは言った。青春という言葉が思い浮かんだけど、恐怖とも感動ともつかないざわめきが心いっぱいに広がって口が動かない。(P162) ここで、写真について語っているママイヤちゃんですが、主人公のキャラクターの描写が、作家の記述の狙いの第一番目にあることは、お読みになればすぐにわかるシーンですが、その後、撮るだけ撮って、今までは現像しなかった筈の写真を、夏の終わりのクライマックスのシーンでは、現像して二人で見ます。 で、二人が見る写真の描写だけ引用するとこんな感じです。 砂利道の脇に並んだ丈の高いヨシ。奥を見通せないほど密生しているが、何本か倒れて少しだけ明るく見える所に、斜めに倒れた自転車の後輪がかろうじて見える。原っぱの片隅にある小屋の中、寝そべって顔を出している白ヤギ。船だまりに係留されている沢山のボート。杭を挟んできれいに並んで、内側の白や淡い水色が明るく光を弾く。順行だから水は深い青、一面にさざなみが建っている。半分ほど車で埋まった大きな駐車場の奥にぽつんと建つ観覧車。フレームに透けている青空に、一つ一つ色分けされたゴンドラが虹のように円を描く。 これを読みながら、この小説が描いている二人の夏はかなり以前に終わっていて、書き手のわたしが、その時の写真を見ながら書いているらしい、その場面というか、記憶を反芻している雰囲気がただよっていて、すでに大人になった一人の女性が、ボクには浮かんでくるのですが、考えすぎでしょうか。 まあ、それが、作家が方法的に意図したことかどうか、ボクには定かではありませんが、面白いことは事実ですね。ひょっとしたらこの作品は、青春ど真ん中の少女の「この夏」の思い出ではなくて、アラフォーだか、アラフィフだか知りませんが、まあ、そういうお年の方を励ます「あの夏」のお話かもしれませんね。 久しぶりに、青春! いかがでしょうか(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)
2024.03.04
コメント(0)
-

週刊 読書案内 乗代雄介「最高の任務」(講談社・講談社文庫)(その1)
乗代雄介「最高の任務」(講談社・講談社文庫)(その1) ここのところ、乗代雄介という、1986年生まれらしいですから、37歳の寅年、我が家の愉快な仲間の3番目のカガククンと、たぶん同い年の作家に、ちょっとはまっています。 始まりは、2023年の、第169回芥川賞の候補になって落選したのですが、その後、織田作之助賞とかをとった「それは誠」(文藝春秋社)を読んだところからです。 で、すでに案内しましたが、2020年に芥川賞に落選しながら三島由紀夫賞、坪田譲治文学賞を連取した「旅する練習」(講談社文庫)を読んで、今回は「最高の任務」(講談社文庫)です。「最高の任務」(講談社文庫)には「生き方の問題」と「最高の任務」という二つの作品が入っているのですが、そのうちの「最高の任務」は2019年、乗代雄介が初めて芥川賞にノミネートされ、その後の芥川賞4連敗! の始まりの作品です(笑)。 落選し続けている作家の作品を、なぜ追いかけて読んでいるのか? まあ、そういうふうに尋ねられそうですが、面白いからですね。何が面白いのかというと、「作家の方法意識」です。あからさまなのですね(笑)。 たとえば、「旅する練習」では、姪と歩いた旅を作家である叔父が記録しているという設定でしたが、この作品集にある「生き方の問題」の書き出しはこうです。 歴史を遠ざけよ。同時性の状況に立つのだ。これが基準である。私が同時性を基準にして物事を裁くように、私もまた裁かれるのである。背後に流れる無駄話はすべて幻想だ。 キェルケゴール貴子様 これを読まなくちゃ ― 今まさに貴方が読み始めた、世にも珍しいエピグラフ付きの手紙を、そんなふうに認識したのはいつだった?今日か昨日かそれよりずっと前か。 かと言って、僕はその答えを知りたいわけじゃないし、そもそもこの手紙が貴方の家の郵便受けに届く日(二〇一八年七月七日)も知っている。なにしろ僕自身がそのように指定する張本人だし、今貴方がこうして読んでいるということは、僕が立派にやり遂げたってことに違いないんだから。(単行本P7) ご覧のように、この作品は「僕」が、父方のいとこの「貴子さん」にあてた手紙です。単行本で、ほぼ90ページ、全文、一通の手紙! です。ボクがあからさまな「方法意識」と呼んだのは、とりあえずそういう書きかたです。 わざわざキェルケゴールなんか持ち出しているのも、手紙の書き手である僕という登場人物と作家自身の、それぞれの意図が重ねられていて、読みながらのハテナ? の答も複数化するはずですね。 それが、どうしたといってしまえばそれまでですが、手紙の小説化、小説の手紙か、といえば、有名なのは、例えば高校のときにお読みになったことがある(だろう)、漱石の「こころ」ですが、教科書に掲載している部分というのは全編手紙ですね。 で、授業では「覚悟」とか「精進」とか、登場人物の、哲学的、宗教的、人間性を象徴するような「ことば」にこだわって「知ってるか? わかるか?」 と、いたいけな高校生を脅す方が多いのですが、そんなことより、死ぬ前になって「ある人間」が、なぜ手紙を書くのか、なぜ、その場面、あの場面を(いろいろありますが)思い出すのか、そしてそれを書かねば気がすまないのか、という、人間の記憶、あるいは、生きてきた時間に向き合っている態度に対する興味は、高校生にだって、案外、リアルで、そうなると、作家が、何故、登場人物にその場面を思い出させるのかという問いをも成立するわけで、教室も盛り上がって、なかなか面白かったのですが、この作品も、まあ、そういうことをあれこれ思わせて面白いというわけです(笑)。 この作品の手紙の場合は、どっちかというとラブレターのようなものですが、当の貴子さんに伝えたいのか、小説の読者に伝えたいのか、訊き質したいような内容もあって驚きます。まあ、それはそれで面白いのですが、なんというか、「旅する練習」もそうでしたが、オチをつけたいようなのですね。結果、わけのわからなさが解消してしまうというか、そのあたりが???でした。 でも、その結果、いいお話でした! という後味でしたがね(笑)。それでいいのかなと思わないでもないのですよね(笑)。で、次は表題作の「最高の任務」ですが、それはその2に続きます(笑)。また読んでね(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)
2024.02.28
コメント(0)
-
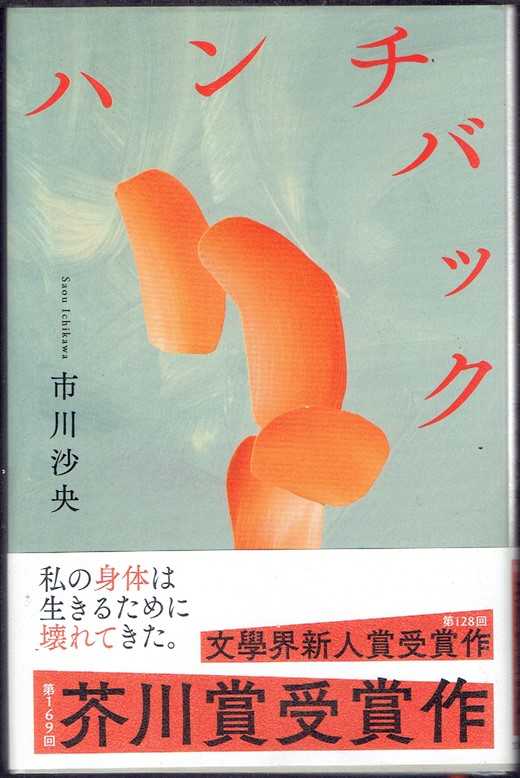
週刊 読書案内 市川沙央「ハンチバック」(文藝春秋社)
市川沙央「ハンチバック」(文藝春秋社) 今日の読書案内は、2023年の夏、ボクの見立てでは「文学」とは何か?! という、まあ、いわば基本的な「問い」を投げかけたことが理由なんだろうなということで話題になった芥川賞作品、市川沙央の「ハンチバック」(文藝春秋社)です。 単行本として出版されてすぐに読み終えたのですが、読書案内に感想を書くことをためらっていました。で、先日、三島有紀子という監督の「一月の声に歓びを刻め」という映画を見て、何となく得心がいって、書いてみようかなという気分で、こうして案内し始めています。 まずは、ちょっと、悪口を言うための揚げ足取りのような引用からです。 アメリカの大学ではADAに基づき、電子教科書が普及済みどころか、箱から出して視覚障害者がすぐ使える仕様の端末(リーダー)でなければ配布物として採用されない。日本では社会に障害者はいないことになっているのでそんなアグレッシブな配慮はない。本に苦しむせむし(ハンチバック)の怪物の姿など日本の健常者は想像もしたことがないだろう。こちらは紙の本を1冊読むたびに少しずつ背骨がつぶれていく気がするというのに、紙の匂いが好き、とかページをめくる感触が好き、などと宣い電子書籍を貶める健常者は呑気でいい。EテレのバリバラだったかハートネットTVだったか、よく出演されていたE原さんは読書バリアーフリーを訴えてらしたけど、心臓を悪くして先日亡くなられてしまった。ヘルパーにページをめくってもらわないと読書できない紙の本の不便を彼女はせつせつと語っていた。紙の匂いが、ページをめくる感触が、左手の中で減っていく残ページの緊張感が、などと文化的な香りのする言い回しを燻らせていれば済む健常者は呑気でいい。出版界は健常者優位主義(マチズモ)ですよ、と私はフォーラムに書き込んだ。(P34~35) こう書いているのは井沢釈華と名付けられている小説の語り手であり主人公です。引用個所は、せむし(ハンチバック)の怪物と自称するこの人物の心象の語りで構成されているこの作品の中で、この作品を読むであろう、いわゆる「健常」な読者が暮らしている「日本」という社会に対する、いわば「告発」が語られているわけですが、まだ冷静でわかりよい箇所です。 実は、老化の中で、身体的健常だけを頼りにして暮らしているボクのような人間には、作品のほぼ全体が、辟易するしかない、誇張した自己暴露か、露悪的な健常社会否定としか受け取れない、まあ、悪態! と呼ぶしかない叫びの連鎖でした。 で、作者市川沙央の履歴を見て考え込んでしまいました。市川沙央 いちかわさおう1979年生まれ。早稲田大学人間科学部eスクール人間環境科学科卒業。筋疾患先天性ミオパチーによる症候性側彎症および人工呼吸器使用・電動車椅子当事者。 考え込んだ理由は、作品の冒頭から、読み手に向かって「悪態」を吐き続ける井沢釈華という語り手は、ほぼ、等身大の市川沙央として描かれていたことについてですね。この悪態のどこが「文学」なのだろう? という、まあ、いってしまえば、ストレートな疑問ですね。 問題は、作品そのものに対する作者の在りようを知ったときに浮かんでくる、作者と作品との関係というか、「書く」という行為の意味 ですね。 ボンヤリ考えているボクに見えてきたのは、一読したボクには文学的昇華とはとても読めないこの作品のテキストの向うに、作家が自らの苛酷な生を肯定するために、書くという行為に賭ける姿 が垣間見えるのではないか、それはひょっとしたら文学かもしれない!? のではないかという朧気ながらなのですが、作品肯定の道すじでした。 こういうふうに、頭からこだわりを抜けた原因は、最初に書いたように三島有紀子という監督の「一月の声に歓びを刻め」を見たことにありますね。三島が、その映画を撮った動機は、彼女自身の中にあった「性的暴力」の被害者としての「心の声」ですね。何というか、映画そのものは、もっと上手に伝えられないものなのだろうかと、スクリーンを前にしていら立つ作品だったのですが、映画が訴える監督自身が伝えたいことを考えながらこの小説のことを思い出したからです。 思うに、「露悪的」とも思える悪態の数々は、多分ですが、健常な読者からの、ありがちな、「同情」の拒否! なのでしょうね。語られている内容のどうしようもなさとは裏腹なのですが、その口調の中に、かすかに漂うユーモア の中にこそ、読者と共有できるかもしれない、作家自身の、がけっぷちの「生の肯定」の意思 があるのかもしれませんね。 意見を聞くことができた小説読みの友人は言っていました。「一度目はうんざりするんだけど、二度目に読むと印象が変わるよ。もう一度読んでご覧なさいよ(笑)。」 まあ、当分、読み返すことはないと思いますが、拍手することをためらいながらも、目が離せない作品の登場でした。
2024.02.20
コメント(0)
-
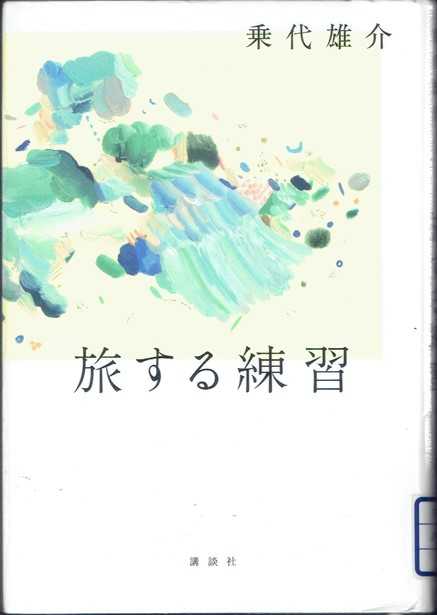
週刊 読書案内 乗代雄介「旅する練習」(講談社・講談社文庫)
乗代雄介「旅する練習」(講談社・講談社文庫) 本日の案内は乗代雄介という、1986年生まれですからまだ30代の作家の、「旅する練習」(講談社・講談社文庫)です。2021年の三島由紀夫賞受賞作品で、その年の芥川賞の候補にもなった作品のようです。知らなかったのはボクだけで、有名な方かもしれません。 こんな書き出しです。 亜美の中学受験は無事に終わった。学力もぎりぎりのところで周囲も心配していたが、本人の楽観と勉強への身の入らなさはそれ以上で、塾に行く以外の勉強はほとんどしなかったと聞いている。 書き手は「私」、職業は「作家」。中学受験をした亜美という少女は「私」姉の娘で、だから姪っ子です。女の子ですがサッカーが大好きで、叔父さんの「私」は、彼女の練習相手です。そういうわけで、亜美ちゃんは女子のサッカー部がある私立中学を受験して、無事合格したようです。 時は、2020年の3月ですが、これが、読み手の世界の実時間に重ねられていて、受験を終えた小学生の亜美ちゃんの、卒業までの最後の一月が、コロナ騒ぎの始まりと重なっていて、学校からのこんな連絡ですることがなくなります。 臨時休校期間 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、市立小中高等学校を臨時休校にいたします。三月二日現在の予定であり、今後変更があった場合は、ホームページなどで周知いたします。 で、「旅」です。関東地方の地名で、具体的には思い浮かびませんが、安孫子という町から、アントラーズというサッカー・チームの本拠地、鹿島という町まで、利根川の堤防を歩く旅、ロード・ムービーならぬロード・ストーリーの始まりです。 題名から、「旅」をするための「練習」か? と思って読み始めましたが、亜美ちゃんは移動のあいだ、ずっとボールを蹴って歩いています。リフティングっていう、あれですね。作家である「私」は、休憩の度にノートに「目に見える風景」とか「鳥」とかについて「文章」を書いています。 「リフティング」と「描写」の練習をしながらのロード・ストーリーの始まりというわけです。コロナで、学校もお休みになり、することのなくなった小学6年生と、もともと暇そうな叔父さんの「練習」の旅 というわけです。三月九日 11:40~12:12 ハケの道は崖線沿いの道全般をさすが、ここでは、手賀沼公園のある小さな入江から崖の前を通る文化財の多く残る道を通りの名にしているようだ。住宅の並ぶ細い道に面した、一段上がった存外広い敷地が志賀直哉邸跡である。当時の庭木が多く残るというが、一際目立つのは立派なスジダイで、赤い花をたっぷりつけたヤブツバキの上に、葉でいっぱいの枝を伸ばしている。(中略)84 これが旅の初日の文章です。まあ、こんな調子の「練習」成果が記録されていきます。最後の数字は亜美ちゃんのリフティングの数ですね。三月十四日 14:07~15:15 257 旅の終わりの日です。文章の方の記録の内容は省略しますが、257回、新記録で旅は終わります。 で、ここまで読み終えたボクは、あれ? 何か変なところがあったな。あれは、なんだったんだ? と、ふと気になる箇所にもどりました。三月十三日ですから、この日の前日あたりに挿入されていた文章です。そこまで、旅の時間の流れに沿って記述されていた「小説」が、ここらあたりだけ、未来の時間で書かれていたところです。 私は二カ月以上経った後でまたこの場所を訪れ、あの時三人で立っていた場所に今度は一人で座り、忘れ難いその時のことを必死に思い出しながら書いた。五月二十六日 14:09~14:54 鳥栖大橋から西へ四キロほど来ると、軽野港という船の係留地がある。その手前の取水門、何となく明るい青のペンキで塗られた螺旋階段のわき、コンクリートで護られた堤防を下りて座る。釣り人が捨て置いた魚が腐臭を漂わせるこんなところでわざわざ書こうというのは、今年の三月十三日に、ここでカワウが死んでいたのを見たからだ。 (中略)水面すれすれに滑りかつ翻りながら何羽も川を渡ったツバメが宙へ駆け上がる。西方の空は地平から天まですっかり雲が覆っていて、南の青空との境は不思議なもどまっすぐだ。雲の低いところは立派な形をとって陰影を際立たせて連なり、高いところは霞んで貼りついたように広がり、大きな太陽に今にも幕を引こうとするようだ。上空を旋回しているトンビも届かいない高い高い雲の影に隠されたものをじっと眺めても、湿った生温かい風に運ばれてきた魚の腐臭が、私を地べたに引き戻してしまう。それは、この開かれたページのすぐ後ろにある旅の風景を未だに振り替えることができないのによくいている。あの旅について書かなければと私は思う。(P128~P129) あたかも、出来事と同時にここまで進行しているかの小説が、全て終わった後に書かれているという暗示です。「えっ?この旅の後なにかあったの?」 三月十四日の記録のページにもどったボクは、残り数ページの結末部分を、そんな期待を持ちながら読み終えました。あの旅について書かなければと私は思う。 という記述の意味がよくわかる結末でした。 で、この、五月二十六日の記録の挿入が、この小説の評価を、おそらく二分させるに違いないというのが読後の感想です。 小説家の「私」は、なぜ、この記録を書かねばならないと思ったのか。結末までお読みになれば一目瞭然だと思うのですが、164回の芥川賞の最終候補に残ったこの作品について、選者の小川洋子は「文学とは何なのか、を追い求める小説になっている。」 といい、同じく選者の山田詠美は「そして、結末は……私には、たくらみが過ぎてあざとく思える。」 と、まあ、真っ二つなわけです。 お二人とも、さもありなんですが、ボクは、どっちかというと山田詠美さんのバッサリ!に1票でしたね(笑) 皆さんはいかがでしょうね(笑)。
2024.02.08
コメント(0)
-
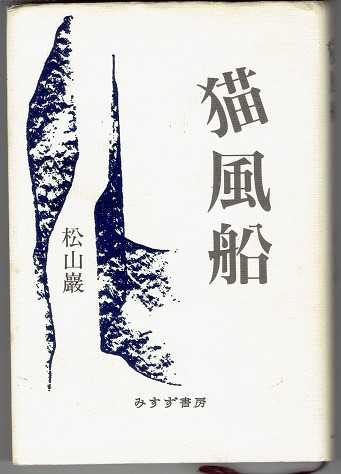
週刊 読書案内 松山巌「猫風船」(みすず書房)
松山巌「猫風船」(みすず書房) 松山巌って、ボクにはどう説明したらいいのかわからない人ですが、まあ、とりあえず、作家ということにしておきます。そのうち、あれこれ案内しそうですが、今日は「猫風船」(みすず書房)という、なんというか、掌編小説集です。下に目次を貼りましたが、全部で41篇入っています。 もともとはみすず書房のPR誌「みすず」に「路地奇譚」と題して連載されていた作品に、かなり手を加えての単行本にしたという触れ込みですが、もとの「みすず」連載が20年ほども昔のことなので、我が家には多分揃っていたと思いますが、今、見直すことはできませんから、何とも言えません。手元の単行本が2007年の初版ですから、まあ、古い本です。 で、内容ですが、とりあえず書名になっている作品をお読みください。 「猫風船」 今年の夏は、梅雨がなかなか明けなかったから涼しいまま終わるのかと思っていたら、急に暑くなった。そのせいで寝つきが悪く、眠りも浅くなった。眠ったと思ったら、悪夢にうなされて目覚める。おかげで日中に眠気が襲ってくる。強い陽射しのなかを歩いていても、頭はボーッとしたままだ。 どこかで休みたい。小公園があった。いくつかベンチはあるが、涼しい木陰の席にはすでに先人がどこも横になっている。陽射しが当たっているベンチさえ、三毛猫が丸くなっている。暑くないのだろうか。近づくと猫は薄目を開け、こちらを見上げた。先住者の権利を主張しているようだが、私はベンチに腰を降ろした。 ベンチの座は陽に照らされている。それでも風が涼しい。腰を下ろし、背にもたれた。猫はベンチの端まで歩いてまた丸くなったが、眼をギラリと光らせてこちらを睨む。どうしてもこのベンチを死守するつもりらしい。そこまで私は占拠するつもりはない。少しでも休めればいい。 それにしても陽射しは激しい。蝉の声が騒がしい。それでもやがて蝉の声も気にならなくなった。たぶん少し眠ったのだろう。 気づけばギャーギャーと猫の声がする。うるさいから眼を開けると、眼の前に三毛猫の大きな顔がある。しきりに声を上げている。なんだって猫はこんなに大きくなったのだろう。きっと暑くて、熱で膨れたに違いない。猫の臭いもする。うるさいから、あっちへ行けと、膨れ上がった猫の顔を手でどけた。 手には抵抗感はなかったのに、猫の顔がフッと消えた。どこへ行ったか。ベンチの下か。いない。またギャーギャー鳴いている。なんだ上か。膨れた猫は宙に浮かんでいた。風が吹く。気持ちがいい。見上げると猫はさらに大きく膨らんで、上空に舞い上がっていく。よく見ると空には、いくつもの猫風船が浮かんでいる。白、黒、ブチ、虎毛、三毛。ギャーギャーと鳴く声も小さくなった。なんだ、真上にギラギラ燃えているのも巨大な猫のめじゃあないか。空はどうやら一杯に膨れ、広がった猫風船におおわれてしまったらしい。猫の目は激しく燃えている。怒っている。暑くてたまらない。 いかがですか(笑)。原稿用紙3枚くらいの量ですから、写すのも気楽です。写していると奇想への展開がよくわかって面白いですが、たとえば「降ろす」と「下ろす」とか、「眼」と「目」とかが書き換えられているのはどう違うのだろう?なんていうことに目がいって、まあ、それはそれで面白いんですが、どうでもいいのかもしれませんね。 ようするに、はあ???という感じの奇譚集です。好き好きですが、ボクは結構好きです。そのうち、別の作品も案内しようかな、という気分です。とりあえず目次を載せておきます。単行本は品切れ、絶版のようですが、図書館にならあるかもしれません。お暇な方にはおススメです(笑)。目次アカンベー 7 ホホエミ食堂 10 ラブレター 14 そっくりな他人 16 ヒトデナシ 23 みんな待っている 26 琉金 29 落書き 33 ゴキブリ 41 ウミ、ドチデスカ 43 球体住居 47 落とし穴 51 素晴らしき伝説 55 猫風船 59 蝉 61 小さなゴジラ 64 とてもセクシー 67 指人形 70 ヒノハナ 73 烏たち 78 筋肉隆々 82 ロボット売ります 86 陽気な三人 94 座敷のイロハニー 98 蟻 101 天使のくせに 104 カレー味の消防団 110 平和ですなあ 112 破れ太鼓 116 大事なもの 119 プチ家出 123 冬眠 125 風邪はひけない 128泣き虫サンタ 134 節分 139 動物園に行こう 141 花見の女 148 ポロポロ落ちる 150 誰もが眠る日 152 新住民 155 万物創生 159
2024.01.21
コメント(0)
-
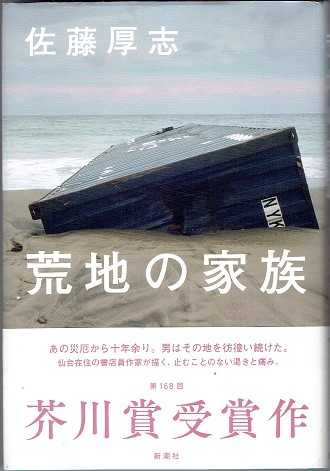
週刊 読書案内 佐藤厚志「荒地の家族」(新潮社)
佐藤厚志「荒地の家族」(新潮社) 2024年の1月2日に、実は2023年の1月に芥川賞を受賞した作品の案内で、トンチンカンなのですが、しようがありませんね(笑)。 坂井祐治はクロマツの枝を刈っていた。肩の筋肉が熱を持って膨れ、破裂しそうだった。酷使して麻痺しかけている両腕と刈込鋏が一体となって動いた。脇を緩めすぎず、胸筋を絞るようにして枝を刈る。鋏が意志を持ち、ただ手を添えているだけでよかった。 2023年1月ですね、第168回芥川賞受賞作「荒地の家族」(新潮社)の書き出しです。作家の名前は佐藤厚志、植木職人ではなく書店員をなさっている41歳だそうです。 書き出しで紹介されている坂井祐治は、あの災厄から10年以上たった阿武隈川の河口の町で植木職人をしている、40歳の男性です。災厄の年から2年後に妻を亡くし、息子と二人暮らしです。 作品では、妻を亡くして5年後、だから3年前に再婚した女性とのいきさつ語られていますが、どうやって出会い、なぜ別れることになったのか、読み終えて見て、語ろうとしてもうまく思い出せません。 読後の記憶として立ち上がってくるのは、海岸沿いに、ずーっと続いている防潮堤の外側の浜辺で、老人が一斗缶で焚火している 光景でした。 立ち枯れしている松林、あたり一帯に広がる更地を突っ切って、白くすべすべした防潮堤に上ると、そこにある光景です。「切った枝も、稲わらも、畦掃除して出たゴミも、前は畑で燃やしてたんだけど」 老人は木切れでどうやら自分の畑があるほうを示したが、見えるのは白い防潮堤といよいよ沈み始めた赤い日の名残りだけだった。「いつもここで」 祐治は聞いた。「たまに」 老人はぽつりと言う。(P10) 風を受けながら防潮堤の階段をのぼり、浜へ降りていった。黒々とした海が、左手の荒浜港や船の光を拾い、ちらちらと光っている。 火が焚かれていた。 ついさっき足袋の泥を落としたばかりなので、柔らかい砂を避け、草の生えている場所を選んで進んだ。 頭を下げると、老人は頷く。黙って一斗缶をつつく老人の反対側に立ち、火を見つめた。暖かかった。火から目が離せなくなる。火の中に、災厄の風景が浮かびあがる。(P80) 浜で揺らいでいる炎に祐治は近づいた。 いつもの老人が棒で一斗缶をかき回す。火の粉が舞った。 火の中に、あらかた消え去った町が現れた。 中略 一斗缶の炎が呼吸するようにぼうっと勢いを増し、また静まる。老人が棒を動かす。火の粉が赤い蛍のように暗闇に軌跡を描いて閃く。火が顔に近かった。(P110) 全部で150ページほどの作品ですが、その始まり、半ば、そして終わりかけに、まあ、今思い浮かべられる限りでは、ですが、焚火のシーン! がありました。この焚火の光景の中で、祐治の脳裏に浮かび上がってきているのであろう生活の実景が小説だったとボクは思いました。人は生きている限り、いつまでも焚火を眺めているわけにはいきませんが、作家が舞い上がる火の粉に見いる祐治の姿 を繰り返し描いていることに、共感というか、ホッとするというか、この作品のよさを感じました。 いわゆる「災後小説」の一つに数えられることになる作品だと思いますが、苦いながらも後味のいい佳作だと思いました。
2024.01.02
コメント(0)
-

週刊読書案内 深緑野分「ベルリンは晴れているか」(ちくま文庫)
深緑野分「ベルリンは晴れているか」(ちくま文庫) 深緑野分という、ぼくには新しい人の「ベルリンは晴れているか」(ちくま文庫)を読みました。2019年の本屋大賞第三位ですね。ツィッター文学賞とかいうのがあるらしいですが、それは一位ですし、直木賞の候補にもなっているようです。ようするに、巷の評判がすこぶるいい作品です。 読み終わって、ちょっとがっかりしました。ミステリーなのか、歴史小説なのか、あるいは、1945年のベルリンという都市小説なのか。どれも及第点とは言えなかったですね。 歴史や地理的事実について、とてもよく調べて書かれているようなのですが、細部に対するこだわりと、全体といいましょうか、釣り合いがとれていないんですね。ぼくにはベルリンの町が、全くリアルではなかったですね。もちろん行ったことも見たこともないわけですが、少なくとも、今読んでいる事件の現場としての立体感が描写できていないという印象ですね。どこで、何が起こっているのかわからないということですね。 たとえば、森鴎外に高校の教科書にも出てくる「舞姫」という有名な作品がありますが、主人公の太田豊太郎が彷徨うのが、ベルリンの裏町であると実感させてくれる何気ない地名の挿入や描写を思い浮かべながら、何が違うのか考えましたが、おそらく、書き手にとってのベルリンが具体的に想起されているか、いないか、というあたりに描写のイメージの差が出ているのでしょうね。ようするに、調べて書いている場所だということかもしれません。ミステリーとしては謎解きの安易さがまず、どうしようもないという感じです。ここまで引っ張ってこれですか? まあ、そういう感じでした。これで、直木賞はあり得ないでしょう。 しつこいようですが、「パリは燃えているか」という、たしかヒトラーの有名なセリフのモジリとして、「ベルリン陥落」の日を題名化したようですが、これも空振りでしたね。ヒトラーの言葉に宿っている歴史的アイロニーのかけらすら感られませんでした。なんで、こんな題になったの? そう考えたときに、客を呼ぶためのシャレたイメージを求める編集者の存在とかが浮かんでしまうのが率直な感想でした。 今回、新刊本を購入しましたが、腰巻のにぎにぎしさに加えて、大手の書店では平積みの棚に、積み上げられていました。図書館では数十人待ちです。なぜ、この小説がそんなに売れて、好評なのかポカンとしますが、やっぱり本屋大賞がらみなんでしょうか。 作品の良し悪しの判定はむずかしい問題ですが、本屋大賞の始まりにかかわった「本の雑誌」で書いていた目黒孝二、別名、北上次郎あたりの方がどうおっしゃるのか、ちょっと興味がありますが、とかなんとか思っていると「本の雑誌の目黒孝二・北上次郎・藤代三郎」(本の雑誌社)という、目黒孝二追悼特集本に偶然出合って、思わず、ため息をつきました。時は流れているのですね。 出版不況、本が売れない、そういう現場からアイデアが出て、本屋さんが「こんな本売りたい!」と差し出す本いうコンセプトから生まれた本屋大賞が空疎な「市場原理主義」を文学とかに持ち込んだとしたら、「本の雑誌」を愛していたぼくとしては、ちょっと寂しい、そんな感じですね。 なんか、話題がよれてしまいましたがおもしろい! を疑う時代がやってきているのではないでしょうか。そんな思いが頻りに浮かぶ今日この頃ですね(笑)。
2023.10.22
コメント(0)
-

週刊 読書案内 宇佐見りん「くるまの娘」(河出書房新社)
宇佐見りん「くるまの娘」(河出書房新社) 「かか」(河出文庫)で2019年の文藝賞、2020年の三島由紀夫賞、「推し燃ゆ」(河出文庫)で2020年後期の芥川賞の宇佐見りんの最新作のようです。まあ、贔屓の作家ということもありますが、快調でした。 書き出しはこんな感じです。 かんこ、と呼ぶ声がする。台所から居間へ出てきた母が二階に向かってさけぶ声が聞こえてくる。かんこ、おひる、かんこ、お夕飯。しないはずの声だった。夢と現実のあいだを縫うように聞こえてきた。むかしは「にい。かんこ。ぽん」だったと思う。にい、かんこ、ぽん、ご飯。兄が家を出て「にい、かんこ、ぽん」は「かんこ、ぽん」になった。今年の春、弟のぽんが祖父母の家に住みはじめて「かんこ」になった。母が階下から呼ぶ。いつまでも聞こえてくる。にい、かんこ、ぽん。にい、かんこ、ぽん。かんこ、ぽん、かんこ、ぽん。かんこ。かんこ。・・・・。(P3) 階下から聞こえてくる母の声が響きます。外側から聞こえてくる音としての声と、それに連動して、頭の中に響く、自分だけに聞こえている音としての声が、ことばとしての意味の姿をまとわせて立ち上がらせながら、語り手である、高校生の「かんこ」の内面の物語が始まります。 小説のページに書きしるされているのは文字ですが、読み手の中には音が広がっていく、そんな印象を作り出す書き出しです。これが宇佐見りんだ! ボクは、チョット、ドキドキします。 父と母、今は家を出ている兄と弟、そして、かんこの家族の物語が、父方の祖母の葬儀に、行きは父、母、かんこの3人、帰りは弟のぽんちゃんを加えた4人の自動車旅行として語られます。「音」と「息」が充満して、読んでいるだけでも窒息しそうな狭い車内で、家族4人、死ぬか生きるかの七転八倒騒ぎが展開される中で、声にならない悲鳴のような叫びをあげながら、こんな結論にたどり着くのでした。 かんこはこの車に乗っていたかった。この車に乗って、どこまでも駆け抜けていきたかった。(P124) 「くるまの娘」という、この作品のけったいな題名の所以ですが、ようやくのことで帰り着いたにかんこは「くるま」から降りることができなくなって「くるまの娘」になってしまうところが、宇佐見りんですね(笑)。 あの時、日がのぼるのが苦しかった。日が沈むのも苦しかった。苦しみをなにかのせいにしないまま生きていくことすらできなかった。人が与え、与えられる苦しみをたどっていくと、どうしようもなかったことばかりだと気づく瞬間がある。すべての暴力は人からわきおこるものではなかった。天からの日が地に注ぎあらゆるものの源となるように、天から降ってきた暴力は血をめぐり受け継がれるのだ。苦しみは天から降る光のせいだった。あの旅から帰ってきて、自分が車から降りることができなくなってしまったと知ったとき、かんこはそう思うことにした。そしてかんこは、車に住んだ。毎朝母の運転で学校へ行った。(P140) はまってしまうと、一気に暴君化する父、今日の記憶を次々と失っていく母、通っていた学校に耐えきれなくて祖父母と暮らす弟、父親の世界から逃げ出した兄、そして、くるまから出られなくなったかんこ。 まあ、実際、どんな家族の物語なのかは、お読みいただくほかないのですが、かんこが、自分に浸るのではなくて明日を生きようとしていることだけは確かで、後味は悪くないのです。 宇佐見りん、快調に走っていますヨ(笑)。
2023.10.21
コメント(0)
-

週刊 読書案内 小池水音「息」(新潮社)
小池水音「息」(新潮社) 上の写真のこの本は若い作家の処女出版だそうです。1991年生まれの小池水音、みずねと読むようですが、という人の「息」(新潮社)という作品集でした。 収められた「わからないままで」という作品が2020年、第52回新潮新人賞をとったデビュー作だそうです。新潮社が新人の作家をたたえる賞には三島由紀夫文学賞という賞があって、有名ですが、新潮新人賞というのもあるのかと、初めて知りましたが、この人の受賞が第52回なわけですから、実は昔からあるのですね。ちなみに、その2020年の三島賞の受賞作は宇佐見りんの「かか」(河出文庫)でした。 で、本書の表題になっている「息」という作品は、2023年の三島賞の候補作だそうです。 とりあえず、表題作の「息」ですが、こんな書き出しでした。 わたしは暗い天井を見上げ、そこからなにかを読み取ろうとする。 ちょうど棺桶ほどの大きさの長方形を縦に横に組み合わせたような継ぎ目が、コンクリートの天井に走っている。読み取るというよりもむしろ、天井のほうから投げかけてくるものをきちんと受け止めなければならないのだとも感じて、継ぎ目の端から端まで、わたしは慎重に視線をたどらせる。 大学生のころ以来、十五年ぶりに起きた発作だった。けれど夜明けにふと目覚めて、自分の気管支がほんとうにひさびさに狭まっていると気がついたときすでに、わたしは無意識のうちに、幼いころの習慣を再現していた。(P9) 小説は「わたし」、大学を出て、15年ほどたった女性によって語られています。彼女は、今、イラストレーターとして暮らしていますが、夜明けの自室で、15年ぶりに起こった気管支が狭くなるという発作の中で「息」を求めて仰向けに横たわりっています。彼女が、どんなふうに「息」を求めているのか、その部屋でのリアルな描写が続きますが、一方で、その姿勢で見上げている「天井のほうから投げかけてくる」ものがなんであるのかを、静かに語りだし、語り続けた趣の小説でした。 日がすっかり昇ったら近所の内科へ行くことにしよう。そう思いながら、わたしはまた瞼を閉じてみる。そのときふと、目を覚ますまで見ていた夢の体感がよみがえった。それはこの十年のあいだ、くりかえし見てきた夢だった。夢にはいつも必ず、弟がいた。私はその夢のなかで、一歩、一歩と、弟のいるほうへ歩み寄ってゆく。その足取りを思い出す。(中略) ふたたび天井に目を向ける。さきほどからなにひとつ変化のない粗い継ぎ目が、コンクリートの天井には走っている。意味のあるなにかがそこには示されている。(P13) 父、母、そして、くりかえし夢に出てくる弟、主治医とその娘、彼女の脳裏に浮かぶ人々の姿、そして、子どもころから「空気のかたまり」求めて続けてきた彼女の、おそらく、三十数年にわたる生活が、静かに、しかし、誠実に語られていました。 おそらく、作家自身の体験が作品の底にあるのだろうと思いますが、この作品の面白さは「喘息」体験のリアルな描写によるのではなく、「空気のかたまり」を求める語り手の生を希求する姿の普遍性を描こうとしたことにあると感じました。 併収されている「わからないままで」という作品は、「息」という作品と、丁度、裏表の構成で、小池水音という作家の実体験と小説との関係を暗示していますが、二つの作品を読み終えて、驚いたのは作家が男性だったことでした。 作家の名前と「息」という作品が、女性の語りで書かれていたことで錯覚したのかもしれませんが、女性作家だと思い込んで読んでいました。まあ、ボクの迂闊さはともかく、この若い作家の力量がなせるワザでもあり訳で、なかなかやるな! という印象を持ちました。読んで損はないと思いますよ(笑)。
2023.10.16
コメント(0)
-

週刊 読書案内 松田青子「英子の森」(河出書房新社)
松田青子「英子の森」(河出書房新社・河出文庫) 「スタッキング可能」(河出文庫)で登場したのが10年前です。当時、若い本読みの方からすすめられて読みました。その後「あばちゃんたちのいるところ」(中公文庫)という作品が英訳されて短編部門ですが世界幻想文学大賞を受賞したのが2021年でした。今回、案内する「英子の森」(河出文庫)は2014年ですから、「スタッキング可能」の直後の作品です。 元は、女優さんだったそうです。松田青子というペンネームはまつだせいこと読む人がいるの狙ったそうです。なんか、笑ってしまいました。 高崎夫人は、自分で低脂肪乳を買ってくるといった。 それはその方が助かるかも、帰るの多分夕方すぎるから、といって出て行った娘の後姿を玄関で見送った。高崎夫人はドアを閉めると小花柄のエプロンを締めなおしながら奥のキッチンに引き返した。小花柄のシャツの肱を上までまくると、さっきまで朝食が載っていた小花柄の皿を洗い始めた。白い窓枠にとまった小鳥が、高崎夫人のためだけにリサイタルを開いた。(P7) これが書き出しです。もう少し読めば、もっとはっきりしますが、ここまで読んで「小花柄」があやしいと気付いた方は、なかなか鋭い「読み手」だと思います。ぼくは読み終えて、次の掌編にとりかかったあたりで気付きました。 とりあえずこれが本書の目次です。6作所収されています。英子の森*写真はイメージですおにいさんがこわいスカートの上のABC博士と助手わたしはお医者さま? で、先ほど触れた「*写真はイメージです」という掌編の書き出しがこんな感じです。 写真はイメージです。この写真はイメージです。青い空はイメージです。白い雲はイメージです。青い空の、ほら、ここ、誰かが手を離して飛んでいった赤い風船はイメージです。晴天でした。昨晩の天気予報を裏切っていい天気でした。気持ちのいい風に葉がさわさわ音をたてて揺れる木々にとまった鳥たちはイメージです。(P85) まあ、予想はつくだろうと思いますが、「~はイメージです。」が延々と4ページにわたって続いて、「この写真を見ているあなたはイメージです」 にたどり着きます。で、ラストはこんな感じです。 このページはイメージです。ページに印刷された小さな文字はイメージです。文字の羅列はイメージです。あなたが読んでいるはしからすぐにイメージです。ええ、そうあなた、あなたです。さっきの物語上のあなたではなく、今度は本当にあなたです。あなたが読んだここまで全部イメージです。いいんです。別にたいしたことを言ってません。すぐに忘れて構いません。文字の連なりはイメージです。言葉の連鎖はイメージです。小説はイメージです。あなたが今読んでいる小説はイメージです。(P89) いかがでしょうか。本作をお読みになっていない方に、いかがでしょうかというのも何ですが、「英子の森」の注釈といっていいような掌編ですね。 トートロジーというのでしょうか、あるいは「イメージ」という、かなり主観を意識させる用語が、「私はウソつきです」的な自己言及の落とし穴をつくっていて、堂々巡りなのですが、ぼくは、「ええ、そうあなた、あなたです。さっきの物語上のあなたではなく、今度は本当にあなたです。」 という、言い回しで、なんだか白けましたね。「イメージであるあなた」ではなくて、「本当のあなた」がいたのでは、ここまで、何をいってきたのかわからないじゃないかといいたくなりますね。 演劇をやっていた方の小説、まあ、少ししか知りませんが、古くは阿部公房とか井上ひさしが思い浮かびますが、この手の言葉遊びがお好きな気がしますね。舞台には必ず生身の俳優がいますからね、この手のセリフが飛び交うのは笑えるわけですが、文章だけで出てくると、あざとい気がしますね。 こうした言い回しにおいて、書き手だけはイメージから自由だということはありえないわけで、そこのところの「自己隔離」というかはどうなっているのでしょうね。 認識はすべて、松田青子のいうイメージだとして、その認識の場にいる「存在」はどうなるのでしょうね。で、その「存在」の当人が「書く」とすれば、何をどう書くのか、そのあたりについて、ちょっと伺いたい読後感でしたね。まあ、その作品が、たとえば「英子の森」とかなのでしょうから、読んで分かればいいのでしょうが、それぞれの作品でも、彼女は小説はイメージです。 ということを書いていらっしゃるだけのような気がするのですね。まあ、そう読んで下さいねというわけです。ところが、読んでいるこちらは、書いている当人は「書く」という行為もイメージだとお考えなのかどうか、そのあたりが気にかかってしまうのですね。 そんなふうに、くだくだ考えさせる作品なのですが、くだくだしていると、そもそも、イメージって、何ですかね。とまあ、読んでる方も堂々巡りで、元に戻ってしまいましたね(笑)。
2023.03.24
コメント(0)
-
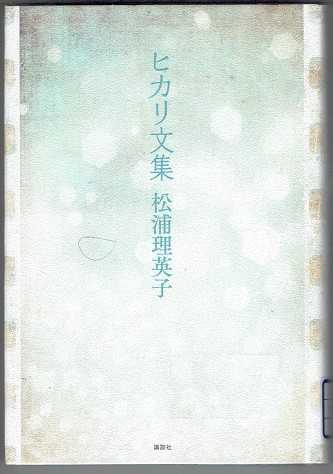
週刊 読書案内 松浦理英子「ヒカリ文集」(講談社)
松浦理英子「ヒカリ文集」(講談社) ネットで検索していると、朝日新聞の「好書好日」という文芸欄に松浦理英子の最新作「ひかり文集」(講談社)について、作者のこんな言葉が載っていました。 身近で「心を使わない人」に会ったことが構想のきっかけ。巨大アイドルグループをテレビで見かけても「心を使わない人」が気になる。「腹黒」「あざとい」と言われながら慕われている。「複雑で興味深く、いろいろ書きようがあると思いました。肯定的に描ければとても魅力的になる、と」 「こころを使わない人」を書いたということでしょうか。 東北の被災地にヒカリという女性を捜しに出掛けて、当地で客死した破月悠高という中年の戯曲作家で演出家が残した未完成の戯曲の主人公(?)である賀集ヒカリという,行方が分からなくなった女性をめぐって、かつて、破月悠高が主催していた学生劇団のメンバー、看板俳優だった鷹野裕、レズビアンの飛方雪実、今は既婚者の小滝朝奈、悠高の妻真岡久代、団員の中で一番若かった男優秋谷優也が、それぞれ手記を書くことで「ヒカリ文集」という私家版の冊子ができあがったという、まあ、わざとらしいといえば思いっきりわざとらしい体裁で、松浦理英子の最新作「ヒカリ文集」は出来上がっています。 作家が「こころを使わない人」として描いているらしいヒカリという女性が、すでに亡くなった破月悠高をはじめ、手記を書いている全員と、いわゆる肉体関係を結び、その全員に、偽りのない「愛」の対象として記憶されていることが、どこか不自然で、異様な人間関係、ゆがんだ記憶だとぼくには感じられたのですが、作品は2022年の野間文芸賞として評価されているようです。 「親指Pの修業時代 上・下」(河出文庫)、「犬身 上・下」(河出文庫)と、いわば奇形の「愛のかたち」を書き続けてきた作家によって、新たな「奇形の愛」が描かれたということでしょうか。 ノーベル賞のカズオ・イシグロがクローンの「愛のかたち」を描いた「わたしを離さないで」 (ハヤカワepi文庫)が話題になったことがありますが、ああ、この作品の登場人物ヒカリは人間ですが、今の流行りでいえばAI、人工知能ロボットによる「愛のかたち」をふと思い浮かべさせる読後感でした。 それほど出来がいい作品とは思いませんが、なんとなく、世界の底が抜け始めているような印象は残りました。
2023.02.11
コメント(0)
-

週刊 読書案内 小川糸「サーカスの夜」(新潮文庫)
小川糸「サーカスの夜」(新潮文庫) 「食堂かたつむり」(ポプラ文庫)が評判で、柴咲コウ主演で映画にまでなったころ、高校の図書館の仕事をしていて、棚に並べるために購入した記憶はありますが、内容は全く知りません。本なんて読まない高校生たちに、そこそこ人気があったせいもあって、ぼく自身はついに手に取って読むことはありませんでした。 小川糸という名前はその時に覚えました。で、月に一度、読んだ本の感想をしゃべっている「本読み会」という集まりの課題になったこともあって「サーカスの夜に」(新潮文庫)という作品を読みました。 僕は今、道なき道を走っている。 餞別にとおじさんがくれたオンボロ自転車は、大人用だった。自分で望んだことだけど、やっぱり僕の体には大きすぎる。爪先をまっすぐ伸ばさないと、ペダルに足が届かない、茶色く錆びたチェーンからは、ひっきりなしに耳障りな音が響いている。(P5) こんな書き出しです。全部で16章の短編連作風ですが、冒頭の「今」に始まって16章の「今」まで、「僕」の体験が、「僕」自身によって、ほぼ、時間の流れに沿って書き綴られている作品です。 「僕」は13歳、本来なら中学1年生になる、多分、春のことです。両親に捨てられて以来、世話になりながら、一緒に暮らしてきてグランマと呼んでいるオバサンの屋根裏部屋から出発して、大人用の自転車に乗って、「道なき道を走って」います。 「僕」がグランマの部屋を出発した理由の一つは、まあ、読みはじめれば、すぐにわかることですからばらしますが、10歳になった時に、ホルモンの分泌が止まり、もう、それ以上大きくならないという体になってしまったことにあります。だから「僕」にとって未来は「道なき道」の先にあって、自転車は大きすぎるのでした。 で、目的地は、街の番外地で興行しているサーカス小屋です。第2章以降「僕」が綴るのは、たどり着いたサーカス小屋での出会いと体験です。 なんだか、この国のそこらあたりの出来事の雰囲気で書き出されているのですが、小説の世界の実際は、体の成長が止まるとか、13歳になって中学校ではなくてサーカスに行くとか、要するに「ここ」ではない「どこか」のお話であって、SFとまでは言いませんが、ファンタジーなのですね。で、まあ、「僕」の成長を語るビルドゥングス・ロマンというわけでした。ここではない場所での成長譚ですから、どこか夢物語というわけでした。 というのも、「僕」という一人称で書き出されているこの小説の主人公には、実は名前がありません。マア、グランマとかはご存じなのでしょうが、読者は「僕」を知っているだけですし、サーカスの人たちは、彼のことを「少年」と呼んでいます。 名前のない少年が名前を得ることが「道なき道」の向こうに「道」を見つけるということだというわけでしょうかね?少々、ありきたりな構成が透けて見える気もしますが、この作家の人気の秘密は、実は、そのあたりかもしれませんね(笑)。 さて、作品のクライマックスです。「僕」が名前を手に入れて未来への道を歩きはじめる、その瞬間はこうでした。 今だ。 誰かがぼくの耳元でささやいた。ぼくは、綱雄上に爪先をかける。 一本の細い綱が鮮やかな虹になるのをジメージした。虹が、ふわりと柔らかく、ボクの体を受け止める。その瞬間、僕は虹の上の××××になる。 僕は、虹の上をそっと歩く。そしてこれからもずっと、未来を見つめて歩き続ける。 引用中の××××は「僕」の新しい名前です。グランマの好きなロシアかどこかのスープの名前のようです。このサーカスの登場人物たちは、皆さん、自分の好きな食べ物で名乗っていらっしゃるわけで、「僕」も食べものの名前を手に入れたわけです。 気になる方は、どうぞ作品に当たってください。この作家のいいところは料理の話が上手なところかもしれませんよ(笑)。
2023.01.26
コメント(0)
-

週刊 読書案内 絲山秋子「末裔」(新潮文庫)
絲山秋子「末裔」(新潮文庫) 「まっとうな人生」(河出書房新社)で絲山秋子に再会して、気が向いたというか、買い込んでいたのに読んでいなかった「末裔」(新潮文庫)という文庫本に手を出しました。 「まっとうな人生」という作品は「逃亡くそたわけ」(講談社文庫)という10年以上も前の作品の続編で、前回は九州横断という舞台だったのですが、今度は、なんと、小説とかにあまり出てこない富山を舞台に、二人の同じ登場人物のその後を描いていた作品でしたが、手に取った「末裔」(新潮文庫)は東京の世田谷に住む役所勤めの男の物語でした。 こんな書き出しです。 鍵穴はどこにもなかった。 最近の住宅にはあまりない、白いペンキを何度も塗りなおした木製のドアはいつもと何ら変わりはなかった。年季の入った真鍮のドアノブも見慣れた通りだった。しかし、ドアノブを支える同素材のプレートなのっぺらぼうで、丸の下にスカートを穿いたかたちの鍵穴は形跡さえなかった。鍵でつついても、指でなぞっても、しゃがんで見直しても、五秒目を閉じても、ややがさついた手触りの真鍮の板には凹みも歪みもなかった。 鍵穴があらまほしき場所にないのだった。 そんなばかなことがあるものか。 二、三度チャイムを鳴らしてみたが、もちろん誰が出てくるわけでもない。ドアノブをつかんで前後にゆすぶってもごとごとと鍵のかかっている手応えがあるばかりだった。もちろん鍵は手の中にある。しかしその鍵は受け入れられない。 鍵穴だけが消えてしまったのだった。 富井省三は、締め出された。(P5~P6) とりあえず、紹介すると、主人公は富井省三、58歳、職業は公務員です。家族は妻靖子に三年前に先立たれ、息子の朔矢は結婚して家を出ていて、大学を出たばかりの娘の梢枝も靖子の一周忌が過ぎたころ書置きだけのこしてでていってしまった結果、いわゆる、一人暮らしの男やもめです。 実母は存命ですが、介護施設で寝たきりというか、鼻歌は歌いますが、息子を認知することはできない状態で、時々見舞いますが、この家にはいません。 職場でどういう地位にいるのか、よくわかりませんが、まあ、そういう男が、ある日、自分の家に帰ってみると、ドアから鍵穴が消えていたという不条理な出来事に直面して、さて、どうするのか?という作品です。 いろんな読み方があると思いますが、ありえない設定が最初に出てくるわけで、「鍵」と、消えた「鍵穴」の関係についてを最後まで謎として読んでしまいましたね。 この作品が書かれたのは2011年ですから、ほぼ10年前です。読み手のシマクマ君は1954年生まれですから、当時の主人公と同じ年です。書き手の絲山秋子は1966年生まれだそうですから、執筆当時は40代の半ばですから、主人公より10ほど年下だったことになります。 もしも、発表当時、読んでいれば、主人公と業種は少し違いますが、同じ年齢で、配偶者はいますが、子供たちが出ていった「家」に暮らし始めた男だったわけで、そのことが、10歳ほど年下の女性作家に書かれていることをどう思っただろうということが思い浮かびました。 ちょうど、義父や実母、少しして実父がなくなっていったころでした。小説の設定は自分が暮らしている「家」でしたが、鍵は手元にあるから、いつでも入ることができる「家」だと思っていた建物を、いざ開けようとすると鍵穴がないという、ある種、象徴的な感覚が、その頃の何かを失いつつあるという気分にリアルに重なりました。 当時、誰も住まなくなった実家の玄関で、なんとなくためらいながら鍵を出して鍵を開けながら、うまく鍵が回るとホッとしたことをありありと思いだしたりしました。 もしも、発表当時、読んでいればシマクマ君は「自分のこと」が書かれていると読んだ可能性がありますが、あの頃から10年を過ごした今は、それを「過去」の事のように感じるのが不思議ですね。 小説は数十日間(?)の富井省三の放浪生活を描きながら、鍵穴のない「家」に入る実力行使のシーンまでを描きますが、滑稽に描かれれば描かれるだけもの哀しさが湧いてくるのが絲山秋子の実力だと思いました。 マア、しかし、20代、30代の人が、これをどう読むのか興味がありますね。カフカばりの不条理小説とでも読むのでしょうか。ちょっと違うような気もするのですが。
2022.10.25
コメント(0)
-

週刊 読書案内 日野啓三「台風の目」(新潮文庫)
日野啓三「台風の目」(新潮文庫) 日野啓三は1929年生まれで、 2002年、大腸がんで亡くなった作家です。今回案内する「台風の目」(新潮文庫・講談社文芸文庫)という作品は、1990年に肝臓癌が発見されて摘出手術ののち、1992年、大病の予後の生活の凝視を描いた「断崖の年」(中公文庫)ののち書かれた作品です。それぞれ伊藤整文学賞、野間文芸賞を受賞していますが、今時、若い人の中で「この人を読む人いるのか?」どころか名前を知っている人も少ない人のような気がしますが、参加している「本読み会」の課題になるという偶然の機会を得て再読しました。 病後の作家が、自らの来し方を回想するという形で書き起こされる作品ですが、じゃあ「自伝小説」かというとそういうわけでもありません。 父親が暮らした中国地方の田舎町を訪ねるところから始まりますが、そこで思い浮かんだ記憶は、少年時代を過ごした大日本帝国統治下の朝鮮半島の田舎の村、京城での中学時代へとうつろっていきます。たとえば京城での中学時代、暮らしていた城内という地域で行われていた「冥婚」と呼ばれる民俗行事の記憶がこんなふうに記述されています。 水際で人たちはまた人形に語り掛け、泣いて笑った。人形は大きな動かない目で見かえしている。花婿の黒塗りの紙の冠が、花嫁の原色の紙製の盛装が、外の光で一層濃く鮮やかになった。 輿は流れの中にかつぎこまれた。きょうも穏やかな河の流れは、黒塗りの輿も静かに受け入れるようだった。男たちは深さが胸までくる中流で、輿を水面におろした。その動きで人形の腕と腕が絡み合う格好になった。木製の輿は水に浮いた。ふたつの人形は並んで水面に座っているようだった。(中略) 人たちは子供たちまで岸を去らなかった。河が本当にあの世まで続いていることを信じっ切っているように。花嫁の派手な紙衣装の色がいつまでも見える。 病院で繰り返し私はその先のこと、「城内」のところで河が大きく湾曲して輿が視界から消えてからあとのことを考えた。考えたというより、意識の奥に幾度も鮮やかに見えた。 「城内」の岸から先の、再び東方へと向きを変えて再び「駅前」に近づくまでの、一番湾曲度の大きな部分、人家もなく畠もなく人たちもめったに行かなければ、私自身もとうとう一度も行ったことのない部分の光景が、幾度も浮かんでくるのだだった。(中略)その光景、肉眼では一度も見たことのない光景が浮かんでくる度に、私の気分は濃く妖しく和んだ。 死者たちの結婚を、古来朝鮮では「冥婚」と呼ぶことを知ったのは最近のことである。 ここから作家は、次々と浮かんでくる記憶の光景を巡って、「茫々と」考えこみます。 多くの人たちが持続的に自分の過去を(まるで上空からすっと眺め続けてきたかのように)書いている文章を目にするたびに、私は驚く。深く驚く。単に一般的な記憶力という能力なら人並みのはずなのに、自分自身の過去となると。ありありと濃密にいつでもその場に帰ることができる少数の場合と、概括的に年表的事実のようにしか思い出せない多くの日々に、はっきりと分かれている。つまり私の過去は、無残に切れ切れと隙間だらけだ。 ということについて茫々と考えているうちに、こんなことに思い至る。今から振り返るわたし自身の記憶力、想起力が問題なのではなくて、そのときそのときの体験の質そのものに違いがあるにちがいない。意識の表面の日常的な層でそのときは正常に行動し他人とも話し合っていたはずの多くの普通の日々と、不意に世界の思いがけない感触と出会い溶け合った謎めいた内面の時と。 意識の表層と深層との明確な境界があるわけではないけれども、表面的な意識で単にまともに生活していただけの時は、多分脳波はなだらかに安定しているのだろうが、刻々に流れ過ぎ去ってゆくだけのように思われる。逆に何らかの仕方で深層にじかに触れた時―多くは不安と憂愁の時、そのときが言葉の深い意味で、現在すなわち現に在ることであって、だから同じように心ざわめくどのいまとも通底している。時計と暦の時間ではどんなに遠い過去のことであっても、つねに現在となる。現在とは刻々の数秒間のことではない。そのときそのとき露出した深層の震えが、通常の知覚と意識を越えて、現にある状態を形づくっている。 過去と現在というのは、実は時間概念ではないのだろう。世界と意識が表面的に対応したか、より深層で触れ合ったか、といういわば空間的概念と考えることもできる。多くの正常な日々は初めからすでに遠くにあったのだ。表面的でしかない事柄も経験も、どこかに消えたのではなく、初めから意識の地平線に見え隠れしていただけなのである。反対に現に在るものはつねに現前にある。覚えているのではない。今見えるのである。多分この世界を生きるということは刻々に流れ去るひとすじの流れないし物語のようなものではなく、つねに甦る現在が少しずつ増えて膨らんで奇妙な球体のようなものにちがいない。歪んで、隙間だらけの。(単行本P61) 作家の頭の中に浮かんでくる記憶、想起される過去をめぐって、やがて人間が生きている時間が問い直されていく思考のプロセスが、ぼくにはいかにもスリリングなので、長々ですが、引用しました。 で、作家が現実の生活の中でたどり着くのは、今はこの世の人ではない父親のかつての寝姿と声を想起するこんな地点でした。 いきなり背後で父の声がした。「人間の一生なんて、ウシやウマとそう変わらんもんだのう。」低い声だが、はっきりとそう聞こえた。寝言ではなかった。(単行本P269) 父は一ヵ月後、年が明けて一番寒いときに死んだ。直接の死因は肺炎だそうだ。いま私は退院後三年目に入って生きている。転移するとすれば今度は確実に肺だ、と医者に言われながらもタバコを吸い続けて。(単行本P273) 300ページにわたる記憶の記述を続けてきた作家が「つねに甦る現在が少しずつ増えて膨らんで奇妙な球体」としてとらえた「生きている時間」としてとらえた、今、この時の「生」は、書斎の窓から差し込む夕日の光の中に浮かび上がる、机の上や部屋の床に散在している、なんでもない日用品の輝きでした。ガスのなくなりかけた百円ライター。耳かき棒。タバコの箱。ステンレススチールの爪切り。(以下略) 普段は気にもとめないこんな物体たちが、どうしてこんなに深く気配を帯びて輝くのか。沈黙の威厳を、用途を越えた優雅さを。 それに気づくために、私の六十年の生涯があったみたいだ。(単行本P276) 上に引用しましたが、「不意に世界の思いがけない感触と出会い溶け合った謎めいた内面の時」が突如現れ出て、「露出した深層の震え」そのものにたどり着いた、今、このときの作家の姿が美しく描かれたラストシーンでした。 病後の作家が、浮かんできた、もう何年の前の父の生前の記憶のなか、死の床の父の声の想起の中でたどり着いた究極の「時間」が、こんなふうに描かれていることに意表を突かれながら、生の実相を描こうとする作家の静かな執念を思い浮かべ、しばし、瞠目の結末でした。 実は、光り輝く身の回りの品々は数ページにわたって、延々と記述されています。その描写に心打たれるかどうか、それは読んでいただくほかありませんが、ぼくにとっては、50代の半ばに読んだ時には気づけなかった、この作家の本領との出会いでした。あるいは、小説という表現形式のたどり着くべき「達成」を感じたというべきでしょうか。 いかにも、彼が、古井由吉や後藤明生と肩を並べる「内向の世代」であることを再確認させる傑作だと思いました。
2022.10.22
コメント(0)
-

週刊 読書案内 高村薫「我らが少女A」(毎日新聞出版)
高村薫「我らが少女A」(毎日新聞出版) 久しぶりに高村薫の名前を思い出して、一応、最新作「我らが少女A」(毎日新聞出版)を読みました。2017年8月から2018年7月までの1年間、毎日新聞で連載された新聞小説だそうです。何となく読み始めて、一泊二日、休むことなく読み続けて読み終えました。最近では珍しい「かっぱエビせん」読書でした。 もともと、高村薫は贔屓の作家で、ずっと読んできましたが、数年前に評判になった「土の記」(新潮社・上下2巻)を読んで以来、ご無沙汰でした。ご無沙汰の理由は、特にありませんが、まあ、読み始めるとやめられなくなって、ヒマな生活のせいもあって、際限がなくなってしまうからかもしれません。 たとえば、今回の「我らが少女A」の書き出しあたりにこんな文章があります。まだ、どんな事件がたち構えているのか、全くわからない、読もうか、読むまいか、ちょっと考えるあたりです。 ほら、すぐ近くの調布飛行場を離陸した小型機が、線路に沿って立ち並ぶ車返線の門型鉄塔の上を、斜めに横切ってゆく。風向きによって離陸する方角が変わるそれは、近隣の住民たちの風向計のようなものだ。滑走路の南側から北へ飛び立った今朝は、北風。(P10) 書き手は、登場人物ではない作家自身(?)です。で、この情景描写が呼びかけている相手は読者に違いないのですが、調布飛行場を飛びたつ飛行機を見上げて、「今朝は北風。」と畳みかけられても、普通は「調布飛行場ってどこだよ?」ってなるのですよね。でも、高村節ともいうべき、このトーンというかテンポというかに引き込まれて、行ったこともない東京近郊の風景の中で、思わず、空を見上げることになると、もうやめられません。 冷静で理知的、リアリズムの描写の権化のような印象の高村薫ですが、彼女の小説の本領は、この「語り口」だと思います。 多摩駅のホームでは若い駅員が一人、目を細めてその薄青の空を仰ぐ。ニキビ痕のある頬に光が降る。 あれは新島行きの便か―? 午前五時三十八分の武蔵境行き始発から三時間以上もホームに立っていると、夜勤明けの駅員の脳内では規則的に出入りする電車の刻む時計と、伊豆半島への定期航路の小型機の刻むそれが溶け出して混じり合い、いま何時なのか一瞬わからなくことがある。離陸と着陸のたびに駅の上を横切っていく小型機を仰ぐのはほとんど条件反射だから、それで弛緩した脳内時計が元通りになるわけでもなく、駅員はあまり意味のない自問自答をしばらく続ける。(P10) 続けて語られるのは、登場人物の今の姿です。ここに登場する駅員の名前は小野雄太、勤務している駅は西武多摩川線の多摩駅です。 多摩川線というのはほかにもあるようですが、この小説の多摩川線というのはJR中央線武蔵境駅から、終点の是政駅までの、たった8キロを走る西武鉄道の支線です。近くに多摩川の支流である野川が流れていて、東京外大や警察大学校がありますが、それらの学校の最寄り駅が多摩駅のようです。 関東平野の西の端の丘陵地帯で、野川は「はけ」と呼ばれる地形とセットの地名です、関西から出たことのないぼくが、何故そんなことを知っているのかというと、大岡昇平の「武蔵野夫人」の舞台で、古井由吉や長野まゆみの作品の題名にもなっているからです。特に大岡は空間に着目した作家として有名ですが、「はけ」の地形にこだっわってあの作品を書いていました。で、この作品は「野川公園」というかなり大きな、川沿いの公園が舞台でした。高村薫は関西在住の作家だと思いますが、この支線の沿線にあるICU、国際基督教大学は彼女の出身校です。見よ、今日も、かの蒼空に 飛行機の高く飛べるを。給仕づとめの少年が たまに非番の日曜日、肺病やみの母親とたった二人の家にゐて、ひとりせっせとリイダアの独学をする眼の疲れ・・・見よ、今日も、かの蒼空に 飛行機の高く飛べるを。 唐突ですが、1911年、明治44年、25歳の石川啄木が書いた「飛行機」という詩です。小説とは何の関係もありませんが、書き出しの文章で思い出したのはこの詩でした。 小説に戻ります。件の小野雄太は27歳、三流大学をやっとのことで卒業し、電車の運転手になる夢を見てでしょうか、電鉄会社に就職しましたが、眼病を患い、車掌、運転手の夢を断念して、支線の小さな駅の駅員として働いています。 その青年が、改札を通り過ぎる客の中に、あの、高村薫ファンであればおなじみの、合田雄一郎の姿を見つけ、高校1年生のときに近所で起こった、今でも未解決の殺人事件のことを思い出して、警察小説が始まりました。 合田雄一郎は12年間の事件の捜査現場の責任者で、殺された被害者の勤めていた学校にも顔を見せていたのを、当時、在校生で、被害者の教え子の一人だった小野君がフト思い出したというわけです。 何でもないことのようですが、この「想起」の偶然性のリアリティーがこの小説全編のリアルと直結しています。 作品では、小野雄太と彼の中学時代の同級生、被害者の孫である栂野真弓、ADHDでゲーム中毒の浅井忍、作品の冒頭で同棲する男性に殺される上田明美の四人と、その家族たちが主人公たちでした。小説は、その十人ほどの人物たちの、12年前の上田明美、すなわち「少女A」についての記憶の物語、いや、想起の連鎖、何かのきっかけで、ふと思い浮かぶあれですね、を描いた物語だと思いました。 12年前の出来事の関係者の想起の連鎖を追い、やり残した事件の真相の輪郭を描こうとするのが合田雄一郎ですが、警察大学校の教官として「証拠」や「立証性」を論じながら、繰り返し、やり残した事件の現場、野川公園の河川敷に立ち戻る合田の上空には、今日も、あの日と同じように飛行機が高く飛び去って行くのです。見よ、今日も、かの蒼空に 飛行機の高く飛べるを。 読み終えて、やっぱりこの詩句が浮かんできたのですが、作家の中にこの詩句が浮かんでいたのかどうかは、当たり前ですが定かではありません(笑)。 犯人捜しのエンターテインメントを期待されるむきには空振りかもしれませんが、高村薫の作品をお読みになりたい方にはミートしているのではないでしょうか。ネットのレビューも、評価真っ二つのようですが、ぼくは二重丸でした(笑)。
2022.10.05
コメント(0)
-
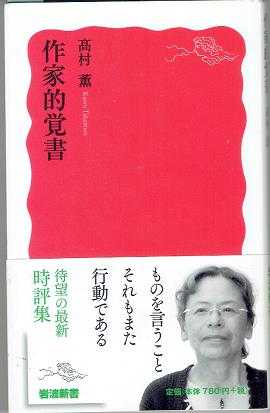
週刊 読書案内 高村薫「作家的覚書」(岩波新書)
高村薫「作家的覚書」(岩波新書) 元気になったので、久しぶりに三宮に出ました。高架下の古本屋さんの棚で高村薫の岩波新書「作家的覚書」が目に入って、棚からとり出してみると200円だったので買いました。2017年の新刊ですが、2014年ころ、岩波書店の「図書」とか、新聞とかに書いていた時評を集めた本です。 ほぼ、10年前の、それも時評ですから、書かれている内容や、中には講演の記録もあるわけで、その発言が古びているに違いないとは思ったのですが、まあ、200円なので買いました(笑)。 読み始めてみると、過去10年の、そして、今、現在、たとえば、仕事からほぼ引退した徘徊老人を困惑させる社会事象の、「はじまの出来事」の指摘でした。 例えば、こんな文章があります。「想像もしていなかったこと」「図書」2014年6月号P26 あるとき市井の想像を超えてゆくのは、時代の状況も同じである。たとえばこの二十一世紀に、ロシアがウクライナを併合するようなことが現実になろうとは―。国連安保理やEUの外相会合で欧米各国の代表が右往左往している状況を眺めながら、二十世紀の二つの大戦や太平洋戦争の前夜はこんなふうだったのだろう、などと想像したりするのは、二十世紀半ばに生まれて多少なりとも戦争の時代の残り香ぐらいは嗅いでいる世代の杞憂だろうか。 それにしても、自国民の保護を名目に軍事力で他国の領土を併合するという帝国主義の論理が今どき現実にまかり通りことを、欧米各国も日本も想像だにしていなかったように見える。想像ができなかったのは、国境を越えて経済的に依存しあう今日のグローバル世界を、旧来の帝国主義が易々と踏みにじってゆくこと、そのことである。あるいは、そんなことはたぶんおこらないという根拠のない希望的観測をもって地政学的なリスクに眼を瞑らない限り、グローバル世界など、標榜できないということなのだろうか。 かつて、未来に行けば行くほど人類は賢くなって所問題は解決に向かい、世界は平和になってゆくだろうと信じていた私はかの9・11とともにいなくなったけれども、未来を悲観しながらも、原発の重大事故や、軍事力を誇示する帝国主義の台頭など想像できなかったこの頭は、まだどこかで明るい未来の幻想を捨てられないでいるのかもしれない。(P27) あれこれ、言葉はいりませんね、2022年、今年の冬、ロシアのプーチンが、高村薫の言う帝国主義の論理を、夜郎自大に振り回し、隣国ウクライナに対して武力による侵略を始めたときに、実は何が起こっているのか徘徊老人には理解できませんでした。 しかし、今、こうして読んでいると、10年前にはじまっていた出来事の、10年後の未来の帰結にすぎないことを、彼女はすでに予言していたといっていいでしょう。ぼくたちは、彼女の予言していた10年後の「明るくない未来」を、今、生きていることに気づかされるわけです。 案内はこれくらいでいいのですが、つい先だって「国葬」とかで祭り上げられ、世間を騒がせている、当時、宰相の地位にいたAについてもこんな発言があります。「いつもの夏ではない」「図書」2015年十月号沖縄戦終結の日から、広島・長崎の原爆投下を経て終戦の日にいたる日本人の毎夏の厳粛な気分が、今年は安倍首相の歪な歴史観や個人的な思い入れによって、たびたびかき回され、混ぜ返された。広島の原爆記念日の挨拶ではあろうことか非核三原則の文言を削って国民の顰蹙を買い、終戦の日に合わせて発表された戦後70年の首相談話では、事前の有識者懇談会の提言で示された侵略や植民地支配の事実から主語を抜いてしまい、長すぎる戦後になんとか一つの区切りをつけたいと願う一国民の切実な思いを、今さらのように愚弄してくれた。60年以上生きてきて、これほど不快な思いが募る八月十五日はほかに知らない。 謝罪や反省とは本来シンプルなものであり、その論理も文言も当然シンプルになる。微妙な言い回しや複雑な文言は無用であり、微妙な言い回しが使われる限り、それは謝罪にも反省にもならない。否、より正確にいえば、戦後七十年談話で語られた「反省」は「我が国は(中略)繰り返し、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明してきました」という過去形であり、談話を出した首相本人はけっして反省も謝罪も表明していない。このことを言い換えれば、「アジアの人びとの歩んできた苦難の歴史を胸に刻み」「歴史の教訓を深く胸に刻み」と神妙に繰り返される文言はみな虚言だということである。(P108) ここで話題にされているのはAという人物の「虚言」についてですが、彼の虚言を支えていたのが、おそらく、虚言を弄して巨大化したインチキ宗教団体であったことが、その、一見すれば、悲劇的だった最期のおかげで、今、明らかになっているのですが、さすがの高村薫も、インチキ教団については、この時評のどこでも触れていません。 「晴子情歌」三部作をすでに書いている高村ほどの作家であれば、昭和の妖怪Kにはじまり「虚言」の宰相Aにいたる一族の、権力に対するなりふり構わない欲望の実相を見破ることは、さほど難しいことではなかったと思いますが、高村がその演説を「虚言」であると喝破した10年後の未来にさらけ出された実相は、高村をしても、まさかこれほどまでにという醜態ではなかったでしょうか。 まあ、古い時評を読むという、ズレたことをしながら、この作家の次作に、ちょっと期待してしまいますが、まあ、お書きになることはないのでしょうね。それにしても、200円はお安い1冊でした(笑)。
2022.09.30
コメント(0)
-
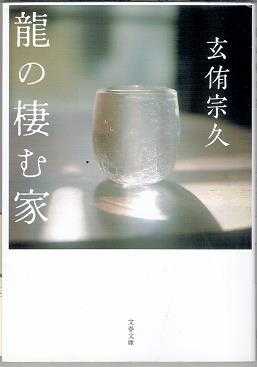
週刊 読書案内 玄侑宗久「龍の棲む家」(文春文庫)
玄侑宗久「龍の棲む家」(文春文庫) お話のお上手な和尚さんが檀家の人たちを集めて法話をするなんてことは、最近でもあるのでしょうか。 玄侑宗久は「中陰の花」とかいう作品で芥川賞をとった作家ですが、禅宗のお坊さんでもある方のようです。本作を読み終えて、最初の印象は、なかなか懐の広いお坊さんのお説教という感じでした。 2メートルほど先を歩く父に、幹夫は同じ間隔を保ちながら従(つ)いていく。息子の存在を、どの程度意識しているかは知らないが、とにかく車の危険だけを気にしながら幹夫はどこまでも従いていこうと思う。(P7) こんな書き出しです。市役所勤めだった父親は70代の半ば、定年退職して15年だそうです。5年前に妻を亡くし、一人暮らしになりましたが、その後、引用文中に登場する幹夫の兄の哲也夫婦が都会から帰ってきて世話をしながら暮らし始めたようです。 で、ここ数年、日々世話を焼いてくれていた哲也の妻が肝臓がんを患い、まだ、50代という若さで亡くなってしまうというショックのせいなのか、父親の言動が変化したようです。徘徊するというのです。 書き出しは徘徊老人の保護者として、後ろに付き添って歩いていている幹夫の内心ですが、50を超えて、独り者である幹夫が仕事をやめて、父の介護(?)のために同居し始めたある年の春の終わりころから一夏越えての出来事が「小説」になっています。 読み始めて、まず。気にかかったのは季節の花の描写でした。 兄の哲也から急な電話で呼び出されたのは先々週の日曜日だから、もう二十日ほど前だ。 亡くなった母の好きだった大手毬が、父の家庭には満開だった。(P9) 杜若、ニセアカシア、サクラ、連翹、桐の花。父の徘徊の道筋で出会う花々に、読み手のぼくは気をとられていきます。花が紫陽花、木槿、バラ、ユリと季節とともに変化していくところも、ありきたりといえばありきたりですが、この作品の素直さとでもいえばいい変化でしょうか。上品なお坊さんのご法話という気がする所以です。 何気なく読んでいたのですが、やがて、老いた父親の徘徊という物語はこんなクライマックスを迎えます。 木槿や梅、花桃、梅もどき、柘植、珊瑚樹、柏などはもちろん、ドウダンツツジ、皐月、沈丁花、梔子、躑躅などの灌木、ことごとく伐り倒されている。縁側にぼんやり座る佳代子を見遣り、それでも庭を巡ってみると、一番外側の黒竹だけは除いて、他にユリや矢車草、ダリヤや百日草などの草花も咲いたまま刈られ、それらが庭一面に暴風でなぎ倒されたように積み重なっている。(P143) もちろん、すべて、穏やかに徘徊していたはずの父親の所業です。縁側でなすすべもなく座り込んでいる佳代子さんは、偶然知り合って世話になっている介護職の女性ですが、ここまで、折に触れて描写されてきた花木がすべてなぎ倒されて要り、このシーンこそがこの作品の肝だと思いました。認知とかアルツハイマーといった、徘徊老人の病像についていっているのではありません。 「老いる」ということの隠しようのない真実がここには赤裸々に表現されいるのではないでしょうか。作品はここから、いかにも、お坊さんのご法話に似つかわしい、まあ、とってつけたような結末へ向かうわけですが、作家としての玄侑宗久の評価すべき性根は、この描写に尽きると思いました。 まあ、お坊さんというの、職業柄もあるのでしょうが、ぼくのような無宗教というか、杜撰というかの人間にとっては、時々、ギョッとすることをおっしゃるものですが、この章でも、その片鱗は「露出」しているというべきかもしれませんね。まあ、気になる方はお読みください、すぐ読めますよ(笑)。
2022.09.17
コメント(0)
-

週刊 読書案内 南伸坊「笑う茶碗」(筑摩書房・ちくま文庫)
南伸坊「笑う茶碗」(筑摩書房・ちくま文庫) 単行本は2004年の新刊です。今ではちくま文庫になっています。著者の南伸坊は「ガロ」の編集長をしていたりした人で、路上観察とかハリガミ考現学とか、1980年代に才気あふれる活躍をした人です。 いろいろやっていらっしゃったことは、まあ、バカバカしいといえばバカバカしいのですが、面白いといえば面白いわけで、結構はまりました。なにが面白いと言って、まあ、イラストレイラーということもあるのでしょうね、しょっちゅうお目にかかるお顔には、才気とかいうような鋭いものはまったく感じないのですが、だれもがすぐ覚えるに違いないというようなところです。 1947年の生まれですから、2000年を超えたあたりから「老人」を標榜して、ネコに俳句を作らせたり、問題の顔を使っての「本人の問題」を追求するなど、徹底した遊び感覚の人です。 本書は「月刊日本橋」という、東京のタウン誌の連載です。はっきり言って、ちょっと時代とともに古びたようなところがあって大して面白くないのですが、ぼくのようなズレた人には受けるかもしれません。 いまどき、ケータイ いまどき、ケータイ電話を買ってしまった。つまり、いままでケータイ電話を持ってなかった。買わなかったのは、ケータイ電話に批判的だったからではない。目のカタキにしてたわけでも目くじらを立てていたわけでもない。 ようするに必要なかったのだ。たいがい事務所にいて、手許に電話が置いてあるし、外出先で電話の必要があるときは公衆電話からかければよかった。ただ、一度だけこんなことがあった。古河に蓮見に行った時だ。真夜中から明け方まで待機して、蓮の香りをかぐ。満喫して、さて、駅まで帰るタクシーを呼ぼう、というのでいつもそこから電話していた公園入口の電話BOXのところまでいくと、そのBOXがコツゼンと姿を消していたのだった。あれは何年前だったか? ともかくしかたがない。どこか赤電話のあるところを探そう(赤電話は実はとっくの昔からない。あるのは緑電話だが、近頃は緑電話とも言わないし、そもそもその緑もどんどんなくなっているのだった。)(P160) ケータイ電話が普及して、公衆電話が消えたのは90年代の事だと思いますが、実はボクは2020年まで、ケータイを持っていませんでした。 シンボーさんのように、タクシーを呼ばないと動きが取れないような場所に旅した経験も皆無ですし、外出中に誰かと電話で連絡を取る必要が、ほぼ皆無な生活でしたから、学生さんとかや、自分の若い家族たちが所持することは、トランシーバごっこの延長くらいにしか感じていませんでしたし、実は、今でも感じていません。 というわけで、この後、彼がケータイを手に入れるまでのバカ話が、あれこれ書かれているわけです。で、それも、さほど面白いわけではないのですが、まあ、「クダラネー」とか感じながら読んでしまう本です。 なんか、あんまりすすめてませんね。マア、そういう本ですね(笑) でも、こういう感じが「面白かった時代」は確かにあったんですよね。若い人は、どう思うのでしょうかね?
2022.08.31
コメント(0)
-
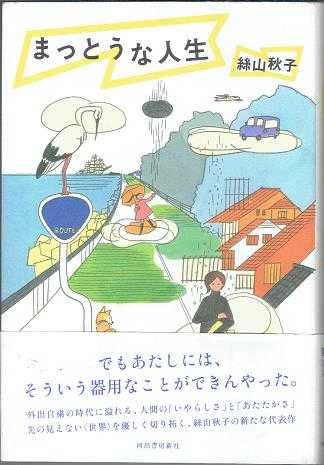
週刊 読書案内 絲山秋子「まっとうな人生」(河出書房新社)
絲山秋子「まっとうな人生」(河出書房新社) 絲山秋子という作家が、ぼくは案外好きなのですが、彼女の最新作「まっとうな人生」(河出書房新社)という作品を読んで、ひさしぶりに「そうだよな。」と納得しました。 もう十年以上も昔のことですが、彼女の「逃亡くそたわけ」(講談社文庫)という作品を読んだことがあります。その後、映画化されたりしたらしいのですが見ていません。小説は「なごやん」と「花ちゃん」という、二十代の男女の二人組が入院していた博多の精神病院を抜け出して九州縦断の逃避行をする話で、なんだかとても哀しくて痛快だったと記憶している作品でした。 この本の見開きページにある「まっとうな人生」の舞台のイラストです。なぜ、そうなったのかよく分かりませんが、あれから、十数年経って「花ちゃん」は富山で暮らしていますというのがこの作品の始まりでした。「よそ者のことを、富山では「たびのひと」と言う。何十年住んでいても出身が違うだけでそう言う。大学から関東や関西へ行って有名人になった人が、いつまでも地元でちやほやされるのと同じしくみだ。よそ者、ということを考えない日はなかった。(P10) これが、まあ、ほとんど書き出しですが、九州から富山に移住(?)して、今ではアキオちゃんと呼ぶ配偶者と、10歳になる佳音ちゃんという女の子と三人で、まあ、そこそこ平和に暮らしているお話です。 まあまあ元気、というのは一応通院しながら病気をコントロールしているということで、二年に一度くらいは再発もある。 肌のハリや髪の艶がなくなっていくように、病気も少しずつ鮮度を失っていくと感じている。麺類でいえばコシがなくなるというか。病気そのものの主張が弱くなるというか。でも他人から見たらわからない。激しく見えることもあると思う。特に妊娠中は予防のための炭酸リチウムや向精神薬が中止されて、大変やった。中略 発病したときは「そううつ病」だったのが、今は「双極性障害」に名前も変わった。初めて躁状態になったときは、なんかどこか、自分の奥の方で力をためて準備していた病気が躍り出たみたいだった。病気は強くて真っ黒で弾力があって、その勢いであたしを乗っ取ろうとしていた。気持ちの悪い病気の粒が、体の中から表面に出てきておはじきみたいにざらざらするのを感じた。あたしの皮膚には、さまざまな大きさの目が無数にあって、脳に映像が伝えられることはないのに、たくさんの目が開いて、あるいはこれから瞼を押し上げて開こうとしていると思った。神社でしか目覚めない目、台風のときだけ開く目があって、耳には聞こえない周波数の音だけに反応して目覚める目があって、生きているそろばん玉みたいなそれらの目を意識するのを狂っていたというのは簡単だが、あのときは、これでわかったと思った。うまく言葉にできないけれど、気がつくとというのはそういうことではないだろうかと今でもちょっと思う。(P11) というわけで、身体的、精神的不調と付き合いながら暮らしている「花ちゃん」の独り言小説ですが、あの時の「なごやん」もまた、なんと富山に暮らしているという偶然の再会で、作品は急展開するかと思いきや、別に何も起こりません。 まあ、それが絲山秋子というわけで、読んでいる方も、何か事件が起こったり、人の生き死にのドラマが盛り上がったり、男女関係がややこしくなったりというふうな、まあ、ありがちな「おもしろさ」どこにもありません。あるのは、なんとなく蔓延してるコロナの世相ですが、それとても、とりわけ騒ぎ立てて書かれているわけではありません。もちろん「双極子障害」という今では、はやり言葉のようになっている病気や、その病像についてのカミングアウト小説というわけでもありません。 花ちゃんの独り言は、ただ、「わかること」の、ちょっと手前で、うまく言葉にならない「わからないこと」に、じっと、辛抱しながら「ことばあそび」を楽しんでいる(?)、いや、苦しんでいる(?)風情で続いていきます。 干していた寝袋を回収に行くと、海を背にした佳音が両手をひらいて、腕を広げた。「お母さんもこうやってみて」小さかったころの「抱っこして」のポーズみたいだ。あたしが真似したら祝福を与える怪しい宗教家みたいやんと思った。「なにこれ?」「お日様が当たると、気持ちいいでしょ?」たしかに、掌のくぼんだところに朝の光が当たっている。小さくてあたたかい温泉を載せているみたいだった。「滝とか、風に向けても気持ちいいんだよ」「くぼんだところって、握手しても触らないとこだから、敏感なのかな」「焚火にあたってるみたいね」これが受け止めるってことなのか、とうっすら思った。(P250~251) 作品は2019年4月にはじまった花ちゃんの日々の独り言の記録ですが、2021年10月、コロナ騒ぎのなか、家族でキャンプにやってきた海岸での花ちゃんと佳音ちゃんのこの会話で記録は終えられます。 読み終えたシマクマ君は、ベランダに出て掌をお日様にかざします。で、「そうだよな」という納得が掌に広がるのを感じます。他人事だと思っていたコロナ騒動の当事者を経験して、ようやく、外に出てもよくなった朝の出来事でした。
2022.08.28
コメント(0)
-

週刊 読書案内 川本直「ジュリアン・バトラーの真実の生涯」(河出書房新社)
川本直「ジュリアン・バトラーの真実の生涯」(河出書房新社) なんだか、ヘンテコな小説を読みました。川本直「ジュリアン・バトラーの真実の生涯」(河出書房新社)です。単行本で一段組ではありますが、ほぼ400ページの長編です。 川本直という作家は、批評家としての仕事はあるようですが、小説に関しては、いわゆる新人作家で、この作品がデビューらしいのですが、いきなり、読売文学賞を受賞するという快挙(怪挙?)です。知られざる作家 日本語版序文 ジュリアン・バトラーの名前を知ったのは1995年、15歳の時だ。トルーマン・カポーティとゴア・ヴィダルを単独していたぼくは、二人と並び称されるジュリアン・バトラーという作家を発見した。戦後アメリカ文学をだ評する小説家だが、邦訳はすべて絶版になっている。日本ではいまだ知られざる作家といっていい。 現在でも英語圏ではバトラーのすべての長編小説はペンギン・モダン・クラシックスから再版され、作家自身も著名人としての華麗な遍歴で知られているが、作品論やテクスト論はあっても作家論や評伝はない。バトラーの生涯はその名声に反し、長きにわたって夥しい伝説的なゴシップの靄に包まれていた。 2017年に出版されたアンソニー・アンダーソンの回想録「ジュリアン・バトラーの真実の生涯」によって、謎めいたバトラーの実像は明らかになった。アンダーソンは覆面作家だったが、この回想録で自らの正体も公にしている。 本書はAnthonyAnderson.TheRealLifeofJulian Butler:AMemoir.(RandomHouse,2017)の全訳である。 川本直 単行本の冒頭には、後半は省略しましたが、こんな「日本語版序文」掲げられています。巻末には10ページに渡って参考文献がリストアップされています。ジュリアン・バトラーの邦訳書や、ペンギンブックス等に所収されているという原書の作品リスト、その作品に言及した批評だけでも20項目を超えるのですが、その中にこんなリストを見つけて、ようやくはてなと思いました。吉田健一「米国の文学の横道」(垂水書房)1967年三島由紀夫「不道徳教育講座」(角川文庫)1967年 三島由紀夫に該当の書籍はあります。しかし、吉田健一には「英国の文学の横道」(講談社文芸文庫・垂水書房)という書籍はありますが、「米国の文学の横道」(垂水書房)という書籍はありません。架空の書籍なのですね。ありそうな書名ではありますが、吉田健一に興味を持った経験がある方であれば、彼が「米国の文学」を批評の対象にして言及するということはちょっと考えにくい気がします。 で、ようやく、この作品、及び「ジュリアン・バトラーの真実の生涯」(河出書房新社)という書籍そのものの正体の輪郭が浮かび上がってきました。 世の中には巨大なジオラマとか鉄道模型に熱中する、いわゆる「オタク」と呼ばれる、趣味の世界に生きている人が、けっこうたくさん生息していると聞きますが、本書は米国戦後文学というジオラマの舞台に、同性愛、異性装の異端作家ジュリアン・バトラーという実に念入りに作った人形模型、フィギュアを配置し、動かして見せるというクィア小説なのですね。米文学のもっともスキャンダラスな時代、一際スキャンダラスに生きた恋人たちの生涯を、川本直は微塵の妥協もなく正攻法で描き切る。佐藤亜紀予想をはるかに上回る大傑作。クィア文学の嚆矢、ジュリアン・バトラーに魅了された。その秘められた真実に打ち震えた!伏見憲明 新刊本の腰巻に載せられた、まあ、販売促進のためのキャッチ・コピーではあるのですが、「絶賛」の言葉です。ネット上のレビューでも好評です。が、所詮、模型は模型、インチキはインチキ、「微塵の妥協」もしないのはジオラマ・オタクの本領と感じてしまう読み方もありそうです。オタク的精巧さがこの作品、あるいは書籍の特徴で、そのあたりには感心しながら楽しんで読みましたが、読売文学賞で称えるのは、ちょっと?というのが正直な読後感でした。 フェイクが囃し立てられる時代の風潮の薄っぺらさに対する「不安」を実感するには格好の書籍、本だと思いました。そういえば三島由紀夫の「不道徳教育講座」には「大いにウソをつくべし」とかいう項目もあったように思います。まあ、一度、読んでみてください。
2022.07.28
コメント(0)
-

週刊 読書案内 李琴峰「生を祝う」(朝日新聞出版)
李琴峰「生を祝う」(朝日新聞出版) 「彼岸花が咲く島」で芥川賞の李琴峰の最新刊「生を祝う」(朝日新聞出版)を読みました。中華民国、台湾生まれの女性で、中国語で育った人ですが、日本語の小説が評価されている作家です。 以前「ポラリスが降り注ぐ夜」(筑摩書房)という、同性愛をテーマにした作品を読みました。不夜城、新宿の街の裏通りで星空を眺めているシーンが印象的な作品でしたが、今回は「生と死」、あるいは「出生」を巡るお話でした。 「生を祝う」という、まあ、立派というか、オメデタイ題名なのですが、さて、内容どうでしょうか。 平成生まれの直木賞!と評判になった朝井リョウというという作家が本書の腰巻にこんなことを書いています。ずっと誰にも話せずにいた思いをこの小説に言い当てられた。驚き動揺し焦り―安心した 読み終えて、朝井リョウが何に「安心した」のかが全くわからない作品でした。 作品は、大流行した疫病後の世界という、まあ、ちょっと思わせぶりな近未来の社会を舞台にしています。その社会は同性婚が認められ、国籍差別もなくなった理想的な社会で当事者の責任制、つまりは今はやりの自己責任ということを絶対的な根拠として、個人の意思、それぞれの自由な生き方、死に方が「法」と「社会制度」によって尊重されている社会という設定です。 で、この作品の社会が合法化した「生死」の自己決定権=個人の意思の尊重ということで、具体的に作家が考えついたことが「安楽死の合法化」と、もう一つが「合意出生制度」という二つの制度でした。 「安楽死の合法化」というのは、まあ自分の人生に見切りをつけた人が「死ぬ」のは自由で、その死を助けるのも合法だという制度だそうで、「合意出生制度」とは、妊婦のおなかにいる胎児に「生まれるか」・「生まれないか」を問いかけ、胎児が拒否を表明した場合は、親が勝手に生むことは犯罪であるという制度ということだそうです。 胎児の意思表明はチョムスキーの生成文法理論の応用で可能になったという、シマクマ君にはかなりインチキで、マンガ的だとしか思えない説明があるのですが、まあ、その点はともかく、この作品の最大の欠陥は図式化だと思いました。 私達の生活は、まあ、年齢とか、収入とか、体力とか、ほぼ、数値化が可能な条件によって支えられていて、たとえばシマクマ君の現在を数値化し「統計的=図式的」結果を根拠に「もう死んだほうがましだ」という結論に達するということが可能であると判断するのは思考の放棄なんじゃないでしょうか。 作品の主人公で、語り手である「私」は、同性婚で暮らしながら、愛し合う二人の遺伝子で人工授精した卵子の母親役を引き受けて妊娠している女性で、受精後9か月だかの胎児から出生拒否の意志表示があり、「合意出生制度」によって中絶を余儀なくされるまでの、生活や心境を語るというのがこの作品の構成なのですが、この告白を読んで朝井リョウは、何に「安心」したのでしょう。シマクマ君には、李琴峰がこの作品で何を言いたいのかわからなかったというのが正直な感想でしたね。「生んでくれと頼んだ覚えはありません。」というのが、ある年齢に達した少年、少女の親に対する憎まれ口の定番ですが、「頼みもしないのにこの世に出てきてしまった」のが人間であって、今、「現在」における「未来」に対する予測で、死を選ぶ可能性はありますが、「未来」を生きた結果、選ぶわけではありません。 まあ、そういうわけで、胎児には「生まれるより死んだほうがましだ」という判断はできないと思うのですが、その判断の不可能性をすっ飛ばして「生を祝う」という、皮肉めかした題をつけて作品を差し出すのは作家の怠慢なんじゃないでしょうか。 作品は、まあ、ディストピア小説としても、かなりキワモノだと思うのですが、今の人間たちなら、こういう社会を作るんじゃないかという意味では、この図式的発想こそが、案外、リアルかもと思ってしまう現実があることは否定できませんね。 いやはや、どうなるのでしょうね、こんなふうに考えこんでいると「死んだほうがましだ」にたどり着くんでしょうかね(笑)。
2022.07.11
コメント(0)
-

週刊 読書案内 砂川文次「ブラックボックス」(講談社)
砂川文次「ブラックボックス」(講談社) 歩行者用の信号が数十メートル先で明滅を始める。それに気づいてか、ビニール傘を差した何人かの勤め人が急ぎ足で横断歩道を駆けていく。佐久間亮介は、ドロップハンドルのポジションをブラケット部分からドロップ部分へと変えた。状態がさらに前傾になる。 サドルから腰を上げ、身体を左右に振って回転数(ケイデンス)を上げる。車体は、降られた身体とほんのわずかだけ逆方向に傾くが、重心は捉えている。雨音の合間を縫うようにしてラチェット音が聞こえる。速度が上がるにつれて頬を打つ雨粒一つ一つがチクリとした痛みを伴うようになった。 信号なんかで足止めを食らいたくなかった。 歩行者の信号が赤に変わる。サクマは口をすぼめて腹の底から息を吐きだす。視線を車道の信号に一瞬向ける。ドロップハンドルをさっきより強めに握った。パーテープのクッション感と心地よい反発がグローブを通して伝わってくる。追い越し車線を走る車のブレーキランプが先頭から順々に点灯しだす。車道の信号は黄色。横断歩道まであと少し、左右の景色が流れていく。(1P~2P) 2021年の後期の芥川賞受賞作、砂川文次の「ブラックボックス」(講談社)の冒頭部分です。自転車に乗っている男が前に見える交差点の信号に反応しながら、混雑する自動車の脇を抜けて一気に走り抜けようとしている瞬間の描写です。 交差点の黄色の信号は、ふつう3秒程度だとおもいますが、描写は始まったばかりです。残りの2秒ほどの間に起こった出来事がこのあと3ページにわたって描写されますが、凝縮された時間を描く文章に無駄はなく簡潔で充実しています。この交差点で、なにが起こったのかは本作を手に取っていただくほかありません。 芥川賞の新人作家の文章としては出色の出来栄えで、このあと、作品の結末まで緩むことがありません。 作家は引用部の冒頭、すなわち作品の冒頭では、登場人物を「佐久間亮介」と呼びますが、二度目から結末に至るまで、一人称表記の誘惑にあらがうかのように「サクマ」とカタカナ表記し、ハードボイルドに徹します。感情移入を拒否した、ただ描写の対象であるサクマが描かれ続けていますが、意識の深部からの告白にも似た言葉を読みながら、作家自身がサクマであることを確信する作品でした。 作品冒頭からサクマは信号が黄色から赤に変わる瞬間の交差点を走り抜けようとする運動体としてとらえられていますが、作品全編にわたって、凝縮された時間の中の運動体であり続けようとするサクマが、信号が変わる瞬間の交差点の時間の淀みのような人間関係のブラックボックスの真ん中で前傾姿勢のままクラッシュを繰り返す作品です。 きわどい隘路を一条の光に向けて走り抜けようとする青年に、うまく言えませんが希望のようなものを感じました。ただ、うまくいかないんですよね、こういう生き方って。 自転車便の職場、女性と二人で暮らす家庭、そしてたどり着いた刑務所、それぞれの場所で、決して前傾姿勢を崩そうとしないサクマを描き続ける砂川文次という作家に、年甲斐もなくなのですが、共感の拍手!を贈りたいと思った作品でした。追記2022・06・02 ただの噂なのかどうかよく知りませんが、ロシアのウクライナ侵攻がはじまって義勇軍に志願して出国した作家がいるということなのですが、この人のことなのでしょうか?何となく、そういう行動をしそうな気がする人なのですが。まあ、どなたであろうとも、無事であることを祈るしかありませんね。
2022.06.04
コメント(0)
-

週刊 読書案内 矢作俊彦『マンハッタン・オプⅠ・Ⅱ』角川文庫
100days100bookcovers no73(73日目) 矢作俊彦『マンハッタン・オプⅠ・Ⅱ』角川文庫 遅くなりました。 仕事の忙しい時期と重なったこともありましたが、今回は何を採り上げるかなかなか決まらなかったということもあって時間がかかりました。申し訳ないです。 前回のSODEOKAさんのチャンドラーの『長いお別れ』の次に採り上げるものとして最初に思い浮かんだのは、矢作俊彦の『ロング・グッドバイ』だった。 カタカナにすると同じタイトルかと思うが、英題が付いていて、それが『The Wrong Goodbye』。記してみると、それらしいタイトルになる。 矢作俊彦は、17歳でダディグース名義で漫画家デビューし、その後1972年に作家デビュー。 たぶん、代表作というか「ファン」が多そうなのが神奈川県警の刑事・二村永爾が主人公として登場するシリーズで、本になっているものではこれまで『リンゴォ・キッドの休日』(1978年。帯には「ハードボイルドの旗手」とあり、2編収められた中の表題作には「警官にさようならを言う方法は未だに発見されていない」という『長いお別れ』の最後の一文が引用されている[細かいことではあるが、手許にある清水俊二訳のハヤカワ・ミステリ文庫版では「警官にさよならをいう方法はいまだに発見されていない」と少し表記に違いがある])から以降、都合4冊出ているが、その3作めが『ロング・グッドバイ』である。「私が初めてビリー・ルウに会ったのは夏至の三、四日前、夜より朝に近い時刻だった。 彼は革の襟がついた飛行機乗りのジャンパーを着て、路地の突きあたりに積み上げられた段ボール箱のてっぺんに埋もれていた、 酔ってはいたが浮浪者ではなかった。目をつむり、調子っぱずれの英語の歌をゴキブリに聞かせていた。」 小説はこんなふうに始まる。むろんチャンドラーの『長いお別れ』の「本歌取り」である。ちなみにラストも同じような「オマージュ」が採用されている。 しかしこの小説、591ページもある。未読の『フィルムノワール/黒色影片』は除くとして、個人的に一番印象深い『真夜中へもう一歩』も363ページ。二村永爾が初めて登場する『リンゴォ・キッドの休日』では中編が2編収められているが、それでも163ページと133ページ。これなら何とかなったかもしれないが、それでも長いと思ってしまった。 それではと、機会があればと考えていた別の作家の作品を、と読み始めてみたのだが、記憶の中のものと中身が少々違っていて、さてどうしようかということになり、結局、『マンハッタン・オプⅠ』『マンハッタン・オプⅡ』 矢作俊彦 角川文庫を採り上げることにした。 そもそもは、80年から83年にかけてFM東京で放送されたラジオドラマ『マンハッタン・オプ』の放送台本(矢作俊彦・作)で(ナレーションは日下武史)、それに著者が加筆訂正したもの。私も大昔、FM大阪で放送を何回か聴いた記憶がある。 最初は、昭和60年(1985年)1月から3月にかけて光文社文庫として出た『マンハッタン・オプ』1、2、3。その後、今度は角川文庫として同年5月と7月に2冊が追加される。確か、文庫オリジナルだったはず。紹介したのは後者。CBSソニーが版元になった版もあるようだが、未確認。 この後、2007年にソフトバンク文庫で全63編(数えてみたら光文社版と角川版に収められているもので都合63編だった)を4冊に再編集して再発売。今はそれも(紙版は)絶版のようではあるのだが。 光文社と角川の5冊は家の本棚に収まっていたので確認したが、前者では1編がほぼ20-40ページ、後者では10ページあまりからせいぜい20ページくらいと短くなっている。 今回、実際に読み直したのは、『マンハッタン・オプⅠ』所収の初めから6編。 各編のタイトルにはそれぞれジャズのスタンダードが借用されている。例えば「LOVE LETTERS」「I CAN'T GET STARTED」「MISTY」等々。カヴァーとイラストは、かの谷口ジロー。 ちなみにご承知だとは思うが、念のため、「マンハッタン・オプ」の「オプ」について。 ダシール・ハメットの「コンチネンタル・オプ」でも使われている「op」は「oprerative」の省略形で、要は「探偵」の意味。探偵と訳される単語は他に「(private) detective」「private eye」等もあるようだが、ここでなぜ「op」を採用したのかははっきりしないが、たぶんハメットを意識したのだろう。 ちなみに矢作は、たしか雑誌にのインタビューで、チャンドラーは評価するが、「ハードボイルド」などという下品なものは嫌いだ(ないし「書いたことがない」)というようなことを語っていたのを覚えている。いかにも言いそうなことだ。 矢作俊彦は、ともかくは、文体の作家である。 たとえば最初に置かれた「LOVE LETTERS」の冒頭を引いてみる。少々長くなるがご了承を。「ずいぶんお安いのね」パーク・アヴェニューから来た女は、すみれ色の目の端でこっそり笑った。「一日、二百ドル?それで全部?」もちろん、ベベ・クロコのハンドバッグから出された小切手帳に、二百ドルが高いわけはない。彼女は、それを、つまらない講義のノートをとる女学生みたいに開き、私の事務机に乗せ、銀色のボールペンの尻で折り目をしごいた。「他に必要経費」と、私はつとめて平静に言った。「アルコールとバァテンダーへのチップが、それに含まれることもある」「それだけ?」「拳銃のいらない仕事ならね」彼女の眸(ひとみ)が、やっと真直ぐ私をとらえた。「要る仕事なら五十ドルほど割増しをもらいます」「判らないわ。でも、今夜一晩、三百ドルで話を決めていただけそうね」彼女はペンを持ち直し、小切手帳にかがみこんだ。うなじと後れ毛が見えた。ジョイが匂った。私は立ち上がり、窓へ歩いた。その日、ニューヨークはすばらしい天気だった。恋を知ったばかりの少年のように、どこもかしこもぴかぴかに煌(ひか)っていた。空は青く、風はやさしかった。気持ちだけは、まったくの四月だった。ユニオン・スクウェアでは、早合点した小鳥たちが春を歌っていたが、誰一人それをとやかく言う者はなかった。三月はまだ少し残っている。しかし、冬はもう戻って来ない。今日、この町を往く者は誰も――人間も犬も、リスもドブネズミも、ジャンキーも切り裂き魔も、ニューヨークの冬をまた一つ、生きたまま乗り越えた自分にすっかり感動しているのだ。そこへぶ厚い小切手帳、夏服を着たプラチナ・ブロンド、誰が小鳥を嘲(わら)えるだろう。しかし、だからと言って、どんな仕事でも好きになれるというほどの陽気ではない。 引用はここまで。*小説内の時代設定がはっきりしないが、出版された昭和60年=1985年、あるいはFM東京で放送された80年から83年の、ドル/円のレートは、1ドル=200円から250円。だとすると、300ドルは6万円から7万5千円。と考えると、この「料金」はそんなものかもしれないと思う。 擬人法や比喩で彩られた文体は、こういう短編というか掌編で、よりその効果を発揮する。これを「過剰」だとか「嫌味」だと考えるかどうかは読者次第だろう。 各編が短い分、ストーリーは省略も少なくないし、細やかとはいえないが、それは放送音源の台本が元になっているという物語の出自を考慮すれば、せんないことだ。会話が多く、ストーリーよりシーンで読ませる趣は、チャンドラーがそうであったように映画の脚本みたいなところがある。 でも考えてみれば、この作家の場合、長編でも、これほどではないにしろ同じようなことが言える。ただ文体は(初期は概ね同じようだった記憶があるが)、作品によって自ずと変わる。日本が戦後2分割されるという『あ・じゃ・ぱん!』や、堀口大學のメキシコでの青春期を追った『悲劇週間』、あのTVドラマの最後から30余年後を描いた『傷だらけの天使』ではまったく異なる文体だった(はず)。 この作家は雑誌で連載を始めても未完成で終わったり、本にならないことも少なくないらしい。Wikiを見るとそんな作品が7作ある。実際はもっとありそうな気がする。 そういえば、かつて光文社文庫オリジナルで『コルテスの収穫』という小説が上、中、下巻で出る予定のところ、なぜか下巻が出なかったということもあった。 真相は、2002年の「作家に聞こう」と題されたインタビューで語られていて、何というか好き放題喋っているみたいなので本当かどうかはわからないが、おもしろいと言えばおもしろい。https://web.archive.org/.../book.../authors/index.php... たしか大学時代に友人の故・中井くんに教えてもらった作家で、読み始めて以降、一応の「ファン」だと思っていたのだが、司城志朗との共作を含め、未読にものも増えてきた。 せめて二村永爾ものは読もうと思って上で触れた『フィルム・ノワール/黒色影片』が文庫化されるのを待っているのだが、未だ果たされない。 たぶん読者をいくらか選ぶ作家なんだろうが、その魅力に一旦気づけばなかなか離れがたい作家でもある。では、次回、DEGUTIさん、お願いします。もし体調がすぐれない場合は、ご遠慮無くそうおっしゃってください。T・KOBAYASI・2021・08・14追記2024・04・20 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)
2022.06.02
コメント(0)
-

週刊 読書案内 馳星周「神の涙」(実業之日本社文庫)
100days100bookcovers no71 71日目 馳星周「神の涙」(実業之日本社文庫) 前回の70日目から20日が過ぎました。遅くなってすみません。 「外出が続きます」と投稿が遅れることを告知していましたが、わけがわかりませんよね。1週間、沖縄に行っていました。勝手に「フィールドワーク」と命名している「沖縄を知る」旅です。2月にフライトチケットを格安で取り(往復6,340円!)、全国・沖縄のコロナ感染状況や社会情勢を気にかけ、キャンセルも視野に入れていました。最終的にひとり旅で北部や中部を中心に計画し直し、決行しました。出発前にbookcoversの投稿が間に合わなかったのが残念でした。 「読売文学賞」をバトンに、degutiさんの庄野潤三『夕べの雲』からsimakumaさんの色川武大「狂人日記」へ。色川武大は私の知らない作家でしたが、直木賞作家、阿佐田 哲也・井上 志摩夫・雀風子とペンネームを複数持つこと、雀士でアウトロー生活、などから私が次に選んだのは、馳星周。 2020年の第163回直木賞を『少年と犬』で受賞。坂東レーニン・佐山アキラ・古神陸というペンネーム、『不夜城』などの暗黒小説、麻雀ではなくけれどゲームに詳しいなどなど…。実は他にも新宿ゴールデン街という共通点も! 馳星周は色川武大と同様、私は全くご縁がなかったのだけれど、『少年と犬』が気になっていた上に、この「100days100bookcovers」のどこかにsimakumaさんかkobayasi君のコメントがあったと記憶しています。映画監督・俳優の周星馳の名前を逆にしたものというペンネームの話題だったかな?そんなきっかけで図書館で何冊か借りて読むようになりました。『ゴールデン街コーリング』『雨降る森の犬』『ラフ・アンド・タフ』『少年と犬』…。 『少年と犬』は、いつ予約したのか忘れたころにやっと順番が回ってきました。仙台から熊本まで、さまざまな弱者に寄り添う野犬タモンを通して、東日本大震災の地震や津波、原発の事故に対する国や人々の姿勢を問い続けています。特にこの度のオリンピックの復興五輪という当初の意義は今やほとんどの人の意識にないのでは!?と思っている私は、小説そのものや犬への畏敬だけでなく、馳星周の社会的な姿勢にも大いに共感したのです。 では次に、どの作品にしようかと図書館で迷った結果、『神(カムイ)の涙』にしました。アウトローものではないけれど、北の大地を舞台にしたアイヌ民族に関する話でしたので…。20数年前に北海道の静内に青春切符で鉄道旅をしたことがあります。(また鉄道話ですみません。)加古川に舞台公演に来てくれた静内のウタリ協会のみなさんと沖縄のエイサーのみなさん(アイヌと沖縄を学ぶ人権企画は、すばらしかったなぁ!)との懇親会の中で、「また静内に来てくださいよ」という社交辞令を真に受けてひとりで行ってきたのです。私のいつものフィールドワークのスタートではないかな。大学、行政、地域の方にアポを取ってお話を聞きに行きました。当時朝日新聞に連載していた『静かな大地』(池澤夏樹)で静内の歴史や淡路島との関係も知り、また加古川でアイヌの文化と歴史を学ぶ会に参加し、『旧土人保護法』など同化政策を学び、ネイティブアメリカンなど先住民の教えなども友人から聞いていたこともアイヌ民族に魅かれた理由です。 『神の涙』のあらすじは、だいたい以下のとおり。 アイヌの木彫り作家の平野敬蔵は、両親を交通事故で亡くした孫の悠と二人暮らし。敬蔵に弟子入りを願って東京からやって来た尾崎雅比古が関わることによって、アイヌであることを否定し、高校から敬藏の家を出ることを決意していた悠の心が少しずつ開かれていく。同時に雅比古のルーツと、彼がなぜ敬蔵を訪ねて来たのかが明らかになっていく。福島原発事故の責任に向き合わない国や東電に対する憤りに対して友人と無謀に行動し、結果として警察に追われることになる雅比古のストーリーとカムイモシリ(神々の住まう地)である北海道の壮大で優美な自然を舞台にした敬蔵と悠、雅比古が本物の家族になっていくストーリーが絡まり合って織りなされる、タペストリーのような小説でした。 まず表紙の「摩周湖の滝霧」―「雲海」という名称ではなく、「滝霧」と言われるのは、周囲の断崖から滝のように“白い塊”が流れ込むからだとか。実は今回、沖縄でやんばるをひとりでドライブし、国立公園「大石林山」に行ったのですが、ちょうどその時上から霧が下りてくる一瞬を見たので、ちょっと背筋がゾクッとしました。休園中だったので、入り口でスタッフの方に説明してもらっていた時です。晴れている時より雨の後や雨が降っている時の方が荘厳さがあって僕は好きなんですと言っておられましたが、ここでも神々の住まう地を感じました。 「この辺りの山は昔はみんなアイヌのものだったんだ。」と敬蔵が言う山の神様が住まうところ。摩周湖の滝霧は、山の神様が摩周湖の水を飲みに行く印だという。オホーツク海、知床、藻琴山を訪れ、悠も雅比古も自然の神々しさに圧倒されていく。悠は自分が嫌悪していた故郷やアイヌであるという事実をだんだん肯定するようになるのです。 そんな山に住む、羆(ひぐま)やシマフクロウやエゾシカの生態は自然を破壊する人間への批判になっています。木彫りに最適な木を探し得られるのも、動物たちに向き合えるのも、カムイを信仰するアイヌしかいない。精魂込めて動物を彫り上げていく敬蔵は、木彫りに命を吹き込む時にユーカラを唱える。雅比古は母が口にしていた「銀の滴降る降るまわりに、金の滴降る降るまわりに…」が『アイヌ神謡集』の中の梟の神の自ら歌った謡だと知っていきます。 敬蔵はいつも「はんかくさい」(「ばかもの」「恥知らず」という意味の北海道や東北の方言)と口にします。本当に今の日本の人間どもは「はんかくさい」し、どうにも未来が望めないくらいなのだけれど、この本の中には「赦し」が書かれています。最後はちょっとヒヤヒヤする暗黒の山での騒動があるのですが、バッドエンドにならないのも救われました。エゾシカの肉で作ったカレーや豆を挽いて淹れるコーヒーなどが美味しそうで、嗅覚や味覚まで刺激された作品でした。 馳星周の他の作品の中では、『不夜城』を外せないと手元に置いています。加古川のレトロな図書館は休館となりましたので、限度いっぱい借りてきました。いつも上手くリレーできたかどうか心許ないのですが、sodeokaさんに繋ぎます。どうぞよろしくお願いします。2021・06・27追記2024・05・11 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目) (81日目~90日目) という形でまとめています。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)
2022.05.27
コメント(0)
-
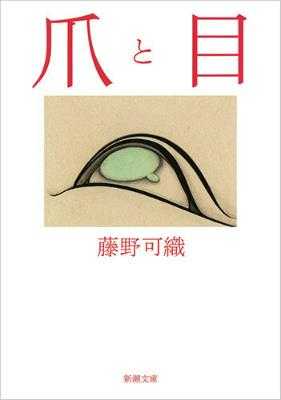
週刊 読書案内 藤野可織「爪と目」(新潮文庫)
藤野可織「爪と目」(新潮文庫) 小説という表現形式は、たぶん、どこまで行っても「誰か」の眼で見た「世界」が、「誰か」によって書かれるほかには書きようがないと思います。その「誰か」が「私」であれば、自分の内面だらか見えちゃう心の奥底を告白したり、なんでも見えてしまう「神様」だったら、あの人のことも、この人のことも全部説明出来ちゃったり、たとえば漱石は「ネコ」の眼で「人間」を見させることで「人間」の生活を描いて、まあ、笑わせたわけで、読むときも、なんとなくそのルールを信頼して読んだりするわけです。 この作品は、その「誰か」の設定が工夫されているところがミソなのですが、驚いたことに、その「誰か」は作品中に実在する幼い少女であるにもかかわらず、彼女には見えるはずのない他者の経験まで「書き」つけることが出来てしまうという、ぼくのような老人から見れば、ただのルール破りの存在なのですが、なぜか「芥川賞」だったりするわけです。 老人にはルール破りとしか思えない方法によって生まれるのが、好意的にお読みになっている方がおっしゃっている「ホラー」な感じであり、「不気味さ」なわけですが、老人にはマニュキアの爪の皮でコンタクトレンズを穿るという結末に対する作家の思いこみこそがホラーで、この作品を評価した選考委員の評価基準が不気味でした(笑)。 いやはや、何をしてもムードが描ければいい時代がやってきているようですが、そこのところが実に不気味ですね(笑)。
2022.05.22
コメント(0)
-
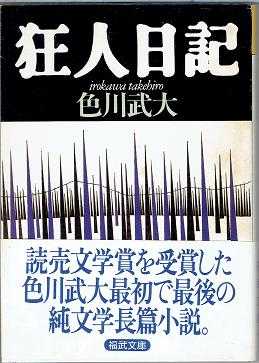
週刊 読書案内 色川武大「狂人日記」(福武文庫・講談社文芸文庫)
100days100bookcovers no70色川武大「狂人日記」(福武文庫・講談社文芸文庫) KOBAYASI君の星野博美『のりたまと煙突』から、「内省」をバトンにして、DEGUTIさんが差し出してくれたのは庄野潤三の『夕べの雲』でした。 作品名を見ながら、ふと、浮かんできたのは「ああ、いよいよ、出発点かあ・・・」 という感慨でした。 ぼくがこの作家の名前に出会ったのは高3の時でした。私淑していた世界史の先生の下宿の棚から借り出した江藤淳の「成熟と喪失」(今では講談社文芸文庫、当時は、たぶん、河出書房の単行本)という「第三の新人」を論じた評論の中でのことです。変なことを詳しく覚えているようですが、今思えばそれがぼくの「文学オタク」の始まりだったからなのかもしれませんね。 「オタク少年」は、翌年の一年間、午前中しか学校がない浪人生活をいいことに、「成熟と喪失」で論じられた作家たちを読みふけったわけですが、その中で、その後も読み続けたのが、遠藤周作や吉行淳之介ではなくて、庄野潤三と安岡章太郎、そして小島信夫だったというところに、まあ、「性根」の好みがあらわれているようでおもしろいですね。 庄野潤三が『プールサイド小景』で芥川賞を取ったのが1955年で、ぼくが生まれた翌年です。昭和30年。以後、一年間だったかのアメリカ留学の生活をつづった『ガンビア滞在記』、初期の代表作とも言うべき、釣りをする父と息子の話を書いた『静物』、で、『夕べの雲』が1965年です。 作風は、DEGUTIさんのおっしゃるように「平和な家庭の風景」の「おだやか」で「ユーモラス」な描写ということなのですが、うまく言えませんが、どこかに「喪われたもの」と「壊れそうなもの」の「不安定」を感じさせるところのある「おだやかさ」に惹かれたのでしょうね。たとえば、DEGUTIさんが引いていらっしゃる、こんな描写がぼくは好きです。 家ごと空に舞い上がって、その中には寝間着をきた彼と細君と子供がいて、「やられた!」と叫んでいる。 そういう場面を空想するのなら大風の方がよく似合う。台風では、そうはゆかない。 長々と思い出話をしてきましたが、バトンは「読売文学賞」 です(笑)。 なんだ、それなら、さっさとそっちに行けばいいじゃないかと言われそうですが、庄野潤三は読み直したい人でもあって、語りたかったのでしょうね。 『夕べの雲』が読売文学賞を取ったのは1966年ですが、23年後、1989年の受賞作が色川武大「狂人日記」(福武文庫、今は講談社文芸文庫)でした。 「麻雀放浪記」の直木賞作家、阿佐田哲也という方が通りがいいのかもしれませんが、ぼくにとっては「百」、「狂人日記」の色川武大です。彼はこの作品で読売文学賞を受賞しますが、受賞を知らないまま心臓破裂で世を去ったそうです。60歳の生涯だったそうです。 作品は「自分」と自称する「元飾り職人」の「狂気」と「正気」の間を行き来する日々の暮らし、「目」に見える外側の世界と内側の世界を描いた一人称の小説です。 主人公は病院で暮らしているのですが、彼が生きているのは、まあ、こんな世界です。「一番怖いものは、何ですか」と医者が上機嫌でいう。自分が黙っているので、さらにうちとけた調子で、「誰にもあるでしょう、怖いものが。蛇とか、蛙とか、虫とか」「そういうことなら、べつにないようですねえ―」自分はにべもなくいった。「ただ、怖くなりだすと、なんでも怖いです。」如何に生くべきか。そいうことを考える年齢では早くもなくなった。もう五十を越した、一生は短きもの也。このまま転げるように生き終えてしまいたいものだ。一人では、やっぱり生きていかれない。他者が居ない分だけ、幻像が繁殖してくる。自分の病気はここから発していると思う。他者に心を開け。簡単に思う人も居るだろうが、自分がやろうとすると、卑屈になったり、圧迫してしまったりしてしまう。そればかりでなく、どの場合も不通の個所がこつんと残る。死んでやろうと思う。ずいぶんよそよそしい言葉で、人に告げても信じるまい。自分にも、まだ嘘くさくきこえる。死んでやろうじゃない。死ぬよりほかに道はなしということだ。それで、自然史がよろしい。今日から、喰わぬ。 引用していて、ちょっとヤバい気分になりますが、こういうのをひと様に紹介していいのかどうか、不安になりますね。 とはいえ、この作品が1988年に上辞されたことに絡めていえば、戦後社会という経済成長はあれども、確たる支柱の「喪失」の中で生きることを余儀なくされた「個人」を描いて、「自我」を描き続けてきたといわれる「近代文学」と、「社会的人間」を描こうとした「戦後文学」の終焉を鮮やかに描き切った傑作だというのが、ぼくの思い込みです。 「平成」や「令和」の文学が、色川武大の荒涼とした「崩壊」の世界 を、どう受け止めているのか、興味深いのですが、どうも、だれも論じないまま忘れられて行く雰囲気ですね。 なんだか、老人の繰り言になりましたが、YAMAMOTOさん、お次をよろしくお願いします。T・SIMAKUA・2021・06・07追記2024・05・11 投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目)(51日目~60日目)(61日目~70日目)(71日目~80日目)(81日目~90日目)というかたちまとめています。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)
2022.04.07
コメント(0)
-

週刊 読書案内 須賀敦子「遠い朝の本たち」(ちくま文庫)その2
須賀敦子「遠い朝の本たち」(ちくま文庫)その2 須賀敦子の「遠い朝の本たち」(筑摩書房)の「案内」を始めて、彼女の早すぎる死と、短すぎる執筆期間に気を取られて、あれこれ書いているうちに長くなってしまったので、「その2」に譲ることにして、投稿の記事を終えました。 というわけで、今日は「その2」です。 このエッセイ集の最後の文章は「ダフォディルがきんいろにはためいて・・・」という、若き日の彼女の詩との出会いを綴った美しい文章ですが、そこで、彼女はワーズ・ワースという、19世紀初頭のイギリスのロマン派詩人の「The Daffodils」という、かなり有名な詩を話題にして学生時代の思い出を語っています。 ぼくはロマン派に限らず英国の詩人なんて全く知りませんが、彼女の文章を読んでいたちょうどその日に団地の庭に咲いている水仙の花を写真に撮ってきたところで、ちょっと嬉しかったということにすぎません。 それが上の写真ですが、彼女の文章はこんな感じです。谷や丘のずっとうえに浮かんでいる雲みたいに、ひとりさまよっていたとき、いきなり見えた群れさわぐもの。幾千の軍勢、金いろのダフォディル。みずうみのすぐそばに、樹々の陰に、そよ風にひらひらして、踊っていて。 この詩を、私たちは英語で暗唱させられていた。暗記というのは正確でない。暗唱させられるのだった。大きな声で、ひとりひとり直立して、暗記した詩をみなのまえで朗誦するだから。典型的な強弱四歩格の単純な詩行で、内容もいま読むとむしろほとんど幼いほどの自然描写なのだけれど、目をつぶると、丘の斜面に群れ咲くダフォディルが風に揺れた。 ページの上に貼っている写真は、彼女が訳しているダフォディル、花全体が黄色いラッパ水仙ではなくて、いわゆる日本水仙と呼ばれる花で、そこがなんとも残念だったのですが、それでも、まあ、なんとなくな偶然がうれしくてこうして案内しているわけです。 彼女がここで思い出しているワーズ・ワースの「ダフォディル」という詩の原文はこれです。英詩のお好きな方には常識なのでしょうが、ぼくなどには難しすぎるので、岩波文庫版の訳もつけておきます。彼女の訳は、この詩の冒頭部分ですが、1950年ころの岩波文庫の田部重治(たなべしげはる)という方の訳と少し違います。何となく、彼女の性分が出ているようで面白いですね。 The Daffodils William WordsworthI wander'd lonely as a cloudThat floats on high o'er vales and hills,When all at once I saw a crowd,A host of golden daffodils,Beside the lake, beneath the treesFluttering and dancing in the breeze.Continuous as the stars that shineAnd twinkle on the milky way,They stretched in never-ending lineAlong the margin of a bay:Ten thousand saw I at a glanceTossing their heads in sprightly dance.The waves beside them danced, but theyOut-did the sparkling waves in glee:A poet could not be but gay In such a jocund company!I gazed - and gazed - but little thoughtWhat wealth the show to me had brought.For oft, when on my couch I lieIn vacant or in pensive mood,They flash upon that inward eyeWhich is the bliss of solitude;And then my heart with pleasure fillsAnd dances with the daffodils. 水 仙 ウィリアム・ワーズワース(田部重治訳)谷また丘のうえ高く漂う雲のごと、われひとりさ迷い行けば、折りしも見出でたる一群の黄金(こがね)色に輝く水仙の花、湖のほとり、木立の下に、微風に翻りつつ、はた、踊りつつ。天の河(あまのがわ)に輝やきまたたく星のごとくに打ちつづき、彼らは入江の岸に沿うて、はてしなき一列となりてのびぬ。一目にはいる百千(ももち)の花は、たのしげなる踊りに頭をふる。ほとりなる波は踊れど、嬉しさは花こそまされ。かくも快よき仲間の間には、詩人(うたびと)の心も自ら浮き立つ。われ飽かず見入りぬ──されど、そはわれに富をもたらせしことには気付かざりし。心うつろに、或いは物思いに沈みて、われ長椅子に横たわるとき、独り居(ひとりい)の喜びなる胸の内に、水仙の花、しばしば、ひらめく。わが心は喜びに満ちあふれ、水仙とともに踊る。 ここまでお読みいただいて、どうも、ごくろうさまでした。こういう詩に心がときめくという年ごろが、まあ自分にもあったことや、大学や高校の教員が学生に読ませたがる時代があったりしたことが、ぼくには懐かしいのですが、ウイリアム・ブレイクとかウイリアム・ワーズワースとか、この年になって翻訳で読み直したりしている、だって、翻訳でないと歯が立たないのですから、自分の教養のなさもまた、つくづくと感じるのでした。
2022.02.07
コメント(0)
-
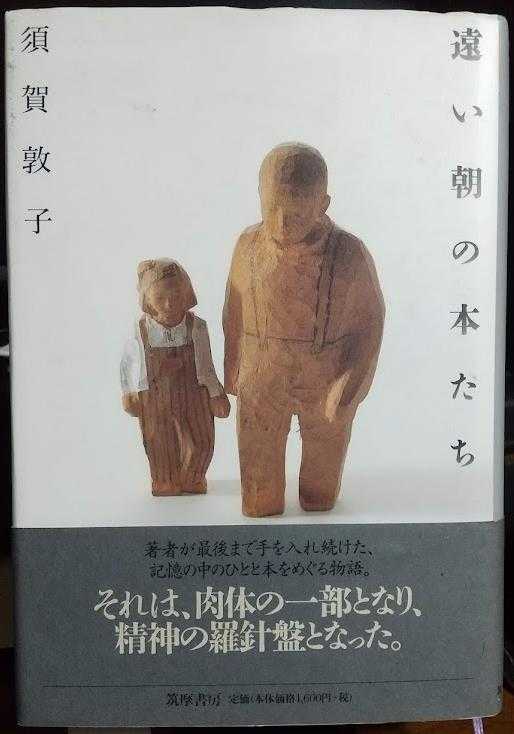
週刊 読書案内 須賀敦子「遠い朝の本たち」(筑摩書房)
須賀敦子「遠い朝の本たち」(筑摩書房) 今回案内するのは須賀敦子の「遠い朝の本たち」(筑摩書房・ちくま文庫)です。今更案内するもなにも、名著中の名著というべきエッセイ集です。幸田文の「父 こんなこと」や「みそっかす」を読み直していて、なんとなく気にかかったのがこの人のエッセイでした。 新年になって何気なく手にとって、巻頭に収められた「しげちゃんの昇天」を読み始めて止まらなくなりました。 夫が死んだとき、北海道の修道院にいたしげちゃんから、誰からももらったことのないほど長い手紙がイタリアにいた私のところにとどいた。卒業以来、彼女からもらった、はじめて手紙だった。学校も病院も経営していない、ひたすら祈りだけに明け暮れる彼女の修道院がひどい貧乏で、シスターたちが食べるものまで倹約しているという話も、人づてに聞いていたが、しげちゃんの手紙にはそんなことは一言もふれていなくて、むかしのままのまるっこい書体で、私の試練を気づかうことばが綿々とつづられていた。こころのこもったそのことばよりも、なによりも、私は彼女の書体がなつかしかった。修道女になっても、まだおんなじ字を書いている、と私は思った。もう変体仮名はまじっていなかったけれど、教室でとなりにすわったとき、私のノートのはしに、思い出したことなどをちょちょっと書きつける、あのおなじ文字だったし、なによりも、むかし、あなただけよと言って読ませてくれた、うすい鉛筆で書いた堀辰雄ふうの小説の、あの字だったのがなつかしかった。手紙の終わりのほうに、修道院では人手がたりなくて、冬のあいだの屋根の雪おろしがたいへんだとだけ書いてあった。じげちゃんの、ぷくぷくした色白の手が、しもやけになっていないかと私は思った。赤くはれた手で、ペンを持つしげちゃんを、私は想像した。(P91~92) 須賀敦子が、昭和の10年代でしょうか、その頃、阪急があったどうかはわかりませんが、今の阪急今津線の沿線にある小林(おばやし)駅の聖心女学院に通っていたころから東京の聖心女子大学まで、ずっと同級生で、大学を出て修道女になった「しげちゃん」という旧友の死に際して、思い出を語った文章の一節です。 調布で会ったとき、大学のころの話をして、ほんとうにあのころはなにひとつわかっていなかった、と私があきれると、しげちゃんはふっと涙ぐんで、言った。ほんとうよねえ、人生って、ただごとじゃなにのよねえ、それなのに、私たちはあんなに大いばり、生きてた。 しげちゃんが、ただごとでない人生を終えて昇天したのは、それからひと月もしないうちだった。(P93) こんなふうにこのエッセイは終えられるのですが、そこまで読み終えて、読んでいた本の奥付を見て愕然としました。須賀敦子(すがあつこ)1929年生まれ1998年3月20日、没。「遠い朝の本たち」1998年4月25日第1刷発行 1998年9月25日第8刷発行 彼女が読者に向けて書いていた期間は10年に満たなかったのです。ぼく自身が彼女の作品を読み始めて30年の年月が経つわけですが、うかつにも、ただの一度も、そのことに気づかなかったのです。たった8年間のあいだに全集8巻分もの作品が書き残されたわけですが、そこにある彼女の仕事は、あたかも、限りある人生の短い有余を知るかのような緩みのない美しい文章で、ぼくの中では、今でも色あせることはありませんが、それにしてもたった8年間だったのです。 須賀敦子が「ミラノ霧の風景」(白水社)でエッセイストして、初めて脚光を浴びたのは1990年のことでした。そのとき彼女は61歳です。で、今回の「遠い朝の本たち」(筑摩書房)が出版されたのが1998年4月25日です。 彼女が69歳で亡くなった翌月に出された本ですから、遺作ということになるかもしれません。しかし、この本に所収されているエッセイは1991年ごろから、筑摩書房の「国語通信」、高校の国語の教員とかにサービスで配布されたPR誌のようなものですが、その雑誌に書き継がれた作品で、今思えば、むしろ初期の作品ということになるのかもしれません。とはいうものの、この本に収められたエッセイに初期を感じさせる文章はどこにもありません。そのうえ、その当時亡くなった友人の死についての思い出が、まあ、本を作った編集者の意図もあるのかもしれませんが、巻頭を飾っています。そのあたりにも、限られた有余に対する、覚悟のようなものを、今となっては感じてしまうのです。 本書では、ここから「ただ事ではなかった」人生の始まり、子供時代の彼女の本との出会いが、思い出を楽しみながらかみしめる風情で記されています。 最近よく思うことですが、以前、一度ならず読んだことのある作品や文章が、記憶とは違った印象で、妙に胸を打つのです。その感覚は須賀敦子も、これらのエッセイを書くにあたって、ひょっとすると感じたことではないでしょうか。彼女が亡くなった年齢を目前にした老人が、新しい年の始めに、ゆっくり読みすすめるに恰好の文章でした。 話が須賀敦子の生没年の方向にそれてしまいましたが、読んでいて案内したいと思ったのは別のことでした。というわけで「案内」はその2に続きます。そちらも覗いていただければと思います(笑)。
2022.02.01
コメント(0)
-
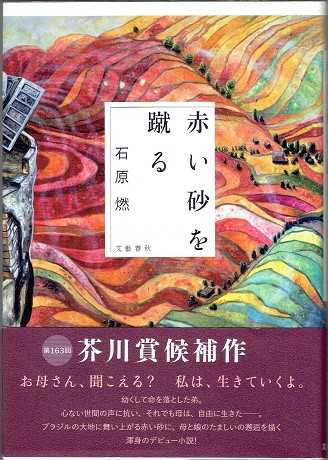
週刊 読書案内 石原燃「赤い砂を蹴る」(文芸春秋)
週刊 読書案内 石原燃「赤い砂を蹴る」(文芸春秋) 本読みのお友達にすすめられて石原燃という人の「赤い砂を蹴る」(文藝春秋社)という小説を読みました。2020年の芥川賞の候補になった作品だそうです。 読みすすめながら、久しぶりに「寵児」(講談社文芸文庫)、「光の領分」(講談社文芸文庫)、そして「火の山 山猿記(上・下)」(講談社文庫)の作家で、2016年、68歳の若さで逝った津島祐子を思い出しました。 読みながら「はてな?」と気になって調べたのですが、石原燃という方は女性で、津島佑子のお嬢さん、だから、太宰治のお孫さんに当たる方だそうで、お名前は「いしはらねん」とお読みするようです。「なるほど、そうか。」と納得しました。「赤い砂を蹴る」と題されたこの作品は南千夏というフリーのライターである女性が、画家である母恭子の友人で、日系ブラジル人芽衣子とともに、芽衣子の故郷であるブラジルの日系移民の経営する農場を訪れる、いわばロード・ムービー風の旅の物語でした。 その部屋には母と、父親のちがう弟の大輝と、三人で暮らしていた。 引っ越してきたのは、大輝が小学校に上がる年だっただろうか、私は四つ年上だったから、小学校四年生だったことになる。それから、中学を卒業するまぎわまでここに住んでいたのだが、そのとき大輝はもういなかった。 私が小学校を卒業する二日前の夜、大輝はひとりでお風呂に入り、心臓発作を起こして息を引き取った。(P20) 大輝を失ってからしばらく、母は大輝の姿だけを描くようになった。それが何枚も積み重なるうちに、大輝の姿は歴史の中で命を落とした子供たちの姿と重なり、一つの壮大な連作として、母の中期の代表作となった。 あの頃の母もこんなふう気持ちで大輝を描き続けたのかもしれないと思う。いや、どうなんだろう。よくわからない。 母の絵から自分の姿が消えてしまったことに傷ついたこともあった、でも、今はそんな単純なことでもないと思う。だって私は生きているのだから。生きている人間を一方的に絵に閉じ込めることはできないのだから。(P22) 作品が始まって、主人公がこんなふうに語り始めるのを読みながら、石原燃という作家が小説家津島祐子の長女であるということが、否応なく浮かんできました。津島佑子の作家としての登場に出会ったのは、40年以上も昔、学生時代でしたが、その頃の彼女の「光の領分」という作品には、中学生の少女が登場したと思いますが、作家であった母、津島佑子によって、その作品中に召喚された少女が、今、自分の言葉で語り始めているという印象です。 「赤い砂を蹴る」という、この作品中の母恭子のモデルが、石原然という作家の母であろうがなかろうが、作品の小説としての価値という観点に立てばどうでもいいことです。 実際、この作品には日系ブラジル移民の私生児で、日本人の男性と結婚し、来日して数十年、この国で暮らしながら、国籍を取得できないまま、アルコール依存症の夫を見取り、今、「日本国籍」取得のために、故郷ブラジルを訪れる旅をしている芽衣子という、実に魅力的な女性が登場します。 作家は芽衣子の生い立ち、日本での生活の様子を描きながら、ブラジル移民の戦後史、国籍や、近代の家族制度といった、今時珍しい大きな構図の作品に挑んでいる様子で、実にすがすがしい印象を持ちました。 しかし、主人公千夏が語る物語は、否応なく作家石原然の母津島佑子と、その作品を彷彿とさせてしまいます。理由は、読者であるぼく自身の思い込みによるところが大きいのでしょうが、たとえば、引用のなかの「あの頃の母もこんなふう気持ちで大輝を描き続けたのかもしれないと思う。」という記述などには、主人公千夏の、という以前に、今、小説を書いている石原然自身の述懐としか思えない唐突さ、あるいは、不思議な二重底を感じさせて、実に興味深く読みました。 どれくらい時間が経ったのだろう。ぼんやりと立ち尽くして、風呂上がりの子供のように拭かれるままになっていた。小さいころ、こんなふうに身体を拭かれたことがあった。やわらかいタオルの感触が懐かしい。 「びっくりしたよ、雨の中走りまわっているんだもん。」 聞き覚えのある声が、耳元で聞こえる。 ぼんやりと、肌に当たる冷たさを思い出す。 震えが止まらない。そういえば服が濡れている。髪の毛から水がしたたる。 タオルを肩にかけたまま、めがねを外してTシャツで拭いた。濡れたTシャツではうまく拭けず、めがねをかけると、水滴のつぶが見えた。(P156~P157) 主人公千夏がブラジルのスコールにずぶぬれになったシーンです。彼女が耳にする声はその場にいる芽衣子の声であり、思い出の中の母恭子の声でもあるというダブル・ミーニングに加えて、作家にとっての母、津島佑子の声が優しく聞こえてくると感じさせる哀切なラストです。 母の小説の登場人物であった少女が、小説家石原然として産声を上げたという印象を持ちました。 「めがねをかけると、水滴のつぶが見えた。」という、この作品の最後の一文を読みながら太宰治の娘であった津島佑子が、自らのルーツをさぐる「火の国 山猿記」で、父の姿を書いていたことを思い出したのでした。 皆さん、あの太宰のお孫さんが小説を書き始めましたよ(笑)。
2021.12.11
コメント(2)
-

週刊読書案内 金子薫「道化むさぼる揚羽の夢の」(新潮社)
週刊読書案内 金子薫「道化むさぼる揚羽の夢の」(新潮社) 蛹の形をしたの拘束具に首から上だけ出した形で閉じ込められ、糞尿まみれのまま吊るされている「機械工」、天野さんが、自らが蛹であることを信じ、やがて、蝶になって羽搏くことを夢想するお話を読みました。 金子薫という1990年生まれらしい、若い作家の「道化むさぼる揚羽の夢の」(新潮社)という作品です。 微睡の中で天野はしばしば蝶になっていた。夢の中で色取り取りの翅をはためかせ、晴天の下、花畑に舞っていることが多かった。ー中略ー ああ、早く蝶になりたいものだ、それだけを願い、固く眼を瞑った。すると直後、スプリンクラーが散水を開始した。ー中略ー 瞼を閉じたまま、水滴を味わい、天野は考える。この雨は羽化の予兆であるに違いない。自分たちは越冬蛹で、降り注ぐ生温かい水は春雨なのだ。冬が過ぎ去り春が来た。無数の蛹が破れ、蝶が一斉に飛び立つ日は近い。(P6~P7) 天野は眼を瞑って歓びを嚙み締め、内なる熱に身悶えしながら、変わっていく自らの躰と、迫りつつある昇天について思いを巡らせた。織物または硝子細工の如く美しい、二枚の翅を羽搏かせ、私はどこまで飛んでいけるだろうか。一頭の揚羽蝶はどれほど天に近づけるのだろうか。(P198) いきなりネタバレのようですが、本書の始まりと終わりの一節です。主人公「天野」君が「蝶」を夢想するに至るきっかけは、上に書きましたが「蛹型」の拘束具に閉じ込められた結果、「蛹」であるという、まあ、いわば無理やりな自己確認にあるわけですが、拘束を解かれて工場で機械工として働く作業着が「蝶」柄であり、彼が作るのもまた金属製の蝶であるという反復によって、「蝶」が作品のテーマ(?)のように君臨してゆきます。 当然「蝶」とは何だろうという疑問がわくのですが、「蝶」は「蝶」であるにすぎません。比喩でも寓話でもない、ひらひら飛翔する昆虫であるただの蝶です。おそらくそこが、この作品の肝だと思いました。 2021年に発表されたということからでしょうか、コロナ禍の社会のありさまの寓話のように読まれている面があるようですが、おそらく何の関係もないと思います。 いってしまえば、ある種「美的な観念小説」を目指した作品だと思いまいました。硬直した権力社会にトリック・スターとして登場する「道化」とか、「道化の笑い」の昇華としての「蝶」の飛翔とか群舞とかいうアイデアは面白いですが、荘子を持ち出すまでもなく、ありがちでしたね。道化と蝶というセットでは、いかに自由に描こうともイメージがあらかじめくっついてしまうのです。 結果的に、細部の描写や言及に関して、よく勉強なさっているという感想を持ちますが、そういう言い草は、こういう小説だと誉め言葉にはならないでしょうね。 最後に、クライマックスとして描かれた子供たちの手から金属製の蝶が舞い上がっていくシーンがありました。作家が勝負に出ている感じでした。 小さな道化たち、秀人、明弘、奏太、司、真弓は、手当たり次第に落ちている蝶を拾い、両の手に包んでいる。何をするつもりなのかと眺めていると、黄色い蝶が一頭、秀人の合わせた手から抜け出し、舞い上がっていった。司の手からも、烏揚羽か黒揚羽、あるいは架空の黒い蝶が高く舞い上がっていく。其処彼処で、子供たちが捏ね廻した蝶が、どういう訳か本物になって自在に飛び始めていた。―中略― 太陽の光に照らされて、蝶たちが戯れあうように飛んでいる。偽の木が真の木に変化するのみならず、地面もゴムから土に変わり、花まで咲いている。(P197) 作家の描いてきた地下世界に初めて陽光が降り注ぐ、ここまでにはない「明るい」シーンですが、このシーンの後に、最初に引用した言葉「私はどこまで飛んでいけるだろうか。」というセリフがあって、その自問が印象に残りましたが、自問しているのが天野君なのか、作家自身なのか。最初から最後まで、作家的な自意識の過剰な作品だと思いました。 ただ、こういう自己言及的というか、堂々巡りというか、自らの観念を掘り続けるかに見える作品を20代くらいの読者はどう読むのか、ウザイになるのかリアルになるのか、ちょっと興味があります。 蛇足ですが、ヴィジュアル的なジメージとしては面白い作品、まあ、具体的な指摘はできませんが、最近のちょっとグロテスクな絵のマンガとか、ディストピア的イメージの映画とか、どこか共通している同時代的な感覚が漂っているような感じでした。 ついでに蛇足で、アゲハです。これは本物。
2021.11.22
コメント(0)
-
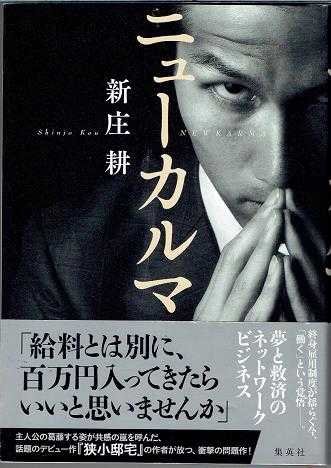
週刊 読書案内 新庄耕「ニューカルマ」(集英社)
週刊 読書案内 新庄耕「ニューカルマ」(集英社) 一緒に「面白そうな本を読む会(?)」で集まって本を読んでいる人に二十代のジャーナリストの卵というか、ひよこのような方がいらっしゃるのですが、彼が提案した本がこの本、新庄耕「ニューカルマ」(集英社)でした。 会の名前は、実はありませんが、長く続けていることもあって、会のメンバーの多くはぼくも含めて「時代」についていけていない傾向があるわけで、斬新な提案でした。 で、勇んで読みましたが、不満だらけでした。 震え続けている電話を操作し、耳に当てた。 「あっ、ユウちゃん、久しぶり、俺、シュン」 少年のそれを思わせる高い声が聞こえ、幼さの残る顔がうっすらと呼び起こされた。 「ああ・・・・、なんだ、シュンか」 平静を装って言ったつもりが、かえってわざとらしい口調になった。 大学時代の同級生だった。初年度の必修科目のクラスで話すようになったが、専門課程に分かれてからは接点もなくなり、たまにキャンパスで会えば挨拶する程度の仲だった。最後に話したのはいつだったか、卒業から今日までの五年間、何の交流もない。 「何度も電話しちゃってごめんね。いや、ユウちゃん、最近どうしてるかなって、ちょっと思って。」 遠慮がちな相手の声が、通りを往来する車の走行音と重なる。(P6) まあ、こういう電話がかかってきて「ユウちゃん」の「カルマ」が育ち始めるわけです。題名の「ニューカルマ」を見て、仏教用語だったような気がしましたが、読み終えて調べ直すと「業」ということらしいですね。 20代後半の独身サラリーマンが、ぼくはよく知りませんでしたが、いわゆる「ネットワーク・ビジネス」にはまっていく話で、はまっていく「ユウちゃん」の一人称語りの「物語」です。 だから、どうしても「内面」というか「意識」の世界を物語ることになるのです。 「みなさん、今はやりのネットワーク・ビジネスにはまっていく人間の内面って興味ありませんか?」 作家は、そんなふうな誘いを囁きながら、凡庸な「内面」の変化をサスペンス仕立てで描くのです。 そして、まあ、ネタバレのようですが、この作品はこんなふうに終わります。 先程まで明るい光に満ちていたはずの外は、夕暮れとは思えぬほど暗く沈んでいる。窓辺に椅子を近づけて空を見ると、煙のようにくすんだ雲が折り重なり、むかいに立ちならぶ雑居ビルの頭上を覆いつくしている。 しばらくの間、作業に戻ることも忘れ、重く垂れこめた黒い雲をながめた。 デスクの上の携帯電話を手にとり、窓の外に視線を戻して耳に当てる。 呼び出し音が鳴る。 四コール目で、耳になじんだ声が聞こえた。短い沈黙のあとで、僕は口を開いた。 「タケシ、話があるんだ」(P258~259) この小説はここで終わりますから、この電話で「ユウちゃん」が、親友(?)「タケシ」に何を語ろうとしているのかわかりません。おそらく作家は 「ここから先は、読者に想像していただきたい、想像の根拠になる、電話の主ユウちゃんの内面についてはすべて書き込みました」 とおっしゃりたいわけですが、果たして「書き込まれているのか」、「想像が可能なのか」と考えると少々心もとないですね。ただ、携帯電話で始まった人間関係の描写が、やはり電話で終えられるところが、いかにもこの作品の描いている関係性を象徴しているようで興味深いですね。 ついでに、付け加えると、この主人公のイメージが、この単行本のカバーの写真の男のような人物であるということが、作品が描く物語に「先行」なのか、「追加」なのか、ともかく情報として載せられている製本レイアウトなのですが、残念ながら、こんな男はこの作品のどこにもいなかったような印象しか持つ事はできませんでした。 で、もう一度、ただ、なのですが、ただ、凡庸で臆病で正直な青年が、知らず知らずのうちに、こんな顔を、その内面に持ち始めるということの暗示なのかもしれません。それはそれでリアルといえばリアルなのですが、少しやりすぎな感じもしました。 まあ、そんな、実もふたもない感想だったのですが、そんなことをノンビリしゃべりあっているときにしゃべってくれた、この本を紹介してくれた青年の感想は驚きでした。 かなり長い感想を聞かせてくれたのですが、勝手に要約するとこんな感じでした。 10年ほど前、不況のときに、小林多喜二の『蟹工船』が流行りました。『ニューカルマ』は、現代の蟹工船ではないか。ただ、冷戦が終わり、共産主義、社会主義への理想も語れない世代なので、労働者は団結するどころか、お互いを食い合うしかない。そういう、リアリティーを持った小説でした。 というわけで、ニューカルマは、僕にとってはめちゃくちゃリアリティーありました。知り合いにも、ネットワークビジネスをやってるような友人もいて。やたら金の羽振り良くて。怖くてどんな職業かは聞けません。 三宮とか、大阪のなんばとか、その辺の喫茶店、マクドナルドなどに長時間いれば、割と頻繁に、ネットワークビジネスの勧誘に遭遇します。日中、お昼すぎくらいですね。 青年のこの感想には、ぼくなどには、全く気付けない視点というか、現代社会に対する「生な実感」があって、その感覚からこの作品を読むと、かなりリアルな実況中継というか、ある種の情報小説として読めるということです。 気にかかったので、ゆかいな仲間のピーチ姫に聞いてみると、彼女も二十代の後半なのですが 「そうだよ。身近にあるよ。そういう話。」 と一言で片づけられて、あっけにとられる始末でした。 というわけで、新しい書き手の作品を読む心得云々以前に、なんとなく殺伐とした「現代社会の実相」の一面を教えられ、ちょっとオロオロしました。 今や、終末期資本主義とでもいうべき、とんでもない時代が始まっているのかもしれません。いやはや、何とも、どうなるのでしょうね。
2021.11.06
コメント(0)
-

週刊 読書案内 宇佐見りん「推し燃ゆ」(河出書房新社)
週刊 読書案内 宇佐見りん「推し燃ゆ」(河出書房新社) 話題沸騰の宇佐見りん「推し燃ゆ」(河出書房新社)です。書店ではピンク色のカヴァーで平積みされていましたが、カヴァーをとった姿はこんな感じです。 これが派手なカヴァーです。 2020年の下半期、冬の芥川賞です。書き手の宇佐美りんさんが21歳の大学生であるということで、かなり盛り上がりました。「かか」(河出書房新社)というデビュー作が前年、2019年の「文藝賞」(河出書房新社)、「三島賞」(新潮社)をとって、二作目の「推し燃ゆ」(河出書房新社)で「芥川賞」でした。 「かか」を読んで、「あれれれ!」という感想で、「それじゃあ「推し燃ゆ」も」というわけで、友達に借りて読みました。 図書館も順番待ちが半年先の雰囲気で、通販の古本も、値段が高止まりで、ああ、どうしようかと思っていると、まあ、本読みともだち(?)である友人が「面白いよ」といいながら貸してくれました。「『推し』ってなんのこと。ああ、それから『燃ゆ』も。」「読めばわかるよ。」 まあ、あっさりそういわれて読みましたが、貸していただいた本にカヴァーがなかったので、上の写真になりました。 読み始めると、とりあえず「推し」についてはこんな風に書かれていました。 「アイドルとのかかわり方は十人十色で、推しのすべての行動を信奉する人もいれば、よし悪しがわからないとファンと言えないと批評する人もいる。推しを恋愛的に好きで作品には興味がない人、そういった感情はないが推しにリプライを送るなど積極的に触れ合う人、逆に作品だけが好きでスキャンダルなどに一切興味を示さない人、お金を使うことに集中する人、団同士の交流の好きな人。 あたしのスタンスは作品も人も丸ごと解釈し続けることだった。推しの見る世界を見たかった。(P17~18) 推しを始めてから一年が経つ。それまでに推しが二十年かけて発した膨大な情報をこの短い期間にできる限り集めた結果、ファンミーティングの質問コーナーでの返答は大方予測がつくほどになった。裸眼だと顔がまるで見えない遠い舞台の上でも、登場時の空気感だけで推しだとわかる。(P32) 世間の動向に疎い60代後半の老人にも「推し」という言葉の意味が「名詞」としては動詞として使われている「推す」の対象を指し、知っている言い方で言えば「アイドル」を指すことは理解しました。で、「推す」ことに熱中することを「燃ゆ」という古典的言い回しで表現したのが本書の題になっているようです。 まあ、間違っているのかもしれませんが、まずは、第1関門クリアというところなのですが、こうやって主人公のあかりちゃんがブログ上、ないしは自己告白として記している文章を写しながら、不思議なことに気づきました。 高校2年生のこの少女は、とても端正な文章の書き手だということです。これはいったいどういうことでしょう。 本当にそれがあるのかどうか、よくわかりませんが、「推し文化言語」というものがあるとして、作家はその文化の中に暮らす少女を描き、その文化の中の意識や心情、行動を書き込んでいます。しかし、彼女の文体そのものは、まあ、こういうとほめすぎになるかもしれませんが、近代文学で繰り返し書かれてきた告白体小説と、とてもよく似ているのです。 もう私は、属目の風景や事物に、金閣の幻影を追わなくなった。金閣はだんだんに深く、堅固に、実在するようになった。その柱の一本一本、華頭窓、屋根、頂きの鳳凰なども、手に触れるようにはっきりと目の前に浮んだ。繊細な細部、複雑な全容はお互いに照応し、音楽の一小節を思い出すことから、その全貌を流れ出すように、どの一部分をとりだしてみても、金閣の全貌が鳴りひびいた。(三島由紀夫「金閣寺」新潮文庫P30) どうです、あんまりな引用に、びっくりなさったでしょうか。三島由紀夫の「金閣寺」の第1章の末尾、主人公の青年が「金閣寺」に鳴り響く音楽を見出した瞬間の描写です。 「金閣寺」は今や古典ですが、考えてみれば1956年に書かれた「推しモユ」小説と言えないこともないのではないでしょうか。 で、上の引用は二つの作品の「推し」のありようについて「推し」ている当人の告白なのですが、なんだかよく似ていると思いませんか。 両方「推しもゆ」小説だとして、三島の作品では「金閣」が、宇佐見りんの作品では「アイドル・タレント」が、「推し」の対象です。 で、二つの作品は、本来、客体であった「推し」に対して「どの一部分」を取り出しても「全貌」が自分の主体の中に入ってくるというふうで、とてもよく似ています。 宇佐美りんの場合は対象が人間なので、その「意識」や「感受性」の主観への取り込みという形になっていますが、三島由紀夫が駆使しているい音楽のメタファーを当てはめても、さほどの違和感はありません。 ここで、もう一度、「これはどういうことなのでしょう?」と思うわけでした。 で、最後まで読んでみて、それぞれの作品の結末を比べてみると、金閣は焼けて、アイドルは普通の男性に戻ります。で、「燃えて」いた主人公はどうなるかというわけです。 私は膝を組んで永いことそれを眺めた。 気がつくと、体のいたるところに火ぶくれや擦り傷があって血が流れていた。手の指にも、さっき戸を叩いたときの怪我とみえて血が滲んでいた。私は遁れた獣のようにその傷口を舐めた。 ポケットをさぐると、小刀と手巾に包んだカルモチンの瓶とが出て 来た。それを谷底めがけて投げ捨てた。 別のポケットの煙草が手に触れた。私は煙草を喫んだ。一仕事を終えて一服している人がよくそう思うように、生きようと私は思った。(「金閣寺」新潮文庫P257) 有名(?)な結末です。実際に金閣に火をつけた小説のモデル、林養賢という人物は現場で自殺を図ったうえでとらえられたようですが、小説の主人公は「推し」を失いながら「生きる」ことを決意します。 で、所謂「ネタバレ」でしょうが、こちらが宇佐見りんの「推し燃ゆ」の結末です。 綿棒をひろった。膝をつき、頭を垂れて、お骨をひろうみたいに丁寧に、自分が床に散らした綿棒をひろった。空のコーラのペットボトルをひろう必要があったけど、その先に長い長い道のりが見える。 這いつくばりながら、これがあたしの生きる姿勢だと思う。 二足歩行は向いてなかったみたいだし、当分はこれで生きようと思った。体は重かった。綿棒をひろった。(P125) この小説は「推し」に「燃え」た結果、高校を中退した18歳の「あかり」ちゃんの語りなのですが、その語りの文章は、ある端正さで維持されており、金閣寺の主人公の語りが作家の文体そのままの文章であることと共通しています。 この相似性のなかに、「推し」というハヤリ現象を題材にしながら、小説書くという意識において「三島由紀夫」や「中上健次」のあとを歩こうとしている匂いを感じるのですが勘違いなのでしょうか。 異様にたくさん、あちらこちらで見かけるこの作品についてのレビューのなかに、「発達障害」という病名に関わる話題がたくさんありました。主人公の少女の診断書の件りが作品の中にありますから、話題になることは予想できますが、実は三島の作品でもモデル人物の精神障害が、当時、話題になったようです。三島が作品を発表したのは、その人物が結核と精神障害の悪化で、服役中に亡くなった直後のようです。 あてずっぽうですが、「金閣寺」も「推し燃ゆ」も、病者を描いた作品ではないと思います。ちょっとたいそうないい方になりますが、思想であれ美であれ、まあ、恋愛でもあこがれでもですが、精神性の純化の結果引き起こされる「反生活」的な事象を「病気」として解釈するところに、芸術は成り立たないのではないでしょうか。 「推し燃ゆ」は、今どき珍しい、れっきとした文学だと、ぼくは思いました。
2021.10.12
コメント(0)
-
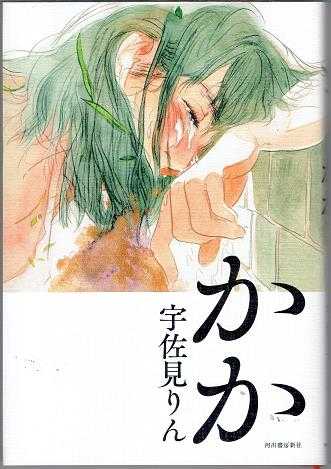
週刊 読書案内 宇佐美りん「かか」(河出書房新社)
週刊 読書案内 宇佐美りん「かか」(河出書房新社) 19歳の浪人生の女の子「うーちゃん」が「おまい」に語りかける、宇佐見りんの「かか」(河出書房新社)という作品はこんなふうにはじまります。 そいはするんとうーちゃんの白いゆびのあいだを抜けてゆきました。やっとすくったと思った先から逃げ出して、手のなかにはもう何も残らんその繰り返し。(P3) 書き出しの一文からもうかがわれますが、この作品の特徴は何といっても「ことば」です。作品の題として使われている「かか」という母に対する呼びかけの言葉に始まり、語り続ける「うーちゃん」が「おまい」と呼びかける二人称も、ある種、独特な「身内ことば」、ジジ、ババ、姉弟、親子というような世界で流通することばです。そのあたりのことを「うーちゃん」自身がこんなふうに語っています。 イッテラシャイモス。うたうような声がして、しましま模様の毛糸のパジャマに身を包み前髪を少女のようにばっつし切ったかかが立っていました。怪我した素足を冷やこい玄関の床にぺたしとくっつして柔こい笑みを赤こい頬いっぱいに浮かべています。かかが昔早朝から仕事に出ていたときのように、うーちゃんは本来であればイッテキマンモス、と答えなくちゃいけんかった、でも答えませんでした。このトンチキな挨拶はむろん方言でもなければババやジジたちの言葉でもない、かかの造語です。「ありがとさんすん」は「ありがとう」、そいから「まいみーすーもーす」は「おやすみなさい」、おまいも知ってるとおり、かかはもかにも似非関西弁だか九州弁のような、なまった幼児言葉のような言葉遣いしますが、うーちゃんはそいをひそかに「かか弁」と呼んでいました。(P10~11) わたしたちは故郷の言葉として、あるいは、一般的な始まりの言葉として「方言」を知っています。石川啄木が上野駅に聞きに行ったあの言葉ですが、実は、その「故郷の言葉」以前に、人は「家族のことば」とでもいうべき最初の言葉で世界と出会うのだという、当たり前のことなのですが忘れていたことに宇佐美りんという若い作家が挑んでいる作品でした。 生まれて最初に出会う「はじまりの言葉」の世界には人間という存在にとって、不可避の宿命のように始まってしまう、まだ形をとらない「するんとゆびのあいだから抜けてゆく」頼りない「不安」のようなものが漂っているのでしょうね。 19歳の少女が、そんな「はじまりの言葉」の世界から自立し、「自らの生の世界」を獲得するための「祈り」のような作品でした。 作品を読み始めた当初、熊野へ旅する「うーちゃん」に、横浜で暮らす19歳の少女がどうして「熊野」を目的地にするのかというところに無理やりなものを感じていたのですが、作品の後半、熊野の森にたどり着いた「うーちゃん」の姿を読みながら、1973年の芥川賞候補作「19歳の地図」の中上健次を彷彿とさせられるとは想像もしませんでした。 かつて「19歳の地図」の少年は、緑の公衆電話を武器にしていたのですが、「うーちゃん」はスマホの画面に広がるSNSの世界を生き抜くことで戦いを挑んでいるかに見えます。 「うーちゃん」にとって、ネットの世界はこんな感じなのです。 インターネットは思うより冷やこくないんです。匿名による悪意の表出、根拠のない誹謗中傷、などいうものは実際使い方の問題であってほんとうは鍵をかけて内にこもっていればネットはぬくい、現実よりもほんの少しだけ、ぬくいんです。表情が見えなくたって相手の文章のほのかなニュアンスを察してかかわるもんだし、人間関係も複雑だし、めんどうなところもそんなに変わらん、ほんの少しだけぬくいと言ったのは、コンプレックスをかくして、言わなくていいことは言わずにすむかんです。第一印象がいきなし見た目で決まってしまう現実社会とはべつにほんの少しだけかっこつけた自撮りをあげることもできるし、「学校どこ?」なんて聞いてくる人もいないし、教室でひとりお弁当を食べている事実を誰も知らないわけです。みんな少しずつ背伸びができて、人に言えん悩みは誰かに直接じゃなくて「誰かのいる」とこで吐き出すことがでるんです。(P34) 「公衆電話」であろうと「SNS」であろうと、それぞれ、時代を描く「道具」としてリアルなのですが、この作品では、ある原型的な「人間存在」の疎外を、SNSを使い今の社会に生きている人間の姿で具体的に描いているところが「あたらしい」と思いました。 ただ、そういう「うーちゃん」を描く、宇佐見りんという作家は、案外、正統派のオーソドックスな作家ではないかという気もしたのですが、どうなのでしょうね。追記2021・10・10 宇佐見りんさんは、二作目の「推し燃ゆ」(河出書房新社)で2021年の冬の芥川賞を受賞しました。面白かったのは受賞のインタビューで「中上健次」の名前が出ていたことです。「かか」の主人公うーちゃんが熊野に旅をするのは、うーちゃんにとっての必然ではなくて、書き手の宇佐見りんにとっての必然だったようです。 それにしても、久しぶりに中上健次の名前を口にする作家が誕生したことに、何ともいえず「嬉しい」気持ちになったのでした。 もうそれだけで、この作家のこれからに期待してしまいそうです。
2021.10.10
コメント(0)
-

週刊 読書案内 尾崎真理子「現代日本の小説」(ちくまプリマー新書)
週刊 読書案内 尾崎真理子「現代日本の小説」(ちくまプリマー新書) 詩人の谷川俊太郎に対するインタビュー集「詩人なんて呼ばれて」(新潮社)のインタビュアーをしていた尾崎真理子という人が気にかかって手に取った本がこの本でした。 「現代日本の文学」(ちくまプリマー新書)です。 1987年から、本書が出版された2007年の20年間の「現代日本文学」について、感想を交えながら「年表」化、あるいは「文学史」化して、エピソードを紹介解説した著書でした。 著者の尾崎真理子は1959年の生まれで、1992年に読売新聞の文化部に配属され、2020年に退職したときには文化部の次長さんだったようですが、現在は早稲田大学の教授さんのようです。 尾崎さんの「文学史」の肝は「1987年」という年を「終わり」と「始まり」に設定したことだと思います。 本書のプロローグに、1987年とは、二葉亭四迷が本邦初の言文一致体小説「浮雲」を発表してから、ちょうど100年目にあたることを指摘しながら、第1章を「一九八七年、終わりの始まり」と題して、こんなふうに書き出しています。 ここでは四人の人物の紹介を引用します。一人目は「ばなな伝説」の始まりと小見出しをつけてこの方です。 「受賞者は吉本さんの娘らしい」 一九八七年九月十六日。午後七時頃に第一報は飛び込んできた。応募書類の住所に見覚えがあった編集者が気付いたのだという。東京・文京区内の自宅に急行した読売新聞文化部の先輩記者に、吉本夫妻は、「どうぞ。娘は浅草のアルバイト先から三十分もすれば戻ってきますから」。そんなふうにのんびり応じたという。よしもとばなな伝説は、この日から始まった。 文芸雑誌「海燕」の今年の新人文学賞に、詩人、評論家の吉本隆明さんの二女吉本真秀さん(23)が入選したことが十六日明らかになった。 「吉本ばなな」という人を食ったペンネームで応募した受賞作「キッチン」は原稿用紙六十八枚。祖父母に育てられ、台所の冷蔵庫のそばにいる時が一番心が休まるという孤独な少女が、祖父母の死後、友人の家庭に引きとられる。その家で、友人の母親として親し んだ女性が、実は女装の男だった―という奇妙なストーリー。(P13~14) 二人目が、今や「世界の村上」、村上春樹の「ノルウェイの森」です。 一九八七年九月十七日。「100パーセントの恋愛小説」。その帯の文章も赤と緑の上・下巻の装丁案も作家自身が手掛けたという、村上春樹(当時38歳)の書き下ろし長編『ノルウェイの森』が全国の書店に平積みでお目見えしたのは、その一週間前、九月十日のことだった。初版は講談社の文芸書としても異例の二十万部。 ― ハンブルグ空港に着陸する直前の飛行機のなかで、BGMとして流れてきたビートルズの「ノルウェイの森」によって、三十七歳の男性主人公が、不意に記憶をかき乱されることころから、曲と同名のこの物語は始まる。(P14~15) 三人目が、さて、この方は「始まり」を象徴するのか、「終わり」の人なのか。まだ「ノーベル賞」はとっていませんが、デビュー作「奇妙な仕事」を東大新聞に発表したのが1957年です。30年後の大江健三郎です。 翌十月、戦後を生きてきた知識人の精神的自伝ともいうべき書き下ろし長編が発表された。大江健三郎(当時52歳)の『懐かしい年への手紙』。同年末の文芸作品の回顧記事で1987年の収穫として批評家各氏が多く挙げ、今日でも大江の代表作の一つとして名高い。だが、当の大江は、発表当時の忘れられない光景を次のように語るのだ。〈『懐かしい年への手紙』が出た直後、沖縄だったと思いますが、地方に出掛けていて、気になりますから東京に戻るとすぐ大きい書店に行ってみた。そうすると平積みされているのが一面、赤と緑のきれいな装丁の『ノルウェイの森』で、私の本はその奥から恥ずかしそうにこちらを見ていた(笑)。非常に印象深いんです。そう小説が読まれる機運の転換が。〉(P15) そして、もう一人、新しく始まったのは「小説」の言葉だけではありませんでした。 五月。前年に短歌の芥川賞ともいわれる第三十二回角川短歌賞を受賞した歌人、俵万智(当時24歳)の『サラダ記念日』が河出書房新社から初版三千部で出版されると、直後から問い合わせが殺到し、ベストセラーリストのトップに躍り出た。〈「嫁さんになれよ」だなんてカンチューハイ二本で言ってしまっていいの〉〈万智ちゃんを先生と呼ぶ子らがいて神奈川県立橋本高校〉 若い国語教師の第一歌集から、現代短歌の口語化が一気に加速した。歌壇のみならず、文学史上の事件になっていった。(P17~18) いかがでしょうか、1987年、すごい年だったのですね。世界文学の動向を知りませんから、まあ、日本文学という、範疇に限ればという面はあると思いますが、同時代に30代だった目から見て、なるほどなあと感心しました。 引用箇所が日付で始まっているのは、著者である尾崎さんが、新聞紙上に載った記事の引用で、解説を進めているせいなのですが、ここから20年、実にジャーナリスティックに「新しい文学」と、終わったのかもしれない「古い文学」が対比されて、紹介、解説されていきます。 2000年を超えたあたりに現れる「蹴りたい背中」の綿矢りさと「蛇にピアス」の金原ひとみを次の画期として、IT化、デジタル化が、さらに「新しい文学」の方向性として論じられて「現代日本の小説」史は幕を閉じます。「簡にして要を得た」というべき内容で、同時代を生きてきた人間には、とてもよくできた見取り図でした。 ただ、不思議なことは、この本が「ちくまプリマ―新書」の一冊に入れられたことです。果たして、この本が出版された2007年当時の高校生はこの本を読んだのだろうかということでした。 当時、図書館係だったゴジラ老人には、棚に並べたこの本を手に取った高校生の記憶が全くないのです。「アーカイブ」という言葉が流行りはじめた頃でしたが、「イイネ!」の前に「歴史」が廃れる時代が始まっていたのでしょうか。 本書の帯には、「激変した日本人の感受性」とありますが、ひょっとしたら「ばなな」も「春樹」も過去かもしれないと感じる読後感でした。
2021.09.29
コメント(0)
-
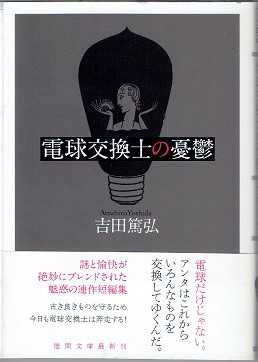
週刊 読書案内 吉田篤弘「電球交換士の憂鬱」(徳間文庫)
週刊 読書案内 吉田篤弘「電球交換士の憂鬱」(徳間文庫) 吉田篤弘の小説を案内するなら「つむじ風食堂の夜」(ちくま文庫)からにするべきなんじゃないかとは思うのですが、最近、偶然、読んだのでこっちからということになりました。 今日の案内は吉田篤弘「電球交換士の憂鬱」(徳間文庫)です。 ご覧のように、表紙は灰色の地に、なんだか古めかしい電球が黒く描かれていて、ギリシア風の女性でしょうか、何か掌に載せていますが、よくわかりません。 ページを開くと「目次」とあって電球の挿絵です。もう一枚めくるとこんな感じです。不死身 7よく似た人 51北極星 93煙突の下で 135砂嵐とライオンの眼鏡 175屋上の射的場 217静かなる電球 259 全部で7章、オシリについているのはページ数のようです。で、もう2枚ページをめくると始まります。「道に詳しいのに、自分の行き先がわからないもの、なあんだ」 いきなりマチルダが、謎謎を仕掛けてきました。(P8) 場所はバー〈ボヌール〉のカウンター、語っている「おれ」は酒も飲めないのに常連で、謎謎を仕掛けてきたマチルダをはじめ、春ちゃんとか、西園寺なにがしという刑事なんだかタクシーの運転手なんだかよくわからない謎の男とか、夜な夜な集まってだべっているのが、まあ、作品の発端というか舞台ですね。 バー〈ボヌール〉のママについてはこんな風に書いてあります。 ママは自分の煙草の煙に目を細めていた。その立ち姿は、オレに云わせれば「とびきりの一級品」である。美女とか何とかを超越している。(P14) 7章立ての短編集の体裁をとった物語の始まりというわけで、登場人物の紹介です。まあ、詳しくはお読みいただくほかないわけですが、さすがにこれは言っておいたほうがよろしいでしょうというのが、書名にも出てきますが、主人公「おれ」のお仕事のことです。 さて、おれはいよいよ「おれ」について話さなくてはならない。 なぜなら、おれもまた〈ボヌール〉の半永久的常連客=「おれたち」の一人だからだ。おれの肩書きはヤブ医者に伝えたとおり、「電球交換士」で、世界でただひとり、おれだけに与えられた肩書である。似たような作業をするヤツは他にもいるかもしれないが、肩書通り電球の交換だけを専門に引き受けているのは世界広しといえども、おれ一人だ。 きっかけは遺産だった。おれの親類縁者は、親父の血筋もお袋の血筋もことごとく早死にで、ただ一人おれを残して、全員、さっさとあの世にいってしまった。全員が判で押したように、短い人生で、だから、全員、大した蓄えもなく、全員がおれにしみったれた小金をのこした。 が、小金とはいえ、かき集めればそれなりの額になる。おれはそれまで、父親の生業だった軽業師になるつもりで弱小サーカス団の一員として修業を積んでいた。そこへ、思いがけず小金の遺産を手に入れたのだ。 さて、早死にの家系を覆すような仕事とは何だろう・・・・・。 対策を練る必要があった。なにしろ、次に殺られるのは、ただ一人のこされたおれなのだから。 しかし、じつのところ、考えるまでもなく答えは出ていた。 電球を交換すること ― いや正確に云おう。それは、儚く短い電流の時間を終え、ぷつりと切れた電球をすみやかに交換すること ― である。(P15~P16・太字引用者) 主人公というか、出来事の語り手は「おれ」で、彼の職業が「電球交換士」というわけです。ほかの登場人物たちの職業は、案外ありきたりというか、現実的なのですが、「おれ」は「電球交換士」なわけです。皆さん、電球交換士って知ってますか? マア、この後もしばらく自己紹介が続くのですが、いかがでしょう。かなりご都合主義で、かつ牽強付会な論理展開なのですが、とりあえず、こういう「おしゃべりな文章」がお嫌いでない方には、この小説は悪くないと思いますよ。 で、まあ、読むにあたって問題は、その電球交換士とやらが、いったい何をするのかということなのですが、もちろん、電球を交換するのです。実際、美術館とか博物館とかの天井の電球から、とどのつまりは「東京タワー」と思しき展望台の電球交換の話まで出てきます。 でも、そういう仕事の話を読まされたにしても、「そりゃあそういうお仕事もあるでしょうよ」とは思いますが、「早死に」から「不死身」への変身と、電球交換がどうつながるのか、という、あっけにとられるような職業選択の「理由」というか「秘密」はわかりませんね。 そろそろお気づきでしょうが、この小説はその「理由」だか「秘密」だかを「ミステリー」というか「謎」にして読ませる作品なのですね。 すまして言えば「時間」をめぐって、冒頭の謎謎「道に詳しいのに、自分の行き先がわからないもの、なあんだ」を追いかけている話だといえないわけではないのですが、まあ、「灯り」ネタの小話集といえないこともないというのが感想でした。 読み終わってみると、フーンという感じで軽いのですが、ちょっと残るというのは、たぶん「時間」ネタのせいですね。吉田篤弘のいつもの手だと思いました。 ちなみに。主人公の名前は十文字扉(じゅうもんじとびら)さんで、交換して回る電球は「十文字電球」ですね。皆さんは「十文字電球」ってご存じでしょうか?マア、それよりなにより、白熱電球って、お宅にあります? もう一つ、ちなみにですが、ご存じの方は、当然ご存じなわけですが、吉田篤弘は「クラフトエビング商会」の事務員さんですね。もう一人の吉田浩美さんがデザイナーらしいですが、ありもしない本を作ったりして評判の会社です。 そうそう、ちくまプリマ―新書のブックデザインとかやっている、あの会社です。マア、今や事務員稼業より、小説書きのほうが忙しそうですが。(笑)
2021.09.27
コメント(0)
-
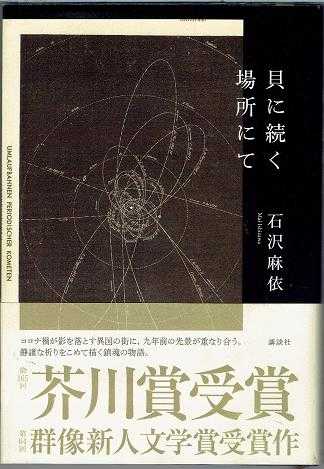
週刊 読書案内 石沢麻依「貝に続く場所にて」(講談社)
週刊 読書案内 石沢麻依「貝に続く場所にて」(講談社) 今年の夏の芥川賞は李琴峰(り・ことみ)さんの「彼岸花が咲く島」(文芸春秋社)と石沢麻依さんの「貝に続く場所にて」(講談社)でした。 お二人とも女性で、李琴峰さんは、作年、「ポラリスが降り注ぐ夜」(筑摩書房)で、新宿の夜の酒場を描いて芸術選奨文部科学大臣新人賞とかを受賞して評判になった作家ですが、今年は芥川賞ゴールインです。拍手!ですね。 石沢麻衣さんは、芸術学、西洋絵画の研究者で、ドイツの大学に留学中の才媛だそうです。で、その才媛が書いたこの作品の出だしはこんな風でした。 人気のない駅舎の陰に立って、私は半ば顔の消えた来訪者を待ち続けていた。記憶を浚って顔の像を何とか結び合わせても、それはすぐに水のように崩れてゆく。それでも、断片を集めて輪郭の内側に押し込んで、つぎはぎの肖像を作り出す。その反服は、疼く歯を舌で探る行為と似た臆病な感覚に満ちていた。(P003) いかにも、賢そうな文章です。ただ「記憶」、「肖像」、「臆病な不安」というイメージを「水のように」という直喩でまとめようという雰囲気なのですが、このパラグラフに限っても「水」のイメージでうまくまとめ切れていないために、アンビバレンツな読みにくさを作り出しているというのは、ぼくの謬見でしょうか。 おそらく「水のように崩れる」という表現を、小説の冒頭に持ってきたかったんだろうというのが、勝手な憶測ですが、その憶測は全編読み終えて浮かぶことで、この場面を読む限りでは「水のように崩れる」という表現が、東北の震災と深くつながっていること読み取ることは難しいのではないでしょうか。 作品は、いわゆる「東北震災」をテーマにした「災後小説」というべき佳作だと思います。ただ、ちょっと嫌味を言えば、いかにも才媛らしく「頭の中で考えた世界」をことばをあてはめて描こうとする「硬さ」が目立つ作品だと思いました。 あの三月以来、鳥の視点で街という肖像画を眺めるようになった。 三年前ドイツに出発する日の朝、仙台空港から成田空港へ飛行機で移動した。機上となり窓から見下ろすと、海岸がくっきりとした線を青の中に刻み付けている。線の内側には地面の茶色の下地が広がり、そこにわずかな建物だけが点在している。素描の途中で手をとめてしまったかのようだった。以前の絵をなぞろうとして、再現できずにいる記憶の図。私の中に、その印象が浮かび上がる。海の手が暴力を振るった後を消し去ることはできず、そこは素描のための下地を整えることから始めなくてはならない。記憶を底に重ねようとしても、その投影が覆いつくすのは痛みを刻んだ別の顔。引き裂かれた時間の向こうに消えた肖像を、甦らせることはできないままだ。 ある場所や土地を描くと、風景画ではなく肖像画になっていることがある。額縁に囲まれた土地や町の中に、「顔」が浮かび上がってくるのだ。時間の中で変化し続けてゆくものを捉え、その記憶を重ねてゆくと、街や場所の肖像画となる。様々土地から土地へ移動を繰り返すうちに、風景画と場所の肖像画の違いが次第に見て取れるようになってきた。そこには、時間の異なる視点が関わっているのかもしれない。風景に必要なものは、現象の細やかな観察や写真的な視点であり、それを見ている者と場所の現在の対話的な時間の記録となる。しかし、ある場所を見て過去を重ね、そこに繋がる人の記憶に思いを寄せる時、場所の改装という独語(モノローグ)の聞き手とならなくてはならない。その時それは、風景画ではなく場所の肖像画となるのかもしれなかった。 失われた場所を前にした眼差しが探し求めるのは、破壊される前の土地の顔である。時間が跡を残し、記憶がしみ込んだ馴染みの深い顔。あの日以来、だれもが沿岸部を訪れるたびに、それを探し求める透過した過去への眼差しを向けている。(P115~P116) 小説が中盤を超えたあたりの引用ですが、「以前の絵をなぞろうとして、再現できずにいる記憶の図」という記述を「頭の中に浮かんできた絵をなぞろうとして」と置き換えると、このパラグラフ全体が、彼女の作品の解説になっているようで面白いのですが、絵画の研究者の絵画論としてとても面白いと思いました。とっつきの悪い作品でしたが、この辺りまで来るとかなり読みやすくなるのも不思議です。 いろいろ、嫌みを言いましたが、実に誠実な自己告白小説というべき作品で、「記憶がしみ込んだ馴染みの深い顔」を探し求め、「時間」を透過することができる方法を探り、幻想小説を思わせるイメージを駆使した努力が芥川賞として評価されたことは、素直に讃えたいと思いました。
2021.09.25
コメント(0)
-
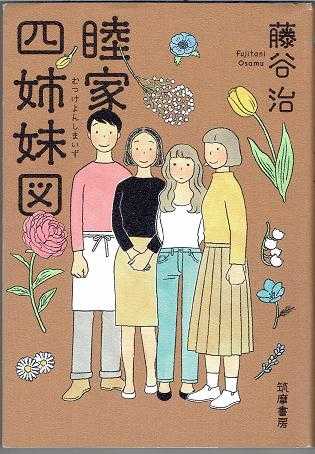
週刊 読書案内 藤谷治「睦家四姉妹図」(筑摩書房)
藤谷治「睦家四姉妹図」(筑摩書房) 藤谷治という作家も作品も知りませんでした。読んだことのない作家や作品を「ちょっとこれどう?」という感じで、まあ、いつも教えていただく知人から差し出されました。「4人姉妹といえば、谷崎の細雪なんだけど、これも4人姉妹よ。ちょっと読んでみない?細雪は900ページだけど、これ200ページくらいで済むからね。」 なんだか、意味深な笑顔です。「はずれなの?」「さあ、どうでしょう。」 というわけで自宅に持ち帰って、いつものように食卓に放りだしているのをチッチキ夫人が見つけていうのです。「あら、この人知ってるわよ。」「えっ、なんで?」「筑摩書房の『ちくま』の連載でしょ。」 そうなんです。彼女は岩波書店の「図書」とか講談社の「本」とか、いわゆるPR誌の鬼というか、とっても熱心な読者なのです。「ちょっと。先に読んでいい?」「はい、はい、どうぞ、どうぞ。」 二日ほどして、本は食卓に戻ってきました。「ちょっと、これ、さっさと読んでみてくれる?」「えっ?なに?なにかあったの?」「いいから、読んでみてよ。」「面白かったの?」「さあ、どうでしょう。」 振出しに戻りましたね。じゃあ、読み始めましょうか。最初のページにこんな図が載っていました。 1988年、昭和63年の1月2日の「睦家」の家族写真です。「睦家四姉妹図」という作品名はこの仕組みからつけられているようですね。 この作品は8章で構成されていますが、各章の冒頭には必ずその年の1月2日に撮られた家族写真か掲げられています。記述はその日に集まった家族の様子です。なんで、1月2日なのかというと、その日が四姉妹の母、睦八重子さんの誕生日だからですね。 上の写真を撮った第1章「揺れる貞子と昭和の終わり」の冒頭はこんな感じです。 貞子が帰ると、家の中には誰もいなかった。「明けまして、おめでとうございまあす・・・・」 人の気配は全然しなかったけれど、一応、挨拶しなながら入っていった。コートを脱ぎ、荷物と一緒に応接間のソファに放り出し、台所の方をチラッと見たが、やはり無人である。「ふん・・・・・」 貞子はため息をついた。 長女貞子二十四歳、正月の二日目、毎年恒例になっている、母八重子の誕生パーティーのために帰宅したのですが、残りの家族は、なぜか留守だというシーンです。 この日から、ほぼ二十年後、平成二十年、2008年のこの日は第6章「このごろのサダ子さん」です。 まずこの写真があります。 妙に人数が増えていますが、冒頭はこうです。 もはやいちどきに全員が応接間に収まることはできない。子どもたちは年齢に差もあるし、そうしょっちゅう顔を合わせているわけでもない。男の方が多いからお互いへのけん制もあるかもしれないが、それでも応接間から食堂、奥の間や浴室に向かう廊下を、みんなで甲高い声を上げて走りまくっている。 ついでなので、最終章「楽しき終へめ」も引用してみます。(ちなみに、ぼくはこの題が読めませんでした。) 日付はご覧の通り、2020年の1月2日です。30年余りの年月が立ちました。写っているのは1988年の写真と同じ6人。ただし撮っている人が余分に一人います。場所は埼玉県のURの賃貸住宅です。 乗り慣れない電車の乗り換えに手間取って、各駅停車だけが止まる小駅にたどり着いた時には、電話で告げた予定の時間よりも一時間以上遅れていた。「電話しとこうか?今来たって」という梶本に、「いいよ」貞子は答えた。「あと五分だもん」 駅からの道は、迷いようもない。駅を背にして広々とした歩道を、ただまっすぐに歩いていくと、十字路の先に巨大な白い集合住宅が、二、三百メートル先の行き止まりまで並んでいるのが見える。 まあ、こんなふうに、さほど手間もかからず読みえたわけです。読み終えると、さっそくチッチキ夫人が聞いてきました。「どう?」「うん、まあ、おもしろいんじゃないの。」「どこがあ?」「それぞれの章の始めにある写真の図かな。これ、架空の家族でもいいけど、本物の写真だったら、投げ出していたような気がする。最初6人だった写真が、年ごとに増減すやんな。一応、長女の貞子の語りでその日のことが語られるねんけど、みんな、薄っぺらいねんな。子どものいない貞子の目という都合に合わせた、勝手な客観描写があるだけやし。でもな、その年その年の写真の名前を見ながら、だんだん、膨れ上がっていくねん。苗字が変わったり、何年か前はあったはずの苗字と一緒に男の名前が消えたり、また新しい名前がふえたり。 正月の二日に、オバーチャンの誕生会に集まる子供や、その親がどんな暮らしをしているかなんて、急にピアノ引き出した子がおったり、寝てたのに泣き出したり、もうそれでなんかわかるというか、離婚の事情とか、最後の章の書き出しでも、写真の名前見て、ああ、梶本って貞子の男で、こういう奴やんなって。」「どういうことか、ようわからへんわ。」「そやから、繰り返し8回写真の名前見て、読んでる読者は昔のホームドラマを勝手に思い浮かべるように、自分の生活とかに浸るように仕組まれてんねんって。」「地震のこととか、流行りのマンガとかのことはなんで出てくんの?」「細雪が昭和の初めの歴史やってんから、こっちは平成の歴史でっせって」「それって、インチキくさくない?」「うん、舞台背景、書割っていうやろ、それしかない。まあ、それも、通俗ちゃあ通俗やねんけど。個々の登場人物の気持ちの描写ってステロタイプやろ。その人物らしいこと、その事件らしいことだけ書かれてて、他には、ほぼ、なにも書いてへんねんけど、そやから、みんな同感できんねん。名前と年齢だけ見て読者が考えてくれる。写真には名前と年齢しかないからイメージは読み手の自前。だから、リアルやねん。」「でも、読み終わっても、何にも残らへんやん」「残ったら、ウザイやろ。この作品は読者の30年間の平和な夢なんやから。これ、かなりなたくらみや思うで。」 と、まあ、老人だから、そう思うにすぎないかもしれない意味不明な会話でしたが、なんというか、「細雪」との隔絶は近代文学の終焉どころの話ではなさそうです。ひょっとして、「文学」以外のジャンルでは当たり前の現象に過ぎないのかもしれませんね。 勝手な言い草ですが、広告会社が「感動」とか「同感」とかの「肝」みたいなもの集めて、それを、それぞれの「事件」の「リアル」として構成するためだけのアイデアをひねって生まれてくる「作品」というのが、「自然」な「情感」にフィットするという、恐るべき時代が始まっているのでしょうね。 それにしても「ちくま」の連載だったということが、それはそれで感慨深かった読書でした。お暇な方におススメです。(笑)
2021.08.16
コメント(0)
-
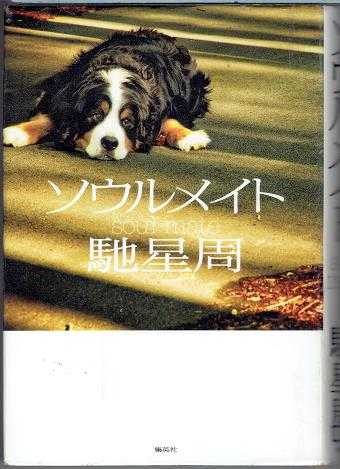
週刊 読書案内 馳星周「ソウルメイト」(集英社)
馳星周「ソウルメイト」(集英社) 市民図書館の返却の棚で見つけました。馳星周の「ソウルメイト」(集英社)です。2013年に単行本が出版されて、その後、「ソウルメイト」、「陽だまりの天使たち ソウルメイトII 」(集英社文庫)と文庫化されているシリーズの、まあ、第1巻ですね。一言でいえば「犬」の話でした。 馳星周が直木賞を取ったのは昨年、2020年ですが、彼が最初に評判になったのは「不夜城」という作品で、もう30年前のことです。 新宿の夜を描いた「ノワール」小説だったと思います。評判になったころ読みましたが、忘れてしまいました。当時、作品よりも、馳星周という人が内藤陳というコメディアンがやっていた「深夜プラス1」という酒場の、アルバイトのバーテンだったことに、ミーハーな興味を持ちましたが、ぼくのなかで内藤陳が旗を振っていた「冒険小説」のブームが終わるとともに忘れていた作家でした。 で、昨年の直木賞で思い出しました。受賞作は「少年と犬」(文芸春秋)だそうです。 「えっ、まだ取っていなかったの?」 それが正直な、最初の感想でしたが、その次に来たのが、「犬って何よ?」という疑問でしたが、この作品を読んで氷解しました。 この方は「犬」が好きです。それも半端ではない「愛し方」です。この本には7頭の犬の話が書かれていますが、どの話も誰かが誰を「愛する」とか「信頼する」ということが、人間という枠を超えて描かれています。いや、犬という仲間を通して描かれているというべきでしょうか。 で、読み終えてわかるのですが、あの内藤陳さんが褒めたたえた「冒険小説」の血脈はここに流れていますね。何せ、題が「ソウルメイト」、「魂の友達」ですよ。 ぼくは、犬が嫌いなわけではありませんが、とりわけ好きなわけでもありません。そういう人間が、ページを繰ってみると、そこにあるのは「犬の十戒」です。「おいおい」というか、「ええー、なによ」とい気分でやり過ごして、本文に向かいました。マア、どっちかというと、あっという間に読み終えました。で、なんと「十戒」に戻ってきてしまいました。面白かったのでしょうね。Be aware that however you treat me,I will never foget it.ぼくにどんなことをしたか、ぼくはずっと覚えているからね。 第6の戒です。一番短いので写すわけではありません。「冒険小説」の真髄の一つだと僕が思うことが、戒律としてここにあると思うからです。言い直すとこんなふうになるでしょうか。 「ぼくのこの世界での経験は『魂のこと』として、ぼくのなかに刻み付けられていく。」 まあ、そういう生きざまの登場人物を描くこと、それが、件の「冒険小説」の要素の一つだったと思うのですが、「犬」と暮らすということと、実に、ぴたりと重なるのですね。 マア、馳星周がそう書いているということではあるのですが、犬好きの人はもちろん、その手のお話が好きな人にはぴったりかもしれませんね。ぼくは結構はまりました。直木賞の受賞作にも手を出してみようかなと思っています。なかなか読ませますよ。
2021.07.18
コメント(0)
-
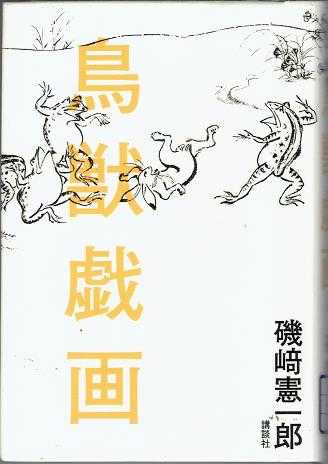
週刊 読書案内 磯崎憲一郎「鳥獣戯画」(講談社)
磯崎憲一郎「鳥獣戯画」(講談社) 磯崎憲一郎という作家は2007年、「肝心の子ども」という作品で文芸賞をとって登場した人で、三井物産かどこかのサラリーマン作家と聞いたことがあります。 「肝心の子ども」をすぐに読んで、なんだかわけがわかりませんでした。そう思いながら、なぜか、「終の棲家」とか「赤の他人の瓜二つ」とか、なんとはなしに読み続けて、さすがに「電車道」という長編(?)を読み終えてダウンしました。 文章が難解でわからないとか、「て、に、を、は」がおかしいとか、そういうことではありません。ただ、ひたすら、作家、ないしは文章の書き手として登場する人物が、なぜ、「こんなこと」を延々と描いているのだろうという、ほとんど「いらだち」に近い「わからなさ」に翻弄されてしまったからです。 で、本作はどうだったのか。これが、異様に面白いのです。作品の題は「鳥獣戯画」、読み終えて、なぜこんな題がつけられ、装丁にも、やたらと有名な絵が使われているのか、実はわかりません。 そうは言いながら、「題」があれば「題」に引きずられて読むのが読者というもので、頭の中で、ちらちらそういうことを考えながら読み始めたわけです。 私は道を急いだ、ある人と待ち合わせをしていたのだ。ある人というのは高校時代からの古い女友だちだったが、二十八年間の会社員生活を終えた、ようやく晴れて自由の身となったその第一日目に会う相手として最も相応しいのはその女友達であるように、私には思えたのだった。「凡庸さは金になる」 ここは都心の一等地に一軒だけ奇跡的に残った昭和の喫茶店だった、白塗りの壁は煤で汚れ、杉材の柱も黒い光沢に覆われている、薄い、しかししっかりとした一枚板を使ったテーブルと椅子は細かな傷だらけで、交互に組み合わされた寄木の床も靴跡と油で黒ずんでいる、古い暖炉には本物の薪が焼べてある、季節は春だったが、まだコートの手放せない気温の低い日が続いていた。「凡庸さは金になる」 というわけで、ココから「物語」が始まるわけですが、で、男は、その「女友達」に会ったのかというと、なぜか、「若い女優」と遭遇し、あろうことか、その女優と「京都で落ち合う約束」までするという所で「凡庸さは金になる」という、意味深な、あるいは意味不明な第1章が終わります。 書き手の作家は、その女優とどうなるのかという興味に引きずられそうですが、いや、もちろん、引きずられますが、ここでは、最初の興味の「題名」に戻りましょう。 「鳥獣戯画」はどうなった、どこにいったのだということですが、第1章から70ページ後、第6章「明恵上人」という章で、ようやく出てきました。こんな書き出しです。 先斗町で湯葉料理を食べた翌朝、私と彼女は京都駅前から栂ノ尾行きのバスに乗った、「鳥獣戯画」で有名な栂尾山高山寺は、もともとは奈良時代の終わりに天皇の勅願によって建てられた寺だが、その後荒れ果てて粗末な草庵が残るばかりになっていたのを。鎌倉時代に、明恵上人が再興した、国宝の石水院は後鳥羽上皇から学問所として贈られた建物で、現在まで高山寺に伝わる経典、絵画、彫刻の類も全て明恵上人の時代に集めあられたものだ。バスが京都駅前を出発してものの五分も経たないうちに、またしても、窓から見える景色が昭和の町並みに変わってしまっていることに私は動揺した、床屋の入り口では赤・白・青三色縞模様のサインポールが回っているし、八百屋は店先のキュウリやトウモロコシを笊に盛った生姜を初夏の日差しから守るため、簾を人の背の高さまで下げている、「谷山無線」というトタン板の大きな看板を下げた電気屋はまだシャッターを上げていない、雨で汚れた漆喰壁に無数のひびが入った釣具店の中では老いた店主が立ち上がって、誰かに向かって怒鳴っているのがガラスの引き戸越しに見える、しかしこんな大都市の真ん中にどうして釣具店が必要なのか?商売として成り立つのか?こういう昔の町並みはもはや東京では決して見ることはできない、それとも本当はまだ見ることができるのに、私がただ単に、見て見ぬ振りをしているだけなのだろうか?大宮松原という停留所から赤ん坊を抱いた若い母親が乗ってきた、座席は空いているのだが寝ている子供を起こしたくないからだろう、吊革に掴まって立ったままでいる、白い半そでのブラウスから覗いた二の腕が細い、まとめ髪の下の襟首も痛々しいほどに細い、若い母親は抱っこ紐の背中側のロックを締めようとするのだが指先が届かない、バスが揺れると身体も揺れてますますうまく行かない。手伝ってやりたい気持ちが、懐かしさと性欲の入り混じった感情とともに私の中に沸き起こったのだが、隣に座る女優に不審に思われることを恐れてぐっと堪えた、穏やかな、楽しげな表情で京都の商店街を見る彼女の横顔は、午前中の銀青色の粉のような光を浴びてますます美しかった、昨晩と違い、しっかりとした化粧が施されていた。「明恵上人」 写し出したら止まらなくなったので、ここまで写しましたが、なんか変だと思いませんか?「句点」がほとんどないのです。「改行」もありません。男はバスに乗っています。隣には女優が座っていて、窓の外や、社内の様子が描かれています。書き手の、おそらく意識を刺激することの連続が、句点なし、改行無しで書き綴られていきます。辛抱して読んでいただいて、そのうえ、質問なのですが、「綴っている」この瞬間、書き手がどこにいるのか、気になりませんか? 第1章の文章が、なんとなく過去を振り返っているのに対して、引用した部分は、今、現在を思わせるのですが、この後、高山寺に到着して始まる明恵、文覚に関する記述は、「明恵上人」「型のようなもの」「護符」「文覚」「妨害」「承久の乱」「入滅」と全部で七章にわたり、明らかな過去であるにもかかわらず、不思議な時制で、延々と、ほぼ100ページにわたって続きます。 で、それが、まず異様に面白いのです。意識の臨場感の赴くままに1000年近くも過去にさかのぼり、やがて、自らの少年時代、高校時代から、会社員時代へと、実に自由に記述は帰ってきます。 その間「鳥獣戯画」はどこにいったのでしょうか。さあ、どこにいってしまったのでしょうね。相撲を取るウサギや、走って逃げるサルたちの面影が兆したような気はするのですが、果たして、この作品とどう結びついているのか、そのあたりはお読みいただくほかありませんね。 句点のない、長々しい文章を自在に操りながら、とどのつまりは、肌寒かった春の日の半年後、再び、あの「昭和の喫茶店」のドアに手をかけるところで小説は終わります。 作品の中で流れる半年の時間の中で記述されていく、あるいは、1000年前に起こった出来事が、あるいは、作家自身が何年も前に経験したはずの出来事が、果たして本当に起こったことなのかどうか、そして、今、再び、作家自身が昭和の喫茶店のドアに手をかけていることは事実なのかどうか、それは何とも言えませんが、作品の中では確かに起こっていて、その1000年とか、何年もの年月とか、そして、半年とかの時間は作品の中に、確かに流れていることは、お読みになれば実感していただけると思います。 いやはや、これは、ちょっと、すごいことだと思うのですが。わからないのは、その実感がどこから来るのかということと、「鳥獣戯画」という題名は、一体何だったのということで、はい、なにがなにやらさっぱりわからない、にもかかわらず、異様に面白いという結論でした。うーん、何がこんなに面白いんでしょうね。やれやれ。
2021.05.09
コメント(0)
-

週刊 読書案内 保坂和志「この人の閾」(新潮文庫)
保坂和志「この人の閾」(新潮文庫) 保坂和志の「この人の閾」(新潮文庫)を久しぶりに読み返しました。1995年夏の113回芥川賞受賞作です。 学生時代に同じ映画サークルの1年先輩だった女性「真紀さん」の家に、仕事で近所まで来て、偶然時間が空いてしまった「ぼく」が訪ねて行きます。二人で庭の草むしりをしたり、缶ビールを飲んだりして、半日を過ごした日のおしゃべりと、おしゃべりをしながら「ぼく」がふと考えたことが記されている作品です。P65(新潮文庫版) 真紀さんのいる場所は今この自分の家庭の中心ではなく、家庭の「構成員」のそれぞれのタイム・スケジュールの隙間のようなところで、それでは「中心」はどこにあるかといえばたぶんそんなものはない。子育てというか子どもの教育を中心においてしまうような主婦もいるが、真紀さんの場合どうもそれもなくて、たとえばモンドリアンの絵のように彩色されたキャンバスの上で何本もの車線が交差しあっているような絵を、ぼくはそのとき想像した。そして、現代芸術というのは絵画も音楽も何でもどんどん抽象度を増すが、家庭もそうだったのかと思ったりした。P75「ホラ、ヨハネの福音書のはじめに『初めに言葉があった』っていうのがあるじゃない」「うん」「 ― 『初めに言葉があった。言葉は神とともにあった。言葉は神であった』っていうの。 それから何だったっけ? 細かいことは忘れちゃってるけど ― 、すべてのものは言葉によってつくられて、言葉に命があって、その命は人の光で、光は闇の中で輝いた。闇は光に打ち勝たなかった―っていう意味のこと言ってるでしょ?」「うん」ぼくも真紀さんもキリスト教の信者ではないが、聖書の有名な箇所ぐらい知っていてもおかしくはない。「―だから言葉が届かないところっていうのは『闇』なのよね。そういう『闇』っていうのは、そこに何かあるんだとしても、もういい悪いじゃないのよね。何もないのと限りなく同じなのよね。」P77 ぼくは、このとき真紀さんの言ったことは、真紀さんがその場で考えたことではないはずだと思った。こんなこと即席で考えられるはずがない。これはイルカについてのことではなくて、真紀さん自身のことなのだろうと思ったけれどぼくは黙っていた。「静かね」真紀さんは言った。「洋平が一度あらわれて、消えてみると静かさが、こう、這い上がってくるようだ」「気になる?(ぼくはあいまいに頷いた) 二人でいるからね。 一人だといいわよ。この静けさにずっとつづいてほしいと思うわよ。 でも、洋平もルミも前ぶれなしに帰ってきちゃうのよね」 自分の家なんだから当然だとぼくは笑った。「そうなのよ おかしなところよね。家って。 自分でもずっとそうしてたわけだけど、出ていくときはまあ、いちおう 『行ってきます』って言うけど、帰ってくるときはフッて帰ってくるからね。 で、しまいには大きくなって平気で家をあけるようになってるのよね」 ぼくは少し悲しいような気がした。真紀さんの口を借りて普遍的な母親がしゃべったような気がしたからだ。普遍的な母親というのはぼく自身の母親と言い換えてもいいのだろう。 作品の終盤の光景です。引用していると楽しいのですが、引用をお読みになっても、ここがクライマックスだとぼくが思ったことは伝わらないでしょうね。 この作品が芥川賞を受賞した際に、選考委員だった作家たちの感想から、三人の感想を引用します。日野啓三 「他の都合もあって合計四回読んだが、読む度に快かった。(引用者中略)いまこの頃、私が呼吸しているまわりの空気(あるいは気配)と、自然に馴染む。こういう作品は珍しい。」 「バブルの崩壊、阪神大震災とオウム・サリン事件のあとに、われわれが気がついたのはとくに意味もないこの一日の静かな光ではないだろうか。」 「その意味で、この小説は新しい文学のひとつの(唯一のではない)可能性をそっと差し出したものと思う。」黒井千次 「他人の既成の家庭を覗き込むという形で書かれているために、語りのしなやかさと人物の主婦像とがくっきり浮かびあがり、三十八歳の女性の精神生活の姿が過不足なく出現した。」 「女主人公の精神的な自立と自足とが、どこまで確かであるかは必ずしも定かではない。しかしもし危機が訪れるとしても、それがいかなる土壌の上に発生するかを確認しておく作業も等閑には出来まい。その意味でも、この一編は貴重な試みであると感じた。」古井由吉 「今の世の神経の屈曲が行き着いたひとつの末のような、妙にやわらいだ表現の巧みさを見せた。」 「三年後に、これを読んだら、どうだろうか。前提からして受け容れられなくなっている、おそれもある。」 ぼくが、今回、この小説を読み直したのは、古井由吉の評を「書く、読む、生きる」(草思社)で見かけたからです。「三年後に、これを読んだら、どうだろうか。」 という問いに促されて、25年後に読みなおしました。ぼくには古井由吉がここで言っている「前提」の意味がよく分からないのですが、とりあえず、この作品が発表された1995年の今、ここ。この作品が描かれている時代の「生(なま)の社会」。あるいは、こういう会話をする30代後半の男女が存在しうる場だと考えてみると、それはもうないのかもしれません。 ぼくは、今から25年前に、同時代の同世代の登場人物を描いている作品として「リアル」に読みました。今、これを、当時のぼくと同じように「リアル」と感じる30代の読者がいるとは思いません。しかし、25年ぶりに読み直して思うのですが、この小説はそんなことを書いているのでしょうか。 「言葉が届かないところっていうのは『闇』なのよね。」 という真紀さんの言葉が指し示している『闇』のリアルは、果たして25年の歳月で古びたのでしょうか。 その真紀さんが、数年間の「主婦」の生活でたどり着いた「普遍的な母」の「識閾」の哀しさは古びたのでしょうか。 保坂和志は、その後、「ネコのいる世界」を描きながら言葉の届かない「闇」に言葉の触手を届けようとしつづけているように思いますが、それは、古井由吉が言葉の底にある「記憶」を「言葉」で紡ぎ続けているように見えた晩年の作品に、どこか共通すると感じるのは、読み損じでしょうか。 保坂和志は実に静かに、「新しい文学の可能性」を追い続けているのではないでしょうか。
2021.03.14
コメント(0)
全100件 (100件中 1-50件目)
-
-

- 経済
- 2024.9.3.財界オンライン:2024-09-03 元…
- (2024-11-12 00:09:27)
-
-
-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…
- duta89 link daftar terbaik dengan …
- (2024-09-11 01:49:11)
-
-
-

- お勧めの本
- 「モリスといっぱいのしんぱいごと」…
- (2024-11-20 19:20:09)
-








