2020年01月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-

晩秋の若草山の麓で鹿とたわむれ、聖武天皇の御陵へと
元号の「令和」は、奈良時代に大伴家持が編纂をした「万葉集(まんようしゅう)」から選ばれて注目をされたが、天皇や貴族、防人、庶民などと様々な人たちの歌は4500首にものぼると言うその中に「鹿」を題材にしたものは68首もあるそうだが、その多くは秋が深まる頃になってきて雄鹿の求愛で鳴く声が、織り込まれているそうだ百人一首に選ばれた猿丸太夫の有名な鹿の歌だが古今和歌集に詠み人知らずとされたものだったとか奥山に紅葉踏みわけ鳴く鹿の声聞く時ぞ秋は悲しきユーチューブに奈良公園の雄鹿の鳴き声があったんで載せておきます。↓ 確かに悲しげにも聞こえますさてさて奈良の正倉院展を見に、昨年11月14日に姉と出かけた日帰りバス旅行。興福寺を見学した後にやってきたのは「若草山」の麓です若草山(三笠山)は、真冬の山焼きでも有名ですが二月堂のお水取りともども見た事はないです。標高は342メートルで、山頂には鶯塚古墳がありますが登ったこともありません若草山の山頂からの夜景は、新日本三大夜景(他には山梨県笛吹川フルーツ公園と、北九州の皿倉山)が選ばれているそうだ。じゃ新のつかない三大夜景となると函館山、神戸摩耶山、長崎稲佐山だそうですさてさて、そんな若草山の麓にあるお食事処の「春日野」で少し早めのランチだ。今回の旅は午後の正倉院見学などにたっぷり時間がとってあるのも魅力的だ。人によっては春日大社とか参拝した人もいたみたい(入館後はフリータイム)ヘルシーそうなお食事を食べたら、お土産売り場でお買い物タイム。お店の前は若草山なのでのんびり眺めているのもいいだろうしというか、鹿もいっぱいいるし。集合時間までは飽きることなく時間をつぶせそうお店の中には入ってこないけど、かわいい白い斑点の残る鹿が水を飲んでいた。この白い斑点が鹿の子(かのこ)模様で、夏場のカモフラージュらしく、雄雌を問わず大人の鹿にも出るらしいここでも鹿のエサやりが観光客に大人気のようだこうゆう石垣があると鹿との距離感もあって良かったかも。私は前にバッグから出ていたガイドブックを鹿にかまれて、取り戻した経験がある。ご注意をこんな愛らしい目をして見上げられたら、そりゃ鹿せんべいを与えたくなるだろうな。でも横から体のでかい鹿に奪われたりもして・・・おじぎをしている鹿もいたし、赤信号で人と待ち青信号になったら、人と一緒に横断歩道を渡る鹿(偶然?)も見たしやっぱ、頭や方にも乗られるハトのエサやりの方がきついかなぁ~なんだかんだでバスに乗車する時間になったので次の見学場所へバスで移動。車窓からはポスト・カードのような光景やっぱ歩かずにピンポイントで見学場所に移動出来るのは、お年寄りには便利な観光手段だし時間的にもとても有効にまわれる。お昼過ぎに出かけた先は東大寺や、奈良の大仏を作った事でも有名な「聖武天皇(しょうむてんのう)」の御陵(ごりょう)である。正倉院は東大寺の蔵な訳だが、聖武天皇や、妃の光明皇后のゆかりの品々も収められている事からの参拝であろう奈良にはかなり来た事があるけど、ここまで来たのは初めてだ。トラピックス(阪急交通)さん、なかなか良いコースでした♪ 右の方に行けば光明皇后の御陵もあるが、流石に聖武天皇の御陵のみの参拝だ。聖武天皇だが、文武天皇(天武&持統系列)と藤原不比等の娘の宮子の間に生まれたが、幼くして父を亡くし、病弱だった事と外祖父である不比等の勢力が盤石になるのを待ち、中継ぎの女帝らを挟み24歳で即位をした天平年間は災害や、疫病(天然痘)が多発した為聖武天皇は仏教に深く帰依し、各地に国分寺建立や東大寺盧舎那仏像の造立の詔を出した。娘に譲位(孝謙天皇)して太上天皇となった。天平勝宝4(752)年に東大寺大仏の開眼法要。天平勝宝6(754)年には唐から鑑真が来日をして、皇后や天皇とともに手厚く出迎えたそうだ天平勝宝8(756)年に崩御し、聖武の七七忌(四十九日法要)に於いて、光明皇后は東大寺盧舎那仏に聖武遺愛の品を追善供養のため奉献その一部が正倉院に伝存しているのだ。今回の東京と奈良での正倉院展では聖武天皇の愛蔵品なども並ぶスペシャル版であった父の文武天皇(天武と持統女帝の孫)が亡くなり幼なかった首王子(聖武)が即位するまで中継ぎであった元明女帝(天武の娘、文武の母、聖武の祖母)や次の元正女帝(元明の娘、文武の姉、聖武の伯母)といった近しい人たちの天皇陵も近くにあるようだ最近になって愛子様のご誕生や、他の王室などで男女を問わず長子が王位を継ぐ傾向にある事から女帝論が出てきているが、そもそも日本において何人も女帝が存在し、その多くは彼女らのように次期後継男子が幼かったりでの中継ぎであるか藤原不比等の娘である光明皇后と、聖武天皇の娘の孝謙女帝や、二代将軍徳川秀忠の娘の東福門院和子と後水尾天皇の娘の明正女帝のように時の権力者である母親の実家の意向を受けての即位もあった。後桜町女帝(桜町天皇の娘)が、江戸中期に女帝にもなり女性天皇が認められなくなったのは最近の話だ女帝の特徴としてはもともとが天皇の妻であったか天皇の娘で生涯独身であったかという点で、女帝の他に、女系天皇(天皇の娘の血統が天皇を継ぐ)も議論をされている。まぁ私の生きているうちにどうこうなるものでもないのかな?そうこうしているうちに、東大寺の門前に戻ってきました。東大寺の近くの大きな駐車場でバスを降りて、今度は東大寺大仏殿の北側に建っている「正倉院」の見学です。そこまでは20分近くはかかるのかな?テレビで鹿せんべいを売るおばちゃんが怖いことを鹿たちは知っていると言っていたけど、店先のは厳重装備だというか、ほんとお店の中には鹿は入ってこないし。時間があればせんとくんと記念撮影がしたかったなぁ~奈良らしいガシャポン。外国人観光客や修学旅行生などにも人気だろう。息子とか修学旅行で、鹿のふん(チョコ菓子)を土産に買ってきて喜んで食べていたし土産物屋の前で鹿がそそうをすると、さっとお店の人が片付けてくれていた鹿もそそうをするので、観光客も気を付けるようにと、立て看板にイラスト入りで注意喚起がされていた。と言う訳で東大寺を横切り正倉院へと向かいます。日記は続きます~! ではでは 2019年11月14日に奈良市で撮影にほんブログ村
2020年01月29日
コメント(54)
-

前泊は名古屋。バスは西へと・・・久々の奈良の鹿
さてさて今回からは新シリーズ。とは言っても、昨年の「11月14日」に姉と出かけた、日帰りバス旅行の話をしたい。NHKのうたコンの収録録画の観覧が当たって、10月下旬に東京へ姉と出かけてそのついでに、上野の東京国立博物館で開催していた御即位記念特別展「正倉院の世界」を堪能したのは、このブログでも紹介をさせて貰ったけど、やはりここは毎秋に、奈良で行われている正倉院展にも行きたくなるというものだ独身の頃には毎年のように出かけていた正倉院展もここ最近はご無沙汰だったし何せ、こちらも御即位記念で普段は展示されないようなスペシャルな宝物を見る事が出来るというのだから行くしかないネットで検索をすると名古屋駅から1万円以下で、日帰りバスツアーも出ているので姉とそれで奈良へ正倉院展を見に行く事にしたのだが、いかんせん朝早い出発なので始発電車に乗車するのは、どちらも嫌なので名古屋駅近のビジネスホテルで前泊を決めたリニアモーターカー駅の着工も近い名古屋駅は再開発なども始まっておりいつもビルの工事が行われ、10年後にはどんな有様になっているんだろう名物のナナちゃんのいる場所も変わるかもしれないし姉とは夕刻に名古屋駅で合流する事にしていたが、せっかく名古屋に行くのだからと私の方は家の事も終えてから昼過ぎには一人で名古屋に出てきた前回の日記で紹介をした付近にある洋食家ロンシャンJR名古屋駅店で体に良さそうなランチをいただいたこんな、名古屋駅にはかわいいケーキを食べれるお店もあるけど写真だけで11月半ばだったので、名古屋駅周辺もクリスマスモードで駅前には、おっきなクリスマスツリーも真っ白なシックなクリスマスツリーも見物をして・・・夕刻に近づいたのでデパートで開催していた東北の物産展で山形のお蕎麦を食べる事にした。何でも庄司屋は創業150年の老舗らしい日本各地のそば処は、もともとは信州諸藩のお国替えで広がったようでして出羽山形へは伊那の高遠藩から保科氏出羽鶴岡には松代藩の酒井氏が入ったそうだ今回のバス旅行の前泊に使った名古屋駅近のホテルです。姉と泊まる場合に限らず禁煙ルームはお約束。しかもこのホテルは全室禁煙なのが有難いし更に大浴場が完備してあるのもポイントの一つだ。なかなかに小じゃれたお部屋でぐっすり眠る事が出来ましたよお部屋からの名古屋の眺めはこんな感じでした。前回の円頓時商店街にも近い立地ですといった訳で、名古屋駅から朝出発の団体バスに姉と揺られて、西へと向かいましてやってきたのは奈良で~す。久々です結構、好きで以前は何度も出かけてた場所なのですが、娘が都会が好きなので最近はご無沙汰です高台には、今までに2度泊まった事があるクラシカルな奈良ホテルも、車窓から見えましたそして池越しに興福寺の五重塔。今回の最初の訪問地は、この興福寺になりますご本尊である釈迦如来坐像(江戸期の再興)も安置され、寺の中心的な建物である中金堂はたびたびの火災で焼失し、江戸末期に小さめの仮堂が建てられ、現在の国宝館に収められている仏像はそこに安置されていたそうですがそれが老朽化も進んできたので、本来の創建当時の中金堂の姿に建て直すこととなり発掘調査などもした上で、2018年10月に落慶されたピッカピカのお堂だ内部は撮影不可だが、興福寺のご本尊の釈迦如来坐像(江戸期に再興)の他にも国宝の四天王像(南円堂にあった)とか薬王菩薩像と薬上菩薩像(重文)なども安置されていたさて興福寺についてウィキペディアでいつものように、聞きかじりしますね>興福寺(こうふくじ)は、奈良県奈良市>登大路町(のぼりおおじちょう)にある>南都六宗の一つ、法相宗大本山である>日本の仏教寺院。南都七大寺の一つに>数えられる>藤原氏の祖・藤原鎌足とその子息・藤原>不比等ゆかりの寺院で、藤原氏の氏寺で>あり、古代から中世にかけて強大な勢力を>誇った。南円堂は西国三十三所第9番札所で>ある。「古都奈良の文化財」の一部として>世界遺産に登録されている。>藤原鎌足夫人の鏡大王が夫の病気平癒を願い、>鎌足発願の釈迦三尊像を本尊として、天智天皇>8年(669年)に山背国山階(現・京都府京都市>山科区)で創建した山階寺(やましなでら)が>当寺の起源である。壬申の乱のあった天武天皇>元年(672年)、山階寺は藤原京に移り、地名の>高市郡厩坂をとって厩坂寺と称した。>和銅3年(710年)の平城京への遷都に際し、>鎌足の子不比等は厩坂寺を平城京左京の現在地に>移転し「興福寺」と名付けた。この710年が>実質的な興福寺の創建年と言える。中金堂の>建築は平城遷都後まもなく開始されたものと>見られる。>その後も、天皇や皇后、また藤原家によって>堂塔が建てられ、伽藍の整備が進められた。>不比等が没した養老4年(720年)には「造>興福寺仏殿司」という役所が設けられ、元来>藤原氏の私寺である興福寺の造営は国家の>手で進められるようになった。>慶応4年(1868年)に出された神仏分離令は、>全国に廃仏毀釈を引き起こし、春日社と一体の>信仰(神仏習合)が行われていた興福寺は>大きな打撃をこうむった。一時は廃寺同然と>なり、五重塔、三重塔さえ売りに出る始末>だった。>五重塔は250円(値段には諸説ある)で>買い手がつき、買主は塔自体は燃やして>金目の金具類だけを取り出そうとしたが>延焼を心配する近隣住民の反対で火を>付けるのは取りやめになったというバーミヤン遺跡の大仏がダイナマイトで破壊をされる映像はショッキングだったが明治の廃仏毀釈においても、日本の貴重な文化財がかなり破壊をされている。そしてお城もね・・・・(泣)中金堂に入場してからは、集合時間までフリータイムだったので、せっかくだからと、別料金の東金堂や国宝館に並ぶ数々の仏さまも拝見をしてきた。阿修羅王像も♪奈良と言えば東大寺の大仏と、鹿だがウィキペディアによると、その由来は>7世紀後半から8世紀後半にかけて編纂>された『万葉集』では奈良の鹿の歌が>詠まれ、このころは純粋に野生の鹿>だった>同時期の767年には春日大社が創建され、>その由来で主神の建御雷命が鹿島神宮から>遷る際に白鹿に乗ってきたとされ、神鹿>(しんろく)と尊ばれるようになる。氏社>参詣の藤原氏からも崇拝の対象となり、>人間が鹿に出会うと神の使いとして輿から>降りて挨拶した。>やがて神仏習合で事実上の大和国守護だった>興福寺からも神鹿として厳重に保護され、>傷つけた場合は処罰処刑や連座追放の対象と>なる。しかし、住民とのトラブルが多く、>(中略)共存が困難で様々の事件が起きた>半割の木の丸い方を道路に向けた鹿に害を>与えない奈良格子など町屋の様式にも影響>している。こういった事情から、人に害を与えないよう「鹿の角伐り」も始まったそうだ。紆余曲折あったが、1957(昭和32)年に奈良市一円の鹿が、「奈良のシカ」として国の天然記念物に指定され、今ではマスコット的な存在として観光客や修学旅行生から可愛がられている奈良のいたるところにシカ、シカ、シカ奈良県庁は、東京オリンピックのメインスタジアムだった旧国立競技場の設計を行った片山光生の設計で建てられたそうで寺院伽藍の配置をイメージしたそうだそのすぐ横には、テレビでも話題になってた渋滞緩和を狙って45億円もかけ、乗り降り専用の新設のバスターミナルだけど、想定の半分以下の利用にとどまっているそうだ。バスターミナルで乗客を決まった時間に乗り降りさせるだけで、バスは遠くの専用駐車場まで行くのがネックのようだ。今回の団体バスは、興福寺拝観時は興福寺専用の昼食は昼食場所の、正倉院は東大寺のというように、それぞれの専用駐車場を使っていた仏さまに鹿の角とは!と、登場当時はクレームもついたせんとくんは、今も奈良県のマスコットとして活躍をしている。旅は続く! ではでは・・・・ 2019年11月14日に名古屋市と奈良市で撮影にほんブログ村
2020年01月27日
コメント(57)
-

尾張名古屋の街角に三英傑と、あの隠居。大山は鳥取県
前回の浜松に続いての、ハート♪です息子のアパートに、娘と泊まって浜松などに出かけたお正月明け。1月4日の朝は息子は会社へ。私と娘はバスで駅に出て東岡崎駅から名鉄電車で、名古屋駅へと出まして、「マカロニ」でモーニング・サービスを食べることにしまして私は小倉トースト。娘はエッグトーストやっぱ名古屋の朝は、こうじゃないとねそうこうしているうちにお店なども営業時間になりまして、普段だったらそちらに向かうところですが今日はちょっと名古屋の街歩きをしてみますか。名古屋駅から東にのびる地下街のユニモールを端まで歩いて地上に出ると、堀川が流れていた1610(慶長15)年、家康の命を受け福島正則が名古屋城築城の天下普請の為の資材を運搬する為、掘削をしたのが始まりとされているそのスグ西側には東海道の宮宿と、中山道の垂井宿を結んだ脇往還(脇街道)の美濃路があった。この道は古くからあり、関ヶ原の戦に勝利をした徳川家康が凱旋をした道で、「吉例街道」とも呼ばれており、将軍のご上洛や、朝鮮通信使琉球王使、お茶壺道中などが、この美濃路を利用していたという歴史を刻む道である堀川、美濃路ときて、そのお隣に位置していたのが「四間道(しけみち」だこの辺りは名古屋城築城にあたり清州から越してきた商人たちの街であったが元禄13(1700)年の大火で1600軒が焼失尾張4代当主の徳川吉通は、大火を防ぐ為堀川沿いの五条橋から、中橋までの道幅を四間(7メートル)に拡張し、道の東側は石垣の上に土蔵が奨励をされていた。娘と一緒にいたので今回は四間道を通ることは出来なかったと、いうのも今回のお散歩の目的は四間道ではなく、五条橋から西へと続く「円頓寺(えんどうじ)商店街」に出かけてみるという事だったので。名古屋駅から近い割に娘は一度も来た事がなかった(私は一度)日蓮宗の長久山円頓寺(えんどうじ)は徳川家とも所縁が深く、創建時には本堂などに名古屋城の天守の余材が使われたそうである。江戸の大火や名古屋空襲で焼失。戦後に再建がされたその円頓寺の門前町が今の円頓寺商店街になった。西の先はノリタケ、トヨタ紡織の工場などもあり、大変な賑わいだったのも名鉄堀川駅と市電の廃線で失われてしまったそれでも商店街の活性化のために、様々な試みもされ、こじゃれたお店も出来てきている。あいちトリエンナーレ2019ではここも会場の一つとなった名古屋弁のおみくじ、気になる~まだ正月休みをしている個人店などもあってのシャッター街なのか、寂しい状況だった昨日に続いて、ついついハートを探してしまう交差点の四つ角に、鉄砲を手に持つイケメンの信長様ちょい貧相なのは秀吉様。三英傑(名古屋にゆかりのある、天下を取った戦国大名)と言えば家康ですか。厳密には尾張じゃなく三河だけど、息子が御三家で尾張藩主だから名古屋にゆかり。別に歯が痛い訳でなく前回紹介をした、武田軍にこてんぱんにやられて、命からがら三方ヶ原から逃げ帰った時に、これを教訓にと絵に描かせた(しかみ像)で、尾張徳川家の名古屋にある徳川美術館に所蔵されたものだなむむっ。。。名古屋なのにご隠居が。まぁ物語的に旅の途中で、名古屋も立ち寄ったかもしれないが・・・・これ、7体を注文して(徳川吉宗も)納期的に無理だとかで四体になったそうなので、御三家つながりだと思うそれにしてもドラマの初代の黄門様によく似てるし。水戸も紀州和歌山にもまだ行ったことがない。そうそう驚いた事に、まだ行った事がないと思ってた鳥取県に行っていた事が、最近に判明団体バスで、岡山から松江に行く時に大山の真横を通過した事があったけどず~っと、島根県だと思っていたのが最近見たBSの大山の番組で鳥取県だと判明。バスで通過とはいえ鳥取県にも行っていたんだと言う訳で、あとは高知、香川、徳島と栃木、茨城、福島、宮城、山形、秋田岩手、青森の11県に行っていないのでなんとか踏破して行きたいものだ。廃校となった校舎が商業施設にリノベーションした「なごのキャンパス」散歩もそろそろ終了。名古屋駅前の大きなビル群が見えてきた。今度はそんな駅前のビルの上階へ展望室から名古屋の街を見下ろす。名古屋駅付近以外は、まだ高層階のビルは少ないが、栄なども高層ビルが建ったりするそうだ。リニア駅となる名古屋駅は更に変わるだろうこれって作ってるの? 壊してるの?屋上にショベルカー名古屋駅前には名古屋市制100周年の年に、モニュメント「飛翔」↑が設置をされたが、リニア駅に伴う再開発で別の場所に移設されるそうであるお昼には、サンマルコ近鉄名古屋店でカレーを食べる事にした。レーズンやナッツなど、好きなものをカレーにトッピングも出来ますサンマルコはヨーロピアンカレーとして大阪で創業し、今は東京から福岡までにチェーン展開をしている。大阪(9軒)の次に店舗数が多いのは、愛知(4軒)だ 2020年1月5日に名古屋で撮影にほんブログ村
2020年01月22日
コメント(60)
-
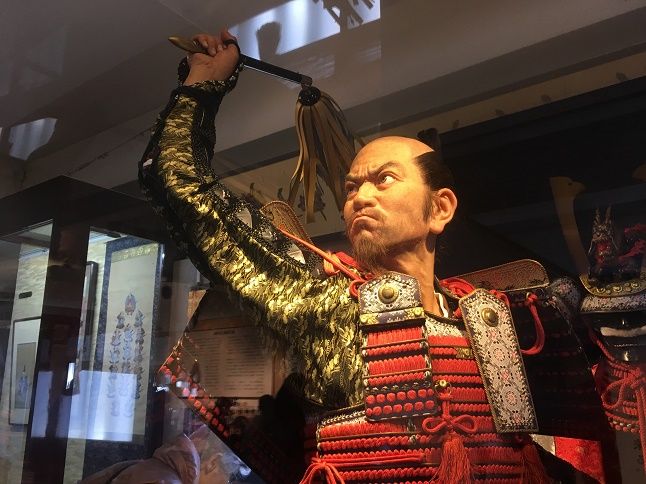
ハートにキュン♪した出世の城で、初春を祝う
愛らしいタイトルな割に、かなり濃い写真からスタートをします。前回から更新が開きましたが、娘と岡崎の息子のアパートに泊まった次の日に、二人で岡崎から電車で出かけた静岡県浜松市の旅の続きです。写真が多いので、前回とは別にまとめて紹介をするのは、見ての通り「浜松城」です浜松市にはゼロ戦を見に来たり、餃子を食べに来たり、砂丘に来たりと何度か来訪したのですがここ浜松城には今回が、初見参となります。浜松城と言えば、やっぱり家康ですよね。最初のワイルドな武将ですがやっぱ家康です。タヌキじじなイメージ強いのですが、こんな時期もあったんだろうなぁ~そういった意味からも英傑が、まだ天下に名をとどろかす前の、普通に若かった頃を描いている今年の大河「麒麟がくる」は楽しみでもありますそれにしてもマムシの道三がイケメン信長みたいだし松永弾正は、ちょい悪オヤジだし(笑)鉄砲から道三推しの、彼の畳み込むようなスピーチには圧倒されました急遽の濃姫は、勝気な姫ぶりが道三の娘っぽくて良かったです日曜のお昼過ぎには、浜松城で彼らに出会えるみたい。それにしても直虎から、トラの耳と尾浜松のピアノの袴と、みかんの紋ドジョウのちょんまげな家康とは三方ヶ原(浜松市)の戦いとは、家康と信長の連合軍が、信玄に挑んだものだが家康軍は大敗。有力な武将も討ち死にし家康自身も命からがら、浜松城に敗走をしたそうだ逃げ帰った家康が、鎧を掛けたというそんな松が今も残っているかと思えば流石に、三代目の樹であるらしい家康が浜松城にいたのは29才から45才だそうで、天下取りへの足掛かりにも繋がる重要な城でもあった無論、戦国期の城である為、攻め込まれた時の防御なども考えられていたようだ結構、今どきの庭石を使ったような綺麗な石垣であるが、当時のものであるようだこの城を見て、やっぱ石垣が一番印象に残ったし天守が見えてきた。ここで浜松城の概要をウィキペディアでを丸写しで説明をさせていただくと・・・・>浜松城の前身は15世紀頃に築城された>曳馬城であり、築城時の城主は不明で>ある。16世紀前半には今川氏支配下の>飯尾氏が城主を務めていた。この頃の>引馬城は、江戸時代の絵図にみられる>「古城」と表記された部分であり、>現在の元城町東照宮付近にあたる。>徳川家康が元亀元年(1570年)に曳馬城に>入城し、浜松城へと改称。城域の拡張や>改修を行い、城下町の形成を進めた。徳川>家康在城時における浜松城の具体像は>不明確であるが、古文書や出土遺物から>現在の本丸に向けて城域が拡張された>ことが窺える。>また、徳川家康が築造した浜松城は、土造りの>城であり、石垣や瓦葺建物を備えていなかったと>される。拡張・改修は天正10年(1582年)ごろに>大体終わったが、その4年後の天正14年(1586年)>家康は浜松から駿府に本拠を移した。家康の在城>期間は29歳から45歳までの17年になる。>慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦い以後、>江戸時代を通じて徳川家譜代大名の居城と>なり、浜松城から豊臣色は失われる。江戸>時代の浜松城主は九家二十二代に引き継が>れていき、歴代の城主によって城域の改変・>改修が進められた。>堀尾氏在城期に創建された天守は、17世紀の>うちに姿を消し、天守台のみが現在に伝わる。>以降、天守門が浜松城の最高所に位置する>建造物といえ、江戸時代を通して浜松城を>代表する建物であったことが窺える。>明治6年(1873年)の廃城令により、浜松>城の建物や土地の払い下げが行われ、三の丸、>二の丸の宅地化が進行した。天守曲輪と本丸の>一部は大きな開発を免れ、昭和25年(1950年)の>浜松城公園開設に至るではでは城内へ。といっても陳列品が並んでいるタイプなので、展示室とか撮影禁止でした。天守の地下には井戸籠城では水は大変に大事でしょうね天守台よりも少し高いところがありここには八幡台といって、城を守る神社があったそうだ二の丸御殿跡や、三の丸御殿跡などの発掘調査が行われているそうで、江戸時代の絵図にもない、家康時代以前の引間城時代の堀も見つかったようだ天守からは東方向に富士山(向かって左側)も見ることが出来たこのリアルな家康の像は、撮影がOKだったので。戦国も前半の今回の大河では家康はまだ若造なんで、風間俊介さんが演じます。(検索中) えっ?彼ってジャニーズだったんだ。知らなかった~徳川家康の天下取りの足掛かりになった浜松城は、その後の歴代城主も後には幕府の要職に就くことが多いので、別名「出世城」とも呼ばれているそうだし↑最近は、石垣でも人気を集めているわかります?ハートの石がちょこんと乗ってますよね。自然石を使う野面(のづら)積みだからこそ、こんな石もあるのかもしれませんこちらの石垣にもありますが、わかりますか? なんだかどれもがハートに見えてもきますが大きなハートの上に、小さなハートがちょこんと寄り添った、夫婦ハートと呼ばれる石です浜松城主時代の壮年期を思わせる徳川家康像。手に持っているのは「勝草」という名のシダだそうです今年の初旅行が徳川家康がテーマというのも、何だかめでたそう頭の上でガサゴソと音がするので見上げたら、大きなリスがお花を食べていた(右上)駅に戻る途中にもハート。なんだかハート探しがクセになりそう。昨年の上海に続き、今冬は北京にでも行こうかと、最終候補に入っていたが国内の別観光地にしたので時期的に助かりました。過去にサーズが流行した時、コカ・コーラの懸賞でペアでベトナム旅行が当たって、国内どこでも好きな旅先へという事になり、湯布院や黒川、別府などに姉と出かけた事があり姉はその方が良かったと喜んでいました 2020年1月4日に浜松城で撮影にほんブログ村
2020年01月21日
コメント(50)
-

福袋に十日市。半額オンパレードな初春に入浴剤詰め放題
お正月の初売りのデパートの福袋は高価なものが多く買った事はないが地元のスーパーでも、購入が出来る全国チェーンや食品メーカーの福袋は手頃なので、私もよく購入をしている人気のスターバックスや無印良品などは事前にネットで申し込み、当選した人が福袋を購入出来たり、店頭販売のものも短時間で売り切れてしまったりで、このミスタードーナツのポケモンとコラボの福袋も大人気早速、販売日に出かけ3000円の福袋を購入してきた。ポケモンのひざ掛けや手帳カレンダー、エコバック、ファイル、テープの他に、ドーナツ30個分のプリペイドカード(6月末までに利用)~160円(税抜)のドーナツが30個となると、最大で5000円弱のドーナツが3000円で買える事、自体がお得だし↑そして、お次に紹介をするのは日清のチキンラーメンのひよこちゃんの福袋だもはや袋すらかわいい。1000円で日清の袋めんや、カップラーメン、ひよこちゃんのぬいぐるみがついてくる。これも人気ですぐ売り切れていた雑巾代わりに、普段から利用をしているユニ・チャームの山ほどのシルコットの除菌シートやマスクのセットも、これはもう買うしかない!という感じで。殆ど1000円ポッキリの福袋が多かったがコーヒー系などは1500円のもあったデカフェにこだわる娘がいるので、このごぼう茶や、ルイボス茶、シナモン茶のセットもありがたい。これらの福袋だがどれも年末のスーパーで買ったものです最近は年前に販売をしているので要注意お正月には売り切れいてるものも。千円飲料系の福袋は、先ほどのデカフェのセットとこのお湯を注ぐだけのもの&娘の好きな菓子セットだけだったが、事前応募で当たった人だけが購入ができるスターバックスの福袋の内容が、今年のは私好みだったし応募しとけばよかった。次はチャレンジしようかな。千円かたや昨年(3年前も)購入したタリーズの福袋は一番安いタイプのが、3000円から3500円に値上げしたので断念。昨日は前々から購入をしたかった、お得な1万円タイプのものに初めて遭遇、購入をしようか迷ったけど今回はパス。やっぱ1万円は・・・そして今年のおせちです。うちの地域では大晦日の31日の夜に食べます。テレビで北海道や東北も31日におせちを食べると言ってましたが、旧暦では日の入りをした夜は新しい日(次の日)と考えられていたので、一年の初めの食事は31日夜だったからだそうです31日の午後には、三食98円になってたお蕎麦も、おせちを使って正月らしくなりました。とりあえず紅白、ゆく年くる年を見て、午前0時に地元の神社に参拝をして1時くらいには就寝。翌朝には娘と二人で家を出かけて、元日営業のマクドナルドへ例年は遅くまで売られているマクドナルドの福袋も、年末に内容が公開されて、ネットでみんなが買いたい!と、人気を集めてました3000円ですが、バーガーや様々な商品券だけで3270円分あります(6月末までに利用)おまけグッズのポテトの形をしたタイマーはティロリティロリ♪とポテトが出来た時の音だそうで大人気。更に10袋に1袋の割合で500円の商品券が入っていたが、うちは×毎年買うのがサーティワンアイスクリームの福袋で、2000円だが500円の券が4枚あって元が取れる。しかも利用期限がなくてお釣りも出るギフト券なので使用がしやすく財布にいつも1枚入れている寝具の西川の5千円のまくらに、980円のまくらカバーが付いて3000円というのは娘が購入。写真を撮り忘れたが娘は半額処分の羽毛布団19800円も購入してご満悦だここからの福袋は、お手頃な1000円ポッキリ。普段使いの実用的なものばかりなので有難い。ここの味噌や鍋の素もよく利用をしているバスクリンも1つあたり250円で購入が出来ると思うと、これも買うしかないです息子の家に行くときに、これやレモンティーラーメン、除菌シートなどもお土産に少し持って行きましたし。 千円様々な日用品がセットになったのもあってこれも無駄がない福袋だ。今年はいつになく福袋を購入したような気もするが、最近の福袋は中に何が入っているかがわかるのでどんなものがいくら入っているのか事前にわかるのが多いので失敗はないです。千円そして福袋以外にも、お正月のスーパーの売り場はお得なものがいっぱい。この三品どれもが100円の見切り品。しかも賞味期限が結構あるお歳暮や迎春ギフトも半額処分になっていてこの迎春用のお祝いの日本酒(一升瓶2本)定価は5000円だけど、半額価格で買えたこちらのお高めのお酒(720ミリリットル2本)も定価で4500円位のが、半額だし冬場のお晩酌は、日本酒がメインになるのでありがたい実家では1月2日の朝には自然薯をすりとろろ汁を食べるのだか、正月過ぎには自然薯も398円で売っていて、正月用の高級なお肉もお値打ち価格なのが、更に30%オフで購入、美味しいお肉でした最高級の5等級の飛騨牛の小間切れお肉も良い霜降りで、思ったより大きな肉で流石飛騨牛という感じ。これで数百円とは岐阜県に住んでいるからこそかもさて1月10日はテレビでは、兵庫県の西宮神社の福男のニュースをしているが中津川市に、明治期にその西宮神社から御分霊をした西宮神社があって、十日恵比寿が行われる今年は、9時前に舅と姑を整形外科に連れて行って、そこに置いてきてから参拝に出かけたので、いつもより早い時間だった為なのか、とても空いていた千円でお札を頂戴すると、くじを引けておまけの福箸を貰うだけのが、今年はお神酒が当たった。しかも娘の好きな恵那山だ和菓子屋の多い中津川市街、夏に娘とかき氷を食べた、御菓子所しんでもお店の前に、商品などを並べておりだるまの絵の入った、550円の開運迎福袋を購入した。えびす饅頭は先程の西宮神社の境内で500円で購入したものだ。和菓子の街は、やっぱこれがないと・・・えびす饅頭は、上品な味わいの酒饅頭でぺろっと1個、食べてしまった。しんの方はどら焼き、饅頭、かりんとう、金箔入りの昆布茶のセット。おみくじもあり吉だった西宮神社の近くに、かつては地元スーパーのチェーン店舗があったが、今はなくなってしまったが、十日市には同じ場所に出店をしていて日本ハムの焼き豚やハムなどの、ギフト解体品と思われるものが、どれでも5つ500円だったので、安すぎ♪と購入した商店街では、広告にあったくじ引き券でガラガラ~、今年も末等袋めんを貰った市街中心地は歩行者天国となり、様々な出店などもあり、暖かな日差しの中をてくてくしてから、スーパーで買い物して病院へ舅や、姑を迎えに行った十日市での収穫だが、まだまだ沢山あって国内産の干し芋というのが4袋で1000円だったので姑と半分こした。黒ニンニクも小ぶりだが500円で、かなりの量があって毎日、一粒ずつ食べているスーパーでは、お正月の福袋が売れ残り半額処分になっていたので、4袋合計で2000円ちょいで購入ができたオタフクの福袋は一番高くて1500円が半額の750円で、商品の他にもしっかりした生地のエプロンがおまけに入っていた1000円の福袋も500円。お釜にポンというのに、興味があっても買えなかったのでお試しにもよさそうだ去年も半額で購入できた浜乙女。これで500円はお得すぎる。無駄の全くないラインナップだ♪そして、スガキヤのスーちゃんタオルの入った福袋も400円以下になっており鍋の素や、みそ煮込みスープとか楽しみこれは13日、成人式の祝日に娘と出かけた時に、ピアゴに立ち寄って毎年恒例の小さな袋に入浴剤の詰め放題300円。チャックをちゃんとしめないといけない。家に戻ったらもう開いていた。これをやらないとお正月を迎えた気がしないです日記で確かめると3年前は小さめの入浴剤ばかりで25袋。昨年は色々タイプを揃え17袋。今年は18袋だった。まっ少しはお得だろうし(イオンはよりどり〇〇円の店舗ばかりだったんで残念だった)更に、タイムセールにちょうど居合わせてギフト品の割引がされ、↑4000円のと↓3000円の二箱の合計で、2200円程で購入ができた。消費期限も春から夏と長めなので有難い最後に。殆どの福袋が、税込みのポッキリ価格ですが、一部のものは税抜きでしたが面倒なので表示を略させていただきました外食もですが、内税と外税で色々あるので料金がわかりにくいです 昨年末から2020年1月13日に地元で撮影にほんブログ村
2020年01月14日
コメント(73)
-

冬に桜が咲く道を三河へと。そして浜松餃子
1月ですが桜です。大晦日に帰省してた息子が1月3日に、転勤先の岡崎に帰るというので、その車に娘と同乗をして今年初めての行楽先は三河です。下道を岐阜県瑞浪市から、愛知県豊田市へとその途中の豊田市小原地区の道沿いには小原四季桜が今も咲いてました。この桜は春と秋の二度咲くそうでして、前にセントレアに行く途中にも冬の時期に桜を見たのですが、その時もピークは少し過ぎてましたピークは11月半ばで、紅葉とのコラボなども楽しめるようです。豊田の市街地に出てきました。中津川ではいらっしゃいをおいでんさいと言うが、三河弁はおいでんというらしいイオンスタイル豊田に行くと、来店者にねずみの絵の描いてあるどら焼きを一つずつ配っていたので、三人で一つずつ朝食はタリーズで。入り口でコーヒーの試飲もあったので、そちらもミニカップで貰った。お正月らしい店内を一通りまわり今度はイオンモール岡崎へ息子の車に乗せて行ってもらって、ここからはバスでも息子のアパートに行けるので、息子を解放。娘と二人でイオンモール岡崎をうろつくお昼ご飯はフードコートで、京都北白川ラーメン魁力屋でラーメンを食べました夕刻にイオンモールから路線バスで東岡崎駅へ。ここで路線バスの乗り換えが必要なのだが東岡崎駅に、新しいショッピングスポット「オト・リバーサイド・テラス」が出来たばかりだと娘がいうので立ち寄ってみたどこで、そんな情報を得たんだろ。正月でまだお休みのお店なども。パンケーキのお店が繁盛してたが、ラーメンも食べたし今日はパステラスにはどど~んと、徳川将軍初代の徳川家康の騎馬像が。岡崎は徳川家康の生誕地である。岐阜県可児市の彫刻家で日本芸術院会員の彫刻家神戸峰男さんが制作したものだそうだこの奥に家康の生まれた岡崎城があるせっかくだから、夕刻の岡崎城下を散歩してみた新しく橋を架けていた。桜城橋(さくらのしろばし)といい、「乙川リバーフロント地区整備計画」の目玉施策だそうだこちらは西の方を流れる矢作川にかかる矢作橋で、日吉丸(秀吉)が蜂須賀小六に出会ったという橋で、かつては東海道。今は国道1号線の橋である夕刻の岡崎をてくてく歩いて、岡崎シビコの食品売り場で特売品を買い込んでから、路線バスで息子のアパートで、簡単な食事を作り次の朝は娘と二人で、JRを利用して浜松まで、餃子を食べに行こうという話となったJR岡崎駅前には、若き日の松平元康(徳川家康)像。最近、テレビで母親と引き離され、人質生活を長く続け、父を早くに失った苦労続きの少年期をやっていたがこちら静岡県浜松市は青年期の29歳から45歳までの17年を過ごした城下であるJRの駅ビルメイワンの奥には地上45階建最高部の塔屋上ヘリポートの高さ、212.77メートルの超高層ビル、浜松アクトタワー駅ビルメイワンの最上階にあるのが本屋に併設された「エクセルシオールカフェ浜松メイワン店」で本を3冊、持ち込めるので景色を眺め1時間ものんびりしてしまったエクセルシオールカフェはドトールコーヒーよりもちょっぴり高級路線な、イタリアンエスプレッソを中心とした系列店だ今回は餃子を二店舗は食べたいと思っていたので、ランチ営業が始まったばかりの「初代しげ」へ。ここは浜松餃子まつりのG1餃王座グランプリにも輝いた実績がある他にも食べたいので、一人前を頼んで半分こフードコートなので、こうゆうこともできるビールは娘がぐびぐび飲んだ餃子の町として、その消費量を宇都宮とトップ争いを繰り広げている浜松餃子は肉の使用量が多く、ジューシーで使われる野菜は白菜よりもキャベツがメイン、玉ねぎを刻んで入れる店も。餃子を円形に並べ、中央にはもやしをのせるお腹も一杯になったので、地元の小さな神社に次いで参拝に来たのは、五社神社諏訪神社。五社神社は、太玉命、武雷命斎主命、天児屋根命、姫大神の五柱の神を主祭神とし家康が浜松城主時代、三男の長松(後の徳川秀忠)が誕生すると、当社を産土神とし現在地に社殿を建立した。家光の命により諏訪神社は、五社神社の隣に社殿が造営され遷座をしたが、共に浜松空襲で全焼した国学者の賀茂真渕が幼少の頃、師と仰いだ五社神社の神主である森暉昌の功績を記した顕彰碑東海道五十三次の江戸から数えて、29番目京から数えて、25番目にあたる浜松宿は東海道最大規模の宿場で、本陣が6軒あり旅籠も94軒もあったそうだネットで浜松のスターバックスがおしゃれだと娘が見つけて、立ち寄ることにした。「浜松城公園店」といいまして、名のごとく直前には浜松城に出かけたんですが、次回の日記で紹介します娘がスターバックスの会員になっているのでコーヒーのおかわりを100円(税抜き)で一緒に購入できるので、二人の場合はいつもこうしている。(会員外のおかわりは税抜き150円)ここ最近はちょっとな~という感じだった抽選で当選しないと購入ができないスターバックスの福袋、今年はなかなか良かったみたいで、だったら抽選に申し込んでたら良かった。来年は応募してみようかなタミヤやバンダイなどの国内プラモメーカーの大半が静岡県に生産拠点があるそうだが、昔家康が腕利きの宮大工や彫刻士師を、駿府に集めたことから木造模型が盛んになったとかかつてはテレビチャンピオンでも名をはせたプロモデラーの山田卓司さんは、浜松出身だそうで、その作品が展示されていた静岡県磐田市のイメージキャラクターの悉平太郎(しっぺいたろう)をモデルにした「しっぺい」君。怪物退治のために信州駒ケ根からやってきたワンコだ「浜松魅力発信館ザ・ゲート・ハママツ」は 遠州鉄道高架下に設置されており、つい最近まで、いだてんの展示がされていたそうだ後半の主人公である田畑政治は、浜松の出身だったそうだ。↑もはや家康ではなく田畑に見えてくる。そして女城主の井伊直虎もまた浜松北部だし「ガヴリールドロップアウト」というアニメの聖地が浜松らしいが、「苺ましまろ」「干物妹!うまるちゃんR」「クラシカロイド」といったアニメも浜松が舞台らしいこの人が何者かわからないけど、繁華街で絵馬が沢山あった浜松と言えばさわやかハンバーグ。駅前のお店の前は通ったが、今回は餃子を食べに来たのでパス。静岡おでんとか、マグロや日本茶、メロンなどと静岡県には美味しいものがいっぱいなのだけど午後も遅くなったので、浜松を離れる前にもう一軒の餃子店に出かけた。このお店は以前に、ドライブで立ち寄った事があるが今回は、居酒屋的な「浜太郎」駅前店へと言うのも、夕方のハッピーアワーにはレモンサワーとハイボールが、何杯でも99円になるというので、もはや餃子より酒が目当てな娘であった無論、お酒のあてに餃子も頼む。ここも浜松餃子まつりで、餃王座グランプリを受賞 している。美味しいのでガンガン食べれるしマツコの知らない世界の餃子激戦区で迷ったらここで食べろ!のコーナーで紹介もされた赤餃子と、黒餃子も食べてみた。完食~!と言うわけで、ハートな浜松編へ続きます 2020年1月3、4日に三河&浜松で撮影にほんブログ村
2020年01月08日
コメント(65)
-

艶やかな時代絵巻を、晩秋の馬籠宿で和宮御降嫁行列
正月(むつき)立つ 春の初めにかくしつつ 相(あひ)し笑(ゑ)みてば 時じけめやも令和の出典ともなった万葉集にある、大伴家持が天平勝宝2年(750)年に、宴で詠んだ歌ですその意は、お正月の春の初めなのだからこのように、皆で笑いあえるのは楽しいものですね。との事で、令和2年のスタートです。今年もよろしくお願い致します!今年最初の日記は、前回に続き地元の馬籠からご紹介します。昨年11月3日に開催をされた和宮降嫁行列です。皆さん、知ってらっしゃいますよね。幕末の孝明天皇の異母妹で仁孝天皇の第八皇女であった和宮親子内親王ですが公武合体(朝廷の権威と、幕府を結びつけて幕藩体制の再編強化を図る)の懸け橋として江戸幕府第14代将軍である徳川家茂の正室(御台所)になるべく、中山道をご降嫁されたという行列を再現したものです既に和宮には有栖川宮 熾仁親王という許嫁がいたのを反故にされて、東国に下ったのですが、皮肉な事に王政復古後の新政府によって、有栖川宮は東征大総督に任命されて東征に際しては、明治天皇から錦旗と節刀(天皇が出征する将軍や遣唐使の大使に持たせた任命の印である刀)を預かり、京都を出立し江戸開城を成し遂げたのであるさて和宮降嫁行列には、地元の有志や中津川の中京学院大学や、名古屋外国語大学の学生さんたちが当時の装束に身を包み、馬籠宿を下から上へ(東国へ)と練り歩いた和宮は、16才で降嫁をされたそうだがこの行列では、地元の中学3年生の女の子が和宮をやっているので、年齢的にもぴったり。こんな少女が、知らぬ世界に飛び込んでいくのは、さぞかし心細かった事だろうお付きの女官たち。中津川の中山道歴史資料館には、降嫁行列で和宮のお世話をした家に、礼の品物などが贈られたとして展示がされている文久元年10月20日に京都を出立した降嫁行列は京都方が一万人、江戸方が一万五千人京都からの通し人足が四千人というもので、その長さは50キロにも及んだそうである行列の先頭が通過してから、最後尾が通過し終わるまで4日間もかかったそうだ。和宮を奪還すべく過激な攘夷派が行列を襲撃するという噂があり、御輿の警護に12藩、沿道の警護に29藩を動員し、幕府の威信をかけての大行列となったのだ馬籠宿では行列の為に、街道沿いの石垣を2尺引っ込めて、道幅を2間(約3.6m)に拡幅する工事がされたそうだ迎える宿場、街道でも様々な約束事もあり伝馬役以外は一切の外出禁止前後3日間の遊興と売り物禁止女は姿を見せないこと通行を上から見下ろしてはいけない正座して迎えること看板を取り外し、2階の雨戸は閉めること寺の鐘などの鳴り物を鳴らしてはいけない犬猫・牛馬は、鳴き声が聞こえないよう遠くに繋いでおくことその降嫁の道中に、和宮が歌ったのが 落ちて行く身と知りながら、もみぢ葉の 人なつかしくこがれこそすれこのような経緯があったにも関わらず和宮と同じ年の若き将軍、家茂とは仲睦まじい夫婦であったそうだが、僅か4年後に、家茂は脚気衝心のため亡くなってしまうそんな中山道には欠かせない和宮ですが私が知ったのは、替え玉説の有吉佐和子「和宮様御留」の大ヒットからです。中学くらいでした。私にとって中山道を旅したといえば、西行法師で、その次は新選組といったところでした今回の御降嫁行列は100名程のもので地元有志や、大学生が美しい装束を身にまとって、再現をしているものだけど皆さん、なかなかお似合いですよね宿場の中ほどの藤村堂記念館で、お昼の休憩の前には、しばし写真撮影タイムちょっぴり現代人の表情にも、戻ります和宮を中心にハイ、ポーズ和宮そっちのけでハイ、ポーズ扇子使いも様になり現代人にまじっての休憩タイムお侍が小さく樹の奥に。この写真なかなか好きです。タイムスリップしたみたいさてさて、後半戦のスタートです幅が広くて、ここって奥まで行列が綺麗に観れて、なかなか良いですね歩くより、正座して輿に揺れるというのも大変そうな気もしますさてさて前回の燈籠やライトアップの準備もですが、今回の時代絵巻にも地域役員の旦那は参加をしておりますハリボテですが刀も持てて喜んでました図柄を決めるのも面倒なので、うちの今年の年賀状は、この行列での旦那の時代装束姿です。まっ、正月らしくていいんじゃないかとこれはないなと思った、くしゃくしゃの宝くじマークご祝儀も募ってました子供たちは後半だけ、行列に参加をしてました馬籠は左右に並行して脇道(車道)もありそれを使ったりして、行列の先回りも出来ます。このあたりまで来ると見物客も随分少なく、見やすいです緑も多くて、下の方より良い写真が撮れるかも今回は旦那も出るので、気合を入れてあちこちで、写真を撮りまくったので行くところ、行くところにお前がいるから恥ずかしいと旦那に言われましたが次は、上の方と展望台だけでいいな。あっ旦那の写真はたくさんあるけど、ここでは特に紹介しませんいよいよ行列も終盤。陣場の急坂ですキツイ勾配で、普通に歩いていてもふ~ふ~言います(ここと、最初の大きな水車のところ)草鞋なんでしょうね。歩き心地はどうなんだろうキツくても、顔には出しません宮様もあと、わずかゴールの展望台が見えてきました既に展望台にいた娘が、スマホで上から撮影した行列。私も次回は先に上に行っていようかな車の前を、御輿に揺られる和宮行列も無事に終え、表情が明るい和宮その背後には恵那山もよく見えます令和の世になっての、幕末の時代絵巻楽しませてもらいました。皆さんお疲れさまでした♪という事で、皆様。今年もよろしくお願いします 2019年11月3日に中津川市馬籠宿で撮影にほんブログ村
2020年01月01日
コメント(73)
全7件 (7件中 1-7件目)
1










