2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年12月の記事
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-
読売新聞 東北ベースボール賛歌 より
昨日の続きです。やる気があんのか、ないのかわからないわがチーム。やる気のあるやつが一生懸命がんばっている中、もっともっとがんばらなければいけない彼らは何をしているのだろう。チームの底上げもままならないわがチーム。それでも一歩ずつやっていくしかありません。東北版の読売新聞の土曜の特集。「東北ベースボール賛歌」。実は先週の土曜日で最終回でした。こんないい企画が終わってしまうのは残念です。最終回は、山形の天童エンジェルスという2001年に結成された少年野球(硬式)クラブチームの総監督、五十嵐晋さん(47)。中学の先生の肩書きを持ちながら、クラブチームの総監督。小5から中3まで、部活動との両立を認め、楽しんでやることを最大のモットーとし、「やりたい時にこればいい」という姿勢で、出入りは自由。勝利至上主義の対角線上にあるチーム。このチームを率いて、7年の指導で地区大会優勝5回、東北大会出場2回、全国大会出場1回の実績を残す。チームにバントのサインもない。背番号も希望制。なんと自由で洒脱な雰囲気のチームだろう。こころからのenjoy baseball強豪高校でプレーする高校生は、このチームのいるリーグから巣立つことが多くなったそうだ。そして、高校を卒業したOBも地元にもどり、指導者となる。OBには、横浜の加藤武治、広島の栗原健太もいる。なおも監督は、「これからどんどん出て行くでしょう。」ともいっている。そして舞台は世界へ。山形県選抜チームが国際大会に出場したのを機会にエンジェルスは日本代表としてキューバで開催された国際大会に参加もした。どんどん世界はひろがっていき、子供たちの夢も広がっていく素晴らしい環境。そんなエンジェルスに、最近女子のソフトボールあがりの選手が入団したそうだ。五十嵐監督はいう。「好きなら誰でもいい。思い切り投げて、思い切り打ってもらいたい。打撃は自分の力。守備は助け合い。野球は両方を兼ね備えた素晴らしいスポーツなんです。」このように締めくくっていた。こんな指導者がいる環境で育つ選手は幸せだと思う。選手の自主性にまかせる。選手を信じている。「来たいときにくればいい。」という、自己管理。そして試合さえも自主性で戦う。そのスタイルを終始貫いて、世界を目指す。私が目指す、太陽と北風の中にある「太陽スタイル」の徹底がここにあると思う。コートを脱がせるために、強風を吹きまくる北風ではなくて、あたたかい光で自らコートを脱がせるスタイル。彼ら野球少年、少女のハートに火をつける。自然とやる気になって、練習にも自らいくようになる。そこには絶対の信頼感がある。まず、指導者が信じなくては、彼ら選手はわれわれを信じてくれない。しかし、このスタイルで戦っていくには、かなり厳しいと思う。辛抱強く、待つことも指導の一環だと五十嵐監督はいっていると思う。そして、タイミングを逃さない丁寧なメンタル、フィジカルの両面からのケア。亡くなった仰木監督にもにた空気。その栄養をたっぷりと吸い込んだ選手たち。自主性はおそろしく育ち、どんどんうまくなっていく強力なエンジンが形成される。後輩の指導陣もそだつ。そのサイクルたるや、すばらしい。おもしろくないときもあるが、選手たちを手放しで信じてみること。これを来年の課題にしたいと思います。
2005.12.27
-
H17、最後の練習
平成17年、今日が最後の練習になりました。全員の参加を望みましたが、願いかなわず・・・最近この手の話題が多くなってしまう・・・みなで高みをめざそうとしている中、残念です。少数で戦う以上、強くなるには全員のレベルアップが条件だということをもっと意識する必要があります。親も子も。この選手をうまくしたいという気持ちはあるのに肝心なそいつがこない。連絡さえない。そんないい加減な気持ちなら勝ち負けにこだわらないレクリエーションでいい。この大雪の中、くそ寒い中、練習に参加する君らの意気込みに正直、私は救われます。私だって寒い。そこにきて人数がすくないとダメージが大きいです。彼らにありがとうといいたいです。そして、そこまで一生懸命野球をやりたいという気持ちに、いまいちさせられない練習に来ない子。自分の無力さを感じますが、そうもいってられない。そいつらをどうやって、来させるか。練習に参加させるか?自分たちからいきたいと思わせるようにできるか?やる気がないなら、やめろ!ということは簡単。でもかえはいませんし、このメンバーでやっていくしかない。それに練習にきたら、きたで一生懸命にやる子めらなんです。電話をかけたり、首根っこをつかんで、無理やり練習させることはできます。でも、根本的な改善にはならない。自らのやる気を育てる。ゲームの楽しさや、寒さにかつ「やる気」。それしかないと思います。やる気を支える一番のもの。enjoy baseballでしょう。それには保護者のフォローは必須ですね。年の最後の練習。新たなる決意とともに終えました。これについて、考えていたら、読売新聞の面白い記事を発見しました。それについては、明日書くことにします。
2005.12.26
-
初雪大和
大雪の会津。朝から、トラクターにのって雪かたしです。といってもおやじがですが・・・私は、運転できません・・・去年の11月にうまれた大和。一冬経験しているとはいえ、自らの足で雪を踏みしめるのは初めて。完全防備をさせて、庭にほっぽりだしました。びびり、はいってます。スキーのインストラクターだったおやじは、そのうちスキー場につれていくといって準備を始めています。1歳になったばかり。大丈夫なのか。おやじ(じいちゃん)。
2005.12.24
-
ソフトボールのシンクロ
明日から、また大型の寒波が会津を襲います。週末、大雪必死。暇をみてボードにきってきたいと思います。希望者の子めらとOBをつれて、磐梯山へ。足腰鍛えてきます。今日は、ソフトボールが20:00まで、中学生野球教室が21:00まで。家に帰ると、息子は寝ている。息子よ、一緒に練習やるのにはやく大きくなっとくれ!さて、ソフトボール。切れ目ない打線にするために導入を考えているもの。シンクロに挑戦しました。野球と違って、どこでピッチャーにシンクロをかけるか?今日、やってみたところ、やはり、ピッチャーの軸足が沈み込むところ。ここがシンクロどころだと私は思いました。野球と違うのはそこから、ウィンドミルだと腕が回転する。若干、シンクロのタイミングが早いようでした。待ちきれないこめらが続出。ただ、今日はかなり遅めの投球だったので、バンバン、ウィンドミルで速球を投げ込めは次第にあってくると思います。このシンクロ。なにがいいって、スウィングの始動のきっかけを与えてくれます。クンと踏むことによって、軸足にしっかり乗れる。乗れることで、体重移動ができる。力強いスウィングを生む。ピッチャーに対して、いつスウィングをはじめていいかわからなかった子、それがあいまいだった子めらには、効果覿面。バッキンバッキンあたります。自分のタイミングをもっていた子は調整しずらかったみたいですが。手塚さんの本の中で、シンクロはジャンケンと同じ、とありました。いきなりシンクロをかけるのではなくて、声にあわせる。「せーのーで、クン」そこでシンクロを仕掛ける。わけがわからずとも、タイミングがばっちり合った子めらはうれしそうでした。チームで野球がわかるこのところに集まって、ああでもないこうでもないと議論しています。指導者として、よしよし、いい傾向だ!と心の中で思います。「えー、なんで合うんだろう!」(タイミングが)合う。笑っちゃいます。そんな言葉すら、わからなかった子めら。いっちょまえなことをいっていますが、そんな彼にほくそえんでしまいます。そうだろうそうだろう、別に俺が考えたわけじゃないが、世の中いろんな方法がある。いろんなヒントがある。ただ、それはきっかけに過ぎず、それを自分の中に消化していかなきゃいけない。その楽しさがわかったなら、最強への第一歩。あとは自分で掘り下げる努力。彼らを野球天国地獄にひきづりこんでやろうと思います。
2005.12.21
-
元気のないやつら
練習いってきました。このくそ寒い中、よく40人もくるよなぁと思っていましたが、いまいち楽しくない。お通夜のように、静かです。前面にたって、俺が俺がといくやつがいない。さめています。違う中学同士、打ち解けるようなメニューを用意したらいいんじゃないかと具申する必要があるなと感じました。どうしても、ダッシュ系のメニューが多い。ただのダッシュ。立花流をとりいれたサーキットも提案してみます。今日は、素振りでした。体育館が狭いので、2班に分けての練習。片方は、素振り、もう片方は、ペッパーです。うまい振り方をする子もいますが、目に付くのは違和感のあるスイングの子。身長は172,3。私と同じくらい。やや細身ですが中1にしてはでかい。しかし、スウィング。ドアスイングで、体に似合わず、小さな軌道。野球をやってきていないスウィングでした。極端狭い外向きのスタンス。つったちスタンス。右バッターなのですが、軸足が回らず、上半身に頼るスウィング。振り切れていない。聞けば、大好きなコースは、外郭低め。速球には振り遅れる。そうでしょう、そこしか打てないスウィングですもの。スタンスを広めで、ひざに余裕をもって重心を低めに。ひとつのきっかけを与える意味で、前足をやや大げさに上げさせて、後ろ足にのっかる。そこから、スウィング。きれいに腰が回りました。まだぎこちない部分はありますが、ひとつきっかけをつかんでくれたようです。そんな子がごろごろ。きっかけを与えて、実際に打たしてやりたいなぁと思ってしまいます。守備も考えていかなくては。指導陣が二人では、隅々まで目が回らない。
2005.12.20
-
素振りVS実際に打つ
中学生の中心の野球教室。人数が多いことと、場所がせまいために、いまいち効率的な練習ができていないことに不満を感じます。せっかく、大雪の中保護者の送迎でくるのだから、すこしでも実り多くもってかえってほしい。そう思ってやっています。今秋からは打撃に入ります。こんどの練習は素振りの練習だそうです。でも私はちょっとまってよと思ってしまいました。せっかく人数もあつまっているのだから、生きている球を打ちましょうと新聞紙ボール打ちを提案しましたが、素振りのやり方もしらない連中もいるとのことで却下。スポ少では、私がやりたいと思ったことはできるのですが、コーチの立場になると、なかなかそれも難しいですね。裁量が限られてくる。疑問に思ったことはばんばんぶつけています。投げ方についても、意見が違う。シャドーピッチングのやり方。私はタオルの真ん中をもって投げるやり方でしたが、総監督は、タオルの端を結んで、結んでいないほうをもって投げる。総監督のやり方に反抗するわけにもいかず、一同統一。素振りもただ黙々と振るだけではなく、軸足だけで振るとか、いろんなアレンジを加えていきたいと思っていますが、大々的にやるわけにもいかず・・・延々素振りばかりでも面白くない。動くものを打つ感覚を忘れないようにも、新聞紙ボールうちはやったほうがいいと是は強く具申しようと思います。ひとりでもできる練習を、みんなで集まってやることはないと思うんです私は。方向性に微妙な誤差が出てきています。でも、やらないよりはぜんぜんまし。指導者同志の方向性をあわせつつ、効率のいい練習をしていこうと思っています。
2005.12.19
-
ママVSオトン 子供のなつきかた
ご無沙汰しております。大雪の会津です。吹雪です。マイナス7度です。前の記事のレス遅れております。書き込んでいただいた方すいません・・・レスは明日書くとして、とりあえず書きます。以前にも少し触れましたが、わが息子YAMATO。私と、嫁さんの中間において、どっちにくるかやってみても、ほぼ私のところにきます。最初は自慢していたのですが、最近は嫁さん、真剣に悩んでいるようです。私のなつくことが、面白くないし、自分になにか落ち度があるのかとがっかりしています。1年間の育児休暇を終え、職場に復帰。ここ一年間、息子と接する時間は私よりもはるかに長い。密度も濃いはずです。夜泣きしても、私が抱いてあやすとぴたりと泣き止む。嫁さんでは収まらない。私も最近心配になってきました。普通、母親だろうと。友人に聞いてみても、母親にべったりで、後追いしてたいへんだという話はききますが、息子はそれがない。正直、嫁さんはまじで落ち込んでいます。私が風呂に入れていましたが、嫁さんが入れるようにしたり、添い寝も私がしていましたが、嫁さんがやるようになり、息子の愛情をとりもどそうとやっきになっています。飲んで帰ってきたときなんかは、泣きが入るほどです。私もむずさく(かわいそうに)なってきてしまいます。なんでなんだろう?私が嫌われようとは思いませんが、嫌がる頭を押さえつけての歯磨きは私がやっています。そんなに気にする必要はないと思いますが、息子と接する時間を少しでも多くとり、父親とか母親とか、そんな区別はなくて、親子三人、そこにじい、ばあ、おおおばあ、おとうとの家族もふくめて愛情をかけていきたいと思います。別に誰が一番だっていいと思いますが、やっぱ「おかん」であってほしい。今日、「男たちのYAMATO」を見てきましたが、戦場で散っていった兵士たちの叫び、「おかあちゃーん」でしたもの。せめて、最初の言葉「ママ」であってほしいと思います。
2005.12.18
-
冬場の練習。練習に来ない子。
講演会にメモしたノートを職場においてきたので、今日はスポ少のことを書きます。さて、冬場の練習について。わがチームは、水、金は18:00-20:00まで、土曜は8:30-11:30まで練習をしています。ここ最近、会津は雪が積雪30-40センチ。今日は路面がつるつるでした。マイナス5度くらいかな。内股に力をいれて歩かないと、滑ります。そんな中の練習。最大のネックは、練習に行くまでに決心がつくかということ。くそ寒い日に、学校からいったん帰った小学生が、わざわざ寒い体育館まで練習にくるか?毎回毎回、そのモチベーションを持ち続けれる子は、稀です。1回休んじゃうと、休み癖がつく。休むとどんどんいきづらくなる。寒さで弱った決心を喚起するもの。それは、やはり保護者、家族の一言でしょう。「そんなに行きたくないなら、行かなくていい!」と逆切れする人もいるでしょう。私の親はそうでした。でも実は、そういうことで突き放してるといいつつ、ほっぽり投げているだけなんです。子供に任せているといいつつ、放任しているだけではないかと思います。子供は練習にきたらきたで、一生懸命にやるもの。問題は、どうやってその場に行くようにさせるか?そこが親としてもみせどろこだと思います。私も練習に来ない子に電話して、迎えにいったりしましたが、なんで俺がこんなことしなきゃいけないんだと思いましたが、チームのためには全体の底上げが必要。その子がうまくなってくれないことには、チーム力として上昇はない。グランドにたてないこの時期だからこそ、がんばれるこめらを育てていきたいと思いますが、練習の場にひっぱりださなくてはお話にならない。そういうやつがまたいるんです。人数が少ないので、見逃せません。練習にひっぱりだして、モチベーションをあげていって、自分から積極的に練習するように仕向ける。こういったフォローも指導者のつとめ。でもなぜか、やるせない気持ちになってしまいます。さて、また土曜日から練習。自ら来たくなるような練習メニューを考えなくては!
2005.12.15
-
スポーツジャーナリスト 神田 憲行氏のお話
昨日に引き続き、講演会についてです。講師二人目は、ジャーナリスト 神田 憲行氏。松坂 横浜VSPL学園の死闘を描いた「ドキュメント横浜vs.PL学園」などの著者です。講演会終了後の、交流会で同席に座りました。実は狙っていました。いろんな人に出会い、いろんな場面に遭遇するジャーナリスト。講演の神田さんのお話からするともっともっといろんな話を聞けるはずだと。私が東北、会津から来たことを知ると、できたばかりの本97敗、黒字。楽天イーグルスの一年をおもむろに取り出し、「差し上げます。」と。本を書いている人から、直接手渡しでもらったのはこれが初めてです。サインを!とお願いしたら、サインは書けませんと頭をかくようなしぐさ。マスコミ嫌いの野茂にも取材したことがあるそうです。気さくで、きどらない、確かな目と耳をもったジャーナリスト。これなら、野茂英雄もかぶとを脱ぐはずです。その講演の中の衝撃的な一言。野球だけでは、飯がくえない。世に野球人は数あれど、野球という分野のみで文章を書いて飯をくって、家族を養っている人はほんの一握りだという。野球選手よりも、なることが難しい職業なのではないかと私は思った。ただし、はじめるのは簡単。東急ハンズにいってフリーライターと書いた名刺をつくるだけで、誰でもなれるという。なることと、成功することはべつである。門戸はおそろしく広いが、成功するには針の穴をとおすほどの確率。収入にもかたよりも多く、専業でやってくには多くの苦労があるようだ。書きたいことは、10%。食うために90%。ジャーナリストとして、生計を立てるためには、野球のことばかり書くわけにはいかない。コンピュータ雑誌も書くし、ゴーストライターもする。なんでも書くので、自らを雑食といっていた。最近のテーマは、歌舞伎町のホスト界。まったく野球と関係ないように思えるが、そこには野球に通じるものがあるのではないかと私は思う。気持ちと行動力が前面にでてくる世界。愛憎もうずまく。裏切りや下克上。人の気持ちがむき出しになっている世界。そんな状況が神田さんをひきつけるのではないかと私は思った。いろんな場面に、自ら飛び込んで、それを多くの人に伝える。伝えるのは、感動であったり、偉業であったりするときもあれば、失敗であったり、挫折であったりもするかもしれない。野球という一分野にすぎないが、その面白さに魅せられた神田さん。自信の野球経験は、ほとんどないという。視点が野球人の視点ではないところから、野球を見れる。そして数多くの野球人と接しているために野球人の視点にもなれる。神田さんの書いた本。「97敗、黒字。楽天イーグルスの一年」。私はまだこの一冊しか読んでないが、そのほかの著作を読みたくなった。野球ジャーナリスト。そこへの道は、おそろしく険しい。
2005.12.14
-
横浜野球改革会議 慶応高校 上田監督のお話
まず、第一印象。飄々としているなぁと。この講演会、せっかく遠いところからきているのだ、私は少しでも講師の型のだす空気、オーラを感じようと一番前の席をだんどっていた。最初の講演は、現 慶応高校野球部 上田監督。春の選抜で慶応高校をベスト8まで導いたので、闘将らしきものを探してみたが、表面上からは見て取れない。野球の指導や、プレーに関する話はなかった。それでも、会場がぐいぐい引き込まれていく。話が面白いのだ。年齢を問わない非常に広い人脈。そして話の舞台は世界。正直、スケールの違いを感じたが、吸収できるところは吸収していこうと開き直れた。何の準備もないまま単身、アメリカにわたっていまはメジャーリーグのトレーナーを勤めるまでになった学生の話。野球、ベースボールの起源の話。これは面白かった。ご自身も一年間アメリカにコーチ留学をされだそうだ。野球、そのものを深く掘り下げている。大学でも教鞭をとっているとのことだった。たしか、日米野球構造比較論!?もちろん慶応大学でなのだろうが、大学にそんな授業があったら絶対にとっていただろう。やはり魅力的な先生がいるという点で、慶応はすごいと思ってしまった。話のトーン、スピード、相手の反応を見ての機転の切り替え、強弱=緩急。野球の技術に関してはほとんどといっていいほど触れなかったが、離し方や内容から、この監督とならば、野球の楽しさを追求したくなるだろうなぁと思った。ひきこまれずにはいられない。野球に限ったことではないと思う。高校の英語の先生であるから、野球部以外の生徒とも接する。その生徒達も巻き込んでしまう人間的な魅力がある。英語の授業も、絶対面白いと思う。上田監督の今回の位置づけは、兼業野球監督だと私は思う。野球を指導するのみで報酬を得る職業監督に対しての兼業監督。上田監督は、監督である前に高校教諭なのである。ここは、後に書くことになる竹内元羽黒高校監督とは違う立場になる。しぜん学校の仕事もあるので練習にいけない場合もある。そんなとき、指導者がいなくても生徒自らが練習をできるような意識をもっているとサラリとおっしゃっていた。選手の高い意識、高い理解力(ここが慶応か?)、行動力。それをはぐくむ指導者の魅力。これこそ ENJOY BASEBALL。強豪ひしめくなかで独自のカラーで燦然と輝く慶応高校。その強さを垣間見た。まだちょびっとしかみていないので、今後はじっくり見ていきたいと思います!上田監督、野球はどのように指導するのか?興味がわいてきました。
2005.12.13
-
12.11野球改革会議 講演会にいってきました。
12.11横浜 開港記念館で行われた野球改革会議の講演会にいってきました。最初に、この講演会の実現にあたって関係各位のご尽力に深く感謝いたします。ありがとうございました。まずは、感想から。ここにいかなければ、私はこんなにも大きな決意をもつことはできなかっただろうということ。よーし、やってやるぞー!慶応高校、上田監督、ジャーナリストの神田憲行さん、元羽黒高校監督の竹内さん、そしてSHIMA代表。山田さん、円谷さんなどの主催者側の立場の方。参加者としては大阪の芦田さんなどなど、多くの方々に出会うことができました。ものすごい影響力のある方々ばかり。ものすごい刺激を受けました。最初はスケールのでかさに自分のやっている地域、やっていることがちっぽけに見えて、すこしびびりましたが、話を聞いているうちに、末端には末端のたましいがある。吸収できるところは吸収していこうとかえって貪欲になりました。テーマは、「野球にかかわるお仕事」。三人の方が講演をなされたのですが、タイプにわけると、兼業高校野球監督、野球ジャーナリスト、職業高校野球監督に分けられたと思います。三者三様の立場から野球を語る。角度が違う分、野球の見え方に違いがあるなと思いましたが、三方に共通していること。人間的な魅力があるということ。人はそこにひきつけられる。そして、自らを過大評価しないし、過小評価もしない(ジョークでは使うが)。しかし、誰にも負けないぞという自負であったり、意思であったり、経験であったり、自信であったりするものが確かにあるなと思わせるものがある。自分のバックボーンがどこにあるかというものを持ちつつも、常に見直しをかけて、行動している。そりゃあ、聞いてる話も面白くなるはずである。その話は長くなり書ききれないし、まとまらないので、明日以降、おいおい書いていくことにします。一番うれしかったのは、生のSHIMA代表に会えたことです。電脳ブログだけのつながりだけでしたが、私は初めて会う気はしませんでした。しかし、会わないでつきあっていくのと、あのエネルギッシュで精悍さを生で体験できたのは、生身の人間として感じることができたのは大きなプラスです。SHIMA代表をはじめ多くの方々が、野球を愛し、いろんな行動をさまざまな地域で起こしている。ネットワーク化されています。そんな中。私は、会津から。SHIMA代表が走っている姿を想像しながら、私も野球改革の一翼を担っていきます。5年後、いやその前に、会津にお連れしたいと思います。野球改革会議、講演会は第2回、3回と継続するので今後もぜひ参加したいと思います。
2005.12.12
-
明日から横浜! 野球の講演会にいってきます!
明日から横浜野球の講演会にいってきます!ブログで交流をさせていただいている元甲子園球児のアマチュア野球革命!DREAM CHAMPLEのSHIMA代表をはじめ野球を熱くしたいという人々が主催する企画です。野球をするにあたって、最高の目標はプロ野球選手になることをあげる人は多いかもしれませんが、実際になれるのは一握り。プロになれなくても、野球が大好きで、野球に携わって生きていこうと考えた場合、どんな選択肢があるか?そう子供たちが考えた場合、指導者としてどんなアドバイスができるか?この答えを探しに講演会にいってきます。今話題の野球留学や旬なお話が多く聞けそうで楽しみです。ただ、息子と3日間も離れるのがつらいです・・・講演会のお知らせ■ 「野球というお仕事」 ~野球に関わる仕事をしたい人のために● 対象 学生及びその保護者、少年野球チーム関係者等● 日時 12月11日 18:00~20:00● 場所 横浜市 開港記念会館● 入場 無料● 内容1.高校野球監督(教員監督) ~慶応義塾高校監督 上田誠2.高校野球監督(専任監督) ~羽黒高校前監督 竹内一郎3.スポーツライター ~神田憲行(「ドキュメント横浜vs.PL学園」などの著者)
2005.12.09
-
会社の野球チーム
スポ少監督、中学野球教室のコーチをしている私。私自身も現役の選手です。会社の野球部。選手は20人。高校までの野球経験者が3人。そのほかは、中学までの経験者がいますが、小学校までの人がほとんど。一時期、いいところまでいったこともありますが、今は成績がついてこない。でも野球ができる喜びで私は十分でした。その野球部。大人になると、いろんな事情(家庭、仕事、彼女など)ができて野球ばかりに専念できなくなる。そんな中、厳しい野球を推し進めていくべきか、それとも交流を主とした野球を続けていくかで、チームが割れている。若い世代は、どちらかというと交流重視で、練習もそんなにしたくないというのが本音のやつらが多い。野球の優先順位がそんなに高くないのがありありとわかる。そんな中途半端なやつらなんぞ、きってしまえという意見もあったが、きってしまうと部が存続できない。そのチームの私は、庶務をやっている。キャプテン、監督などの首脳部と選手たちの橋渡し、グランドの確保、お金の管理などもろもろ全般。上の人も考えつつ、下も考えなければならない。はっきりいって、この一年はつらかった。交流目的、または上からの強制で入部したものもいるので、野球が好きな人ばかりの集まりではないので、試合の時の人数確保に奔走したり、足りないときは助っ人を呼んだり、気苦労が多かった。へたくそなやつもいる。うまいやつもいる。勝ち負けには、私はこだわるが、こだわらないやつもいる。それでも、試合をしてる時は野球ができることに感謝しながらプレーしている。一生懸命にやっているやつがひとりでもいてくれるなら、私も一生懸命にがんばろうと思ってやってきた。上をめざそうとする動きがでてきた。そうなると交流重視派はいずらくなるというわけ。せっかくここまでやってきたのに、やめていくやつも出てくるだろう。シビアな野球をめざすか?交流重視の仲良し野球をとるか。私は、シビアにやりつつも交流もする。これでいきたいのに、そういうについていけないという人もいる。その人はその人で価値観があるのだろうが、いままでやってきただけに一抹の寂しさが残る。すべてが大団円。今年はその難しさを痛感している。
2005.12.08
-
小学生と中学生
昨日は中学生、今日は小学生。その指導の仕方について、違和感を感じました。その違和感の正体。中学生は自我があるということ。別に小学生がないということではなくて、小学生よりもはるかに強い。その自我にうったえかけなければ、本当の意味での信頼関係を築くことはできないだろうし、信頼関係がなければ、本当の指導(精神面、技術面など)はできないだろうと感じました。なぜそうするのか?なんのためにそうするのか?中学生は、それに納得しないと行動が鈍るのがわかります。それにかっこつけたがる。他人の目に自分はどう映るか?自分の中のいい閉鎖的な集団にたいして突出しないようにする。「おまえら、アホか、突出してなんぼだろ!」と喝をいれましたが、どこ吹く風。こっからはじめなきゃいけないのかとちょっとがっかり・・・小学生の時に指導していた子めらも数人いたのですが、昔はすぐにいい意味で馬鹿になれましたが、中学生になるとさめている。さめている人(先輩?)を見てきたので、それがかっこいいと思っているんでしょうか?たしかに、さめている人が多い中でひとり馬鹿になっては浮いてしまって恥ずかしいでしょう。でも小学校の時はできていた。声の出し方にしてもそうです。「こいつ、アホか?」と思わせるくらいみんながやれば、誰もアホだとは思わないでしょう。なかには、そういうのが大好きで爆発したくてうずうずしている子もいます。そういうこめらをうまく使っていく、言い方悪いかな、そういう子めらを先頭に導いていくのがここ最近の課題になると思います。いい意味で、馬鹿になる。一皮むけさせる。一所懸命になることに恥じらいなど、感じている暇はありません。それでも、彼らも自我がある。そのあたりを尊重してあげることも必要かなと思って練習していこうと思います。
2005.12.07
-
35人の参加者
脱学区中学生野球教室プロジェクト。はじめて参加しました。指導者の方がことごとくこれないということで、指導者は私ひとり。指導者同士、メニューも方針もコンセンサスをとらないままの参加となりました。最初は、中学生同士よそよそしさが見えましたが、メニューをこなしていくうちにだんだん打ち解けてきました。指導者ひとりで最初は心細かったですが、自分のやりやすようにアレンジできるので気持ちよかったです。先輩指導者の方がおられたら、サポート役に回ろうと決めています。中学生の中に入って、一緒にメニューをこなし、いきおいやリズムを作る手助けをしてあげるのが私の役目だと思います。まずは、彼らのハートをつかまないと、指導者の言葉は通じません。選手との信頼関係。通じるようになったなら、その次の段階にいけると私は思います。その方法として、私は北風よりも太陽をとりますし、罵倒系のやり方はしません。今日も「ちょっと甘いんじゃないか。」言われましたが、選手の中に練習は面白いという意識付けはできたと思います。初日の感想。35人もいたので、まずそれに感動。(うちは14人の零細チームなので)中学校にいくと背の小さかった子も大きくなりますね。だけど、声は小さくなっていた。意識付けは、小学生よりも楽です。やる気になるのが速いし、飲み込みもはやい。こちらが意図したことが伝わります。おもしろい素材、人材もいました。これでチームを組んだらおもしろい。いち早くコンセンサスをとり、どんな指導をしていくか先輩指導者にぶつけてみたいです。また楽しみが増えました。反対に嫁さんは、私がまたいそがしくなり、帰りがおそくなるので機嫌が悪かった・・・
2005.12.06
-
<キャッチボール訴訟>双方の親が3000万円で和解 宮城
怖いニュースをみました。確率的にかなり低いとはいえ、軟球があたったくらいで・・・わがチームなど、ぼこぼこあたっています。公園でのキャッチボールには指導者はいなかったでしょうが、もしこれがグランドでおきていたら・・・安全管理。これはできてて当たり前。極端な話ですが、何かあったとき、保護者は敵にまわるといいます。こういうのを聞くと予見がつかないので、怖いなと思います。キャッチボールの球が胸に当たって長男(当時10歳)が死亡したのは、外部からの衝撃で心拍が停止する「心臓震盪(しんとう)」が原因として、宮城県角田市に住む両親がキャッチボールをしていた子供の親を相手取り、計6200万円の支払いを求めた訴訟の控訴審が5日、仙台高裁(大橋弘裁判長)で和解した。 被告側が死因が心臓震盪であることを認め、和解金計3000万円を支払う内容。原告代理人によると、心臓震盪を引き起こした責任を問う訴訟で和解が成立したのは初めて。 1審・仙台地裁は心臓震盪が死因と認定し、被告に約6000万円の支払いを命じた。被告側は「死因が心臓震盪とする証拠はなく、事故の予見も不可能」と争っていたが、高裁の和解勧告を受け入れた。 訴えによると、長男は02年4月、大河原町内の公園で遊んでいたところ、キャッチボールをしていた小学生2人の軟式ボールが胸を直撃し、約4時間後に死亡した。
2005.12.05
-
デジカメがほしい!
スポ少だけでなくいろんな場面でつかうデジカメ。今は携帯にもカメラがついていますが、私のFOMA N901iは使い勝手がわるい。よって、今まではFINE PIXを使っていましたが、ついに壊れました。画面が紫になって、シャッターを押しても真っ黒。雨の日でも、くそ暑い日でもポケットのなかにいれて酷使していましたので、とうとう寿命がきたかも。修理に見積もりを出すと共に、新しいカメラを物色してきました。その中で、目に留まったもの。PENTAXのOptio WP。なにがすごいって、1.5mまで水中で撮影が可能。川の中の魚や海の中での撮影ができます防水、防塵で耐久性にすぐれている。スポ少や、つり、スノーボード、農作業、山といろんな過酷!?な状況にいく私にとってはもってこい。携帯電話のようなフォルムで小さいし、500万画素もある。ただ気になるのは、レンズのカバーがない。それと、ピッチングやバッティングのフォームを高速連写でとることが可能かということ。まぁこちらはデジタルビデオカメラがあるのでなんとかなります。たぶん、買うでしょう。スポ少のためとはいわずに、大和を撮るためだと嫁さんを説得します。
2005.12.05
-
指導者と保護者 連盟の納会にて
会津はすっかり冬です。雪がごそっとふったためにタイヤ交換に大慌て。今年はタイヤを新調しましたが、その際3時間近く待ちました。この時期のタイヤ関係の仕事の人は朝からタイヤ交換の日々。まっくろになった手をみて、ご苦労様だと思いました。さて昨日、わが連盟の納会がありました。本年度の役員の首荒いと来年度の計画などをお酒を飲みながらいろいろ話し合ってきました。そこで、ペナントレースのようなリーグ戦の構想、そしてわが連盟でも大会を主催しようということを提案しました。私の提案に賛同していただいたチームもあり、感触は上々です。みんなが力をあわせれば、できないことはありません。ただ心配なのは、昨日は旧役員のあつまり。新役員になったときその提案が引き継がれるかが心配です。その飲み会で、他の指導者の方の苦労をしりました。「私のチームは私が(監督)も育成会長も兼任しているようなものです。」その監督さんは、試合の時に送迎の車がたりずに、嫁さんをかりだして送迎をやったり、審判がたりない時、次に試合を控えていながら監督みずから審判もやり、試合で飲むこどもらのスポーツ飲料のタンクの管理までやらなくてはならないそうです。熱くしっかりとした指導をなさる監督さんです。本来は指導のほうに重きをおきたいのにその他のことまでやらなければならない。保護者との温度差に苦労されているようでした。かと思えば、他のチームでは、送迎のためにバスをかった保護者もいると聞きました。私もバスがほしいなぁとおもってオークションや、ミリオネアの参加してみようかなんて思ったこともありますが、かっちゃった人がいるとは。そんな保護者のいるチームは、一枚岩。やっぱ強いですし、こめらも生き生きしています。保護者の中に、そういうもろもろをまとめてくれる人物がいるとかなり心強いです。私よりも年配の方々ばかりなので、多少いいずらいところはあるのですが、そこは割り切って言うべきことはいうようにしています。そのほうが指揮系統としても機能するということがわかってきました。やはり名物監督と言われる人は、保護者もまとめるのもうまい。そしてお酒も強い人が多いなぁと私は思いました。歌もうまいです・・・
2005.12.04
-
「息ぴったり」 呼吸のシンクロ
私が毎週読んでいるす週刊ビックコミックスピリッツ。その中に面白い特集があった。だいぶ前の話なのでうすらおぼえだが。意中の人の気持ちをひきつけたいとき、雰囲気を良くしたいとき、相手の呼吸に自分の呼吸をあわせると良い。そんなような内容だった。つまり「呼吸のシンクロ」だと私は思った。バッティングのシンクロについて勉強しているので「シンクロ」という表現には敏感になっているせいもあったのかもしれない。気がついたときは実践している。どんな場面で?赤ちゃんである大和に対して。おんぶばかりして寝かせているので、おんぶをしないと寝なくなってしまった。保育園に預けるときに苦労すると指摘があったので、添い寝にきりかえるがなかなか寝てくれない。そこで呼吸のシンクロを思いだし、使ってみた。その効果なのかはわからないが、大和と呼吸(赤ちゃんなので少し早い)をあわせると寝るまで時間が短くなっているように思える。また寝るときは、嫁さんと私で大和をはさんで川の字になって寝ている。最初は嫁さんのところばかりに大和は擦り寄って言ったが、ここ最近は私のところへ頭をぶつけながら擦り寄ってくる。嫁さんが嫉妬している。気のせいか?呼吸のシンクロのおかげとは言い切れないが、言葉にも「呼吸が合う」「息ぴったり」とかそういった表現があるのであながちうそではないのかもしれないと思い始めた。同じ空間の同じ空気を同じタイミングですったりはいたり。言葉のわからない赤ちゃんにも効果!?がある。スポ少の子めらたち。ピンチになったとき。心をひとつにする場面。手を胸にあてて全員の深呼吸のシンクロ。使えるかもしれない。もうやっているところはあるかな?
2005.12.02
-
フリスビーをつかった練習
フリスビーをつかった練習をしています。100円ショップで売っていて経済的です。100円ショップには工夫をすればいいトレーニング用品になるものがいっぱいおいてありますね。利点は1、 ボールよりも落下速度が遅いために、落下点を予測するまでの時間が長く取れる。2、 落下速度がおそいために、移動しながらの捕球体勢がとりやすい。3、 おもしろい。その他利点はあると思いますが、落下速度がボールよりおそい。ここが最大のメリットです。練習方法は、お父さんのための野球教室、metooさんの練習を参考にしました。題して「ゴー・バックノック~フリスビー編~」1、「せーの」で1、2で揺らぎながら二岡式スタート2、「GO」でダッシュで前進。3、「バック」で、バック。腰をきりながらダッシュバック。4、スタートのラインあたりまでバックしそうになったら、フリスビーを投げる。 なるべく高めに投げてやることで、落下点まで到達するまでに一生懸命こどもたちは走ります。この練習での注意点。バックしながらダッシュ。亀の子バックでは速く走れません。捕球体制は次に投げることも考えながら、なるべく前をむいて、ひざがつっぱらないように余裕を持たせてとる。ブレーキと同時に踏ん張ってなげることを意識する。などがあげられます。みんな犬になったように、フリスビーを追っかけます。競わせるように、5回とったほうから次のメニューにいくなど目標をもたせます。そしてこれを踏まえて、今度は実際のボールをつかう。落下速度が速いので戸惑いますが、捕球体制、追い方はフリスビーと一緒。こめらはもっともっと難しいところを要求してきます。そうなればしめたもの。雰囲気はよくなるし、モチベーションもあがります。わがチームの定番メニューになりました。ブログをやっていなかったら思いつかなかったと思います。みなさんに感謝。
2005.12.01
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-
-

- 楽しい競馬・やっぱり馬が好きっ!!…
- 行き掛けの駄賃のレガレイラ負けられ…
- (2025-11-16 14:04:04)
-
-
-
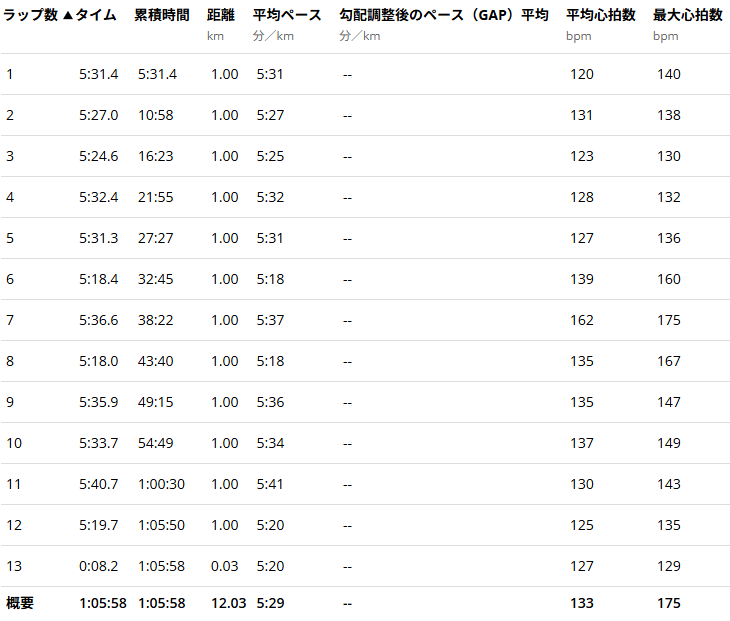
- マラソン&ランニング&ジョギング!
- 小松島逆風マラソンに向けて その1
- (2025-11-16 06:50:04)
-








