全337件 (337件中 1-50件目)
-

「疑獄と謀殺 戦後、「財宝」をめぐる暗闘とは」を読みました
怪死重要証人はなぜ自殺するのか。宮内庁に保管してあった貞明皇后の大粒ダイヤが消え、日銀地下金庫の供出ダイヤも持ち出されていた。戦後、GHQの進駐は、民主化と同時に新たな権力者としての略奪、政治腐敗をももたらした。その後、次々と起きた疑獄事件や贈収賄事件でも、重要証人や関係者が決まって不審な死を遂げていく。その裏に何があったのか。戦後疑獄事件にまつわる「死」、その真相に著者(森川哲郎氏)が迫ります。本書のあとがきで、著者はこう言っています。「疑獄史には、その背後に一度入ると迷って出てくることのできない森林に似た地帯が横たわっている。その深い森には、数多くの疑獄の鍵を握る人々・・・その故に抹殺された人の死体が投げ込まれている。この永遠にもいわぬ沈黙の森の入り口には”自殺という名の他殺の墓”と記された墓標が、ポツンと一つ建てられているだけだ」今までどれだけの人達が、口封じのために「自殺」や「他殺」と決めつけられて、この深い森の中に投げ込まれたのでしょうか。疑獄の根は、単純に日本という土壌だけの話ではなく、やはりそこには、GHQをはじめとした米国の巨大な黒い陰謀工作も含まれているようです。戦後に起きた有名な事件についての著書を読むたびに思うんことなんですけど、GHQが絡んだ事件というのはどれもこれも、なぜ謎めいているのでしょうか?GHQとは、どれだけ強固な組織だったのでしょうか?著者も「一度入ると迷って出てくることのできない森林に似た地帯」と言っているように、事件の内情に通じている者や事件に深くかかわっていた人達があっけなく死んでいるにもかかわらず、本書で取り上げている事件そのものの構造もかなり複雑で難解です。特にロッキード事件では、捜査中に、鍵を握ると思われる重要証人や事件を追及中の記者達が次々と怪死(その数16人とも18人とも言われている)するという現象が起き、それが疑獄の対象にもなったようですが、人格をも変えてしまう”お金の魔力”に取り憑かれてしまった人々と、その魔力に消されてしまった人々が絡み合った謎の事件と言えますね。日本国内では、昭和16年に完全殺人薬が既に開発されていたようで、無臭、無刺激、無味の小さな実一粒程度の物体を飲むと、まったくなんの異常も表れない日が7日間も続いた後、ぽっくりと頓死してしまうそうです。もっともこの薬は、731部隊が開発した薬の改良版だそうですが。さらにCIAの暗殺用薬物は非常に発達しており、高血圧で2、3日後に死ぬもの、心臓麻痺が一定時間後におこるもの、精神錯乱がおこるもの等々、現在ではもっと巧妙な薬が完成しているという事実を、アメリカ上院のCIA査問委員会が発表したとのことです。何の証拠も残さないという完全犯罪。名探偵コナンもお手上げですね。真面目な話、かなり恐い・・・(-_-)そんなことをここで暴露してしまったぼくも、CIAに狙われる恐れがあるので、このへんで執筆を終わらせることにします。狙われないっつーの(笑)オススメ度:★★☆☆☆(あまりオススメしません)【送料無料】疑獄と謀殺
2011年03月09日
コメント(0)
-

「逮捕されるまで 空白の2年7カ月の記録」を読みました
東京→北関東→静岡→東北→四国→沖縄→関西→九州。電車、船、バス、自転車、徒歩で転々と移動した。誰にも語らなかった「逃げた後、捕まる」までの2年7カ月の間、どこにいて、どのような生活をし、何を考えてきたのか。捜査機関に対し黙秘を続けてきた市橋達也が、これまでほとんど明らかにしてこなかった逃走生活の全貌を克明に書きました。2007年3月26日に千葉県市川市の自宅マンションから逃走し、2009年11月10日に大阪南港のフェリーターミナルで逮捕されるまでを綴った内容ですので、事件についてはまったく触れていません。この逃亡が自分なら可能かということを想像してみて下さい。遊びに行こうと数万円が入った財布と音楽プレーヤーのみを持ち、そのままの姿で2年7ヶ月彷徨い歩けるかどうかということを。ぼくは無理ですね。そう考えると、彼の精神力は凄いのか?と、違う意味で関心してしまいそうになるし、捕まりたくないという信念が、そこまで強靱な精神にさせてしまうものなのだろうか?と考えてしまいます。○○でした。○○でした。と文章能力はかなり劣っているので最初は読みづらかったのですが、不思議と後半はそんな文章も慣れてきます。さらに、前半は逃亡中の歩いている話ばかりであまり面白くなかったんですけど、後半は、逃亡資金を稼ぐための仕事の事や、彼を取り巻く人々、そして少しずつ迫ってくる捜査網を感じながら逃亡している心境などをうまくまとめているので臨場感が出ています。逃亡場所とは違った透視を得意な顔で発言する超能力者の予言や、嘘ばかり報道するマスコミというのも、彼が言うようにまったく意味が無いのかもしれないですね。人の命を奪うということは、人間をここまで追い詰め、惨めにさせるということなんだということがよくわかり、本書の内容にもうまく表現されていると思います。そして殺人という行為が、不運にも殺されてしまった人はもちろんのこと、殺してしまった人間も合わせた二人の人生を狂わせることなんだということも、つくづく思い知らされる内容です。読んでいて、少し切なくなってきました。逃亡中の彼が印象に残った言葉。「I may be through with the past. But the past is not through with me.」~過去は捨ててもついてくる~オススメ度:★★★☆☆(普通かな)【送料無料】逮捕されるまで
2011年03月07日
コメント(0)
-

「ひとり旅」を読みました
終戦の年に空襲で避難した谷中墓地で見た、夜空一面から朱の光が降りそそいでいた情景。銀行の現金引出し専用機の前で、チャリンと出てきた十円硬貨一枚に一瞬頭が錯乱したこと。小説家を目指す少年からの手紙や、漂流記の魅力について・・・事実こそ小説である、という徹底した創作姿勢で知られる著者(故 吉村昭氏)が遺した、珠玉のエッセイです。平成18年に著者は亡くなってしまったため、本書は著者が残した最後の著作物になります。研究家の書いた著書も、公的な文書も決してそのまま参考にせず、一人で現地に赴き、独自の方法により徹底的な調査をする執念。そして、余計なフィクションは加えず、あくまでも「事実こそ小説である」という創作姿勢がこの著者の作品には表れています。「学者の方というのは自分の書斎に籠もりきりで出掛けていかない」と著者が言い切っているように、まさに「百聞は一見にしかず」を著者は身にしみて感じていたんだと思います。例えば松があったといっても、それが赤松なのか黒松なのか、それがわからないと書けない。馬が駆けてゆく場面を書くとしても、巻き上がる土埃が茶色なのか、あるいは砂っぽいのか、実際に駆けていった場所を見ないと書けないではないかというこだわり。だから、わざわざ現地に行くことに意味があるのだそうです。この作家としての執着心は、凄いですよね。そんな「著者のこだわり」が本当かどうかは、物語の背景が事細かに表現されているこの著者の作品を読めばすぐに納得できると思います。本書は「史実というものはそのままがドラマなんだから、史実を忠実に書くだけで小説になってしまうんだよ。」という著者の声がたくさん詰まっているエッセイです。ひとりで旅をするからこそ、隠れた史実が見つけられたんでしょう。著者が書き残した、数々の史実に基づいた小説を書く際の苦労話も読み応えありますが、この著書は、著者が亡くなってから発刊されているので、エッセイで語っている著者の言葉と、途中途中で挿入されている対談形式での著者の言葉が二度三度ダブっているのがかなり残念でした。生前の著者だったらあり得ない編纂です。オススメ度:★★★☆☆(ということで、残念ながら普通かな)【送料無料】ひとり旅
2011年03月04日
コメント(0)
-

「日本霊界地図 呪われた恐怖のタブー地帯」を読みました
並木伸一郎氏が監修した、知られざる恐怖のパワースポットが123箇所収められています。この世を儚んで自ら命を絶った人や、不慮の事故に遭い亡くなった人など、霊現象の正体はその人たちの現実への未練、恨み、つらみ、嫉みによって生じた「負の思念」と言われています。本書は、日本列島の北から南にかけて、怨念である「負の思念」がより強く憑いてしまった土地や建物・現場をベストセレクトした霊界地図です。余計な脚色を加えず、各々のタブー地帯をコンパクトに淡々とまとめているところが、また微妙な怖さを感じさせてくれます。ただ、淡々と書かれている分、深く追求したいと思っている読者にはちょっと不向きな著書ですので、雑誌感覚で読むことをオススメします。さらに、MAPも付いているので、行こうと思えば行けるとは思いますが、やはり行かない方が賢明でしょうね。自殺の名所「日光華厳の滝」。学校の遠足などで行くと、必ずと言ってよいほど学年に一人は撮った写真に怪しい白い影が映っているような心霊スポットとして超有名ですが、元々は悲しい物語があった場所だったなんて知りませんでした。この世に未練を残して亡くなった方のいる過去を持つスポットが、一番怖いような気がしますね。場所によっては、MAP部分が「諸事情により地図を掲載することはできません」と書かれているので、読んでいる途中から、本書の内容そのものよりもMAPをなぜ掲載できないのか、という理由の方が気になってしまいました。ギャラリーが多すぎて地元の人が困っているからなのか、本当に危険な場所だからなのか・・・最近、この手の著書を読めば読むほど「そもそも幽霊は存在するのだろうか?」という疑問が沸いてきました。人間が見る夢だって、あたかも目で見たような錯覚になるのと同じで、目から入ってきた情報意外でも「見た」と錯覚することもあり得るのかな?なんてね。そもそもぼく自信が霊というものを見たことないからそう思うんでしょうけれど。霊感の無い人にとっては、永遠のテーマかもしれないです(笑)オススメ度:★★★☆☆(普通かな)【送料無料】日本霊界地図
2011年03月02日
コメント(0)
-

「いちばん危険なトイレといちばんの星空」を読みました
自転車で世界を一周した著者(石田ゆうすけ氏)が見た、感じた「世界一」の数々です。危険な場所、危険なホテル、危険なトイレ、大峡谷、巨大滝、遺跡、星空、メシがうまい国、メシがまずい国、うまいビールなどの全30篇。184回もパンクしながら約9万5,000キロの自転車旅を綴った、前作「行かずに死ねるか」では、世界87カ国を訪れ、旅の期間もなんと7年半もかかったそうですが、帰国後に行った講演などで必ず寄せられる質問は「○○が一番だったのはどこか?」なんだそうです。そんなに聞かれるんだったらいっそのこと「独断による世界一」を決めてしまおう!という意味も込めて書いたのが本書です。「行かずに死ねるか」の続編とは言いつつも、前作では書ききれなかったエピソードや、内容そのものもまったくカブってないので、新鮮な気分で読むことができます。しかし、この著者の文書能力や表現など、どれをとっても素晴らしいですね。読んでいるだけで自分もその場で体験しているような満足感に浸ることができます。ぼくも海外旅行の際にはいつも感じることですが、日本から海外に出ると、時間がゆっくり流れているように感じるのは気のせいでしょうか?気のせいではないんでしょうね。いかに日本人がせかせかと日々暮らしているかがわかるような気がします。ぼくもそんなせかせか人間の一人なんでしょうけど(笑)本書で取り上げている著者独自の世界一からいくつか抜粋すると、遺跡部門では一つがメキシコのウシュマル遺跡。あの階段、高所恐怖症のぼくには完全に登頂不可能ですね。仮に昇ることができたとしても、まず下りることは不可能だと思います。頂上で「エ~ン、エ~ン」と泣くかもしれないです。下りられない場合は、どうなってしまうのでしょうか??ちょっと視点がズレてしまってゴメンナサイm(_ _)mそれと87カ国の旅で最も印象に残っているのはアフリカとインドだそうです。サバンナの草原が揺れ、動物の群れが静かに草を食べ、太鼓の音が響く。そんな褐色の大地に沈む夕陽・・・う~ん、行ってみたいですね。見てみたいですね。人類が生まれた場所だということを、意識の根底で感じるのでしょうか。インドは、インド人のあのまとわりつく様な視線が・・・ちょっと勘弁です(>_
2011年02月28日
コメント(0)
-

「捜査指揮 判断と決断」を読みました
警察官の基本は、いざという時に頼りになること。捜査指揮官にとって重要な資質は的確な判断力と決断力。簡単な事件や推理小説ならば必ず犯人に到達するが、現実におきる難しい事件であれば解決できる指揮官とできない指揮官とがでる。それどころか指揮官によっては、とんでもない人権侵害を引き起こすことすらある。このようなことは刑事の世界だけでなく、一般の社会、特に人を動かす仕事をしている人たちにも当てはまることが多い。では的確な判断力を身につけ、タイムリーな決断を下すにはどうすればよいのか。質の良い経験を積み、現場と現場の資料を見て、徹底的に考え続ける以外にない。20世紀における犯罪捜査の歴史は科学捜査の歴史と言われ、それは同時に拷問からの解放の歴史でもあったと言われているそうです。戦後の科学捜査の歴史を振り返ると、1.指紋自動識別。2.自動車ナンバー自動読み取りシステム(Nシステム)3.DNA型鑑定4.掌紋自動識別システムと、中でも4の掌紋自動識別システムにおいては、掌紋は紋様が複雑すぎて、かつ大きすぎるために自動識別は不可能だと言われてきたものですが、それが可能になったということは、コンピュータの技術の発展がいかに凄まじかったかということになるかと思います。(ちなみにオウム事件では、この掌紋により逮捕された信者が多数いるんですよね。本人達もまさか掌紋が識別されるとは想像もしてなかったようです。熱い鉄板に指先を押しつけて指紋を消した苦痛はなんだったのでしょう。(-_-))日本で指紋認識が最初に使われたのは、犯人を捕まえるためではなく「無実の証明」のためだったそうですが、指紋もDNAも、様々な科学捜査が発展してくれたおかげで、冤罪が少なくなっているのでは?と思いきや、データベースへの蓄積件数がアメリカやイギリスに比べると少ないようで、冤罪という不安がまだ残ります。本書は、70件にも及ぶ現実の事件を素材として、二人の刑事警察最高幹部経験者が「刑事捜査の形」を示したものです。数々のエピソードと貴重な失敗談が次々に語られます。捜査指揮官の責務や行動・判断とはなんたるものか!はもちろのこと、捜査における苦労話などを実話をもとに編集されているので、内容が新鮮でおもしろいです。本書の後半は、著者が尊敬する捜査指揮官、寺尾正大元警視庁捜査第一課長が警察大学校特別捜査幹部研修会で行った講義内容をベースに、捜査指揮官のあるべき姿を著者が独自にまとめています。講義と言っても堅苦しい話ではなく、実際の捜査において経験した成功例はもちろんのこと、失敗例も列挙されているからこそ、講義内容に味があるのではないでしょうか。警察関係者のみならず、ぼくたち一般市民にとっても、テレビや小説、報道などで紹介されている事件や捜査と一味違った「本物の捜査」を知ることができますよ。警察関係者やこれから警察人生を目指す人達には特にオススメしたい一冊です。是非読んでね。(は~と)【参考】本書より「法隆寺五重の塔は、見えにくい所まできちっとしているから長持ちする」という言葉が著者は好きなのだそうです。見えにくい所での努力が大切、ということなんですね。オススメ度:★★★★☆(少しオススメ)【送料無料】捜査指揮
2011年02月24日
コメント(0)
-

「鉄道員裏物語 現役鉄道員が明かす鉄道の謎」を読みました
鉄道員をしているというと、さまざまな質問をされることがある。 「人身事故の処理は誰がやっているのか?」 「電車を停めると、1億円を請求されるというのは本当なのか?」 「コインロッカーの忘れ物にはどんなものがあるのか?」 「駅で放送している声ってなんで変なのか?」 鉄道の世界というのは、周りから見ると不思議でつかみどころのないものに映るようだ。本書は、某大手私鉄の現役鉄道員が鉄道の世界や鉄道員の知られざるエピソードなど、まさに真実の姿を赤裸々に綴っています。第1章「鉄道の事件簿」では、人身事故や痴漢、不正乗車やコインロッカーの忘れ物などについて、第2章「誰も書かなかった鉄道の秘密」では、放送している独特の声の謎、乗務員のトイレの謎、改札機の値段などについて、第3章「世にも奇妙な鉄道の世界」では、労働組合と政治、鉄道員の一日などについて、と、目次だけでも興味がわく内容です。そして、オタクの聖地というイメージの鉄道や完全なオタク集団と思っていた鉄道員の姿が見事に覆されました。そして鉄道マニアの方々はもちろんのこと、ぼくのように普段あまり鉄道の世界に関心の無い人も楽しんで読める内容です。ただ、著者が現役駅員というだけあって、事件や事故が起きた際に発すると言われている乗務員の放送用隠語についての記述がなかったのがちょっと残念でしたが(>_
2011年02月21日
コメント(0)
-

「人類はなぜUFOと遭遇するのか」を読みました
1947年以来のUFO事件について記述し、考察を加えた年代記。米国スミソニアン協会刊行の、現在望みうる最高レベルのUFO本です。皆さんはUFOを目撃したことはありますか?ぼくは2度あります。一度は小学生の時、夜空にジグザグ飛行しているオレンジ色の物体を見て、2度目は20歳くらいの時、青空の中、2機のグレーの物体がジグザグ飛行したのち消えてしまいました。本書は「なぜ人々はUFO神話の虜になるのか」に焦点を置き、空飛ぶ円盤の歴史についてまとめた年代記です。米国の歴代大統領は円盤の存在を否定してきましたが、空軍にとって円盤は過去22年にわたり頭痛のタネとされ、議会やCIAさえも円盤について調査を行ってきたという経緯を前提に、円盤(UFO)にまつわるあらゆる事件を徹底的に調査し、検証しています。UFOの存在については著者自身が懐疑論者ではあるものの、頭から疑ってかかるのではなく、体験者の証言やFBI、CIAなどの資料をきちんと紐解き、信奉者、懐疑論者を問わずかなりフェアな考察を行っているところに本書の読み応えを感じます。おそらく、UFOに関する事件についてここまで詳細に分析した著書は他には無いと思います。(各々の言い分を事細かに掲載しているので、詳細過ぎてかなりのボリュームになっています。)そして、エリア51やロズウェルなど、どこかで聞いたことがある事件や名称が次々と現れては、それらの神話が形成されてきた経緯をきっちりと解明することにより、「アメリカという国家が生み出した都市伝説だった」という衝撃の結末に結びつけてくれます。本書において下している結論はあくまでも著者個人のものであるため、読者自身で判断して頂きたい、と著者は述べています。しかし、著者は最後までUFOの存在自体を否定しませんでした。それはUFOは存在すると思っているからなのでしょうか・・・ぼくも見てますし(笑)。【参考】ロズウェル事件・・・本書より1947年7月8日、当時ロズウェル陸軍航空基地で広報官を務めていたウォルター・ハウト中尉が、地元マスコミに向けて「ロズウェル基地近くの牧場に円盤が墜落し、米軍がその機体を回収した」とプレス発表をしてしまったことに端を発しているそうです。最初の発表から数時間後、軍は「回収したのは円盤ではなく、気象観測気球の間違いだった」と正式に訂正のアナウンスを発表したが「円盤を回収した」と一度発表してしまったその言葉だけがその後一人歩きを始めてしまい、いまだに謎の事件として語り継がれることになったとのこと。最初のプレリリースが配布されることがなかったら、今日までのロズウェル騒動はありえなかったとまで言われています。ロズウェル騒動のタネを蒔いたのは、米軍自身だったんですねー(>_
2011年02月16日
コメント(0)
-

「三浦和義との闘い 疑惑の銃弾」を読みました
まずはこの事件を振り返ってみましょう。昭和56年11月18日、ロサンゼルスを旅行中の日本人夫婦が、白昼、強盗に襲われた。被害にあったのは三浦和義(34)、一美さん(28)の夫婦で、二人は前日ロサンゼルスに到着したばかりだった。インテリア家具等を輸入販売する「フルハムロード」を経営する青年実業家であった三浦は、同社が独占販売契約しているTシャツの宣伝用写真を撮るために、妻の一美さんをモデル代わりに大きなヤシの木の前で撮影していたところ、車から降りてきた強盗に一美さんは頭を、夫の和義は左足を銃撃された。妻の一美さんは前頭葉を除去する6時間の大手術にもかかわらず同年11月30日に死亡したにもかかわらず、夫の和義は左足大腿部を撃たれたもののわずか1週間程度の軽傷だった。しかし事件から3日後、まだ病院のベットにいる和義は、アメリカ大統領、カリフォルニア州知事、ロサンゼルス市長あてに抗議文書を送りつけた結果、アメリカ軍の異例の協力により空軍病院機で一美さんを日本に連れ戻した・・・当時、美談として有名になった事件です。”植物人間”になった妻に対する夫の献身的な愛情物語が、主として女性週刊誌やワイドショーで大きく紹介され、社会的にも話題になったほどです。しかし、女が先に、しかも頭を撃たれて男が足だけしか撃たれないという誰もが考える不可解さが、この事件の単純にして最大の疑惑になりました。この著書は、著者をはじめとした週刊文春の取材班が、事件の真相を知りたい、三浦和義の疑惑を限りなく正確に構築したい、という記者根性によるまさに地を這うような前例のない長期取材により追求することができた事件の真相をまとめています。当時の三浦は、父を”お父ちゃま”と呼び、母を”お母ちゃま”と呼ぶ幼児言葉が抜けていなかったどころか、ものすごい偏食家で、野菜はネギ以外は食べず、異常なチョコレート好きだったそうです。嫌いなことはしたくない、好きなことはいつまでもしたい・・・そう、我慢という自己コントロールが欠如した大人子供だったんですね。この性格を理解するには、子供とオモチャを連想すると良いです。子供は新しいオモチャに夢中になるけど、さらに新しいオモチャを手に入れると、前のオモチャには見向きもしない。そんな三浦にとっては、女性はオモチャと同じ。飽きたら捨てる。飽きたら壊す。では人間を壊すとはどういうことか、それは「殺す」ということ。過去にも三浦の周りで謎の死をとげていた女性の存在や、三浦にまつわる不可解な黒い噂が出てくるにつれ、もはや絶対絶命ともいえる状況だったにもかかわらず、当時はなんら捜査権が及ぼうとせず、平成20年2月23日に旅行中のサイパン島で逮捕されたことがまだ記憶に新し方もいるかとは思いますが「なぜ今になって逮捕?」と思った方が大半だったのではないでしょうか。さらには突如現れた日本人顔のロス群検事局、ジミー佐古田氏とやらは何者なんだろう?と。思いませんでしたか? そう思ったのはぼくだけ??(^^;)米国には時効が無いから、というのも「今になって逮捕」に関係あるようですが、三浦の犯罪をこれまで長年のあいだ守ったものは、三浦の綿密な計画性にあったのではなく、ロスの人間社会の曖昧性や不透明性が捜査を難航させたという背景と、過去に行方不明になっている女性や一美さん、三浦を含めた人間関係が形成されているのが日本であるがために、事件関係者の人物象について知識のないロス市警、また、事件が起きたロサンゼルスという犯行現場の知識がない日本の警察という、まさに日本とアメリカの法の網の間に見事に落ちた事件だったからなんです。本書の発刊は昭和60年なので、最後に留置所で自殺するまでの経緯は書かれてはいないのですが、地味ながらも着々と疑惑を追及し三浦を追い込んでいく取材班の能力と記者としてのプロ根性は凄いです。グイグイと引き込まれていく内容です。最後に自ら死を選んだということも、留置所という自由のない世界に生涯身を預けることになるということを悟った三浦の「我慢ができない性格」ゆえのことだったのかもしれないですね。書き忘れるところでしたが、本書では、ジミー佐古田氏がこの事件を解明するにあたって”実はかなりのキーマンだった”ということもわかりますよ。オススメ度:★★★★★(かなりオススメ)三浦和義との闘い
2011年02月14日
コメント(0)
-

「東京ふつうの喫茶店」を読みました
通も唸る名店から、地元民の憩いの店まで。街歩きの名手(泉麻人氏)が歩いて見つけた、おじさんもホッとくつろげる56軒を紹介してくれます。お洒落なカフェは増えたけど、昔ながらの「喫茶店」はめっきり減ってしまいましたよね。ぼくのような中年世代としては、かつて「サテン」と呼んでいたお店が妙に落ち着いてしまいます。(ドトールやカフェドクリエなど、レジで注文しその場で商品を受け取るお店は、商品を受け取る前から座る席があるのかないのか毎回ドキドキしてしまいます。たとえ座れたとしても、隣の人が近すぎ(笑))そんな昔ながらの喫茶店を、著者独自の基準で選定し取材したのが本書です。その基準とは、珈琲の味はもちろんのこと、お店の佇まい、店主の人柄や語り口、窓越しに見える町並みやそれとなく聞こえてくるお客の会話などなど。数あるお店の中でも、メニューの料金の端数がすべて5円という喫茶店がありました。なぜだかわかりますか?これは「ご縁」にあやかったもので、勘定を支払うとリボンを結んだ5円玉が一つ、おつりとして返ってくるという仕組みになっているそうです。粋な計らいですねー。ちなみにこのお店は、高円寺にある「珈琲亭 七つ森」。「東京ふつうの」という題名でありながらも、著者が仕事などで立ち寄った地方の素敵なお店もいくつか取り上げています。本書の最後には「気になるお店を見つけたら、定期入れにしのばせよう!」という著者の配慮から、本書で紹介されたお店の所在地や営業時間、定休日などが明記してある小さなカードが添付されているので、気になるお店があれば切り取って持っていると良いかもしれないですね。この著書を読み終わると、珈琲を飲みながら、バターがたっぷり塗ってあるトーストが食べたくなると思いますよ。オススメ度:★★★☆☆(普通かな)【送料無料】東京ふつうの喫茶店
2011年02月09日
コメント(0)
-

「フニオチ手帳」を読みました
矛盾だらけのこの世の中、納得できないことばかり。ふかわりょうによる「腑に落ちないもの」大集合。あまりテレビを観ないぼくですが、ふかわりょう、出川哲朗、江頭2:50、エスパー伊東が出ている番組は観ます。別格です。ついワクワクしてしまいます。 ん?ちょっと変わってますか?(笑)腑に落ちない事だらけの世の中ですが、政治、思想、グルメ、エンターテイメントなどなど、あらゆるジャンルについての腑に落ちない事を詩の様に綴っているのが本書で、ふかわファンとしては笑いながら一気に読める内容です。イラストを担当しているのが蛭子能収氏、そして所々で出てくる「フニオチ太郎氏」のコメントがこれまた面白いです。 ※フニオチ太郎:世の中の腑に落ちない事を探求する謎の詩吟詩人。日本フニオチ協会の主宰でもある。(思いっきり著者本人なんですけどね(笑))「CMのあともまだまだ続きます」と言っといて次週予告。 ↑これ、なんとなーくわかってはいるものの、毎回ムカッときますよね?「怒らないから話して」と言った人が実際に怒られる確率。 ↑たいがい怒られます(笑)しかもこのセリフを言っている段階で既に怒ってる。本書で取り上げている腑に落ちないことは、本当に何気ない事ばかりですけど、実際に言われてみると納得してしまう事ばかりです。おどけているようでおどけていない、とぼけているようでとぼけている、そんなふかわ氏の顔が読みながら頭に浮かんでくるので面白さが倍増されているような気もしますが。オススメ度:★★★★★(かなりオススメ)【送料無料】フニオチ手帳
2011年02月07日
コメント(0)
-

「日本のバラバラ殺人」を読みました
明治から平成まで日本人の背筋を凍らせた数々の事件。特殊な犯罪?理解不能?否。その裏側を覗けば、哀れとしか言えぬ人間の業がごろり横たわっている。数ある殺人事件の中でも、特にバラバラ殺人のみを著者(龍田恵子さん)が取り上げた理由として、殺人に至る経緯もさることながら、”死体を殺す”までに至った殺人者たちの事情、動機などを明治・大正時代まで遡ってみたかったからだそうです。本書は、そんな恐ろしい事件の背後にある「物語」に焦点を当てて書かれています。どれもこれも結果としては薄気味悪い事件ばかりですが、その事件に至るまで、極限状態に自らを追い込んでいった殺人犯達の物語にとても人間臭さを感じてしまいます。計画的か無計画かに関わらず、貧困、嫉妬、保身、絶望といったいわゆる「動機」が背後に存在する事件がほとんどですが、中にはそんな動機すらもないような事件もあります。今まで色々な殺人事件関係の著書を読んだつもりでも、本書で取り上げている事件は知らない事件ばかりだったのでぼくもまだまだですね。「死体は語る」の著者(上野正彦氏)も言っている通り”バラバラ殺人イコール残酷事件”と思われがちですが実は違うんですよね。もしも自分より躯が大きい人間を殺したら、どうやって運びますか?その結果としてバラバラにしてしまうんです。一部はそうじゃないケースもあるけれど・・・しかし、加害者たちの犯行に至るまでの足跡をどうイメージしても、人命を絶ち切って死体を切断した土壇場の心理だけは、どうにも理解できないや(>_
2011年02月04日
コメント(0)
-

「テッカ場」を読みました
「テッカ場」。それは理性が影を潜め、欲望がほとばしる場所。いい大人が我を忘れ、普段は封印された別の顔をうっかり垣間見せる。競走馬セリ市、鳩オークション、ネットアイドル撮影会、テディベアの大集会・・・独特のムード溢れる“欲場”の活況とコーフンを著者(北尾トロ氏)が参加者目線で追いました。隠したいと思っている理性を隠し切れず、思わず理性のリミッターが振り切れてしまう場所を「テッカ場」と名付け、そんなマニア以外にはちょっと理解に苦しむような現場で理性を振り乱し奮闘している人々を著者の冷めた目線(笑)で取材しています。競走馬に鉄道部品、鳩や切手などのオークション会場やコミックマーケットやネットアイドルの撮影会など、10ヶ所のテッカ場巡りを収録していますが、わかった気になれた現場もある一方で、最後まで理解に苦しむ現場もあります。特にオークション会場では、出された資料の読み込みと独自の事前調査、そして限界値の設定に購入資金の目処と、プロ落札者の出方を推測しながら落しどころを探る素人集団の奮闘ぶりが凄いです。オークションでついついムキになってしまう気持ちもわかります。人からゴミ扱いされようが、自分にとっては宝物のような物が存在していることもわかります。ただ・・・10ヶ所全てがマニアック過ぎる現場なので、そもそもどのジャンルにも興味のないぼくにはつまらなかったです。(読む前に目次でわかるだろうって??)オススメ度:★★★☆☆(ちょっと内容がマニアック過ぎたので、普通かな。でもそのジャンルに興味のある方が読むと面白いかも)【送料無料】テッカ場
2011年02月02日
コメント(0)
-

「寺門ジモンの取材拒否の店」を読みました
雪のようにふわふわでソースに溶けるキャベツ、芸術的コロッケパン、日本一予約の取れない高級ステーキ、宝物のようなドーナツ、「表3秒・裏3秒」の悶絶焼肉、59年間変わらない煮込み、女性ウケ必至の薫り高き路地裏ピザ、最後の晩餐にしたい牛テールおじや、“肉好きの聖地”が誇る刺し身。テレビ・雑誌でほぼ見たことない究極の30店を寺門ジモン氏が紹介します。本書の活用方法として「気になるお店があれば行ってみたいなぁ~」という気持ちで読むのであれば、本書はあまり活用できないかもしれないです。なぜならば、本書で取り上げているお店の半分以上が高級店だからです。リーズナブルなお店かな?と思えるお店は、店構えがモザイク写真だったり、所在が都内某所だったり。コースで15,000円前後って・・・そりゃぁ美味いに決まってるでしょう(笑)ただ、確かに本書で取り上げているお店は他のメディアではお目にかからない秘密のお店ばかりです。そしてどのお店も美味しそう(^o^)。各店舗毎の最初のページに丸々1頁を使って”ドカーン”と掲載している料理の写真を見ただけで、かなりの食欲増進作用があります。既に記しましたが、ジモン氏一押しという料理の写真がモノクロだったり、料理や店構えの写真がモザイクだったり(モザイクにするなら掲載しなければ良いのに)と若干残念な画像も所々にはあるものの、”落ち着くお店に落ち着かない芸人”がいるというギャップがその残念さをカバーしてくれます。「これは間違いなく世界一だよ!」というコメントも多用し過ぎていて、どの料理がホントの世界一なのかわからなくなるのも難点ですが(笑)本書の冒頭「本書の読み方・注意事項」にも明記されている通り、本書を読むと、ジモン氏と一緒にお店を訪れた気持ちになれるし、実際にジモン氏と一緒に食事に行った際に感じる疲労感・面倒くささが味わえる。なんだか・・・わかるような気がしますね(^^;)良い食材を、腕のいい職人が、良い仕事をしたときに初めて”旨い”と感じる。そんなお店の食材についてのウンチクや、謎の調理方法などをとしっかり調査しているのがこれまた意外でした。(決して著者をバカにしているわけではないです)そもそもが取材拒否のお店ということで、ジモン氏自身も相当通ったんでしょうね。それぞれの人が、美味しいと思う食べ物は違うかもしれないけれど、人が美味しいと思うものって、最終的には子供のころに食べた懐かしい味に戻るんじゃないか、と著者は言いますが、確かにそうかもしれないですね。そんなぼくは、いまだにハンバーグとナポリタンが大好きです・・・(子供かよ)昔なつかしいコッテコテのナポリタンを出してくれるお店、なくなっちゃったなぁ~。オススメ度:★★★★☆(少しオススメ)【送料無料】寺門ジモンの取材拒否の店
2011年01月31日
コメント(0)
-

「銭湯の女神」を読みました
切なくも騒々しく、温かい街から戻ってみれば、異和感のなかに生きる私がいた。それは、自分の存在そのものが異物になってしまったようだった。現在の東京を象徴する両極、銭湯とファミリーレストランを周遊する暮らしから芽生えた思いを、著者(星野博美さん)の鋭い観察眼と端正な文体で描いた39のエッセイです。香港で暮らしたことのある著者は、香港という比較の対象が一つできたことにより、日本において今まで当然だと思っていたことが当然でなくなり、それまで何の疑問も持たなかったことに疑問を抱くようになったそうです。著者が何よりも愛する銭湯とファミリーレストランでの出来事や、フラッと散歩しながらの出来事が、確かに言われてみればの疑問と謎のオンパレードで著者の鋭すぎる指摘がもの凄く新鮮に感じてしまいます。ほとんどが集団行動で、一人でいられないファミリーレストランの客に「あなたは一人になれないの?」と懸念を感じつつ、銭湯の個人主義者達に安堵する。いつまでもだらだらと携帯電話で喋り続ける人に「時間を無駄にするな!」と思いつつ、無駄の動きを見せない、まるで機械仕掛けの人形のように秒刻みで合理的に動く、銭湯のお客に職人芸の潔さを感じる。流行の服や最先端の携帯電話で武装する若者に「お金を大事に使いなさい!」と言いたくなりつつも、不必要な贅沢を一切排除した銭湯の客を見て安心する。単に銭湯好きなだけだろう。と言ったらそれまでです。生まれたままの姿になり、人間の本能として動いている銭湯の人々と比較しているところが面白いんです。またそんな著者の純粋な気持ちや苦悩がとてもよくわかるような気がします。人生全てがプラスとマイナスで成り立っている、と常日頃感じているぼくですが、電子メールや携帯電話といった便利な道具を手にするたびに、膨大な時間と手間を省けるというプラスがある反面で、相手の感情を読み取る能力を基礎としたコミュニケーション能力の欠如というマイナス作用も起きているのではないかと思います。それはまさに著者が断言しているような「鈍感な人達が増えている」現象に直結しているのかな?いつもの当たり前の風景(当たり前と思う様にしている風景)を、ちょっと異様に感じる人がいるということが、同じ日本人として嬉しかったですね。日本とたいして離れているわけでもなく、顔も妙に似ている超多忙都市に暮らす香港人の生活スタイルが「日本とそこまで違うの?」という意外な一面も参考になりますよ。オススメ度:★★★★☆(少しオススメ)銭湯の女神
2011年01月28日
コメント(0)
-

「TVで放送できなかった超怖い話 あなたにも見える戦慄の心霊現象」を読みました
心霊研究の第一人者・中岡俊哉氏が、身も心も凍りつくような心霊・恐怖現象の全てを語る。さらに氏が所有する数万枚余の中から「これぞ本物!」と言える心霊写真の数々を厳選して一挙公開。“見える”“感じる”、霊界からのメッセージを体験できる驚愕の一冊です。引き続き怖い著書のご紹介となりますが、そうなんです、ぼくは毎年「稲川淳二のミステリーナイトツアー」に参加するほどの心霊マニアだったのです。(でも最近は話の内容が怖くなくなってしまったので、昨年から行かなくなってしまったんですけどね)そんなぼくが見つけた本書「TVで放送できなかった超怖い話」って、おいおい、マニアとしては気になるじゃないかぁ~! と読んでみましたが、ハッキリ言います。まったく怖くないです。いっそのこと「怖くないからTVで放送できなかった話」に改名した方が良いかと・・・掲載されている写真もなんだか胡散臭いです。”この部分に女性の霊の姿が!”と四角で囲んであってもなんにも見えなかったり、どうみてもたまたま人の顔に見えているだけの写真だったり。本当の怖い写真というものは、見た瞬間に「ゾッ!」とするものですよねぇ。それが本書にはまったくないのです。心霊体験談も同様で、だいたいが話の中盤で恐怖のあまり「ぎゃーっ!」と悲鳴を上げ、その後入院してしまったとか、仕事を辞めたとか、行方不明になったとか。本当にそんな人達いるのかな?少なからずぼくの周りには精神不安定になったり、行方不明になったりした人はいないのですが、皆さんの周りはどうでしょう?本を読むのがめちゃくちゃ遅いぼくですら、本書の後半は「これが速読術の元祖か?」と思える程の早さで流し読みしてしまいました。【参考】本書より心霊写真が公に認められるようになったのは、今から100年以上も前のことだそうです。ヨーロッパで、紳士や貴婦人を写真館で専門の写真技師が写したところ、実在しない死者の姿が写っていることが発見されたのが始まりと言われています。オススメ度:★★☆☆☆(あまりオススメしません)【送料無料】TVで放送できなかった超怖い話
2011年01月26日
コメント(0)
-

「テレビで報道された戦慄の霊現象 これを知ったら、確かめずにはいられない」を読みました
「プリンセスの亡霊か!?ダイアナ元妃の事故現場に霊の姿!!」「ニュースでも取り上げられた、映画に映り込んだ子供の霊!」「立て札を立てるほど危険!怪現象が続出するトンネル!!」他、マスコミで報道された戦慄の心霊・怪奇事件を一挙公開。大量写真と心霊スポット・マップを掲載しているので、恐怖現象の数々をあなた自身も体感できます。人々の中には、霊現象に遭いやすい人とそうでない人がいます。その理由は、その人が生まれつき持っている霊チャンネルによって、霊と交信しやすい人とそうでない人に分かれてしまうと言われているようですが。しかし、もし霊現象がテレビで放送されたとしたらどうでしょうか?本書では、ダイアナ元妃の事故現場に現れた霊の姿や、血で描かれた生首の絵をワイドショーにて放送中に目が開いた怪奇現象など、ぼくの年代前後の方々だったら一度はテレビで見たことのある怪奇現象が勢揃いです。そうなんです。霊現象が見えるか見えないかは問題ではないんです!!(そんな大袈裟なことではないんですけどね(^^;))知っていながらもやっぱり気持ち悪いし、その霊現象に纏わる背景を詳しく知ることにより、さらに気持ち悪さが倍増します。「座敷わらしを見た人は出世する」と言われて全国的に有名になった岩手県の「緑風荘・槐の間」は、残念ながら火事により緑風荘自体が焼けてなくなってしまいましたが、この宿に泊まった漫画家のつのだじろう氏が描き残していった座敷わらしの絵がまばたきしたのには、観た当時は驚きました。超人気宿のため、槐の間に泊まりたくても数年先まで予約が取れなかったようですが、泊まれもしないくせに「出生のために槐の間に一人で泊まれるか」を自問自答したぼくでした。でも実際問題として、あの人形だらけの部屋に寝ろと言われてもなぁ~(>__
2011年01月24日
コメント(0)
-

「フリーズする脳 思考が止まる、言葉に詰まる」を読みました
「・・・・・」(あれ?今何を言おうとしていたんだろう?)まるでパソコンがフリーズするように、不意に言葉に詰まる。度々思考が停止する。人や物の名前が思い出せなくなる。そういう「空白の時間」が増えている気がしないでしょうか?放置しておけば深刻なボケ症状につながりかねない“フリーズする脳”の問題を、臨床経験豊富な専門医が語る。現代人の脳に今、何が起きているのか。忙しすぎる仕事を抱え、身近にある便利で魅力的な道具(携帯やPCなど)を使い、普通に生活しているだけなのに人間は様々な事をしなくなっているということがよくわかります。そしていつの間にか記憶を引き出す力や情報を組み立てていく力、また組み立てたものを脳の中で保持しておく力、聞き分ける力などを低下させ、話している最中に脳がフリーズしてしまう。本書では、都内に「高次脳機能外来」を開設し、これまで何千人という方々のボケていく脳を診てきた医師である著者が、実際の臨床経験に基づいた「フリーズする脳」という状態を様々な角度から考察し、実例の解説を通してその分析の指針も示してくれます。執筆するにあたって、できるだけわかりやすく、専門的な用語を使わずに解説するよう心がけられただけあって、とてもわかりやすい内容です。長い期間をかけた高次脳機能の低下によるボケ症状も、その原因は悪い生活習慣の膨大な積み重ね。だから回復するのも一朝一夕にはいかないそうです。脳の原始的な機能として「ボケるようにできている」ことを事前に回避するためには、活動をある程度マルチにすることにより積極的に脳を訓練することが良いようです。いつも同じお店に行ったり、いつも同じ人と同じような会話ばかりしていませんか??「仕事は忙しい人に頼め」と著者は言いますが、ぼくも知り合いの公認会計士の先生にまったく同じアドバイスを受けたことがあります。毎日ぼーっと過ごしている人に急いでやらなければいけない仕事を頼んでも、ぼーっとしている人は脳の基本回転数が落ちているので、急に「忙しくしろ」と言われても脳が対応できないからだそうですが。「充電期間」と称して半年くらい休んで復帰してきたときに、むしろ放電してきたんじゃないかと思えるくらいぼんやりした人になってしまった芸能人の人達をみてもわかりますよね。社会的に非常に増えてきているとまで言われている「ボケの予備軍」とも言える、まさにそのレベルに自分が達してしまいそうか否かを判断するのにも良い著書だと思います。オススメ度:★★★★☆(とにかくたとえ話がとてもわかりやすいので、少しオススメ)【送料無料】フリーズする脳
2011年01月20日
コメント(0)
-

「南米ブラックロード」を読みました
ブラジルにはファベイラと呼ばれるスラム街がある。山肌にびっしりと建ち並んだバラック小屋に低所得者たちが暮らす一帯である。映画『シティ・オブ・ゴッド』の舞台になったことで、世界的にも有名になった。ファベイラに暮らす人々はその日暮らしの生活を送っている。ファベイラの中にはマフィアが乱立し、些細なことで争いが起こる。争いに用いられるのは、拳銃、機関銃などといった銃器であり、マフィアだけではなく、住人が巻き込まれ命を落とすことも多い。ブラジルといえば、世界でも有数の犯罪多発国家であるが、源流を遡ればファベイラに行き着くのだ。そんな恐ろしい街(ファベイラ)に挑んだのが著者、嵐よういち氏です。南米と聞いただけで「治安が悪い」「遠い」「物価もそれなりに高い」「暑い」というマイナスイメージが先行してしまいがちですが、この著書を読み、やっぱりイメージ通りだったということが確認できました(笑)。しかし著者は、そんな南米の魅力に惹かれてしまったそうです。それは人々の温かさ、ノリの良さ、女性の美しさ、そして何よりも刺激になったのは緊張感伴う”アウェー感”・・・今回は、世界屈指の犯罪多発地帯”ファベイラ”への潜入取材です。内容も3章構成となっており、第1章は「危ない南米旅行」、この章ではファベイラをはじめとした南米の危険情報について書かれています。とても華やかなイメージのある”リオのカーニバル”ですが、実は下流階級のお祭りだったって知ってましたか?お金を持っているブラジル人は、カーニバルが騒々しいということからお祭り開催時にはカーニバル休暇と称して海外へ飛び出してしまうそうです。意外でしたね。今までのイメージが崩れていく・・・第2章は「南米の夜遊び」、この章では南米各国の夜遊びについて書かれています。この章はドラッグあり、売春ありの想像通りの内容です。家族旅行を主とするぼくには、興味はあるけど関係ないですねぇ~。第3章は「差別の現状」、この章では多くの旅行者が味わっている差別について書かれています。差別と言ってもさまざまですが、南米では「チーノ攻撃」が多いようですね。「オーイ、チーノ、チーノ、アホ!」なんてね(-_-)(そもそも”チーノ”とは、チャイニーズの略だそうですけど)かなりの貧富の差があるにしろ、読んでいて哀しくなってきます。そして、他民族が同居する日本という国がつくずく他国の人(外人)に対して優しい国であり、やさしい人の集まりだなぁ~と心底感じてしまいました。危険信号がピコピコしていても、取材で行っているということから「さらなる一歩前進」を余儀なく実行するところが、気楽に読んでいる読者としては面白いです。さらに今回の旅は、著者のクセのある知人達が危険な旅をそれなりに盛り上げてくれます。国境が陸続きの国は、治安が「良くなった」とか「悪くなった」とか言っても、結局は犯罪者の締め付けが強くなれば新しい狩り場を求めて移動しているだけのことなので、治安の善し悪しは一時的なものなんでしょうね。やっぱりぼくは一生行かないと思います。南米は。コワいコワい。オススメ度:★★★☆☆(今回は著者より友達の方が危険な活躍をしているので、普通かな)【送料無料】南米ブラックロード
2011年01月18日
コメント(0)
-

「タクシー運転手にきいたコワ~い東京の話」を読みました
東京のコワ~い話はタクシー運転手がいちばんよく知っています。本書は著者である小菅宏氏がタクシーに乗るたび、運転手に聞いてメモし、また主なタクシー会社にアンケートを依頼してベテラン運転手から回答してもらった話を元に、その運転手からさらに詳しく取材してまとめた東京のコワ~いスポットの決定版です。上野の山周辺、青山墓地周辺、池袋サンシャインビル周辺、渋谷道玄坂周辺、その他新しい都市伝説の始まり、江戸から現代へ、死者・敗者の怨念がさまよう魔界都市・東京。大都会東京の「ふしぎ現象」を目撃したり、あるいは出逢ったりした体験談が妙に現実感を帯びるのは、誰もが持っている「怖い物見たさ」という期待感の表れだと思っています。そして一般の人よりはるかに行動範囲が広く、深夜まで車を走らせることもごく普通の仕事であるタクシー運転手の怖い体験談となれば、気になりますよねー。本書の1章「現在最もコワ~い東京魔界」では、縁を知ることでそこが魔界として現象している意味を知ることができます。2章「時空を超えてコワ~い江戸魔界」では、当時その地で何があったのかを知ることで、現代まで続いている過去からのメッセージがわかります。中でも東京の超優良一等地、大手町に奉ってある「平将門の首塚」。GHQをも撃退したと言われる日本で最大最凶の怨霊と言われているだけに、ここの怪しさだけは別格ですね。会社からも近いのでちょっと行ってみたい気もするのですが・・・ちょっと怖いなぁ(>_
2011年01月13日
コメント(0)
-

「おみごと手帖」を読みました
あっちでオバマ、こっちで鳩山政権誕生。でもやっぱり注目はWBC!事件、映画、演芸、本、スポーツの話題とともに激変の一年を振り返る、中野翠さんの痛快コラムです。本書は、2008年11月から2009年11月の1年間に著者が感じたこと、考えたことをまとめた「手帳」です。あらためて本書を読んでこの1年間を振り返ってみると、色々ありましたねぇ~。定額給付金から始まり、WBC、北朝鮮のミサイル騒動、読み間違えの麻生政権、スマップメンバーの全裸泥酔騒動などなど。そしてこの著者の本を何冊か読んでまったく飽きないのはなぜか?ということにやっと気がつきました。不思議に思うことやムカつくことなど、ぼくと感性が同じなんです。また著者の言い回しが面白い!! 女性ならではの雰囲気を全面に出しながらもかなり鋭い視点で世の中の様々な事を見ています。本書で取り上げている内容も、メディアを騒がせたニュースや映画・本・落語などまさに様々です。その中で”特に”共感を持った話題を3つ程ご紹介します。まず一つ目は「定額給付金」。生活支援の一策として「お金あげるから何か買えよ!」と考案されたこの給付金ですが、給付金とは言いつつも、もともとはこっちが納めた税金じゃないかよ!!(コメントが短くてゴメンナサイ)二つ目は「落語」。落語と言えば「おやじ臭いなぁ~」と今まで感じていたぼくですが、真剣に聞いてみるとこれが面白い!あれだけの長い話を原稿も見ずにスラスラと喋る事にまず驚きます。まさに江戸から伝わる日本の文化ですからね。CDで聞くだけでも面白いのか、DVDで観た方がより面白いのか、どちらを買うべきか悩んでます。(よくよく考えたら、自分がおやじになってたということです。はい)最後の3つ目「四角問題」。なんだかわかりますか? TV番組の画面の隅にタレントたちの顔面リアクション映像が映し出されるあの小さな四角い小窓です。あの割り込み小窓、ウザくないですか?目障りじゃないですか?不快極まりないのについつい見てしまう自分に怒りを感じてしまいます。タレントの反応なんてどうでも良いでしょう・・・感じ方なんて人それぞれなんだから。著者と同じ愚痴でした。(^^;)オススメ度:★★★★☆(少しオススメ)【送料無料】おみごと手帖
2011年01月11日
コメント(0)
-

「素人バカ自慢」を読みました
自分のバカ、家族の莫迦、友達のBAKAを自慢するボー大な投稿の中から、「権威」であり著者の高橋春男がセレクトした全国バカ話大全500選。全編、泣かせるぜ、のコメント&バカ度診断付き。初めから最後まで、全国から投稿されたバカ話が満載ですが、面白い話は少しだけ。ほとんどつまらない話の羅列で飽きてきます。一つ一つの話に付加している流れ作業的な著者のコメントが、これまた輪をかけてつまらないです。でも、せっかくですので500のバカ話からぼくがチョイスした、面白い(と思った)話をご紹介します。初めて海外旅行に行ったときのこと。入国審査で英語がまったくダメという夫は「パーパス?(目的は?)」と聞かれて”パンパース”と聞こえたらしく、後ろにいる私に大声で「うちはムーニーちゃんだったよなぁ」と尋ねてきた。こんなクスッと笑える話は少しだけ(>_
2011年01月06日
コメント(0)
-

「謀殺下山事件」を読みました
新年あけましておめでとうございますm(_ _)mいつもお立ち寄り下さっている方々の足跡がなによりの励みになりますので、今年もよろしくお願いします。(^_^)昭和24年7月6日、午前零時20分頃、東京郊外の常磐線・下り線レール上で中年男性が列車に轢かれた。初代国鉄総裁・下山定則氏である。総裁は5日の朝、車で自宅を出て日本橋・三越に立ち寄ったあと消息を断っていた。その日は、国鉄従業員10万人の大量首切りが発表された翌日であった。総裁は自殺したのか?殺されたのか? その真相はいまだ解かれぬ謎のままである。本書は、新聞記者だった著者(矢田喜美雄氏)が真実を追究し書き上げたドキュメントです。総裁の死をいったいどう判断すべきなのか。一人の人間の命が終わりを告げた時、それが自ら命を絶ったものと、他の人の手で命を絶たれたものではまったく対立した死因であるため、この総裁の死の謎をめぐって新聞、報道、学者、捜査官たちの間に広まった自殺、他殺の両派に分かれる対立論争は、一人の人間の死をめぐっては前例のないことだったそうです。事件当時、朝日新聞社会部記者だった著者は、偶然なめぐりあわせでこの事件の鑑定作業に協力することになったのですが、その結果として一つの絶対的な結論を導き出すことになります。それは「他殺」。当時最先端の薬剤だった、血液に反応し発光する”ルミノール液”との出会いがこの事件を他殺説に導いていったとも言えます。轢断現場より手前数百メートルにわたって点々としている総裁の血痕や、その逆に轢断されているにもかかわらず血痕がまったく付着していなく、血痕のかわりに大量のヌカ油が付着していた衣類。「総裁を列車で轢かせる計画が進められている」ということを事件の数日前にタレこんできた韓国青年の存在からも、この事件がある組織による計画的な犯行だったことがわかります。さらに数多くの目撃者や関係者からの供述からおかしな点を排除し、事実に近い話のみを著者独自の視点でまとめた結論を、他殺と呼ばずして何というのでしょうか。事件直後にあっさり「自殺」と断定した警察も、実は苦しかったのかもしれないですね。(この事件はアメリカが絡んじゃってますから)最後には、事件から14年目にして「運び屋の仕事を請け負ったけど、運んだのは実は総裁の死体だった」という男まで登場します。(当時、死体を3人で運ぶ際の「各人の死体の持ち位置図」が妙に気持ち悪いです)本書では、総裁が死体となって発見されるまでの詳細な足取りや、関係者からの事情聴取、そして著者自らが見つけた数々の科学的データ(顔の傷、轢断現場の散乱箇所及び血痕箇所、血液データ等)が記載されていますので、それだけで他殺説としての説得力を持っています。これでぼくの中でモヤモヤしている未解決事件の一つが解決したような気分です。やっぱり、他殺だったかぁ~(>_
2011年01月04日
コメント(0)
-

「神戸大学院生リンチ殺人事件 警察はなぜ凶行を止めなかったのか」を読みました
2002年3月4日未明、神戸市西区の団地敷地内で当時27歳の神戸商船大学院生がまったくの言いがかりから暴力団員たちに暴行を受け拉致される。通報で現場に駆けつけた警察官たちは、なぜか被害者を捜索せず暴力団員に言われるがままに引き上げていく。その後延々と続いた凄惨な暴行の果てに、被害者は生命を絶たれたのだった。明らかな異状を目の前にしながら、警察はなぜ何もしなかったのか。納得できない被害者の母親は、やがて警察の責任を求めて国家賠償請求訴訟を起こした。そして2006年1月、最高裁によって警察の非が全面的に認められる。警察を相手取る国賠訴訟は決して勝てないと言われてきたが、それを覆す初めての画期的な判断だった。本書は元警察官(黒木昭雄氏)の視点で事件を克明に検証し、ヤクザたちの暴行現場で何もしなかった警官たちの理不尽なその行動の謎や、国賠に勝訴した事件の全容を、元警察官ジャーナリストが明らかにします。警察現場を知る著者が、3年もの歳月をかけて取材し書き上げたのが本書です。長年警察現場に身を置いていた著者だけに、警察の仕組みや捜査態勢を熟知しているため、事件の存在を認知した刑事が何を考え、110番通報を傍受した警察官にどれだけの緊張が走るのかということなど、経験者でなければわからないことをとてもわかりやすく描き、警察組織に対するかなり鋭い指摘もこの著書の良いところです。もちろん事件そのものも悲惨極まりないですが・・・口の中はズタズタで、耳はちぎれかかり、顔は原型をとどめないほど腫れ上がっている。そしていたるところの表皮が剥がれ、2リットル近い血液が失われ、折れていなかった骨折はほんの数本。これが壮絶なリンチの結果殺されてしまった被害者(Uさん)の状態です。夜中に友人の車で送ってもらい、マンションの前で車から下りた所に「たまたま」マンションからイライラしながら出てきた暴力団組長と出くわしいきなり殴られてしまいます。しかし、逆にUさんとその友人に組み伏されてしまったその暴力団組長は、絶対に見せたくないぶざまな姿を加勢に来た手下に見られてしまったんです。最悪の事態です。組長が堅気に押さえ込まれているという情けない状況が、ヤクザのメンツに火を付け、その結果、警察官が認知するヤクザの常識を越えることになります。ただし、神戸西署の警察官が「ふつう」に活動していれば、Uさんの命が奪われることはなかったんです。つまり、あり得ない事が現実になってしまった。ではそのあり得ない事とはいったいなんだったのか。○事件現場から数百メートルしか離れいない交番の警察官が”二人揃って”仮眠していたこと。○最初の通報から警察官が現場に駆けつけるまで約17分もかかってしまったこと。(110番通報を受けてから警察官が現場に到着するまでの時間を”リスポンスタイム”といい、2001年の全国におけるリスポンスタイム平均は6分22秒)○信じられないような警察官の弱腰。○ヤクザはカタギに危害を加えても、絶対に殺さないだろうというまったく根拠の無い警察の思惑。その他まだまだ書ききれないですが、信じられないような警察組織の失態により、通算で7回もUさんを救出するチャンスを警察は逃しています。これはミスというにはあまりにも大きすぎる過ちです。そこには現場警察官の「怠慢」と、ヤクザに貸しをつくったあとの見返りを期待する警察官の「下心」。いわゆるヤクザ組織との「持ちつ持たれつ」というなれ合いがバレバレになっています。しかし「捨てる神あれば拾う神あり」で、敗訴率がほぼ100パーセントと言われている警察官と兵庫県を相手にした国家賠償請求訴訟に挑む3人の若手弁護士達の活躍は、かなり頼もしいです。でもね、殺すことはないですよね・・・オススメ度:★★★★★(かなりオススメ)神戸大学院生リンチ殺人事件
2010年12月27日
コメント(0)
-

「サギ事件ファイル」を読みました
本書では、平成になってから詐欺師が起した事件を一挙に公開。代表作となった振り込め詐欺を筆頭に、結婚詐欺、保険金詐欺、そして女詐欺師の事件など、仰天ニュースを平成サギ研究会がずらりとピックアップしています。詐欺師たちは、あらゆる知恵を動員して、演技力を磨き、臨機応変に騙しの現場を演出します。しかも周到な準備と繊細な注意力を持って、大まじめに取り組んでいるから始末に負えないのも事実です。もはや他人事とは言ってられないほど身近になってしまった詐欺事件の数々ですが、こちらとしてもあまりに無防備なのも考え物です。本書にてあらゆる手口を知ることで、事前に防御策を考えておくのも一つの知恵かもしれませんね。ただ、こうしている間も詐欺師たちは、日々進化し工夫を凝らしているのでしょうけれど。本書では、あらゆる種類の詐欺事件について各々2~3頁内とコンパクトにまとめていますが、事件の内容は新聞の三面記事のようにかなりかいつまんで書かれているので今ひとつ物足りないような気がします。事件そのものの詳細より、世の中にはびこっている詐欺事件を知る事が本書の目的なのかもしれません。2003年に起きた有栖川宮の祭祀継承者と名乗る夫婦の結婚披露宴詐欺事件も、当時はかなり笑わせてくれて、なおかつ本書でも取り上げていますが、この事件を思い出すたびに緊張した面持ちで式に参列していた石田純一氏を思い出すのはぼくだけでしょうか?数々の女性問題ですっかり有名になってしまった石田さんですが、きっと人柄は良いのでしょうね(^^;)しかし、各メディアや銀行をも巻き込んで「振り込み詐欺にご注意を!」と大々的に呼びかけているにもかかわらず、未だに振り込み詐欺の餌食になり、老後にと蓄えていた大事な貯金を何百万・何千万と振り込んでしまう人が絶えないというのはどういうことなんでしょうか?毎日毎日、新聞の事件欄を読むたびに不思議でならないです。オススメ度:★★★☆☆(普通かな)サギ事件フ...
2010年12月22日
コメント(0)
-

「女という病」を読みました
彼女たちは、醜く哀しい。殺人、詐欺、謎の失踪。ツーショットダイヤルで命を落としたエリート医師の妻、我が子の局部を切断した母親、親友をバラバラにした内気な看護師。殺した女、殺された女。際限ない欲望、ついに訪れた破滅。彼女たちは焼けるような焦りに憑かれて「本当の私」を追い求め、狂い、堕ちた。女性が主役を演じた「女の事件」の闇に迫る中村うさぎさんのドキュメントです。女の自意識は、それ自体が病である。これは、あなたの物語かもしれませんよ。容貌も、生い立ちも、境遇も、性格も、それぞれが違う13人の女たちの心境を突いた内容ですので、事件の内容そのものより、その事件を起こした主人公である「女」の物語です。ようやくみつけた王子様を親友に奪われてしまった女や、少女期の性的虐待によって「呪われた私」を背負わされた女など、殺された女、殺した女、世間を騒がせた女たちが起こした事件を振り返って見てみると、彼女達の弱さや愚かさは一体何が起因しているのだろう・・・と考えてしまいます。もっともっと生きがたい現実をきちんと受け入れて、敢然と生きている人達だっているというのに。著者は事件の詳細をつかみ、現場を丹念に歩いています。しかし、冒頭で著者自身が言う通り、その事件に関わった女と自分を重ね合わせることにより、著者の強い思い込みや過剰な深読みが大量に混じり、冷静で客観的な事件のドキュメントになっていないというのも事実ですね。当事者の想いと著者の妄想がごっちゃになって描かれているため、どちらの気持ちを描いているのかわからなくなる時もあるのがちょっと残念かな。オススメ度:★★★☆☆(普通かな)【送料無料】女という病
2010年12月20日
コメント(0)
-

「通販な生活 一生を1ギガで終えないための買い物学」を読みました
一生を1ギガで終えないためのヒガキ流買い物考現学。前書きより「なぜ通販なのか。正しい突っ込みである。よく考えてみれば了解されるとおり、現代人の生活は「生産と消費」で成り立ってきた。しかし同時に、私たちは最近「何かが大きく変わり始めている」ことにうすうす気がついている。ネット上のマーケットでは、ずいぶん前から「売る人と買う人」は分かれていない。もっと端的に言えば、結果や商品そのものではなくプロセスを楽しむ時代になった。」人はなぜ通販にハマるのだろうか!?メールマガジン「ガッキーファイター」好評配信中の著者が、テレビショッピング、ネット通販などを通して世の中を斬りまくります。みなさんはネットショッピングを活用してますか?ぼくはかなり活用してます。でも・・・結果は期待通りだったり、予想通りだったり。やっぱり他店で実物を見てから購入しないと、危険が危ないですね(笑)。一時期お気に入りだったタングステン。この金属はダイヤモンドに次ぐ硬さと言われているので、キズが気になる指輪やネックレスに良いかな?と、まずは店頭で指輪を購入しネックレスはネットで探したら、あったんですよ、適度な大きさのネックレスが。即購入してワクワクしながら届いた商品を開封したら、驚きました(>_
2010年12月16日
コメント(0)
-

「男の作法」を読みました
男のダンディズムを追求した著者、池波正太郎氏渾身の語りおろしです。本書は、生前の著者が編集部からの問いに答えるという対話形式の構成で、男の生き方や作法の教科書として語りおろされたものです。男というものがどのように生きて行くかという問題は、結局、その人が生きている時代そのものと切っても切れない関わりを持っているとも言えますが、その大前提をもとに、著者は「あくまでも自分が生きた時代の常識」として話すだけであって、今の若い人達に役に立つかどうかはわからないよ。と言っています。はたしてそうでしょうか?昔なじみのバーテンが自分で店を出した。そのお店は女の子がいないから安い。そこのカウンターの止まり木でカクテル二杯も飲んで、軽く食べてサッと帰る。いいですねぇ~。これはまさにぼくが常日頃、自分の中で理想としている飲み方です。その他、蕎麦屋や鮨屋でのエチケットなど、まさに粋なはからいが満載です。つまらないお店に毎日行くよりも、ちょっとでもお金を貯めていい店を一つずつ覚えて行くことが自分の身になるんだよ。う~ん、同感 m(_ _)m自分の人生が一つであると同時に、他人の人生も一つでるということ。だから他人との付き合いにおいては、時間がいかに貴重かということを常に意識していれば、約束の時間に遅れるなんて相手に迷惑をかけることはしないでしょ?って。またまた、同感 m(_ _)m「時は金なり」とも言いますからね。著者の一言一言が、とても味わい深いです。最近はこの方の生き方や著書がかなり注目されているようですが、亡くなってから人気が出るというのも、皮肉なものですね。オススメ度:★★★★★(かなりオススメ)男の作法
2010年12月13日
コメント(0)
-

「地獄のドバイ 高級リゾート地で見た悪夢」を読みました
無実の罪で砂漠の拘置所にぶち込まれる。ホモセクシャルに支配された国。鼻持ちならないオイルマネー成金たち。あまりに劣悪で低賃金の労働環境。高級リゾートなんてとんでもない、地獄のドバイを峯山政宏氏が暴露します。人口が120万人程度であるにも関わらず、人口11億人を超えるインドをしのぐ観光客と、ヨーロッパの大半の国を上回る外国投資を引き寄せているドバイですが、そんな一見優雅に見える国でも日本のマスコミが決して報じることのない負の側面を持っていたんですね。今や成金大国として世界的に有名なドバイで働く労働者たちが、どれほど劣悪な環境に置かれているのかはあまり知られていないようです。前編では、ドバイやUAEで散見することのできる非常識な問題を取り上げています。たとえばオイルマネー成金たちの素顔や労働者たちの過酷な労働環境など。後半では、ドバイという都市の裏側、特に日本人初となる著者がアブダビ中央拘置所へ送りこまれてしまった、あまりにも悲惨で矛盾だらけの体験を語ってくれます。勤めていた会社が倒産しただけで拘置所に送られてしまうって、信じられますか?ドバイという都市の偽らざる真実に、驚きました。以前掲載したブログにも書いた通り、仕事でアトランタに行った時に同じ業界のある人と仲良くなりました。その人が言った「ぼくの親戚がドバイに居ます」という一言で、ぼくを含めたコッテコテの日本人軍団は豹変し、ド~バ~イ!ド~バ~イ!とドバイコールを連呼しつつ、「是非、末永いお付き合いをm(_ _)m」と手をスリスリしながら連日飲み明かしたのですが・・・ハッキリ言ってその人、ケチなんです。会計になると、どうにかこうにか理由を付けて自分の勘定を安くしようとする。食べる物だって「これは食べるけどあれは食べることができない」とかいちいち面倒臭い。冷静に考えてみれば、親戚がドバイにいるからどうしたんだって話です(笑)。インド人みたいな顔だったけど、どこの国の人だったかは忘れてしまいましたが。適度な本の厚さのわりには紙が厚いので、サラサラっと読めますよ(^^)オススメ度:★★★★★(かなりオススメ)地獄のドバイ
2010年12月08日
コメント(0)
-

「人の砂漠」を読みました
一体のミイラと英語まじりの奇妙なノートを残して、ひとりの老女が餓死した。老女の隠された過去を追って、人の生き方を見つめた「おばあさんが死んだ」や、元売春婦たちの養護施設を取材した「棄てられた女たちのユートピア」をはじめとした8編のルポルタージュ。陽の当たらない場所で人知れず生きる人々や人生の敗残者たちを、ニュージャーナリズムの若き担い手(沢木耕太郎氏)が暖かく描き出します。砂漠を歩いていると、地平線の彼方にまでつづいているかのような白いまっすぐな道の傍らに、ただ石を無造作に積み上げただけの墓を見ることがある。往きに死んだ者と還りに再び会えるかどうかも知れず、しかし遊牧民は石を積む。人は誰しも、無垢の楽園から追放され「人の砂漠」を漂流しなくてはならない。アルベール・カミュ最後の作品「追放と王国」は、追放されてしまった人間の悲哀を多様な方法で描いたそうです。そして本書も、世の中から追放されてしまった人の砂漠の漂流者たちを様々な方法で描いています。一人の老女が死んでいた、しかし隣にはミイラが・・・を描いた「おばあさんが死んだ」。天皇に対する事件を起こした人々のその後を描いた「不敬列伝」。売春婦や精神病者などの養護施設”かにた婦人の村”を描いた「棄てられた女たちのユートピア」など、どの内容も著者のやさしさやあたたかさ、あるいは悲しさを取り入れてかなり詳細に調査し描かれているのですが、一つ一つの物語(もちろん実話ですけど)がかなり長いので、残念ながらどの話も後半は飽きてきます。もうその話はいいですから!って。「この話、あと何頁続くんじゃろか?」って度々不必要な確認をしてしまいました。「人の砂漠」を彷徨う人達・・・色々な人達がいるのは確かですが。オススメ度:★★☆☆☆(あまりオススメしません)人の砂漠改版
2010年12月06日
コメント(0)
-

「〈超訳〉論語 自分を磨く200の言葉」を読みました
多くの偉人たちから愛され、日本人の道徳観の柱とも言える『論語』。しかし“とっつきにくい”というイメージから、敬遠している人も多いのでは?本書は、論語の中から岬竜一郎氏が現代の荒波を力強く歩むための言葉を厳選し、そのエッセンスだけを読み解くことにより「どんな人からも学ぶことができる」「悩んでもどうしようもないことは悩まない」など、不朽の名著がかつてないやさしさで甦ります。世の中が乱れて住みにくくなると「論語」がもてはやされると言われています。それはなぜか?論語は、複雑な人間関係の中で人として何を守るべきか、その心構えと実践を説いた本であり、日本人の道徳観の基本であり、さらには自らの道徳実践の”ものさし”だからなんですね。ところが、論語は”儒教の聖典”と呼ばれ、政治家や経営者達が座右の書としているためか「難しい」というイメージが先行し、読む前から拒否反応が起きてしまう傾向もあるようです。そこで、論語で使用されている「漢文」をあえて使用せず、新しく現代語訳したのが本書なのです。確かに読みやすく、孔子の言葉もとても良くわかる様に編集されているのですが、漢文の論語を読んだことのある方にはかなり読み応えの無い著書になるかと思います。やっぱりある程度の漢文あっての論語なのかな?残念ながら、論語独特の「味」がまったく無くなってしまっているような気がしました。と、いいつつも気になった論語を一編ご紹介しましょう(^^;)~ 外見と中身のバランスがとれた人 ~内面が高潔な精神の持ち主でも、外面に表れた言動が礼を欠き、徳にそぐわないとその人は野卑な田舎者となる。反対に内面が下劣であるにもかかわらず、外面をうまくとり繕って美しくしている人は、これはちょうど心にもない美辞麗句をつらねた公文書のようだ。内面と外面がほどよくバランスのとれた人物を初めて立派は人といい、この状態を「文質彬彬(ぶんしつひんぴん)」という。これを一言で漢文にすると「文質彬彬として然る後に君子なり」となります。【参考】本書より論語とは・・・今から約2,500年前の中国で誕生した、孔子とその弟子たちによる「言行録」のこと。孔子の死後、孫弟子達が中心となって孔子の言行を忘れないようにと記録し、紀元前一世紀頃に統合整理され、今日の「論語」になったそうです。オススメ度:★★☆☆☆(あまりオススメしません、でも論語初心者にはオススメです)「超訳」論語自分を磨く200の言葉
2010年12月01日
コメント(0)
-

「日本の黒い事件 封印された恐るべき「真相」」を読みました
世間を震撼させた数々の事件、だが事件の真相は闇へと葬り去られてきた。あの事件の真相とは何だったのか。あの事件の背後ではいかなる力が働いていたのか。抹殺、封印された真相というパンドラの箱を開けた時、私たちが目にするのは、希望か、それとも絶望か?猟奇事件や怪事件などなど、この手の事件に関する本を読んでいてつくづく思うことは、正気のつもりでいるぼく達と、事件を起こす人達とは一体何が違うのかということ。そこには科学でも哲学でもまったく解明することのできない何かがあるのではないでしょか?真相を究明しているようなしていないような、一見ざっと書いているようで微妙に鋭いと、まるで週刊誌のような本書も、恐い物見たさをくすぐられるようでたまには良いですね。東京・広尾に自宅を建てた香港出身の女性芸能人。アイドルとしてデビューしてから数十年、変わらない片言の日本語で話す・・・ってこの人、どう考えたってアグ○ス・チ○ンでしょ?いまだに片言の日本語しか喋れないということの方が、事件性があるような気がしますけどね(笑)。そんな施主でもある彼女は、香港の風水師に従って自宅を建設するよう指示したそうです。それが後にとんでもないことに・・・土地を建てる時は、昔からその土地のしきたりを守るべきなんですね。コワいコワい。真偽のほどはさておき、興味深い内容もありました。それは、一連の凶悪犯罪において出てくる「竜」という文字。酒鬼薔薇少年Aが被害者の胴体を遺棄したのは「竜」の山。同少年が小学生女児二人を襲ったのも「竜」が台。茨城県で自衛隊ヘリと軽飛行機が空中衝突したのは「竜」ケ崎市。熊本県で女子大生が誘拐されたのは「竜」田町。そして島根の女子大生がバラバラにされ遺棄されたのは広島県の臥「竜」山。偶然とはいえ、薄ら寒いものを感じてしまうのはぼくだけでしょうか?オススメ度:★★★★★(かなりオススメ)日本の黒い事件
2010年11月29日
コメント(0)
-

「殺人データ・ファイル」を読みました
DNA判定、指紋検出、血液型鑑定。検死官が気の遠くなるような地道な捜査で追いつめた、殺人犯たちの残酷な手口と残された手掛りをヒュー・ミラー氏が描きます。法科学者の高度な技術と能力によって謎が解き明かさ、犯人が捕まった数々の犯罪事件について、事件関係者の生の声をもとに簡潔にまとめています。冒頭に掲載されているリアルな証拠写真にまず驚きますよ(>_
2010年11月24日
コメント(0)
-

「事件 1999‐2000」を読みました
通り魔、保険金殺人、警察不祥事、凶悪化する少年犯罪等、事件の現場から法廷までを事件ウオッチャーのベテラン二人(佐木隆三氏、永守良孝氏) が徹底的に解剖し、世紀末犯罪を読み解きます。この著書は、毎日新聞の編集局長(永守良孝氏)と佐木隆三氏が、新しく起きた事件や審理中の刑事裁判について語り合うという対談形式の内容構成になっていて、1999年9月から2000年10月までに行われた14回分の対談が収められています。情報のプロである新聞社の局長と、傍聴マニア兼作家の佐木氏の対談ということで、語り合っている事件数もかなり多く、またお互いの意見は流石に鋭いです。自殺願望があるにもかかわらず自分で死ぬこともできない「通り魔」や、少年法改正のきっかけにもなった17歳の少年達が起こした「少年犯罪」、また各メディアを総ナメにした「オウム事件」などについて、編集局長としての意見や感想に対し、佐木氏は裁判傍聴の様子や自身の意見で答えています。佐木氏と言えば、ぼくのブログにも掲載されている「復讐するは我にあり」(第74回直木賞受賞作)の作品イメージが強かったので、その点本書はちょっと物足りないかな?対談形式でなくても良かったような気が・・・オススメ度:★★★☆☆(事件の話題がコロコロと変わるので、普通かな)事件(1999-2000)
2010年11月22日
コメント(0)
-

「ひとりガサゴソ飲む夜は…」を読みました
熱帯の禁酒国でこっそり手に入れた、悶え苦しむ“秘密のビール”の味とは。南の無人島で食べた、ゼイタクな酒シャブシャブについて。初めて行った国で飲んだ酒に、破壊的ダメージを受けた痛恨の二日酔い。与那国島の巨大蜘蛛のようなヤシガニの絶品カニミソなどなど。一度は飲んでみたい幻のお酒の数々から、ちょっと遠慮しておきたいゲテモノオツマミまで、ありとあらゆる酒と肴を、縦横無尽に書き綴る椎名誠氏の極上エッセイです。人間が住んでいるところ、絶対に何かしらのお酒がある。この鉄よりも固い信念に基づき、著者が訪れた世界各地の食やお酒の文化をまとめたのが本書です。読んでいる最中に、必ずお酒が飲みたくなると思いますよ。その国に沢山ある食材からその国の代表的なお酒が造られているそうですが、考えてみれば当たり前のことだけど、改めて言われると納得してしまいますね。米が主食の日本は醸造酒、農業大国フランスはブドウからワイン、イギリスは大麦からウィスキー、サボテンの国メキシコはテキーラ、サトウキビの西ドイツはラム酒と。さらには日本人だけの確信として、モンゴル料理と思われている羊の焼き肉(ジンギスカン)はモンゴルには存在しないということ。中国には焼き餃子が無いということ。などなど。世界各国のお酒や食についての雑学も所々にサラッと入っているのがまたニクイですね。日本酒と言えば「おしゃく」がつきものですが、著者はこのおしゃくが面倒でしかたないそうです。ぼくもまったく同じ意見。それなりの理由でお猪口も小さくなっているんでしょうけど、接待などで日本酒になってしまったら最後、相手のお猪口に入ってる日本酒の量が気になって落ち着かなくなってしまいます。そして「どうぞどうぞ」と注ぐ・・・「そんなに飲むならもっとデカイコップで飲めよ!!」と心で叫びながらね(笑)。とりあえず、日本酒はおいしいけれど接待の時は非常に面倒くさいお酒だ、という話でした。この著者の本は初めて読みましたが、語り口は村上春樹氏のエッセイを思い出させてくれます。村上春樹氏のエッセイが好きな方には、このエッセイはまさに極上エッセイになるはずです。そして、週末は深夜までひとりガサゴソと飲んでいるぼくにぴったりのエッセイでした。【参考】本書より平均的な人間が18歳ぐらいから70代まで生きる中で、毎日ビールの大瓶を2本飲んだとしてその総量を計算すると、25メートルプール1杯分になるそうです。この量が、かなり多いと驚きましたか?それとも意外に少ないと思いましたか??オススメ度:★★★★★(かなりオススメ)ひとりガサゴソ飲む夜は…
2010年11月17日
コメント(0)
-
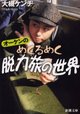
「オーケンのめくるめく脱力旅の世界」を読みました
「何?それは一体どんなだ?んー、行けばわかるさ」ひなびた温泉街に伝説のロックミュージシャンを探し、熱海ではスイカ割り、そして中国拳法勢揃いを見ようと一路栃木へ。思わず全身の力が抜ける、旅の日々。はたしてその先に、何があるのか?!行ったらいったい、どうなるのか?!オーケンこと大槻ケンヂ氏の、笑えあり、ちょっとしんみりありのエッセイ集です。本書の内容は、まったくのタイトル通りが半分、残りの半分は脱力しているようなしてないような・・・それがまた味があって面白いのですが。ひなびた温泉にストリップを観に行ったり、失神すると言われている激辛カレーを食べに行ったり、女性と熱海秘宝館に行ったり、さらには男同士でマザー牧場でうたたねをしたりと、脱力系のダラ~ンとした超ゆるゆる旅を詰め込んでいます。この著書を書かれた時の著者は、タイで食べた「マジックマッシュルームオムレツ」が原因でパニック障害となり、数年間に渡るその発作の不安からようやく復活し、平穏な日々を取り戻そうと奮闘している時期だったそうです。でもその病状が本書に出ているかというと、まったく感じませんね。いきなり第二章では酔拳を見に行ってるくらいですから(笑)。オーケンならではのムフフ(^^)と笑える内容で、ゆるゆるとした心地よさによりサクサク読めますよ。オススメ度:★★★★☆(少しオススメ)
2010年11月15日
コメント(0)
-

「事件のカンヅメ」を読みました
ドブ川に浮かんだ大枚は誰のもの?「夫、募集」の広告に誘われた男の悲惨な末路は?“火曜日の放火魔”の正体って?うーむ、って奥が深い。村野薫氏が集めた奥が深~い三面記事に掲載された事件の数々です。事件は事件でも、新聞の「尋ね人欄」を使う意味ありの人々についてや、誘拐犯達の身代金事情、ハイジャッカーの心理など、新聞を読んでいても普段あまり意識したことのない事件の「裏」に焦点を絞り、それぞれ類似の事件でジャンル毎にまとめ、著者独自の分析を行っていますので他の著書にはない新鮮さがありました。本書のタイトル通り、色々な事件が詰まったカンズメのようです。似ているようで微妙に似てなく、似ていないようで似ている事件って、こんなに起きてたんですね。特に誘拐犯については、松本清張の「点と線」や名画「天国と地獄」などからヒントを得て実行していることが多く、賢いのか単純なのかわかりませんが。犯罪小説などは、作者が考えに考え抜いた犯行のカラクリをサラリと流用されてしまったら、作者としてはどんな気分なのでしょう。意外と嬉しかったりして・・・(>_
2010年11月10日
コメント(0)
-

「獄窓記」を読みました
そこは「塀の中の掃き溜め」と言われるところだった。汚物にまみれながら、獄窓から望む勇壮なる那須連山に、幾重にも思いを馳せる。事件への悔悟、残してきた家族への思慕、恩人への弔意、人生への懊悩。そして至ったある決意とは。国会で見えなかったこと。刑務所で見えたこと。秘書給与事件で実刑判決を受けた元衆議院議員の山本譲司氏が陥った、永田町の甘い罠と獄中の真実を描きます。生活に困窮していた著者は、購読紙意外の新聞を読むために新聞の拾い読みが週間として身についていたそうですが、路上生活者の話を聞こうと隅田川沿いを歩いている時に拾った新聞に掲載されていた「衆議院議員 菅直人 政策スタッフ募集」という求人広告が、後の人生を大きく変えることになります。やはり努力だけでは変えることのできない「運」というものが人生にはあるのでしょうか。しかし、順風満帆な議員生活に釘を刺したのは「秘書給与詐取」を根拠とした検察による逮捕・起訴。数々の国会議員が裏で行っている「秘書給与詐取」とはいえ、法に違反していることであることは明確ですねただ、またしてもここで「運」というものが・・・「運」が悪かった。そして著者は、自分の起こした事件や獄中での経験について、記憶が薄れぬうちに文章として書き留めておくということが、今後の自分に対する有効な戒めになるという気持ちで書いたのが本書だそうです。事件の概要や東京地検特捜部からの呼び出し、新米受刑者としての入獄、鬱状態にもなりかけた出所までの日々と、433日にわたる獄中生活をかなり詳細に描いています。刑務所の掃き溜めと言われている寮内工場の指導補助に任命されたことにより、障害者という受刑者の世話を行うことになりました。(清水健太郎もやっていたそうですが)世話する相手は痴呆症、自閉症、知的障害、精神障害、それに同性愛者などなど・・・あったんですね、刑務所内にそんな強烈な工場が。出所の日が僅かながら見えてきたことにより、安定した精神状態に戻りつつも「出所後の自分は、周りの人間にどんな目で見られるのだろうか。生計を立てるに足り得る仕事を見つけることができるのだろうか。前科者を父に持つことになった息子はまともに育ってくれるのだろうか。」という悶々とした不安がつきまといます。出所の日がまったく不明な無期懲役者達は、一体どんな精神状態なのだろうと想像してしまいました。マスコミ報道によって、段々と容疑者の悪人象が作り出されていくというマスコミ操作も、もし自分が容疑者になったら?と想像すると恐ろしいです。【参考】本書より― 喜びを人に分かつと喜びは二倍になり、苦しみを人に分かつと苦しみは半分になる ―ドイツの詩人、ティートゲの言葉だそうです。良い言葉ですね。オススメ度:★★★★★(かなりオススメ)獄窓記
2010年11月08日
コメント(0)
-

「キム兄の人間設計図 相手を不快にさせない正しい間違え方」を読みました
人々の会話や行動の中にしばしば見られる、さまざまなコミュニケーションタブー。これらを決して見逃さず、「考えられへん!」「ありえへん!」の口癖とともに、痛快に一刀両断することで知られるのが、本書の著者であるキム兄こと木村祐一氏。そのキム兄が初めて語った、究極のマナー論は、上司への発言、接客の基本、後輩の育て方など、あらゆるビジネスシーンに即活用可能。この本を読めば、どうすれば相手を不快にさせることなく、スムーズな人間関係を築けるのかが、まるで一枚の設計図を目にしたかのように間違いなくわかります。電話をかけた相手に「今、大丈夫ですか?」と聞かないでおこう協会の副会長を務める著者ですが(ちなみに会長は松本人志さんだそうです)、この著書では、普段キム兄が感じている、人に不快感を与えてしまう50の出来事を列挙することにより、「大人だったら人の気持ちをもう少し考えてあげて」という思いが入っています。見た目はゴッツイけど、意外と細やかな方なんですね。でも言っていることはかなりうなずけますよ。まさに「人の振り見て我が振り直せ」という感じです。他人の欠点というものは目に入りやすいものの、自分の欠点に気がつくのはなかなか難しいですからね。そんなキム兄も、いちばん身近な「社会」は、やはり家族だと断言しています。キム兄自身も、お父さんの存在にかなり影響を受けたとのことですが・・・子供の人格が形成される上で、一番重要なのはやはり家族であり、親のしつけだとぼくも思います。レストランで騒いでいる子供の親を見ると、「この親にしてこの子あり」と最近つくずく感じますね。甘やかすことが「愛情」と、勘違いしてるんでしょうか?言ってくれれば、ぼくがすぐにひっぱたいてあげるんですけどね(笑)話が逸れましたが、章毎に挿入されている「キム兄の写真館」も、街にある無駄な看板や案内表示などの写真に対するキム兄のツッコミがまたイイ味出してます。この写真館だけでもかなり面白いです。オススメ度:★★★★☆(少しオススメ)キム兄の人間設計図
2010年11月04日
コメント(0)
-

「津山三十人殺し 日本犯罪史上空前の惨劇」を読みました
その男は三十人を嬲り殺した、しかも一夜のうちに。昭和13年春、岡山県内のある村を鮮血に染めた「津山事件」。入念な取材と豊富な捜査資料をもとに再現される、戦慄の惨劇。筑波昭氏による不朽のノンフィクションです。通っていた小学校始まって以来の秀才と目された青年が、自身が結核患者だという絶望感と、病気の自分を馬鹿にしていた部落民への憎悪、さらに本人の強烈な自己顕示欲により起こした日本史上空前の惨劇です。映画「八つ墓村」のモデルにもなった事件だということを、ご存知でしたか??黒の学生服を着て、地下足袋にゲートル。頭には二本の小型懐柔電灯を手ぬぐいで巻き付け、頭の両側から前方を目玉のように照射する。自転車用の箱形前照燈を紐で首から胸に吊り下げ、日本刀を左腰にさして紐でくくり、9連発に改造したブローニング猟銃を持って暗黒の中を向かってくる姿を想像してみて下さい。凶行時の犯人の姿を再現した写真も掲載されていましたが、かなり気味が悪いです。「二つ目の怪物に見えた」という被害者もいたくらいですから・・・被害者全ての家屋内の間取りや殺害場所などもの見取り図も付記され、犯行状況も詳細に記述されているのが生々しいです。その部落内で行われていた「夜這い」のために、真夜中にもかかわらず各々の家が戸締まりをしていなかったということも犯行を容易にさせた要因ではないかと思います。この事件は、最後に犯人が自殺してしまうため、まさに「死人に口なし」となってしまったので、生存関係者が犯人を悪く言うこともあり得るし、ましてや生存者が自分に不利な事を口にするはずもないので、部落の人々はこの事件に触れることを危惧するというタブーな事件と言われているようですが、その事実は、昭和50年に刊行された1,000頁を優に超える「加茂町史」の中においても、この事件について書かれた記事が僅かな記述しかないということでもわかりますね。余りにこの事件に関する情報が少ないため未解明のまま残された部分が多く、その真相は謎に包まれているそうですが、そんな現実を目の当たりにした事が、元新聞記者である著者が本書を書き上げることを決意した一因だったそうです。犯人が生まれた1歳から、事件を起こした22歳までの22年間の生い立ちをその歳毎に整理しているという手法もなかなか他の著書には無いまとめ方なので読み応えもあり、純情だった少年が、段々と憎悪に満ちた青年に変化していく様子も不気味ながらもよく表わされていると思います。オススメ度:★★★★☆(前半は昔言葉の羅列でかなり読みづらいですが、少しオススメ)津山三十人殺し
2010年11月01日
コメント(0)
-

「まれに見るバカ」を読みました
人の世に一定程度のバカがいるのは常識である。「浜の真砂はつきぬとも、世にバカの種はつきまじ」と。しかし、そうは知りつつも、平成の世にわが日本に次々とバカが異常発生している驚くべき事態をいったいどう考えればいいのか。性別も年齢も、収入も地位も関係がない。さらには有名人・無名人も問わない。なぜ、こうした事態がこの国に出現したのか?「バカ」の生態と由来とその現状をあますところなく伝え、読む人に不思議なことに、生きる勇気が湧いてくる勢古浩爾氏の「当世バカ」生態図巻です。自分の周りをみても、世の中を見渡してみても、感動的なことに正真正銘のバカはやはりいるものです。本書では、有名バカと無名バカ、全身バカと部分バカ、大人のバカと子供のバカ、要するに世の中に存在する全てのバカ諸君たちが集まっています。それでは登場している「バカの基準」とは何か。その基準はただ一つ! 著者の一方的な決めつけです。田嶋陽子、桝添要一、野坂昭如を三バカと断言し、相手が東大の教授であろうと、外務省の役人であろうと、著者が認定した場合はサッサとバカの仲間入り。読んでいて気持ちが良いくらいバッサバッサと毒舌で斬りまくっているので、余計なお世話ですが著者が夜道で襲われてしまうのではないかと心配してしまいました。「バカは隠そうとしても隠しと通せるものではない。バカは必ず目に見えて現れるのである。どんなに偉ぶろうと、口だけで立派な事を言おうとダメである、バカは当人のあらゆる細部に宿っていて、否応なく無意識のうちに現れてしまうのだ」そうです。そして著者の基準である「全身バカ」の定義。 1)とにかく自分のことだけしか考えていない 2)恥を知らない 3)自分の正しさを毫も疑わない 4)悪いのはすべて他人である 5)一見、もっともらしい言葉を口にする。 6)欲望を我慢できない 7)自分が助かるためには人を裏切るどうですか?まんざら間違えてもいないと思いませんか?ぼくの職場にもいますねぇ~、かなり一致している人が。でも7)の「自分が助かるためには人を裏切る」という基準はぼくもにも当てはまります。そりゃそうでしょ? そりゃそうですって。 なんて冗談です(笑)ぼくの好きな著者の一人、日垣隆氏と著者には独特な共通点があるような気がします。それは、圧倒的な知識を根拠とした絶対に相手には負けないという強さ。言い換えれば、日垣氏の著書が嫌いな方はこの著書を読んでも面白いと思わないかもしれませんね。【参考】新明解国語辞典よりバカとは・・・記憶力・理解力の鈍さが常識を超える様子。また、そうとしか言いようのない人。オススメ度:★★★★☆(少しオススメ)まれに見るバカ
2010年10月27日
コメント(0)
-

「イマイと申します。 詐欺を追いつめる報道記者」を読みました
「もう電話してくんじゃねえよ!」。悪徳業者の怒号が響き、電話ががちゃりと切られる。だがイマイ記者はひるむことなく、リダイヤルを続ける。奴らがボロを出し、降参するまで。現代日本に蔓延する、架空請求という名の詐欺。その巧妙な手口を白日のもとにさらすため、今日もイマイは、受話器を片手に追及を続ける。日本テレビの人気ドキュメント『報道特捜プロジェクト』を収録した、執念と笑いの激闘録です。被害にあっても声も出せず、辛い思いをしている被害者に代わり、日本国内どころか海外のどこえでも”徹底追求の旅”に出かけ悪と対峙する人気報道マン、イマイ記者の活動を記録した奮闘記です。この特集は、テレビで観ていてもハラハラ・ドキドキで面白かったですね。メディアというバックがあるからできるんじゃないの?と言ってしまえばそれまでですが、危険が伴うことにより素人では決して超てはいけない一線を、イマイ氏はのほほ~んと超えているということが、この特集が人気となった要因ではないかと思います。さらにテレビで放映され、本書にも収録されている悪徳業者との対峙は、会話を積み重ね、とてつもない数のフィルターを潜り抜けた業者のみ「これは放送できる!」とプロデューサーがGOサインを出した業者のみだそうですよ。「血の気の多い若い衆」や「これから行くから待ってろ!」「指詰めたろか?」などなど、これでもか!これでもか!という位、かなりいっぱいいっぱいになりながらも必死に次々とお決まりの脅し文句を出してくる悪徳業者に対して、あっけらかんとした口調にて対応しながらもリダイヤル攻撃という猛反撃に出るイマイ氏に、番組を観て知ってはいたものの、読みながらニタニタ笑ってしまいました。業者「お前これ以上電話かけてきたら、殴って拉致どころじゃないよ!もっと激しいことやっちゃうぞ。おめえ!」イマイ氏「殴って拉致するだけで十分激しいじゃないですか・・・」業者「おう!上等だ、おまえ!おまえも武器持っとけよ!」イマイ氏「何の武器ですか?」業者「・・・・・」こんな感じで(笑)【参考】本書よりイマイ氏の正体は謎に包まれているそうで、局内でもその素顔を知る人はわずかだそうです。干支も血液型も知られておらず、そもそも日本テレビの社員なのかどうかさえも、日本テレビ側は肯定もしないし否定もしないとのこと。そりゃっそうですよね。身元がバレたらかなりヤバイでしょ(>_
2010年10月25日
コメント(0)
-

「危ない世界一周旅行」を読みました
世界一周航空券が発売され、数十万円で世界一周の夢がかなうようになった。それに伴い、世界一周に旅立つ旅行者も増えたが、そこに危険がひそんでいることを忘れてはならない。ペルーで首絞め強盗に襲われ、南アフリカの凶悪都市ヨハネスブルグでは黒人集団の「狩り」に遭い、ブラジルでは南米美女に1000ドルを抜き取られた。世界では日本の常識は通用しないのだ。本書を読むことで、世界一周の「裏」も「表」も味わうことができる、宮部高明氏の危ない旅行記です。320日の旅行中に遭遇した災難は、強盗2件、スリ4件、暴力事件4件。世界各地で過ごした約1年という滞在日数を考えると、この件数が多いのか少ないのかはわかりませんが、自ら危険地帯へ足を踏み入れることを拒んだ著者ですら、これだけの事件に巻き込まれてしまっているんです。その反面、親切な人達との出会い、日本では考えられないような雄大な景色、歴史的な建造物・・・物を奪う人もいれば無償で親切をしてくれる人もいる。マイナスイメージよりもプラスイメージの方が自然と強くなるのか、海外旅行が止められない理由がわかったような気がします。アフリカ大陸で著者が感じたこと、それはこの土地の強盗も、スリも、詐欺も全てがハンターである狩猟民族。平和に生きてきた農耕民族の日本人がかなうわけがないではないかと。うまいこと言いますね。まさに身体に宿っている本能が違うのかもしれません。美味しいご飯をお腹いっぱい食べる。熱いお風呂に入る。暖かい布団で眠る。日本では普通の生活スタイルが、いつのまにか最高の贅沢になっている。一期一会の出会いもあった思い出深い国々の話も満載ですが、やっぱり日本という国が最高なんだなぁ~と、つくずく実感してしまうから不思議です。それぞれの国に対しての印象を「治安の良さ」「人柄の良さ」「物価の安さ」の項目別に5段階評価しているので、被害に遭いたくないと思っている人は、危険度を参考に被害を未然に防げると良いですね。言葉も肌の色も違う旅人の方が圧倒的に不利な海外旅行では、少しでも怪しいと思ったら逃げるべき。と著者は断言しています。世の中には「逃げるが勝ち」な時もあるんです。これからはぼくも、妻と娘達を残してでも必死に逃げることにします。(ウソです)【参考】本書より本書の巻末に掲載されている世界一周ベスト3の一部をご紹介します。『危険な国』 1)南アフリカ(ヨハネスブルグ) 2)コロンビア 3)ブラジル『二度と行きたくない国』 1)南アフリカ 2)モザンビーク 3) ブラジル※南アフリカ、コロンビア、モザンビーク、ブラジルには、ぼくは間違いなく行かないでしょう。(笑)オススメ度:★★★★★(かなりオススメ)危ない世界一周旅行
2010年10月14日
コメント(0)
-

「やがて哀しき外国語」を読みました
初めてプリンストンを訪れたのは1984年の夏だった。F・スコット・フィッツジェラルドの母校を見ておきたかったからだが、その7年後、今度は大学に滞在することになった。プリンストン大学滞在中、異文化にかこまれて感じた日本、日本人であることの違和感、そして2編の長編小説(「国境の南、太陽の西」「ねじまき鳥クロニクル」)を書きあげることになった。そんなアメリカでの生活を綴った村上春樹氏のエッセイです。1991年から約2年半にわたってアメリカ・ニュージャージー州プリンストンに滞在した間、当時の著者の心情や著者の周りで起きた出来事を「心情の記念写真」として綴ったエッセイです。英語小説の翻訳もこなし、海外にもかなりの間住んでいた著者ですが、実は英語を使って人と喋るのがかなり苦手だそうです。ちょっと意外でした。要するに「自分の思っていることを日本語ですらすらと口語的に表現できない人は、外国語をいくら熱心に勉強したところで、その言葉でもやはりうまくは話せないだろう」と言っています。以前掲載した「不実な美女か貞淑な醜女か」の著書、米原万里さんも同じ事を言っていました。まったく無関係なお二人が同じ事を言うとは・・・かなり説得力がありますね。やはり、母国語をきちんと習得するというのは大切な事なんでよ。それから床屋の話。著者が数年間悩みに悩んだ事が、お気に入りの床屋を探すこと。またこれが簡単な悩みのようでかなりの試練。1週間から10日程度の海外旅行しか経験のないぼくの様な短期旅行者は、今まで想像したこともなかったですね。旅先で髪を切るなんて。おそらく一生行くことのない他国の床屋ですが、そもそも日本人の頭の形というものが欧米人と違うということ、また、他国では日本人の様に器用なカット技術を持っている理容師が少ないそうで。う~ん、もしも床屋やヘアーサロンに行ったら、一体なんと注文すれば良いのだろう。そしてどんな髪型に生まれ変わってしまうのだろう。想像しただけでも恐ろしいですね。(>_
2010年10月12日
コメント(0)
-

「レジ待ちの行列、進むのが早いのはどちらか するどく見抜き、ストレスがなくなる心理術」を読みました
攻撃的な交渉者は?面接で採用されやすいのは?ダイエット効果のあるコースは?愛想笑いをしているのは?不倫しやすいのは?セックスのテクニシャンは?研究結果にもとづいた裏読み術を、イラストを使って解説した「こっそり知りたい」ことが一瞬でわかる内藤誼人氏の著書です。本書は「読者の”観察力”と”推理力”を養うための本」ということですが、心理学の本というよりは、ドリル形式で学べる問題集というような内容構成です。物事をきちんと観察(判断)し、そこから正しい結論を導き出すことができれば、日常生活のさまざまな場面において有利な行動をとることができるでしょう、ということですね。シャーロック・ホームズはこい言ったそうです「人間というものは、個人個人は不可解な謎かもしれないが、全体としてみると、数学的な正確さで予知できるものである」と。「十人十色」などという言葉がありますが、全体としてまとめると、統計的な確率にてかなりの部分まで行動が予測できるそうです。問題の中には「電車の中で、ストレスがたまる席はどこ?」なんていう設問もあります。他人が自分に接する場合に許容できる距離というものがると思うので、ストレスを感じるかどうかと言えば個人差があるとは思うのですが、やはり統計上ちゃんとあるんですね、自然とストレスになってしまう席が。ちなみにぼくは、座るだけでストレスを感じる場合もあるのでよっぽど疲れている時以外は立ってます。中には、座ることに対して異常な執念を持っているような人も見かけますが・・・「朱に交われば赤くなる」という諺もある通り、長年一緒にいるペットと飼い主は顔が似てくるという統計も出ているそうです。それはなんと長年連れ添った夫婦にも言えるとのこと。どうですか?あなたの隣に座っている奥さん(または旦那さん)は、自分と同じ顔をしてませんか?オススメ度:★★☆☆☆(なるほどねぇ~!と感心できる項目が少なかったので、あまりオススメしません)レジ待ちの行列、進むのが早いのはどちらか
2010年10月08日
コメント(0)
-

「探偵裏事件ファイル 不倫、愛憎、夜逃げ、盗聴…闇世界のすべて」を読みました
夫の愛人にナイフで切りかかった妻、母娘の涙の再会、大学助教授痴漢冤罪事件、ヤクザからの奇妙な依頼など、探偵生活40年の著者が経験した闇世界を洗いざらい明らかにする。ひと口に探偵と言っても、世界中にはホテル探偵、霊感探偵、コスプレ探偵など風変わりな探偵も存在していることから、この一冊で探偵業界の事情通になれる小原誠氏の著書です。欲しい情報が手に入った時の喜び、依頼人が喜んでくれたときの快感、調査の裏にある人間ドラマを垣間見た時の驚きなど全てを総合し、著者はこの仕事が面白くてたまらなかったそうです。まさに、天職とはこのことですね。本書は、探偵の仕事とはどのようなものか、実際にどんな調査をしているのかなどを、著者の経験談に基づき実像を明かしてくれます。続いて現在の探偵業界における問題点(悪徳探偵の見分け方)、業界事情、さらには元警視庁刑事の北芝健氏も執筆に加わり、刑事から見た探偵の存在や現職時代に出逢った一般には知られていない探偵、風変わりな探偵について語ってくれます。そして最後には、調査を依頼する前に知っておくべき調査料の話や、信頼できる探偵社の見分け方についてまで、全体を通してとても良くまとめられています。「ぼくがカツラだということを周りの人達が気がついているかどうか調べて欲しい」という笑えるけれども笑ってはいけないような依頼から、ストーカー調査まで、請け負う依頼はほんとうに多種多様で、次々と繰り出す実話がまた面白いです。しかし、男として生まれたことにより一番恐ろしいのが痴漢の冤罪。ブランド物欲しさに痴漢されたことを装い、40年以上真面目に生きてきた男の人生に、「迷惑防止条例違反という前科」と「辞めたくもない会社の強制退職」いう最悪のプレゼントを与えたくれた10代の女の子の話には、正直言ってムカッ!!!ときました。やっぱり電車に「男性専用車両」が必要じゃないかと・・・設置されたらされたでかなりむさ苦しいですけどね(笑)【参考】本書より探偵業務を要約すると、他人の依頼を受けて調査員が、1)聞き込み、2)尾行、3)張り込みなどの方法で調査を行い、特定人の住所、または行動について情報を収集し、その調査結果を当該依頼人に報告する業務をいう。また、探偵や興信所、調査会社にかかわらず、探偵業務を営む業者は、平成19年6月以降、全て探偵業法により届け出が必要となった。オススメ度:★★★★★(かなりオススメ)探偵裏事件ファイル
2010年10月06日
コメント(0)
-

「血滾ル三島由紀夫「憲法改正」」を読みました
消された憲法案、血滾る三島由紀夫憲法案、現憲法への問題提起と改正案、クーデター計画のまぼろしの四章構成。「天皇主権」「再軍備」「核武装」。30余年の時を超えて、松藤竹二郎氏によりいま禁忌の封印が解かれます。著者が自衛隊や楯の会へ取材を進めていくうちに、三島由紀夫が死の直前まで「憲法改正」にむけて情熱を燃やしていたことを知ることになります。そして、クーデター成功後にはその新憲法を宣布する予定であったことも・・・テレビでは何度も放映されていますが、かつての陸軍士官学校である自衛隊市ヶ谷駐屯地での割腹がなかったら、日本の何かが変わっていたような気もします。三島由紀夫は、カナダ、スイス、ノルウェーなどの民兵組織について様々な方面から研究し、日本にも民兵による国土防衛組織を作れないものか、と考えていたそうです。しかし、当時の「敗戦国日本」という社会情勢により、当然のことながら同調する者はなく、ついに一人で「楯の会」を結成するに至ったのです。いつまでもアメリカ軍に頼っていてよいのか。日本の国土に、あたかも占領軍のような基地を、沖縄をはじめ列島各地に存在させておいてよいのだろうかと。日本人として、日本という国を自分達だけの力で守るためにも、三島由紀夫は一人で考え、悩んでいたことを思うと、何か切なさが伝わってくるようです。今更ですが、鳩山くんがやらかしてしまった「普天間問題」をみれば、三島由紀夫が心配していた事が数十年たった今、現実に問題となっているから驚きますよ。楯の会の「血」がながれている憲法改正案は、まさに三島由紀夫の「遺書」だったんですね。中国からの不当な圧力に負け、誘拐犯養成国である北朝鮮に気を使う日本政府にイライラする毎日ですが・・・【参考】本書より少々過去のデータとはなりますが、2003年の世論調査によると、憲法改正を望む国民は6割にも達し、「日本は核を保有してよいか」という問いに対して、実に53%の人が「イエス」と回答したそうです。(読売新聞調査)日本は、世界において唯一の被爆国であり日米安保条約も存在するため「核武装など論外」というのが長年の常識だったのですが、今の北朝鮮を見てもわかる通り「核保有」が対外においては世界最強のカードになるということも、事実なのです。オススメ度:★★★★★(かなりオススメ)
2010年10月04日
コメント(0)
-

「毎日一人はおもしろい人がいる よりぬき」を読みました
街ですれ違った人からハリウッドスター、ニュースになった悪者まで、とにかく「人間大好き!」という著者が見た、驚きと感動の人々が続々登場。人気コラムニスト中野翠さんの鋭くも優しい眼を通して綴られた人間観察日記です。映画を見たり、本を読んだり、落語を聞いたりと、色々な事が好きな著者が一番関心のあること、それは何を隠そう人間観察だそうです。人間社会は、滑稽で、奇怪で、謎めいていて、興味深い。確かにそうかもしれませんね。この著書は21世紀の最初の年でもある2001年の1年間に、著者が出逢ったり「ん?」と感じた人々について日記形式にまとめています。実はぼく自信も(ちなみに妻も)「自称人間ウォッチャー」です。街を歩く人達をかなりの時間見ていることができます。せかせかと歩く人、季節外れの服装をしている人、見ていて不愉快なカップルやバリバリのカツラな人などなど、見ていて飽きないですね。もしかすると親愛する人が亡くなっていたり、離婚していたり、子供が不治の病だったりと、平然と歩いているように見えても人それぞれ色々な思いを胸にしているんだろうなぁ~、なんて思いながら見てしまう時もありますけど。本書でも取り上げていますが、その人独特の「話すクセ」も妙に気になりますね。「逆に・・・」「逆に・・・」と言いながら、内容的には全然逆になっていない人。「要は・・・」「要は・・・」と言いながら、ちっとも話を要約していない人。「変な話・・・」と言いながら、別に変な話ではない人。(←これはぼくが追加しました)「早い話・・・」と言いながら、特段早くもなっていない人などなど。いますよねぇ~(笑)そんな言葉のクセによって、そのクセが気になりだすと肝心な話の内容が耳から入らなくなってしまいます。こんな言葉のクセがある方、早急に改善しましょうね(笑)。街中の見ず知らずの人物から有名人まで、とにかくこの著者の着眼点はおもしろいです。しかし、観察している対象人物は多種多様なのですが、落語や歌舞伎に関する事柄が多かったので、残念ながらどちらもあまり興味の無いぼくとしては残念ながら★は3つ。オススメ度:★★★☆☆(普通かな。でも、映画や歌舞伎が好きな方にはオススメです。)毎日一人はおもしろい人がいるよりぬき
2010年09月29日
コメント(0)
-

「これからの「正義」の話をしよう いまを生き延びるための哲学」を読みました
哲学は、机上の空論では断じてない。金融危機、経済格差、テロ、戦後補償といった、現代世界を覆う無数の困難の奥には、つねにこうした哲学・倫理の問題が潜んでいる。この問題に向き合うことなしには、よい社会をつくり、そこで生きることはできない。アリストテレス、ロック、カント、ベンサム、ミル、ロールズ、そしてノージックといった古今の哲学者たちは、これらにどう取り組んだのだろう。彼らの考えを吟味することで、見えてくるものがきっとあるはずだ。ハーバード大学史上空前の履修者数を記録しつづける、超人気講義「正義」をもとに書かれたマイケル・サンデル氏の全米ベストセラーです。この著書は、アリストテレス、イマヌエル・カント、ジョン・スチュアート・ミル、ジョンロールズといった人々が登場し、その方達の思想をもとに道徳と政治をめぐる考察を行い、正義に関する見解を導き出そうとするものです。最大幸福を目指すベンサム、個人の自由な選択を重んじるカントやロールズ、徳を培うことこそ正義の目的だと説いたアリストテレス・・・正義に関するこれら3つのアプローチの強みと弱みを探り、最終的に正義とは、美徳の涵養を説いたアリストテレスに当ると結論ずけています。「哲学の世界というのは難しい」という先入観がないですか?実はぼくも同じ先入観がありました。しかし、ハーバード大学の生徒が毎回1000人も興味津々で聞いている講義での哲学の世界は、また違った意味でわかりやすいのでは?と思い読んでみたのですが、・・・やっぱり今ひとつピンとこなかったですね。しかも「正義」とは結局なんなんだろう、という悶々とした気持ちが見事に残ってしまい、結局は「哲学は難しい」という原点にまた戻ってしまったような気がします。だから、「正義とはなんですか?」とぼくに聞かないで下さいね!(ハート)誰も聞いてこないと思うけれど(笑)たとえばカントの考え。あなたが友人を自宅のクローゼットにかくまっている。隠れている友人を捜しに来た殺人者が戸口に来た。あなたは殺人者になんと言いますか?A.「いいえ、友人はここにはいません」B.「1時間前、ここからちょっと行ったところにあるスーパーで見かけました」カント曰く、Bの答え方は道徳的に許されるが、Aの答え方は許されない。要するに相手が誰であろうと嘘をついてはいけないということだそうですよ。・・・・・・・・なんだかなぁ~(-_-)【参考】身近な事例を題材に賛否を問い、討論する。著者が学生だったころ、政治哲学の講義は抽象的で、自分の関心から懸け離れたものとしか思えなかったという不満から生み出された手法により、ハーバード大での講義は、同大学史上最多の履修者数を誇り、毎回1000人以上が出席したそうです。オススメ度:★★☆☆☆(あまりオススメしません)これからの「正義」の話をしよう
2010年09月27日
コメント(0)
-

「死体は語る」を読みました
偽装殺人、他殺を装った自殺。どんなに誤魔化そうとしても、もの言わぬ死体は背後に潜む人間の憎しみや苦悩を雄弁に語りだす。浅沼稲次郎刺殺事件、日航機羽田沖墜落事故等の現場に立会い、変死体を扱って30余年の元監察医(上野正彦氏)が綴る、ミステリアスな事件の数々です。退官後執筆した本書が60万部を超える大ベストセラーとなり、以後、テレビ、雑誌などで活躍することとなった著者ですが、この方の著書は意外と多く読んでいるにもかかわらず、今更ながら「最初の著書」を読みました(^^;)わかりやすい文章表現や、話の展開、またやさしく話しかけられているような口調も、初作から引き継がれていたんですね。著者の厳しい「死」の捉え方には頷かされる事が多く、あまりにも多い世の中の悲喜劇についてもかなり考えさせられてしまいます。「死人に口なし」とは言うけれど、著者には聞こえるんです。「私は自殺や事故なんかで死んだんじゃないんです。殺されたのです」という声が・・・最後の夏樹静子氏の解説も、読みごたえありですよ。【参考】人が死に至った場合に行われる解剖は、犯罪捜査が目的の「司法解剖」、公衆衛生などのための「行政・承認解剖」、そして明かな病死や老衰を除く異常死が対象となる「法医学解剖」に区分されますが、2009年における法医学解剖の総数は1万6,184件で、10年前の1999年と比較すると1.6倍に増えているそうです。その反面、異常死解剖率は先進国では最低の10%とのこと。オススメ度:★★★★★(かなりオススメ)死体は語る
2010年09月22日
コメント(0)
全337件 (337件中 1-50件目)
-
-

- イラスト付で日記を書こう!
- 一日一枚絵(11月5日分)
- (2025-11-19 00:45:45)
-
-
-

- 連載小説を書いてみようv
- 60 イタリア港と仙台藩
- (2025-11-17 06:29:47)
-
-
-

- ジャンプの感想
- 週刊少年ジャンプ2025年51号感想その…
- (2025-11-19 13:50:48)
-








