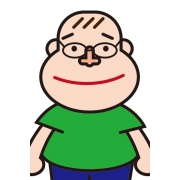PR
X
カレンダー
2024.06
2024.05
2024.04
2024.05
2024.04
2024.03
2024.02
2024.02
コメント新着
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ: 正岡子規
心太の桶に落ち込む清水哉
(明治30)
茶屋を見て走りついたる心太
(明治30)
トコロテンは天草(テングサ)という海藻を煮出したもので、古くは奈良時代から夏の間食として食べられていたようです。奈良時代はところてんを「心太(こころぶと)」と呼んでいました。これは「ココルブト」のことで、海藻が固まる(=ここる=こごる)ことを意味します。『大言海』では、「ココロブト→ココロテイ→トコロテン」へと転訛したとあります。
トコロテンは、そのぐにゃぐにゃしたところから、はっきりしない人間を「トコロテンに目鼻を付けたよう」とか、オートマチックな連続を「トコロテン式」といったり、トコロテンの食感と、天突きから押し出されて出てくる姿が人々の心を妙に刺激します。海藻のテングサをよく晒し干して、煮こごらせるトコロテンは、暑気をはらう食べものとして古来より愛されました。
トコロテンを戸外で凍結乾燥させたものが寒天です。テングサを煮溶かして固めたものを冬の夜に一気に凍らせ、昼に天日で乾燥するのを繰り返してつくります。特に、昼と夜の温度差がある方が良い品質になるといいます。この製法を始めたのは、万治元年(1658年)に伏見の美濃屋太郎左衛門が島津候に届けたトコロテンの残りを、店の裏に捨てていたところ、凍ったトコロテンが湯で元通りになることを知り、工夫を重ねて商品化。寒天の保存がきくようになったため、料理などにも使われるようになりました。煉り羊羹は、乾物の寒天が誕生したことで普及しました。
東海道五十三次の近江水口宿と石部宿の間に夏見の里があり、この辺りにはトコロテンを売る店が多くありました。『近江名所図会』には「この所、桜川の名酒。また四季ともに心太(トコロテン)を売る茶屋多し。その家ごとにはしり水をしかけ、木偶(にんぎょう)をめぐらして旅人の目を悦しぬ」という記述があり、四季を通じてトコロテンが売られていたことがわかります。
各々の店は、裏の山から水を引き、その水でトコロテンを冷やすとともに、流れる水の力を利用してからくり人形を動かしていたのです。
関東以北や中国地方以西では、二杯酢や三杯酢をかけたトコロテンに和辛子を添えて食べます。
『守貞謾稿』には「心太、ところてんと訓ず。三都とも、夏月これを売る。しかし、京坂、心太を晒したるを水飩(すいとん)と号く。心太一箇一文、水飩二文、買うて後に砂糟をかけ、あるいは醤油をかけこれを食す。京坂は醤油を用いず」 とあります。昔は、トコロテンに砂糖と醤油をかけて食べていたようです。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[正岡子規] カテゴリの最新記事
-
子規と食べものの句86/好きなもの 2022.08.04
-
子規と食べものの句85/カステラ 2022.08.02
-
子規と食べものの句84/ケータリング 2022.07.31
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.