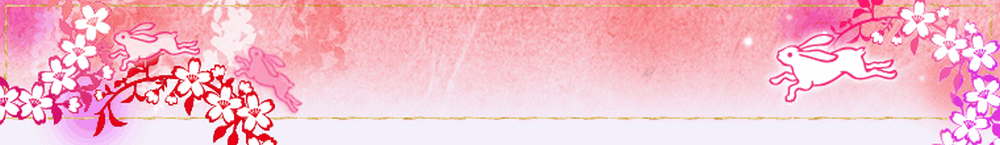全1137件 (1137件中 1-50件目)
-

羅刹 -193-
長かったこの物語の連載もようやく終わりました!それにしても、更新が遅い!!!スマホにしてから、すっかりPCはご無沙汰になってしまい、なかなか更新ができずにいました。まあ、スマホから更新できるようにすればいいんですが……なんとなく、めんどくさい。。。こんなことでは、読んでくださる方にも失礼だな……と思いつつ、これからこのブログをどうしようか、考えています。もともと、このブログは私のボツ原稿の墓場(~_~;)、もとい、記念の置き場として開設したものなので、すべてのボツ原稿はここに残していきたいと思っていましたが、他の小説投稿サイトなどの方がいいのか……とか、いろいろ考えてしまいます。でも、小説投稿サイトをちょっと利用してみると、投稿している他の人々の作品とのあまりの内容・ジャンルの違いに、気後れしてしまい……(~_~;)もうちょっと考えてみるつもりです。とにかく、このサイトはこのまま維持しますので、またご報告します~(@^^)/~~~↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年10月05日
コメント(2)
-

羅刹 -192-
いつの間にか、兵藤太は握り締めていた能季の手を離し、その顔を心配げに見守っている。 その目には、まことの父のような慈愛の心が映っていた。 そこにも、あの餓えと渇きを満たす方法が記されているように、能季には思えた。 誰かへの、一身を投げうった愛と献身。 それによって、兵藤太は己の心の中の暗闇を照らしてきたのだろう。 私にも、何かあるだろうか。 斉子女王を失った今、その餓えと渇きを満たす何かが。 能季にはわからなかった。 ただ、今は胸が苦しく、焼け付くように痛むだけだ。 だが、やがてそれは見つかるだろう。宮中の日々の勤めと責任の中にか、誰かの優しい眼差しや腕の中にか、それとも幼い者への鍾愛(しょうあい)の想いの中にか……一体どこにあるのかは、まだ知れないけれど。 いつか必ず。 中秋の明るい月が、いつの間にか堀河殿の軒端の下にまで傾いている。 少し肌寒いほどの風が、庭池を渡って釣殿の上を吹き抜けて行った。 いつの間にか、もう夏は過ぎ、秋がやってきたのだ。 こうやって、日は過ぎ、旬は巡る。人の想いも知らぬげに、飛ぶように速く。 ふいに、庭先の草葎(くさむら)の中から、今年最初の虫の音が聞こえてきた。 それは、涼やかな声で、能季に問い掛ける。 虫であろうと人であろうと、その一生の儚(はかな)さには変わりはない。その短い生を、お前は一体どう生き抜いていくのか。 姿の見えない秋虫の問いに、能季はいつまでも耳を傾けていた。 (了)↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年09月14日
コメント(2)
-

羅刹 -191-
能季はその恐ろしさにぞっとした。 今のこの苦痛がずっと続くとしたら。 自分もまた、道雅のように人を喰わずにはおれなくなるのではないか。 その時、能季はふっと、あの老尼の手文庫にしまわれていた道雅の歌の一つを思い出していた。 今はただ 思ひ絶えなん とばかりを 人づてならで いふよしもがな(今はただ、こう思うだけです。もうあなたのことは諦めてしまおう、と。でも、それを人伝ではなく、もう一度あなたに逢って直接言うことはできないのでしょうか) 涙の雫のような流麗な歌の調べ、清澄な感じさえする透明な言の葉の連なり。 今はもう逢うこともかなわない恋人への想いが、胸に迫るように伝わってくる。 それは、あの羅刹鬼の詠んだものとは到底思えない、美しくも哀しい歌だった。 もしかしたら、道雅には他に生きる道があったのではないか。 己の心の餓えと渇きを、人を喰らうというおぞましい方法ではなく、もっと別なことで満たすことができたなら。 それは、あるいは歌への傾倒だったのかもしれない。 この歌は、頼宗や斉子女王をはじめ、それを読んだ全ての者を感歎させ、その心を打ち震わせたほどの力を持っていた。 道雅がこの歌に詠んだように、当子内親王への想いを振り切り、その餓えと渇きを歌に詠むことによって昇華させていたとしたら、道雅の晩年は穏やかなものになっていただろうか。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年09月09日
コメント(0)
-

羅刹 -190-
月光に浮かぶ兵藤太の顔を眺めながら、能季はふと真砂(まさご)のことを思った。 どれほど思っても、真砂の想いが兵藤太へ受け入れられることはないのだろう。 能季は真砂が哀れになった。 だが、兵藤太の想いはそのまま自分自身のものでもあることに、能季は気づいていた。 誰かに心と魂を奉げてしまったならば、その想いは生涯変わることはない。 その誰かが、自分の前から姿を消し、二度と再び会うことはかなわないとしても、やはりその面影は心の奥底から決して失われることはないのだ。 だが、それはどれほどの苦悩をもたらすことだろう。 脳裏に焼き付いた幻に過ぎない面影を抱き締め、僅かな思い出を胸の中で手繰(たぐ)りながら、心は次第に高まる恋慕と愛執に惑(まど)い焦(こ)がれる。 まるで、砂漠にたった一人打ち捨てられた者が、食物と水を求めて喘(あえ)ぎ彷徨(さまよ)うように。 その癒(いや)す術のない餓えと渇きは、人の心を蝕み、やがて胸を掻(か)き毟(むし)らんばかりの苦痛でのた打ち回らせることになるのではないか。 ああ、そうだ。 道雅が人を喰うのは、その餓えと渇きを、何か別のもので満たそうとしているからなのだ。 心が餓え渇いている時、人は何かを口にすることで、腹だけでなくその心まで満たすことができる。 ほんの僅か、ほんの一時のことに過ぎないけれど。 道雅はあの皇女を喰らった時、それを知ってしまったのだ。 そして、当子内親王を想う心の餓えと渇きに耐え切れなくなると、また人を喰わずにはおれなくなった。 それはおそらく、生きている限り繰り返される。 いや、もしかしたら、死んだ後も。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年09月08日
コメント(2)
-

羅刹 -189-
兵藤太は欄干を離れて、能季の前へ腰を下ろし、能季の手を取りながら言った。「そして、傍らに寝かせていたあなた様を私に抱かせ、こう言われたのです。わたくしはもう逝かなければならない。わたくしの代わりに、この子を可愛がっておくれ。そして、自分の本当の息子だと思って、この子をずっと護って欲しい。そうすれば、そなたとわたくしは、この子の父と母も同じ。この子がいる限り、いつまでもわたくしたちは本当の妹背なのだと」 能季の手を握り締める兵藤太の手は震えていた。 その涼やかな目元にも、苦渋と哀しみに満ちた涙が宿っている。「私はその時、あの方に誓いました。自分の命をかけ、すべてを捨てても、若君を生涯慈しみ護ると。それから、私はその約束をずっと守ってきました」「だから、朝廷での栄達も望まず、家庭を持つこともなく、ただ私のためだけに」「それが私の喜びだからです。私にはあの方への想い以外に価値あるものはない。だから、あの道雅を本当に憎み蔑むことはできない。私も所詮は同じですから。あの男が当子内親王様を想うのと同じように、私もあなたの母上を忘れることはできない。あの方がこの世にいる限り、私にとって女とは、あの方以外にはいないも同然だった。いや、死してこの世を去られても、なお」↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年09月07日
コメント(0)
-

羅刹 -188-
兵藤太は俄かに能季の方へ向き直った。 真っ直ぐな瞳が、能季の瞳を見つめている。「私が枕辺に行くと、あの方は私におっしゃいました。わたくしの命は、もうそれほど長くはないと思う。だから、せめて最期に、自分の本当の気持ちを打ち明けてから逝きたいと」「母上は何と言ったのだ?」「わたくしは長い間ずっと自分への求婚を退けてきた。幼い頃から、わたくしにはただ一人、心に想うお人がいたから。でも、頼宗様から求婚の文が来た時、父は大そう喜んで、すっかり婿に迎えることを決めてしまった。わたくしが身分の高い頼宗様と結婚すれば、わたくしの父も兄弟も栄達が望めるから。わたくしには父に逆らう術がなかった。だから、どうかわたくしを連れて逃げてくれと、そなたに何度も頼もうと思った。本当に、そなたのいる曹司の前まで行って、そう頼もうとしたのだけれど、結局勇気が持てず、言い出すことはできなかった、とおっしゃっておいででした」「母上がそんなことを」「ええ。そして、こう続けられました。結局わたくしは、わたくしの親や兄弟たちのためにと自分へ言い聞かせて、頼宗様との結婚を承諾してしまった。後で、それをどれほど後悔したか。いくら可愛がられ大切にされても、本当に愛してはいない夫との暮らしは空しいもの。それを、このいまわの際にまで、しみじみと思い知らされるなんて。そう言って、お泣きになりました」↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年08月31日
コメント(0)
-

羅刹 -187-
「私は……そなたにとっては、憎い男の息子だったというわけか」「はじめはそうでした。私は頼宗様が憎かった。そして、二人の間に生まれたあなた様のことも。権力のある者が、私が心から大切にしているものを、いとも簡単に奪っていく。頼宗様から見れば、私など虫けら同然で何の力もない。それが心底悔しかった。それに、若君を授かったとわかった時、あなたの母上はそれはそれは喜んでおられました。私の居場所など、もはやどこにもないように思われた。若君がお生まれになった時も、私は悔しくて憎くて、若君の細い首に手を掛けようとすら考えたほどでした。でも、あの方は……亡くなる前に、私に言われたのですよ」「私の母が?」「あなた様が生まれる時は大そうな難産で、その時に床に臥して以来、あの方は結局最期まで起き上がることはできませんでした。お側にはいつも私の母や頼宗様がいて、私など近寄ることすらできなかった。でも、ある夜、看病に疲れた頼宗様が寝殿へお引取りになった後、私の母が呼びにきたのです。あの方が呼んでいると」↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年08月07日
コメント(0)
-

羅刹 -186-
月を見上げていた兵藤太は俄(にわ)かに視線を下ろし、自分の拳(こぶし)を強く握り締めた。「いや、そうではない。私はただ単に勇気がなかっただけだ。世の非難を浴び、厳罰を受けてこの命を絶たれるかもしれないとしても、それを甘んじて受ける勇気さえあれば、あのお方を背負って逃げることができたのかもしれない。あの道雅のように」 月光のせいなのか、それとも心の苦しみのせいなのか、兵藤太の頬は青白くなり、小刻みに震えている。「でも、私はそうできなかった。そして、自分の苦しみに酔い、ただ漫然とそれに浸っているうちに、時を失った」 兵藤太は能季の方を見ない。 能季はようやく、自分が兵藤太に心ならずも与えてきた苦悩に気づいた。「母の元に、私の父が通うようになったと」「どれほど後悔しても、頼宗様ほどのお方が通って来られるようになっては、もうどうしようもありませぬ。私はただ忠実な家臣として、あの方に仕え続けることしかできなかった。でも、それがどれほど辛かったか。それでも、私はあの方のお側を離れることなどできなかった」↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年08月01日
コメント(0)
-

羅刹 -185-
能季は驚いて兵藤太の顔を見上げた。 兵藤太が母の話をするのは初めてだった。 それまでは能季が何を聞いても、美しい人だったとか、優しい方だったとか、ただ通り一遍のことを言うだけだったから。 兵藤太は能季には目を向けずに、静かに話し続ける。「私は若君の母上の乳母子(めのとご)として生まれ育ちました。ごく幼い時は、本当の兄妹だと思っていた。私は可愛らしい妹がいつも自慢で、あの方も私を兄と慕ってくれました。それが、いつの頃から変わってしまったのか」 兵藤太の眉が苦渋に歪(ゆが)む。「私は、いつしかあの方と一緒にいるのが苦しくなった。本当の兄妹ではない。でも、身分があまりにも違いすぎる。あの方にとっては、私は兄どころかただの家臣に過ぎないのだと。そうどれほど自分に言い聞かせても、あのお方を愛しく思う心を押し留めることができない。それがどれほど苦しかったか。いっそ、昔話の芥川(あくたがわ)の男のように、あのお方を背負って、どこか遠くへ逃げてしまおうかと、何度もそう決心しかけました。でも、私にはどうしてもできなかった。君恩あるあのお方の父君の藤原親時様を裏切ることはできない、乳母である我が母は私の不義を嘆いて命を絶つのではないかと」↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年07月30日
コメント(0)
-

羅刹 -184-
兵藤太は夜風に揺れる灯火を見つめながら呟いた。「道雅の言ったことも、道雅の本心ではございますまい。あの男がそれに気づいていたのかいなかったのかは知りませぬが。当子内親王様が亡くなってこの世からいなくなってしまえば、憎しみと共にその裏にあるものも消えたとあの男は言いましたが、それならばなぜ斉子女王様へあれほど執着する必要がありましょうか。当子内親王様への愛がなくなったのなら、その方への執着も消えるはず。でも、そうではなかった。あの男は結局最期まで、当子様への想いだけは捨て去ることができなかったのでしょう」「人を喰らうような羅刹(らせつ)であっても、やはりただ一人の女人への想いからだけは逃れることはできなかったと?」「まことに、恋とは恐ろしいものでございます。一人の男の運命を弄(もてあそ)び、支配し、永劫(えいごう)の檻(おり)の中へ閉じ込めてしまう。どれほど、そこから逃れようともがいても、いっそそれを打ち壊してしまおうとしても、決してその檻から出ることはできない」 兵藤太はふらりと立ち上がると、能季から少し離れた釣殿の欄干(らんかん)に手をついて空を見上げた。 煌々(こうこう)と輝く淡い月光が、兵藤太の端正な横顔を照らしている。 兵藤太は視線を能季の方へ戻すことなく、空を見上げたまま言った。「若君は、御母上のことを覚えておられまするか」「まさか。母上は私がまだ赤子の時に亡くなった」「私は覚えております。共にわが母の胸で甘えていた幼子の頃のことも、一緒に花を摘んだり庭を駆けたりした童の頃のことも。髪を額で振り分けた愛らしい衵(あこめ)姿も、裳着の式の時に垣間見た天女のような麗しい姿も、尼そぎの髪に縁取られたあの美しい死に顔さえ……何一つ忘れたことはございませぬ」↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年07月15日
コメント(0)
-

羅刹 -183-
「だが、あの怨霊はあれほどの悲惨な目に合い、ひどく道雅を恨んでいたではないか。その憎しみが錘(おもり)となって、何十年もあの大宮川に縛り付けられてしまうほどに。それでも、道雅を愛していたと?」「憎いということは、同時に愛してもいるということ。人間は愛していればこそ、その裏側に強い憎しみを抱くこともございます。でも、あの道雅も言ったように、それらは所詮表裏一体。どちらも元は同じところから生え出たものにすぎませぬ。己が求めていたのは、道雅への復讐ではない……そのことに、あの怨霊は気づいたのでございましょう。ようやく道雅の魂を手にした、その時に」「だから、道雅を一緒にあの水底へ連れて行ったのだと?」「はい。愛と相対するものは憎しみではなく、何の関心もない、ということでございますれば。愛すればこそ、あの怨霊は道雅と離れることができなかったのでしょう」 能季は自分の痛む胸にやっていた手を眺めた。 斉子女王を殺したいと思うほどの胸の痛みも、よく眺めてみれば、それは決して斉子女王が自分のものにならないから憎いということだけではない。 それよりももっと深いところに、もっと強い想いがある。 それは、ただ斉子女王と一緒にいたいという焼け付くような熱望だった。 誰かを愛しいと思い、その存在を抱き締め、ただ永遠に側にいて共に慈しみ合いたい。 それは人が誰しも持つ本質な望みであろう。 たとえ、その裏側に胸をえぐるような憎しみがあったとしても。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年07月08日
コメント(0)
-

羅刹 -182-
そう思った瞬間、能季は己の浅ましさに、思わず両手で顔を覆ってしまった。 この私も、所詮はあの食人鬼……羅刹と同じではないか。「若君、いかがなさいました」 気がつくと、すぐ傍らの几帳の上に、長身の兵藤太の顔が覗いていた。 片手に小さな燭台(しょくだい)を持っている。どうやら、わざわざ明かりをつけに来てくれたようだ。 兵藤太は釣殿の軒下燈篭(のきしたとうろう)の幾つかに火をつけ、小さな燭台は能季の傍らに置いた。そして、すぐ近くに腰を下ろしながら、労(ねぎら)うように優しく言った。「大宮川で師実様がお倒れになって以来、いろんなことがありましたな。今はただお疲れでございましょう。何も考えず、ゆっくりお休みなされませ」 能季は兵藤太の心遣いがありがたかった。 だが、胸の痛みは治まらず、むしろ次第に強まっていく。 能季は思わず、うめくように呟いた。「あの怨霊は、なぜ道雅の命を捻(ひね)り潰し、地獄へ落としてしまわなかったのだろう。あの男は人でなしだ。救いを与える価値などありはしない。それに、あれほど苦しい思いをし、ようやく手に入った命なのに」 兵藤太はしばらく能季の顔を見つめていたが、やがて静かな声音で言った。「それは、あの怨霊が道雅を愛していたからでございましょう」↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年07月05日
コメント(0)
-

羅刹 -181-
能季には、斉子女王の心の奥底はわからなかった。 だが、斉子女王の決意は能季を打ちのめした。 もう二度と、斉子女王に会うことはできない。 堀河殿の釣殿の上で中秋の月光を浴びながら、能季は息が止まる程の衝撃を、今更ながら激しく味わった。 胸がちぎれるように痛み、喉の奥が詰まって息もできない。 心の中に冥(くら)い獣がいて、それが始終のた打ち回り所構わず喰らいついているかのようだ。 手足が痺れ、額に冷や汗が湧いてくる。息を吸っても吸っても、胸が苦しくて喘ぎが治まらない。 目の前が暗くなり、苦痛のあまり能季はその場に蹲った。 こんなに苦しい想いをしながら、これから先も生き長らえていくことなどできるものか。とても我慢できない。 もう何もかも終わりだ。 あのお方に逢えないのなら、これ以上生きていたって仕方がない。 いっそ、鴨川の淵にでも身を投げ捨ててしまおうか。 いや……どうせこの世では添えない運命なのならば。 両袖の中に打ち伏せられた能季の眼が、俄かに冥い光を帯びる。 人をこれほどの苦しみの只中に放り出しておいて、自分だけ勝手に平穏の向こうへ去っていくなんて到底許せない。 絶対に手放すものか。 何としてでも。 そうだ、今から小一条院へ押し入って斉子女王を盗み出そう。 今夜なら、主だったものは全て宮中の宴に参列しているから、そうすぐに追っ手がかかるはずがない。 そして、どこか静かな場所に二人で行って、今までの積年の想いを遂げ、この手で女王の命を奪って、永遠に自分だけのものにしてしまおう……あの道雅がそうしたように。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年06月23日
コメント(0)
-

羅刹 -180-
あの夜、三条の師実の屋敷を辞した能季は、その足ですぐに斉子女王を預けていた高陽院へと向かった。 ところが、高陽院に着いてみると、斉子女王は先ほど強いて願い出て、小一条院へ帰ってしまったという。 能季には、斉子女王からの文が一通残されていた。 御座所に備え付けの白い檀紙に、さらりと書き流された美しい手蹟でただ一行。 あなたのお役に立つことができて嬉しかった、これでもう思い残すことはない、と。 もちろん、能季は翌朝すぐに小一条院へも行ってみた。 だが、斉子女王は姿を現さず、応対に出た瑠璃女御も今後はこちらへ来るのは遠慮して欲しいと言う。 その後も、諦めきれずに何度かご機嫌伺いに行ったが、いずれも同じことだった。 斉子女王はすでに、もう二度と能季には会わないと、自ら決意されたのだ。 あの夜、道雅との間に何があったのか。 それが能季にも会えないと思うほどに、斉子女王を傷つけてしまったのだろうか。 それとも、これから先も実ることのない二人の縁を、自らのその手で永遠に閉じられたのか。 能季の中にまだ美しい思い出だけが残っている、今この時に。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年06月22日
コメント(0)
-

羅刹 -179-
釣殿の上を吹きぬける夜風が少し冷たい。 能季は袖を掻き合わせて腕組みしながら、欄干にもたれて遠くの寝殿に目をやった。 父が外出しているせいで、父付きの女房たちも自分の局に下がっているのだろうか。 寝殿には明かりが見えず、群青の暗い空の下で重々しい桧皮葺の屋根が鎮まりかえっていた。 ただ、撫子色の装束を身につけた年若い女房が一人、手に紙燭のようなものを持って簀子を通っていくのが見える。 その袿の色に、能季の胸は急に締め付けられるように痛んだ。 斉子女王は今頃どうしておられるだろう。 私と同じように、今夜の名月を小一条院の軒端越しに眺めているのだろうか。 能季は胸の痛みを止めようとするかのように、腕組みしていた両腕を強く胸元へ押しつけた。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年06月21日
コメント(2)
-

羅刹 -178-
父は何か知っているのだろうか。 結局、能季は父には何も打ち明けなかった。 年老いた父にはできるだけ迷惑は掛けたくなかったし、それにもう済んでしまったことだ。 ただ、数日前、父はふと思いついたように、能季へ道雅が死んだことを告げた。 曲がりなりにも、廟堂の長老の一人である父のことだ。おそらく誰かから報告を受けたのだろう。 もちろん、能季が友人の婿入りの件と偽って、以前道雅のことを詳しく尋ねたことを思い出したからかもしれない。 だが、そうさりげなく切り出した父の眼差しには、どことなく深い慈愛のようなものが感じられた。 もしかしたら慧眼の父は、能季が一人で苦悩していることを、すべて見抜いていたのかもしれない。 だが、自分の力だけで何とか問題を解決しようとしている能季を、一人前の男と信頼してじっと見守っていてくれたような気もする。 能季はそんな父の心遣いが嬉しく、せめて一つくらい父に頼って親心を満足させたくなった。 それで、当子内親王の乳母から預かった道雅の文を、父に見せたのだった。 父は古い結び文を解いて、書き記された和歌を何度も読み返した。 それは、和歌の上手として知られ、当代一の審美眼を誇る父の心さえも、揺り動かすようなものだったらしい。 やがて、父は感慨深げに溜め息をつきながら、静かな声で能季に言った。「これは私が預かっておこう。このまま埋もれさせてしまうには惜しい歌だ。私の手元にあれば、いつか何らかの形で、この世に残していくこともできようから」↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年06月17日
コメント(0)
-

羅刹 -177-
帝の側に控える頼通と師実から少し離れた席には、能季の父である頼宗の顔もあるはずだ。 得意の篳篥(ひちりき)か琵琶でも、膝の上に乗せているだろうか。 本来なら能季も、今宵の管弦の宴には父の傍らで竜笛を吹く予定だった。 だが、能季はどうしてもその気になれなかった。 長い間心労に苛(さいな)まれてきたせいか。 それとも何か別のことか。 師実の命を取り戻したあの夜から、何か憑(つ)き物でも落ちたかのように、能季は何をする気もおきなくなった。 それで、はかばかしく宮中へ出仕することもなく、堀河殿の自分の部屋に引き篭っていたのである。 今宵の観月の宴も、物忌みだ何だと理由をつけて断った。 父は残念がったが、雲龍は頼通に取り上げられて代わりの笛ももらえずじまいだったし、第一このところの一件で稽古すらろくにしていない。 仕方あるまいと笑って、父は一人で出かけて行った。 能季にそれ以上何も言わず、責めもせずに。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年06月16日
コメント(0)
-

羅刹 -176-
濃い縹(はなだ)色の夜空に、冴え冴えとした白銀の満月が浮かんでいる。 今宵は中秋。 宮中では今頃、観月の宴が華やかにひらかれているだろう。 清涼殿の東庭には、豪華な作り物で月の名勝の風景が再現され、その前に帝をはじめ文武百官が居並んで、この同じ月を眺めている。 その光景を、能季は堀河殿の釣殿で、欄干(らんかん)に頬杖を突きながら思い浮かべていた。 清涼殿に集う人々の顔の中には、能季から取り上げた雲龍を吹く頼通と、その傍らに控える師実の姿もある。 師実はあの夜、確かに魂が身体へ戻ってきたのであろう。 能季が大宮川から急いで三条の屋敷へ行ってみると、師実は死人同然の悲惨な姿から俄(にわ)かに息を吹き返し、側に寄り添う頼通に手を握られたまま安らかな寝息を立てていた。 頼通は能季の姿を見ると、無言で頷いて、もう堀河殿へ戻れとでも言うように片手で能季を促す。 その顔は心労のあまりかひどく老け込んで見えたが、瞳には安堵の涙が光っているようだった。 それで、能季もそれ以上何も言わず、黙って三条の屋敷を辞したのである。 これでよい。 ようやく師実の命を救い、役目を果たし終えたのだ。 後日、師実の従者の行綱が大そう喜んで報告してきたところによると、師実はそれからめきめきと回復し、十日も経たないうちに起き上がって、頼通の待つ高陽院に帰ったという。 今ではもう以前と同じように、毎日宮中へも出仕しているらしい。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年06月14日
コメント(0)
-

羅刹 -175-
怨霊はじっと、自分の手の中で揺らめいている真紅の炎を見つめていた。 怨霊の手が動く。 道雅の魂を、力を込めて握り潰そうとするかのように。 だが。 やがて、その手は炎を消し去ることなく、逆にそっと両の手の中に包み込んだ。 そして、我が子でも愛しむような優しい手つきで、その炎を胸に抱き締める。 能季は驚いて、怨霊の姿を見つめていた。 怨霊はそのまましばらく炎の中に佇(たたず)んでいたが、やがてゆっくりとその姿を消していった。 残された炎はしばしの間大宮川の川面にたゆたっていたが、それもいつの間にか暗い水底へと沈んでいく。 ふと気がつくと、能季の身体はすでに自由になっていた。 隣の兵藤太が、すぐに庇(かば)うように能季へ駆け寄ってくる。 心配げに顔を覗き込む兵藤太に、能季はただ無言で頷くだけで、まだ視線を川面から外せずにいた。 目の前の黒い溜池のように澱(よど)んだ水の面に、何かがふわりと浮かび上がってくる。 それは、澄んだ薄紫色をした小さな炎だった。 その炎はふわふわと戸惑うように能季の周りを飛び交(か)ったかと思うと、急に高く舞い上がり、そのまま東の虚空へと飛び去っていく。「三条の……師実様のお屋敷の方ですね」 安堵の溜め息とともに、兵藤太の低い声が耳元へ聞こえてくる。 能季はその声に頷き返しながら、炎の飛び去って行った方角をいつまでも見つめ続けていた。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年06月03日
コメント(0)
-

羅刹 -174-
道雅はふらりと立ち上がり、次第に青ざめた色に変わっていく怨霊の炎に近づきながら言った。「私は今まで悪行を重ねてきたなどとは微塵(みじん)も思ってはおらぬ。仏の慈悲など無用。私は好きなことを好きなだけして、もはやこの世にも飽き果てた。そろそろ、地獄とやらへ行くのも悪くはあるまい」 怨霊の炎は、揺らめきながら後ずさりする。「それほど私が憎ければ、この命をそなたにくれてやろう。心から憎らしく思う相手が死ねば、憎しみの裏にあるものも一緒に消えていく。その裏にあるものこそ、本当の地獄なのだから。私にも覚えがある」 そして、道雅は僅かに微笑を浮かべ、歌うような声で言った。「人を愛しく思う心も、殺したいほど憎く思う心も、元をたどれば裏と表に過ぎぬ。一つが消えれば、もう一つも消える」 その言葉が終わらぬうちに、怨霊の炎は俄かに燃え上がり、道雅に襲い掛かった。 炎が道雅の身体を取り囲み、締め上げ、胸の真ん中に喰らいつく。 見る間に、そこから燃え立つような真紅の炎がつかみ出された。 道雅は音もなく、その場にくずおれていく。 いつの間にか、炎の中に、女の姿が現れていた。 さっき見た、水に濡れた恐ろしげな姿ではなく、紅の袴に唐風の高雅な文様を織り出した白い袿を羽織る女房装束。艶やかな黒髪が肩先を流れ、袿に重ねた濃紫の単襲(ひとえがさね)の上に波打っている。 その臈(ろう)たけた目鼻立ちは、どことなく斉子女王にも似ていた。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年06月02日
コメント(0)
-

羅刹 -173-
怨霊は悲鳴のような声で叫んだ。 道雅は苦痛に身を捩(よじ)ったが、それでも俯(うつむ)いたままうめき声一つ上げなかった。 それどころか、炎に身を焼かれ、締め上げられながら、嘲笑(あざわら)うような笑みを浮かべている。 道雅は笑いに喉をひくつかせながら、しゃがれた声で怨霊に言った。「私を地獄へ落すてか。ふん、そなたに落とされずとも、私の行く先など決まっておる」 怨霊の炎が僅かに弱まる。 道雅は炎の戒(いまし)めを解き、その場に座り込むと高らかに哄笑(こうしょう)を上げながら言った。「このように姿形を変えたとて、仏が私を浄土へなど連れて行くものか。仏の慈悲は心から己の所業を悔い改めた者だけのもの。私は端(はな)から自分の生きざまを悔いてなどおらぬ。むしろ、十分に楽しませてもらったよ。自分の思うままに振る舞い、好きなだけ犯し奪い、どんなことでもやりたいと思えば躊躇(ためら)ったことがなかった。そう、人殺しさえ……いや、人を喰らうことさえな」 道雅は怨霊の炎を見据えながら嘯(うそぶ)く。「富や権力を奪い合う闘争がなければ、この世はあまりに退屈なところ。富は、私は生まれながらに持っている。権力の方は物心ついた時には奪われて、もはや戦いようもなかった。退屈なこの世を生き抜いていくためには、気晴らしが必要だ。昔は、ずいぶんいろんな気晴らしを試したものだよ。間抜けどもを驚かすような派手な振る舞いや色恋沙汰、喧嘩に乱暴狼藉。だが、私を一番楽しませてくれたのは、傷つけられた者の顔だった。特に、犯され辱められた女の顔はな。痛めつけられた悲鳴は、私には心地良い楽の音のようなものだ。滴り落ちる血のしずくの美しさ、切り裂かれた傷の鮮やかさ。舌の上で蕩けるような、肉の味も……」↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年06月01日
コメント(0)
-

羅刹 -172-
道雅の冷笑が響く。「ならば、極楽へ行けば良いものを。そうしたら、そなたの父の花山院も、大手を広げて迎えてくれよう。いや、果たして花山院も極楽におられるものかな。あのお方のおかげで煮え湯を飲まされた者も多いでの」 道雅の顔は、怨念と嘲笑に満ちて醜く歪んでいた。 もしかしたら、この男は中関白家の没落を決定的にした花山院への復讐も込めて、その皇女であるこの怨霊に近づいたのだろうか。 赤黒い光だけの怨霊の目が、急に禍々(まがまが)しい色合いを増してぎらりと光る。 だが、怨霊はそれを飲み込むように苦しげな息をつきながら、道雅にこう答えただけだった。「わたくしはそなたに騙(だま)され、甚振(なぶ)られ、殺され……挙句の果てに、喰(く)われたゆえ、その恨み苦しみが重くてならず、到底極楽へ登っていくことは叶わぬ。ただ、この呪われた地に縛り付けられて、永遠にこの世の闇を彷徨(さまよ)い続けるだけ」 突然、怨霊はそれまでの弱々しい女の姿をかなぐり捨て、赤黒い炎となって道雅を飲み込んだ。 炎は道雅の身体を締め上げ、僧衣を焦がし、首から下げていた木蓮寺の数珠も焼き尽くしていく。「それなのに、わたくしをこのような苦しみに陥れたそなたが、人間の所業とも思えぬ悪行を尽くしたそなただけが、仏に許しを乞うて出家し、死んで極楽へ行こうというのか。そんなことが許せるものか。そなたは断じて極楽へは行かせぬ。地獄の責め苦に遭うが良い!」↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年05月19日
コメント(1)
-

羅刹 -171-
しんと静まり返った東大宮大路に、道雅の奇妙な笑い声だけが響く。 風もなく、虫の音も聞こえない。 いつの間にか、大宮川の瀬音すら止まっていた。 能季ははっとして大宮川の水面を見た。 黒々とした水が、まるで川底の澱(よど)んだ泥のように鎮まっている。 それが、見る間にじわりじわりと盛り上がり、やがて二つの赤黒い目が現れた。 その目はまっすぐに道雅の方を見つめ、じりじりとこちらへ近づいてくる。 あの怨霊だ。 そう思った瞬間、能季の身体は縛られたように動けなくなった。すぐ側にいる兵藤太も同様のようだ。 だが、道雅だけは違うらしい。 道雅は兵藤太の固まった手を振り解くと、後ろ手を縛られたままゆらりと立ち上がった。そして、ゆっくりと川面の二つの目に近づきながら、低い声で言った。「なるほど。大宮川に怨霊が出るという話は聞いていたが、やはりそなたであったか。それにしても、まだこんなところにいたのか。とうの昔に地獄へ落ちたと思っておったに」 二つの目は、しばらくじっと道雅の顔を見返していた。 だが、やがてずぶずぶと音をさせながら、その全身を現した。 黒髪を白い肌に纏わせた裸身。 怨霊はどこから聞こえてくるのかも定かでない、低く掠れた声で道雅に言葉を返した。「地獄は悪行を尽くして死んだ者の落ちるところ。わたくしは何の悪行も犯してはおらぬ。ただ……男を愛しく思っただけ」↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年05月15日
コメント(0)
-

羅刹 -170-
小さくなっていく車を見送っているうちに、能季の胸は哀しみに詰まり、猛っていた心は逆に鎮(しず)まっていったようだ。 能季はようやく後ろを向き直り、兵藤太の方へ近づいていった。 道雅は後ろ手に縛られたまま、嘯(うそぶ)くような目でこちらを見ている。 その目は能季を何となく嘲笑(あざわら)っているような気がした。 能季は再びこの爺を殴りつけたい衝動に駆られたが、強いて自分を押さえて言った。「そなた、ここがどこだかわかるか」 道雅は黙っている。 ただ、小八条第で最初に見た時のような、無機質な玻璃(はり)の珠のような目で、じっとこちらを見返しているだけだった。 能季は少し呼吸を置くと、ゆっくりと言った。「ここは、今から三十年前、一人の女が殺された場所だ。この大宮川の中で、そなたに切り刻まれ、食い荒らされた女の……」 道雅の玻璃の目は、能季の身体を突き通して、その向こうにある大宮川をじっと見つめているようだった。 だが、道雅はやがて目を閉じ、自分の膝に目を落すと、背を小刻みに震わせ始めた。 泣いているのだろうか。 己の罪を悔い、女を哀れんで。 いや、そうではない。 道雅は目を閉じて俯(うつむ)いたまま、くぐもった声を上げながら笑っているのだった。 その声は、最初は微かなものだったが、次第に大きくなり、いまや哄笑(こうしょう)とも言えるほどになっていった。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年05月13日
コメント(1)
-

羅刹 -169-
外から、高陽院(かやのいん)から牛車の供をしてきた郎党に指図する兵藤太の声がする。「お前たちはこの車を連れて、一足先に高陽院へ戻れ。後は関白様の下知(げち)に従うように。ここで見たことは他言無用。良いな」 能季は名残惜しげに斉子女王の身体から手を離し、それでもなお乱れた髪を掻き揚げてやりながら、震える声で問うた。「私のせいで、こんな恐ろしい目にお合わせしてしまって。お詫びの言葉もございませぬ。どこか、お怪我でもなさいませんでしたか。それか、何か……不快なことでも」「いいえ」 斉子女王はそう言ったが、俯いたまま能季の顔を見ることもできず、唇をわななかせているその様子をみれば、何があったかは薄々察しはできる。 ただ、幸いにも衣装にひどい乱れは見えず、けしからぬ振る舞いにまでは及ばれていないようだった。 だが、それでも能季を激怒させるには十分だ。 能季は斉子女王の髪を優しく撫で、その頬にそっと口づけをすると、すっと身を翻(ひるがえ)して車を降りた。 そして、兵藤太に引き据えられている道雅の顔を、いきなり拳で殴りつけた。 兵藤太はなおも殴りかかろうとする能季をかろうじて片手で押さえながら、車の側の郎党に合図する。 郎党は頷くと、上げられていた車の御簾を丁寧に下ろし、牛飼い童を促して高陽院の方へ去って行った。 能季はごろごろという車輪の音で我に帰り、胸の痛む想いでその車の姿を見送った。 私のために、ひどく傷つけてしまったのではないか。 大したお詫びの言葉も言えないまま、別れねばならないとは。 今度は一体……いつ会えるのだろう。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年05月07日
コメント(2)
-

羅刹 -168-
やがて、右手に朱雀院の重々しい築地塀が連なってきた。 それを過ぎると、左手の先に神泉苑の小暗い木立の影も見えてくる。 もうすぐだ。 暗闇に目を凝らすと、突き当たりの空間に東大宮大路の柳並木が見えるような気がする。 牛車はなおもがらがらと音を立てながら進み、神泉苑を過ぎたところで左へ曲がると、そこでぴたりと急に止められた。 能季はもう堪えきれずに太刀を抜くと、目の前の網代車の簾を跳ね上げて、真っ暗な車中に躍り込んだ。「な、何をする」 暗闇の中で、白っぽい衣装の影がこちらを振り返る。 郎党が差し出した松明の明かりに照らされたのは、気味悪く目を血走らせた道雅の顔だった。 能季は有無を言わさず道雅の襟首を掴み、太刀を首筋に突きつけながら網代車の外へ引きずり出した。 馬を下りた兵藤太がすかさず道雅を受け取り、後ろ手に縛り上げる。 それを見届けると、能季は慌てて車の中に戻った。 車の隅に、撫子襲(なでしこがさね)の袿(うちき)がくずおれるように蹲(うずくま)っている。 能季は必死になって、斉子女王を助け起こした。 両袖の中に顔を伏せていた斉子女王は、ますます怖(お)じ恐れて自分に触れる手から逃れようとする。 だが、やがてそれが能季の手だとわかったのか、今度は無言のまま能季の胸に縋(すが)ってきた。 微かな嗚咽(おえつ)の声が聞こえる。 能季はしっかりとその細い身体を抱き締め、優しく背を撫でてやることしかできなかった。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年05月04日
コメント(1)
-

羅刹 -167-
小八条第の門を出ると、すぐに鋭く誰何(すいか)する声がする。 先を騎馬で進んでいた兵藤太が、行く手を遮(さえぎ)る数人の人影に向かって叫んだ。「こちらは小一条院の斉子女王様のお車だ。今日は方替(かたが)えでこちらに滞在されたが、急用でこれより退出される」 男たちの影は、それを聞くとすぐに物陰へ消え去った。 兵藤太はまた合図をし、車は静々と進み始める。 あれは小八条第を見張っている頼通殿の手の者だ。これからすぐに三条の師実の屋敷にいる頼通へ注進し、大宮川の辺りに他の人間が近づかないよう警備もしてくれるだろう。 牛車はゆっくりと北に向かって進んでいく。 辺りには家もまばらで、明かりはまったくない。時折冷たい風が吹いて、供の郎党が持つたった一つの松明(たいまつ)の明かりが揺れるだけだった。 空はどんよりと曇って、月も星も見えない。 あの、大宮川の怨霊と出くわした夜のように。 能季は思わず身震いし、気持ちを引き締めるように、腰につけた太刀の柄を握り締めた。 三条大路に出ると、兵藤太は俄かに東へ車の向きを変えた。 この大路をまっすぐ進めば、やがてあの怨霊が出る大宮川へぶつかる。 車の中から、くぐもった声が聞こえてきた。「おや、嵯峨野とは方角が違うのではないのか」 兵藤太はすぐに答えた。「老尼のおわす家は、このすぐ先にございますれば。今しばらくご辛抱くだされ」 それを聞いて安心したのか、声はそれきり聞こえなくなった。 兵藤太は牛飼い童に合図して牛を急(せ)き立てると共に、能季を振り返って微かに頷いて見せた。もし、この先また道雅が訝(いぶか)しく思って騒ぎ出したら、手足を縛り猿轡(さるぐつわ)を噛ませてでも黙らせて、無理矢理大宮川へ連れて行く手筈(てはず)になっているのだ。 能季は網代車の後ろ簾の前に塞(ふさ)がるように立って、腰の太刀に手を添え、身構えながら進んでいった。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年05月03日
コメント(2)
-

羅刹 -166-
東の対に一人残された能季は、二人の姿が見えなくなると急いで尼衣を脱ぎ捨て、用意してきた狩衣に着替えた。 そして、部屋中の明かりを全て消し、寝所の褥(しとね)の上へ人の形にうまく尼衣を打ち掛けた。 これで、誰かが来ても、もうここで眠ってしまったと思うに違いない。 能季は妻戸から外をうかがい、辺りに人影がないことを確かめると、庭に降りて車宿りの方へ走った。 今日の昼間、車を降りた場所には、既に簾(すだれ)の下ろされた網代車(あじろぐるま)が止まっていた。 辺りに明かりはないが、牛車の周りには数人の武者らしい影も見える。 能季はその中でも一際丈の高い影に近づいて、小声でそっと囁いた。「うまくいったか」「はい。二人とも既に車の中に。若君は車のすぐ側におつきくださりませ。私が車を先導いたします」 兵藤太はそう言うと、ひらりと傍らの馬に飛び乗った。そして、短く合図をすると、牛車はごろごろと動き出す。 能季は他の供人に紛れながら、さりげなく網代車の脇に張り付いた。 耳をそばだてながら、中の様子をうかがってみる。 だが、車輪が鳴る音がうるさくて、中の気配はまるでわからない。 能季は不安でいらいらしながら、それでも黙って車に従うほかなかった。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年04月27日
コメント(1)
-

羅刹 -165-
斉子女王はほっと小さな安堵の息をもらした。 能季の方は、今度は逆にだんだん不安が募ってきた。 斉子女王とこの男を一つ車に同乗させるなんて、本来なら死んでも嫌だ。 だが、今はそんなことを言っている場合ではない。何とかこの男を大宮川へ連れて行かなければ。 斉子女王はそんな能季の葛藤にもまるで気づかないように、道雅を甘い声で促す。「それでは、これから準備をして出かけませぬか」「え、今から? こちらは明け方に立つのでは」「老尼のために、ゆっくり話せる時間が欲しいのです。それに常盤の御寺には明日の朝には必ず詣でると頼通様に約束しておりますから、今から出た方がよろしいかと。当子様の乳母はこのところ少し具合が悪いので、右京三条の知り人の家に預けております。常盤は嵯峨野の入り口。ちょうど御寺へ行く道筋でございますから」「それもそうですな。では、そのように」 道雅は斉子女王と共に出かけることに有頂天になっているようだ。それ以上何も聞かず、熱に浮かされたような足取りで席を立ち、身支度をするために御前を下がって行った。 そして、小半刻もたたないうちに、尼に身をやつした姿で戻ってきた。すでに、牛車の用意まで整えてきたらしい。 道雅は能季に向かってここで待つよう言い置くと、斉子女王を伴い車宿りへ向かっていく。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年04月17日
コメント(2)
-

羅刹 -164-
「でも、私は仔細があって、この屋敷から出ることを禁じられております」「それでは、わたくしの車に乗ってこの屋敷を出れば良いのではございませぬか。幸い、わたくしは供人を一人連れております。その者の振りをして、牛車にお乗りくだされ。供人はこの屋敷に置いていきますから」「でも、もし誰かに見咎(みとが)められたら」「そのお姿ですもの。頭巾を被ってこっそり牛車に乗り込みさえすれば、よほど夜目の利(き)くものでなければ見破られることもございますまい。それとも、わたくしとの同乗では気詰まりでしょうか」 斉子女王と狭い車の中で二人だけになれる。 それが、道雅のすべてのためらいを吹き飛ばしてしまったらしい。 道雅は慌てるほどの勢いで答えた。「いえ、滅相もない。女王様さえお気に障らなければ、私は何の異存もございませぬ」↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年04月11日
コメント(2)
-

羅刹 -163-
道雅はいまやすっかり己を失っているようだった。 どこか得体の知れない感じは影をひそめ、あの奇妙な瞳の輝きだけが異常なほどに増している。 斉子女王はそんな道雅の様子を見極めたのか、もう一度小さく吐息をつくと、最も肝心な用件を切り出した。「老尼は昔を懐かしがって、しきりにあなたのお話をしておりました。実は、老尼はあまり身体の具合が良くありませぬ。もう年でございますから、それほど長くはないでしょう。死ぬ前に一度でよいからあなたに会いたいと常々申しておりました。そう言って何度も涙を流すので、わたくしも哀れでなりませぬ。どうでしょう。一度密かに老尼に会ってやってはいただけませぬか」 道雅にはまるで関心はないようだった。酔ったように斉子女王の方を見つめながら、気のない声で答える。「いや、そういうわけにも参りますまい。今更会っても、どうなるわけでもありませぬゆえ」 斉子女王は声に優しさを込め、幼子を諭すようにゆっくりと言った。「あなたの顔を見れば、老尼もきっと元気になるでしょう。もしそうでなくても、これで心残りがなくなって、安らかに浄土へ参ることができると思います。老尼には子供の頃からいろいろと可愛がってもらい、わたくしの方でもまるで本当の祖母のような気持ちでおりますの。わたくしのたっての頼みでございます。どうぞ一度会ってやってくださいまし」↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年04月05日
コメント(1)
-

羅刹 -162-
「わたくしの住む小一条院に一人の老尼がおります。それは亡くなられた当子内親王様の乳母だったのだとか」「あの乳母が、今は小一条院に」「その者から、わたくしは何度も当子様の恋のお話を聞きました。内親王という尊い身分のために、恋しいお方と添うことができず、その悲しみからとうとう若くして亡くなられてしまったと。わたくしには、そのお話が何とも寂しく哀れなことに思われて。まるで自分のことのように、思わず涙してしまったこともございました」 それはどういうことだろう。 能季の胸は高鳴った。 道雅の顔からも、当惑はやがてきれいに消え去り、喜びの表情が露わになっている。 それに追い討ちを掛けるように、斉子女王は細く甘い声音で、道雅に囁いた。「老尼がいうには、わたくしは当子様と姿形がよく似ているそうです。それで、当子様と過ごした昔を懐かしがって、わたくしが訪ねていくと大そう喜んでくれるのですよ。あなたが当子様へお奉げになったというお歌も、老尼から見せてもらったことがあります。とても素晴らしいお歌で、わたくしも胸を打たれました。何度も読み返し、今ではそらんじてしまったほどでございます。あの歌をお読みになった当子様も、さぞかし嬉しく思われたことでしょう」「本当ですか。あの歌を、当子様がご覧になった。あのまま誰かに捨てられてしまったと思っていたのに」↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年04月03日
コメント(2)
-

羅刹 -161-
「父院のことをよくご存知なのですか」「はい。若い頃は何度もお会いしたことがあります。それに、その他にもいろいろと思い出が。あなた様のお声を聞いていると、遥か昔に聞いたある御方のお声を思い出します」 やはり切り出してきた。 能季はぐっと拳を握り締めた。 斉子女王も俄かに緊張したようで、小さく一つ息を吐いた後、改めて道雅に尋ねた。「もしかして、それはわたくしの叔母上のことではございませんか」「それは……」「当子内親王様とおっしゃるお方です。父院の同母の妹君であられた」 道雅の顔に変化が現れた。 それまで面を覆っていたつるりとした上機嫌は消え、その代わりに訝(いぶか)しげな困惑と、それを押しのけるように何か歓喜のようなものが頬の赤みと共に立ち昇ってくる。 それと同時に、あの瞳の奇妙な光からは、冷たい無表情さが薄れ、獣じみた熱狂が湧き上がってくるように見えた。 道雅は僅かに声を震わせながら問うた。「何故それをご存知なのですか」↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年03月13日
コメント(2)
-

羅刹 -160-
斉子女王はすらすらと能季が頼んだ口上を口にする。 思いがけず腹の据わった斉子女王の態度に、能季の方が面食らっていた。 やはりあの聡明だった小一条院のお血筋なのか。 斉子女王の貴人らしい毅然(きぜん)とした振る舞いと、姫君らしい優しげな雰囲気に、道雅の方もどうやら感歎しているようだった。「それは、お優しい御心ですなあ。亡き御方もお喜びになりましょう」「でも、わたくしはちょうど物忌みの時期にあたっており、墓所へ直接行くのは方角が悪うございます。陰陽師がいうには、一旦西の京へ居を移し、その後改めて常盤へ赴けば良いとのこと。それで、急遽こちらへご厄介になることに。ご迷惑をおかけして申しわけありませぬ」「いやいや、西の京はご覧の通り草地や畑ばかりですからな。尊い姫宮をお迎えできるような屋敷はこの小八条第以外にはございませんでしょう。それに、我が家にとっても名誉なことで」「でも、あなたとわたくしとは何のゆかりもございませんのに」「いや、他でもない関白殿のご依頼とあらば、どなた様であろうと大歓迎でございます。それに、あなた様は小一条院の姫宮。小一条院は私にとっていろいろと思い出のある懐かしい御名でございますれば」↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年03月06日
コメント(2)
-

羅刹 -159-
斉子女王と和やかに歓談している道雅には、何のおかしなところもなかった。 話し振りにはそつがなく、立ち居振舞いも名門の貴族らしく優雅で洗練されており、微かに笑みを浮かべた顔は若々しく好感が持てるほどだ。 この人が本当に人間の肉を喰らうというのだろうか? まさか。 だが、道雅の眼差しにある光だけは、どこか得体の知れない感じがして、能季はどうしても自分の心の中がざわめくのを鎮めることができなかった。 斉子女王の方はどうだろう。能季はそっと隣を盗み見た。 斉子女王はすっと背を伸ばして端坐し、静かな面持ちのまま道雅に言葉を返していた。「頼通様からの文は届きましたか」「はい、今日の明け方に。何でも、頼通殿のからの願いで、わざわざ常盤の御寺へ詣でられるとか。あそこは確か、小一条院の別荘があったところですな。院が亡くなられた後は、その菩提を弔うため寺に直されたと聞いておりますが」「ええ。頼通様の夢枕に、このところ三晩続けて亡くなられた小一条院がお立ちになり、様々な恨み言をおっしゃったのだそうです。陰陽師に占わせたところ、それは小一条院の御霊(ごりょう)の障(さわ)りなのだとか。でも、故院は生前大そう可愛がっていたわたくしに会いたがっておられるので、故院の御霊が祭られている常盤の御寺に詣でて、わたくしから懇ろに供養すれば、頼通様への障りはなくなり、夢にも現れなくなるとのこと」「それであなた様が寺詣でに」「はい。父君の御霊がわたくしの供養くらいで慰められるのなら、いと容易いこと」↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年03月02日
コメント(0)
-

羅刹 -158-
道雅は御簾の前に腰を下ろし、優雅に袖を払いながらこちらを見た。 その眼差しは玻璃(はり…ガラス)の珠のように無表情だったが、それでも強い光を帯びてこちらを射抜くようだった。 母屋のこちら側には明かりも灯されておらず、間は御簾に隔てられているから、道雅からはこちらが見えない。 そう自分に言い聞かせなければ、斉子女王の顔も自分の正体も、全て道雅に見破られているのではないかという気さえするほどだ。 だが、道雅は御簾に向かって深々と一礼し、顔を上げると今度は全く違った表情を見せた。 道雅はどこか快活な感じさえする明るい声で、御簾内の斉子女王に語りかけた。「この度は、このような寂しい舘に花の如き姫宮をお迎えすることができ、恐悦至極(きょうえつしごく)にございます。私がこの舘の主、左京大夫藤原道雅にございます。どうぞ、以後お見知りおきくだされ」 道雅は口元に薄い笑みを浮かべて、じっと御簾を見つめている。 その様子には、何となくぞっとするような奇妙な感じがあった。 だが、やつれも見えないその顔は、とても出家するほどの重病人には見えない。 斉子女王も訝(いぶか)しく思ったのか、衣擦れの音をさせながら道雅に向かって軽く一礼すると、細い声で挨拶を返した。「ご病気で臥せっておられると聞いておりましたのに、わざわざのご挨拶、痛み入ります。お加減はもうよろしいのですか」「ええ。高徳の聖の祈祷を受け、このように出家もいたしましたら、すっかり気分も良くなりました。それに、尊いお方を我が家へお迎えしたのですから、主がご挨拶に出るのは当然の礼儀でございます。こちらへついたばかりの時は、お疲れと聞き及びご挨拶は遠慮いたしましたが、もうゆっくりとお休みになれましたかな」「はい。お心遣い、ありがたく思っております。急な方替(かたが)えにも関わらず、このようにご歓待くだされて」「なんの。ここは西の京の端。普段は訪れる人もなく、私も長らく引き篭もっておりますゆえ、気の利いたおもてなしなどとてもできませぬが、とにかくごゆるりとおくつろぎくだされ」↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年03月01日
コメント(2)
-

羅刹 -157-
やがて、辺りに夕闇が満ち始めた。 明かりをつけるよう、人を呼ぼうかと能季が思案していると、果たして女房らしい人影と明かりが一つ、向こうの渡殿を渡ってくるようだった。 いや、その後ろには、もう一つ誰かの黒い影がある。 その丈の高い影に、能季ははっとして身構えた。 斉子女王も人が近づいてくるのに気づいて、いつの間にか顔を上げ居住まいを正している。 女房は庇の間に入ると、母屋との仕切りの御簾際(みすぎわ)に置いてある燈台に火を移して周った。 俄(にわ)かに辺りは明るくなる。 その明かりの中に、僧形の男が一人立っていた。 数珠を握る骨ばった手に、剃ったばかりと見える青々とした頭。まだ着慣れないらしい僧衣の中で、痩せた身体が泳いでいる。 だが、その顔を目にしたとたん、能季は驚いて目を見張った。 すっきりと弧を描いた眉の下の、睫(まつげ)の濃い切れ長の瞳。細い鼻梁は高く整い、薄い唇は仄(ほの)かに赤く潤(うるお)っている。 色白の肌は滑らかで、額にも頬にもほとんど皺らしい皺はない。 その眼差しには奇妙な強い光があって、どこか人に魅入るような艶な感じさえした。 老人、というには、あまりにも若々しく生々しい。 能季は自分の父である頼宗の顔を思い浮かべた。 確か同じ年くらいのはずであり、若い頃どちらも美貌で持て囃されたそうだが、二人の様子はあまりにも違っていた。 父の方は、長い年月の間に多くの苦渋や悲しみにさらされながら、それらを得心と諦めの中で静かに受け入れ、やがて穏やかに晩年を迎えた人の平安があった。 だが、今目の前にいるこの男は、そうではない。 まるで、若く美しい時代のまま年を取らず、それでいて内部は棺の中で朽ち果てた死人のように腐り爛(ただ)れている。 そんな感じがした。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年02月14日
コメント(0)
-

羅刹 -156-
能季と斉子女王が小一条院を出たのは、暑い昼下がりの頃だった。 だが、今はだんだん日が翳(かげ)ってきたのか、それとも池や沼の多い西の京を吹く風はやはり少し冷たいのか、この小八条第はいくらかひんやりとして過ごしやすい。 いや、ひんやりというよりは、どこかじめじめとした陰鬱さがあるというべきか。 能季はいつの間にか自分の額から汗が引いているのに気づいた。 御簾の降ろされた東の対の母屋は、何ともいえない冷たく禍々(まがまが)しい翳りがある。 豪華な調度類に満たされた部屋の片隅の暗がりに、じっとりとしたものが蹲(うずくま)りながらこちらをじっと窺(うかが)っている、そんな感じがした。 斉子女王の方も、そのような小八条第の異様さに、やはり気づいているようだった。白い額が少し青ざめ、不安げな眼差しで俯(うつむ)いている。 だが、そうやって節目がちになると、長い睫(まつげ)が頬にかかるようで、なおさら可憐で愛らしい。 能季はそんな斉子女王の横顔に見とれながら、気遣うように話し掛けた。「道中暑かったから、少しお疲れになったのではございませんか」「いいえ」 そう言うと、斉子女王はまた俯いたまま黙ってしまった。 それ以上掛ける言葉も見つからず、能季の方も着慣れない袈裟の端を引っ張りながら所在無くうろたえるだけだった。 無言のうちに長い時が流れる。 能季は固まったように斉子女王の傍らに腰を降ろしたまま、時折ちらりちらりと女王の横顔に目を走らせることしかできなかった。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年01月27日
コメント(0)
-

羅刹 -155-
昨夜、遅くまで頼通と策を練(ね)った能季は、夜が明けるのを待って小一条院へ赴いた。 頼通が用意してくれた貴重な唐渡りの香炉を献上するという名目で斉子女王に会った能季は、ことを全て斉子女王に打ち明けて、その助力を乞うたのである。 果たして斉子女王は応じてくれるだろうか。 そのような危険な役目に、斉子女王は恐れて拒否なさるのではないか。 能季はどきどきしていたが、斉子女王は黙って最後まで能季の話を聞くと、ただあっさりと頷いた。 どうしても師実を助けたいという能季の願い、父親としての悲痛な頼通の心情を理解してくださったのだろうか。 斉子女王は能季から事の段取りや口上をもう一度確認しただけで、すぐに今からここを出て小八条第へ向かおうと言ってくれたのである。 姫宮の急な外出に驚いた母君の瑠璃女御には、すでに頼通からの懇(ねんご)ろな文が用意されていた。 内裏の極秘の用事のために斉子女王の力を借りたいから、自分が責任を持つので女王を預からせて欲しいというものだ。 最高権力者である関白からの申し出では、瑠璃女御も嫌とはいえない。 能季はその文を女御に差し出しながら、改めて頼通の用意周到さと権力に舌を巻いたのであった。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年01月17日
コメント(0)
-

羅刹 -154-
出迎えの女房の先導で、斉子女王は小八条第の東の対へ通された。 急なことでさぞかし手狭なことかと思いきや、対の屋の中は美々しく整えられ、特に御座所の豪華さは目を見張るばかりだった。 部屋中を覆い尽くす色鮮やかな大和絵の屏風に、細部にまで精緻(せいち)な螺鈿(らでん)の施された蒔絵(まきえ)の調度類。 さすがは派手好きの道雅だけのことはある。長年引き篭もっている病身の老人の住処(すみか)とは思えない華美さだ。 その中央の座の上に腰を下ろした斉子女王は、案内してきた女房へ細い雅な声で言った。「明日は早朝のうちに嵯峨野まで参るゆえ、こちらは夜の明ける前に出立することになろう。少し休みたいから、気遣いはどうぞ無用に」 その声音には凛とした近づきがたい威厳があった。 院御所の奥深くで大切に育てられた、世慣れない深窓の姫君であるはずなのに、斉子女王は微塵(みじん)も気後れや緊張を感じさせない振る舞いで、能季がお願いした通りのことをすらすらと言ってのける。 能季は正直斉子女王をはじめてみるような思いだった。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年01月15日
コメント(2)
-

羅刹 -153-
急に牛車が止まり、外で咳払いの音がする。 下ろされた御簾の向こうから、兵藤太の低い声が聞こえてきた。「ご到着でございます。どうぞ牛車からお降りくださいませ」 御簾が上げられたので、能季は扇で顔を隠しながら牛車を降りた。 簀子に打ち掛けられた牛車の長柄の脇には、人目を避けるための几帳が並べてある。 案内の者らしい年若い女房が、簀子の上でかしこまって平伏しているのに、兵藤太が声をかけた。「こちらは女王の乳母でござる。今日は忍びゆえ、お供はこの尼君だけ」 能季は老女らしく身を屈め、顔を尼頭巾と扇で隠して階を昇ると、あまり目立たぬよう簀子の隅に座った。 続いて斉子女王が車から降りる。 鮮やかな袿姿は、まるでそこにだけぱっと花が咲いたかのようであった。 能季は扇の陰から顔を上げて、そっと辺りを盗み見た。 脇の随身所の半蔀が一つだけ不自然に上げられている。御簾は下ろされているものの、中には人の気配がある気がした。 道雅はきっと自分の目で斉子女王の姿を見たいと思うはずだ。屋敷へ入って御簾の奥に隠れてしまうその前に。 どうやら能季の狙いは的中したらしい。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年01月12日
コメント(0)
-

羅刹 -152-
能季は網代車(あじろぐるま)の小窓の隙間から、前方に見え始めた長大な築地塀を見つめていた。 かなり古びてはいるが、きちんと手入れをされていて、いかにも粋人の住処といった趣きだ。 牛車の傍らを騎馬で従っていた兵藤太が、先触れを告げるために東の門の方へ馬を駆っていくのが見える。 能季は小窓を閉じ、慣れない尼頭巾のせいでひどく汗ばんだ額を拭(ぬぐ)った。幾重にも重ねられた鈍色(にびいろ)の袿も重く、肩に打ち掛けられた袈裟(けさ)だけでも取ってしまいたいくらい暑い。 目の前にいる斉子女王も同じように撫子襲(なでしこがさね)の袿(うちき)を着ているが、こちらはその白い額に汗一つかかず、涼しげな表情を微塵(みじん)も崩してはいなかった。「女装束というものは、何ともうっとおしいものですね。これでは暑くてかなわない」 能季が尼頭巾の端で汗を拭いながら呟くと、斉子女王はほんの少し微笑んだが何も言わなかった。 能季の方も、傾(かし)いだ尼頭巾を所在無く引っ張りながら、それ以上何も言えない。 何とも気詰まりでならなかった。 斉子女王と二人きりになることをあれほど夢見ながら、その機会がやってきたというのに、気の利いた素振り一つできない。 もちろん、これからの試練を考えれば浮ついた気持ちでいられないのは当たり前だが、それでも能季の胸はそれとは違った高鳴りで詰まり、汗が流れてならないのも暑さのせいばかりではないらしかった。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2016年01月10日
コメント(0)
-

羅刹 -151-
小一条院の辺りにはうんざりするほど建て込んでいた家並も、西の京へ入る頃にはすっかり減って、見渡す限り草ぼうぼうの畑や稲田に変わっていた。 ところどころに庶民の小家や納屋のような建物が見えるだけで、とてもまだ都の中にいるとは思えない。 建都当初、東の京と同じように整然とした都が建設される予定だった西の京は、元々湿地が多く都作りには適さない土地だったため、次第に建物が建てられなくなって放置され、今では京の郊外とさほど変わらない田畑や荒地になっていた。 それでも、いくつかは大きな屋敷や寺院があり、草地の彼方に高い塔や長い築地塀が見られることもある。 その一つが、小八条第だった。 小八条第は西の京の南端近くにあり、東西二町の広大な敷地を誇る大邸宅である。 清少納言の枕草子でも名邸の一つに挙げられている、趣き豊かな美しい館だ。 元は源昇の屋敷だったが、長い間に様々に伝領されて、道雅の父である伊周の別荘となっていた。 世間から身を引いた後の道雅は、ずっとこの屋敷に引き篭っている。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2015年12月20日
コメント(2)
-

羅刹 -150-
能季の胸の中では、美しい斉子女王の顔とおぞましい師実の顔とが、交互に渦巻いている。 だが、だんだん師実の哀れな顔の方が、胸の中を占めるようになっていった。 私のことを兄のように信頼している、師実の澄んだ瞳。 どうしても、私には師実を見殺しにすることはできない。 そう思った瞬間、能季の口は勝手に動いてしまっていた。 頼通は既に目を輝かせ、能季の方へ詰め寄ってきている。 もはや後戻りはできない。 能季は観念したように目を閉じ、頼通に斉子女王のことを話した。 当子内親王にそっくりな斉子女王なら、道雅は必ず興味を示す。その導きなら、きっと屋敷からおびき出すことができるだろうと。 頼通はふいに能季の手を取って言った。「道雅のこと、そなたに任せよう。私からの助力は惜しまぬ。小八条第の周りを見張らせている手の者たちも、そなたの自由に使ってよい。どうか、師実を救ってやってくれ」 頼通は必死の面持ちで、能季の手を握り締める。 その顔は父親らしい心配と熱意に溢れていたが、目の暗い底にはやはり冷たい光があった。 頼通にとっては、斉子女王のことなどどうでも良いのだ。 世間から忘れられた女王の一人や二人くらい、師実の命に較べれば塵(ちり)のようなもの。朝廷を平和裏に収めていくことを考えれば、大して重い犠牲ではない。 そう考えているのは明らかだった。 斉子女王は何としても私が守らねばならぬ。 襲ってきた緊張と心痛に、能季は唇を噛み締めて頷いていた。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2015年12月13日
コメント(2)
-

羅刹 -149-
頼通は冷や汗の滲(にじ)む額を押さえながら言った。「どうしたら、道雅をあの屋敷からおびき出せるだろう。手の者の話では、祈祷を施し出家までしたのが功を奏したのか、道雅はかなり持ち直してきたようだ。今は外出できぬほどの病状ではないと思う。私が使者を遣わして、どこかへ呼び出すこともできるが……果たして素直に出てくるものか」「それはなぜ?」「私は今まで散々道雅に脅しをかけてきた。ちょっとでも妙な真似をしたら命はないとな。道雅には例の風雅の宴の一件がある。おそらく、世間の噂から、私がそれを知っていることにも、薄々感づいているだろう。私から呼び出しがあれば、その件を追及されると思うに違いない。そうすれば、また病いと称して屋敷のうちに引き篭もってしまう」「関白様の御威光をもってしても無理ですか」「道雅もひとかどの貴族だ。それに人柄から言っても、簡単に私へ頭を下げるような男ではない。無理強いすればするほど頑固になって、手におえなくなるだろう。そうなったら、もはや夜討ちでもかけて、強引に屋敷から引きずり出すしかない。しかも、道雅は用心のために侍どもを屋敷内に大勢飼っているから、少々の人数では無理だ。だが、私が数多の兵を動かしたりすれば、都中が大騒ぎになる。それだけは、何としても避けたいのだ」「できるかぎり、隠密裏(おんみつり)にことを進めたいと」「そういうことだ。それに、師実が怨霊に祟(たた)られて死にかかっているなど、できるだけ他の人間には知られたくない。そんなことがわかれば、あの教通らをどれほど喜ばせることになるか。これに乗じてよからぬことを画策するかもしれぬ。何か、世人にも知られぬようにこっそりと、道雅を屋敷からおびき出す手立てはないものか」「あることは……あります」 能季は口から搾(しぼ)り出すように、小さな声で呟(つぶや)いた。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2015年12月07日
コメント(0)
-

羅刹 -148-
頼通はしばらくの間、すすり泣きながら師実の頭を撫でていたが、やがて乳母に師実の世話を頼み置くと、能季を促(うなが)して席を立った。 能季も無言のまま、塗籠(ぬりごめ)を出ていく頼通に従う。 頼通は師実の居間だったらしい寝殿の一間まで来ると、くるりと能季を振り返った。 その顔にはもはや涙はなく、牛車の中で能季を震え上がらせた冷酷な政治家のものに戻っていた。 頼通は疲れたように腰を下ろし、脇息(きょうそく)へもたれかかりながら能季に言った。「私はかつて息子を一人失った。もう二度と我が子を失いたくはない」 頼通の眉間に、また苦渋の皺(しわ)が現れる。 頼通には師実以前に、藤原通房という嫡子がいたのだ。 通房が生まれたのは、頼通がまだ若く道長も存命中の頃で、嫡子の誕生に二人は大いに喜んだという。 その期待に答えるように、通房は容貌美しい優秀な公達(きんだち)に成長した。 そして、次代を担う摂関家の嫡子として、世人の注目を一身に集める存在だったのだが、無情にもたった二十歳の若さで夭折(ようせつ)してしまったのである。 通房に期待の全てをかけていた頼通は、悲嘆の極みに追いやられた。 そして今、同じことが、またもや起ころうとしている。 頼通が必死になってそれを防ごうとしているのも当然であろう。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2015年11月29日
コメント(0)
-

羅刹 -147-
やがて、頼通は座を降り、師実の病床に近づいていった。 褥の上に投げ出された腕を取って、そっと寝床の中へ差し入れてやる。膿(うみ)に汚れた衾(ふすま)を厭(いと)うこともなく、師実の肩口まで引き上げて着せ掛けてやった。そして、腐臭漂うぶよぶよの師実の額を、何度も何度も撫(な)でさする。 乱れた額髪を掻(か)きやってやるその手つきは、まぎれもなく優しい人の子の親のものだった。 頼通は鼻を啜(すす)りながら、涙に詰まる声で呟いた。「師実。父じゃ、わかるか。もう一度目を開けておくれ」 先ほどまで、庶民の命など毫ほどにも重んじてはおらぬ冷酷な政治家の顔を剥き出しにしていた頼通であっても、やはり内心は結局ただの一人の父親なのだろうか。 能季の疑問に答えるように、頼通は余人には聞こえぬような微かな声で囁いた。「もし怨霊が私の命で勘弁してやろうというのなら、この命などいつでもくれてやるものを」 能季の胸の中が熱くなる。 父親と言うものはこういうものなのだ。 家族の者を守るためなら、自分の命を捨てることも厭わない。 たとえ、頼通のような冷酷非情な人間であっても。 我が父も、きっと私のために命を賭(と)してくれるだろう。 能季は胸の中で、頼宗の老いた慈顔を思い浮かべていた。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2015年11月25日
コメント(2)
-

羅刹 -146-
乳母がまた、激しくすすり泣き始める。 能季は自分も泣きたくなるような気持ちで、俯(うつむ)きながらそれを聞いていた。 が、よく耳を澄ましていると、その声は低い男のもののようだ。 能季がはっとして顔を上げると、目の前の頼通の肩が微かに震えている。 泣いているのは、頼通だった。 頼通は嗚咽(おえつ)をこらえながら、掠(かす)れた声で乳母に問うた。「私の寄越した叡山の僧は来たか。祈祷(きとう)の首尾はどうじゃ」 乳母は鈍色(にびいろ)の袖を瞼(まぶた)に押し当てながら答えた。「はい。確かに昨夜のうちに密かにお越しになり、先ほどまでずっと祈祷を続けておられましたが、まるで験が現れぬ様子。一度山へ戻り他の僧を連れて参ると言われ、殿がお越しになる少し前にこの屋敷をお出になりました」「何の効果もないとは、日頃の口ほどにもない。私にあわせる顔がなくて、早々に逃げ出しおったか」 頼通はじっと師実の顔を眺めているようだった。 師実は時折弱々しい息を吐くのでようやく生きているのがわかるくらいで、指先一つぴくりとも動かさない。 自分の周りに人がいるのも、まるで気づいていないようだった。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2015年11月23日
コメント(2)
-

羅刹 -145-
出迎えに来た師実の乳母に従って、師実の病間のある寝殿へ近づいていくにつれ、辺りには異様な臭気が濃くなってきた。 寝殿の一番奥にある塗籠(ぬりごめ)が、師実の寝室だ。 乳母がそっと塗籠の戸を開けると、中から凄まじい腐臭が鼻を突いてきた。 能季は思わずその場に立ち竦(すく)んだが、頼通は無言のまま塗籠に入っていく。 そして、頼通が高麗縁(こうらいべり)の畳の座所へ腰を下ろすと、乳母はすすり泣きながら目の前の几帳の帳(とばり)を揚(あ)げた。 能季はようやく頼通に従って塗籠に入ろうとしたが、揚げられた帳の向こうに横たわる師実の顔を見たとたん、足に震えが来てそれ以上動けなくなった。 師実は解いた髪を枕の上に広げるようにして仰向(あおむ)いていたが、その髪の中央にある顔はもはや髪と区別がつかないほど青黒く腫れ上がっている。 耳や鼻からは膿のようなものが流れ出し、褥(しとね)や枕を茶色く汚していた。 無造作に投げ出された片手は、既に血の気がなく老人のように痩せ細っている。 ますます強くなった腐臭に思わず吐き気を催して、能季は頼通の背後に力なく座り込んでしまった。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2015年11月15日
コメント(2)
-

羅刹 -144-
「だが、最近になって、少し気になることがあってな」 頼通はふいに能季の方へ身を寄せてきて囁(ささや)いた。「ここ数年、あの小八条第で風雅を楽しむ宴が時折開かれるようになった。一人で屋敷の中にいるのはどうしようもなくわびしいから、時折昔の歌仲間などを呼んで、歌会や管弦の集いを開いても良いかと、道雅が私のところへ言ってきたのでな。そのくらいなら良かろうと許したのだが、どうも最近妙な噂を耳にした」「噂? どんな噂です」「屋敷に集まってくる者たちのことだ。もちろん皆、名の知れた歌詠みや風流な趣味を持つ上達部(かんだちめ)などばかりなのだが……風雅以外にも、妙な趣味を持つ者ばかりなのではないかと」「妙な趣味とは?」「つまり、女を甚振(いたぶ)って楽しむのが好きな連中ばかりだということだ」 能季には女を苛(いじ)めて喜ぶ人間の性向などまるで理解できない。若者らしい潔癖さもあって、能季は忌(い)まわしげに顔をしかめた。 頼通も同じく顔をしかめていたが、こちらはもっと深刻な別の理由でだった。「このまま道雅たちをほおっておけば、いずれは噂が広まり、公にも知られるようになるだろう。そうすれば、今度は道雅一人の始末ではすまなくなる。都中が大騒ぎになり、朝廷の権威が地に落ちるのは必至。このまま捨て置くわけにはいかぬ。だが、小八条第に集まっているのは、いずれも名のある者たち。その上人数も多いから、簡単に始末したり言いがかりをつけて流罪に処したりするわけにもいくまい。さて、どうやって始末をつけようかと、悩んでいたところだったのだ。ところが、手の者から数日前に、道雅の具合が悪くなり俄(にわ)かに出家を遂(と)げたという連絡があった。道雅さえ死んでしまえば、もう安心だと思っていたのだが」 頼通は能季を睨(にら)みつけながら、低い声で言った。「道雅には、生きて怨霊と対峙(たいじ)してもらわねばならなくなった。さて、どうしたものかのう」 能季は頼通の目つきの迫力に、思わず逃れる場所を探して辺りを見回した。 だが、その時牛車ががくりと揺れて止まった。外からは、供人の誰かが門番の爺と何やら言葉を交わしている声も聞こえてくる。 どうやら、師実のいる三条邸へ着いたようだ。 能季はようやく頼通から逃れられると、ほっとして密かに溜め息をついた。↑よろしかったら、ぽちっとお願いしますm(__)m
2015年11月01日
コメント(0)
全1137件 (1137件中 1-50件目)