PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(11)Interior
(35)Travel
(91)Travel(ベトナム)
(41)Travel(フランス)
(65)Travel(ハワイ・NY)
(36)Travel(タイ)
(82)Travel (イタリア&シチリア)
(47)Travel(チェコ)
(11)Travel (インドネシア、バリ)
(18)Travel(日本)
(38)Travel(日本、九州)
(39)Travel(日本、中国地方)
(30)Gourmet (Asian)
(10)Gourmet (Japanese)
(11)Gourmet (European)
(23)Gourmet (Sweets)
(71)Gourmet (Curry)
(18)Gourmet (Others)
(7)Gourmet(荻窪)
(13)Gourmet & Shop (西荻窪)
(8)Gourmet(阿佐ヶ谷)
(3)Gourmet & Shop (吉祥寺)
(6)Recipe
(6)Essay
(137)Movie
(158)Movie(フランソワ・トリュフォー)
(3)Movie(ジャン・ピエール・メルヴィル)
(3)Movie (アンドレ・ユヌベル)
(4)Movie(フェデリコ・フェリーニ)
(10)Movie(エットレ・スコラ)
(1)Movie(ドミニク・サンダ)
(3)Movie (ベルナルド・ベルトルッチ)
(1)Movie(ルキーノ・ヴィスコンティ)
(4)Movie(ジュード・ロウ)
(12)Art (ジャン・コクトー&ジャン・マレー)
(12)Art(オペラ・バレエ・ミュージカル関連)
(6)Figure Skating
(26)Figure Skating(2008-2009)
(90)Figure Skating(2009-2010)
(49)Figure Skating(2010-2011)
(71)Figure Skating(2011-2012)
(1)Figure Skating(2013-2014)
(21)販売書籍のご案内
(1)Figure Skating(2014-2015)
(28)Figure Skating(2015-2016)
(8)フィギュアスケート(2016-2017)
(4)Travel(日本、関東)
(7)フィギュアスケート(2017-2018)
(12)Figure Skating(2018-2019)
(6)Figure Skating(2020-2021)
(3)Figure Skating(2021-2022)
(10)猫
(5)Figure Skating (2023-
(4)手塚治虫
(49)購入履歴
【楽天ブックスならいつでも送料無料】最新!自動車エンジン技術がわかる本 [ 畑村耕一 ]
★西川 羽毛布団 シングル 綿100% 掛け布団 フランス産ホワイトダウン90% 東京西川 日本製 増量1.3kg羽毛布団 西川 シングル 東京西川 あったか増量1.3kg フランス産ホワイトダウン90% DP400 綿100%側生地 日本製 リビング 冬用 厚手 暖か 掛布団 掛け布団 ふとん シングルロングサイズ ぶとん
★羽毛肌布団 肌掛け布団 西川 イギリス産ダウン85% 0.3kg 綿100%生地 洗える シングル 西川20日限定★P10★ 羽毛肌掛け布団 ダウンケット シングル 東京 西川 洗える 羽毛布団 夏用 イギリス産ホワイトダウン85% ふんわり『0.3kg』 側生地 綿100% 日本製 肌掛けふとん バイオアップ加工 ウォッシャブル 薄手 薄い 肌
★羊毛 寝心地抜群!ボリューム厚い!いい寝心地DX!西川の敷布団 シングル 巻綿ウール100%で暖かい!さぁ!春活★最大5000円クーポン [古布団回収特典付] 敷布団 シングル 西川 羊毛 敷き布団 ボリュームデラックス 厚みしっかり 硬め 暖かい羊毛100% 巻綿 ウール100% 防ダニ 抗菌 綿100% 日本製 ふとん 東京西川 リビング シングルロングサイズ
★西川 羽毛布団 シングル 綿100% 掛け布団 フランス産ホワイトダウン90% 東京西川 日本製 増量1.3kg羽毛布団 西川 シングル 東京西川 あったか増量1.3kg フランス産ホワイトダウン90% DP400 綿100%側生地 日本製 リビング 冬用 厚手 暖か 掛布団 掛け布団 ふとん シングルロングサイズ ぶとん
★羽毛肌布団 肌掛け布団 西川 イギリス産ダウン85% 0.3kg 綿100%生地 洗える シングル 西川20日限定★P10★ 羽毛肌掛け布団 ダウンケット シングル 東京 西川 洗える 羽毛布団 夏用 イギリス産ホワイトダウン85% ふんわり『0.3kg』 側生地 綿100% 日本製 肌掛けふとん バイオアップ加工 ウォッシャブル 薄手 薄い 肌
★羊毛 寝心地抜群!ボリューム厚い!いい寝心地DX!西川の敷布団 シングル 巻綿ウール100%で暖かい!さぁ!春活★最大5000円クーポン [古布団回収特典付] 敷布団 シングル 西川 羊毛 敷き布団 ボリュームデラックス 厚みしっかり 硬め 暖かい羊毛100% 巻綿 ウール100% 防ダニ 抗菌 綿100% 日本製 ふとん 東京西川 リビング シングルロングサイズ
カテゴリ: 手塚治虫
「11日ひきのねこ」で有名な馬場のぼるは、朝日ジャーナル1989年臨時増刊4月20号『手塚治虫の世界』で、
手塚さんは、どんなところでも原稿を描いた。列車の中でも、蒲団の中でも……。あれは人間わざではないです。
と手塚治虫の超人技を追悼している。言わずもながだが、馬場のぼるだってめちゃくちゃ巧い人だ。
ねこたちの描き分けなど、手塚治虫に勝るとも劣らない。だから、今でも馬場のぼるのねこキャラは人気だ。その馬場氏をして「人間わざではない」と言わしめる手塚治虫の作画の技量よ。
しかも、蒲団の中でも描ける、つまり「寝そべって延々と描ける」というのは、後にも先にも手塚治虫だけではないだろうか。
寝ながら描けたらラクだと思うかもしれない。でも、やってみたらすぐ分かる。寝ながらでは、逆にすぐ疲れてしまうし、そもそもうまく描けるものじゃない。
「寝ながら手塚」のイラストは、それを目撃した漫画家によってあちこちで描かれている。
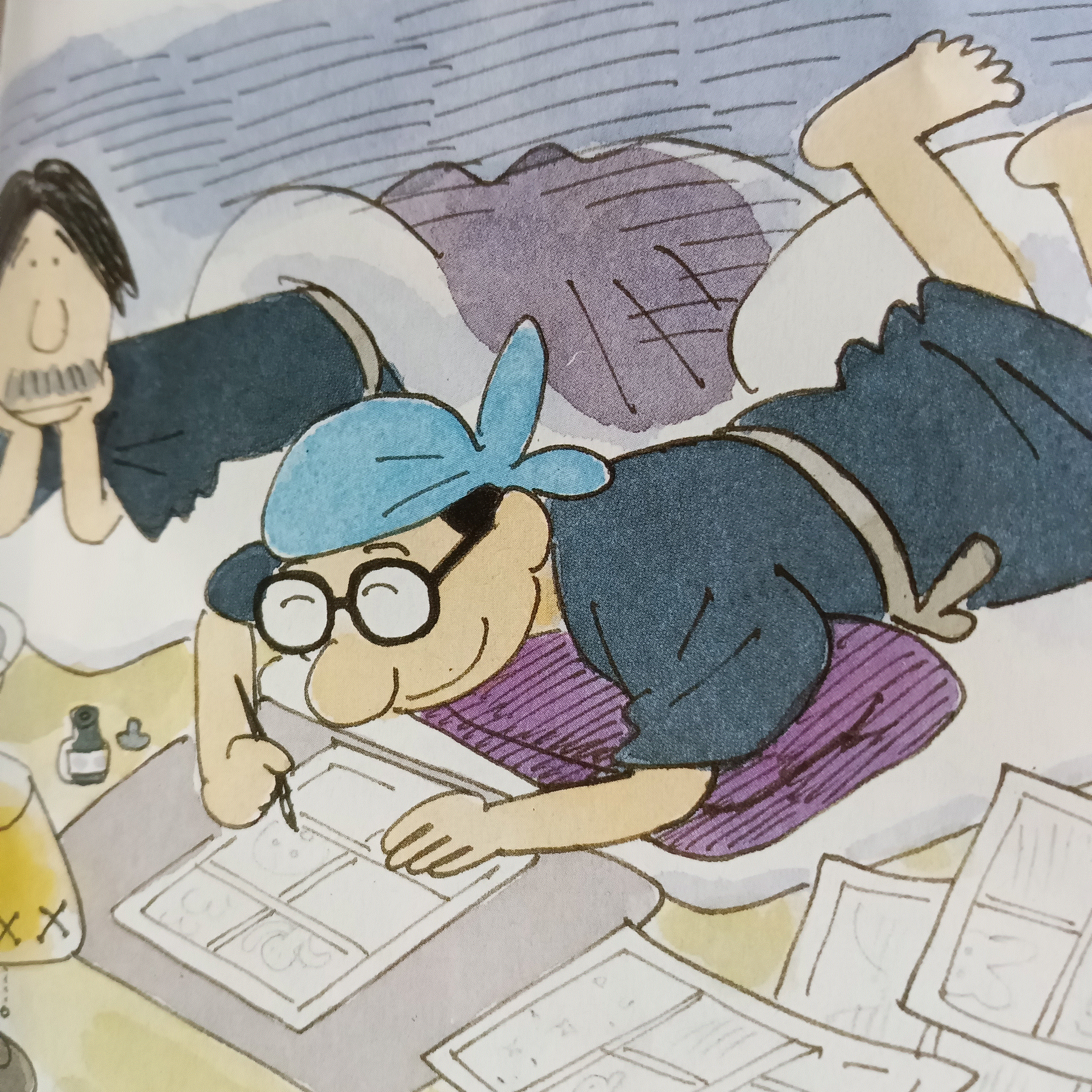
こちらは馬場のぼる(前掲書より)。ふたりが親しく交流できた、おそらくは初期のころのイメージだろうと思う。ニコニコ顔で楽しそうに描いている手塚治虫。それを「へーーっ」という顔で見ている馬場氏本人。どこか牧歌的なほのぼのとした雰囲気が漂うのは、時代もあるだろうけれど、馬場のぼるのイラストならでは。

これはコージィ城倉の『チェイサー』より。

これは、福元一義著『手塚先生、締め切り過ぎてます!』中の著者本人によるカット。若き日の手塚治虫に編集者として出逢い、その後一時漫画家として売れるも、最終的には手塚プロに入社し、チーフアシスタントとして長く手塚漫画を支えた人物なので 、締め切りに追われながらシャカリキになって描いている手塚治虫の姿は、さすがに臨場感がある。
ちなみに右下で待っているのが、「手塚番」と呼ばれる編集者たち。
福元一義氏は、基本的に「描く」側の人間なので、『手塚先生、締め切り過ぎてます!』も、描き手としてのアプローチで手塚治虫の実像に迫っており、非常に読んでいて面白い。
中でも 「スピードの秘密」 として書かれたエピソードは、手塚治虫の作画手法がいかにユニークなものだったかを明かしている。
手塚治虫が生涯でもっとも多忙をきわめた昭和49年~51年のある日、 アシスタントの福元一義に先生が話しかけてくる。
「福元氏はペンだこの痛いことがあるかね?」
「あります。とくに、締め切りに遅れて徹夜した時など、疼くように痛みました」
「僕も、ここのところ疼くように痛くてかなわないんだ。ホラ、こんなに堅くなっている。触ってごらん」と右手を差し出すので、人差し指と中指のグリップ(握り)のあたりを触ってみましたが、それらしい部分がありません。
そうすると先生は不思議そうな顔で、「君、どこを触ってるの? ここだよ、ここ」と手裏剣をかざすような仕草をしました。唖然としながら見つめると、なるほど小指から手首にかけての部分が少し赤紫色になっており、触ると堅くごわごわして、デニムのような肌触りでした。ふつうペンだこといったら、少々の個人差はあっても人差し指か中指のどちらかにできるものですが、先生の場合は違っていたのです。( 福元一義著前掲書より抜粋)
ここで面白いのは、手塚治虫は普通の人は、「ペンだこ」と言ったら、人差し指か中指にできるものだと思う――ということを知らなかったことだ。そして、この多作の漫画家のペンだこは、「小指から手首にかけての部分」にあったということ。
この独特のペン使いを見抜いた漫画家がもう一人いる。『鉄腕アトム』の人気エピソード「地上最大のロボット」をリメイクした、天才・浦沢直樹だ。
ごくごく最近だが、『手塚治虫 創作の秘密( 1986年初放送のNHK特集) 』で原稿を描く手塚治虫の映像を見て、浦沢直樹は、「小指が浮いてるね」「手首を中心にして描いているみたい」と指摘していた。
こんな描き方は普通できない、というような話になり、その場に同席していた堀田あきおが、「浦沢さんならできるかも。僕はできない」と言っていた。
福元一義は、さすがに元漫画家のチーフアシスタントだけあって、
(手塚)先生は、手首を支点に、手先全体を使って大胆にサッと描かれるのに引き換え、私たちの場合はグリップを中心に小さなペン運びで描くので、その違いがペンだこのできる場所の違いになったのだと思います。( 前掲書)
と端的に説明している。
『手塚治虫 創作の秘密』では、残念ながらペン入れ時の手塚治虫の手元はあまり鮮明には映っていない。だが、手塚治虫の筆致の大胆さと繊細なディテールと比べ合わせると、Mizumizuは氏の描き方が中国の伝統的な墨絵(日本で言う水墨画の本家)に似ていると思うことがある。
中国の伝統的な墨絵(Chinese ink painting)の描き方は、日本の今の水墨画の描き方とは似ているようで異なる。さまざまな技法があり、一概には言えないのだが、以下の描き方は、手塚作画に非常に似ている気がする。
https://www.youtube.com/watch?v=UAmZ3Hb0aQM
中国人のChinese ink paintingのプロが、壁に張った紙に墨絵を描いて見せる動画もYou TUBEにはたくさんあがっているが、手塚治虫もよく講演などで、観客に見えるように大きな模造紙を床に垂直におろして、そこに即興でキャラクターの絵を描いて見せていた。こうした手塚ショーは観客の驚きを誘い、いつも場は大いに盛り上がったそうだが、みなもと太郎氏によれば、こういうことができる漫画家は1960年以降は、ほとんどいなくなったようだ。
そのエピソードが載っているのが、以下の『謎のマンガ家 酒井七馬伝』だ。 酒井七馬は手塚治虫を一躍有名にした『新宝島』の共作者であり、手塚本人はそうとは思っていなかったようだが、ある意味、手塚治虫の師匠と言ってもいい存在だ。

【中古】 謎のマンガ家・酒井七馬伝 「新宝島」伝説の光と影 / 中野 晴行 / 筑摩書房 [単行本]【メール便送料無料】【あす楽対応】
酒井七馬 (1905年~1969年) が活動していた時代には 、漫画家なら似顔絵ぐらい描けて当たり前で、よく漫画家がイベントに登壇し、大きな模造紙に即興で似顔絵を描いたりするショーは人気。実は若き日の手塚治虫も 酒井七馬とこういうイベントに参加していたのだという。
ところが、 酒井七馬の晩年、たまたまこうしたイベントに参加した みなもと太郎は、酒井氏の司会で、呼ばれた漫画家が大きな模造紙に即興で漫画を描くように言われても、まるで原稿のひとコマを描くように、チマチマとした絵しか描けない姿を見て、酒井氏が当惑する様子を目撃している。
「似顔絵を描いて」と酒井氏に促されても「描けませ~ん」と言われたそうで、当然、場は盛り上がらない。
『謎のマンガ家 酒井七馬伝』の著者である中野氏は、みなもと太郎から聞いた、この「盛り上がらなかったイベント」の終焉が、酒井七馬が「自分の時代が本当に終わった」ことを実感した瞬間であろうと、大いなる寂寥を込めて書いている。
酒井氏は、若い漫画家に筆で描く練習をするようにとアドバイスをしていたという話だが、そんなことをする漫画家は彼の晩年にはいなかったのだろう。ちなみに、漫画を描き始めたころの手塚治虫は墨を自分ですっていた。使っているペンはガラスペンだったという。
ガラスペンの形は筆の穂先に似ていて、滑りは軽く描き具合は良好だが、1回分の 浸 けるイングの量が少ないので、しょっちゅう浸けていなければならず、時間のロスが大きいので、手塚治虫が東京に出て連載を持ってからはお役御免となったという( 福元一義、前掲書より要約)。
手塚治虫の登場で、ストーリー漫画は隆盛を極めていき、さらに発表する雑誌も月刊誌から週刊誌へとスピードが速まっていく。その経過の中で、「漫画家」という者に求められる技量が変わっていったということだ。
実際、石ノ森章太郎は、自分を「漫画家」ではなく「萬 画家」と称している。伝統的な呼称との決別は、自分の描く世界は 「漫」ではなく 「萬」だという自負もある。
手塚以前・手塚後で変わったものはあまりに多いが、マンガ家に求められるものが変わるにつれ、消えていった描き手の素質もあったということだ。消えていく技量を高いレベルで維持していたのが手塚治虫本人だった、革新者でありながら実は伝統の継承者であったというのも、あまり指摘されることはないが、まぎれもない事実だろう。

手塚先生、締め切り過ぎてます! (集英社新書) [ 福元一義 ]
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.02.02 11:11:02
[手塚治虫] カテゴリの最新記事
-
鈴木まもる『火の鳥』はアクリル画法の最… 2024.05.18
-
宝塚に行く――ティーハウスサラのシナモン… 2024.05.12
-
やなせたかし(アンパンマン)は晩年、手… 2024.05.07
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.









