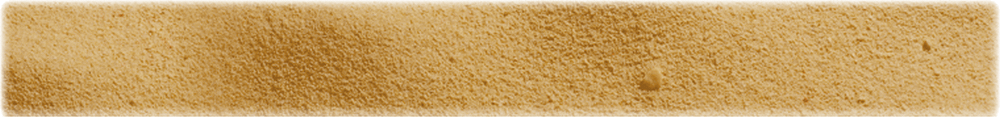全1266件 (1266件中 1-50件目)
-
THE BAND-MAID rising 7.
この「REAL EXISTENCE」、直訳すれば「真の存在=実在、厳存」などということになるのでしょうか?英語でもたぶんめったに使わない用語だと思うのですが、世界大戦直後には「existentialism (実存主義)」という、気難しい哲学が流行りましたね。爾来、ハードロッカーのなかには、体制批判、反権力の象徴として、音楽のタイトルや歌詞で、やたら難しい用語を振り回すグループがいましたが、もちろんBAND-MAIDのこの曲には、そうした重苦しさは微塵もありません。むしろ最もシンプルなロックナンバーとして、歌とインストを楽しんでね、という出来映えで、ロックファンにはごく馴染みやすい音楽なのでしょう。 しかし聴きようによっては、かつて存在した難儀なハードロックに対する、強い反射体を示しているような気もする。ちなみにこの曲、作詞作曲とも外部委嘱の作品で、活動初期はそうした音楽が主だったようです。なるほど。 ところでかつてのハードロッカーたちが、なぜ反体制、反権力の身振りで哲学用語をはじめとして、難しいタイトルや歌詞を採用したかという問題は、ロック音楽そのものの本質とも絡んでくると思うので、あらためて(出来たら)話したいと思っています。 言い忘れましたが、ミクさんが京都に魅かれた点が、もう一つあるかなと、私は思うのです。それはこの前のような「京都人のエートス(立ち居振る舞い、ものの考え方)」といった抽象的な話ではなくて、はるかに具体的な、例えば西陣あたりで行われている、職人たちの分業システムのような形態ではなかったか、とまたまた想像してしまう。 百年後あるいは一千年後に残すような一つの着物、あるいは工芸品とかを生み出す工程に、どれぐらいの職人が関わっているか。各職人は名は残さないけど、高いプライドと互いの技術をリスペクトし、信頼しあう関係で結ばれているじゃないですか。肝心なことは、ここには「リーダーは存在しない」ということです(言い出しっぺは、いるかもしれないけど)。こういうスタンスって、何かと「我が、我が」と個の名前と業績を追求しがちな、今どきの風潮に対して、敵対的ではないけれど、ほとんど冷笑的とさえ思えるスタンスで、私たちを見返しているように見える。 この職人的スタンスは、ある意味BAND-MAIDの今あるスタイルに似ていません?志のある技能者が集まって、それぞれ分担された技量を磨きながら、一つの作品を生み出していくという点において。これは例えば、お祭りの神輿(みこし)に似ているような気もするのです。自分たちは神輿を「担ぐ側」なのか「担がれる側」なのか、企業の社長さんや政治家あるいはアーティストの中でも、自分はアプリオリ(先験的)に「担がれる側」だと勘違いしている人って結構多いんじゃないか(自分はもともと才能があったから、とか)?しかし担ぐ対象は「神輿」に祀られている神様であって、ここから先も人間ではない(神様が怒ってしまいますよ)。 で、そこにいる神様は何なのかと言えば、担ぎ手の集団意志にそって、それが企業体であっても選挙民であっても音楽であっても、イワシの頭であっても何でもいいのです。それぞれの集団やグループが、その中で共有できるある「大いなるもの」を措定したとき、それは「神様」として祀り上げられ、全員がその担ぎ手になるのです。ここで「担ぎ手」に名前は必要ない。みんなが措定したある「大いなるもの」が、充分に奉祝されるかぎりは。 ここの話で最初のほうに取りあげた「Don't you tell ME」なのですが、例の中間部のところ、ギターとベースの対話が強く印象に残ります。しかしよく聴いていると、この間、背景放射のように漂っているシンセサイザーの持続音と、時を刻むかのようなドラムの打撃音が、きわめてスリリングな音の空間を創り出しているでしょう。これらはその前のMVにはなかったものであり、ライヴを重ねるごとに、メンバー内で出てきたアイディアだと思うのです。これがあることによって、ここのギターとベースソロが突出せずに、曲全体にうまく溶け込んでいる。聴き終わったあとのゴージャスな印象というのは(かなり満腹感もともないますが)、こういう細部に対するアイディアとか、仕上げへの「こだわり」から生み出されてくるのだと思う。 これって、やはり一種の職人的な「こだわり」だと思うのです。で、そうした空気感をバンド仲間に作り出していったのは、やはりミクさんとみて間違いないでしょう。彼女は自らリードヴォーカルを捨てることによって、より「大いなるもの」を祀り上げていく、巫女のようなポジションを見出したと言っていいのではないか?それかあらぬか、「thrill」のころセカンドヴォーカル的な位置にいたミクさんは、次第にバックコーラスに退いて、むしろそこからバンド全体の「サウンドを眺める」ことに面白味を感じていたようですね。 それにしても、この時のアカネさんのドラムは素晴らしく、テンポを守りつつ、何だかリズムセクションの枠を超えて、主役二人のセッションが作り出すサウンドに深く嵌入している気がする。こういうドラムというのも、私の数少ない経験ではあまり聴かないんですよね。ベースのミサさんがアカネさんについて来たというのも分かる気がする。 とはいえ、進化を求めてやまないミクさんは、昨年ソロプロジェクトcluppo(くるっぽ、鳩語で「こんにちわ」という意味らしい) を始めたり、最近の作品ではバックコーラスとリズムギターというポジションは変わらないものの、音楽的には以前と比べて、より前にせり出してきた感じがします。それのよく出た曲を聴いてみましょう。「Manners, BLACK HOLE」
2022.11.17
コメント(0)
-
THE BAND-MAID rising 6.
自作曲の発表をするようになってからの、BAND-MAIDの楽曲創作パターンというのは、メンバー各々の抱く曲のイメージをまとめ、それに沿った旋律とリズムセクションの元曲をカナミさんが作り、ミクさんが歌詞をつけたうえで、各部門ごとにブラッシュアップして完成していくというのが、もっぱらだったようです。面白いのは多くの場合、歌詞はミクさんの名前で上がっているのに、作編曲はBAND-MAIDと表記されていることで、言い換えれば創作の過程で、かなりの改変修正が行われていることを想像させます。 このあたり、元シンガーソングライターとしてのカナミさんは、あまりこだわりがないというか、むしろそうした他の手にかかる改変修正の過程を楽しんでいるフシがある。「じゃあミクさんの歌詞だって他の手が入るんじゃないの」という話になりそうですが、どうもそういうわけではないらしい。 これも自作曲を作るにあたって、誰が作詞するかについて、当初みんなの持ち寄りで決めようということになったらしい。で、結果的にミクさんので行こうというか、他の皆さんのに比べて(書いてこない人もいたのではないか?)サマになっていたということではなかったか?彼女は多くを語りませんが、各作品のタイトルや歌詞を見ればお分かりのとおり、かなりの文字フェチというか文章好きを感じさせる言葉つきであって、これはちょっとほかの皆さんにはマネが出来ないな、と思わせる部分があったのではないかと思うのです。 それについてまたまた妄想がわき起こるのですが、四年ほど前にエイプリルフール企画として、ミクさんの発案でBAND-MAIDならぬBAND-MAIKO名で出した「secret MAIKO lips」。じつはこれ、その一年ほど前にリリースした「secret My lips」の替え歌で、歌詞も全編京都弁という念の入れよう。メンバー全員京都とは縁がなさそうで、これを収録するまでのサイキさんの(すごい)顔が思い浮かびますが、それはさておき、ミクさんは昔からの京都ファンであった由。しかし彼女の言うところの京都ファンとは、たぶん上っ面の観光京都ではなく、かなりディープな穿った入り方をしておられたのではないか、という疑いが私の頭にはよぎるのです。 とはいえ、このHVの出来映えはと言えば、おそらく京都人にとっては、はなはだ噴飯ものだったろう。着物は何やらいやにカラフルで、ちっとも上品じゃないし(失礼!)、だいいち背景が浅草寺と東京タワーでは、誰だって怒ってしまいますよね。要するに外国人が喜びそうな仕上がりなのです。当初から海外を意識したバンドとは言うものの、こういう安手の観光案内みたいなのはやめてもらいたい。 と思いきや、その一年後には本格的に現地ロケを敢行して、今度はBAND-MAIKOオリジナルの「祇園町 "Gion-cho"」をリリースして、こっちは冗談じゃなく良く出来ているのです。ミクさんの入れ込みようは、ことほどさように尋常じゃない。彼女を引き付けてやまない京都というのは、うわべのきれいな街並みや神社仏閣ではなく、容易に本性を現さない京都人のエートスにあるのではないか? なぜなら京都という街全体が、先ほどの紫式部じゃないですが、私に言わせると、いわば「韜晦した都市(倒壊じゃないですよ)」だからです。このよそ者に容易に本性を現さない土地柄というのは、一千年以上日本の政治文化の中心であり続け、であるがために、政争がらみの内紛や外部からの侵攻で、何度も焼け野ヶ原となった洛中の住人にとっては、それが生き延びるうえでの甲斐性とならざるを得なかったのでしょう。しかし別に京都でなくても、一般に人はよそ者には警戒しつつ、その様子を遠目でしばらく窺うものですが、京都人はそういう無粋なそぶりは一切しない。積もりに積もった重層的な文化と、極度に洗練された習俗の蓄積で、来るものは一見誰も拒まない。 しかし本質的なところで、洛中の人は他者と自己を峻別しているので、それに気づいた京都ファンというか、例えば下宿学生(特に女子)などは、数年経つと一変、たいへんな京都嫌いになって、帰ってしまうという仕儀になるのです(京都市の若手人口が、なぜ減るのかって当たり前です。女子が居つかないからですよ)。 まあこのあたり、かなり大げさに喧伝されている部分なしとはしないですが、「京都嫌い」を立て看板にして、逆京都宣伝にいそしむ洛外の学者さんもいらっしゃるわけです。このうわべ「はんなり」中「真っ黒」という、極度に洗練されたエートスというのは、ミクさんの立ち居振る舞いにピッタリはまるじゃないですか。もちろんミクさんは「はんなり」でも「真っ黒」でもないのですが、自身をメイド衣装にくるんでパッと隠しおおして、世間が誤解しながら、こっちを見る様子を面白がっているというような。 したがって、はたから見ると、「この人何を考えているのか、サッパリ分からん」ということに(とくにサイキさんなど)なってしまうのです。それを見越してかどうかは分かりませんが、インタヴューとか人前に出るときは、ミクさんはサイキさんと必ずいっしょに出ておられる。メイドキャラのパフォーマンスは、いくらでも自分が引き受けるにしても、メインヴォーカルはやっぱりバンドのでっかい立て看板ですから、いつも前に出てもらわないと、ということでしょうか。サイキさんはそのあたりの呼吸に最近慣れてきたか、女王様然とした立ち居振る舞いは相変わらずですが、以前に比べてメイドパフォーマンスに積極的になって来たような気がする。ご本人は「ミクの唄いかたが、だんだん私に似て来た」とおっしゃってますが。 それにしても最近、ミクさんはミサさんには作曲を、サイキさんには作詞をさかんに勧めているらしい。この人の深謀遠慮というか、「世界征服」への大構想は止まるところを知らないという感じですね。初期の作品で、このバンドの未来を予見したような傑作「REAL EXISTENCE」を、やはりライヴヴァージョンで聴いてみましょう。
2022.11.13
コメント(0)
-
THE BAND-MAID rising 5.
こんなどうでもいいような話をしているというのは、結局いろいろ逸話に満ちた「人集め」話というのは、すこぶる面白いからです。「七人の侍」前段の面白味は、いわくありげな浪人たちを募っていくエピソードにあるのですが、それぞれの逸話や秘密が後段のアクションにつながって、大きく展開しますよね。それと似てBAND-MAIDに集まったメンバーは、よくぞここまで癖のある人ばかりになったか、と思わせるほどの個性派ぞろいで驚いてしまう。 ベースのミサさんなんか、ライヴ中でもお酒が入らないと、セッションが乗らないという無頼派ぶりで、先ほどのカナミさんはギターを手に取ると人格が豹変する、肝心のミクさんじたいがメイド姿で「ポッポッ」と鳩語を臆面もなく連発するとなると、ヘタすれば収拾がつかなくなるのは必至というような顔ぶれなのです。 ここでミサさんのベースドライヴが光る「Turn Me On」を聴いてみましょう。このミサさん、ついでに言うと、2018年のヨーロッパツアーでは裸足で演奏していたらしい。それらしき動画もありますが、ここでは挙げません(オランダでのライヴ)。 そういうようなことで、比較的まとも(?)とみられたドラムのアカネさんが、一時期このバンドのリーダーと目されることもあったようですが、どうもハッキリしない。というか、このバンドにはリーダーが存在しないのです。それぞれが、かなり強い自律性を持って集っているという印象が強い。これはクラシックでいうなら、例えば弦楽四重奏団なんかが思い浮かぶし、フルスペックの大オーケストラでも指揮者を置かずに「第九」を演奏したりする試みが行われていますが、それを定型化するのはなかなか難しい。早い話、二十人たらずの室内管弦楽団でも、音楽的なリーダーがいないと、楽団を維持するのは大変でしょう。 かろうじて先ほどの四重奏団レベルで、各人がかなりの自律性を保持し得るのではないか?しかしこれもまた各様で、名ヴァイオリニストの率いる四重奏だと、ほかのメンバーは何だか伴奏者みたいな位置づけにどうしてもなって、なかなかうまくいかない。これはジャズなどのグループでも同然でしょう。 サイキさんはもちろんそんな難しい話ではなくて、彼女独特の嗅覚で「このグループは、面白いかもしれない」と嗅ぎ取ったに違いない。この場合の「面白い」とは、「かなり自分の好きなようにさせてもらえる」、そして「オリジナルな曲を作ってくれる」かもしれない、ということだったでしょう。この人、見かけのとおり何でもズケズケ言ってのけて、そのかわりあとに残さないという、ごくサッパリした性格のようで、「全然趣味が違う」「性格が正反対」「高校時代なら絶対仲間に誘わないタイプ」だの、 ミクさんに向かってもずいぶんなことをおっしゃってますが、対するミクさんも大人ぶりを発揮して、全く動じるところがない。 サイキさんが友達を引き連れて(当然自分が女王様の)得意になっていたとしても、ミクさんは付かず離れず泰然と適度な距離を保って、たぶん一人でなにやらいわくありげな本を読んだりしていただろう。サイキさんはおそらくそういう存在が、気になって仕方がなかったに違いない。 何だかこれまた女子アニメ風の景況を呈していますが、そのミクさんがまた競馬が趣味だと、サイキさんを脅かすようなことを言って煙に巻くのです。ミクさんというのは、その扮装おしゃべり趣味その他、さまざまな点で自分を覆い隠す「韜晦癖(とうかいへき)」(自分の本心や才能・地位などをつつみ隠すこと)があって、作詞にかんしても「情緒不安定になるから、自分を語ることはしない」とかおっしゃってましたね。メイド服も鳩語も競馬も、自分の身を隠す一種の扮装あるいは、方便のように使っておられるのです。 こういう自身も含めて、周囲から一歩距離を置いたような目線で、世間と対峙する人というのは、数は多くないけど、この世には必ずいるので、私などすぐ平安時代の紫式部を思い出します。元祖「こじらせ女子」なんだそうですが、「内心の悪魔」からできるだけ距離を置きたいがために、あれだけ長い長い物語を書き続けたのではないか、というのが以前「源氏物語」を舐めるようにして読んでいたとき、終始感じていた気分で、その印象は今も変わっていません。 その伝でいくと、対するサイキさんは、まさしく「枕草子」を書いて一世を風靡した清少納言にあたるので、この人の語ることはすべて「自分のこと」。才気煥発で当意即妙、「私のように才能のある人は、この世にいないわ」とばかり、終始さまざまな話題を宮廷中に振りまく。紫式部が宮廷に出仕したときには、彰子と定子の入内争いはほぼ決着していて、彼女が清少納言と直接対決することはなかったはずですが、宮廷中の話題をさらっていた彼女のタレント性には、よほど腹を据えかねていたとみえて、のちに日記に彼女を罵倒する文章を長々と書き記すこととなります。人を観察する怜悧な目は、小説では人物を生き生きと活動させますが、現実の人間を描くと、それが精確になればなるほど、逆に描くほうの性格があらわになってしまい、「これは付き合いきれないな」という話になってしまう。 紫式部はそういう自身の内部に潜む「内心の悪魔」の存在を十分知っていたので、宮廷では絶対「私」を出さない。それが彼女のどのような生まれや育ち、あるいは経験から来たものなのか、想像するしかありませんが、幼い時からさまざまな漢籍に親しんだことも、あるいは内省性をはぐくむ起点になったのかもしれません。 ミクさんはもちろん「こじらせ女子」ではなく、その姿形とは裏腹に内々では「オヤジさん」と呼ばれているらしい。彼女のお顔をよく拝見すると、確かに丈夫そうな顎の張りぐあいからみて、相当な肉食系であることは間違いなさそうです。それがよく分かる動画を観てみましょう(失礼!)。「about Us」 コロナ禍にあって、どうしても世界に伝えたい、人々への激励のメッセージという意味で、きわめて美しい作品ですよ。
2022.11.10
コメント(0)
-
THE BAND-MAID rising 4.
「ON SET」は、エレキギターのサウンドの魅力を、キャッチーなメロディーラインに乗せて、あますところなく引き出した名曲で、意のあるギタリストなら一度は弾いてみたいと思わせる魅力を持った作品でしょう。あちらの(往年の?)ハードロッカーたちも、よほど刺激されたと見えて数多くのリアクション動画が出回っていますが、インストルメンタルだけでヴォーカルがないのを幸い、オンライン仲間と組んで、そっくりカバーした演奏を披露している方たちもいますね。 それにしても、ここまでカナミさんのリードギターが鮮やか過ぎると、そのメイド服姿が何となくサマになって、「ON SET」はこのカッコじゃないと、と思えてくるから不思議ですね。 しかし、このBAND-MAIDの演奏で注目すべきは、リードギターのピッキングやタッピングなどのかっこよさもさることながら、むしろドラムとベースを中心とした「爆進的なリズムの推力」のすごさで、このグループの演奏スタイルがよく出ている点だと思うのです。 ともすれば爆進的なリズムセクションのパワーに、木の葉のように翻弄されそうなリードギターの進行を、陰に陽に巧みに支えているのが、リズムギターを担っているミクさんで、カナミさんのタッピングの間、主旋律を補強しているのはミクさんのギターですよね。このあたり、なにやら彼女の立ち位置を、よく現しているようで面白い。 ヴォーカルのほうでも、サイキさんのバックコーラスとして、とても効果的な出入りをしてらっしゃる。こうした彼女の役回り、ライヴでは舞台のあちこちを駆け回って、時にリズムセクションに入ったり、あるいはリードヴォーカルを補強したり、そして何より幕間の「お給仕タイム」では、ミクさんが主導してパフォーマンスを披露しているというか、そもそも彼女のほかに「キュンキュン、萌え萌え!」なんて誰もやる人がいない。 というところで、サイキさんの話に戻るのです。四人でスタートしたバンドですが、すぐロックバンドに必要な強いヴォーカルとしては、ミクさんの声質は高過ぎるとご自身が考えた。そこで新たなヴォーカリストのスカウトを始めたのですが、ネットでいろいろな話を見ていると、同じ事務所にいたサイキさんにミクさんが目を付けたというより、事務所のほうからミクさんのほうに紹介があったというのが本当らしい。とすれば、ピックアップされたヴォーカリストは、一人や二人じゃなかったろうというのが、私の勝手な推測です。 ミクさんは何人かのデモテープを聴いて、サイキさんの低めで強い声質に白羽の矢を当てた。となると、サイキさんとBAND-MAIDとをアレンジするのは、事務所側の仕事ということになります。ミクさんはおそらく同じ事務所とはいえ、サイキさんのことを知らなかったでしょう。今では「メイド服とは知らずに、だまされて入った」という話は笑い話になって、さまざまな「物語」の尾ヒレもくっついているようですが、要は事務所側は声をかけるときに、かなりサイキさんに気を使ったということでしょう。何に気を使ったかといって、もちろんサイキさんの高い高いプライドに対してです。何しろ「おめえら、かかって来い!」と観客に言ってのける人だったそうですから。 面接のときに、ミクさんは顔を出さなかったとか、どうだったとか、このあたりは物語が多すぎて、話に気をつけなければいけないのですが、要はハレモノに触るようなスカウティングだったのでしょう。 とはいえ、これまたまったくの想像ですが、そうした彼女のパーソナリティーを、ミクさんはきっと面白いと思ったに違いない。そうしたじゃじゃ馬的女性(失礼!)は、メイド喫茶で何人も見て来ただろうし、むしろそれくらい気概のある子のほうが、仕事が出来ることを知っていたのでしょう。案の定、最初のライブのあと、サイキさんはメイド衣装のエプロンを投げ捨ててみせた由。普通の女子会なら、そこですべておしまいというところですが、ミクさんがそのように動いた形跡はない。 ここで、なだめに入ったというか仲裁したのが、これも完全に推測ですが、おそらくカナミさんだったろうと私は思うのですよ。カナミさんとしては自身の作品が世に出せるかもしれないこのチャンスは、どうしても物にしたかった。そこでの彼女のサイキさんへのアプローチは、たぶん「あなたの唄う曲を、必ず作りたい」というようなことではなかったか? この話があったとすれば(実際は知りませんよ)、興奮したサイキさんをかなり鎮める効果があったのではないか、自信はあるとはいえ、鳴かず飛ばずの歌手として一人で活動するよりも(安室さんが目標だったそうです)、かなり技量のあるバックバンド(!?)と、何よりも作曲家がグループにいるというのは、その衣装はさておき、やっぱり魅力だったに違いない。 それかあらぬか、実際にはカナミさん自作の作品が、BAND-MAID結成後なかなか取り上げられなかった時期、一番寄り添って作品を作り続けるよう励ましていたのは、今度は逆にサイキさんだったとか。そのあたりの二人の関係を想像させる動画があります。「アコースティック版パズル&アネモネ」 もともとハードロックナンバーである「パズル」が、すっかりフォークデュオのような音楽になりおおせているのも一興ですが、中間の二人のたわいないおしゃべりを聞いていると、何やらただならぬ二人の関係がただよっているじゃないですか。サイキさんの声が好きで好きでたまらないカナミさんに対して、おそらく年下のサイキさんのいかにもツンデレっぽい応対。笑ってしまいますね。 と、ここまで書いていて、ミクさんとサイキさんが気が合わないだの、カナミさんとサイキさんが妖しいだの、といった話は結局BAND-MAIDの個性を売り出す、さまざまな尾ヒレつきの物語になっていて、バンド仲間自身がそれを楽しんでいるフシがある。私もしゃべっていて、何だかよくある体育系の女子アニメ(観たことありません)を観ているような気がしてきました。 いずれにしても、サイキさんがBAND-MAIDに止まる決心をした瞬間に、彼女もグループもそのありようと方向性の輪郭がハッキリして来たのではないか?
2022.11.06
コメント(0)
-
THE BAND-MAID rising 3.
彼女たちの話を聞いていると、ミクさんは熊本時代からメイド喫茶でアルバイトしていた由で、結局通算で三年ほど働いておられたらしい。私は思うのですが、三年も同じアルバイトをしていれば、接客のポイントとか、メイドという自身の振りもだんだん分かってくるのじゃないか、私はメイド喫茶に行ったことはないので、想像するしかありませんが、接客業というのは多かれ少なかれ、一種の「扮装」の仕事だと思うのですよ。 この場合の「扮装」とは、外見だけの話ではなくて「与えられた役を演じ切る」という、気持ちの切り替えのようなことを言っています。まあこれは何も接客にかぎらず、営業職だって公務員だって、仕事となれば多かれ少なかれ「求められた役を演じる」という部分があるものですが、この「演じる」という意味あいを本当に分かって、仕事してる人って案外少ないのではないか?「役を演じ切る」には、自身も含めた仕事場を、ちょっと距離を置いて俯瞰するような構えが必要なのです。 ミクさんはメイド喫茶をたんなるアルバイトではなく、自身も含めた仕事する側、やって来る客の反応など、つぶさに知る機会として、見ていたのかもしれません(想像ですよ)。 なんでこんな話をしているかというと、BAND-MAID結成時、ミクさんのヴォーカルにギター、ドラム、ベースをそろえた時に、ロックバンドで行くなら、もう少し低いヴォ―カルが欲しいということで、最後にサイキさんを引っ張った。で、ツインヴォーカルなら面白いけれども、それならギターもツインで行こうということになって、彼女はその時からギターを始めたというのです。 このあたり、ミクさんの発想はとても興味があるというか、物事に対する姿勢が面白い。言い出しっぺのバンドで、当然自分がリードヴォーカルをやっていくつもりが、BAND-MAIDのコンセプトを考えたとき、むしろ上のような次第が面白いとなれば、自身の役に必ずしもこだわらない、さらにバンドとしての守備範囲も拡がるとなれば、役柄を変えて、やったことのないポジションに挑戦するという姿勢がです。 ここで私はまた妄想するのですよ。ミクさんはメイド喫茶の三年間、たぶんたんなるメイド仕事じゃなく、かなりマネージメントにも関わっていたのじゃないか、自身も含めたメイドという役回り、あるいは客層の観察とか、経営の実際というものを。どういう女の子が仕事ができ、どんな客が上客か、トラブルはどう回避するかといった、まあ生きていく上での世間知みたいなものです。間違いないのは、十代前後でポッと世に出るというか、街角で拾われたアイドルのような、世間知らずでは絶対なかったということです。 そうした彼女がバンド結成を思い立ち、人探しに乗り出したとき、動画がステキだからとか、自分と相性が良さそうといった基準で、仲間を募っていったとは、やはり私には考えにくい。もっともっと戦略的な考え方で臨んだであろうと思うのです。 カナミさんにアプローチするまでに、ミクさんがどのような人探しをしていたか知る由もないのですが、これまた想像ですが、おそらくカナミさんのUPした動画の出来映え以上に、彼女の音楽に対する「取り組み姿勢や、ものの考え方」を観察していたのではないか、という気がする。ミクさんはおそらくざっくばらんに、メイドコスチュームのバンドというコンセプトを、カナミさんに話しただろう。カナミさんはすでに自作自演の動画をいくつも出していて、さらに作りためた作品を世に出す機会について、いろいろ模索していたのだろう。そうしたタイミングで来た話で、ミクさんの話すコンセプトをどうとらえるか、彼女は案外早く「これはいける」と判断したのではないか?それが証拠に彼女は自身の楽曲づくりに参加してもらっていたドラムのアカネさんをすぐ誘っているのです。で、そのアカネさんが音楽学校時代の知り合いのミサさんを引き入れた。 バンド編成として、リードヴォーカルにギター、そしてリズムセクションとしてのドラムとベースが、案外短期間にそろったわけですが、メイドコスチュームという出で立ちについて、新しい二人はどう捉えていたのでしょう。二人ともすでに現役の楽器奏者として活動しており、ご自身の技量についてもそれなりの自信があったに違いない。いうたら何ですが、カナミさんは書き貯めた作品が発表できるなら、メイド姿でも何でも構わないというか、こういう創作家によくある本質的に天然な感じがあって、十年近くたった今でもミクさんと同様のメイドコスチュームをしているのは彼女だけです。 ほかの二人はリズムセクションということもあったのかもしれませんが、「そんな恰好、やってられるか!」とばかり、出で立ちに抵抗の跡がありますね(想像ですよ)。ミクさんもそのあたり、いかにもこだわらない人で、音楽事務所が作ったバンドじゃないので、ゆるい縛りで済ませたようです。 問題は最後に入ったサイキさんのことですが、話が長くなったので、BAND-MAIDの珍しいインストルメンタルだけの作品「ON SET」を聴いてみましょう。演奏力の技量が知れる素晴らしい音楽ですよ。
2022.10.30
コメント(0)
-
THE BAND-MAID rising 2.
さて、前回取り上げた三曲に「FREEDOM (Official Live Video)」を加えると、今現在の彼女たちのもっともスタンダードで、入りやすいライヴパフォーマンスということになるのでしょう。いずれもごく親しみやすいメロディーラインに、分厚いハードロックのサウンドを取り混ぜて、とてもゴージャスな雰囲気を曲に与えていますね。 で、それを可能にしているのは、各パートのスキルが飛び抜けて優れていて、いずれも個々に聴かせどころを持っているからで、曲じたいもそれらを際立たせるように工夫してある。ロックにかぎらずグループというのは、ややもすると傑出した一人か二人に引っ張られて、どうしてもそちらに焦点が行ってしまうものですが、このバンドグループは五人のメンバーが、ほぼ均等にその存在を主張していて、この豪奢な感じというのは、他ではあまり見られないような気がします。といっても、ほかのガールズバンドを、そんなに聴いたわけじゃないけど。 となると、このグループのサウンドがどのように形成され、十年近く同じメンバーを維持してきたのか、というのがどうしても気になってきますね。彼女たちの話によるとグループ結成二年ぐらいまでは、メイドコスチュームでやるということは決めていても、ポップアイドルで行くのかロックで行くのか、いろいろ模索があったらしい。で、その方向性がハッキリ決まったのが、「Thrill (スリル)」という曲で、強いハードロックのサウンドの上に、ポップなメロディーラインに乗せるという、現在のBAND-MAIDスタイルがよく出ていますね。彼女たち自身もこれの出来映えには納得していたようで、「この路線で行こう」みたいな話になっていたようです。 それにしてもこの曲の発表が2014年。ところが驚いたことに、この曲の発表をもって、グループの解散話が出ていたとか。まあ音楽業界にかぎらず芸能界というのは、新しいタレントを二年ぐらいかけて売り出して、それで芽が出なければ、そこでおしまい。また新しいタレントの発掘に注力するというのが、(予算という大人の事情もあるし)だいたい普通な世界なのでしょう。 とはいえ、この「スリル」のMVが、アメリカのJ‐ROCK専門チャンネル(日本のロック専門のサイト、こんなのがNETにはあるのですね)に取り上げられて、欧米で先に話題になった。 BAND-MAIDはそもそもその結成当初から、欧米も視野に入れた曲作りを意識していたようですが、ネットの「コメント欄が急に英語であふれ出して、ビックリした」とミクさんが語っているように、どう欧米市場にコミットしていくかというような話は、まだ具体的にはなかったようです。 そういう意味で、彼女たちの躍進は偶然と幸運から始まったとも言えなくはないのですが、もちろんそれだけですべてが片付くというわけではなくて、この曲がよく練られた作品だったから刺さったということでしょう。それが証拠にいまだにあちらのチャンネルでは、「Thrill」の再生回数がほかの傑作群を押さえて一番多いらしい。まあUPされたのが、一番古いということもあるのでしょうが、初見の人でも「覚えやすい、分かりやすい」ということが大きかったのではないか?それともう一つ、欧米ではジャパニーズ・ガールズバンドというのが、BAND-MAIDに先だって、BABY‐METALというグループのKAWAIIジャパンカルチャーを押し出した活躍で、その筋の人たちには、よく知られていたということもあったでしょう。 それにしても、「スリル」のヒットまで試行錯誤していた二年間、発起人というか言い出しっぺのミクさんはじめ、五人のメンバーは必ずしもゴリゴリのハードロックサウンドということに、こだわっていなかったらしい。むしろどうやって「このグループの存在を、世に知らしめるか」ということのほうが、優先課題であったようです。このあたり、仲良しの音楽仲間で好きな音楽をやりたい、といったインディーズグループとは少し考え方が違う。はたまた音楽事務所やプロダクションが仕掛けた、出来合いのガールズバンドというのとも違う。 となると、やはりバンド結成の経緯には、もっと入り組んだ物語があっただろう、という気が私には強くするのです。メンバーの出身地を見ると、ミクさんが熊本、カナミさんは神奈川、アカネさんは兵庫、ミサさんは岡山、サイキさんは山梨というように、カナミさん以外は首都圏外、おそらく二十歳前後の音楽好きの女の子たちが、かなり大きな夢を描いて東京にやって来た。それぞれが自分の夢を実現すべく、いろいろ活動していたのだろう、という風景が浮かびます。そういう時、秋葉原のメイド喫茶でバイトしながら、音楽活動を模索していたミクさんが、メイド服姿のガールズバンドを作ったら、面白いんじゃないかと思い立ち、メンバー探しを始めたというのです。 ことの発端は、ネットの動画サイトに自身の歌を投稿していたカナミさんの動画が、ミクさんの目に止まり連絡を取ったのが始まりというのですが、見ず知らずの人同士が、ネットの情報だけですぐ意気投合というのは、今どきの出会い系じゃあるまいし、そんな軽いノリでスルスル事が進んだとは、古錆びた年寄りのアナログ人間には、到底信じ難い話ではあります。
2022.10.26
コメント(0)
-
THE BAND-MAID rising 1.
LiSAさんの話をしているときに、彼女にとっての本籍であるロックをYouTubeで聴いていたら、またまた気になる音楽を見つけてしまいました。BAND-MAIDの「DOMINATION (Official Live Video)」というのを見つけて、大いに驚倒したというわけです。 私だけではないと思いますが、このBAND-MAIDというガールズバンド、その扮装からして、たぶん「よくあるアイドル系バンドの一種じゃないの?」と思っていた人が多いのではないか。ところが実際に聴いてみると、ごくポップなメロディーラインの下半分で、ゴリゴリのハードロックサウンドが吠えまくっている、という仕掛けになっているのです。私たちはメイド服姿という見た目と繰り出されるサウンド、さらにポップとヘヴィメタサウンドという二重の落差にさらされて、目が眩むということになります。しかもその演奏歌唱ともスキルが超一流。こんなバンドだったのかと、今ごろになって目を向いたというわけなのでした。 このバンドで面白いのは、ミュージックビデオの音楽より、ライヴ映像のほうがはるかに出来がいいというか、さらに工夫が加えられて聴きどころが増えているということでしょう。ライヴ演奏を重ねながら「こうしたほうが、もっと面白いんじゃないか」といった、常に進化を求めてやまない姿勢には、大いに好感が持てますね。 まあ、最近のライヴでの録音技術や編集技術が、スタジオ録音と遜色ないぐらい格段に進んでいるということもあるのでしょうが、となれば臨調感に勝るライヴのほうが、LiSAさんの「THE FIRST TAKE」のときと同じく面白いに決まっている。一発勝負の緊張感と観客のレスポンスは、とてつもない迫力を音楽に与えるのです。 というわけで、もう一曲「Don't Tell Me」のライヴを聴いてみたいのですが、残念これはオフィシャル映像はMV以外、単体では公開されてないらしいので、リアクション動画に頼らざるを得ません。リアクション動画の性質上、途中でおしゃべりや音楽を止めてコメントが入る場合が多いのですが、それの出来るだけ少ない動画を見つけたので観てみてください。 先の「DOMINATION」のライヴ動画と同様、ヴォーカルもインストルメンタルも絶好調なうえに、観客のレスポンスもうまく取り込んで、すごい出来映えとなりました。オフィシャル動画との大きな違いは、明らかに真ん中のギターとベースのバトルで、この曲の白眉と言っていいのですが、これって私にはずいぶん懐かしい響きなのかなと思ったりもします。 私はハードロックには70年代に、一時少しだけはまったことがあり、ほとんどのタイトルもグループも忘れてしまいましたが、それでも確かにかつてこんなことをやっていたな、という記憶がよみがえる。とはいえ、そんな記憶をほじくり返してるヒマはないので、「そうか、今どきの若い世代は、こんなふうにロックを演奏したり、聴いているのか」と思うと同時に、「では、その仕掛人は、いったい誰なんだ」というほうに関心が向くということになります。よくあるじゃないですか、AKBじゃないですけど、腕利きのプロデューサーが、今ふうのトレンドを取り込んで、あたらしい音楽のビジネスモデルを作り出すということが。 ところが、このBAND-MAIDにかんしては、そうした既存プロダクションの影が薄いというか、「ない」のです。このグループの結成は案外古くて、今からほぼ十年前の2013年、熊本から出て来て秋葉原のメイド喫茶でアルバイトをしていた小鳩ミクさんが、音楽グループを結成したいと思い、シンガーソングライターをやっていた遠野歌波(カナミ)さんに声をかけたのがきっかけ。で、カナミさんが知り合いのドラマー廣瀬茜(アカネ)さんを誘い、アカネさんが同じ音楽学校のベース奏者MISA(ミサ)さんを引き込み、さらにミクさんが同じ事務所の彩姫(サイキ)さんを引っ張って出来たというのですが、現状の五人の驚異的なスキルを考えると、何だか話がスルスルとしすぎな感じもしますね。 とはいえ、そっちの話を詮索するよりも、やはり当面は彼女たちの音楽をもう少し楽しみたい。というわけで、もう一曲「PLAY」.
2022.10.19
コメント(0)
-
エレクトーンというガラパゴス 35.
LiSA’s blade ここであらためて、PVに使われたLiSAさんの「炎」を聴いてみると、テンポは多少早くなっているとはいえ、発語やブレスの位置など、厳密に「THE FIRST TAKE」と同じで、formatじたいはいささかも変更していないことが分かる。であるにもかかわらず、私たちはまったく別の音楽を聴いたような印象を受けてしまう。先にも言いましたが、これはどちらが好いとかという話ではなくて、それぞれの音源には、それぞれの目的やコンセプトがあって、それに沿って制作されているということです。 さて、以下は例によって、私の完全な妄想話となります。 「彼女の頭の中に、『声』が飛び込んできた」というのは、私の解釈ではLiSAさんの身体に、不意に上から別の声が降りて来た、というふうになるのですが、この場合の上からとは、自身が意図した歌唱とは別の声が、外から降りて来て身動きできなくなった、あるいは「別の声に唄わされている」という感覚になったのではなかったか?「途中で落ち着かなきゃ~」というのは、その常ならぬ声にわが身を任せていいのか、操られるまま唄っていったら、音楽が壊れてしまうのではないか、というような恐れを現していると思うのです。 LiSAさんはおそらくその時、我が身をその「声」に任せるほうを選んだので、おしまいのほうでは、ほとんどしどけないほどの歌唱を見せることになりました。彼女は技術的にもそうですが、歌唱が壊れる寸前のところで、何とか踏みとどまっているような、非常に危ない唄いかたをしているわけです。いわば刃の切っ先線上を伝い歩きしているような印象を受けるでしょう。 とはいえ彼女はライヴでは、いつでもギリギリの歌唱を披露してきたわけで、そのあたりの予感と対処の仕方はある程度知っていたかもしれません。 しかし、また元に戻りますが、唄い終えたあとずいぶん時間をかけて、考え考え「いろいろなことを~」と語りだすところを見ていると、私はここの「思い出しました」という言葉は、たぶん後付けなんだろうと思ってしまう。「常ならぬ声」を聴いた後の感覚を、とりあえず自身も納得させるかたちで合理化した、ということではなかったか?もしそれが明瞭な感覚だったのであれば、もう少し早くコメントがあってもいいような気もするのです。 これはもちろんLiSAさんを揶揄しているのではなくて、こうした「常ならぬ声」に導かれるなどという感覚は、純粋個人的な体験に属するもので、そもそも言葉で説明不可能な種類に属するのです。イチローがどんなに自身のバットコントロールを説明したところで、結局誰にも共有出来ない純粋個人の感覚であるように。したがって彼は比較的早くから、そうした話はしなくなったでしょう。 で話は、ではその「声」とは何であったか、という命題にまた戻るのですが、それはたぶん炭次郎や煉獄やLiSAさん個人の「痛みや悲しみ、怒り」ではなく、それらのさらに奥のほう、ヒトだけが持ちヒトだけが共有することの出来る「痛みや悲しみ、怒りの声」であったろうという気がする。動物は身体的「痛み」を感じることは出来ても、心の「痛みや悲しみ、怒り」を感じることは出来ない。そうしたヒトだけに通底する「痛みや悲しみ、怒り」から来た、はるか奥からの「声」を聞いたのでしょう。 これは歌手にかぎらず、いわゆる優れた芸術家に通有に備わっている感覚で、自身の穴ぼこを掘り続ける作家や、目くるめく光に立ち向かうことをやめない画家、法悦の感覚に溺れて、自身の命を顧みないような音楽家は、これまでに何人もいましたよね。 LiSAさんが唄う第三節、「手を伸ばし、抱き止めた、光の束~」と続くところ、彼女は手の表現がとても巧みで、歌が身体表現であることを強く感じさせる人ですが、「輝いて消えてった、未来のために~」 で広げられた両手は、私にはまたしてもリルケの「ドゥイノの悲歌」の一節を連想させます。― ああ、たとい私がいかに叫んだとて、いかなる天使が聞いてくれよう? すべての天使は恐ろしい ― この場合の天使とは、もちろん宗教的な意味はなく、絶対的美を体現するものとしての「天使」なのですが、美はそれに近づこうとする人間を拒みはしないが、近づく人間をことごとく焼き尽くす、そういう相貌を片方で持っているということです。LiSAさんが「常ならぬ声」を聞き、それに我が身を任せながら唄っていたら、終わりのほうでは、その「声」の放つ光芒のすさまじさに、思わず手をかざしてしまった、というふうに私には見えてしまう。 それにしても、いちばん最後に、「この白い空間、ずるいと思う」と照れ隠し気味に笑うLiSAさんを見ていると、何やら医務室で身ぐるみ剥がされて、身も具も全部見せてしまい、「しまった!」みたいな気分があって面白かった。 彼女がこの先どんな道筋をたどられるのか、想像もつきませんが、LiSAの刃が光り続けることを願ってやみません。
2022.10.14
コメント(0)
-
エレクトーンというガラパゴス 34.
LiSA’s flame 時系列をたどっていくと、オープニングテーマ「紅蓮華」の発表は、テレビアニメ{鬼滅の刃 立志編」の放映に合わせた2019年4月、「THE FIRST TAKE」の「紅蓮華」が発表されたのは2019年12月5日で、同年末には「紅白」初出場をLiSAさんは果たしています(動画の中に、それらしき言及がありますね)。「THE FIRST TAKE」の開設は、同年の2019年11月5日で、彼女の「紅蓮華」はこのサイトがUPした5曲めになるのですが、開設運営者が言うとおり、このLiSAさんの歌唱で「THE FIRST TAKE」のコンセプトは、完全に固まったと言っていいのでしょう。 それは言ってみれば、世の中が「鬼滅」フィーバーで沸くなか、独立した音楽としての「紅蓮華」、ヴォーカリストとしてのLiSAさんに、どこまでも肉薄してやろう、ということだったのではないか。マイク一本という超シンプルな画像なのに、カメラもマイクも歌い手の一挙手一投足を、寸刻も逃すまいという構えじゃないですか。 面白いのは、この出来上がった「THE FIRST TAKE」の音源は、そのままテレビアニメのオープニングに使うわけにはいかないということです。なぜなら、この「紅蓮華」はそれだけで、テレビアニメ「鬼滅の刃」の世界観を、語り尽くしているからです。もし、この音源を番組のはじめに聴かされたら、かんじんの本編が、かすんでしまうかもしれない(「音楽負け」という言いかたを、フィギュアスケートで言ったりするじゃないですか、曲が壮大すぎてスケーターの演技が、追いついていけない場合など)。 そういう意味で、作曲者や作詞家がどれだけ原作や原案に共鳴し、精魂を傾けて作品を作り上げたとしても、むしろその完成度が高いほど、実際に使われる音楽はその半分ほどの中味でパッケージされる運命にあると言っていい。オープニングテーマのコンセプトが、本編に視聴者をいざなう役目を負っている以上、それは仕方のないことなのです。 という意味で、あらためて「THE FIRST TAKE」の「紅蓮華」を聴いてみると、逆に本編に縛られないぶん、LiSAさんのナラティヴな力が存分に発揮されているように感じる。narrativeという言葉については何度か触れたことがありますが、たんに「物語」を語るのではなく、より「共感性あるいは想像力を、聴き手の心に喚起する」ような語りかたを言うので、いわゆるstory tellingとは異なる。 それが如実に表れたのが、先にも触れた中間の「人知れずはかない、散りゆく結末~」と続くブリッジ部分の朗誦で、ここの根を詰めた発語のしかた、明らかにLiSAさんの「鬼滅」感を雄弁に語っていて、これはやっぱりオープニングには使えませんね。最近アメリカのラッパーと思しき人物の、笑ける「紅蓮華リアクション動画」が出たので見てみてください。 さて、「炎」はほぼ一年後の2020年10月16日の発表で、劇場版「鬼滅の刃、無限列車編」の公開日にあたりますね。この年は年末の日本レコード大賞、「紅白」の二年連続出場など、LiSAさんにとっても画期の一年だったでしょう。 じつはこのかん、彼女は「THE FIRST TAKE」に、「unlasting」(19年12月25日)と「catch the moment」(20年10月28日)というアニソンを前後して発表していて、「一発撮り」の面白味というのを充分熟知していたことでしょう。この二曲も彼女らしさ満載の歌唱で上出来ですよ。ではLiSAさんはこの「炎」の一発撮りに、どのように臨んだのでしょうか?映画の公開日と同じということは、OSTのエンディングテーマと「THE FIRST TAKE」の「炎」のUPが同日だったということで、どっちが先の収録だったのか、これも私の関心を引くところですが、些事にわたってキリがないのでここではしません。 いずれにしても映画本編に盛られた世界観を、一年前の「紅蓮華」のコンセプトに沿って、歌唱だけで克明に描き切ろうとされたに違いない。したがって伴奏も華やかなインストルメンタルやコーラスを排して、ピアノ一本。テンポもOSTより「紅蓮華」と同じように、心なしゆっくりしていて、歌詞の意味するところを、じっくり伝えたいということなのでしょう。 歌は当然曲想に沿って、「痛みと悲しみ、あるいは怒り」のような色調を、さまざまな発声法を駆使しながら、唄われいくわけですが、ここでかの美人ヴォイストレーナーが、「そしたら、突然彼女の頭の中に、『声』が飛び込んできた」という場面が現れます。それがどこかは判然としませんが、このトレーナーさんはかなり早く、その気配を嗅ぎ取ったようですね。ではその『声』とは、いったい何だったのか? LiSAさんが歌い終えたあと、気持ちを鎮めるように、だいぶ経ってから「いろいろなことを思い出しました」とか、「今までのいろんな自分の中の思いが、~途中で落ち着かなきゃ、落ち着かなきゃと思いながら、~すべて息も想いも、この中(マイク)に入って行った気がした」と語った言葉、おそらく自身のこれまでの順風とは言い難かった、歌手人生も重ねていたんだろうとなるわけですが、どうもそれだけでは、私は片付かないような気もするのです。
2022.09.23
コメント(0)
-
エレクトーンというガラパゴス 33.
LiSA’s Language それにしても、日本語を知らない外国人に、LiSAさんの音声はどのように聴こえているのか?彼女の歌声を、なかにはacrobat voiceと表現する人もいて、それを英語とは違う日本語の特性のようにも言うヴォイストレーナーもいるのですが、もちろん日本人の私だって、彼女のような日本語は聴いたことがないのです。 これはまぎれもなく、アニソン界で創り上げられた独自の音声なのだと思うのですが、訳文が付いているとはいえ、結局彼らの言っていることはイマイチ腑に落ちない。要はベルティングだのチェストヴォイスだの、専門用語が頻発するからそうなるので、日本人のこの手のリアクションはないかと探していたら、いくつかありました。しかしたいていが便乗型の受け狙い動画で、どうも私にはしっくりしない、外国以上に業界用語を振り回す人も多いのです。 その中で少し面白いと思った動画があったので、一つ紹介します。北米にエンタメ留学していたMayuさんという現役歌手(存じ上げません、すいません)の「Mayu’s洋楽Study」というサイトなのですが、そこで「紅蓮華」のリアクションと解説をしてらっしゃる。このかた、コテコテの大阪出身のバイリンガルみたいで、欧米流のズケズケした指摘が、関西なまりのツッコミで入るので、けっこう面白い。 で、この人もやはり「THE FIRST TAKE」のテンポは遅いとおっしゃる(1.5倍とは思わないけど)。さらに興味深かったのは、従来のヴォーカルというのは、一般に発声法を一曲中でちょくちょく変えるということはしない、という点でした。なぜそうなのか、という説明はなかったのですが(そんなことあたりまえやん、という口吻り)、例えばオペラやミュージカルだと、各々が別々の発声法をやったら、音色が合わなくなるということはあるでしょう。あるいは発声法をひんぱんに変えると、音程が不安定になるとか、だいいちそもそも面倒くさくて誰もやらないとか。 逆に言えばLiSAさんの発声は、あらゆる発声法のオンパレードみたいのが、一曲中どころかワンフレーズ内に出て来て、しかもそれがことごとく正確にヒットしている(音程を外さない)ということなのです。 以下はまったくの私見ですが、これはやはりLiSAさんがアニソンのあらゆるキャラクターにアジャストするために、多種多様な発声法を身につけた結果なのではないか、と私は想像してしてしまいます。声優さんはキャラクターごとに、声音をまことに器用に使い分けるじゃないですか。で、それが逆に今のLiSAさんの歌唱を特徴づけている大きな要素だと思うのです(全部とは言いませんよ)。 それともう一つ、発語の明晰さもアニソンならではないか?劇中歌でもそうですが、アニメの挿入歌というのは、ミュージカルは別としても実写版以上に、話の中味にかかわって来ることが多いように思う(これも想像)。である以上、発語が明晰であることは、アニソンの必須条件になるのです。 私が音楽の歌詞に惹かれたのは、1970年代の和製フォークからでした。それまで洋楽一辺倒、日本語の歌詞に目を向けるなどということはまずなかったのですが、陽水や拓郎が嫌でも耳に入ってきて、で、その言葉がやたらに耳に刺さる。それまで和声ポップスなんて聴きもしなかった私ですが、彼らは「歌詞の理由」を知らせるために、私の耳を無理やりこじ開けたのです。当時の歌謡曲の歌詞といえば、これまた素人の印象ですが、いまだ和歌や浪曲のような紋切り口調を引きずっていて、私には全然届かない、そういう代物だと思っていたものです。 洋楽のそれもインストルメンタル中心、ヴォーカルは結局その言葉の意味ではなくて(英語は分からない)、発せられる声音の「響きの魅力」として聴いていたので、歌曲を聴く態度としては、かなり片手落ちだったということになりますね。とはいえ、和製フォークが歌詞の理由を知らせてくれたといっても、それに深くはまるということはありませんでした。 今回のLiSAさんの発語、とくに「紅蓮華」で顕著だと思うのですが、言葉の意味する中味と発せられる音声の響きがテンポよく連動して、まことに小気味よく私の耳に届く。長ーいベルティングも一本調子じゃなく、体でテンポを取りながら、おしまいの語尾をキチッと発声するので、グルーヴ感に浸りながら言葉の意味もスッと頭に入る、という仕儀になります。こういう唄いかたというのは、なかなかないですよ。 あるいはひょっとして、PV版の「紅蓮華」でヴィジュアルとしては納得できても(さすがパンクロック出身ですね)、LiSAさんとしては音楽として飽きたりなかったものを、「THE FIRST TAKE」で試みたのではないか、と私は思っています。間違いないのは、PV版とかOST版では、私の耳には絶対届かなかったということです。 というわけで、彼女にとってパンクロックから転換して(たぶん芽が、なかなか出なかったのでしょう)、アニソンの世界に入ったというのは、結果的に大正解だったということになりました。彼女の創り上げたアニソンの発語法が、今やそれをはるかに飛び超えて、世界を席巻しているからです。 それにしても、「紅蓮華」の作曲は草野華余子さん、作詞はLiSAさん本人、「炎」の作詞作曲は梶浦由記さん、ついでに言えば「鬼滅」の原作者吾峠呼世晴(ごとうげ こよはる)氏 も、じつは女性らしいということで、日本の女子力はものすごいね。
2022.09.12
コメント(0)
-
エレクトーンというガラパゴス 32.
LiSA’s anison LiSAさんと言えば、いまやアニソン界の女王と言われていますが、この呼称は何だかおかしい。日本のミュージック・シーンでアニソンが普通に唄われ出したのは、せいぜいこの四、五年で、それ以前は傍系もしくはまともな認知さえされていなかったのではないか? 私は日本の音楽エンタなど、まったくの関心の外なので、あまり大きな声では言えないけれど、音楽業界の本流としてはアイドルグループが全盛で、その周りをJ・ポップや歌謡曲の歌い手が取り巻いていて、アニソンやゲームの付帯曲など、存在しないも同然だったのではないかしらん。それをあたかも以前からアニソンが日本の音楽シーンに、ジャンルとしてれっきとあったかのようにして、「アニソンの女王」と祀り上げるのはおかしい。彼女はアニソンの女王ではなく、「アニソンの創造者」なのです(もちろん、これは彼女一人の功績ではないけれど)。「だって、久石譲がいたじゃん」と言われそうですが、彼はたまたまジブリと出会って、自身の音楽実現の方法を見つけたのであって、アニソン・プロパーではないというスタンスでしょう。 LiSAさんの場合は、ロック・ミュージシャンからさまざまな経緯があって、アニソンのテーマを引き受けるようになった。で、アニメに求められる音楽を、自身のパフォーマンスと向き合いながら、創り上げて定着させた(一時、声優も志したようですね)。で、いつのまにやらアニソン独特の発語や唱和が認知されるようになっていった、という経過になるでしょう。これは良くも悪くも、一つの「定型」感をアニソンに与えることになったので、アニメを見れば必ず同じような乾いた響きが流れる、というような景況も呈することになったのではないか? いずれにしても私などアニソンの響きなど、アイドルグループの喧騒と同然で、もっとも縁遠い存在として聞き流していたものでした(子供が聴いていたから、しょうがないでしょ)。 私から見ると、「THE FIRST TAKE」の「炎」は、「紅蓮華」からさらに一歩進めて、アニメから独立したよりスタンダードなヴォーカル、ひらたく言えば「鬼滅」を見ていなくても、聴く人に充分届けられる音楽になったのではないか?早い話、私のような頑ななるクソじじいにも、やっと届いたわけです。 ところでこのところ、とくに外国で大はやりのreaction動画、日本人は私も含めて顔出しでの感想動画というのは、大いに怯むところがあるのですが、世界は芸能人や政治家はともかく、一般人でもとにかく「認知」されるためには顔が一番とばかり、ごくふつうに皆さんUPしているようにみえる。そのなかには、このLiSAさんの「THE FIRST TAKE」に対するreactionも結構あって、かぶりつきの近撮だからか、あるいはLiSAさんの発語が明晰だからか、ヴォイス・トレーナーなる人たちの動画もあるのです。 で、これらはあちらのアニメオタクの感想ではなく、こうした自称音声の専門家たちは、おそらく「鬼滅」を観たことないだろう、ひょっとするとアニソンじたい初めてかもしれない。とすれば、より客観的なreactionがみられるかなと思っていたら、ほとんどの投稿者が最後涙ぐんでいるので、笑ってしまいました。抄訳(誰が翻訳しているのですかね)が付されている動画を挙げてみます。 美人ボイストレーナーが聴く!炎へのリアクション! 女優かと見まがう美人さん(ホンマに!)ですが、顔の表情も言葉も正直で面白い。最後は感極まって言葉を失ってしまいましたね。こっちにも別の記録映像が現れることになりました。彼女はおそらくアニソンどころか、日本の歌手のヴォーカルなど初めてだったので、驚きの連続だったのでしょう。それでも途中、私的には大事なコメントをしていて「不意に彼女(LiSA)の頭の中に、声が飛び込んできた」というところ。彼女は音楽のミューズが、この時LiSAさんの身体に嵌入してきたと感知しているのです。 もう一人紹介しておくと、こちらは以前「紅蓮華」のreaction動画も出しており、LiSAさんの声も実力もかなり知っていて、あるいはアニソンも聴き、アニメも観ているのかもしれない。プロのボーカルコーチがLISAの炎解説で涙 途中割って入って、さかんに彼女の発声法を解説するけれど、曲が進むたびそれを覆す響きが現れて驚倒している。多少やりすぎな感じはしますが、新たな発見と驚きを楽しむという姿勢は悪くないですよ。 それにしても、この種のリアクション動画、スペインだのイタリアだの、中国韓国だのさまざまなところから寄せられていて、いまだに続いているのが面白い。日本人はインスタやTikTokに映える画像や動画をUPするのが精一杯で、この手の感想は、顔の出ないコメント欄への書き込みやSNSでのおしゃべりで終始させているのではないかしらん。
2022.09.08
コメント(0)
-
エレクトーンというガラパゴス 31.
LiSA’s document テレビやミュージックヴィデオ、あるいはCDなどは、音楽を撮るのに1テイクで済ませるということは、まずないでしょう。とくにCDなどは商品として世に出すので、一つの傷もないように、何度も撮り直しをくり返して仕上げていく。結果、出来上がった音楽は、口当たりはいいけれど、意外と生気に乏しい響きになったりもする。このあたりの判断は、ディレクターとかミュージシャン本人の趣向にかかってきます。 対するにライヴ演奏はポップ、クラシックを問わず、いったん始まったら誰にも止められない。失敗も含めて取り返しのつかないパフォーマンスを、そのつど披露するというのが、ライヴの醍醐味ということでしょう。もう一つライヴの妙味は、これまたポップ、クラシック問わず、そのパフォーマンスに聴衆が関与できる状況があり得るということなので、その痕跡をわずかでも演奏に見止めたときは、大満足を得るということになります(だって、そのパフォーマンスは二度と起きない類のものじゃないですか)。 クラシックなんて畏まって聴いてるだけじゃん、と思われるかもしれませんが、会場全体を領する空気というか、聴衆の呼吸というのは、案外指揮者は背中に感じているはずだし、私的にはそうでないとちょっと困る(聴き手まったく無視で、忘我の境に入ったきりという演奏をする、あるいはそのふりをするアーティストが、世の東西を問わずいますが、案外つまらないことが多い!?)。 で、このライヴの一回こっきりのスリルを保証するものは何かと言えば、これまた話が戻りますが、「生きた身体」の介在そのものなのです。ものすごい音響機器を並べて、生演奏でございとやられても、これは論理必然的にライヴにはなり得ない。そのパフォーマンスは何度でも再製可能だからです。 と、考えてくると、LiSAさんの本籍がロックミュージシャンだというのは、示唆的ですね。私はとてもじゃないが、ロックフェスのようなライヴにはついていけないので、動画をチョイ見するレベルですが、パフォーマーが煽り、煽られた聴衆の興奮がさらにパフォーマンスを加速するというのは、こうしたライヴの一種定番でしょう(私はライトペンを合わせて振る、聴衆の趣味がサッパリ分かりません、すいません!)。 しかしこれも前に言いましたが、クラシックのコンサートでも、聴衆の興奮した呼吸が楽員に反射し、それを検知した指揮者が驚愕しながら、未踏のフィナーレに突入する、という演奏がたまにあるのです(だからと言って、それがクラシックの魅力すべてということじゃ、もちろんないですよ)。 「THE FIRST TAKE」は、スタジオ録音に一発撮りというタガをかけることで、ライヴのようなナマな感じを企図したのでしょうが、それは期せずして動画にドキュメンタルな印象を与えることになりました。つまりコンプリートな作品としての音楽ではなく、「音楽が立ち上がる瞬間の記録映像」のような作りに、結果的になっているということです。 ちなみに、カラヤンはコンプリートにこだわった人で、本人は間違いなくその記録された音楽も映像も、永遠に固定され保存されるべきもの、として捉えていたでしょう。面白いのは、それでも彼の音楽にはいまだに「立ち上がる瞬間」があるのです。これについては思いつくことがあるのですが、またまた話が長くなるので、ここではしません。 このあたり、ほかのミュージシャンの動画がどうなっているかは、見てないので分かりませんが、LiSAさんの動画は間違いなくそのへんをよく理解していて、むしろそれを逆用するかように、思い切った唄いかたをしたのではないか?「紅蓮華」「炎」ともOSTやPVより、はるかにナマな作りで、アタックやブレスもより強い。であるにもかかわらず、私たちはそこから「音楽が立ち上がる」のを、ありありと見止めるということになります。 私自身の長年の禅問答、「音楽はどこにあると言えるのか?」の回答を、一つここに見た気がしました。 このヴァージョンで用いられた「紅蓮華」のテンポは、私の気のせいかもしれませんが、OSTやPVより若干遅めで、そのぶんLiSAさんのヴォーカルの神髄がよく分かる。遅めのテンポで一語一語が分かるように、さらにリリカルなヴィブラートやアタッキングを明晰にすることで、むしろよりダイナミックな疾走感を出しているでしょう。ひたすら早いのではなく、その間に動的な色合いの変化を出しているのです。で、そのさまざまな発語の色合いの変化は、連続アニメ「鬼滅」の物語に直結しているじゃないですか。 ただこの音源がもし、テレビアニメのオープニングにそのまま使われたとしたら、ちょっと困ったかもしれない。本編とあまりにも密着しすぎるのは、かえって観る側の想像力を奪ってしまう場合があるのです。 その意味で、この「紅蓮華」は「鬼滅」の物語を充分に知悉しつつ、アニメ本編から一歩「踏み出した音楽」になっている、ということが言えるのではないかしらん。で、それがいっそうあらわになったのが、「炎」だったのではないか?
2022.09.06
コメント(0)
-
エレクトーンというガラパゴス 30.
LiSA’s groove このあたり、先のJ.アンドリュースなどと違って、バーブラはマイクの使い方が、F・シナトラのように巧みで、若いころから幅広い音楽的視野を持っていたということでしょう。 前にも話しましたが、私の二十代は、ヴォーカリストとしてのB・ストライザンド全盛期(1970~1980)の時代で、舞台で鍛えた驚異的な声量と広音域、精確で独特な発語は、英語を理解できない私にも、「届くもの」があると何度も思い、なぜそうなのかと自問したりしていました。で、当時の理解では、それはたぶん言葉ではなく、「発せられる声音」そのものの心地好さ、私の言う「発語力」のせいかとも勝手に思ったりもしました。 とくに若いころのバーブラは、一つ一つの発語にものすごい神経を張り巡らせていて、ヴィヴラートのかけかた、高音域への駆け上がりかた、そして子音の結びまで、それらが音声としてどのように響き、どのように聴衆に届くか、すべて計算され尽くしている、そういう唄いかたをしていましたね。で、それに加えてミュージカル特有のドラマ性を、必ず一曲に盛り込むので、「三分間の歌に、三幕物の劇を持ち込むようだ」と言われたそうです。ただそうした唄いかたは、全体として重厚な感じにならざるを得ず、なかには「しつこい、重苦しい」と嫌う人もいましたね。 とはいえ、そうした発語の魅力で、聴くものを一瞬にして自身の世界に引き込む力というものには、なかなか出会えず、先般、平原綾香さんの発語力で久しぶりに感じたことは、前にも言いました。 では、LiSAさんのどうした発語力が、私に届いたのかと言えば、それは間違いなく「強さ」でしょう。彼女の「紅蓮華」を聴くと、もともとの地声の美しさに加えて、惜し気もなく強いアタックを連発して、しかもそれらが疾走しながら精確に音程をヒットするので、聴いていてスリリング。なんだか、それまでピーチクパーチクさえずっていた小鳥が、急に音程をそろえて唄い出す、そんな小気味良さを感じるのです。 こうした強いアグレッシヴな歌唱、昔ロックやラップで聴いたような記憶がありますが、残念ながら私の趣味ではなかったので、詳しいことは分かりません。ついでに言うと、彼女の軽い乾いた声質というのも、昔、シティポップの山下達郎などがやっていたような気がしますが、これも確かなことは知りません。肝心なことは、では、今回何が私の耳朶をチャームしているのかということでしょう。 私はそれはたぶん、またまたグルーヴ感としか言いようのないものなのだと思う。grooveの語義については、以前やったように思いますが、巷間したり顔で、ジャズやロックの専売特許のような言われかたをされては、全然腑に落ちない。私はカラヤンや小澤征爾にだって、grooveを感じてしまうのです。 askaさんの鬼滅の刃【 無限列車編メドレー 】の冒頭2分(オープニング)だけ聴いてみてください。汽車の汽笛を模したであろう悲劇性を帯びたホルンの咆哮のあとに続く、炎のモティーフ、重層的な弦の響きを巧みに処理するaskaさんの動きは、指揮者のような雰囲気を示していて、見事な全曲の開始となっています。 前にも話したように、私はここしばらく「鬼滅」のEpicversionを何度も聴いていたと言いましたが、ではそれらとaskaさんの音楽を分かつものは何かと言えば、結局この冒頭示されたグルーヴ感にあるのではないか、と思ってしまう。 Epicversionは詳しくは知りませんが、おそらく自動演奏機器を用いたサウンドでしょう。確かに迫力や音の明晰度はすごいのですが、それを超えて人の心に入って来るというところがない。たんにサウンドが鳴り響いているということになりかねないのです。 同じく極度に電子化されたエレクトーンでありながら、そこから繰り出されるサウンドは、まぎれもなくaskaさんという身体が聴き届けた「鬼滅」そのものであって、それ以外の何物でもない。と言うわけで、この「身体性の介在」こそgrooveの根源であろうという気がするのです。 LiSAさんの「蓮華紅」は、そうした音楽における「身体性の介在」というものを、きわめて分かりやすく示してくれる。ラップのような早口の歌唱のあと、「人知れず儚い~」と続く間奏部、LiSAさんの真価が現れたレシタティーボ、どんな器械がこんな朗誦できると思います?そしてそうした彼女の魅力にどこまでも肉薄しようとする、かぶりつきの映像。私は曲そのものは「鬼滅」のアニメで知っていましたが、この映像がなければLiSAさんの真の魅力を知ることがなかったかもしれません。 「音楽番組にいっぱい出とったやん !」と、またまた怒鳴られそうですが、私はテレビの音楽番組ほど(紅白も含めて)見ないものはなかったし、 テレビ番組で果たしてLiSAさんが、この「THE FIRST TAKE」のような歌唱を出来たのかどうか、じつは疑問に思っています。歌唱だけを厳密にドキュメントしているのはこの動画だけだからです。
2022.09.04
コメント(0)
-
エレクトーンというガラパゴス 29.
LiSA’s voice それにしても、やっぱり音楽の話は楽しい。アニソンとか今どきのポップにはまったく縁遠いクソじじいでも、どういうはずみでか、「新たな響き」に出くわす。私はこういう予期せぬ驚きにブチ当たるのが大好きです。 826askaさんの熱心な発表がなければ、絶対に聴くことのなかったであろう「鬼滅の刃」の音楽。まことに頑ななる私の趣味のせいで、アニメは「鬼滅」どころか、ジブリだってまず観なかったのですが、明らかにaskaさんのおかげで、ちょくちょく観る機会が増えてきました。 先日民放でやっていた「ラピュタ」は、なかなかおもしろかった。同じ系統で「ナウシカ」や「紅の豚」も好きなアニメです。しかし私がアニメをしたり顔で語ることは、まず永遠にないでしょう。生前の父がなぜか「千と千尋」と「トトロ」のビデオ(DVDと違いますよ)を持っていて、繰り返し観ていたのが私には一種のトラウマとなっていて、依怙地にならざるを得ないというところがあるのかもしれません。しかしまあこれは別の話。 以前にコロナ禍の自粛期間中、「鬼滅」のepicversionの動画を繰り返し聴いていたと言いましたが、その後これまたaskaさんがらみですが(よみぃさんという人気ストリートパフォーマーとのどっきりコラボ動画が出てましたな)、ストリートピアノ系の動画を観、ときに驚倒するようなパフォーマンスを見せるピアニストもいて、しばらくはまっていました。 しかし各人のあふれ出る貴重なリソースを、いかにもキャッチ―な大道芸(!?)に費やすのはいかがなものか、というこれまたうるさいクソじじい根性が芽を出して、ストピ指向はいたって短期間で終わりました。それにしてもキャッチ―であろうとすると、なぜあんなに音の数が多くなるのか(そのくせ音楽の種類は少ない)、あなたがたは一音で「沈黙と測りあえるほどの音」を生み出す気はないのか、と問いかけたくなりますが、この話もまた紛糾するのでここまでにしましょう。 ところがそうしたストピを外国でやっている人がいて、その人の「炎」がなかなかいいというか、リンツの住人たちが結構熱心に聴いている。で、その「炎」がこの曲を特徴づけていると、私がかってに思っていた第二フレーズ(Bメロ)を、オクターブ下げて弾いている。「ハハァなるほど」と思ったものです。国内にあまたあるストピの「炎」動画でも、こういう演奏は聴いたことがない。で、「なるほど」というのは、ではこの「炎」の魅力とは、このうねうねとした構造にあるのじゃないか、ということで、先のような感想となったわけです。 と、振り返るとホンチャンのLiSAさんを聴くまでに、だいぶ「炎」を聴きこんでいたというこということがバレてしまいましたね。 LiSAさんの地声は美しい、と先に言いましたが、これは歌い手たちにとって、基本の生命線のようなもので、一声で聴く者を魅了するような響きということです。昔、英米のヴォーカルに凝っていた時期があって、例えばヘレン・レディという実力派歌手がいて結構活躍していたのですが、同時期唄っていたペトゥラ・クラークに比べて魅力がない。何が違うかといえば、結局地声の魅力としか言いようがないのです。J・アンドリュースもミュージカル俳優としては大スターでしたが、ついにスタンダードな歌手にはなれなかったでしょう。私の大好きなB・ストライザンドが、ミュージカルスターから大飛躍してLPのミリオンセラーを連発していたのとは対照的ですね。 この違いは何なのかということになると、やっぱり地声の魅力、ヘンな意味でなく人を引き付けるセクシーさが基本にないと、どうしようもないということなのかな、と思ったりもします。B・ストライザンドの貴重なライブを聴いてみましょう。驚異的な音域の広さと、肺活量そして自在なテクニックは彼女独特ですが、やはり第一のチャームポイントは地声の魅力。いささか鼻にかかった、しかし何となく無垢な感じを与える響きは、一聴にして私たちを彼女の世界へ引き込む、そういう力があるのです。
2022.09.02
コメント(0)
-
エレクトーンというガラパゴス 28.
LiSA’s structue LiSAさんの話です。「何を今さらLiSAやねん!遅いわ」と蹴飛ばされそうですが、これまた最近知ったのですが、某有名企業が中心となって、「THE FIRST TAKE 」というサイトを立ち上げて、「一発撮り」の音楽動画を数年前(2019.11.5~)から始めているらしい。スタジオ録音なのに本番は一回かぎりということで、ライヴの緊張感も合わせ持つ動画にしようという趣向だったのでしょうか。奇しくもそれがコロナ禍と重なって、多くのミュージシャンが参加することとなりました。 その中で、圧倒的再生数を叩き出しているのが、LiSAさんの「紅蓮華」で、なんと最近までの三年弱ほどで、一億二千万回以上!コメント数が四万五千回以上というあり得ない数字で、さらにその一年ほど後に出した「炎」が、五千八百万回以上、コメント数が二万八千回以上というあり得ない数字。 とはいえ、私にとってそんなお化けみたいな数字は、あまり興味がない。むしろこの「一発撮り」のコンセプトで、初めてLiSAさんの魅力を知ったということのほうが大事なのです(やっぱり遅いね)。 「炎」の構造なのですが、一聴して分かるとおり、全体が三つの大きな山で出来ていて、それに至る道筋がそれぞれ異なっている、メロディ―ラインでいうと「さよなら、ありがとう、~」で始まるAメロ「このまま続くと思っていた~」と続くBメロそしてピークに向かう「僕たちは燃え盛る~」と続くCメロとなるわけですが、AとCの間にBメロが入っていて、これがこの曲に大きなニュアンスを与えている。LiSAさんはこのAとBの間をノンブレスで唄っているので、曲調の変化に気づかないぐらいですが、これがあることによって、スッキリした山容ではなく、うねうねとした尾根筋を登って行く、というような印象を与えますね。そしてCメロに入ると転調して、クッキリとしたピークが姿を現す、という仕掛けになっています。 この一つめの山だけでも、Bメロの存在によって充分ドラマティックな印象を与えますが、真ん中の山はさらに手が込んでいて、ABのあとCメロをとばして(「僕は守り抜くと誓ったんだ~」のあと)、転調させた新たなフレーズを重ねていますね。この部分、ソナタでいう展開部にあたるのですが、伴奏のピアノも含めてものすごい盛り上がりで、ここがこの曲の最長不倒距離かとさえ思わせます。 ここまで真ん中が盛り上がると、普通若干のクールダウンが入るものですが、曲の内容の痛切さからか三つめの山は、今度はABをカットして、いきなりピッチを上げたCメロから来る。そこでこの三つめは、これまでのうねうねとした穂高連峰のような山容とは違う、槍ヶ岳のような屹立した厳しい姿を現すということになります。 この曲の構造を考えたのは、もちろん作詞作曲編曲を手掛けた梶浦由記さん(アニソンの女王と言われているそうです)でしょうが、作詞にLiSAさんも入っているところからみて、お二人で充分練り上げた末での作品となったのでしょう。「THE FIRST TAKE 」は、そうした作曲者や歌い手の思いや意図を、かなりナマに近い形で引き出しているので、こんな話をしているのです。 LiSAさんもそうした「一発撮り」のコンセプトを意識して、普通のライブやコンサートでは見られない、時にしどけないほどの熱唱ぶり。私はどちらかというと、こうした熱演は苦手なのですが、彼女自身が歌い終わったあと、興奮を鎮めるように語っているように、「いろいろなことを思い出して~」と、もともと美しい地声の持ち主で、しかも完璧なテクニックがありながら、長く続いた不遇の期間、おそらく自信家であったでしょうから、抑えられなくなっちゃったんでしょうね。 こういう瞬間というのは、まさしく一回限りで、同じ唄いかたは二度と出来ない、そういう歌唱となりました。
2022.09.01
コメント(0)
-
エレクトーンというガラパゴス 27.
ウクライナ戦争に続いて、安倍元首相暗殺事件について話そうと思っていたところが、日ごろ時たまaskaさん他気になった動画に投稿したコメントの中に、なぜかボツになったものもあったので(おそらくリンクの問題でしょう)、整理もかねて下にまとめておきます。音柱 何かと腹を立てつつも、じつを言うとコロナ自粛期間中、何度も繰り返し聴いていたのが、YouTubeに数多く出回っている「鬼滅」のEpic Versionのサウンドでした。もともと壮大なオーケストラの響きが好きなうえに、エレクトーンとの相性も良さそうだということで、826askaさんにはひそかに期待していたのですが、満を持してというか、今回おそろしく気合の入ったパフォーマンスを見せてくれましたね。その高い志と取り組み姿勢に、取りあえず立ち上がって拍手喝采です。 askaさんは「ルパン三世」と並んで、「鬼滅」への思い入れが強く、これまでも何度も取り上げて来られたのですが、画像もよけいな背景をなくして、楽器とaskaさんだけに絞っているあたり(ついでに最後のご挨拶もなし)、今回はとりわけ「音楽だけ」を楽しんでくださいね、という強い意志の表れなのでしょう。 まあ聴いてみてください。「鬼滅の刃【 無限列車編メドレー 】 」。 さてこれは826askaさんとしては、たぶん「君の名は。」以来の独自編集のメドレーで、13分超という長尺版となりました。音楽の出来映えと時間の長さは、必ずしも連動しないのですが、今回はそれでも短い、あるいは短いと思わせてしまう密度の濃さを感じてしまう。そしてそれは同時に、この「鬼滅の刃」が映画「無限列車編」を超えて、「音楽」として別の地平に乗り出している「無限列車編」だという気がするのです。 白状しますと、私は爾来アニメが苦手で、映画館へ観に行ったことがありません。今回は音楽が好いということで、よほど行こうかと思ったのですが、結局コロナもあって行きませんでした。しかし音楽というのは不思議で、「鬼滅」のEpic Versionや今回のaskaさんの演奏を聴いていると、自分の中に独自の炭次郎や煉獄が立ち上がってくるのを感じます。 これは前にも言いましたが、その演奏が映画音楽の再現性に優れているということではなくて、ひとえに飛び切り「喚起力」にとんだサウンドを響かせているというところから来ているのです。その場合、オリジナルサウンドは新たな音楽を生む「起点」、あるいは「触発物」と言っていいのかもしれません。イプセンの戯曲「ペールギュント」など誰も知らないけれど、グリークの付帯音楽ならだれでも知っている、我々はそうして音楽のほうから、ペールギュント像を自身のうちに作り出しているじゃないですか。私はそれで好いのだと思うのです。 さて「じゃあYouTubeに出回っている「鬼滅」Epic Versionと、askaさんの演奏は同列なのか?」という問いが生まれてきますが、もちろん全然違う。話が長くなるので端折ってしまうと、Epic Versionは画像に記録された一回限り、askaさんのはまぎれもなく「生身のパフォーマンス」であって、繰り返し演奏され得るものだということでしょう。この違いは大きいのです。Flying Dutchman 年を挟んでずいぶん力作が並びましたね。二十歳になられて一区切り、という気持ちがおありだったのでしょうか。「パイレーツ」といえば、言わずと知れたaskaさんの最初のメルクマール。それを「再演」ではなく、まったく違った音楽世界で描いて見せるというところに、並々でない決意というか強い意欲を感じてしまいます。 multi taskingという言葉がありますが、askaさんの演奏はまさしく複数作業の同時進行、なにも手足が別々に自在に動かせる(ように見える)ということでありません。マルチタスクとは音楽で言えば、錯綜する複数のリズムやサウンドが驚くほど高いレベルで統合されていて、寸刻の乱れもない響きということなのです。これを聴いていてテンポの同期性は言うまでもないのですが、ハーモニーやディナーミクにも、たぶん意図されざる統合された響きが感じられて、改めて彼女のキャパシティの凄味を感じてしまいました。 それにても、ここまで洗練された演奏を聴くと、これはもはや映画「パイレーツ」ではなく、前回の「鬼滅」もそうでしたが、音楽としての「パイレーツ」が、独立して動き出していると思ってしまいますね。終りのほう、永遠に海を放浪することを運命づけられた海賊の悲哀のような響きも聴こえて、私はなんだかこの映画の元ネタ、ワーグナーの「さまよえるオランダ人」を思い出してしまいました。Waltz 久石氏がフランス古参のオーケストラ、ラムルー管弦楽団を指揮したときに、何となく手探り感のあったオケが「人生のメリーゴーランド」(1時間9分過ぎ)になったとたんに、わが意を得たりとばかりに生き生きと演奏する動画があって笑ってしまったのを覚えています。三拍子というのはウィンナワルツを挙げるでもなく、よほどヨーロッパ人の肌に合うらしい。 久石氏は西欧音楽への畏敬と造詣が恐ろしく深く、古典から現代まですべて知悉したような人ですが、初期の「風の谷のナウシカ」のサントラはヘンデルのバロックから、ベートーヴェン以降の古典とロマン派、ドビュッシー以降の印象派から現代音楽に至るすべてのサウンドを詰め込んだような音楽になっていますね。 これは何も皮肉を言っているのではなく、「ナウシカ」から発せられる音像が、そのように聴こえたからそうなった、という経路をたどっているので、ちっとも嫌味な感じがしないでしょう。 「ハウルの動く城」も同系統の音楽ですが、それを当のヨーロッパの楽団が演奏したとき、どんなそぶりを見せるのかと思っていたら、上記のような次第となりました。さてでは、askaさんにかかるとどんな三拍子になるのかしらん? と、言ったような三つのコメントでした。言葉足らずな部分は、また機会があればということで。
2022.08.18
コメント(0)
-
インテルインメッツォ 106.
ウクライナ戦争 私が腹が立ってしかたがないのは、プーチンや山上容疑者の、ごくエゴイスティックな言い分の中味ではなくて、それによって引き起こされる社会的ハレーションが、私の個人的生活リズムにもネガな影響を与えている、というところにあるのです。 それは何も「ウクライナ戦争」で物価が上がっただの、景気が悪くなったなどということではなく、それまで連日「コロナ禍」の話題で埋め尽くされたマスコミ報道が、手の平返しに「ウクライナ戦争」の話題を持ち出して、これまたほぼ同じ顔ぶれの専門家たちのコメントを流し続ける。私たちは当然侵略されたウクライナに同情し、侵攻したロシアが苦戦しているのを見るにつけ、「それ見たか」と快哉を叫ぶ自分がいることを知ることになってしまう。 ここでの私たちの心理的景況は、言うなればスポーツ観戦の「赤勝て白勝て」の心理に近く、そうした野次馬根性を自身のうちに見い出すつど、私などウンザリしてしまう。生活リズムがネガに傾いて腹が立つ、とはそういう意味です。 それにしても、日本に避難してきたウクライナの人々。人権団体の中には「ウクライナの避難民だけを優遇するのはおかしい」という声があり、例によってポリコレで「正義」を振りかざすのが大好きなマスコミの一部が騒いでいましたが、岸田政権は参院選への思惑もあって、世論の動向をジィッと見、特別扱いを敢行しましたね。で、世論はそれを非難するどころか、地方自治体によっては、避難民に対して考えられないほどの支援を打ち出しているところもありました。 この状況について、内田樹氏がブログに面白いことを書いていた。―ゼレンスキー大統領は国際社会に向けて「われわれは、自国領土や市民の自由と権利を守っているだけではなく、この戦いを通じて、世界中の人々の自由と権利をも守るためにも戦っているのだ」というメッセージを発信しました。ウクライナは自国の独立や国益より「上位の価値」を守るために戦っていると訴えた。 ― 結果、この戦争が今まで世界中で繰り返されてきた紛争とは全く異質な戦争であるということを世界の人々が検知した、と言うのです。はたしてそうか? これまで難民支援と言えば、どこの国あるいは機関のメッセージも、当該国地域への援助と救訴のみで占められていたのに対し、ゼレンスキーは世界に対してたんなる支援ではなく、より高い自由と民主主義を守るという「上位価値」に訴えたので、主として先進民主主義国の政府国民に「これはこれまでの戦争あるいは紛争とは異なる」という印象を植え付けることに成功した。対してロシア(あるいはプーチン)は、身内の理屈だけを持ち出して戦争を始めたので、西欧各国からつまはじきにされた、ということでしょう。 政治的メッセージとして、ゼレンスキーの言明は議論の余地なく正しいとしても、それを直ちにウクライナからの避難民に対する特別優遇という結果に結びつけるのは、ちょっと無理筋かなという気が私にはします。ポリティカリーコレクトネス(政治的正しさ)だけでは、やはり万人の共感と支持は得難い。げんに西欧民主主義各国以外の国々はわりと冷めた目線を向けているじゃないですか。これは何もロシアの鼻息に気を使っているのではなく、こんな紛争はそれらの国々ではしょっちゅう起こっているからです。彼らから見れば、なぜウクライナだけが特別視されるのか、ということになるのでしょう。 さて、ではなぜ岸田政権は、ウクライナからの避難民に対し特別処置を取ったのか?それは言うまでもなく、世論の熱い支持があったからです。ではなぜそれまでアジア、アフリカ他からの難民受け入れに消極的、あるいは冷淡とさえ言いうる日本人が、ウクライナにかんしてそれを支持したのか?それはおそらく同じ生活感覚あるいは誤解を恐れずに言えば、文明感覚を持っている人々に対する共感があったからでしょう。 まあ、もともと日本人には白人コンプレックスがあり、とくに西欧型美人の典型とされるウクライナの女性を見るにつけ、同情を誘ったことは事実ですが、もちろんそれだけではない。来日直後の避難民の態度物腰や言葉に打たれたんだろうと私は思う。受け入れに対する感謝の言葉と、日本で仕事ができるか心配という、非常に「自律した精神性」が、刺さったのではないか? 残念ですが、これまでの難民の方々は泣訴哀願のポーズばかりが目立って、確かに気の毒とは思うが「共感」にいたるには、ちょっとシンドイところがあるのです。「受け入れてくれてありがとう。で、私たちに何してくれる?」では、こっちは応対に困るでしょう。援助慣れしたと言っては語弊がありますが、態度物腰についていけない理由が、今回のウクライナ避難民の様子を見ていて、ようやく分かった気がしました。 私たちはそれまでほとんど知らなかったウクライナの避難民に、同じ生活感あるいは市民感覚のようなものを検知したのです。物事に感謝し、自活するためにどうするかにすぐ感覚が向くというのは、日本国内の災害避難民と同じエートスじゃないですか。で、それはそのままその人たちの高い「矜持」となっているじゃないですか。 そういう共有できる市民感覚を持った人々が、いきなり侵略され、人権蹂躙どころか虐殺拉致暴行レイプ略奪といった、およそ考え得る暴虐の限りを受けたとなれば、我々は政治感覚でなく生活感覚で、その「痛み」と「怒り」を共有してしまうのです。 それにしてもロシア。私は以前から外国人ユーチューバーのファンで、その中にはアシヤさんとかアリョーナさんといったロシア出身女性も含まれる。ロシア語というのは、その音列がほとんどの日本語音をカバーしているので、彼女たちの話す日本語はおどろくほど違和感がない。彼女たちのアップする動画は、ほとんどが日本の風物食物旅行といった、たわいのない話題ばかりでしたが、その時の雰囲気が周囲にごく馴染んで、全然違和感がない。私はそれがどこから来るものなのか、それが面白くて見ていたものです。 早い話、彼女たちが時に里帰りして現地語で会話するとき、その態度物腰は明らかにあちらふうになっている。考えてみれば当たり前の話ですが、こういうときエートスの変換というのは起こり得るものなのか?まあこのお二人にかぎらず、最近の若い来日外国人のほとんどが、日本を知るきっかけとしてアニメや漫画を上げているのをみると、彼ら自身が来日以前から、日本のエートスにそれほどの違和感を感じていないというところもあるのかもしれない。私たちが映画その他の媒体によって、アメリカ人のエートスにあまり違和感を感じないように。 とはいえ、そうしたのどかな状況は、今回のウクライナ戦争で一変してしまいました。上記お二人にかぎらず、ロシア人ユーチューバーとウクライナ人ユーチューバーは、いきなり両国代表として話すことを強いられることになったのです。
2022.07.21
コメント(0)
-
インテルインメッツォ 105.
プーチンと山上容疑者 と、昨年末にボヤいていたら、今年に入るや、まことに前時代的なウクライナ戦争に始まって、このたびの安倍元首相銃撃殺害事件。いったい人間という生き物は、どこまで退化していったら気が済むのだろう、と思ってしまいますね。 人間が自意識を持った社会的動物である以上、各々が何がしかの不満やハレーションを抱えているのは当たり前。そこを何とか他者と折り合って生活を維持しようと、みな知恵を絞って日常生活を送っているのに、この種の人たちの頭の中には、「他者」あるいは「外部」というものは、一切存在しないらしい。 以前、「想像」と「空想」の違いをここで話したような気がしますが、私の独りよがりな見かたでは、「想像」とは「他者」あるいは「外部」に向けられるような「開かれた」エートス(性格・習性)。対して「空想」というのは、厳密に自己完結というか、自身の中空をブンブン飛び続けるようなエートスであって、絶対に「他者」ないし「外部」に開いていかない。プーチンも山上容疑者も完全に「閉じた」人たちなのです。私たちは我から「閉じた」人格性を、まともな社会の成員にカウントすることなど到底出来ません。 こうした黒々とした地獄をしょった人格性というのは、何も犯罪者や独裁者だけに見られるエートスではなくて、しばしば芸術家や作家などにも見られます。となると、これは何やら人間の基本的属性として、あらかじめ遺伝子に刻印されたものであるようにも見える。大多数の人間はそうした危ない因子になるべく触れないよう、無意識にその近くを回避するように振る舞うのですが、中にはそうした暗黒をどうしても覗きたい、触れずにいられないという人たちも、多くはないが「必ず、いる」のです。 早い話、幼児たちはこうした「暗黒」を回避しません。大多数の人は成長するにつれ回避のすべを身につけるのですが、少数ですがそうでない人もいる。(ピカソなど幼児の目線を、いつでも起動出来る人だったでしょう)。 というか、そういう性向が少数とはいえ、人間の基本的因子として刻印されているからこそ、人類は多様性を獲得し世界中に広がったわけでしょう。 先ほど「暗黒」という言い方をしましたが、それは犯罪者や独裁者を見る私たちからはそう見えるのであって、その外形的相貌はしばしば甘味な形を取って現れるものらしい。リルケは長詩「ドゥイノの悲歌」で、「まことに美の天使は恐ろしい(手塚富雄訳)」と言っているでしょう。甘味な美的相貌を凝視し続けるうち、彼の眼はイカロスのごとく焼き尽くされそうになる。この詩のなかで、美の光芒のすさまじさに、思わず手をかざしてしまう場面がありましたね。 三島由紀夫や村上春樹なども、あるいはそうした美的相貌の芯に隠れた、マグマのような暗黒を見続けた作家だったのかもしれず、三島はエロティックな身体の裏、村上ならファンタジックな相貌の裏に隠れた得体のしれない何物かを、「確かにこれだけは、私は見た」という仕方で、文字に刻んだのです。という意味で芸術家と私たちは言葉とか色とか音とか形で、かろうじて繋がっていると言えます。 私たちはそうした得体のしれないマグマに近づいてリポートする彼らの振る舞いを、ハラハラしながら見守るしかない。しかし、そうして残された彼らの営為の結果は、しかるべき敬意を払って検証されるでしょう。なぜなら、それらは仮にかなりドス黒い相貌を放っていたとしても、私たちの社会的資産としてカウントされるからです。 暗黒のマグマに気づきそれに近づくにしても、何とか正気で踏みとどまって、言葉や色彩や音楽といった表現手段で記録しようとするとき、それらはおそろしく孤立した営為であったとしても、間違いなく「社会と繋がっている」と見做せるでしょう。 しかし犯罪者や独裁者は違う。暗黒のマグマに魅かれるにしても、彼らはその甘味な相貌に簡単に我が身を投じてしまえる性向があるのではないか?プーチンと山上容疑者には不思議な共通点がある。二人ともバカではないということです。否、むしろ恐ろしく冷徹沈着かつ無慈悲に事柄を見すえ、自身の感情をコントロール出来る人物たちである。プーチンはそもそもそういう訓練をKGP時代に何度も受けて来ただろうし、山上容疑者は奈良の県立トップ高校出身だそうだから、世間並み以上の知力を持っていたでしょう。 オウムの時もそうでしたが、犯罪と知力のレベルはあまり関係ない。犯罪を犯すトリガーは、どうも知力とは関係のないところからやって来るらしいのです。と、ここまでプーチンと山上容疑者のことを考えてきて、犯罪とカルトとの関係について思いつくことがあるのですが、ここではしません。 要は、こうした人格性に共通するのは、心の深奥に潜むドス黒いマグマに対してのハードルが恐ろしく低い、言ってみればそうした事象に出会うとき、ほぼ無抵抗に酩酊してしまえる性格なのだろう、で、それはおそらく最近あったほかの大量殺人事件、例えば「京アニ放火殺人事件」とか、「大阪心療内科放火事件」の容疑者たちにも共通する心象なのでしょう。 自身の抱えるドス黒いマグマを解消するためには、いかなる理由をつけてでも、「他者」あるいは「外界」を攻撃しなければならない、そして「私にはそれが特権的に許されている」といった心理的経路を持つという点で。 プーチンならば旧ソ連の版図と名誉の回復のためには、目の前で起きているウクライナ人ロシア人の死体の山は簡単に捨像される。山上容疑者の場合は「旧統一教会」への復讐のためには、それが一国の元宰相であっても、自分には関係ない(今のところの証言他が事実であれば)。 こうした自己完結的な論理というのは、最終的には自分以外は全部敵、したがって自分は何をしてもいい、「私にはそれが特権的に許されている」という帰結に至らざるを得ないのでしょう。
2022.07.18
コメント(0)
-
インテルメッツォ 104.
ポリコレを叫ぶ人たち ずいぶんながく、ここでしゃべるのをやめていますが、今年に入ってあまりに不愉快なことが多く、パソコンの画面に向かう気がしない、という日々が続いているのです。 そもそも私は多人数に紛れて過ごすというのが苦手で、仕事以外で都市部に繰り出したいなどと思ったことは、ただの一度もありません。なかば世捨て人のような兼好さんみたいな生活スタイルが、私にはごく魅力的で、したがって今回の「コロナ禍」のような状況は、そのはるか以前から自粛同然の生活をしてきた私にとっては、ほとんど「奇禍」みたいなもので、「周囲の社会状況が、かってに俺の生活スタイルに近づいて来たわい」などと、ほくそ笑んでいたものです。 何が「奇禍」かと言えば、「これで、誰彼に気兼ねなく、思い切り自宅で好きなことが出来るわい」という期待であって、大好きな音楽の話や、ひそかに懸案にしていた「源氏1000年」のおしゃべりの再開も、ようやく落ち着いて出来るのではないかと、勝手にもくろんでいました。去年の第一回めの「緊急事態宣言」下では、電車の中もスーパーの中も一種異様な緊張感に満ちていて、くしゃみでもしようものなら、それこそ袋叩きにされかねまじき雰囲気だったのですが、私にとってはとくに都市部の一種異様な雰囲気が心地好く、それを体感したくてわざわざ電車に乗ったりしに行ったものです。 ところが、そうした景況も二年目に入ると新鮮味が薄れて、明らかに私も周囲も毎日の行動がマンネリ化している。そうした中にあって、わけの分からない苛立ち感だけが勝手に増幅して、日々の生活リズムを脅かすということになって来たのでした。 さて、その苛立ち感の中身はというと、コロナ禍がなかなか収束しないというか、先が見えてこないというような直接的な話ではありません。そんなものは何でもない。武漢ウイルスがコロナという風邪の一種であるならば、それを完全に封じ込めるなどというのは絵空事で、いずれどこかで折り合いをつけて付き合っていくほかないだろう、というのが私の観測です。 そうではなくて、それを連日報じる既存メディアの呆れるばかりの古びた報道スタイル、あるいはこの災禍を何かにつけて政治的に利用しようとする内外の勢力が、思惑たっぷりの言動と振る舞いを繰り返すというところにあったように思う。 既存メディアの頽落ぶりというのは、たとえば一波二波三波と感染が再拡大するたび、その判で押したような報道。増えだすと「なぜ緊急事態宣言を出さない」と騒ぎ、宣言が出たらとたんに「経済はどうする」と手の平を返す、のパターンが一回二回ならともかく、マッチポンプ式に三回四回とやられると、よくここまで飽きもせずに同じ報道が出来るものだと感心してしまいます。騒いでるメディア自身もバカバカしくなってたんじゃないか? で、その報道の中に見え隠れする、何が何でも現政権を潰したいという身ぶり。そもそもコロナパンデミックは自然災害であって、政権の施策が引き起こしたわけじゃないのに、あたかも安倍、菅政権の愚策がこれを招いたかのような口ぶりです。もしそれを指摘するなら、真っ先に北京政府の責任を問うべきではないのか?その口ぶりは、あたかも天気予報士に天気の文句をつけるような感じで、聞いているだけで不快になる一方です。 こうした報道と野党の姿勢というのは、今に始まったことではなく、敗戦後ずうっと繰り返されてきたナイーヴな左翼的世界観が、無反省なまま現在にも受け継がれてきた結果にほかならないわけで、この間に醸成された社会全体の知的劣化というのはひどい。メディアも左翼的自称リベラル野党も、出来れば日本国民全体を政治的に無感覚、無関心に釘づけにしておきたいと思っているかのようです。無関心無感覚な国民が大多数を占めるかぎり、時のメディアの報道を批判的に距離を置いて見ることをせず、無反省に「まあ、そんなものだろう」と受け入れてしまうからです。 私自身も含めて一般国民というのは、日常生活に忙しくて政治外交経済その他、そっち方面の専門的な問題に関心を抱き続けるというのはむつかしい。年金生活者が比較的関心が高く、投票行動も高いというのは、新聞テレビ他に時間を割くヒマがあるからでしょう。 私は幸い時間だけはたっぷりあったので、ほかの人より世界を多少斜に見られる余裕があったと思うのですが、今般のコロナ禍では毎日退屈極まるニュースを見ざるを得ず、そうしたニュースをほぼ二年間見るたび、ついに噴火してしまったということでしょうか?しかしそうしたやりきれない感情を抱いていたのは、私だけではなくてほとんどの国民の共有するところであったようで、その結果は総選挙での野党の惨敗という形で現れましたね。 しかし政治はそうであっても、日常飛び込んでくる既成メディアの頽落ぶりは今も続いているわけで、気を付けていないとまた噴火してしまうかもしれません。
2021.12.13
コメント(0)
-
エレクトーンというガラパゴス 26.
「第九」三昧 2. さて、もう一人はというと、このブログではなぜか触れて来なかったのですが、「aki-Electone solo」という動画を8年近く、精力的に配信されている方で、私は3年ほど前に、この人の「TWILIGHT IN UPPER WEST」を知り、そのしゃれたセンスにいっぺんに惹かれてしまいました。 そのときした私のコメントとは、― 電子楽器なら誰が弾いても同じ音と思いきや、これなどを聴いているととんでもない。設えられた効果音を抑え目にして、まるでピアノとサックスが対話しているかのような演奏がとても個性的、中間部のピアノソロは耳コピということですが、いっそ倍ぐらいにアレンジされたら、どんな豊かな楽想が沸いて出ただろうと、あらぬ想像してしまいますね。 好い演奏とは、私など「繰り返し聴ける」かどうかということに尽きるなどと、勝手に思っているのですが、この演奏は何度も聴かせていただくことになりそうです。なぜそうなるのかと言えば、結局譜面に託された作曲者の「歌心」のようなものを、演奏者が真摯に受け止め、「私にはこう聴こえました」という仕方で、聴き手に届けようとされているからでしょう(想像ですよ)。 不思議なもので、そういう敬意のこもった演奏は何度でも聴きたくなる。なぜならそういう感応をした演奏者の宿す「歌心」は、一聴しただけではとても分らないからです。―と、相変わらず力んでいますが、要は826askaさんの同曲の響きと、あまりに違うので驚いたということです。その後このakiさんの動画を数多くフォローするにつれ、私のエレクトーンという楽器に対する捉えかたには、若干の変化があったように思う。 ひらたく言えば、この楽器には「演奏する楽しみ」のほかに、自分流に「アレンジする楽しみ」がほかの楽器にくらべて多量にあるのじゃないか?ここ最近のakiさんの動画を聴いていると、市販の楽譜ではあき足りず、もっぱら耳コピで自分流にレジストも作成されて演奏されているようです。と、気付けば、他のエレクトーン奏者でもかなりの方が、自作の楽譜をオンラインに乗っけておられる。聞くところによれば、エレクトーンの楽譜作成というのは、その多様すぎる音色ゆえに、膨大な手間がかかるものの如くで、演奏者としてはそれも見てほしいというところもあるのでしょう。 とはいえ、こういう「音楽の楽しみ方」もあるのだとすれば、自称クラシックファンの私としては、かなりショッキングな事態とならざるを得ないのです。前にも触れましたが、クラシック音楽は原則として「原譜第一主義」で、作曲者の残した譜面を忠実に指定どおり演奏するのが、まず基本にあると特に第二次大戦後言われてきたと思うのです。厳密に譜面をたどりながら、そのごく制約された中から、いかに迫真的な「響き」を取り出してみせるか?戦前まではある意味、そうした規制はおおざっぱで、原譜にはない音が演奏家によって加えられたり、省かれたりしていたようです。 これは前にも触れましたが、思い切り自由に歌わせているようにみえるカラヤンでも、原譜に記された音と楽器以外は絶対に使いませんでしたが、ワルターとかフルトベングラーなどは、この「第九」終楽章の冒頭にしても、ベートーヴェンの時代出なかったはずのトランペットの音を、景気よく吹かせてますね。作曲家が「こうあるべき音」と望んでいたとしても、当時の楽器がそれに追いつかなかった場合、今の演奏家はどうあるべきか? このあたり、歴史の改ざんというより、「今の都合」による過去の歪曲というのが、人類にどういう惨禍をもたらすかという深い反省が、何も枢軸国側だけでなく連合国側にも、二度の世界大戦後の空気としてあったのだと私は思う。それと並行して歴史資料の校訂や批判が、かなり厳密かつ科学的に行われるようになって、軽々に「歴史」を物語ることには慎重にならざるをえない、ということもあったでしょう。 こうした風潮は、クラシック音楽の世界にもあって、「原譜に付されていない音は、やはり使うべきでない」というのが、今どきの流れなのでしょう。 しかし、エレクトーン業界はそうしたクラシック界の重たい制約からは、かなり自由というか、そもそもエレクトーンという楽器にとって、クラシック音楽はその包含する広大な楽器のキャパのごく一部に過ぎない。したがって今のところ、この楽器はそうした「歴史の反省」をするには、まだ早すぎるということになるのでしょうか? 前置きが長くなりました。ではakiさんによる「第九」第4楽章を聴いてみましょう。
2021.01.20
コメント(0)
-
エレクトーンというガラパゴス 25.
「第九」三昧 1. コロナコロナでさんざんだった2020年がようやく終わり、21年が明けましたが、何やら首都圏を中心としたオーバーシュートの予感があたりに満ちていて、とてもじゃないが浮かれた気分にはなれません。 さて、皆さんはいかがお過ごしですか。明けまして、おめでとうございます。本年が皆さんにとって、今度こそ良き年でありますように。 第三波が思いのほか大規模で、収束の兆しどころか、感染者数、重傷者数、死者数とも第一波を超える事態になっている現状については、いくつか私なりに思うところがあるのですが、うっとうしいので別段で話するとして、取りあえず年末にあった多少楽しい話題を一つ。 それは例によってyoutubeにUPされた二本の動画のことなのですが、奇しくも二人のエレクトーン奏者が、年末ということで「第九」を演奏されていたのです。日本ではまるで歳時記のように年末になると「第九」がさまざまな形で演奏され、特に昨年はコロナ禍の年の瀬ということで、「歓喜の歌」に希望を見出す人も多かったのかしらん。 私は以前から申し上げるとおり、かなり古さびた(!?)保守的なクラシックファンなので、軽いタッチのポップな「第九」のメロディーが街中に流れてくると、それだけで背筋が凍るというか、腹を立てながら歩くという仕儀となるのですが、このお二人の動画からは、不思議とそういう「いらだち」が沸いてきませんでした。どころか、むしろ爽快感をさえ覚えたものです。 お一人はもちろん826askaさん。年末に自宅からのライブをやっておられて、自作も含めて全九曲、いずれも大熱演でしたが、その中でも冒頭の「リベラ 彼方の光 」、7曲めの「鬼滅の刃」から「鬼殺隊」、そして8曲目の「第九」(1時間32分ぐらいから)が出色の出来映えで、思わず拍手しそうになりました。期間限定なので、いつまで見られるのか分かりませんが、聴いてみてください。 その時書いたコメントを、以下にそのまま記します。― 街に出ればポップな軽いノリの「第九」がどこでも流れている時節柄、自称クラシックファンの私としては、ときに怒りさえ覚える今日この頃ですが、askaさんの「第九」はまったく違う。早い話彼女の「第九」はスーパーのBGMにはなじまないでしょう。 それほどに彼女の演奏には切迫性があって、ある種のエレクトーン奏者が本気を出せば、どういう音楽が出現するか、その片鱗を見た気がしました。もちろん細かいことを言えば、「歓喜の歌」のフレーズはやはり原曲に近いリフレインで聴きたいし、コーダはこの数小節前のコーラスが終わるあたりからがベストだと思うのですが(何しろ聴力を失ったベートーヴェンが、どこかから「確かに聞き取った」フレーズなので)。 それでも私はこのaskaさんの挑戦というより、クラシック音楽と対等に渡り合おうとしているかのような、「挑発!?」的な姿勢が大好きです。なぜならスーパーのBGMならクラシックはビクともしないけど、「切迫性」のある響きは間違いなく、「音楽とは何だ」という「問題を提議」するから。 と、回りくどい言い方になりましたが、音楽の「何が人の心にまで届くのか?」というような根本的な問いかけの前では、クラシックもポップも関係ない。ピアノもエレクトーンも、プロもアマも関係ない。すべての楽器、アーティストは、演奏が始まったとたん同じスタンスで、その「問い」にさらされるのです。 askaさんの演奏を聴いていると、その軽々としたフットワークから、そうした根本的な問いかけが驚くほど明晰に見えてくるのね。― と、例によってかなり興奮気味に、駄文を連ねておりますが、正統的なクラシックファンから見れば、ある意味ほとんど「冒瀆的」な響きであっても、晩年のベートーヴェンが「第九」に託した精神の一部は、確かにここに見ることが出来るのです。 私、実は街中のポップな「第九」だけでなく、ホンチャンの演奏会でも「本当に」納得した演奏というのには、数えるほどしか出会ったことがありません。というか、中一の時に聴いたカラヤン、ベルリンフィルの「第九」の衝撃があまりにも大きく、いわば私にとっての「原音」みたいな響きとして残ってしまい、それ以外の「第九」の響きがなかなか受け入れがたい、という時期がずいぶん長く続いたものでした。こういった「原体験」的な音楽の響きというのは、けっこうありますよね。
2021.01.13
コメント(0)
-
インテルメッツォ 103.
リモート コロナ禍のあいだに、ロックダウンだのオーバーシュートだの実効再生産数だの、専門用語とも業界内用語ともつかない新語がつぎつぎ現れましたが、「リモート」という言葉もその一つかもしれません。自粛を余儀なくされる中で新しい生活様式が求められ、職場でも家庭でもオンラインによるリモートなスタイルがやたらと増えましたね。 私議になりますが、私などもともと人だかりが苦手で、仕事以外で梅田とか河原町に繰り出すというようなことは一切しないクチです。休日など文字どおり家にすっこんでリモート状態だったのですが、それは田舎暮らしに憧れるなどというしゃれた話ではなくて、たんに「引きこもり」が性に合っていただけです。したがって(と、怒鳴るわけじゃないけど)、今回の自粛はその前からの生活習慣の延長線上にあって、まったく違和感がないので、世間がなぜこれほど騒ぐのかサッパリ分からない、というはなはだひねくれた感慨に浸るということになる。というか、トランプさんふうに強がってみせているだけという、困った状態と相成るわけです。それにしても、たんに公衆衛生の具であるマスクが、なぜ「勇気」や「忠誠心」の表象となるのか、これまたサッパリ分からん。 さて、そんな世間全体が首をすっこめて、周囲を息を潜めて窺っているような状態の中で、時にビックリするような作物が現れたりもする。七月に取り上げたのは、自粛以前のYouTubeから拾い上げた邦楽だったのですが、今回のはライナーノーツによれば、2020年5月13日にYouTubeにUPされていて、まさしくコロナの緊急事態宣言下に造られた平原綾香さんと藤澤ノリマサ氏のデュエット曲です。これはいいですよ。 「The Prayer(祈り)」という曲なのですが、まずは聴いてみてください。原曲は二十年ほど前にC・ディオンとA・ボチェッリが唄った名曲ですね。C・ディオンと言えば、映画「タイタニック」の主題歌でブレイクしたフランス系カナダ人歌手として皆さんご存じの通り。例によってWikipediaを見ると、― 彼女が曲を発売する度、その圧倒的な声量と技術的に卓越した歌唱力が主に評価される対象となっている。その音楽は、ポップス、ロック、R&B、ソウルの他に、ゴスペル、クラシックなど幅広いジャンルに影響されていて、ファンや評論家には彼女自身の声、歌詞の持つ本来の意味を歌い上げる能力などが高く評価されている ―とありますが、これって何だか、そのまま平原さんの個性を言い現わしているようで、面白い。 相方のA・ボチェッリとは盲目のイタリアン・テナーで、L・パヴァロッティ亡きあとの後継とも言われ、S・ブライトマンの「Time To Say Goodbye」の元歌でよく知られた人ですね。 さてこの平原、藤澤コンビの歌唱、C・ディオンとA・ボチェッリの元曲が、フルオーケストラをバックに、ごくスタンダードなヴォーカルを聴かせているのに比べると、伴奏をキーボード一本に絞って、きわめてドメスティックで求心的な印象を与えますね。藤澤さんのキーボード、ピアノ音が主体ですが、弦の音が背景放射のようにあえかに全体を領していて、見事な伴奏になっています。さらに音大声楽科出の歌唱力をいかんなく発揮して、前に出るところ、後ろに下がって支えるべきところ、自在に出し入れしているのは、さすが。 こういう相方の伴走を得て、平原さんは自身の歌世界の両ウィングを、思い切り羽ばたかせている感じ。中間部でベルカント唱法に切り替えるところ(ディオンはやってないね)、イタリア語で歌っているのは、本場オペラに対するリスペクトかなと笑ってしまいます。 本編はお聴きのとおり、大変荘重な仕上がりなので、歌詞対訳を「Andrea Bocelli 愛」という方のブログから引用します(一部編集してます)。I pray you'll be our eyes, and watch us where we go,And help us to be wise, in times when we don't knowLet this be our prayer, when we lose our wayLead us to a place, guide us with your graceTo a place where we'll be safe...どうか私達の目になって 行く先々で私達をお守りくださいそして迷った時に 賢い決断ができるように助けてください道を見失ったとき この祈りを聞いてくださいあなたのお慈悲で 私たちを 安全なところへお導きください(La luce che tu dai)I pray we'll find your light(Nel cuore resterà)And hold it in our hearts(A ricordarci che)When stars go out each night(L'eterna stella sei)あなたの光あなたの光を見つけられますように祈ります心の中に心の中に抱きましょうあなたの存在を感じます夜空に輝く星を見たらあなたは永遠の星です(Nella mia preghiera)Let this be our prayer(Quanta fede c'è)When shadows fill our dayLead us to a placeGuide us with your graceGive us faith so we'll be safe私の祈りで私の祈りで篤い信仰で影が私たちの一日を埋めるときあなたのお慈悲で 私たちを 安全なところへお導きください(Sognamo un mondo senza più violenzaUn mondo di giuztizia e di speranzaOgnuno dia la mano al suo vicinoSimbolo de pace e di fraternità)苦悩と悲しみの世界は終わり傷ついた心はすべて癒されるでしょう私達はみな神の子であることを忘れませんそしてあなたを求めて 手を差し出します(La forza che ci dai)We ask that life be kind(E' il desiderio che)And watch us from above(Ognuno trovi amor)We hope each soul will find(Intorno e dentro a sé)Another soul to loveあなたが私たちに与える力幸せな人生を送ることができますように願います空から見守っていてください誰もが愛を見つける見つけることができますように私の中にも外にも私達が心の底から愛する人をLet this be our prayerLet this be our prayerJust like every childJust like every childNeed to find a place, guide us with your graceGive us faith so we'll be safe祈りましょう祈りましょうそう、無垢な子供のようにそう、無垢な子供のようにあなたのお慈悲で 私たちを 安全なところへお導きください(E la fede cheHai acceso innoiSento che ci salverà)あなたを信じればお慈悲で私たちは救われるのですと、大変長い引用になってしまいましたが、キリスト教臭満載とはいえ、このコンビがこの曲を今この時期に取り上げたわけは、歌詞に明らかですね。
2020.10.14
コメント(0)
-
武漢ウイルス・クライシスとフライング・プリンセス 13.
ひょっこりひょうたん島 それにしても、このコロナ禍のあいだに、まあ世界ではいろいろなことが起こるもので、トランプさんも感染したとか。 イギリスのジョンソンさんならお気の毒、ブラジルのボルソナロ大統領とか、ベラルーシのルカシェンコ大統領なんかだと、その素行から見て「そら、みたか!」という笑い話ですむんだけど、アメリカの大統領となると、いくら漫画チックな図柄とはいえ「冗談じゃない」って話になる。 最短でも二週間程度の政治的空白ということであれば、大統領選挙の行方という国内問題にとどまらず、この空白そのものがもたらす世界の攪乱が心配ですね。中国もロシアも、こうした時間的空隙には、とても鋭敏かつしたたかで、何らかの駒を動かして来そうな気がして仕方がない。その意味でも、世界で絶対罹ってはいけない人間の一人のはずですが、まあ強がりもここまで来れば、まさしく「病、膏肓(こうこう、回復不能)に至る」のレベルで、自身を反省して悔い改めるなんて発想は、もちろんここから先もなく、おそらくご本人はこのうえは劇的回復を演出して、一挙に失地回復をねらおうという頭でいっぱいなのでしょう。 トランプ支持者には、このコロナ罹患こそトランプさんが編み出したフェイクニュースで、これによって大逆転サヨナラホームランをねらっている、という話がまことしやかに噂されているとか。したがって、この大統領の感染はオールドメディアが騒ぐほどには、支持率に影響しないのではないか?この大統領にして、こういう発想をする支持者たちのいる国だから、ということです。 昔、S・キューブリックの「博士の異常な愛情」という傑作ブラックコメディー映画がありました。すでに大陸間弾道弾が飛び交おうかというさなかに、O・ウェルズ似の悪相のソ連大使が、ペンタゴンの機密会議室を盗撮しているのを、アメリカの将軍(J・C・スコット)が目ざとくみつけて、くんずほぐれつの取っ組み合い。「お前ら、世界の終わりが近づいても、まだそれをやっているの」といっているうちに、水爆が破裂して文字通り一巻の終わりという映画でした。 同じようなくんずほぐれつを、このコロナ禍に「やるな」と言っても、彼のような国々は生理的にそれが出来ない、という厄介ではた迷惑な体質を、ずうっと持っているのです。安倍さんならそのあたり「警告」ではないにしても、軽い「牽制球」ぐらい(他の国を動かして)投げそうな気もしますが、菅さんはどうなのかな? ところで政治学者としても、バラエティー番組コメンテイターとしても、今や引っ張りだこの三浦瑠麗氏、私がこの人を知ったのは、五、六年前例の「朝生」で、珍しく青山さんが顔を出していて、それに同席していた時からです。断っておきますが、私はこの田原総一郎氏の「朝生」が嫌いで、普段見ることがないのですが、青山さんが出ていたのでチャンネルを合わせたのでした。 その時の三浦氏の印象ですが、その美貌と滑らかな口舌ぶりは、他を圧していて面白く、しばらく注目する日が続きました。政治討論でのこの人の特色というのは、自分の主張を述べ立てるというよりも、その場の論点の整理ないし、解説のような体を成しているというところにあるんじゃないか、と思ったりもしたのです。しかしこれはある意味、持論の主張に熱中して、相手の話に聞く耳を持たない数多くの論者にとっては、はなはだ癇に障るところがあったのではないか。 私はそれにつけて、思い出してしまうテレビ番組があるのです。表題にあげた「ひょっこりひょうたん島」という、それこそ五十年以上前の人形劇なのですが、登場するキャラクターがそれぞれ出色で、すこぶる面白く、中学生時代の記憶が今でもよみがえります。かなりヒネた中学生の私にとって、人形劇などというのは子供向け、まして「チロリン村」など死んでも見るまいと思うタチだったのですが、子供目線から大人を意地悪く風刺するという視覚が斬新で、知らぬ間に結構入れ込んで見ていましたね。 そこに登場する大人たち、口先ばかりで大統領気取りのドンガバチョ、小者のくせに自分は金儲けがうまいと信じて疑わない海賊トラヒゲ、ややこしいことには我関せずの元貴族ガラクータなどなど、要はこの島にはまともな大人が誰一人いない。子供たちを引率しているはずのサンデー先生も、ときどき逆上して長刀を振り回したりして、手が付けられないという時がありましたね。 そうした漂泊する島にさまざまな危難が押し寄せ、何とかみんなで切り抜けていくという物語なのですが、実質的にこの島の困難を見通して、解決していっているのは、六人ほどの子供たち。中でも「博士」と称せられる少年が際立っていました。島を牛耳っているつもりのドンガバチョやトラヒゲに対して一歩も引かず、その怪物的博識と超論理的語り口で、グウの音も言わせずに問題を解決していく。サイズと口の大きさだけが取柄の大人たちは、頭ではかないっこないので、文句は言いつつも従っていくほかない。 とはいえ、生意気な子供に「腹ふくれる」思いは、大人の側に常に沈降するわけで、時にガバチョがトラヒゲをそそのかして、博士(確か中山千夏さんが声やってましたね)を陥れたりもする。そういう場面もありました。 この図柄、先日の(見ないと言っていたはずの)「朝生」で、同じような構図となって顔を出していて、すこぶる面白かった。番組を仕切っているはずの田原氏に対して、三浦さんが一歩も引かず、終わりのほうでは、この番組を動かしているのは、実質的に三浦さんのほうじゃないか、と思ったりしたものです。もうお分かりだと思いますが、この三浦さんの立ち位置、「博士」とそっくりだと思いませんか?
2020.10.03
コメント(0)
-
武漢ウイルス・クライシスとフライング・プリンセス 12.
イタリア ところで、前回取り上げたヤマザキ・マリさん、同じトーク番組で「少なくとも北イタリアの私の周辺で、中国人を恨むとか非難する人はいない」。どころか、例の中国の医療支援隊がやって来たとき、彼女の親戚たちは異口同音に感謝していたという、部外者から見ればちょっと意外な発言をされてました。イタリアの人はいたって素直なのか、あるいはまた別の哲学があるのか? 中国人移民労働者の歴史は、改革開放を唱えた鄧小平の時代からと古く、イタリアの経済は構造的に中国に絡め取られて、にっちもさっちも行かなくなっている。迂闊な発言で北イタリアの経済的没落が始まっては、ただでさえ不振な彼の国の経済にとってはたまらない、ということでしょうか。 とはいえ、ソーシャル・ディスタンスを守りマスクをつけて、押し黙ってスーパーの入り口に並んでいる本国人の映像を見て、在日イタリア人のある人が「こんなのイタリア人じゃねえ!」と吐き捨てるように言っていたのには参りました。この人からすれば、これはある種文化的な屈服に見えたのではないか?しかし、命と文化のどちらを取るかと言われれば、別にイタリア人でなくても「命」を優先せざるを得ない。この人の発言は、別に本国人をくさして言っているのじゃない。現実の不条理に対する、「怒り」とでもいうほかないものだったのでしょう。 と考えてくると、もっと過激な形でのマスク拒否や、ほとんど偽悪的としか思えない「三密」の大騒ぎをやらかしているアメリカの景況も、何となく「こりゃ、しょうがないかな」という気もしてくるのです。これを簡単に「民度」の差みたいな話にしてはいけない。「三密」のないアメリカなど「アメリカじゃねえ!」と思うアメリカ人は多いのではないか?マスクをするかしないか、というのが公衆衛生の話ではなく、政治的態度の表明にすり替えられている、といった指摘もありますが、それも少し違うような気もする。 要は、口元を隠しハイタッチもハグも拒否する人間は、万事カジュアルであることが自由平等と民主的態度の根幹的エートスであるような文化から見れば、これらは「気持ちが悪くて、しかたがない」ということなのではないか?で、それでもって、数多くの犠牲が出るのであれば、それは自国の文化的エートスを守った結果なのだから、「これは、しかたがない」という筋になってしまう。 「そんなバカな!」という話になりそうですが、ここで少しだけ想像力を拡げてみるのも一興でしょう。今回の武漢ウイルスと真逆の性質を持つ病原体が、仮に日本で蔓延したとして、「公衆衛生のために、明日から土足で家に入りなさい」と時の政府から言われた場合に、私たちはどう振る舞うだろうか?相当数の人たちが「それは文化の破壊だ!」と言って拒否し、場合によっては犠牲者も出るかも分からない。諸外国からいろいろ言われても、おそらく大半の日本人は、「これは、しかたがないわい」と思うのではないかしらん。 私がここで申し上げたいのは、世界のさまざまな文化的エートスがたまたま「凶」と出たからと言って、その原因を「民度」のような話で概括してしまうのは、乱暴な考えかただということです。お上の言うことには、いろいろ文句はあっても、取りあえずは従っておくというエートスは、今回はたまたま「吉」と出たけど、高度な自律性が求められる民主社会において、はたしてそれが理想のエートスなのかと言われれば、そんな有頂天になるような話ではないでしょう。 ところで、話はまたイタリアに戻るのですが(好きですね)、同じような感染爆発と多大な犠牲者を出しながら、イタリアではマスク拒否のような話は、それほど先鋭化してないような気がする。私はこれもたぶん、それぞれの国が背負った歴史文化伝統のなせるエートスなのだと思うです。一つは教会があらゆるパニック的事態の受け皿になってるのかもしれないし、あるいはまたひょっとすると、イタリア人に特有の屈折した感情が、どこかにあるのかもしれない。 考えてもみてください。古代ローマ帝国とまでは言わないけれど、西欧諸国のなかで真っ先にルネッサンスを先導し、ヨーロッパの繁栄を導いた輝かしい歴史と伝統を持ちながら、近代においては大航海時代においても、帝国主義の時代においても、イタリアはついに一回も、その主役に躍り出ることはなかった。今どきギリシャ・ローマのような世界文明の栄光を継承しているのは俺様だとばかり、イギリスやフランスやドイツが次々名乗り出たのですが、イタリアは一回もそうした表舞台に立つことがなかった。今やギリシャやスペインと並んで、EUの「お荷物」扱いされる現状で、それでも偉大過ぎる文化遺産に寄り掛かって生活していかざるを得ない国民なんて、やっぱり屈折せざるを得ないんじゃないか。余計なお世話かもしれないけれど。 コロナに対しても中国に対しても、これは他所さんのことなので言いにくいことなんだけど、一種「諦め」の気分が漂っているような気がして仕方がないのです。 しかし、中国への絡め取られぐあいでいうなら、日本なんかイタリアの比ではないわけで、そのわりには現在の共産中国には、ほとんどの日本人は非好意的と言っていい。少なくとも、恩着せがましく空港に降り立った医療救援隊と称する宣伝部隊を、諸手で歓迎する日本人はいないでしょう。 では、なぜそうしたエートスの違いが、出てくるのかと言えば、それもやはりそれぞれの民族や国家が経て来た歴史の結果としか言いようがない。近現代において日本は、西欧列強の帝国主義的覇権の圧力に正面から立ち向かい、唯一独立を守ったアジアの国という歴史的経緯があるのです。 日本の立憲主義と民主主義は、あたかも敗戦後アメリカから、初めて付与されたかのような通念が、今だにオールドメディアを中心とした、いわゆる知識人たちから何の疑問もなく呈せられることが多いですが、中学校の教科書でもそんなことは教えてない。江戸幕末から明治維新にかけて、西欧近代主義の有りようを必死で研究し、国力とは何か、民意を汲むにはどういう制度が日本にはふさわしいか、あれこれ試行錯誤を重ねながら、日本は自力で統一近代国家を形成してきたわけでしょう。 このあたり、イタリアは同じ幕末の時期(1861年)に統一国家を形成しながらも、小国分立と王国、さらには教皇支配という入り組んだ歴史が長く、実質的な共和制に移行したのは、なんと第二次大戦後(1946年)のことなのです。イタリア人が自国を語るとき、古代ローマやルネッサンスの輝かしい文化遺産と歴史は声高らかに語れても、現代のイタリア共和国という民主政体について、必ずしも声高に語らないというのには、その短すぎる歴史から見て、無理からぬ理由があるのでしょう。 と、ずいぶん遠くの話になってしまいました。私はそれでもイタリア人の持つ、「豊かさ」の有りようというものが好きでたまらない。生まれた時から同じ村で育ち、一歩も外に立たこともないのに、「私たちは幸せです」と気張らずに言える国民性が。
2020.09.30
コメント(0)
-
武漢ウイルス・クライシスとフライング・プリンセス 11.
クレモナ 話が変わりますが、私は民放のBSでやっている「イタリアの小さな村」という番組が好きで、ときどき見ています。もっぱらイタリアの片田舎の村を次々まわって、そこの住人にインタビューするというだけのドキュメンタリーなのですが、これがなぜか無類に面白い。その中には例えば、生まれてこのかた、村からほとんど一歩も外に出たことがないという老夫婦もいて、なぜか口をそろえて「私たちは幸せだ」と言う。 江戸時代ならともかく、今どきの日本ではどんな片田舎の住人であっても、一生その村から一歩も出たことがない、というような人生はちょっと想像しにくい。というか日本では小中から、修学旅行という集団外出訓練を行っているでしょう。 牧畜や果樹園を代々営む農民が隣村の娘さんを見染めて結婚し、子供も育て上げて今や悠々自適、自家製のワインやチーズで毎週やって来る子や孫と会食するのが、何よりの楽しみという生活。もちろん長い人生の間に、さまざまな困難があったろうことは、(戦争とか事故とか死別とか)容易に想像できるし、げんに離婚だの就職難だのいろいろな問題を抱えて、会食にやってくる子や孫もいる。とはいえ、それらを見つめる老夫婦の目やしぐさや話しかたは、年相応に優しく落ち着いているのです。 私は思うのですよ。似たような風景は(まあ、毎週は無理でも、年二回ぐらいは)確かに日本にもあるのかもしれないけれど、そうした己の人生を淡々と語る語り口、しぐさや表情というのには、明らかにイタリアの歴史とか文化が色濃く反映していて、決して日本では見られない光景なのです(何も日本人の表現ベタをくさしているわけじゃないですよ)。彼らの表現は言葉もしぐさも、地中海風にとても豊かで、さすがペトラルカやダンテを生んだ国という気が、ついしてしまう。 この老人たちが自国の歴史文化について、学者のように知悉しているとは思わないけれど、彼らの表現の豊かさには明らかに、そうした誇り高い伝統文化の反映があるのです。同じように日本には、日本人の歴史に刻まれた伝統文化の反映が、今どきの若者の表現やしぐさにも現れているでしょう。 今般のコロナ禍で、イタリアに帰れなくなったヤマザキ・マリさんが、テレビでおっしゃってましたが、イタリア人の家族パーティーというのは、食べるよりしゃべるのが主のようで、スパゲッティを食べる以上に、親戚縁者の唾のシャワーを浴びに行くようなものだとか。それにハグだのキスが加われば、絵に描いたような「三密」が発生するのは当たりまえで、だからこそ悲劇も起こった。 しかしだからといって、彼らの生活習慣がなってない、対して日本人の伝統的な生活作法は、今般のコロナ禍を低減させている、などという短絡的な話には、もちろんならないわけで、それはいわば「偶然の結果」に過ぎない。真逆の結果を招来する病原体その他のパンデミックは、地球上どこにでも等価に起こり得るということです。 迂闊にも私は全然知らなかったのですが、北イタリアで欧州最初の感染爆発が起きたとき、「なぜ北イタリアなの?」と疑問に思われた方は多かったのではないか?北イタリアの繊維アパレル業界が、二代三代と続く中国系移民の労働者によって、長く支えられていたなどという話は、今回初めて知りました。さらにはイタリア観光産業の多くが、中国資本の軍門に下っているなどという話も、これまでついぞ報道されたことはなかったですね。 感染爆発で北イタリアの医療機関が崩壊し、医療トリアージによって老人が見捨てられて行くのを見るにつけ、「これはイタリア独特の生活習慣のせい」だの「医療体制が予算削減で脆弱になっていた」だの、さまざま論評されていましたが、この国の医療体制が遅れていたなどということはないだろう、どころかイタリアは医療先進国の一つであって、それは報道される映像を見ていても、例えば武漢の病院の映像と比べても明らかでした。であるにもかかわらず、医療崩壊が起こり多数の犠牲者が患者だけでなく、医療従事者や聖職者にも出るという凄惨な状況を呈したというのは、どういうことだったのか?よその国の話で想像するしかないのですが、あるいは日本にも共通するかもしれない医療先進国特有の、医療資源の偏りがあったのかもしれないのです。 それは高齢化社会と現代的な疾病への対策に、もっぱら医療資源の重点が置かれて、医療後進地域で警戒すべき感染症対策などは、必ずしも十分ではなかったのかもしれない。先進医療国であるがゆえの弱点を、「武漢ウイルス」は精確かつ無慈悲に突いて来たということではなかったか? 私が残念でならず、かつ持って生きようのない憤りを覚えるのは、今般の武漢ウイルス・パンデミックは、たんに夥しい犠牲者を出したというだけでなく、それぞれの国の伝統文化習慣をも、こなごなに破壊しているという点です。イタリアの場合、とくに聖職者の死亡例が目を引きますが、要は重篤患者の臨終に際して、聖職者が最後の「祝福」を行うのが、カソリックの生活儀礼であったため、多くの感染者を出した結果だというのです。 臨終にも火葬にも立ち会えないという不条理な悲劇は日本でもありましたが、重大な危険が分かっていて、なお使命を遂行していったこうした人たちの振る舞いは、私たち(カソリックでもクリスチャンでもないけれど)にも刺さるところがありますね。歴史や伝統はこういう仕方で、人々を「無私」の行動に駆り立てるのです。 それにしても同じような悲劇は、世界各国であるいはもっと深刻に発生しているというのに、なぜイタリアを取り上げたのかというと、要は彼の国には「歌」がある、この場合の「歌」とは、中世イタリア・ルネサンス以来の長い伝統に裏付けられた「物語」が、この国にはあるからと言い換えてもいい。 と、ずいぶん深刻な話になってしまいました。やはりここは音楽が必要ですね。四月ごろテレビでも話題になった、クレモナの病院屋上における横山令奈さんのヴァイオリンソロ。 黙祷。
2020.09.26
コメント(0)
-
武漢ウイルス・クライシスとフライング・プリンセス 10.
平成の終わり 4. 「賛成」「反対」という対論の設定は、弁証法じゃないけど、必ず両者のより高い次元での和合が前提にされていなければ、すべては不毛な議論に落ちます。またもや「甘い」と言われそうですが、議論というのは、究極的には全員の「合意」(むつかしいけど)を目指さなければ、実りある結果は生まないだろう。その前提なしに繰り広げられる議論で蕩尽される知力からは、何の新たな叡智も生み出さないだろう、というのが私の観測です。 「それって、妥協ということか」と返されそうですが、もちろん違う。「妥協」とは「勝ち」「負け」の議論を前提にした、例のディベートの発想であって、弁護士の弁論と同じく、「取り引き」と「売り買い」の対象となるのです。トランプさんの話がまさしくビジネスマンの「ディール」の発想だと言われるのは、この政権の(言うたらなんやけど)安っぽい性格をよく表しているじゃないですか。 「合意形成」というのはそうではない。かぎりなく難しくめんどくさいけれども、全員が納得できる結論を、全員が知恵を振り絞って生み出すプロセスを前提とする、ということです。もちろん現実には限界があるわけで、だから最終的に多数決という処決を下すわけですが、この場合肝心なのはプロセスですよね。同じ「決」を出すにしても、互いが議論の前よりも、多少賢くなったと思えれば、それはそれで(いろいろ不満不平はあるにせよ)実りがあったと考えるべきではないか。 議論をディベートと捉えるかぎり、勝っても負けてもその当事者全体は一歩も前進しない。以前から「朝ナマ」は見ないというのは、そこでの議論が相手を論破することだけに終始して、互いの意見から新たな知見を見出そうなどという契機など、ここから先も伺えないからです。こうした議論をおこなって、仮に言い勝ったとして、果たして勝ち組は賢くなったと言えるのか?むしろ勝つことによって、おのれの知恵は退行したと考えたほうがいいんじゃないかしらん。なぜなら始まる前と終ったあとで、ここでの当事者たちは、全員「何一つ変わっていない」からです。 話が、安倍さんでも武漢ウイルスでもなく、とんでもないところに行ってしまって、我ながら笑ってしまいます。地球儀俯瞰外交などと言って、文字どおり世界中を飛び回った安倍さんですが、こうした雄大綿密な戦略眼に基づいたフットワークの「首脳外交」は、もちろんその相当部分が、安倍さん個人のパーソナリティーに由るところが多いとはいえ、やはり幾分かは「平成的エートス」のようなものが、働いていたのではないかと私は思う。 それは昭和でも大正でも明治でもなく、平成に至って日本の憲政史上に初めて現れたタイプの政治家像であり、これと同じような人物像を探すとなると、例えば新井白石や坂本龍馬のいた江戸時代の知性まで遡らないといけないでしょう。これは何も安倍さんを礼賛して言っているのではなく、世界俯瞰的な戦略眼と異国異人に対する率直な物怖じしない態度、そして何より「無私」な行動力という点において、似ているということです。こうした人物は時間を超越して特異的に現れるのではなく、ときどきの歴史的経緯や要請によって生み出される。私はそういう仕方で、「平成」という時代を見つめておきたい。 あるいはひょっとして、今般のコロナ禍における最大の痛手は、日本にとっても世界にとっても、安倍さんの辞任だったのではないか?安倍さんのいない世界政治の風景を見るとき、ふとそうした想念に駆られます。まあコロナが直接の原因ではなかったかもしれないけれど。 彼が世界を飛び回って構築しようとしてきた「世界戦略」は常に一貫していて、それは言うまでもなく「対中政策」でした。それは何も「対中国敵視政策」ではなく、この取り返しのつかなくなったバケモノ国家を、何としてでも現在の世界秩序に止め置こうとする戦略であったでしょう。安倍さんの打ってきたさまざまな布石は、この武漢ウイルスというコロナ禍を契機に、もしかして、かなりな進展を見せていたかもしれないのです。なぜなら世界中が、一党独裁という共産中国の危うさに、コロナという痛い代償と引き換えに、ようやくハッキリと気付いたからでしょう。 これまで潤沢なチャイナマネーの恩恵だけに関心を示して、この怪物国家の具体的な脅威には、ほとんど見て見ぬふりをして来たEUですが、コロナ禍の間に「香港問題」に端を発した中国警戒感はかなり強い。旧宗主国の英国は別として、ドイツやフランスといったEUの主要国が、中国の香港に対する「国家安全維持法」への懸念表明を出したことは、北京にとってもかなりな誤算だったのではないか?今回のこうした懸念表明の裏には、明らかに武漢ウイルス・パンデミックに対する北京政府の、一連の対応の傲岸さと不誠実さがあったはずです。 かたやで、大ナタを振り回しつつあるアメリカ、大いなる疑念を抱きつつあるEU、東南アジア諸国、さらにはインド、オーストラリアまで含めて、孤立感を深める中国政府という世界の構図において、日本の立ち位置は驚くほど重要になっている。それは何も深謀遠慮、権謀術数が利くタイミングなどという安っぽい話ではなくて、結果的に世界が日本の動向に注目せざるを得ない、という構図になっているからでしょう。 表向き傲岸な態度に終始する北京ですが、このコロナ禍における、あからさまな強権的振る舞いは、裏を返せばきわめて脆弱な統治力を表しているからです。こういうとき権力というのは、自らを変えるということが出来ない。何らかの外部からの働きかけがないと、どうしようもないのではないか? となると、間違いなく中国は日本にさまざまな外交的手管をかけて来るでしょう。さしあたっては、棚上げになっている「公賓としての来日」というカードですが、日本としては当然かなり高い対価を乗せるということになる。さしあたって中国には、世界復帰へのカードは、これしか見当たらなさそうです。この場合、日米同盟基軸という基本は揺るがないにせよ、まったくの対米追従では、この米中対立という世界史的な危機は回避できない。綿密な連携を取りつつ、こん棒を振り上げているアメリカとは別の仕方で、中国に自ら変わってもらう道筋を示すのが条件となるでしょう。 このあたりのパワーバランスや、それぞれの国家の機微を十分に読み込んで、新たな世界秩序を構築するというのは、途方もない話ではあるけれど、安倍さんとすれば、ある意味ドキドキするようなシチュエーションだったのではないかしらん。 しかし、これは平成の終わりとともに、見果てぬ夢になってしまいました。とはいえ長い間の当番、お疲れさまでした。まあ再々登板というのは、なんぼ何でもないでしょうが、むしろさらにもっと軽いフットワークで、世界を駆け巡る日は案外早く来そうな気もします。たぶんそれを世界が必要とする時期が来るでしょうから。
2020.09.18
コメント(0)
-
武漢ウイルス・クライシスとフライング・プリンセス 9.
平成の終わり 3. しかし、そうした出自であるからと言って、安倍さんが最初から軽々とした国際感覚を持っていたというわけではないでしょう。繰り返しになりますが、第一次安倍政権の時は、第二次以降よりはるかに狭量な保守政治家のイメージが濃かったのです。 ところで安倍さんご自身は、いつぞや「民主党政権の暗黒の3年間」という言いかたをされていましたが、それはそうではないだろう、ご自身も含めたその前の自民党政権3年間も含めて、「日本憲政史上の暗黒の6年間」と言うべきではないか。肝心なのは、その暗黒部分から目を逸らさずに、何がダメで何が生かせるのか、しっかりとした検証をそれぞれがどこまでやったかということだと思う。旧民主党はそこでの読みを完全に間違えた、末期的醜態を繰り返す自民党にうんざりして、国民がなぜ民主党に政権を附託する気になったのかといえば、時の民主党が多少なりと現実的な路線を示したからでしょう。しかし政権を奪取したとたん、急速に元の教条主義的な左に戻ろうとしたので、完全に信頼を失ったのです。 自民党はそのあたり、やはりしたたかというか、よく世間の空気の移り行きを心得ている。なかんずく安倍さんは自身の失敗から逃げずに、ずいぶん反省したのではないか。第二次以降の安倍政権は、先ほども言ったように元々安倍さんが把持していた、いわば原理主義的党派性をコモにくるんで、より現実主義的な政権のイメージを打ち出したことで成功したのです。結果として、彼の元からの岩盤の支持者からは、欲求不満の声が常に立ち上がってくるし、さりとて、いわゆるオールドリベラルな層からも、微温的かつ不毛な意義申し立てはあったのですが、国民全体としてはこのバランスの取れた政権のありようを長く支持したのでしょう。 株高と雇用安定をベースにした民心の安定と、いかにも軽いフットワークによる外交政策は、国民にたんに安心感を与えるだけでなく、一種の晴れがましさを感じさせたのではないか?こうした晴れがましい気分というのは、今までの日本の政治家にはなかったものなのです。 外交の各論において、「拉致問題」や「北方領土」、はたまた尖閣や竹島問題などなど、具体的な成果は何一つ達成されてないどころか、課題山積じゃないかという声が当然出て来ますが、肝心なのは、であるにもかかわらず、この政権ほどこうした問題に真正面から取り組み、具体的な行動を起こした政権は今までなかった。文句をつけるのは簡単ですが、言っている当の本人たちが、具体的な行動や施策を打ち出しているかと言えば、もちろん何も行っていないし持っていない。オールドメディアやオールドリベラルな人たちは、この未解決の課題の一つでいいから、具体的な解決案を持って物を言ってもらいたい。衆目はすべてそれらを見て、比較考慮しているのです。 喫緊の課題を数多く残しているとはいえ、それでもなお評価すべき具体的な成果として「平和安全法制」の整備や、日米印豪にインドネシアなどを加えた「インド太平洋戦略構想」、一度流産しかかったTTPの日本主導による再構築とTPP11の発効、さらにはEUとのEPA締結などは、将来的な経済安全保障を見据えた、壮大な外交的達成であったというべきでしょう。 しかし、そうした専門分野における評価は、政治経済の評論家諸氏に任せるとして、一番肝心なことは、戦後の日本の政治家において、安倍さんははじめて「日本人としての範たる事例」を、示し得た点にあるのだと私は思う。ひらたく言えば「親が子供に堂々と話すことが出来る政治家」ということです(岸さんも佐藤さんも立派な政治家でしたが、やはりちょっと怯むところがあるじゃないですか)。 青山さんがしきりとおっしゃってましたが、国会における議員さんたちの立ち位振る舞いは、およそ社会人としての則を逸脱し、妙な業界用語と阿吽の空気が全体を領する、ごく特殊的な世界のようです。とうてい子供には聞かせられない罵詈雑言(早い話、当の本人が家で、同様の言葉づかいをしているとは思えない)が飛び交い、不毛な議論の応酬と選挙目当てとしか思えない、揚げ足取りの発言ばかり。この様子を見て、若者に政治に興味を持てだの、選挙は国民の重大な権利と言っても、誰も聞く耳を持たないし、教育熱心な親御さんも、わが子をこういう世界に送り出そうとは思わないでしょう。 結果、全員とはもちろん言わないけれど、そうした特殊業界内の専門用語や振舞いに慣れ親しんだ二世三世議員や、一発逆転を狙う山師的エートスの持ち主が幅を利かせる世界となって行くのです。こうした特殊業界的空気というのは、外部の人間を拒む代わり、その内側にいる者にとっては、(与野党問わず)よほど居心地のいいものであるらしい。これは何も国会議員の世界だけじゃなく、オールドメディアをはじめ他の業界においても、多かれ少なかれ見られる様態なのでしょうが。 「何を幼稚なことを、今どき言うてんねん」と蹴飛ばされそうですが、私は思うのですよ。議論というのにはディベートとディスカッションの二通りがあって、今どきの風潮はディベートこそがすべてという雰囲気なのですが、それはそうじゃないだろうという気がするのです。 ディベートが賛成側反対側に分かれて行われる討論なのだとすれば、その目的は結局「勝ち負け」に帰せられる。極論すれば中味の正誤より、結果に価値が置かれる議論だということです。この場合、議論によってお互いが以前より少しでも賢くなり得る、という機会は想定されていません。これの典型的な例と言えば、弁護士の弁論というのがそれに当たりますね。「すべては依頼人の利益のため」という前提に立てば、「勝つ」ことだけが目的化して、その弁論の中味自体が当事者たちの価値を高めるということには、もちろんつながらないでしょう(まあ、スキルの強化にはなるかもしれないけれども)。 爾来、日本人はディベートが苦手で、ディスカッションが好きと言われますが、それはだから「日本人は話下手なのだ」などという話ではもちろんなくて、「勝ち負け」だけが目的化した議論が、しばしば不毛を呈し、ややもすれば勝っても負けても、お互い「品下がる」気分になるのが嫌だからなのではないか? 「品下がる」とは、要は自身の容儀が何やら卑しく見えて、「気色悪い」ということでしょう。日本の議会制民主主義はとっくに百年以上の歴史を経たにもかかわらず、いっこうに人の心に届く議論や弁論というのが出てくる気配がしないのは、それらによって互いが少しでも賢くなった、叡智が付加されたという気分に到底なり得なかったからでしょう。 安倍総理の米国議会における歴史的な演説、例によって日本ではオールドメディアによって過少評価されていますが、その決して上手いとは言えない英語の発語でも、アメリカ人の琴線に届くところが大いにあったらしく、背後に並んでいる席にいる議員の中には、ハンカチで目をぬぐっている人もいましたね。スタンディングオベーションは、儀礼的でよくあることとしても、あの「泣いてはいけないアメリカ文化」の議会人が泣くというのは、よほどの事態と言うべきですよ。 それはたんに不幸な過去の反省と和解といったフレーズの中にあるのではなく、新たな「歴史の叡智」をここに記しつつあるという、その演説の趣旨に共感したからではないか?
2020.09.13
コメント(0)
-
武漢ウイルス・クライシスとフライング・プリンセス 8.
平成の終わり 2. すでに終わりを迎えつつある安倍政権について、十分な総括をしておくというのは、何もそれが歴代最長政権だったからではありません。この政権を見直すということは、同時にそれと共に過ごしてきた七年八ヶ月の自身や日本、あるいは世界を見直すという作業でもあるからです。 既存のメディアは総括は出来るだけ簡単に、そしてさっさと新政権の話に話題を移そうと必死ですが、そこに見え隠れする底意には、いかにも安っぽい意図が感じられる。意地悪い見かたですが、さんざんモリカケや桜その他でこき下ろし続けてきたにもかかわらず、安倍政権は計六回の選挙を勝ち続け、一回も負けなしでビクともしなかったうえに、辞任表明と同時に支持率がハネ上がる、という事実に直面しているからでしょう。つまり安倍政権を総括をするということは、そのまんまオールドメディアの連敗の事例を検証することに他ならない。 ところで、この退任直後の支持率急上昇という朝日新聞の世論調査データかんして、似たような数字の不自然な変動を、私は今年まったく別のところで見たような気がしました。他ならぬ中国政府発表の、武漢および中国全体における感染者データの推移なのです。はじめ発表していた感染者数について、取り方の基準を変更すると称して、途中から数字がうなぎ上りに上がった、それも基準の変更を二回やってです。これってデータの座標軸をずらすようなものだから、疫学的数字としてはまったく意味をなさない、というか、事実を前提とした議論の対象にももちろんなりえません。 ではこの政府発表の数字は何かといえば、要はそれは、中国政府が求めて止まない「であるべき数字」だということが分かる。ただ残念なことに「であるべき数字」が、実体とあまりに乖離してしまったので、座標軸のほうを変更したのではないか?さらに言えば地方政府が、北京が考えている「であるべき数字」を忖度して、まともな数字を上げない、事実を報告したら何をされるか分からないということなると、はじめから実体などどこにも存在しない数字が、ただ中空で踊っているということになってしまいます。 あまり言いたくはないけど、今回の支持率急上昇というのも、それまで朝日新聞が発表してきた安倍政権の支持率低下傾向という世論調査が、あまりに実体とかけ離れていたので、辞任表明をこれ幸いに一気に修正しただけなのではないか?考えてみれば、去っていく政権の支持率調査って、なんだかヘンですね。自分たちが作り出した事案を執拗に繰り返し、何とか「であるべき数字」に持って行こうとして来たが、ビクともしない実体に、どうしようもなくなって座標軸を変更して取り繕うという、およそ知的媒体としてあるまじき実体が顔を出したということではあるまいか? こうした「ゴールポストを動かす」とか「ハードルを下げる」といった、厳しい事実から目を背け、「であるべき空想世界」を次々繰り出すという児戯めいた行為は、先ほどの共産中国だけでなく、隣の国でもよその国でも往々ありますが、朝日もどうやらそのクチらしい。クオリティーペーパーとはよく言ったもので、オールドメディアの知的劣化をこれほど明瞭に示した数字もないのではないかしらん。 とはいえ、その評価の中味を見ると「外交・安全保障」と「経済」が過半で、これはごく常識的。で、ここで話は「外交」のほうに移るのです。よく言われる「安倍トランプの蜜月関係」ですが、これはもちろんたんに相性が良かったなどというものではなく、安倍さんのほうからかなり戦略的に動いた結果だと言うべきでしょう。早い話が、相性が悪いと言われたオバマさんについても、「広島訪問」という大統領としてのレガシーを演出して、いささかなりと「貸し」を作っているのです。 ではトランプさんに戦略的に近づいたわけはというと、それはたんに日米同盟の強化ということではなしに、大統領になる前から彼が繰り返し訴えていた「アメリカ・ファースト」という孤立主義を、何が何でも阻止するという意図があったからではないか?世界の警察からアメリカが手を引けば、世界秩序の不安定化、中でも東アジアでの共産中国の伸長激化を招くのが明らかだったからです。そうしたごく常識的な判断を進言する自国の国務省や国防省の言うことを、まったく聞かないトランプさんが、安倍さんの言うことなら聞くというのは、なんだかヘンな話ですが、これはトランプさんのかなり固有な性格によるものであるらしい。少なくとも「歴代のアメリカ大統領という退屈な規格に、俺様は絶対入らないぞ」と思っていたことは間違いないので、なぜなら、それが彼の岩盤の支持層の根源でもあったからです。 そうした彼の性格を早々に見抜き、友誼を交わすのに成功した安倍さんという人は、やはり昭和の人ではなく純正の平成の宰相と言うべきでしょうね。中曽根さんでも小泉さんでも無理だったでしょう(小泉さんは平成の宰相ですが、手法は旧来のものでした。彼は自身の政治的レガシーのために、拉致被害者を利用したのです)。旧来の政治家としての権威性を、多少でも意識した政治家ではこれは無理。それが証拠にEU各国の首脳もトランプさんを嫌っているというか、手をつかねて安倍さんに聞きに来るという始末。これってやっぱり日本の憲政史上あり得なかった事態だと思いますよ。 では歴代総理大臣(戦前も戦後も)がなしえなかった、各国首脳との自然体の付き合いが、なぜ安倍さんの場合出来たのか?それはおそらく、政治家一族としての安倍さんの出自が、この場合「吉」となって出たということだと思う。叔父の岸さん以来、外国人との交流が普通に行われてきた一族の中で、安倍さんは自然と国際交流の雰囲気や呼吸を身に着けたに違いない。 G7や中国ロシアの首脳と立ち混じって、まったく「臆する雰囲気がない」日本の首相というのは、安倍さんが初めてでした。中曽根さんも小泉さんも、その面にかんしては相当「気張った」首相でしたが、いかんせんその「気張った感」が丸見えで、自然体と言うにはほど遠い。安倍さんがそれをごく自然体に出来たというのは、大成した名門一族のサラブレッドとして、政治家によくある「権威や権力指向性」を、あえて表に出す必要がなかったからでしょう。 同じような雰囲気を醸し出していた人として、私は緒方貞子氏を思い出します。この人も犬養毅のひ孫であり、外交官の家に育ってごく自然に国際感覚を身につけた人でした。大事なのは「名門には名門としての責務と役割がある」ということを、本人たちがどれだけ意識しているかということでしょう。両者に共通するのは、一言でいえば「私欲がない」ということです。政治家の世襲化が問題視されたりもするし、青山さんのようなフツーの人で、国際社会と丁々発止渡り合える人ももちろんいるでしょうが、日本の政治家の中で、そうした器量を自然と保持している人がどれほどいるのかしらん。
2020.09.08
コメント(0)
-
武漢ウイルス・クライシスとフライング・プリンセス 7.
平成の終わり 1. 「さまよえるオランダ人(Flying dutchman)」に引っかけて、「武漢ウイルス・クライシスとフライング・プリンセス」なる表題で、現下のコロナ禍のようすを、私が感じるかぎりの範囲で話しておこうとしていたところが、情勢の変化はまことに早く、安倍政権の終焉という想像もしない状況に至っています。 別に安倍さんに肩入れして言っているというわけではなく、よく考えてみれば2020年の9月と言えば、青山さんが以前言っていた安倍さんが勇退すべきという時期でもありましたね。その心はと言えば、確かオリンピック開催を経て、「任期を待たず余力を残して引く」というのが、政治家としてベストだというようなことだったと思います。コロナ禍はそうしたすべての期待値を吹き飛ばして、ただし勇退時期だけは外してくれなかったということでしょう。 さて世の中の関心は、すでに次期政権の行方のほうに焦点が移っていますが、私はやはり歴代最長の政権を維持し続けた安倍政権の評価を、もう少ししっかり見定めるべきだと思う。これについては以前もこのブログで触れたことがありますが、第一次政権の失敗をしっかり踏まえて、ニューカラーで押し通したことが長期政権誕生の根本にあったように思う。で、そのニューカラーとは第一次政権で前面に押し出した「戦後レジームからの脱却」というフレーズを引っ込めて、第二次以降はこの文言を注意深く封印したということでしょう。 「戦後レジーム」とは言ってみれば昭和の遺物であり、それからの脱却ということは昭和からの決別ということを意味するわけですが、逆に言えばそれをたかだかと掲げれば掲げるほど、安倍さんの立脚点が昭和にあるという印象もまた強くしたわけです。で、その昭和のイメージとは、いわゆる岩盤の保守層、誇り高き日本の復活を希求する層を連想させるところがあったわけで、一次政権発足時はほとんど右翼の政治家のような書かれ方をしていましたね。 第二次政権ではそうした古びた保守性を封印し、「三本の矢」という経済再生を表看板にすることによって、イメージの転換に成功したのではないか?いろいろな書かれ方をずうっとされているけれども、アベノミクスの効果は株価の上昇だけでなく、戦後最低水準の失業率という形になって現れていたわけで、これが果たした社会的安定というのは計り知れない。平成の世が昭和に比べて暴動とかストライキ、はたまた学生運動のような社会不安をもたらす事件がはるかに少なく、自然災害を別にすれば、きわめて穏やかな時代であったことを指摘する人はあまりいませんね。 現上皇陛下が、ご譲位の折りに平成の世を振り返って、「戦争がなくて、良かった」と、しみじみおっしゃったことが、私には非常に印象に残っています。共産中国の台頭、テロ国家北朝鮮の核実験やミサイル発射など、疎開を経験された陛下からみれば、現下の日常の平穏は、いつ破られてもおかしくないということを、常に覚悟しておられたのでしょう。 これは全くの私見で、前にも言ったことがありますが、「クールジャパン」といった、いわば居心地のいい日本見直しのような風潮は、平成のいわゆる「失われた20年」の間に生まれて来たものであり、その長期にわたるデフレの社会にあって、なぜか民心は荒れることなく、むしろ日本的エートスは洗練の方向に向かって行ったのです。昭和懐古的な映画がヒットしたりしますが、実際生きてきた戦後40年ほどの昭和の時代というのは、けっこう人心は荒れていたし、社会不安も多かったですよ。「バブルもあったじゃないか」という声が返って来そうですが、この時期、都市部の私学に通う学生なんか、BMBで通学してディスコに通うのが、「ナウい」と言われたりしていて、では、そうした振る舞いが洗練されたエートスであったのかどうか。 今どき、外国人観光客が口をそろえていう「日本人の清潔好き」というのも、平成のそれも後半になってから顕著に現れてきた日本人の行動様式であって、それ以前の私たちの生活や都市空間は、お世辞にも「清潔」とは言えなかった。他ならぬ私自身も、くわえタバコで街を闊歩するのは普通にやっていましたよ。今では街中どころか田舎でさえ、公衆のゴミ箱が姿を消し、自分の出したゴミは(悪いけどコンビニか)家に持って帰って始末するのが、当たり前になってしまいました。 肝心なことは、こうした「清潔好き」というイメージが、あたかも元々日本人が持っていたエートスのような(例えば神道の「禊」の伝統に通じるような)文脈で、しばしば語られているということです。そうじゃないだろう、こうした日本人の行動様式や都市景観は、ここ20年ほどで醸成されたものだろう、というのが私の観測なのです。 今はコロナ禍で止まっていますが、日本へのインバウンドの需要は上昇することはあっても、当分下がることはないでしょう。世界は平成の洗練を経た日本を、今発見している最中だと言っていいのではないか。それを生み出したのが、低失業率に裏打ちされた民心の安定という平成の世であったことは、もう一度確認しておいたほうがいいように思う。 話が少し飛びますが、先日高橋洋一さんの出ていたNewsチャンネルが面白かった。黒田日銀のインフレ・ターゲット2%とは、単なる物価上昇目標でも金融緩和でもなく、雇用安定策としてとられていたというのです。 このマクロ経済におけるフィリップス曲線の理論を本当に分かって「アベノミクス」を論じたジャーナリストや学者、政治家が日本には一人もいないというか、どうしても「分かりたくない」層が、オールドメディアを筆頭に、日本の知識層の大半を占めているということでしょう。 政治的思惑や妙な同調圧力のようなものが入り込むとき、冷静な分析や議論が封じられ、知的不調を招くという不幸がここにも現れている気がしました。雇用政策に関するかぎり「アベノミクス」は歴代政権と比べても、飛び抜けて高い実績を残したという事実は揺るがないのです。
2020.09.04
コメント(0)
-
インテルメッツォ 102.
政治家は使い捨てでいい 武漢ウイルスに事寄せて、中国の話をしようと思っていたら、そのあまりの広大無辺さに頓挫してしまい、楽しい音楽の話に乗り換えたものの、これまた何だか重たいことになって参っています。ここは少し気分を変えるために、軽めの音楽を聴くのです。岩内佐織「Mother Tree」 なのですが、各楽器群の選択と出し入れが、例によって快調そのもので、何だかいつかどこかで(例えば昔、テレビのCMで)聞いたような懐かしさを感じてしまう。これは何も曲調が古いだのと言っているのではなくて、私たちが作り手側の「歌心」に素で触れられる瞬間というのには、そういう感じ方もあるということです。 逆に言えば、今どきの音楽や文学、あるいはその他さまざまな社会事象で、素のままスッと我が身に引き寄せるには、ちょっとためらってしまう事例が、とくにコロナ禍以後、多くなったような気がする。 今や飛ぶ鳥を落とす勢いの吉村大阪府知事、先般の「うがい薬」問題でまたまた話題沸騰ですが、どちらかというと関東の中央局メディアで、医事専門家やコメンテイターも含めて、「拙速」だの「買占めを助長した」だのといった批判的な意見が多かったように思う。では吉村知事や松井市長が、そうなるだろうことを予想しなかったかと言えば、もちろんそんなことはなくて百も承知。しかしこの「維新」のツートップには、「お行儀よい政治」をやる気は、ここから先もないらしい。「そんなこと言ってる場合か」という構えが、会見場に現れていて面白かった。 この半年間、武漢ウイルスの挙動を見るにつけ、つくづく思うのは、この病原体は「人の常識的予測と淡い願望を、常に裏切る仕方」で、感染を拡大させて来たということでしょう。当初インフルエンザより感染力も致死率も低いと言っていたWHO、社会的免疫を獲得するために、あえて防疫を行わなかったスウェーデン、勝利宣言をしようとするたびにクラスターが発生した韓国、春になればほっといても収まると公言したトランプさん、挙げていけばキリがないですが、医療従事者あるいは専門家さえも、誰も彼も手痛い打撃を受けて口をつぐむ中、明らかに有意な数字上の違いが、アジア諸国と西欧諸国の間で出て来て、「ファクターX」なるものの存在が、特に日本でささやかれるようになりました。 曰く「公衆衛生の意識の高さ」だの「自己規律」だの「医療体制の完備と、従事者のモラルの高さ」だのといったことですが、緊急事態宣言解除後の感染の増加を見ていると、事柄はそんな高尚な話ではなくて、要は人が家に引っ込めばウイルスも引っ込む、外へ出ればウイルスも一緒に顔を出してくるというシンプルな状況が、いよいよハッキリしてきたということじゃないか? 今だにウイルスという存在は、生物か無生物か判然としないようで、逆に生命の定義の仕方によって、それはいかようにも変容する、つまり人間の都合によってどちらとも取れるという態様を持っているようです。間違いないのは、この武漢ウイルスにかんしては、それは優れてヒトに付随し、ヒトの振舞いかたによって、増殖と減衰を繰り返すということでしょう。と考えれば、仮にウイルスを無生物と規定すれば、これはある意味「マネー」と酷似した様態を持っているということですね。ヒトが動かなくなれば経済は頓挫するし、ひとたび動き出せばマネーは逆方向に移動を開始するのです。 今、巷間に言われる「With Corona」とは、「マネーとウイルスのダブルクラッチで過ごしましょう」ということで、どっちが先にネを上げて退散するか、というようなチキンレースは、かなりな敏腕レーサー(青山さんみたいな)でも、なかなか難しいのではないか? 現在、日本は第二波に見舞われていると言いますが、そんな区分はどうでもよろしい。肝心なことは「心配だけれども、今は見守るしかない」。では、「じゃあ、この推移が第一波の時と同様、いつか収束するのか?」と言われたときに、それを「そうだ」と根拠を持って断言できる人は、誰一人いないということなのです。とすれば、それが逆目に出て春のニューヨークやイタリアのような惨状を呈していいのか、という話になるのですが、どうもそういう想像をする人は日本では少ないらしい。考えてもみてください。毎日数千人単位の感染者と数百人単位の死者が、バタバタ出てくる生活って想像できますか? 吉村さんは、ひょっとしてそうした事態も、少なくともこの秋以降はあり得るということを想定していたんじゃないかと思う。ただそれが秋よりもはるかに早く、梅雨明けと同時にやって来た。このウイルスは例によって人の常識的な予測と願望を見事に裏切る形で、胎動を始めているのです。そうした時に「こちらに武器がない」という春と同じ事態にはしたくない、何か一発でも撃てる弾はないかと考えたときに、「ポビドンヨード」の研究結果が出てきたということでしょう。 この人、見かけより「ケンカ好き」というか、「負けず嫌い」のようですね(藤井君もそうですが)。何だか映画「プラトーン」に出ていたW・デフォーという俳優の面構えを思い出してしまいました。それもこれも、この人がいつも言っている「政治家なんて使い捨てでいいんですよ。有権者が必要とすれば選べばいいし、いらなければ落とせばいい。それだけのことです」。こうした構えの政治家、行政マン果たしてどれぐらい日本にいるのかしらん。いっそ「維新」はこれを党是にしたら。「政治家は使い捨てでいい」
2020.08.06
コメント(0)
-
エレクトーンというガラパゴス 24.
こぼれ落ちるもの エリオットは、自身の詩心の起点を「思想」に置き、現代詩の有りようを切り開いた巨人の一人ですが、当然こうした一種冷めた「詠いかた」には、情緒優先の象徴派詩人たちからは反発があったでしょう。しかし第一次大戦後の荒廃し尽くしたヨーロッパ諸国の惨状を見るとき、彼はとてもじゃないが、従来の「詩心」で詠うことは出来なかったのです。 爾来、彼の詩は難解かつ衒学的と言われ、早い話、代表作の「荒地」など、作者自身のダダ長い脚注が付いていて、素で詩を味わおうとする者の興をそぐ。しかもその注記が何を意味し、この詩が何を構想しているのか、西欧文学や哲学、宗教によほど精通した人でなければ、さっぱり分からないという代物で、この詩一編の解釈だけに、分厚い本を物した学者もおられるほどです(しかし、そもそも自身の作品を、自分の解説付きで出版するというのも、考えてみればヘンな話ですよね)。 まあ、それはさておき、私がここで申し上げたかったのは、美学の起点が感情であれ思索であれ、それを学術論文みたいな分析でなく、「バラを嗅ぐような仕方で享受する」というアプローチが、芸術分野では確かにあるだろうということなのです。 従来そうした美学教育というか、人の情操にかんしては、結局現物を当たらせるしかなく、教育現場では、現物の周辺情報を伝えるのが、精一杯だったような気がするのですが、物事を「享受する」という、人のいたって主体的な行為というものについて、もう少し論理的というか、意識した教育があってもいいのではないか?まあ今どきの受験体制教育では、そんな時間はとてもじゃないが、割けないのかもしれませんが。結局、そうした「享受」のヒントは現場の先生の器量に丸投げされているので、たまたま気の利いた先生に当たれば、大いに感性豊かな子供たちが育つのでしょうが、そうでなかった子供たちは、永遠に豊かな内面世界の涵養から外れるということになる、これって不公平ですよね。 昔は(というか、私の小中時代は)、まだ教育現場の自由度が高いというか、良い意味でも良からぬ意味でも「面白い先生」がいて、例えば左翼系ビンビンの運動家先生と、旧日本将校あがりとおぼしき、強権的先生が同じ教壇に立っていました。今や文科省の縛りがどんどんキツくなっているので、そうした名物先生に出会うことはまずないでしょう。 話は戻るのです。 それにしても、寄田さんの響きを聴いていると、邦楽と洋楽の根本的な有りようの違いに、あらためて気付かされる。「洋楽」が、いわば分節された「単位(モナド)としての音」の集積で成り立っているのに対し、「邦楽」は明らかに分節されない音、あるいは分節以前の音で成り立っているのです。 洋楽がなぜこうした「単位としての音」に、音楽をどんどん分節化することによって、西欧音楽を花開かせたのか、いろいろ説はあるのでしょうが、一つ言えるのはルネサンス以降の科学的合理主義の進展が、音楽の分野にもかなり早くから浸透していたのではないかしらん? しかし、尺八の一音は、たんなる単位ではなく、時間的にも空間的にも自由に伸び縮みしているようにみえる。となると尺八は、極端な言いかたをすれば、一音だけで人に届けられる「音楽」を構成することもあり得るわけで、そのあたりから、普化宗尺八の「一音成仏」などという言葉も生まれてくるのでしょう。 じつをいうと私は、こうした格言的な言葉は、あまり好きではありません。「一期一会」だの「即身成仏」だの、いささか権威性を持って語られる熟語は、それが発せられるとき、その言葉の意味するところが十分に嚥下されないまま、言葉だけが勝手に飛び回ってしまうからです。 とはいえ、分節されざる音なら、一音でも音楽が可能ということになれば、音楽世界が一挙に拡がるのかと言えば、そんなことはない。むしろそれは「音楽そのものの解体」という、恐ろしい地平に足を踏み入れるという、かなりな危険とも隣り合わせになっているのではないか? 考えてもみてください。リズムもハーモニーも音階も溶解していくような音から、いわゆる「音楽」というものを、改めて構成することが出来るのかどうか。 これには、一つの回答が待っているのです。それは西欧楽器も含めて、近代以前の世界の楽器というのは、多かれ少なかれ、こうした溶解した音たちによって、奏でられていたということです。このあたりは最近の民族楽器や古楽器などの研究で、明らかになって来たことでした。 尺八に似た奏法とか音声を持つ木管楽器は、けっこう世界各地で見られるし、琵琶のような弦楽器でもそうでしょう。ただそれらと尺八や琵琶が違うのは、これらは十分洗練され尽くした楽器であって、いわゆる民族楽器とか古楽器に、尺八とか琵琶をカテゴライズするのは、明らかに無理があるということです。 横山勝也や青木静夫の尺八が、すでに洋楽器に比肩し得る、洗練された響きを持っていたということは、今さら言うを待たないことですが、ただ一つ申し上げるとすれば、それらが普化宗尺八直系の海童道だの琴古流の伝承を多量に引き継いで、逆にそれらに付随した物語が、この楽器の響きが指し示している真の姿を、見え難くしていたところはあったかもしれない(別にそうであったことを、くさしているわけじゃないですよ)。 しかし寄田さんの演奏には、不思議なほどそうした付随した「物語」、あえて言い換えれば夾雑物がない。あまたある伝承をすべて引き受けつつ、発せられる音は、まさしく「今、そこで生成されつつある」という新鮮さに満ちている。音楽が真に人に届くとは、どういうことなのか?というのは、ここのおしゃべりの根本命題ですが、何だか一つの回答を聞いたような気がしました。 西欧的な分節的アプローチでなく、むしろそれによってこぼれ落ちる多量な響きのほうに注力し、それを洗練させて行くところには、何やらより自然に近しい生き物、例えば粘菌のような、私たちから見ればどうみても不合理、あるいは予測不可能な生命の有りようを感じてしまう(ちょっと、大げさですが!)。肝心なことは、それらが西欧音楽とは全く違ったアプローチでありながら、非常に堅牢な構築性を持って奏されているということでしょう。
2020.08.05
コメント(0)
-
エレクトーンというガラパゴス 23.
思想あるいは思考が立ち昇る これを聴いていると、やはり音楽はかなり意識して、「観る」ものだなと思ってしまう。何も尺八にかぎらず、琵琶だのヴァイオリンだのピアノとかの、いわゆる「名手たちの演奏」というのには、一種舞踊的な様式美みたいなのがあって、たんに耳で聴くのとは別の響きがあるのではないか(何も振りが大きいのがいいと言っているわけじゃないですよ。ときどき嫌味のような振りで演奏するミュージシャンもポップに限らずいて、これでは逆に聴くのを大いに阻害されてしまいます)。 「産安」という表題は、創造の困難と孤独を、妊婦さんの生みの苦しみに仮託したものとも言われますが、何しろ古典本曲というのは江戸時代以来の伝承音楽なので、いろいろいわくありげな物語が、あとからくっついたようなのが多い。先に取り上げた「鶴の巣籠」も、いかにも鶴の鳴き声を連想させる響きがあるし、有名な「鹿の遠音」という本曲も、琴古流などだと鹿の求愛を模したような奏法が現れる。 しかし、かといってそれらの音楽が、ズバリ「鶴」とか「鹿」を表現しているのかと言えば、もちろんそんなことはない。それらは表現の起点ではあっても、それらが伝えようとするところは、もっとはるか彼方、司馬さん流に言えば、坂の上の雲のように仰ぎ見て、それをつかもうとして追っかけても、ついに届かない(届きようのない)彼岸のようなものを指し示そうとするのです。 蛇足かもしれませんが、起点が「鶴」だの「鹿」だのというのは、それら生き物が人の歌心を刺激するから取り上げられるわけで、早い話「猿の遠音」とか「熊の巣籠」ではやはり具合が悪いでしょう。マーラーが「大地の歌」で猿の鳴き声を取り入れましたが、それは猿の叫喚が十九世紀末ウィーンのデカダンな雰囲気を表すのにピッタリだったからで、たんなるエキゾチシズムで取り入れたわけではありません。 現代芸術は音楽にかぎらず、多かれ少なかれ前時代の素材では、新鮮な美の起点が見出せず、いろいろ変わったものが登場する時代なので、例えば便器を逆さまに置いたオブジェが出て来たりもする。こうなると歴史的経緯は分かっていても、こちらの賞味力が相当タフでないと、到底ついていけないという仕儀となります。 一時風靡した「前衛音楽」が、今どき全く顧みられなくなったのは、受け手側の賞玩力がついていけなくなったというのもあるかもしれないけれど、何よりも作り手側の「絵心」「歌心」の減衰が、今の景況を招いているのではないか?武満が晩年、前衛から調性音楽へ移行したのは、何やら示唆的ですね。 ところでこの横山勝也という人、その自己に厳しくストイックな求道性は、学生時代の私にとってほとんど偶像でしたが、同時に「これは、とてもかなわんわい」という存在でもありました。この場合の「かなわん」とは、こうした求道性に深入りした場合の危険と覚悟は、とても自分には持てないという意味です。私の友人知人にも、何人か高い志を目指した人がいましたが、なかなか苦労されてるようですね。 私は幸か不幸か、前にも言いましたが、ごく初めに自身の分というものを、痛いほどを知らされてしまったので、ただただこういう人たちを遠くから、ひそかに眺めることになってしまいました。 これは個人的な好みですが、私はどちらかというと、華やかで明朗な音色の都山流よりも、いささか枯淡な感触のする琴古流が好きで、なかでも青木静夫の枯れた中にも、洗練されたキレを交えた演奏のファンでした。それが横山勝也の普化宗系尺八とはまた違った形で、西欧楽器のどれともなじまない、独自の音色と奏法を持っていると思ったからです。この人の動画で奥州薩慈(おうしゅうさし)を聴いてみてください。 民謡らしいモティーフを基にしながら、虚無僧的な求心性よりも、どことなく乾いた都会的な洒脱を私など感じてしまう。 最近は洋楽器のようにスタイリッシュな演奏を聴かせる、注目すべき若い尺八ミュージシャンたちも現れているようですが、その多様な試みと一般への普及の努力は認めつつ、果たしてそれでいいのかという不安もよぎります。これらの人たちのテクニックと音色は特筆もので、なんだか和洋の音色にずうっと囚われている、こっちがバカみたいに思えてくる。とはいえ、そうした若い一群から寄田さんのような才能が生まれてきたのですから、すそ野が広がっていくのは、やはり良いことなのでしょう。 その寄田さんの演奏で、古典本曲「鹿の遠音」を聴いてみてください。 先にインテルメッツォ101.で取り上げた「鶴の巣籠」と並ぶ古典本曲の代表で、意のある尺八吹きなら一度は挑戦したいと思う曲でしょう。寄田さんの演奏は例によって、古伝その他のあらゆる技法を駆使しつつも、過度に求心的にならない。サラリとは言わないけれど、破裂やムラ息の後に残る弱音を際立たせるために、これらは駆使されているのではないか、という気さえしてしまいました。 したがって、本曲尺八を聴いたあとの「疲れた感」が全然しないというか、むしろ何度でも聴き返したいという清々しい気分にさせられるのです。これって、なかなか大事なことなのではないかしらん。「それが、それぞれの持ち味というもんだろう」という声が聞こえてきそうですが、私は多分そういうカテゴリーを踏み越えた「何物か」なんだろうという気が、これはする。 昔、T.S.エリオットというアメリカ生まれの英国詩人が、詩を読むことを「思想をバラのように嗅ぐ」という言い方をしましたが、横山、青木、寄田とこの三人の演奏からは、言葉からではない、しかし確固と自立した「思想あるいは思考が立ち昇っている」のです。
2020.07.27
コメント(0)
-
エレクトーンというガラパゴス 22.
音楽を観る このイギリスの名手S・ラトルと、名門ベルリンフィルの演奏などを聴いていると、音楽が紡ぎ出されてくる瞬間は、やはりしかと「観ておきたい」という欲求にかられます。世界中の超一流の才能が集ったようなこのオーケストラ、当然かなりうるさ型の審美眼や主張をさまざま持っている集団が、ここ一番で集中する気迫、聴き手に何かを必ず届けたいという強い気概には、息を飲みますね。 コンサートマスターの樫本大進さん、指揮者とオーケストラのつなぎ役として大奮闘ですが、これくらいのオケになると、まとめようとか指揮者の意図を伝えようとかのレベルじゃなくて、各楽員の「歌心」を何とか極限まで引き出そう、という一点に注力しているように見える。それも各員バラバラの「歌心」じゃなくて、指揮者と同じビジョンを共有するような仕方で。 それらが時に幸福に一致するとき、そこから立ち昇る音楽は、指揮者の意図からも、名手たちの奏でる楽器からも解き放たれて、何やら別のところから包み込むように響き渡っているように見える。私は思うのですよ、そうした瞬間には、じつは音楽は聴き手も含めた、会場全体が作り出しているのではないか、と。 しわぶき一つ許されないクラシックコンサートですが、音楽が本当に聴き手に届いたとき、音楽は指揮者やオーケストラの手を離れ、ある意味自然物のように勝手に動き出す。それはあるいは先の見えない、ひょっとして不安もともなう進行であるかもしれないけれど、同時にかぎりなく「心地好い」瞬間でもあるのです。 なんだか禅問答のような意味不明の話になってしまいましたが、「音楽は、どこに本当にあると言えるのか?」という例の命題を考えたとき、私には上のような想念がよぎってしまう。カラヤン以前のいわば全権委任型の音楽じゃなく、オケも聴衆も一緒に音楽を作り上げようとするのが、今どきの流れではないかしらん。 だから!と言い張るわけじゃないですが、演奏家はやっぱり顔を出すべきだと思いますよ。ラトルや樫本さんの表情や身振りを観ることによって、私たちは音の紡ぎ出される瞬間に立ち会うことができる。時に苦悶の表情であったり、喜びや憂いを含んだものであっても、それはいわば「集中」がなせる業なのであって、一流アスリートたちが本番で見せる厳しい表情と一緒でしょう。私たちはそれらを「美しい」と感じるはずです。 それにしても、ベルリンフィルというのは、各楽員の表情や振りが大きいのが印象に残る。ザアとらしい歌舞伎みたいな見栄は、イヤミったらしくてゴメンですが、それぞれが集中し、なおかつ全体として驚くほどシンクロしているというのは、かつて指揮者以外、だれ一人微動だにしなかった、お堅いクラシックオーケストラの演奏を見慣れた者には、ずいぶん新鮮に映ったものでした。 樫本さんの身振りや表情は、ときに楽員に向かってではなく、なんだかもっと遠いところに向かっているようにさえ見える、「音楽のミューズよ、ここに降りて来い!」みたいな。 私が意識して「音楽を観る」ようになったのは、先にも触れた高校の時、武満徹「ノヴェンバーステップス 」の横山勝也、鶴田錦史の尺八と琵琶の協奏を聴いてからです。この曲のカデンツァ部分、さながら二人は剣士の立ち合いのごとく、命がけで音を生み出しているかのようです。横山勝也と言えば、普化尺八直流と言われる海童道祖(わだつみどうそ)のただ一人の弟子で、その求道的な姿勢には、ある意味、私たちが抱く音楽という通念を超える部分がありますね。 それもそのはず、普化宗とは鎌倉禅仏教の一派で、経典を持たず、尺八を奏することによってのみ、悟りに至ろうという教義を持つ(いわゆる虚無僧尺八)ので、尺八は楽器ではなく法具なのです。法具(仏具)であるなら、これを改変改造するなどということはあり得ない、という仕儀になるのでしょう。かの楽器が古体のままの姿を残しているというのには、しかるべき理由があったのでした。 私は鶴田錦糸と横山勝也の協奏で、武満のもう一つの邦楽曲「エクリプス(蝕)」という曲を、実演で一回だけ聴いたことがありますが、残念、この二人の演奏風景の入った動画が見当たりません。先ほど剣士の立ち回りなどと言いましたが、見ようによってはバレエのデュエットのような優雅さも、そこから感じたものでした。 横山勝也の代表的な演奏と言えば、どうしても古典本曲ということになってしまいますが、貴重な動画があったので、音も画像も今一つですが聴いてみてください。「産安 」。
2020.07.19
コメント(0)
-
エレクトーンというガラパゴス 21.
ワインヤード ところで、岩内さんの動画の中で、すっかり面食らってしまったのがありました。これまた自作自演で、「水琴の庭」という曲です。先に挙げた「セレナーデ」と似た小品なのですが、聴いていて皆さんどう思われます?画像が京都妙心寺の庭で占められていて、演奏場面が一つも出て来ない。で、聴いているうちに「これ、ホンマにエレクトーンかいな?」と思わせる響きが現れてビックリさせられる。だって弦楽器特有の雑味を帯びた擦過音まで、確かに聞こえて来るじゃないですか。 しかし、そこで首をひねらずに聴き続けていると、そのミニマルな反復に誘われるように、そんなことはどうでもいいような気がしてくる、という仕掛けになっているのです。演奏場面を隠してあるのは、要はここでは「音の響きだけを堪能してね。」という意味なのではないか。 話が飛びますが、先にインテルメッツォ101.で取り上げた「古伝 鶴の巣籠」の動画では、演奏動画と鶴の写真が交互に出て来ますが、奏者の寄田さんによると、これは「秘伝、秘儀に属する部分は、公開が許されてない」との由。まあいろいろあるのでしょうが、私はこうした秘密主義というか、日本の伝承法によくある「秘匿癖」というのは、あまり好きではありません。かといって、なんでも「見える化」というのも、政治の話じゃあるまいし、賛成はしないけれども。 岩内さんのは、もちろんそんな秘術めいた理由でそうしているのじゃなくて、「ことさらにエレクトーンを意識しないで、これは聴いてください」ということでしょう(想像ですよ)。とはいえ、インスタ映えじゃないですけど、強力な美しい画像はややもすると、かんじんの耳への集中が阻害される、ということもあるのではないか? ここ最近、とくに明らかになって来たのは、一枚の画像は、一編の音楽や原稿用紙十枚百枚の文章なんかより、はるかに優先的に人の脳髄に入り込みやすいらしい(したがって、私のこんなおしゃべりなんか、それこそケシ粒みたいなもんだ、ということになってしまうのですが、まあそれは横に置いといて)。 かつて、デカいオーディオセットと、にらめっこするような仕方でLPを聴くというのが、音楽鑑賞(!?)のスタイルだった私にとっては、こうした画像というのは雑念雑味に属するもので、はなはだ耳で「聴く」という行為をそがれるような気がするのですが、皆さんはいかが? しかし、沈思黙考して渋面顔で音楽を聴くというのも、何やら今どきふうでないというか、あんまりスタイリッシュな感じがしません。いつぞや、私はLPから急速にライブに趣向が変わって行ったという話をしましたが、その理由として「いつでもどこでも聞ける」CDより、理屈上「一回限りで、二度と再現できない(帰ってこない)」ライブのほうが、音楽の有りようとしては、その本質に近いんじゃないか?音楽が本質的に時間の芸術であるとすれば、これは当然の帰結ということになるでしょう。 しかし私は、ライブの魅力には、この「一回限り」という時間性の中に「だからこそ、しっかり見ておきたい」という願望も含まれていることに気付くのです。だからライブは、パンクのように何でもカラフルにやれ、という意味ではありません。しわぶきも身動きも原則御法度のクラシック演奏会だって、それはただたんに音楽を「聴きに行く」のじゃなくて、より積極的に「見に行く」ものなんだと思う。一回限りの演奏を「五感全体で堪能」しようとするなら、会場に行くしかないのではないか? このあたり、「音楽を聴くこと」におけるビジュアルな位置づけというのを、最初に大いに意識したのはやはりカラヤンだと思いますが、彼の場合自意識が強すぎて、誤解も生むことにもなりました。しかし彼が主導したワインヤード型の新会場ベルリンフィルハーモニーホールは、その後のクラシックオーケストラ演奏会場の一つのひな型となりましたね。このあたかもブドウ畑のように、観客がオーケストラと指揮者を取り囲む会場配置は、音楽を「聴く」から「体感する」ものとして、明確な形を与えたと言っていいでしょう。 ちょっと話に疲れました。その会場での演奏を聴いてみましょう。マーラー交響曲第五番から「アダージェット 」。
2020.07.18
コメント(0)
-
エレクトーンというガラパゴス 20.
岩内沙織 一聴して気づかれると思いますが、アナログ音の再現性という点では驚くばかりであるにしても、「で、それでどうした?」という感じがしないでもない。まあ、これがデモ用というせいもあるのでしょうが、この場合、自然音の忠実な再現性というのは、ちっとも電子楽器の魅力につながってない気がする。 このデモでちょっと取り上げられた三曲目を、岩内沙織さん の「オペラ座の怪人」と比べてみましょう。ライブ録音なので音は少し悪いですが、明らかに音楽から発出された切迫性が全然違う(余談ですがこのライブ、四年ほど前に香港のショッピングモールらしきところで行われたようですが、現今の香港情勢を考えると、暗澹たる気分に誘われます)。 しかし、これは考えてみればあたりまえの話で、演奏者の音楽に対する姿勢というのは、デモ演奏と本番の演奏では違って当然、それって何も電子楽器にかぎった話じゃなくて、あらゆる楽器と奏者について言えることじゃないですか。 ところで、この岩内沙織という人、知れば知るほどこんなブログで手軽に触れるのは恐れ多く、エレクトーン業界では知らない人はいないアーティストでいらっしゃるのですが、かといって一般にそんなに広く知られているわけではない。youtubeはおろか、おそらくネット配信が始まる以前から、活躍されて来たこの人のことは、もっと知られてしかるべし。 今どきのエレクトーンの特質を知り尽くしているであろう、この人の最大のテーマは、これまた推測ですが、まさしく「電子音の弱点の克服」ということではないかしらん。整序された乾いた電子音をいかに生身の音に引き寄せるか?この人の他の公開映像を見ていると、そういう気がして来ました。 その一つ、ご自身作曲の「セレナーデ 」を聴いてみてください。私はこの音楽を初めて聴いたとき、年甲斐もなくやたら興奮して、動画に以下のような恥ずかしいコメントをしてしまいました。―なんて蠱惑(こわく)的な音楽なのでしょう。私はこういうクラシカル・フィールなサウンドが大好きです。アコースティックな響きの代表のような弦と、オーケストラ・サウンドを擬した電子音のコラボが、こんなに自然に融け合っている音楽は聴いたことがありません。 それにしてもこんな美しい音楽が、なぜ一般に膾炙(かいしゃ)されないのか私は理解に苦しむ。まあ知ってる人は知ってるのでしょうが、少なくとも私の耳には今まで一度も入って来ませんでした。もったいないね!― このあたかもヴァイオリン協奏曲の緩徐楽章を思わせる響きは、いとも簡単に人の心を捕まえる。その大きな要因は、ロマン派音楽のイディオムとエートスを、なんの衒いもなく駆使されておられるからで、それは間違いなく、岩内さんの音楽に対する幅広い学識と、深い感性の修練の裏付けがあってのことなのです。でなければ、ややもすると「古い」とか「時代遅れ」と言われかねない技法を、「今の時代の音楽」として、このように歌わせることは出来ない。 ヴァイオリンの山本理紗さん(どんな方か知りません)は、ここを先途とばかり、アナログとしてのヴァイオリンの響きを前面に出して大熱演。対する岩内さん、そのアナログの響きに、恐ろしく神経を使ってらっしゃるのがよく分かる。カラヤンなら間違いなくもっと押し出して来るであろう、オケのフレーズも、そこはご自身の作品という余裕からか、かなり抑えておられて笑っちゃいますね。 こういうのを聴いていると、私には逆に、このすっかり古さびているであろうクラシック音楽の書法が、まだまだ侮れないというか、じつはまだ充分に渉猟され尽くしていないんじゃないか、という気さえしてきました。これに関連して、例の久石譲の音楽が浮かんで来ますが、ここでは触れません。 かといって、岩内さんの書法がどれも保守的なのかと言えば、もちろんとんでもない。かなり挑戦的な音楽もまた物にされていて、例えばおそらく代表作の一つになるだろう「Rhythm Junction~Hong Kong~ 」など、最もエレクトーンらしい快活洒脱な音楽で、見どころ聴きどころ満載。エレクトーンの特色と奏者の技量を、もっとも端的に示した音楽の一つと言って好いのではないかしらん。 この方、数年間香港に暮らしておられたことがあるそうで、東洋の金融センターとしての国際性と、文化のダイナミズムを色濃く感じさせる作品ですが、繰り返しますと現今の中国情勢を考えるとき、何やら今昔の感を押さえることが出来ません。
2020.07.16
コメント(0)
-
エレクトーンというガラパゴス 19.
波形 エレクトーンにかぎらず、なぜ電子楽器一般が乾いた無機質な音に聞こえるのか?私たちの耳は、もうそうしたサウンドに長いこと取り巻かれていて、ほとんど何とも思わなくなっているのかもしれませんが、私はやはり「本当に耳に心地よい音」というものにこだわっていきたい。 美しいメロディー、見事なハーモニー、グルーヴ感あふれるリズムというのが、電子楽器でもいくらでも可能だということを、私たちはasukaさん他の電子楽器奏者で知ったわけですが、さわさりながら、それらを発する音源そのものの質感だの量感というのが、クラシックファンとしての私だけではないと思いますが、どうしても気になるというか、潤いに乏しいのではないか、という憾みが残るのです。 昔、新幹線が走り始めたころ、案内のチャイムを、当時代表的な現代音楽の作曲家の一人とされた黛敏郎に委嘱したところが、音源が電子音であるうえに、すこぶる現代的な無調整のフレーズだったので、乗客その他から「気色悪い」という評判が立ち、すぐ別の音楽に切り変えたという話がありました。その時の黛の「私はメロディー・メーカーじゃないので」というコメントは、いかにも現代音楽家としての矜持を示していて、何となく納得させられたものですが、さて今どきの音楽シーンで同じ言葉が通用するのかどうか? この話で、今の私が面白いと思うのは、乗客その他(おそらく乗務員でしょう)の「気色悪い」という感想なのでした。電子音、無音階、無調整という、いわば20世紀現代音楽の基本ツールというのは、本質的に人間の耳朶になじまないというか、不快にさせる要素があったのではないか?早い話、テポドン発射の時に流された警報音は、何となくこれに近かったような気もする。 少し、話が逸れました。かつて、絶対分かりっこない現代音楽を、気難しい顔をして聴いていた私には、電子音とはオシロ・スコープで、きれいに整序された波形を描く音、ないしそれらの組み合わせでできた音という先入観が、大いにあったのです。実際のところ、エレクトーンにかぎらず電子楽器全般が、そうした整序されたさまざまな音の波形を加工して、いかに現実の楽器音に近づけていくかというしかたで、アプローチをしていたように思う(想像ですよ)。 結果、出来上がった音というのが、確かに言われてみれば、木管の(ような)弦楽の(ような)響きであったにしても、それよりも何よりも一聴して最初に電子音という印象が残るというのは、皮肉なことではありました。それかあらぬか、「では、いっそのこと電子音そのものを、音源の前面に押し出したほうが手っ取り早い」とばかり、富田さんや喜太郎さんがシンセサイザーを用いた音楽で一世を風靡してました(ヴァンゲリスという映画「ブレード・ランナー」の作曲者も、この後継になりますね)。 しかし、電子音そのものが新鮮に響く期間というのは、そんなに続かないのであって、街中にあふれ出れば、それらはたちまち飽きられてしまうのです。今や映画館はもちろん、テレビCMや駅中にもこの種の音響は充満しています。 肝心なことは、電子音であれアナログの自然音であれ、音楽そのものの本質的な魅力とは何か、何が人をチャームするのか、を絶えず問い直す姿勢がなければ、この種の音楽や楽器は早晩飽きられてしまうということでしょう。大事なことは、今に伝わる西洋音楽や楽器、あるい邦楽や和楽器その他には、今に残る画然とした「歴史」があるということです。 それは技術的理論的な話である以前に、ごくシンプルに「耳に心地好い」から、あるいはそうした「心地好さ」とは何か、という問い直しが絶えず行われてきたから、今に残っているということではないか。今に残り、なお私たちをチャームして止まないのには、私たちが意識している以上に、何やら厳然とした「理由」があるのだと思うのです。そうしたチャームの歴史というか、過去の人々の営みを甘く見てはいけない。 鳥の声や水のせせらぎの音は飽きないけれども、それに似せた電子音は、どれだけ近似したとしてもやはり飽きるのです。 とすれば、結局私たちの周囲には、オシロ・スコープでは包み切れない世界が、広大に横たわっているということを、もう一度知るしかないということでしょう。考えてみれば、音叉のような純音が描くきれいな波形と違って、例えば雑味満載のヴァイオリンの擦過音が描く波形など、グラフに現れた波形以上に、そこからこぼれ落ちた音のほうが、はるかに多いのではないか?測り切れない世界を、測り切れる波形で包み込もうとするのは、いかんせん、ちょっと無理筋という感じがあるのです。 で、それかあらぬか、エレクトーンはいつごろからか、その音源を電子音の加工でなく、自然音の集積加工に切り替えて、逆の発想から新しい楽器の提案を行ってきたようですね(想像ですよ)。その色合いはSTAGEA シリーズでより鮮明になってきたというか、世界中の一流ミュージシャンの音源を集積加工してパッケージしているみたい。 しかし、この手法は何もヤマハの専売特許ではなくて、ドイツあたりの電子オルガンでもやってるらしい。自然音の再現性という点では、いかにもドイツらしく、もうほとんど生のオーケストラと変わりがないという感じ。WERSIというメーカーのデモビデオらしきものを聴いてみてください。
2020.07.15
コメント(0)
-
インテルメッツォ 101.
令和の響き 多少毛色の変わった中国の話をしようとして、なんとなく予感したとおり難渋しています。こういうふうに鬱屈した時は、ネットをググって何か元気の出る話題がないかと探して回るのですが、面白いもので年に一回か二回は、顔を叩かれたように覚醒する画像や音楽に出会うものです。 それは例えば荒川静香さんであったり、826asukaさんであったりするのですが、今回は寄田真見乃(よりたまみの)さんという京都生まれの尺八奏者(またしても女性!1990生まれ)。で、これまた知る人ぞ知る、恐るべき才能を秘めた人であるようです。とはいえ、なぜか今どきの一般的なメディアにはなかなか登場しない。したがって、私の前にも長いこと現れないということになってしまいました。 これまでにも何回か話したことがありますが、私は学生時代、高校の時に聴いた武満徹の「ノヴェンバーステップス」に刺激されて、少し尺八をかじったことがあります。しかし、すぐさまそっち方面の才のなさに気づいて(要は「歌心」皆無の自身の正体に嫌気がさして)、早々に退散したのですが、洋音楽に疲れたときに、和の音を口直しのようにして聴くのは好きで、ひそかにマーラーやB・ストライザンドと並行して聴いていました。武満徹の音楽は、それほど日本人にとって音楽とは何かを問いかける力を持っていたのです。 当時、ことのほか好んで聴いていた尺八の音楽があります。松本雅夫作曲「鼎(かなえ) 」という尺八三重奏曲ですが、まあ聴いてみてください。これ、尺八三本会が1970年にリリースした、「三本の響き」というLPに入っているのですが、邦楽部の仲間と食い入るように聴いていたのを思い出します。私的には武満のいささか高踏過ぎる現代音楽としての和楽器の取り扱いに対して、もう少しカジュアルで、なおかつ尺八の音以外では考えられない音楽という意味で、「鼎」は格好の入り口なのでした(早い話、これをフリュート三本で聴いても、ちっとも面白くないでしょう)。 この音楽、今ふうの不協和音から尺八独特の音の揺らぎ(これを「ユリ」と言います。譜面を見ると、どの音をユリで奏するか、細かく指示してありました)まで、大胆に取り入れながら、一方でごくカジュアルなメロディーラインを、バロック音楽のように朗らかに聴かせていて、すこぶる面白い。これの二番煎じはごめんだけども、これと似たような方向性を持った邦楽が、もっと現れたら良いのにと思いもし、当時それを期したかのような現代邦楽なる音楽も結構書かれたのですが、残念ながら、広く人口に膾炙するには至りませんでした。 「なぜ現代邦楽なる音楽が、一般に受け入れられないのか?」という疑問は、そのまま「日本のクラシック音楽は、なぜ西欧音楽ばかりなのか?」あるいはまた、「なぜ日本には、日本を代表し世界中で普通に演奏されるような音楽がないのか?」という、このブログがずうっと問いかけている疑問に直結するのです。しかしこの大命題については、ここでは深入りしません。 ところで、この「三本会」というのは、当時を代表する尺八演奏家、青木静夫、山本邦山、横山勝也が集ったドリーム演奏団だったのですが、何しろ流派も違い、尺八や音楽に対する考え方も異なる(たぶん)うえに、名うての個性派ばかりでしたから、会としての活動は短かったような気がします。これを聴いていても、それぞれがかなり辛抱して、音色その他を合わせているところがあり、結果的に持ち味が消されるということもあったに違いない。 というわけで、LPとして後世に残されたのは、この一枚だけということになってしまいました。 さて、話が一挙に飛んで寄田さんのことなのです。ホームページによればこの人、小学三年生のころに都山流大師範三好芫山に師事し中三で師範に当第、高校に入るや琴古流大師範谷口嘉信に師事、高校二年にして史上最年少で琴古流大師範を充許、さらにそのかん、流派にとらわれず先ほどの青木静夫や横山勝也などにも指導を受けたとありますから、その才能のほどが分かるうえに、二十歳前にしてすでに尺八の学際的知識と奏法を、手中にしていたということになりますね。その後東京芸大に進み、卒業と同時にCDをリリースするといった具合で、まさに異能が大過なく見事に開花したといった経歴ですね。 ま、しかしこうした話は、826asukaさんのところでも触れたとおり、人にはそれぞれ自身の持っている才能や能力を、爆発的に開花させる時期というのが必ずあり、それがさまざまな要因でもって幸福に重なり合ったとき、とんでもない人たちが現れるということなのであって、私は、そうした人たちを、世間がなべて「天才」呼ばわりして、一言で片付けてしまう風はあまり好きではありません。 とはいえ、前置きがずいぶん長くなりました。尺八独奏曲「古伝巣籠(鶴の巣籠)」です。 古典本曲とも称される尺八独奏ないし二重奏曲などは、古来さまざまな流派によって、独自にオーソライズされ、例えばこの「鶴の巣籠」と称される曲にしても、十種類ほどあるとか。琴古流の本曲を長く聴いてきた私から見ると、これはもう全く別の曲に聴こえる。実際のところ、はなはだいわくありげな元祖「鶴の巣籠」という曲が、本当にあったのかどうか、私はあやしいと思っているのです。むしろ話は逆で、さまざま玄妙な物語をもって語られる「鶴の巣籠」という名前に引かれて、いろいろな流派が「これこそ、あの『鶴の巣籠』直系の秘伝曲」と言い始めたのではないか? この「 古伝巣籠」というのは、古典本曲の中でも、さまざまな秘伝の技法が駆使された難曲中の難曲だそうですが、面白いのは寄田さんのは、そうした演奏の難しさを不思議なほど感じさせない。 否、確かに難しい技法のパーツは山ほどあるのですが、この人の音はそうした困難をはるか超えたところから、降りかかってくるように聴こえる。私が感心したのはとくにムラ息や、フラッターなどの倍音や破裂音が入ったあとに残る、純音のピアニシモの美しさでした。尺八は五孔しかないため、運指はシンプルな孔の開閉だけでは済まなくて、半開とか三分開きとか微妙な指さばきが必要なのです。同時に歌口も弁がなくて、直に息で竹全体を響かせるため、音程も純音もはなはだ安定しない。まあ、西洋楽器に比べたら、「これが楽器?」と思えるぐらい古体な姿を成していて、むしろ先史時代からあったであろう縦笛を思わせる。 ところが日本の縦笛は、楽器そのものの改変はせずに、いわば古体のままのキツい縛りの中で、その響きをどんどん洗練させていったという感じがしますね。なぜ、そうした進化を遂げたのだろう、という話に入って行くとキリがないので、ここではしませんが、いずれにしても、雑味を生じさせる破裂音から瞬時に純音に戻すのは、なかなか厄介な楽器ではあるのです。 実際、こういう秘儀めいた技巧てんこ盛りの曲を普通の人がやると、わざとらしく嫌味な演奏に陥りがちで、聴くほうはしんどくて大変。奏者も大変でしょうが、聴く側だって「これぞ古典本曲」と持ってこられると、息が詰まりそうになる時があるのです(ホントですよ)。 寄田さんの演奏には、途中驚くほどの破裂や雑味が、何度も発出するにもかかわらず、聴いていてとても心地が良い。何回聴いても疲れないのです。それは先ほども言ったように、そのあとに続く純音の安定性にかかっているので、たいていの奏者は破裂のあとは、息も絶え絶えになってしまう。 これを聴いていると、音楽というよりは自然界の有りようを、おのずと感じてしまうのです。常に雑味にあふれ、不規則に破裂を繰り返す自然ですが、それでも結局は一様な純音に帰っていく。この陰と陽の吹き分けがとても明晰でしょう。 私はなぜか唐突に「源氏物語」を思い出してしまうのです。ほとんど動きのない眠ったような宮廷社会に、ある日勃然と破裂が発生する、しかしそれも一時、しばらくするとまた元の時間が、あたりまえのように進行していく。私はこの長い物語はいったい何を書こうとしたのか、いろいろ考えあぐねていましたが、結局のところこの読後感、つまり「時間」と「自然」としか言いようのないものを、描こうとしたのではないかと思ったりもしているのです。 話が逸れました。この「古伝巣籠」には、それとすぐ分かるメロディーラインもリズムもなく、一見さまざまな音たちのクラスター進行のみで構成されているように思え、西洋音楽に慣れた今どきの耳には、いささか面食らう部分があるかもしれません。 しかし、たいていの人はすぐに気づかれるでしょう。この音たちの生成には、西欧音楽とはまったく異なった、しかしおそろしく堅牢な構築性があることを。で、それが奈辺から来るものなのだろうと考えるとき、私たちはそれまでとまったく違った階梯に、自身が立っていることに気づくはずです。 長くなりました。それにしても、「鼎」の三人の響きが、明らかに竹林を吹き抜ける一陣の風、あるいは息吹のようなものを感じさせるのに対し、寄田さんの響きは、眼前に飛び散る水の透明なしずくのように明晰で、「今まさしく、そこで生成されつつある音」を感じさせる。和楽器や邦楽の未来は、これまでもそうであったように決して明るいものではなく、考えれば考えるほど、むしろ困難ばかり私には見えて来るのですが、それでもこうした響きが、もし令和の世を告げる響きであるならば(厳密にはこの演奏は平成ですけど、まあ、いいじゃないですか)、多少の希望は抱いて良いのかなと思ったりしたのでした。
2020.07.09
コメント(0)
-
武漢ウイルス・クライシスとフライング・プリンセス 6.
白熱教室 最初に断っておかなければなりませんが、私は「共産中国」という現在の国家権力のエートス(有りよう)について触れてみたいのであって、いわゆる「反中国人」論を始めるわけではありません。世の中には、この二つをごっちゃにして、「反中マフィア」のような中国人蔑視の議論を吐く人たちが、かなりの知識人(と称される方々)にもおられますが、そうした論は結局、相手を罵倒する以上に、自身の品格を貶めることになっているわけで、私はそうした「ウサ晴らし」的な話には汲みしたくない。 早い話、同じ中華系権力体制であっても、台湾など民主主義と個人の自由が、しっかりと機能しているわけです。かと言って、何も自由と民主主義が、万古不滅で議論の余地のない最良の国家体制、というわけではありません。他と比べてまだしもマシというレベルなのですが、少なくとも「個人の自由と、自発的な向上性を拒まない」システムということは言えるかもしれません。しかし、これは後で話します。 とはいえ、これらをしっかり峻別して話するのは、じつはなかなか厄介であり、結局「反中論」の一つと誤解されるかもしれません。というわけで、こんな話はひょっとしたら永遠に不可能なのではないか、とさえ思ってしまいますが、少なくとも一般の中国の人たちを見るかぎり、そのエートスのある部分は、そんなに我々と違ってないのだろう、と私は思いたい。 要は、顔に「面子」という建前を、宿痾のように張り付けた天安門に集う面々と、村上春樹や宮崎駿を賞玩するナイーブな若者たちとの懸隔は、ほとんど異次元の世界かと見まがうほどの開きがあるということなのです。まあこれは、何も中国に限った話ではなく、権力指向型の人種というのは、世界どこでもよく似た顔と振る舞いを見せるもので、それは一般人には恥ずかしくて、たいていマネできない種類のもの、見ようによっては吹き出しそうな面表の独裁者も、あちこちにいますよね。 それを嗤ってられないのは、そうしたある種「恥ずかしさ」を捨て去った特異的なエートスを持つ権力者と権力体制が、実効的な武器や財を携えた場合、隣国だけでなく世界は大いに迷惑する、どころか世界の破滅を招く危険性さえ持ち得てしまうということなのでしょう。今回の「武漢コロナ禍」は、以前から指摘されていた独裁政権の危険性を、はしなくも一挙に世界に知らしめる事件となってしまいました。 今現在の共産独裁中国は別として、かつて学校で世界史を習っていたころ、私はよく年表を横において教科書を読みましたが、地球上に現れたあらゆる文明の中で、「古代からずうっと途切れなく存在し続けている地域は、結局中国だけじゃないか」という事実に、目がくらむような気もし、畏敬の念さえ覚えたのを思い出します。これはもちろん私だけじゃなくて、世界史を習った多くの日本人が、抱いていた感情ではなかったか?西欧文明が日本にやってくる以前、日本人にとって世界文明とは、ほぼ中華と同義であり、日本人は中華の文物や古典によって、文明化していったのです。 その影響は、ここ最近の西欧なかでもアメリカ化した現代日本にあっても、深層のところで中華的エートスに彩られているのであって、早い話、私たちは「漢字」を使う。古代日本人は中国漢籍の文字を「真名」と呼び、ひらがなを「仮名」つまり仮の文字としました。 ところで、ちょっと前少し話題になった「サンデル教授のハーバード白熱教室」。なぜかNHKは特に熱心で、日中韓の学生たちによる「日中韓の未来を考える」なるタイトルの番組を企画し、この三国の学生たちを集めた「白熱教室」をやったことがありました(2014年)。もうすでにこの企画自体からして、ある意図が働いていると思ったものですが、実際の内容は案の定、「歴史認識」に対する日本への糾弾に終始し、日本の学生たちは一言の反駁も出来ないという、まことに奇妙な討論会だったのを記憶しています。 中韓の学生諸氏が、まことしやかに「南京虐殺」や「慰安婦」問題を取り上げて、いわば「勝ち組」の余裕で、疑いようもない日本の罪を主張するのに対し、一言の異議申し立てもしない日本の学生たちに対して、私は彼らを一様に責める気にはなれませんでした。なぜなら彼らはまさしく中韓の主張する内容でしか、学校またはメディアから歴史を学んでいないから。この二つの問題にかんしては、その事実関係について、さまざまな検証が必要とされているにも関わらず、そうした疑義が出ているということすら、彼らは少なくとも学校では知らされてこなかった。 となれば、誰も彼らの卑屈なまでの「懺悔」の姿勢を非難することは出来ないでしょう。まあそれでも、この時の日本の学生たちの一人でも、例えば「では、あなたたちは十九世紀から二十世紀前半の世界史、取り分け東アジア史を、どのように認識しているのか?」というような問いを投げかける人がいれば、まだしも救われるというか、もう少しマシな議論が成立したのでしょうが、いかんせん番組の企画自体が、反日宣伝を前提に企画されているので、仮にそうした議論があったとしても、恐らくボツになったことでしょう。 この時以来、サンデル教授に対する私の評価は大いにダウンしました。 あらかじめ設えられた「何も教えられてない日本人学生」と、中韓で正史とされる「南京」「慰安婦」問題をひっさげた学生を集めれば、議論は始まる前から決まっている。私はそういう企画をしたNHKとサンデル教授のほうが、学生たちよりはるかに罪深いと考えるのです。まあ両者とも、以前から中韓の手が入っているのだから、当たり前といえば当たり前ですが。ここに集められた学生たちは、日本という国を一方的に「貶める」ためのダシに使われたに過ぎない。 しかし、思うのですよ。村上春樹の熱狂的な愛読者や、宮崎駿のアニメを賞玩するファンが、ひょっとして数百万単位で、大陸や半島にもいるのであれば、この抜き差しならぬ他者(村上)あるいは異物(宮崎)に対して、シンプルに「共感」する柔らかな感性を持った人々が、大多数ではないにしても、間違いなく「そこにいる」ことになるわけで、となると、やはりしんどくても語り続けなければならない、ということになりますね。 さて、全く異なる切り口で中国というか、日本を除く東アジアの人たちのエートスを考えるとき、以前から気になっていたことがあります。それはひょっとして、近代文明とか近代思想あるいは西欧文明一般といったものに対して、彼らは何の思い入れもないんじゃないか、どころかあるいは、もしかするとそれに対して「恨み」こそあれ、「憧憬」のような心象などみじんも抱いたことがないのじゃないか、と思ったりもするのです。少なくとも私たち日本人に映っている「西欧」と、彼らに映っている「西欧」はかなり違った姿形をしているのではないかしらん。
2020.06.05
コメント(0)
-
インテルメッツォ 100.
卜部兼好 WHOについてさんざん悪態をついた勢いで、共産党中国なる怪物国家の話をしようとしていたら、ネットその他で、すでに山のような「中国叩き」の話題があふれていて、何やら屋上屋を重ねる話題になりかねず、少し鼻白んでいます。中国だけじゃないですが、私は出来ればマッチポンプ的な「月並み」な話は避けたい。かといって、私は中国の専門家でも何でもないので、しかるべき話をしようとすると、それなりに調べも必要となり、つい億劫になって頭の回転が滞りがちとなります。 ところで、最近日本がロックダウンなしに感染爆発を避けつつ、「緊急事態宣言」を解除したことについて、「日本モデル」のようなことが言われ、当初かなり批判的だった海外メディアも、何だか手の平返しのようにして、日本のコロナ対策に注目したり、あげくは礼賛する記事が出たりしているようですが、まだまだそういう話をするのは早い。確かに欧米に比べれば、コロナによる死者数は二桁くらい少ないけれど、何もそれは日本だけに特異的に起こった話ではないでしょう。 であるにもかかわらず、この死者数の少なさだけに話を限定して、日本人の清潔好きだの、規律だの、医療システムの先進性だのをあげつらっても、あんまり生産的な話は出て来そうにない。ここで面白いのは、なぜそういう途中経過を示しているのか、例によって日本人自身が例えば台湾だの韓国だのと比べても、その中身を自信をもって「外に向かって明晰に説明出来ない」という状態のことなのです。この手の「外には明晰に説明出来ない」けれども、なぜか結果的に世界がびっくりするような復活をしてみせるというのは、過去日本には「敗戦」だの「大震災」だので何度もありました。 しかしそれら一切合切の理由を、「日本人の特異的な精神性」みたいな話に帰してしまっては、何ら世界に資するところがないどころか、裏返しの「不気味な日本人」というイメージが張り付くことになってしまう。 というわけで、こうした世界同時多発的な災厄に際して、私たちに特異的な振る舞いというものが、果たしてあったのかどうか、ということを考えてみたくて、こんな話をしているのです。世界的な同時多発的災厄というのは、戦争とか隕石落下という事態でもなかなか考えられない。同じ災厄を全世界がほぼ同時期、同時進行で被るというこのような事態が、果たしてこれまであったのかどうか。スペイン風邪が引き合いに出されますが、災厄の同時共有という点では、この「武漢ウイルス・パンデミック」は比較になりません。 少なくとも、各国の政府、市民、医療従事者たちの振る舞いが、同時進行形で毎日伝えられるという事態は、間違いなく歴史上初めてなのです。それによって見えてくるもの、見えているものは今書き止めておかないと、おそらく半年もたたないうちに、時系列さえ判然としなくなってしまうでしょう。私たちはそうした歴史的事態に、今まさに遭遇していると言うべきでしょう。 それかあらぬか、自粛自粛で引きこもりがちで、ストレスが溜まるかと思いきや、私にかぎっては怒られるかもしれませんが、歴史に立ち会っているという高揚感がずっと続いているのです。まあ、もともとコロナ以前から、実質的な引き籠り生活を意図して長く送ってきましたから、お上から「自粛要請」が出たところで、何ら普段の生活リズムに変りがあるわけではありません。それでも、さすがにマスクと手洗いは人にも迷惑をかけるので、かなり念入りに行うようになりましたが、他府県への移動にかんしては、親の介護という不要不急でない用事にかこつけて、毎週外出しています。 世界中から飛び込んでくる衝撃のニュース映像と、実際に我が身の周辺に生じている風景の変化を、「怖いけど目撃しておきたい」という衝動は、なかなか抑え切れるものではないですね(要は「野次馬根性」丸出し)。 毎年の冬なら電車の中では必ず、咳をし鼻をすする音が聞こえたものですが、今年はそれこそしわぶき一つ聞こえず、全員固唾をのんで息をひそめている感じ。マスクをしていると、不思議と咳も止まってしまうものです。 それにしても、マスクをして分かったこととは、我が身の口臭のひどさ加減でした。まいったな、これは! 兼好法師はどうも早くから我が身の行く末を予見して、おそらく半ば意図的に、我が身を「用なき者」として早々と出家し、はなはだ優雅な隠遁生活を送ったらしいのですが、人格的にはかなり「困ったチャン」であったとしても、その生きかたは「人には迷惑をかけない」という点では結構スマートでしたね。私は「徒然草」には、ちっとも共感しないけれども、「隠遁」という言葉には惹かれる。 西行や芭蕉その他もそのクチの人たちであったとするならば、何かこう娑婆から離れて、なおかつ娑婆の出来事を眺めていたい、そうした「美学」を持った「生きざま」みたいなのが、けっこう日本には継承されているのかもしれません。私の場合はもちろんそんなにスマートでも何でもない、ケシ粒みたいな人生ではありますが。
2020.06.03
コメント(0)
-
武漢ウイルス・クライシスとフライング・プリンセス 5.
WHO この国際機関が、共産中国の傀儡組織となり果てて、かの国のプロパガンダを専一に行って来たことは、以前からも指摘され、今回も事務局長の言動をはじめとして、さんざん批判されているので、ここでは繰り返しません。ただし、これはたんに完全に取り込まれた事務局長一人の問題ではなく、WHOの上部組織全体が前事務局長時代からの十年間で、すっかり中国に「汚染」されつくした結果、招いた惨劇であるということは言っておかねばならないと思うのです。 あえて過激な「惨劇」と表現したのには、今現在分かっている事実を上げていくだけでも、それに値する虚偽の報告、役に立たない勧告、そのミスリードによって、本来救われるべき犠牲者を生み出した、という事実は否定しようがないからです。ひょっとしてこの機関は中国と並んで、世界中から医療訴訟の対象にされるかもしれませんね。 「世界保健機関」として、国家を超越して人々の健康を守るという立場からすれば、特定の国家に偏った政治的発言はあってはならないはずですが、テドロスさんの「中国はよくやっている」という驚きの声明以来、ここから発せられるコメントの類はすべて、政治臭に色濃く染められていて、私たちがまともに受け入れることを不可能にしている(ヘタに受け入れたら、それこそ命に関わる)。 かつて、天然痘を世界から根絶した栄光ある機関が、今現在はということです(そこには数多くの日本人医療従事者の、献身的な活動が含まれていました)。 しかし、これらは先代のM・チャン事務局長の時代から言われていたことなので、それほど驚くにはあたらない。むしろ私が驚きを越して、背筋が寒くなるような思いをしたのは、この本部組織に在籍する日本人メディカルオフィサーが、事務局長と同じような「中国礼賛」をぶち上げたことなのでした。ダイヤモンド・プリンセスの対策に日本が苦心しているさなかに、その方はあるテレビ番組で「今、世界は中国よりも、日本に注目している」とおっしゃってました。同様の発言は、医療専門家の講演でもされていました。 「世界中が今、心配しているのは、日本。中国はちゃんとやってくれると思う。ぜひ日本に踏ん張っていただきたい」(日本環境感染学会「緊急セミナー」2020年2月14日) 一見、日本への激励とも期待とも取れますが、当時「今でも世界が最も注目し心配すべきは、まごうことなく武漢だろう。ロックダウンされた一千万都市と、三千七百人のクルーズ船では全然ケタが違し、比較にならないんじゃないの」と、すぐに誰でも思ったのではないか? 私はただちに、これはおそらく中国の世界的な世論工作の一環なのだろうと感じました。ダイヤモンド・プリンセスの取材にやって来た欧米メディアの中にも、知らずこうした中国の世論誘導に乗せられた記者がいたでしょう。中国にとって「武漢」の惨状から目を逸らすに、これほど格好な素材はなかったのです。何度も言いますが、このころの欧米にとって「武漢ウイルス」は、アジアのどこかで流行っているいつもの騒ぎであって、それが中国であろうと日本であろうと、本音のところでは「関係ない」。要は白人が乗船しているので、これは「面白い」、高みの見物でメディア映えする素材として取り上げただけだったのです。 それにしても、そのあまりにあからさまな「中国礼賛」発言に、同席していた自民党のコロナ対策本部長が、さすがに色を成して「中国の発表する数字は、そんなに正確なんですか?」と思わず聞き返してしまうほど。それに対するこの方の冷笑的な表情を見るにつけ、呆れるというより、私はなんだか悲しくなってしまいました。平然と発言されるその態度物腰には、日本人というより中国の官憲や政治家に、時に見られる傲岸なエートスを感じてしまったからです。 この方、確か以前NHKの「プロジェクトX」でも取り上げられた著名なヒロインで、WHOのエボラや鳥インフルエンザ対策では、現地指揮官の一人として、かなり危険なミッションをこなされてきた人です。その当時の記録は今もyoutubeで見ることが出来ますが、表情態度物腰いずれを取っても、颯爽と生き生きしていて、今のこの方とはハッキリ言って「別人」に見える。ここから先は、かなりプライベートな部分になるので、気を付けなければいけませんが、いったいこの十年の間にWHOに何があったのか? テドロス事務局長に関しては、その出自から中国との関係まで事細かく、いわば権力獲得という利権と個人的欲望のために、かの国にがんじがらめにされ、完全に取り込まれた無残な姿が報道されているので、「これは無理もないわい」ということになるのですが、この日本人メディカルオフィサーに関しては、詳しい経緯は全くわからない。 ハッキリしていることは、WHOの理事会他上層部のほとんどは、M・チャン前事務局長の時代に、完全に中国に取り込まれたのだろう、ということです。で、その懐柔策はおそらく現ナマだけではない。かつて海上自衛官で中国人女性と結婚し、自殺した人がいましたが、その理由は潜水艦の機密情報をこの女に漏らしたことでした。中国の政府機関は最初からそれが目的で、この女スパイを接近させ結婚させたのです。標的をがんじがらめにして取り込むとは、このようにして硬軟取り混ぜのスパイ合戦の様相を呈するのです。 WHOの理事たちがどんな面々であるにせよ、一人一人に上のような工作と脅しを十数年かけて行って、首根っこを押さえる。理事たちの記者会見を見ていると、誰一人自分の言葉で語っている人がいない。つまりこちらに届く言葉を発する人がいない。テドロスさんの素っ頓狂な声明を、横で聞いている理事の人たちの顔には、いわば弱みを握られた「疚しさ」を隠そうとする「無表情」か、傲岸に虚勢を張った「薄笑い」しか見止められませんでした。 末端の現地指揮官や専門家たちは、それでも高い志をもって医事医療に励んでおられると思いますが、上層部がこのように腐敗し、一国の長に阿諛追従するようになってしまっては、志気の低下は免れないでしょう。 今現在たまたまWHOから距離を置いた位置にいる尾身さんや押谷さんが、まさしく高い志のまま、日本で獅子奮迅の努力をされているのと対照的ですね。 この話は何もWHOだけにかぎらない。WTOだのUNESCOだの中国が関与した国際機関は、かつての栄光は完全に換骨奪胎されて腐敗し、無残な傀儡組織になり果てています。「これが中華風の国際流儀だ」と言わんばかりに。何だかまた悲しくなって来ましたが、それでも次回は中国という怪物化した国のことを少し話してみたい。
2020.05.12
コメント(0)
-
武漢ウイルス・クライシスとフライング・プリンセス 4.
「平時」と「非常時」 日本政府は、過去にやって来た「新型インフルエンザ」だの「SARS」だの、中国由来の病原体を、なんとかうまくやり過ごしてきたせいか、多少、自国の医療体制とか検疫システムに、過信があったのかもしれない。逆に台湾や韓国やヴェトナムは、これら二つにずいぶん痛い目にあわされているので、かなり敏感に反応しましたね。彼の国々は感染症にかぎらず、常にこの巨大な隣国に脅威を感じざるを得ないので、当然それに対する準備もしている。先にも触れた「非常時」という概念に属する対応策をです。 最近になって分かってきたことですが、日本には「平時」の法律はあっても、「非常時」の法律がないというか、そもそも敗戦後日本の法体系には、「非常時」という概念がどうも存在しないらしい。「非常時」法といえば、紋切り型に戦前の「国家総動員法」のような、国民の権利を根こそぎ剥奪し、政府の権力行使を無限化する法という、きわめて論議不十分な前提が、今でもこの国にはまかり通っているのではないか。 何も「戦前に戻せ」と言っているわけじゃなくて、「平時」とは違う状況は、大地震とか戦争とかテロとか、今でも普通に起こり得るのであって、要はそうした時に発令施行されるべき法体系がない、ということなのです。これは明らかに国の形として不完全、つまり脆弱性そのものに他ならない、ということなのではないか? 今回の武漢ウイルスへの対応は、チャーター便の帰国者が最初だったと思いますが、まさしく「平時」の検疫と防疫で対処しました。当時、一般だけでなく医療の専門家の中にも、「このウイルスは風邪の新種だから、一年もたてば季節性のインフルエンザと同じように扱われるだろう」と、ずいぶん楽観的というか、強気の発言をする人がいましたね。その根拠はおそらく、中国およびWHOから流れてくる、先に触れた「感染力、毒性とも中程度」という情報から来ているかと思われますが、それにしても、同時期の武漢の映像を見たときに、多少の疑念もわかなかったのかという気がしますね(最初WHOは「この新型ウイルスは、ヒトヒト感染しない」とまで言ってましたよ)。 皮肉な言いかたをすれば、この場合の中国やWHOのいう「中程度」とは「ペストやエボラに比べたら、そんなに怖くない」という含意があったのではないか。それを丸ごと勝手に信じた、日本ほうが悪いということになってしまうのですが、さて世界中で、こうした見解をまともに受け入れていた国は、当の中国人も含めて、ほとんどなかったのじゃないか。ただ欧米諸国は、それらをまともに聞かないと同時に、やはり「SARSやMARSと同様、多分うちには来ないだろう(関係ない)」というしかたで、冷ややかに見ていたに違いない。 おかげで、手痛いしっぺ返しを食らうことになったのですが、これもまた日本とは別の仕方で油断していたのだから、「誤認したほうが悪い」ということになるのでしょうか。 日本はそれに比べれば、「平時」の体制とはいえ、よほど緊張感を持って対処していました。したがってチャーター便の帰国者からの感染拡大は、民間のホテルを借り上げたりと、かなり泥縄式だったとは言え、ほぼ無かったといっていい(このチャーター便を引き受けた、全日空は偉いと思いますよ)。 問題はダイヤモンド・プリンセスのほうが、いわばまったくの不意打ちで、日本にやって来たということでしょう。そもそも三千七百人を超える乗客乗組員を、一挙にすべて隔離する施設なんて、日本にあるはずがない(諸外国だって、あやしいもんです。したがって、隔離停泊しているダイヤモンド・プリンセスを、あたかも「打ち捨てられた船」のように触れ回る、欧米メディアの報道はおかしい)。 後からの調査で分かったことですが、船内感染の大半は横浜入港直前に発生していたのであり、入港後、個室隔離を行ったあとの感染拡大は、最少限に止まっていることが、疫学調査で分かっているらしい。「何も処置せず放置したから、感染が拡がった」という論説は、合理的根拠を欠いたフェイクだったということになります。どころか、重傷者はしかるべき専門病院に搬送して、当時として精一杯の医療を施したのではないか。地元の病床では足りず、静岡まで運んだ患者もいましたね。これはコロナ以外の重症患者を守るために、首都圏の病床を確保する必要があったからで、果たしてほかの国で、そこまでの対応をしたかどうか。 記者団に対し、「私たちは検疫の任務を行っただけ」と口惜しそうに話していた、加藤厚労相の顔が印象的でした。まさしく、「平時」での対応しか意識しようのない厚労省が、現行の法制にしたがって粛々と指揮を執ったということでしょう。 面白いのは、そうした中にあって、応援に駆け付けた自衛隊員からは、一人の感染者も出さなかった。検疫のプロである厚生省の係官や、横浜の職員から感染者が次々出たのに対し、きわめて対照的な結果となっています。テレビのインタビューに対し、「むしろ『検疫』というものに対して素人だったことが、幸いしたのではないか」と自衛隊幹部の人が語っていました。この場合の「素人」というのは、感染症や検疫のことを、まったく知らないということではもちろんなくて、「未知のウイルスであるがゆえに、より意識して徹底的に防護に努めた」という意味でしょう。 船内に乗り込んだときの検疫官他と、自衛隊員のものものしい装いの違いは、そのまま「平時」と「非常時」の意識の違いを明瞭に表していて、日本でそれを本当に理解し、そのための訓練をしているのは、自衛隊員だけだったということです。同じような話ですが、東京の自衛隊中央病院も目下、コロナ重症患者の拠点病院の一つとなっていますが、院内感染を起こしていません。 何も自衛隊礼賛をしているわけじゃなくて、しつこいようですが、「平時」と「非常時」の意識の切り替えという概念が、敗戦後日本には存在しないということなのです。早い話、「非常時」とは一定程度の「『私権』の制限」が前提されるわけですが、現在の日本でそれを普通に受け入れる人は少ないでしょう。政府側もそれを知っていて、したがって「非常事態宣言」ではなく、「緊急事態宣言」ということになる。明確な「私権の制限」ではなく、国民への「自粛」と「要請」という、はなはだ不鮮明な宣言となってしまうのです。 これって一面、国民の「民力」に一方的に寄り掛かった、際限のない「要請」に見え、施政者側の責任と覚悟という面でも、不明瞭な「宣言」ということになりますね。私は今回の全国民十万円一律給付というのは、この「非常時」にともなう「『私権の制限』に対する、国からの保証ないし支援」と考えています。しかし、今だに基本的人権絶対視の人たちには、この「私権の制限」という言葉は禁句なのでしょう。したがって、その決まり方も、途中で低所得者に制限した三十万円給付案が出てきたり、はなはだ不明瞭なプロセスとなってしまいました。
2020.05.04
コメント(0)
-
武漢ウイルス・クライシスとフライング・プリンセス 3.
スタートレック・ヴォイジャー 国際法や海洋法の間隙をつくような仕方で、横浜にやってきたダイヤモンド・プリンセス。その船籍はイギリスで所有会社はアメリカ、でその船長はイタリア人で、船員はそれこそ世界中から集めた約一千人。そして乗客もまた日本人、アメリカ人をはじめとして、五十カ国以上から約二千七百人。 ということは、乗員乗客合わせて約三千七百人が、乗組員は別としても、付き合いの薄い村サイズの人数が、未知のウイルスにさらされて、船に乗り合わせているという状況は、ちょっと私には想像しにくい。何もなければ結構で豪奢なクルーズが、いったんことが起きると極めて危険な状況に陥るという、パニック映画の定型のような景況を示しましたね。 それかあらぬか、武漢の情報が、中国当局によって厳重に封鎖されていることもあって、世界中のメディアが横浜に集まって来ました。欧米人にとっては、自国民が乗っているということもあったでしょうが、こうした絵になる状況というのは、間違いなく「メディア映え」するニュースソースだったはずです。それに加えて船内からは、乗客たちがスマホで動画を発信したりするので、虚実取り混ぜの記事が世界を飛び回ることになりましたね。 あとから考えれば、このころすでにアメリカでもヨーロッパでも、武漢ウイルスはひそかに拡がっていて、遠からず大爆発という段階に来ていたはずですが、欧米メディアは明らかに、これらをはるか地球の裏側の話として、要は自国の乗客の話も含めて、恰好の見せ物としてこれを扱っていました。 「遠いアジアの港の汚染された船に、欧米人が放置されている、日本は何をしているんだ」というシナリオは、彼らにとってはある意味、非常に居心地のいいトーンであったのではないか?私は今回のダイヤモンド・プリンセスにかんする、外国一流メディアの一連の報道ぶりを見ていて、彼らも案外いいかげんな憶測記事や煽情ネタを流すんだなと思ったものでした。 元来、武漢ウイルスの集団感染が船内に発生しているらしいので、乗客を降ろしたいと言って来たのはダイヤモンド・プリンセス側であって、であれば、厚労省は国民防護の立場で、「検疫」を前提に対処することになる。乗客乗員の「医療」を施すのは、身もフタもない言いかたをすれば、日本人乗客は別として、「放っておけない」から、いわば人道的立場で行なっているというスタンスになるのです。げんにこの時の医療負担は、さしあたって日本側、乗客乗員の食費はプリンセス側ということだったらしいですね。これって何だかヘンで、じゃあ船籍を持つイギリスや最大の乗客人数だったアメリカ他は何も負担しなくていいのか?という話になります。後になって、アメリカ大使が日本側に謝意を表したということですが、果たしてそれで済む話なのかどうか。 いずれにしても、あたかも善意を施すのが当然であるかのように、強要して回る欧米メディアのありようは、はなはだ人の心に水を差すものではありました。ついでに言うと、そうした海外の論調に敏感に反応して政府厚労省批判を繰り返した、日本のオールドメディアに至っては、ほとんど笑止の沙汰でしたね。しかし、そうした日本の論調を見ていて、ひそかに戦略的に世界の目を逸らそうとした国がありました。これは後で触れます。 それにしても、最近の大型豪華クルーズ船の姿かたち。私はその極限まで利益率を優先した、胴長で膨れ上がった船体を少しも美しいと思いません。今どき数十万トンのタンカーでも、乗員十数名というのがあたりまえの時代、よくもこんな奇怪な形の船を造ったもんだと思ったものです(日本製らしいですね)。 話は変わります。ダイヤモンド・プリンセス騒ぎですぐ思い浮かぶのは、タイタニックということになりそうですが、まああまりに語りつくされた話なので、私は別の連想をしてしまう。昔、テレビでやっていた「スタートレック・シリーズ」のヴォイジャー号のことなのです。ジェーンウェイ艦長率いる宇宙艦ヴォイジャーが、謎のビームに巻き込まれ銀河系の果てに飛ばされて、果てしない地球への帰還の旅に出るという物語でした。そこに登場する様々なキャラクターが面白く、テレビの連続シリーズということもあってか、人気の出たキャラクターは何度も使うということもあったみたいですね(私的には、後半登場したセブン・オブ・ナインがお気に入りでした)。 毎回、お決まりの異星人だの謎の知性体だのが現れて、クルーを危機に陥れるわけですが、元祖スタートレックの戦艦エンタープライズと違い、戦闘能力はそれほどでもないので、女性艦長以下さまざまな星人種族が知恵を絞って何とか切り抜けていく。とはいえ、最後に現れた知性集合体ボーグは、思いのほか強敵で、とうとう艦長本人までボーグに取り込まれてしまう。さて結末はいかに、というようなストーリーでした。 スタートレック・シリーズは、神話的要素とスペースオペラのエンターテインメントで、より万人受けに作られたスターウォーズ・シリーズに比べ、多少地味ですが本格SFの風合いを色濃く出して、今だに根強いファンがいますね。初期はカーク船長とミスター・スポックという、魅力的なキャラクターで引っ張っていましたが、特にピカード艦長率いる新スタートレック以後のシリーズは、素粒子理論やパラレル宇宙、あるいはタイムトラベルなど、最新物理学理論のテイストがふんだんに取り込まれていて、かなりのハードSFファンにも納得のいくものではなかったか? ヴォイジャー・シリーズは、その傾向がもっとも洗練された時期ということが出来、そのころすでに、いい大人だった私でも、毎回ビデオに録画して楽しみにしていました。逆に言うと、スターウォーズ・シリーズは初回の三編だけ見て、それ以後のは気恥ずかしくて見てません。 先ほど触れた最大の強敵ボーグは、まったく人智を介さず容赦なく人間界に侵入し、それを同化して巨大な知性集合体に組み込むという、ある意味自動機械に近い振舞いかたをする厄介な敵なのですが、最後はジェーンウェイ艦長の献身と、その圧倒的な自動機械の力をテコに、ヴォイジャーは一気に地球に帰還するという離れ業をやってのけます。 さて目下の武漢ウイルスという、はなはだ厄介で奇妙な振舞いかたする病原体に対して、私たちはヴォイジャーのような逆転のシナリオを描けるのかどうか?
2020.04.25
コメント(0)
-
武漢ウイルス・クライシスとフライング・プリンセス 2.
官邸 ところで、今回の武漢ウイルス・クライシスの渦中にあって、どうも安倍政権の一連の対応に危惧というか、不安を感じている方は多いのではないか? 外交安全保障と危機管理といえば、なんとなく安倍政権の得意分野という、漠然とした先入観があったのですが、今回の騒ぎにかんするかぎり、動きが鈍いというか、主導して引っ張っているという印象が薄い。どころか、チャーター便の派遣だの、中国からの入国制限だの、今回の十万円一律給付にしても、むしろ周りから(青山さんはじめ)やいやい言われて、戸惑いつつ腰を上げているという感じ。 やっていることは、決して遅いということではないと思うのですが、印象としては「鈍重」という言葉がピッタリ。安倍さんが外交で見せる、軽いフットワークと切れが感じられません。肝心なのは、国民に与える官邸の、なにやら「受け身な雰囲気」なのです。盤石の長期政権を築いてきたこの政権、かなり脇が甘い場面がいくつかあったにせよ、外からの提言をやすやすと受け入れるというようなことは、これまでついぞ無かったように思う。 不思議なのは、本来こうした緊急事態というのは、ある意味「リーダーの腕の見せどころ」みたいなところがあって、台湾とか韓国とかドイツとか、政権の立て直しに、このコロナ禍を利用して、まんまと成功した事例もあります。騒ぎの発出から、もし官邸主導で武漢ウイルス対策をやっていたら、当時話題になっていた「桜を観る会」問題など、あっという間に吹き飛んでしまったはずですが、実際はそうはならなかった。すべての対応を厚労省に「丸投げ」して、安倍さんは後ろに控えるというスタンスでしたね。なぜそういう動きになったのか、私には判然としません。 武漢で、「新型コロナウイルス」が発生しているらしいという情報は、十二月の中旬ぐらいから入っていたと思うのですが、そのころの国内の関心事は、なんといっても消費税増税にともなう景気の鈍化具合と、今では信じられない話ですが、今年のインフルエンザはどれくらい流行るのか、といった話題だったように思う(今となっては、なんだか別世界の話になってしまいましたが)。 一つには、この新型ウイルスの情報にかんして、中国側が当初それを否定し、隠し切れないとなると、「確かに発生しているが、感染力は弱い」とか「毒性は中程度で、大したことはない」など、かなり重大な偽のコメントを、しかも国際機関であるWHOを巻き込んで、流し続けたことが大きいのかもしれない。しかし、そうした中国政府や国際機関のコメントを、素直に受け入れていたように見える日本政府の対応も、ちょっと信じがたいのです。台湾や香港は、早くからというか、ほとんどのっけから、こうした中国式官製情報に疑いを持って接し、独自に準備を進めていたみたいですね。 おかげで年が明けてからも、武漢を含めた中国人観光客は、じゃじゃ漏れ状態で日本にやってきては、マスクを買い漁っていくという仕儀となりました。中国本土以外で、最初の感染者が確認されたのは、確か日本だったと思います(観光バスの運転手さんとバスガイド)。 そのころになると、武漢市内の猖獗をきわめる映像も入ってくるようになってきて、さすがにちょっと「やばいんじゃないの」という空気が出てきたのですが、それでも病院に押し寄せる群衆の阿鼻叫喚騒ぎというのは、あまりにも現実離れしていて、例によっていかにも中国式のパフォーマンスをやっている、要は「他所事」と捉えた人も多かったのではないか。 いよいよそれらが現実のものと認識されるようになったのは、おそらくチャーター便が武漢からの帰国者を乗せて飛来し、そこから感染者の発生が確認されてからでしょう。クルーズ船が横浜港にやってきたのも、確かちょうどそのころ、ひらたく言えば現実の危険が、日本の大都市圏の真ん中に鎮座するという事態となったのです。 このあたり、本当は時系列を確認して話すべきですが、私はジャーナリストじゃないので、この年末から今現在までに生起している、あまりに多くの「物語」を忘れないように記すだけに止めます。私が様変わりした京都駅に遭遇したのが、一月二十六日。そのころには中国人観光客はウソのように姿を消し、いよいよ我々も身構えざるを得ないのかな、という感じを抱いたものでした。
2020.04.22
コメント(0)
-
武漢ウイルス・クライシスとフライング・プリンセス 1.
楽しい話題を少しずつ再開しようと思っていたら、このたびの新型コロナウイルス騒ぎ。826asukaさんの話題を中心に音楽の話をもっと深掘りしようと思っていたのですが、すっかり水を差されて白けてしまいました。下書きはできているのですが、気分的にどうもUPする気になれません。 武漢ウイルスがパンデミックになって、はなはだ先行き不透明な同じ危機を、世界が同時的に共有しても、今どきの世界の政治家や首長、医療従事者あるいはそれぞれの国民のエートス(ものの捉えかた、考えかた、立ち居振る舞い)の違いがあらわになって、さまざまな教訓を与え続けていますね。 メディアではさまざまな人物(主として医療関係者)が登場して、コメントをされていますが、同じことを話すにしても、人によって何だかネガティヴな気分になるものと、ポジな方向性を感じさせる話し方があって面白かった。ああ、それにしても「コロナの女王」だの「コロナ・プリンセス」だの、皆さん、すっかりお茶の間の馴染みになってしまいましたね。 しかし、私はもちろんこれらの方面の専門家ではないので、こうした一連のコロナ・パニックの論評じゃなくて、そうしたナラティヴ(物語り方)の在りようを考えてみたいと基本的には思っているのです。national security それにしても今回の騒ぎの中で、少し話題になった言葉として「ナショナル・セキュリティーnational security 」というのがありました。国家安全保障という意味ですが、日本以外の各国で感染症対策が、生物化学兵器といった軍事的脅威への対処と同様の、国家安全保障の概念でとらえられているのに対し、日本ではそうした考えかたは希薄で、通常の保健衛生の範疇でとらえようとする傾きが強いということでした。 実際のところ、今回の新型コロナウイルスが示している挙動は、見ようによっては、きわめて生物兵器的な在りようをなしている、と言っていいのかもしれない。従来想像される強毒性の天然痘だのエボラだのといった生物兵器と異なり、むしろ強毒でないことによって、その兵器としての政治目的を、最も効果的に発揮していると言えるのではないか?早い話、戦争の最中なら敵兵士および市民を殲滅ないし無力化することが、この種の兵器の主目的になるかもしれませんが、それは同時に「やり返される脅威」に自国をさらすことを意味する結果、核兵器と同様の「使えない兵器」にならざる得ないのです。 しかし、隠密性が高く致死性が比較的低いという、不思議な特徴を持つ今回のようなウイルスは、平時に敵対国あるいは世界を撹乱し、人心をパニックに陥れ、経済社会生活を停止させるという、ある種の政治目的達成には、恐ろしく叶っているのです。今回の騒ぎを生物兵器の開発過程における事故が原因だ、とは私は思いませんが、少なくとも各国の軍事アナリストやテロリストたちは、これを今後起こり得る生物化学兵器使用の際の好個の事例として、目を皿のようにして見ているはずです。 早い話、武漢でコロナウイルス肺炎が蔓延しているという噂がたったとき、最初に中国からの渡航を全面禁止にしたのは、たしか北朝鮮だったでしょう。当時は、自国の保健衛生体制があまりに脆弱なので、仮に唯一の友好国である中国であっても、背に腹は代えられないということなのかな、とも思っていましたが、今はもう少し穿った見かたをしています。かの国はおそらく、武漢の情報が入った瞬間に、そこで起こっている事態を、かなりの確度で推定し得ただろう。なぜなら、彼らは似たような兵器の開発を、間違いなくやっているだろうからです。北朝鮮が中国と、この種の兵器の情報を共有しているとは、もちろん思いませんが、同じようなことをやっていれば、大体のことはすぐ類推できるはずだからです。 続いて同じような反応をしたのがアメリカとロシアで、これも「国家安全保障」という観点から、生物化学兵器の研究をしているのをなかば公然化しているかの国々にとってみれば、当然の処置ではありました。アメリカのCDC(疾病対策センター)がカバーする範囲というのは、驚くほど広範囲で、ある意味疾病対策に特化した戦略的高度情報機関という体をなしている。 これに対応する日本の機関は国立感染症疫学センターだと思うのですが、これは明らかに医学の専門家組織で、国家安全保障の概念で疫学を捉えている研究者はいないでしょう。むしろ自衛隊の防衛医科大の広域感染症疫学制御・研究部門や、サリン事件で活動した実働部隊としての陸上自衛隊中央特殊武器防護隊などのほうが、これに近いかもしれない。 いずれにしても、ダイヤモンド・プリンセスが横浜港にやって来たとき、それに対応するのが厚労省の防疫対策部門であったのは、日本ではごく自然な成り行きであったのですが、実際に検疫と救命が始まった時点で、national securityの概念の希薄さが露呈してしまう結果となりました。
2020.04.21
コメント(0)
-
エレクトーンというガラパゴス 18.
無機質な音 クリュイタンス、パリ音楽院Orのコンビで不思議なのは、もう一つのフランス音楽の雄ドビュッシーの録音がほとんどないということで、その理由はさっぱりわかりません。ドビュッシーがフランスはおろか、ヨーロッパの近現代音楽に与えた影響は、おそらくラベルその他よりはるかに大きく、あるいは21世紀の今日に至るも、まだそれらを吟味し得たのかどうか、私は門外漢なのでうかつなことは言えませんが、マーラーがそうであると同様に、じゅうぶんには終わっていないのではないか。クリュイタンスもいわば満を持して手を付けようとした矢先に急逝したのかもしれず、いずれにしても残念なことではありました。 彼の死後パリ音楽院Orは発展的改組として、それこそフランスの代表オケとして「パリ管弦楽団」と改称したのですが、往年の洒脱な雰囲気は失われ、一言でいえば世界のどこにでもある一流オケという感じで、何だか印象が薄くなってしまいましたね。 さて、話はなぜかここで、唐突に本題のエレクトーンに戻ってくるのです。これまで、気ままにながながとクラシックの話をしてきたというのは、エレクトーン独特のあまりに整序され、乾いた電子音を繰り返し聴いていると、無性にアコースティックなサウンドを耳が求めるのに従ったまでで、ずいぶん寄り道してしまいましたね。 826asukaさんは昨春にCD,DVDで、いよいよメジャーデビューを果たし(今春にも二枚目が出るらしい!)、半年ほどの全国ライブツアーを行いながら、ユーチューブへのUPも精力的にこなされていて、そのパワフルな活動には敬服するばかりですが、還暦をはるかに過ぎた私には、それら一つ一つを吟味していくのは明らかに手に余る。したがって例によって私は、時々の私が気になったもの、心惹かれたものについて、時節柄に関係なく少しずつ話していきたいと思っています。CDの印象についても、ぜひ話したいと思っているのですが、タイムリーにコメントをUP出来なくてごめんなさいね。まあここは、音楽時評欄でも何でもないし。 昨年中に彼女がユーチューブにUPした曲は全12曲。結果的に月平均一曲ということになりますが、その中で私のお気に入りは4曲。クィーンの「I Was Born To Love You」 と、ディズニー映画アラジンの「A Whole New World」 、そして新海誠監督の「君の名は。」と、「 Let It Go (映画『アナと雪の女王』挿入歌)」です。 私にとってクィーンというのは、もともと古いファンであることに加えて、ロックやエレキの奏法はまったくの門外漢ということで、冷静かつ公平なコメントをするのはむつかしい。一つだけ言うとすれば、エレキ特有のチョーキングやクリッピングといった奏法は、結局生きた音楽のグル―ヴ感を表現する手段として現れてきたのではないか。もともとアコースティック・ギターは、きわめて細やかな表現が可能で、数多くの愛用者がいるにもかかわらず、その絶対的な音量の小ささゆえに、クラシック音楽界では片隅に置かれているような印象がありました。今でこそ収音マイクやアンプ、スピーカーなどの発達で、電気的な増幅が可能になって、ごく普通に演奏会場に登場していますが。 エレクトリック・ギターは、そうした電気的な音の増幅過程で登場した楽器で、スピーカーとアンプのキャパが許せば、その音量はいわば無限大に拡大できる。プレスリーが席捲した50年代のアコースティックなロカビリーは、60年代に入るやたちまちエレキのロックに変身したのです。しかし電気的な迫力だけでは、どれも同じ音に聞こえてたちまち飽きられてしまう。ヴォリュームのつまみを上げ下げすれば、簡単に迫力が出せるというのは、考えてみればずいぶんシンプルな話ではありました。それにしてもJ・ヘンドリクス、R・ブラックモア、E・クラプトンといったエレキ・ギタリストの名手たちが、60年代から70年代にかけて、綺羅星のようにさまざまな試みをしていましたね。 この原曲のリード・ギターは、その後継の一人ともいえるB・メイですが、結局目指すところはみな、無機質な音源からいかに「生きたサウンド」を生み出すか、というところに収斂していくように見える。 しかし、エレキ・ギターは電気的な加工を施しているとはいえ、その音源は手指がはじく鉄弦から拾うという意味で、純粋に電子的な音とは言えない。それに比べると、エレクトーンはエレキ・ギター以上に音源は無機質なのであって、逆にその無機質な部分において、エレキ・ギターとの音質の相性はいいのでしょう。しかし、お気づきだと思いますが、それは同時に、そのまま電子楽器通有の弱点も表していると言っていいのではないか?
2020.02.03
コメント(0)
-
インテルメッツォ 99.
ボッチめし 怠惰にまかせてUPをズル休みしていたら、あっという間に半年が過ぎ、年も改まって令和二年となりました。好きでやっている事柄というのは、面白くないと続きません。ここ数年、話したい内容は以前と変わらず、次から次へと湧いてくるのですが、いざ文章化するとなると、なぜか下書きの段階で指が止まってしまうのです。そうして滓のように溜まった草稿が、パソコンの中で持て余し気味に眠っています。 間違いなく言えるのは、以前と比べて、どうも周囲の時間速度に、自身の感覚が大幅に追いつけなくなっているということでしょう。感覚的には一日が一時間に、一週間が一日に、一か月が一週間ぐらいの速度で、目の前を通り過ぎているという感じで、これは明らかに老化の始まりと言っていいのではないか?これは何も令和の世が、やたらせわしなくなった(多少はあるかもしれません)ということではなくて、私の身体の代謝速度が歳相応に遅くなっているということの現れなのです。 と、こうしていたら、大学時代の仲間から年明けに集まらないかという誘いがあり、久しぶりに会ってきました(三年ぶりかな)。そうしたら、こういう会合には、まず出てこないだろうと思っていた後輩がなぜか来ていて、勝手に興奮してしまいました。というか、年甲斐もなく彼に居丈高に振る舞ってしまった私が恥ずかしい。多少アルコールのせいもありますが、これって大学時代の私の振りだったからです。同窓会というのは、それぞれの現況はとりあえず棚上げにして、四十年以上前の序列を疑似的に再現してしまうので、こういう事態になったのでしょう。 この男、私と少し似たボヘミアンタイプで、他の同窓がすんなり社会に同期化していったのに、彼も私もそうしなかった(たぶん)。彼からは異論もあるでしょうが、おそらく長い長いモラトリアムの時間を、別々の経路で過ごしてきたのではないか。それが証拠に他の同窓が、つつがなく会社務めを果たして次々とリタイアし、歳相応の老たけた相貌を呈しているのに対し、私と彼だけは経年変化を遂げない(要は、成長してない)「悪相」を今だに放っているのです。 それほど付き合いはなかったにせよ、何となく気になっていた男が現れたとなっては、こちらとしても何やら血が騒ぐものがあるじゃないですか。 というわけで、新型ウィルス肺炎の不安があるなか、多少の緊張感とともに(要は、マスクと手袋などをして!)京都に入りました。しかるべきイベントのあと、京都駅に集まって食事会をやったのですが、意外というほどの閑散ぶりに驚いてしまいました。日曜の午後と言えば、京都駅前はどこもかしこも外国人観光客であふれているのですが、人は決して少なくないのだけれども、何となく歯が抜けたような欠落感がある。 それは一言でいえば「喧噪」の度合いがいつもと違う、一番騒がしい中国語の音声が抜け落ちているということです。言い換えれば、いつもの京都駅は中国人観光客の大群が喧噪の大半を占めていて、それはもうこのあたりの景観の一部になっていたということか。知らず私たちは、そうした光景になじんでいたということなのでしょう。 こうした欠落感は、食事会が催されたレストラン街でさらに露わになってしまいました。そのフロアを歩く人影はほとんどなく、店によっては閉まっているところもあって、俺たちは来る場所を間違えたんじゃないか、どこか田舎の場末にいるんじゃないかという気分に襲われる。とはいえ、それは逆に、予約なしの宴席が奇跡のように開ける、ということも意味していたので(というか、当日の電話予約は受け付けていないみたい、アポキャンも多いみたいしね)、世話役にとってはよかったですね。おかげでけっこう大人数の宴会が、即席で楽しく開けるということになりました。それにしても、七十近い年齢の男女の集まりというのは、見た目もそうですが、何だか滋味深い趣がありすね。一言でいえば、「お互い無事生きてこれて、良かった!」みたいな。この場にいない先輩後輩同輩の中には、病気その他で亡くなったり、行方不明の人もいるわけです。四十数年というのは、そういう重みを感じさせる時間でしょう。 私は平成の世というのは、おそらく日本史史上でも、もっとも穏やかな時代の一つではなかったかと思っているのですが、それでもみんなそれぞれ固有の苦労や努力や辛酸を経て、ここに会しているわけで、しかもその中味などいちいち声高に口外しない。言わなくったって分かってるじゃん、というスタンスで穏やかにしているのです。 時に、「自分史」なるものを記したい、あるいは喧伝したいという欲求を持つ方がいるようですが、残念ですが、そんなものに興味を持つ他人などいませんよ。「熟年」というのは、共有できるものと、絶対共有できないものの分別がつく人たちのことを言うのではないかしらん。 前にも触れましたが、阪神大震災の被災者が私の周りにいましたが、これほど近い距離にあっても、その揺れを「共有」することは絶対にできない、要は他人の体験を追体験するというのは絶対不可能だということです。これは亡父の戦争体験も同じで、「共有」は最初から閉ざされている。であるにもかかわらず、他人ができることとは何かを考えたとき、それはただただ黙って、「寄り添う」ことだけなんじゃないか。「死」は、生き物全員に必ず訪れる経験ですが、厳密に閉ざされた個人的な体験なので、あたりまえの話ですが「共有」など絶対できない。であるにもかかわらず、私たちはただただ、「寄り添う」わけでしょう。 自身の職歴をたどってみたところで、おそらく大半の人はレポート紙二枚ぐらいで、語るべきことは済んでしまう。で、それが自分史だというのでは、これはやっぱり寂し過ぎる。かといって、特段の趣味でも書き記すのかといえば、これまた自身の「物語」としては、何やら貧寒とした感じがあるじゃないですか。要は今ここにいる自分を、しかと「定位」して、令和の世の中を、ひたすら面白がっていくしかないんじゃないか。 過ぎ去った過去の断片を拾い集めても、何も出てこないけれど、そうした自分の過去を一切合財引き受けて、目の前のさまざまな事象を語り続けるほうが、どうもいいような気がするのです。 二次会の少人数になった男同士の話は面白かった。それにしても、さっきの後輩がまだいて、何やら名刺のようなものをみんなに配る。このあたりの「鼻持ちならなさ」かげんも、以前のとおりで、笑ってしまいました(悪く言ってるんじゃないですよ)。 一人が「お前のブログは、難しくて分からん」、「やっぱり、じかに会って話するのが好い」と言ったのは、言い得て妙で、何万語費やした「言葉」よりも、生身の「身体」のほうが、はるかに「面白い」ということでしょう。さて、次の邂逅は何時のことになるのやら、来年か、再来年か、十数年先か。 表題の「ボッチめし」とは、一人ご飯のことですが、よく考えてみたら、私はこの十数年他人にご飯を作ることはあっても、作ってもらったためしがない。なぜそうなったかについては、あまりに個人的なことなので話しませんが、間違いないのは自分用に作るご飯は、人のために作るご飯より、確実にまずいということです。「自立単独」主義が是とされ「自己責任」論が吹聴されるなか、人の行動原理の根っこには、そうした単純な議論ではとても包み切れない動因要素があるのではないか。 「ボッチおでん」をつつきながら、そんなことを考えました。
2020.01.31
コメント(0)
-
エレクトーンというガラパゴス 17.
A・クリュイタンス それにしてもこのクリュイタンス盤、私が手に入れた当時でも、そのLPはすでに廉価版で録音は古い、したがって演奏もカラヤンのオートバイで疾走するような、「今ふう」ではないという印象があったのですが、このyoutubeの復刻版は私の手元にあるレコードより、明らかに解像度がいいような気がする。同じ音源でありながら、アナログのレコードでは音割れはするは、高音は抜け切れないは、、低音は濁るという具合で、まあ何回も擦り切れるほど聴いたせいもありますが、各楽器ごとの鮮明さ加減は、今どきのデジタルな音色を彷彿させて、ビックリしてしまいますね。 しかし彼の十八番は、何といってもフランス音楽。手勢のパリ音楽院管弦楽団と残した数々の名盤は、比較的録音が新しかったせいか、今でも十分堪能できます。その中でもバレエ音楽《ダフニスとクロエ》は、私の中の決定版で、とくに第三部の無言劇で奏されるフリュートのソロ(46分ぐらいから)は、これぞ音楽のミューズ、パンの奏でる音かと思わせる、なんと妖しい音色であることか。 繰り返しになりますが、彼の演奏スタイルは「洒脱」さ(俗気がなく、さっぱりしていること。あかぬけしていること )と、「端正」さ(姿・形や動作などが正しくてきちんとしていること )が、ごく自然に溶け合っているという点でしょう。軽妙洒脱(軽やかでしゃれていること。俗っぽくなく、さわやかで洗練されて巧みなこと)な演奏と言えば、今どきの指揮者には、大いにしなやかで、気の利いた演奏を聴かせる人が結構いるのですが、それと曲全体の端正な佇まいを両立させるのは、なかなか厄介なのではないか。 彼の指揮はオーケストラを十分歌わせながらも、決してカジュアルなジャケット姿とはならない。そんなスタイルは古いと言われそうですが、私はむしろクラシックに対する敬意に満ちていると感じます(私自身が古くなったのかもしれません)。 そのあたり、例えばM.ラベルの「亡き王女のためのパヴァーヌ 」とか、「ボレロ 」など、教科書の第一番めに載せるべき、ごく正統的な演奏なのに、各ソリストの歌心をのびのびと引き出して、しかも何の衒いもない。その後の指揮者は、多かれ少なかれこの演奏を意識せざるを得なかったのではないか?かのカラヤンも手勢のベルリンフィルで、負けじと名演奏を披露していますが、いかんせんドイツ的秩序と、フランスの闊達な風土は異なる。五十年代六十年代のフランスは、世界の文化思潮の明らかな一つの中心で、とくに思想哲学界では名だたる英智たちが綺羅星のように世界を牽引していましたね。 クリュイタンスは、そうしたフランス的汎ヨーロッパ文化の音楽の担い手として、期待を一身に集めていたのですが、惜しむらくというか、返す返す残念でならないのは、指揮者として円熟期に入る手前、たしか六十歳ほどで癌で急逝してしまったのです。当時の日本の音楽評論家の中には「世界の医学界は音楽家に対して頭を垂れるべきである」みたいなことを叫んでいる人もいましたね。それほど一回かぎりに終わった彼とパリ音楽院オケの来日公演は、日本のクラシック界にとって衝撃だったのです。 ベートーヴェンを筆頭にドイツ的な、いわば肩肘の張った「真面目な音楽」が、それまでの日本のクラシック界の主潮だったのに対し、彼らは一瞬にして目から鱗を落とすような鮮やかな伝説的名演を残したのでした。今やそうした語り草はLPの復刻版でしか、知るよすがはなくなってしまいました。 あらでものことを言ってもしかたがないのですが、もし彼が存命でカラヤンと同じく1980年代ぐらいまで指揮していたら、世界のクラシックシーンは今とは多少変わっていたのではないか、と私など妄想してしまう。少なくともカラヤンさんは、もう少し「彼らしい」というか、自身の霊感に忠実な演奏を行ったのではないかしらん。クリュイタンスがいなくなってしまった結果、彼に比肩し得るドイツ以外の指揮者がいなくなってしまったのです。 それは彼をドイツのクラシック代表から、否応なくヨーロッパ音楽代表のような立ち位置に押し上げてしまい、聴衆もまたそれを望んだのでしょう。そうした趨勢は彼自身の指揮振りにも、多少影響を与えたのではないか?要は彼が取り上げる音楽は、そのつど汎ヨーロッパ的な精神の体現を求められたということです。で、時には彼自身の意にそぐわない音楽も、取り上げざるを得なかった場合もあったのではないかしらん。 彼らの一世代前のクラシックシーンと言えば、ドイツならご存じフルトヴェングラー、イタリアならトスカニーニ、フランスならP・モントゥーといったカリスマ的指揮者が鼎立して、それら全体が醸し出す「多様性」の花びらこそ、汎ヨーロッパ的精神の希望を形作っていたと思うのですが、クリュイタンスの死後、何となく貧寒な相貌に変わっていったような気がしたのは、私だけでしょうか。 クリュイタンスという、そろそろ忘れかけている指揮者について、まとまって話する機会はたぶんそうそうないと思うので、横道と知りつつ長話になってしまいました。
2019.08.22
コメント(0)
-
インテルメッツォ 98.
「自由」の意味 ひところ話題になった「名古屋トリエンナーレ騒動」。思ってしまうのは、全般に「自由の行使」という意味を、はき違えているのじゃないかということでした。この騒動では、「表現の自由」があたかも人間の「所与の権利」のごとく扱われ、例によってネット上の炎上や威迫によって、結果として「官憲が不当な圧力を加えた」みたいな報道が、当然至極のように流されてましたね。 しかし、さしたる検討もなく「自由を無限大に行使」しようとすれば、どういう結果を招くかという点では、いつものとおり驚くほど(あるいは情けないほど)退屈な事例となってしまいました。 「トリエンナーレ騒動」で不思議でしかたがないのは、主催である芸術監督や展示物の製作者たちは、自分たちが唱導したい「自由な表現」を行えば、それと対極の位置にあるであろう、「他者」たちの「自由な表現」(あるいは行為)も同時的に認めることになるということに、まるで意識がいっていないという点です。要は「リスクを自ら取る」気配が、はじめから感じられないということでしょう。あたかも自分たちだけが、「特権的に自由という檻に守られている」かのようなそぶりで、「表現の自由」を行使するというのは、考えてみればずいぶん滑稽な図柄じゃないですか。 この二つは厳密に「等価」であって、自身の行為に対して、一方の「自由」が制限されるのであれば、それは少し考えればすぐ分かることですが、相手方の自由を奪っているという点で、真の「自由の行使」とは言えないでしょう。 「自由の行使」には厳密に、常にそれと等価のリスクとコストが伴う。それは何も「威迫」とか「圧力」といった下世話なリスクではなくって(そんなものは「表現者」にとって、何のリスクでもありません)、自身の表現力に掛けるリスクということです。この人たちは「この表現で自身の伝えたいことを、本当に伝えられるのか?」というような、検討や葛藤をどれほど重ねたのだろうかという気がする。 真の検討や葛藤があれば、先のような馬鹿げた威迫や圧力はなかっただろうし、かりにあったとしても、それだけの身銭を切って、わが身の身体を本当に賭しての展示物であるなら、堂々とした反駁も主張もできたはずなのですが、ずいぶんあっさり引いてしまったじゃないですか(それもいかにも他人のせいであるかのような素振りで)。ということは、最初からそんなリスクは取る気などなかった、と言われてもしかたがないんじゃないか。となると、この人たちの「表現者」としての資質も、疑いを入れざるを得ないということになってしまう。モーツァルトや漱石など、文字どおり「身体を削って(身銭を切って)表現に掛けた」わけでしょう。 さしたる自己検討も行わず、ごく手軽に「表現の不自由」を表現しようとするから、こういう結果を招くのです。変な例えですが、仮に「偽の少女像」に対置するに「ベトナムの慰安婦像」、天皇の肖像を焼く写真の正面に「文さんの肖像を焼く写真」を展示したら、もう少しまともな問題定義が出来たのでは。もちろん、あっちからもこっちからも、文字どおり十字砲火を浴びたでしょうが、表現者としてはそれこそ本望じゃないですか。要はこの程度の「表現」には、このレベルの反発しか返ってこなかったということです。 真の「自由の行使」には、常にその行使のレベルに対応したリスクとコストが掛かる。そんなこと青山さんの在りようを見ていれば、すぐ分かることです。「ほかの何者からも独立した、真に自由な立場と言説を確保する」、つまり真に「自由」であるために、どれだけ危険と身銭を切らねばならないか、ということをです。 しかし、だからこそ意見や世界観に若干相違があるような私のような人間にも、この人の声は確かに届く、これって大事なことじゃないですか。 肝心なのは、日本では相応のリスクとコストを、「わが身が引き受ける覚悟」があるのであれば、それこそ何をやっても自由の国だということであって、そうでない国は世界中にごまんとあるということでしょう。それを当然の権利のごとく、手軽に持ち出すのは(ネットの書き込み欄じゃあるまいし)止めてもらいたいというか、もうちょっと頭を冷やしてよく考えてみたらいかが?
2019.08.21
コメント(0)
-
エレクトーンというガラパゴス 16.
ドメスティックな「私」 「未完成」の冒頭に現れる、有名な低音のモティーフは第一主題ではなく、この曲の主調がB Minor(ロ短調)とあるとおり、曲全体の厳粛な気分を予告するもので、展開部ではこのモティーフが大きく扱われてますね。しかしこうした重厚な響きを、直截に彼の人生的な深刻さと捉えるのは早計で、素顔の彼はウィーンの街で数多くの友人の助けを借りながら、若者らしいボヘミアン生活を送っていたのです。 とすれば、ここに表現された深刻な気分というのは、たぶん彼が畏敬してやまなかったベートーヴェンのような、堂々たる交響楽を志向したからではないか?となると、この第一楽章、あまりガッチリ演奏されると、かえって生身の彼らしくなくなるという仕儀になります。クリュイタンスの演奏は、そのあたりじゅうぶんしなやかに、むしろ若者の哀感を感じさせる歌わせ方をしていて、私は好きです。 それにしても、ベートーヴェンと並んでロマン派の創始とされるシューベルト。じつは形式的には、ごく古典的な枠組みを守っていて、決して革新的とはいえない。むしろベートーヴェンのほうが形式については、はるかに挑戦的だったでしょう(何しろ、交響曲に合唱をくっつけたりしたのですから)?であるにもかかわらず、私たちは彼の音楽に溢れるばかりの感情の表出を感じる。この曲は二十五歳ごろに書かれているのです。 そうした気分は「未完成」の第二楽章に至って、より鮮明になって来ますね。 第一主題の憧憬に満ちたモティーフと、何やら不安を感じさせる第二主題の対照が見事で、こうした未来への希望と不安、繊細で移ろいやすい気分というのは、芸術的な青春そのものの音楽と言っていいでしょう。とくに第二主題の主旋律に伴走する弦の響き(2分20秒あたりからと、再現部8分5秒くらいから)は、コードを複雑に変えながら進行させていて、微妙な気分の揺らぎを表して余りあるでしょう。 しかし、ここまで細やかな表現をしてしまうと、壮大な四楽章編成の交響楽を維持するのは難しかったのではないか。ご存じのとおり、彼は歌曲の名手として名を残したのです。そうしたドメスティックな「私」を表現するのに、歌曲はちょうど良い形態だったのでしょう。 私、思うのですよ。自身の移ろいゆく気持ちを、このように微細に表した響きというのは、確かにそれまでの交響楽にはなかったので、こうした「私」の率直な吐露こそ、ロマン派の精神と言われ、ブルックナーやマーラーに(時に、しどけないほどの仕方で)継承されていったのではないかと。 ベートーヴェンは確かに従来の古典的枠組みを大々的に壊して、「私」を堂々と主張したけど、このような仕方での自己表明はしなかった。このあたり彼はどこまでも「意志」の人で、その響きはさながら国会演説のように、常に「外向き」に発せられた「私」の表明なのです。ベートーヴェンが「内向き」な響きを見せ始めるのは、晩年のピアノソナタや弦楽四重奏あたりからではないかしらん。 おしまいにもう一つ、先の話とようやく結びついて来るのですが、この第二楽章、じつは展開部のないソナタ形式で、第一第二主題の提示とその再現という、あたかも長大な二部形式のようになっているということです。で、それを繋ぐ経過部(4分30秒から5分44秒くらい)は、一分ほどと短いですが第一主題を基調として、とてつもなく美しい響きを聴かせる。まさしくブリッジパッセージの華と言っていい瞬間なのではないかしらん。 ここを聴いていると、またまたシューベルトが歌曲の神様であったことを思い起こさずにいられません。歌曲は先の「天使のくれた奇跡」が、まさしくそうであったように、一連のまとまったフレーズに歌詞を一番二番と重ねていく楽曲形式でしょう。シューベルトのフレーズは(この場合は二つですが)、その提示部だけでじゅうぶん自足していて、これ以上展開のしようがないというか、ここに展開部が入ったら冗長になって、この第二楽章のあえかな印象が、あるいは不鮮明になったかもしれない。彼はそれをやめて簡潔な経過句にすることで、全体の気分が淀まないようにしたのでしょう。これってやっぱり自家薬籠中の歌曲の手法から来たのではないか(異論はあるでしょうが)。 この曲は昔から、未完の名曲ということで「果たして、この一二楽章だけで、楽曲として完結していると言えるか」といった議論が、延々と続けられていました。現に彼自身が三楽章のスケッチも残していて、構想としては全四楽章の壮大な交響曲を目指したらしいのですが、結局のところ途中放棄したらしいというか、この人、わりと途中で中断して別の楽曲に取り掛かるということの多かった人でした。 「完結しているか」と言われれば、もちろん完結していない、だから「未完成」ということになるのですが、シューベルトはあるいは「この曲に盛ろうとした歌心は、もうこれで充分」としたのではないか?今でも指揮者によっては、「未完」の作品としての印象を強調して、この第二楽章を案外あっさりと済ますケースもあるのですが、クリュイタンスの場合はそうしない。コーダのところ、あり得ないほど長く伸ばして、「ここまでで完全に自足している、これで充分だよ」と、聴く者に暗示をかけているかのようなエンディングになってますね。
2019.07.05
コメント(0)
-
エレクトーンというガラパゴス 15.
音楽のプロトコル 一つのまとまったフレーズに、ごくシンプルに歌詞だけを取り換えて、童謡や民謡(「赤とんぼ」みたいな)のように繰り返し奏するしかたを、仮に西欧楽理式に解析するとすれば、一部形式AA´またはAB(A´はAの終止形、BはAとは別の終止形)ということになります。 ならば、同じ反復の単調さに飽き足らず、途中にある変化を加えたとするなら、それは「二部形式」ということになるでしょう。分かりやすい例として、「荒城の月」のようなAA´BA´という典型がありますね。 この「荒城の月」の絵に画いたような二部形式とは、「主題の提示」「主題 の終止」「展開」「主題 の終止の再現」と言い替えることも出来ます。しかしこれってよく見ると、もうすでに「提示部」「展開部」「再現部」という、ソナタの基本形の三部形式を予感させるじゃないですか。 西欧クラシックを考えるうえで、一つの完成形である「ソナタ形式」というのは、この「提示部」の主題を二つにし、「展開部」もそれにともなって大規模化させたうえに、前後に序奏とコーダもくっつけたものとみるべきで、ご存じのとおり、それらはバッハやヘンデルといった諸形式乱立のバロック時代の後、ハイドン、モーツァルトの頃に完成し、宮廷やオペラ劇場で大いにもてはやされたのでした。 私、思うのですが、なぜこの形式が、いわゆる古典派時代に多用されたのかを考えるとき、おそらく当時の聴衆には、それがいちばん聴き心地が良かったからなのだろう、という気がするのです。レコードもDVDもない時代、それは一回で聴き取れる、分かりやすい楽曲形式だったのではないか? ハイドンは百曲以上、モーツァルトでも四十一曲の交響曲を残し、さらには同じ形式でオペラの序曲なども書いていたわけで、しかも作曲家は彼ら以外にも大勢いたことを考えるなら、一回こっきりで二度と演奏されることのない楽曲も多々あったでしょう。してみれば、一聴にして聴く者の耳を捉える、要は「収まりのいい形式」として愛用されたのではないか。さながら音楽の量産形式が出来たようなものですね。 それにしてもここまで、しんきくさい話をして来て思うのは、他の人にも分かるような仕方で、音楽の話をしていこうとすると、当の私がずうっとそうであるように、結局また西欧語法に従うしかないということです。考えてみれば、ト音記号も五線譜も全部西欧音楽のプロトコル(手順書)。今や世界中の音楽がほぼすべて、西欧語法によってしか語れないというのは、英語があたかも万国共通語のような形で蔓延している現況よりも、はるかに恐るべき事態かもしれない。なぜなら音楽は直截無意識のうちに、五感に入り込んでくるからです。 音楽教育がそのプロトコル(手順書)の指南にあったと考えてみれば、それが全然面白くなかったのは当たり前で、英語教育のプロトコル指南と一緒だったからということでしょうか? とはいえ、問答無用に西欧の楽理楽典を、あたりまえのように振り回すより、先に触れたような「歌唱の始まり」のようなものを意識していれば、あるいはもう少し生産的な話が出来るのではないか?というか、自分の話し方も、話している当の音楽自体も「相対化」して、見つめることが出来るかもしれない、という淡い期待があるので、こんな話をしているのです。 さて、「音楽を楽しむ」という話からはほど遠く、昔習った悪夢のような音楽教育さながらの(今は知りません)、小難しい議論にはなはだ疲れたので、ちょっと一服してシューベルトの交響曲第八番「未完成」の第一楽章を聴いてみたいのです。六十年ほど前(!)の録音と古いですが、私はA・クリュイタンス指揮ベルリンフィルのが好きです。 これ、以前にも取り上げたかもしれませんが、クリュイタンスはベルギー出身でもっぱらパリで活動していたせいか、フランス的な洒脱な側面とドイツ的な謹厳性が、不思議なほど調和していて、この「未完成」も本場独墺の指揮者とは、かなり違ったテイストを感じます。テンポはあきれるほど悠揚として迫らず、歌わせるところは思い切り歌わせながら、絞めるところはガッチリ絞めるという絶妙のバランスですね。重厚そのもののベームさん、ドラマティックな演出優先のカラヤンさんと比べると、何だか「近しい」というか、「心にこめがたくて、言ひおき」はじめざるを得なかった作曲家の、こぼれるような「歌心」を再生させている。 で、その味は荘厳なドイツ系の指揮より、親しみやすい生身のシューベルトを、結果的に感じさせるということに、私の場合にはなってしまうのです。 まあこの感想には「シューベルトの味は、そんなものではない(彼はウィーン子であって、断じてパリっ子ではない)」とばかり、さまざま異論もあるのでしょうが、ベルリンフィルもフルトヴェングラーやカラヤンのような絶対的帝王の時とは、かなり異なるクリュイタンスの在りように刺激されたか、ずいぶんしなやかな演奏をしているじゃないですか。同時期に録音された「田園 」や「英雄 」も、とくに弱音の取り扱いが出色で、私の懐かしいライブラリーの一つです。 余談ですが、子供のころ初めて「未完成」の第一主題を聴いたとき、楽器の種類が分からず大いに首をひねったことを思い出します。それがクラリネットとオーボエの重奏で紡ぎ出されている音色であることを知ったのはずうっと後のことで、ハーモニーというのが主旋律と伴奏などという単純なものでなく、さまざまな楽器群の「混ぜ合わせ全体の響き」を指すのだと勝手に合点したものでした。
2019.07.03
コメント(0)
全1266件 (1266件中 1-50件目)