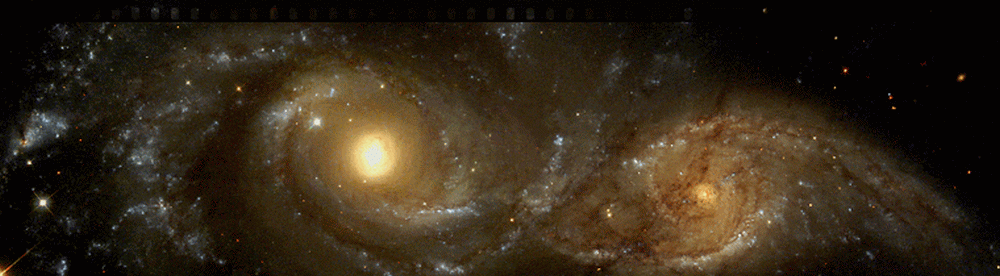全140件 (140件中 1-50件目)
-
中心と調和 その1
左の足を踏みしめる。動かない。だから右の足が踏み出せる。静が動を生かしている。光は闇の中で冴える。昼の行燈は役にたたぬ。死ぬんだ。こう思って生きることに必死なる。死ぬ自覚が生きることの尊さを教える。世の中は相反するものの生かしあいである。
2012.09.23
-
平和の意味 その2
肉体の中心は目である。目が覚めない時、からだの平均も自由も失われる。居眠りする。目の力がぬける。絵も字もかけぬ。爪楊枝さえも持てぬ。目は心の窓である。人間の全体の中心は心である。心が勇めばからだの疲れが消える。宇宙の中心は神である。中心に副え。これが天地の教える秩序の道である。
2012.09.22
-
平和の意味 その1
われわれは平和な生活が欲しい。だれでも安らかな社会を願っている。それなら本当の「平和」というのは、どんな姿であろうか。「平均のとれた調和」これが、平和であるまいか。平均がとれる。釣り合いがとれる。釣り合いがとれたら、見事に調和が保たれる。見ても気持ちがよい。これが平和の姿ではあるまいか。まず「平均をとる」こと。これが平和への第一歩である。平均がとれる。釣り合いがとれる。それは中心が定まっている時の姿である。物の中心をみつけてそれを守る。それが「平均と平和と安定」の許される道である。
2012.09.21
-
中心を守る生き方 その3
私は三十七歳の春、2度の大喀血をやった。その時、第三回目の大喀血をやったら死にますよ、といわれた。ちょうど綱渡りのような危ない前途であると思った。よし。自分を守ることをやめる修行だ。自分は自分を忘れて、中心に近づこう。こう考えた。自分を空にすることをつとめた。たのしく本を読む。たのしく人の話を聞く。感心して我を忘れる。なるほど。なるほど。なるほどと感心していく。人を感心させることよりも、自分の方が感心することの上手な人になる。これをつとめてきた。それから気楽になった。疲れが少なくなった。人生に疲れのない生き方とは、これだなあと思っている。
2012.09.19
-
中心を守る生き方 その2
サーカスの綱渡りをする人は、自分のからだの方をみない。自分を忘れているようである。忘れているわれが守られている。この生活が中心を保つ生活である。すべてがちょうどうまく調和する生活である。
2012.09.16
-
中心を守る生き方 その1
なるほど。ウム。そうだ。と感心する。人の話にとけ込む。相手に共鳴する。そんなとき、自分は空になっている。自分を空にするとき、不思議に疲れは出て来ない。
2012.09.15
-
危ない前途 別冊中心1 真理を求めて より
春夏秋冬、四季は移る。変化する。流転する。これは世の姿である。人の世は無常。はかないといわれる。浮世と言う言葉もある。たしかにそうも言える。船が沈む。電車が焼ける。汽車が転覆する。自動車が衝突する。新聞記事の種は尽きない。まったく危ない前途である。浮世を渡る人の一生は、サーカスの綱渡りにも似ている。一調子、狂えば落ちる。ちょうどよかった。うまくいった。まったく幸運だ。こおどりして喜ぶ。この喜びが度重ねれば、富もできる。よき地位にものぼる。世にも出ることにもなる。あっ危ない!しまった!残念だ!まったく運が悪い。こんなことがたび重なったらもうだめだ。失敗する。亡びる。すべて調子よく運ぶ人がある。それと反対に何でもチグハグになる人がある。それはどこからわかれるのであろうか。中心を誤るか、否かできまる。
2012.03.03
-
包まれて 別冊中心1 真理を求めて より
舟に乗る。舟より大きい人は無い。海に浮かぶ。海より大きい舟はない。空より大きい海もない。空が荒れる。嵐が起こる。その時、海はいやでも荒れる他は無い。海が荒れる。航海の舟は揺れる。舟がゆれれば、旅人は苦しむ。人間は包まれた環境によって支配される。われわれは、この天地の間に生まれた。だから天地の大道に支配されて、生きるほかはない。天地の大道は中心を守ることを教えている。地球も人間も天体運行の秩序に抱かれている。太陽系の運動は、太陽を中心として秩序を守ってきた。レールもないのに同じ所を走っている。永遠に休むことなき流転の道をつづけている。(中略)中心が守られるところに、平和が与えられる。これが天地の大道である。
2012.03.02
-
自分をみがく 別冊中心1 真理を求めて より
どんなに美しい目でも、鼻でも、人のものならあきらめる。奪い合いはおこらない。他人に譲られないもの。盗られないもの。その人だけにしか役立たないもの、それを大切に。立派なものにする。人格を磨く。徳分を育てる。心を美しくする。それは持ち主の責任である。その為には、与え主の心にそって毎日努力する。修行するほかはない。徳を積む。心を磨く。心身を鍛える。これはどんなに勤めても善い。すべては自分のものになる。それは他人に盗られず、また迷惑をかけないで増やせる。豊かに出来る事である。自分が立派になれば、他人の尊敬と信頼と親しみが集まってくる。よく人から損をさせられて、怒っている人がある。それは身につかぬもの、特につりあわぬものをを持っていたのだと考える。取られたり、損をしたりする。それでこそ、いままでもっていた不徳が1つ1つ削られていくのではあるまいか。不徳が削られたら、次のよき運命が輝き出る。
2012.02.27
-
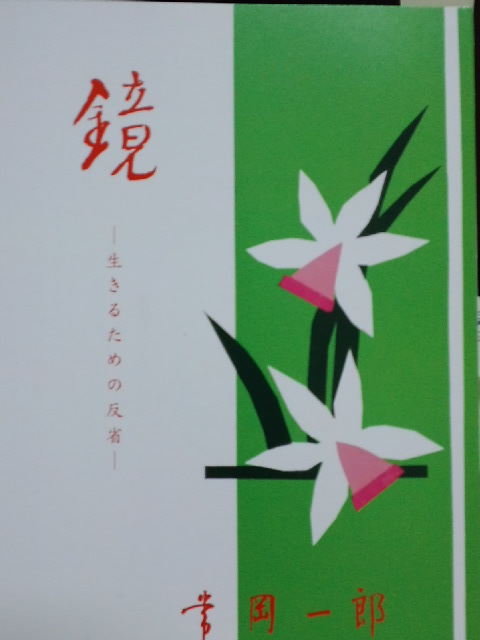
再刊情報 鏡ー生きるための反省ー
常岡先生の 鏡ー生きるための反省ー が再刊されました。 購入希望の方は下記,中心大学のホームページを参照ください。 http://homepage2.nifty.com/chushin/Library.htm 一部抜粋 目を開ければすぐ見える。それは人の顔である。自分の顔は自分の目で直接みることはできない。だから鏡に映す。そうして間接に見るほかは無い。映ったものを間接に知る。これが自分である。 自分の心、自分の魂、自分の不徳、心のゆがみ、未熟、こり、頑固さ、これは自分ではなかなかわからない。だからそれを映す鏡がいる。 (中略) また、運命や環境となって映される。見るもの聞くものすべての中に自分自身が映し出されている。そこで一切の出来事を見つめて自分を見つけ出す。色々なことを聞いてその中に自分の本体を知る。そこに人間として育つ道が生まれる。
2012.02.25
-
形見分け 別冊中心1 真理を求めて より
形見分けできるものと、出来ないものとがる。時計や、着物や、指輪は、形見分けができる。もらっても役にたつからである。ずいぶん立派な鼻の人がある。その人が死ぬ。その鼻を「形見に」と願う人はない。すぐれた頭脳でも形見にならぬ。それはもらっても役にたたぬからである。よく洋服や靴をぬすまれる人がある。ものが少ない時は何でも役に立つ。すこしくらい身体にあわなくても、辛抱する人がある。だから盗んで売る人も出てくる。もしも人の生命やからだが盗んだ人の役にたつものなら、大変であろう。汽車に乗って、安心して眠ることもできないことになる。われわれは安心して汽車で眠る。それはからだも、生命も、運命も、盗む人がないからである。それはその人だけに特別に与えられたものだからである。他人には間に合わないからである。
2012.02.23
-
本当に愛するなら 別冊中心1 真理を求めて より
馬は世界中に子孫がひろがっている。鹿は奈良の宮古の春の日を悠々と歩いている。広いくらし。安らかな日々。これは自らの力ではない。他の力に守られた安らかさである。親しまれる鹿。感謝される馬。馬は自分で馬小屋は建てない。嵐の吹く日、家を守る。その場合、家の外からささえる棒もある。内からつっぱる棒もある。内からささえる棒は雨戸やガラス戸を守ることは出来る。しかし、家そのものを守る力はない。外からささえる力こそ家を本当に安らかに守る。自分を自分で守ることは、本当の守りにならぬ。他人から尊敬される。感謝される。親しまれる。他人にささえられる。これが本当の安らかな守りと成る。(以下略)
2012.02.22
-
生活の本義 別冊中心1 真理を求めて より
何も食べない前から、人間は生きている。まず生まれる。生きている。だからお乳を呑みだした。ものも食べはじめた。これが順序だ。人間は「生かされて活きてきた」ものと思う。生きることを許す力がこの世にみちあふれている。生活。こういえばすぐ「食べること」を連想する。食べることが生活だと思いやすい。しかし「生活」ということは、生かされて活きている、だからお互いに活かしあって生きよう。生かすものが活かされるのだ。こうかんがえるべきではあるまいか。生かしあいが、生活の本当の意味ではあるまいか。(以下略)
2012.02.21
-
むこう向きの顔 別冊中心1 真理を求めて より
自分の顔を自分で見た人はいない。鏡に映した影はみたことがある。自分で本物の自分の顔は見たことがない。自分の顔は毎日他人に見てもらっている。どんな顔でも「むこう向き」に出来ている。自分の方をむいている顔はひとつもない。しかもその顔は自分のものであって、実は自分の知らない間にできている。この「むこう向きの顔」。自分の方は見なくても良い設計。これは何を教えているのであろうか。自分中心の考え方。利己的生活。その誤りを教えているのではあるまいか。自分のことと下り坂は急がぬものはないといわれている。自己本位の考え方は人間生活の調和を破る。美しく化粧する。口紅をつける。にこやかに笑顔する。これはすべて自分がみるためではない。相接する人に見てもらう。相手に不快を与えないためである。他人を大切に見守ってあげる。これが人間の顔にふさわしい生き方ではあるまいか。
2012.02.20
-
シッカリとウッカリ 別冊中心1 真理を求めて より
たしかに人はシッカリ守られて、ウッカリ生まれた。だから人の一生は、ウッカリとシッカリとを見事に調和させるべきではあるまいか。またこれを調和させることこそ正しい生き方ではあるまいか。畑を耕す。種をまく。肥を与える。これを農夫がシッカリやる。やがてその種が芽生える。葉が出る。花がさく。実がみのる。それは人間の力ではない。じっと見ている他は無い。ウッカリしていても良い分野ではあるまいか。昼はシッカリ働く。夜はウッカリ眠る。夜中までシッカリ勉強したら、朝になって、ついウッカリすることがある。前をシッカリ見ている時は後ろは見えない。何から何まで、全部、シッカリする必要は無い。半分はシッカリする。半分はウッカリして良い。むしろウッカリすることが大切である。結局、自分を投げ出す。全身全霊をささげつくす。その点をシッカリつとめる。自分を守ることはウッカリする。天命に安ずる。それが人生の正しい生き方だと思う。
2012.02.19
-
ウッカリ生まれた 別冊中心1 真理を求めて より
すべての人はウッカリ生まれている。シッカリ生まれた人は一人もない。人間は大切なことを、何もきめないで生まれてきた。だから人間は『ウッカリ』から始まっているともいえる。何にも願わず。考えず。求めず。無心で生まれている。自分の親を誰にするか。生まれ故郷はどこにするか。顔の長さ、鼻の高さ、目の大きさ、足の長さ。こんなことは一生の大切なことである。それだのに何にも決められないでうまれてきた。たしかにウッカリから始まったといえる。なぜ人間はウッカリして生まれてきたか。それはシッカリ守って貰っているからである。シッカリ守られて、ウッカリ生まれた。これが人間の姿である。このことはちょうど人間の親子関係に似ている。幼児はウッカリしていても育つ。これは親がシッカリ守っているからである。人間はウッカリ生まれた。大自然の御親のめぐみに、シッカリ守られているために。
2012.02.18
-
苦心 工夫ありて 別冊中心1 真理を求めて より
住み心地のよい家。便利な設計。そこには人知れぬ苦心がこめられているはずである。工夫がこらされている。親切がにじみ出ている。この工夫。その苦心。あふれる親切。それは目に見ることは出来ない。しかし、これが根元となっている。これがあってのちに、姿が組み立てられている。無形が元である。人間のからだは全くよく組み立てられている。口の上に鼻がある。鼻の上の方に目がおいてある。だから香りをたのしみながら、酒が飲める。飲みながらコップの底までよく見える。匂いながら、ながめながら、呑める。大自然の親切である。砂漠に咲くサボテンの美しい花。色とりどり、味とりどりの果物。何という行き届いたこの世のめぐみであろう。われわれは頼みもしなかったのに、めぐまれている。このめぐみに包まれて、天地の限りなき親切を身にしみて感じる。この大自然の御親のめぐみを神の摂理と呼び、御仏の慈悲とたたえる。名前のつけ方はどうでもよい。要は人の力を超えた守りがこの世にみちあふれている。
2012.02.17
-
からだの重さ 別冊中心1 真理を求めて より
横綱、※照国のからだ。42貫(註、1貫 = 3.75キログラム)。2表半の重さである。かつて私は照国と夕食を共にした事がある。食事を終えて、2人とも立ちあがった。たわむれに照国のからだをかかえてみた。その重さに驚いた。私の力では1分ももちあげられない。やがて玄関に行く。にこやかに笑いつつ歩く。照国が自ら運べば、42貫のからだも軽い。わけなく運ぶ。無造作に歩く。一体これはどうしてであろうか。何のためであろうかと考えてみた。自分で持ったら、その重さを感じる。子供をかかえてもそうだ。重いと思う。しかし、その子を人の腕に渡す。他人に持ってもらう。そうすれば子供の重さは感じられない。すべての人間は、自分のからだの重さを少しも感じないで歩いて行く。それは、自分で持っていないからである。抱えてもらって、自分が使うだけだから軽い。それでは、誰が持っていてくれるのであろうか。ここにも無限の恵みを感ずる。※照國 萬藏(てるくに まんぞう、1919年1月10日 - 1977年3月20日)は、大相撲の第38代横綱。(ウィキペディアより引用)
2012.02.13
-
物ではない 別冊中心1 真理を求めて より
(前略)冬の寒い日、鴨緑河の流れも凍る。その上でスケートをする。その人々は、わずか36度の体温である。それが二時間もすべっている。しかし、一度の体温も下がらない。鉄瓶の熱湯なら、二時間ですっかり冷えているだろう。これと反対に、熱い風呂に入る。からだはエビのように紅くなる。汗だくだくで飛び出す。しかし、36度の体温が39度にあがったということがない。うすい皮膚一枚の中は、外から体温の増減ができない。神の支配する領分である。からだは単なる物質ではない。無限のめぐみに守られた天の賜物である。物の法則にくくられた死物ではない。いのちあふれるもの。天地の御親の慈悲の表現されたものといえる。靴の皮は厚い。鉄の鋲まで打ってある。それでも毎日使えば減る。破れる。足の皮は八十年たっても修繕がいらぬ。使っても減らず、使うほど強くなる。タコまでできる。人間の体は単なる品物ではない。
2012.02.12
-
人の力を超えるもの 別冊中心1 真理を求めて より
石炭を掘り出すのは坑夫である。その石炭を作って大地に埋める。これは坑夫の智慧ではない。人間のハカライではない。自然のたまものである。畑を耕す。大根の種をまく。肥をやる。これは農夫の仕事である。しかし、緑の葉を出す。白い大根を設計する。その味をつける。これは農夫の智慧ではない。真理を悟る。見つけ出す。そうして新しい発見をする。これは学者の役割である。しかし、真理そのものを『作る』のは学者ではない。自然が定めたものである。学問はその真理を見つけ出すのである。(中略)この世の中には人間の智慧や力をこえたものがある。宇宙の根と成るものがる。
2012.02.12
-
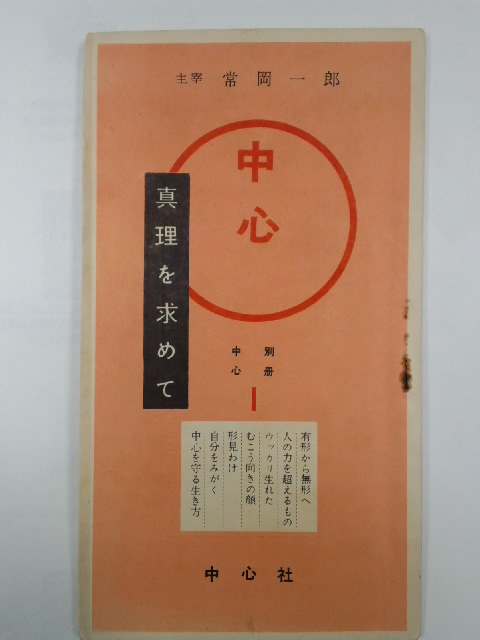
有形から無形へ 別冊中心1 真理を求めて より
別冊中心1 真理を求めて(昭和30年7月1日発行)時は移る。流れる。そうして歴史を作る。しかも時の流れは目に見えない。姿なき時の流れを時計で読む。小さい針の動きで悟る。そこに有形と無形がつながる。大海原を旅する舟人。たよりにする羅針盤。あの小さい針の動きが、広大なる南北の方向を教える。ここにも形あるものに導かれて、姿なき方向が悟られる。見る。読む。悟る。新しく発見する。これで文明が進む。今の世は物理の上では驚くほど進んだ。原子力時代にまでなった。世の中は一変しようとしている。物の面のみでよいか。心の理法はどうか。天地の声を聞く道はおくれていないか。こう反省する。このままでは人の世の調和は崩れる。天の理法。運命の法則。心の道。これも並んで拓かれねばならぬ。
2012.02.11
-
心が運命をかえる その4
無常と常、変化と不変不動、有形の出来ごとと無形の法則、これが見事に組み合わされている。これが世の中である。だから、現在をみれば次の運命はわかってくるはずである。
2012.02.10
-
心が運命をかえる その3
運命といえば、すぐ易者を思い出す。誰でも明日のことはわからない。しかし、その明日はきっとやってくる。さけられない。その明日が前にはわからないから不安もわく。わからぬことがわかりたい。そこに迷いもおこる。易は陰陽学ともいわれる。陰陽の変化を教える。移り変わることが易である。時も流れる。太陽も地球も動く。爪も伸びる。毛も伸びる。皮膚もかわる。一瞬も同じ所に同じ姿ではない。それが万物流転のこの世の姿である。その変化の中に法則がある。それを見つけ出す。そこに易がある。昼と夜で一日、吸って吐けば九十年でも吸える。吸って吸ったら一分でまいる。左と右で歩ける。男と女で一家をつくる。陰と陽で電燈は光る。生と死あわせて一生。すべては相対立する二つが調和して、完全な一つを組み立てている。無常の世だ、変わりゆく世だという。それは、変わらない不変不動の真理が貫いているからである。
2012.02.09
-
心が運命をかえる その2
自分の運命ですよ。あなたの心があなたの運命の本体ですよ。自分の心に映った姿が運命ですよ。こう呼び掛けたい。自分を支配する運命、自分は運命のままにただよっている。自分と一分間もはなれることのできない運命、それをもっと真剣に考えてみて下さい。よく自分をみつめて下さい。こう願う。
2012.02.08
-
心が運命をかえる その一
一寸先はわからない。外に出たら交通地獄、運命の嵐も吹いている。しまったと思ったとたんに破産もする。夢ではないか。自分の身をつねってみるほど幸せな時もある。もうかることもある。興亡、盛衰、栄枯、無常、これが私たちの生きる世の中である。その中で私たちはもまれている。吐息もつく。小羊のように善人はさまよう。予言者がホクホクする。運命とはどんなものか。よく運は天にあると考える人が多い。運を天にまかせて無茶をやる人もある。つまずいては世をうらむ。みずから反省もしない。運命の本体がわかっていない。だから迷う。欲につられる。人に喰われる。だまされる。不幸の上塗りなっている。
2012.02.07
-
前進のために
抵抗を生かして使うものは、すばらしく前進する。抵抗にくじける意気地なしは滅びる。失敗も病気も災難も、人生行路の一つの抵抗である。前進のためには必要なものである。
2012.02.06
-
むだ
むだな働きは人間を疲れさす。むだな費用は行き詰まりの元になる。むだな話を好む人は人間の値打ちを落とす。心のむだ使いは運命の乱れとなる。
2012.02.05
-
二つで一つ その2
空気をすう。次には必ず吐き出す。これは二つの相反する運動と思う。しかし、これは二つの運動ではない。吸うて吐いて、二つ合わせて本当の一つの運動になる。吸うて吐けば、90年も吸える。吸うて吸えば一分間でまいる。
2012.02.04
-
二つで一つ
右の足を踏みしめる。動かない。そのおかげで左の足が進める。動ける。動かないものが、動かしている。静が動を生み出しています。よく切れる包丁と、なでても切れないマナイタ。この二つで一つの料理が出来る。動く車と動いては成らないレール。それで汽車は走れる。
2012.02.03
-
危ない前途
船が沈む。電車が焼ける。汽車が転覆する。自動車が衝突する。新聞記事の種は尽きない。全く危ない浮世である。浮世を渡る人の一生は、サーカスの綱渡りにも似ている。一調子、狂えば落ちる。ちょうどよかった。うまくいった。全く幸運だ。小躍りして喜ぶ。この喜びが度重なれば、富もできる。よき地位にものぼる。世にでることにもなる。あっ危ない!しまった!残念だ!まったく運が悪い。こんなことが度重なったらもう駄目だ。失敗する。亡びる。すべて調子よく運ぶ人がある。それと反対になんでもチグハグになる人がある。それはどこからわかれるのであろうか。中心を誤るか、否かできまる。
2010.12.26
-
許されて出てきたもの
幸も不幸も、健康も病も、この世にあらわれてくるものは、いっさいが自然に許されて出てきたものである。許されるためには、必ずそれだけの理由がある。原因がある。原因が半分、結果が半分、表裏一体となる。それでこそちょうどよく釣りあう。これがこの世の姿ではあるまいか。
2010.10.11
-
ねうちを高める
運は天にありといわれている。自分の自由にはならない。運が悪かったら、アッという間に滅びる。人間の一生は運命に支配されている。よい運命に守られるためには、どうしたらよいのか。どんな考え方、生き方が大切であろうか。運は一人一人のものである。一つの品物でも、ねうちのないものは大切にしてもらえない。よい運命に守られる前に、人間は自らのねうちを高めねばならない。
2010.10.08
-
運命の責任者
人間の運命は天がきめる。しかし、それは、その人の日ごろの心づかい、行いによって決められる。徳、不徳にちょうど釣り合った結果が与えられる。これが運命というものである。結局、われわれは自分の運命の責任者である。
2010.10.07
-
曇ることなき魂
いかにして逆境から逃れるかということが大切なのではない。節も逆境も問題にならぬほどの感激に冴えた心を作り上げることの方が大切である。われわれは、いつも曇ることなき魂をみがけば、人生の曇りから切り離される。よい運命の芽は開かれてくる。
2010.10.05
-
願うよりも
よい境遇を願ってあせるいらだつ。現状に不満をもつその結果、幸福を願いながら逆に不幸と合致しやすい世の中は願いどおりにはならない心の内容通りになるだから願うよりも自分の内容を美しく清める生き生きとしておくことが一番大切なことになる
2010.06.21
-
下手に実がなる
ヘタに実がなるといわれている。 柿でも茄子でも、ヘタから実を生んでいる。 ヘタが実を支えている。 たとえ下手でも努力である。 熱心な工夫と誠実の積み重ねである。 そこに真実の心あふれる人格が生まれてくる。
2010.05.20
-
知ってる割に
人間はいろいろなことを知っている。 月に行く方法さえ知った。 それでいてその割りに知らぬこと、 それは自分のことである。 人間が人間を知らない。 そこに非常な誤算が生まれて来る。 不平不満、なやみもだえる基がそこにわく。 それがまた不幸、不運の源になる。
2010.04.01
-
光と闇
光は闇のなかで冴える。多くの悟りは、迷いから生まれる。生きているよろこびは死ぬことを自覚したときにわく。黒板は白いチョークに働く場所を与える。
2010.02.16
-
黒を生かす白
古い新聞紙がひろげられる。その上に字を書いてくれとたのまれても立派なものは書けない。書いても墨色が冴えない。真白な紙、美しい紙、その上なら黒い墨の色が冴える。書いた字が生きてくる。
2010.02.08
-
中心を悟る
すべての秩序には中心がある。 そこに平均と平和と安定と 自由自在の許される基本がある。 本当に平和が欲しいなら、中心を見つける 賢明さが必要である。 一切の安定を願うなら、謙虚さがいる。 中心はどこにあるかを悟って、 中心に副うすなをさがいる。
2010.01.07
-
熟慮断行
準備ができていない。覚悟ができていないという時は、意外な怪我をするものである。熟慮断行ということがある。よく考える。よく疑う。よくなやむ。その結果なるほどと見透しをつける。信念を固める。これが物事を一気に断行する勇気を生む。
2009.12.28
-
どたんばの光
日頃、困難なことに当たって鍛えられる。そこに理の成人、心の成人がつまれる。信仰を練る努力がつまれる。毎日、人の目にはつかない。みとめられもしない。しかし、一度それが表面に表れると、驚くほど不思議な尊い姿となる。どたんばに追い詰められたとき、日頃のつとめがはっきり光るのである。
2009.12.24
-
永遠なるもの
秋の日には木の葉が落ちる。姿は変わる。しかし、それは滅亡ではない。次の年の新しい葉を出し枝を伸ばすためである。姿を変えて次のいのちへと伸びていくのである。世は無常だとなげいてはならない。変わり行くことこそ生命の伸びる道である。こう悟るべきである。自ら進んで変化の大道に躍り出ることが尊い。
2009.10.15
-
自らを甘やかす
このくらいのことは誰でもやってる。 俺だけではない。 これは自分を甘やかす言葉である。 そんな人は逆に他のあやまりはビシビシと責める人である。
2009.10.13
-
あたまと心
よくだまされる人がある。それは頭の悪い人か、心がよすぎる人か、欲に目がくらんだ人に多い。だます方の人は頭が良い。しかし心は悪い。人間として頭と心の平均がとれていない。だから時々自然の戒めを受ける。八分くらいできあがったらひっくりかえる。思わぬ手違いで倒れる。不時の出来事でころがる。目の前の欲に迷う。だから正しい判断力がくもる。せっかくよい頭であるのに色眼鏡で見る。そこで悪い人まで信用する。裏切られてから驚く。怒る。悲しむ。自分の不徳をいやというほど見せつけられる。頭のよい割合に心が悪い人である。
2009.10.03
-
果たした後も
前途に希望がある時は心がいさむ。何でも軽く持てる。たやすく困難に打ち当たる気にもなる。希望が果たされたら心はゆるむ。果たされても同じように心の勇む人、心に油断のない人、心豊かな人こそ教養の高い人といえる。まして他人の責任を引き受けて重いと感じない人は尊い人である。
2009.09.18
-
順応の構え
夏は暑い。とても毛のシャツは着ていられない。浴衣がけの散歩が楽しい。だからといって秋10月、涼しくなっているのに浴衣一枚では風邪をひく。雪が降って来たら、ドテラとコタツが楽しくなる。自分の方をかえる。これは外界の変化に順応する生き方である。
2009.09.04
-
自らを監督
他人を監督するより、まず自分のわがままを監督することである。おごり、贅沢、油断、不勉強、なまけ心、これが自分をさびつかせる。滅びる種になる。心明るく、心広く、心生き生きと、これを心がける生活で手いっぱい、他人の監督などは、とても手がまわらないといった生き方こそ望ましい。
2009.08.20
-
愛する心
愛する心、愛しえる人は幸せである。多くを愛する人、深く愛する人、色とりどりである。どんなに愛する力があっても、心がいらだったら愛は迷う。心配なことがあれば暗いこころになる。腹を立てればトゲトゲしい心になる。心がやつれる。それは愛するゆとりを失わせやすい。心は常に豊かにしたい。静かに保っておきたい。安らかにゆとりを持ちたい。そのためには生活を正すことである。つねに心に張りをもつことである。
2009.08.04
-
よき人の棲み家
外観がよくても住みにくい家がある。妙に人がかわる。それは居心地が悪いからである。落ち着きが悪い家、それは内の造作が悪い家である。神仏の住みやすい心の人、よき友を安らかに心の中に住まわせる人、心の中に親兄弟を落ち着いて住まわせる人が、造作の良い人である。荒々しい心、すさみきった心、雑草のたえない心、しまりのない不埒な心、これは悪魔の棲み家になりやすい。
2009.07.19
全140件 (140件中 1-50件目)