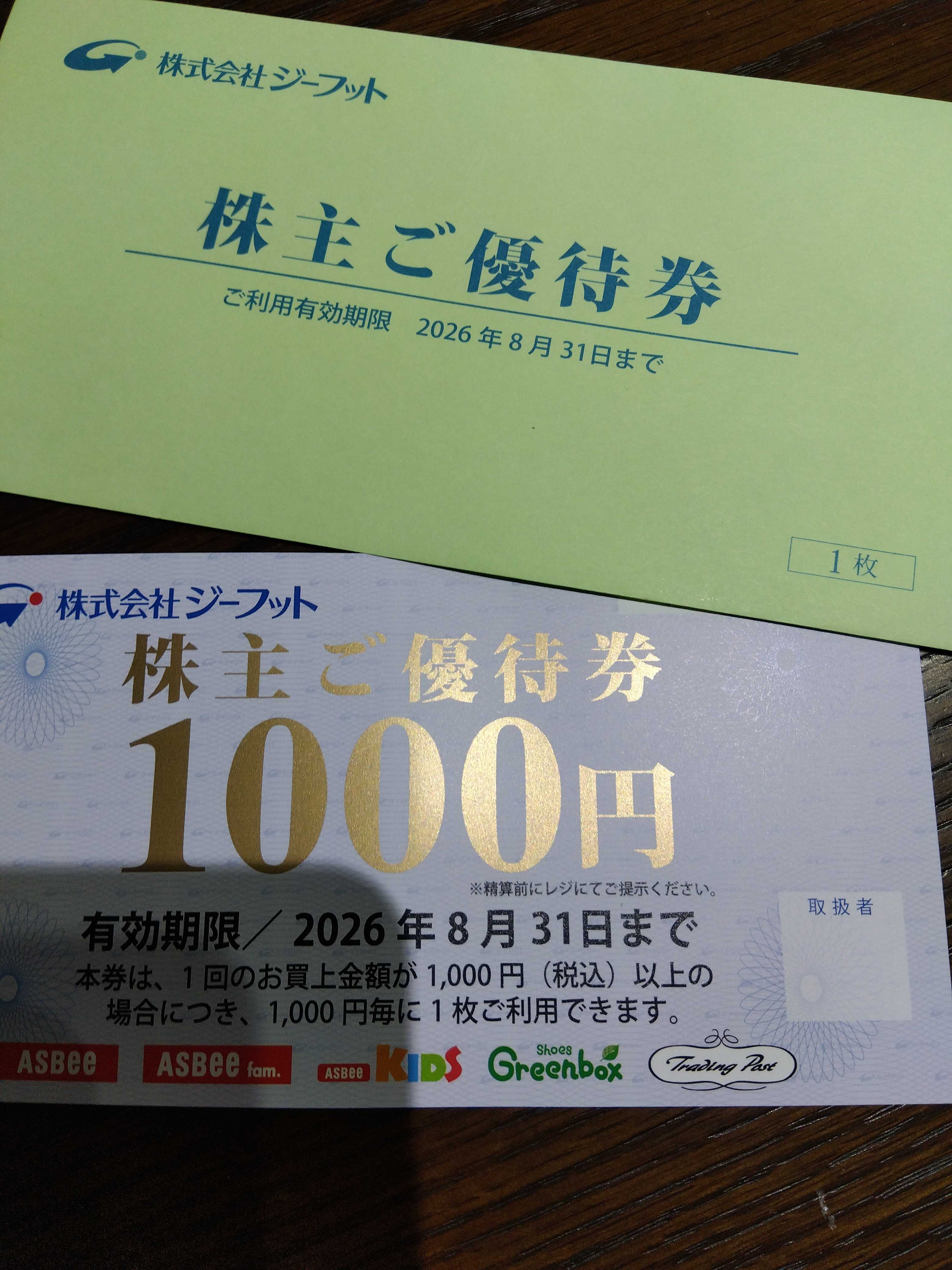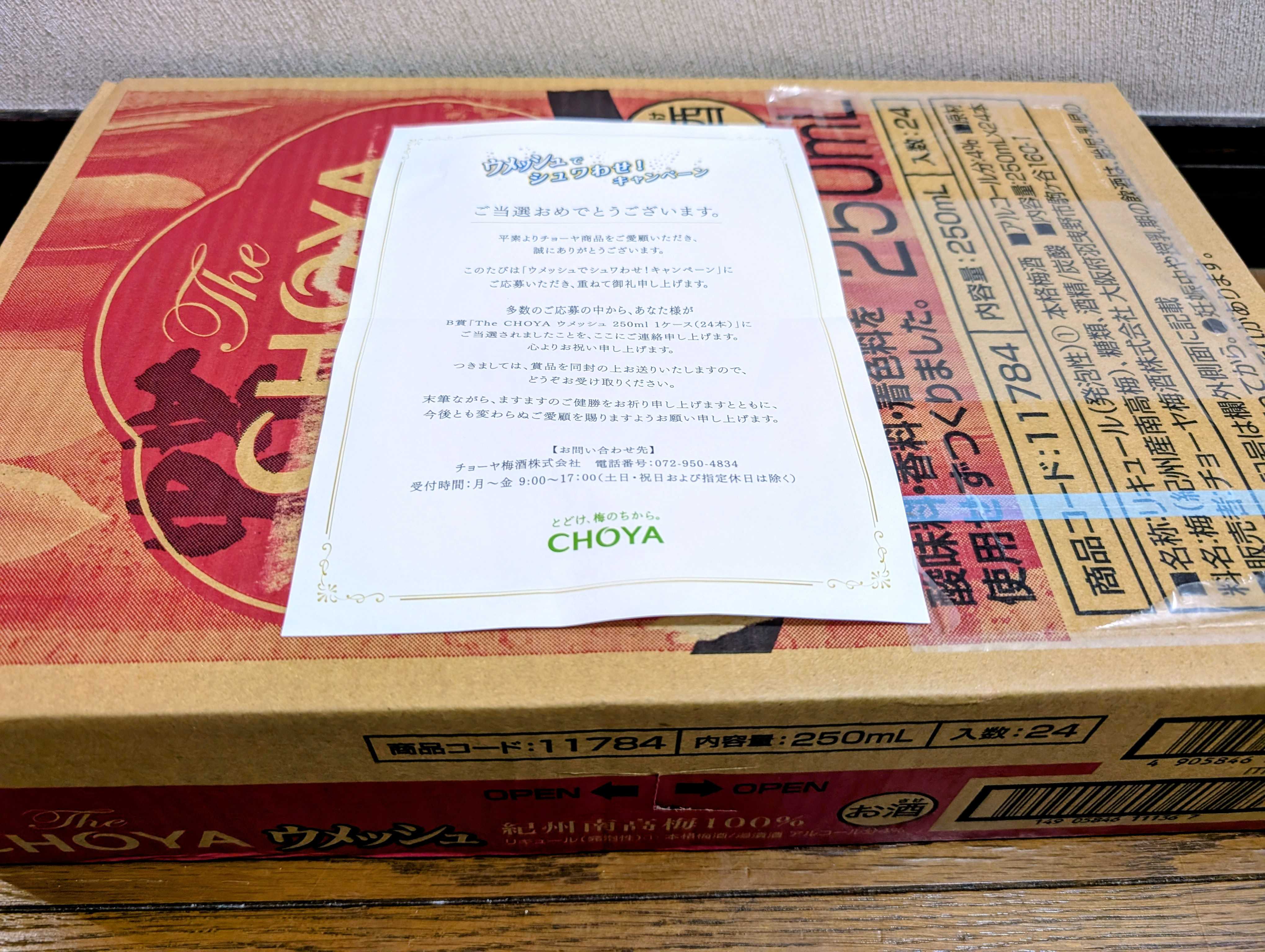全1417件 (1417件中 1-50件目)
-
高倉健さんに捧ぐ。
イデオロギーを別物として、右翼でも、左翼でもなく・・真ん中の「なか」を取り、「なかよく日本人の心」が揺さぶれるようなコラムな一日でした。日本の政治・社会を先導する立場であるのにもかかわらず、国会審議中に居眠りをする国会議員の先生たちにも読んでいただきたくなるような日本各地の今日の新聞コラムです。北から南へ、日本各地の新聞コラムを下記転載させていただきました。感謝。・・高倉健さんへ捧ぐ。「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「日本映画の全盛期にデビューし、斜陽の時代にも気を吐き、80歳を超えても演じ続けた人が消えた喪失感はファンの胸に日増しに募ろう。スクリーンの健さんに揺さぶられ、映画館を出てもしばらくはその気分で街を歩いた――。それは昭和のいつかであったが、昨日のような気がする。(日経)「男が生きていくには我慢しなければならないことがいっぱいある」▼誰もが健さんのように生きたかった。健さんならそんなことはしない。それでも現実は厳しくて、ずるいことも考える。調子よく立ち回りもする。泣き言と言い訳の日々▼「そういうのを草野球のキャッチャーちゅうんじゃ…。ミットもない」(「幸福の黄色いハンカチ」)。北風に向かって背中で「男」を教えた人の旅立ちに大人たちが狼狽(ろうばい)している。(東京)「網走番外地」「幸福の黄色いハンカチ」「南極物語」…。健さんはひたすら、あらまほしき「日本の男」を演じ続けた。(産経)高倉さんのたたずまいは、孤高に深く錘を下ろしている者だけが醸す存在感に満ちていた。吹雪の中に立つだけでこれほど絵になる人を、ほかに知らない。(朝日)映画館を出た男たちはみんな健さんになっていたといわれる1960年代の任俠映画のブームである。やがて自ら求めて活躍の場を広げた健さんは、背負った運命を静かに引き受け、見る者の心の奥深くにポッと火をともすような男たちをひたむきに演じ続けてきた。(毎日)健さんの多くの映画を貫く一筋のものがある。持って生まれたやせ我慢の美学、と言えばいいだろうか。信じたものや愛する者のために耐え忍び、逆境をはね返していく寡黙でいちずな男たち。その真っすぐな役柄に、健さんはぴったりだった▼だが任侠(にんきょう)映画のヒーローになった時には、なぜ観客が熱狂するのか不思議で、有頂天になれなかったという。そんな銀幕の自分を見つめる冷静なまなざしが、名優・高倉健を育てたのかもしれない▼耐えて、筋を曲げず、慎み深く。日本人が大切にしてきた美徳を誰よりも深く体現した、国民的な大スターだった。(京都) 「自分、不器用ですから」。CMの台詞(せりふ)がやけに決まっていた。寡黙で無骨、でも心根は優しく、仕草(しぐさ)に哀愁が漂う。10日亡くなった俳優の高倉健さんは、男にして「こんな男になりたい」と憧れてしまう大きな人だった。(東奥)その演技はファンの心のスクリーンから消えることはない。(上毛)その時の一番気になる人の名を挙げ加護を祈ったという。耐えしのぶ映画の健さんを見るたび背筋が自然に伸びてすがすがしい気持ちになるのは、人柄が伝わってくるからだろう。あこがれの人はスクリーンで生き続ける。(信濃)元東映東京撮影所長の幸田清さんが以前本紙に語っていた。「健さんは礼儀が正しすぎると言っていいほどの人。掃除のおばちゃんにも必ず頭を下げる」(新潟)そんな光景に震えるほど心を動かされた高倉さんは、絵本『南極のペンギン』(集英社)に書いた。<ぼくの仕事は俳優だから、よくひとから拍手される。でも、拍手されるより、拍手するほうが、ずっと心がゆたかになる。そう思いながら、ぼくは手をたたきつづけていた。(中日)寡黙でストイック。でもロケでは市民エキストラにもよく声をかける気さくな人だったという。たびたび訪れた熱海温泉の定宿からコーヒーの注文を受けた喫茶店ボンネットのマスター増田博さん(85)は「コーヒーも一本道だった」としのんだ。(静岡)受刑者を前に、健さんがあいさつをした。「皆さんのようなユニホームを日本で一番多く着た俳優です」。聞きようによっては、ドキッとする。嫌みや皮肉にとられかねない。殊更言わなくても済むあいさつだろう。あえて、同じような「ユニホーム」という不思議な縁を口にし、相手を和ませる。素顔の健さんも「男気」のある人だと知って、また憧れた。着流し、軍服、鉄道員姿など、私たちも健さんと同じ「ユニホーム」をひととき装い、スクリーンに男の夢を追った。(北国)本人は「作品を選ぶなんて偉そうなことはしてません」と語った。一方で、死肉をあさるハイエナを例に「まずい餌の獲(と)り方をしていると姿が悪くなる。人間にも通じるんじゃないですか」と述べている(「高倉健インタヴューズ」プレジデント社)▼長く残しておくべき話(映画)をやりたい。声高に主張せず、伝えたいことは低い調子でそっと伝えればいい、とも語っていた。健さんならではの美学を貫いた83年のスター人生だった。(山陽)「義理と人情を 秤にかけりゃ 義理が重たい 男の世界」。俳優の高倉健さんの訃報に接して、心に広がったのが、この歌だった。健さんが歌う任侠映画の主題歌は、日本人の心情に訴えかける。 背中の入れ墨も鮮やかな健さんが日本刀を構え、悪党に「死んでもらいます」と引導を渡すシーンに観客はしびれた。忍耐がいつ限度を超えるのか、ファンは今か今かと待っていた。 健さんが背負っていたのは、工場や商店、漁場、田畑で汗と油にまみれ、社会の悪や理不尽さに怒り、耐え抜いてきた庶民の心ではなかったか。 北海道を舞台にした映画「幸福の黄色いハンカチ」では、妻への愛を心に秘めた刑務所の出所者を演じ、観客を感動と涙の渦に包んだ。「昭和残侠伝」「八甲田山」「南極物語」「居酒屋兆治」「ブラック・レイン」「鉄道員(ぽっぽや)」「あなたへ」と、健さんはさまざまな役柄を演じ分けた。寡黙で、忍耐強く、謙虚で、優しく、思いやりがあって、絵になる男。それが健さんのイメージだが、素顔は気さくな人だったという。昨秋、健さんが文化勲章を受けた時、国は俳優を見る目があると分かった。 ありがとう健さん。別れに、寂しさも悲しさも尽きないが、唯一の救いは、健さんの出演作が200本余りあることだ。きょうは家でどんな役の健さんに会おうか。(徳島)高倉健さんはフランスの映画俳優ジャン・ギャバンが好きだったという。「望郷」「現金に手を出すな」「暗黒街のふたり」などで見せた渋い演技を覚えている人は多いだろう。「セリフでも動作でもない。ただ黙ってカメラを見つめてる表情のなかに感情の動きが表現されてる」(野地秩嘉「高倉健インタヴューズ」プレジデント社)。このギャバン評は、そのまま高倉さん自身にも当てはまるのではないか。 「八甲田山」「幸福の黄色いハンカチ」「駅 STATION」「南極物語」「鉄道員(ぽっぽや)」…、そして最後の作品となった「あなたへ」。演じた役柄は違っていても、スクリーンの中にいるのはいつも高倉さんその人だったように思う。 芸能プロダクションのマネジャーになるつもりが、ひょんなことから映画界入りし、任俠(にんきょう)映画でスターの座に駆け上がった。存在感のある静かな名優への「変身」には多くの苦労があったに違いない。共演経験の多い小林稔侍さんの「努力の人」「忍耐の人」という評がそれを物語る。酒を飲まず、たばこも3年がかりとなった「八甲田山」完成への願掛けでやめた。「熱くなるから」と賭け事にも手を出さなかった。「普段の生き方が芝居に出る」との信念が禁欲的な生活につながったのだろう。表情はむろん、背中だけで喜びや悲しみを伝えることができる数少ない俳優だった。さようなら、健さん。(高知)文化勲章を受けたとき《彼》は「日本人に生まれて本当によかったときょう思いました」としみじみと語った。《彼》がそう言うのを聞いて、私も「日本人に生まれてよかった」と思った。(宮崎)主演俳優の名前だけで映画館に観客を呼べるのが「銀幕のスター」だとすれば、最後のスターというべき存在だった。背筋正しく、寡黙で、どこか影があり、情に厚い男。後半生はそんなイメージの役柄が多く、ファンは映画の主人公に高倉さん自身を重ねて引きつけられた。(佐賀)CMを出した健康家族(鹿児島市)によると、実直な人柄が、土作りから手間暇かけた商品のイメージに合うと出演依頼したところ快諾を得た。小林市など撮影現場ではうわさ通り、周りのスタッフに遠慮して休憩中は絶対に座らなかった。 鹿児島では知覧の特攻隊員を描いた映画「ホタル」を撮った。制作のきっかけとなった故鳥浜トメさんの孫の明久さんは、関係者の話に「はい」「はい」と正座したまま聞き入る様子に律儀さを感じたという。色紙にサインを求めると隅っこに小さく書いた。トメさんゆかりの資料館では、多くの人が待ち構える中に入っては迷惑になるからと見学を遠慮した。「いつかまた来ます」は実現しなかった。寡黙で義理堅く、ここ一番の時に立ち上がる勇気を秘めた存在感は、日本人の美学を体現していた。背筋をすっと伸ばし、含羞(がんしゅう)ある姿を見ることはかなわなくなったが、私たちの心に刻まれた数々の名演技が消えることはない。(南日本)▼1960年代の任侠ものでは若い男性を魅了した。代表作中の代表作「幸福の黄色いハンカチ」で真骨頂を発揮し、人気を不動にした。必死に生きてきたのに報われず、武骨さの中に哀愁や優しさがにじむ愚直な役に魅せられた。(沖縄)」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」以上、とても遠い存在のようで、とても近くにある日本人の良心・善・美徳を体現した高倉健さんへの全国から届けられた日本人の想いです。・・高倉健さんへ捧ぐ。
November 20, 2014
コメント(0)
-
始めと終わり
初めてヨーロッパ旅行に出かける方には、「北から南に周るとよいでしょう」とアドバイスします。ヨーロッパ巡りの始点が、イタリアならば、その後の仏国のパリやら英国のロンドンの魅力が半減するような気がします。例えば、初めにディズニーランドを入園したあと、翌日に地方の遊園地を行くと、その魅力が半減するようなものです。丸ごと博物館のようなヨーロッパの旅巡りの終点は、イタリアが似合います。イタリアは、それぐらい魅力的な国です。昨日、福井県立美術館で開催されている「ミケランジェロ展 天才の軌跡」に見学に行って参りました。今回のミケランジェロ展は、福井県立美術館の学芸員の方が企画立案したということで、開催場所は、東京と福井だけの二会場ということになったとのこと。2013年6月28日〜8月25日 福井県立美術館2013年9月6日〜11月17日 国立西洋美術館今年は、イタリア・ルネッサンスを代表する三人の巨匠の展示会が、奇跡的に日本で開催されました。ラファエロ展とダ・ヴィンチ展は、東京のみでの開催・・今回のミケランジェロ展は、例外的に福井開催ということでした。おそらく、このような展示会は、二度と無いとのことでした。そのせいか、県外からの美術ファンの来場者も大変多かったです。開催から50日未満で既に6万人を超えたようです。さすがに、ミケランジェロの彫刻や天井画や建築物を、日本まで持ち運ぶのは不可能です。実際の展示品は、素描の習作や現物の手紙が多く、システィーナ礼拝堂の天井・壁画の傑作「最後の審判」がプリントされた薄い布地のレプリカやカラー写真で説明されたものがあり、ミケランジェロが何を意図して描いていたのかと分かりやすく説明していたのは、ヨカッタ!!勿論、展示会場内は、写真撮影禁止です。今回のミケランジェロ展の目玉作品は三点・・世界一美しいと言われる「レダの頭部」素描習作。ミケランジェロが15歳の時の作品、大理石のレリーフ「階段の聖母」・・日本初公開の門外不出作品。ミケランジェロの最後の作品と言われる・・木彫りの「キリストの磔刑」。ミケランジェロの最初と最後の頃の作品が、展示会の出口に置かれてあるのが、とても印象深いものがありました。今回のミケランジェロ展・・なかなかよかったです。それよりも、福井県立美術館の学芸員の企画力に感心しました。地方でも、こういうことが出来るんだという「実行力」と「運営力」です。・・見倣いたいものです。神のごときの芸術作品を生み出したミケランジェロ。・・陰気、情熱的、偏屈、孤独だったミケランジェロの言葉です。「わたしは金持ちになったが、けれど始終貧乏人の暮らしだった」
August 19, 2013
コメント(0)
-
ブレーク・バック
ウィルブルドン・テニス大会、準々決勝男子・・ジョコビッチ(セルビア)とベルディッチ(チェコ)。今、・・息詰まるような試合展開をしています。深夜に目が覚めてしまいました。お互いが、UNIQLO(ユニクロ)とH&M(ヘネス・アンド・モーリッツ)のテニスウエアを着用して闘っているのも見ものです。世界No.1シードのジョコビッチの袖に、カタカナで「ユニクロ」の文字も映っています。ブラックではなく、オレンジ色に白抜きです。
July 3, 2013
コメント(0)
-
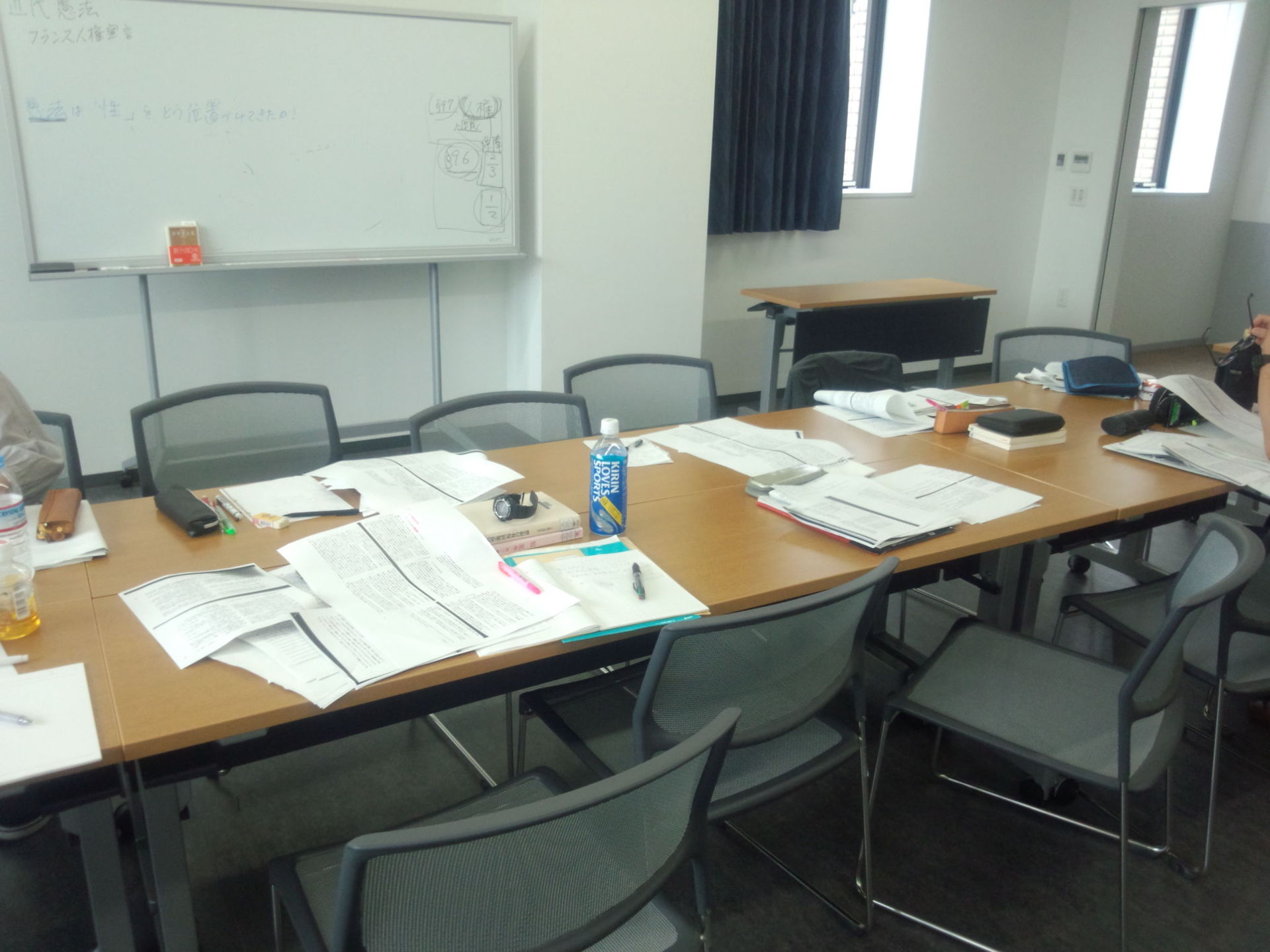
文月一日
昨日、一昨日の講義は、ゼミナールのような形でしたが、とてもよかったです。・・この大学に編入して、いちばんよかったかなぁ。あまり言いたくはないのですが、「この先生、大学レベルで教える立場?」と思える方も時々います。余程、大学の先生よりも、幼稚園や保育所で働く先生方の給与を多くした方がいいのでは?「だって、大人を教育するというのは、幼児を教育するよりも重要なのかな?」・・と言ってたのは、昨日、大学で教えていただいた先生でした。(笑)昨日は、「ジェンダーの問題」が、テーマでした。エミールから・・。フランスの人権宣言。ソビエトの登場。ドイツのワイマール憲法。そして、日本国憲法。家族というものは「労働共同体」から「職住分離」によって、大きく変化していきました。身分制度があった時代、職業の選択の権利、自由というのは皆無でした。身分制度が撤廃されたあと、男女の差別、区別は、どのように明示されているのか?個人の尊厳? 両性の平等?そして、いつの頃から人権の保障、社会制度としての福祉という概念が展開されたのか?その生存権とは、何か?もう、35年ほど昔、ぼくが受けていた・・ある教授の講義を忘れることができません。その教授は右翼的な思想傾向があり、試験問題も「終戦時に詠んだ昭和天皇の和歌に関する」ものでした。単位修得をするためには、天皇制批判よりも、天皇擁護の立場でレポートを提出していました。・・まさしく、右に倣えという心構えです。その教授の最後の講義です。憲法改正について、延々と自説を述べていました。アメリカから押しつけられた憲法だとか、自衛隊の存在理由だとか・・?日本という国家、日本民族としての意識を自覚せよ・・という強烈なメッセージでした。その教授が、最後に言い放った言葉です。「みんな、でも、いいものはいい。この日本国憲法は、ほんとうにいい。それだけだ」と。その言葉で、僕の胸の中にモヤモヤしたものが消えたような気がしました。日本国憲法・・この不思議な奇跡のような憲法。昨日、講座が終わって、世界文化遺産に登録された富士山へ弾丸登山に向かった滋賀県の方へ。ご来光が見えず残念でした。日本国憲法も同じく「光」が見えません。せめて、世界記憶遺産に。そして、琵琶湖を世界自然遺産に。今日から文月。七月一日は、「びわこの日」だそうです。
July 1, 2013
コメント(0)
-
黙祷
今日の午後0時、福井市街地で一斉にサイレンが鳴り響きました。・・黙祷。今から65年前(昭和23年)の今日・・福井地方は、大きな地震に襲われました。犠牲者3800人余り、倒壊家屋3万5千戸を超えた大災害でした。その3年前、昭和20年、福井は、米軍の空襲により市街地の95%が焦土と化しました。やっと、復興しかけた矢先、今度は、大地震に遭ったのです。福井人の足跡を調べると・・粘り強く、凄いです。ほとんどの日本人が知らない・・日本の土台となる縁の下の力持ちのような印象があります。それは兎も角、別の機会に譲るとして・・~今日の地元福井新聞「若水越山」のコラムから~▼二十九日早暁(そうぎょう)、通信・交通の途絶した震災地一番乗りを行った記者が、数分ごとに襲ってくる余震におびやかされつつ、子をさがし親を求める阿鼻(あび)叫喚の巷(ちまた)に三十日朝を迎えた…。▼1948(昭和23)年6月、大阪の夕刊紙に掲載された福井地震の記事である。クレジットは【三十日朝福井にて 佐野・福田特派員発】と書かれている。▼2人の記者のうち、福田という人こそ後に作家となった司馬遼太郎である。産経新聞京都支局の記者だった司馬は、地震が起きた28日夜のうちに急ぎ福井へと向かった。▼「新聞記者 司馬遼太郎」(産経新聞社、文春文庫)によれば、司馬は映画館崩壊などの様子を伝え、戦後の復興建築の大半が手抜き工事であることをいち早く指摘したという。▼20代半ばの司馬が惨状を目にした福井地震からきょうで65年になる。マグニチュード7・1の直下型地震で、死者行方不明者3800人余り、倒壊家屋3万5千戸を超えた。▼地震国日本で長く戦後最大と位置づけられたが、最近では1995年の阪神大震災、2011年の東日本大震災と福井をしのぐ大地震が続発している。▼さらには最大34万人以上の犠牲者が予想される南海トラフ巨大地震も想定されている。われわれは福井震災から阪神、東日本大震災と悲惨な歴史を記憶にとどめている。日々の備えをいま一度確認したい日である。 合掌。
June 28, 2013
コメント(0)
-
ムムム都会
ちょっと気になったコラムな言葉。~今日の日本経済新聞「春秋コラム」から~好きな食べ物は何? 都会の子供たちにそう聞くと、ハンバーグやカレーライスなど料理の名前が返ってくる。ところが身近に生鮮品が採れる地方は違う。北海道の小学校で尋ねるとトウモロコシ、ジャガイモ、アスパラガスと、料理ではなく野菜の名が次々とあがる。▼調理して味つけする前の、おいしい野菜の味を知っているからだろう。先入観がない子供の舌は正直である。畑でもぎ取ったナスやカボチャをそのまま食べる機会は、都会人にはめったにない。夏の太陽を浴びて自然に育った作物はいまが収穫の本番。料理せず生で食べたくなるような甘い夏野菜は、どこで出会えるのか。▼香川県に「ムムム農場」という一風変わった農園がある。有機栽培のさらに上をゆき、化学肥料、農薬、畜産廃棄物を使わない。3つの無だからこんな名がついた。化学物質が染み込んでいない耕作放棄地を借り、刈り取った雑草から堆肥をつくる。手間がかかるので値段は2倍近いが、その豊かな野菜の味に誰もが驚く。▼経営者は土建会社の社長と日銀の元高松支店長の異色コンビである。農家ではない新規参入だから、放棄地や雑草を宝の山に変える大胆な農法が生まれたのだろう。都市部を中心にどんどん売れるというから、安心で高品質な農産物に需要があるのは間違いない。貿易自由化の嵐の中で、たくましく実る日本の農業もある。地方に暮らす人ならば、ちょっと思うこと、ちょっと感じることが理解できるかもしれません。ナマズのような感覚なのかもしれませんが、「東京方面に、気持ちと足が向かない」のです。何だか知らないけど、大地震と出くわすような気分。何だか知らないけど、地下に潜るとモグラになったような気分。富士山よ、爆発しないでおくれ・・と祈るような気分。東京(関東)方面の都会に暮らす身内・友人の皆々衆へ。いざという時、土が無い、水が無い、電気も無くなるぞ。田舎が、いいぞ。地方回帰だよ。
June 27, 2013
コメント(0)
-
目を閉じて耳を澄ませば。
若い頃、恋に夢中になる思春期の頃、こんなことを想った人が多いのではないのかと思います。「もし、自分の目が見えなかったならば、美人と醜人、善人と悪人を、どういうふうに見分けするのだろうか?」と。昨日、とても仲良くしていただいているリハビリ・ルームで働く全盲の方に、そのものズバリ「心の中で、美しい人と醜くい人、善い人と悪い人を、どういうふうに判断して、今まで生きてきたのか?」と訊いてみました。聞きたいですか・・?基本的なことは「挨拶の有無」です。次に、声の張りで、相手の気持ちを捉えるようです。どうも、心弾む声、心弾ませる気持ちが、大事なのは間違いないようです。「目を閉じて、耳を澄ませば・・」・・次にくる言葉は、何だったかな?何か・・聞こえてきましたか?
June 13, 2013
コメント(0)
-
老人党宣言
「長生きしてよかった」という社会を築くために、 「強い国」より「賢い国」へ 。(なだいなださん提唱) なだいなださんのご冥福を心よりお祈りします。合掌。
June 11, 2013
コメント(0)
-
時の日
もし、自分が怠け者だと思うならば、たくさんの友達を作りましょう。そうでなければ、怠けてはいけません。人間である限り、多少の好き嫌いはあります。でも、その好き嫌いを社会的な位置や価値に結びつけはツマラナイです。たった一度会っただけなのに、二度と忘れられない人は大勢います。
June 10, 2013
コメント(0)
-
優しい力
荒々しい言葉より、優しい言葉を投げかけましょう。怒った目つきよりも、優しい目つきで見つめましょう。荒々しい言葉で人を責めたり、怒った目つきで睨んだりしても、お互いの成長は望めません。
June 6, 2013
コメント(0)
-
やりがい
仕事も、何事も、修行で、自分が始めたと思えば、いつか、役に立つと思えば、悩みも、苦しみも、きっと消えてゆくものです。
June 6, 2013
コメント(0)
-
式年遷宮
よりよい豊かな福祉国家となる未来に想いを馳せながら、今朝から目がチカチカしながら、大学の提出課題レポートを書き上げています。課題を書くよりも、直接、自分の想いを政権与党、野党、多くの政治家に進言した方がいいのかなぁ?安部さん、10年後、国民一人あたりの所得を150万円増加させるとか、農業・農村所得を倍増させるとか、「民間活力の爆発」とか、グローバル化の競争時代とか、申しますけど・・?10年後の日本は、認知症の高齢者だらけなのです。グローバルな人材とは、世界で何と闘う人材ですか?海外へ出て、日本のモノを売りに行く人材ですか?勿論、そのようなグローバルな人材も必要かもしれません。しかし、地域で、お年寄りを大切にするローカルな人材も必要なのです。数字計算も強くて、英語も出来る国際感覚の優れた能力も必要です。数字計算も弱くて、英語も出来なくても、お年寄りの手を繋ぐ能力も必要なのです。だから、そこの能力の違う部分で、所得格差があっては、ならないのです。一、高齢者の貧富格差拡大を解消するために、国民全員一律に受給年金金額を「生活保護受給者」並みに補償する。二、福祉関連の現場に従事する者には、地方公務員と同レベルの給与所得を補償する。以上の二点だけでも、政治公約すれば、日本の未来は、明るく安定したものになります。さて、公約した国会議員の大幅な定員削減は、どうなったのでしょうか?天照大神も、失われた20年を取り戻すかのような・・今年は、20年ごとの伊勢神宮式年遷宮にあたります。10月に、その御祭りが、執り行われます。それから半年先の来年の春ぐらいが・・檜が、いちばんプ~ンと薫るよい頃かと思います。個人的なお勧めの御参拝時季です。経済成長よりも、国民ひとりひとりの安心できる安定生活の方が大事です。
June 6, 2013
コメント(0)
-
政策打破
もっとグローバルな人材育成を!もっと女性は社会進出を!そして、要介護老人を在宅で!・・?誰が家に残って介護すればよいのですか?そんな矛盾した政策を打破できる政党を応援します。
June 1, 2013
コメント(0)
-
黒部ダム50周年
関西電力の黒部第四水力発電所・・昭和の日本が誇る偉大な建造物です。数百年にも耐えるコンクリート建造物だと言いますが、立山の雪深い山間部でのメンテナンスも管理も大変です。それと比較しての原子力発電所問題・・これまた厄介な問題です。さて、今日から、金沢では「百万石まつり」。そちらに行く予定でしたが、未来塾の講演会の方に出かけます。太陽と海と・・雪が、これからの時代のキィー・ワードになるような気がします。電気と水は、現代社会の生活を快適に維持する必要なものです。今日から、水無月。
June 1, 2013
コメント(0)
-
春は何?
金閣寺よりも、銀閣寺の方が、個人的には自分好みです。銀閣寺は、慈照寺と言います。しかし、銀閣寺を築造した室町幕府の将軍足利義政は、慈照という想念を窮民にではなく、贅沢な東山山荘の建立に集中したのです。当時、最大の飢饉に直面しているのにもかかわらず全く対策を講ぜず、日々、銀閣寺の築造に没頭した将軍だったようです。だから、立派な世界遺産として残っていますが、天下の統治者としては、無能というか、失策です。一方、鎌倉幕府を開いた源頼朝は、飢饉に際して、領国内の農民に年貢を免除したと言います。(天下草創)さらに、江戸幕府を創始した徳川家康は、二代将軍秀忠に、金銀の大いなる遺産を軍事の次に「窮民に対しての慈恵的救済」に使うようにと厳命しています。(天下一統)近代社会になっても、同様です。国家政府が、何を基準として、国民の「さいわい」を導こうとするのかが・・問われるのです。「夏は麦、秋は米、冬は銭、多少にかぎらず、老若男女各志を運び申すべき事」・・三浦梅園さんへ。「春は何?」
May 28, 2013
コメント(0)
-
ギャップ・イヤー
人生に寄り道やら通回りをしていない人の考えは、どうも理解しかねることが多々とあります。昨日の厚生労働省の社会保障対策の具体案・・いわゆる、2025年問題以降に生じる大都市での高齢者増加問題に対する検討会内容。もう20年昔からの日本の緊急課題なのに、やっと重い腰を上げたような印象を持ちます。杉並区の先行事例を示していましたが、地価が高い、用地取得の難しい「都会の事情」で、杉並区が所有する150KM以上離れた静岡県の南伊豆町に特養施設を整備を検討しているとか・・?小生、元杉並区民として述べさせていただくと、理解し難い「愚の骨頂」ではないかと思います。杉並区の高齢者が、なぜ南伊豆で終の生涯を閉じなければならないのでしょうか?受け入れる施設が足りないから、地方にある杉並区所有地で整備するというのは、行政マンの視線で捉える思考論理でしかありません。それ以前に、その施設で働く介護職員の確保が、出来ますか?この頃の日本・・アベノミクスとかという造語もできて勢いづいて見えますが、民主党政権時代と比較してのことでしょうか?あるいは、バブル崩壊後の「失われた20年」を比較してのことでしょうか?安部さん、嫌いではありませんが、首相としての「強いリーダー」を意識しすぎです。「世界で勝つ人材を!」・・と掲げます。「♪あの素晴らしい愛をもう一度」を歌う安部さん・・。・・これからは、「グローバル化に通用する人材育成時代」だと強調します。このスローガンは、安部さんも学生だった時代、既に、30年以上昔の高度経済成長期の学生の間で「日本人が国際人として」という標語で一世風靡したものです。その結果が、「ゆとり教育」に落ち着いたのです。そして、「ゆとり教育」の否定のあとに、再び「グローバル化教育の台頭」。英語をコミュニケーションとして稼ぐ生活も、勿論面白く愉快な時間、一生懸命な時代です。しかるに、ギャップ・イヤーを体験した者ならば、「ローカルに役立つ人材育成」が基本教育であることを認識しています。高齢者になれば、安心して生涯を終える孤独ではない「ゆとり」と「楽しさ」を求めます。優しい人間に囲まれた、優しい場所を求めるものなのです。極楽往生とは、家族、友人、善人が、幸せになるのを見届ける生き方だと思います。それが、ギャップ・イヤーという「道草教育」なのでしょう。道草を食うのは、昔ならば、馬であり、牛であり・・自分の乗り物でした。現代に譬えるならば、車であり、自分の足跡です。
May 21, 2013
コメント(0)
-
原発問題に関連して
前にも書いた記憶があります。原発廃炉で、イライラするか? ワクワクするか?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~一体、市場経済、否。市場生活とは、何だろう?広辞苑では、生存して活動すること、生きながらえること、世の中で暮らしてゆくことだとか。仕事とは、何だろう?仕事とは、どのような意味を持っているのか?自分のやりたい仕事を持っている。働く事に意義も感じている。生活してゆくには、仕事が不可欠なのは言うまでもない。病気や怪我で入院して、しばらく休まざるをえない場合、普通は、不安や寂しさを覚える。「サルがヒトになることに、労働はどのように関与したか?」経済学者エンゲルスの一節。直立に歩みだした人類の祖先は、手を自由に使い、新しい技能を次々と得ることに進化した。労働という仕事は、人間の能力を発達させてきたのは、歴史的事実である。人間の労働は、自然まかせの狩猟や採取の段階から、言語を持ち、人間が主体となる社会的集団労働に発展した。集団での多面的な労働を構築して、計画的な分業協業による組織性が生まれてきた。こうして、仕事は、社会的な性格を備えるようになった。仕事は、人間の自己実現の場であり、社会への参画でもあり、生きがいにも相当することにもなる。「仕事は、人間生活の第一の基本条件」は、揺るぎない事実。封建社会の時代、身分制度のもとで、農民は農民、商人は商人として、与えられた身分職業を全うするほかなかった。近代となり、資本主義社会は、身分制度を廃止して、強制的に縛られていた人間を解放した。自らが、職業の自由を選択できるようになったのは、誰もが知っている。それでも、なぜ?仕事が苦しいという生活感覚が、現われてくるのか?資本主義社会の矛盾?現代社会における、失業問題、ホームレスの増大、日雇い労働者の高齢化、派遣労働の有期雇用、低賃金、農業の低迷、商店街の衰退、巨大企業と中小企業の格差拡大等々・・貧困、生活困難の社会問題が浮かびあがる。例えば、先進国の多国籍企業が、途上国の安価な労働力を使って生産する。社会は、不変ではなく固定的なものではない。絶えず、変化、発展してゆくもの。ただ、その変化、発展の本質を考えるのも大事。仕事が苦しくなるのは、労働者による労働する過程で自主的管理、利潤獲得範囲での裁量があるにせよ、それ以上のコントロールを、自分では、できないから?消費者に生産物を購入させて利潤をあげるだけの労働仕事。消費者に生産物を使用して、より豊かになってもらう労働仕事。自ら考えて判断できる人間としての労働意欲ではなくて、資本・経営側による最終判断を委ねるような疎外されて、労働に従属されているような現実社会の状況。現場の自由を制限して、管理ばかりが強化されると、自律性も自立性も失われてゆく。自立的で自由な思考、発想、精神を失った仕事や生活は、楽しいはずがない。労働者が、労働過程での適切な労働時間、適切で安全な労働内容、環境を備える社会の実現を備えるのが、先進国としての基本条件かと考える。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~原発再稼働で、イライラするか? ワクワクするか?
May 15, 2013
コメント(0)
-

紫式部の末裔
ドナルド・キーンさんの言葉は、日本人に勇気を与えてくれます。昨年、日本に帰化したドナルド・キーンさん 九十歳。日本人以上に、日本人の情感を分かりやすく具体的に説明してくださいました。今回の福井での講演会・・地元に関わる橘曙覧、近松門左衛門の「曽根崎心中」も取り上げていましたが、個人的には「源氏物語」との出会い話が印象深いものとなりました。ドナルド・キーンさん曰く、受験のための古文の文法を学ぶより、現代訳の「源氏物語」を読む教育のほうが、余程人生が豊かになるとおっしゃっていました。彼が、初めて日本と接したのは、学生時代に読んだ英訳された「源氏物語」だったそうです。「源氏物語」は、世界最高レベルの長編恋愛小説だそうです。作者の紫式部が描く光源氏の情感・・千年の歳月を超えて、非常に美しく、ほんとうに驚かされたようです。例えば、日記が、日記文学へと昇華するのは、日本人独特の情感だと説明されていました。第二次世界大戦中・・日本は、敵国の言語、英語を使うのも学ぶのも禁止しました。一方のアメリカは、徹底的に日本語を研究しました。日本に興味を抱いていた若きドナルド・キーンさんは、アメリカ海軍の日本語学校に入りました。戦線で日本語の通訳官も勤めるようにもなります。そして、戦場では、多くの日本兵士が残した日記を読むことになったそうです。(アメリカの軍隊では、兵士が戦場での日記を書くことは禁じられています。)千年昔の恋文ひとつとっても、日本人の情感の素晴らしさを源氏物語は、伝えているとのこと。・・恋人に、文をしたためるのにも、どんな紙をつかおうかと迷う情感。・・文を書くのにも、墨の濃淡さえ考える情感。・・文に、どんな花の芳しい香りを添えるか惑う情感。圧倒的に美しい情感が、千年の時を超えて、胸の奥まで迫ってきたと言います。越前市にある紫式部公園です。平安朝の庭園を再現しています。カップルが、多いです。父の藤原為時が越前国司として赴任した時、紫式部も、約二年間、ここで娘時代を暮らしました。向こう側に見える越前富士(日野山)・・紫式部が毎日見たであろう山は、千年昔も今も変わりなく座しています。山を眺めて、感じたこと・・ドナルド・キーンさんは、紫式部の末裔かもしれません。
May 12, 2013
コメント(0)
-
ちょっといい、意外な話。
京都の喧騒から離れて、やっと、福井に戻りました。今日の午後、福井では、日本人になられたドナルド・キーン氏の講演会「私と日本文学}がありました。この話の内容は、後日・・。京都の大学に通うのも2年目になりました。この1年間で、さまざまな同級生にも出会うことが出来ました。人と人との出会い・・すべてが善となるような御縁でもありません。不運とも思えるような出会いだって、沢山あります。ある程度の年齢を重ねれば、お互いの器量とか、バックグランドとか・・それらを隠しながら、明かしながらの付き合いも始まります。今、通う大学の通信制もそうなのですが、いろんな年齢層、職業の方がおられます。ここでは、守秘義務も伴うので言えませんが、とても興味深い方も何人かいます。・・今回、ちょっと印象に残った出来事があったので、書き残して置きます。大学からホテルに戻って、シャワーを浴びようかと思っていると、九州から来られている同級生の方から電話が入りました。「学校で財布を失くした」という連絡なのです。「まだ学校なんです。お金を一万円ほど貸して戴けませんか?」という申し出でした。彼は、朝早くから学校へ行き予習、夜遅くまで残って課題を復習をされています。僕より、一回りほど年下ながら、なかなかの好人物です。この一年間、彼の学習姿勢を見ていますから、勿論、手助けになるような返答をしました。「タクシーに乗って、私のホテルまで来てください。外で待っています。お金を渡しますから」と。・・彼は、申し訳けなさそうな顔をして到着しました。「どこで落としたのかもわからないし、学校の事務局に行っても、落とし物の届けもなかったんです」財布には、現金もクレジットカードも入っていたようで、がっくりと来ているはずです。一緒に夕食を摂ることにしました。僕の心臓が元気ならば、もっと陽気になるために、四条界隈にあるアイリシュパブへでも飲みに行くのですが、アルコール類は、禁止になっています。簡単な食事となりました。食事中に、彼は呟くのです。「ほんとうに申し訳けないです。でも信用してくださいね。実は、私、弁護士をやっています。必ず明日、返しますから・・」「弁護士・・?!」「はい、インターネットで検索されると私のことが出ています」調べてみると、高齢者虐待犯罪等の講演もされている正真正銘の弁護士でした。・・翌日。彼の奥さんが、九州から京都まで来られて即返金、そして、僕は、たくさんのお土産を頂戴しました。僕も、社会に貢献できるような人間になりたいなぁ・・と感じた意外な一日でした。彼には、第二の中坊公平さんのような市民派弁護士になって欲しいなぁ。
May 6, 2013
コメント(0)
-
昨日のお話
昨日は、縁起のよい珍しい苗字の方と、続けざまにお話する機会がありました。勿論「いいお名前ですね」というお言葉も添えました。百とか万とか八十八とか・・合せて、やおろずの八百万でした。それから、ゴールデンウィークの動向を尋ねて、昨日は、同級生二名と電話でお話しました。昨日の夕方、普通自動二輪免許取得をトライ中の息子と食事をしました。会話の内容は、「単車欲しいなぁ」という繰り返す息子。「ふ~ん、単車欲しいんだ?」と繰り返す親父でした。昨日の朝、ラジオあさいちばんで「著者に聞きたい本のツボ『ナマケモノに意義がある』」のコーナーで、著者の池田清彦さんの話を聴くことができました。「人生に意義なんてない。多くのものを望まない」・・面白かったです。さて、昨日は、食べすぎました。・・怠け者としての意義は、あったのか? なかったのか?昨日のお話でした。
April 28, 2013
コメント(0)
-
恋愛と幽霊
昨日の新聞コラムのほとんどが、「鉄の女」と呼ばれた英国のサッチャー元首相を悼むものでした。「英国を救った」とも称賛される一方で、「貧富の格差を拡げた」とも批判されるサッチャー氏の生涯です。サッチャー政権末期に、英国に滞在した時間は、よい意味で振り返れば、「生きる楽しみ方を学んだ」体験でした。当時のサッチャー氏は、日が昇る勢いの日本経済の成功や日本人の勤勉さを、よく称賛していました。でも、あの頃の日本の社会風潮のテーマは、「働きすぎから、もっと休もう。日本」だったと思います。サッチャー氏の語り口は、「まるで、小学校の先生が児童に語りかけるようなものだ」と、当時、お世話になった英国人の方が言っていた事を思い出します。「政府が社会を富ませるものではなく、民間の企業や人が社会を富ませる」というのが、サッチャー氏の持論でした。だから、小さな政府と国有企業の民営化でした。市場原理の競争のうえで、正当に報われる社会が理想の姿だったのでしょう。鉄の女は、英国病という「揺りかごから墓場まで」の高福祉政策をも切り捨てました。家庭の貧富収入の格差関係無く、家族の構成人員を基本とした人頭税という税収政策に踏み込みます。ロンドンで、反サッチャー政権への暴動デモが頻発します。英国病蔓延と言われた英国社会・・。不思議だったのは・・、犬や猫や・・ペットが多かったこと!家庭に洗濯機が無いのかと思うぐらい、街の中にコイン・ランドリーが多かったこと!スーパーマーケットのレジは、既に商品にバーコードがあり、それを通すだけで自動的に金額が計算清算されていました。・・計算が苦手なのか? 手先の指が不器用なのか?・・と考えていました。何故なら、当時の日本は、まだレジで金額の値段を指先で打っていましたから。クレジットカードを使用している多くの英国人、テイク・アウトのお店、冷凍食品専門店もいっぱい多かったです。・・これも英国病という、ちょっと怠けた横着かな?というイメージがありました。思い出せば、まだまだ何か「遅れている英国病の現実」というものを勘違いしていたものが多くあります。当時の遅れていると考えた英国社会のシステムが、進んでいると考えた日本社会に、あとあと続々と入り込んできます。今では、ペットも多い、日本のあっちこっちにコインランドリーがあります。独り暮らしや、高齢者の居る家庭の洗濯物を区別するのに必要な存在なのかもしれません。レジのバーコード導入も、今の日本では、当り前になりました。持ち帰りのtake outも、冷凍食品も当り前の時代になりました。映画批評もそうでした。「東京物語」の小津安二郎監督のよさを、日本人よりも、多数の英国人の方が、早く理解していました。東の果ての島国日本と、西の果ての島国英国は、鏡とは言いません。そんなふうに映りません。恋愛という自愛、幽霊という他愛のような関係に思えるのです。今思うと「英国病」は、「余裕(ゆとり)病」ではなかったのかと・・?今の日本は、景気の経済政策よりも福祉の政策を優先しないと、「ゆとり」の無い経済優先の貧富格差社会になると考えます。英国や日本という国家やら一定の地域が、豊かになっても・・どうかと思います。その国の国民、その地域に暮らす住民が、豊かで、ゆとりある生活にならないと・・話になりません。これまた、恋愛と幽霊を相手にするような不安だらけの未来ですが、未来は、ゆとりのある希望です。
April 11, 2013
コメント(0)
-
ケア・コンサルタント
東京おもちゃ美術館が、「おもちゃコンサルタント養成講座」という資格認定講座があります。これまでに、全国で5,000人を越える「おもちゃコンサルタント」が誕生しています。資格取得後、おもちゃの知識と遊び方を身に付けて、子育てに生かす方、おもちゃの専門店を立ち上げる方や、幼児教育や保育にいかす方など・・大学生からご高齢のシニアの方まで、様々な方が受講しています。(東京おもちゃ美術館説明)最近では、無印良品の店舗内で、東京おもちゃ美術館監修のもと、赤ちゃん木育広場に近い環境を再現しているとのこと。・・おもちゃに関心がある方は、どうか、周りの方にも、お勧めください。僕自身が、個人的に興味があるのは、「アクティビティ・ケア」という資格認定講座です。東京おもちゃ美術館館長の多田千尋さんは、他にも、芸術教育研究所所長、高齢者アクティビティ開発センター代表でもあります。「摂食」、「排泄」、「入浴」に加えて、「遊び」、「芸術」、「自然」を合わせた六大介護の推進をミッションとしている内容の深さです。「ゆりかごから墓場まで」の社会福祉への熱い想いと情熱を伝える・・新しい時代の旗手となるかもしれません。
April 11, 2013
コメント(0)
-
元気の出る朝
小田急線の下北沢駅が地下に移転したのに伴い、「開かず踏切」も無くなるとのこと。その現場に大勢の人が集まり、最終電車を見送り、消えゆく「開かず踏切との別れ」を惜しむニュースが流れていました。東急東横線渋谷駅も地下へ移転したとのこと。あのヨーロッパの鉄道駅のような始発終着フォームの佇まいが消えてゆくと思うと、名残惜しいものがあります。昭和の時代・・京王線、井の頭線を、よく通勤に使っていました。京王線の車掌さんが、ちょっとした勇気を出して、楽しい車内放送を流していたのを想い出します。「当列車、まもなく夢のパラダイス新宿駅に到着します。朝からの痛勤・・皆様、大変お疲れ様です。・・慌てず焦らず乗降に注意・・今日一日、頑張りましょう♪」・・そんなアナウンスを車内に流していたと思います。ちょっと元気の出る楽しい思い出が、甦りました。日本全国・・月曜日の朝から、元気よく朗らかにファイトです。
March 25, 2013
コメント(0)
-

彼岸の中日 春分日
仁和寺 五重塔東寺 五重塔春に種まきをしなければ、秋に収穫できません。同じく、善行を行わなければ、幸福を収穫できません。(真言宗開祖 空海)
March 20, 2013
コメント(0)
-

門跡寺院
昨日の京都地方・・あちらこちらの大学の卒業式が行われていました。社会人になると、楽しいことも、悲しいことも多くあります。社会人というよりも、単に生活を支えるために、年を重ねてゆくだけのことです。晴れ晴れとした門出に祝福です。御室と嵯峨、嵐山方面に足を伸ばしました。近くには、世界的にも有名な石庭のある龍安寺がありますが、個人的には、仁和寺本堂の内庭のが好いかな?仁和寺・・世界遺産、真言宗御室派の総本山です。888年(仁和4年)、宇多天皇は退位後に出家されて、仁和寺を住坊としました。御室御所とも呼ばれた仁和寺は、日本初の門跡寺院となりました。門跡寺院とは、明治維新まで、天皇または皇族皇子皇孫が住職に就かれた寺院です。もうひとつ、門跡寺院の旧嵯峨御所 大覚寺にも参りました。何十年ぶりかに眺めた・・左近の梅と大沢池です。門跡・・寺院やら芸道も含めて、企業やら家業を継ぐ者は、継ぐ苦労というものもあるでしょう。京都にオムロンという企業がありますが、御室を発祥の地として名付けられたようです。卒業生から新入社員となる若者へ・・。「させられていると思う仕事感覚」から、「百人に無償奉仕していると思う仕事感覚」へ。・・そう、思えばです。人生が、劇的に変化します。
March 17, 2013
コメント(0)
-
ケアという物語
今も、地球のどこかで、命が誕生して、老いて、病んで、死んでいく人間のドラマが展開しています。それを、ケアする・・、ケアしない。care・・不思議な言葉です。何を、いつ、どこで、誰に・・ケアするのか?何を、ケアする行為とみなすのか?辞書を開くと、日本語としてのケアの意味には、世話、介護、管理、維持、注意、用心、配慮、努力、心配、不安、面倒、負担、厄介、重荷等々・・とても気がかりな言葉です。「注意を払い、気を使うこと」・・でしょうか?その監督、維持、責任は、誰に誰が担うのでしょうか?赤ん坊・幼児・児童への世話、高齢者への介護、障害者への介助に対して、親、教師、介護者、医師、看護師等がケアの担い手になります。そのケアする行為に、虐待(ハラスメント)という状況が表われるならば、その背後に人間の限界線への歪みとなるジレンマ(delemma 精神的葛藤、板挟み)が、存在します。最近、「ストレスに弱い人間」「アトピー体質で敏感」とか、PTSD(心的外傷後ストレス障害=トラウマ)とか・・そんな言葉に、よく出会います。とりわけ、震災以後、ケアする対象は、「こころ」と「からだ」を含む「生活の再建復興」と「その方法」へと拡大しています。ケアという言葉に近い意味で、キュア(cure:治療)という言葉があります。ヒール(heal:癒し)という言葉もあります。ヘルス(health:健康)、聖なる(holy)・・語源は、Whole(全体性)という概念から派生しています。例として、ヒーリングアート(癒す絵)、ヒーリングミュージック(癒しの音楽)、ヒーリングタッチ(手当て)です。その他、マジック、トリートメント、セラピィ、サポート、ヘルプ、アシスト、チャリティ、フィランソロピィー、ナース、ジェネレイティピティ・そして、最後に「養生」・・というホメオスターシスという人間の蘇生という真髄を表現する言葉もあります。余談ですが・・それぞれの語源を知りたいですか?人間には、痛みがあります。痛みに対するケアには、苦痛を除去する、緩和する・・という発想があります。しかし、痛みを感じない「無痛症」を抱える人間もいます。痛みが無ければ、人間は長く生きることは、非常に困難だと言います。痛みを感じるということは、ストレスを感知して、自然治癒力を働かせる重要なサインです。(ストレスにも、有益ストレスと有害ストレスがあります。)つまり、ケアには「痛みを取り除く:緩和除去」と「痛みを感じる:感覚の回復再生」という二つの観点と役割があるのです。「この地上に生きている限り私たちの本当の名前はケアであり、言い換えれば、私たちは、本質的にはケアなのです。ケアは、私たちが生きている限り、私たちを所有している。私たちがケアすることをやめるとすれば、それは、私たちが人間であることをやめることである」(シスター・M・シモーヌ・ローチの言葉より)
March 13, 2013
コメント(0)
-

二の次
今日の福井地方は、快晴でした。でも、花粉が飛んでいます。・・中国からの黄砂やPM2.5は、どうなのかな?昨日は、3.11。心から・・合掌。咲く花は好かれて、飛ぶ花粉は嫌われます。黄砂やらPM2.5の公害汚染よりも、はるかに・・放射能汚染の方が怖いです。でも・・中国産と福島産の同じ食品が並んでいたならば、迷わず日本の「福島産」を買います。昨今、タバコを吸うと健康が損なう・・と言います。禁煙、肥満等の成人病対策・・でも、タバコを吸う人の自殺率は、非常に少ないとのこと。地元で仲良くしていただいている警察官OBの方が、先日、東京まで行かれたようで、お土産に国会議事堂で買われた歴代首相の似顔絵の入ったマッグカップとお菓子とを頂戴しました。それにしても、なぜ、マッグカップ・・?ペン立てにしようと思います。マッグカップを眺めならがら・・二の次を考えています。日本の初代首相は、伊藤博文・・では、第二代首相は、誰でしょう?日本で一番高い山は、富士山・・では、二番目に高い山は、何山?答えは、黒田清隆と北岳です。二の次、三の次を楽しめると、人生が美味しくなります。
March 12, 2013
コメント(0)
-
桃の花 百歳まで
花見と言えば、桜ではなく、かつては、梅だったようです。平清盛と同時代を生きた西行が詠んだ和歌・・「願はくは花の下にて春死なん、そのきさらぎの望月のころ」それ以降、日本人の花見への美意識と死生観は、桜を意味するようになりました。さて、それよりも以前の時代、中国伝来の思想として、梅よりも、桃には魔避けの力があるという考え方がありました。今日は、桃の節句・・お雛祭りです。桃の花を愛でたり、桃の花を浮かべたり、桃の葉をお風呂に入れたり、無病息災を願う禊ぎ祓いの「桃の節句」の日でもあります。お雛祭りは、女の子の厄除けと健康祈願のお祝いとして、お七夜やお宮参りと同じく健やかな成長を願う行事です。(草木や紙でヒトの形を作って、それで自分の体の悪い部分を撫でて、焼いたり、川などに流すことで厄払いを現在も行う神事があります。このときに使うヒトの形をしたものは「人形(ひとがた)」と呼ばれ、これが現在の「ひな人形」の始まりではないかと考えられています。)旧暦三月三日・・桃の季節でもあります。だから「桃の節句 」になったわけではありません。昔から桃には邪気を祓う力があるとされ様々な神事に取り入れられていました。節分に桃を使って邪気祓いをする神事も多数みられるようです。邪気祓いをする上巳の節句が桃の節句 になったのです。昔から邪気の象徴は、鬼とされておりました。節分には、鬼は外・・鬼を祓います。邪気を祓う力のある桃には、鬼を退治する力もあると考えられたのです。桃から生まれた「桃太郎」が鬼退治をする民話が、それにあたります。桃源郷となる原点をも意味します。桃は、不老長寿をも意味します。桃は、百歳(ももとせ)まで長生きできるように願う・・邪気祓い、魔除けの祝い花なのです。
March 3, 2013
コメント(0)
-
お水送り神事
春を告げる行事として、全国的にも有名な奈良東大寺二月堂の「お水取り」。その「お水取り」に先がけて、毎年三月二日に行われるのが、若狭の国、神宮寺(福井県小浜市)の「お水送り神事」です。和銅7年(714年)、遠敷明神(おにゅうみょうじん)を祀ったのが、若狭の神宮寺の始まりとされています。東大寺を開山した良弁僧正は、若狭の小浜の出身とされます。大仏建立には、当時若狭で修行中の渡来僧・実忠(じっちゅう)が招かれていました。天平勝宝4年(752年)、この実忠が、東大寺二月堂を建立し、修二会(しゅじえ)を開いて、「全国の神々を招きました。ところが、遠敷明神が、時を忘れて、遅刻します。そのお詫びに、本尊に供えるお香水を、若狭から送ると約束しました。二月堂の下の岩をたたくと、水が湧き出しました。この湧水に命名されたのが、東大寺二月堂の「若狭井」です。そのお香水は、今日から十日かけて、東大寺二月堂の「若狭井」に届くとされています。1200年以上も続く・・このような神事にして、奈良の東大寺二月堂の「お水取り」は 三月十二日に行われるのです。
March 2, 2013
コメント(0)
-
社会問題と社会化問題
はじめに、階級・階層に関わる社会問題である。階級・階層は、社会的地位だけではなく、生活を支える収入格差の問題でもある。生活上の質をも左右する・・この階級・階層の固定化が進展しており、貧富の格差により様々な社会問題が現われてくる。その一方で、社会化に関わる地域問題と呼ばれる社会問題である。労働問題、都市問題、農村漁村問題等・・同じ地域に居住する者が、共通して生じる社会化問題である。我々の生活は、家族・家庭内の生活で完結することは難しくなっている。さらに、社会層ごとの社会問題である。児童、障害者、高齢者といったカテゴリーを設定して、その共通した特質をまとめて整理した社会層問題である。生活というものは多面的で、どのように生活の貧しさを掴み、生活関係をどのように展開させていくのかという判断が求められる。
February 26, 2013
コメント(0)
-
貧困の発見
貧困が、個人的な資質の問題ではなく、社会が生み出す問題であるという認識が生まれたのは、19席末から20世紀初め、英国においての社会調査の結果が発端となった。当時、産業革命後、世界の工場となった英国市民の貧困状態が明らかにされる。チャールズ・ブースによる調査「ロンドンにおける民衆の生活と労働」という報告書がある。極貧とみなされる原因は、低賃金・無就業55%、疾病・高齢・多子家族27%、飲酒・浪費等18%という結果となったのである。さらに、英国全土の大都市における人口の30%が、貧困状態であるという衝撃的な結果が出たのである。明らかに、貧困の大部分が社会的要因なのである。当時、世界の名だたる大英帝国も。救貧政策を社会改良政策に転換せざるをえなくなったのである。これまでの貧困の概念が、より客観的な貧困の存在を発見・証明することになったのである。この20世紀初頭の英国での社会調査によって、最低賃金制度の確立、疾病・失業対策等の社会保険、社会事業というシステムが、生み出されていったのである。その後、二度の世界大戦間にもたされた世界的不況と、それに伴う大きな社会問題を生み出すことになった。
February 26, 2013
コメント(0)
-
貧困観
近代、早期に福祉国家になった英国においても、19世紀の1800年前半まで、経済的貧困状態は、個人としての資質に問題があると考えられていた。一般的に求められる生活習慣の欠如・・節約節制もせず、怠惰であり、能力の無さからくる落伍者の問題とも考えられていた。当時の救貧対象は、働くことのできない病人、高齢者、孤児等に限定されていた。働く能力がある者は、「怠惰」という理由で、強制労働が課せられたのである。慈善事業の救貧対象として、救済すべき価値のある貧民、価値のない貧民と区別したのである。日本においても、明治以降の原初の救済事業であった対象は、誰からも援助を受けられない孤立無援の者、高齢者、孤児等に厳しく限定されていたのである。それは、貧困問題は、個人的な問題、運命的な問題として考えられていたのである。
February 26, 2013
コメント(0)
-
福祉 生存権
憲法25条の生存権保障の規定に基く、国民に用意される社会的制度、施策である。「健康で文化的な最低限度の生活」を保障することが、生存権の保障と目的なのである。でも、健康で文化的な生活とは、どのような意味を持つのだろうか?生活権を保障するものではないのか?自らの力で、生活力が発揮できるための条件、基盤整理が必要なのでは?社会的な自立が強要される社会における昨今、経済的な自立が前提になる。しかし、経済活動に参加できる者のみに価値を見出すのには、市場化による生活の社会化となる。社会から、一方的に支配され、操作される生存権では、家族個人の生活力は弱まってゆく。生活の自立性が問われるのである。
February 25, 2013
コメント(0)
-
社会福祉の目的
社会福祉は、歴史的に生み出された制度である。社会には、さまざまな生活問題がある。生活問題とは、社会の構造上の不備矛盾が、個人の生活に立ち現れる問題である。その生活問題に社会的対応するのが、社会福祉である。しかし、すべての問題に、社会福祉が対応できるものではない。社会福祉は、社会問題対策のひとつとして、他の制度と結びつき展開されて機能するものである。対象となる生活問題の質・量によって、社会福祉のありかたが決まるのである。その個別な機能と目的を整理しなければならない。
February 24, 2013
コメント(0)
-
生活力 高齢者
近年、高齢者のみの世帯は、高齢者の独居世帯を含めて増加の一方である。生活基盤が脆弱な高齢者生活が増加しているのである。そして、要介護状態になった場合、このような高齢者世帯では、介護機能を発揮できないのである。こうした事態に対応できる社会福祉施設やサービスの整備が遅れているのである。介護に関わる環境の知識も不足している世帯では、高齢者虐待や介護心中という痛ましい事件も起きる。子供がいるとはいえ、その息子夫婦、娘夫婦にも家庭がある。親の扶養を充分できるとは限らないのが、現代の家族の実態である。老老介護、認知症患者の増加・・生き方よりも、死に方が、大きな課題となる社会問題なのである。世の中には、さまざまな生活問題を抱えた人々がいる。現代の社会福祉の課せられたものは何か?それを考えなくてはならないのである。・・社会福祉の目的なのである。
February 24, 2013
コメント(0)
-
養育・教育力
養育・教育の生活条件に不可欠なものは、各家庭の経済基盤である。夫がリストラされて、ローン、借金の返済に追われて、妻は、手のかかる子がいるのならば思うように働けない。夫は、生活破綻に意気消沈、再就職の道も険しく、自暴自棄。夫婦関係も悪化して、その捌け口が、子供に向かって、虐待にもなったら大変である。妻も離婚しても、経済的自立できる就職は難しく、交際相手が出来れば、その相手に依存せざるをえない。子供を引き取った場合ならば、尚更、親としての未熟さと自覚と・・それを補うサポート機関、生活支援システムの構築が必要なのである。・・労働問題、子育て問題を背景とする社会文化の豊かさ、貧しさが問われているのである。次は、高齢者をめぐる問題である。
February 24, 2013
コメント(0)
-
生活力 養育教育
加えるならば、生活力の減退と欠如に関わる問題も生じている。そのひとつは、養育・教育問題である。未成熟な親、無知な親、子育て能力が欠けた親が、増えている。炎天下に自動車の中に幼児を放置したままパチンコに興じる、子供が病気になっているのに放置、義父になつかない子供への虐待、子供の受験をめぐる怨恨・・殺人・遺棄等々・・枚挙に暇がないほど新聞記事を賑わせている。これらの問題の背後にあるのは、何だろう?生活力の欠如から生じる社会構造の歪みや貧しさを要因とする生活の手段、生活との関係、生活の条件を再構築する必要があるのでは?戦後の都市型生活様式のもとで育てられた若い親たちには、地域社会と隔絶された都市型住宅の中で育てられたのも要因ではないか?年上年下の異年齢集団の交流もなく、同年齢の子供同士とも十分に遊んだ体験がないのでは?子育てを身近に感じる生活環境を体験もせず、親になってしまっているのでは?さらには、子育ての基準レベルに達していない「わが子」を過度に敏感になる。メディアが煽る「素直でかわいい子」「頭のいい子を作る子育て」の躍らせて、「乱暴でかわいくない子」を受容できないのでは?気を病むような養育教問題も生活問題の一部であり、大きな問題である。
February 24, 2013
コメント(0)
-
生活問題 経済
介護保険制度に見られるように、今の日本において、社会保障、社会福祉の基礎構造改革による生活自助原則を掲げている。つまり、自己責任を前面に打ち出しているのである。社会的固定費の生活費負担に耐えられない者は、預貯金を崩し、ローン返済も難しくなり、自宅も手離し、その地域に住めなくなる。このような生活問題の状況において、社会福祉施策が有効に実行されなければ、ホームレスになったり、最悪は自殺行為に陥ることもある。とりわけ、高齢者や障害者の居る世帯には、このような危惧が多く、健康で文化的な最低限度の生活とは・・ほど遠い危険な社会になる可能性が高くなるのである。このような経済的な深刻な生活問題には、何よりも経済補償システムの有効化が、求められるのである。
February 24, 2013
コメント(0)
-
恵み二首
神主さんによれば、研修会で一堂に会して食事をする際は、次の二首短歌を唱和するとのこと。・・食前感謝のいただきます。たなつもの 百の木草も 天照す 日の大神の 恵み得てこそ・・食後感謝のごちそうまでした。朝宵に 物食う毎に 豊受けの 神の恵みを 思え世の人~出典:本居宣長「玉鉾百首」~
February 23, 2013
コメント(0)
-
生活問題 序章
バブル破綻のあと、1990年代には、国内産業は、空洞化の時代に入る。21世紀を迎えても、日本経済の動向は、益々混沌とする視界不良の状態である。経済的貧困格差が広がりつつある。生活の基盤となる雇用確保の困難、給与収入の停滞・・中小企業、大企業のリストラが行われる。終身雇用を前提とした住宅ローン、教育費、老後の生活プランは、破綻してゆく。さらに、若者の雇用問題・・大学新卒のの就職困難、再就職の道も険しい。たとえ採用されても、有期雇用、非正規社員の場合、労働条件の悪化、生活安定は困難。こうした経済的困難状態の中で、生活保障システムは機能せず、生活破綻も増加してくる。歴史的に、雇用不安、貧困拡大は、社会福祉と社会保障の最大の課題なのである。
February 23, 2013
コメント(0)
-
生活力
生活学研究において著名な一番ヶ瀬康子先生は、このように説明している。第1に、生活とは、生命活動の略である・・日常的継続性を伴う。それは、死に至るまで一瞬も休むことなく、一定のリズムを伴い展開するとのこと。その過程において成長が伴い、と同時に継続性が保持される。生命の保持であり、さらに生殖によって、次世代に継承される。第2に、生活とは、生存ではなく、人間の生活である。労働を基軸として、主体的に環境に働きかけて労働力を生み、次第に文化的、精神的なものを含めて多様な生産と創造が展開される。その意味で、生活力は、主体的創造的なものである。第3に、生活は、歴史的なものであり、社会的性格を含んでいる。それは、社会構成の状況、性格に規制される。資本主義における人間の労働力は、商品化され、商品としての価値えお媒介される。人間としての生活と生産事態が壊れてゆく。日常的継続性に問題が生じる・・生活問題である。
February 22, 2013
コメント(0)
-
仕事と生活
通常、仕事と生活は、対比される。仕事という労働時間以外の生活を、私的な時間となす。指摘な時間において、経済的生産価値は生まれない。だから、私的な時間は、消費的過程の時間である。労働時間で得た給与は、私的な時間・・私生活を支えるために消費される。維持している私生活は、過去と未来の労働時間の支えられているのである。労働時間と私的時間は、対比ではなく対極すべきものではない。生活という中の枠組みに組み込まれなければならないものである。では、生活力とは?
February 22, 2013
コメント(0)
-
日々の生活
日々働き、日々学び、日々寝て、日々食べて、ぼんやりしたり、音楽を聴き、誰かと話す。家族や友人と、日々触れ合う者あれば、外にも出ず、誰とも触れ合わない者もいる。この日常的な繰り返しを、生活と呼ぶ。この生活に生じる不幸に対応するものを、生活問題と呼ぶ。個人的な問題ではあるが、社会との関係で生じてくる問題でもある、生活とは?生活問題とは?その現状を探っていく。
February 21, 2013
コメント(0)
-

アマゾンやら楽天気分?
楽天とアマゾンの売上高の年々の数字をみていると、右肩上がりの急斜面。既存の小売店の売り上げの展望は、ますます難しくなる一方です。小生、ネットやら通信販売で、モノを買うことがありません。先日、イタリア製のデロンギ(メーカー名)を買って参りました。ヨーロッパ暮らしの寒さ対策で、一番役立ったのが、デロンギの温暖器でした。それ以来、もう20年以上も使っていたデロンギですが、とうとう壊れてしまいました。本当に、よく働いてくれました。・・ありがとうです。部品も無いということなので、電気店で、新製品を買いました。新しいデロンギです。・・嬉しいなぁ!ところが、ネット販売だと、もっと安く購買できることを知りました。楽天やらアマゾン、ディスカウントショップ、100円ショップの存在が、これだけ大きくなると、デフレからの脱却は、難しいのでは?息子曰く・・ほとんどネット販売でモノを買っているとのこと。車のトランクに積んでいるウーファー(スピーカーユニット)やらスロットマシーンも買ったとのこと。・・何か、役立つのかな?楽天気分で、アマゾンが流れるジャングルに入るようなもの・・人生は、ポーカーゲームのようなものかな?・・とは言えです。もしも、今後、店舗を構えて生き残る道を探るのならばです。・・これも、時代の流れなのでしょうか?
February 21, 2013
コメント(0)
-
観光立国
~昨日の日本経済新聞「春秋コラム」より:「富士山を国立公園に、瀬戸内海を一大遊覧地帯にして、世界中から外国人客を呼び込めないものか」。日露戦争が終わったころ、木下淑夫という鉄道官僚は、留学先の米国でそんな構想を立てて政府に建白書を送った。のちに現在のJTB創立の中心になった人物だ。~今も昔も、このような人物・人材は、必要なのかもしれません。
February 21, 2013
コメント(0)
-

百面相 白山信仰
以前、この時季・・我が家の窓から、白山(はくざん)を仰ぎ見ることができたのです。・・が、最近、近所に、高いビルやら出来て、全く見えなくなりました。残念です!ほんとうに、真っ白い山なのです。日本三霊山のひとつです。富士山、立山、そして・・白山です。白山信仰というのがあります。日本各地にある白山神社は、約3000社が鎮座するとか。とりわけ、東日本では、被差別地区にあるとか・・これに関して述べるのは、江戸時代の身分差別に関わるタブーにも触れることになるので気が滅入ります。室町時代までは、士農工商という身分制度はなく町人が刀を持っていたこともあります。白山信仰の開祖は、泰澄大師・・越前の人で、渡来人の子であったといいます。泰澄は、700年頃、白山で修験道の修行を行い、白山信仰に仏教的な意義付けをしたのです。白山信仰は、奈良時代から中央貴族の間で盛んとなり、京都の醍醐寺にも白山信仰が受け継がれています。三宝院には、白山権現を祀る社があるとか・・、山上には白山遥拝所があるとか・・。天台宗比叡山にも、曹洞宗永平寺開祖道元とも深い関係があります。さて、昨日、天台宗百済寺の写真をアップしましたが、百済寺と同じく天台宗比叡山、鞍馬山・・ずっと西へ行くと朝鮮半島にある韓国の百済寺、東は、熱田神宮と線を結べば、北緯35.1度線上に位置するとのこと。天台宗開祖、最澄は、近江国で渡来系の三津首百枝(みつのおびと・ももえ)の子として生まれています。一方、高野山真言宗開祖の空海(弘法大師)の母親も渡来人だとのことです。飛鳥とは、鳥が飛ぶこと・・朝鮮半島の百済人が、亡命・渡来して文化が倭国に伝わったことを意味しています。大化の改新(645)は、絶大な専横権力を持つ蘇我氏一族を倒した中大兄皇子(のちの天智天皇)や中臣鎌足(藤原家祖)による政権交代です。蘇我氏など飛鳥の豪族を中心とした政治から天皇中心の政治へと変化が始まります。日本初の元号(大化)律令制国家の始まりです。社会の歴史で習った・・公地公民制、国郡制度、班田収授の法、租・庸・調等々の始まりです。これらの政策導入に百済人が大いに関わっているのです。その百済国が、660年、唐と新羅に滅ぼされます。663年(天智2年)8月、日本書記によると、天智天皇の時代、朝鮮半島の白村江(はくそんこう)で、百済再興のため倭国・百済復興軍の連合軍と、唐・新羅連合軍との間で海と陸の戦いが始まりました。白村江の戦いです。戦いに敗れた倭国は、亡命・帰化・・渡来人の力によって改革が急速に進みます。唐の国に傾く革新勢力と保守勢力との軋轢・・各地に朝鮮式山城を築き、主に、東国の農民を徴収して、約三千人の防人(さきもり)を配備します。さらに、壬申の乱以降、より強力な中央集権体制となります。701年の大宝律令制定により、倭国から日本へと国号を変えたのです。百済は、日本の歴史の源泉となるキィ・ワードのひとつなのは、間違いないのです。今も昔も、隣国との関係は、難しいものです。隣国の中国や朝鮮から「倭国」と呼ばれるのが嫌だった大和朝廷は、701年、大宝律令によって、隣国に向けて「日本」と名乗るようになったのです。さて、白村江の戦いと白山信仰の関わりですが・・何か関係?漢字文化の歴史も百面相です。
February 19, 2013
コメント(0)
-

百済寺
百済寺は、地上の天国。四季百彩に包まれた「地上の天国」というパンフへの説明文もあります。1400年昔、呼び名の通り、推古天皇の時代に聖徳太子の御願により、百済(くだら)人のために創建された近江の国の最古級の古刹です。時代は、移り変わり・・。この百済寺(ひゃくさいじ)の未来も、万全ではありません。寺院神社の運営も、大変な時代になりつつあります。息子よ、這い上がって来なさい。毎日、何とか生きていれば、何とかなる。天候がよければ、見晴らしが抜群の「喜見院の庭園」からの遠望です。名神高速道、新幹線も見えて、琵琶湖の湖面の向こうには、湖西の比叡山に列なる山並が眺めることができるのですが・・。廻遊式の庭園を巡りながら、のんびりと時間を過ごしました。途中、彦根経由で帰福へ。人力飛行機による鳥人間コンテスト大会の舞台となる桟橋ピアです。百済寺は、地上の天国だったかな・・?。判りません。でも、上機嫌で、微速前進です。
February 17, 2013
コメント(0)
-

親子詣り
琵琶湖東側の近江山中へ、息子に運転を任せての参道ドライブでした。多賀大社です。時々、吹雪いて、一寸先は真っ白な見えない世界でしたが、楽しかったです。人間は、褒めて褒めて、育てる術もあります。が、褒められて育つ人間は、世間体ばかり気にする人間になるかもしれません。怒られてばかりの人間は、どこかの部分に、自信を無くすのでしょう。一寸先も真っ白な見えない雪の世界・・堪忍観が頼りです。その後、百済寺へ。
February 17, 2013
コメント(0)
-
流れ星 尾行
天から、隕石が落ちて来たという・・ロシアからのニュース。今、人生が幸福な人にとっては、怖い話です。地球が爆発して欲しいと思うぐらい人生の苦渋の真っ只中にいる人にとっては、心の重石が少し取れたかもしれません。昨日、よく買い物に行く近所のスーパーで、84歳の女性がバッグを盗んだという窃盗の疑いで現行犯逮捕されました。この84歳の女性・・住所不定、置引きの常習犯のようで、兵庫県県警の捜査員が神戸から福井まで、ずっと尾行していたようです。ホテルに宿泊しながら、各地を転々としていたようです。被害者にとっては、怒り心頭でしょうが・・84歳という高齢を考えれば、何とも逞しい生き方なのかと感嘆します。冷暖房完備、三食保証付きの留置場、もしくは刑務所暮らしを望んでいたのかもしれません。
February 15, 2013
コメント(0)
-

照日の前
・・冬ごもりです。目が、やはり痛いです。心臓も、圧迫感があります。この身体、体の継ぎ目・・何とかならないものかな?でも、気持ちは、和やかです。これぐらいの薄い雪景色の眺めながらの散策は、穏やかな気持ちにしてくれます。近所の散策コースにある北の庄跡(柴田神社)です。柴田勝家、お市の方(織田信長の妹)の終焉の地なのです。因みに、新田義貞の終焉の地も、福井にあり、新田塚という地名もあります。ここは、敗者と終焉の地?・・そう考えれば、マイナス思考になります。ここは、子供の頃から憧れていた雪降る街です。この雪降る世界は、楽しいです。嬉しいです。これぐらいの雪景色ならば、感謝です。いつも、気持ちを新鮮にしてくれます。さて、さてと・・プラス思考です。もともと、織田家の祖先は、福井の織田(おた)村の神官でした。そして、この場所から、お市の方の三人姉妹が、この国の歴史の表舞台に躍り出たのです。もっと古くは、現皇室の祖とも考えられる継体天皇は、この越前の地から旅立ったのです。花筐(はながたみ)・・世阿弥。冬ごもりは、春にかかる結び目の季節です。今日は、建国記念日です。
February 11, 2013
コメント(0)
全1417件 (1417件中 1-50件目)