2013年01月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-

★誰のために就職活動していますか? その4
★誰のために就職活動していますか? その4本気で取り組むとなにが変わるのか。今日は行動面ですが、昨日志望動機のお話をしたついでに履歴書でご説明します。本気で就職活動に取り組むと、出来るだけ一番良い自分を伝えたいと考えるようになります。そうなると、履歴書の書きかたも変わります。出来るだけ丁寧に書こうとするでしょう。字が少しいびつになってしまったとか、インクがすれて紙が汚れてしまったら書き直します。大変ですけど、また一から書き直し。自分が納得出来る履歴書が書けるまで何度も書き直すようになります。だってその会社に採用されたいからです。これを、恋愛に置き換えてみるとわかりやすいかもしれません。好きな人にラブレターを書くとしたら最高に上手に書けたものを渡したいと思いますよね。誤字があったり、コーヒーのしみが着いたようなラブレターを渡そうとは思わないでしょう。それと同じことです。でも、しょうがなく就職活動していれば、ここまでの思い入れはありませんから、どうても「まぁ、こんなもんでいいか」となりがちです。そして、そのまま提出⇒結果不採用となります。これが続くと、益々就職活動のやる気が無くなってくるのは当然のことです。だから、ここで本気で就職活動に取り組んでみましょう。ここまで読んでも、どうしても本気になれなかったらどうしたらいいのか。ご安心ください。下記のサイトをご覧になれば恐らく本気になれると思います。【我武者羅応援団】http://www.youtube.com/watch?v=6TLSVrynIu8人気サイトランキングへにほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村就職活動・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
2013年01月31日
コメント(0)
-

★誰のために就職活動していますか? その3
★誰のために就職活動していますか? その3お早うございます。今日も皆様にとって良い1日になるますように。昨日、本気で取り組むと志向が変わるというお話をしました。その結果、一つの例として志望動機が書けるようになるということをお伝えしたのですが、少しわかりにくかったかも知れませんので、違う例に例えてみます。恋愛で考えてみましょう。あなたに、好きな人がいたとします。そしてその人に告白することに決めました(そういれば、もうすぐバレンタインですね)。その時、自分の伝えたいことははっきりしているでしょう。ただ、どの場面で、どんなことを言うかは色々と迷うので、友達に相談したりアドバイスをもらうこともあると思います。それと同じで、応募したいと思う会社があれば、なぜ応募したいと思うようになったのか、その会社でどんな仕事をしたいのかという気持ちや思いははっきりしているでしょう。それをどのように伝えるか。効果的な伝えかたについては先生や友達に相談したり、就活本を参考にすることもあると思います。応募しようという意思がないのに応募しなければならないとき、志望動機は書けません。「好きでも無い人」に告白しろと言われたら、なんて言えばいいのだろうと悩むのと同じです。私は、「履歴書やエントリーシートの志望動機が書けない」という相談を受けるとき、「この会社(公務員の場合は行政機関)を応募しようとしているけど、それはあなたの意思なの?」と質問します。するとたいていの場合、親から言われたとか、友達も受けるから一緒に受けてみようと思ったとか、練習の積もりで取り合えず受けようと思ったという返答が返ってきます。あなたがもし、ある会社の人事担当者だと仮定して、このような動機で応募してきた人を採用しますか?自分で「こんな人なら採用しない」と思ったならば、当然人事担当者だって同じように思うはずです。不採用になるのは目に見えています。仮に、それで内定されたとしましょう。その時は「ラッキー」と思うかもしれませんが、これって、ただ問題を先送りしただけなんですね。年が変わって晴れて入社。そして、実際に現場に配属されます。しかし、すぐに退職してしまいます。まぐれで採用された会社ですから、その会社や仕事に思い入れやこだわりはありません。ですから、ちょっといやなことやつらいことがあれば「辞めます」となってしまいます。昨年、私が実際に面談した人では、4月に入社して3週間で退職した人がいました。その前の年、おととしには1週間で退職という人もいました。だから、内定を取ることを就職活動の目標にしてしまうと、取り合えず受かればいいということになり、どうすれば受かるかというテクニック重視になります。自分が「これから社会のなかでどのように働いていくのか」ということを考えるのが就職活動の第一歩ですから、常に『自分が』ということを意識してください。明日は、行動面の変化についてご紹介しますね。 ~~~~ つづく ~~~~人気サイトランキングへにほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村就職活動・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
2013年01月30日
コメント(0)
-

★誰のために就職活動していますか? その2
★誰のために就職活動していますか? その2今日もこのブログをご覧くださり、ありがとうございます。本気で取り組むとなにが変わるのか。まず思考面が変わります。自然に、自分で物事を考えるようになります。自分で考えるとはどういうことか?わかりやすい例をあげると「志望動機」です。よく志望動機が書けないという相談を頂きます。これって、私からすればとっても不思議な相談です。だって、何かきっかけや理由があるからその会社を(行政機関の場合もありますが)応募するわけであり、志望動機が書けないということは「とくに応募するきっかけや理由はないけど応募したい」と言っているわけですよね。このような状態では、そもそも応募すること自体に無理があります。本当に自分の意思でその会社なり団体組織に応募しようと考えているのであれば、志望動機が書けないはずはありません。ただし、志望動機が「書きたいことははっきりしているけど、それをうまくまとめられない」とか「私の考えていることを、どのように書いたら一番わかりやすく伝わるか(表現できるか)」という相談なら話しは別ですけど。志望動機が書けないとか思い浮かばないということは、親の勧めとか、友達が受けるから自分もとか、有名企業だからとり合えず応募したら受かるかも、程度の動機しかないからでしょう。しかし、真剣に就職活動に取り組むようになると、まず志望動機が書けないということが無くなってきます。なぜなら、応募先を選ぶところから考えかたが変わってくるからです。求人情報を見たり、合同企業説明会で会社の説明を聞いたとき「この仕事は私のやりたい仕事だろうか」とか「この会社では、私のやりたいことが出来るだろうか」という視点で会社を判断するようになるからです。そして、この会社で働きたいとか、この仕事をやってみたいという気持ちになれば、それを素直に伝えるよう自分なりに志望動機を考えるようになります。こうなると、同じ志望動機の相談でも「書くことが思い浮かばない」というような内容が「書きたいことが、うまくまとめられない」とか「どう書けばわかりやすく自分の伝えたいことがうまく表現できるか」という相談に変わってきます。次に行動面です。それは明日のブログでご紹介しますね。今日一日、あなたにとって素晴らしい一日になるよう心よりお祈り申しあげます。 ~~~~ つづく ~~~~人気サイトランキングへにほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村就職活動・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
2013年01月29日
コメント(0)
-

★誰のために就職活動していますか? その1
★誰のために就職活動していますか? その1今日も当ブログをご覧くださりありがとうございます。今週も良い1週間でありますよう心よりお祈り申し上げます。長野県工科短期大学の先生や一緒に行った講師の方、堀内精工の矢嶋工場長とお話をして話題になったことです。それは、誰のために就職活動しているの?と質問したくなるような就活生が多いということ。あなたは誰のために就職活動していますか?お父さん? それともお母さん? 学校の先生でしょうか?それとも友達のため?就職活動は、ぜひ自分のためにして欲しいと思います。そんなの当たり前じゃないか!と思った方は大丈夫。これから先は読む必要はありません。でも、「えっ」と思った人がいたら要注意です。それだけ「親がうるさいから」とか「友達が(就職活動)しているから」という理由で就職活動している人が多いということです。自分の意思ではなく、言われたり周囲に合わせて就職活動しているわけですね。だから志望動機があいまい。自己PRもできない。当然、内定も得られない。就職を自分の事と真剣に受けとめて就職活動している人と、しょうがなく就職活動している人が同じ結果になるはずがありません。勉強も同じですね。真剣に勉強すれば、ちゃんと成績が上がります。就職活動も一緒です。真剣に就職活動に取り組んで内定が出ないはずはありません。ただし、気をつけて欲しいことがあります。真剣に勉強してもそれが身について成績が上がりだすまでには時間が掛かります。それと同じで、真剣に就職活動に取り組んでも内定を得られるようになるまでには時間が掛かる。だからと言って、なにもしなければずっと今のままです。結果が出るまでに時間が掛かるからこそ、早く真剣に取り組むことが大切ですね。今から始めても大丈夫。充分間に合います。ぜひ「自分の事」という自覚を持って就職活動に取り組みましょう。じゃあ、真剣に就職活動に取り組むとなにが変わるのか。それは、明日のブログで。 ~~~~ つづく ~~~~人気サイトランキングへにほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村就職活動・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
2013年01月28日
コメント(0)
-
★採用担当者はドコを見ている 後編
★採用担当者はドコを見ている 後編有限会社堀内精工の採用担当者である矢嶋慶一工場長による「採用担当者はドコを見ている」という就職活動中の方を対象に開かれた就職支援の講座の続きです。【礼儀やマナー】堀内精工の場合、精密部品の製造のため社内土足厳禁となっているそうですが、応募者の方が来社された場合玄関まで出迎えて応募者の靴の脱ぎ方やしまい方を見ているそうです。「靴くらい、きちんと脱げないような人にもっと難しいことを教えても身につかない」ということらしいのですが、このように入社時の様子を評価の判断材料としている企業は多いですね。私の知っている会社では自動車で訪問した場合、駐車場のクルマの停め方を選考基準に入れているところがあります。【企業研究】応募してきた人に当社の印象を尋ねると、きちんと答えられない人が多いとおっしゃっていました。企業研究や業界研究が不足しているのでしょう。これは、私も模擬面接の面接官をして痛感していることです。例えば事務職を希望される場合。求人情報に「経理事務」と書かれていたとします。面接で、「経理事務とはどんな仕事だと思いますか」とか「経理事務を遂行するうえで大切なこと、気をつけなければならないことはなんだと思いますか」と質問するときちんと返答できます。しかし「当社の主力商品はご存知ですか」とか「当社が力をいれている分野をご存知ですか」と、その会社の業務について質問した場合返答できない人が多いですね。つまり、自分のやりたい仕事には興味があるけど、その会社そのものには興味がないということです。【野心】この会社で将来どうなりたいのか、将来どのような仕事をしたいのかを必ず質問するそうです。野心という言葉を使っていらっしゃいましたが、この野心があるかないかで入社後の成長スピードが違うとおっしゃっていました。これは女性でも同様だそうです。将来の目標とかビジョンが明確な人ほど成長スピードが早い。反対に、将来どうしたいのかがあいまいな人はあまり伸びないとのこと。【誠実さ】正直に自分を伝えること。当たり前のようですが、これはなかなか難しいことです。つい、自分をより良く見せようと背伸びをしてしまいがちになります。自分の良いところをアピールすることは大切ですが、あまりにも背伸びして実力よりもかけ離れたことを話せばウソになります。たとえば「○○○ができるように出来るだけの努力をしたいと思います」と言えばOKですが、「○○○なら、たぶん出来ると思います」と言ってしまうとNGですね(本当に出来る自信があればOKですが)。お話をうかがって思ったことは、結局就職活動にマル秘テクニックというようなものはなく、地道にコツコツと活動をしていくことが大切だと感じました。焦らず、慌てず、休まず。自分のペースで構いませんから、地道にコツコツと就職活動に取り組んでいきましょう。次回の更新は28日(月)です。では、みなさん良い週末をお過ごしくださいね。
2013年01月25日
コメント(0)
-

★採用担当者はドコを見ている 前編
★採用担当者はドコを見ている 前編1月17日(木)長野市で、有限会社堀内精工の採用担当者である矢嶋慶一工場長を講師に「採用担当者はドコを見ている」という就職活動中の方を対象に開かれた就職支援の講座がありました。この日、時間をとって矢嶋工場長のお話をうかがうことが出来ました。矢嶋工場長は自己紹介で「採用活動に携わって30年以上になるが採用に「絶対」は無い」とおっしゃっていました。面接試験で「この人なら大丈夫」と思って採用しても実際に現場に配属するとあまり有能ではなかったり、反対に「あまり期待して採用した訳ではなかったが、数年経った今では基幹社員になっている」ということもあるそうです。30分の面接だけで人と評価するということは、それだけ難しいのでしょう。今日は矢嶋工場長からうかがったことをいくつかご紹介したいと思います。【自己PR(自己アピール】)矢嶋工場長は面接で自己PRをしてもらうそうですが、そのときありきたりの話しではなく、その人らしさが感じられるものが印象が良いと話しておりました。以前応募された方のなかに「声が良く通る」ことを自己PRされた方がいるそうです。そのため、選挙になるとウグイス嬢(選挙時に広報車に乗って立候補者の名前等を連呼する人)の依頼を受けているとエピソードも交えて話されたそうですが、製造業なので声が良いことが直接仕事にはつながらないが選挙のときになると何度も依頼されるということはそれだけ頼りにされていること、つまり人から信頼されている証拠。だから採用したとおっしゃっていました。【面接時の姿勢】面接時に面接官が質問して返答を考えているときに多少視線が下を向く位ならば問題ないが、なかには下を向いてしまう人がいる。面接もコミュニケーションが大切だから、完全に下を向いてしまうようだと印象は悪いとのこと。【質問に対する沈黙】上記の「下を向く」と似ているのですが、質問して返答を考えるときに急に黙り込んでしまう人がいる。やはり面接はコミュニケーションが大切だから、もしそのような場合「少し考える時間を頂けませんか」とか「緊張してすぐ返答できないので少し考えさせてください」と返答することをアドバイスされていました。確かに急に黙り込まれると、質問した側(面接官)からすれば、考えているのか、それとも聞こえなかったのか判断がつかないでしょう。【「なんでもやります」は逆効果】やる気をアピールする積もりで「なんでもやります」という発言をされる人がいます。このような人はあまり採用したくないと、矢嶋工場長はおっしゃっています。なんでもやりますという人ほど、実際に仕事をさせると「これは○○○だから無理」とか「あれは○○○だから難しい」といって結局何もしないことが多いそうです。どうしてもこの仕事がしたいとか、ぜひこれをやらせて欲しいという思いがやる気や熱意であって、仕事ならなんでもいいということは当社の仕事でなくてもいいのではないかとも受けとめられるようです。 ~~~~ つづく ~~~~人気サイトランキングへにほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村就職活動・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
2013年01月24日
コメント(0)
-

★「面接講座」で聞いたお話
★「面接講座」で聞いたお話今日もこのブログをご覧くださり、ありがとうございます。1月16日、長野県上田市にあります長野県工科短期大学にお招きいただき、就職対策講座「面接講座」に私ともう一名で参加してして参りました(二人で講師を担当)。写真のとおり、14日から降り続いた雪が多くて、駐車場には雪の山がいくつも出来ていました。講座は、午後1時から5時までの4時間、途中10分の休憩が1回のみというかなりハードな内容です。最初1時間ほど面接のポイントを説明、その後、全員でグループディスカッションを行い、そのあと代表者による集団面接、そして個人面接と続けました。4時間通しの講座なので、終わったあと学生の皆さんはかなりヘロヘロなのかと思いましたが、質問が相次ぎ5時半過ぎまで会場から出られない状態でした。担当の先生からも「普段の授業の様子から考えると、これだけ質問が出るとは思いもしなかった」とおっしゃっていましたが、それだけ学生の皆さんが面接に対して不安感を強く持っていることがうかがえました。そこで学校の先生や、一緒に参加されたもう1人の講師の方とのお話のなかで私が聞いたことを二つご紹介します。その1[履歴書は両手で渡そう]これは私も気付かなかったことですが、ある会社では応募した学生から履歴書を受け取るとき、両手で渡さない学生はその時点でマイナス評価をしているそうです。履歴書は自分自身の分身であり就職活動においては、命の次に大切なもの。それを片手で相手に渡すようでは、採用後現場に配属したとき、丁寧な仕事は出来ないと判断されるそうです。ですから、今後履歴書やエントリーシートを採用担当者に直接手渡す機会があれば、必ず両手で相手に渡すようにしてください。その2[スーツのフラップ]男性用のスーツには、両側の腰の辺りにポケットがあります。そして、そのポケットにはフラップ(雨蓋)が付いています。雨蓋という位ですから、スーツの外側出しておくのが基本ですが、これをわざわざ中に入れている人がいます。モノを出し入れしているときに入ってしまったのではなく、意図的に入れている。どうやら中に入れるほうがカッコイイというウワサが流れているようですね。実際、この学校でも数名の学生がそのようにしていました。そしてフラップを出すように私が助言すると、「(フラップを入れている)このほうがカッコよくないですか」と、言われてしまいました。この学生との会話で気付いたことは、そもそも採用担当者はマナーからその学生の社会性を判断しています。したがって、他人からどう思われるかという視点が大切なのですが、この学生は自分がカッコよければそれでOKと考えている。ここですでにズレが生じています。たかが、スーツのフラップと思われるかもしれませんが、その表に見えることよりも、この学生の思考面で「未熟だなぁ」と感じてしまいました。スーツのフラップは、キチンと外に出しておきましょう。時々、このような就職活動にまつわる都市伝説的なウワサ(当人の思い込み?)が流れることがあります。以前も「履歴書にプリクラを貼ると採用される」という話をご紹介したことがあります。【11月5日のブログ】学生(友達)から聞いた話とか、ネットで得た情報はあまり鵜呑みにしないほうが無難でしょう。それが全部間違っているとは思いませんが、情報を発信している人が思い違いをしたり誤解している可能性は充分考えられます。よくわからない場合は、ゼミの先生やキャリアセンターの担当者に確認することが大切です。怖いのは、最初に間違って覚えてしまうとそれが当人にとって当たり前になってしまい、本当のことや事実に直面したときに、それが違っていると判断してしまうことです。人気サイトランキングへにほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村就職活動・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
2013年01月23日
コメント(0)
-

★2015卒生との面談 後編
★2015卒生との面談 後編今日もこのブログをご覧くださり、ありがとうございます。昨日の続きになりますが、2016卒生との面談から、どのようなことを履歴書やエントリーシートに書けば有利になるか、差別化できるかというノウハウやテクニックを駆使することが就職活動だと、普通に受け止めてる学生が多いのではないかと思いました。それに対して就職活動は、自分の長所や興味はなにか。それをどの会社で、どのように活かすか。また、自分が働いてみたい会社はどのような会社で、どこに関心を持ったのか。前半は自己理解といわれ、後半は企業研究とか仕事理解といわれるものです。このようなプロセスを通じて、少しずつ学生から社会人へとシフトしていくことが就職活動だと思うのですが、そのようなことは一切スルーして、入りたい会社にどうやって入社するかを競うことが就職活動だと考えているように感じられました。確かに内定を取ることが就職活動の目的とすれば、面倒な自己理解や企業研究はやめてしまい、内定を取れる方法だけ学べばいいということになります。しかし、その結果が入社後の早期離職になっていることも事実です。【文部科学省 新規学卒就職者の在職期間別離職率の推移】http://www.google.co.jp/imgres?q=%E6%96%B0%E8%A6%8F%E5%AD%A6%E5%8D%92%E5%B0%B1%E8%81%B7%E8%80%85%E3%81%AE%E5%9C%A8%E8%81%B7%E6%9C%9F%E9%96%93%E5%88%A5%E9%9B%A2%E8%81%B7%E7%8E%87%E3%81%AE%E6%8E%A8%E7%A7%BB&um=1&hl=ja&sa=N&tbo=d&biw=1036&bih=598&tbm=isch&tbnid=6e_A-blPvQQsXM:&imgrefurl=http://xn--ebkua185u6l1bknxa.biz/archives/category/%25E3%2580%258C3%25E5%25B9%25B4%25E3%2581%25A73%25E5%2589%25B2%25E8%25BE%259E%25E3%2582%2581%25E3%2582%258B%25E3%2580%258D%25E3%2580%258C7%25E3%2583%25BB5%25E3%2583%25BB3%25E3%2580%258D%25E3%2581%25AF%25E6%259C%25AC%25E5%25BD%2593%25E3%2581%258B%25EF%25BC%259F&docid=Rh8CINoSWWXGSM&imgurl=http://xn--ebkua185u6l1bknxa.biz/wp-content/uploads/2012/04/753.gif&w=649&h=868&ei=4OL0UJ3BAomhkQW_xoG4Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=217&dur=1040&hovh=260&hovw=194&tx=81&ty=202&sig=100607211389811178219&page=1&tbnh=128&tbnw=96&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:10,s:0,i:110入社してから実際どのように働くのかが本当は大切なのですが、とにかく内定を取ればいいとなってしまうと「働き出してから、こんなはずではなかった」となり、やがて退職してしまうのでしょう。大変かもしれませんが、自分を見つめ自分自身を良く知ることが就職活動のスタートであり、原点になると思います。人気サイトランキングへにほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村就職活動・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
2013年01月22日
コメント(0)
-

★2015卒生との面談 前編
★2016卒生との面談 前編今日もこのブログをご覧くださり、ありがとうございます。このブログも1年を経過しました。1年間のお付き合いに心より感謝しています。そして、この1年を振り返りつつ、今年の就活生の傾向に触れたいと思います。1月14日に、東京で長野県が主催した「ふるさと合同企業説明会」がおこなわれました。【長野県公式ホームページ】これは、長野県商工労働部労働雇用課雇用対策係が中心となり、長野県出身で首都圏の学校に進学した学生のUターン就職を支援するために開かれた合同企業説明会です。対象は25年卒生と26年卒生の両方となります。このとき、私も就活生の相談に対応するために会場におりました。ここで5名の26年卒生(全員大学生)と面談しました。ここで複数名の学生から「履歴書の志望動機」の書きかたについて相談がありました。応募したい企業があるが、志望動機が思い浮かばず、どのように書けばいいのかという相談です。「どのように書けば有利になるか。他の学生に差別化できるか」と、ズバリ切り込んだ質問をした学生もいました。近くに多くの企業の人事担当者の方々もおり、話しに聞き耳を立てている気配を感じたので、その場では言いませんでしたが、私は内心このような先にテクニックありきの就活はまずいだろうと思いました。もちろん例年同様の質問を受けることがあります。しかし、合同企業説明会会場で近くに企業の人事担当者が聞いているにも関わらず、このような質問をされたことはこれまでありませんでした。ここからは、私の憶測になりますが、どのようなことを履歴書やエントリーシートに書けば有利になるか、差別化できるかというノウハウやテクニックを駆使することが就職活動だと普通に受け止めてる学生が多いということなのでしょう。自分の長所や興味はなにか。それをどの会社で、どのように活かすか。また、自分が働いてみたい会社はどのような会社で、どこに関心を持ったのか。前半は自己理解といわれ、後半は企業研究とか仕事理解といわれるものです。このようなプロセスを通じて、少しずつ学生から社会人へとシフトしていくことが就職活動だと思うのですが、そのようなことは一切スルーして、入りたい会社にどうやって入社するかを競うことが就職活動だと考えている学生が多いということなのでしょうね。 ~~~~ つづく ~~~~人気サイトランキングへにほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村就職活動・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
2013年01月21日
コメント(0)
-

★2012年12月のお話 後編
★2012年12月のお話 後編15日のブログでは、就職活動を継続することの大切さについてご説明しました。そして、就職活動を続けるということは、実際に応募することであり、応募しようかどうか迷ったらまず応募する。そして、内定を得てからそこに勤めるか、それとも辞退するか考えるようにしましょう。今日は、もう一つの精神的強さについて触れたいと思います。「就職活動が人生初めての挫折」という学生が多くなりました。これは決して大げさな話しではなく、今の学生の置かれた状況や背景を考えると無理もないでしょう。ゆとり教育の導入により、生徒の評価方法が変わりました。競争を通して個々の生徒の力を伸ばそうという視点から、生徒一人ひとりの個性を尊重してなるべく競争とか順位付けをしないようになりました。また、偏差値が今まで以上に重視され、中学から高等学校、高等学校から大学への進学にあたり、先生も生徒に無謀な応募をさせず、合格圏内の学校しか受験させないようになりました。そのため、これまでの人生で人と比較されて自分の能力を問われるとか、不合格の通知をもらうということが無くなりました。しかし就職活動は、企業から見れば何名応募してこようが必要な人材だけ確保できれば良いわけですから、それ以外の応募者は不採用とせざるを得ません。そこで大量の不採用者が発生します。この不採用の通知を何通も受け取ると、これまで体験したことのない挫折を味わうようになります。だから就職活動を諦めてしまう学生も少なくありません。しかし、この就職活動を続けていくことで打たれ強くなります。挫折を乗り越えたわけですね。そうなると、入社してから仕事が思うように行かなくても既に挫折を味わっていますから、簡単に諦める(退職する)ことが少なくなります。このような強さを持った人材を企業は求めていますから、就職活動を通じて得た精神的強さもアピールポイントになるわけです。企業に応募し続ける⇒不採用が続く⇒それでも諦めずに応募していく⇒精神的に強くなる⇒その強さ、タフさを企業が評価するだから、就職活動を続けることが大切になります。昨年から支援してきた3名の学生のこれまでの1年間を振り返って、継続することの大切さを私も再認識した次第です。もし、保護者の方がこれをご覧になっていらっしゃるなら、ぜひともお子さんに、不採用が続いても就職活動を継続することの大切さを伝えてあげてください。次回更新は1月21日となります。すぐに、更新できずにごめんなさい。人気サイトランキングへにほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村就職活動・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
2013年01月17日
コメント(0)
-

★2012年12月のお話 中編
★2012年12月のお話 中編今年に入って3名の2013年卒生から頂いた内定の連絡。なぜ、今彼や彼女が内定されたのか考えてみました。私は2点理由を考えました。ひとつは就職活動を続けたこと。もう一つは、就職活動を続けることで精神的な強さを身につけたことです。就職活動を続けるとは、応募し続けるということです。当たり前のことを書いているように思われますが、このことを理解している学生は意外に少ないように感じています。応募しないと採用されない。応募しても不採用になる場合もありますが、応募しなければ絶対採用されることはありません。宝くじで考えてみましょう。宝くじは買わなければ当たりません。買っても当たる可能性はほとんど皆無に近いので最初から諦めて買わない人が多いわけですが、それでは当たることはないでしょう。それと同じで「どうせ応募しても採用されないから」と、最初から応募することを諦めてしまっている方が多いです。しかし、後になって「応募しておけば良かった」と思うわけですが、もうその時になって後悔してもあとの祭りですね。もちろん「どこでもいいから応募しなさい」と言っているのではありません。最初から興味や関心のない仕事や会社に応募する必要はありません。でも、迷ったなら応募してみましょう。応募しなければ採用されることないからです。もし、内定後に「この会社は自分の理想と違う」と思ったなら辞退すればいいのです。私は多くの学生達の就職活動を支援して感じることは「迷ったら応募しない」と考えている方がとても多いことです。まず、この発想を変えていきましょう。迷ったら応募すること。実際に、内定の連絡をくれた3人の学生もそうでした。散々迷った末に応募しない。そもそも、この迷っている時間がもったいないですね。2~3日間、ある企業に応募しようかどうか迷っていたとします。その結果、応募することに決めました。そこで、これから応募書類を作り始めるわけですが、この迷っている時間で応募書類を作ることも出来ました。就職活動を続けるということは、実際に応募するということです。そして、応募しようかどうか迷ったら応募してください。次回は、もう一つの精神的強さについて説明いたしますね。明日から二日間出張となり、ブログの更新が出来ません。そのため次回更新は1月18日となります。ごめんなさい。人気サイトランキングへにほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村就職活動・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
2013年01月15日
コメント(0)
-

★2012年12月のお話 前編
★2012年12月のお話 前編2013年になり11日が過ぎました。まだ学校はお休みのところも多いと思いますが、就活生にとってはここが就活の一つの山場ですね。12月からナビがオープンになり、丁度合同企業説明会や会社説明会のピークになるからです。今年3月に卒業される2013年卒生のお話になります。年が変わってから今日までに3名の方から「内定が決まった」という連絡を頂きました。この方たちは、2011年の12月から就職活動を始めたわけですから、実に丸1年間就職活動をされていたことになります。途中、就職活動放棄? されていた時期もありました。内定が出なくて面談中に泣き出した方もいます。色々ありましたが、最終的には内定までたどり着きました。3人の方から内定の連絡をもらい、一人ひとり初めて会ったときのことを思い返してみました。3人に共通して感じたことは、みんな「逞ましく」なりました。最初の頃は、不採用の通知が届くたびに泣き声交じりの電話が掛かってきました。それが段々と「ダメでもともと。受かれば儲けもの」位に割り切って考えられるようになりました。最初は不安感からでしょうか、週に1回は電話か来所されていたのが段々と自分で考えて行動できるようになり、電話や来所回数も減っていきました。年が変わって「みんなどうしているかな~。もう少ししたら連絡してみるか」と思っていた頃に内定の報告をもらいました。連絡をくれた本人も勿論うれしいし、彼や彼女を支援してきた私ももちろんうれしいです。ここでちょっと冷静に、なぜここに来て内定されたのかを考えてみました。 ~~~~ つづく ~~~~続きは、1月15日の更新となります。人気サイトランキングへにほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村就職活動・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
2013年01月11日
コメント(0)
-

★健康管理に細心の注意をしましょう 後編
★健康管理に細心の注意をしましょう 後編体調が悪くなると気力も萎えてきますね。そのため、細かいことが面倒臭くなって「まぁ、いいか」と考えるようになりがちですが、これが危険です。それは、このささいなことが就職活動の採否結果につながるからです。人の能力には、それほど大きな差がありません。それでも、採用される人となかなか採用に至らない人がいる。その差は、このささいなことの積み重ねです。応募書類でいえば、履歴書やエントリーシートが丁寧に書かれているか。通常、左側の氏名や住所欄から書き始めますが、なかにはこの氏名や住所欄は丁寧に書かれているのに、免許や資格欄になるとすこし乱暴になる人がいます。また、写真はまっすぐに貼れているでしょうか。少し斜めになっている人もいらっしゃいますね。気力ややる気が充実しており時間も充分にあれば、このようなときは、自分でも気付いて書き直そうとか貼り直そうと思いますが、疲れていたり気力が萎えていると「まあ、この位大丈夫だろう」と自分に甘い判断をしてしまいます。そう、つまり健康状態が悪いとついつい自分に甘くなってしまいがちになります。その甘い判断が、結果的に不採用の要因にもつながります。採用担当者は、常に応募者を比較してみています。言い換えれば、ささいな差を見つけて応募者の優劣をつけている訳です。したがって、病気や怪我などの体調不良だけではなく、飲み過ぎや食べ過ぎ、ゲーム等による夜更かしなど不規則な生活による体調不良も避ける努力が必要です。また、健康な方でも花粉症気味の方は注意してください。【環境省】『東北地方の一部を除く東日本を中心に、例年よりもかなり多い飛散が予測』されています。ちょうどこの時期に、企業の1次試験と重なります。筆記試験対策として遅くまで勉強、翌日花粉症の薬を飲んで睡魔に負けてしまい試験に遅刻というケースを毎年耳にします。私も例年花粉症に悩まされています。色々な薬や民間療法を試しましたが、コレといった決め手はありません。どうしても鼻水を止めたい場合は薬を飲みますが、やはり猛烈な眠気に襲われます。そのため、前日はできるだけ早く寝て睡眠不足にならないように心がけています。健康管理の原則は、睡眠、食事、運動の3つといわれていますが、自分なりの健康法を今からつくっておきましょう。人気サイトランキングへにほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村就職活動・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
2013年01月10日
コメント(0)
-

★健康管理に細心の注意をしましょう 前編
★健康管理に細心の注意をしましょう 前編お早うございます。今日もご覧くださりありがとうございます。年末に風邪をひきました(笑)。これまで何度か、このブログをお読み頂いている方に、健康管理の大切さについてお伝えしてきました。そう言っている当人が風邪をひいたので、あまり説得力がないのですが、今回実際に自分で風邪をひいたことによって改めて健康の大切さを実感しました。年末に義父が亡くなったことを、以前ブログでお伝えさせて頂きました(12月27日のブログ)。告別式と、以前からお話を頂いていた講演が重なってしまい非常に忙しいというか、慌しい日を過ごしていました。義父は以前から入退院を繰り返していましたが、今回は非常に危険な状態をいわれました。入院時のお見舞いから、お通夜、告別式と続き、それと平行しての仕事。しかも、どちらも他人に代わってもらうことが出来ず、なんとかやりくりして、そして周りの人の協力もあり、なんとか両方とも無事終えることが出来ました。その後の脱力感からでしょうか、クリスマスイブと重なった3連休はぐったりとしてしまい、発熱、頭痛、せきと鼻水、口内炎と風邪をひいてしまいました。私は基礎体温が低く、通常の体温が35度3分から5分しかないのですが、37度から37度4分の熱が続きました。私は発熱するといつも関節が痛くなるのですが、今回は腰が痛くなり寝たくても寝られず、かといって起きるとフラフラして、なにかにつかまらないと立っていられない状態でした。25日には、面談の約束があったので仕事はしましたが、まだ軽い頭痛やのどの痛み、せきと鼻水が続いていました。ようやく29日頃になって治ったのですが、改めて健康が大切だと痛感しました。体調が悪くなると気力も萎えてきますね。細かいことが面倒臭くなって「どうでもいいか」と考えるようになります。実は、これが危険です。 ~~~~ つづく ~~~~人気サイトランキングへにほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村就職活動・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
2013年01月09日
コメント(0)
-

★新年の挨拶にかえて 後編
★新年の挨拶にかえて 後編「エンプロイアビリティ」という言葉の意味は「雇用されうるだけの能力のこと。Employ(雇用する)とAbility(能力)を組み合わせた用語です。産業構造の急速な変化や終身雇用制度の崩壊に伴い、個人は環境の変化に素早く適応し、必要に応じて異動や転職をスムーズに行う能力が求められている。~中略~ 個人は自分自身のキャリア・デザインを戦略的に考え、常にエンプロイアビリティを高める努力が求められる。」となります。【コトバンク】そして、このエンプロイアビリティの向上を支援する人が必要となります。それが、日本におけるキャリアコンサルタントの誕生のいきさつです。キャリアコンサルタントは現在7万人いるといわれています。【厚生労働省HP】私自身もこのキャリアコンサルタントとして活動しています。そして色々な分野で活躍されている方がたくさんいますが、大きく分けると下記の4つに分けられます。・大学のキャリアセンター等「学校や教育部門」・ハローワークや就職支援会社等「需給調整機関」・総務部門や人事部門等「企業・行政」・地域の就労や社会参画を支援している「地域」私は、事業仕分けで無くなってしまった「キャリア交流プラザ」のほか、「ハローワーク」「ジョブカフェ」でも就職支援に携わった経験があります。また日本産業カウンセラー協会が厚生労働省より受託した若者の進路や就労を支援する「ヤングキャリアナビゲーション」事業のカウンセラーを3年間担当していました。これまでに約2500名の方と、カウンセリングしてきました。そこで気付いたことや感じたことが、このブログの原点にもなっています。ブログのヘッダーにもあるように、私の子供たちも含めて若者が笑顔で元気に働ける社会作りをこれからも続けていきます。人気サイトランキングへにほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村就職活動・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
2013年01月08日
コメント(0)
-

★新年の挨拶にかえて 中編
★新年の挨拶にかえて 中編なかなかブログが更新できなくて申し訳ありません。ブログはまだまだ続けて参りますので、今後とも宜しくお願いします。4日の続きです。政権が変わっても大きな改善はみられないとなれば、自分の身は自分で守るという自助自立が大切になりますね。これからは、会社に頼るのではなく自分のスキルや能力を高めることでどこでも生きていけるようにすることが大切です。これは私がいっていることではなく、平成13年に厚生労働省は、職業能力開発促進法を改正しました。そこにはっきりと明記されています。原文には『労働者個々人の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発および向上の促進労働者のキャリア形成を支援するためには、労働移動の増加等により、企業主導の職業能力開発だけでは限界がみられるようになっている。 そのため、事業主が労働者の自発的な職業能力開発を促進するために講ずべき措置を明確化し事業主に対し助成金や相談援助業務等適切な支援措置を講ずることとしている。』とあります。とっても大雑把に訳すと「今後、労働移動(転職)する人が増えるため、企業による人材育成だけでは無理なので、企業に対して助成金や相談する機会を増やします。」ということです。ここで書かれている転職する人というのは、自己都合による離職や転職ではなく、企業主体の離職つまりリストラということです。そして、このころから「エンプロイアビリティ」という言葉もがよく使われるようになりました。【コトバンク】このコトバンクの説明に、これからの国や企業の方向性が的確にあらわさせています。一部をご紹介すると「雇用されうるだけの能力のこと。Employ(雇用する)とAbility(能力)を組み合わせた用語。産業構造の急速な変化や終身雇用制度の崩壊に伴い、個人は環境の変化に素早く適応し、必要に応じて異動や転職をスムーズに行う能力が求められている。~中略~ 個人は自分自身のキャリア・デザインを戦略的に考え、常にエンプロイアビリティを高める努力が求められる。」いつ他の部署に飛ばされても、いつ会社をクビになっても困らないようにしておきなさいということですね。このような社会の変化において、働く人やこれから働こうと考えている人の支援をする人が必要になります。それが、日本におけるキャリアコンサルタントの誕生のいきさつです。 ~~~~ つづく ~~~~人気サイトランキングへにほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村就職活動・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
2013年01月07日
コメント(0)
-

★新年の挨拶にかえて 前編
★新年の挨拶にかえて 前編新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申しあげます。今年はどんな年になるのでしょうか?政権が変わり、再び自民党による舵取りが始まります。12月16日の選挙に対して、どの政党も雇用対策の強化を政策に掲げていました。そこで、自民党のHPを見てみましょう。【自由民主党】http://www.jimin.jp/activity/colum/117957.html山口俊一地方分権・地域活性化特命委員長のコメントが紹介されています。ここからいくつかのキーワードがあげられます。・2兆円の交付金の創設 (1兆円は雇用対策、もう1兆円は地域活性化) ・過疎対策振興法や離島振興法 (IT(情報通信技術)の活用、観光業の振興)・第1次産業の活性化、中小企業、地場産業の振興・公共事業、農林水産業支援2兆円の交付金を使って、農林水産業や地方の中小企業、土木建設業や観光事業を支援することで地方都市の産業を発展させ雇用創出をしようと考えていることがうかがえますね。長引く不況やデフレ経済により、一番ダメージを受けているのが上記の産業ともいえます。そのため、停滞している産業や業界にカンフル剤を打ち、会社を活性化させて失業者を積極的に雇用してもらおうという意図がみてとれます。この政策を見る限りでは、民主党時代になる前の自民党がしてきたこととあまり変わりはありません。したがって、今後の景気対策は失敗もしないが、大きく改善されることもないだろうと思います。3年前の状況に戻るということでしょうか。しかし実際は、震災復興、TPP、原発の是非、中国との外交摩擦による不買運動など、3年前にはなかった問題も新たに発生しており、先行きが見えません。そうなると、結局は国とか政治に頼るのではなく、自分の身は自分で守るという自助自立が大切になると思います。これは労働者という視点で考えても当てはめることができます。会社に頼るのではなく自分のスキルや能力を高めることでどこでも生きていけるようにすることが大切です。実は、これは平成13年からいわれていることでした。 ~~~~ つづく ~~~~人気サイトランキングへにほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村就職活動・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
2013年01月04日
コメント(0)
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
-
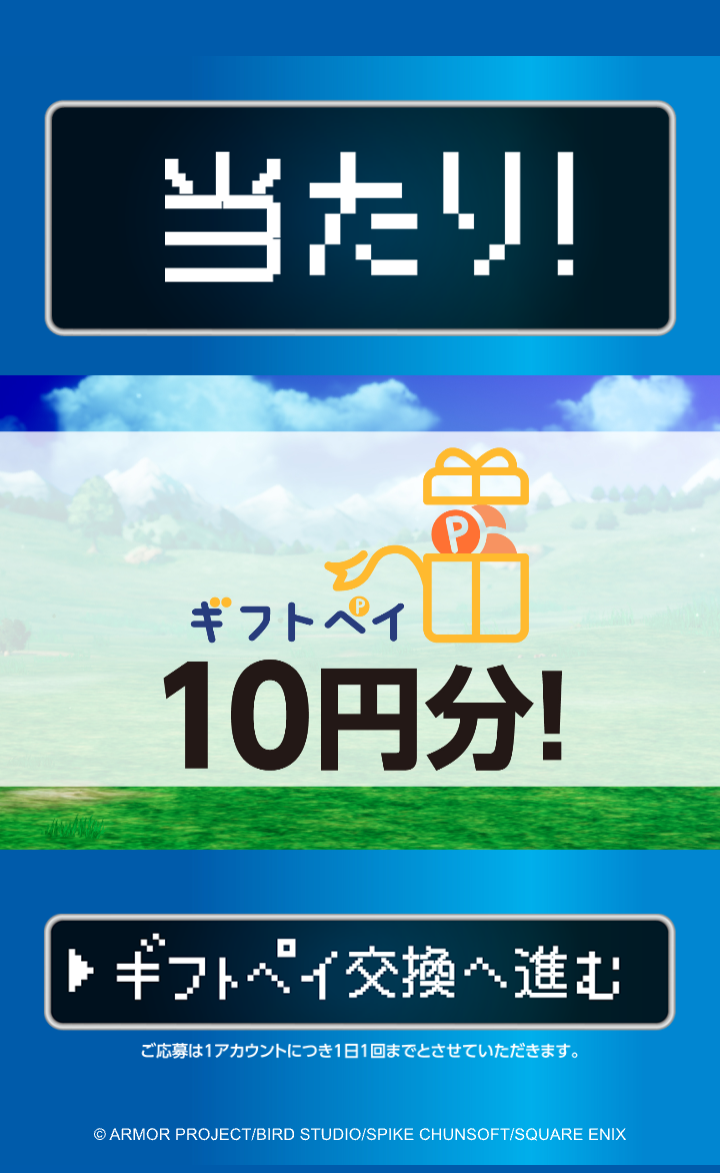
- 懸賞フリーク♪
- ドラゴンクエスト× BOSS キャンペー…
- (2025-11-21 22:13:37)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 【気まずい…】楽天お買い物マラソン…
- (2025-11-21 20:30:04)
-








