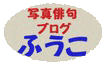2011年01月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
預金保険機構にネット公開質問~日本振興銀行のペイオフ発動で露見した‘その利息’の曖昧さ~
2010年9月10日経営破綻してペイオフ発動第1号になった日本振興銀行。私が預けていた10年定期(2.2%)の解約金が今日やっと振り込まれた。4月に承継銀行に引き継がれる(金利はたぶん0.03前後)ことを承諾しないことを選択した預金者が元本+破綻日までの利息を受け取る‘特例中途解約’という独自の手続きをしている。前にも触れたが私は全額保護の時代に預金先が破綻した経験が3回ある。当時は定期預金の期間と言えば基本的には1年だった。破綻しても満期まで待てばその後事業を引き継ぐブリッジバンクが当初の約定金利で計算した元利金を払い戻してくれた。結果的には預け先が破綻しようが何ら失うものがなかったのだ。そんな‘甘い体験’をしてきたせいか今回の振興銀行の破綻処理に関してはいくつかの疑問を抱いてしまった。ペイオフ制度が解禁になり定額の預金保護に移行した時に、詳細はともかくひとつだけ覚えろと言われれば‘元本1000万までとその利息は保護されます’という大原則だ。実際ペイオフ発動時のマスコミ各社もこの決まり文句を繰り返した。元本1000万までというのは単に数字の問題で誰でも簡単に判断できる。ただし‘その利息’が何を指すのかは結果的には実に曖昧だということが今回の振興銀行の例でわかった。本来ならば過去何度もそうしたように預金保険機構に直接電話をして質したいところだが、今回はそこまで燃えていない。経験上電話を録音している旨を相手に伝えると‘飽くまでも私見で機構としてのオフィシャルの見解ではない‘と逃げ腰になる人が多いのも虚しい。あとは私の大好きなフリーダイヤルでないのもひとつの理由だ。じゃあネット上で文字通り公開質問しちゃいましょうかということにした。法律の知識も何もない人間の表現なのでナンチャッテ調なのはお許しあれ。1.預金保護の本来の意味合いは当初約定した預金契約を履行すること、つまり10年定期なら残存期間を含めて当初の利率に基づいた利息を保護することではないのか。2.破綻後の中途解約に関しては預金規定に則り利息が20分の1、50分の1にされた。形式上は預金者が自ら申し出たからそれらの懲罰的な条件を適用することに問題は無い。しかし中途解約に至った要因は預金者の自己都合では無く経営破綻した振興銀行側にあり、預金者がペナルティを払わされる形になるのはおかしくないか。これがもし仕組み預金と呼ばれるデリバティブを絡みの場合、中途解約条項が適用となると元本そのものを大きく毀損するケースが考えられ預金者保護にならないのではないか。3.破綻後約7か月半後の2011年4月25日に預金が承継銀行に移管される予定だが、それに同意しない預金者は破綻日までの利息しか受け取れない。私のケースで言えば約4か月半の期間無利息の扱いとなる。現在の市場金利で計算すれば微々たる額だが、額の問題ではなく預金者がこの期間資金を拘束されているのに付利されないことが納得できない。機構のある人には根拠法は民事再生法と言われた覚えがあるが自信満々ではなかった。本来付利される預金であれば拘束期間中は‘その利息’の対象となるのではないか。4.破綻日以降は民事再生法に基づき経過利息を付けないと言いながら破綻後に満期解約、中途解約をした場合は9月10日以降も利息を付けて処理されてきた。承継銀行に引き継がれることに同意した場合は破綻後の7か月半は当初の高金利で利息が付く。預金者の中で‘空白期間’を持つ者と持たない者が混在することになるのはどう説明するのか。5.預金保険でいう‘その利息’が利率も期間も破綻日までを限定して意味するのなら、預金保護対象部分の全預金者に対して遅滞なく元本+経過利息を支払えばいいのではないか。狼狽気味に中途解約して泣いた人たちも救えるし、無利息期間に納得できない人々も生まない。第三者的な視点でも高金利が破綻後は維持されないというのは支持されそうだ。これがいわゆる保険金支払い方式になると思うのだが、預金保険機構は消極的だ。いつも10何年前の金融審議会の答申に従っているだけだと言い訳している。以上最後は質問なのか感想なのかつぶやきなのかわからなくなってきたが、今回の経験を通して思った事を書いてみた。関係当局は或る意味で‘念願’だったペイオフ第1号の‘社会実験’を小規模で影響も限定的な日本振興銀行という‘逸材’を使って行うことができた。近い将来もっと大規模で複雑なペイオフ発動が起こった場合に備えて、今回露見した‘その利息’の算出の仕方等の諸問題を今後どう改善するか真摯に向き合ってほしい。という訳で2011年第3弾も当事者以外の人にはどうでもいい話になってしまった。預金保険機構の皆さん、私見で結構ですから是非書き込み期待していますよ。
2011.01.26
コメント(0)
-
ビール、餃子、ラーメンを同時に頼んだ時の小悲劇~回避する究極のオーダーの仕方はこれだ~
成人の日にいきつけの中華屋さんに行ったら、いました、いましたカウンターで昼ビールをやっている新成人とは程遠いおっさん。そして見事に術中に嵌っていた。ビール、餃子、ラーメンの組み合わせは実にポピュラーだ。私の人生でも主に一人メシの時が多かったが何度頼んだことか。この場合の餃子は歴史的には決して王道ではない焼き餃子だ。麺はラーメン屋なら普通にラーメンだが街の中華屋さんならタンメンを選ぶことが多かった。問題はこの3品を同時にオーダーしてしまった場合に運ばれる順番にある。瓶ビールだろうが生ビールだろうがビールは直ぐにやってくる。一口、二口飲んだ後やや間延びをした頃に届くのは十中八九麺類だ。放置する訳にもいかないので麺を食べ始めるとその途中でやっと餃子のご到着だ。酷い場合だと麺を食べ終わった後に出てくることもある。おいおい、俺は餃子をツマミにビールを飲んで麺で〆たいのになんだよこれは・・・(`´)何とかしようと注文時に最初に餃子で麺はその後でと文字通り‘注文’をつけても、当時私の通っていたようなチープな店ではサーヴィスの質も低く思うようにならなかった。こんな苦い経験を繰り返した若い頃。相手に期待してはいけないのだ。話は簡単だ。ビールと餃子だけを注文する。店の混雑具合を勘案して餃子が運ばれてきた時、或いは1,2個食べた頃に麺類をオーダーする。これで小悲劇は回避できる。ところがある時ビールを飲み始めてから餃子が現れるまで30分近く待たされたことがあった。生憎と夏だったせいかビールは温くなり完全に生気を失ってしまった。そこで到った究極のオーダーの仕方はこれだ。「ご注文は」「餃子1枚」「他には・・・」「いや、先ずは餃子1枚」「へぃ、餃子お待ち」「では瓶ビールを1本」「へぃ、ビールお待ち、ご注文は以上で・・・」「いまのところは」「すみません、タンメンを下さい」「へ~ぃ、タンメンお待ち、まだなんか頼むんでしょ」「いいえ、これで完全におしまいです」店側から見れば客の回転を悪くする嫌な奴になるのは必至だが、客がこれぐらいの満足を求めて何が悪いと思うのだが・・・。この小悲劇の話を他人にすると、みんな一様に大きく頷く。経験上麺類が餃子より先に出てくることが多いのだろう。それでいてこの究極の回避の仕方を話すとやや空気が怪しくなる。実際この方法を採用したという人の報告は無い。私にとっては大悲劇だが世の中の人々には実は小悲劇でさえもないのだろうか。或いはこの程度の悲劇は耐えるのが当たり前だと考えてしまうのだろうか。というわけで2011年第2弾も殆どの人にはどうでもいい話でした(チャンチャン)・・・(>_
2011.01.10
コメント(2)
-
CMキング石川遼に‘Let’s chewing’と言わせたロッテ~英会話教材スピードラーニングの立場は?~
今やぶっちぎりのCMキングになった石川遼。2009年でCMのギャラが30億円以上と言われているが、去年は更に増やしただろうし、今年もその傾向は続くだろう。一部には既に露出過多という声もあり近いうちに臨界点に達しそうだが、ここまで絵に描いたような好感度キャラだと製作者側も無難で安易な選択をしたがるのだろう。さて17社のCMに出演するとなると同業種を避けるとか色々と配慮することはあるだろうが中には‘干渉’してしまうこともある。まあこれはあくまでもナリポン的視点での‘干渉’だが・・・(^。^)去年の秋口から始まったロッテの‘グリーンガム・チューインガムでいく篇’その中で石川遼が‘Let’s chewing’と言っている、というか言わされている。Let’s の後に~ingはおかしいだろう。先月、イギリス人と会う機会があった時に念のために確認したがやはり文法的には有り得ないと言われた。CMを良く見ると実は‘Let’s!チューイング’となっていて、英語とカタカナが混じっている。だから‘容認してよ’というつもりなのかどうかはわからないが、遼君の英語としては飽くまでも‘Let’s chewing’として流れているのは事実だ。まあ、世の中の各種メディアや出版物、町中の看板やチラシでも間違った英語が使われることは別に珍しくもなく日常的だ。いちいち目くじらを立てていたら、こちらの‘目’が持たない。ただ今回の問題点は石川遼が英会話教材のスピードラーニングのCMにも出演していることだ。その謳い文句が‘1日5分聞き流すだけで英語が話せるようになる’というから、スピードラーニングの立場としては‘聞き流せない話’になると思うのだが・・・。へぇ~、スピードラーニングをやると‘Let’s chewing’とか平気で言えるようになっちゃうんだ・・・(-.-)会社の規模や格から言えばスピードラーニングは謎めいている。石川遼をいちはやく起用したのは先見の明があったと言えるが、あそこのCMを見ているとNYYのディレク・ジーターの出演するZIP HITのCMに似たどこかアンバランスな世界を感じる。さて話をロッテのトンデモ英語に戻すが‘Let’s chewing’と言わされているのは石川遼の他にもいる。永ちゃんこと矢沢永吉もそのひとりだが‘世界のYAZAWA’が泣いてるぜ。人物像を大きく歪めてしまうのがゴルゴ13ことデューク・東郷だ。wikiによれば英語をはじめとする20カ国の以上の言語に精通し、現地の人間が違和感を持たない程のネイティブな発音・会話が可能、とされる。それが‘Let’s chewing’じゃ、違和感どころか折角の依頼もキャンセルされそうだ。緻密で完璧主義のイメージが強い‘さいとう・たかを’らしからぬ不整合だ。というわけで2011年の第1弾は、またまた殆どの人にはどうでもいいことでした。
2011.01.06
コメント(6)
全3件 (3件中 1-3件目)
1