2024年12月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
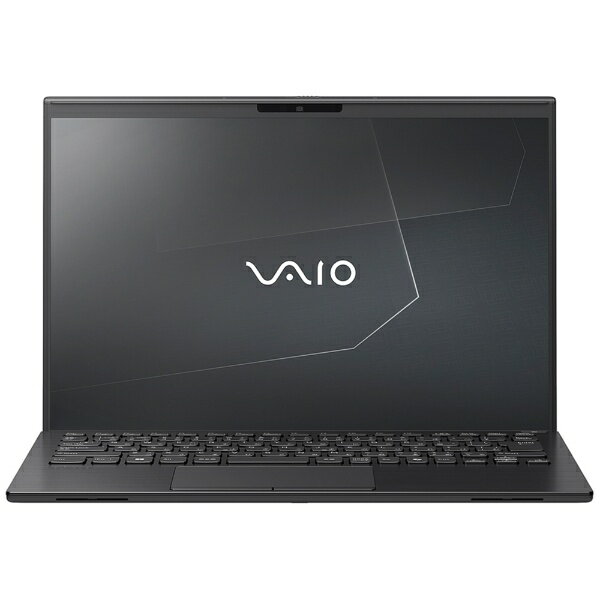
【Windows 11搭載の14インチ・モバイル】ノートPC「VAIO SX14-R」(VJS4R190)
ノートPC「VAIO SX14-R」(VJS4R190) 1kgの軽量ボティでバッテリ駆動時間は約30時間製造/販売VAIO製品情報ノートPC「VAIO SX14-R」(VJS4R190)価格比較ここをクリック VAIOのモバイルノートPCにおけるフラグシップモデルとして開発されたモデルで、「VAIO SX14」の上位として位置づけられる。ボディーには新設計のカーボンファイバープレートを採用し、最軽量構成は約948gと14型ながらも1kgを切る重量を実現した。軽量設計だが、米国防総省の物資調達規格「MIL-STD-810H」(MIL規格)に定める耐衝撃/耐環境性能を満たしている。CPUは「Core Ultraプロセッサ(シリーズ1)」のHシリーズで、VAIO PCとしては初めてNPU搭載CPUを採用している。メモリはLPDDR5X規格で、容量は16GB。Windows 11 HomeとMicrosoft Office Home and Business 2024をプリインストールする。Webカメラは、顔認証機能/AIビジョンセンサー付きの約921万画素センサーを搭載している。このカメラはHDR(ハイダイナミックレンジ)明るさ補正やピクセルビニングにも対応しており、さまざまなシーンできれいに撮影できることが特徴だ。なお、Pro PK-Rについては顔認証対応のフルHDカメラ(約207万画素)に変更することも可能だ(HDR明るさ補正やピクセルビニングには非対応)。電源ボタンには指紋センサーも搭載しているが、Pro PK-Rについては「指紋センサーレス」構成も用意できる。内蔵マイクは3基構成で、AIノイズキャンセル機能も備える。スピーカーは2基(ステレオ)構成で、Dolby Atmosによるサラウンド再生に対応している。ポート類は左側面にThunderbolt 4(USB4)端子とUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1) Standard-A端子を、右側面にイヤフォン/マイク端子、USB 5Gbps Standard-A端子、HDMI出力端子、有線LAN(1000BASE-T)端子とThunderbolt 4端子を備える。Thunderbolt 4端子はUSB PD(Power Delivery)準拠の電源入力と、DisplayPort 2.1 Alternate Modeによる映像出力にも対応する。本機の場合、左右どちらの側面にもThunderbolt 4端子を備えていることが特徴だ。ワイヤレス通信は、SX14-RはWi-Fi 7(IEEE 802.11be)とBluetooth 5.4に対応している。キーボードはLEDバックライト付きで、かな印字のある日本語キーボードが標準となる。CTOモデルの場合は、かな印字のない日本語キーボード(SX14-Rのみ)や米国英語(US)キーボードも選べる他、特別仕様モデルでは「隠し刻印キーボード」(日本語かな印字なし/US)も用意されている。いずれの配列/仕様でも、VAIOノートPCとしては初めて「Copilotキー」を備えている。また、プリインストールの「VAIO オンライン会話設定」アプリを起動するためのショートカットキーも新設された(設定で別機能に割り当てることも可能)。【主な仕様】基本ソフトWindows 11 Home 64ビットCPUCore Ultra 7 155H(P-core×6: 1.4GHz(最大4.8GHz)E-core×8:0.9GHz(最大3.8GHz)LP-core×4:0.7GHz(最大2.5GHz))グラフィックIntel Arc graphics(CPU内蔵)表示14.0型ワイド液晶 1,920×1,200ドット(アンチグレア)主記憶16Gバイト(最大 16Gバイト)補助記憶SSD 512Gバイト(PCI Express×4: 64Gb/s)ネットワーク有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be(Wi-Fi 7準拠)×1Bluetooth 5.4×1インターフェースUSB Type-C(Thunderbolt 4, USB Power Delivery, USB4, USB 3.2, DisplayPort 2.1)×2USB 3.0(うち1ポートは給電機能付き)×2ヘッドホン出力(ステレオミニジャック, ヘッドセット対応)×1HDMI出力×1サウンド機能インテル High Definition Audio準拠(Dolby Atmos)×1ステレオスピーカー(Dolby Atmos)×1内蔵トリプルマイク(AIノイズキャンセリング機能)×1WebカメラFull HDカメラ 921万画素(Windows Hello 顔認証対応、AIユーザーセンシング対応)×1セキュリティセキュリティーチップ(TPM)(TCG Ver2.0準拠)×1セキュリティーロック・スロット×1カメラプライバシーシャッター×1Absolute Persistence technology×1指紋認証(電源ボタン一体型, Windows Hello対応)×1顔認証(Windows Hello対応)×1バッテリ駆動時間 約14.5時間(JEITA 3.0 (動画再生時))充電時間 約3.0時間(電源OFF時)本体サイズ(幅)312.0×(奥行)226.4×(高さ)13.9~18.9×(直径)×(全長)ミリ本体重量約1067グラム付属アプリケーションMicrosoft Office Home and Business 2024ラインナップVJS4R190111B(ファインブラック)Core Ultra 7 155HVJS4R190311B (ファインブラック)Core Ultra 5 125HVJS4R190411T (アーバンブロンズ)Core Ultra 5 125HVJS4R190511G (ディープエメラルド)Core Ultra 5 125HVJS4R190611S (ブライトシルバー)Core Ultra 5 125H
2024.12.31
コメント(0)
-

【歴史を裏で支える女性たち】女たちの平安後期
女たちの平安後期 八条院領は鎌倉幕府に近いネットワークだった。というより、鎌倉幕府そのものが、八条院と同様の権力体を王権に認めさせて成立したものといえるように思う。著者・編者榎村寛之=著出版情報中央公論新社出版年月2024年10月発行著者は、斎宮歴史博物館学芸員で関西大学等非常勤講師の榎村寛之 (えむら ひろゆき) さん。日本古代史が専門で、本書は2023年に刊行された『謎の平安前期―桓武天皇から「源氏物語」誕生までの200年』の続編にあたる内容だ。藤原道長の時代は、支配層が「オール藤原」といえる摂関政治の全盛期だったが、平安時代後半になると、藤原氏だけでなく、源氏・平氏、そして皇族などいろいろな人たちが登場する。地方で受領として実績を積み、富を蓄え、大貴族の家政を預かる「家司 (けいし) (お屋敷のマネージャー)」になる下級貴族や、出家した元皇后(皇太后 (こうたいごう) )に送られる称号である「女院 (にょいん) 」が活躍した時代である。紫式部は当時の宮中の様子を『源氏物語』に反映させたと考えられているが、政治的背景の弱い藤壺が女院となり、皇族の家長に上り詰めたサクセスストーリーとして描かれている。その意味では、女院の活躍を予言した物語とも言える。藤原彰子 (ふじわらのあきこ) は、藤原道長の長女で、道長は12歳の彰子を女御として内裏に送り込み、一条天皇の中宮とする。彰子は、後一条天皇、後朱雀天皇を産み、太皇太后 (たいこうたいごう) となり、官位で道長を上回った。そこで道長は太政大臣を辞し、出家し大殿 (おおとの) (法名は行観)となることで、臣下の序列から離れて外部から王権をコントロールするようになった。彰子も、それに倣い、藤原氏の中宮経験者では初めて、上東門院 (じょうとうもんいん) という女院となり、天皇家と摂関家の双方に君臨する地位を道長から引き継ぎ、1074年、87歳の天寿を全うする。一方、死の直前、冷泉系と円融系の天皇家の合一を目論んだ道長は、次女・妍子 (きよこ) と三条天皇の間に産まれた禎子 (さだこ) 内親王を後朱雀天皇の皇后となり、後三条天皇を産む。禎子もまた長命で、太皇太后となり陽明門院 (ようめいもんいん) と呼ばれる女院となる。道長の長男・頼通 (よりみち) と彰子が没するが、禎子は1094年に80歳まで生き続け、白河天皇の子、堀河天皇の時代で、院政と呼ばれる時代になっていた。禎子は、生きながらえることで摂関家を権力の座から追い落としたのだった。10世紀に入ると、地方では大貴族や寺社の荘園ができたり、国府の力が強くなり、律令体制下にあった群とその下部組織の郷という地域支配システムが機能しなくなり、治安維持能力をもった武士が台頭してくる。たとえば、986年に斎宮・済子女王と密通事件を起こしたという滝口武者平致光 (たいらのむねみつ) は、996年の長徳の変の際には伊周の郎党として逃亡を余儀なくされたが、1019年の刀伊の入寇で活躍した平致行と同一人物と目されている。また、藤原道長に武力をもって仕えたなかに、清和源氏の源頼光がいた。四天王ともに大江山の酒呑童子を退治した伝説の主である。このように摂関家とコネクションをバックに、全国を流れ渡る武装集団が現れてきた。彼らは鎌倉武士とは性質が異なる。榎村さんは、「専制的な君主の政治は、行き当たりばったりから始まることがしばしばあるようだ」として、桓武天皇と白河天皇の2人を挙げる。白河天皇は、薄いながらも藤原能信を通じて摂関家との繋がりがあったため、藤原頼通へのトラウマを持ちつづけた禎子内親王や後三条天皇にとっては邪魔な存在であり、白河体制の船出はじつは割合不安定なものだった。白河天皇は8歳の堀河天皇に譲位する際、すでに母親の藤原賢子が没していたことから、自らの長女の?子 (やすこ) 内親王を未婚のまま堀河天皇の母后の代理である准母 (じゅんぼ) として指名し、天皇の後見人となった。1093年に?子は郁芳門院 (いくほうもんいん) と呼ばれる女院となり、自由に権力をふるえるようになったのもつかの間、1096年に急逝してしまう。白河上皇は郁芳門院のために六条殿を建造するが、この建設事業に携われ白河に認められたのが平正盛――平清盛の祖父である。白河上皇は、中宮こそ摂関家出身(藤原師実養女で村上源氏の源顕房の実娘)の賢子を置いたが、彼女の没後は祇園女御のような出自のよく分からない女性たちを、気に入りさえすれば身分を問わず身近に置くようになった。白河上皇と祇園女御のに養われた藤原璋子 (たまこ) は、1124年に崇徳天皇の母となり、女院・待賢門院を名乗る。待賢門院の女房や侍は、荘園経営の中間窓口である預所などの権限(@職@しきruby)を代々受けつぎ、独自の権力を持つようになる。さらに和歌の家元ともいうべき新たな特権を武器にした六条藤家 (ろくじょうとうけ) 、御子左流 (みこひだりりゅう) (藤原道長の子孫)がのし上がってくる。白河天皇は、後三条院が亡くなってからの57年間、政治の世界に君臨し「治天の君」と呼ばれた。その権力の根源は、家長として自分の好きな人物に権力を与え、国家の最高決定機関である太政官を無力化することができるという点に尽きる。平氏は源氏に比べてマイナーで、平氏は桓武、仁明、文徳、光孝の4系統しかなく、12世初頭の時点で残っているのは桓武の子孫の高棟王と高望王の2系統だけだった。高望王系兵士は地方で武士化し、そのなかに白河院の近臣となった平正盛がおり、その孫が清盛である。清盛は、高望王系の文人平氏の時子との結婚することで、武人平氏と文人平氏を合一し、さらには後白河院や二条院との強いパイプを構築した。1156年の保元の乱、1159年の平治の乱を経て、平清盛の権力基盤が固まると、1171年に娘の徳子を高倉天皇に入内させる。この頃、斎王がほとんど機能しなくなり、その結果として女院となった女性たちも悲喜こもごもの生涯を送ることになる。源平合戦は、1180年の以仁王の挙兵で幕を開けるが、後白河院から親王宣下を受けないまま成人した皇子であり、榎村さんは、それほどの権力をもっていなかったのではないかと推測する。むしろ、以仁王を猶子としていた(養母の)八条院?子内親王(鳥羽院と美福門院の皇女)が所有する膨大な数の荘園(八条院領)の経済力と、それを警護する武士団の戦闘力を背景に挙兵したのではないかという。だが、榎村さんが「超お嬢様」と呼ぶ八条院は、政治的な動きをまったく見せず、誰の味方にもならず、1211年に75歳で死去する。八条院領は順徳天皇に継承されるが、1221年の承久の乱で佐渡に流されたため、一時期鎌倉幕府に没収される。のちに大覚寺統と呼ばれる天皇の系統、つまり亀山上皇から後醍醐天皇を経て南朝に至る天皇家の家産として継承されていく。本書は、藤原道長の絶頂期を平安時代の折り返し点とみなし、そこから鎌倉幕府へ至る約200年のあいだ、上東門院彰子、陽明門院禎子内親王、八条院?子内親王という、歴史の表舞台に出てこない女性たちにスポットを当て、天皇家や摂関家との関係を分かりやすく系図で示しながら歴史の流れを解説している。〈女院〉を通してみることで、「なんだかよく分からない平安時代」に歴史的な一貫性をみることができた。ちょうど本書を読んでいるとき、藤原道長と紫式部が活躍するNHK大河ドラマ『光る君へ』が最終回を迎えた。この2人が武力によらない平和な社会を願ったにもかかわらず、荘園の発達が進み、それを守るための武力集団が誕生し、武士の時代が到来する。一方、紫式部が仕えていた一条天皇の中宮・藤原彰子は太皇太后となり、ドラマではどんどん存在感が大きくなっていくのだが、その様子は本書でも取り上げられており、その後、〈女院〉が歴史を裏で支えていることがみてとれる。平安時代最後の女院・八条院は、全国に200箇所以上ある荘園・八条院領の元締めであり、多くの武士を抱えていた。以仁王は、その経済力と武力を背景に挙兵するが、八条院自信は誰の味方にもならず、鎌倉時代まで生き延びる。八条院領は、のちに大覚寺統と呼ばれる天皇の系統へ受け継がれ、南北朝の争乱を引き起こす。また、『源氏物語』『枕草子』から『百人一首』まで、和歌がもつ力と、それを詠んだ女性たちの存在を再認識した。わが国には女系天皇が存在しなかったため、こうした女性たちが発揮した権力・権能は一代限りのものであったが、皇統を裏で支える太い糸のような流れを感じた。付録として、「男もすなる」歴史書を「女もしてみむとて」書かれた大長編歴史書『栄花物語』の一覧表があり、参考になった。正編の著者は、NHK大河ドラマ『光る君へ』の中で、藤原道長の正妻・源倫子に、宇多天皇から書き始める必要があるとドヤ顔で言い放った赤染衛門。榎村さんの前著『謎の平安前期―桓武天皇から「源氏物語」誕生までの200年』に記されている通り、道長の時代には国(男)が編纂した歴史書が無くなっていることと対照的だ。これは想像の域になるが、歴史の表舞台に見えている男系皇統を裏で支えているのが、こうした女性たちの存在であり、両者のバランスの上に、わが国は征服も支配もされずに続いてきたように感じる。道長と紫式部の願いは、千年の時を超えて今日まで受け継がれていると言えよう。
2024.12.30
コメント(0)
-

【SOHO向け】NAS「HDL1-LASOHO」シリーズ
NAS「HDL1-LASOHO」シリーズ 小規模オフィス向けとなる1ドライブ構成のエントリーNAS製造/販売アイ・オー・データ機器製品情報NAS「HDL1-LASOHO」シリーズ価格比較ここをクリック 個人事業主などの利用を想定したエントリークラスモデルのNASで、外出先からのリモートアクセス機能も搭載。同社製ビジネスNAS向けとして展開しているクラウド管理サービス「NarSuS(ナーサス)」も利用できる。内蔵HDDには高耐久仕様のNAS向けHDDを採用。接続インタフェースはギガビット有線LAN×1を装備する他、USB 2.0ポートも利用できる。容量ラインナップ1TB2TB4TB8TB
2024.12.29
コメント(0)
-
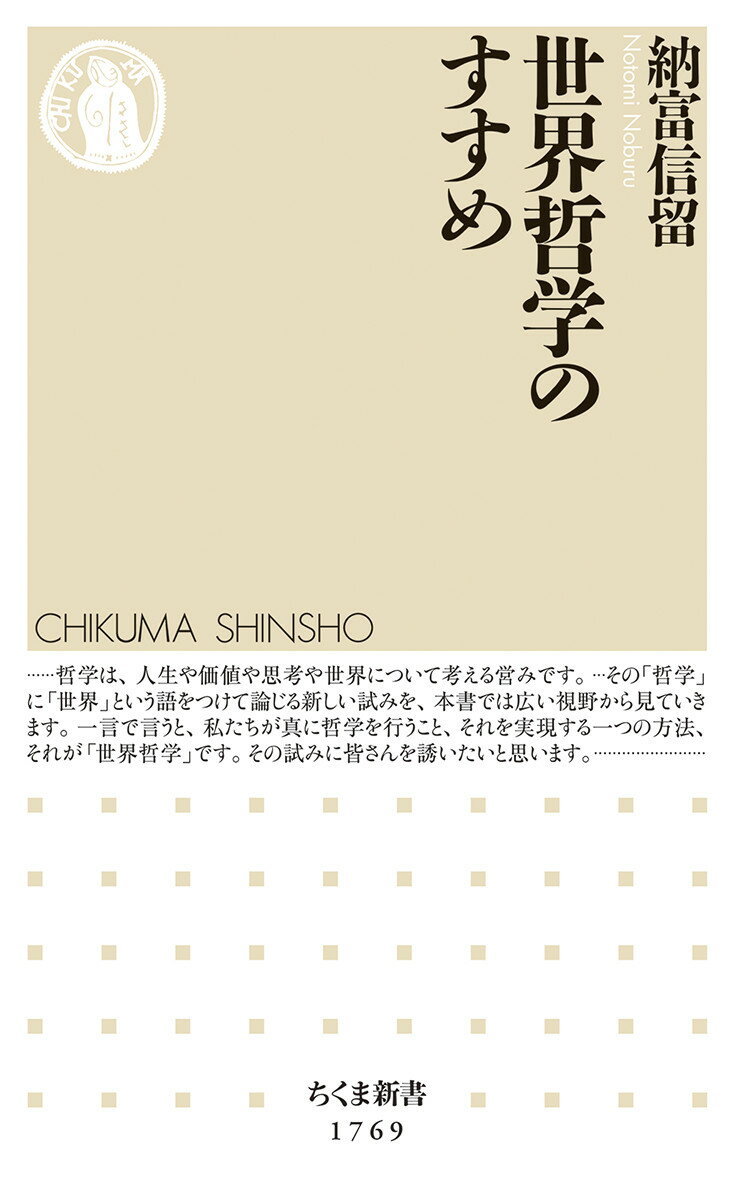
【西洋哲学を超えて】世界哲学のすすめ
世界哲学のすすめ 近代に限定せず、古代からの日本の「哲学」を語っていくこと、それが現代の私たちに求められる世界哲学なのです。著者・編者納富信留=著出版情報筑摩書房出版年月2024年1月発行著者は、東京大学大学院教授で、西洋古代哲学が専門の納富信留 (のうとみ のぶる) さん。世界哲学とは、西洋中心の「哲学」を根本から組み替え、より普遍的で多元的な哲学の営みを創出する運動だという。古代ギリシア哲学、ルネサンス哲学、中国哲学、ロシア哲学、現代フランス哲学も、全てはローカルな哲学であり、宗教や思想が哲学に劣ることはないという。I部では、世界哲学とは何かについて解説する。哲学がローカルになる背景の1つとして「暦」がある。私たち日本人は現在、欧米人と同じグレゴリオ暦(太陽暦)を用いているが、明治5年までは太陰暦を使っていた。欧米も国や地域によってグレゴリオ暦に移行した時期が異なる。イスラム圏ではヒジュラ暦という異なる暦法が使われている。つまり、時代が違ったり、国や地域によって時間に対する感覚・概念が異なるのである。また、国や地域によって普通に見る世界地図も異なる。私たちの世界地図は太平洋西岸が中心にあるが、アメリカの世界地図は南北アメリカ大陸が中心だし、南半球諸国の世界地図に至っては南北が逆転している。さらに母国語の違いがある。数え方にもよるが、世界には3千から7千におよぶ数の言語があり、母語とする人口で言えば、一番多いのは北京語、次いでスペイン語で、英語、ヒンディー語の順に続く。自然科学や技術の分野では、現在は英語が主流だが、時代を遡ればドイツ語やロシア語、ラテン語が使われていた時代もある。また、人文社会科学の療育では多言語状態が続いている。イスラーム教の文化圏ではアラビア語が主流であることにも留意すべきだろう。言語独自のスタイル、とりわけレトリックや言葉遊びは、異言語では再現が難しい。したがって、異なる文化の間で哲学テクストを翻訳する場合、自動翻訳を含め、単に言語を理解可能な形で別の言語に置き換えるだけでは不十分だ。たとえば「普遍 universal」という概念にしても、元の漢語は「ひろく行き渡っている」という意味で、中国や日本でも早い時期から使われていたが、この語を哲学概念に用いたのは明治以降のことだという。「ユニバーサル Universal」という語に「一統、普遍、全稱(論)」という訳語を、そして「ユニバーサルズ Universals」に「通有性(論)」という訳語を当て、以後、哲学では「普遍」という訳語が、論理学においては「全称」という訳語が定着している。英語の形容詞「ユニバーサル universal」は、ラテン語の形容詞「ウニウェルサーリス universalis」に由来し、「他の多くのものに対する一(ウーヌム・ウェルスス・アーリア unum versus alia)」という表現から作られたとも言われている。納富さんは、ギリシア哲学が求めた普遍性とは、「あらゆる時空や状況を通じて同一である」という単純な画一性ではなく、むしろ、「個別特定の状況において普遍的に説明されうる universalizable」という可能性ではなかったか、と考えている。II部では、世界哲学の諸相としてアフリカ哲学、現代分析哲学、東アジア哲学という3つの事例を検討する。納富さんは、「アフリカ」は政治、言語、民族、文化、宗教など、あらゆる点でけっして同質世界ではないとした上で、アフリカには昔から哲学があり、それを探求するには、ヨーロッパ哲学の「現実、知識、真理」といった認識論の概念が植民地アフリカに押し付けられ、その哲学的パラダイムのもとで支配され奴隷となっている状況のくびきから脱却する必要があるしている。西洋哲学が前提している言語分析や論理の基盤が改めて反省に晒され、西洋哲学では把握しきれない宇宙の全体性を捉えるのが、ウブントゥ哲学である。英語圏、とりわけアメリカの教育では「明瞭であれ Be clear!」が重視され、それが分析哲学の論文スタイルにも反映している。だが、分析の対象となる概念は英語、さらに命題や用例も固有名も英語のものに限られる。世界哲学考えるのに、中国哲学史を基本軸に据えて、そこに朝鮮、日本、ベトナムなどの動向を重ね合わせてみる。納富さんは、そうした東アジア哲学史を構築することが大切だと説く。日本人は、明治以降に西洋からもたらされた「哲学」と、それ以前からあった「思想」を分けて考える傾向があるが、海外の研究者から「哲学でないのなら、真面目に論じるには値しない」と返されるはずだと指摘する。納富さんは、近代に限定せず、古代からの日本の「哲学」を語っていくこと、それが現代の私たちに求められる世界哲学だと説く。納富さんは、ダレイオス一世(前558~前486)の時代、古代ギリシアと古代インドが接触した歴史的事実を挙げ、さらにアリストテレスから教育を受けたアレクサンドロス大王(前356~前323)によりギリシア哲学とインド哲学が影響を与え合ったと推測する。納富さんは、前2世紀半ばに成立したとされる『ミリンダ王の問い』(ミリンダ・パンハ)として伝わる仏教外典に触れる。それは、当時ギリシア人の王国があった北西インドの都サーガラのミリンダ王と、彼と対話して仏教へと帰依させる僧ナーガセーナの対話が記録されている。ミリンダ王はギリシア哲学の根幹にある「魂」について問いかけると、ナーガセーナは「無魂」と答える。私という実体を「魂」に置くギリシア哲学に対し、インド哲学は「縁」をもって返したのである。III部では、未来の哲学を論じる。まずギリシア哲学に立ち戻り、納富さんは、西洋哲学がギリシア哲学の直系とは限らないことを指摘する。なぜならば、ローマ経由でキリスト教哲学となったルート以外に、ビザンツ帝国に入ったルートや、シルクロードを経由して遠く日本まで伝わったルートもあるからだ。ギリシア哲学を動かしたもっとも基本的な対立軸は、神と人間という区別、その関係だった。また、類比アナロジーも特徴的だ。類比は「モデル」を用いる思考法でもあり、単純な基本要素が結合と分離によって世界の多様なあり方を形作るという見方は、自然多元論の基礎となった。こうして古代ギリシアの哲学者たちが思索し、後世に伝えた最も重要なものは「人間とは何か」の理念であった。では、世界哲学を展開するために、今後どのような作業が必要となるだろうか。納富さんは、「普遍性」という理念を含むギリシアの「フィロソフィアー」の基盤を、成立状況や特殊性や考え方の偏向も含めてさらに検討することで、その限界を明らかにする作業が出発点になるという。その上で、「普遍性」をめぐって思考された、他の可能性を探る。私たちにとっては、まずは日本、韓国、中国など、東アジアの哲学を射程として、ギリシア哲学や西洋の限定を超える視野を開こうという試みを提示する。最後に、納富さんは世界哲学における「対話 dialogue」の重要性を説く。対話は、時に衝突の引き金となることもあるが、それ自体は自主的で主体的な営みであるから、強制されて参加することは望ましくないという。荒川弘さんの漫画『鋼の錬金術師』第22話「仮面の男」で、主人公の1人で錬金術師のエドワード・エルリックが次のようにつぶやく――>>オレもアルもその大きい流れの中のほんの小さなひとつ――全の中の一。だけど、その一が集まって全が存在する。この世は想像もつかない大きな法則に従って流れている。その流れを知り、分解して再構築する‥‥それが錬金術。3Ubuntuは、アフリカの単語で「他者への思いやり」や「皆があっての私」といった意味を持ちます。LinuxディストリビューションであるUbuntuは、Ubuntuの精神をソフトウェアの世界に届けます。
2024.12.28
コメント(0)
-

【拡張性を重視】Mini-ITXマザーボード「MPG Z890I EDGE TI WIFI」
Mini-ITXマザーボード「MPG Z890I EDGE TI WIFI」 多機能拡張カードを標準で付属したZ890チップセット搭載Mini-ITXマザーボード製造/販売エムエスアイコンピュータージャパン製品情報Mini-ITXマザーボード「MPG Z890I EDGE TI WIFI」価格比較ここをクリック Core Ultra(シリーズ2)の搭載に対応したIntel Z890チップセットを採用するMini-ITXマザーボードで、付属拡張カード「5 in 1 XPANDER Card」によりマザーボード側と合わせて計4基のM.2 SSDを搭載することが可能(マザー側×3、拡張カード側×1)。この他インタフェースとしてUSB Type-C(20Gbps)×1、USB Type-A(5Gbps)×4、SATAポート2基の増設も合わせて行うことが可能だ。メモリスロットはDDR5×2(最大128GB)を、拡張スロットはPCI Express 5.0 x16×1を装備。5GbE対応有線LAN、Wi-Fi 7対応無線LAN、Thunderbolt 4 Type-Cなども利用できる。
2024.12.25
コメント(0)
-

【超静音】薄型メンブレンキーボード「FKB-R249」
薄型メンブレンキーボード「FKB-R249」 静音性を高めた薄型設計のメンブレンキーボード製造/販売ナカバヤシ製品情報薄型メンブレンキーボード「FKB-R249」価格比較ここをクリック 独自の静音構造を採用したメンブレン式キーボードで、キーキャップを本体に直接接触させない静音ラバードームを用いることで従来製品以上の静音性を実現しているのが特徴だ。無線接続モデルのFKB-R251とFKB-R249には、Windows Copilotを直接起動できる「Copilotキー」機能を備えた。いずれもキーピッチは18.6mm、キーストロークは1.2mmとなっている。それぞれブラック/ホワイトの2カラーバリエーションを取りそろえている。ラインナップFKB-R2512.4GHz無線接続/テンキーレスモデルFKB-R2492.4GHz無線接続/フルキーモデルFKB-U250USB有線接続/フルキーモデル
2024.12.23
コメント(0)
-
【14型×2面を手軽に増設】デュアルモバイル液晶ディスプレイ(DMAC24HBK)
デュアルモバイル液晶ディスプレイ(DMAC24HBK) 14型パネルを2枚備えたUSB Type-C接続対応モバイル液晶ディスプレイ製造/販売サンコー製品情報デュアルモバイル液晶ディスプレイ(DMAC24HBK)価格比較ここをクリック 1920×1200ピクセル表示対応の14型IPSパネルを2面内蔵したデュアル仕様のモバイルディスプレイで、2枚を1画面として映せる“フルスクリーンモード”、それぞれ別の画面として表示できる“拡張モード”の利用が可能だ。映像入力はmini HDMIおよびUSB Type-Cに対応。本体サイズは312(幅)×12(奥行き)×430(高さ)mm(展開時)、重量は約1.3kgだ。
2024.12.22
コメント(0)
-

【約610gの軽量筐体】Type-C接続対応の14型モバイル液晶ディスプレイ「LCD-YC141DX」
Type-C接続対応の14型モバイル液晶ディスプレイ「LCD-YC141DX」 フルHD表示に対応した14型モバイル液晶ディスプレイ製造/販売アイ・オー・データ機器製品情報Type-C接続対応の14型モバイル液晶ディスプレイ「LCD-YC141DX」価格比較ここをクリック 1920×1080ピクセル表示対応のADSパネルを内蔵する14型モバイル液晶ディスプレイで、本体サイズ約325(幅)×16(奥行き)×208(高さ)mm、重量約610gのスリム筐体を採用した。表示機能として、低解像度コンテンツの解像感を向上する“超解像技術”や、映像の鮮やかさを高める“エンハンストカラー”などを利用可能。映像入力はHDMIおよびUSB Type-Cに対応、Type-C接続時にはケーブル1本で給電も合わせて行える。
2024.12.21
コメント(0)
-

【想像を超える没入感】ポータブルゲーミングスピーカー「TQ-PG300」
ポータブルゲーミングスピーカー「TQ-PG300」 片手にすっぽりと収まるコンパクトさがかわいい製造/販売パイオニア製品情報ポータブルゲーミングスピーカー「TQ-PG300」価格比較ここをクリック 携帯ゲーム機で遊んでいて「この音、もっとよくしたいな」と思ったことはありませんか。または、スマートフォンで動画などを見ていて「もう少し迫力のある音だったら、もっと楽しいのに」とか。パイオニアのポータブルゲーミングスピーカー「TQ-PG300」は、まさにそういう用途のためにある製品。スピーカー部分がスプリングで伸び縮みする仕組みになっており、携帯ゲーム機を上下から挟み込むかたちで使用する。ゲーム機との接続はUSB Type-Cで、接続先のデバイスからの給電で駆動する。特に設定は必要なく、つなぐだけで使い始められる。背面には折り畳み式のスタンドを備えているため、机の上などに自立させることができる。本製品は、上部スピーカー部分に左右1つずつフルレンジドライバーを搭載しており、Dirac Research ABの「クロストークキャンセリング技術」に対応している。これにより、左右の音の干渉を抑え、分離感のあるクリアなサウンドを実現している。特に、小型スピーカーで顕著な音の干渉問題をデジタルフィルターで解消する点が特徴である。実際の音質は非常にクリアで、特にオープンワールドRPGなどの環境音でその効果を強く感じる。風や砂の音、鳥の声など、音の方向性が明確で、ゲームの没入感が高まる。また、アクションRPGでは振動と音の迫力が相まって臨場感が向上する。さらに、スクロール型アクションゲームでも、細かく調整された音響が楽しめ、ゲーム体験全体がリッチになる。携帯ゲーム機のテーブルモードとの相性も良く、少し離れた場所に置いても音がはっきり届くのが特徴である。外付けスピーカーとしての利便性は高く、本体側面のスイッチで「ハイボリュームモード」と「ワイドモード」の切り替えが可能で、最大出力や広がりのある音場を選べる。さらに、設定不要で接続できる点や、スタンド代わりとしてスマートフォン利用時にも便利で、音質向上を図れる点が実用的である。これらの特徴により、本製品は手軽で高品質な音響体験を提供する一石二鳥のアイテムである。カラーバリエーションホワイトブラック
2024.12.20
コメント(0)
-
【16色カラーとグラデーション点灯が楽しい】USBフロアライト「RGBコーナーフロアライト」
USBフロアライト「RGBコーナーフロアライト」 好みに合わせてカラー変更やグラデーション点灯が楽しめる間接照明フロアライト製造/販売サンコー製品情報USBフロアライト「RGBコーナーフロアライト」価格比較ここをクリック 土台部分と中央部、先端部の3本のLEDライトで構成された、USB給電式のフロアライト。リモコンを使用して多彩なカラー変更やグラデーション点灯に設定、部屋のイメージに合わせた間接照明として使用できる。3本のライトを連結させた状態では高さ122.5cmで、中央部分を外して高さ82.5cmの2本で使用することも可能。カラーは16色から選ぶことができるほか、色が変化するグラデーションモードを4種類搭載。明るさは6段階で調整できる。また、左右90度に展開する直角の土台により、コーナーピッタリ寄せて設置することができる点も特徴。電源は5V/2A以上のUSB給電で、本体サイズは幅29×奥行き29×高さ82.5~122.5cm、重さ約950g。
2024.12.19
コメント(0)
-

【音質重視】ワイヤレスイヤフォン「ZE3000 SV」
ワイヤレスイヤフォン「ZE3000 SV」 大径ドライバーを採用し音質重視をうたった完全ワイヤレスイヤフォン製造/販売final製品情報ワイヤレスイヤフォン「ZE3000 SV」価格比較ここをクリック Bluetooth 5.3接続に対応した完全ワイヤレスイヤフォンで、10mmの大口径ドライバーを搭載し高音質再生を実現。また有線イヤフォンと同等の音響設計を可能にする「f-LINKポート」を採用しているのも特徴だ。音声コーデックはSBC/AACに加えて高音質再生が可能なLDACにも対応、音質を損なわない独自アルゴリズムを採用したノイズキャンセリング機能「コンフォートANC」を搭載した。遅延を低減できる「ゲーミングモード」機能なども利用できる。IPX4準拠の防水に対応、バッテリー駆動時間は本体が最大約7時間(充電ケース含め最大約28時間)だ。
2024.12.18
コメント(0)
-

【宙に浮くような軽快なデザインが魅力】液晶ディスプレイ「FlexScan FLT」
液晶ディスプレイ「FlexScan FLT」 薄さ24.4mmでアームも付属製造/販売EIZO製品情報液晶ディスプレイ「FlexScan FLT」価格比較ここをクリック パネルは非光沢のIPSパネルで、24.4mmと薄型、モニター部の重量も約2.4kg(アーム込みで約4.5kg)に抑えている。ベゼルもフレームを感じさせないデザイン。宙に浮いているような外観だ。インターフェースをあえてUSB Type-Cのみとし、PCからの給電のみで動作可能。デイジーチェーンで増設することも可能。標準消費電力は6W。環境負荷の少ない再生プラスチックを95%使用し、梱包体積も減らすなど環境にも配慮したモデルだ。国際サステナビリティ認証「TCO Certified, Generation 10」を世界で初めて取得した。リフレッシュレートは60Hzで中間色応答速度が5ms、色域がsRGB 100%、輝度が250cd/m2、コントラスト比が1000:1、視野角は上下/左右ともに178度。
2024.12.17
コメント(0)
-

【消費電力のチェックもできる】電源タップ「700-TAP080」
電源タップ「700-TAP080」 PD対応USB充電ポート×3を装備製造/販売サンワサプライ製品情報電源タップ「700-TAP080」価格比較ここをクリック キューブ型デザインを採用した3カ口タイプのAC電源タップで、本体前面側に充電用USB Type-Cポート×3基を装備(最大で計67W)。また接続デバイスの消費電力(USBポート3基の合計消費)を表示できる電力表示パネルを備えた。本体サイズは62.5(幅)×62.5(奥行き)×49(高さ)mm、重量は332g。ケーブル長は2mだ。
2024.12.16
コメント(0)
-

【240Hz駆動+4K対応】32型有機ELゲーミングディスプレイ「G32T9W」
32型有機ELゲーミングディスプレイ「G32T9W」 中国Titan Armyブランド製となる曲面32型4Kゲーミングディスプレイ製造/販売リンクスインターナショナル製品情報32型有機ELゲーミングディスプレイ「G32T9W」価格比較ここをクリック 3840×2160ピクセル表示に対応したQD-OLED(量子ドット有機EL)パネル採用の32型ディスプレイで、リフレッシュレートは最大240Hz、応答速度は0.03ms(中間域)を実現しAdaptive-Syncにも対応した。曲率1700Rの湾曲デザインを採用。10bitカラー表示に対応しており、DCI-P3カバー率99%、Adobe RGBカバー率97%の広色域表示に対応した。HDRについては“HDR True Black 400相当”をサポートするとしている。映像入力はHDMI×2、DisplayPort×1を備える他、USB Type-Cポート×1(PD 65W)、USBハブ機能なども利用可能だ。
2024.12.14
コメント(0)
-
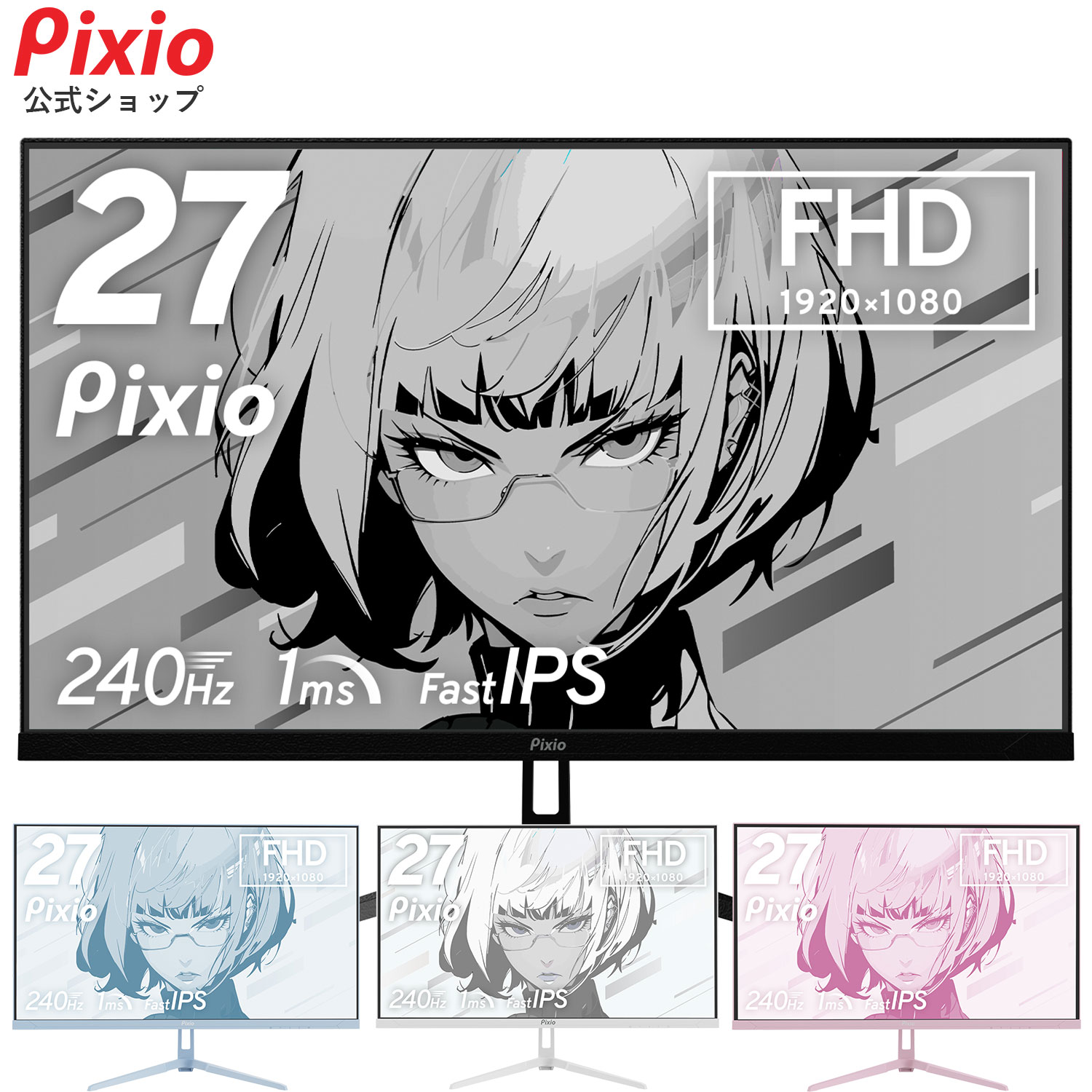
【240Hz駆動に対応】フルHDゲーミング液晶ディスプレイ「PX279 Wave」シリーズ
フルHDゲーミング液晶ディスプレイ「PX279 Wave」シリーズ カラーバリエーションは“ブラック”“ホワイト”“パステルブルー”“パステルピンク”の4タイプを用意製造/販売Pixio製品情報フルHDゲーミング液晶ディスプレイ「PX279 Wave」シリーズ価格比較ここをクリック 1920×1080ピクセル表示対応のFast IPSパネルを採用する27型液晶ディスプレイで、リフレッシュレート最大240Hz、応答速度1ms(中間域)を実現した。FreeSync PremiumおよびG-SYNC Compatibleに対応、HDR10もサポートしている。映像入力はHDMI 2.0×2、DisplayPort×1を装備。本体サイズは614.8(幅)×210.9(奥行き)×461.7(高さ)mm、重量は4.4kg。
2024.12.14
コメント(0)
-

【X870チップ初のMini-ITXマザー】Mini-ITXマザーボード「X870I AORUS PRO ICE」
Mini-ITXマザーボード「X870I AORUS PRO ICE」 AMD X870チップセット採用、Socket AM5対応のオールホワイトのMini-ITXマザーボード製造/販売GIGABYTE製品情報Mini-ITXマザーボード「X870I AORUS PRO ICE」価格比較ここをクリック 基板やヒートシンク、コネクター、スロットにいたるまで、オールホワイトで塗装したAMD X870チップセット搭載のマザーボード。Mini-ITX対応マザーとしては初のAMD X870チップセット搭載品となるほか、帯域幅40GbpsのUSB4を備えるのも特徴だ。電源回路は8(VCORE/110A SPS)+2(SOC/80A SPS)+1フェーズ(MISC/30A MXL)構成。基板には2oz銅層を備えた10層のサーバーグレードPCBを採用する。拡張スロットはPCI Express(5.0)×16×1、メモリーは、DDR5 DIMM×4(DDR5-8400(オーバークロック)、最大128GB)。オンボードインターフェースは、2.5ギガビットLAN、Wi-Fi 7+Bluetooth 5.4、サウンド、M.2×2、SATA3.0×2などを装備する。
2024.12.13
コメント(0)
-

【未来の鉄道は?】最新図解 鉄道の科学 車両・線路・運用のメカニズム
最新図解 鉄道の科学 車両・線路・運用のメカニズム 鉄道の安全性や利便性が今後も向上し、他の輸送機関と足並みをそろえながら交通全般の発展に貢献するという技術的な方向性は、変わることはないでしょう。(282ページ)著者・編者川辺謙一=著出版情報講談社出版年月2024年7月発行本書は、ブルーバックスにおける3冊目の『鉄道の科学』だ。著者は、鉄道関係の執筆も多い交通技術ライター、川辺謙一さん。2024年時点の最新情報を交えながら、多くの図や写真を使って鉄道技術を解説する。そして、現在鉄道が抱える課題と、その技術的解決策を提示する。第1章は鉄道の基礎知識。鉄道は陸上輸送での大量高速輸送に優れ、エネルギー効率が高く、CO2排出量が少ない。人による操舵が不要で、16世紀にはドイツやイギリスで木製レールが使用されていた。鉄道車輪は車軸と一体化した輪軸 (りんじく) で、デファレンシャルギアを持たず、円錐形の踏面 (とうめん) によりカーブでの内輪差・外輪差を吸収する。内側のフランジは脱線防止機能を果たし、粘着駆動による加減速が可能だが、空転しやすい点が弱点である。第2章は車両のメカニズム。2024年4月時点で、日本の鉄道車両の81.2%が電車である。戦前、石炭消費量を抑えるため電化が進み、戦後はフランスの影響で交流電化も導入され、現在は保守性に優れる交流モーターが主流だ。日本の鉄道車両は台車で支えられるボギー車が一般的で、建築限界内で運行される。VVVFインバーターによる交流モーターの採用で省エネ化が進み、カルダン駆動が主流となった。保守では TBM(時間基準保全:Time Based Mentenance)から CBM(状態基準保全:Condition Based Maintenance)へと進化し、車両状態を監視・予測する技術が導入されている。第3章は線路のメカニズム。軌道にはバラスト軌道と、維持管理が容易なスラブ軌道がある。レールは通常25メートル(定尺レール)で、長さに応じて短尺、長尺、ロングレールに分類される。ロングレールは継ぎ目が少なく、振動や騒音が減り、負荷も軽減される。レール間隔(軌間)は標準的に1435mmである。単線の運転本数上限は1日約80本、複線では1時間片道最大30本まで運行可能である。第4章は運用のメカニズム。輸送計画は需要予測に基づき、列車ダイヤを中心に進行する。ダイヤ決定後に乗務員や車両の行程表が作成され、信号や標識とともにATSやATCが導入される。近年は無線制御の ATACS (アタックス) が導入され、無人運転の GoA4 を実現するATOも普及している。東海道新幹線ではCTCやCOMTRAC (コムトラック) が導入され、運行管理が効率化された。鉄道はバリアフリーやユニバーサルデザインにも配慮している。第5章は新幹線と高速鉄道。新幹線は1970年に施行された「全国新幹線鉄道整備法」に基づき定義され、戦前の「弾丸列車計画」で取得した用地により、東海道新幹線の建設が短期間で完了した。新幹線の技術は、スピード、安全、確実性を重視した。1992年に登場した 300系は、騒音基準の壁を克服し、最高速度を220km/hから270km/hに引き上げ、「のぞみ」として営業運転を開始した。新幹線の影響で、フランスTGV、ドイツICE、アメリカAcela Express、中国の高速鉄道網などが発展した。1960年代には鉄輪走行の限界があり、超伝導磁気浮上式鉄道(超電導リニア)の開発が始まった。現在、超電導リニアは日本と中国で開発中で、常伝導リニアも運行されている。さらに、イーロン・マスク氏はハイパーループを提案し、1000km/h以上の速度を目指している。第6章は街を走る都市鉄道として、地下鉄やモノレール、新交通システムなどを紹介する。世界初の都市鉄道は1832年のニューヨーク・アンド・ハーレム鉄道で、1863年にロンドンで世界初の地下鉄「メトロポリタン鉄道」が開業した。ニューヨーク地下鉄は1904年、東京は1903年に山手線と中央線を開設した。AGT(自動案内軌条式旅客輸送システム)は1981年に神戸で無人運転を実現した。多くの都市が地下鉄整備後に路面電車を廃止したが、近年は再び路面電車が注目され、ストラスブールや富山、宇都宮でLRTが導入されている。第7章は山岳鉄道というニッチな話題。鉄道は粘着駆動という物理現象に依存しているがゆえ、山岳地帯の勾配対策は避けて通れない。まずは、軌道を工夫するスイッチバックやループ線。大井川鐵道に残るラック式(アプト式)。粘着駆動を諦めたケーブルカー(鋼索鉄道)やロープウェイ、リフト。日本におけるケーブルカーの最急勾配は、高尾登山電鉄の608パーミル(斜度31度18分)だ。第8章は進化する鉄道として、川辺さんは現在鉄道に求められている課題として、 ?環境対策 ?モビリティ革命への対応 ?人口減少への対応の3つを挙げる。?は気動車がかかえる課題だ。蓄電池電車や水素電車の試験運用がはじまっている。?のモビリティ革命は、自動車において、自動運転や電気自動車といった革新的な車両が実用化されていることを指し、自動車が電車に近づいてきたと指摘する。そして、これは?人口減少への対応にもつながる。現在、鉄道各社が展開している MaaS (マース) (Mobility as a Service)――国土交通省は「地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービス」と説明――が繋がり、キャッシュレス・チケットレスになることで、利便性が向上する。鉄道の維持や運営に関わる業務の省力化も必要だ。川辺さんは最後に、鉄道を取り巻く技術には、さまざまな輸送機関との「競争」から「協調」へシフトすることが求められている一方で、鉄道の安全性や利便性が今後も向上し、交通全般の発展に貢献するという技術的な方向性は変わることはないだろうと締めくくる。わが家には自家用車がない。私は運転免許をもっていない。必然的に公共交通機関に頼らざるを得ない――というわけで、ぱふぅ家のホームページには、わが家が利用した様々な公共交通機関の写真を掲載している。全国津々浦々まで公共交通機関が伸びている日本だからこそ、安心して楽しい旅ができるというものだ。そんななか、地域の人口減少や相次ぐ自然災害で、廃線になる鉄道路線が増えている。ビジネスとしては致し方のない決断であろうが、これから歳をとり、いよいよもって、公共交通機関がないと旅ができなくなる私にとっては、どんな姿形になってもいいので、全国比に広がる公共交通網を維持してほしいと願う。その解決策の幾つかが、本書の第8章に提示されている。私はIT技術者でもあるので、MaaS(国鉄時代の MARS (マルス) に発音が似ており懐かしい響きだ)が事業会社を超えて連携し――インフラ周りはGoogleのような海外資本に占拠されてはいけない――スマホでもマイナンバーカードでも何でもいいので、窓口は券売機に並んでチケットを買うことなくスマートに旅行が続けられるといいと願う。毎度の家族旅行では大量の切符を持たされるのだが、歳をとると、たぶん、忘れたり紛失したりする。若い駅員さんに迷惑を掛けたくはないので、どうか早くチケットレスに移行してほしい。そして、鉄道が大改革を遂げ、生きているうちに、ブルーバックスから4冊目の『鉄道の科学』が発刊されることを願ってやまない?
2024.12.12
コメント(0)
-
【お湯の温度と量にこだわった】96度ハンドドリップコーヒーメーカー
96度ハンドドリップコーヒーメーカー お湯の温度と量にこだわったハンドドリップコーヒーメーカー製造/販売サンコー製品情報96度ハンドドリップコーヒーメーカー価格比較ここをクリック 4杯分まで対応するドリップ式コーヒーメーカー。コーヒー粉と水をセットして抽出ボタンを押すと、96度のお湯で抽出を始め、その後は93度を維持しながら6カ所の穴からお湯を注ぐ。抽出後のコーヒーサーバーは70度で保温する。サンコーは「バリスタが手で入れたような美味しいコーヒーがボタン1つで味わえる」としている。本体両サイドにはLEDライトを搭載。「湯沸かし中」は青、「抽出中」は紫、「出来上がり」は赤という3色でコーヒーの抽出状態が一目で分かるようにした。
2024.12.11
コメント(0)
-

【エントリー価格帯を実現】23.8型ゲーミング液晶ディスプレイ「G-MASTER G2445HSU-B2」
23.8型ゲーミング液晶ディスプレイ「G-MASTER G2445HSU-B2」 エントリー価格帯を実現した100Hz駆動の23.8型フルゲーミング液晶ディスプレイ製造/販売マウスコンピューター製品情報23.8型ゲーミング液晶ディスプレイ「G-MASTER G2445HSU-B2」価格比較ここをクリック 1920×1080ピクセル表示に対応したIPSパネル採用の23.8型液晶ディスプレイで、リフレッシュレート最大100Hz、応答速度1ms(MPRT)を実現した。映像の暗部の視認性を高める“黒レベル補正機能”を搭載、Adaptive Syncもサポートする。映像入力はHDMI×1、DisplayPort×1を装備。USB 2.0対応の2ポートUSBハブ機能も利用可能だ。
2024.12.10
コメント(0)
-
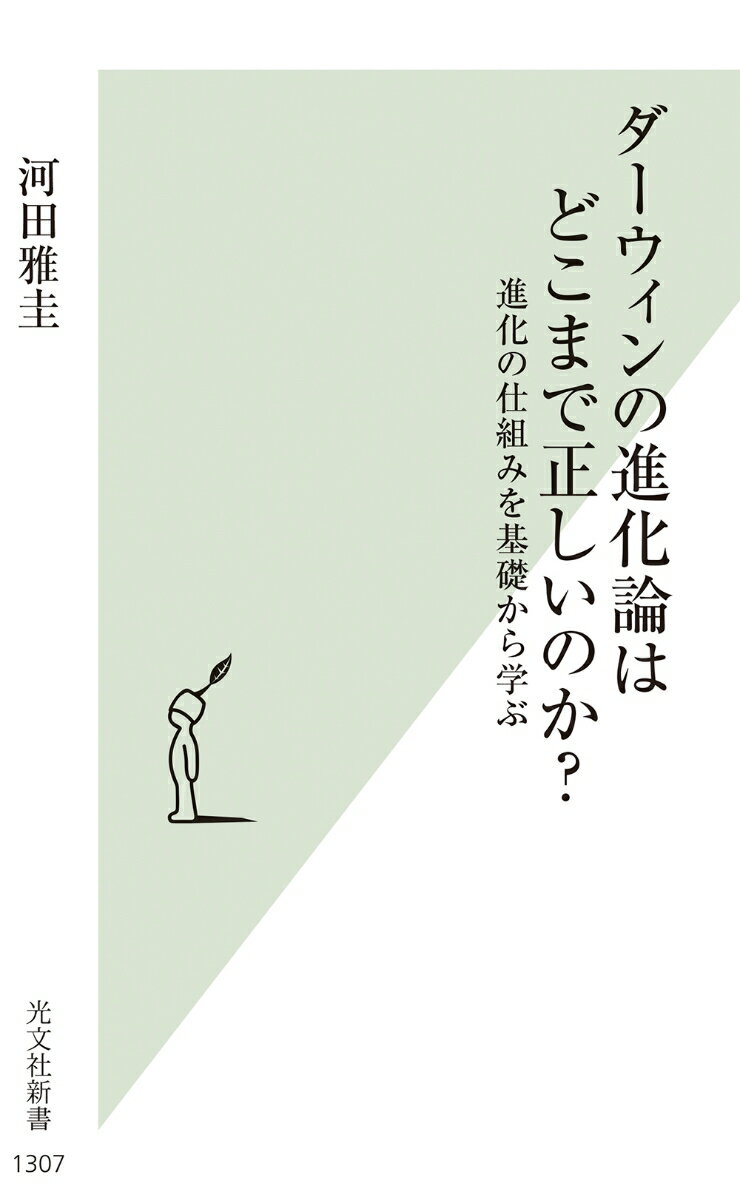
【知識をアップデートしよう】ダーウィンの進化論はどこまで正しいのか?
ダーウィンの進化論はどこまで正しいのか? 本節で考察してきたように、「小進化では大進化が説明できない」という理解は誤解である。著者・編者河田雅圭=著出版情報光文社出版年月2024年4月発行著者は、進化学、生態学がご専門で、ヒトを含め様々な生物を対象にゲノムレベルから集団などのマクロレベルをつなぐ進化研究を行ってきた河田雅圭 (かわだ まさかど) さん。本書を読んで、中学・高校の生物で習った「進化」が、間違いではないにせよ、相当曖昧な内容であったことを再認識させられた。オオモリシモフリエダシャクの工業暗化やヒトの身長の変化について、教科書や参考書で曖昧な触れ方だったが、本書を読んで「進化」の定義に当てはまることがわかった。進化とは何か――第1章では、ポケモンの「進化」が進化でないことは衆知のこととして、ネットの辞書やWikipediaの定義も必ずしも正しいとは限らない。河田さんは進化を「生物のもつ遺伝情報(主にゲノム配列)に生じた変化が、世代を経るにつれて、集団中に広がったり、減少したりすること、またそれに伴って、生物の性質が変化すること」と定義する。進化は生物の生存に有利な方にも不利な方にも起きる。さらに、本書でよく使われる用語の意味を図表1-1に整理している。ダーウィンの進化論には様々な解釈があるとしながらも、河田さんは大きな枠組みとしては現在の進化学にも引き継がれているという。ただし、ゲノム解析を含む様々な生命現象が解明されてきたことで、より複雑で多様な進化メカニズムが明らかになりつつあるともいう。第2章では変異・多様性について解説する。まず注意することは、ヨーロッパ人が高身長になったのは、身長を高くする突然変異が、低くなる突然変異より頻繁に発生したのではなく、自然選択によって方向付けられたということ。ヨーロッパ人では身長を高くするようなアレルに自然選択が働き、日本人の場合は低くなるようなアレルに自然選択が働き、数千~数万年かけて進化したと推定されている。だが、環境要因によってる突然変異率が増加するかどうかは、まだ確かめられていない。遺伝的多様性は、個体の生存や繁殖への効果が有利になるようなアレルと同時に、有利にも不利にもならない中立なアレルや不利になるような有害なアレルが増大するということだから、必ずしも種の存続に有利に働くとは限らない。分布域の中心地域の環境に適応しているアレルは、分布域の境界付近では不利になる。このため、分布域を越えて拡大できない可能性がある。集団中の遺伝的多様性は、突然変異と遺伝的浮動のバランス、突然変異と負の自然選択のバランス、平衡選択の3つのメカニズムで創出・維持されている。遺伝的多様性によって、生物が環境に適応するように進化が促進されることもあるが、それは結果であって、環境への適応を促進することが原因となって遺伝的多様性が生じたり、増大しているわけではない。ここで河田さんは、遺伝子の定義として、「主にタンパク質に翻訳されるゲノム領域(コード領域)とその翻訳を調節する領域」を指すと定義するが、場合によってはコード領域のみを遺伝子と呼ぶこともあるという。学校の生物学では、獲得形質は遺伝しないと習ったが、近年、DNA配列の変化に依存しないで遺伝するエピジェネティク遺伝が話題になっている。せいぜい数世代の遺伝にとどまる者だが、なかには何世代にもわたって遺伝するエピアレルと呼ばれるものがある。エピアレルは進化の原動力となったり、DNA配列の変化による進化をより効果的にする場合がある。第3章では自然選択について解説する。冒頭、ディズニー映画『白い荒野』で有名なレミングスの集団自殺を取り上げる。だが、現在の進化学での一般的な理解は、集団にとってはプラス(集団の維持や保存)に働くが、個体の生存や繁殖にはマイナスに働く性質が、集団にとって有利だという原因で進化することは少ないと理解されているという。生物は種の維持のために進化しているわけではない。「種の保存」の定義についても再確認する。たとえば、イリオモテヤマネコやツシマヤマネコは保存すべき対象となっているが、これらは大陸に生息するベンガルヤマネコの亜種であるから、「種の保存」ではなく、あくまで地域集団の保存である。次に>河田さんは、1976年にドーキンスが出版して話題になった『利己的な遺伝子』を取り上げ、ここでいう遺伝子が荒れるという意味であるならば、「利己的な遺伝子が個体の表現型を進化させた」という比喩的表現は当てはまらないと指摘する。1973年にシカゴ大学のヴァン・ヴェーレンは、化石の種の絶滅確率を調査し唱えた仮説がその後修正され、生物は常にほかの生物と相互作用をしており、ほかの生物が進化することで、生物をとりまく環境は常に変化することや、その変化が常に新たな自然選択を働かせ、適応進化が継続していくという共進化があることが間違いないと考えられるようになった。第4章では種や大進化を解説する。「種」という用語は、生物学的に見ると曖昧で、すくなくとも進化とは関係しないという。たとえばイヌは、最初から人間によって選抜され、オオカミから進化したわけではない。オオカミが、人間のゴミを漁るように適応していくことで、イヌに分化したと考えられている。その後、ヒトの生活圏に定着したイヌは、オオカミとの交雑頻度が減り、結果的に「生殖隔離」が行われた。この生殖隔離機構が進化した結果、独立した遺伝的性質をもつ集団が進化し、地球上に様々な種類の生物が進化してきたという。さて、こうした種の中で起きる「小進化」は、種を超えて、属、科、目、綱、門という高次分類群間で見られる生物の大きな違いを引き起こす「大進化」を起こすことができるだろうか。河田さんによれば、時間をかければ、小さな進化の積み重ねで大きな進化が達成されるという。だが、それほど時間がかからず、不連続に大きな変化が生じたようなギャップは説明できるだろうか。まだ研究途上ではあるものの、その説明もできるようになっているという。たとえばキリンの首の長さも、化石標本の解析から中間の長さを持つ化石が同定されている。遺伝子は遺伝子によって調節されているが、これらが複雑につながった遺伝子制御ネットワークが変異することで大進化が起きるケースもある。魚が陸上にあがり、ヒレが肢に変化していった様子も、遺伝子制御ネットワークを使って説明ができる。また、これまでの地球史上で何度か起きた大量絶滅のような大規模な環境変化は、自然選択の力を緩和し、それまで淘汰されていた突然変異個体が生き残る余地を広げるという。脊椎動物も、過去に数回の全ゲノム重複が生じ、植物の倍数体のようになった時期が確認できている。倍加した領域は急速に消失し、もとに近い状態に戻るが、その消失率は一定していない。ヒトでは2回目の全ゲノム重複後、20~30%の割合で倍加したゲノム領域が保持されている。大規模な環境変化の時にゲノムを倍数化した生物は、大量絶滅を免れたようである。本書は、進化に関わる最新の定義を明確化し、その理論を整理するだけでなく、豊富な実験・観察データを紹介し、その理論の確からしさを担保する。結果として、学生時代に曖昧だった生物進化の要所要所を補強してくれた。全体的に、実験や観察の結果から導かれる遺伝子頻度の図表を使って、論理的に(数学的に)厳然たる事実を提示する。また、「アレル」という用語は初めて目にしたが、こうした新しい概念も定年に説明しており、曖昧だった記憶の整理に役立つ。冒頭で触れた、イギリスの産業革命の時の大気汚染がもとでオオモリシモフリエダシャクが工業暗化したのは、いまでは、チョウやガの色素沈着や鱗粉の発生速度を制御する遺伝子であるcortex遺伝子の発現調節領域に転移因子(トランスポゾン)が挿入されたためだということ分かっている。その意味では、これも進化である。本書では触れられていないが、オランダ人が世界一の高身長になったのは、高身長な配偶者を求めたからだという研究報告がある。これを自然選択といっていいのかどうか分からないが、突然変異の頻度の違いで起きたことではないのは確かだ。だとすると、日本人が江戸時代に低身長になったのは、そういう選択が働いたからかもしれない。また、近年の平均身長の伸び悩みは、バブル期のような高身長のパートナーを求めなくなった結果かもしれない。オランダ人も、1980年生まれをピークに身長が低下傾向にあるという。これも本書で触れていないが、人類進化のミッシングリンクも、多くの研究成果を積み重ねていくと、ミッシングリンクではなくなりそうだ。つまるところ、学生時代の授業で分からなかったこと、曖昧だったことをそのままにして思考停止するのではなく、常に新しい情報・知識を学ぶことの大切さを、本書は教えてくれる。
2024.12.09
コメント(0)
-

【メッシュWi-Fi対応】Wi-Fi 7無線LANルーター「RT-BE14000」
Wi-Fi 7無線LANルーター「RT-BE14000」 複数のルーターでメッシュネットワークを構築できるAiMeshテクノロジーに対応製造/販売ASUS JAPAN製品情報Wi-Fi 7無線LANルーター「RT-BE14000」価格比較ここをクリック Wi-Fi 7接続に対応した無線LANルーターで、複数のルーターでメッシュネットワークを構築できるAiMeshテクノロジーに対応した。7基のアンテナを内蔵した小型デザイン筐体を採用、6GHz帯最大8643Mbps、5GHz帯最大4323Mbps、2.4GHz帯最大688Mbpsの接続をサポート。有線LANポートは2.5GbE×2(WAN×1、LAN×1)、ギガビット有線LAN×2を備えている。
2024.12.08
コメント(0)
-

【Wi-Fi 7対応の高機能無線LANルーター】無線LANルーター「ASUS RT-BE92U」
無線LANルーター「ASUS RT-BE92U」 Wi-Fi 7接続に対応した高機能無線LANルーター製造/販売ASUS JAPAN製品情報無線LANルーター「ASUS RT-BE92U」価格比較ここをクリック Wi-Fi 7接続をサポートした多機能設計の無線LANルーターで、6GHz帯最大5764Mbps、5GHz帯最大2882Mbps、2.4GHz帯最大1032Mbps(いずれも理論値)の接続に対応、計7ストリーム(6GHz帯×2、5GHz帯×2、2.4GHz帯×3)の利用が可能だ。4基の外付けアンテナを搭載、高パフォーマンスを発揮できるクアッドコアCPUを内蔵した。有線ポートは10GbEポート×1(WAN/LAN)、2.5GbEポート×4(WAN/LAN×1、LAN×3)を備えている。
2024.12.07
コメント(0)
-
【ワット数表示や巻取りケーブルが合体】PD充電器「エアベロス」
PD充電器「エアベロス」 最大65W充電または3台同時充電が可能なUSB PD充電器製造/販売エアリア製品情報PD充電器「エアベロス」価格比較ここをクリック USB Type-Cポート、80cmの巻取り式USB Type-Cケーブル、USB Type-Aポートからなる、3つの出力ポートを搭載したUSB充電器。さらに充電している合計のワット数を表示するチェッカー機能まで備えた、マルチなアイテムだ。USB Type-Cポートと巻取り式USB Type-Cケーブルは、5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3.25A出力に対応し、単独使用でそれぞれ最大65W充電が可能。USB Type-Aポートは5V3A/9V2A出力に対応し、単独使用時に最大18Wで充電できる。また、2ポート使用時はUSB Type-CポートとUSB Type-Cケーブルで合計最大65W充電、USB Type-CポートとUSB Type-Aポートで合計最大15W、USB Type-CケーブルとUSB Type-Aポートで合計最大63W。3ポート同時使用時は、合計最大60Wで充電できる。本体サイズは幅50×奥行き50×高さ53mm、重さ159g。電源プラグはコンパクトに本体に収納できるスイングプラグが採用されている。
2024.12.06
コメント(0)
-

【180Hz駆動をサポート】27型WQHDゲーミング液晶ディスプレイ「GIGABYTE M27QA ICE」
27型WQHDゲーミング液晶ディスプレイ「GIGABYTE M27QA ICE」 台湾GIGABYTE TECHNOLOGY製27型WQHDゲーミング液晶ディスプレイ製造/販売シー・エフ・デー販売製品情報27型WQHDゲーミング液晶ディスプレイ「GIGABYTE M27QA ICE」価格比較ここをクリック 2560×1440ピクセル表示に対応したIPSパネルを採用する27型ゲーミング液晶ディスプレイで、リフレッシュレート最大180Hz、応答速度1ms(MPRT)を実現した。DCI-P3比95%の広色域表示をサポート、VESA Display HDR400に対応している。映像入力はHDMI×2、DisplayPort×1、USB Type-C×1を装備。PIP(ピクチャーインピクチャー)/PBP(ピクチャーバイピクチャー)での2画面同時表示機能やKVMスイッチ機能も利用できる。
2024.12.05
コメント(0)
-

【ゲーマー必見の新技術搭載で登場】マザーボード「X870 EAGLE WIFI7」
マザーボード「X870 EAGLE WIFI7」 GIGABYTEのEAGLEゲーミングATXモデルで、AMD X870チップセットを搭載製造/販売GIGABYTE製品情報マザーボード「X870 EAGLE WIFI7」価格比較ここをクリック X870 EAGLE WIFI7は、GIGABYTEのEAGLEゲーミングATXモデルで、14+2+2フェーズ・デジタル電源設計に加え、VRM用大型ヒートシンクとM.2 Thermal Guardを備える。PCIe x16スロットはEZLatchによるボタン式のクリックリリース設計が施され、DDR5 EXPOおよびXMPをサポートしている。また、リアに2連のUSB4 Type-C(40Gb/s)、フロントにUSB 3.2 Gen.2x2 Type-C(20Gb/s)を搭載し、さらなる拡張性を提供している。接続面でも優れた性能を持ち、2.5 GbE有線LANとWIFI 7 802.11be無線LANにBT 5.4が組み合わさった設計となっている。アンテナもEZ-Plugでワンタッチ着脱可能。さらに、Q-Flash PlusとSmart Fan 6などの機能も充実しているため、快適な使用感をユーザーに提供するという。
2024.12.04
コメント(0)
-

【ビデオ会議にも役立つ】USB接続コンデンサーマイク「HyperX QuadCast 2 S」
USB接続コンデンサーマイク「HyperX QuadCast 2 S」 イヤフォンのマイクとは違う製造/販売日本HP製品情報USB接続コンデンサーマイク「HyperX QuadCast 2 S」価格比較ここをクリック ゲーム実況者や配信者向けのマイクであるHyperX QuadCastシリーズだが、動画制作などで純粋に高品質なマイクを必要としているクリエイターにも、広く人気を集めているシリーズだ。その最新モデルとなるHyperX QuadCast 2とHyperX QuadCast 2 Sは、録音音質の強化や多機能ノブの追加、ショックマウントの改良などが施されたアップグレードモデルとなっている。音質にこだわるプロフェッショナルな用途向けの製品ではあるが、ビデオ会議やウェビナーなどで少しでも音質良く声を届けたいと思っているなら、一般の人でも検討してみる価値はありそうだ。前モデルの「HyperX QuadCast」と「HyperX QuadCast S」は、どちらもオーディオ品質が16bit/48kHzだったが、新モデルではそれぞれ24bit/96kHz、32bit/192kHzにアップデートしている。マイク感度は単位が異なるので直接の比較はできないが、ライティングは赤色LEDのみのQuadCast 2に対して、HyperX QuadCast 2 Sはフルカラーとなっている。スタンドにはショックマウントも搭載し、振動を極力拾わないようになっている。また、スタンドを外して、市販のマイクアームを取り付けることもできる。新モデルの大きなアップデートは、多機能ノブが追加されたことだろう。従来モデルでは、ゲインの調整は底部のダイヤルで調整、指向特性は背面のノブで調整する必要があったが、これらが多機能ノブだけで操作可能になった。また、多機能ノブでは、背面に接続したイヤフォン/ヘッドフォンの音量調整やモニターミックスの調整、指向特性の変更を行える。背面には3.5mmジャックがあり、イヤフォン/ヘッドフォンを接続することが可能だ。PCやゲーム機からの音声を再生するという通常の利用方法に加え、マイク入力の音声を確認するライン出力としても利用できる。普段、マイクを通した音がどのように聞こえるのかは自分では把握しづらいものだが、ライン機能を使えば簡単に把握できる。この辺りはゲーマー向けというより配信者を意識した機能なのかもしれないが、普通にマイクを使う上でも便利な機能だ。指向特性は従来と変わらず、以下の4つを搭載する。カーディオイド:手前側(自分側)の単一指向性。ビデオ会議などで通常のマイクとして使用する場合は、このモードを使うことになるだろうオムニディレクショナル:無指向性。リアルな会議など、複数人で話すのを録音する場合に使用するが、自宅ではあまり使うことはなさそうだステレオ:左右方向の指向性。楽器演奏などを録音する場合には、手軽にステレオ録音が可能となるバイディレクショナル:手前側と向こう側の2方向の指向性。対面での会議などを録音するのに使う多機能ノブを2秒長押しすると、「カーディオイド→無指向→ステレオ→双方向」と切り替わる。普段使いということを考えるなら、カーディオイドモードで固定して使うことになりそうだ。基本的な設定は全て本体だけで行えるが、ゲーミングらしいライティングの設定は専用ソフト「HyperX NGENUITY」から行える。なお、HyperX QuadCast 2/2 S自体はMacでも利用できるが、macOS用のHyperX NGENUITYはリリースされていない。HyperX NGENUITYでは、マイクの音量や接続したイヤフォン/ヘッドフォンの音量調整、マイクのミュート、指向性パターンを画面上から変更できる。また、本体では設定できないハイパスフィルターも有効にできる。筆者の環境ではそこまで大きな違いは感じなかったのだが、PCのファンのノイズやエアコンの動作音など、低音域の騒音をカットしてくれる機能だ。ラインナップHyperX QuadCast 2 SHyperX QuadCast 2
2024.12.03
コメント(0)
-

【再生プラ筐体を採用】テプラ PRO SRR560
テプラ PRO SRR560 PCレスによる単体印字にも対応したラベルライター製造/販売キングジム製品情報テプラ PRO SRR560価格比較ここをクリック バックライト搭載液晶パネルを標準で搭載。出力フォントとして、視認性に優れるモリサワのユニバーサルデザインフォントを採用。内蔵する文字変換辞書を強化しており、「建築土木」「医療」向けの専門用語をスムーズに変換できる。また今回のモデルでは筐体素材に再生プラスチックを約30%採用しているのも特徴だ。Windows PC用ラベル出力ソフト「テプラ クリエイター」(SPC10)の利用にも対応。本体サイズは約184(幅)×238(奥行き)×79(高さ)mm、重量は755gだ(電池/テープ含まず)。
2024.12.02
コメント(0)
-

【USBドングルで超低遅延】ワイヤレスイヤフォン「HyperX Cloud MIX Buds 2」
ワイヤレスイヤフォン「HyperX Cloud MIX Buds 2」 ANCにも対応したTWSイヤフォン製造/販売HyperX製品情報ワイヤレスイヤフォン「HyperX Cloud MIX Buds 2」価格比較ここをクリック 2022年に発売された「HyperX Cloud MIX Buds」の後継モデルだ。前モデルはHyperXブランド初のゲーミングイヤフォンとして、Bluetooth接続に加え、USB Type-C接続の専用ドングルを利用した独自の2.4GHz接続に対応しており、超低遅延を実現していた。HyperX Cloud MIX Buds 2にも、これらの特徴はしっかりと受け継がれている。接続はBluetooth 5.3の他に、付属のドングルを利用した2.4GHzワイヤレス接続に対応する。20msの超低遅延を実現しているのも見どころだ。ドングルはUSBポートに直接挿して使用するが、ノートPCなどで隣のポートと干渉する場合に備え、延長用のアダプターも付属している。ドングルを使用する場合、面倒なBluetooth接続などの設定が必要ないのもメリットだ。USBオーディオに対応しているデバイスであれば、ドングルを挿すだけでイヤフォンが利用可能になる。バッテリー駆動時間は約7時間で、ケースを併用すれば最長26時間となる。イヤフォンの充電時間は約1.5時間となっている。Bluetoothとドングルでの2.4GHz接続で、別々のデバイスに接続するマルチコネクションに対応しており、PCにはドングルを挿して2.4GHzワイヤレス接続、スマートフォンとはBluetooth接続という利用が可能だ。PCでゲーム中にスマートフォンに着信があった場合、ドングルのボタンを押すとスマートフォンで通話できる。このマルチコネクトはBluetoothのマルチポイントのように思えるが、実態はかなり異なる。ドングルを使った2.4GHz接続とBluetooth接続を併用する場合、デフォルトではBluetooth側は通話用にしか利用できない(メディア再生用の機器としては認識されない)。ドングルのボタンを長押しすることでBluetooth側でもメディア再生が可能になるが、ドングル側を利用する場合には再度長押しが必要だ。前モデルのHyperX Cloud MIX Budsはアクティブノイズキャンセリング(ANC)には非対応だったが、HyperX Cloud MIX Buds 2ではANCが搭載された。公式な数値は公表されていないが効果は高く、カナル型のパッシブなノイズキャンセルと相まって、低音だけではなく人の話し声など中音域もかなり打ち消してくれる。音質は、低音がやや強めで若干ドンシャリ傾向にある。アプリから5つのプロファイルを切り替えられるが、そこまで大きな差は感じなかった。また、自分でカスタマイズすることもできない。この辺りは、ゲーミング向けとして割り切っているのかもしれない。イヤフォン自体は、やや太めのステムが印象的な形状だ。ステム上部がタッチセンサーになっており、再生/停止や曲送り、ANCの切り替えなどの各種ジェスチャー操作を行える。専用アプリ「HyperX NGENUITY」からカスタマイズも可能だ。イヤーチップはS/M/Lの3サイズが付属しており、標準でMが装着されている。専用アプリのHyperX NGENUITYは、Android/iOS/Windows用が用意されている。残念ながらmacOS向けにはリリースされていないが、イヤフォン自体はMacでも利用可能だ。Macで利用中に、iPhoneにインストールしたアプリから設定を変更することもできる。Bluetoothの対応コーデックはSBCとAAC、それにLC3に対応している。
2024.12.01
コメント(0)
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
-

- 楽天アフィリエイト♪
- 【低消費電力を実現】スタンダード23…
- (2025-11-26 12:10:13)
-
-
-

- 大好き!デジカメ!
- 10年以上昔のコンデジに復活の日を
- (2025-11-12 07:20:04)
-
-
-

- 家電よもやま
- [楽天市場] 薪ストーブ ・ 石油ス…
- (2025-11-25 18:43:40)
-







