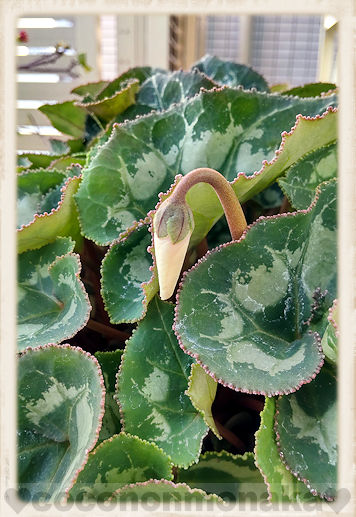2015年01月の記事
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-
吉野弘さん
クローズアップ現代で、吉野さんを取り上げていた。 一番最初に吉野さんの詩にふれたのは、茨木さんの『詩の心をよむ』だった。その後、「夕暮れ」という死にふれ、心をゆすぶられた。調べたら吉野さんの詩だった。 今日の番組の中でも朗読されていた。私はこの詩に弱く、つい涙腺が緩んでしまう。 吉野さんが詩人になろうと決心したきっかけは敗戦体験であったことを初めて知った。 「詩人になる」、という言葉にはっとした。「詩を読もうと思った」は、しっくりこない。やはり、「詩人になる」のだ。そういう道を選ぶのだ。 「詩人」は、なるものなのだろうか、という思いはある。「詩人」はやはり神様に選ばれた人だという思いが私にはある。 ただ、どうでもいいことなのだが、ゲスト出演していた詩人で国語の先生が、「好悪」を「こうあく」と読んだ。アッと思った直後に、字幕が出て、そこにはご丁寧にも、「こうお」という字幕が出ていた。生徒と同僚からからかわれないだろうか・・。こういう時に、再収録とか編集とかしないのかな・・。 クローズアップ現代で吉野さんを取り上げてくれたこと、敗戦体験が出発点になったことを取り上げてくれたことについてNHKに感謝のメールを入れた。
2015.01.27
コメント(2)
-
『ローザ・ルクセンブルク』
『ローザ・ルクセンブルク』パウル・フレーリヒ 伊藤成彦 お茶の水書房 「両端の燃える蝋燭のように」生きることをモットーとした彼女は、1919年1月15日、虐殺された。 本文は、360ページほどであるが、そのあとに付されている「ローザ・ルクセンブルクと現代」(フレーリヒ)、「バウル・フレーリヒの横顔」(伊藤成彦)を読むと、ローザも著者フレーリヒも甚だしい毀誉褒貶の中を生きてきたことが分かる。それは、もっぱら、ソ連内部での権力闘争の結果として現われてきた現象だった。 学生時代にレーニンと彼女との党組織論を巡る論争を少しかじっただけであったから、今回の読書で、彼女の全体像にふれることができたことを遅まきながら嬉しく思っている。 彼女自身の著作を全く読んだことのない私にとって、彼女が理論的にどんな過ちを犯したかは評価できない。ただ、以下の箇所を読んだ時に、その先見性に驚嘆した。 「全国の政治生活の抑圧とともに、ソヴィエトの内部の生活もまた次第に萎縮していかざるを得ない。普通選挙や、何ものにも妨げられぬ出版・集会の自由や、自由な論争がなければ、あらゆる公共機関における生活は亡び、偽りの生活になり、そこには官僚制度だけが唯一の生きた要素として残ることになる。公共生活は徐々に眠り込み、無尽のエネルギーと無限の理想主義を持った数十人の政党指導者が支配と統治を行い、実際にはその中の十数人の卓越した幹部たちが指導に当たり、労働者階級のエリートたちが指導者の演説に拍手を送り、提出された決議を満場一致で承認するために時折会議に召集されるという事になる。それゆえにこれは派閥政治である。もちろん独裁には違いないが、しかし、プロレタリアートの独裁ではなくして、一握りの政治家の独裁、すなわちブルジョア的な意味でのジャコバン支配の意味での独裁である。戒厳状態の長期継続は、どんな場合にも、政治の専横化をもたらさずにはおかず、専横化は社会を堕落させずにはおかない」(p297~8) これは、10月革命の直後といっていい時期に書かれている。もちろん彼女は、10月革命を称賛し、革命政府がやむを得ず犯さねばならなかった人権の抑圧、反対者への苛酷なまでの弾圧を批判しつつも、その原因をドイツをはじめとする西欧諸国での革命の挫折に求め、嘆いている。 そしてもう一つ、彼女の人柄をよく示すエピソードを紹介しておこう。1907年にベルリンで開かれた演説会でのことである。この演説会を監視するために一人の憲兵士官と、青服の老巡査とが会場にいた。彼女は士官が解散命令を出しそうになるとテーマを変え、警察が許可した内容の範囲にとどまって、士官に命令を出させなかった。 彼女は士官が腰を下ろしたのを見計らって、資本と労働との間に挟まれ押しつぶされていく小市民の惨めな生活について語り始め、国家の従僕が抑圧機構の中に組み込まれ、犠牲になっている現状を語り、以下のように続けた。 「『そしてあなたも』と彼女は憲兵士官の方に向き直っていった。『あなたもまた、ブルジョアジーとその人民収奪機構に奉仕する、単なる道具以外のなにものでもないのです。あなたがそれを知っているか知っていないかにかかわりなく』と。彼女の大胆な言葉に心を打たれて全聴衆が緊張した。そして特に鋭い言葉の嵐が嵐のような拍手をよんだとき、口髭をはやした青服の巡査がその拍手に合わせて手をたたいた。ローザの演説が彼自身の生活を、彼自身の生活の虚しさをついたときに、彼は一切を、自分の役職も職務も自分自身をさえも忘れてホールに集まった大衆の一人になり、思わずその大きな、がさがさした手をたたいたのである。あまりの驚きに思考も停止して呆然としていた士官の顔を見るまで、そしてその士官の顔に気が付くや、彼は拍手をやめて、両手をズボンの縫い目にぴたりと下し、興奮のあまりなお呻きながら、人間となったその数分前の職務にまた戻ったのであった」(p235~6) ローザ・ルクセンブルクは虐殺された。第一次世界大戦勃発と同時に戦争予算に賛成し、そして彼女とリープクネヒトを捕え、撲殺した社会民主党のために。この行為は、その後のドイツに大きな代償を支払わせることとなる。ドイツ共産党は「社会民主党主敵論」を取り、ついに共同してナチスの台頭を防ぐことができなかった。その経験から「人民戦線」が誕生するのだが、その紆余曲折はまた別の書物のテーマとなる。 300ページほどの本を紹介するのにはあまりにも貧しい文章となってしまったが、あとは、みなさんに読んでいただくことを薦めるのみである。 この本を読む機会を与えてくださいました。薔薇豪城さんにお礼を申し上げます。
2015.01.27
コメント(0)
-
『ペテルブルクからモスクワへの旅』
知人から、「ロシアの農奴制について書いた小説がないか」との問い合わせを受け、とりあえず『猟人日記』をすすめた。ただ、気になったので検索してみると、『ペテルブルクからモスクワへの旅』という作品があることが分かった。図書館で検索すると、抄訳を収録した本はある。世界文学集(ブッククラブ)の中のロシア文学全集全35巻の最終巻に「諸家」として30ページほどの抄訳が入っていた。ともに収録されているのは、「イーゴリ軍記」「親がかり」「知恵の悲しみ」「雷雨」など。 『ぺテルブルクからモスクワへの旅』の作者は、ラヂーシチェフ。貴族である。しかし彼は、自らの階級を裏切る形で、農奴制の非人道性をこの作品で告発する。最後は自殺に追い込まれる彼は、階級的利害に首まで浸っているのではなくて、真実に生きようとして非業の死を遂げる。 ネクラーソフの『デカブリストの妻たち』も、そうだ。ナポレオン戦争で、フランス軍を追撃して西ヨーロッパ社会を実見することになった青年貴族たちは、ロシアの現状に愕然とする。そして体制変革ののろしを上げるがあえなく逮捕されシベリアへと流刑になる。そして、彼らの妻たち、深窓の令嬢としての生活しか知らなかったはずの娘たちが夫の後を追う・・。 ロシアの大地はなんという作品群を生みだすのだろうか。 何冊かロシア文学の未読の本がある。再読したい本もある。 後日紹介したい。
2015.01.26
コメント(0)
-
歳を重ねるということについて
昨年の年末で65歳になった。『天才柳沢教授の生活』(山下和美 モーニングKC)という漫画を読んでいてふと考えたことがあったのでそれを書いてみる。 何年か前の卒業生と教授は再開する。その卒業生は、学生時代には柳沢教授を愚弄するようなセリフを吐いていた、「時代の先端」を疾走している(と思っていた)男であったのだが、教授に向かって「あの頃の自分」を否定し、恥ずかしく思うという。 教授は言う。「当時のあなたをあなたが否定するのであれば、私もあなたのことを否定します」(確かこんな意味だった)と。 私は今でも昔通りのバカである。進歩したと思うのは、読んでもいない本についてさも読んだように語ったり、不十分にしか知らないことについてまるで通暁しているかのように語る技術である。この点については格段の進歩である。 ただ、この「進歩」には副作用が伴う。やはり私も人並みに罪悪感に襲われ、慌てて本を読んで「そうだったのか・・・」と慨嘆せねばならないことである。 私は、学生時代の私を心の底から馬鹿だったと思っている。しかし、その私を今の私は否定しようとは思わない。実は、これは、学生時代から思っていたことで、「将来、『あれは若気の至りで』などというセリフだけは死んでも言わないようなジジイになろう」と固く決心していた。 だから今の私は、学生時代の私と考えていることはほとんど変わっていない。趣味も嗜好もほとんど変わっていない。寝る前に養命酒、あるいはごくごく少量のワインを飲むようになったことが変わったと言えば変わった点である。麻雀もやらなくなった・・・。 「進歩がない」と言えるかもしれない。 ただ、思想を、季節が変わったからと言って軽々と脱ぎ捨てて、最新のファッションに身を包むような人間にだけはなりたくないという気持ちはここ40年ほど変わっていない。 できれば将来、このままで棺の中に入りたいものである。
2015.01.21
コメント(2)
-
『アッラーのヨーロッパ』(2)
オランダの事情を紹介しよう。92年の統計でオランダの総人口1520万人に対して移民の人口は130万人であり、8.5%に達している。オランダも当初は、景気の循環に応じて移民は入国と帰国を繰り返すと考えられていた。しかし、定住化の傾向がはっきりしてきた70年代後半からオランダ政府は、彼らと共生しなければならないという方途を探り始めている。その結果打ち出されたのは、ドイツともフランスとも異なる「多極共存型」と表現できる方式である。複数の文化の柱が対等な関係で並立している状態、「列柱をなしている状態」と著者は表現している。 一方でオランダは、「何人も生きたいように生きる権利を持つ」という考え方がコモンセンスとなっている国でもある。「生きる」だけではなく、「死ぬ権利」も認められている。「安楽死法案」である。麻薬も医師の指導のもとで公認されている。 「飾り窓」という言葉で有名になっているような制度も公認されている。皮肉なことにこの「自由さ」がこの国のムスリムたちを戸惑わせている。彼らからみればオランダは確かにドイツやフランスに比して自分たちの宗教に対する寛容さを持っている。しかし、ムスリムたちから見れば「先進国特有の病理」があふれかえっている国でもある。 「ムスリムであってよかったと思うときは?」というアンケートの中に以下のような答えがある。 「オランダのテレビ番組で、妻を複数の男が分け合うというドラマを見たとき」(35歳男性 滞在歴22年)(p189) そしてこの本の主要なテーマとして詳述されているのが、「政教分離」をきびしく国是としているトルコについてである。 「政教分離」は、トルコ建国の父、ケマル・アタチュルク以来の方針であり、軍がこの方針を堅持しているために、紆余曲説はあっても、守られている。問題は、ヨーロッパで生活しているムスリムとトルコ政府との関係である。ムスリムたちはモスクで金曜日の集団礼拝をおこなう際に導師(イマーム)を必要とする。イスラームには、キリスト教や仏教のような聖職者(僧侶)は存在しない。その代わりに、「クルアーン(コーラン)」やシャリーアに通じた学者が権威を持ち、導師となる。現実の社会で起きている諸問題についてファトゥワー(解釈 指示)を発することもある。トルコ政府が派遣する導師はトルコの宗務庁公認の人物であるから、当然のことながら、「政教分離」を人々に説く。しかし、トルコ政府が導師を派遣する以前から、ヨーロッパ在住のムスリムたちの中から自然発生的に出てきた「導師を派遣してほしい」という声、あるいはムスリムたちが異郷(異教でもある)の地で日々ぶつかっている諸問題について積極的に取り組んできたのがAMGT(ヨーロッパ・イスラム共同体の視座・組織)という組織である。この組織は、ムスリムたちが異郷の地でムスリムとして生活するにはどうすればいいかを活動の軸としている。 その結果、トルコ出身者の間における移民組織は多様な形態をとらざるを得なくなっている。P295にその図が掲載されているのだが、問題の複雑さが視覚的にわかる。この図を見ただけで、「ムスリムとは・・・」とひとくくりにして語ることの無謀さがよくわかる。 著者の最新の単著は『イスラームから世界を見る』(ちくまプリマー新書 2012年)である。この本も読んでみたくなった。
2015.01.21
コメント(0)
-
『アッラーのヨーロッパ』(1)
『アッラーのヨーロッパ』内藤正典 東京大学出版 ヨーロッパで生活しているムスリムたち、そして彼らを受け入れている国々がどのような問題に直面しているかを様々な角度から取り上げた本である。 ヨーロッパの国としては、ドイツ、フランス、オランダが取り上げられており、ムスリムは、主としてトルコ出身者が取り上げられている。 ほぼ全ページにわたって付箋を貼り付けるほど啓発された本であったが、その第一は、ヨーロッパ三カ国の間におけるムスリムへの対し方の違いを知ることができた点である。 フランスが、厳密な政教分離を行っている国であることは、数年前に問題となった「スカーフ事件」を思い出させた。フランスでは、公立の学校では、宗教的表象を身につけて登校することは固く禁じられている。キリスト教徒であれば、十字架、ムスリムであれば、神を覆うスカーフである。 フランスはカトリック教会と世俗権力との間に厳しい対立を経験してきた国であり、「非宗教的公教育」という言葉が憲法の中に記載されている。しかし一方で「フランスはすべての信仰(信条)を尊重する」という文言が書き加えられ、「政教分離」特に「公教育の現場における信仰表明の禁止」の問題が、そんなに簡単に割り切れるものではないことを教えてくれる。 P137以降で著者は、「スカーフ問題」を振り返っている。 1989年にパリ市郊外にある公立中学校に、モロッコとチュニジア系のムスリムの女生徒がスカーフを着用したまま登校し、校長はスカーフをとるように命令、女生徒達が従わなかったために登校を禁じられたことが事件の発端であった。国民教育相であったジョスパンは、「生徒から教育を受ける機会を奪うことはできない」との決定を下した。この決定に賛同する人々は、「スカーフを着用した生徒を排除してしまえば彼らにフランスの普遍主義、解放と中立、自由の概念を教え、模索させる機会が失われてしまう」と主張し、反対する人たちは、「ライシテ(国家と宗教の分離 非宗教性)が失われ、ライシテの原則を承認しない異質な集団を国内に包摂することによってフランス社会がモザイク化する」と主張している。 最高裁判所(コンセイユ・デタ)は、この件に関して、「これみよがし」の行為によって「改宗への勧誘」抑圧や扇動につながる場合は、宗教的表象(この場合はスカーフ)を身につけてはいけない、という極めて慎重な、というか、「これみよがし」とは具体的にどんな行為を指すのかという疑問を新たに生じさせるような判断を下している。その後、94年には「スカーフを着用したままの女生徒の登校を認めるか認めないかは学校長の判断に任せる」という状態に落ち付いているようである。 フランス政府は、「フランスが得意とした分割統治」投稿(p152)の手法を採用した。内務省は、「交渉可能な相手」を指定したのである。「交渉可能な相手」とは、「ライシテの原則を受け入れるムスリムたち」ということであり、「神への絶対的な帰依」を掲げるイスラム復興組織はその対象とはなっていない。 さて、ドイツはどうか?総人口の8%を外国人が占めるドイツで、最大の人口を持つのがトルコ出身者である。ドイツは、「ドイツは移民国ではない」という姿勢をとっており、「外国人労働者とその家族が半永久的にドイツ国内に定住する」という状態を認めていない。 ドイツが背負っているのは、「ホロコースト」である。外国人、違う人種の人々を公然と差別することは法によって禁止されている。しかし、「国籍を取得したいのならば、永続的にドイツ国民たらんとする意志を持ち続ける覚悟が必要」(p95)という姿勢は崩していない。つまり、「統合か帰国か」であり、極右団体は「絶対的同化か追放か」ということになる。 ドイツの「国民」とは、「ドイツ民族性」を持つ人々から成り立つとされてきた。それは、「血統によって継承される国民」という意味であり、「ホロコースト」を経てなお残存している価値観であるともいえる。 二重国籍の問題は、トルコ国内のクルド問題とリンクしている。トルコ系とクルド系とは東南アナトリアを中心として激しく対立している。双方に二重国籍を与えた場合、ドイツは深刻な民族対立に巻き込まれると主張する人々もいる。
2015.01.21
コメント(0)
-
読みたい本ばかり
読みたい本がたまってきた。「ロシアの農奴制についての本がないか」と問い合わせがあったので、ウィキで検索してみた。アレクサンドル・ラジーシチェフと言う人に行き当たった。彼は貴族である。『ペテルブルクからモスクワへ』という本で農奴の実態を克明に描き、シベリアへと流刑になり、のちに自殺へと追い込まれる。 こんな人がいる!!図書館で書籍検索したら、抄訳があることが分かった。予約した。 今日、1月15日は、1919年にローザ・ルクセンブルクが殺害された日でもあると知った。彼女についてもきちんと調べてみたい。
2015.01.15
コメント(0)
-
『新・戦争論』を読んだ
『新・戦争論』池上彰・佐藤優 文春新書 「今、世界で何が起こっているのか」について、私が今、最も信頼している二人の対談集。 読み始めて、いきなり目が点になることが書いてある。以下は概略。 集団的自衛権の問題。ホルムズ海峡の国際航路帯の封鎖が議論された。封鎖されても自衛隊は出動できない。国際航路帯は、公海ではなくオマーンの領海を通っている。ホルムズ海峡の周辺はアラブ首長国連邦の領土だが、海峡を望むムサンダム半島の先端だけはオマーン領の飛び地。イランがホルムズ海峡を封鎖するならオマーンの領海内に機雷を敷設することになる。その瞬間に宣戦布告となり、戦争状態となる。閣議決定で「戦闘状態の地域には自衛隊はいかない」ということを決めているから、自衛隊は行けない。 北朝鮮から日本人の母親と子どもがアメリカ船に乗って避難するというけれど、日本船はすでに出せないという状態になっており、アメリカ船はまずアメリカ人を、次にイギリス人を避難させるから、そののちの残り船で日本人を救助するということになる。危機の末期だからすでにアメリカは北を攻撃している。そんな状態のときに、北は避難船を黙って見過ごしてくれるのか。 以上は、佐藤氏の発言。氏は、宗教問題についても深く考察している人なので、イスラムの諸宗派の違いについても解説してくれている。 「アラウィ派は、輪廻転生を認めている」「そんな仏教的な宗派をなぜシーア派は(シーア派すべてではないが)、同じシーア派と認めているのか」 「スンニ派の中に、ハンバリー法学派という宗派があり、これは徹底的な原理主義で、コーランとハディースしか法源として認めない。墓にも価値を認めず、聖人を認めない」 池上氏も、快刀乱麻。EUとウクライナ問題を概略、以下のように語る。 東ヨーロッパの社会主義国が崩壊してのち、EUは東に拡大した。チェコ、ポーランドの低賃金労働者が魅力となった。それなりの教育を受けており、良質な労働力だったから。しかし賃金が上昇し始めると、さらに安い労働力を求める。ついに、ウクライナまで行き着いた。ところが、そのことによって社会の混乱が発生、反移民、反EUの動きが起きている。 将来予測もある。 「今後危ないのは、ベルギー」と佐藤氏。 「北からの日本人の大量帰還」も起こりうるという予測も。「帰国希望の旧日本人国籍所有者が2万人いるから受け入れてくれ」と言ってきたらどうするか? 直近の問題。ミズーリ州で起きた白人警官による黒人射殺。池上氏は、「イラク撤退後、イラクで使っていた装甲車が大量に余ってきたので、全国の警察に無料で払い下げ、ちょっとした抗議行動に対しても装甲車が出てくるようになり、より反発を招くようになった」と指摘。佐藤氏はそれをうけて、「アメリカの公民権運動はまだ成功していない」「オバマは名誉白人」と応じている。 アメリカには、進化論を学校で教えられるからといって学校に行かせない選択をする人たちが100万世帯いる、と池上氏。 第八章は、お二人の情報術。基本は公開情報を精密に読んでいくこと。公式筋のホームページ、国際面ではベタ記事も見逃せない。新聞は複数、それも論調の異なったものを読むこと。何かを分析するときは信頼できる人に乗っかってみること。信頼できる人とは、予測が外れたときに謝る人。 250ページほどの新書ではあるが、詰め込んである情報量は膨大である。
2015.01.15
コメント(0)
-
私は〇〇
イスラム教徒の活動家はTwitterに「私はシャルリーでなくアハメド。殺された警官です。シャルリーエブド紙が私の神や文化をばかにしたために私は殺された」と書き込み[ただしこの記事は誤訳に基づいている。より正確に訳せば「……私の神や文化をばかにしたが、そうする権利を守るために私は死んだ:ridiculed my faith and culture and I died defending his right to do so.」これは週刊誌批判でも人種分離の訴えでもではなく、より高い倫理性を持つ書き込みである]、週刊紙を批判しながらアハメドへの支援を訴え、書き込みを拡散するリツイートは3万2000件(日本時間10日午後7時の段階)にのぼった[50]。ガーディアン紙によれば、アハメド・メラベはイスラム教徒だったという[51]。事件後、アハメド・メラベの家族が会見し、「野蛮な行為に対して心が打ち砕かれた」とした上で、「過激派とイスラム教徒を混同してはいけません。ごちゃまぜにしないでください。モスクやユダヤ教の礼拝堂を焼いてはいけません。それは人々を攻撃するだけで、死者は戻ってこないし、遺族の悲しみを癒やすことはできないのです」と訴えた[52] ウィキペディアより。 ☆「私はシャルリー」とは言いたくない。言うのであれば、「私はアハメド」である。フランスの思想家ボルテールの言葉として多くの人たちに記憶されているのは、 「私はあなたの意見には反対だ、だがあなたがそれを主張する権利は命をかけて守る」である。この言葉に最もふさわしいのは、アハメド・メラベではないのか。 ただ、「私はアハメド」ということ自体、気恥ずかしい思いがある。とても彼のやろうとしていたことなんか出来そうもないからである。私にできることは、「アハメド・メラベ」という名前を記憶にとどめることである。 「シャルリー」誌は、最新号の表紙に、「私はシャルリー」という紙片を持ったムハンマドの画像を掲載している。いい加減にしろといいたい。モスクが襲撃され、ユダヤ教の礼拝堂が焼かれているという事態をどう考えているのか。「私たちはみんなを笑わせたいだけだ」そうだが、ばかも休み休み言え、と思う。私には到底理解できない神経である。ただ、「こんなことが起こってから急に友達面する奴らには反吐が出る」と「シャルリー」誌の関係者が語ったというが、これはこれで根性が座っていると思う。以上に書いたことから、「お前はテロを容認するのか!」というお叱りの声が出てきそうなので、付け加えておくと、テロには断固反対である。しかし、言論と表現の自由は無制限に許されるものではないとだけいっておきたい。
2015.01.14
コメント(2)
-
コミックトークについて
少し前から、「ビブリオ・トーク」に参加させていただいています。世間様では、「ビブリオバトル」としてしられているようですが、ワタクシ、「バトル」という言葉に違和感があり、演劇部の顧問をやっていたという関係でもあるのでしょうか、主観的にしか判断できないものに順位を付けるということが嫌なのです。 どんなプレゼンでも学ぶところは多いですし、一生懸命準備してきた方ががっかりするようなことも本意ではありません。 で、(なにが、「で」なのかはわかりませんが)、本日は、「コミックトーク」ということで、出席者お奨めの漫画の大紹介会となったのであります。きっかけは、前回の「ビブリオ」のあとで、出席者の一人の方と電車でご一緒させていただいたときに、ワタクシが「漫画でやっても面白いかもしれませんね」と申し上げますと、その方が、言下に「漫画なんか、こんなビブリオトークの会に参加するような人たちが読んでいるはずありません」と否定され、「Nさんなんか読んでないと思うし」とおっしゃったのであります。Nさんに、「〇〇さんがこんなこと言ってた」と「告げ口めーる」をさしあげますと、Nさんは、「私だって、漫画ぐらい読みますとも!!」と激怒(若干の脚色があります)され、今回の「コミックトーク」の進行役、会場予約、日時設定の労をとっていただく運びとなったのであります。 結論から言いますと、ワタクシの「仮説」の正しさは見事証明され、ホントに楽しい会になったのであります。 会の最後に、本の貸し借りをするという幸運にも恵まれ、今ワタクシの手元には『ヘルタースケルター』(岡崎京子 祥伝社)『チュー坊がふたり』(田渕由美子 スコラ)があるのであります。 なお、ワタクシのプレゼンは、「レベレーション」、「あの」山岸凉子様が、「モーニング」(講談社)に隔月連載を開始されたジャンヌ・ダルクを主人公とした作品であります。お買い求めになっていない方は七転八倒して悔しがっていただきたいのですが、この表紙、すごいのであります。これぞ山岸!!というできばえ。次作は2月26日号に掲載予定とのことです。
2015.01.12
コメント(2)
-
黙っていることが罪になりそうな予感
政府・自民党が2015年度当初予算案で沖縄振興予算を減額する方針を固めたことで、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の県内移設反対を掲げる翁長雄志知事との亀裂がさらに深まる。政権は財政難を表向きの理由とするが、移設を容認した仲井真弘多(なかいま・ひろかず)前知事と予算面で差をつけ、移設反対派に圧力をかける思惑がにじむ。翁長氏は8日、減額に一定の理解も示したが、政権と現県政のパイプは細る一方で、対立の行方は不透明だ。 【「このままではもう沖縄は独立するんじゃないか」】自民党県連の長老格がつぶやいた 自民党は8日朝、15年度の振興予算などを議論する沖縄振興調査会を開催。翁長知事は招待されず、猪口邦子調査会長は記者団に「出席の希望があれば正式に言ってきてほしい」と述べるにとどめた。昨年11月の知事選で、かつて自民党県連幹事長も務めた翁長氏に敗れた自民党内の空気は冷ややかで、「裏切り者」(沖縄県連幹部)と厳しい声が上がっている。 自民党はその後、山口俊一沖縄・北方担当相に予算の確保などを要請したが、政府関係者は「党には『どかんと減らせ』と強硬論もある」と明かした。 予算減額について、政府側は消費再増税の先送りなどで財源確保が難しいと説明する。だが仲井真氏の在任中に決定した14年度予算は、概算要求から約50億円上乗せされた。繰越金が発生しても、15年度概算要求では14年度からさらに300億円積み増しており、移設反対の県政誕生で手のひらを返した印象は否めない。 態度を硬化させる政府・自民に対し、翁長氏側は当面静観する構えだ。翁長氏は8日、東京都内で記者団に「沖縄に限らず、予算が厳しく査定されている。決まるまで話しにくい」と評価を避けた。 ただ、翁長氏と山口氏以外の閣僚らとの面会は、11月の知事選以降実現しない異例の状態が続いてきた。翁長氏は「県民や本土の方々があるがままを見て考えてほしい」と遠回しに政府をけん制。一方、沖縄の自民党議員は「『頼んでも会ってくれない』と政府を悪役にしようとしている」と反論し、さながら情報戦の様相も呈している。【影山哲也、小田中大】「毎日」2015年1月9日 ☆これほどわかりやすい手法もない。「政府方針に反対する自治体に対しては金の面で締め上げるぞ」と言っているわけである。 原発の立地でも、金をちらつかせた。岩国の市長選の時にはもっと露骨な手を使った。それに屈した市民のおかげで、自民党は、「最後は金だ」という思いを強くするようになった。それが今回の行動の背景ではないか。 「党にはドカンと減らせという強硬論」を吐いたのは誰なのか?それを言い訳に使う「政府関係者」とはだれなのか?是非とも調べて、実名で報道してほしい。 私は首相官邸に対して、抗議のハガキを出すつもりでいる。メールも送るつもりである。ここでしっかり意志を示しておかないと「明日は我が身」となる。 今後は、「黙っていることそのものが罪」となりそうな予感がする。
2015.01.10
コメント(2)
-
『法のタテマエとホンネ』
『法のタテマエとホンネ』柴田光蔵 有斐閣選書 「タマのパパ」さんからご教示頂いた本である。「江川事件」から第九条に至る様々なテーマをもとにして、「日本人の法に対するタテマエとホンネ」に鋭く迫った本である。 印象的な部分がある。 「想像もしたくないことなのだが、もしどこからか誰かが攻めてきて有事となったら、超法規的行動でも、国家的正当防衛でも、国家緊急避難でも、抵抗権でも、生存権でも、何でもよいから理論構成などそっちのけで、とにかく国の存立と国民の生命を自衛隊に守ってもらって、その過程で憲法違反の行動が続出しても、大目に見て、上手く嵐が収まれば、憲法秩序が息を吹き返せばそれでよいという、いきあたりばったりの柔らかい対応をすればよいのだと日本人は考えているのではないだろうか。法治国家は平時には立派に存在するが、いざという時には平気で捨てられかねないのである」(p244~5) 著者は、ローマ法の研究者であり、その方面の著書も多い。 「あとがき」の部分で、著者は、11の問題設定を行っている。紙面の都合で、最初の二つだけ紹介しよう。 (1)日本の法体系は整備され、公知されているか? (2)日本の国民は自国の法を熟知し、その内容を十分に理解しているか? 実に頭が痛い私的である。 著者は、第二章に「破られがちな約束事」という題名をつけ、「日本的契約術の諸問題」という項において、日本人は、保険とかその他の売買契約書の場合でも、いい加減にしか読まないと指摘し、会社側も、それを承知で、泣きつかれたところで、「まぁまぁ」という「落としどころ」を心得ていると指摘している。そして、「江川問題」が約30ページというスペースを取って詳細に論じられている。この部分だけでも史料的価値がありそうである。 この切込みの鋭さ、とぼけたユーモアと皮肉。これは著者が京都人であることと無関係ではないだろう。「今日の茶漬け」という噺をご存知の方なら、この事がお分かりと思うのだが。 本山の「ローマ法」まではまだまだ道は遠いが、少なくとも、「法律とは何か」という家屋の玄関までは辿りつけたかなと思っている。 そんな目で、ローマの「十二表法」や日本の「御成敗式目」にあたってみたい。
2015.01.09
コメント(0)
-
『法とは何か』渡辺洋三
『法とは何か』渡辺洋三 岩波新書 を読んだ。論旨は実に明快である。 「法の精神とは、一言でいえば、正義である。この原点を忘れたものは、法について語る資格はない。このような人が、法を学び、使うことはむしろ有害でさえある。法律知識を独占し、その知識を、正義のために使わない職業的法律家が多ければ多いほど、其の国は国民にとって不幸な国であるといわざるをえない」p8~9 「正義は、個人的なものであると同時に、その社会において普遍的なものである。被害者が泣き寝入りをすればどういうことになるか。被害者が救われないという個人的問題にとどまらず、社会的不正義が大手をふって世間にまかり通ることになろう。それゆえ、権利の主張は社会的不正義との戦いにほかならない。裁判に勝っても失われた命はもどらず、身体の障害もなおらない。それにもかかわらず、病躯にむちうち、命を懸けて頑張ってきたのは、もちろん、やむにやまれぬ個人の心の痛みの訴えが根底にあるからである。が同時に、これらの患者たちが黙っていたら、同様の被害はもっと果てしなく広がったことであろう。彼らが権利を主張したことによって原爆被害、公害、薬害などの深刻さが広く世間に知れ渡った。そして、このような苦しみを二度と多くの人が味わうことのないようにと願う患者たちの未来に向けたメッセージが広く人々の普遍的共感を呼び起こし、正義の輪を広げてゆく」p9~10 ただ、著者は、「正義は一つだけではない」という。正義は複数あるということを「前提として、人はそのいずれかを自分の頭で考えて、選ばなければならないのである」、と述べる著者は、「死刑をどう考えるか」「嫡出子と非嫡出子との差別」「脳死移植は認めるべきか」という三つのテーマを提示し、それぞれについて相対立する立場からの意見を紹介する。 そして、法は歴史的環境の変化に応じて変化し、経済と制度との変化に応じて変化すると説明する。 「商品交換と市民的正義」(p65)以下の、叙述は、実に面白かった。 「市民社会の経済的基礎は、商品交換における等価交換法則である。この法則を保障するのが近代の民法や刑法の役割である。経済的には市民は商品所有者として市場に登場し、自由・平等の立場で競争する。この競争秩序のルールたる法は等価交換による富の移転を「正義」に合致するものとし、不等価交換、たとえば詐欺や脅迫による不当な取引を処罰する」 そしてp72から、「資本主義社会と法」という項が始まる。ケインズによる「修正資本主義」、そしてその反動としてのサッチャー、レーガンの手法が「国家の役割」、「国家は何のためにあるのか」を軸として述べられる。 最初に、著者の論旨は明快であると記した。それは、自分の立場をハッキリさせるということであり、誰の利益のために法を学び、使うのかという点に現れる。日本の現状は、厳しく批判される。そしてその批判は、その状態を放置している主権者たる私たちにも向けられている。 繰り返し読むべき本であると思う。
2015.01.06
コメント(0)
-
『父と娘の法入門』(2)
『父と娘の法入門』は、対話形式で書かれている。 のっけから、「日本の高校や中学では、憲法の話はともかく、『法』の考え方を教えるってことをしていない」(p12)と指摘されると、私に限って言えば、「そのとおりでございます」と言わざるを得ない。 まず、「犬の登録」がなぜ必要かということがテーマとなる。関連して「狂犬病予防法」という法律が提示される。 そして、「人間の登録」。戸籍のこと。戸籍を取得することによって社会のメンバーとして承認されるということ。里親と養親の違い、と進んでいく。 「親子であること」(第三夜)には、ちょっとドキッとするようなことが書いてある。それは、「親子の条件」の部分。「母親と子どもの間の親子関係は簡単で、子どもを産んだという事実だけで親子関係は決まる」(p63) 問題は、父親の場合。対話の部分を引用する。 娘 生まれたときにDNA鑑定をしておけば、だれが父親かなんて問題にならないじゃない。その方がいいと思うけれど。 父 血がつながっていない限り、実の親子ではありえないという考え方をとるなら、そうしたほうがいいけどね。 娘 えっ、血がつながっていなくても、実の親子ってありなの? 父 ありだろうね。すべての子について生物学的な親子関係を明らかにするというのは、親の性関係を明らかにするという意味をもつだろう。わざわざそんな事をしないで、自分の子どもだと考えて子どもを引き受けて育てようという者を父親にすればいいとも考えられる。 娘 母は産んだ人、父は手をあげた人? 父 おおまかにいえばそういうこと。 娘 じゃ、パパは手をあげたわけ? 父 パパとママは結婚しているからね。結婚するってことは、ママが産む子の父親になるって産まれる前から手をあげるってことだと言える。だから、結婚していれば、いちいち手を上げなくても父親が決まるんだ。でも、結婚していなければ、手を上げる必要がある。「認知」といって、自分の子ですという届け出をするんだ。(p64~5) ホントにいろんなことを考えた。 民法三条(権利能力) (1) 私権の享有は、出生に始まる。 (2) 外国人は、法令又は条約の規定により、禁止される場合を除き,私権を享有する。 父は、「これがすごいと思えないと、法学部で勉強したとは言えないね」(p77)という。それは、「人間はみんな『物』じゃなくて、自分で財産をもち、管理したり処分したりできる」ようになったのが、歴史的な産物であるということだからである。奴隷は「物」として扱われた。日本の場合、女性が財産をもち、管理したり処分できなかった時代があったことを忘れてはならない。 「人格権を守り、財産権を守るのが民法」(p93)という言葉も、なるほどと腑に落ちた。 第八夜では、「不法侵入」という概念が出てくる。「宅地の庭に入ったら不法侵入」だと言えそうだが、その庭自体がどのくらいの広さによるかで、不法侵入になるかならないかの見解が分かれているようだ。 他に、児童虐待の問題については、条文が引用されている。 法律の条文というのは、確かに独特の言い回しで記されている。それは、厳密さを重視するところからきており、他の法律、特に憲法との整合性が重視されているからなのだろう。 さて、次は、『法とは何か』に進みたい。
2015.01.05
コメント(0)
-
『父と娘の法入門』
『父と娘の法入門』大村敦志 岩波ジュニア新書 西宮に帰ってきてから、この本と『法とは何か』渡辺洋三 岩波新書 を買った。いきなり「ローマ法」にとりついて、わけがわからなくなったからである。いったん撤退し、装備を整えてから、再び挑戦しようと思った。で、この二冊を買い、図書館には、柴田氏のエッセイを予約した。 私は文学部史学科・西洋史の出身である。ただ、語学については怠惰きわまる生活をしていたため、卒論については、思い出したくもないモノを提出してしまい、よくもまぁ卒業できたものと学校側の温情に感謝している。ただ、これには別の見方もあって、学校側は、「あのうるさい連中」を早く厄介払いしたかったという説もある。 閑話休題。 身の程知らずに「ローマ法」関係の本にとりついたとき、思い知らされたのは、「文学部と法学部とは違う学部なのだ」という平凡きわまる事実だった。 もちろん、社会科のいろいろな科目を教えてきたので、「法」について全く触れなかったわけではない。 世界史(以下、山川出版の『詳説 世界史B』の文章を引用)では、リキニウス・セクスティウス法により「コンスルのうち一人は平民から選ばれるようになった」こと、ホルテンシウス法によって、「平民会の決議が元老院の許可なしに全ローマ人の国法となること」が定められたことは授業では扱う。しかし、条文の中身までは踏み込んだことはなかった。 また、<ローマの生活と文化>の項目には以下のような記述がある。 「国家支配の実用的手段として後世にもっとも大きな影響を与えたローマの文化遺産は、ローマ法である。ローマがさまざまな習慣をもつ多くの民族を支配するようになると、万人が従う普遍的な法律の必要が生じた。十二表法を起源とするローマ法は、はじめローマ市民だけに適用されていたが、やがてヘレニズム思想の影響をうけて、帝国に住むすべての人民に適用される万民法に成長した。6世紀に東ローマ帝国のユスティアヌス大帝がトリボニアヌスら法学者を集めて編纂させた『ローマ法大全』がその集大成である。ローマ法は中世・近世・近代へと受け継がれ、今日のわれわれの生活にも深い影響を及ぼしている。」 この部分は、さらっと流しただけであり、自分なりに調べたことはなかった。だから今の状態は、そのツケが来たということである。 日本史でも、「三世一身の法」、「墾田永世私財法」を扱う、そののち、「御成敗式目」も取り上げるし、「武家諸法度」、現代に入ってからは「治安維持法」も取り上げる。 憲法の第九条、第二十五条なども意識的に取り上げてきた。ただ、真正面から「法とはそもそも何なのか」とか、「ローマ法はどのような意味で『万民法』と称され、後世にまで大きな影響を及ぼしえたのか」「ローマ人はなぜそのような法を作り上げることができたのか」「巨大な帝国を作り上げ、多民族国家を形成した支配者たちはすべてローマ法と同じ『万民法』を作り上げて支配地域を統治したのか」などといった疑問は、今回、初めて頭をかすめたものである。根本から学びなおさねばならない。まず、「法とは何なのか?」ということ。
2015.01.05
コメント(0)
-
最初の一冊
大みそかの夜、そして元日の夜にかけて読み終えました。今年最初の一冊です。 『アジア・太平洋戦争』吉田裕 岩波新書 シリーズ日本近現代史の(6)です。 240ページほどの新書に、重要なポイントが整然と配置されています。一ページ書き進めるために、何冊の資料が必要だったのかを予想させる濃密さです。 実は、この本、二冊手元にあります。つまり、買って、読んだことを忘れてまた買って読んだ本であるということです。書き込みを見ると、08年の11月29日に読了しています。ですから、今回で三回読み終えたということになります。 加藤さんの『それでも日本人は「戦争」を選んだ』、家永三郎さんの『太平洋戦争』(これは、旧版の方がお奨めです)など、結構読んできたつもりで入るのですが、やはり今お奨めしたいのはこの一冊でしょうか。 天皇の年頭所感の中に、「満州事変に始まる戦争の歴史を十分に学び、今後の日本人の在り方を考えていくことが極めて大切」という部分がありました。テレビは、この部分を紹介もしていません。 過去の愚行からいかに学ぶか、それを忘れた時に、すでに私たちは、「戦前」を生きているということになりかねません。 今年もよろしくお願いいたします。
2015.01.02
コメント(8)
全16件 (16件中 1-16件目)
1