2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年01月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
振り込め詐欺
我が家の親戚の家に、いわゆる「振り込め詐欺」と思われる書面の通知が届きました。最近この手の話が多いようですが、僕のブログをご覧になっている方は大丈夫でしょうか?ご参考までに、今回届いた書類をご紹介します。タイトルは、「総合消費料金未納分請求最終通達書」といいます。結構笑えます。まず、総合消費料金って、何の消費料金?ですよね・・・。また、通達というのは行政から出される指示連絡みたいなもので、支払いとか、そういう事を言いたいのだったら「支払命令」でしょうねえ。本文にも、契約会社及び回収業者から委託を受けましたので、という文言があるのですが、委託を受けたという送付もとの名前が出ていません。この手の文章は典型的な詐欺のパターン。あげく、「総合消費者民法特例法」に基づき、とのこと。そんな法律聞いたこと無いですなあ。「当局」として表示してあるのも、日本財務局というもの。そんなのあったっけ?究極は、こちらへは今日FAXで通知し、裁判所への執行差し止め期日が明日。ありえないですねえ。通常の適法な手続きなら、しかるべき期日を設けて書面で通知でしょう。それも内容証明とか、そういう特殊な郵便ですね。あんまりひどかったので、思わず爆笑でしたので、ご紹介させていただきます。経済とは直接関係無いですが、最近多いので、一言述べさせていただきました。くれぐれも皆さん引っかからないようにしてください。これを見て、もっとうまくやろうと思った悪い人、どんなに厳密にやっても、発送元を明らかにしない限り、まともな書類にはなりませんからね。やめておいたほうが良いですよ。それではまた。
2005/01/24
コメント(2)
-
閑話休題
なかなか忙しく、毎日更新できない日が続いており、反省しております。しかし、少しずつではありますが、皆さんからアクセスしていただいているので、やり甲斐を感じている今日この頃です。さて、常々申し上げていることなのですが、我々一般庶民のように、億単位や数千万円単位のお金を自由にできない人たちは、本当は資産運用などしないほうが良いです。同じ労力とリスクをしょっても、1億円で5%運用するのと、10万円で5%運用するのでは、得られるリターンが絶対的に違うわけですね。おまけに損をしたときに、余力がない分ダメージが大きい。でも、これは投資効率だけを追求した場合の話です。我々一般庶民があえて、運用をするのは、それを通じて世界の動き、日本の動き、身の回りの動きを知り、予測を立て、問題に対処する力を付けるためだと思っています。だからこそ、損を覚悟でやっているんです。一分一秒の値動きで鞘を抜いて、いくら利益が上がろうとも、僕はあんまり意味が無いのではないかと思っています(貧乏人のひがみもあるかな?)。とはいっても、一般庶民の最大の資産は体です。体が健康であれば、労働とその対価としての給料という形で、最高のリターンが返ってくる、つまり資産運用ができるのです。10万円損しても、何日か働けば取り返せる(日数は人によりますが・・・)。ですから、くれぐれも健康には気をつけて、ガシガシ資産運用しましょう。ではまた。
2005/01/19
コメント(0)
-
為替相場急変
14日のニューヨーク(以下NY 日本では15日の朝)のマーケットで、一時1$101円台の円高になったそうです。この水準は5年ぶりとの事です。日経新聞の報道では、ECB(欧州中央銀行)理事が、ユーロ高を懸念し、問題はアジアにあるという発言をしたことが発端のようです。アジアってどこかといえば、恐らく中国のことでしょう。さらにいえば、人民元と米国$の固定相場(ペッグ制といいます)による不健全(?)な為替相場を指していると思われます。世界のマーケットでは、実需を伴う資金移動(本当に使ったお金)の数百倍ものお金が取引されています。その、余りに余ったお金が、どこに行くか、というのが問題なのですが、ここ2年くらいは、ユーロに行っていました。それが行き過ぎてしまい、ユーロ圏の国々の競争力(輸出面ですが)の足を引っ張り、冒頭の発言に至ったというわけです。いまや世界の工場といわれる中国は、安い労働力と、米国$と同じ動きの為替相場によって、潜在能力以上の人民元安が放置され、不当に輸出競争力が強くなってしまっているということでしょうね。では、今後どうなるか、ということですが、もはやこの問題は国際政治マターになってしまいました(実際次のG7の議題になるようです)ので、予測は難しくなってきました。しかし、考えられるのは、円高・ドル高・ユーロ安の可能性です。これとあわせ、比較的金利の高い資源国通貨に資金が流れる可能性も無いではないでしょう。ただ、心配なのは、国際政治の場で、人民元の変動相場への移行が本格的に議論されるようになると、今年の政治経済は大荒れになると思います。引き続き注意して観ていく必要がありそうです。ではまた。
2005/01/15
コメント(0)
-
杉田かおるさんご結婚おめでとうございます。
なーんてタイトルをつけてしまいましたが、今日はちょっと税金、特に相続税のお話をしてみようかな、と思っています。相続税は、ご承知のとおり、どなたかがお亡くなりになったときに、残された相続財産を取得した方に課される税金です。相続は、財産を残される方にとって、さまざまな気持ちが入る出来事ですので、その辺のところは国も考慮してくれていまして、相続税は、税金の中では、かなりの割合の方が払わなくていいものです。実際相続税の支払いの対象になる方は、全国民の5%程度といわれております。だから、私のように、親もサラリーマン、自分もサラリーマン、みたいな人にはほぼ無縁です。しかし、残りの5%のかたがたにとっては、非常に重要な問題なんです。というのも、払うとなると、結構税率が高いんです。日本では、何もしないでいると、どんなに大資産家の家系でも、三代目には普通の人になるといわれているくらいです。また、国の借金が多いとよく言われますが、そんなものはこれからどんどん亡くなっていく方の相続税で穴埋めができる、という笑えない冗談もあります。ですから、たくさん資産のある方は、日々(というほどでもないですが)相続税をいかにして減らすか、ということに頭を悩ませているわけです。減らすやり方はいろいろあります。借金を作るとか、財団を作るとか、それだけで本が一冊書けるくらいですが、その辺は税理士の先生にお任せします。我々庶民からすると、そんな税金けちけちしないでどばっと払えよ!っていいたくなりますが、資産家にとっては、何百年も守り続けた土地を切り売りするとか(美智子皇后のご実家で似たようなお話がありましたな)、自分の代ではできないですよね?また、払いたくても土地や、上場していないオーナー企業の株ばっかりで、現金が無いとか、いろいろ事情があるんですねえ。本当に皆さん大変そうです。さて、杉田かおるさんのお相手は、日産自動車の創業者のお孫さんだそうですが、ワイドショーのキャスターが、「創業者の一族がこういった方々だったとは知りませんでした。」といっておりましたが、実際日産コンツェルンの創業者も、税金で殆んど持っていかれて、「三代目は普通の人」になってしまっているかもしれませんね。まあ、そんなことは無いと思いますけどね。何らかの形で資産を防衛しているはずです。と、まあ、そんなことを思い出したので、こんなタイトルをつけさせていただきました。ではまた。
2005/01/14
コメント(0)
-
NHK政治介入報道について。
さて、今日の話題といったらNHKの番組に対して政治圧力がかかり、放送内容が変更された、というニュースでしょうか?それがへそくり運用と何の関係があるのか、といいますと、直接は関係が無いのですが、我々が投資判断をする際に、メディアからの情報を参考にすることが、かなり多いわけで、メディアのあり方が問われているこの問題は、全く無関係ということではありません。報道メディアには、政治や、社会からの中立性が求められ、メディアの流す情報が正確であり、それが国民にうまく伝わることによって、健全な社会が営まれるというのが報道メディアの役割でしょう。これは民主主義の基盤をなす重要な前提であり、だからこそ、今回これだけ大きな話題になっているんでしょうね。革命やファシズム、クーデターでも、最近ではテロリズムでも、メディアを抑えるのが重要な戦略となっています。抑えることで、既存の政治権力を覆し、国民全般に大きな影響を与えることができるわけです。さて、しかしながら、報道メディアが、純粋に中立かどうか、というと、非常に難しいといわざるを得ません。NHKは国営放送ですから、国会の予算審議等で運営が決定されます。そんな状況で、現政権に批判的な報道ができるでしょうか?民間メディアは営利企業ですから、スポンサーや広告主に反したり、あるいは読者が面白がらない記事や番組を作ることができるでしょうか?経済ニュースについても同様です。メディアを通じて入ってくる情報は、何らかの方向性をつけられて我々の許に届いてきます。日経新聞などの大新聞でも、疑ってかかったほうがよいでしょう(データは別ですが)。PHPから、「日本経済新聞は信用できるか」(東谷 暁氏著)という本も出ています。読んでいませんが、読んだ方、感想をぜひ教えてください。いずれにせよ、我々が投資をする際、メディアからの情報には、方向性が既についているということを強く認識すること、また、同じ情報を複数のメディアで確認をし、最終的に自分の頭で判断をするということが必要だと思います。そういった意味で、今回の事件は、投資判断はあくまで自分で、という大原則を思い起こさせてくれるものでした。
2005/01/13
コメント(1)
-
運用レポート6
さて、僕の投資の最後は、投資信託の積み立てをやっているお話です。積み立てというのは、毎月一定額、投資信託を購入するというやり方です。メリットとしては、買うタイミングを分散することで、安い月に沢山買って、高い月は少ししか買わないということです(ドルコスト平均法といいます。)因みに買っているファンドは、外国の不動産に投資しているファンドです。外国不動産といってもいろいろあるのですが、僕の買っているファンドは、主にアメリカと、オーストラリアの不動産に投資し、毎月一定額の分配、再投資があります。不動産は、債券と株式の中間位の動きをするといわれていますので、今ある、グローバルソブリンとあわせて、後は株式に投資すれば、預金・株・債券・その他(不動産)といろいろなものに分散投資ができているということになります。今日時点では、円高が進んでしまっているので、若干マイナスですが、まあ、そのうち何とかなると思います。次回からは折々の話題を、マーケットに絡めてお話ができれば、と思っています。お楽しみに。
2005/01/09
コメント(0)
-
運用レポート5
で、毎月分配型の投資信託ですが、うまい話ばかりではないと、前回書いたのは、当然リスクがあるということです。まず、外国の資産に投資しているため、円高になると値段が下がります。しかも、たいてい複数の国に投資をしているので、動きが読めません。世界の通貨の中で円だけ高いという状況が一番痛いです。一日で1~2%は動きます。それから、債券に投資しているものだと、債券そのものの値動きも影響します。これもまた相当の数・種類に投資しているので、まったく読めません。ましてやいろいろな国の債券ですから、わからない。為替と、債券の値動きの組み合わせなので、毎日の値動きとか、来月どうなってるとか、予測することはまず不可能ですね。円安になって、景気が悪くなると値段が上がる(債券の値段は、景気が悪くなると値段が上がることが多いです。)、位のことしか言えません。また、投資信託は手数料がかかります。一定期間保有しているとタダになるタイプもありますが、運用期間中に信託報酬という手数料を抜かれているので、同じことでしょう。手数料を払って元本を購入するので、マイナスからのスタートになります。値動きが無かったとしても、毎月の分配金でマイナスを取り戻すのは、3ヶ月~7・8ヶ月かかります(ファンドによります)。だから、最初の数ヶ月は我慢の月なんですね。本当は。実際のところ、これらのことを知らないで買っているお客さんは結構いると思います。しかし、投資の基本的な考え方として、長期で運用することが、リスクを抑えるということがあります。ですから、毎月分配型の投資信託については、じっくり、腰をすえて運用することが大事です。ちょっと下がった位で慌ててはいけないですし、あわてるような人は買ってはいけないのです。勿論「これでいい」、という位値段が上がったら、売ってしまってもいいんですよ。ですから、僕の場合、長期投資でグローバルソブリンを買っていますし、分配金は元本に組み入れています(ソニー銀行はもともと分配金を預金で受け取ることができないんですけどね・・・。)。再投資であれば、無手数料で元本をひたすら増やす、ということができます。まあ、どれくらい増えるかは、将来の楽しみにしています。
2005/01/08
コメント(0)
-
運用レポート番外編
今日は、僕が銀行時代に投資信託を売っていたころのお話をしてみたいとおもいます。かれこれ1年以上前になってしまうので、「もう古い!」というご意見もあるかもしれませんが、悪しからず。今もそうですが、当時よく売れていたのは、「毎月分配型」といわれるファンド(ここでは投資信託のことです。)でした。毎月分配型のファンドは、主に外国の債券に投資をしているものが多いです。日本より高金利の国債や社債は、世界中探せばいくらでもあるので、そういったもので運用し、値上がり益や、クーポンといわれる利息を、毎月投資家に還元するんですね。お客さんの普通預金に分配される場合もあれば、再投資という形で、投資元本に組み入れられることもあります。毎月分配型のファンドのパイオニアであり、今日本で一番残高が多いファンドが、私も投資している、国際投信投資顧問の「グローバル・ソブリン・オープン」です。これは、安定した利回り(ざっくりで5%くらいでしょうか)と配当で、かなり人気がありました。それだけ人気があったのは、銀行の低い預金金利に嫌気が差したのと、お小遣い感覚で入ってくる分配金(百万円投資して毎月数千円にはなります。定期預金だと1年で3百円くらいしかありません。)に喜びを覚えたお客さんにがっちりはまったからです。まあ、でも世の中そんなにうまい話ばかりではないのですが・・・。続きはまた次回。
2005/01/07
コメント(0)
-
運用レポート4
えー。大分飛んでしまいましたが、更新いたします。どうも年末年始はばたばたしてまして・・・。さて、今回は投資信託のお話です。投資信託って何ですか、という話からさせていただくと、ずばり、大勢の人たちからお金を集めて、いろいろな商品に投資する投資商品のことです。何に投資をするのか、誰が投資をするのか(運用会社のことですが)、が商品選別の決め手になります。株に投資をすれば、それ相応のリスク・リターンがありますし、債券に投資をすれば、それもまた、相応なものになります。で、投資信託に何のメリットがあるか、ということですが、株なら株、債券なら債券で、いろいろな種類のものに投資をするので、単品で勝負するより、リスクが小さい(従ってリターンも小さいですが)ということ、それが、少ない資金でもできるということです。分散投資をしようと思って、株を20銘柄買おうと思ったら、相当の資金量が必要ですよね。でも投資信託なら、ものによっては1万円からでも分散投資ができます。また、債券に関して言えば、単品の債券を買うと、期限前に解約すると元本が割れたりすることがあるのですが、投資信託なら、いつ売ったり買ったりしても基本的には自由です。それから、普通ではなかなか投資が難しい商品に投資ができることもあります(インドの株を買おうと思っても普通の証券会社では扱ってないですよね・・・。でもインド株の投資信託というのもあります。)。逆にデメリットですが、購入時・運用期間中・解約時(かからないものもありますが)にそれぞれそこそこ手数料を取られます。また、分散はいいのですが、運用会社にお任せになるので、投資対象を自分でコントロールできないという点があります。これが嫌いな人は嫌いです。特に株が好きな方は株式投資信託をなかなか買わないですね。この辺の実態は、1年以上前の経験ですが、実際に販売していたころのお話をしてみたいとおもいます。続きはまた次回。お楽しみに・・・。
2005/01/06
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
-

- 株式投資でお小遣いを増やそう
- 少しだけ
- (2025-11-19 16:50:16)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 楽天お買い物マラソンは“買い方”で決…
- (2025-11-19 12:00:07)
-
-
-
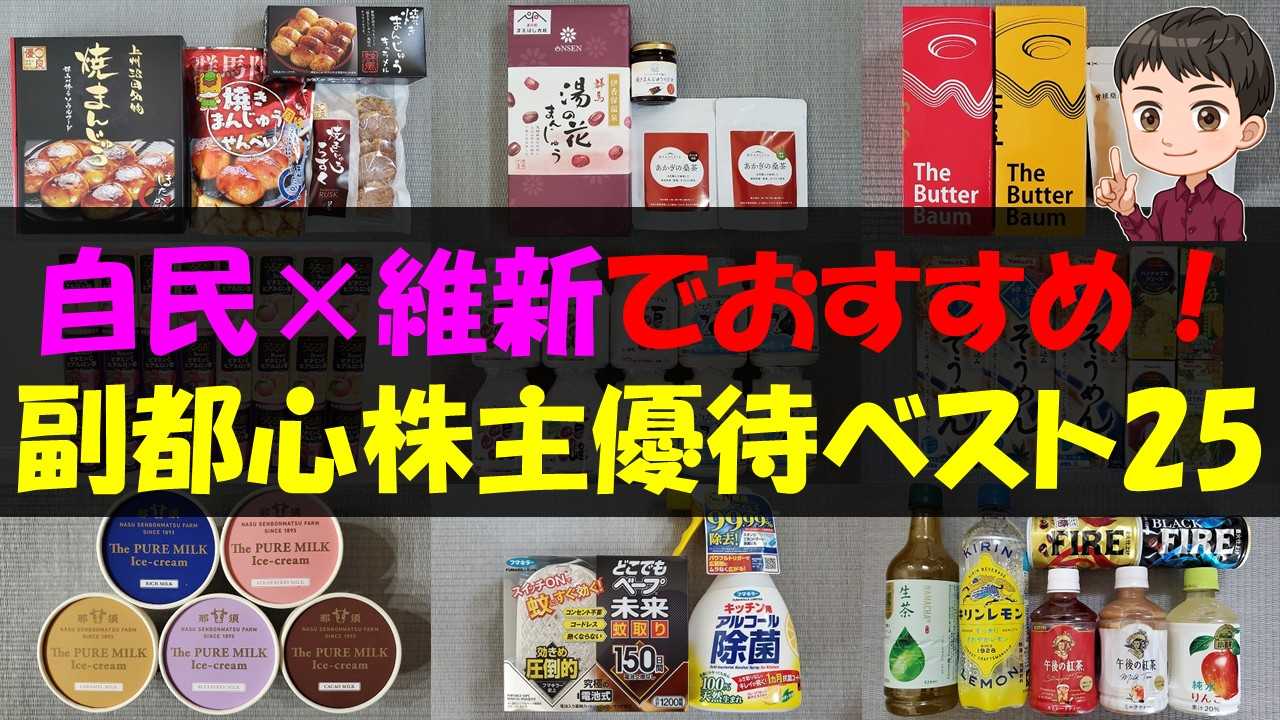
- 株主優待コレクション
- 【大阪】自民×維新でおすすめ!副都…
- (2025-11-19 18:00:06)
-







