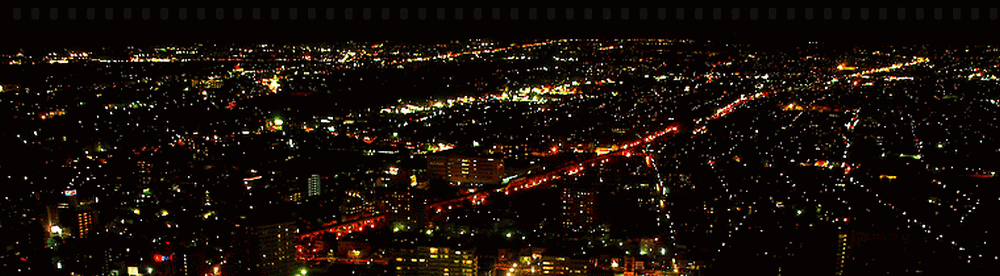2008年10月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
白色白光
枚教組の平等主義は、行き過ぎたときに真実から逸脱したのではなく、言語化したその瞬間に、すでに逸脱していたのだ。 だが、肝心なことは、言語化するその直前の瞬間の意識には、真実がはらまれていたということであろう。 それは、「すべてのものは、おのおの自らの光を放つ」という真実だ。 だが、それでも人には好みやこだわりというものが生じるのである。恋愛もするのである。そして自らのカルマを生きるのである。 自らのカルマが自らの美しい光となるのであるから、「すべてのものは、おのおの自らの光を放つ」と観ているだけではなく、自分は自分の光を放つしかない。
2008.10.18
コメント(0)
-
教育過剰
教育はほどよい加減が難しい。 現在の教育は基本的に過剰である。手取り足取り教えることで、本人の力を育てるのではなく、奪っていく。特に自分で考える力や、対処する力を奪っていく。 いったんこれが始まると悪循環に陥る。自分ではできないようになるから、さらに手取り足取り教えるしかない。手取り足取り教えるから、ますます自分ではできなくなっていく。 そして最も問題なのは、その結果、覚醒した自己として生きる主体性そのものが、抹殺されていくことである。
2008.10.12
コメント(0)
-
幸せへの道
本当はやりたくないのにしていることをひとつひとつ手放していくやめていくそうすれば微笑みが生まれ愛が生まれ創造性が生まれ幸せへの道が見えるただそれだけのことなのに互いに抑圧しあい牽制しあい気を使いあってやりたくないことをするために人生のほとんどを費やしてしまう場合がなんと多いことだろうか
2008.10.06
コメント(0)
-
学校という環境
それぞれの存在がそのまま認められなおかつ全体が調和するためにはたとえば大自然がある、テリトリーが大きい、社会的抑圧が低いなどの条件がある。学校の教室はそのどの条件も満たさない。
2008.10.04
コメント(2)
全4件 (4件中 1-4件目)
1