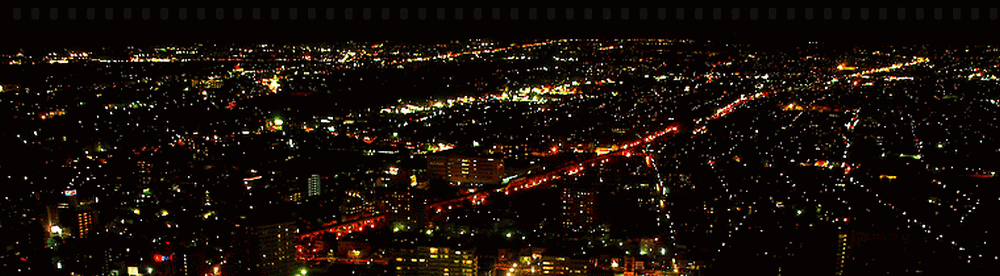2008年01月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
今ごろ東井義雄
日記過去ログによると、僕は2006年の秋に東井義雄の本をすべて捨てたのだ。そして今日、「東井義雄賞いのちのことば」秀作入選の知らせが来た。 それで表彰式のある会場などをネットで調べていて初めて知ったのだが、東井義雄には記念館まであるんだなあ。 一小学校の教師としてはこの島で珍しいことではないのだろうか。 東井義雄記念館 http://www3.city.toyooka.lg.jp/toui-kinenkan/index.html■日付2006年10月29日(日)■タイトル東井義雄を捨てる■本文 そして教育書の処分は続く。次に東井義雄を処分しよう。 『村を育てる学力』は、日本の村の子どもたちがスポンジのように教育を吸い取り、皆で一緒に上昇していく時代には、よい本だったと思う。そして、東井の教育者としての仕事は、結局、その延長線上にあったという気がする。 彼がひとりひとりの子どもや人間を見るまなざしの、明治人的やさしさには敬意を表しよう。ジェンダーに関しては、かなり問題もあるが、それもまあこの際大目にみよう。 だが、やはり、今の日本は東井の時代とは決定的に違う。もはやまったく新しいものを創造するしかない。こと、学校教育に関していえば、行き着くところまで行き着いて、いったん壊滅するしかない。 今回処分する本の中には何冊か、東井のサインと贈る言葉がある。そのあて先は渡辺恵美子。この渡辺恵美子は、実は僕の小学校1年生のときの担任の先生である。 渡辺恵美子は東井義雄を師と仰ぎ親交も深かったようだ。なにしろ彼女は、東井の学校と自分のクラスの子どもの文通の記録も『紙のかしわもち』という本にまとめている。そんな渡辺は、僕が教師になったときに東井のサイン本を何冊かと、自分の『紙のかしわもち』をくれた。 確か退職直後だった彼女は、後進に願いをこめたのである。 その前に僕は大学時代に、浄土真宗の僧侶でもある東井の話は何度も聞いていた。一度は彼を大学に呼んで講演を催す企画側にもなった。彼の普及本はもちろん、講演テープなども持っていた。 あびが教師になったとき、渡辺がそれを聞いて「それは奇遇だ。私も東井先生とは親交があった」などといいつつ、何冊かの東井の本(やや専門的なもの)をくれたのだ。 これら東井のサイン本の裏表紙裏には、若い頃の渡辺が教師としての決意なども書いたメモ書きも残っている。若書きだが、情熱は伝わってくる。 これらサイン本、講演テープ、みんなみんな、今回、あびから、さらなる後進に譲ろう。
2008.01.17
コメント(0)
-
心理療法におけるインフォームドコンセントについて
ジュディス・L・ハーマンの『心的外傷と回復』より「患者のインフォームドコンセントの如何は個々の薬物の有効性と同程度に予後を左右する。患者が単に《症状が抑えられるから薬を飲みなさい》と命じられるだけであるならば、患者はまたしても力を抜き取られることになる。もし、逆に、患者が自分が最善と思う判断に従って使ってよい一つの道具として薬物を提供されるならば、患者が自分には有能性と自己統御性とがあるという感覚は強められるだろう。この精神で薬物をさしだせば協力的な治療同盟関係が築かれる」 現実にはこのことがわかっていない精神科医、心療内科医が多いことは嘆かわしい。 そして、薬だけではなく、心理療法等についても、枠組や意図を説明し、そういうものであるとしての参加の意志、選択性をクライエント自身が持つことが重要であろうと思う。 専門家の側が「疑問には答えられないが、こちらには専門家としての意図があるのだから、黙ってつづけなさい」とだけ言うならば、クライエントは「またしても力を抜き取られ」「協力的な治療同盟関係」は生まれないだろう。 疑問点を提出しても回答しないで、「しばらく黙って付いてくれば、やがて深い意図がわかる」というのは、自己啓発セミナーや宗教、マルチ商法におけるマインドコントロールの場面以外では、今まで経験したことがなかった。 ところが、今参加している「官製」の集団精神療法では、疑問点を質問しても質問してもそう言われるので、オドロキ!だ。
2008.01.09
コメント(0)
-
りりあんワーク「ドラマチックしゃべり場」
NPO法人りりあん、ワークのお知らせ(誰でも参加できます)ワークショップ「ドラマチックしゃべり場!」~違いを越えて、言葉を越えて、語り合う!~立場によって感じ方が違うことを体感しながら話し合う、学びと交流の場です。日時 1月20日(日)10時~11時半 1時~3時半場所 ラポールひらかた 三階和室(京阪枚方市駅徒歩3分)ファシリテーター 松田裕樹 & あび参加費 1000円定員 16名 申し込み先 あび 左下のMail「メッセージを送る」よりメールください【前半 10時~11時半】言葉以外のコミュニケーション手段を活性化するために、身体を動かしながらコミュニケーションを深めるゲームを通して、交流を深めながら、心と身体をほぐします。【後半 1時~3時半】プロセスワーク(プロセス指向心理学)のグループプロセス(ワールドワーク)の手法を使い、いろいろな立場の声を表現していきます。その場に集まった人たちの中で、最も関心が集まる話題を選んで、その話題をめぐって、どんな立場のどんな声が存在するのか、話し合いながら、明らかにしていきます、ドラマや小説には、さまざまな登場人物が現れて、すっかり感情移入できるほど自分に近いと感じる役もいれば、ひたすら反感を感じて自分とはほど遠いと感じる役もいます。そのように、人にはさまざまな立ち位置(役割)があります。それはひとりにひとつの固定した立ち位置ではなく、自分自身の中に、「いろいろな立場・役割からの声」があることに気づくことがあります。参加者の中のさまざまな声がどれひとつとして切り捨てられることなく表現され、聞き届けられれば、ことがらの全体像についてより深い理解が生じ新たな視野が広がってくる可能性が高まります。さあ、どんな声があるのか、一緒に探って、表現してみませんか?
2008.01.04
コメント(0)
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…
- スタンフォードの自分を変える教室
- (2025-11-27 03:39:17)
-
-
-

- 今日読んだマンガは??
- 『この婚約はお仕事です!』
- (2025-11-27 00:00:13)
-
-
-

- 最近、読んだ本を教えて!
- 風に向かって クリスティン・ハナ
- (2025-11-24 16:36:01)
-