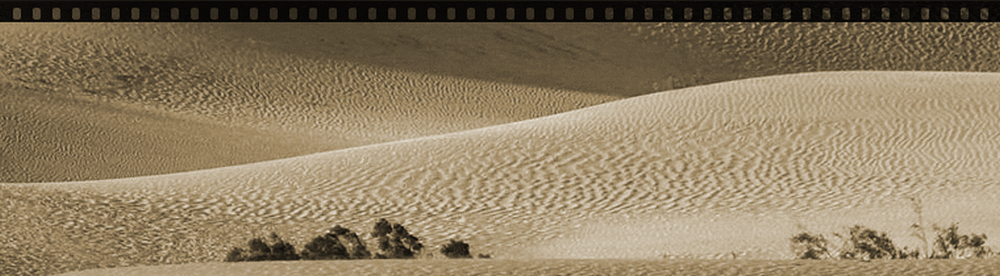全762件 (762件中 1-50件目)
-

『イントゥ・ザ・ワイルド』 ~荒野へ
【中古】 イントゥ・ザ・ワイルド(Blu−ray Disc)/エミール・ハーシュ,ハル・ホルブルック,キャサリン・キーナー,ショーン・ペン(監督、脚本、プロデューサー),ジョン・クラカワー(原作)2007年公開のアメリカ映画。原作はジャーナリスト、作家、登山家であるジョン・クラカワーによる1996年のノンフィクション作品『荒野へ』。1992年に青年が放浪の末にアラスカで遺体で発見された事件を描いたものだ。自分の人生が親に拘束されていることに我慢のならなかったクリス(クリス・マッキャンドレス、主人公)は、物質至上主義に抗い、真の自由を求めて自分の本性を信じるままアラスカへと至る長い旅に出る。旅の先々で出会う人々とのふれあいを通して、クリスはいろいろと好意的な誘惑を受けるのだが、「自由と孤独」の極限を体験するため頑として目的地アラスカを目指す。アラスカの荒野で一人過酷な狩猟・採集暮らしの日々を送るその姿は、さながら苦行を続ける仏陀のようだ。そのなかでクリスは新たな悟りを得たようだが、運命の罠にはまり新たな人生の一歩を踏み出すことは叶わなかった...若い時にクリスの生き方を夢見た人は決して少なくないだろう。私もその一人だ。そしてクリスの行動に共感を覚える人は、程度の差こそあれ、みなその心の内にニヒリズムを抱える人だと思う。誰もが「そう生きたい」と願いながら、そう生きることができないもどかしさを、この映画を観て強く感じるのではないだろうか。「人は自由を自ら放棄している」-そんなクリスの声が天から聞こえてきそうだ。私は今でも、最初で最後の放浪の旅に出ることを夢見ている。病院のベッドで虚しく死ぬつもりはない。映画の再現映像では旅の辛さや荒野で暮らす日々の過酷さがもう一つリアルに伝わってこない。関心をもたれる方にはジョン・クラカワーの原作本をお勧めしたい。書籍の方がクリスの性格、考え方、家族との関係、また放浪中の出来事やアラスカの荒野での様子が想像力豊かに描かれている。
2025.10.14
コメント(0)
-

新総理は誰になる?🤔 ~参議院選挙が終わって
参議院選挙が終わった。大方の予想どおり、自公与党の惨敗だった。しかし壊滅的な大負けとまでは言えない。石破総理は自公与党で50議席以上との目標を出していたところ、結果は47議席。目標を下回ったが、マスコミや識者たちは選挙後半に「40議席を割る」との観測を出していたのだ。私はその予測に懐疑的だった。比例代表のほうは石破不人気の影響が出るだろうが、選挙区ではそう大きくは減らないとみて「46~48議席」と予想していた。これは当たった。しかし石破政権が国政選挙で連続2回、都議選を含めれば3連敗した事実は重い。有権者(国民)は石破政権にNOを突きつけたわけで、石破さんもここまできてまだ総理職にしがみつこうとは思ってないだろう。しかし潔さがなく、幼稚な事由を並べ立ててのらりくらりと辞任を引き延ばしている。各方面の観測によると、どうやら8月末くらいまで延命したいようだ。その理由は「戦後80年談話」を出したいかららしい。愛国者としては、これはなんとしてもやめさせたい。なぜなら、その内容はおそらくチャイナと半島二国を喜ばす「敗戦国懺悔謝罪談話」になるだろうからだ。さて、いずれにせよ石破総理は降りるとして、新総理(総裁)は誰になるのか?すでにいく人か名前は挙がっており、なんといっても高市さんにいつもの小泉進ちゃん、それに加藤勝信、林芳正、河野太郎、茂木敏充各氏も資格はあるだろう。まず小泉進ちゃんはあり得ない。自民党の総裁選に出るには本来議員としての十分なキャリア、重要閣僚や党三役などの経験が必要である。彼は人気はあるが、キャリア、経験ともに足らず、いまはまだ総理職を担える力はない。では誰が?-私が最有力と考えているのは林芳正氏だ。国会は衆参両院で与野党逆転となった。この後も自民・公明の連立政権でやっていくなら、野党の協力を得なければ法案を通せない。とりわけ立憲民主党の協力が必要だ。左派野党が喜ぶのは石破さんのような親中韓総理だ。その点で林さんならうってつけ。河野氏も考えられるが、河野さんは麻生派。現キングメーカーの岸田さんは旧宏池会の議員を総理につけたいと考えているだろう。まだしばらくは政権と党を自分がコントロールしたいはず。ちなみに、有力視される高市さんはどうだろうか?私は「いまはない」と思っている。高市政権となれば、左派野党からの総攻撃がはじまる。法案は通せず、内閣不信任案が出されるだろう。では衆議院の解散-総選挙で切り返せるか?勝つのはちょっと難しい。なぜなら、すでに無党派保守層が自民党を離れ国民民主党や参政党に移っているからだ。いずれにしても、政界は激烈な再編期に入った。政局はこの先長く混迷を続けるだろう。高市早苗は天下を取りにいく(月刊Hanadaセレクション) [ Hanada編集部 ]
2025.07.26
コメント(0)
-

参院選は、日本人ファースト&石破退陣ファーストで!
参議院選挙も早後半戦に入った。ネットでは大いに賑わっているが、外ではそれほどでもない。投票率はおそらく前回並み(2022年、52.05%)になるだろう。今回は投票選択に悩んでいる。選挙区(都道府県)では政党・候補者が限られておりさほど迷いはないのだが、比例代表のほうは迷っている。投票したい候補者が複数おり、絞り切れないのだ。まあ、まだ時間(期間)はあるのでじっくりと検討しよう。さて選挙情勢はどうだろうか。石破自民はそうとう負けるとの観測が強いのだが、私は言われているほどの大負けはしないと見ている。全国都道府県の一人区をそれぞれ見ると、現職をすんなり倒せそうな新人候補者はそれほどいない。少し波乱がありそうなのは東京、大阪など大都市選挙区だ。結果を左右するのは比例代表で、こちらは石破不人気の影響がはっきり出ると思われる。ちなみに、高橋洋一さんは自公与党で46~53議席との当初予想を出している。私も46~48議席くらいかなと予想。自公の基盤(後援会組織)はしっかりしていて、政権交代がかかった選挙でもなければ、超大負けは考えにくい。ただ、小負けでも石破さんは辞任しなければならないだろう。国政選挙2回連続敗北となればね。問題は後任総理が誰になるかだ。ネットでは“高市総理”を望む声が多いが、私は高市さんの可能性はやや低いと考えている。いま自民党では左派議員団が主流派となっており、そのかけ引きで左右中間派の人が総理(総裁)に選ばれるかなと。ただアメリカにトランプ政権があり、この後に衆議院選挙(解散-総選挙)があることを考えれば、やはり保守派の人かもしれない。外国人労働者問題、不良外国人による犯罪増加、社会保険福祉と税制の改革等々、いま日本は解決の難しい多くの問題に直面している。石破総理は頼りなく、これらの問題に対処できないことは誰の目にも明らかだろう。米トランプ政権による関税攻勢にもまったく対処できていない。我々が望むのは、日本人ファースト&石破退陣ファーストだ。杉田水脈の逆襲 [ 杉田水脈 ]
2025.07.14
コメント(0)
-

『バニラ・スカイ』 ~ほんとうに明晰夢の中? 🦋
バニラ・スカイ【Blu-ray】 [ ペネロペ・クルス ]『オープン・ユア・アイズ』(1997、スペイン)のリメイク作品で、トム・クルーズ主演によるハリウッド版である。公開当時(2001年)、私はこの作品にいたく魅了され繰り返し鑑賞したものだった。当時の私は身体的、精神的病に蝕まれ、現実を離れ夢の世界に逃避したいと毎日願っていたからだ。この作品は私を大いに癒してくれた。もし本当にリアルな夢のなかで暮らせるなら、それが現実と区別のつかない世界なら、そのための自死をも厭わないと本気で思いつめていた。人は誰も当てにはならなかった。それまで親友と思っていた同僚でさえ、軽薄な偽善者だと気づかされ失意のどん底に落とされていた。久々に観なおして、ハッと気付いたことがある。それは、実は真相は明らかにされてはいないのではないか-ということだ。ストーリーの進行からすると、デヴィッド(主人公)が人口冬眠中にみていた明晰夢の世界から目覚めた瞬間で話が終わったと受け取れる。しかし映っているのは開いた瞬間の目だけで、それ以外の状況は不明だ。たとえば事故で崩れた顔とか、そこが人口冬眠していた施設とわかる描写はないのだ。ということは、こうも考えられる。人口冬眠でみていた夢の世界は、交通事故後の昏睡状態中にみていた夢で、つまり夢の中で夢をみていたのだと。そして目を開けた瞬間は、事故後の昏睡状態から目覚めた瞬間であると。さらにいえば、単純に一夜の夢から目覚めただけで、すべての出来事は夢の中の出来事だったと考えることもできる。この映画では夢と現実の区別は完全に示されてはいないのだ。だがそれはさして重要ではない。最初に友人のセリフとしても出てくるが、最後に救護員がデヴィッドに話す忠告、『酸っぱさがあるからこそ、甘さがあることを忘れるな』-この言葉に映画のテーマが集約されている。常に良いことばかり、あるいは楽しいことばかりで満たされたいという思いは、人の性だ。しかしながら、「禍福 は糾える縄の如し」で、幸福と不幸とはつねに一体なのだ。それがいつどこでどのように発現するか、人はそれを事前に知ることはできない。さりとて、患難を避けようと何もせずに生きれば、退屈で虚しい日々が続くだけ。欲を生きる-と、それしかないのかな... ただ、健全な欲でありたいと思う。そして、ささやかでいいから最後に望みをひとつ叶えたい。神よ、少しでいいから力をかしてくれ。
2025.05.22
コメント(0)
-

『第七の封印』 ~イングマール・ベルイマン
第七の封印 【4K修復版】 [ イングマール・ベルイマン ]この作品はベルイマン監督の作品中もっとも知られている作品ではないか。なんといってもあの黒いローブを身にまとった白い顔の男という死神のイメージが有名。主人公の騎士がその死神と命の取引をするという、いかにも西洋的で神秘的な作品だ。チェスで対決する中世の騎士と死神を通して「神の存在」を問うた作品ということなのだが、初見では話がちょっとわかりにくい。死神が目の前にいるのに、その死神に「神を知っているか?」と問うところなどなんか妙な感じで、この死神はアントニウス(騎士)の自殺願望(分身)なのかもしれないのだけど、ラストに来て彼の居城での最後の晩餐の様子はさらに不自然な空気に満たされている。謎解きに挑戦するような気持ちで久々の鑑賞。そのラストの晩餐シーンは作中もっとも不可解な場面になっている。晩餐の場に死神が現れたとき、ある1カットの後に食卓上のアントニウスの前の杯が消え、さらにその後の1カット後にはそれまであった肉らしき食べ物を入れていた大き目のボウルが忽然と消えている。アントニウスの妻はずっと新約聖書のヨハネ黙示録を音読しているので片付けるはずはない。このときの間を考えても、他の女が片付けたとも思えない。私の解釈では、実はアントニウスと仲間たちは森の中ですでに死んでおり(その描写はないが)、居城に着いた一行は彼らの霊体と思われる。晩餐の場は死神を待つ控えの間であり、たぶんこの世とあの世の踊り場なのだ。その後場面は変わって旅芸人夫妻と子のシーンになり、そのとき夫ヨフは死神と死神に引き連れられる騎士と従者ら(の死の舞踏)を幻視するのだが、そのなかにアントニウスの妻はいない。つまりアントニウスの妻は夫が帰るより前にすでに死去していたということだ。この物語では登場人物それぞれに、人の類型が割り当てられている。神の存在に疑いを持ち信仰に苦悩する騎士アントニウス、それとは対照的に実存主義一徹の従者ヨンス、姦淫に耽る鍛冶屋の妻や座長、強欲で心の汚れた神学者、そして純朴な旅芸人夫妻と子。聖書には「天国に入るには、無垢な幼子のようでなければならない」とのキリストの言葉がある。この旅芸人家族が死神の魔の手から逃れられたことは、信じる者への“福音”による恵みなのだろう。しかしながら、私には神の沈黙に苦悩する騎士の気持ちがよくわかる。私も迷える子羊だから。小さな教会で自身の心情を吐露し告解する騎士の姿は、私自身のこれまでの生き方、考え方に重なる部分があった。しかし同時に、私の中にはヨンスの部分もある。冷静で冷めた実存主義も捨てられないのだ。この映画のとおり、欧州の中世においても現代と同様に神の存在に関する考えは、人によって内心いろいろと複雑なものがあったのだろう。この映画が製作された時代(1957)、世界は不穏な空気に包まれていた。東西冷戦による核兵器開発の競争が大国に広がり始め、世界が終末に向かうのではないかと、暗い不安が人々の心に浸透していった時代だった。14世紀の欧州では黒死病(ペスト)が猛威を振るった。この疫病による異様な死者の大発生は当時の人々に世界の終末を予感させたはずで、ヨハネ黙示録の内容に真実味を与えたかもしれない。ベルイマン監督は核拡散という現代の脅威を中世の黒死病大流行になぞらえ、聖書の黙示による終末観を媒体として、ひょっとしたら預言者になったような気持ちも少しは手伝って、その危機を作品で訴えたということなのかもしれない。
2025.05.08
コメント(0)
-

『冬の光』 ~イングマール・ベルイマン
【中古】 冬の光 HDリマスター版/グンナール・ビョルンストランド,マックス・フォン・シドー,イングリッド・チューリン,イングマール・ベルイマン(監督、脚本)沈黙する神に疑いをもつ不信心な牧師と、その牧師を愛する女のそれぞれの苦悩を描いた作品。これは実際にありうる職業牧師の現実を生々しく描いており、製作された1962年当時はなにかと物議を醸したのではないか。聖職者はじめ教会リーダーの秘め事はそうとう昔からあったと思われるが、それが公になることはほとんどなかったはずで、その点ベルイマン監督はキリスト教団体などの大きな反発を買わないスタイルで控えめにそれを映像化している。ラストの方、信者の一人でトマス牧師の執事のような振る舞いをするアルゴットの相談話が秀逸だ。彼は身体が少し不自由なようで、その痛みを緩和するためにと牧師から読書を勧められたのだった。読書に聖書を選んだアルゴットはキリスト受難のエピソードを読み、そこにある疑問をもった。それは、キリストの受けた苦しみははたして肉体の苦しみだけだったのか?という素朴な疑問だった。彼は“ゲッセマネ”で自身の運命を前に祈るイエスをよそに眠りほうける弟子たちや、ローマの官憲たちが現れるやイエスを見捨てて逃げ去ってしまった弟子たちの様子から、十字架上のイエスの苦しみが肉体の苦しみよりもむしろ弟子たちに理解されず孤独に陥ったことの虚しさと、最後のその場に至っても“沈黙する神”に対して疑いをもった自身に苦しんだのではないかとの自説を述べるのである。遠藤周作さんの『イエスの生涯』という本を昔読んだことがあり、そこに書かれている遠藤さんのイエス観がこれと同じだったと記憶しているが、ここに映画の主題である「信仰の本質」の問題が提示されている。キリストにさえ沈黙していた神に、その後の数多の信者が疑いをもってしまうのは当然だと思う。実は、神が“いる”“いない”は問題ではなく、自身がそれを信じているかどうかが問題である。牧師を愛するマルタは生の哲学を訴えており、トマス牧師とマルタの相反はキリスト教と実存主義の対立とも受け取れるのだが、そもそもが次元の違う価値観なのであり、その融合を図ることは叶わない。トマス牧師は、その後自殺を遂げることとなる相談者ヨナスに対して自身の真実(本音)を吐露し「人生は無意味」とまで言い放つのだが、無意味なのは彼の“苦悩”なのだった。神の沈黙について、少し自説を書いておこう。神は人のことばを話さない。が、その知らせ、メッセージはしばしば発信される。それは導きであったり、警告や戒めであったりする。もちろん恩寵もある。ただ、それは誰にでもわかる形では顕れない。内に神の本質をもち、神とつながっている人(神の子)がそれを感じ取れるのである。その点で作品中のトマス牧師にはそれがなかったと思われる。神の本質を高い山の頂上にたとえるなら、そこへと到るいくつかの登頂ルートが諸宗教である。キリスト教も真実へ到るための手段の一つにすぎない。その教義や教理はあくまでテキストであって、目的ではないのである。しかしテキスト自体を目的と思い込んでいる信者は多い。それがこれまで人の世に多くの不幸をもたらしてきた。そしていまも続いている。
2025.04.20
コメント(0)
-

「家族」は、男にとっては厄介なもの 😟
運び屋 [ ブラッドリー・クーパー ]C・イーストウッドもだいぶお年を召されたけど、やはり大御所俳優で、今の自分を映画に巧みにはめ込んでしまう勘どころはナイス。この作品は家族の絆の大切さを描いた話なんだけど、アメリカ社会の恥部、その現実を素材にしているところがうまい。さすがに作品作りにそつがない。でも、やっぱり「夕陽のガンマン」とか「ダーティー・ハリー」といった昔の当たり役を思い出してしまうし、彼にはそうしたクールな一匹狼ヒーローのほうがよく似合う。私の好みでは、この役柄ならハリー・ディーン・スタントン(故人)あたりだったらピッタリかなと。もっとも、彼はいい役者なんだけど、名バイ・プレーヤーだから興行収益は赤字になるな。彼が主演した『パリ、テキサス』(1984)という作品があって、内容的に合ったキャストなんだけど、主演俳優として有名な人を充てればもっと売れただろうになぁと思ったもの。もっとも、それでは中身の印象が変わってしまうかもしれないし、難しいところだな。ところで、若いときにはわからなかったけど、壮年期も後半に入って「家族」がなぜ人生において大切なものなのか、少しわかってきた。でも、それを育てる(維持する)のがどれだけ大変なことなのかも昔からよく知っている。「家族」てのは、男にとっては厄介なものなんだよな。仕事をバリバリやって、家庭も大切にしてってのが理想だけど、これを全うできる人はそう多くはないんじゃないかな。アール(主人公)は自分の人生の来し方を後悔したけど、世間全体に視野を広げれば、自分の家族をもてたことだけでもいい。今の日本では核家族化を超えて、人生の孤独化が急速に広がっている...この作品では“デイリリー”花が話のシンボルとして使われている。終末の床でメアリーは夫アールに「家族も花と同じよ」と語った。そう、「家族」を育てその花を咲かせることは、自然の花を育て咲かせる以上に大変なことなのだ。私はそれを忌避して生きてきた。世間から見れば異質な人間だろう。だが後悔はない。偽善を生きるよりましだ。私は孤独だが、神に顔向けできない生き方はしていない。
2025.03.22
コメント(0)
-

いしださんの「ブルー・ライト・ヨコハマ」永遠に 🎵
ゴールデン☆ベスト いしだあゆみ [ いしだあゆみ ]歌手・俳優として活躍したいしだあゆみさんが3月11日に亡くなった。76歳だった。天国で安らかに🕯いしださんといえば、何と言ってもすぐに「ブルー・ライト・ヨコハマ」(昭和43年、1968)が思い浮かぶ。彼女の代名詞ともいえる昭和ムード歌謡の大ヒット曲だ。’70年に出された「あなたならどうする」もいい歌で、こちらは「ブルー・ライト・ヨコハマ」の続編のような作詞で別れの歌になっている。私はどちらかというと「あなたならどうする」のほうが好きだ。思うと、あの時代の空気感が甦る。また昭和の時代が遠ざかったように感じられる...歌手としての活動が一段落した後は俳優業を中心に活躍された。いしださんの出演作品で私が印象に残っているのは、映画『男はつらいよ 寅次郎あじさいの恋』(昭和57年、1982)だ。寅さん映画で毎度話題となるマドンナ役で、高名な陶芸家の家で働く影のある女中を演じている。いしださんは美人でいい女なのに、どこか薄幸な雰囲気があり’60~70年代にヒットした一連の持ち歌のように「尽くしても報われない女」のイメージがあった。この映画は、そんないしださんのイメージに合わせて脚本を書いたような恋物語で、寅さんよりもマドンナのほうが存在感の強い作品だ。いしださんの一連のヒット曲で使われた「尽くしても報われない女」のイメージは、後に別の歌手に受け継がれた。日本で再デビューしたテレサ・テンだ。彼女のトーラスR時代のヒット曲「つぐない」「愛人」「時の流れに身をまかせ」はいずれもこのイメージで作られている。テレサは病のため早世したが、いしださん、テレサともに女性としての家庭の幸せを掴めなかった(私観)点は共通している。お二人が、もしもう一度同じ自分(自我)として生まれたならどう生きるだろうか...人生は生まれた環境、才能の有無、機会の多寡などに大きく影響を受ける。あるはずの選択の自由もなかったりする。人は人生を選択できない。それを己の宿命と受け入れて生き続けるのもいい。また、それを途中で放棄することも、私は「あり」だと思う。「生まれ」を選べないなら、せめて「人生をやめる決断」は自分の意思によりたい。ところで、歌から遠ざかっていたいしださんのソフトな歌声を、あるラジオ番組で思いがけなく聴いたということがあった。NHKラジオ放送の『ラジオ深夜便』という番組のなかに「深夜便の歌」というコーナーがある。このコーナーのために制作された楽曲を、往年の名歌手・アーティストらが歌う企画で、歌は2・3か月ごとの入れ替えで放送される。いしださんも平成20年(2008)に「オアシス」という曲をそこで歌ったのだった(録音)。作詞・作曲は阿木燿子、宇崎竜童。これがほんわかとしたいい歌で、いしださんにピッタリの歌だった。宇崎・阿木夫妻はいしださんの雰囲気、イメージをよく醸し出した良い曲に仕上げたと、当時いたく感心した。
2025.03.19
コメント(0)
-

『ブルーベルベット』は『ツイン・ピークス』の原型? ~奇才デヴィッド・リンチ監督逝く👂
ブルーベルベットー日本語吹替音声収録 4K レストア版ー【Blu-ray】 [ デヴィッド・リンチ ]映画界の奇才デヴィッド・リンチ監督(米国)が1月15日に亡くなった。故人を偲んで『ブルーベルベット』(1986)をもう一度観ることにした。リンチ監督の作品はほとんど観ているのだが、この作品だけはまじめに見ておらず内容も覚えてなかったからだ。のどかな田舎町を舞台とした話なのだが、社会の表と裏の対比をエログロに映し出して妖しい空気に満たされた奇作である。高い評価を受け多くの賞を受賞したのだが、私にはそれほど優れた作品とは思われない。全撮影分で4時間あるものを2時間にカットして劇場公開版にしているせいか、話のつながりがわかりにくい部分があるし、主人公(演:カイル・マクラクラン)の行動もなんか不自然でリアリティがない。むしろ悪人グループボスのフランク(デニス・ホッパー)やその仲間たちの奇矯な言動の方が自然に見えてしまうちぐはぐさなのだ。これは未完成版、あるいは不完全版だと思う。また「これはテレビシリーズにしたほうがよかったのに」と思いながら、観進めるうちにハッとあることに気づいた。同じ作風で、舞台設定や地域社会の暗部をミステリアスに映し出したよく似た作品がある。あの『ツイン・ピークス』だ。そのテレビ版放送開始が’90年だから『ブルーベルベット』後の企画、制作期間に合う。推測だが、リンチ監督や製作陣が『ブルーベルベット』の未完成度を意識し、作品の特徴を生かしつつ話を翻案してテレビシリーズとして完成させたのが『ツイン・ピークス』なのではないだろうか。なにより両作品でカイル・マクラクランが主人公を演じているのが決定的で、世の表と裏、魂の善悪、異世界と妖しげな登場人物たちなど共通点はたくさんあるのだ。ところで、リンチ監督は日本(日本人)嫌いだったのではないかと私は思っている。『マルホランド・ドライブ』DVDの特典映像にリンチ監督へのインタビューが入っているのだが、インタビュアー(たぶん日本人)への受け答えがかなり横柄で不躾なのだ。なんであんな態度で受けるのか?と奇異に感じられた。また『ツイン・ピークス』のある回で、ステテコを着て尺八を吹く悪人が登場したのを覚えており、私のなかでそれは確信に近い。でも彼の作品の個性は評価する。特に、暴くことがタブー視されている人の世の闇、心の闇、善と悪の正体、魂が往くべき異世界の想像...等々、これらを映像作品として形に残した功績を評価する。とかく商業主義を押し付けられることが多い映像製作の世界で、よくぞこれだけ独自の創作を続けたと感心する。
2025.03.11
コメント(0)
-

『エクソシスト』ファンをがっかりさせる小品 😞
エクソシスト 信じる者 4K Ultra HD+ブルーレイ【4K ULTRA HD】 [ レスリー・オドム・Jr. ]『エクソシスト』(1973、初作)の直接の続編ということなのだが、あまりにも残念な出来でB級の評価。初作で母娘を演じたエレン・バースティン(母役)とリンダ・ブレア(娘役)の二人が出演していることを除けば内容につながりはなく、とり憑いた悪魔が同じパズズというだけ。今作ではパズズは二人の少女に憑依する。森のなかで降霊術を試みた二人が悪魔パズズに憑依され、二人の両親と関係者が協力して悪魔と戦う話になっている。なぜB級評価かというと、まずキャストがダメ。二人の少女のうち一人が黒人で、その父親役の黒人俳優が話の進行役になっているのだがパッとしない。演技力がもう一つだし、なによりオカルトホラー向きじゃない。他の出演俳優を見ても、それなりのレベルの人たちばかりだ。よかったのは悪魔祓いに加わった看護師役の女優さん(アン・ダウド)くらい。この看護師は元修道女見習いの過去をもつ設定になっており、その「過去」のストーリーでの役割、それに因る悪魔とのやり取りがよかった。むしろ、この看護師を話の進行役(事実上の主人公)にした脚本のほうがよかったのではないか。憑依された少女ふたりの演技は不気味なほどうまかった。つくりの粗さも目立つんだよな。黒人少女の母親は話の初めに地震災害で亡くなるのだが、お腹にいた胎児(黒人少女)が生き残って後の憑依物語へと続く。お腹の大きさの感じからすると臨月のようで、しかも双子のように映る。もしかしたら当初の脚本ではこの母親から生まれた双子が悪魔に憑依されるという筋書きだったのかも。しかし身重の妻とハイチへ新婚旅行に行くというのが不自然だし、その妻は現地で妖しげな祈祷(ブードゥー教?)を受けてしまうのだ。これが少女が悪魔に憑依される原因か?と思って見進めたのだが、そうではなかった。これは撮影の途中で、あるいはその後半で脚本の大幅な改変があったのかもしれない。まあとにかく、あの『エクソシスト』の直接の続編というのは、ややおこがましいのではないか。“続編”と宣伝するためにエレン・バースティンとリンダ・ブレアを出演させたのではないか-などと勘繰ってしまう。少し前にラッセル・クロウ主演の『ヴァチカンのエクソシスト』(2023)を観たが、こちらのほうが数段出来がいい。内容的には初作のリメイクだが、正統「エクソシスト」もの感がバツグンだった。
2025.02.15
コメント(0)
-

イエスには影武者がいた? 🕎 🔯
復活 [ ジョセフ・ファインズ ]福音書の映画化はいくつもあるけど、イエスの死から昇天までの部分をじっくり描く作品は珍しい。この作品ではローマ帝国の護民官を話の主役に据え、その護民官が復活の奇跡を目の当たりにし、キリスト信仰の証人となるというストーリーになっている。最初に熱心党のバラバが戦闘で殺されるシーンがあり、これは福音書には書かれていないエピソードなので、復活物語に独自の解釈による脚色を施した斬新な内容を期待したのだが、やはり教会の批判を受けない護教寄りの作品となっていた。でも、総督側が過激派(熱心党、反体制派)らによる暴動を恐れて秩序維持のためにイエスを処刑したことや、イエスの遺体が弟子たちによって盗まれることを危惧したりといった、史実としてあったと考えられる事柄を取り入れた点は評価したい。それらの点で、この作品は今の時代にふさわしい作りによる聖書物語になっている。私がもっとも感心したのは壮大な神殿の威容や、枯れ果て荒涼としたかの地の景観など、当時のイスラエル(パレスチナ)のイメージをよく再現した映像美。あの神殿、CGによるものではないし、あれを全部セットとして作ったとも思えない。現実に残っているどこかの城郭でロケしたのだと思うが、そこに行って見てみたいと何とも旅情をそそられる。復活の奇跡はどう考えたらいいものか...キリスト者なら信仰上の受け止め方があるのだが、キリスト教の一ファンというだけではそこは難しい。福音書のマタイ伝には、イエスには「4人の兄弟と他に姉妹たちがいた」と書かれている。その4人の兄弟のなかにユダという名前が見られる。 一方、イエスの12弟子の中にトマス(ディディモ・トマスとも)という人がいるが、この“トマス”とはアラム語で〈ふたご〉という意味で、ギリシャ語ではディディモといいやはり〈ふたご〉の意味とのこと。この人物は外典のトマス行伝では「ユダ・トマス」と呼ばれており、ほんとうの名はユダで、トマス(ディディモ)はあだ名ではないかと考えられている。私は、このトマス(ユダ)がイエスの兄弟の一人であるユダと同一人物で、イエスと双子の兄弟ではなかったのかと考えている。そして“復活の奇跡”は、このトマス(ユダ)が双子の利を生かしてイエスの身代わりとなって処刑されたか、もしくはトマスが復活したイエスを演じたのではないかと想像している。ラスト、ガリラヤの荒れ地を歩きゆくクラヴィアス(護民官)はどこへ行くのか...この話にはある史実の示唆がある。それは「原始キリスト教(ユダヤ教の分派)はローマ人が外地へ伝えた」ということ。ゴルゴタで刑死したイエスに心打たれた百人隊長の言葉は有名だが、使徒伝(ルカ)10章にコルネリウスという別の百人隊長のエピソードがあり、この人はカイサリアでペトロから洗礼を受け回心した敬虔なキリスト者である。ローマ軍には帝国領内での転任があったはずであり、ローマ兵士が小アジアやギリシャ方面へとその信仰を伝えたことは十分考えられる。キリスト信仰は、パウロが長旅の伝道活動をするより前にすでに異邦人の地に伝わっていたのだ。クラヴィアスが向かったのはダマスコかアンティオキア(ともにシリア)にちがいない。
2025.01.28
コメント(0)
-

ラッセル・クロウが個性豊かな神父役を好演 👍
ヴァチカンのエクソシスト ブルーレイ+DVD セット【Blu-ray】 [ ラッセル・クロウ ]ラッセル・クロウが神父役?どうかなぁ...と思っていたが、意外にもハマってた。彼が演じた主人公であるガブリエーレ・アモルト神父(故人)は特異な変わり者らしかったので、そのイメージにうまく合ったのかもしれない。あの『エクソシスト』(1973)が世に出て大ヒットして以来、“エクソシスト”をタイトルにした、また主人公にした数多くの作品が生まれてきた。が、オリジナル作があまりに出来がよいので、その後の派生作品にはB級ものもけっこうあるようだ。この作品は及第点をあげられる出来と思う。’70年代のフィルム時代の作りが窺われ、最近流行りのCG、VFX使用は控えめだ。ただ、内容的には『エクソシスト』のリメイク的な改変版の印象。時代に合わせて、悪魔にとり憑かれた少年の変貌ぶり、奇矯な行動などはソフトに表現されており、鑑賞者への衝撃を和らげている。二人の神父が悪魔に挑む場面では、オリジナル作へのオマージュとわかる心憎いシーンがある。大きく違うのはヴァチカンの関わりで、ローマ教皇自身が悪魔祓いに積極的な姿勢を見せていることだ(あくまでもこの話のなかで)。この作品はガブリエーレ・アモルト神父の回顧録『エクソシストは語る』の映画化とのこと。回顧録にどんなことが書かれているのか知らないが、映画化に際してはかなりの脚色、創作が施されたはずだ。作中で少年にとり憑いた悪魔はアスモデウスという名だが、アモルト神父(本人)が祓魔中にそうした悪魔の名を相手から聞いたとは思えないし、映像化されたような超常現象もまずなかっただろう。だが、私はエクソシズムの本質を否定はしない...悪魔を見たことはないが、その力(悪の作用)を感じたことはこれまで何度もある。目に見えない負のエネルギーとでも言ったらいいだろうか。また世にはその負のエネルギーを纏った、言い方を変えれば悪霊に心を満たされた邪悪な人間が存在する。他者に悪意をもって故意に嫌がらせをしたり(イジメ、パワハラ)、傷つける、盗む、殺す等々の悪行を平気でする...そして、その行為に対して心が痛まない。ところがその一方で、どれほど苦難に遭ってもどうしても悪いことができない人がいる。この違いの原初には未知の何かがある。酷い悪事を犯す人にはその脳に障害がある(病気)場合もあるのだが、人には本体(精神、心、魂、霊)の違い(そのルーツの違い)による「光の子」と「闇の子」といった区別があるように思えてならない。
2025.01.14
コメント(0)
-

『刑事 ジョン・ブック』~アーミッシュの暮らしは理想形なのか🎄
刑事ジョン・ブック 目撃者 スペシャル・コレクターズ・エディション [ ハリソン・フォード ]筋書き、結末がわかっていても、何度でも観たくなる映画がある。『刑事ジョン・ブック』(1985)は、私にとってそんな作品の一つだ。警察内部の汚職にまつわる摘発事件を軸に話が進むのだが、真に描いているのはアーミッシュの村と都市部との対比とともに、そこで暮らす人々の人生の違い、世界観の違いだ。主演のハリソン・フォードにとっては、それまでアクションヒーロー系で売ってたイメージを変え役の幅を広げつつある時期の作品であり、ハン・ソロやインディアナ・ジョーンズとはまた違った彼の魅力を味わえる。アーミッシュとはプロテスタント・メノナイト派から派生した分派で、自給自足生活をするキリスト教者共同体だ。メノナイト系教会の信徒はアナバプテスト(再洗礼者)と呼ばれ、信徒の資格が厳しく問われる。破門制度があり、規律に反した仲間は忌避されるとのこと。映画のなかでも、ジョンが身を寄せた家(アーミッシュの村)の主が、村人みなから疑われ追放されることをひどく恐れるシーンがある。宗教団体の共同体にとって規律は絶対的だ。信仰と規律こそが共同体を維持するための両輪であり、それに瑕疵が生じればコミュニティはたちまち崩壊へと向かうのである。16世紀の宗教改革によって、ローマ教会(カトリック)を離れ福音主義による新しいキリスト教信仰がうち立てられた。その後時代を経ていくつもの教派に分かれ、以来多くのプロテスタント諸教会が存在する。なかでもメノナイト派(アーミッシュ他)は、原始キリスト教会(エルサレム教会)に近い信仰共同体を志向した人たちだ。いろいろな考え方があろうが、イエスとその弟子たち、またイエス亡き後の弟子たちの信仰活動をみれば(福音書、使徒伝)、自給自足の共同体生活を営むというのは原初の信仰形態に最も近いものだろう。だがこれは信徒が多くなり広がっていくと、それを維持するのが難しくなる。理想のあり方とは思うが、あくまでもその信仰を基にした村落の一形態なのだ。さて、実のところ神はどこにでもいる。その至高の存在は時間と空間を超えたものであり、我々にはその正体はわからない。だがそれは我々に何かを知らせ、警告や導きを伝えることがある。我々を手助けすることもあれば、過酷な試練を与えることもある。そのことに、誰にでもわかる客観的な証しはない。至高の存在を信じる人にそれを感じとることができるのだ。2024年のクリスマスを迎えた。キリストの生誕を祝う日ということだが、市井では年末の風物詩で楽しい宴や催しの機会という感が強い。グループで、あるいはカップルで過ごすのもよいが、一年に一度聖書やキリスト教関連の映画を何か一つ鑑賞してみてはいかが?
2024.12.24
コメント(0)
-

『All You Need Is Love』♪💖か...
魂のゆくえ [ イーサン・ホーク ]息子を戦争で失い、妻とも別れて、失意の底で生きる牧師の苦悩を描いた作品だ。トラー牧師は息子に軍への入隊を勧めたものの、その息子が戦死したことで自責の念に押しつぶされつつ牧師生活を送っている。その苦悩を酒で癒す日々が続いており、身体の異変に気づくも酒をやめられないでいた。そんな折、若い女性信者の夫から相談を受けることになったが、その彼が突然自死したことからトラー牧師のなかにサタンが侵入を試みた...う~ん、完成度がもうひとつかなぁ...環境問題を採り上げてるのは善しとして、作品全体としてもう一つまとまりがないというか、監督の主張がクッキリと浮き出ていない感じ。イーサン・ホークの牧師姿、振る舞いはよいのだけど、話自体になんかリアリティがない。とくにメアリーとの絡みで、後半の瞑想場面とラストの唐突な抱擁... 彼女どうやって館に入ったのか?ドアには鍵がかかっていてジェファーズ牧師は入れなかったのに。その前も、トラー牧師の爆弾ジャケットから有刺鉄線ぐるり巻きとあまりにクレイジーな展開に呆れてしまった。邦題から、もしかして死んだマイケルの魂がトラーに乗り移って-なんて考えも浮かんだのだが、そういった伏線は無く、トラー牧師が心を病んでいたとしても、話の流れが不自然なため惹き込まれることがなかった。もう一方の主題、教会について。その体質はローマ帝国による公認、国教化へ、そして中世から近代まで続いたキリスト教会の大権力・大権威時代と同じ。教会も、布教を広め信徒を増やし拡大していくためにはお金が必要。また、大きくなった組織を維持していくのにもお金が必要と。ローマ教会は帝国というスポンサーを得て、持ちつ持たれつの関係から巨大な権力機構へと変貌していった。キリスト教国になったからといってローマ帝国が戦争をやめるわけもなく、身分制社会のなかで弱者に対する抑圧・横暴は続いていたはずだ。しかし教会指導者たちはスポンサー側の立場を守り、不都合な事実には目を瞑ってきた。社会の構造は基本的に昔も今も変わっていないのだ。この作品はまさにこの問題をテーマとして扱っており、企業と教会の偽善を告発し、その癒着が信仰に反し神の創造したこの世界を破壊しているのではないかと訴えてるのだ。もっとも-「愛は律法を凌駕した。律法の目的は愛によって成就した」と、ユダヤ教の不完全さを克服した(とされる)キリスト教の本質によって評価するなら、あの結末は「あり」かな。
2024.12.13
コメント(0)
-

「日本創生」という名の“原日本破壊”を、決してゆるすな 😠
「日本創生解散」なる総選挙が終わり、第二次石破内閣がスタートした。総選挙の結果は与党の惨敗。予想されていたことだが、私は選挙前までは自公でギリギリ過半数は維持できるのではないかと思っていた。石破政権がほとんど動いてないうちの速攻解散だから、今回は自民党総裁選への国民審判となった。安倍政治の継承者とみられている高市早苗議員の敗北の影響は、ことのほか大きかったのだ。特別国会での首班指名をめぐって与野党間、とりわけ自民党と国民民主党との連携が取り沙汰され報道を賑わせたのだが、11月11日の衆議院で決戦投票の結果比較第1党の自民党総裁石破茂指名となった。衆議院で少数与党による政権運営となるが、これも予想どおりだ。いまの野党に政権を担える政党はなく、連立内閣をどのように組むにしても自民党が核となる政権しか考えられない。それに、なにより石破政権の継続を望んでいたのは野党側なのだ。いま自民党は左派議員団が主流派だ。彼らの政策は立憲民主党のそれとほぼ同じであり否定する必要がない。それに野党多数であれば、伝家の宝刀「内閣不信任決議案」という切り札を実効性をもって使える。その後臨時国会を迎えるにあたって、衆院与野党逆転の効果が各委員会の委員長ポスト振り分けにも表れた。なんと自民党は予算委員長をはじめ法務委員長、さらに特別委員会の憲法審査会長まで立憲民主党に渡してしまったのだ。これは前代未聞のことで、自民党は衆議院で立憲民主党と共同会派を組んだも同然である。いくら少数与党になったからといって、予算委員長まで野党に任せるというのはもはや投げやり政治としか言いようがない。さらに問題なのは法務委員長ポストだ。立憲民主党ほか左派野党は来年通常国会での「(選択的)夫婦親子別姓制度」実施のための民法改正に野心を燃やしている。法務委員長ポストが立憲民主党議員なのでは、これは成立してしまう可能性が高い。夫婦親子別姓制に関しての国民の意見は大きく分かれている。国民各個の考えの違いもさることながら、この制度改正には非常に重大な問題がある。夫婦親子同姓は「家」を構成する家族のあり方なのであり、これまで日本人の文化、社会を形成し、国の歴史を紡いできた大切な伝統であるということだ。つまり日本という国体を成すための、それがあるための土台といっていいものであり、家=家族の一体が国家存立の大事な要素となっている。これを単に合理性、個人の優先のみをもって改変することは、国の存続にとって非常に危険なことである。しかも、これの制度化を積極的に進める人たちには大きな目標があり、この取組みはその前段階との冷徹な見方もあるのだ。その“大きな目標”とは戸籍の廃止である。日本の戸籍は父系を遡って先祖を辿ることができ、遺産相続の際などにも非常に確かなツールとして社会的に機能している。意外にも世界でこの制度が整っている国は少ないらしく、日本の戸籍制度は世界に誇り得る制度なのだ。ところが、これを嫌う人々がいる。自身のルーツを隠したい、あるいは無きものにしたい人達だ。いま政府は少子化や人手不足を口実になし崩し的な外国人受け入れ政策を進めている。全国の一部地域でその弊害がすでに深刻な形で表れており、日本の形が崩される危機が進行中なのだ。「(選択的)夫婦親子別姓制度」の導入は原日本の破壊に拍車をかける。その先には皇室の廃止による国の共和制化もあるものと、私は大いなる警戒心を抱かざるを得ない。安倍総理亡き後の岸田政権から石破政権への衣替えは、私たちの祖国日本にとんでもない事態を惹き起こす虞がある。天皇は「元首」である [ 竹田恒泰 ]
2024.11.20
コメント(0)
-

飯山あかりの乱 ~日本保守党の闇を告発 😎
衆議院選挙の期日前投票を済ませてきた。今回はけっこう迷い、また戸惑いながらの選択になった。昨年9月に旗揚げした日本保守党(政治団体)を支持してきたので、そのまま同党に投票するつもりだったのだが...4月に行われた衆議院東京15区補選(江東区)に同党から出馬した飯山陽(イスラム思想研究者、博士)さんが、同補選を通して自身が見た日本保守党の闇を告発し出したことで、信頼の気持ちが揺らぎ始め迷いが生じてしまった。選対陣営の中の様子は我々にはわからない。まさか飯山さんが選挙中に内部であれほど酷い仕打ちを受けていたとは...飯山さんは「旧虎ノ門ニュース」終了後にYouTubeで「いかりちゃんねる」という配信番組を始めた(現「飯山あかりちゃんねる」)。私はその番組を最初からずっと視聴してきたので、飯山さんが話した日本保守党との関係や彼女の政治に対するスタンスを知っている。まず基本的なこととして、飯山さんは日本保守党の一党員であって、党運営や党務には関わってきていないということである。また彼女は政治活動をしておらず、政治家(議員)になる考えもないということ。これを飯山さんは自身の配信番組のなかで明言していた。しかし日本保守党代表の百田尚樹氏と事務総長の有本香氏が、東京15区補選で飯山さんに出馬要請し選挙に引っ張り出したことから彼女の人生は急変した。飯山さんは出馬をまず断わり「百田氏か、有本氏が出るべき」と進言した。ところが二人は飯山さんが断ることを予見しており(推測)、説得するための巧妙な理由を用意していた。詳細は長くなるので割愛するが、その決定打は「私(有本)は7月の都知事選に出るので、補選には出れない」というもの。ところがその後保守党は都知事選挙を回避し候補者を出さなかった。飯山さんは結果的に騙されたような形になったのだ。しかし選挙運動がスムースに運んだなら問題はなかった。選挙期間中飯山さんは百有コンビを含め選挙スタッフから村八分にされ、数々のイジメ、仕打ち、嫌がらせを受けたのだ。さらに、つばさの党の者たちから悪辣で執拗な選挙妨害を受けて(同党3人が逮捕され勾留中)、心に酷い傷を負う破目に至った。この事実について、飯山さんはいまスクショ他で残しておいた証拠を基に自身のYouTube番組で告発を続けている。日本保守党は昨年9月に百田・有本両氏が起ち上げたのだが、その後の動きを見ていて「二人は、この保守新党プロジェクトを自分たちのビジネスにも活用するつもりではないのか?」との思いはあった。しかし政治団体の設立には金がかかる。政治活動にも金がかかる。その資金を「YouTube」や「ニコ生」で稼ごうとするのは仕方ないことと見守ってきた。ところが東京15区補選での飯山陽さん擁立の頃から「なんか怪しい」と、それまでの<見守り>が徐々に<疑い>へと変わってきた。そしてここに来ての飯山さんによる「告発」によって自分の疑いは正しかったと確信するに至った。日本保守党の政治理念、主張、政策の柱を私は支持している。しかし今回の投票で、比例代表の投票用紙には「国民民主党」と書いた。人ひとりの心の痛みをわからぬ人たちが運営する政治団体に、掲げてるような政治の理想を実現できるのか?という疑いからだ。選挙区では参政党の候補者の名を書いた。参政党も日本保守党と同じく、まだ比較的新しい新興保守政党だ。私は同党にはやや妖しいものを感じており、とくに支持してはいないのだが、他候補者はまったく支持できない人ばかりなので消去法による選択となった。「いい人」の本性 [ 飯山陽 ]
2024.10.25
コメント(0)
-

第50回衆議院選挙 ~日本創生解散は、原日本破壊解散か😨
第50回衆議院選挙の真っただ中だ。9月の自民党総裁選で石破内閣が誕生。その後10月9日(水)に衆議院は解散された。石破総理は会見で「この解散は“日本創生解散(選挙)”だ」と言った。「なんじゃそれ?」と多くの国民が苦笑したと思うが、これ実は案外的を射ているかもしれない...いま政府・与党は(事実上の)移民受入政策を爆推進している。これが日本全国各地に様々な問題を惹き起こしている。とくに目立つのは埼玉県川口市のクルド人集住地区だ。彼らのなかに悪辣な者がおり、ルール無用で好き勝手に振る舞い、街の治安を乱してそれこそクルド人自治区化するかごときの勢いらしい。その中には日本に不正侵入・不法在留している者が多数いる(らしい)とも聞く。また中国からやベトナムなど東南アジアから来た定住者の犯罪も多くなり悪質重罪化してきている。最近で衝撃だったのは、中国人運転者による重大交通事故だ。若者によるスポーツカー暴走事故と酔払い運転による一方通行逆走暴走事故。どちらも過失のない日本人運転者の非業の死を招いている。さらに、急増するイスラム系定住民の問題も顕在化してきた。いま一番気がかりなのは、大分県日出町で造成へと向かう大規模イスラム教土葬墓地の問題だ。同地域では山林の水資源を飲料水として利用しており、山を切り開いての大規模土葬墓地造成は日々の生活にかかわる大問題なのである。同町では今年8月に町長選挙が行われ、イスラム土葬墓地の建設反対を唱える元町議が当選した。これで建設が白紙に戻るかわからないが、建設推進に一応ブレーキがかかった形だ。その他にも、外国人による地域神社の破壊行為、放火(推測)といった粗暴な振る舞いがここのところ相次いでおり、これが歪んだ宗教原理主義による行為である可能性は否定できないだろう。政府は経済界の要請に抗しきれず、国外から安価な労働力を入れ続けている。これが純然たる出稼ぎで一時的な滞在ならいい。しかし政府は出稼ぎ労働者の定住化を促進し、事実上の「移民制」として運用しようと進めているのだ(「技能実習制度」から「育成就労制度」への転換)。これが石破総理の掲げる「日本創生」だ。“日本再生”ではなく、「来る者は拒まず」の外国人定住化をなし崩し的に進め、日本を秩序なき多民族国家にしようとの日本改造宣言なのである。いま欧州各国は「移民政策の失敗が社会の破壊を招いた」と、誰の目にも明らかなほどの悲惨な状況と混乱に陥っている。先の大戦に敗れて、我々はGHQ(アメリカ)による占領政策とユートピア憲法の押しつけによる<日本の改造と破壊>を見続けてきた。人権絶対&世界市民主義によった戦後憲法を聖典と崇め、日本政府は原日本の破壊を自ら進めている。それを止め、真の日本を再生するべく獅子奮迅の働きをした救世主は凶弾に倒れた。この選挙で安倍さんの非業の死や不良外国人の問題がクローズアップされないのはなぜなのか?我々は「岸-破内閣」など断じて支持しない。高市早苗議員のリベンジを固く信じて、真保守派の大同団結を企図していく。反回想ーーわたしの接したもうひとりの安倍総理 [ 青山繁晴 ]
2024.10.23
コメント(0)
-

イコライザー THE FINAL 💥
イコライザー THE FINAL ブルーレイ + DVD セット【Blu-ray】 [ デンゼル・ワシントン ]米国版「必殺(仕事人)シリーズ」の第3作にしてファイナル版をようやく観た。マッコールの秒殺業は相変わらずの切れ味で見応えバツグン。さらに新作を見たいと思ってしまうが、マンネリ路線に乗ってしまうかもしれないので、切りのいいところだろう。第2作はCIAの高官でマッコールのよき理解者であるスーザン(演メリッサ・レオ)の敵討ちがそのストーリーなのだが、後半のクライマックスはなんかマカロニ-ウエスタンの西部劇風で、初作に比べるとちょっと物足りない感じがあった。今回は舞台をイタリアに移し、助演にあのダコタ・ファニングを迎えて、風光明媚な土地柄を活かした旅情的なつくりになっている。今回、彼はマフィアの子供に油断し重傷を負って瀕死状態になる。それを地元の老医師エンゾに助けられ、その町に魅せられ溶け込むことからそこを安住の地と定める。エンゾはマッコールに問う-「君は善人か?それとも悪人か?」と。マッコールは「わからない...」と苦悩の表情を浮べ答えるのだが、後にエンゾは「そう答えるのは善人だけだ」と問うた理由を話す。この最終作は、暗殺業を続けてきたマッコールがその自分と向き合う苦悩をよく映している。ところで、日本の時代劇ドラマ「必殺シリーズ」もそうだが、ここには武断主義の真実が込められている。退治される極悪人に裁判を受ける機会は与えられない。ただ「闇に裁いて仕置きする」なのだ。作品はこれを肯定してるわけではない。しかし、行き過ぎた人権絶対主義がかえって社会を歪めているのも事実である。日本は特にひどい(私観)。こうした作品が受けるのは、人々のなかに「いまの世の中、どうなのよ?」という疑念があるからなのだろう。
2024.10.10
コメント(0)
-

おばあさんだけは、本物のスピリチュアル系!👵
ベルイマン (新装版 人と思想 166) [ 小松 弘 ]イングマール・ベルイマン監督(スウェーデン、故人)は、他の有名映画監督に広く影響を与えた20世紀を代表する映画監督の一人だ。その作品を時々選んで観ているのだが、今回は『魔術師』(1958年)という作品を鑑賞。19世紀半ば、近代という時代にあった西欧社会の雰囲気がよくわかる作品で、魔術師の一座がある町の指導者らに嫌疑をかけられ、領事館で受ける苦難が話の筋になっている。陰鬱で深刻なムードのまま、スピリチュアルなものと科学との対立という図式で話が進むものの、ラストは意外にも喜劇風に終わり拍子抜けしてしまう。一番印象に残ったのは、旅芸人一座に同行するおばあさん。一座の者たちは“魔術”を売り物にする旅芸人なわけだけど、そのおばあさんだけは本物のスピリチュアル系なんですね。出だしの場面でカラスに唾を吐きかけたり、領事館の御者の運命を暗示したりとか、また館の柱に逆十字(かな?)を書く所作などが見られ、キリスト教の世界観でいうところの「魔女」なわけですね。でも、ほんとうはドルイド教(キリスト教が広がる前の土着の宗教)における特殊なスキルをもった人たちの末裔なのだと思いますね。彼女たちは森の中で薬草などを採り、それを生活に役に立つ薬として調合したりするスキルを伝統的に受け継いでいる貴重な存在だった。作品中でもおばあさんは様々な薬を保持しており、それを売って蓄財していたことが最後に明かされている。ところが、西欧でキリスト教の布教が進み優位になると、彼女らの存在は邪悪なものとされ、「魔女」のレッテルを貼られて表社会から追い出されることになった。旅に暮らす遍歴芸人とそこに身を置く老婆の存在は、当然にそうした社会事情が背景にあるはずだし、ヴォーグレル(座長)とマンダの夫妻もかつて家を買って一度は定住しながら、結局また巡業の旅に出たとのエピソードが語られている。“魔術師”といわれる人たちは、イエス(キリスト)が生きた時代にも存在した。福音書にもそれが書かれており、預言者とは容易に区別のつかない妖しげな人たちは世にずっといたのだ。だがその本質(実態)はここでも描かれているとおり、基本的に生活の糧だった。道具や手品、催眠術などを駆使して人を当惑させる、今でいうマジシャンだ。ニセモノは時間とともに忘れ去られる。だが、ナザレのイエスという人の言行が強固に残り、「キリスト信仰」となって二千年も消えることなく続いていることには理由があるはず。彼はたとえニセモノと疑われても、人々がその言行をインチキと単純に否定することのできない、なにか特別なものをもった人物だったのではないだろうか。
2024.09.24
コメント(0)
-

テーマは「異質な者との共生、そして絆」だ 🖖
500ページの夢の束 [ ダコタ・ファニング ]『スタートレック』の応募脚本執筆に夢を託し、グループホームで暮らす自閉症のウェンディをダコタ・ファニングが演じている。ダコタ・ファニングというと、天才子役として大変有名な人なのだが、成人してからの作品を見るのはこれが初めて。なかなかいい女優ぶりに感心した。少女の頃の可愛らしさもほどよく残して、すっきりした大人の女性になっている。子役で脚光を浴びた俳優は、大人になって躓き大成できない人が少なくない。その点彼女は確かな素質を維持して順調な俳優活動を続けている。こういう人はハリウッドの宝だと思う。それと、顔はそれほど似てないが、彼女は若い頃のジョディ・フォスターとどこかイメージが重なるところがある。物事の真実を見つめるようなあの目元のあたりかな。彼女には共演したベテラン俳優、監督から数多くの称賛の声があるそうだけど、それも至極納得。ハリウッドは「女優は40歳を過ぎると役がなくなる」という厳しい世界だそうだが、彼女は長く活躍できるタイプと思うので今後も地道に俳優業を続けてほしい。なぜ『スタートレック』なのか?“トレッキー”にはその答えは簡単だ。この作品の主人公をめぐるエピソードと「スタートレック」には共通のテーマがあるからだ。それは「異質な者との共生、そして絆」である。宇宙船エンタープライズ号のメインクルーは国際色豊かだ。白人、アフリカ系、アジア人、そして宇宙人とのハーフと。深宇宙の有人探査ができ、宇宙人とのコンタクトが成った未来の話だから違和感はないんだけど、この設定は同SFドラマの放送が始まった時代には新鮮だった。「スタートレック」の作者であるジーン・ロッデンベリーは、このSFドラマに「異質な者との共生と絆(あらゆる差別の超克)」をテーマとして折り込み、理想とする未来像を描いたのだった。いろいろなハンデをもって生きていくのは大変なこと。これは女優が演じる映画作品だからソフトできれいに作られているが、現実のあり様がもっと深刻であるのは誰しもわかることと思う。けれど、「夢をもって生きる」と。自分を支える何かが無ければ、人は人生に失望して虚無の奈落に落ちたまま。「スタートレック」もそうなんだけど、こうした作品を見て希望の光に接することは癒しになる。
2024.07.13
コメント(0)
-

『タイムマシン』 ~人類はどこへ行くのか...
SF映画『タイムマシン』(2002、米)を久々に観た。H・G・ウェルズの傑作小説の映画化だ(リメイク)。ただ、物語には大幅な脚色がなされており、映画版として映像効果を重視したアクション・アドベンチャー風に作られている。タイムマシン 特別版 [ ガイ・ピアース ]結婚を約束した女性を失った物理学の大学教授が、その後研究を極めてタイムマシンを完成させ、女性の死を防ぐべく過去へ向かう。しかし、何度時間を遡って行動を変えても恋人の死を回避することはできなかった。彼はその“答え”を求めて未来へと向かう。21世紀の人類を襲う危機的惨事を経験し、さらに80万年後の世界へとたどり着いた彼はそこで人類の驚くべき変貌を見ることになる。人類の末裔は地上と地下とに分かれて生き延びており、地下で生きる『モーロック』は異形の変異を遂げていた。そのなかに、地上で生きる『エロイ』(言葉はちがうが見た目はそのまま人間)とともに両種を支配、管理するウーバー・モーロックという超能力をもつ個体がおり、教授は彼から求めている“答え”を得ることになる。「エマ(恋人)が死ななければタイムマシンは生まれなかった。あるはずのない機械で救えるはずがあるまい」と。これはタイムパラドックスだ。21世紀の場面でAIが教授に「タイムトラベル?それは不可能だ」と告げており、時空連続体を旅することが空想であることは示されている。この物語は人の性(さが)を扱ったSFファンタジーなのだ。人は残酷な因果律に翻弄されて生き続ける。「もし、こうだったら...」と人生に悩み続けるのだ。物語は、アレクサンダー(教授)が未来を変えようとしてウーバー・モーロックに逆襲し、エロイとともに生きる道を選んだ所で終わる。人生には無数のパラメーターがある。過去は変えられなくとも、未来を変えるチャンスはある。
2024.06.15
コメント(0)
-

『サムソンとデリラ』~ イスラエルの誇り、そして名誉の回復
長年関心を持ち続けてきた映画をようやく観た。セシル・B・デミル監督の『サムソンとデリラ』(1949、米)だ。ヘブライ聖書『士師記』にあるサムソンとデリラの物語を原作としている。サムソンとデリラ リストア版【Blu-ray】 [ ヘディ・ラマー ]この作品は米アカデミーの美術賞と衣装デザイン賞を受賞している。そのほかには技術的な部門でのノミネートがあるだけで、内容面や俳優の演技についての評価は低かったようだ。そもそも原作エピソード自体がそれほど面白いものではなく、どう映画化したか(脚色、脚本)に関心があったのだが、『十戒』のようなスペクタクルな映像表現はなく、大作感に乏しい退屈な作品だった。セシル・B・デミル監督は『史劇の巨匠』として知られ、映画創成期に最も成功した映画製作者のひとりとのこと。同監督の作品で私が観て感銘を受けたのはやはり『十戒』(1956年、自身のリメイク版)だ。大変有名な、紅海を二つに割るあのスペクタクルな特撮シーンは決して忘れることができない。それに比べると『サムソンとデリラ』はだいぶ小品なのだが、この題材は映画だけでなくオペラや絵画などでもこれまでよく採り上げられている。英雄と美女の愛憎劇の惹きもあるだろうが、デミル監督がそうであるように、ユダヤ系のクリエイターが自身の遥か遠いルーツ、その歴史のなかの英雄劇を扱いたいという思いもあったのではないだろうか。また、この物語がユダヤ系の人によく採り上げられるのは、古代イスラエルの主要な敵であるペリシテ人のこともあるのかも。ペリシテ人はパレスチナ(ペリシテ人の土地との意味)の先住民で、紀元前12世紀頃に同地に定着した元地中海の海洋民族らしい。このペリシテ人とイスラエルの民との間には様々な攻防、関係があったようで、「サムソンとデリラの物語」はダン族(イスラエル12部族の一つ)がペリシテ人の都市国家支配下にあった時期の話となっている。紀元前604年に新バビロニア王国による侵攻があり、ペリシテは同帝国に編入された。これ以降ペリシテ人は歴史記録から消える。しかしイスラエルの民(ユダヤ人)はその後に遭う幾多の苦難・逆境に耐え、民族の歴史を紡ぎ、第2次大戦後約1900年ぶりに祖国を再興した。ユダヤ系クリエイターには、迫害を乗り越えて今日まで生きてきた民族のその歴史を誇り、世界に顕示したいとの思いがあったものと想像する。いまガザ地区(ここはペリシテ人の繁栄拠点であった。これも何か因縁めいている)での紛争によりイスラエル国は世界中のアラブ人から憎まれているが、祖国を失い世界に離散しながらも民族としてのアイデンティティを失わなかったユダヤ人を、私は心から尊敬している。
2024.05.20
コメント(0)
-

千里の道も一歩から ~日本保守党の国政選挙初陣!
衆議院の補欠選挙が終わった。(28日投開票、全国3か所-東京15区、島根1区、長崎3区)注目していた東京15区(江東区)は自民党の議員が2代続けて汚職事件で退場した問題の選挙区で、9人が立候補し激戦が繰り広げられた。また某政治団体による酷い選挙妨害があり、その様子が連日ネットで伝えられた。応援し期待した日本保守党の飯山あかり(飯山陽)さんは惜しくも落選。しかし出来て半年ばかりの新興政党(団体)であり、江東区での政治活動も2か月ほどの短期間であることを考えれば、24,264票(有権者数430285人、投票率40.70%)の得票はたいへん善戦したといえる。党としては初の国政選挙挑戦で、結果の予測はある程度できてたはずなのだが、とにかく一度やってみたほうがいいとのことだったのだろう。この経験値は今後の活動において大きな糧となるはず。当選者は立憲民主党の酒井菜摘氏だ。得票は49,476票。選挙前から、そして選挙中を通して優勢が伝えられ続けた。これは当然なのである。彼女は江東区の元区議(二期)であり、昨年12月に行われた同区長選に出ているので他候補者に比べて大きなアドバンテージがあった。しかも共産党が候補を取り下げ立憲に協力したので、同区の共産党票2万が入ったといわれる。立憲民主党と共産党はもはや特別友党関係。やはり“立憲共産党”なのだ。選挙結果については飯山陽さん自身がYouTube配信「飯山あかりちゃんねる」で的確な分析をされてるので、関心のある方は視聴してみてほしい。さて、この結果を得て日本保守党の今後の政治活動、選挙へ向けての戦略、戦術も新たに固まってくるだろう。最大の目標は来年の参院選になるだろう。それも全国比例だ。新興政党で資金も人材も不足する日本保守党には、選挙区での戦いは大いに不利なのだ。だが全国比例なら逆に百田・有本両氏の人気が大いに力を発揮する。候補者にもよるが、私は2名当選者を出せると予想している。今回の結果に党の執行部、関係者に落胆はないと思う。日本保守党はまだ千里の道を一歩踏み出したばかりなのだ。日本保守党 ~日本を豊かに、強く。~ [ 百田尚樹 ]
2024.04.30
コメント(0)
-

ブレグジット ~ 国民投票の主役は「IT」だった?!
衆議院の補欠選挙が全国3か所で行われている。東京15区、島根1区、長崎3区で、4月28日(日)に投開票が行われる。なかで東京15区(江東区)は自民党の議員が2代続けて汚職事件で退場した問題の選挙区だ。ここには9人が立候補し激戦が繰り広げられており、某新興政治団体による過激な選挙妨害が連日ネットで話題になっている。関連で、少し前に観た『ブレグジット EU離脱』(2019、英)というテレビ映画を思い出したので紹介したい。ブレグジット EU離脱 [ ベネディクト・カンバーバッチ ]2016年に行なわれたイギリスのEU離脱(ブレグジット)の是非を問う歴史的な国民投票の内幕、とくに離脱派運動団体を指揮したドミニク・カミングスの国民投票攻略法について描いたものだ。政治家やその秘書が選挙に強いとはかぎらない。新人ならまったくのどシロウトだし、ベテラン議員でも選挙は苦手という人が少なくない。そういう人、とくに落選が続いた人などは選挙の攻略法に長けている職人、いわば“当選請負人”のようなその筋のプロを雇うのだ。有権者にはあまり知られていないが、結果を出すために激戦のなかで黒子役に徹する特殊な才覚者が現実にいる。ドミニクもそういった“余人をもって代えがたい”人物だ。だが、ここでクローズアップされているのは彼のそうした才能よりも、むしろ彼が目的達成のために用いた最先端の情報操作技術だ。ドミニクは情報技術の専門家を使って有権者の心理を深く詳細に分析し、これまで投票に行かなかった層も新たに掘り起こして、それを離脱支持の投票行動へと結びつけた。これは政治活動に限ったことではない。ビッグデータ活用による企業の商業戦略などが広く進行しており、情報による大衆心理の操作はあたり前のことになりつつある。ドキュメンタリータッチの解説的作品だから話のおもしろさはないが、政治や社会問題に関心の高い人なら見ておいて損はないはず。翻って日本の選挙はといえば、“溝板(どぶいた)”という言葉が死語になっていないとおり、いまだ地縁、血縁、義理人情による集票システムが強いようだ。今補選での注目は東京15区。ここは日本保守党の国政選挙初挑戦の場。同党の飯山あかり候補になんとか勝利してほしい。天にある安倍総理の恵みが日本保守党と飯山あかり候補に注がれることを願う。
2024.04.23
コメント(0)
-

「祟り」はあるのか? ~映画『八つ墓村』から
女優の山本陽子さんが亡くなった(2月20日、81歳)。和服がよく似合う日本美人の雛形のような綺麗な人で、また潤いのある声も魅力だった。映画、テレビドラマ、舞台と活躍されたが、私が印象に残っているのは映画『八つ墓村』(1977、野村芳太郎監督)での多治見春代役かな。山本さんらしい品のいい役柄だった。天国で安らかに 🕯あの頃映画 松竹DVDコレクション 八つ墓村 [ 萩原健一 ]『八つ墓村』のおもしろさ、出来栄えの良さなどはもう定評となっているので改めて書くこともないだろう。ただ、この映画のテーマとされている「祟り」とか「怨念」「因縁」といったオカルトチックなものについて少し書いておきたい。都会ではこうしたものは「ばかばかしい」と一笑に付されることが多いかもしれない。しかし、地方部では今も高齢者たちのなかに、これらを軽視できない重い事柄として恐れる人がけっこういると思う。私の両親は東北地方の寒村の出だが、母の出身の村でこの多治見家と同じような恐ろしい因縁めいた家があったと聞いたことがある。その村には非健常者の出生が何代にも渡って続いた家があって、なんでもその原因が昔あった家どうしの泥沼化した諍いにあるというものだった。詳細は忘れたが、その村のA家とB家の間になにか争いごとがあって、その結果一方の家が没落するに至ったらしい。その没落した家の当主が今際の際に「○○代まで(あの家を)祟ってやる」と言い残した。そしてその後、存続し続けた家の子孫には非健常者の出生が続いたというのである。母が若い頃に聞いた話だというから、両家の争いがあったのは近世後半か近代に入った頃だろう。もちろん今なら、これは遺伝学による説明によって済む話かもしれない。しかし、単に偶然の出来事とは思えない、あるいは合理的な説明のできない不可思議な事象は世にたくさんある。キリスト教では、神の前に「すべての人は罪人である」という前提がある。人間なら誰でも罪を犯してしまうということだ。学校なら「イジメ」、実社会なら「パワハラ」と、その当人が法の裁きを受けない悪事はつねにある。実害の発生はなくても、相手の気持ちを考えずに悪態をつく、陰で悪口を言う、悪意の謀をするといった人が必ずいるのだ。また、心ならずも相手に悪いことをしてしまった-ということは誰にでもあるはずだし、過去のそうした言動を忘れてしまっている人もいることだろう。これまでの経験則で、「因縁」「因果応報」といったものは実際“ある”と私は信じている。それが神、仏と呼ぶ存在によるものかわからないが、重力や磁力のような目には見えない不思議な力が確かにある。
2024.02.22
コメント(0)
-

「君の許には誰が来た?」 ~劇中のセリフから
【中古】 パッセンジャーズ(Blu-ray Disc)/アン・ハサウェイ,パトリック・ウィルソン,デヴィッド・モース,ロドリゴ・ガルシア(監督)元日に能登半島地震、2日には羽田空港で飛行機事故と、令和6年は大変な年明けとなった。今年は世界政治が大きく揺れる年と目され、その影響は当然日本にも及ぶ。この大きな災害と事故は先行きの不安を思わせる。羽田での事故では海保機乗員5名が亡くなった。地震での犠牲者とともにご冥福を祈りたい。旅客機乗員は全員無事とのことでなによりだった。このときの乗務員の冷静な行動が世界で称賛されたようだが、報道された映像を見るとなによりも衝突後の旅客機が姿勢を崩さずスムースに止まれたことが大きいだろう。『パッセンジャーズ』(2008、米・加)という映画を思い出し再見した。飛行機墜落事故後の生存者のカウンセリングをめぐるサスペンススリラーだ。興行成績が振るわなかったようだが、とても内容の濃い作品で私は何度も観ているお気に入り映画の一つである。主演のアン・ハサウェイ好きということもあるかな。最後に「ええっ!」と思わせられるネタがあるのでこの作品の妙味が詳しく書けないのだが、興行成績が振るわなかった理由について私が思うところを少し書いておこう。人の死後について、宗教の世界では天国(浄土)行き?⇔地獄行き?、科学的には何もない?哲学的には?-等々あるわけだが...「死後、親族など近しかった人がお迎えに来る」というのは、東洋的な(あるいは仏教的な)宗教感覚によるもので、キリスト教圏の人々には奇異に感じられることだろう。だが私はこの作品の世界観、雰囲気が好きだ。肉体の死後も「自分」が消滅することなく、異世界に存在し続けるということに安堵感を覚える。「人生はもう一つある」との儚い夢かもしれないが...
2024.01.29
コメント(0)
-

宗教団体の本質を知る~新約聖書のあるエピソードから
新約聖書は信者によって書かれたものであり、その内容には史実もあれば創作もある。口伝によって伝わるうちに最初の出来事が変容したり、想像や信仰により書き加えられたりしたのだ。また書き写しで複製されていた時代には、間違って書き写されたり、意図的に挿入がなされたりもした。原初の正確な出来事はほとんどわからないのである。しかし読んでると、これは本当のことが書かれてるのではないか-と思う記述に出くわす。その例の一つとして使徒行伝(使徒言行録)の第5章を挙げたい。ここには原始キリスト教会(エルサレム教会)の信者である夫婦が教会に献金をしようとしたエピソードが書かれている。夫婦は持っていた地所を売り、その一部を教会に献金しようとした。ところが教会指導者のペテロは、夫婦が売却益の全額を寄付しようとしなかったことを「神への冒涜だ」と叱責し、この夫婦はペテロとのその話の最中に突然死んでしまった(記述では夫妻別々に)というのである。この話をどう解釈するか?あくまで信者でない私の個人的解釈として書く。「教会は夫婦をその場で殺害し、その財産をすべて奪った」が史実だと思う。ユダヤの律法では、神への冒涜は死刑に値する。エルサレム教会は信仰共同体を形成しており、その生活は信者が拠出する資産によって成り立っていた。だが信者が増えるにつれ、その配給に滞りが生じていたことも使徒伝には書かれている。そのことが原因で信者グループ間に溝が生まれたことが窺われる。ヘブライ語を話す信者たち(元々のユダヤ在住者)⇔ギリシャ語を話す信者たち(邦外ユダヤ人、ディアスポラ)のことであり、このグルーブ間の溝はやがて対立関係になったものと私は想像している。ちなみに今日まで続くキリスト教(本流)の元は、ギリシャ語を話す信者たちの「キリスト信仰」である。ところで、安倍総理が凶弾に倒れた後、旧統一教会問題が起こりこれが政治問題に発展した。問題の根本は旧統一教会の霊感商法を用いた悪徳商法(教会側は否定)や信者を破産に追い込むほどの高額献金の要求だ。一般の常識感覚からすればかなり異様なことだし、なんで騙される?と素朴に思うのだが-。また宗教団体からのこうした非常識な献金要求は旧統一教会だけでなく、程度の差こそあれ他にもあるのだろうと思いたくもなる。ところが、先に記したように宗教団体によるこうした法外な献金要求は、2千年前の原始キリスト教会(正確にはユダヤ教の異端派、-ナザレ派)にもあったのだ。福音書にある他のいろいろなエピソードからも、イエス運動のグループ、ガリラヤ出身者のその集まりは、当時の民衆からは「かなり怪しい特殊な信仰集団(少数派)」と思われていたのではないだろうか。少なくとも、その信仰が広く一般化したのはパウロが布教活動をした時期のずっと後の時代である。最後の誘惑 [ ウィレム・デフォー ]
2023.12.25
コメント(0)
-

“The Last Generation” ~スタートレック:ピカード
スター・トレック:ピカード ファイナル・シーズン DVD-BOX [ パトリック・スチュワート ]ファイナルシーズンをようやくDVDで観た。今回の10エピソードは『新スタートレック』の主要クルー再集結による「TNG」シリーズの完結編といえる。可変種とボーグQの共謀により宇宙艦隊と惑星連邦が重大な危機を迎える。それをピカード提督はじめ再集結したTNGメンバーが中心になって解決する-というファンには堪らない趣向となっている。もちろんセブン・オブ・ナインやラファエラなど本作品からの主要メンバーも大活躍。とくに今回セブンは宇宙艦隊の次世代リーダーとしての位置付けがなされており、『ST:ヴォイジャー』を見てた頃にぼんやりとそれを想像してた私はびっくり。またセブン役のジェリ・ライアンはスタートレック向きの趣きがあり、この世界の絵によく映えるんだよな。制作側の企画意図による起用だけでなく、おそらく「セブンの艦隊士官姿を見たい」というファンの声が多く寄せられていたのだと思う。でも、今シーズンのキャラクターで私がもっとも心惹かれたのはU.S.Sタイタン-Aのリアム・ショウ艦長だ。視察名目でタイタンに乗り込んだピカードとライカ―に対し、ショウ艦長は不遜で無礼な態度をとる。実はこれには理由がある(ウルフ359の戦い)のだが、副長のハンセン中佐(セブン・オブ・ナイン)とも反りが合わない様子が描かれる。しかしピカードとライカ―はビバリー・クラッシャー救援のためウソをついてタイタンに乗り込んでおり、私事のために艦を使われるショウ艦長の方がいい迷惑を被っているのである。話ではしだいに可変種による艦隊乗っ取りの陰謀が判明し、双方はきちんと協力関係になる。そして終盤彼は殉職することになるのだが、大危機回避後のセブンの処遇場面で思わぬサプライズが用意されていた。ショウ艦長の本心の発露で、セブンは艦長に就任(大佐に昇進)することになる。サプライズはもう一つあった。ラストでなんとあの「Q(高次元生命体)」がジャック・クラッシャー(ピカードの息子)の前に突然現れ、「君の試練はいま始まったばかりだ」と告げるのだ。新シリーズを示唆した一場面と思われる。スタートレック・シリーズはいつまで続くんだ? トレッキーももう卒業したいところだが、こりゃ死ぬまで離れられないな。🙂※ コメント欄に「追記」あり
2023.12.17
コメント(1)
-

ブレインストーム ~ 臨死体験の真実とは...
ブレインストーム [ クリストファー・ウォーケン ]’80年代の主だったSF映画はだいたい観てるはずなのだが、この作品は知らなかった-それもそのはず。興行収益が大赤字の作品で、日本でも劇場公開はされたようだがテレビ放映はないと思う。たまたまYouTubeでこの作品が「未来を予言していたSF映画」として紹介されているのを見て、その内容に興味を引かれた。脳の情報を装置でアウトプット/インプットし、他者のそれを自身の脳で体験する-という研究が主題で、その成果を軍事利用しようとする政府機関とのトラブルがストーリーになっている。この研究はいまも続いているはずだが、近年ではむしろAIを人の脳に近づける技術開発のほうが先行しているようだ。観てみると、まあこれが残念至極のB級づくり。扱ってるテーマは高尚なのだが、脚本、場面の展開・流れ、全体の構成といろいろ粗が目立ち完成度が低いんだな。監督は『2001年宇宙の旅』のSFXを手掛けたダグラス・トランブルという人なのだが、この人は総合クリエイターとしての監督業は不向きだったのかもしれない。S・キューブリックやJ・キャメロンといった大作作りに定評のある大監督であれば、素材のよさを活かして大ヒット作品に仕上げることができたかも。作品のハイライトは、ラストでの臨死体験の映像だ。主任研究員のリリアン・レイノルズは持病の発作により作業中に急死するのだが、今わの際懸命にブレインストームを起動し、自身の「死」の瞬間を記録に留めたのだった。「臨死体験」は本当にあるのか、単に身体の物理的死の最後に見る夢-脳内現象なのか、年齢を重ねてその時が近づくにつれ益々気になってくる。これを臨床医学と理論物理学の立場から研究している人たちがいる。量子論からのアプローチだ。彼らによる仮説があるのだが、それは驚くべものだ。彼らによれば、残るのは量子データとしての記憶で“自我(意識)”ではない-ということのようだが、どうなんだろう...お釈迦様の答えは明快だ-「わからないことは考えるな」!
2023.11.30
コメント(0)
-

サイレンススズカ ~世界一の快足馬 🐎
もう秋の天皇賞か...毎年このレースが来ると必ず思い出す馬がある。サイレンススズカ(武豊騎手騎乗)だ。’90年代に競馬ファンだった人なら、この馬をよく覚えているだろう。天皇賞(秋)の大一番で悲劇に見舞われた名馬である。あの時ファンの関心は出走馬の“勝ち負け”にはなく、この馬が勝つのは当たり前で、みなの関心は世界レコードになるであろうその「勝ちタイム」にあった。ところが、結果は全国競馬ファンが唖然とする故障による競走中止であった。あの結果には驚いたが、改めてしみじみとわかったのは「これが競馬なんだなぁ」ということ。どんなに精度の高い予想をしても(したと思っても)、結果は事前にはわからない。未来に起こることはわからないのだ。このレースは私に競馬の本質を教えてくれた一戦だった。これは人生にも言えること。10年、20年、30年先の自分の身に起きることは決して事前にわからない。若い頃の自分は、壮年期に至った「今の自分のあり様、状況」を予想などしていなかった。心身ともに健全な自分がそのまま続くと思い込んでいて、病苦に苛まれる日々など想像もしていなかったのだ。競走馬はある意味哀しい生き物である。人の都合によって生産され、人の経済活動のために生き、そして商用価値がなくなると人の手によって命を絶たれる。「そんなこと考えるなら競馬などやるな」と言われそうだが、不思議なことにやめることができない。馬券もあるけど、やっぱり名馬がターフを疾走して鮮やかに勝つ雄姿を見たいと思ってしまう。生き物にも「魂」があるなら、サイレンススズカは今なにを思う...【中古】 サイレンススズカ スピードの向こう側へ…/(競馬) 【中古】afb
2023.10.28
コメント(0)
-

イカレテイルのは、アル中の機長だけか?
フライト【Blu-ray】 [ デンゼル・ワシントン ](2012年、アメリカ、ロバート・ゼメキス監督)テレビ地上波で放送されたので久々に観た。デンゼル・ワシントンが、酔っぱらったままフライト業務に就くロクデナシな機長を演じているのだが、ラストの公聴会シーンではやはり魅せてくれる。この人の演技、表情には妙に惹きつけられるところがあって、凡庸な作品でも彼が出演していれば自然と画面に引き付けられてしまう。この作品も彼が主役でなかったら、“アルコール依存症”を扱った平凡な作品の評価になっただろう。この作品、外形的にはアルコール依存症を扱っているのだが、その内に「キリスト教信仰の復興(への期待)」を全編に織り込んだのが特色だ。飛行機が不時着したのがペンテコステ派の教会地だし、副操縦士夫妻は敬虔な信者だった。そして、何といってもラストの公聴会。事故調査委員会のエレン・ブロック(メリッサ・レオ)による巧妙な質問に窮したウィップ(機長、D・ワシントン)は、思わず「神よ、お力を」とつぶやいてしまう。それまで酒に関して嘘をつき続けてきた彼も、神にまではウソをつけなかったのだ。もっとも、神の御業はすでにその前夜から始まっていた。宿泊しているホテルの部屋で彼は禁じられていたはずの酒に手を出してしまったのだ。しかしそれは、その後ウィップが改心し復権する機会が与えられるためであった。かつて私もアルコール依存症になりかけた時期があった。だからウィップや二コール(薬物依存症の女性)の心裏は少しわかるところがある。強いストレスや葛藤、憤まんを酒(あるいはクスリ)の力で解消しようとするのだ。傍から見れば愚かなことだが、本人は理屈でそれがわかっていても、なかなかその愚行をやめることができない。そして、どっぷりと浸かったその泥沼から抜け出そうとするとき、たいていは大きな代償を払うことになる。私もそうだった...酒を飲んで仕事をするなんて許されるはずがない。まして人の命を預かる仕事なら、一生の自由を奪われても仕方のない重罪だろう。だがこの現代社会には、どこか人に道を誤らせる重苦しい空気に満たされた部分がないだろうか。そうした空気が年々広がっていないだろうか。酒やクスリへの依存に限らず、行方不明になる、自殺する、“誰でもよかった”型の凶行に走る等々、自身の内なる迷宮から逃れようともがく人々は年々増加しているのだ。この映画でも、イカレテイルのはウィップだけではない。航空会社やパイロットの組合は自らの保身のために、酒を飲んでフライトに臨んだ機長の罪を隠蔽しようと運動する。この映画が描くのは、そうした現代社会の歪み、「常識」が常識でなくなってしまう怪しい空気の広がりへの危機感だと思う。
2023.09.26
コメント(0)
-

百田・有本の方舟、は真日本再生の<はじまり>となるか 🤔
作家の百田尚樹氏とジャーナリストの有本香さんが政治団体(新党)の起ち上げを進めている。すでにSNS「X」上にそのアカウント(「百田新党(仮)」)ができ、情報発信がはじまっている。新党の発足日も10月17日(火)と発表された。お二人はDHCテレビの「虎ノ門ニュース」終了後YouTubeで「あさ8」というニュース解説配信番組を続けているが、6月に同番組内で新党の起ち上げを宣言していた。安倍総理亡きあとの岸田政治の変節(急なリベラル寄り)ぶりにお二人は厳しい批判の声をあげ続けてきたなかで、直接のキッカケになったのは与党(政権)が拙速かつ強引に成立させた「LGBT法」にあったようだ。宣言後有本さんは、「新党設立は百田さんの唐突な思いつきによるもので、あまりにも無謀な試み」と不安を滲ませていたが、何とか進水式まで来れたようだ。しかしこの方舟、真日本再生のはじまりとなるのかどうか...私も大いに応援する。が、正直期待は大きくない。これまでも保守新党はいろいろ起ち上げられてきた。しかしそれが安定した政治勢力として定着した例はない。最近登場した参政党も、ここにきて内紛があったようで早くもガタつきが出ており先は不透明だ。そうしたこれまでの結果を思うと、百田・有本両氏にどれだけ人気があっても、先に行ってお二人が活動から離れれば“集まり”は霧消するのではないかと危惧している。「あさ8」にゲスト出演している政治学者の岩田温氏も、自身が「次世代の党(日本のこころ)」に関わった経験から保守新党の存続維持の困難さを自身の配信番組でしっかりと語っていた。「あさ8」のなかで有本さんは“この試み”の困難さを十分自覚しながらも、長い先の希望を語っていた。お二人の気持ち、危機意識はよくわかるし、その意気込みに共感して活動を支援し手伝う人も少なからずあり、応援するファンも多いことだろう。が、現実の政治は熾烈な権力闘争で、真摯な理念や情熱がそのまま通用する世界ではない。お二人が本気でこの運動を現実の政治に影響力を及ぼす勢力にし、その勢力を安定的に維持したいなら、団体を組織政党(例:共産党、公明党)として構築したらどうだろうか。個々の自由が制限され息苦しさを感じるかもしれないが、組織の維持と議員確保は安定的となり、運動体の短期での消滅は避けられるのではないだろうか。ところで、この百田新党の<はじまり>は、細川護熙さんが政治改革を掲げて’92年に起こした日本新党のそれを思い起こさせる。雰囲気がよく似てる。あの時は自民党を離れた小沢一郎さんらのグループを核に非自民政権(短期で終わったが)ができて驚愕した。百田・有本両氏に小沢さんのようなプロ業を期待するのは無理なのだが、あれから30年、百田新党は政治にどれだけインパクトを与えられるだろうか。「日本国紀」の副読本 学校が教えない日本史 (産経セレクト) [ 百田尚樹 ]
2023.09.05
コメント(0)
-

ヴァンゼー会議 ~ ホロコーストの決定 💀
ヒトラーのための虐殺会議 Blu-ray&DVD【Blu-ray】 [ フィリップ・ホフマイヤー ]「ヴァンゼー会議」は第2次大戦中の1942年1月20日にドイツの高官らがヴァン湖畔の別荘に集まり、ユダヤ人の移送と殺害について分担と連携を討議した会議だ。ナチスは会議以前から占領地の東欧やソ連において組織的なユダヤ人虐殺を行なっていたが、この会議においてその「最終的解決(ホロコースト)」が決まった。それにしても、欧州すべてのユダヤ人、その数約1100万人を消滅させようとはあまりにもクレイジーな計画だ。すでにアメリカが参戦し、ソ連との戦いも先行きが怪しい状況で、政府・軍高官いずれにも「これ、今やることかよ?」と思った者が少なからずいたはずだ。この会議においても文民高官には異論を呈する者がいて、特に内務省次官のヴィルヘルム・シュトゥッカートは議長のラインハルト・ハイドリヒ(親衛隊大将)に強く抵抗した。彼は法律家(博士)だからこの「最終的解決」の危うさとともに、戦争と政権の行方も冷静に考えてた部分があったことだろう。ユダヤ人は欧州どこでも嫌われ、迫害されてきた歴史がある。異民族の流入、自国の多民族化は困難な問題を惹き起こす大きな要因なのだ。いま日本は政府によってこれが進められている。少子化、労働力不足を理由(口実)に事実上の移民制が着々と進んでいる。他民族との共生は簡単なことではない。言葉の問題もさりながら、生活習慣や宗教(文化)の違いに起因して地域社会に深刻な亀裂、歪みをもたらし得る。平時においては些細な諍いでも、深刻な有事となればその問題はたちまち社会に顕在化し、悲惨な内紛、ナチス独の蛮行のようなことになりかねない。先ごろ斎藤法務大臣が「国内不法在留者のうち日本生まれの18歳未満の者について、法務大臣裁量による『特別在留許可』を与える」方針を発表した。一定の条件があるが、子だけでなくその親の在留も認められることになる。これはつまり、親の不正入国(定住目的の侵入)や不法在留の罪を問わない-ということだ。すでにSNS上で多々指摘されているが、これは危険な決定である。政府は「今回だけの措置」などと言ってるが、わが国の政治・行政において“前例がある”は大きな力をもつ。この措置は前途において繰返し踏襲されるだろう。そして戸籍取得における生地主義(⇔血統主義)への転換にもつながりかねない要因をも孕んでいる。いまわが国の施政は重大な分水嶺にあるのだ。
2023.08.11
コメント(0)
-

LGBT法は、世界に再び“魔女狩り”を惹き起こす 😱
ベネデッタ 豪華版【Blu-ray】 [ ポール・ヴァーホーベン ]『ベネデッタ』は17世紀の修道院(イタリア、ペーシャ)を舞台とした映画だ。修道院に預けられた少女が修道女として大人になり、彼女に起きた聖痕騒ぎ(真偽不明)をめぐる大騒動が話の本筋。庶民が窺い知ることのできない聖域の秘部も扱っているのだが、全体として宗教改革後に教会の権威が薄れていく中世から近世への欧州社会の変容をよく映している。キリスト教会は過去長く欧州社会を支配した。ローマ帝国によって公認され国教となったことがその土台になっている。しかし宗教団体が強大な力をもち社会を支配することは、とてつもなく危険なことなのだ。納得のいかないことを、権力と権威によって強制されることがどれだけ社会を歪めるか、歴史をよく学んだ者なら誰でも知っているはずだ。暗黒の時代と言われた欧州中世のような不気味な空気が、いま静かに日本社会に醸成されはじめている。今年の通常国会終盤で成立してしまったLGBT理解増進法(正式名「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」)のことだ。この性の解放、自由化の波は自由主義世界で大きくなりつつあり、厄介な運動となっている。すでに良識ある識者らからこの運動が共産主義の変異体(亜種)であるとの指摘があり、これが既存の社会秩序を崩壊させるためのある種政治活動であるのは明らかだ。彼らはそのために無制限の「人権」を盾にする。レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダーに関する国民の理解増進は、法律によって国民に強制される。しかもそれは義務教育から行われ、自治体のプログラムによって地域社会で推進されるのだ。先日TGである経済産業省職員の女子トイレ使用(省舎内)をめぐり、最高裁は上告した当該職員の主張を認める判決を出した。この判決の社会全体への影響は必至であり“その流れ”は確実に強まっている。すでに司法まで洗脳される(私観)という異様な事態なのである。私は予言する。この流れはやがて中世さながらの“魔女狩り”を惹き起こすことになる。
2023.07.17
コメント(0)
-

LGB・T理解増進法に怒る 😡
今年の通常国会終盤でとんでもない議員立法が成立してしまった。LGBT理解増進法(正式名「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」)だ。レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダーに関する国民の理解増進を、法律をつくって国を挙げてやるというのだから呆れる。しかもこれは義務教育から行われ、自治体のプログラムによって地域社会で推進される。小学生に対して同性愛や性自認を理解させるなんてバカげてるし、それは教育ではなく刷り込み、洗脳だろうと私は思う。もうSNSではさんざん批判されていることだが、これは明らかに反体制派(左派)による国体変容のための策略だ。ようするに男女の別を無くそうとする謀であり、その波はやがて皇室にまで及ぶ恐れがある。この呆れた、そして恐るべき謀を見て、思い出した映画先品がある。J・カーペンター監督の『ゼイリブ』(1988、米)だ。人間になりすましたエイリアンが街に平然と暮らし、人間を洗脳・支配・搾取し、人類を衰退させてゆくSF映画。大量消費社会や一方向の情報照射(テレビ)を痛烈に批判してもいる。観ようによっては、劇中のエイリアンは資本家(市場原理主義者)や政治指導者など社会の支配者階級にそのままなぞらえることもできる。そして、エイリアンと手を組み、彼らに味方する連中は金(カネ)で己の魂を売った中産階級だ。カーペンター監督の作品はどれも優れているが、この作品はH・G・ウェルズ級の着想で特に傑作だ。ゼイリブ [ ロディ・パイパー ]私にはLGB・Tに対する偏見はない。個人の嗜好で好きに生きればいい。だが、それを政府が特に保護し特権を与えるかのごとき政策を施行するなら、それには断固反対する。7月は流れたが、この先衆院の解散・総選挙がおそらく行われるだろう。こんな法律を拙速かつ強引に成立させた自民党には再びお灸を据えなければならない。
2023.07.05
コメント(0)
-

『街の灯』~名画を観る
街の灯 City Lights【Blu-ray】 [ ヴァージニア・チェリル ]AFI(American Film Institute)の11位(2007年)にあるこの名作を、ようやくの初鑑賞。この作品には音楽と効果音があるものの、やはりサイレントは観るのに根気がいる。放浪者と盲目の花売り娘、あの二人の出会いと再会の場面がなんといってもハイライトですよねぇ。ラストの再会後あの二人はどうなったのか気になってしまうわけだけど、実はそれはどうでもいいのだろうと思う。なぜなら、この映画の真のテーマはあの二人のラブロマンスではないから。この映画が製作された時代、アメリカは株の大暴落(「暗黒の木曜日」)を契機とする世界恐慌に襲われていた。労働者や失業者による暴動が頻発するなど、ひどく不安な社会状況にあったのだ。ところが、そんな状況下でも富裕層は日々レストランでの飽食やパーティーに興じて豪奢な暮らしを送っている様子が作品で描かれている。富はいつの時代にあっても偏在しているのだ。今のアメリカでも「1%の富裕層が国富の99%を独占している」などと言われたりする。娘は姿の見えぬ紳士(実は放浪者)からの大金によって貧困を脱し、目に光も得られたが、その大金は彼自身のカネではなかった。それは、にわかに彼の友人となった富豪の金だったのだ。チャップリンはこの後共産主義者の疑いをかけられアメリカを追放されるが、当時の為政者には、少なくともかなりの体制批判者に見えたのでしょうねぇ...ところで、チャップリンの作品にはコントのルーツがいっぱい。放浪者と富豪が波止場で互いに助けようとして海中に落ちるシーンや、パーティーで泥酔した放浪者が足腰が崩れて立てない演技などは、亡くなった志村けんさんがあのヒット番組『だいじょうぶだぁ』のなかでよく使っていた。志村さん、天国でチャップリンに会ってコント談議に花を咲かせてるといいなぁ。
2023.06.26
コメント(0)
-

不法在留外国人は増え続けている~入管難民法改正について
通常国会で「入管難民法改正案」が審議されている。すでに衆議院は通過し、いまは参議院での審理が続いている。現行の入管難民法には問題点が少なからずあり、現在わが国が抱える不法在留外国人の問題に適切に対処できないからだ。この法案は菅内閣において国会提出され成立がなされるはずだった。ところがある一件がもとで法案の成立が断念された経緯がある。2021年3月に名古屋出入国在留管理局の施設で亡くなったスリランカ人女性の件だ。左派野党と支援団体などがこの件を強く訴え抵抗し、また政府・与党側も国政選挙を意識したことなどから法案成立はならなかった。いまこの改正案をめぐって一部野党や支援団体らが再び反対運動を続けている。その前面に掲げるのは、やはり亡くなったスリランカ人女性の悲劇だ。反対運動には故人の遺族も参加している。しかし、スリランカ人女性の死には入管側の対応だけにすべて責任があるとは思われず、故人にも相応の責任があったと考えられるので、ここで再びこの件の概要を示しておきたい。-------亡くなったのはウィシュマ・サンダマリさん(当時33歳)で、2017年に留学生として来日した。来日後日本語学校に通っていたというのだが、なぜかその学校を1年足らずでやめ、交際相手のスリランカ人男性とともに静岡県の三島市に移り同棲していたという。このスリランカ人男性は質の悪い人物のようで、ウィシュマさんは男性から暴力を受けていたようだ。そして彼女の在留期限が2020年8月に切れ、彼女が生活費の半分を負担できなくなると、男性は彼女をアパートから追い出したのだという。行き場を失った彼女はやむなく交番に駆け込んだのだが、不法残留の疑いで逮捕され入管施設に収容された。遺族の支援者側は(実質的に)「入管職員による業務上過失致死」の疑いを主張し、これに野党側政党(の一部)が同調して国会でこの件を問題視した。しかしあり様は、団体等による“人権”を盾にした政治運動の面が強く、野党側政党(の一部)は「入管法改正」を阻止するためにこの件を狡猾に政治利用していたように見えた。なぜなら、彼らはウィシュマさんの「大人としての個人の責任」と「法治国家における秩序維持」という点についてはまったくスルーし、留学生として来日した彼女が目的を逸脱し不法残留者となった事実には触れなかったからだ(今も同じ)。彼女は教養のある人だったはずだから、自身の行動を客観的に見れなかったはずはない。「入管職員が見殺しにした」かのごとき訴えは、人権活動団体側にとって都合のいい、あまりにも一方的な物言いではないか。私はこの件に関してNHKとTBSで放送された特集番組を見た。来日する前の生前の彼女の写真が多く映され、単独や家族と映ったものなどあったが、妹さんたちと一緒に映っているものを見ると、妹さんたちと比較して彼女は明らかに痩せていた。テレビ番組の構成で彼女が入管施設に来てから急激に痩せたような印象をもたせる点には、やや疑念がある。それと、私はウィシュマさんの留学来日自体にも疑いを抱いている。彼女はなぜ勉学を放棄して、質の悪いスリランカ人男性と逃避行したのか?これは憶測だが、もしかしたら彼女と男性とは来日前から親しい関係(ネット、SNSで)にあり、来日は男性に会うことがその目的だったのではないか。“留学”はそのための方便だったのではないのか?亡くなったこと自体は痛ましいことと思う。しかし、彼女の来日後の足跡には疑いをもたれてもしかたのない面がある。移民難民ドイツ・ヨーロッパの現実2011-2019 世界一安全で親切な国日本がEUの轍を踏まないために [ 川口マーン惠美 ]
2023.05.24
コメント(0)
-

ヤノマミの暮らしを真似することはできないが...
NHK DVD::ヤノマミ ~奥アマゾン・原初の森に生きる~ [ 国分拓 ]ヤノマミ族はアマゾンの熱帯雨林に居住している南米の先住民族の一部族だ。狩猟と採集を主な生活手段にしている。NHKで放送された取材番組を見たことを思い出し、その劇場版DVDを借りてみた。こうした映像を見てよく思うことは、もし我々の生活で化石燃料が無くなったら、原子力も然るべき理由でまったく使えないとしたら、我々はかつての自給自足的生活にどれだけ耐えられるだろうか?ということ。食料生産の量はかなり限られるから、水資源など恵まれた土地をもっている地域はそこを閉ざして余所者の出入りを厳しく制限するだろう。適宜分け合うことが必要になるのだが、人間はなかなかそれができない。そのことは今の日常生活でも同じだ。人類の抱える多くの問題の根源は、ほとんど人口の爆発的増加に帰着する。世界人口はなんらかの形で管理されなければならないと私は考えるが、とてもできそうにない。ヤノマミには新生児の生死(生存)をその母親が決めるという風習がある。生まれた子が<精霊>か<人>かの判断によるというのだが、これはいわゆる“間引き”だろう。森の資源は限られている。集落の適正人口を保つために、彼らの先祖が古い時代に決めたルールと思う。これはそう遠くない過去の時代まで、日本でも地方地域などにあったと聞いている。ヤノマミの人々の生活を見れば、都市社会の一部の人々が絶対視する「人権」という概念も、実は相対的なものだとわかる。もし先に挙げたような危機が本当に訪れた場合、世界社会はそれをどう解決しようとするか?歴史を振り返れば、その手段に「戦争」が選ばれる可能性は高い。我々がヤノマミの人々の暮らしを真似することなどできないが、なんでも文明の利器頼みという生活は改めるところがあるのではないだろうか。資源を利用した文明生活は大きな脆弱性を抱えているのだ。電気を使わずにできることは、使わずににやればいいと思う。私は来るべき超先進国の姿が、科学・技術の粋を極めたデジタル社会だとは思っていない。
2023.05.08
コメント(0)
-
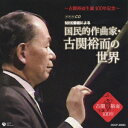
「国民的作曲家・古関裕而の世界」~NHKのラジオ番組から
NHKのラジオ番組に『ひるのいこい』というのがある。1952年(昭和27年)から続く長寿番組だ。もうだいぶ前からテレビ視聴を離れて、いまはラジオ聴きが多いのだが、正午の時間帯はあまり聴いていなかった。昼食時にはテレビのニュース番組を視聴していたからだ。しかし昼のニュースもラジオ聴きとなり、ニュースに続く番組『ひるのいこい』に出会った。リスナーからの地域便りなど紹介し、その合間に音楽をかけるという構成で高齢者向けの落ち着いた内容だ。私が惹かれたのはそのテーマ曲。荘厳な出だしから始まり、昔の時代劇映画のBGMを思わせる名調子風リズムなどバラエティーに富んでいるのだが、語りの裏で流される数曲がじつに心地よいのだ。日本の原風景を思い起こさせるその曲調に’70年代の空気感を感じ、懐かしさこの上ない。聴きながら、作曲者は冨田勲さんかなと思ったのだが、古関裕而さんだった。古関裕而さんというと、私はテレビの音楽番組『オールスター家族対抗歌合戦』(フジ系、1972年~)の審査員をしていたことを覚えているくらいだった。少し経歴を見ると、戦前~戦後を通してなんと5千にも及ぶとされる曲をつくった大作曲家。NHKにも多くの番組に楽曲を提供している。興に乗って古関さんの音楽をレンタルCDで聴いてみた。『NHK番組による「国民的作曲家・古関裕而の世界」』というタイトルだ。童謡、ドラマのBGM、スポーツ番組のテーマ曲などのオムニバス版なのだが、さすがに時代のちがいもあって『ひるのいこい』のテーマ曲以外は楽しめなかった。クラシック版のほうがよかったかな。古関裕而さんは明治42年(1909年)のお生まれで、平成元年(1989年)に亡くなられた。昭和の時代をまるまる生きられたわけで、その間ずっと作曲に携わった生涯だから、日本の近代化を文化の面で進めた功労者といっていいだろう。古関さんのメロディー、楽曲のアレンジには昭和の空気、香りが満ちている。昭和時代後期に多感な時期を過ごした者としては、原日本の郷愁感に浸らずにはいられない。また古関さんは福島県のご出身であったということで、両親が福島県出身である私も、どこか親しみ近しさを覚えるところがある。~古関裕而生誕 100年記念~ NHK番組による 国民的作曲家・古関裕而の世界 [ (オムニバス) ]
2023.04.28
コメント(0)
-

小西怪文書騒ぎの総括~高市大臣が正義の圧勝 🕊
3月の国会参議院で、小西洋之議員による<総務省怪文書>質疑が世間を騒がせた。立憲民主党の小西議員一派は高市早苗大臣を辞任に追い込もうと図ったが、結果は高市さんの正義の圧勝。小西議員は独自に手に入れた総務省の内部文書(約8年前の高市総務大臣時代の記録)を材料に高市大臣に辞任を迫った。その「文書」は確かに総務省の行政文書ではあるのだが、高市大臣は当初から「自分や安倍総理にかかる部分(4枚)は捏造である」旨きっぱりと主張していた。総務省もその「文書」をホームページ上で公開したが、確かに「作成者不明、日時不明、配布先不明」など怪しい点がいくつもあるのだ。もっとも、文書内容のメインはむしろ当時の礒崎総理補佐官が放送法の解釈について、総務省に圧力をかけたのではないか?の方なのだが、立憲の議員たちは高市大臣の答弁のなかから「捏造」発言と杉尾秀哉議員に向けた「質問しないでください」発言だけを捉えて、予算委員会で高市さんに対して幼稚な侮蔑質疑を執拗に続けた。が、そもそも小西があの「文書」を総務省から入手した経緯(不明)が問題だし、後に高市大臣が答弁で明らかにするのだが「高市大臣にかかる文書」は職員によって<創作>を差し込まれた可能性が高い(高市さんは総務省職員への聞き取りによる裏づけがあると明言した)。この騒ぎでは小西の児戯がいくつもあるが、最初のしくじりはあの「内部文書」をSNSに上げてしまったことだ。あの「文書」は公務員(正職員、行政職)またそのOBが見れば、それがどういう性格のものであるかはすぐにわかる。あの時点で、国民のなかの一定の人々には高市大臣の答弁の正しさはすでにわかっていた。そしてその後質疑で判明するが、その当該「文書」が総務省の<行政文書ファイル管理簿>に載っていなかった-というのは決定的で、その時点で立民党小西一派の姑息な思惑、企みは破綻した。のに、その後も質疑でみっともない「高市降ろし」を唱え続けた立憲民主党議員の幼稚さには呆れかえってしまった。それにしても、いくら令和5年度予算が実質決まっているからとはいえ、参議院でこんなワイドショー質疑するかね?一日約3億円かかると言われる国会を、大臣潰しや選挙対策のパフォーマンスを目的にあんな怪文書を使って利用するなんて、立憲民主党は政党としてレベルが低すぎる。主演の小西議員を参議院懲罰委員会にかけたいくらいだ。それに、小西に協力した杉尾に福山、その手先として高市さんに汚い侮蔑質疑を浴びせた立憲民主党のスケバン議員たちを許せん。あの魔女ども、いつか十字架に括り付けてやる。美しく、強く、成長する国へーー私の「日本経済強靱化計画」-- (WAC BUNKO) [ 高市 早苗 ]
2023.04.06
コメント(0)
-

「鵺(ぬえ)の鳴く夜は恐ろしい...」😱
【中古】 悪霊島/鹿賀丈史 【中古】afb俳優の吉岡秀隆がテレビドラマで再び“金田一耕助”を演じる(「犬神家の一族」)-と芸能ニュースで報じられた。なつかしさが高じて昔の作品を観たくなり、『悪霊島』(1981、角川映画)を選んだ。金田一耕助を鹿賀丈史が演じている。この作品では、なんといっても岩下志麻さんの怪演がみごと。魔女のイメージが似合う彼女には、巴御寮人(ふぶき)役はうってつけ。一方、金田一役の鹿賀さんはちょっとパッとしない。とくにあのカツラ。まるでクリスタルキング(音楽バンド)の田中(ボーカル)みたい。やっぱり金田一耕助役は石坂浩二さんのイメージがいい。それと、市川崑監督のこのシリーズへの味付けが私は好きだ。金田一探偵もそうだけど、等々力警部(「よし、わかった!」のセリフでお馴染み)のあのキャラクターね。適度なユーモアとコメディのスパイスを効かせて、不気味で陰鬱な話にほどよい安堵感を与えている。比べてこちらの篠田監督作『悪霊島』は、大人向けのシリアスな味付けになっており、起用された俳優陣も(いい意味で)灰汁の強いメンバーがそろっている。ところで、再見前この映画で私がもっとも印象に残っていたのは、ビートルズの楽曲が挿入歌に使われたことだった。「Let It Be」と「Get Back」なのだが、とくにエンディングに使われる「Let It Be」は印象度抜群で、この映画のイメージそのものだった。ところが、レンタルのDVD版では楽曲の使用権が切れたため別歌手によるカバー版に変更されている。ソウルタッチの歌なのだが、だいぶ違和感がある。これならシンフォニックなインストゥルメンタルのほうがよかったかも。私は原作である小説はまったく読んでおらず、映画やテレビドラマだけを観ているのだが、この金田一耕助シリーズの土台にあるものはよくわかる。それは、地方の小村や離島で暮らす人々の閉鎖性や息苦しさだ。この作品のなかでも、島の最高権力者である刑部大善(佐分利信)が新時代の価値観である“自由”や“解放”をひどく侮蔑するセリフがある。これは歴史や伝統を守りたいとの怒りなのだが、反面そのために悪事をもその手段にする独善でもある。そこら辺が、横溝正史が好んだ推理サスペンスものの妙味なのだろう。
2023.01.23
コメント(0)
-

「弱さ」こそが強さ、「わたしは弱いときにこそ、強い」🎄
パウロ 愛と赦しの物語【Blu-ray】 [ オリヴィエ・マルティネス ]新約聖書の『使徒伝』と「書簡」、また伝承を基に、獄中のローマで最後を迎えるパウロとその彼を見とどけるルカを描いた作品。凡庸なドラマになっているのではないかと思っていたが、なかなかよくできている。『使徒伝』が獄中での聞き取りにより書かれたというのはいいアイデアだし、牢獄でのパウロとマウリティウス(牢獄管理者)の対話や娘の病に絡むエピソードもストーリーに感動を与える。またパウロとルカ役にもイメージに沿ったよい俳優を充てている。パウロの思想、いわゆる「十字架の神学」というのは理解するのがけっこう難しいものだと思うが、この作品ではそれをドラマ全体としてうまく伝えてる感じ。聖書学者青野太潮氏の『パウロ~十字架の使徒』を読んだが、氏はそのなかでパウロによる“十字架の逆説”を説いておられる。それは、「弱さこそが強さ」「愚かさこそが賢さ」「躓きこそが救い」そして「呪いこそが祝福」というように、パウロはイエスの「十字架」を逆説的な意味で肯定的に捉え直したとのこと。劇中パウロはマウリティウスにこう言っている。「私が誇れるのは“弱さ”だけ」「だからこそ、神の力が私の内に宿っている」と...現代まで続くキリスト教会本流の源はパウロにあるわけだが、この作品はその信仰の本質をコンパクトに伝えている。ところで、私は『使徒伝』やパウロの「書簡」を読んでいて、奇異なことを考えることがある。それは、パウロとサウロはほんとうに同一人物なのか?ということ。ダマスカスへの途上でサウロがキリストと邂逅した(「目から鱗」のエピソード)というのは、ルカによる創作(学者によると)らしいし、「書簡」には地上のイエスの言行についてほとんど言及がない。パウロの信仰は「十字架につけられた(ままの)イエス」から始まっているのだ。いったいサウロはなにをもって真逆の立場に転じたのか...パウロの「書簡」を読んでいると、これを書いた人物は十字架にかけられたイエスをその場(ゴルゴタ)で直接見ていた人なのではないか、と私には思われてならない。その人物とは...ステファノの敵であるサウロはダマスカスへの途上で殺された。その後ヘレニストの一人がサウロになりすまし、パウロと名乗ってローマ市民権を利用して小アジアからギリシャ方面へと大伝道を行った。それが私の想像(妄想?)だ。それにしても、ローマ帝国は信徒を猛獣に食わせたり、油をかけて街路で焼き松明の代わりにするとは、まさに悪魔の所業。私は、人間には神の子とサタンの子の両方がいると信じている。その違いはDNAによる血脈や生後の環境によるものとはちがうと思われるのだ。その本質は人の性格や気質の土台あるいは核となっているもので、一方のルーツは欲や誘惑にとらわれないもの、清冽な水や光の輝きにも似た原初のなにかだ。
2022.12.24
コメント(0)
-

スタートレック:ピカード シーズン2
スター・トレック:ピカード シーズン2 DVD-BOX [ パトリック・スチュワート ]このシリーズ、シーズン1はピカードとデータ(アンドロイド)の友情が話の軸になっているのだが、シーズン2では「Q(高次元生命体)」との友情が核になっている。シーズン3も旧メンバーなど誰かとの友情がエピソードの中心に置かれるのかな。今回の最大の目玉はボーグクィーンを登場させ、ボーグと惑星連邦との新たな関係を見せたことだ。「そうくるか!」との意外感があった。ボーグクィーンが単独で連邦との融和策をとるはずはないのだが、そこは「なるほど」と思わせる工夫が施されていた。やはりスタトレの製作は緻密で抜かりがない。ところが妙な場面もあった。ラ・シレーナ号のリオス船長が宇宙艦隊に復職しU.S.S.スターゲイザーの艦長に就いているのだが、なんともみあげ・アゴヒゲありのモジャモジャ顔のままで、しかも艦のブリッジで葉巻を吸いながら指揮を執っているのだ。規律を重んじる艦隊でこれはありえない。なぜリオス艦長だけ認められた?と不自然きわまりない。シーズン1でも、ピカードは死後に人工の有機性肉体に意識を移され再生するのだが、このときの“つなぎ”がなんか変だった。シーズン3の公開は2月だから撮影はほぼ終えてるはずだが、ピカード役のパトリック・スチュワートは82歳の高齢だ。シリーズ継続中に病気などでその人生に危機が訪れることも心配されたはず。もしかしたら製作陣はそのような場合に備えて、シリーズを中途で終えなければならないとき用に別の「ファイナルエピソード」を早期に撮影してあるのかもしれない。たとえば、エピソードのすべては「(生身の)ピカードが死ぬ間際に見た夢だった」とかね。“妙な場面”があるのはそのため?などと思ったりしてるのだが...
2022.12.16
コメント(0)
-

「忠臣蔵」の決算書!
決算!忠臣蔵 [ 堤真一 ]「忠臣蔵」の映画化も、時代とともにずいぶんと様変わりしたなぁとの感想。これは赤穂浪士の討ち入り劇をその資金面から描いたもので、山本博文著『「忠臣蔵」の決算書』の映画化だ。原作の著書は史料の解説を中心とした堅い内容なのだろうが、この映画化ではお笑い芸人を多く起用してコミカルなコメディ調の作品に仕上げている。「忠臣蔵」の内容が大部分創作で、江戸城での刃傷事件の原因や大石らが吉良邸に討ち入りした動機についても、実はその史実がわかっていないことは今ではだいぶ知られていることと思う。近年は、義士のなかで唯一生き残った寺坂吉右衛門の討ち入り後の行動がドラマなどで描かれ、忠臣による仇討劇として長く楽しまれてきた「忠臣蔵」もその史実にいろいろな形でのアプローチがなされている。この作品もその流れに沿ったドキュメンタリー風「忠臣蔵」だ。前半はおもしろおかしく楽しめたのだが、後半に入ると飽きてしまった。ドラマとして楽しむには、やはり悪役キャラとしての吉良や彼による陰湿なパワハラが必要なのだ。それが前段にあるからこそ、後半の赤穂浪士による仇討劇がおもしろい。「忠臣蔵」は事件にかかる江戸庶民の噂話や作者の逞しい想像によって作られたものだが、現代なら世界中で大ヒットした大作映画のようなエンターテインメントだったのだろう。見どころは“お家”のなかの武士の色分けかな。番方(いくさ担当)⇔役方(実務担当)、体育会系⇔文科系、営業⇔事務と、この人種の違いにも感じられる大別実態は昔から今日まで連綿と続いている。大事を成すには大金が必要。だがお金だけではダメで、体力知力もまた同等に重要。「番方⇔役方」はクルマの両輪であって、そのどちらが欠けても事は成就しない。近代戦争でいえば、これは武力と外交だ。帝国日本の大戦敗北には、その大きな要因として外交を軽視したということがある...とまあ、こんなことをツラツラ考えてしまうようでは、この映画は時代劇としての本分いかにということだろうか。
2022.12.14
コメント(0)
-

赤い闇、スターリンの冷たい大地で
赤い闇 スターリンの冷たい大地で スペシャル・プライス [ ジェームズ・ノートン ]1932~33年にソビエト連邦各地で起きた人為的な大飢饉「ホロドモール」を扱った作品だ。この大飢饉はウクライナ、北カフカース、クバーニなどウクライナ人が住んでいた地域をはじめカザフスタン他でも起きたということだが、その犠牲者は330万人から数百万人ともいわれる。この映画は、その実情を直接見た一人の英国人ジャーナリストの果敢な行動を映像作品として再現したものだ。映画化にあたり、実際の経験の脚色やある程度の演出はあると思われるが、当時のソ連指導部によって引き起こされた農作物収奪による飢饉の凄まじさはよく伝わってくる。今年2月にプーチンのロシアがウクライナに侵攻した時点で観たかったのだが、にわかに人気が出て予約が増え、すぐにはレンタルできなかった。いまだウクライナへの侵略戦争が続いているなか、ここでようやく観れた。それにしても、理想を掲げて革命によって成された「ソ連」の実態がいかに酷いものであったかがわかる。スターリン時代のソ連が超監視・粛清社会の地獄だったことはよく知られてると思うが、「労働者の解放」が目的のはずなのに“支配者が代わっただけ”で以前よりひどくなったとは... 現在ではすでにわかっていることだが、「地上に楽園はないし、作ることもかなわない」ということだね。この作品では『動物農場』を執筆するジョージ・オーウェルを登場させ、まさに革命が独裁体制と専制政治によって裏切られ、革命以前よりも悪くなったその実態にお墨付きを与えている。プーチンは「ウクライナはロシアの一部で、独立国ではない」などとほざいて侵略戦争を始めた。そんなふざけた理屈でウクライナ国に侵攻し、破壊と収奪を敢行する様はスターリンの所業と変わらない。独裁者は、なぜ他者の命を自分の命と同等に扱わないのか。食うか食われるかの生存競争、人類もしょせんは弱肉強食の摂理にあり、仕方のないことだと平然とそれをやってのけるのか。それなら、人間が“人間である価値”はない。民主国に生きる我々はそのような価値観には立っていない。格差はあっても、破壊と搾取、隷属のない平穏な社会に暮らし続けることを望んでいるのであり、独裁専制の体制にないことがその理想を担保するものと固く信じている。
2022.11.24
コメント(0)
-

やすらぎの森
やすらぎの森 [ アンドレ・ラシャペル ]『やすらぎの森』(2021年公開、カナダ)という映画を観た。奥深い森のなかで世捨て人のように生活する老人たちを映して、人生の最後をどう生きるのかを問うた作品だ。重いテーマを扱っており、背景に映るカナダの美しい森がなければ、これをじっくり見るには根気がいる。3人の老人がその森でひっそりと暮らしていた。彼らはそれぞれに困難な事情を抱え森のなかへ逃避していたのだった。そこへ一人の女性(高齢)があるキッカケで舞い込んできた。それが大きなパラメータとなり、彼らの運命を動かすことになる...3人にはそれぞれの最後が訪れる。テッドには神が定めた寿命が... トムはその寿命を受け入れず、自ら人生を終わらせる... 女性と恋仲になったチャーリーは深い森から離れ、二人で(死へ向けた)新たな生活を始める。作者は問うているのだ。「あなたは人生の最期をどのように迎えますか」と...私は両親の晩年にその生活支援をけっこう長く続けたので、人がどのように老いどのように死んでいくのか、その過程をつぶさに見た。高齢者の多くは何気ない一日一日を生き続けて、最後は病院で死を迎えるのがふつうだ。作品でも触れられているが、いまの高齢者の老後生活はある面で薬漬け、検査漬けの日々である。彼らの長い老後生活は医療・介護経済パイの大部分を占めており、そこで働く労働者の生計を支えているのだ。人は自分の死に方を積極的には決められないものだと思うし、長生きは悪いことではない。しかし、本人の意思を曲げて“長生きさせる”のはいかがなものか。高齢者に必要なのは、決して医療、看護や介護だけではない。人は“この世に生まれること”を自分では決められない-のに、その“生まれ”によって人生の大部分が決まったりする...ならせめて、その「死」は、その死に方は自分で自由に決められるべきではないのか。
2022.11.08
コメント(0)
-

レコードアルバムとの別れ
レコードアルバムの処分が終わった。若い頃夢中になっていた時期には200枚はあっただろうか。愛着の薄いものから少しずつ手放し続けて、最後まで残った25枚をようやく決心して手放すことができた。よい思い出の残るモノを手放すのは簡単ではない...死ぬまで持っていてもよいのだが、あいにく私には遺品を受け継ぐ人がいない。死後ただ廃棄されるくらいならと、他者に再利用されることを期待し中古業者に持ち込んだ。その点近年のレコード愛好再ブームは都合がよかった。それにしてもリスニングの環境は激変したものだ。ソフトがレコードからCDへ、さらにデータ配信へと。ハードは大型のステレオからカセットテレコへ、さらに携帯端末での高性能イヤホン聴きへと。音楽そのものも、これはジャンルにもよるだろうが、だいぶインフレ化が進んでしまって多くの若者を魅了するような時代は過ぎ去った。ビートルズに始まったポピュラー音楽隆盛の時代は、マイケル・ジャクソンの他界で終わったのだと思う。私観だが、音楽にはもはや世代を問わず人の苦難、孤独を癒すような力はないのだと思う。私にとっても、それは集中して聴き入るようなものではなくなっており、作業時のBGM聴きが主になっている。それでも、音楽から離れられない自分が好きだ。私はクリエイターが創った世界に浸り続け、夢想に耽った人生を歩んできたが、そんな自分を恥とは思わない。あるべき理想の世界は、そこにこそあると信じ続けてきたからだ。『明日に架ける橋(40周年記念盤)』 [ サイモン&ガーファンクル ]
2022.10.29
コメント(0)
-

安倍さん亡き後、日本はどうなる...😥
参議院選挙が終わって一週間が過ぎた。しかし、なんとも後味の悪い選挙戦になった。言うまでもなく、安倍元総理があのような形で旅立たれたからだ。政治家は命がけの仕事だ。まして総理職にあってはなおさらそうであり、いつどんな事態が待ち構えているかわからない。そうわかっていても、ショックだった。日本が戦後の歪みを正し本来の姿を取り戻すには、なくてはならない存在だったからだ。だが落ち込んでばかりはいられない。我々が安倍元総理のご遺志をしっかりと継がねば。現場から退いて長いが、私もできるだけのことをしようと決意した。今参院選の結果に、私には特段の思いはない。地元神奈川県においても、全国的にもだいたい予想していた結果になったからだ。ちょっと残念だったのは、大分選挙区で国民民主党の足立信也さんが落選したこと。非常に有能な議員で医師でもあり、国会の委員会でも鋭い質問を政府に浴びせて回答する大臣などをよく困らせていた。足立さんの人気は高く当選の安定株と見られていたので、大分選挙区では安倍さん逝去への哀悼票がとくに多かったのかなと思う。あと地元選挙区の松沢成文さん。やはり人気がある。維新の組織票が神奈川で大幅に増えたとは思えず、やはり松沢さん個人の人気が高いのだと思う。維新の会はいま衣替えの時期にあり、ベテランである松沢さんの存在は今後重視されるのではないか。さて、今後の国政はどう動くだろうか。安倍さんを失ったことで、岸田総理は厳しい政権運営を迫られるのではないだろうか。最長政権を維持した大物元総理であり、最大派閥の領袖として安倍さんの影響力は大きかった。岸田総理は今後憲法改正など重要課題に向き合わなければならないわけだが、自民党内の抵抗勢力をうまく抑えることができるだろうか。安倍さんがいれば、「安倍さんの強い意向だから」で抑えることができただろう。しかし今後は逐一自身がすべて決断しなければならないのだ。日本はいま外交内政ともに大きな課題に直面し、その難局を乗り切るために大きな決断を迫られている。安倍さんならその国家観、あるべき日本の姿にブレはなく、力強く突き進んでいく気概があったのだが、岸田さんはどうだろう。まずは安倍さんの送りを国葬と決めたのはOK。調整はほどほどに、「決める政治」で進んでほしい。新しい国へ 美しい国へ 完全版 (文春新書) [ 安倍 晋三 ]
2022.07.18
コメント(0)
-

参院選後、日本はどうなる?
参議院選挙の期日前投票に行ってきた。比例代表はもうだいぶ前から決めてあり、国士無双「青山繁晴(自民党)」候補に一票を投じた。選挙区(神奈川県)のほうは少し迷った。泡沫候補には関心なく国政政党候補からの選択だが、これまでは松沢成文(維新)さんに入れてきた。が、県知事退任後の松沢さんにはどうも精彩がなく、日本維新の会にも妖しい部分が見えてきた(橋下徹や鈴木宗男の存在)ので今回はパス。そこで浅尾慶一郎(自民)候補か深作ヘスス(国民民主党)候補に絞ったが、熟慮のうえ深作氏に入れた。浅尾氏はみんなの党解散後は松沢氏同様パッとしない感じだが、なんといっても毛並みがよく即戦力がある。迷ったが今回は自民候補は二人とも当選する可能性があり、個人への期待よりも国民民主党に力をつけてほしいとの思いで、深作氏に決めた。深作氏は当選ラインに届くかどうか... 共産党の組織票が大きいので厳しいかなと見ているが、次への大事なステップでもあろうと思うのでがんばってほしい。今選挙の争点、あるいは人々の選択にあたっての関心はなんだろうか。それは今後の岸田政権(与党)への期待度だと思う。昨年の衆院選は菅前政権の功績で勝てたので、岸田政権にとっては今回が実質的に最初の審判となる選挙だ。もっとも、野党側がまとまっておらず、ロシアによるウクライナ侵略という事態が起きているので、政権・与党はまず安泰だろう。衆参ねじれにはまずならない。そこで注目すべきは与党の、それも自民党の勝ち幅だ。選挙区ではほとんど勝てるのではないかと言われているが、どうだろうか。勝てば選挙後は岸田総理の黄金の3年間とも言われるが、むしろこの先はより厳しい道が待っているはず。憲法改正か皇位継承安定化のどちらかには必ず取り組まなければならない。私は皇位継承安定化(皇室典範改正)を先にやるのではないかとみている。憲法改正には国民投票が必要で、また場合によっては衆議院の解散も必要になるかもしれないからだ。くらべれば皇室典範改正のほうが取り組みやすいのではないだろうか。それに何よりも急がれるべき課題なのだ。そのどちらもやらず先送りするようなら、岸田政権は葬り去られる。NATOの教訓 世界最強の軍事同盟と日本が手を結んだら (PHP新書) [ グレンコ・アンドリー ]
2022.07.04
コメント(0)
-

参議院選挙、いろいろ思案中...
参議院選挙(第26回)も中盤を過ぎようとしている。事前予想では与党の楽勝と見られているようだが、どうだろう。2月24日、プーチンのロシア軍はウクライナ国に対して侵略戦争を実行し今も続いている。今選挙においてその影響がないはずはないだろう。我が国の隣には独裁・専制主義国が三つもあり、そのいずれもが核兵器を有した危険な国だ。米軍基地の存在(日米安保)と自衛隊によってなんとか抑止力を働かせているが、もし米軍基地が無ければ、我が国は核武装しなければとても祖国を守れない状況にある。今選挙で各党、候補者は国防の重要性について重点的に訴えていいはずだが、どうも争点らしきものは物価高対策や消費税減税のようであり、女性候補者の訴えは相変わらず「子育て」「福祉」中心のようだ。国の存立がまず先にあって、そのうえでの国民生活なんだけどねぇ...さて、どの候補、政党に票を投じるかいろいろ考えてるところなのだが、比例代表のほうはすでに決めてある。自民党の青山繁晴議員だ。氏は議員連盟「日本の尊厳と国益を護る会」の代表として精力的に活動しておられる。また企業献金など受けず、政治資金パーティーなどもやらずに政治活動をされており、まさに国士と言っていい信頼に足る政治家だと私は評価している。氏のYouTube番組『ぼくらの国会』は、自民党部会の内容解説を中心に氏の記者時代のエピソードなども語られ、たいへん興味深く楽しいものになっているのでぜひ視聴してみてほしい。選挙区(神奈川県)のほうは悩んでいる。まあ有力候補と泡沫ははっきりしており、消去法で選択は限られてくる。それにある程度の票読みは可能で当選圏内にある候補は見えている。今回は改選定数4と欠員1の5議席あるわけだが、与党三候補のうち二人と立憲二候補のどちらか一人は大丈夫だろう。残り2議席がどうなるか。今回は自民党の得票が増えると思われ同党の二候補とも当選する可能性があるが、組織票の固い共産党が入るとしたら、それで残り1。この1議席はシビアな争いになりそう。前回は松沢成文氏に投じたのだが、松沢さんは県知事退任後どうも活動が迷走しているように思えて、申し訳ないが賞味期限切れなのかなとの感がある。ほか気になるのは深作ヘスス氏。経歴は立派だが、まだ海の物とも山の物ともつかぬ新人候補。しかし与党を刺激できる国民民主党を応援したいとの気持ちがあり、個人よりも政党への一票として選ぼうかなと考えている。まだ期間はあるので、じっくり考えたい。プーチンの戦争 [ ナザレンコ・アンドリー ]
2022.06.30
コメント(0)
全762件 (762件中 1-50件目)
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 【時短・防災】普通のポリ袋とは別物…
- (2025-11-29 20:00:07)
-
-
-

- 楽天市場
- 可愛すぎてキュン死注意🚨💕 女子力…
- (2025-11-29 20:21:26)
-
-
-

- ひとりごと
- 丸山純奈 Sing & Sing- Live at WWW X
- (2025-11-28 21:10:35)
-