2025年05月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
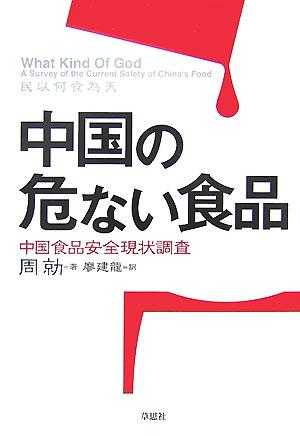
中国の危ない食品(20250521)
2025年5月21日、中国の危ない食品(周勍/著、廖建竜/訳)読了。副題:中国食品安全現状調査奥付を見ると2007年10月5日第1刷発行となっている。この本は中国で出された本の日本語訳だ。表紙をめくると:中国食品が世界の食卓を脅かしている。だが、国内の食品汚染はもっと深刻だ。ホルモン剤を添加した養殖水産物が原因で性早熟児が現れた。喘息治療薬で赤身化した豚肉による中毒事件の多発。発癌性のある合成染料で卵の黄身を鮮やかにする。下水のゴミ油を加工して屋台の食用油や安いサラダ油に。農地には水銀がしみこみ、水道管の八割に鉛塩が使われている。不衛生、利益優先・安全無視。いったい中国では何を食べたらいいのか。4年にわたり、食品の安全問題を取材してきた中国人ジャーナリストが、恐るべき実態とその社会的背景に鋭く迫り、2006年度のドイツ「ユリシーズ国際ルポルタージュ文学賞」佳作となった衝撃の報告。これを読むだけで空恐ろしくなってくるが、中を読むととてもこの国に行って何かを食べる気にはなれない。行ったこともないが今後行くことはあり得ない。各章の初めに含蓄のあることが書いてある。第1章:民族の命運にかかわる「食品汚染」一つの民族の命運は、その民族の人達がどういうものを食べているか、そしてどういう食べ方をしているかを見れば分かる。第2章:豚の赤身肉が「妖怪」になるまで中国の赤身肉嗜好が、ひたすら利益を追求する商人を狂わせた結果、世界一の豚肉生産国、中国の豚肉が汚染されてしまった。第3章:恐るべき食品危害米、麺、油、塩はむろんのこと、ありとあらゆる食べ物が利益追求のために汚染され、食品の安全は失われた。第4章:経済のグローバル化と「食の安全」をめぐる戦い世界はグローバル化し、ある国で風邪を引くと別の国でクシャミをする。食品貿易のグローバル化は、ある国の食品汚染が進むと別の国も汚染されるようになる。第5章:引き裂かれた「天」を修復する―食品の安全は守れるのか明日を考えず、誰をも信用しない社会と権力者の汚職がなくならない限り、食品安全の問題は決して解決されない。私の読書記録索引はこちらをクリック。
2025.05.21
コメント(0)
-
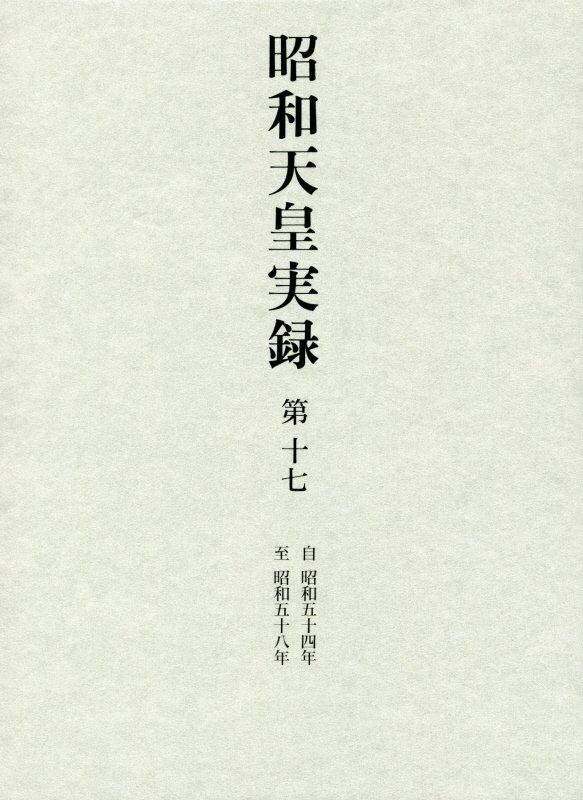
昭和天皇実録第十七(20250518)
2025年5月18日、昭和天皇実録第十七(巻五十五~五十七)読了。 副題:自昭和五十四年至昭和五十八年全部で18巻だから、あと少し。昭和54年。朴正煕大韓民国大統領が暗殺されたが、その事実だけが簡単に書かれている。昭和55年。2月23日、徳仁親王が二十歳になり成年式及び式典が25日まで続く。8月15日の全国戦没者追悼式でのお言葉が「である」から「です」となる。これはこの年から変更になった。昭和56年。「参議院議員市川房枝死去」と出てくる。ここに書かれるとは凄い人だったのだろう。ローマ法王ヨアンネス・パウルス二世と会見。放火により焼失した葉山御用邸の再建が終了し昭和45年夏以来の滞在。昭和57年。1月2日一般参賀で、お言葉を述べられる。これまでなかったこと。昭和58年。9月1日にソ連による大韓航空機撃墜があり、その後、事件に関して何度も色々な人から報告を受けている。私の読書記録索引はこちらをクリック。
2025.05.18
コメント(0)
-
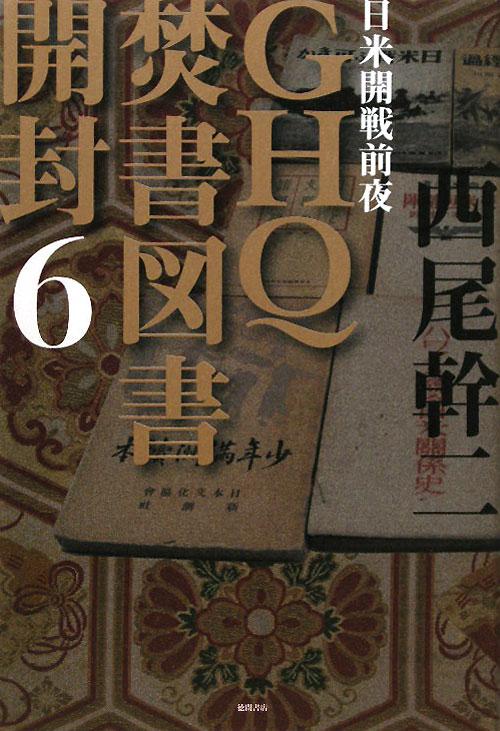
GHQ焚書図書開封6(20250505)
2025年5月5日、GHQ焚書図書開封6(西尾幹二/著)読了。副題:日米開戦前夜奥附を見ると、第1刷、2011年7月31日。因みに、地元の図書館には「12」まで存在しているので全部読みたいのだが、戦後教育を受けた身では12まで行けるか自信がない。敗戦により日本語がかなり改変されてしまったからだ。戦勝国が敗戦国の憲法を創る事、新聞・雑誌・放送・親書の検閲は勿論、相手国の歴史を消す事、書物の発禁、禁書も国際法上許されない。相手国の文化を踏みにじる行為は、絶対に許すことのできない蛮行だ。しかし「自由と平和」を標榜する米国は平然とやった。昭和20年9月から占領期間中の新聞、雑誌、映画、放送内容、刊行物、郵便物などが「検閲」されたし、電話は盗聴された。この本はGHQにより日本の社会から抹殺されてしまった約8千にも及ぶ書籍を掘り起こして紹介しているもので、この本は6巻目。昭和4年頃から「日米もし戦わば」の類の本が繰り返し多数出版されている。当時の日本人は世界をよく見ていたししっかりした現状認識をしていた。昭和15年頃までは日米双方でまさか戦争になるとは思っていなかった。戦後言われている、日本が思い上がって東亞諸国征服を目論んだから痛い目にあったのだとの認識は全く当たらない。日米戦争の背景にあったのは人種問題なのだ。民主主義の国だと思われている米国で普通選挙の施行が1965年で、実際に行われた最初が1971年だ。日米戦争は騙し討ちによる真珠湾攻撃が端緒だとされているが、米国が日本に対して戦闘行為を既に行っていたことは明らかになっているし、50年経過すると公開される米国政府の機密書類が一向に公開されない。一般の日本人は米国を敵国とは考えていなかった。支那を我が物にしようと露骨に手を出してきている英国やソ連をけしからんと思っていた。米国はまだ大国にはなっていなかった。太平洋の島々やフィリピンを手に入れるところまでで、その他は既に英国はじめ欧州の国々に抑えられていて手が出せない状況だった。みんなが支那大陸を狙っているがそこで邪魔になっているのが日本だった。日本と支那が組んだら大変なので蒋介石を支援して日支離反を盛んにやっていた。当時の世界は陽が沈まない国と称された英国が世界中を抑えていた。支那を支配するために使ったのが阿片だ。英国が東インド会社を作ったのが1601年で関ヶ原合戦の翌年。何度も日本にちょっかいを出したがだめだった。しかし、第一次世界大戦で力を落とした、英国を初めとする欧州列強は台頭してきたドイツに歯が立たないでフランスは降伏するし、英国自身は海上輸送をドイツ潜水艦にやられ、空襲で本土を直接爆撃され、青息吐息。大戦で無傷だった米国に参戦して欲しいが、戦争しないと公約して三選を果たした大統領が参戦するのは難しい。しかし、支那大陸への野望を果たすにはその前に細長く伸びた日本が邪魔でしょうがない。なんとか口実を設けてこれを叩きたいし、欧州で始まった戦争にも参加したい。そんなこんなで、戦いたくない日本を苛め抜いていく。第一次世界大戦後の日米の海軍力の差は日本が上で、米国が簡単に攻めてこられる状況ではなかったし、不戦の約束の大統領が攻め込む訳にもいかない。日本の海軍力を削ぐことや、支那大陸での嫌がらせ、日本からの移民を苛める、資源のない日本への資源供給を妨害する等々で、苛め抜いていく。この時代相当数の共産主義勢力が米国政府に入っていたし、共産主義ソ連とも組んで、対ドイツで苦しんでいるソ連を助け、蒋介石を助け日本を苦しめる、等々、日本の堪忍袋の緒を断ち切ろうとあの手この手だが、その辺のことを当時の本を掘り起こしている。昭和7年4月に世界知識増刊として出た、「日米戦う可きか」。昭和の初めころからこの手の本は沢山出ていた。この本は論文集だ。第一論文は海軍大佐・関根群平の「米国の極東政策」日清戦争に敗れて、支那が列強の切り取りにあっていたころ、米国は出遅れて「門戸開放」「機会均等」「領土保全」の三原則を欧州列強に提示したのが始まりとか思われているが、もっと前だ。憲法もできていない1784年の2月に野生の人参を支那に運んで貿易を始めようとしたのが最初だ。当時の支那は清朝で鎖国状態だったが、人参は評判でペリーが浦賀に来た頃の支那貿易の半分は米国だった。支那への航路は大西洋から南米を回りインド洋からだったので、西海岸から太平洋経由の航路を探してペリーは来た。小笠原諸島には既に米国人が入植していてペリーもそこに寄っている。ペリーはハワイ、小笠原、琉球、上海を考えていた。米国における日本人移民排斥は由々しき問題であり、移民たちが酷い扱いを受けていてそのために軍隊が動けば天皇といえども止めるのは困難。排日の具体例。黄白人結婚禁止法は日本人だけでなくアジア人全般に対して白人との結婚を禁止るるもの。仕方ないので、日本に居る人と写真見合いをして結婚しても米国へ入れないとか、奥さんが日本で出産したら日本で生まれたということでその子は米国へ入れない、等々。あまりに酷いので少し緩和されても、実態として散髪してくれない、レストランでの入店拒否、映画館等々、入店を拒まれたり、嫌がらせをされたりした。米国に限らず南北アメリカへ行った日本人の多くが農業に従事した。正に、荒野を開墾して立派な農地にして作物を供給できるようにすると、その土地が剥奪されるという理不尽なことがおこなわれた。モンロー主義は単に南北アメリカから宗主国を追い出して干渉させないための主張。支那大陸に食い込みたいから、「門戸開放」「機会均等」とか言うが、モンロー主義を主張している手前、アジアはアジア人の手でと言いながら石油のあるインドネシア辺りには平気で触手を伸ばしているというありさま。ルーズベルト大統領になっての主張を見ると。・デモクラシーの擁護と称して、蒋介石援助。・全体主義反対と称して、独・伊の欧州新秩序や日本の東亞新秩序への反対。などと、矛盾だらけ。米国の援助がなければ、英国はドイツに敗北していたであろう。当時の英国は世界中に海軍基地を持っていて、米国のフロリダからパナマ運河辺りにかけての海軍基地を99年間租借するのと引き換えに、米国で係留しているだけの老朽駆逐艦50隻を得て、植民地からの物資の輸送の護衛とした。これで米国はカリブ海を支配することとなった。支那大陸が内戦状態で英米独は蒋介石、ソ連は毛沢東、支那の内戦だから日本は満州で見ていればいいがそうもいかない中、英米に散々罵られていたが、そんな中英国は印度人を引き連れてイランを取りに行っている。昭和16年5月には米国で100機もの戦闘機が用意されて、その要員が好条件で募集され支那大陸に送り込まれている。フライング・タイガーと呼ばれる部隊だが、ルーズベルト大統領の承認も後に発覚している。日本が真珠湾を奇襲したとするが、そのはるか前に米国は日本と開戦しているのだ。宣戦布告など無しに。当然のこととして米国はフィリピンにおける戦力強化もしている。当時のアジアで独立を維持していたのは日本とタイだけで、それ以外は主に英国の植民地で英米はそれぞれ協力してこの地域の軍備増強をした。真珠湾攻撃の頃の日本の暗号は解読されていたことも解っている。真珠湾が攻撃されることを知っていながら、あえて攻撃させてだまし討ちだと国民を煽って戦争を始めた。現代日本では先の大戦の開戦日は12月7日となっているが、当時の日本政府の見解は11月26日で、ハルノートが日本政府に渡された日だ。野村大使が交渉していたが、東条英機首相になって来栖三郎が特任大使として渡米し野村大使と共に交渉に当たったが、その交渉は単なる米国の時間稼ぎでしかなかった。来栖大使は開戦後送還船で帰国し、昭和17年11月26日に帝国ホテルで対米交渉を振り返った講演を行った。この講演録は12月に「日米交渉の記録」として出版されたが、敗戦後焚書となって日本から消された。この時点で来栖は各種証拠を上げて、米国は準備万端整えており、真珠湾攻撃が未明に空から行われると言うことまで明らかにして陸海軍に指示している。準備万端整えていたつもりなのに、真珠湾攻撃で大敗を喫したから、騙し討ちなどと言っているが、自らの油断を隠すための詭弁でしかない。演説の中に本年5月30日に国務次官サムナー・ウェルズが戦後の方針を発表しているがその内容が実際に行われたことそのままで驚く。日本はとんでもないことだと決死の覚悟を改めて認識している所だ。真珠湾での大敗後、米国内では非難囂々。たまらず大統領は大審院判事のオーエン・J・ロバーツに命じて委員会を設置して報告書を纏めさせた。これがロバーツ報告書と呼ばれるものだ。ルーズベルト大統領は日米戦の準備を隠蔽したくて、そして日本の攻撃が闇討ちであったとしたくてこの委員会を設置して報告書を書かせたが、その報告書が、米国の戦争準備と日本が戦争せざるを得なくなるように米国が挑発していたことが書かれてしまった。つまり、米国自身が発表した公文書によって、自らの対日戦準備が暴露され、日米戦争の挑発者であることを世界に明らかにした点に、ロバーツ報告書の価値がある。昭和16年11月20日に日本の新提案を出したが11月26日に米側から出たのは最後通牒と取れる内容のもので、事実上の開戦通知だった。それ故、日米戦争の開始は11月26日なのだ。同時に米国大統領は陸海軍に対して開戦準備を指令している。その準備には機密書類の焼却処分まである。当然のことながらフィリピンなどの米軍にも同等の指令が飛んでいた。米国の戦争準備は完了していたが、真珠湾攻撃が米側の大敗となったのは、太平洋艦隊司令長官キンメル及び、ハワイ防衛司令官ショート等の首脳部の不始末と報告書は書いている。米国が仕掛けたの証拠の例:・下院議員のジャネット・ランキンはルーズベルトとチャーチルが共謀して天然資源のない日本経済封鎖して、戦争に追い込んだと語ったが、1942年10月10日の「サタデー・イブニング・ポスト」でルーズベルトは12月7日よりずっと以前に、日本の航空機、艦船を攻撃するよう軍隊を動員していた。・米海軍のクレランス・E・ディキソン中尉は1941年11月28日にパールハーバーを出港した折、空で見つけたものは何でも砲撃せよ、海で見つけたものは何でも砲撃せよ、との宣戦布告なき対日攻撃をルーズベルト大統領から命令されたと証言した。・ハリー・エルマー・バーンズは12月7日以前にはハワイの現地司令官のキンメルとショートに解明した暗号が渡らぬように、どんな警告をも与えないように画策したと証言。後にジョン・トーランドはアメリカ政府が暗号をどう解読し、情報をどう差し押さえたかを研究発表している。・1991年7月18日の「ニューヨーク・タイムズ」はいわゆる「フライイングタイガー」の259人が退役軍事ではなく、1941年の早い時期に国内の軍事基地内で募集がなされ、その年の内に中国大陸で軍務についていたと報じた。以上はほんの一例だが、これだけ出てくるということは隠そうとしても真実はいずれ表に出てくるので仕方のないことだ。この巻の主な焚書書籍。世界知識増刊「日米戦ふ可きか」昭和7年4月「アメリカの実力」棟尾松治、青年書房、昭和16年2月「米國の世界侵略」大東亜戦争調査会編、毎日新聞社、昭和16年10月「英米包囲陣と日本の進路」齋藤忠、春陽堂書店、昭和16年10月「大東亜戦争の発火点:日米交渉の経緯」来栖三郎、東京日日新聞社・大阪毎日新聞社、昭和17年12月「世界史的立場と日本」高坂正顕、西谷啓治、高山岩男、鈴木成高、中央公論社、昭和18年3月私の読書記録索引はこちらをクリック。
2025.05.05
コメント(0)
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
-
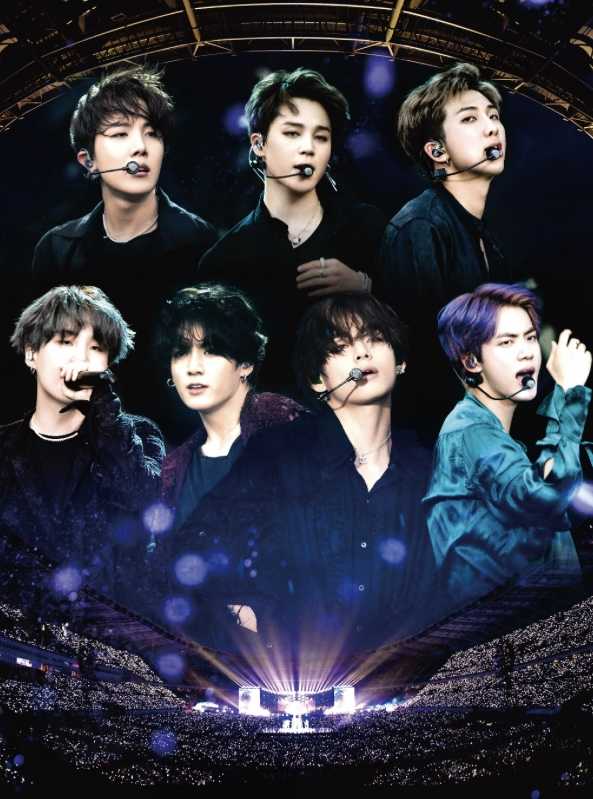
- 防弾少年団(BTS)のパラダイス
- BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF のDVD…
- (2025-11-21 18:37:01)
-
-
-
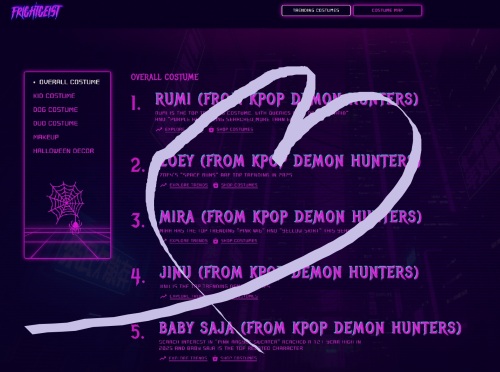
- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 영원히 깨질 수 없는
- (2025-11-11 06:13:39)
-
-
-

- 人気歌手ランキング
- 第76回 NHK紅白歌合戦 全出場歌手…
- (2025-11-15 04:58:28)
-






