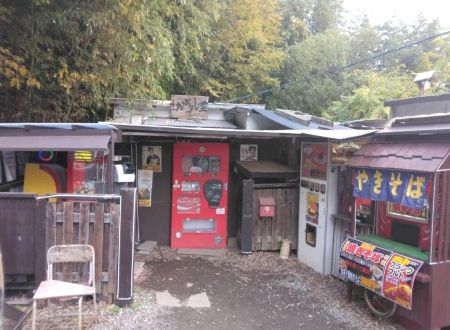2007年12月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
年末に相応しくないエントリ
「インディアンサマー・クリスマス」 などという戯言をはいたところ、それからわずか数日で寒波がやってきた。さすがは12月、「腐っても鯛」 といったところだろうか。 『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』 など多数の著作で知られる、かのマックス・ウェーバー (ヴェーバーと呼ぶ人もいるが) は、政治について 「神々の戦い」 と表現している。 それは、政治が 「理念」 やイデオロギーをめぐる闘争の場であり、しばしば非和解的な対立がもたらされるということ、と同時に、そのような対立は単純な 「善」 と 「悪」 の戦いなどではなく、もじどおり 「正義」 と 「正義」 の戦いなのであるという二重の意味を持っている。 だが、まだ終わったばかりの20世紀を振り返ってみれば、戦争が非常な苛烈さを帯びるようになったのは、そこに 「民族」や 「革命」、「正義」 といった理念が持ち込まれるようになったことと並行している。 なぜなら、その結果、戦争の相手国は、立場こそ違え、自分と対等の 「正義」 を持つものとしてではなく、なんらかの 「悪」 あるいは 「劣等」 なものとして描かれるようになったからだ。 戦争にそのような理念が持ち込まれることで、国家や政治党派は自国の国民と持てる資源のすべてを戦争に動員し、敵に対する情け容赦ない攻撃を行うことも可能になった。そのことはむろん、党派による内戦などの場合でも同様である。 たとえば、第一次大戦は 「すべての戦争を終わらせるための戦争」 と称され、第二次大戦は 「民族の生存をかけた戦い」 として、あるいは 「ファシズムを打倒するための戦い」 として戦われた (第三帝国の所業が 「悪逆非道」 であったことはたしかにそのとおりだが)。 政治に関する「友・敵」 理論で知られ、主としてワイマール時代に活動した、ドイツの法学者・政治学者 カール・シュミットは、こんなことを言っている。 このような (すなわち、人類の、そのときどきに決定的に最終の戦争と自称される) 戦争は、とくに激烈な非人間的な戦争であることは必然的である。 なぜならば、このような戦争は政治的なものの領域を越え出てしまって、敵を、道徳的およびその他のカテゴリーにおいて非難するとともに、予防されなければならないのみならず、決定的に絶滅されなければならない、 それゆえもはや単にそのものの国境の中へと追いかえさるべき敵ではない、非人間的な恐ろしいものにされねばならないからである。「政治的なものの概念」 より むろん、このような戦争の全体化は、近代的な科学の発達によって可能になったことではある。だが、科学の発達一般と、そのような科学を利用して強力な兵器を開発すること、さらには、そのような兵器を生きた人間に対して、実際に使用することとはまた別のことだ。 ダイナマイトを発明したノーベルは、自分の発明品が戦争で利用されるようになったことに心を痛めて、ノーベル賞を創設したと言われている。しかし、当時よりもはるかに 「進歩」 した現代の兵器に比べれば、それはまだまだおもちゃのようなものにすぎないだろう。 そして、そのような戦争の徹底化のあとを追うように、現代では、政治的な 「暗殺行為」 もまた、かつてのような、目標とする人物のみを狙う限定的行為から、その命を確実に奪うためなら、周囲の者らを多数巻き込むことも辞さないものへと 「発展」 したようだ。 「聖戦」 なる言葉は、たしかに宗教的な起源を持つものかも知れない。しかし、現代でのこの言葉は、けっして 「野蛮」 で 「狂信的」 なイスラム原理主義者らによって、ある日唐突に、過去から現代に持ち込まれた言葉なのではない。これもまた、現代の歴史そのものに深く根ざしており、そこから生れた言葉というべきだろう。 この世がデーモンに支配されていること。そして政治にタッチする人間、すなわち手段としての権力と暴力性とに関係をもった者は、悪魔の力と契約を結ぶものであること。 さらに善からは善のみが、悪からは悪のみが生まれるというのは、人間の行為にとって決して真実ではなく、しばしばその逆が真実であること。 これらのことは古代のキリスト教徒でも非常によく知っていた。これが見抜けないような人間は、政治のイロハもわきまえない未熟児である。「職業としての政治」 より 第一次大戦がドイツの敗北で終わり、帝国が崩壊した直後に行われた講演を収録したこの薄い本は、この国の多くの政治家の皆さんが、「座右の本」 としてあげている。それらの諸氏が、本当にこの本の内容を理解しているのならば、この国の政治はたぶんもっとましなはずである。 だが、ウェーバーのこの言葉は、なにも 「職業的政治家」 や、「職業的政治家」 を目指す者らのためにだけ書かれているのではない。なぜなら、民主主義という制度では、すべての国民が多かれ少なかれ、「政治家」 としての役割を果たすことが期待されているのだから。 どこの国にも、確かに国民に対する影響力の強い組織や機関は存在する。しかし、現代の政治はけっして、一部の 「支配者」 や 「権力者」 の意思だけで動いているわけではない。とりわけ、そのことは 「危機」 的な状況や、先の見えない混乱した状況であればあるほどあてはまるだろう。 「理想」 や 「理念」 を語ることは悪いことではない。しかし、そのようなとき、おうおうにして人は 「ナイーブ」 という病におちいりがちである。「主観的な善意」 というものが、それだけではいかなる正しさも保証しえないことは、どんな世界でも言えることであり、そのような 「善意」 が、ときには取り返しのつかない 「地獄」 へとつながるものなのだ。その程度の教訓は、歴史を振り返ればいくつも転がっている。 それにしても、年の最後にはまったく相応しくない無粋な内容になってしまった。
2007.12.31
コメント(2)
-
世界を動かしているのは悪意ではない
振り返ってみると、「陰謀論」 の誤りと、その危険性について、ずいぶんとごちゃごちゃ書きまくってしまった。なにしろ、クリスマスについて書き出した記事まで、最後は 「陰謀論」 批判という結論になってしまったくらいだ。 「陰謀論」 にはまりやすいのは、ナイーブな人が多いと書いたけれど、もうひとつ付け加えることがある。それは、根は同じことだが、「陰謀論」 にはまりやすい人の多くは、世界を動かしているものは、人間の 「悪意」 であるといった発想に捉われているということだ。 たしかに、世界は不条理であり、様々な 「暴力」 や 「不正」、「悪」 に満ちている。しかし、その多くは、誰かのことさらな 「悪意」 によって生じているわけではない。 一昨日、パキスタンでブット元首相が爆弾テロによって暗殺された。帰国直後にも爆弾で狙われ、本人は無事だったものの、周囲に多数の死者を出していた。そのことから考えると、彼女の暗殺は、いわば時間の問題だったかのような感すらある。 そのような状況の中でも、大衆の前に姿を現し続け、公然とした政治活動をやめようとしなかった勇気は、彼女の政治信念などに対する評価を超えて、強く賞賛されるべきものだろう。もっとも、彼女の支持者でもないのに事件の巻き添えになった人にとっては、そんな言葉は慰めにもならないだろうが。 事件の直接の実行犯が、巷間言われているような 「イスラム過激派」 であることは、たぶん間違いないだろう。ただ、ひょっとしたら彼女の政敵である、現在のムシャラフ政権がなんらかの形で関与している可能性というのはあるかもしれない。 言うまでもないことだが、「自爆テロ」 というような、自らの命を顧みない方法で暗殺を決行した犯人が、ただの 「悪意」 や 「計算」 だけで動いていたわけはない。彼には彼なりの、強い 「使命感」 と 「正義感」 があったのだろう。むろん、それはけっして手放しで肯定されるべきものではないだろうが。 「悪」 は必ずしも 「悪意」 から生れるものではない。それは、たとえば 「この国を今の混乱から救える者、この国の政治を担える者は、自分しかいない」 というような、愛国心に基づいた、強い使命感から生れたりもする。 そのような使命感にかられた人間にとっては、自分に対する批判者は、すべて国家の混乱を意図している 「悪者」 であり、方法を問わず、排除すべき対象であるというように見えても不思議はない。 劉少奇ら多くの古参幹部を、党に巣くい資本主義の復活をもくろむ 「走資派」 と呼んで 「文化大革命」 を発動し、その打倒を若者らに呼びかけた、晩年の毛沢東がそうだったし、おそらくは、独裁志向を強めている現在のプーチンの胸のうちも、それと似たようなものなのだろう。 多数の 「異教徒」 や 「異端派」 を弾圧し殺害した、ヨーロッパ中世の 「十字軍」 にしても、その行為は多くの場合、「純粋」 な宗教的動機から発している。むろん、なかには、そこに便乗して、自分の名前を挙げようとか、一旗上げてやろうとかいう、いささか 「不純」 な人間もいはしただろうが。 ブッシュにしても、また彼を支えている支持者らにしても、「世界を野蛮なテロから守らなければならない」 とか、「キリスト教文明を世界に広めなければならない」 というような 「使命感」 に駆られているのだろう。 「正義」 と 「正義」 がぶつかるなかで、この世に 「正義」 は1つしかないと考え、自分の 「正しさ」 を疑わない人間は、当然のことながら、自分の敵を動かしているものは、なんらかの 「悪意」 であると決め付けることになる。いや、そのような人間には、そういうふうにしか考えられないのだ。そこから 「陰謀論」 へは、ほんの一歩である。 その点では、世界中に 「文明世界の破壊を狙うイスラム原理主義者の陰謀」 が存在すると考えているブッシュ政権も、9.11同時多発テロは、「世界の支配と利権を狙うブッシュ政権による自作自演の陰謀だ」 と考えている人々も、同じなのである。 むろん、人間を動かしているものはけっして 「正義感」 や 「使命感」 などの 「善意」 ばかりではない。そこには、個人的な利益や名誉、他人を支配することに対する欲望なども存在はするだろう。 しかし、これは良くも悪くもまさに人間の 「煩悩」 のようなものであるから、「悪意」 とばかりは言えない。ただ、人間は自分の行為を正当化し、合理化するなんらかの 「根拠」 を持っているときほど、かえってそういう 「煩悩」 の誘いにものりがちなのである。 たとえば、 「オレオレ詐欺」 とか 「訪問販売詐欺」 だとかをはたらいて、高齢者を騙している若者らにとって、そのような行為は、おそらく立派な 「ビジネス」 なのだろう。だから、彼らもそのような 「ビジネス」 を離れた日常では、ごく普通のどこにでもいる青年であり、ひょっとしたら親切で優しい青年である可能性すらある。むろん、みんなそうだとは言わないが。 あの 「ユダヤ人虐殺」 を遂行したアイヒマンのような人間も、家庭に帰れば妻や娘を愛するよきパパであったり、芸術を好む、洗練された 「高尚」 な趣味を持つ人間であったりもする。人間はけっして自分が思っているほど、終始一貫した存在でもないし、ただひとつの 「人格」 しか持っていないわけでもない。 なにしろ、世の中には、バイクにまたがったり、車のハンドルやカラオケのマイクを握っただけで、人格が変わる、 というような人種も存在しているそうだから。 世界を支配している者が 「悪意」 によって動かされていると考える者は、「対立者」 のあらゆる行為に 「悪意」 をかぎつけ、ススキが揺れるのを見ても幽霊と勘違いし、結局のところ、相手が持っているものと即断した 「悪意」 を自らが抱え込むことにもなるだろう。 世界は 「悪意」 によって動かされているわけではない。だが、本当の困難は、むしろそのことに気付くことから始まるというべきだ。追記: 一部訂正と削除ありムバラク ⇒ ムシャラフムバラクはエジプトの大統領、パキスタンの現大統領はムシャラフなんとも紛らわしい (←ただの言い訳) http://d.hatena.ne.jp/good2nd/20080504/1209918455http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20080505/p1
2007.12.29
コメント(19)
-
「ナイーブ」 という病
もとマルクスボーイ (古いなあ) としては、心情的に左派を応援したい気持ちはある。しかし、「護憲派」 の現状を見ると、いささか、それじゃだめだよと言わざるを得ないところがある。今日は、ちょっとばかり勇気を出して、その辺を書いてみることにする。 「オオカミが来るぞ!」 式の護憲運動は、戦争と軍国主義の記憶が生々しかった50年代にはたしかに有効だった。しかし、現代ではもはや有効ではない。それは、「高度経済成長」 を経た日本社会の根本的変化と国際社会の変化を、あまりに考慮していないからだ。 たとえば、「護憲派」 の中には、いまなお、9条に少しでも手をつけたら、戦争が始まり軍国主義が復活するかのように言っている人がいるようだ。しかし、このような主張は、まったくナンセンスだ。そのような主張は、かつての 「天皇制国家」 を支えた社会的条件と、現在のそれとの違いをあまりに無視している。9条を含めて、今の憲法が抱えている問題は、そういうところにあるのではない。 たとえ、そのような 「軍国主義の復活」 をもくろむ、悪しきやからがどこかにいたところで、それは現実的に不可能なことだ。現代の日本は、もはやミャンマーのような軍事独裁政権が成立しうるような社会でもなければ、そのような政権によって統治しうるような単純な社会でもない。国際関係への影響を考えてみても、時代錯誤なトンデモ右翼ならばともかく、まともな責任ある政治家が、そのような妄想を抱いているはずはない。 そのことは、たとえば、皇太子夫妻や秋篠宮夫妻に対する、世間一般の振舞いを見ても明らかだろう。畏れ多くも皇太子夫妻の娘に対して、身分卑しき一般の人間が 「愛子さまあー」 などと軽々しく声をかけ、そのへんの芸能人に対するのと同様に手を振って、バチバチと写真を撮る。 そういった行動は、戦前ならばとうてい考えられなかったことだ。戦前ならば、皇族が目の前を通るときは、一般国民は道端にはいつくばって迎えなければならなかったのだ。このこと1つを取ってみても、戦前と同様の 「天皇制国家」 の復活などありえないことは明らかだろう。 戦後の 「護憲運動」 では、50年代のいわゆる 「逆コース」 以来、ことあるごとにそのような主張が繰り返されてきた。しかし、社会状況の根本的な変化をまったく考慮せずに、十年一日のように繰り返されてきた、しかも外れてばかりのそのような安易な 「オオカミが来るぞ!」 式の宣伝こそが、「護憲左派」 の政治的信用を失わせ、結局のところ、多くの国民から見捨てられることに至った最大の原因ではないのだろうか。 ただただ、戦前への回帰ばかりを憂えて、国民に警戒することのみを訴える、一部の 「護憲左派」 の言動には、あたかも、自分の子供の行動にはらはらしながら、あれこれと心配ばかりしている臆病な母親に似たところがある。しかし、少しは、今の国民の政治的常識と、戦後民主主義とを信頼してはどうなのだろうか。 たしかに、前内閣当時の自民党内部での 「憲法論議」 では、かの森元首相ですら苦言を呈するほどの、時代錯誤なトンデモぶりを発揮している連中がいた。しかし、そのような時代錯誤な 「改憲論」 など、とうてい今の国民に受け入れられるはずはない。いや、その前に、国会で三分の二以上の賛成を得られるはずもない。 高い国民的人気のもと、「美しい国づくり」 なるスローガンを掲げてスタートした安倍内閣は、「教育基本法」 の改正など、たしかに一定の 「成果」 をあげはした。しかし、彼のあまりにも哀れな政治的末路は、彼の 「戦後レジームの見直し」 という妄想に対する、国民の圧倒的な反対票の表れとして見ることもできるだろう。 政治的なリアリズムに欠けたそのようなナイーブさは、どちらかというと、戦後左派の宿痾のようなものだった。そのような例は、50年代のスターリン崇拝や、60年代の文化大革命の礼賛、「社会主義」 諸国に対する幻想と実情への無知など、枚挙にいとまがないくらいだ。 それに対して、アメリカによる占領からの独立回復をなしとげた吉田茂を、その源流の1つとする戦後の保守勢力とは、良くも悪くも、計算高い政治的リアリズムをこそ信条としていたはずだ。 しかし、わずか1年で退陣した安倍内閣とそのお友だち議員らの言動を見ると、このような生活者としての国民一般の意識から乖離し、リアルさを欠落させた 「ナイーブ」 という病は、いまや政界全体に無視できない程度に浸透しつつあるようにすら見える。 今、最も憂えるべきは、そのようなこの国の政治と政治家の全般的な劣化状況ではないだろうか。その主要な原因が、与野党を問わず、常態化しつつある議員の 「世襲制」 と、選挙の 「人気投票」 化にあることは言うまでもない。近く行われる大阪府知事選への橋下弁護士の出馬などは、その最たるものである。 政治的左派に関して言えば、ただただ過去の亡霊や反動の影にのみ怯える、後ろ向きの姿勢と、ススキが夜風に揺れるのを見ても幽霊と思い込むようなナイーブさから脱却しない限り、その再生はきわめて困難だろう。 とりわけ、9条を守ろうという熱意のあまりに、今の条文にちょっとでも手が加えられたら大変なことになるぞ!とでもいうような、一部に見られるいささか極端で、相も変らぬ運動や宣伝のやり方は、護憲運動自身と今後の平和運動にとっても、けっしていい結果はもたらさないと言わざるを得ない。追記: 題 変えました。
2007.12.28
コメント(8)
-
X X は今日も晴れだった
最近、いろいろと腹が立ったもので、あちこちのサイトに乱入して、年がいもなくいささか暴れてしまいました。このようなことは、まことにあってはならないことでありまして、二度といたしませんので、ご迷惑をかけた方々には、心よりお詫び申し上げます。 さてと、まあ分かったことは、「陰謀論」 などを信奉している方々は、きわめてナイーブな人が多いということであり、そもそもまともな議論などできる人ではないということである。それは、最初からある程度、予期していたことではあったのだが。 魯迅というと、「水に落ちた犬は叩け!」 という言葉が有名だが、その真意は、清朝の崩壊と共和国の誕生によって、一時的に死んだふりをしている古い勢力がまた蘇ってこないように、徹底的に叩き潰せ! というぐらいの意味だろう。なにも、ただキャンキャン吠えるだけの子犬まで、皆でよってたかってぼこぼこにしろ、というような意味ではあるまい。 先日、「今年の漢字」 ということで 「偽」 の一字が発表された。まことにそのとおりだが、食品の 「偽装表示」 だとか、大毅君の実力の 「偽装表示」 などは、それほどたいした問題ではない。なんといっても、最大の偽装表示は、前首相のおでこにはっついていた、製品性能の 「偽装表示」 なのである。 前首相の健在中 (失礼、まだ生きてた) には、「国民投票法」 の成立によって、「改憲」 を目指す動きが何十年ぶりかに活発化し、あちらこちらで憲法論議がかまびすしかった。改憲派の 「憲法論議」 はあまりにお粗末で、しかも拙速だったので、それがいちおう頓挫したことはめでたいことである。 ただ、その中で少し気になったことがある。それは、いわゆる 「護憲派」 の中に、復古主義的な憲法改正を警戒するあまりに、ただ改正のハードルを高くすることのみを主張しているかに見える人々がいたことである。その方々が、現在の憲法を完全無欠で、今後ともいかなる改正も必要ではないと考えているのなら、それはそれでよろしい。 しかし、そうでないとすれば、改憲のハードルをやたらと高くすることは、今の憲法の復古主義的な 「改正」 ではなく、時代に応じた新しい人権の規定を盛り込むことなど、自らの望むほうへと改正することをも困難にすることを意味する。 実際のはなし、現実にいま問題となっている 「生活保護」 の基準引き下げの問題や、「ワーキングプア」 などの問題で明らかになっていることは、25条の生存権や27条、28条に定める労働者の権利など、憲法で定められている権利が、きわめておろそかにされつつあるということだろう。 そこで、明らかになっていることは、現在の憲法が、政府与党、行政、一部の財界などによって、非常に軽く扱われているということだ。むろん、そのように憲法の規範性が非常に弱まっていることには、長年政権を握ってきた保守政党が一番の責任を負うべきものであることはいうまでもない。 たとえば、憲法は理念=理想を掲げるものであって、必ずしも現実とあっていなくともよい、というようなことを言う人もいる。憲法には、その国の政治理念が掲げられるという意味では、そのとおりである。事実、アメリカの憲法にしてもフランスの憲法にしても、そのような側面は多少なりとも持っている。しかし、そのような主張には、いささか居直りじみたところがありはしまいか。 憲法に掲げられた 「理念」 というものは、少なくともその国の政治勢力を含めた、大多数の国民によって共有されているのでなければ、意味がない。そうでなければ、それはただの 「空文句」 でしかない。いかなる理想主義的な憲法であれ、その国の国民の意識や現実とあまりに懸け離れてしまえば、最終的には憲法そのものが軽んじられ、その全体が粗末に扱われるといったことも起きかねない。 両大戦間のワイマール共和国時代に、いわゆるワイマール憲法がたどった運命が、まさしくそのようなものだった。当時、ワイマール憲法は、世界で最も民主的な憲法だと言われたものだが、そのような憲法も、その出生の秘密を巡って、左右両翼から 「正当性」 に終始異議が唱えられる中では、ヒトラーとナチスの台頭を抑える役目など果たしようがなかった。 どちらも一部であるとはいえ、「改憲派」 は 「護憲派」 を 「反日分子」 と呼び、「護憲派」 は 「改憲派」 を 「好戦主義者」 などと決め付けて、互いに罵りあっているような状況は、左右を問わず、この国がいまだに政治的に未熟であることを象徴している。「改憲」 を主張する人にも、様々な人がおり、様々な内容があり、その理由もいろいろなのである。 おそらく、理性的な 「改憲派」 の主張の根拠には、憲法と現実があまりに乖離しすぎた場合、憲法そのもの、憲法の全体が軽んじられ、おろそかにされていくことになりはしないか、という危惧もあるのだろう。 9条のなし崩し的な 「解釈改憲」 が進められてきたことには、賛成・反対はともかくとして、それなりの根拠がある。自衛隊を完全に廃止して、その創設以前のような憲法と現実の完全な整合性を取り戻すことなどには、現実性もなければ、多くの国民の支持も得られないだろう。 だとすれば、国家の最高法規としての憲法の重みを取り戻すためには、現在の憲法を一定程度、現実にあわせて修正することも必要なのではないのか。上のような危惧は、けっして根拠がないわけではないし、このような主張も理論的に言う限りでは、合理性がないわけではない。 憲法の 「正当性」 の問題にしても、そうである。問題なのは、60年も前の憲法制定の過程や、制定当時の状況といった過去のことではない。現にいま、現憲法の 「正当性」 を疑う人々や、政治勢力が多数存在しているという現実が問題なのだ。そこでは、ただ過去をほじくり返したり、理屈ばかりを言っていてもしょうがない。結局、憲法の 「正当性」 とは、歴史の問題でも理論の問題でもなく、今現在の国民による明示・黙示の承認という、今現在の問題なのだから。 現在の憲法が、事実上あまりに長い間不問に付されてきた結果、このような状況が生じてきたのだとすれば、「国民投票」 によってその正当性を問うということは、けっして意味のないことではない。安倍内閣のもとで成立した 「国民投票法」 に、様々な問題があることは否定しないが、その逆に、ただただハードルを高くすることで、「改正」 を困難にすることだけを目指すのは、現憲法の 「正当性」 をめぐる問題を、根本的に解決することにはならないだろう。 さてと、仕事に戻らねば
2007.12.26
コメント(4)
-
ホワイトクリスマスはすでに死語である
今日は久しぶりにいい天気だった。空にはほとんど雲がなく、歩いていると汗ばんできて、とうとうセーターも脱いでしまった。 冬至であるから確かに日は低いし、すぐに沈んでしまう。しかし、人間は直立して歩くものであるから、太陽が低いほうがむしろ日を受ける面積は大きくなり、熱を吸収しやすくなる。まったく、「ホワイトクリスマス」 どころか、「インディアンサマー ・ クリスマス」 という言葉のほうがぴったりするような一日だった。 クリスマスは、一般にはイエス・キリストの誕生を祝う日ということになっているが、「聖書」 を読む限り、実際の誕生日がいつだったかははっきりしない。イエスの誕生について一番詳しく描かれているのは、新約聖書に納められた 『マタイによる福音書』 である。 イエスがヘロデ王の代に、ユダヤのベツレヘムでお生れになったとき、見よ、東からきた博士たちがエルサレムに着いて言った、「ユダヤ人の王としてお生れになったかたは、どこにおられますか。わたしたちは東の方でその星を見たので、そのかたを拝みにきました」。ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じた。エルサレムの人々もみな、同様であった。 そこで王は祭司長たちと民の律法学者たちとを全部集めて、キリストはどこに生れるのかと、彼らに問いただした。彼らは王に言った、「それはユダヤのベツレヘムです。預言者がこうしるしています、『ユダの地、ベツレヘムよ、おまえはユダの君たちの中で、決して最も小さいものではない。おまえの中からひとりの君が出て、わが民イスラエルの牧者となるであろう』」 そこで、ヘロデはひそかに博士たちを呼んで、星の現れた時について詳しく聞き、彼らをベツレヘムにつかわして言った、「行って、その幼な子のことを詳しく調べ、見つかったらわたしに知らせてくれ。わたしも拝みに行くから」。彼らは王の言うことを聞いて出かけると、見よ、彼らが東方で見た星が、彼らより先に進んで、幼な子のいる所まで行き、その上にとどまった。彼らはその星を見て、非常な喜びにあふれた。そして、家にはいって、母マリヤのそばにいる幼な子に会い、ひれ伏して拝み、また、宝の箱をあけて、黄金・乳香・没薬などの贈り物をささげた。マタイ福音書2章1-11 いっぽう、イエスが厩で生れたという話は、『ルカによる福音書』 の方に出てくる。それによると、夫のヨセフが妊娠中のマリアを連れて、ヨセフの出身地であるベツレヘムに住民登録のために帰省している最中に、「マリヤは月が満ちて、初子を産み、布にくるんで、飼葉おけの中に寝かせた。客間には彼らのいる余地がなかったからである」 ということだ。 というわけで、イエスが実在の人物だったとしても、12月25日がその誕生日であるということには、根拠はあまりないようだ。現代では、ローマ帝国滅亡後の西方教会による、北方のケルト人やゲルマン人への布教の過程で、彼らによって祝われていた 「冬至祭」 が、教会の暦に取り入れられたというのが、クリスマスの起源に関する有力な説のようである。 いろんな宗教の教えがごちゃまぜになることは、「シンクレティズム」 と呼ばれる。明治新政府が出した 「神仏分離令」 によって、神社と寺院が別々に分けられる前の、「神仏混交」 とか 「神仏習合」 などと言われる状態がそうである。 こういう 「シンクレティズム」 という現象は、教義が不純であり、土俗的な宗教やインチキ宗教の特徴でもあるそうで、お偉い学者さんとかには、あまり評判がよろしくない。しかし、クリスマスの起源や、竜を退治したとかいう様々な聖人伝説などを見ると、キリスト教だってけっしてその例外ではない。 新しい宗教を広めるとき、もともとそこに存在する土着の宗教と正面から敵対するのは、広める側にとってもあまり賢いことではない。平安から鎌倉の頃に広まった 「本地垂迹」 説のように、土着の信仰を取り込むことで、既成の宗教に配慮するといったことは、そういう場合によく見られることだ。 また、そのような宗教の混交は、一般信徒である民衆の側から、自然発生的に起こることもある。キリスト教が厳しく弾圧されていた時代にも、マリア様を観音様に見せかけて信仰を守り続け、その結果、もとの姿からは著しく変容してしまったというような例もある。 いつだったか、NHKの 「世界遺産」 シリーズで、メキシコにある 「グアダルーペ寺院」 というキリスト教会が紹介されているのを見たことがある。この教会は、もともとスペイン人による支配よりも古い、アステカ時代の古い寺院の跡に建てられているのだそうだ。同じように、古い宗教の聖地や信仰の中心地が新しい宗教にも引き継がれるという例は、世界中あちこちに見られる。 その意図は、古い信仰の上に新しい信仰を接木して、その正当な後継者であるかのように装うことであったり、古い信仰の聖地をその下にしくことで、自らの優位を誇示することであったりと、様々だろう。だが、この教会は、聖母の声を聞いたというインディオらによって建てられたということであり、虐げられてきた貧しい先住民系の人々らによって熱烈に信仰されている、「褐色のマリア」 という像で有名なのだそうだ。 映像では、教会の前の石畳の広場を膝立ちでゆっくりゆっくりと進む、信徒の姿が映されていた。その姿は、五体投地によって聖地を巡るチベットの巡礼者ともよく似ていた。そこに表されているのは、民衆の祈りであり、希望であり、感謝の気持ちなのだろう。 どんな権力者も、どんなに強大な組織も、人間の心まで完全に支配することなどはできない。白人植民者から押し付けられた、「キリスト教」 という外来の宗教すらも、虐げられた民衆らによって、自身の苦しみを訴え、自身の希望を託す対象として読み替えられ、古い信仰も、その中で形を変えながらひそかに受け継がれていく。 それは、遠くアフリカから連れてこられた、アメリカの黒人奴隷やその子孫たちの場合でも、同じだろう。世界はつねにそのように重層的にできているのであって、けっして 「支配者」 や 「隠れた組織」 の意思だけで動いているのでも、その意図にそってのみ動いているのでもない。
2007.12.25
コメント(0)
-
「結果論」 と 「目的論」 の混同について
気がつくと、いつの間にか今年も残り少なくなっている。今夜はこの国のほとんどの皆さんが、1日だけのにわかキリシタンになるという日である。 昨日、いつものように夕方の買い物に、近くにある大型スーパーに出かけたところ、子供連れの家族客などで店内は熱気むんむんの大賑わいであった。ふと、気がついたのが、4, 5歳くらいの男の子。広い店内を、なにやら泣きそうな顔をしてバタバタと駆け回っている。 どうやら迷子になったようである。店内は大人の背よりも高い商品陳列棚がいっぱいに並んでいるから、見通しが悪い。目の位置の低い小さな子供にとっては、なおさらである。すでに半べそ状態であった。 店員も誰も気付かない (気付かないふりなのかもしれない)。声かけようかな、どうしようかな、でも変なおじさんに間違われてもなんだしなー、などと思いながらしばらく見守っていたら、お兄ちゃんを見つけたらしく、いっぺんで笑顔になってかけよっていった。一件落着のめでたしめでたしであった。 さて、プラトンの弟子であり、したがってソクラテスの孫弟子であり、かのアレクサンダー大王の家庭教師でもあったアリストテレスは、『形而上学』 の中で、世界を動かしている原因として、「形相因」、「質料因」、「始動因」、「目的因」 の4つを上げている。 このうち、「形相因」 と 「質料因」 というのは、ややこしくてよく分からないし、今は関係ないのでおいとくとして、「始動因」 と 「目的因」 というのは、次のようなものである。第三は、物事の運動がそれから始まるその始まり (始動因としての原理) であり、第四の原因とは反対の端にある原因で、物事が 「それのためにであるそれ」 すなわち 「善」 である。というのは、善は物事の生成や運動の全てが目指すところの終わり (すなわち目的) だからである。 こういう、世界を動かす原理としての 「目的因」 という考えでなりたっている世界観は、一般に 「目的論的世界観」 と呼ばれているが、そのような世界観が、世界を支配する 「神」 という存在を必要とすることは明らかだろう。近代の科学というものは、そういう 「目的論的世界観」 を否定するところから始まっている。 たとえば、「進化論」 では、よく 「キリンは高いところの葉を食べるために首が長くなった」 みたいな説明がされる。しかし、これは便宜的な説明であって、正確に言うと間違いである。進化とは、けっして一定の 「目的」 を目指して進むものではない。ランダムに発生する変化の中で、最も環境に適したものが生き残るため、結果的に、進化は環境への適応を目指して進んでいるかのように見えるだけである。 「目的」 というものは、いうまでもなくなんらかの 「意思」 を前提とする。自然界の中に、そのような進化を起こす 「意思」 は存在しない (存在するという人もいるかもしれないが、そういうことにしておく)。そのことを考えれば、目的論的な進化の説明が、結果から振り返った、便宜的なものでしかないことは明らかだろう。 こういう 「結果」 として生じたことを、あたかも誰かの意思によって最初から目指されていた 「目的」 であるかのように勘違いすることは、世界を合理的な必然性をもって進行するものとみなし、そのような論理だけで説明しようという傾向の強い人らが、とくに陥りやすい落とし穴である。 これが極端にまで進行すると、自分がいつも不運な目にばかり遭い、なにをやってもうまくいかないのは、周りの皆が私をねたみ、結託して陰謀をたくらんでいるからだ、みたいな 「妄想」 にまで発展する。しかし、それが 「妄想」 であることに、当人はなかなか気付かないものだ。 そのうえ、こういう 「妄想」 を抱いている人も、そのことを除けば、普通に社会生活を送っていたりするものだから、周りの人も最初はそれが 「妄想」 であることに気付かず、当人の 「妄想」 に巻き込まれてえらい目にあったりする。 宗教でいうと、古代キリスト教の一派であったグノーシス派には、これと同じような傾向が強く表れている。グノーシス思想の特徴は、われわれ人間は神によって欺かれているのだという教義にある。グノーシスとはそのような暴かれた 「真理」 のことであり、つまり、これは巨大にして壮大な 「陰謀論」 なのである。 『カラマーゾフの兄弟』 の中に、次兄イワンがアリョーシャに親に虐待されながら 「神ちゃま」 に祈る幼い女の子のことを語る場面がある。そこで、イワンが提出している問題は、全知全能で、悪などこれっぽちも含んでいない、善の巨塊であるはずの神によって造られたのに、「いったいなぜ世界は不条理なのか」、「いったい世界にはなぜ悪が存在するのか」 ということだ。 この問題 (弁神論) は、昔から多くの神学者たちを悩ませてきた問題であるが、彼らグノーシス主義者に言わせると、その答えはこうである。 物質的なこの世界を作った造物主は、実は本当の神ではない。自分を神と勘違いし思い上がった、偽物のあんぽんたんの神である。この世界はそのような不完全な神によって、物質という穢れた質料から作られている。だから、この世界は不完全なのであり、悪に満ちているのだ。 キリストとは、そのような偽の神の偽りを暴き、われわれ人間に真の福音と知恵 (グノーシス) を伝え、完全にして真なる世界への道筋を示すために、隠れている本物の神からひそかに遣わされた使者なのだ。(適当な要約) なんだか、M78星雲から人類を救いにやってきたウルトラマンみたいな話ではあるが、なかなかよくできた、奥が深い話である。 論理的にいう限り、たしかにこのような説明は筋がとおっている。ただし、もちろん証明は不可能であるし、また反駁することも不可能である。 グノーシス派の影響が強いと言われている 『ユダの福音書』 では、一般に 「裏切り者」 の代名詞のように言われているユダが、実はキリストの一番弟子であり、その秘密を知っていた者として描かれている。 それによると、ユダは、「キリストの復活」 という最大の奇跡を実現するために、あえて 「裏切り者」 の汚名を覚悟して、キリストをローマに売り渡したのだそうだ。これも、確かに形式論理的にはいちおう筋がとおっている。なぜなら、ユダの裏切りがなければ、キリストの復活もなかっただろうから。 それはそうかもしれないし、そうではないかもしれない。本当のことは分からない。ただ、こういう思考の根底には、「世界のすべてを合理的に説明したい」 という欲求があり、単なる偶然や様々な意思・行為の重なりによって生じた 「結果」 をも、「単一の意思」 によって意図的に追求されたものとして、一元的に説明しようという傾向があることは明らかだ。 こういう論理は、たしかにすべてを説明できる。しかし、証明も不可能であれば、したがって反証も不可能である。そもそも、すべてを一元的に説明する論理、なんでも説明できる論理とは、言い換えればそれだけで完結している論理なのであり、したがって 「具体的な事実」 による証明など、必要としない論理なのである。 ある原因によって、なにかの結果が生じたとしても、その結果が、誰かによって当初から目指されていた目的であるとは即断できない。ある事件によって、ある人が大きな利益を得たからといって、その事件はその利益を得た者によって、故意に起こされたのだと推論するのは、一見合理的であるかのように見えるが、それほど根拠があるわけではない。 昨日、クリスマス前のにぎわう店の中で迷子になった子供は、たぶんはしゃぎまわっているうちに親とはぐれてしまったのだろう。不注意の責任が親にあったのか子供にあったのかは分からない。だが、「迷子事件」 の原因はそういうことであり、そのために子供は 「迷子」 になったのだろう。 むろん、むかし、映画 『鬼畜』 で岩下志麻と緒形拳が演じたような親も、世の中にはいないわけではない(「ヘンゼルとグレーテル」 もそうだった)。だが、ふつう 「迷子事件」 はただの偶然で起こるものである。少なくとも、「迷子」 になりたくて 「迷子」 になる子供などはいない。
2007.12.24
コメント(12)
-
やっぱり餅のことは餅屋にまかせるべきである
世の中、なにがいちばん気楽かというと、「素人」 の立場からあれこれと文句を言うことである。野球の試合であれば、ピッチャーがファーボールを連発すれば 「へぼピッチャー、さっさと引っ込めー」 と罵声を浴びせ、バッターが凡退を繰り返せば 「お前なんか、さっさと引退しろー」 などと野次をとばしていればいいのだから。 むろん、こういう野次をとばすのも野球観戦の楽しみの一つだろうし、言っている本人だって、自分が代わりに投げたり打ったりできるわけではないことは、じゅうぶん承知のうえだろう。監督の選手起用のまずさを、屋台で一杯飲みながら批判していても、自分が代わりに監督をやるわけにはいかないことも分かっているはずだ。 スポーツの世界というものは、素人と玄人との違いというものが、誰の目にもはっきりとしている世界である。どんなに偉そうなことを言っている人でも、プロの選手に対して、「バットはこうやって振るもんだ」 とか、「ボールはこういうふうに蹴るんだよ」 みたいに、フィールドに下りてって手取り足取り指導してやろうなんて気を起こす者は、まずいまい。 なにしろ、スポーツの場合、素人と玄人とでは、体力も技量もまったく比較にならないのであり、そのことはお互いじゅうぶんに分かっている。そこでの比較=評価の基準は単純明快であり、そこに 「トンデモ」 学説など、入り込む余地はない。だからこそ、ある意味、そういう世界では、素人が無責任なことを言っていても、よほどのことでない限り許されるのだ。 先般、香川県で起きた、祖母と幼い孫二人が夜間に行方不明になった事件で、自分のブログに気軽なのりで 「犯人は X X だ」 などと書いた若い女性タレントがいた。彼女はけっきょく1年間の 「謹慎処分」 をくらうということになってしまったが、同様のことを匿名のブログや掲示板で書いていた者は、おそらく他にも大勢いたことだろう。 なにか世間を驚かすような事件が起こると、あちらこちらでいっせいに 「犯人当てクイズ」 のような騒ぎが始まる。これは、推理ものの 「二時間ドラマ」 の世界と現実の世界を混同しているようなもので、大宅壮一の言葉をもじれば 「一億総探偵化」 とでも言うべき現象である。 いうまでもなく、このような探偵とは、お湯をかけて5分でできたような 素人探偵 のことである。 こういったことも、テレビを見ながら夫婦や親子であれこれ言っている分には、そう実害はないだろうし、人間というものは自分には直接関係のないことでも、興味をもってあれこれ言いたがるものであるから、仕方がないことでもある。 だが、そうはいっても、やっぱり世の中には、素人が気軽にあれこれと口を出すべきではない領域もある。 どでかい飛行機が高速でビルに突っ込んだらどうなるのか、なんて話がまさにそうである。 そもそも、野球やサッカーの解説ですら素人には務まらないのに、なんでただの素人が、ニュース映像を見たぐらいで、「あのビルの崩れ方はおかしい」、「あの煙の出方はおかしい、やっぱり爆破されたのだ」、「陰謀だ!」 なんてことを言えるのだろうか。そこんとこが、私にはさっぱり分からない。 自分はあの事件以来、その真相解明に全精力をかけてきた、みたいなことをおっしゃっている方々がいる。なかなかの心意気である。見上げたものである。その心意気を、こちらにも少しは分けて欲しいぐらいである。 しかし、そのようなことを言っている人々は、そのことに必要な専門的な教育を、いったいどのくらい受けているのだろうか。たしかに、そのなかには、それなりの教育を受けた人もいるだろう。だが、あのような前代未聞で複雑な事件の 「真相」 を暴くというのなら、1つや2つの分野の専門教育を受けたぐらいでできることではない。 あんな重くてでっかい飛行機がなんで空を飛ぶのかを理解するには、航空力学や流体力学を修める必要があるだろう。ビルの崩壊を論じるならば建築力学や金属工学が、爆破かどうかを論じるならば、爆破工学だとかの理解も必要になるだろう (テキトーに言ってるので、違うかもしれない)。 それだけではない。教わったことを本当に身に着けるには、そこそこの実務経験というのも必要なはずだ。 で、「9.11事件の謎 !」 などと仰っている方々は、そのへんのことをいったいどのように考えていらっしゃるのだろう。ただの気分や戯言で言っているのではなく、本当に本気なのであれば、大学の理学部だか工学部に入りなおして、力学だとか工学だとかの基礎から学ぶべきである。 それだけの覚悟があるのならば、10年でも20年でもかけて、本当に事件の検証に必要な力を身に付けてから、検証を始めても遅くはあるまい。ほんらい 「覚悟」 というものは、そういうものである(ちょっとえらそー)。 むろん、「事件」 の経過とか、発表とかに疑問を持つこと自体は構わない。疑問を持った人が、自分のできる範囲で、いろいろと情報を集めて調べてみることもいいだろう。 しかしながら、生半可な知識で、「あの事件についての 『公式発表』 はでっち上げだー !」 などと触れてまわるのは、滑稽千万であり愚の骨頂であり、百害あって一利なしである。本当の覚悟がないのであれば、そういうことは 「専門家」 の先生に任せておけばよろしい。 むろん、ときには 「専門家」 でも意見が一致しないような問題もあるだろう。そういうときは、われわれ素人としては、いったいどっちを信用すればいいのか分からないのだから、確かに困ったことではある。だが、だからといって、「素人」 が気軽に口を出してもよいということにはなるまい。 「生兵法は怪我のもと」 ということわざもあるが、「素人」 がそういう問題に口を出すときは、少なくとも、自分はただの 「素人」 だということぐらい意識しておくべきである。「無知の知」 ではないが、「素人」 であることを自覚した素人は、すでに単なる無責任な素人ではない。 ある特定の問題について、その解決にはいったいどれだけのどのような能力が必要なのかを判断もせずに、また、いま現に自分が持っている能力はどの程度なのか、といったことを客観的に理解もできないままで、生半可なことを言い、 そのあげくに、太田龍ごときが垂れ流すようなお手軽な 「陰謀説」 などに引っかかるような人は、もしもいま、ヒトラーのような悪魔的デマゴーグが現れたなら、「うん、そうだ、そうだ、そのとおりだ」 と、簡単に騙され、その熱烈な支持者になってしまうことだろう。 いささか大仰ではあるが、オルテガの言葉を借りれば、そのような無責任な言動をなし、専門的能力もなく、またその自覚もないままに、「専門家」 と対等の口を利きたがる 「大衆」 こそが、ファシズムの登場を支えたのではなかったのだろうか。 そこに、決定的な違いなどはなにもない。自分は、善意にあふれ正義を信じる真面目な人間だから、そんな 「悪の道」 に迷い込むはずはない、などと思っている者がいるとすれば、そいつはただのお馬鹿さんであり、人間というものを知らない無知なあほうである。 とはいえ、だからこそ今のところ、そういった 「陰謀論」 に引っかかるようなトンマさんたちが、この国ではごくごく少数にすぎないことは、まことに慶賀すべきことなのである。 社会にとって最も危険な 「勢力」 は、しばしば 「既成権力」 や 「支配体制」 に対する 「急進的な批判」 という形をとって現れてくる。そして、そのような勢力の登場を支え、そのような流れに掉さすのは、どんな時代でも、真面目で行動力と正義感にあふれ、ただし自己を疑うことだけは知らない 「善意の人々」 らである。 5.15事件や2.26事件、様々な暗殺事件などを起こして、昭和の軍部独裁への道を開いた民間右翼や青年将校らも、農村の疲弊に無策な政党や政府の腐敗、金権体質などに憤った、自分は正しいと信じていた 「正義の人々」 ではなかったのか。 起きたことを後から振り返って、道を間違えてしまった者を非難するのは簡単だ。しかし、現にいま進行しつつある歴史においては、こっちが 「正しい道」、こっちは 「間違った道」 などという明確な 「方向表示」 などがあるわけではない。 それは、かつて 「連合赤軍事件」 を起こした永田洋子や坂口弘、あるいは 「オウム事件」 を起こした者らを見ても分かることだろう。 いったん抱いた自己の信念にどこまでも忠実であろうとする 「誠実」 な人間こそ、そういった迷路に迷い込みやすいものなのだ。追記: いささか刺激的な題をつけてしまいましたが、なにも 「素人は黙っとれ」 とか 「素人は口を出すな」 というわけではありません。そのへんの自覚がなく、なんでもかんでも安易に口をはさみたがる傾向がいろんなところに見られるのでは、ということがこの記事の趣旨です。
2007.12.21
コメント(2)
-
なんとも嘆かわしい世の中である
「陰謀論」 のお話はもうおしまいって、いったん宣言したのだが、どうもいまひとつ気分がすっきりしないので、また取り上げることにする。 前回の件は、こちらがいらぬちょっかいを出したために起きたことで、「無敵のコメンター」 氏のトンデモさは誰の目にも明らかだろうから、そのことをいつまでも根に持っているわけではない。 それよりも、憂鬱というか、なんだこれは、という気になってしまったのは、明らかな 「トンデモ」 氏ではなく、それなりに真面目で誠実な人と思われる中に、「9.11陰謀説」 を信奉している人が結構多いことを見てしまったからである。 その人たちは、「ブッシュはんたーい」 とか 「平和憲法を守ろうー」、「イラク戦争はんたーい」、「グローバル化はんたーい」 なんてことを、一生懸命に叫んでいらっしゃるのだ。 まあ、それは構わないのだけど、その一方で 「9.11はブッシュの陰謀だー!」 などと真剣な顔で言っているのを見ると、思いっきり滅入ってしまうのである。いったい、これはなんなのだろう。 なかには、そんな話ありえねーて批判されると、「自作自演説」 に 「陰謀論」 などとレッテル付けて批判しているのは日本だけだ、日本は世界から遅れているなんて言い出す人もいる。 その人が言うのには、「9.11陰謀説」 は世界の多くの人に支持されているのであり、「陰謀説」 に批判的な人が多い日本は、まだまだ遅れているのだそうだ。 たしかに、結構 「陰謀説」 は地元のアメリカを含めて、世界中に広まっているらしい。 で、それがどうしたの? なんで、まともな日本人まで、わざわざそんな世界のお馬鹿な連中の真似をしないといけないの? 日本は世界に遅れているって、あんた、それじゃ、あんたが一生懸命批判しているつもりの、グローバリストとかが言ってることおんなじじゃないの。 彼らも言ってるよ。日本は世界に遅れている、日本人は世界を知らない、日本の常識は世界の非常識だとかね。それといったいどこが違うのさ。あんた、馬鹿じゃねーの。すこしは、自分がなにを言っているのか、考えてみたらどうなのさ。 おまけに、「陰謀論」 なんて呼ばれるようになったのも、「9.11自作自演説」 を貶めるために、誰かが始めた 「陰謀」 の疑いがあるそうだ。 なんじゃ、そりゃ。 それって、ひとつの嘘のほころびを隠すために、次から次へと嘘を重ねて 「無実」 の人を犯人に仕立て上げた、どっかの警察がやったこととどこが違うの。 まあ、昔から、自分は世間一般の大衆よりも政治とか社会問題に関心があって、「意識」 が高いと思い込んでいる人間が、実はただの世間知らずの 「お坊ちゃん・お嬢ちゃん」 にすぎないってことはよくあることで、いまさらのことじゃない。 でもね、そんな荒唐無稽な馬鹿話を信じてる人たちよりも、長屋の八つぁん、熊さんのほうが、よっぽど世間のことを知っていて、ちゃんとした常識も持っているものだよ。だから、「9.11陰謀説」 なんて馬鹿話が、一部業界の狭い中ではやろうと、社会全体から見れば大きな問題ではもちろんないだろうさ。 言っとくけどね、普通に生きてる大衆の皆さんを、本当のことを知らずに騙されている 「意識の低い人間」 だ、みたいに思ってたら大間違いだよ。世間のみなさんのほうが、あんたらなんかより、よっぽどちゃんとしてるよ。 そんな世間様に向かって、「9.11はブッシュの陰謀だー !」 なんて真顔で叫んでるのは、ようするに、「私はこんな荒唐無稽な話を信じている、ただのおばかさんなのでーす」 て言ってるのと同じなんだよ。 結局、この人たちは、権力を握っている者らは、思いどおりになんでもできると思っているんだろう。 でも、まさかいくらなんでも、ブッシュがいくら大統領だからといったって、軍だかCIAだかに、今からペンタゴンにトマホークを打ち込めとか、WTCビルに爆薬仕掛けてこいとか、公然と命令できるはずはないよね。 じゃあ、いったいどうやって、ブッシュは 「陰謀」 を実行したの? 「権力」ってのは、ぶっそうな爆弾とかミサイルみたいに、好き勝手に扱える 「もの」 じゃないんだよ。スイッチを押せばウィーンと自動的に動くような、ただの機械とは違うんだから。 どんな 「権力者」 の命令だって、「はい、分かりました。仰せのとおりに致します」って人間がいなきゃ、意味ないんだよ。 それは法律どおりのちゃんとした活動だろうと、CIAとかがこそこそやってるような 「非合法活動」 だろうと同じことだよ。 それとも、なにかい。ブッシュ政権の中に、なにか妙な 「秘密結社」 みたいなものがあるの? だけど、ブッシュやチェイニーみたいなお偉いさんが、自分でビルに夜中にこっそり忍び込んでって、爆弾仕掛けたりはしないよね。 なら、実際に手を下した実行メンバーは、どこからどうやって選抜したの? いくら大統領だって、そんな汚い仕事、誰にでも頼めることじゃないよね。 これは、キューバだとかイランだとかに潜入して、爆弾を仕掛けてくることとは訳が違うよね。いくらなんでも、そんくらいのことは分かるよね。 それから、まだ倒れていないビルを倒れてしまったって報道した例の女性レポーターとか、ビルの廃墟からひそかに 「爆破装置」 だかミサイルだかの残骸を回収した、土建屋のおじさんとかも、実はその 「秘密結社」 のメンバーだったってわけ? その連中は、麻原から 「地下鉄でサリンまいてこい」 って言われて、そのとおりにした林郁夫たちみたいに、みんなブッシュに洗脳でもされてたの? どう見ても、ブッシュってそんな 「カリスマ性」 のある人間には見えないけどね。 そういう 「陰謀論」 ってさ、なにかといえば 「日本の少子化はフェミニストの陰謀だ!」 とか 「教育の荒廃は日教組の陰謀だ!」 とか言ってる一部右翼の皆さんと、どこが違うわけ? そりゃあ、確かに世の中にはいろんな陰謀があるよ。でも、だからって、どんな陰謀でもありってわけじゃないだろ。そこんとこの区別がつかなくて、どうすんのさ。あんたの頭はいったいなんのためにあるの? ちょっとは自分の顔を鏡でよく見てごらんよ。あんたが批判してるつもりの相手と、そっくりの顔をしてるよ。世間は騙されてても、自分だけは騙されてない、本当のことを知ってるって、ふんぞり返った得意げな顔になってるのも一緒だよ。 そんな、すかすか頭で、よくもまあ 「政治評論」 なんて看板かかげて、「自民党を倒せ!」 とか 「新自由主義反対 !」 とか、ブログで言ってられるよね。恥ずかしくないのかね。 まあ、あんたらが、自分で自分の首を絞めるのは勝手だけどさ。 というわけで、 なんとも胸糞の悪いいやな気分が続いているのであります。
2007.12.19
コメント(9)
-

「陰謀論」 者ってこんなものですよ
Commented by 布引洋 at 2007-12-18 10:30 xかつ君の手口は、普通の庶民の持っている迷信、誰でも漠然と信じている迷信を、さも確定した事実であるかのよう装い確信を持って断定するところにある。 例として、Commented by かつ at 2007-12-13 23:45 >「陰謀」というものについて、まず基本的なことを指摘します。 ・・数が多くなると、裏切りの可能性、ミスを起こす可能性も高・・・関係者の数も膨大な数・・・まず考えられないことのように思います。< 陰謀という言葉から、何か少人数でやるのが陰謀だと思わせようと印象操作するかつ君。 テレビドラマでの陰謀は確かに少人数ですね。しかし最後にばれる。 そりゃそうです、脚本がそうなってるんですから 少人数だとばれないと言う、かつ君説は、もう破綻しています。 少人数ならばれないなどとは言っていません。ばれにくいといっているのです。 この人は、「可能性」とか「確率」といった言葉を知らないようです。 ドラマの陰謀は『陰謀』ではなく単なる犯罪ですよ。かつ君説は犯罪の場合だけ当てはまります。 かつ君の主張する常識の罠。 普通の良識ある市民は誰でも漠然と、陰謀は犯罪と考えている。陰謀=犯罪 良識ある市民の常識を逆用して、『犯罪』は大人数ではばれ易いを、『陰謀』は大人数ではばれ易いに入れ替える。 かつ君のコメントの『陰謀』を『犯罪』に差し替えれば、全くの正論なんですよ。ちょっとしたトリックですね。 Commented by 布引洋 at 2007-12-18 11:10 xばれた『陰謀』といえば日本がやった満鉄爆破や、アメリカがやったトンキン湾事件。 方や15年、方や30年ばれなかった。では何故ばれたか。 両事件とも起こった時から胡散臭いと云われていたし、『陰謀』だと指摘する識者も若干はいたが、当然のように当局は無視したし大手マスコミも当然無視した。 共通点。どちらも『陰謀』を実行したのは軍隊、特務機関。 軍隊とは、こういう場合に使うんです。とんでもなく大勢で『陰謀』『謀略』をやるのが軍隊の役目ですよ。此れなら絶対ばれない。 で何故ばれたか。? 一番目は国家が崩壊したから。 国家が滅亡した時に初めて、国家の犯罪が明らかになる。 国家はいくら悪いことをしても犯罪とはならない。なぜなら犯罪の基準、善悪の基準は国家が握っているから。国家が認めたモノだけが犯罪といわれる。大日本帝国が健在なら満鉄爆破なんてものは此の世に存在しません。日本を貶める悪質な陰謀論ですよ Commented by 布引洋 at 2007-12-18 11:19 x二番目のアメリカの例では、認めた方が国益に叶うから。 当事者がいるんですよ。ベトナムが。 ベトナムは最初から陰謀と叫んでいたが、世界中みんなで無視した。 しかし戦争終結して30年。 認めて国交正常化したほうがアメリカの国益に叶うのは自明の理。国益にそむくとなれば100年たっても200年たっても認めるわけがありません。 『陰謀がばれたから』ではなく、ましてや悪いことをした事を反省したから認めたわけでは決してない。 まあアメリカだけではないが、アメリカは単純に国家の論理で動いている。 自国の国益に叶えば陰謀を認める時もあるし、自分にとって有利と思えば『陰謀』を実行する。 ← ただの一般論です。意味がありません。 冷静に考えて見れば、当たり前のことですね。 Commented by かつ at 2007-12-18 14:05 xそういうことは、私のほうに来て言いませんか。 あなたの言動は、まるで相手が入ってこれないように、他人の家の庭の中に逃げ込んでから、吠え掛かっている、哀れで臆病な犬のようにしか見えませんよ。いいかげん、年長者ぶったはったりと支離滅裂な論理で、人様のブログで暴れるのはやめたらいかがですか。 こんなばかなことばかり書きなぐっていると、そのうちどこのブログでも相手にされなくなりますよ。 Commented by かつ at 2007-12-18 14:12 xあのですね、軍隊や特務機関でも海外、特に「仮想敵国」に対してしかける「陰謀」と、国内の普通の一般市民を多数巻き込む「陰謀」とでは話がちがうでしょう。 Commented by 布引洋 at 2007-12-18 15:25 x変な人から褒められるより、けなされる方が100倍は嬉しいですね。いやいや結構結構。かつ君の品性と頭の程度が段々見えてきました。 品性に欠けているのは、いったいどっちでしょう。 かつ君は、世間の連中は、自分よりみんな馬鹿ばかりと思っているようですね。社会を舐めきっていますね。 人をなめきっているのは、いったいどちらでしょう。 軍隊の存在をうっかり失念していた、お馬鹿なかつ君の説『謀略は少人数でしか、なしえない。多人数では失敗する』が妄言であることを私が証明したら、 テレビドラマの例が 「証明」 なのだそうです。 恐れ入りました。>あのですね、軍隊や特務機関でも海外、特に「仮想敵国」に対してしかける「陰謀」と、国内の普通の一般市民を多数巻き込む「陰謀」とでは話がちがうでしょう。< Commented by 布引洋 at 2007-12-18 15:26 x議論に負けた時は黙っていれば良いものを、 だそうです 基本的には『謀略』『陰謀』は国内の普通の一般市民を多数巻き込む性質のモノなんですよ。 典型的な話のすり替えです。 歴史を一寸ばかり紐解けば簡単に分かるはずです。 大体ですね。敵国人相手に仕掛けるのは戦争です。 国内の人に仕掛けるのが『謀略』『陰謀』なんですよ。一々言葉からして説明しなければならないとはトホホ 大学生かと思っていたが、屁理屈好きの中学生なのかもしれない。 あまり言いたくありませんが、いちおう51歳です。 敵国人を『陰謀』で騙す話は始めて聞きましたよ。人間長生きはするものです。 この人はいったい何歳なのでしょう。とても興味があります。 謀略事件で騙すのは自国民だけ。相手国は最初から真実を知っている。中国人もベトナム人も最初から最後まで真実を知っていた。 知らなかったのは日本人とアメリカ人だけ。 かつ君。『陰謀』だ。『謀略』だというから君には理解できないのです。 陰謀ではなく広告、宣伝、広報、と考えてみてください。此れなら君の頭でも理解可能でしょう。そう広報活動で世界一はアメリカですよ。 そんなことは子供でも知っています。 Commented by かつ at 2007-12-18 15:32 xどこまで愚かなのですか。 私が言っているのは「実行場所」と、「実行行為」の直接の対象者のことですよ。 「宣伝対象」との区別もつかないのですか ___________________________________ かの 「無敵のコメンター氏」 です。たぶん、まだまだ続くでしょう。本当にしょうがない人です。 あきれはてております。 それにしても長い。しかも内容がない。 「妄想」 満開です。アメリカの軍隊は、平気で自国民を多数抹殺するそうです。 これは、大変なことです。この人の頭の中には、軍隊は軍隊だ、という 「公式」 しかないのでしょう。こういう人には、「教条主義者」 という言葉すらもったいないという気がします。 私としては、これ以上相手をするつもりはありません。それほど暇でもないし、ブログ主さんに迷惑をかけることになるので ただいささか腹が立つもので私も人間ですし、「聖人」 でも 「君子」 でもありませんから そうそう、大事なことを忘れてました。議論の主題は 「9.11陰謀論」 が成立するかどうかということです。 この人は戦争体験者で、戦争中は 「隣組」 がいちばん怖かったのだそうです。いったい、いくつだったのでしょう。当時、そんなことを感じた小学生などいるとは思えません。 そんなことは、軍国化する前のリベラルな時代を知っていた人でなければ、言えるはずがありません。 だとすると、どう考えても80歳は越えてないといけません。私には、どう考えてもそのようには思えません。長く生きた人間の持つ重みというものが、まったく感じられません。まあ、老人もいろいろですけど 顔の見えないネット上なら、いくらでも好き勝手なフィクションを言えるものです。 それに多少の薀蓄など、ちょっと時間をかけてネットで調べれば、すぐに手に入るものです。 だれでも、簡単ににわか物知りになれます。なにしろ便利な世の中ですから。ただし、残念なことに、品性と思考力だけはネット検索では得られません。 それにしても、いったい何様のつもりなのでしょう!
2007.12.18
コメント(15)
-
前の記事への追加
そもそも、どうにでも解釈できる、あやふやな 「事実」から一足飛びに 「結論」 を導き出すという点では、このような 「陰謀論」 は、同じようにあやふやで雑多な 「事実」 をかき集めて「超古代文明」 とやらの存在を主張する、かのグラハム・ハンコックの 「トンデモ歴史学」 とよく似ている。 あやふやな 「事実」をいくら集めたところで、そこから浮かび上がってくると主張される 「結論」 など、しょせん 「砂上の楼閣」にすぎない。あやふやな事実でも、大量に集めれば互いに補強しあうことで 「真実味」が増すかのように思わせるのは、本人たちも自覚していないのだろうが、ただの論理的詐術である。ハンコックの本などは、ただの面白いお話にすぎないから、別に害はないだろうが、「陰謀論」 はそうではない。 さらに言うならば、このような論法は、物証も証言もなしに、あやふやな 「状況証拠」 とやらで 「犯人」 を名指しして、「冤罪」 を作り出す論理とも同じである。本文より長い追記: どうやら、ツインタワーの近くに建っていたビルの崩壊を、レポーターが中継で実際より20分ほど早く伝えたということが、「陰謀」 の証拠なのらしい。なんで、そんなことがおきたのかというと、それは、そのレポーターは事前にそうなることを知っていたのか、事前にそう言うようにどこかから指示されていたからなのだそうだ。 こんな馬鹿を言いふらしている人たちは、自分があの現場に居合わせたら、どんな気持ちになるかすら想像できないらしい。あのような前代未聞の大混乱の 「現場」 の中で、事前に手渡された 「でっち上げメモ」 だとかを伝えることができるような、なんの感情も持たない冷徹・非情な人間が、実際にこの世に存在するとでも思っているのだろうか。 現場にいたレポーターが、興奮のあまり、ビルの名前を間違えたとか、言いまわしを間違えたなどと考えるのが、常識というものだろう。それとも、レポーターというものは、どんな場合にも、言い間違いなどせずに、冷静かつ客観的に 「事実」 を伝えうると信じているのだろうか。あほらしくて、つきあいきれない。 こんな馬鹿話を簡単に信じ込むことができる人間は、結局は、どんな馬鹿げた話だって信じ込むようになる。「アポロ陰謀論」 だろうと 「9.11陰謀論」 だろうと、あるいは 「ユダヤ陰謀論」 だろうと 「バチカン陰謀論」 だろうと、そこに違いなどありはしない。ホロコーストに道を開いた 「ユダヤ陰謀論」 者らだって、自分たちは、世界を裏で支配している 「巨大な悪」 と戦っている 「正義の人」 のつもりでいたのだ。 世の中の 「悪いこと」 は、すべて 「悪い人」 らのせいで起きているのだと信じていいのは、「ヒーロー物」 の主人公に憧れる小学生までである。いい年をして、そんなことを信じられるのは、よほどの世間知らずか、いつまでたっても大人になりきれないただの未熟者だ。 「9.11陰謀論」 と 「ユダヤ陰謀論」 とは別の話だなどという言い訳は通用しない。根っことなる発想が同じなのであり、彼らだって、自分たちは確かな 「証拠」 を握っていると信じこんでいたのだから。現に、すでにあちこちで結びつき始めているではないか。 「幽霊の正体見たり、枯れ尾花」 という川柳もあるが、「陰謀論」 に取り付かれた人にとっては、そのような些細な 「言い間違い」 や、単なる偶然の一致なども、すべて 「陰謀」 の証拠になるのだろう。なにごとも、いったん迷路に入り込んだら、すべてがその結論にあうように、解釈されてしまうものである。 こういう 「妄想」 の当否は、饅頭の味のように食べてみればすぐ分かる、というものではないだけに、まったく始末におえない。理屈などというものは、いくらでもつけられるものだ。なにしろ、人間の頭というのは、そういうふうにできているのだから。 歴史を振り返れば、かのスターリン大元帥も、あちらこちらに 「陰謀」 の影を見つける大名人であった。その結果、多数の罪もないかつての同志や一般の市民が処刑され、あるいは、シベリアに送られることになった。ありもしない 「陰謀」 のにおいを、どこにでもかぎつける心性というのは、そういうものなのだ。 そういう心性の本質とくだらなさ、危険性は、いま現に 「権力」 を握っているのか、それとも 「権力」 や 「体制」 に対して、「批判的立場」 なるものをとっているつもりなのか、なんてことには、まったく関係ない。 くだらぬ 「陰謀論」 などに、すぐにかぶれるような人間が、いったん権力を握ったらなにをやるか。それこそ、スターリンがいい手本である。 むろん、そんな心配は無用ではあろうが、まったくもって、歴史の教訓ぐらいは、ちゃんと学ぶべきだろう。 ヒトラーが合法的に権力を握ることができたのも、荒唐無稽な 「ユダヤ陰謀論」 などにいかれた、多数の 「善良」 で 「素朴」 な、自分は正しいと信じこんでいた市民のおかげなのである。 「地獄への道は善意で敷き詰められている」 という有名な言葉は、こういうときのためにある。マルクスが言ったように、「無知がものの役に立ったためしなどない!」 のだから。 追記の追記:「陰謀論」 の話はこれでおしまいにします。まあ、言いたいことはほぼ全部言ってすっきりしたので。それにしても 「無知の知」 という名言を残したソクラテスの時代から、人間というものはちっとも変わっていないのだなと思う、今日この頃であります。人間の本質なんていつの時代も一緒だよ、と言ってしまえば、それまでのことですが。
2007.12.17
コメント(10)
-
「陰謀論」 と 「擬似科学」 あるいはポピュリズムとの親和性
「9.11陰謀論」 の信奉者と、「アポロ謀略論」 の信奉者とは、かなりの部分で重なっているようだ。たしかに、どちらもアメリカ政府による 「謀略」 を主張するという点では、同じ構造をしている。 だが、ほんらい、9.11のような航空機衝突によるビル崩壊という事象にしても、アポロの月への着陸と探査という活動にしても、その検証は、高度の専門的知識と能力、さらには加工された二次資料ではない、大量の一次資料の検討という、気の遠くなるような作業を必要とする (むろん、私はそんな面倒なことはごめんです。それに、そんな能力もありません)。 ところが、このような 「陰謀論」 の信奉者たちは、簡単に手に入る二次資料についての単純素朴な印象と、中途半端な知識に基づいて、「月着陸は捏造だ!」 とか、「9.11はアメリカの自作自演だ!」 などと主張しているように見える。 そこにあるのは、「相対性理論は間違っている」 といった類の、様々な 「疑似科学」 と同様の、生半可な科学知識に基づいた 「専門家」 への不信と批判であり、その底には、5年間の 「小泉政治」 を支えた 「ポピュリズム」 とも共通する心性が見え隠れしている。 そもそも、「専門性」 の否定とは、かつて毛沢東によって主導された 「大躍進」 政策や 「文化大革命」、さらにはカンボジアのクメールルージュ (ポルポト政権) によって進められた 「知識人」 敵視政策の根拠となっていた論理である。 たとえば、50年代の中国の 「大躍進」 では、近代的な製鉄法が否定され、原始的な溶鉱炉 (土法炉) による製鉄が全国民に強要された結果、大量の貴重な鉄製品が溶かされて、なんの役にも立たないただのおしゃかばかりが、山のように生れることになってしまった。 60年代末の 「文化大革命」 を収拾するために取られた 「下放政策」 が、 当時の学生の教育水準を大きく低下させ、社会が必要とする専門家の不足を招いたこと、また70年代のポルポトによる 「知識人」 敵視が、大量虐殺と国民の困窮、さらには長期の内戦という悲劇的な結果を招いたことは、いまさら指摘するまでもないだろう。 世の中には、「専門バカ」 という言葉もあり、たしかにそれに値するような 「学者」 とかもいるかもしれない。しかし、この言葉は、ほんらい自己の狭い 「専門性」 にのみ閉じこもっていて、社会的な常識や責任感が欠如しているような 「専門家」 を揶揄する言葉である。したがって、その 「専門性」 や 「専門的能力」 自体は、否定されるべきではない。 また、たしかに世間には、自己の 「専門性」 をひけらかして素人を小馬鹿にしたり、わざと難解な言葉遣いで、煙にまいて喜んでいるような、品性下劣な 「専門家」 もいるかもしれない。さらに、ときの権力者だとかにすりよっては、彼らに都合のいいことばかりを言っている、「御用学者」 といった者もいるかもしれない。 しかし、いうまでもないことだが、そのようなことは 「専門的問題」 の 「専門性」 そのものを否定する根拠にはならない。それとこれとは、別の話である。 「専門家」 や 「知識人」 を、さしたる根拠もなしに疑ったり、ただこきおろすことで溜飲を下げるのは、ニーチェの言葉を借りるならば、疎外された心情としてのただの 「ルサンチマン」 であり、大西巨人ふうに言えば、たんなる 「俗情」 にすぎない。 ようするに、高度に 「専門的」 な問題に口出しする者には、当然のことながら、それ相応の能力と努力、そして覚悟が要求されるものである。むろん、その程度のことは、自分自身の問題として、「薬害」 や 「食品公害」 といった問題に、真面目に取り組んでいる人々や、そういった経験が少しでもある人たちにとっては、いまさら言う必要もないことだろう。 しかし、昨今の 「謀略論・陰謀論」 の流行を見ていると、どうもそのような 「誠実さ」 が感じられない。むろん、そのような 「陰謀論」 を信じている人の大半は 「善意」 なのかもしれない。しかし、世の中、なにごとも善意だけではかたづかないものである。 ぶっちゃけて言えば、「親ブッシュ・親小泉」 か 「反ブッシュ・反小泉」 かというような、表面的な違いはあっても、非合理的で情緒的、しかも安直だという点では、このような 「陰謀論」 の流行も、「小泉政治」 を支えたのと同じ 「ポピュリズム」 現象にすぎないように見える。 つまるところ、その根底に流れている心性も、多少の差はあっても、同じものにすぎないように思える。「批判」 とは、なによりもまず、自らが持つ偏見や思い込み、独断に対して向けられるべきものである。おのれ自身を疑うことなしに、ただ他人に対してのみ向けられる安直な 「疑い」 の視線など、本来の批判精神や懐疑といったこととはなんの関係もないものだ。 昨今、はやりの 「メディア・リテラシー」 なるものも、まず必要なことは、おのれ自身の知性を磨くことのはずだ。自分を磨くことなしに、多種多様で、しばしば相反するような情報の中から 「真実」 を見抜くことなどできるはずあるまい。自分の趣味や偏見だけで、情報の正邪を見分けることができるならば、誰も苦労しないのだ。 愚にもつかぬ 「猜疑心」 ばかりやたらと発達させて、ただただ、「おれは絶対に騙されないぞー」 とか 「みんな騙されるなよー」 などと、力みかえっていてもしょうがあるまい。「落とし穴」 は、自分の前のほうや自分の外にばかりあるとは限らないのだ。
2007.12.15
コメント(14)
-
「陰謀論」 と 「未開の思考」
アルカイダによる9.11の同時テロ事件が起きてから、すでに6年以上が経過している。この事件がきっかけとなって、ブッシュ政権が 「反テロ戦争」 を旗印にし、アフガニスタンとイラクでの軍事行動を始めたことはむろん言うまでもない。 ところで、この事件については、ブッシュ政権かその周辺のグループによる 「自作自演」 を主張する、いわゆる陰謀論が根強いようである。その根拠としては、この事件に関する公式発表には、様々な 「疑問」 が存在すること。また、この事件をまるで待っていたかのように、アメリカの軍事行動が始められたことなどがあげられているようだ。 こういう論理は別に目新しいものではない。ルーズベルトは世界大戦参加のきっかけを得るために、真珠湾攻撃をわざと見逃したのだ、というような話は昔からあるし、歴史的事実としては、ビスマルクがフランスとの開戦のために起こしたという 「エムス電報事件」 などの例もある。 しかし、ただの電報偽造と、多数の自国民を巻き込む事件の 「自作自演」 とは、いうまでもなく別の話である。戦前の日本の軍部は、出兵の口実を作るために、しばしば大陸で事件をでっちあげたが、さすがに帝都の真中の官庁を自分で爆破するというようなことはしなかった。「9.11陰謀説」 とは、まさにそれに匹敵するような主張なのである。 そもそも、そのような陰謀というものは、旧ソ連や現在の北朝鮮のように、専制的・独裁的な国家で起こることが多い。それはいうまでもなく、そのような国家の支配体制はきわめて閉鎖的な集団によって作られており、国民や報道機関による監視、機密情報の漏洩などの心配をする必要もなく、一方的な情報だけを流すことが可能だからである。 むろん、アメリカの場合でも、諜報機関などが陰謀を企んだことがないわけではない。しかし、かつてのチリやキューバのカストロ政権などに対する陰謀のように、外国でなんらかの事件を起こすことと、国内の、それもニューヨークのど真ん中、あるいは首都ワシントンで、飛行機突入だかビル爆破などという 「陰謀」 を企むこととは、これまた全然別の話である。 つまり、そのような 「陰謀論」 を真面目に主張するには、選挙という 「民主的手続き」 で選ばれた政権担当者やその周辺のグループが、一般の国民 = 民衆とはまったく異なった、爬虫類のように冷血であり、通常の人間には理解不能な心性を持ち、いっさいの秘密も漏らさぬほどに団結した、まさしく異星人のごとき特別な集団だとでも仮定することが、まず前提として必要なのである。 内田樹氏は、『私家版・ユダヤ文化論』 の中で、次のように書いている。 ある破滅的な事件が起きたときに、どこかに「悪の張本人」がいてすべてをコントロールしているのだと信じる人たちと、それを神が人間に下した懲罰ではないかと受け止める人たちは本質的に同類である。 彼らは、事象は完全にランダムに生起するのではなく、そこにはつねにある種の超越的な(常人には見ることのできない)理法が伏流していると信じたがっているからである(そして私たちの過半はそのタイプの人間である)。 だから、陰謀史観論は信仰を持つ者の落とし穴となる。神を信じることのできる人間だけが悪魔の存在を信じることができる。 ある 「結果」 が起きたときに、その 「原因」 はなにかと考えることは、確かに科学的思考の端緒ではある。しかしながら、そのような 「因果論的思考」 が、そのままでつねに科学的なわけではない。 たとえば、リンゴが落ちるのを見て、その原因は万有引力にあるとしたニュートンの思考は科学的だろう。しかし、今の私が 「不幸」 なのはなぜかという問いに対して、それは 「水子のたたり」 や 「前世のむくい」 のせいだ、などという答を出すのは、むろん科学的ではない。 マルセル・モースやレヴィ=ストロースの先輩格に当たる、レヴィ・ブリュルという人の 『未開社会の思惟』 という著書には、次のようなことが書いてある。 まず第一に、死はけっして自然事ではない。これはオーストラリア蛮族、南北アメリカ、アジアの文化度の低い諸部族間に共通な信仰である。 「ムガンダ族の頭には自然的原因による死というようなものはない。病も死もともに、ある精霊の作用の直接的結果である」 「この地方全体を苦しめている最大の災いは呪術の信仰である。アフリカ人は、死をいつも変死であると固く信じている。彼らは二週間前に健康であったものが、病にかかって死に掛けているときには、ある有力な呪者が干渉して病気にかからせ、魔法で生命を絶ちつつあるのだと想像せずにはいられない」 こういう思考が、けっしてそのような 「文化度の低い諸部族間」 に限らないことは、かの 『源氏物語』 を開いても分かるだろう。そこでは、六条御息所という女性が、なんとおそろしくも、生霊となって恋敵に取りついて殺しちゃうのである。 9.11事件のような前代未聞の事件の場合、公式報告に様々な矛盾や疑問がかりに存在したとしても、そのこと自体は、別に不思議でもなんでもない。なにしろ、事件そのものがきわめて異例であり、現場の破壊も検証が困難なほどにすさまじいのだから。そもそも、人間による限られた調査や分析では、間違いや矛盾など、どんな場合にもつきものというものだ。 日本では、そのへんのごく普通の交通事故ですら、しばしばおかしな報告書が作られる。だが、だからといって、そのような交通事故について、「警察の陰謀だ!」 などと大騒ぎする人はいないだろう。そんなものは、たいていの場合、捜査員の思い込みや怠慢、能力不足などのせいにすぎない。 どうも、「9.11陰謀説」 というのには、レヴィ・ブリュルが引用しているような、「未開の思考」 に近いものがあるようだ。人間は、いつでも単純な間違いをしうる存在である。当然ながら、世の中には、たんなる偶然にすぎないこともあるし、様々な偶然、故意、過失、無意識の行為等の重なりによって、誰も意図していない思いもかけぬ結果が生じることもある。 そういった可能性を考慮せず、ありとあらゆるところに、誰かの 「陰謀」 などといった 「架空の原因」 を見つけなければ納得できないというのは、まさにあらゆる 「死」 の理由に誰かの 「呪い」 を想定してしまうことと同様の 「未開の思考」 というべきだろう。 「9.11陰謀説」 に、なにか検討に値する問題があるとすれば、それは、そのような説そのものではなく、むしろ、なぜそのような陰謀説が、現代社会において一部の人間の心を強く捉えて離さないのか、ということのように思える。 つまり、それは肥大した強力な現代の 「国家」 や、その支配層と目されている人たちに対して、激しい疎外感や無力感を抱いている人たちが、アメリカにおいて少なからず存在しているということを表しているのだろう。しかし、そのような 「陰謀論」 は、ブッシュ支持者らが信奉している、世界中に広がる 「イスラム原理主義者」 によるテロの 「陰謀」 という論理とも、きわめて似通っているように見える。 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20080125/1201204697
2007.12.13
コメント(11)
-
public という概念について
英語の単語で日本語に訳しにくいものに、public という言葉がある。一般には 「公」 とか 「公共」 とか訳されるのだが、どうもしっくりしない。辞書をひくと、「社会」 とか 「世間」 といった訳語ものっていて、たぶんこっちのほうが本来の語感に近いのだろう。 たとえば、public domain という言葉がある。例をあげれば、著作権や特許権で保護されていない、誰もが自由に利用できる技術や情報などを、public domain に属するという。また public knowledge は、普通 「公知」 などと訳されているが、これも同じように、特定の個人や団体が独占しているのではない、広く一般に知られた知識のことを意味する。 ところで、public の反対は private である。一方、「公」 の反対は 「私」 である。であるから、public は 「公」 に対応し、private は 「私」 に対応する。ここまでは、たぶん誰からも異議は出ないだろう。 ところが、日本語には 「公」 と 「私」 という対語のほかに、「官」 と 「民」 という区別もある。むろん、英語の public も、「民」 に対する 「官」 という意味で使われることもある。だが、一般的な語感としては、むしろ 「社会一般に開かれた」 という意味のほうが強く、そのように使われる場合のほうが多い。 たとえば、public company とは公営企業のことではなく、純然たる民間企業、ただし、株主を広く一般から募集する 「株式公開会社」 のことを指す。つまり、「公」 とは けっして 「官」 のみに限定されないのであり、それだけでなく、ときには 「官」 をも規制する、「官」 よりもはば広い概念として理解されている。 しかし、日本語で 「公」 といった場合、どうも単純に 「官」 と等置されやすいようだ。必ずしもそうではないと頭では理解している人であっても、「公」 という言葉には、なにかそのような響きがあることは否定できないだろう。こういう言葉のずれの背景には、「公」 という言葉がもともと朝廷を指す言葉であったという語源的な事情もあるのだろうが、おそらくそれだけではない。 ここで話はいささか飛躍するが、そもそも近代国家というものには、「公」 を 「官」 すなわち 「国家」 が独占するという傾向がある。そのような傾向は、とりわけ「近代社会」 がそれまでの歴史の中から自生的に発達してきたのではないこの国では、特に強いようだ。 そのそもそもの始まりは、明治国家によって、社会に対し強引に上から一元的な統制がかけられたことにあるのだろう。そこでは、官とはつまり 「お上」 のことであり、「公」 の問題というものは、すべてそのような 「官」 に任せるべきことなのである。 そしてそのような 「官」=「公」 という意識は、戦後社会の否応なしの近代化によって、それまで存在していた様々な自生的秩序の崩壊が進行してきたことで、下からも支えられ、かえって強化されてきたようにすら思える。 そこでの意識の違いはせいぜい、かつては 「官」 とは 「ははーっ」 と無条件でひれ伏す対象であったのに、現代では逆に、お客様としてあれこれと文句をつけ要求する対象であるということの違いにすぎない。どちらにしても欠けているのは、「民」としての 「社会」 そのものが、ほんらい public としての 「公」 なのだという意識である。 そもそも、社会全体から切り離されて、自立化した 「官」 とは、実際にはそれ自体一つの 「私」 にすぎない。政治家や官僚の腐敗とは、そういうものである。同時に 「公」 としての意識を持たない 「民」 とは、たんなる無責任な 「私」 の集合でしかない。 とはいえ、もともと英語での public に当たるような概念が、けっして日本に存在しなかったわけではない。「世間」 という言葉がそうだ。本来、「世間に顔向けができない」 というような言い回しは、自分や自分の家族、仲間内だけでない、広い社会一般に対する責任意識のようなものを表していたはずだ。 しかし、昨今の 「世間」 とは、むしろ愚にもつかぬ 「正論」 と匿名の 「正しさ」 によって、気に障る個人を押しつぶしたり、たまたま明るみに出たつまらぬ 「事件」 で大騒ぎしているだけの、裸の 「私」 の集まりでしかないように思える。そこでは、叩かれている者と叩いている者のどちらをとっても、public という意識が欠けていることでは大差ないように見える。
2007.12.11
コメント(2)
-
夢からさめてもまだ夢の中
ロシア土産の定番に、マトリョーシカ人形というものがある。ボーリングのピンのような形をしていて、かぱっと割ると中から小さな人形が現れ、それを割ると、また中からさらに小さな人形が出てくるという仕掛けになっている。実物を手に取ったことはないが、だいたい4個か5個ぐらいの人形がだんだん小さくなりながら、中に納められているのだそうだ。 見るからに大金が詰まっていそうな大きな金庫の扉を開けてみたら、また中に扉があって、それを開けてみたらまた扉があってとか、金銀財宝ざあくざくと期待しながら大きなつづらを開けてみたら、その中にまた小さなつづらがあって、それを開けてみたらまたさらにつづらがあって、みたいなのも似たような話である。 たとえば、夢の中で夢を見る夢を見ている人が現実世界に戻るとすれば、まず夢の中で、夢からさめる夢を見なければならないということになるのだろうか。さすがに、それは分からないが、夢からさめたと思ったら、実はまだ夢の続きだったというぐらいのことは、なんとなく何度かあったような気がする。 おやおや、なんだかでだしから、わけの分からぬ展開になってしまった。 「人間は考える葦である」 と言ったのはパスカルだが、人間の行為というものは、すべて多かれ少なかれ、 「意識」 すなわち 「主観性」 という呪いに取り憑かれている。当たり前のことだが、「パブロフの犬」 のような、たんなる反射だけで説明できるのは、熱いものに触れたら手を引っ込めるとか、なにかが飛んできたら身を避けるといった単純な行動にすぎない。むろん、イヌだって、ただの反射だけで生きているわけではないだろうが。 だから、この場合、「意識」 とは、刺激に対する生体の反応の 「遅延」 のことであり、一定のずれのようなものと言うことができる。しかし、逆を言えば、そのように刺激と反応との間に、意識 = 思考というなにやら余計なものが介在することで、人間は他の動物とは違って、直接性という制約から逃れること、つまりは些少なりとはいえ、自由を手に入れたのだろう。 人間は、意識によって現実を把握し理解するものである。そのかぎりで、意識には現実が反映されるものだ。もし、そうでなく、意識の内容がすべてただの妄想にすぎないとすれば、生物としてはまったくひ弱な人間は、とうの昔にトラやライオンにみんな食われて滅んでいたはずである。 とはいえ、意識は鏡のように対象をただ反映するわけではない。意識というメモリにはそれだけの容量はないだろうし、だいいち、そのように対象をそのまま反映した意識などというものは、ただ現実を二重化しただけの、屋上屋を重ねたようなものにすぎず、なんの役にも立ちはしない。 結局、人間が 「考える葦」 であるかぎり、そこにはつねに一定の 「幻想」 としての 「観念」 が伴うものなのだ。そのような幻想は、良くも悪くも、人間のあらゆる生活過程の中から必然的に発生してくるものであり、そのすべてを否定し禁じることは、人間に対して、ただのロボットになれと要求することと同じである。 であるから、このような 「幻想」は、ただ目をつぶれば消えてなくなるようなマボロシなのではない。「幻想」が 「幻想」 として成立し、社会の中で一定の現実として流通し、しばしば大きな力を持っていることじたいは、けっして 「幻想」 ではない。 世の中の 「イデオロギー的構築物」 といわれているものは、すべてそういうものである。ある観念が 「イデオロギー的構築物」 であることが暴露され、かりにみながそのことに納得したからといって、そのような観念=幻想が、いきなりある晴れた日の朝のように雲散霧消し、「現実世界」そのものが裸の姿でたち現れてくるわけではない。 人間が大昔から 「イデオロギー」 などというわけの分からぬものを生み出し、そのためにしばしば自分で自分を縛り苦しめてきたのは、言い換えれば、人間が人間であることの証明なのであり、ようするに人間が自由を得たことの代償なのである。 ただ、人間とはそのような幻想的な観念を日々生み出し、多かれ少なかれ、そのような観念に取り憑かれながら生きざるを得ない生き物だということを自覚することは、たしかになんの腹の足しにもならぬとしても、少なくとも、そのような観念のために無駄に苦しんだり、妄想じみた観念の虜になることへの、予防薬や解毒剤としての役割ぐらいはするだろう。 「おとな」 になるということは、たぶんそういうことでもあるはずだ。先の首相は、どうやら元気を回復したようだが、前の失敗から少しはなにかを学んだのだろうか。テレビで見る限り、どうもそういうようには見えなかった。
2007.12.09
コメント(6)
-
沙翁・奈翁って誰のこと
『論語』 によると、かの孔子様は30で立ち、40で惑うことがなくなり、50で天命を知ったのだという。さすがに、孔子様は釈迦やソクラテスと並んで、世界の 「三大哲人」 と呼ばれるだけあって、われわれ凡人とはずいぶんと違うものである。 世間では、40歳になると 「私もとうとう不惑になりました」 などと、軽々しくいう者も多いようだが、そもそも、これはあくまで孔子様の 「自分語り」 なのであるから、凡人が同じように使ってよい言葉ではない。 さて、明治の書物には、しばしば沙翁・奈翁なる人物が登場する。まるでかぐや姫を竹の中から発見して育て上げた竹取翁のような名前であるが、沙翁とはかのシェークスピアのことであり、奈翁とはフランスの英雄ナポレオンのことである。 このような言葉を誰が最初に使い出したのかは判然としないが、沙翁のほうは、ひょっとすると、彼の戯曲を精力的に翻訳・紹介した坪内逍遥なのかもしれない。 年譜によれば、シェークスピアもナポレオンも、ともに亡くなったのは52歳のときである。であるからいずれも、かの信長のおはこだった 「敦盛」 でいう、「人間わずか50年」 をようやく越えた年齢にすぎない。 たしかに、「人間わずか50年」 とすれば、50を越えた人が翁と呼ばれるのもしかたないかもしれない。だが、これはあくまでも二人が死んだ歳であって、実際に活躍したのはもっと若い頃なのであるから、やはり翁と呼ぶのはいささか奇妙な感じである。 ナポレオンについては、「那破烈翁」 という表記もあるので、これを縮めた可能性もある。ただし、そうだとしても、最後に翁の字を使うのはやはり奇妙である。それとも、歴史上の偉大な人物ということで、年齢にあまりこだわらずに、尊敬の意をこめて意図的に 「翁」 という字を使ったのだろうか。 この奈翁という言葉が使われている例としては、たとえば次のような文がある。 そは奈翁が雀が丘に立ちて莫斯科(もすくわ)を眼下に眺むるの画なり。佛蘭西兵士は銃剣のさきに帽を振りまわして万歳を叫び、奈翁は例のナポレオン帽に大外套、眼鏡持ちし手を背後に組み、黙然と莫斯科を眺む。 莫斯科は夢の如く眼下に隠見し、しかしてなんの煙にやあらん一団の蓬々たる者、斜に奈翁を掠めて、全体の画に「夢」の感を与ふ。エレスチヤギンの命意いかんを知らざれど、生は髣髴としてここに勝つの哀しみ、即ち勝利の悲哀を認めぬ。 これは、小説 『不如帰』 や大逆事件を論じた 『謀叛論』 で知られる徳富蘆花が、1906年、つまり日露戦争のあとの、講和条約への不満が世間一般にいまだ残っていた中で、当時の第一高等学校で行った、「勝利の悲哀」 と題された演説の一部である。 上に出ているエレスチヤギンとは、蘆花によれば、ロシアの反戦画家であり、日露戦争では、旅順艦隊の旗艦ペトロパウロスクに乗り込み、日本海軍が港に敷設していた水雷に船が触れたため、船もろともに海に沈んだとのことである。 蘆花が描写している、ナポレオンのモスクワ戦役図を描いたのが、まさにそのエレスチヤギンという人らしいが、それにしてもこの時期、ナポレオンは40歳をわずかに数年こえたばかりのはずである。しかし、奈翁などと書かれると、まるで白いおひげのおじいさんのような感じが、どうしてもしてしまう。 それはともかく、明治の人らにとって、40代、50代という年齢の意味が、今のわれわれとはずいぶんと異なっていたことだけは、多くの人が指摘しているように間違いないだろう。当時の人々にとって、40代とはすでに立派に成熟した人間を意味していたはずである。 であればこそ、当時の人々は、シェークスピアやナポレオンのような50歳そこそこの人の呼び名に、翁という字をつけても、いささかも怪しがることがなかったのかもしれない。 実際、維新の三傑に数えられ、西南戦争で敗死した西郷隆盛も、死後にしばしば 「南州翁」 などと呼ばれているが、その一生は50年にも満たない。ついでにいうと、ロシア革命で政権を取ったときのレーニンも、頭こそはげていたがまだ47歳である。 ひるがえって現代を見るならば、先の首相は50歳を越えていたにもかかわらず、人間的な未熟さをさらけだしまくりであった。 年長者を敬い、長老をたてるのはもちろん悪いことではない。しかしながら、「やっぱり、せめて60は過ぎてないと首相は務まらないよね」 というのは、やはりいささか問題ではないかという気はする。 ちなみに、ナポレオンを打ち破った、当時のイギリス首相ウィリアム・ピット(通称 小ピット)という人が、最初に首相の座についたのは、弱冠24歳のときだったそうだ。なんと、今の杉村太蔵君よりも若い歳である。むろん、太蔵君に首相になってもらっては困るけれど。
2007.12.06
コメント(6)
-
レーニンについてのちょっとした思い付き
レーニンが 『なにをなすべきか』 で展開した、いわゆる 「外部注入論」 というものは、今日でははなはだ評判が悪い。中には、この理論は理論を独占したインテリゲンチャによる大衆支配を正当化するものだ、などという見当外れの批判すらあるぐらいだ。しかし、レーニンは本当にそんなことを言ったのだろうか。 『なにをなすべきか』 という本は、一般に前衛党の組織論を定式化したものとして読まれている。しかし、そこで定式化されている組織論は、政治活動や結社の自由がまったくといっていいほど存在しなかった、帝政ロシアという時代状況と密接に関連しているのであり、そのためにやむを得ず、彼の主張は、いささか上意下達という性格の強い秘密主義的で厳格な組織という形を取らざるを得なかったのだ。 したがって、この本の中で同時に提起されている、「外部注入論」 の問題と民主集中制という 「組織論」 の問題とは、別個の問題として分けなければならない。一般に、通俗的なレーニン批判者は、この二つをいっしょくたにすることで、レーニンを権威主義的で独裁志向の強い権力亡者として描いているのだ。 さて、そもそも 「外部注入論」 と呼ばれているこの論理は、ドイツ社会民主党の理論家であったカウツキーから受け継がれたものであって、上の本でも、レーニンは次のようなカウツキーの一文を引用している。 社会主義的意識は、プロレタリアート的階級闘争の必然の、直接の結果であるかのように見える。だが、これは間違いである。・・・ この両者は、一方が他方から生れるものではなく、並行的に成立するものであり、またそれぞれ違った前提条件のうえに成立するのである。近代の社会主義的意識は、ただ深遠な科学的洞察をもととして始めて成立しうるものである。・・・ ところで、科学の担い手は、プロレタリアートではなく、ブルジョア・インテリゲンチャである。近代社会主義も、やはりこの層の個々の成員の頭脳に生まれ、彼らによってまずはじめに知能のすぐれたプロレタリアたちに伝えられ、ついで、これらのプロレタリアが、事情の許すところで、プロレタリアートの階級闘争のなかにそれを持ち込むのである。 だから、社会主義的意識は、プロレタリアートの階級闘争のなかへ外部からもちこまれたあるものであって、この階級闘争のなかから自然発生的に生まれてきたものではない。 つまり、ここで問題になっていることは、「社会主義的な意識」 は自然発生的なプロレタリアートの闘争から、直接には成長し得ないということのみであり、したがってインテリゲンチャか労働者かということが、本質的な対立であるわけではない。 考えてみれば、インテリゲンチャにとっても、カウツキーのいう 「社会主義的意識」 なるものは、ある日突然天から降ってきたわけではない。つまり、その点ではインテリゲンチャが属する中産階級であろうと労働者であろうと、同じことである。 ただ、当時のヨーロッパ、とりわけロシアのように、社会全体の教育水準がきわめて低い国では、普通の労働者にはそのような 「科学的洞察」、すなわち知識や理論に触れる機会がなかなかなかったため、そのような役割はインテリゲンチャに限定されていたというだけのことなのだ。 実際、レーニンはこうも言っている。 もちろんこれは、労働者がこれをつくりあげる仕事に参加しないということではない。ただ彼らが参加するばあいには、労働者としてではなく、社会主義の理論家として、つまりプルードンやワイトリングのような人間として参加するのである。 いいかえれば、彼らが、多少ともその時代の知識を持っていて、この知識を前進させることができるときにだけ、またそのかぎりでだけ、参加するのである。 レーニンが言っていることは、つまりはこういうことだ。 すなわち、労働者が (あるいは一般に差別されている人、抑圧されている人などであってもよい) 理論や政治という舞台に参加する場合には、自分たちが直接の当事者として巻き込まれている 「現場」 からいったん離れて、直接の当事者としてではない、より一般的で客観的な立場へと移行することが必要だということだ。 ここでのレーニンの論理は、社会の中で自分は不当に差別されている、抑圧されているなどと感じている人たちがしばしば陥りやすい誤り、すなわち、おれたちこそが問題を正しく認識しているのだ、といった類の、悪しき 「当事者主義」 とでもいうべき素朴な論理とは明確に異なっている。 つまり、レーニンがここで言っていることは、労働者に対して、現場での不満をただぶちまけるだけの 「こども」 ではなく、社会全体を客観的かつ冷静に広く見渡すことのできる 「おとな」 になれということなのである。たんに問題の指摘に留まらず、問題の解決を志向するならば、こういうことはいつの時代でも必要な条件である。 カウツキーやレーニンが考えていたような 「社会主義的意識」は、おそらく現代の社会に対して、そのままの形では通用しないだろう。また、このようなレーニンの要求は、現実に対して、いささか過大な要求なのかもしれない。しかし、このようなレーニンの問題の立て方自体は、けっして古びていないし、普遍的な一般性を持っているように思う。 おお、今日はひさしぶりに、思いっきり左巻きのことを書いてしまった。
2007.12.05
コメント(10)
-
無敵の人々
タイトルをつけてから、しばし考えた。この言葉は、いったいどこからどのようにして、わが脳髄にいたり来たったのであろうか。 しばしの沈思黙考をへて浮かんだのは、かのドストエフスキーの 『貧しき人々』 と、10数年前になくなったイタリアの作家アルベルト・モラヴィアの処女作 『無関心な人々』 であった。あと、やや長いのであれば、戦前に書かれた葉山嘉樹の 『海に生くる人々』 なんてのもある。ただし、これは名前しか知らない。 ところで、タイトルの 「無敵の人々」 という言葉であるが、これは必ずしも 「負けない」 人たちという意味ではない。おやおや、「無敵」 ということは 「負けない」 ということと同じではないか、という異議がちらほらと聞こえてきそうであるが、とりあえず今はそういうことにしておく。 さて、ウェブ上を毎日のように散歩している方々は、おそらくあちこちの掲示板だとかブログのコメント欄とかで、延々と果てしない議論を展開している人らの姿を見かけたことがあるだろう。Wikipediaによると、とくに他人のブログのコメント欄で、こういう議論の展開をもっぱらのこととしている人らのことを 「コメンター」 と言うらしい。 最初、この言葉は 「アムラー」(ちと古いが)とか 「マヨラー」 とかいう類の、いわゆる和製英語ではないのかと思ったが、英和辞書にもちゃんと載っていたからそういうわけでもないらしい。以下は、そのWikipediaからの引用である。コメンターとは、いわゆる「コメンテーター」とは異なる概念で、ブログの進化に伴って出現した人種のことを指す。広義には、ブログにコメントを寄せる人のことをも含有しているともいえるが、一般的には、自分ではブログを開設せず(若しくは更新せず)、もっぱら他所のブログにコメントする人のことを指す。別名 「穴掘り人」。中には、特定の記事のコメント欄に住み着いて個人的な 「ブース」 のようなものを構築し、あたかもそこの主であるかのように振舞うコメンターも存在する。このようなコメント欄は 「コメント穴」 と呼ばれ、ここにコメントを投稿することを 「穴掘り」 などと称する。 上のWikipediaの説明に追加すると、中には、ブログ主に対する保護者だか庇護者だかにでもなったつもりなのか、そこへ異分子 (むろん彼にとってのだが) が登場すると、ブログ主に頼まれたわけでもないのに、ねちっこくからんだり嫌みを言ったりして、排除にかかる人もいるようである。そういう人にとっては、どうやらウェブにも 「縄張り」 というものが存在するらしい。 少し話がずれたようなので、元に戻そう。ウェブ上でやたらと議論を展開したがる人たちの中には、たとえば次のような特徴を持っている人たちがいる。議論の中身ではなく、肩書や体験 (そもそも、こういうものは本当かどうか確認のしようがないのだが)、あるいはちょっとした言葉や語調などで、ことさら相手に対する優越感を示し、やたらと相手より上に立とうとする人議論に行き詰ると、前の論点をむしかえしたり、巧妙に話をずらしたり、あるいは揚げ足をとったりして、延々と議論をやめない人たいした論拠もないのに、「あなたの主張は論破されました」 とか、「私の論点の正しさは証明ずみです」 などという断定的口調を用いる人 こういう人に出会うと、たいていの人は辟易して引き下がるものである。なにしろ、この手の人は、どういうわけだか議論でのスタミナだけは抜群なのであり、そんな人を相手にするのは、リアルな世界でも生きている普通の人にとっては、時間と労力の無駄でしかないのだから。 その結果、このような人は、相手の退散をもって自己の勝利とみなし、勝利の雄たけびをあげ、次から次へと論敵を葬り去り、次から次へと勝利を重ねていくのである (むろん、彼にとってのことだけだが)。 議論というものは、陸上競技や競泳種目とは違って、時間や飛距離などの物理的尺度で客観的に勝ち負けを決めることは困難なものである。であるから、本人がそのことを自覚し、あるいは承認しない限り、決着がつかないものである。矛盾や撞着を指摘されても、面の皮が厚い人にとっては、「そんなのかんけーねー」 なのである。 こういう人たちは、いわば 「マトリックス」 の中の人のように、自分で自分にプラグをつけているのであり、すべての現実が彼自身にとって都合のいいように解釈されてしまうのである。であるから、このような人はけっして負けることがない、というよりも、正確にいうならば、「負け」 というものを認識できないのであり、まさにその意味において 「無敵」 なのである。 おそらく、今日もまた、このような人たちは、広大なウェブ空間のどこかで、「あなたの主張は論破されました」 と、勝利の凱歌をあげていることだろう。「君子危うきに近よらず」 という言葉があるが、できることならば、こういう人種とはあまり関わりたくないものである。
2007.12.03
コメント(19)
全17件 (17件中 1-17件目)
1