全て
| カテゴリ未分類
| 生活をよくする
| 本の紹介
| 共に生き、共に育つ
| たのしいべんきょう
| 個人的な日記
| 体育
| 音楽♪
| 道徳 等
| 問題解決
| 考え方
| 話し合い・話す・聞く
| 特別支援教育
| 小学校
| 阪神間 地域情報
| PC・デジタル関係
| 教材・教具
| 食育(自立生活・家庭科)・園芸
| 仕事術
| 旅行(温泉含む)
| 英語学習
| 環境保護・エコ
| 作文・書くこと・漢字
| よのなか(社会)
| いのち
| 人間関係・コミュニケーション
| 子育て
| 地震・防災
| 算数
| 心理・カウンセリング・セラピー
| 読む・音読・朗読
| エクセルでのプログラミング
| 北播丹波 地域情報
| 教員免許
| 教育改革
| 休校期間お役立ち情報
| 映画 等
| 創造性をはぐくむ
| プレゼン
| 通級
| 健康
| ゲーム
テーマ: 障害児と生きる日常(4490)
カテゴリ: 共に生き、共に育つ
障害者週間は昨日まででしたが、人権週間は今日までです。
人権週間に合わせて本を紹介しておりましたが、本日が最後です。
(前回の日記は こちら 。)
前回までの「 インクルーシブ教育 」に関する本の流れの最後として、日本全国から様々な学校種の「インクルーシブ教育」の具体的実践報告をまとめた本をご紹介します。
タイトルはズバリ、 『地域の学校で共に学ぶ』 。
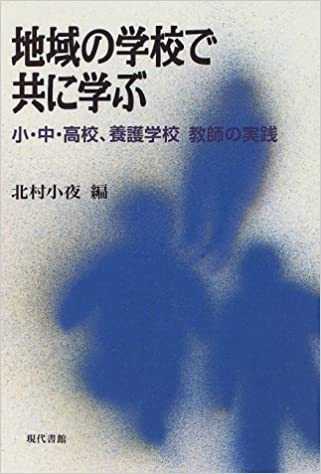
『地域の学校で共に学ぶ 小・中・高校、養護学校教師の実践』
(北村小夜、現代書館、1997、税別2500円)
1997年の発行なので、23年前です。
それだけニーズがあるということでしょうか。
23年前ですので、当然今とは学校の状況も違っています。
しかし、この本の中で報告されている「インクルーシブ」な取組の具体は全く色あせません。
小学校の先生方、中学校の先生方、高校の先生方、当時の「養護学校」の先生方、保護者の方々、それぞれの立場から非常に具体的な報告が出されています。
平成19年に「特別支援教育」が制度化されたときに、「ライフステージをまたいだ支援の連続性」といったことが謳われていたかと思うのですが、この本を読むことで、まさに、「障害」のある1人の子どもが、小学校を出て、中学校を出て、高校はどうするのか、「地域の学校で共に学ぶ場合」を念頭に、イメージを持つことができます。
こういう報告は、具体的であればあるほど、面白いし、勉強になります。
その理由の大きなところは、子どもたちの生の声を取り入れて報告されるところにあります。
「障害のある子もない子も、共に学ぶ」ということは、きれいごとだけでは済まされません。
そこには子どもたちのストレートな反応があり、議論があり、葛藤があり、いざこざやもめごと、すんなりとはいかないあれこれがあります。そこのところこそが、「共に学ぶ」ことを考える上で、一番大事なところではないでしょうか。
理想論ではなく、子どもたちの中で実際にやってみようとして、どうだったか。
実際の話だからこそ、そこから学ぶことは、山ほどあります。
「話し合いは勉強より勉強になる」 (p56)
と言ったそうです。
僕は、この気持ちが痛いほどよく分かる気がします。
本当の勉強というものは、教科書には書いていない。
子どもたちが子どもたちの中から見つけていくものだ、と思います。
今こそ、こういった本を読み、子どもたちの言葉の1つ1つに学びたいと思います。
先ほど引用した子どもの台詞の前には、
====================
もっともめさせようと、「でものり子と一緒に生活したらいろいろ困ることあるやろ」と返してみる
(p55)
====================
という先生の姿が書かれています。
子どもたちの本音を引き出すために、きれいな言葉ばかり言う子どもたちに、あえて返された言葉です。
今、こういう先生がどれだけいるでしょうか。
僕は、これを読んで、
もめたらあかんのやない。
ひょっとしたら、もめへんほうが、あかんのやないか?
と思い、今までの考え方を反省させられました。
(本書の中の子どもたちの素直な言葉に影響されて、関西弁になってしまいました。ご容赦ください。)
また別の報告の中で、ある小学校の先生は、入学式の時、保護者の方々を前に、次のような話をされています。
====================
「これからの社会は共に生きる社会、やさしい言葉で言えば『ごちゃまぜの社会』が必要となってきます」
(p68)
====================
ご自身の言葉で入学式の保護者の方々を前に、「共に生きる社会」「ごちゃまぜの社会」の大切さを訴えられる先生、ステキだと思います。
「インクルーシブな社会」と言われても、言葉の意味を正しく知っている人はほんのわずかかもしれません。
「ごちゃまぜの社会」という言葉のほうが、「インクルーシブ」なんていうカタカナ語を使っちゃうより、分かりやすくていいかもしれない!
と思いました。
この本には、本当に、いろいろな子どもたちが登場してきます。
その行動も細かく報告していただけるので、「そういうことがあるんだ」と初めて分かることがいっぱいです。
全盲のお子さんは、自分の机に貼ってある点字シールだけでなく、他の子の机に貼ってある点字シールも手がかりにして移動していました。(p74)
こういったところからも、障害のある子だけに何かを用意するのでは、その子が社会で生きていくためには全く不十分ではないか、社会全体に何かを用意するという視点が必要なのでは、ということを考えさせられました。
さて、「インクルーシブ教育」の取組は地域ごとの差が大きいと思われますが、23年前の時点で大阪府豊中市の状況は特に驚くべきものでした。
本書の中の報告で 「私の勤務している蛍池小学校のやっていること」 として紹介されていることは、今の最新の「 新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議報告(素案) 」をさらに先取りしているところもあると思いました。
箇条書きで7つ紹介されていましたが、1つめが、
「・籍は普通学級(原学級)と障害児学級の両方に置く(二重在籍)が、すべての時間を原学級で生活する。」 から始まるのです。
これは、1文で短く書いてありますが、実現するのは並大抵のことではありません。というか、ほとんど不可能なことのように僕などには思えます。
その後も、子どもたちが可能な限り共に過ごすために実施されていることが書かれており、圧倒されました。こういう学校も日本の中にはずいぶん前から存在していたのですね。
翻って、現在文部科学省のサイト内で閲覧できる「 新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議報告(素案) 」の中には、
「障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に教育を受けられる条件整備」
「通常の学級に特別支援学級の児童生徒の副次的な籍を導入し、ホームルーム等の学級活動や給食等については原則共に行うこととすることが必要である。」 といった文言が含まれています。
これでもかなり先を行った提案だと思うのですが、豊中はかなり先を行きすぎているような印象です。
さてさて、この調子で書いていたら全然終わらないので、ちょっと間をすっとばして、高校についても少し書いておきます。
「障害」のある生徒が高校で勉強する場合を考えたとき、大変気になるのが「評価」のことです。
そこにも一言では言えないすったもんだがあるのですが、いろいろなすったもんだの末に高校の先生はこう書かれています。
====================
・彼らの存在が学校を変えていったことがある。
最も大きいことは、単位認定・評価のあり方である。
彼らに対して「1年間の生活を通して(学校生活に限らず)どんな小さなことでも発達(進歩)を見過ごさないようにして、良いところを見つけ出し、そのことを評価する」ことが全教職員のものとなった。そのことは、他の一人ひとりの生徒に対しても広がりをみせ、点数で単位不認定が機械的にされることをなくしていった。
(p284)
====================
「点数で単位不認定が機械的にされる」というのは、ともすればこれまでは当たり前のように感じていました。しかし、1人の生徒を人として誠実に評価しようとしたとき、そういった機械的な判定はされなくなっていったことを知り、「障害」があっても評価され学び続けられるという希望を抱くことができました。それこそ、ここに至るまでの粘り強い取組の過程は、想像もできないものがあったと思います。しかし、結果としてこのようなカタチに結びついていったことを知らせてもらえるだけでも、「障害」のある子の高校教育について、希望が持てました。
最後に、「養護学校」の先生方からはどんな報告が出されているかというと、これもまた、貴重なのです。「地域の学校」では当たり前であることが当たり前ではない状況を知り、僕は非常に衝撃を受けました。しかし、それを変えていこうとされている先生方がいることに、勇気をもらいました。
例えば、「 地域の小学校で使っている検定教科書で、みんな一緒に授業をしようと思いました。 」(p337)という先生。積極的に地域の中で生きることを念頭に置いた活動を続けられる中で、「 障害者手帳で切符を買うのに30分もかかっていた駅も、出かけるたびに駅員の対応が変わり、徐々にですがエレベーターやエスカレーターがついていきました。 」(p342)というような社会の側の変化も見られていったことに、深い感動を覚えました。
人権週間に合わせて本を紹介しておりましたが、本日が最後です。
(前回の日記は こちら 。)
前回までの「 インクルーシブ教育 」に関する本の流れの最後として、日本全国から様々な学校種の「インクルーシブ教育」の具体的実践報告をまとめた本をご紹介します。
タイトルはズバリ、 『地域の学校で共に学ぶ』 。
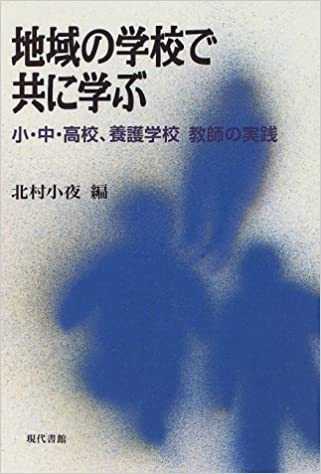
『地域の学校で共に学ぶ 小・中・高校、養護学校教師の実践』
(北村小夜、現代書館、1997、税別2500円)
1997年の発行なので、23年前です。
それだけニーズがあるということでしょうか。
23年前ですので、当然今とは学校の状況も違っています。
しかし、この本の中で報告されている「インクルーシブ」な取組の具体は全く色あせません。
小学校の先生方、中学校の先生方、高校の先生方、当時の「養護学校」の先生方、保護者の方々、それぞれの立場から非常に具体的な報告が出されています。
平成19年に「特別支援教育」が制度化されたときに、「ライフステージをまたいだ支援の連続性」といったことが謳われていたかと思うのですが、この本を読むことで、まさに、「障害」のある1人の子どもが、小学校を出て、中学校を出て、高校はどうするのか、「地域の学校で共に学ぶ場合」を念頭に、イメージを持つことができます。
こういう報告は、具体的であればあるほど、面白いし、勉強になります。
その理由の大きなところは、子どもたちの生の声を取り入れて報告されるところにあります。
「障害のある子もない子も、共に学ぶ」ということは、きれいごとだけでは済まされません。
そこには子どもたちのストレートな反応があり、議論があり、葛藤があり、いざこざやもめごと、すんなりとはいかないあれこれがあります。そこのところこそが、「共に学ぶ」ことを考える上で、一番大事なところではないでしょうか。
理想論ではなく、子どもたちの中で実際にやってみようとして、どうだったか。
実際の話だからこそ、そこから学ぶことは、山ほどあります。
「話し合いは勉強より勉強になる」 (p56)
と言ったそうです。
僕は、この気持ちが痛いほどよく分かる気がします。
本当の勉強というものは、教科書には書いていない。
子どもたちが子どもたちの中から見つけていくものだ、と思います。
今こそ、こういった本を読み、子どもたちの言葉の1つ1つに学びたいと思います。
先ほど引用した子どもの台詞の前には、
====================
もっともめさせようと、「でものり子と一緒に生活したらいろいろ困ることあるやろ」と返してみる
(p55)
====================
という先生の姿が書かれています。
子どもたちの本音を引き出すために、きれいな言葉ばかり言う子どもたちに、あえて返された言葉です。
今、こういう先生がどれだけいるでしょうか。
僕は、これを読んで、
もめたらあかんのやない。
ひょっとしたら、もめへんほうが、あかんのやないか?
と思い、今までの考え方を反省させられました。
(本書の中の子どもたちの素直な言葉に影響されて、関西弁になってしまいました。ご容赦ください。)
また別の報告の中で、ある小学校の先生は、入学式の時、保護者の方々を前に、次のような話をされています。
====================
「これからの社会は共に生きる社会、やさしい言葉で言えば『ごちゃまぜの社会』が必要となってきます」
(p68)
====================
ご自身の言葉で入学式の保護者の方々を前に、「共に生きる社会」「ごちゃまぜの社会」の大切さを訴えられる先生、ステキだと思います。
「インクルーシブな社会」と言われても、言葉の意味を正しく知っている人はほんのわずかかもしれません。
「ごちゃまぜの社会」という言葉のほうが、「インクルーシブ」なんていうカタカナ語を使っちゃうより、分かりやすくていいかもしれない!
と思いました。
この本には、本当に、いろいろな子どもたちが登場してきます。
その行動も細かく報告していただけるので、「そういうことがあるんだ」と初めて分かることがいっぱいです。
全盲のお子さんは、自分の机に貼ってある点字シールだけでなく、他の子の机に貼ってある点字シールも手がかりにして移動していました。(p74)
こういったところからも、障害のある子だけに何かを用意するのでは、その子が社会で生きていくためには全く不十分ではないか、社会全体に何かを用意するという視点が必要なのでは、ということを考えさせられました。
さて、「インクルーシブ教育」の取組は地域ごとの差が大きいと思われますが、23年前の時点で大阪府豊中市の状況は特に驚くべきものでした。
本書の中の報告で 「私の勤務している蛍池小学校のやっていること」 として紹介されていることは、今の最新の「 新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議報告(素案) 」をさらに先取りしているところもあると思いました。
箇条書きで7つ紹介されていましたが、1つめが、
「・籍は普通学級(原学級)と障害児学級の両方に置く(二重在籍)が、すべての時間を原学級で生活する。」 から始まるのです。
これは、1文で短く書いてありますが、実現するのは並大抵のことではありません。というか、ほとんど不可能なことのように僕などには思えます。
その後も、子どもたちが可能な限り共に過ごすために実施されていることが書かれており、圧倒されました。こういう学校も日本の中にはずいぶん前から存在していたのですね。
翻って、現在文部科学省のサイト内で閲覧できる「 新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議報告(素案) 」の中には、
「障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に教育を受けられる条件整備」
「通常の学級に特別支援学級の児童生徒の副次的な籍を導入し、ホームルーム等の学級活動や給食等については原則共に行うこととすることが必要である。」 といった文言が含まれています。
これでもかなり先を行った提案だと思うのですが、豊中はかなり先を行きすぎているような印象です。
さてさて、この調子で書いていたら全然終わらないので、ちょっと間をすっとばして、高校についても少し書いておきます。
「障害」のある生徒が高校で勉強する場合を考えたとき、大変気になるのが「評価」のことです。
そこにも一言では言えないすったもんだがあるのですが、いろいろなすったもんだの末に高校の先生はこう書かれています。
====================
・彼らの存在が学校を変えていったことがある。
最も大きいことは、単位認定・評価のあり方である。
彼らに対して「1年間の生活を通して(学校生活に限らず)どんな小さなことでも発達(進歩)を見過ごさないようにして、良いところを見つけ出し、そのことを評価する」ことが全教職員のものとなった。そのことは、他の一人ひとりの生徒に対しても広がりをみせ、点数で単位不認定が機械的にされることをなくしていった。
(p284)
====================
「点数で単位不認定が機械的にされる」というのは、ともすればこれまでは当たり前のように感じていました。しかし、1人の生徒を人として誠実に評価しようとしたとき、そういった機械的な判定はされなくなっていったことを知り、「障害」があっても評価され学び続けられるという希望を抱くことができました。それこそ、ここに至るまでの粘り強い取組の過程は、想像もできないものがあったと思います。しかし、結果としてこのようなカタチに結びついていったことを知らせてもらえるだけでも、「障害」のある子の高校教育について、希望が持てました。
最後に、「養護学校」の先生方からはどんな報告が出されているかというと、これもまた、貴重なのです。「地域の学校」では当たり前であることが当たり前ではない状況を知り、僕は非常に衝撃を受けました。しかし、それを変えていこうとされている先生方がいることに、勇気をもらいました。
例えば、「 地域の小学校で使っている検定教科書で、みんな一緒に授業をしようと思いました。 」(p337)という先生。積極的に地域の中で生きることを念頭に置いた活動を続けられる中で、「 障害者手帳で切符を買うのに30分もかかっていた駅も、出かけるたびに駅員の対応が変わり、徐々にですがエレベーターやエスカレーターがついていきました。 」(p342)というような社会の側の変化も見られていったことに、深い感動を覚えました。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[共に生き、共に育つ] カテゴリの最新記事
-
6/29シンポジウム「インクルーシブ教育の… 2024.05.24
-
矢田明恵「海外のインクルーシブ教育~フ… 2024.05.23
-
ADHDの子どもにとって動くことは必要! … 2024.05.16
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
Category
カテゴリ未分類
(57)生活をよくする
(204)共に生き、共に育つ
(174)たのしいべんきょう
(146)体育
(12)本の紹介
(176)音楽♪
(275)道徳 等
(12)問題解決
(104)考え方
(146)個人的な日記
(161)話し合い・話す・聞く
(36)特別支援教育
(188)小学校
(78)阪神間 地域情報
(36)PC・デジタル関係
(328)教材・教具
(24)食育(自立生活・家庭科)・園芸
(15)旅行(温泉含む)
(75)環境保護・エコ
(26)仕事術
(74)英語学習
(26)作文・書くこと・漢字
(20)よのなか(社会)
(47)いのち
(27)人間関係・コミュニケーション
(90)子育て
(33)算数
(11)地震・防災
(16)心理・カウンセリング・セラピー
(30)読む・音読・朗読
(9)エクセルでのプログラミング
(21)北播丹波 地域情報
(4)教員免許
(2)教育改革
(34)休校期間お役立ち情報
(21)映画 等
(15)創造性をはぐくむ
(5)プレゼン
(12)通級
(2)健康
(3)ゲーム
(1)Keyword Search
▼キーワード検索
Free Space
<読書>
※過去の「読書メモ」のリストを作成中。
<ICT活用>
Wordの音声入力が進化していた!
GIGAスクール児童生徒端末を活かす「ミライシード」
GIGAスクール構想の1人1台は何のため?何をする? 低学年向けパワーポイント資料を作成しました。
GIGA スクール以後の、今後の方向性について
<特別支援教育>
オリジナル標語
自傷行為のある子への取り組み
「読み書き障害」の理解啓発の必要性を訴える
運動会のBGMで耳をふさぐ子がいたら、BGMのエフェクトを試してみよう
<「今日行く」ユースフル>
駐車場検索のやり方
三宮格安駐車場
♨旅行 毎月5と0の付く日は、楽天トラベルの予約がオトク
<「教育」ユースフル>
教材・教具
携帯コミュニケーションボードCoBo(コボ)
※リンク※
★にかとまのホームページ ※NEW
にかとま情報局
エクセル野球シミュレーションゲーム「ダイナミック・ベースボール」のページ
にかとまの音楽のページ
※過去の「読書メモ」のリストを作成中。
<ICT活用>
Wordの音声入力が進化していた!
GIGAスクール児童生徒端末を活かす「ミライシード」
GIGAスクール構想の1人1台は何のため?何をする? 低学年向けパワーポイント資料を作成しました。
GIGA スクール以後の、今後の方向性について
<特別支援教育>
オリジナル標語
自傷行為のある子への取り組み
「読み書き障害」の理解啓発の必要性を訴える
運動会のBGMで耳をふさぐ子がいたら、BGMのエフェクトを試してみよう
<「今日行く」ユースフル>
駐車場検索のやり方
三宮格安駐車場
♨旅行 毎月5と0の付く日は、楽天トラベルの予約がオトク
<「教育」ユースフル>
教材・教具
携帯コミュニケーションボードCoBo(コボ)
※リンク※
★にかとまのホームページ ※NEW
にかとま情報局
エクセル野球シミュレーションゲーム「ダイナミック・ベースボール」のページ
にかとまの音楽のページ
Calendar
2025.11
Comments
Natashajer@ Откажитесь от стереотипов — это вашим наибольшим достижением — вот почему!
о Ваш сайт — это отличный пример для в…
© Rakuten Group, Inc.



