全155件 (155件中 1-50件目)
-
オーストリアの洪水
オーストリアの洪水 日本ではあまり報道されなかったが、今年のオーストリアの5、6月には雨が多く、国中のあちことで洪水に見舞われた。 特にヨーロッパの家屋は地下室(ワイン蔵、洗濯場、物置)を備えていることが多いので、水が出ると被害は深刻なものとなる。 そもそも例年初春の雪解け水による洪水は、この地域にはつきものである。オーストリアの山沿いの谷あいの村などはしばしば洪水の被害にあう。また特に雪が多かった年は、暖かくなると一気に雪が溶けて洪水による被害がでる。そうした雪の量や、さらに地形による要因が強いが、その一方で、日本のようなコンクリート剥き出しの堤防を作らないヨーロッパの治水のありかたも一つの要因となっている。オーストリアのヴァッハウ渓谷などを歩くとわかるが、ドナウ河の水位と堤防の高さの差がほとんどなく、4-5メートルの増水で水が溢れそうなところをよく見かける。もちろん全ての流域にわたってそうなっているわけではないが、しかし河川の景観を保持するためにも、また日本の台風時のような集中豪雨なども稀であることなどからも、趣味の悪いコンクリート堤防を作らずに、自然な形での治水能力の確保が方針になっている。 しかし近年ヨーロッパでも、かつては見られなかったような天候不順が起こることが多くなってきた。頻発する洪水に対して、どのような対応を取るのか注目されるところだ。
2009年08月01日
-

小沢征爾からヴェルザー・メストの時代へ ウィーン国立歌劇場指揮者を交代
小沢征爾からヴェルザー・メストへ ウィーン国立歌劇場指揮者を交代 次期ウィーン国立歌劇場の監督が、2010年にこれまで15年間この座を占めてきた現在のイアン・ホレンダーから現在パリのシャンゼリゼ劇場の監督を務めるドミニク・メイエールDominique Meyer (51)へ交代することが決まった。契約は5年間。昨日水曜日の午後に、文化省大臣のClaudia Schmiedが語ったところでは、首相のAlfred Gusenbauerと会談を行った結果、フランス人Dominique Meyerの選定を決定したということである。もともとGusenbauer首相は、テノール歌手のNeil Shicoffを推薦していたが、文化省大臣Claudia Schmiedが自分の主張を押し通した形となった。またそれに伴い、音楽監督は現在の小沢征爾から、Franz Welser-Moestへの交代もあわせて決まった。以前から小沢の後継として、メストとティーレマンの名前が挙がっていたが、長年待たれたオーストリア人の指揮者の誕生に沿って、メストがその座を占めることになった。この国では首相に次いで大きな権力を持っているように見える国立歌劇場監督の権力を、フランス人がどのように行使していくのかが見物である。 ウィーン国立歌劇場監督は、G.マーラー以来さまざまな政治的な影響力のもとで話題となる地位であるが、1992年から2010年まで18年間この座に君臨するイアン・ホレンダーの卓越した指導力・経営能力は、あのカラヤンを凌ぐものであった。ホレンダーはユダヤ系のルーマニア人で、始めは技術者になるべく大学教育を受けていたが、学生運動に加担したため放校となり、ウィーンにやってきて声楽の勉強をはじめる。卒業後はKlagenfurtやSankt Poeltenの劇場で歌手やアドヴァイザーとして働いていたが、特に彼が評価されたのはオペラのエージェントとしての才能で、彼自身それに関連するイヴェント会社も経営していた。彼が転機を迎えるのは、Eberhard Waechterが1991年にウィーン国立歌劇場の監督になり、そのアドヴァイザーとして迎えられたときである。そして翌年の1992年にWaechterが急逝すると、その後を受け継いで劇場監督となる。就任当初は契約などについてマスコミから様々な攻撃を受け、関係が良くなかったが、彼の革新的な姿勢が次第に評価され、ウィーンの音楽界に隠然たる力を持つようになる。特に前任者のWaechterが、きわめて保守的でかつての演出を新たに再演する方向、ウィーンで以前採用されていたアンサンブル方式へ傾いていた方向を完全に否定し、前任者のカラヤンやDreseが示した短い契約期間でのレベルの高い客演を増やすような方向へと変えていった。あるいは他のオペラハウスとの交流(演出の売り買い)なども積極的に進めた。 一方Dominique Meyerは、名前から類推できるかもしれないが、アルザス出身で、外交官である父の仕事の関係でしばらくボンに暮らしたことがあり、そこでドイツ語を習得したと言われている。彼はパリで経済学を勉強し、卒業後産業省に勤めるが、 文化省大臣のJack Langに呼ばれ、アドヴァイザーになる。それから最初1986年にパリ・オペラ座で働くが、三年後そこの総監督になる。バルチーユ・オペラの開場にも関係し、1991年に再び文化アドヴァイザーとして文化省に呼び戻されている。しかし彼のオペラへの欲求は高く、ローザンヌ・オペラの監督となり、革新的な上演を推し進め、1999年には再びバリに戻ってシャンゼリゼ劇場の監督となっていた。シャンゼリゼ劇場は、ウィーンのテアター・アン・デア・ウィーンのような劇場と見なされているようである。 またフォルクス・オパーの劇場監督の交代の発表も先日あり、先日紹介した俳優ローベルト・マイヤーが就任することになった。これで2つの国立劇場はいずれもマイヤー氏が監督となることが決まった。 退任する小沢に対する言及が少ないのは、残念である。http://derstandard.at/?url=/?id=2909360
2007年06月07日
-
Deutsche Welle ライブ
Deutsche Welle(ドイチェ・ヴェレ) ライブ テレビ ラジオORF(オーストリア放送協会) ニュース Video on Demand 日本と異なり、ヨーロッパではテレビとネットは比較的良好な関係を保っているように見える。特にネットの放送の可否は出演者などの著作権が問題になるが、著作権については、ヨーロッパでは、単に著作権者の権利を保護するだけでなく、将来の文化の発展のために著作物を供するという考え方が強い。それは日本のように、ブランド品のコピーと知りつつ買うような文化はなく、また他人の著作物のコピーで金もうけすることが難しく、また日本のような強力な著作権の利益保護団体が存在しないことから、著作権の利用に関して比較的寛容であるように見える。特に教育などには、比較的著作権の提供が容易である。 ところで、私の勤めているところでは、いままで衛星放送で、DW(ドイチェ・ヴェレ)を受信していた。しかしもはや衛星放送を利用する必要もないだろう。(最近はその受信装置も調子が悪く、放送がよく中断しているのだが・・・)またヨーロッパでは一部であるが、テレビ局のVIDEO ON DEMANDのサービスも進んできている。上記のORF(オーストリア放送協会)のニュースは、昔よく見ていたものであるが、かつてはそのまま加工せずネットで流していたが、最近は内容毎にデータを分けてくれているし、またDW(ドイチェ・ヴェレ)は、ドイツ語学習者用にゆっくり発音してくれるニュースとそのテキストを容易するなど、外国人にさまざまなサービスをしてくれている。 日本ではNHKは、民放に肥大化を言われるので、ネットについてはまだまだ取り組みが遅れている。衛星放送についても、ヨーロッパのものは驚くほど多くのチャンネルがあり、多くの言語で放送されており、その内容の充実は羨ましい限りである。
2007年06月04日
-
松岡問題
ヨーロッパ人には、今回の松岡農相の自殺は、汚職した政治家が責任をとって自殺したと見えるらしい。 Stanndard紙のHPの読者の書き込みでは、「この伝統は終わらねばならない」と題して、”Diese Tradition muss beendet werden.”Der Verstorbene schrieb 8 Abschiedsbriefe an verschiedene Politikerkollegen, nat?rlich auch an Premier Abe. Unfassbar... Der Agrarminister hat damit alle Beweise und Aussagen, die ver?ffentlicht werden sollten, mit sich in den Grab gebracht und alle Verantwortungen den Verbriebenen hinterlassen. So in der Art bringen sich zahlreiche Firmenchefs und V?ter in Japan um, wenn sie in Schwierigkeiten geraten. Was f?r eine Feigheit und "Unm?nnlichkeit"! Was f?r ein Jammer... 「松岡農相は公開されるべき証拠と発言を墓場に持って行った。日本では同様の自殺が多い。なんて卑怯なのだ、男らしくない」 石原が言っていたようにまさに腹切り=”Samurai”ということになるのかもしれない。しかしその内実はベールにつつまれているので、日本人にすらわからないのだから、ヨーロッパ人にはまったく理解不能だろう。しかし、オーストリアでも最近ユーロファイターの導入を巡る汚職事件があったら、ヨーロッパの政治家もなかなか責任は認めないし、確かにしぶとい。 ハンガリーは自殺率が高いことでかつて有名だが、例えばオーストリア人に聞いてみると、日本のように金に困って自殺なんてことはありえない!!と知り合いが強調していた。オーストリアも19世紀末までは自殺が多い国で有名だったんだが。。。松岡関連記事http://www.kurier.at/nachrichten/ausland/78964.phphttp://derstandard.at/?id=2896987
2007年05月30日
-

フォルクスオパー 「白馬亭」
フォルクスオパーで「白馬亭」を見た。http://www.weissesroessl.at/de-videos-beauty.shtml オーストリアのザルツブルク(「塩の砦」の意)の東側に広がる高原地帯は、ザルカンマークートと呼ばれ、「サウンド・オブ・ミュージック」の舞台として有名になったが、そこでも描かれているように、周囲には美しい湖が多く、夏は多くの観光客が訪れる。ザルツブルクからは少し距離があるため、そこまで足を延ばす日本人はそれほど多くはないが、自動車で良好をする現地の人たちには非常に人気がある観光地である。19世紀までは、この地方は産出される岩塩で経済的に繁栄し、モーツアルトが最初仕えていたザルツブルク大司教の経済的な基盤を作っていた。そこの湖の一つがヴォルフガンク湖であり、その湖畔のヴォルフガンク・ザンクトにあるホテル「白馬亭」がこのオペレッタの舞台となる。このホテルは現存する人気ホテルとなっている。 "Im weissen Roessel"というのは、"「白馬亭」にて"といった程度の意味であるが、この”Roessl”というのは Ross(Pferde「馬」の雅語)の縮小形である。ドイツ語を勉強すると授業で、-chen -leinなどの縮小語尾を習うが、バイエルンやオーストリアでは、-el, -l,-erlなども縮小語尾として使うのである。ザルツブルガー・ノッケルSalzburger Nockerlというザルツブルグの山々に見立てた、焼きたてが命の有名なスフレがあるが、この言葉Nockerlは、Nocke「岩石でできた山頂」に-(e)rlを付けたものである。ただNockerlというのは、ここではもともとスープにいれるような小麦粉から作った小さな団子を意味し、現地ではSpaetzleとも言う。Spaetzleはウィーンではよく付け合わせででてきて、パスタやマカロニのような感覚で使われ、スーパーでもインスタントのものが売っている。 このオペレッタだが、設定は第一次世界大戦前で、オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の統治下で、皇帝自身このオペレッタに特別ゲストで登場する。フランツ・ヨーゼフは1848年に三月革命時に前皇帝が退位したのを受けて即位し、以来第一次大戦中に86歳で逝去するまで70年の長きにわたり君臨した、ハプスブルク帝国の歴代の皇帝の中で国民がもっとも愛着を寄せる人物である。あのエリーザベトの夫であり、マイヤーリングで自殺した皇太子ルドルフ(最近ルドルフのドラマがORFで作られて人気になった)の父親である。 このオペレッタは、一部他の作曲家の曲を使っていて、ローベルト・シュトルツの作曲のものもある。 配役とあらすじを紹介すると、配役 Dirigent Michael Tomaschek Josepha Ulrike Steinsky Ottilie Gabriela Bone Klara Susanne Fugger Leopold Josef Luftensteiner Giesecke Gerhard Ernst Siedler Dietmar Kerschbaum Sigismund Stephan Wapenhans Franz Josef II Peter Minich Adjutant Michael Weber Portier Josef Forstner Gustl Konstantin Hladik Koch Hermann Lehr 一物語一 第一次大戦前のザルツカンマーグート。 舞台:ヴォルフガンク湖畔のザンクト・ヴォルフガンクにある宿屋「白馬ホテル」第1幕 観光シーズンの到来とともに、給仕頭レーオポルトLeopoldは、押し寄せる観光客の対応に大忙しである。(舞台は、右手に客室らしき棟があり、そこに左からぐるりと2階に階段がかかっている。その手前のところがレストランになっていて、そこに多くの客がテーブルについていて、ウェイターは注文・精算に忙しそうに走り回っている)レーオポルトは、このホテルの女主人ヨゼーファ・フォーゲルフーバーJosephaに恋心を抱いているが、彼女と話をするよりはホテルの観光客と話をするほうがうまく話ができるような男である。「あなたに愛してもらえるなら、どんなに素晴らしいだろう。」と愛の告白の歌を歌うレーオポルトだが、女主人の方は、常連客の弁護士ジードラーSiedlerに気持ちが惹かれている。 ジードラーは毎年夏休みの始めにこのホテルに投宿する常連であるが、仕事の都合で夏休みの始めの時期にしか来られないのであるが、ヨゼーファのほうは彼が自分に会いに来ていると勝手に思いこんでいる。(ジードラーはスポーツカーで登場したという設定で、女性に非常に人気があるように演出されている) そこへ蒸気船が到着し、その客の中にベルリンのメリヤス工場主ギーゼッケ一Gieseckeとその娘オッティーリェ一Ottilieがいる。ギーゼッケは競争相手のシュルツハイマーと目下裁判で係争中であるが、そのシュルツハイマー側の弁護を担当しているのがジードラーなのである。レーオポルトは、先にジードラーが予約しておいたバルコニー付の部屋を、独断でギーゼッケに渡してしまう。(ギーゼッケ一は太ったいかにも道化的なハンスブルストで、やや娘のオッティーリェ一とは釣り合わないが、そこがなかなかおもしろい。Gerhard Ernstという歌手であるがどこかで見たような気もする) 一方、ジードラーが到着するのを知ると、ヨゼーファは大いに喜ぶ。「ヴォルフガンク湖畔の白馬亭、ドアには幸せが待っている」と歌う。ヨゼーファはジードラーをすぐに予約の部屋に案内するが、すでにその部屋はジードラーに渡していたため、一揉めあり、結局ギーゼッケがその部屋を明け渡すことになる。 そんなゴタゴタの中で、ジードラーはギーゼッケの娘オッディーリェのことを魅力的に感じるようになる。「君の目を覗き込むと、世界はすべて空色さ……」という二重唱を歌う。ヨゼーファは、ジードラーに嫉妬するレーオポルトに腹を立てて解雇してしまう。レーオポルトは「見ちゃいられない」と嘆く。そこへ、ギーゼッケの競争相手ジュルツハイマーの息子ジーキスムンドが到着する。ジュルツハイマーは、自分の息子とオッティーリエがうまく結ばれれば、裁判も片付くとほのめかすが、しかし息子のジーキスムンドのほうは、旅行中に知り合ったヒンツェルマン教授の娘クレールヒュンに興味がある。舌のもつれるクレールヒュンと禿頭のジーキスムンド。「ハンサムであることは、ジーキスムンドのせいじゃない」の二重唱を歌う。 一方、ジードラーとオッティーリエはバルコニーからお互いに挨拶して、「恋の歌はワルツでなけりゃ、花の香りと日の光に満ちた--」と歌う。またジードラーも敵方の弁護士を利用できると考え、娘の交際を支援している。ヨゼーファの方は、「ザルツカンマークートでは、みんな楽しくなる」などを歌い、ジードラーへ熱烈な気持ちを伝えようとするが、それを見たレーオポルトは、もはや見ていられなくなるほどであった。 しかしフランツ・ヨーゼフが当地にくることになり、白馬ホテルが皇帝の宿舎に決まっると(フランツ・ヨーゼフは、夏は近くのバード・イシュルにある別荘で過ごすのが通例であった。)ヨゼーファはすっかり興奮し、レーオポルトの助力が必要となり、解雇したことを取り消す。皇帝陛下の船が到着、レーオポルトは歓迎の挨拶をするが、ヨゼーファとジードラーが並んでいるのを見て、すっかり混乱してしまう。(続く・・・)
2007年05月30日
-
名優 ローベルト・マイヤー
ある日曜日の昼に、アカデミー劇場で名優ローベルト・マイヤーRobert Meyer(彼は2001年以来恒例の国立歌劇場のジルベスター「こうもり」公演の第3幕であのフロッシュ役を演じている)が、ネストロイの喜劇"Haeuptling Abendwind" (「酋長アーベントヴィント」)を1人漫談形式で演じる朗読会に行った。ローベルト・マイヤーは、日本ではほとんど知られていないと思うが、私はこれまで国立オペラ座の「こうもり」、ブルク劇場のネストロイの「広告配達ペップ」、またブルク劇場の「ハムレット」の義理の父親役、ベルンハルトの「習慣の力」などで見る機会があった。彼は特にこのネストロイの滑稽劇Posseを得意にしているが、オーストリアの多くの俳優のなかでも、一度演技を見たら(また声も独特の魅力がある)忘れられないほど個性派俳優である。その個性的な声の響きに演技がぴったりとはまっている。日本でたとえたらだれだろう?とにかくジルベスターやお正月に「こうもり」をオペラ座で見る機会のある人は、その3幕の彼の演技に注目して欲しい。 この"Haeuptling Abendwind"だが、ネストロイの作品の中でも異色の作品である。舞台は未開の島、酋長アーベントヴィントAbendwindは、敵対する部族の酋長ビーバーハーンスBiberhahnsと和解するために宴会を開く予定なのだが、連日猟がうまくいかず、ご馳走がだせそうもなく焦っている。そこに娘のアタラAtalaと仲良くなった青年アルトゥールArthurがやってくるが、実は彼はBiberhahnsの息子で、昔Biberhahnsがその息子をヨーロッパの理髪師の元に送り、そこで修行させたのである。そしてようやく今日、彼はめでたく故郷に戻ってきたのである。しかしBiberhahnsもその息子も、20年以上一度も会っていないので互いの顔を覚えていない。酋長AbendwindはArthurを見ると、さっそく宴会のための生け贄にすることを思いつき、Arthurを料理しそれをBiberhahnに出すために、コックたちにに捕らえて料理するように命じる。その一方でBiberhahnはAbendwindに自分の息子が今日帰ってくることを話す。事情を知ったAbendwindは、さっき料理した青年がBiberhahnの息子であったことを知り愕然とする。しかし最後に、Arthurはコックたちから逃げていて無事であることがわかり、結局ArthurとAtalaが結ばれることにより、AbendwindとBiberhahnの部族も和解するという話である。 マイヤーは主人公Abendwindをウィーン方言、相手役のBiberhahnをバイエルン方言、そしてAbendwindの娘を標準語で話し、性格の違いをうまく演じ分けていた。彼はもともとはドイツ出身で、ザルツブルクのモーツァルテウムの演劇学科出身だけあって、なかなか歌も良かった。こういう何でもこなせる俳優となると、もちろんオーストリアでも珍しく、貴重な存在である。だからときどき彼の演技が無性に「聞きたく」なる。そう、あと独演会で、演技することなく、その戯曲を「演じる」ことができるオーストリアの俳優の実力は、ほんとうに称賛に値する。やはり徹底的に舞台で鍛えられるこちらの俳優たちからは、日本の演劇のレベルとの差を感じざるを得ない。。(左、ローベルト・マイヤー アカデミー劇場)
2007年05月29日
-

詩の翻訳は難しい・・・・・
いまちょっと仕事で、詩の翻訳をやっているが、これはかなり難しい。散文はちからわざでなんとかなるが、詩っているのはねえ、なんというか、外国語のニュアンスをさらに日本語の言葉のニュアンスと結びつけないといけいないので、ほんとセンスが問われる。おおよそ30編ぐらいだが、1ヶ月で訳せるかどうか・・。ちょうど今週ある事情で特別休暇(こう表現すると怒られそうだが・・)が入ったので、ちょっと集中してやらないといけない。でも来月は事務局をやっている研究会があるし、7月の研究発表会の準備もあわせて進めないと行けないし、結構スケジュールは詰まっている。 4月にだいぶ選挙(都知事選・区長選)にかかわって時間を取られたツケが回ってきた感じだが、なんとか乗り切らねば。。。。うーん、と唸りながら一つ詩を訳してみる。Der DichterNachts kann ich oft nicht schlafen,Das Leben tut weh, Da spiel ich dichtend mit den Worten,Den schlimmen und den braven,Den fetten und den verdorrten,Schwimme hinaus in ihre still spiegelnde See.Ferne Inseln mit Palmen erheben sich blau,Am Strande weht duftender Wind, Am Strande spielt mit farbigen Muscheln ein Kind, Badet im gruenen Kristall eine schneeweisse Frau.Wie uebers meer die wehenden Farbenschauer Ueber meine Seele die Verstraeume wehn, Triefen von Wollust, starren in Todestrauer,Tanzen, rennen, bleiben verloren setehn,Kleiden sich in der Worte viel zu bescheidenes Kind,Wechseln unendlich Klang, Gestalt und Gesicht, Scheinen uralt und sind doch so voll Vergaenglichkeit.Die meisten verstehen das nicht, Halten die Traeume fuer Wahnsinn und mich fuer verloren,Sehn mich an, Kaufleute, Redakteure und Professoren-Andre aber, Kinder und manche Frauen,Wissen alles und lieben mich wie ich sie,Weil auch sie das Chaos der Bilderwelt schauen, Weil auch ihnen die Goettin den schleier lieh. 詩人しばしば夜に眠れず、人生が苦しみとなるそんなとき詩を書きながら言葉遊びをする、好ましくない言葉、行儀のよい言葉肉太の言葉、枯れた言葉を使って、静かに光を反射する海へと泳ぎだす。椰子の生い茂る遠くの島々が、青く浮かび上がり、海岸では芳香を放つ風がそよぎ、海岸では子供が色とりどりの貝殻で遊び、雪のように白い女性が、緑の水晶の中で沐浴する。海を越えてそよぐ色彩のシャワーのように、私の魂を越えて、詩の夢が吹き渡る、それは愉悦をしたたらせ、死の悲しみをじっと見つめ踊り、走り、絶望したままで立っている、多くの言葉をまとって控えめな子供になり、響きや姿や表情を永遠に変え、とても古い(太古)もののように見えるが、しかし無常に満たされている。大抵の人たちはそのことを理解しない、夢を狂気とみなし、私を絶望した人間であるとし、私をみつめるのが、ビジネスマンや編集者、教授たちである。しかし他の人たち、子供や多くの女性たちはすべてを知っており、私が彼らを愛するように、彼らは私を愛する彼らも混沌とした絵のような世界を見るのであり、また神々も彼らにそのベールを与えるのである。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーこれは大雑把に訳したもので、こからイメージをつかみながら、さらに細部の表現にこだわりながら言葉をいじっていく。さてどうなることやら。。。。
2007年05月19日
-
オーストリア人のプロイセン観 (2)
<個人について>プロイセン オーストリア現実的な思考 伝統的な思考、数世紀に渡っての安定 歴史的な思考の欠如 歴史的な本能の所有抽象的思考 規定に従って行動する 巧みさに従って行動する弁証法に優れる 弁証法の拒否弁舌に非常に優れる バランス感覚自己感覚 自己皮肉男性的 未成年 機能的なものへの変化 社会に適応するものへの変化主張と自己弁明 不明瞭なままでいる尊大、うぬぼれ、教師的 羞恥心、虚栄、機知的危機への突進 危機の回避正義のための闘争 なげやり他者を思いやる能力の欠如 自己を失うまで他者を思いやる能力 不自然な性格 役者的権威の一部を担う 全人間性を担う努力家 享楽家誇張癖 解体させるまでの皮肉 これはあくまでも図式ですからかなり単純化されており、またホフマンスタールはオーストリア人であるので、オーストリアをひいき目に見ていることを割り引いて見る必要がある。ここではオーストリア人の自己認識の在り方と、オーストリア・ハンガリー二重帝国という多義的な国家体制のなかで、プロイセンとの二項対立において自己のアイデンティティを規定するオーストリアの在り方が示されているようにも見える。オーストリアのアイデンティティというのは、なかなか面白い問題である。
2007年05月19日
-
オーストリア人のプロイセン観 (1)
日本人から見ると、歴史的経緯は異なるが、同じドイツ語を話しているので、ドイツとオーストリアは同じような国に見えてしまうが、しかしその両国にはかなりの違いの民族性があるようだ。こういう民族性の比較は、えてして血液型の分類(血液型を見つけたのはオーストリア人である!)や星座の性格占いのようなものに陥る危険性があるが、しかし文化や社会を見るときに一応その違いを前提として頭に入れておいたほうがよい場合もある。 世紀転換期に活躍したオーストリア人作家ホフマンスタールはR.シュトラウスの「バラの騎士」のリブレットを書いた作家として日本では知られているが、その彼がオーストリア対プロイセンという興味深い比較を行っている。オーストリアはかつてのハプスブルグ家が支配した国家で、もともとのオーストリアを構成したのが民族的に言えばバイエルン族であったこと(バイエルン族の東進)や、また同じカトリックであることもあり、オーストリア人は一般的にではあるがバイエルン(南ドイツ)に親近感を抱いている。民族衣装も似ており、風習も近いようだ。ビスコンティの「神々のたそがれ」の中で、ルートヴィヒ二世がプロイセン・オーストリア戦争でプロイセン側に参戦したことを深く苦悩する場面が描き出されるが、それはストーリー的にはバイエルン出身のエリーザベトを思ってのことにも見えるが、やはり歴史的背景が関係している。 かつては神聖ローマ帝国としてドイツもオーストリアも同一の国であり、ハプスブルク家の国王が神聖ローマ帝国の皇帝になる戴冠式は、わざわざカール大帝にちなんでフランクフルト(ハウプトヴァッヘのカイザードーム)で挙行されるのが慣例であった。(ゲーテは小さい頃この戴冠式を見て神聖ローマ帝国の歴史を感じたようだ)しかし、近代ドイツの統一の過程で、オーストリアを中心としてドイツ統一を目指す大ドイツ主義とプロイセンを中心としてドイツ統一を目指す小ドイツ主義が激しく対立し、結局オーストリアは1866年のプロイセン・オーストリア戦争と1867年のオーストリア・ハンガリー二重帝国の成立によって、ドイツから排除される結果となった。その中で、オーストリア人はプロイセンに対してその差異を非常に意識するようになったのであろう。日本ではドイツのイメージは、プロイセンのイメージが強いが、ここでホフマンスタールが挙げているプロイセンの特徴は、日本人にはドイツのイメージと重なっているかもしれません。 <全体に関して> プロイセン オーストリア構成された、人工的な構造 自然に成長した、歴史を持つ構造本質的には貧しい国土 本質的には豊かな国土全ては人間の力による 全ては外部から;つまり自然と神(プロテスタント) (カトリック)統合力としての国家思想 統合力としての郷土愛徳・有用性 敬虔・人間性 <社会的構造に関して> プロイセン オーストリアゆるやかな社会組織 緊密な社会組織文化を重視しない 文化を尊重する精密な組織を持つ 全体組織は厳密ではない 官僚組織は統一されている 官僚組織は多様である同一の精神を担っている 多様な思考形態や感情支配者の世界観を共有規律を重んじる国民 自立的できわめて個人主義的な国民学問における社会民主主義の欠如国王への最大の権威 国王へ最大の信頼
2007年05月19日
-
オーストリアワインの楽しみ
ワインを飲むのは、「ワインの記憶を飲む」といった人がいたが、確かにそういう気がする。ワインの記憶とは、その国の歴史であり、その風土であり、その気候、文化なのだろう。オーストリアワインは、フランスワインのようなコクはないし、イタリアワインのような華やかさはないが、しかしその高貴な香りとバランスの良さは、個人的にはとても気に入っている。 でもほんとうにオーストリアワインを楽しむのであれば、ホイリゲに足を運ばなければならない。一度ホイリゲの雰囲気を味わった人は、そのために何度でもウィーンに行きたいと思うほどである。ホイリゲもいろいろな種類があり、観光客向けは、市内から近く交通の便が良いグリンツィンクに多いが、でも本当のホイリゲの雰囲気を味わいたいなら、地元の人間しかこないようなホイリゲを選ぶべきである。ホイリゲとは、地元の人が気軽にいくような場所だけれども、でもやはりそこに行くとなにかがしっくりいくような特別な場所でもある。犬の散歩の途中で気軽に寄る場所であり、子供づれで週末おしゃべりにくるような場所であり、行く場所のない年寄りがワイングラスを片手にゆっくりと時間を過ごすような場所である。ウィーンのカフェも市民にとって特別な場所であるが、ホイリゲもやはりなくてはならないときびり素敵な場所である。こういう空間を持っている人たちをほんとうに羨ましくおもうことがある。 観光客が集まるグリンツィングやノイシュテシフトアンヴァルトもいいですが、個人的にはウィーンの南のBaden方面にあるGumpoldskirchenやSoossあたりの落ち着いた雰囲気が個人的に好きである。特にSoossでは一番といわれるFischerはお気に入りである。ここのMerlot PREMIUM 2004は結構いける。http://www.weingut-fischer.at/ ところで、私はブルゲンラントの赤ワインが好きなのだが、いつもLandstrasseの近くにあるワインショップBurgenland-vinothekで購入していた。ブルゲンラントのアンテナショップのようなところでブルゲンラントのワインしかおいてないのだが、種類も多くかなり安い。http://www.burgenland-vinothek.at/scripts/active.asp?vorlage=32&id=720 日本でおいしいオーストリアワインを手に入れるのはまだまだ難しいので、仕方ないのだが個人輸入する場合には、次の通販を利用している。 http://www.pfanner-weine.com/ 毎年夏にオペラの上演を行っているMargaretenの近くのワインRosi Schusterを扱っている店をいまだに日本でまだ見つからないのはちょっと残念である。日本に輸出するほど量を生産していないからかもしれないが。 ネットの販売店を見ても、オーストリアワインが年々多く取り扱われるようになっているところを見ると、人気がでてきているんだろうが、あまり有名になりすぎるとやはり生産に無理が出て味が落ちるのが心配だから、人気がでるのも複雑な気持ちではある。
2007年05月18日
-

ウィーン国立歌劇場・雑感 チケット購入
ウィーン国立歌劇場のチケット購入について一言。 まずオペラを見るためにはチケットが必要となるが、チケットの購入方法は外国人のためにも様々配慮されており、非常に買いやすいシステムになっている。 インターネット(クレジット決済 http://www.culturall.com/ Culturallという業者が請け負っている。 )・ファックス・手紙(専用の申込書あり)・電話(英語可)・前売りチケット売場・一般の仲介業者(通常手数料を20%から30%取られる。)・当日のチケット売場・立ち見(当日開演2時間前ぐらいから並ぶ)等々の方法がある。ただ通常のインターネットや電話などは、購入開始時期が公演1ヶ月前の1日後になるので、やや不利である。 通常チケットは1ヶ月前から販売される。もし、非常に人気が予想されてどうしてもチケットを買いたい上演であれば、1ヶ月前の朝9時にオペラ座のチケット売場または国立劇場チケット売場(Bundestheaterkasse)に行って並ぶ必要がある。あるいはインターネットでStanbay-Ticket ( https://www.culturall.com/)という項目で、購入の予約を入れることができる。これは購入確実という訳ではないが、1ヶ月前のチケットの販売開始のときに優先的にチケットを購入できるのである。国立歌劇場は通常1ヶ月前発売なので、それまでは座席を指定して予約することはできず、このStanbay-Ticketの予約では、この料金カテゴリーと枚数を指定して事前予約をすることになる。この場合でもクレジットカード情報の入力が求められ、予約が取れた時点で契約が成立となる。事前予約およびスタンバイ・チケットの場合は、予約が正式に取れてからメールで連絡が入る。(表題はCulturall - standby ticketsになる。)。 ただ私は、上記の2つの方法はしたことがなく、いつも1ヶ月のチケット販売開始のあとかなり経ってから購入している。だから当然のことながらいつもそれほどよい席というわけにはいかない。私はふつう、国立劇場チケット売場に行ってその場で席の相談をして買うか、あるいはインターネットで座席の販売状況がわかるのでそこで購入申し込みをし、当日午後3時ぐらいまでに予約したときに届いたメールをプリントアウトしたものを持参して、国立劇場チケット売場でチケットを受け取るか、公演直前(1時間前ぐらい)にオペラ座の当日チケット売場でチケットを受け取るかしている。受け取りの際、受け取り確認のサインを求められる。 ドイツ語会話に不安がある人には、このインターネットでの購入がお勧めである。チケット売場であるとある程度言葉で意志疎通できないと難しいし、時には残っている悪い席(ロジェの2列目の舞台側や、一番右側や左側 ganz rechtsやganz linksなど)を「ここが残っている一番良い席です」などと勧められて、そのまま買ってしまうことなどがあるからである。むこうも商売なので、全てチケットを売ろうとしているので、仕方がないのであるが、たぶん「No と言えない」日本の観光客などはかなりそんなチケットを売りつけられているだろうなあと思っている。 またどうしても公式ルートでチケットが入らない場合は、街中にあるチケット仲介業者で買うこともできる。(私は1度だけ買ったことがある)オペラ座の周辺にいくつか固まってあるので行きやすく、また店頭に売っているチケットの一部が見えるように掲示されているので、買いやすい。店はオペラ座の裏のOperngasseに数軒と、そこからアルベルティーナに行ったところのReitschulgasseに数軒ある。またインターネットでも注文できる。(クレジット決済、郵送あるいは店舗での受け渡し)http://www.viennaticket.at/en/cat_wien/http://w3.ims.at/ 業者を使うと通常手数料を20%から30%(席の値段によって高額なものであれば、20%ぐらい、安いBalkon席であれば30%など業者によって多少異なるが・・)取られるので、私は1度しか使っていない。ただ業者は良い席を押さえているので(例えば安いGalerie桟敷席の Mitte中央などは、ほとんど売り出し開始とともに完売になってしまう・・)どうしても良い席で座って見たくて、経済的に余裕があり、チケットが手に入らない場合(これってGalerie桟敷席のMitte中央か、BalkonバルコンのMitte中央の席でしょうけど・・)は仲介業者を使うのもいいかもしれません。ただ1年通じてみていると、一番高額なParterre平戸間席(157 ユーロや127 ユーロぐらいの)などはたいていしばらく空きがあるので、超人気演目か公演直前でもなければ、そんな業者を使う必要はないであろう。 あと国立歌劇場で一番経済的で確実にオペラを見る方法が「立ち見」である。立ち見の制度は、最近初台の新国立劇場にも導入されたらしいが、知りあいから¥4000(?)と聞いたが本当だろうか?本当であればふざけるな!!と言いたい値段である。確実にオケも席(台本のモニターがついている)も上であるウィーンでさえその1/10なのに。立ち見は、ヨーゼフ2世が統治していた18世紀後半、ヨーゼフ2世がシカネーダにアン・デア・ウィーン劇場の建設を認めた当時からすでに立ち見席は存在しており、封建体制に対する不満を持ち始めた当時の庶民に娯楽を与えようとするハプスブルク家の施策・配慮を示したものであるとも見ることができる。そのためLogeロージェなどは確かに高額であったが、立ち見は一般の庶民が見ることができるほど廉価であった。その伝統がウィーンでは生きているのであり、それによってまたウィーンは文化都市でいることができるのだと思う。日本から来た観光客は、まず立ち見がこれだけ多くあることにやや驚くであろう。(歌舞伎にも「一幕見」座席数90と立見数60があるが・・)Galerie天井桟敷上方は、立ち見客で占領される。 ウィーンの素晴らしい点は、観光客に対しては最大限のサービスを提供しようとする姿勢である。このチケットシステムは、現在私が知るシステムのうち、最も便利なものである。それに比べて旧国立、現在の独立行政法人の新国立劇場のチケットシステムは、購入者の立場から見えればまだまだ改善の余地がある。日本でも、気軽にオペラを見に行ける雰囲気を作ってもらいたいものである。ウィーンではほとんど毎日オペラに足が向いていた私が、日本ではほとんど行きたいと思わないのはどうしてなのだろう。
2007年05月16日
-
ハチャトリアン作曲 バレイ「スパルタクス」
3年前であったが、ウィーン国立歌劇場で、ハチャトリアン作曲、Renato Zanella振り付けのバレイ「スパルタクス」を見た。Spartacus 振り付け:Renato Zanella 指揮:Dirigent Michael Halasz Spartacus Eno PeciMinotaurus Tomislav Petranovic Harmodius Christian Musil Zanellaの振り付けは、以前「クルミ割り人形」を見たが、なかなか壮麗・華麗な演出である。シルクスクリーン(?)を多様して、演出の幅を持たせながら、基本的な踊りの振り付けはしっかりとしている。バレイというある意味では究極の具象性を媒介にしながら、物語・主題という抽象的な内容を盛り込んでいく芸術様式は、ともするとそのバランスを失いがちになる。また振り付けとしては、単に物語りの内容を再現するだけではなく、物語性と身体性の間に緊張感を持たせることによって、オペラや管弦楽とは次元の違う芸術性を主張しなければならないのである。そこにバレイの難しさがあるように思われる。言葉にすれば簡単に通じる内容を、まったく基準の存在しない身体表現によって新たに表現しなければならないのである。観客はどうしても身体表現をその内容に還元して考えてしまう傾向があるが、しかしその対応関係はバレイという様式において、新たに生み出されなければならないのである。そこに振り付けの醍醐味と同時に落とし穴があるのである。 第1場では、子供たちが学校の教室で授業をうけれながら、快活に過ごしているのであるが、その黒板が突然崩れ、そこから奴隷商人の手下たちが、子供たちに殺到するのである。そのようにしてスパルタカスは、奴隷に身を落とすのである。そしてこのバレイでは垂直方向の力が強調されている。地上、そして地下、そして天上、人間の欲望と信仰は常に垂直方向に向けられるのである。 第2場では、スパルタクスたちの仲間が2派に別れ、結局スパルタクスがその集団を統率するのであるが、その両者の対立関係があまり明確に描かれておらず、それがよく理解できなかった。結局スパルタクスがその集団を統率する状況はわかったのではあるが・・。そしてミノタウルスは男性が演じているが、しかし、明らかに他人を誘惑する女性のイメージで演じられている。また女奴隷たちは、円盤のついたスカートを履いて演じられていた。またクラススとバテアトゥスは、今度は逆に、テーブルの上で決闘させられるように演出されている。最後には、二人は戦意を喪失して剣を投げ出し、その場に身を投げ出すが、スパルタカスたちによって見逃されるのである。 第3幕では、スパルタカスの奴隷たちとローマ軍が対決するが、天はローマに味方する。それはハルモディウスの裏切りによるものであった。スパルタカスはとらえられ、処刑されるが、最後には彼の妻となったフリジアと子供がその死を見守るのである。 このテーマは、映画「スパルタカスの反乱」(大根役者と言われたカーク・ダグラスが主演)で印象に残っているが、やはり芸術性を保つために、あまり大げさな戦闘などはあまり見られなかった。(最後の決戦の1場面ぐらいであろうか。)あくまでも優美なバレイに徹していたように思えるが、それでもやはり現代的な振り付けになっていることは誰もが認めることであろう。
2007年05月12日
-
博物館の長い夜 ”Lange Nacht der Museen“
ウィーンには年に2度、”Lange Nacht der Museen“(博物館の長い夜)という企画がある。それは、夜の6時から深夜12時まで博物館・美術館が12ユーロ程度で入り放題になる企画である。(同様に”Lange Nacht der Musik“(音楽の長い夜)というコンサートの入り放題の企画もある。) だから普段あまり行かないような小さい美術館を回るのには、こういう機会は大変都合がよい。またたいてい人気のある大きい美術館はすごく混んでいるので、小さな穴場の美術館を訪れるべきである。 ある時、応用美術博物館、ウィーン市歴史博物館、造形美術アカデミー絵画館、演劇博物館、狩猟・武器博物館、最後にレオポルト美術館とルートヴィヒ財団近代美術館、あと美術史美術館などを一夜で回ったことがある。 夕方5時ぐらいに王宮のところでチケットを売り出すので、まずHeldenplatzに向かった。チケットを手に入れてから、Volktheaterの地下鉄の駅からU3でLandstrasseまで行く。最初に訪れたのは「応用芸術博物館」だった。”応用”と訳すと日本人には何か違和感があるが、要するにガラス、陶器、家具、アクセサリー、食器などの工芸品を主に展示している美術館である。特にここのコレクションのうちウィーン工房のものが有名である。 またマイセン焼きのコレクションも素晴らしく、最初白磁ができなかったころのマイセン陶器が、次第に白くなる変遷が時代を追って示されていた。言うまでもないが地元オーストリアのアウガルテンのコレクションも秀逸である。さらに東アジアの部門もあり、日本の九谷、備前、薩摩、有田などの名品が並べられていた。柿右衛門があり、中国のコレクションもあった。そのほか机・椅子のコレクションも一見の価値がある。 その次に訪れたのは演劇博物館だった。これはAlbertina美術館の裏側あたりにある建物で、かつてロプコヴィッツ侯爵が住んでいた館である。彼は有名なベートーヴェンのパトロンだったので、ベートーヴェンの交響曲の第3番「英雄」はここで初演されているぐらいの由緒ある建物である。この建物の1室は「エロイカ」ホールと呼ばれている。 博物館自体はそんなに大きいものではない。(というか応用美術博物館とか美術史美術館に比べればだが・・)演劇、おもに上演する際の衣装とか舞台装置、宣伝のビラ、それに人形劇の人形などが展示されている。さらに有名人の手紙が展示されているが、ホフマンスタールの手紙が2点展示されていて、一つは「ヨーゼフ・カインツの思いでのために」という有名なエッセイの原稿が展示されていた。ホフマンスタールの筆跡は読みにくいが、とても繊細で綺麗な字を書く。もう1通はヨーゼフ劇場での再上演の時の手紙であった。ほかにマーラー、R.シュトラウス、マックス・ベルンハルト、ココシュカの手稿もあった。なぜかこのコーナーだけは、下に玉砂利のようなものが敷かれていた。人形劇のコーナーでは、操り人形が展示されていたが、プラハでよく売っているような簡素な構造のものであった。1度に6個の人形を操るようなものもあったが、大抵は1体、ないし2体程度の人形を1人で操作するもので、浄瑠璃に比べるとそれほど複雑な構造ではなかった。それからエロイカホールを見学し、豪華な衣装や有名な俳優の写真を見た。特別展では「能」の展示もやっていた。主に二つの部屋に展示されていたが、一通りの能の衣装、面、能舞台の展示であった。もう少しひねりがあってもいいと思うが、オーストリアではこの程度だろう。まあまあ人は入っていた。
2006年04月23日
-
欠航便に対するオーストリア航空の対応
欠航便に対するオーストリア航空の対応数年前であるが、帰国しようとしたとき、ウィーン発成田行きのオーストリア航空が大雪のため欠航となったことがあった。ただ雪には慣れているためか、雪による結構というのはそれほど多くはないということなのだが、たまたまそれにぶつかってしまったのは不運だった。 午後1時過ぎの出発予定が、3時まで待たされ、それから日本人乗客は空港内をたらいまわしされた挙げ句、結局今後の対応についてのメドも立たないままキャンセルとなった。それから日本人客はウィーン郊外の不便なホリディ・イン(Wien 郊外)に連れていかれた。その後ホテルでは、オーストリア航空の説明はおろか、職員が来ることは一度もなく、結局個人で直接オーストリア航空と交渉するしかなかった。ツアーで来ている人たちは、もちろんツアーコンダクターが交渉していたからそのあたりはそつなく、後から知ったが翌日のエジプト経由で帰国したという噂であった。そのそのあたりの情報は、同じホテルに泊まっていても、何の情報もないため確実な情報ではないのだが。 問題はツアー以外の個人客で、さしあたり知り合いになった人たちで個別に空港に行って直接交渉したり、あるいは電話で航空会社と交渉したり、あるいはウィーン・ミッテにオーストリア航空のカウンターがあることを知っている人間はそこに行ったりということで、もうまさに対応は様々であった。特に翌日はオーストリアの祝日にあたってしまったので、状況をさらに悪化させた。通常の職員は休日を取っていますから。特に私が目撃したウィーンミッテのオーストリア航空のカウンターの対応は、十数人ぐらいの日本人が一度に押し掛けると、仕事の交替まであと20分あるにもかかわらず、「私にはもう時間が無い。こんなに多くの人数を一度に出来ない!!」とややヒステリックに語っていた。まあだいたい有能なサラリーマンが1日分の仕事を半日で仕上げると、上司が「そんなに早く仕事をやってどうするんだ?もっとゆっくりやれ!!」というお国柄である。そのあたりはオーストリア的なおおらかさは、このような緊急の事態においてはやや問題となる。結局のところ、ようやく2日遅れでフランクフルト経由ルフト・ハンザで多くの人が帰国することになった。ただこの便で帰国できる人は情報をきちんとつかんだ人で、オーストリア航空によるアフターケアや説明は一切無いため、2日遅れでも帰国出来ない人は残っていたかもしれない。日本語しかできない個人客は、かなり困る状況であったろう。だいたいこういう状況では、言葉は悪いが、抜け駆けで交渉した方が早く帰国できる可能性が高いため、必ずしも日本人だからといって情報を他の人に流してくれる保証はない。一応オーストリア航空には、日本人のスタッフが2人いるらしいが、そのうちの1人は当日休みで、残りの一人も最初は姿が見えたが、その後は姿が見えなくなった。やはり最終的にはなんらかの方法を見つけて個人で交渉しなければならないというのは、 この地での原則である。 オーストリア航空の悪天候に対する対応も問題があるのかもしれない。後から知ったのだが、全てのウィーン発の飛行機が欠航していたわけではなく、他の航空会社では飛んでいるものもあり、それどころか同じオーストリア航空でも成田行きの直前にある大阪行きは飛んでいたというのだ。 旅行のトラブルと言えば、昔アテネからフランクフルト経由で成田に帰るとき、どちらもルフトハンザ航空で乗り継ぎにも余裕を見ていたのだが、アテネからの便が遅れ、フランクフルトで成田便に乗り遅れそうになった。巨大なフランクフルト空港を汗をかいて成田便の搭乗口にたどり着くと、ちょうどドアが閉められてしまったところだった。どうしてもその日に帰国しなければならない用事がったので、そこでルフトハンザの担当者とすったもんだしたが、結局ドアを開けさせた。ルフトハンザの担当者が言うには、ドアを開ける権限は機長が持っているとかで、たまたま機長が良い人だったのだろう。成田に着いた時、機長が寄ってきて、「文句は私にではなく、会社に言ってくれ」という言葉をかけてくれた。当然そのとき私たちのスーツケースが届いていなかったことは言うまでもないが。 数年前オーストリア航空はストをよくやったが、国民の視線は結構冷ややかだ。この国では、役人とオーストリア航空の従業員の高給ぶりは有名だから。
2006年04月22日
-

シュニッツラー「緑のオウム亭」
アルトゥール・シュニッツラー「緑のオウム亭」 Arthur Schnitzler: Das gruene Kakadu その夜は8区Josefstadtにあるヨーゼフシュタット劇場 Theater an der Josefstadt(http://www.josefstadt.org/)で、シュニッツラーの戯曲「緑のオウム亭」を見た。Josefstaedter Strasse 26にあるこのヨーゼフシュタット劇場は、私の最も好きな劇場であるが、1788年ヨーゼフ二世の治下で役者のK. Mayerが建てたもので、ウィーンで現存する劇場の中では最も古く、またかつて城壁の外にあった私立の劇場Theater an der Wienと Leopoldstaedter Theaterの中では最も小さく、座席数は現在714である。戦災を免れているので、200年前のフランス革命の前の時代の劇場の雰囲気をよく伝えており、演劇がわからなくても一見の価値のある劇場である。 私はいつもインターネットでチケットを予約し(クレジット決済)当日窓口で受け取ることにしているが、とても便利である。また座席の料金は46ユーロから19ユーロぐらいまであるが、だいたいパルテレ(Parterre)の後ろから3,4番目にすることにしている。ウィーンの劇場はどこでもそうであるが、ここは特に小さな劇場なので、後ろでも十分楽しむことができる。ここの劇場の規模を知ると、日本の劇場はまるで体育館で演劇をしているような印象を持たざるを得ない。 市電でいくにはJで行くのであるが、劇場はJosefstadt通り沿いにあるので、市庁舎から歩いてもいくことができる。劇場を入るとすぐにGarderobe(座る座席ごとに別れているが、別にどこでも預けられる。Logeは各自にコートを掛けるところがるので、Garderobeに預ける必要はない)があり、コートを預けるとホールの入り口となる。向かって右側に大きなBuffeがあり、また左右にRangに通じる階段がある。劇場の全体は深紅で統一されていて落ち着いた感じであり、装飾も豪華である。ここは普通は地元の人間しか来ないし、比較的年齢層が高いので、(日本人が来るとやはり目立つと思うが)オペラなどとは違う教養を感じさせる雰囲気である。 1988年から1997年まで有名な役者にして演出家であるOtto Schenkが、そして1997年から1999年まで役者であったHelmuth Lohner(Mag. Alexander Goetzも)が劇場監督をしていたが、今回の2003年のシーズンから劇場監督がHans Gratzerに変わったので、やや演出が変わってきているような印象を受ける。 このシュニッツラーの「緑のオウム亭」という作品は、翻訳があるかどうかわからないが、短い作品(レクラム文庫で40ページほど)なので、すぐ読むことができる。舞台はフランス革命当時のパリで、そこにある「緑のオウム亭」という不思議な飲み屋(日本でいるとバーといった感じ)を舞台にした話である。そのバーは一つの演劇の空間となっており、その主人がいわば座長でそこの客は次々と店にやってくる役者たちが演じる劇を楽しむことができる。そこは、現実と非現実的なものが交錯する空間なのであるが、客たちは十分その点をわきまえていて、役者たちの演じる非現実的なパフォーマンスを味わうのである。その役者たちの演じる内容とは、例えば、殺人を告白する話や、放火して逃げ込んできたという設定、あるいは革命が始まったという話など、この「緑のオウム亭」の空間においては、話題・パフォーマンスは何でも可能なのである。劇の最初のところで自分の叔母を殺していま出所してきた男が、ここに職を求めてやってくるのであるが、そのような男であっても、ここでは評価されうる現実として歓迎されるのである。 この作品の筋といっても、いくつかの場面がつなぎ合わされて構成されているので、それほど場面の展開に合理性を感じさせないが、一応粗筋というのは次のようなものである。アンリというこの「緑のオウム亭」で嘱望されているの役者が、別の劇場に出ている人気女優Leocadieと突然結婚したという報告をしにやってくる。そしてアンリは田舎に引っ込み、農民の生活を始めると言い出すのであるが、この主人Prospereは、アンリの才能を高く買っているので、ここにとどまるように求める。しかし叔母を殺した前科を持つGrainは、「緑のオウム亭」に職を求めてここにやってきているのであるが、彼は、この店の常連でちょうどこの店にやってきた公爵Emileがアンリの妻になったLeocadieと数時間前に逢い引きしている現場を目撃し、それを店の主人Prospereに伝える。もちろんそのことはアンリは知らないのであるが、しかし無意識のうちに気づいていたゆえなのか、彼はこの店の引退のパフォーマンスとして、まさにその公爵Emileを嫉妬のゆえに殺す場面を演じてみせる。その場にいた客たちはそのアンリの迫真の演技にすっかり騙され、その店に公爵が再び登場したときには、殺されたはずの公爵がなぜ生きているのかといった感じで、全く信じられない様子となる。しかしアンリは主人Prospereから、妻の浮気を告げられ、彼は自分の演技がまさに現実であったことを思い知り、その場で公爵を殺してしまう。そして折しも、その店の外ではバスティーユ監獄が破られることによりフランス革命が勃発し、その騒ぎが店にも伝わってくるのである。街全体が民衆の騒動に包まれているところであった。それまで常に非現実的なものが演じられてきた空間において、非現実が現実となった瞬間であった。 この作品の初演は1899年である。1幕ものであるので、場面の展開は無いが、しかしその中で様々な人物たちによる会話を楽しみながら、現実と非現実の境界を漂いながら、ある種の奇妙な空間が作り上げられている。この空間の質感こそ19世紀末のウィーンにふさわしいもので、とりあえずはその空間に自分も入ってみるというのが楽しむ一つの方法であるような気がする。その後でこの作品の解釈をやってみるのがいいであろう。演出としては、スタンドバーのような室内で、背景が全体鏡になっていた。シュニッツラーの指定では、店の中にソファーがいくつかあったはずだが、やはり安定性を排除し常に動きをもたらすために、ソファーは排除したのかもしれない。また鏡は非現実がテーマになっている作品の演出としては、オーソドックスであるが、まあ遠くから見ている人には、鏡に映った人物がよく見えるのでいいという実用的な効果も一応はある。 できればもう一度作品を見に行きたいと思っている。(2004.2.10)
2006年04月16日
-

軍事歴史博物館
軍事歴史博物館 この博物館は市内中心部から外れているため、日本人観光客がほとんど訪れないところであるが、なかなか興味深いところである。ここは南駅から南へ徒歩5,6分行った所で、市電Oでウィーンミッテ方面に1つ行ってから歩くと、若干であるが早くいける。ここはかつてのハプスブルク帝国時代の兵舎・兵器庫(アルゼナール)である。日本で兵舎、兵器庫というと、何か殺風景な施設といったイメージであるが、ここの軍事歴史博物館を宮殿のようなビザンチン風に設計したのは、フェルスターとテオフィル・ハンセンである。ハンセンは後に国会議事堂や造形芸術アカデミー、証券取引所を設計したが、軍事歴史博物館の雰囲気としては、造形芸術アカデミーが近いように思われる。兵舎・兵器庫は国立歌劇場を設計したシッカーツブルクとファン・デア・ニュルが担当している。だからここは建物群を眺めるだけでも十分価値があると思われる。 この軍事歴史博物館を含む兵舎・兵器庫の建設のきっかけとなったのは、1848年にウィーンで発生した市民革命3月革命であり、そのときウィーンは反乱市民・革命軍が一時かなり優勢になった状況も生まれたため、革命鎮圧後ハプスブルク家は前からあった要塞建設のプランを実現させたのである。(建設は1848年から1856年まで)つまりこの兵舎・兵器庫はたんなる宿泊施設・倉庫ではなく、万が一の場合には帝室一家を救出しなくてはならず、また堅牢な要塞として、また軍隊の移動のために有利な交通の要所(南駅と北駅の間、ドナウ運河の近く)に建設されたのである。ここは全体で奥行き689メートル、幅が480メートルという広大なものである。ここに31の建物があり(ほぼ現存している)、6千人収容できた兵舎、武器工場、整備工場、指令部、そして印象的なことに初めから軍事史を紹介する博物館があったのである。 この軍事歴史博物館はもちろん軍事史の紹介がその役割であるから、武器などが多く紹介されているのは当然なのであるが、ここの目玉はなんといっても第一次世界大戦開始の引き金となったサラエボでのオーストリア皇太子(フランツ・フェルディナンド)暗殺に関する展示である。皇太子が乗っていたグレーフ&シュティフト社のオープンカー(実物)を見ることができる。そしてその脇には、皇太子が着ていた制服の上着とズボンが展示されている。その上着には、犯人に撃たれた銃弾の跡と彼を手当するために上着を引き裂いた15センチほどの跡を見ることができる。 オーストリアの軍事史の主要なものを並べれば、2度にわたるトルコ軍によるウィーン包囲、神聖ローマ帝国の後進性を決定づけた30年戦争、プロイセンとの7年戦争、ナポレオン戦争、そして第一次世界大戦である。これらの戦争にちなんだ人物、武器、事柄などが詳細に展示されている。特にトルコ軍が残していった軍旗が誇らしげに天井からつり下げられていたり、また今は無きオーストリア海軍の展示(オーストリアが第一次大戦時に使用したU-Boat)などは興味深いものである。 また入り口を入ってすぐのところに、軍司令官の広間があり、そこには等身大の石づくりの歴代司令官たちの像がある。まさに霊廟といったところで、博物館の入り口にいきなり「霊廟」があるのは、オーストリアらしいところである。そこから2階へ上がる階段を上ったところにフランツ・ヨーゼフ1世の胸像が鎮座している。なんといってもこの人物はハプルブルク家にとっては、マリアテレジアと並ぶ人物で、良くも悪しくも国を体現した人物である。この人物に寄せるオーストリア国民の気持ちは、なかなか測ることができない複雑なものであるようだ。 この博物館でオーストリア軍が発明したいくつかの武器が紹介されているが、気球を使っての爆撃、軌道車なるキャタピラ(戦車の原型)の開発、そして魚雷であるが、いずれも保守的なオーストリア軍では採用されることはなく、他国が使用し始めることによって、初めてその価値を認識することになったらしい。これもまったくオーストリア的でありおもしろい話である。また前から思っていた疑問がはっきりわかったことである。ハプルブルク家では、国の名称としてK.u.K.(kaiserlich und koeniglich 帝国と王国) とK.K.(kaiserlich koeniglich 帝国にして王国)をつかっていたのであるが、やはり1866年以前は、主にK.K.を使っていて、オーストリア=ハンガリー二重帝国になってからは、主にK.u.K.が使われていることがわかった。(例外もあったが・・)K.K.は、ハンガリーが神聖ローマ帝国の版土ではないので、「神聖ローマにしてハンガリー王国」としてオーストリアを規定していたのであるが、(例えば当時オーストリアであったボヘミア王国はオーストリアであったので、それはkaiserlichに含まれているのであろう。。)1867年以降ハンガリーがオーストリアと同等の権利を持つと、K.u.K.(帝国と王国)と両者が対等に並立することになるのである。しかし有名な「双頭の鷲」はK.K.の昔から使われていたもので、決してオーストリア=ハンガリー二重帝国になってから採用されたものではないことがわかる。このK.K.とK.u.K.の差異については、オーストリア人でも知らない人が多かったようで、かつてローベルト・ムージルが「特性の無い男」の始めのところで、その神秘的差異の滑稽さについて書いている。
2006年04月16日
-
ドニゼッティの「愛の妙薬」
ドニゼッティの「愛の妙薬」 その日は曇りがちの天気であったが、それほど寒くはなく、夕方家を出るときには手袋無しでも大丈夫なほどであった。ドニゼッティの「愛の妙薬」L'Elisir d'Amore)をウィーン国立歌劇場で見た。 ドニゼッティは、ロッシーニやベッリーニと並ぶ19世紀前半のイタリアオペラ界を代表する作曲家の一人である。いわゆる「ベルカントオペラ」と称されるこの時代の作品は、歌手たちのテクニックを披露するために、美しい旋律とアジリタ(声を転がすテクニック)に特徴がある。この「愛の妙薬」は、典型的なイタリアオペラであり、筋の合理性などを考えるととても評価に値しない作品ということになるが、まあそれはそれとして、その笑劇をそのまま楽しむというのが、正しい鑑賞スタイルだと思う。 粗筋を紹介すると、登場人物は、Adina(ソプラノ) 地主の娘、Nemorino(テノール) アディーナを愛する農民の青年Belcore(バリトン)守備隊の軍曹、Dulcamara(バス) いかさま薬売り第一幕 舞台は北スペインのバスク地方の農村。農作業の合間に農民たちが広場に集まっている。その傍らで気まぐれで裕福な地主の娘アディーナは、家の階段のところで本を読んでいる。彼女に憧れているネモリーノは、賢く美しい彼女に憧れながらアリアを歌う。(「なんて美しいんだろう、なんて可愛いんだろう」)。突然アディーナが、本を読みながら笑い出す。文盲の農民たちは、彼女に本を読んでほしいと懇願する。それは中世「トリスタンとイゾルデ」の物語で、惚れ薬によって永遠の愛で結ばれた男女の物語であった。しかしアディーナにとってこんな話は滑稽なもので、こんな薬が実際になくてよかったと言う。 そこに太鼓の音とともに地方守備隊が村の広場に行進してくる。隊長の軍曹ベルコーレは、早速美しいアディーナに目をつけ、格好をつけながら彼女に言い寄る。(「昔パリスがしたように」)。彼女も内心は悪い気持ちではないが、簡単に相手を許そうとはしない。その様子を見ていたネモリーノは不安な気持ちに襲われる。そこで彼はアディーナに思い切って自分の愛の気持ちを伝えようとする。アディーナもネモリーノに関心があるのだが、気紛れな彼女は、純朴なネモリーノを軽くあしらってその場を去っていく(「そよ風にきけば」)。 そこにラッパの音を伴って、いかさま薬売りのドゥルカマーラが登場する。彼は自分を高名な医者と偽って、あちこちで偽薬を売りつけている。素朴な農民たちは彼の巧みな話術に騙され、みな争って薬を買い求める。そこへネモリーノが現れ、ドゥルカマーラに惚れ薬がないか聞きと、ドゥルカマーラはボルドーの赤ワインを惚れ薬と称して売り付ける。そして24時間したら効果が現れると言う。(二重唱「ありがとう!本当にありがとう!」)。 ネモリーノは薬を飲んで、酔っ払い、いい気分になる。そこにアディーナが現れるが、さっきとは打って変わって冷たくなった彼の態度に驚く。ネモリーノは、明日になれば彼女は自分に惚れると思い込んでいるので、彼女に全く関心がないような態度をとったのであるが、それは逆にアディーナを怒らせてしまう。 そしてベルコーレが再登場し、明日出発するので今日中に自分と結婚して欲しいとアディーナに迫ると、彼女はネモリーノへの当てつけにそれを承知する。ネモリーノは焦り、一日だけ待ってくれと騒ぎだすが、彼の慌てぶりに農民たちは彼を笑うばかりであった。 第二幕 結婚式の前に、すでに祝宴が開かれている。招待されたドゥルカマーラがやってきて余興としてアディーナと歌を歌う。(「私は金持ち、あんたは美人」)。そして公証人が結婚証明書に署名することを彼女に求めると、彼女はサインをするのは夜まで待って欲しいと頼む。彼女にはネモリーノの姿が見えないのが気にかかっている。 農民たちが去った後、ネモリーノが現れ、残っていたドゥルカマーラに助けを求める。薬をもう一瓶飲めば効果を得られるとドゥルカマーラはまた法螺を吹くが、ネモリーノにはもうお金がなかった。そこにベルコーレがネモリーノ、軍隊に入れば金が手に入ると誘うのである。ほんのわずかの時間でもアディーナの気持ちを得たいと思うネモリーノは、軍隊に入る契約をし、受けとった金でドゥルカマーラから惚れ薬を大量に買うのであった。 村の娘達が、噂話をしている。それは、ネモリーノの叔父が亡くなり、ネモリーノに莫大な遺産を残したという話である。何も知らないネモリーノが惚れ薬を飲んで酔っ払って登場すると、娘達は競って大金持ちになった彼に言い寄ろうとする。突然の娘達の変心ぶりに、ネモリーノは驚くが、きっと愛の妙薬の効果であろうと思い違いをする。 一方アディーナは、ネモリーノが惚れ薬を買うために軍隊に入る契約をしてお金を作ったことをドゥルカマーラから聞き出す。感動した彼女は、彼女に惚れ薬を売り付けようとするドゥルカマーラを退け、自分の力で彼の愛を得ようとする。 アディーナの目に涙が光ったのを見たネモリーノは、彼女に愛されたなら死んでもいいと歌う。(「人知れぬ涙」)。そして彼の入隊契約書を買い受けて戻ってきたアディーナは、ネモリーノにこの村にとどまるように頼むが、自分の本当の気持ちはまだ口にしない。ネモリーノはそんな彼女に、愛されていないなら戦場で死ぬと言うと、ついに彼女も愛を打ち明ける。 ベルコーレはこの様子を見て驚くが、女は彼女だけじゃないと開き直る。そこにドゥルカマーラが村人に別れを告げにやってくるが、農民たちはこぞって彼を賞賛し、その歓声を受けながらドゥルカマーラは馬車で村を去っていくのである。 L'ELISIR D'AMORE (133. Auffuhrung in dieser Inszenierung)Dirigent: Frederic Chaslinnach einer Inszenierungvon: Otto SchenkAusstattung: Jurgen RoseChoreinstudierung: Marco OzbicAdina: Simina IvanNemorino: Antonino SiragusaBelcore: Markus NieminenDulcamara: Alfred ?ramekGiannetta: Teodora GheorghiuTrompeter: Konrad MonsbergerDiener Dulcamaras: Michael Burggasser Otto Schenkの演出なので、無難ではあるが、何か新しいものを見つけるというのは難しい。舞台は町の広場で、両側に民家があり、右側がAdinaの家で、階段が2階に通じていて、その途中には踊り場があり、プランターなどの飾りが綺麗に置かれいた。そして2階のベランダにはテーブルと椅子がある。舞台正面は壁になっており、DulcamaraやBelcoreの軍隊の入場は、その壁にある門からされていた。2幕とも同じ舞台装置を使っていた。 Adina: Simina IvanNemorino: Antonino SiragusaBelcore: Markus NieminenDulcamara: Alfred ?ramekGiannetta: Teodora GheorghiuTrompeter: Konrad MonsbergerDiener Dulcamaras: Michael Burggasser Simina Ivan は、日本ではほとんど知られていないと思うが、ルーマニア生まれで1994年まで主にルーマニアのブカレストを中心にオペラ・オペレッタにおいて演奏活動をしていたが、1994年ウィーンのフォルクスオパーでGIANNI SCHICHHIのLauretta役でウィーンにデビューしてから、同じ年に国立歌劇場でもデビューしており、その後「後宮からの逃走」のKonstanze役、 「セビリアの理髪師」のMusett役、「こうもり」のAdele役などを演じてきている。今年はハンブルク国立オペラやドレスデン国立オペラなどの客演も予定されており、活動の幅を広げつつある。彼女の知的で伸びやかな声はAdina役に向いている。しかしややドラマチックな表現に欠けるきらいもあり、2幕の最後でネモリーノに心を寄せていく場面などは、ややその表現に平板さを感じさせた。これからが期待される。 アントーニオ シラグーサは、シチリア・メッシーナ生まれで、96年ジュゼッペ・ディ・ステファノ国際コンクールで優勝し、ベネツィアのフェニーチェ座で最初のキャリアをスタートさせている。DON GIOVANNのDon Ottavio役や、COSI FAN TUTTEのDon Ferrando役、GIANNI SCHICCHIのRinuccio役、そして、ウィーン国立歌劇場ではIL BARBIERE DI SIVIGLIAのAlmaviva伯爵役で2001年デビューしている。彼のオペラ・デビューは今日演じた「愛の妙薬」のネモリーノであり、彼のはまり役なのであろう。私が一昨年の東京の新国立劇場での「セビリアの理髪師」のアルヴァビーバ伯爵を聞いていたが、その明るい心地よい声は、深みを表現するにはやや不向きな面もあるが、聞き手に快感を与える。テクニックも安定感があり、安心して聞いていられる歌手である。 個人的な評であるが、Giannetta役のTeodora Gheorghiuは、歌もさることながら、容貌はなかなか魅力的な歌手であった。
2006年04月16日
-
ウィーンのホテル
今度のゴールデンウィークはヨーロッパでは特にイタリアとオーストリアが旅行先として人気だそうだ。オーストリアはモーツアルト生誕250年だそうだ。もう行く人はホテルを予約しているだろう。 ウィーンは観光都市だけに、ホテルはっきり言って高い。最高級でかつてハプスブルクの迎賓館として使われたインペリアル(天皇陛下もお泊まりである)、トルテで有名なザッハー(一年中周囲はうるさい。昨年は工事中だったが)、レストラン(コルソ)で有名なブリストル、かつてANAが持っていたグランド(ウィーンで一番評価の高い日本料理屋が入っている)など、いずれも5星であるが、はたしてあんな大枚をはたいて泊まる価値があるのだろうかと思ってしまう。まあ、棺桶に足をつっこむぐらいの年齢になったら一度は泊まってもよいかもしれないが。 ただインペリアル以外は、最近は格安のホテル予約などがでてきているので、比較的リーズナブルに泊まれることもある。それでも1泊ツイン(朝食無し)で3万ぐらいである。格安のホテル予約のHPhttp://www.hoteltravel.com/jp/austria/hotels.htmhttp://appleworld.com/hotelinfo/bsrch/bsrchStep3.do?ref=APL&home=http%3A%2F%2Fappleworld.com%2F&areaCode=EUROPE&countryCode=AT&cityCode=VIE コストパフォーマンスの高いホテル(交通の便が良く、ツインで1万5千円以下)をいくつか挙げておくと、 ・メルキュール ウィーン ウエストバーンホフ(旧ドリント アム ヨーロッパプラッツ) 西駅近くで便利 ・オーストリア トレンド ホテル アナナス U-4の地下鉄駅近く。団体客がよく利用。 ・オーストリア トレンド オイローパ ウィーン 1区の街の中心で便利 ・ソフィテル ウィーン アカデミー劇場の近く。シュワルツェンベルク広場まですぐ。 ・メルキュール ウィーン ツェントラム スェーデンプラッツから徒歩3分。 ・K+K マリア テレジア 美術史美術館の裏手 予約によっては高くなる。 ・アルトヴィーナーホーフ http://www.altwienerhof.at/ 地下鉄駅から徒歩2分 長期滞在であれば値切れます。 時期によってもちろん値段は上下するので注意が必要である。あと家族で長期滞在ならば、休暇用アパートがおすすめ。3部屋程度で1泊1万円程度で、1週間や1ヶ月契約もあるが、たいていが1日単位で貸してくれる。 http://www.apartment.at/index.php3/ 特に次のところは私の知人が泊まったが、1区の街中のとてもよいアパートであった。大家さんも親切であったので、おすすめである。 http://www.apartment.at/index.php3/app/9/Lauer
2006年04月16日
-

ウィーンのアパート
私がウィーンで住んでいたのは、3区のラントシュトラーセのアパートだった。ウィーンに着いた当初住んでいたのは12区であったが、後に3区に引っ越した。 ウィーンには東京と同じで1区から23区まである。日本は比較的一つの地区に様々な人間(金持ちから所得の低い人まで、職種の多様な人たち)が住んでいるが、ヨーロッパでは特に大都市で地区によって特徴のあるところが少なくない。ウィーンもその街の一つである。ウィーンでは19世紀に爆発的に人口増加が起こり、ハプスブルク帝国のさまざまな地方から首都ウィーンに人口が流入した時に、その出身や階層によって特定の地域などに固まって住んだということがその理由に挙げられる。例えば、領内の東の地域のユダヤ人たちは、現在のプラーター遊園地のところにある北駅(現在ではあまりその面影はないが・・)に列車で到着し、その周辺に(現在の2区)親類・知人をたよって住み着いたということである。そのため2区にはシナゴーグが数多く作られ、ヒトラー時代の「クリスタルの夜」では、シナゴーグが破壊される被害を受けた。 私の住んでいた13区のシェーンブルンに近いもののかつての労働者地区に近く、お世辞にも高級住宅街とは言えなかった。ウィーンで金持ちが住むのは、1区、13区、19区と相場が決まっている。1区はリングの中の中心部、13区と19区は中心部から西側に車で20分ほどかかるやや郊外に位置した地域である。ウィーンの在留邦人が最も多く住んでいるのは19区であるが、そこはホイリゲのあるグリンツィングで有名である。13区はシェーンブルンがあり、その背後にはかつて「避暑地」であったこの場所に、今でも高級住宅街が並んでいる。かつてゆっくり散歩したことがあったが、ヒーツィング墓地(ミツコの墓などがある)などもあり落ち着いた雰囲気である。http://plaza.rakuten.co.jp/landstrasse/diary/200411010000/http://plaza.rakuten.co.jp/landstrasse/diary/200406230000/ ただ13区も19区も家族持ちの長期滞在にはよいだろうが、単身赴任の私はやや退屈な地区であった。かつて2ヶ月ほど19区の一番端のSalmansdorfという地区に住んだことがあったが、ウィーンの森にも近くとても素敵なウィーン随一の高級住宅地であり、年金生活に入った役人などが多く住んでいたが、ただやや郊外のため街中からは不便であり、オペラなどが終わるとすでにバスが終わっていたりして苦労した。 そこでどこに住もうかと考えたときに、まず1区は理想的ではあるが、家賃は高いし年中観光客がいてあまり落ち着かないのでパスした。次ぎに候補に挙がりそうなのが、リングから西にリーニエヴァルあたりまで広がる6,7,8区あたりだが、ここらも比較的家賃が高いし、バス利用になる場所が多い。バスや市電のデメリットは、時間が計算できない上に終バスの時間が早い。ウィーンで移動するなら、やはり断然地下鉄が良い。やはり地下鉄駅から歩いていけるところが良い。 そこで地下鉄の路線を中心に考えることにした。ウィーンでは地下鉄の車内の雰囲気は、走る地域を如実に反映しているところがおもしろい。ウィーンでは、Uー1からU-6(U-5は無い)まであって、それぞれ個性的な路線であるが、Uー1は最も古い地区を南から北東に延びている路線で、リング内を通るのでよく使うが、なぜか車内に不快な臭いが染みついていてどうも好きになれなかった。ウィーン人が言うには、下水が近くを取っているので、臭いのだろうという話しである。特にシュテファンスドームの駅の地下はあまり快適ではない。やはり一番快適なのは、U-3かUー4の路線だろう。U-4はヒーツィングからハイリゲンシュタットまで伸びる路線で、よく使ったが、車内の雰囲気も悪くない。最初12区にいたころは、カールスプラッツからUー4を使っていた。しかし選んだのはU-3であった。U-3は比較的新しい路線で、ウィーンの中では最も便利な路線で特に買い物をするには便利である。
2006年04月16日
-

George Enescu 「エディプス」
今日は夜オペラ座でOedipeを見た。もちろんドイツ語ではOedipusである。 家を出る前に近くのMerkurで買い物をしたので、出かけたのが7時10分になってしまって、実際にオペラ座についてのがもう7時半で、あやうく見逃すところであった。すでに演奏は始まったいたのた。しかしなんとかぎりぎり入れてもらえた。席はかなり後ろの方であったので、かなり見にくい位置であった。この上演はベルリン・ドイツ・オペラの協力ということで、演出がGoetz Friedrichなので、そのままドイツから舞台かあるいは演出を持ってきたものであろう。ウィーンではこの演出での上演は12回目である。 もちろん原作はギリシャ悲劇のソフォクレス「エディプス王」である。しかしこの作品をウィーンで見ることには若干の意味があるだろう。つまりこの作品は現代的な意味おいて再評価したのは、ウィーンの精神分析学者フロイトだからである。フロイトはこの「エディプス」の神話の中に人間の持つ根元的な欲望、つまり父親を殺して母親と結ばれたいとする欲望を見て、そしてその欲望を自己の中で制御する過程、それが人間の社会化の最初の過程であると見なしたのである。その意味で、まさにこの劇は欲望の劇として見ることができるのであるが、しかしこのオペラのテーマは、人間の欲望というよりはむしろ、運命に翻弄される弱い人間が自分の認識し、最後にはその運命を受け入れるといったものである。むしろここで欲望を体現していたのは、Creonであったが、しかし話の中ではそれほど発展性を持つことはなかった。 George Enescuの音楽は思ったほど悪くはなかった。ワーグナーのように音楽が全面に出るということはあまりなく、やや控えめな感じであり、むしろ「付随音楽」といった感じであった。ただ音楽とオペラの内容が一致していたかどうかは疑問である。すでにワーグナーの音楽を知っている私たちは、やはりライト・モティーフに馴らされているせいか、個々の人間の感情をもう少し細かく表現してもらいたいという印象を持たずにはいられなかった。 Friedrichの演出は悪くはなかった。最後「エディプス王」が黄泉の国に沈んでいく場面は、もう少し工夫があってもよかったような気もしたが。過去に死んだ人々を登場させたのはいいが、もう少し黄泉の国のイメージを出してもらいたかった。単に舞台の奥に消えていくだけでよいのか?やはり下へ沈んで行くイメージを出す必要があるのではないか?キリスト教的な昇天のイメージとは反対の死の概念が提示されるべきであった。 ただ衣装はなかなか綺麗だった。舞台はGottfried PilzとIsabel Ines Glatharが担当である。 指揮: Michael Boder Oedipe: Esa Ruuttunen Laios: John Dickie Jocaste: Margareta Hintermeier Antigone: Antigone Papoulkas (この人は宿命的にAntigoneを歌うのか?) 2004.1.26
2006年04月15日
-
ジョルダーノ 「アンドレア・シェニエ」
今日は昼から国立図書館に行った。注文しておいた「Das gruene Kakadu」のDiss.はどうも貸し出し中で、手に入れることはできず、その他注文した本も手に入れることはできなかった。ちょっと無駄足っぽかったがまあそれなりに時間を使った。どうも私の名前の登録は、姓名が逆になっているようで、向こうは時々混乱しているようである。これからは仕方ないので、姓名を逆に書くことにする。シュニッツラーの”Das gruene Kakadu”を途中まで読んだ後、4時過ぎにそのままオペラ座に向かった。今日はGiordanoの"Anrea Chenier"であるが、前回月曜日に行ったときには結構込んでいたので、今日は早めに1時間半ぐらい前に着くようにいった。途中Bundestheaterkasseで演劇のチケットを引き取りにいくために、国立図書館から歩いてVolksgartenを通ってオペラ座にむかった。Bundestheaterkasseではこちらの申し込みのコピーをそのまま出しただけで問題なく受け取れた。オペラ座に着いたが、あまりまだ客は来て無くて、入り口の突き当たりの、例の手すりのちょっと後ろのほうに並び、結局Parterreは46番であった。一時間前にはチケットを売ってくれ、40分前ぐらいには席に入れてくれた。立っている間、昨夜見た「Das gruene Kakadu」のテキストを引き続き読んでいた。Parterreの立ち見は2箇所に並ぶのであるが、入り口から入ったところと、もう一つ左側の階段から入る方と二つある。どちらが有利なのかよくわからないが、どうも交互に客をいれているようなので、手前のほうが(向かって右から入る入り口)早いように思えるが、前行ったときには、向かって左方が空いていて、しかも左右両方から入れていたような気がするので、場合によってなんとも言えないようである。最近は朝9時ぐらいに石の下に自分の予約を示す紙を置いておいて順番を取る方法が廃止になったようなので、すこし常連が少なくなったということである。 "Andrea Chenier"は月曜日に引き続き2回目であったが、前回はGalerieの一番脇のとても見にくいところだったので、あまり良い印象がなかったが、今日はParterreの前から5列目ぐらいだったので、とてもよく見え、その分印象もだいぶよくなった。休憩は2回入るのであるが、前回と若干変わっていて、1幕の後は同じであるが、前回は3幕の後に入ったが、今回は2幕目の後に休憩が入った。歌手はChenierが、Jose Cura、 GerardがRenato Bruson、そして Maddalenaが Norma Fantiniで指揮はViottiであった。前回比べると場所が違うのでなんとも言えないが、前回に比べると歌手はだいぶよく歌っていたように思った。Jose Curaは今や3大テノールを超える人気があるが、やはりかなり光っていた。私はこのオペラは初めて聞くが、1幕目の体制批判をする歌や、4幕目のMaddalenaと最後合唱するところなどは、かなりの拍手であった。Renato Brusonの評価はちょっとわからない。観客は結構拍手を送っていたが、聞いた感じではまあまあってところで、強烈な印象というほどまではいかなかった。しかし新聞などの評では、Brusonの個性的な演技はかなり評価されている。Norma Fantiniは今売り出し中だけあって、よかったと思う。声に艶があり、声量もあるので、これから確実に将来が嘱望される歌手であることを思わせた。パンフには彼女がこれまで出演したオペラハウスがのっていたが、(東京の新オペラ座にもでている)ほとんど有名なオペラハウスはでていて、ウィーンが最後といった感じであった。 舞台・演出も今回の方がよく見えた。1幕目は絢爛豪華な貴族の大広間、奥に重厚なカーテンがかかっており、中央のドアがあり、そこから人が出入りしていた。2幕目はシェニエが手紙の相手をまっているカフェ、3幕目は即決裁判が行われる広場、4幕目は監獄。3幕と4幕は周囲が住居で囲まれており、同じセットを使っている。演出はオットーシェンクであるが、まあ一般的な演出である。喜劇ではないので、オットーシェンクらしさがでているかどうか疑問であるが、まあオーソドックスにまとまっていた。まあこの手の作品は、演出の変えようがないので演出家もなかなか難しいところではあるが、これからはこのような歴史物も演出を考える時期が来ているように思われる。少なくともウィーンはまだ依然として保守的であることは間違いない。演出で感動させるような場面があまりないのが残念であるが、その代わり歌手とオケはなかなかよかった。Viottiという指揮者は、やはりイタリアだけあって、歌わせるところをちゃんと心得ている。この前のワルキューレのメルクルとはだいぶ違うタイプであるが。 後日新国立劇場でこの「アンドレア・シェニエ」を聞いたが、やはり聞くんじゃなかったと後悔した。
2006年04月15日
-
小沢征爾 「ドン・ジョヴァンニ」
今日は昼からBurgの新王宮にある国立図書館に行った。 この新王宮が面したHeldenplatz(英雄広場)は様々な意味を持っている空間であるが、(もともと英雄広場という名前は、ここに立っているオーストリアの英雄カール大公とプリンツ・オイガン公の巨大な騎馬像に由来している。この像をカール大帝と間違えている人が多いが・・・)かつてナチスドイツが1938年3月12日オーストリアに軍事侵攻をしたときに、ヒトラーがこの英雄広場に面したこの新王宮のテラスから集まった10万人の市民に対して「オーストリア併合」の有名な演説を行った場所である。当時のオーストリア首相シュシニクは、1938年2月に、ドイツのミュンヘンの南ベルヒテスガルテンにあるヒトラーの別荘に呼びつけられ、ヒトラーからオーストリア併合の承諾を迫られた。その対応に窮したシュシニクは帰国後、国民の信任によってこの難局を切り抜けようと国民投票に打ってでようとしたが、それが裏目にでて、国民投票が実際に行われる直前(1部では行われていたが)にドイツが3月12日午前8時にオーストリアへ軍事侵攻した。オーストリアはほとんど抵抗を見せず、この信仰は無血にうちに成功した。そして首相シュシニクは亡命せざるをえず、首相代行となった親独派の内相ザイス=インクヴァルトは、この軍事侵攻をオーストリアによって「要請」されたという形にして処理した。当時オーストリアは潜在的な右派(キリスト教民主党・ナチス系政党)と左派(すでにシュシニク政権のもとでは禁止されていたが、社会民主党・共産党)の対立が根深かったが、これによりオーストリアは第2ファシズム期(シュシニク政権も一種のファシズム政権であった。イタリア・ファシズムに近い立場であったが。)結局オーストリアは、「ドイツ帝国とオーストリア共和国の再統合に関す法律」により、ドイツの1州「オストマルク」となることによって国が消えることになった。 かつてハプスブルク王家の人たちが住んでいたのがHofburugであるが、この新王宮は、造営は遅く、完成したのはすでにハプスブルク帝国は消滅してしまっていた。だから、ここにはフランツ・ヨーゼフは一度も足を踏み入れていない。現在では国立図書館、エフェソス博物館、古楽器博物館、宮廷武器甲冑博物館そして民族学博物館などが入っている。それぞれの博物館が特徴がありおもしろい。特に古楽器博物館、宮廷武器甲冑博物館のコレクションは興味深く、古楽器博物館では現存しないような楽器やこれまでの楽器の進化の過程などがよくわかっておもしろい。またウィーンはピアノのBoesendorferの地元なので、すばらしいBoesendorferのコレクションがある。また宮廷武器甲冑博物館のコレクションも見事である。グラーツにある武器博物館はその量において人を圧倒するが、ここのコレクションは、マクシミリアン1世(Maximilian 1 生没年:1459-1519)やカール5世の甲冑など、工芸品として美術品として、そして歴史的な価値において見事なものである。 図書館では前日インターネットで予約しておいた本を借り受け、コピーをした。(ここのコピーは150枚10ユーロである。1枚9円ぐらい)オーストリアの民衆劇作家であるNestroyとZensur検閲の問題を扱ったものはなかなかおもしろそうであった。この問題は日本ではほとんど扱われていないので、参考になる。一昨日みたシュニッツラーのDas gruene Kakaduに関して現実と仮象との関係から書かれた論文も見たいと思ったが、それはどうも貸し出し中で手に入らなかった。あとJosepf Rothの小説に関するものも手に入ったがそれは翌日以降にまわすことにした。 図書館には3時間ぐらいいて、5時半ごろオペラ座に向かった。今日は小沢征爾の「ドンジョバンニ」である。これは6月に1回見たプログラムであったが、もちろん歌手は違っている。Wiener StaatsoperDirigent: Seiji OzawaDon Giovanni - Michael Volle Komtur - Mikhail KazakovDonna Anna - Anna NetrebkoDon Ottavio - Rainer TrostDonna Elvira - Soile IsokoskiLeporello - Ildebrando d' ArcangeloZerlina - Sophie KochMasetto - In-Sung Sim 印象としては、無難な作品の出来であるが、これといった特徴もないのも特徴である。はDonna Annaの衣装がとても目立ったというところだろうか。このDonna Anna役が一番この作品の中では難しいように思える。つまりDon Giovanniを憎みつつ惹かれるという役回りである。Anna Netrebkoは、伝統的なスタイルを保ちつつ時折そこから逸脱しようとする努力を見せていた。しかし回りの雰囲気から完全に脱することは出来ていなかった。ドンジョヴァンニ役のMichael Volleは、まあ優等生的な出来であった。それほどの感動もないが、まあ満足といった程度である。Elvira役のSoile Isokoskiもよく歌っていたが、これもまあ及第点といったところである。 小沢の演奏であるが、新聞などを見ると厳しい評価もある。Bei Ozawa tragt Mozart keinen Masanzug, sondern Konfektionsware, alles von der gleichen Farbe, ein wenig duster, ein wenig dumpf. 彼のモーツアルトはいつも既製品で、同じ色合いで、陰影が無い。 Der Applaus war stark nachher, aber blieb im Rahmen. Starkult ? fur wen auch immer ? war daraus jedenfalls keiner abzulesen. 拍手はとてもあったが、型どおりのものであった。彼のスター性は、演奏からは感じられなかった。 でもまあモーツアルトはいつ聴いてもいいものである。今日は偶然知りあいのS教授にオペラ座であった。オペラの後で一緒に近くのタイ料理やSiamという所に行った。なかなかよかった。私は「鶏肉のご飯炒め」(Kao Pat Mu)というのを頼んだが、最初は気が付かなかったが、なかなか辛い一品である。これは地元の人では食べられないだろうなあと思いながら食べた。でも辛いものは久しぶりなのでおいしく食べた。こんどまた来ようと思う。(2005.2.12)
2006年04月15日
-
5月のブルク劇場の上演
5月のブルク劇場もなかなか目が離せない、バランスの取れたレパートリーが並んでいる。オーストリア・ドイツの古典から現代まで、それに笑劇もといった具合である。 まず話題になりそうなのが、モーツアルトの「後宮からの逃走」を劇場版にアレンジした作品のプレミアがある。もちろんこれはモーツアルト生誕250年記念の行事の一貫だろうが、意欲的な作品になりそうだ。この「後宮からの逃走」は2年前ザルツブルク音楽祭で見たが、この作品が”行間”に持つ解釈の多様性に驚かせられ、今まで見てきた作品とはまったく異なる斬新で自由な(恣意性も排除できないが・・)演出を見せられたが、劇場版ではさらにその解釈を先鋭化させる路線を推し進めることであろう。「後宮」という欲望うずまく世界が、これまでの演出のようにあまりに素直に人間の徳が称えられている世界として描かれるのにちょっと飽き飽きしたのであろう。 次ぎに笑劇のレパートリーも魅力的である。まずネストロイの「1階と2階」(Zu ebener Erde und erster Stock oder Die Launen des Glücks)は、今はやりの格差社会を先取りしたような作品である。これはむかし「8時だよ全員集合」の舞台装置でよく見かけられたものと言って良いぐらいで、舞台を上下で1階と2階で区切り、そこに金持ちと貧乏人を住まわせ、視覚的に格差を演出させてみせたものである。それにオーストリアで最も人気のある喜劇作家であるネストロイの作品の中でもこの作品は傑出したものの一つで、社会風刺をたっぷり含んだその台詞もそつなくその場の雰囲気を作っている。 もう一つネストロイの作品は「80分のタンホイザー、ワーグナーのパロディ」(Tannhäuser in 80 Minuten - nach Richard Wagner)で、題名にもあるようにワーグナーの喜劇「タンホイザー」のパロディである。オペラファンには必見の作品である。これは後にオットー・シェンクがオペラのパロディを数多く手がけるが、その最初のアイディアを与えたものの一つではないかと思っている。 ネストロイと並ぶ喜劇作家ライムントの「浪費家」も見逃せない。かつてVolkstheaterで上演したものを見たことがあるが、これも当時の資本主義的な社会と痛烈に皮肉った作品である。 古典と言えば、グリルパルツァーの傑作「オットカール王の栄華と最後」、ゲーテの「タッソー」、シラーの「ドン・カルロス」。「ドン・カルロス」は以前数度見たことあるが、秀逸な演出である。かなり長時間の上演であるが、緊張感が途切れることなくドンカルロスと父王、それに后との錯綜した関係が見事に描かれている。一昨年初演であったと思うが、その年にオーストリアの何かの演劇賞を取っていたと思う。「オットカール王の栄華と最後」は残念ながらまだ見たことはないが、ゲーテ、シラーはドイツでも見られるが、グリルパルツァーの作品はここで見るべきだ。ボヘミア王・オットカールは、ハプスブルクの始祖ルドルフ1世が戦った相手であり、1278年ルドルフ1世がオットカールをマルヒフェルトに破ることで、ハプスブルクのオーストリアにおける覇権が確定したが、このオットカールの栄光と挫折の物語の中に運命と自己の欲望に翻弄される人間の普遍的な姿が描かれている。 アカデミー劇場の「エルゼ嬢」は、以前書いたが、これもシュニッツラーの作品を見事な一人芝居に描きなおされている。これは見ていない方は、必見の作品である。
2006年04月15日
-
イースター
春の訪れを告げるのがイースターである。クリスマスはすっかり日本に定着したが、イエス・キリストが十字架にかけられたイースター(ドイツ語ではOstern)はあまり馴染みがない人も多いだろう。この復活祭は、春分のあとの最初の満月の直後の日曜日(3月下旬~4月下旬あたり)ということになっているので、毎年日にちが異なってくるので、いちいち今年の日付を確認する必要がある。だから3月下旬だとまだまだ寒いが、今年のように4月になるとだいぶ暖かいイースターということになる。 イースターといえば、色とりどり、装飾いろいろで飾られるイーストエッグとウサギのチョコレートである。この時期には、ウサギは古来から繁殖力の強いので、繁栄や多産の象徴とされてきたのである。
2006年04月14日
-
外国人にも住み易い街 ウィーン
アメリカのマーサー・ヒューマン・リソース・コンサルティング(MHRC)は世界215都市の「生活の質」を比較した結果、ウィーンは4位にランクされた。ちなみに東京は35位であった。 MHRCはニューヨーク(100点)を基準に外国人にとってその街がどれくらい住みやすいかを評価し、数値化した。 政治・社会・経済・環境など39項目が採点の対象。 1、2位スイスのチューリヒ(108.2点)とジュネーブ(108.1)、それに カナダのバンクーバー、オーストリアのウィーン、ニュージーランドのオークランドが続いた。 地域別にはヨーロッパの都市が上位に入った。 ドイツではデュッセルドルフ・フランクフルト・ミュンヘンが10位以内に入った。フランスのパリは33位、ロンドンは39位と比較的高かった。 アジアではシンガポールが34位で最上位。 アメリカではホノルルが27位、サンフランシスコが28位、ボストンが36位であった。ちなみに最下位は、イラクのバグダッドだった。当然というべきか。
2006年04月13日
-
ウィーンで音楽を聴きたいなら
ゴールデンウィークの海外旅行はヨーロッパが比較的人気だという。もちろん、人数だけみれば、近場の中国や韓国が上位で、それに次いで東南アジア、アメリカ(前年比マイナス)あたりが多いようだが、ヨーロッパもそこそこの人気だという。特にイタリア(トリノオリンピックの影響だそうだが)とオーストリアが人気あるとのこと。何故オーストリア?と思ったが、モーツアルトの生誕250年の影響があるらしい。日本にもまだモーツアルトを聞くためにわざわざウィーンまで出かけていく人がたくさんいると思うと、日本人のモーツアルト好きもなかなかのものなんだだろう。 でもほんとうにウィーンで音楽を聴きたいならゴールデンウィーク後のウィーン芸術週間に限る。この芸術週間のプログラムは圧巻である。ウィーンはもともと街全体が年中芸術週間といったところなので、わざわざ芸術週間などと銘うたなくてもいいとおもうのだが、この時期には特にメジャーな演奏家が大挙してウィーンに押しかける。特に楽友協会のプログラムは目が眩むばかりで、こんなのを日本で聞くとしたら、ゆうに1年間はかかりそうなそんなプログラムである。しかもなんといっても値段も安い。楽友教会で立ち見ならたったの5ユーロ程度だ。 楽友教会のホール(いわゆる黄金のホール)は、古いだけあって、どこからでも見やすいというわけではない。かつてフランスでテニスコートをコンサートホールに使っていたと言われているが、そんなことを思わせる形である。だから特に最前列と正面を除いた2F席からの眺めが非常に悪い。舞台を見えない席もかなりある。ニューイヤーコンサートなどで、立ち上がっている人がいれば、その人の席がそうなのだ。しかしだからといって、値段が安いというわけではない。日本人がいくとよくこの2階席の2列目を売りつけられるから注意すべきである。各日に安く「見たい」なら、立見席に1時間も前に並んでいれば確実に見ることができる。 芸術週間の時期に日本のクラシックファンで休みをとってくるウィーンに来る人も多いようだ。私もリタイアしたら、季節の良い5月にゆっくりウィーンで芸術三昧といきたいところである。特に今年はモーツアルトの生誕250周年で、ザルツブルク音楽祭ではすべてのモーツアルトのオペラ作品を上演するという壮大なプログラムが組まれている。ザルツブルク音楽祭(本来は祝祭劇と言う)といえば、ほんとうは「イエーダーマン」(この作品の上演からザルツブルク音楽祭が始まった)を見るべきなのであるが、その楽しみも将来に残しておこう。
2006年04月12日
-

「サウンド・オブ・ミュージック」・・・オーストリアの憂鬱
「サウンド・オブ・ミュージック」・・・オーストリアの憂鬱 日本人がオーストリアに対して持っている先入観の一つとしてよく譬え話で使われるものが、「サウンド・オブ・ミュージック」という映画である。日本人ならだいたい一度は見たことか、あるいは名前だけでも聞いたことがあるだろう。またこの映画で歌われた「ドレミの歌」とか「エーデルワイス」などは日本では学校で習うぐらい有名であるが、それに対して、オーストリア人はこの映画をほとんど知らない。もちろん知っている人もいるが、多くの人はこの映画に対して不快感を持つし、そのためオーストリアではほとんど上演されることはないらしい。(それに対して「第三の男」は常にどこかの映画館で上演されているというのは本当らしい。) この映画は、ある意味では政治的な文脈をすっかり切り落とした、非常に誤解を与えやすい問題のある映画なのである。 この映画の舞台は、オーストリアのザルツブルク(もちろんモーツアルトの生まれ故郷であり、この映画でもそのザルツブルク音楽祭が舞台になっている)であり、美しいザルツカンマーグートの自然を背景に、ジュリー・アンドリュースが扮する修道女マリアとフォン・トラップ一家(ドイツではvonが貴族の称号)の物語が描かれており、普通に見れば、ある種の政治的メッセージ、つまりナチス・ドイツヘの「抵抗」という主題をこの映画から読みとれると、この映画を見る人は誰しもが思うわけである。 とにかく、見るものをミスリードする要素がいくつもある。例えば、この映画のラストシーンでトラップ一家は、ザルツブルク音楽祭の会場から脱出し、山を越えて外国に亡命する設定になっているが、ザルツブルクから山を越えて逃げたら、ドイツ(当然当時はナチスドイツ)に入ってしまうのである!! つまり、歩いて亡命するという場面設定は、致命的な地勢的な誤解を与えている。しかしそれ以上に問題なのは、主人公の一人であるトラップ大佐の政治的な立場に対する説明不足にある。 この映画は実話に基づいていて、映画で主人公となっているマリアにあたる女性がアメリカに亡命したのち出版したものであるが、このトラップという人物は、オーストリア海軍のエリートで、中国の義和団の乱や、第一次大戦で活躍している。そして彼は、物語の中では、ナチス・ドイツからの出頭命令を拒絶して外国に亡命するという設定になっているので、一見するとナチスの支配に抵抗して亡命した民主主義者か何かのように見えるのである。少なくとも映画の中ではそのあたりの政治的な背景が故意に切り落とされているのである。確かに、トラップ大佐は、ナチスには抵抗していたが、彼がナチスに反対していたのは、実はファシズムへの抵抗の気持ちからではなくて、映画ではほとんど描かれていないが、彼は、1938年にナチスに併合される以前にオーストリアで政権を握っていたドレフス=シュシュニック(Dollfuss ? Schuschnig Regime )体制の支持者であったからである。 ドレフス=シュシュニック体制という一種のファシズム体制(この体制をどのように定義してよいかは諸説あるが・・)日本ではナチスの影に隠れてほとんど知られていないのである。実は、ナチスとほぼ同じ頃1934年に成立したイタリア・ファシズムとカトリック教会に支持された権威主義的体制であり、この政権のもとでは、社会民主党や共産党など、野党政党はすべて禁止され、日本の大政翼賛会のようなファシズム的な翼賛組織がつくられていた。この体制をファシズムと見なすかどうかは、議論が分かれているが、しかし少なくとも現在の言うところの民主主義的とはとてもいえない身分制国家であったことには違いない。だから、カトリックとイタリア・ファシズムの後見を成立したドルフスとその後継者たるシュシュニックの政治体制は、自らの支配体制を脅かす意味で、ナチス・ドイツに反対していたのです。(ファシズム体制初期においては、ドイツとイタリアはむしろ対立関係にあり、その対立関係の中にオーストリア・ファシズム体制も組み込まれていた。しかしその対立関係が終焉すると、オーストリア・ファシズムは行き所を失い、ドイツに軍事的併合されることになる。) 首相のドルフスは、オーストリアをイタリアの影響力から引き離し、直接支配を狙うナチス・ドイツの指示で起こされたオーストリア=ナチスの蜂起によって暗殺され、彼の後を継いだシュシュニックは、1938年にヒトラーにドイツに呼びつけられ軍事的脅迫を受けた際、国民投票によってオーストリアの独立を守ろうとしたが、すでに国民の支持を失っていた。シュシュニックらが拠り所にしていたイタリア・ファシズム(ムッソリーニ)は、彼を飛び越してヒトラーと和解してしまうと、彼らは行き場を失ってしまう。反ナチス勢力として連帯も期待できたであろう反ファシズム勢力は、オーストリア国内においては、すでにシュシュニックらの手で弾圧されてしまっていたという皮肉な結果に至るのである。そのため、トラップのようなシュシュニック支持者は、ナチスと妥協するか、亡命するしかなかったのである。 ナチス・ドイツとの併合後、オーストリアの反ナチスの人々は、国外に亡命していったが、その亡命オーストリア人の内訳は様々であった。例えば多くのユダヤ人がいたが、それ以外にも左翼の人々、そしてシュシュニック派のような右翼の人びともいた。これらの人々は、ナチス・ドイツからオーストリアを解放するという点においては一致し、海外で共同戦線を組む場合もあり、その共同戦線の成果は、1943年モスクワ宣言によって、オーストリアがヒトラーの占領政策の最初の犠牲者であり、「自由で独立したオーストリアの再建」が必要であることを連合軍に認めさせたことに示された。このいわゆる「犠牲者論」が、オーストリアにとってはきわめて得難い政治的成果であることは、戦後になってはじめて認識されることにあんった。つまりこの「犠牲者論」(オーストリアは国家として主体的にナチスに荷担したわけではなく、その犠牲者であり抵抗者であるという神話)とオーストリアの独立(ドイツとの切り離し)が、戦後、連合国に占領されたオーストリアの政府の基本政策となっていったのである。(それによって戦後4カ国に占領統治されながらも、ドイツとは違って分割統治されることはなかった。)戦後は、戦争中にナチス・ドイツに加担した人びとでさえも、都合良くこの「犠牲者論」に便乗したのである。その結果、シュシュニックの支持者であっても亡命した者ならば、立派な「愛国者」であるということになった。 オーストリアは1955年に永世中立国を宣言し、ようやく占領統治を脱し独立を回復するが、その後も長いあいだこの「犠牲者論」は、オーストリア人の政治的原理として生きつづける。オーストリアは、「ヒトラーの最初の犠牲者であったが、現在は永世中立国家として世界平和に大いに貢献している」と喧伝し、ヒトラー支配下で生じた様々な問題は、全てナチスに責任を押しつけ、自らの政治的責任を放棄したのである。もうすこし上品に言えば、少なくとも政治的責任を先送りにしたのである。そのため意外と知られていないが、オーストリアとイスラエルの問題は現在に至ってもなお未解決であり、ウィーンにはイスラエル大使館はまだ無いはずである。 その意味では、映画「サウンド.オブ・ミュージック」は皮肉なことに、そうしたオーストリア人の心情を、政治的文脈から切り離して、実は見事に描いているのである。(しかしさすがにオーストリア人も、それほど無責任にこの映画を見ることはできないし、古傷にさわると見えて、国内では上映しないぐらいの良心は持ち合わせているのかもしれない。) 同じ敗戦国で、連合国に占領されていながら、戦後処理においてドイツとオーストリアが決定的に異なる扱いをされた要因が「犠牲者論」であり、ある意味では戦争責任を曖昧にしているという意味で、オーストリアは日本と似た状況にあるのかもしれない。特にこの映画は世界的にヒットしたため、オーストリアの「犠牲者論」を世界に宣伝するには好都合であったのも事実である。そしてこの政治的スタンスは、1950年代の冷戦構造のなかで(まさにオーストリアは社会主義国家に対する壁であったので)、きわめて高度な政治的な判断によって意図的に維持され続けたのです。 ほんとうに「犠牲者論」は正しくはないのか? ここで問題となるのは、1938年のナチス・ドイツによるオーストリア併合であるが、これは1910年の日韓併合とはだいぶ意味合いが違う。1938年3月12日にナチス・ドイツの軍隊がオーストリアの国境を越えたときに、抵抗する者は一人もなく、3月15日にウィーンのHofburugのHeldenplatz「英雄広場」では、ヒトラーの歓迎集会が開かれ、50万の群衆で埋めつくされたと言われている。そして引き続き4月10日に実施された、この「併合」の是非を問う国民投票では、実に99.73%が賛成票を投じたのである。(ただシュシュニックが国民投票を行っていれば、ナチス反対票が過半数を占めていたのではないかという意見もある) オーストリア人が当時、経済的・軍事的・民族的な理由で、ナチスを受け入れたという事実は否定できず、積極的ではないにしろ、ナチスの政策を支持し、これに加担したのは事実である。例えばオーストリアは、他のドイツの地域と比べても、ナチス党員の割合が最も多い地域だったのであり、ヒトラー自身は元々オーストリア出身であり、例えば、「ユダヤ人問題の最終的解決」つまりユダヤ人の絶滅政策で有名なアイヒマン(「スペシャリスト」というドキュメント映画で話題になったが)もオーストリア人であります。オーストリア人は、ナチスのシステムの中では後発であるが故に、むしろ積極的に加担していったことも考えられる。 この「犠牲者論」が見直されるきっかけとなったのが、長らく国連の事務総長(後にオーストリア大統領)であったヴァルトハイムが、ナチスの将校として非人道的な行為を行っていたのではないかと国際的な問題になった時のことである。この問題によって、ナチスの犯罪におけるオーストリア人の責任の問題、オーストリアをナチス支配に導いたのは誰なのか、そして国民をファシズム的体制に組み入れ、ファシズム体制の抵抗者たちを弾圧したシュシュニック体制には問題は無かったのかということが、問われるようになった。ナチス・ドイツとオーストリアのファシズムの間には大きな落差がなかったことが徐々に認識され始めたのである。例えば、戦時中オーストリアがユダヤ人から没収した美術工芸品の扱いが時々話題になる。エゴン・シーレの展覧会をアメリカで行ったときに、アメリカ在住のユダヤ系亡命オーストリア人が、その絵画が自分の家族の財産であったとして、裁判所に所有者確認の裁判を起こしたのである。それ以来オーストリアはその種の危険のある美術品をアメリカに貸すことは控えているそうで、オーストリア友人が語ってくれたところでは、オーストリアはただ時を待てばいいということである。そうすれば、すでに老人になっている相続人たちは、自分の所有物を手にすることなく天国に召されるのであるから。 シュシュニックに同調することで「愛国者」であったと主張できる時代は去った。それと呼応するように、逆にハイダーのような民族主義を掲げる者が登場する。すでに「犠牲者論」が通用しなくなった現在、逆に開き直るしかないのであるが、もちろんハイダーのような下品な政治家は多くはないが、しかし市民の率直な感情においては、かつての栄光あるハプスブルク帝国がこんなに小さくなってしまった現状のオーストリアにおいて、これ以上の対外的な屈辱にはやはり耐えられないのである。それは未来への展望がはっきり持てない国民、EUに頼らざるを得ないがその組織の中でも絶えず妥協を迫られる現状を目の当たりにして、はっきりその焦燥感が見て取れるのである。 (2005年1月10日)
2006年04月11日
-

オペラ座舞踏会 Opernball
Opernball (オペラ座舞踏会) ウィーンの2月は、冬の憂鬱な季節であるが、一方でそんな冬を少しでも楽しく過ごすために、あちこちで舞踏会(Ball)が催されるシーズンでもある。 市内で1月から2月(灰の水曜日まで。今年は3月3日)にかけて、様々な舞踏会が催される。仮面舞踏会や女性からダンスを申し込める舞踏会、主催が大学や医師会、あるいはカフェのオーナーのものであったり、と実に様々な舞踏家がある。 この舞踏会は、いわばウィーンにおけるカーニヴァル(ウィーンではカーニヴァルをファッシングFaschingと言うが)である。カーニヴァルは、カトリック地域で盛んであるが、ウィーンではドイツのケルン、マインツ、デュッセルドルフのような派手な仮装行列はなどは無い。その代わりウィーンには優雅な舞踏会があるわけだ。 このカーニヴァルなどの名前は、いまでこそ日本でも有名になったが、その宗教的な意味を知っている人は日本ではそれほど多くはないと思う。 カーニヴァルもそして灰の水曜日も、これはこの先にある復活祭(イースター。キリストが復活したことを祝う行事)と関係がある。復活祭の前の40日間を四旬節(Quaresma)といって、この40日というのは、キリストが荒野で断食(fasten)をした40日間にちなむもので、この間本来は肉食を絶たねばならない。そしてその四旬節が始まる日(それは水曜日になるのであるが)それを「灰の水曜日」(Aschenmittwoch)という。そして「灰の水曜日」の前の数日間において謝肉祭(カーニバル)が催される。四旬節において、肉食が禁止されるため、その前にたくさん肉を食って楽しむというのが「謝肉祭」で、リオなど南米のカーニバルでは、多数の死傷者を出す騒ぎとなる。ついでに言うと、復活祭はいつなのかというと、これがちょっと面倒なのである。というのも、復活祭は、春分の日の次の最初の満月の後の最初の日曜日にあたるので(説明するだけでもかなり面倒)本来であれば、春分に日は時差の関係で国によって違うので、国によって復活祭の日取りが1ヶ月も違ってしまうことがある。そのため、カトリック教会では、世界中のキリスト教徒が一緒にお祝いできるように、春分は3月21日に固定して計算することになっている。そして今年2004年は、4月11日が復活祭である。 だいぶ話が横道にそれたが、今日19日はいわば舞踏会の横綱であるOpernball(オペラ座舞踏会)が開催される。例年著名なゲストを呼ぶのであるが、今年は人気ソプラノ歌手びアンナ・ネトレブコと、俳優・歌手のミヒャエル・ヘルタウである。 舞踏会(Ballfest)の起源は、宮廷歌劇場の舞踏会ではなく、劇場の舞台で活躍する芸術家たちが主催者となり、伝説となっているウィーン会議の舞踏会に参加したのが始まりとされている。そして様々な舞踏会が1920年代20年代を通じ、ウィーンの数多くの大小の高級レストランにおいて開かれた。しかし芸術家たちは舞踏会のために親密な関係を確認できる空間を求め、その答えとしてホーフブルクのサロンの利用を考えた。 1848年の血なまぐさい革命の直後は、ウィーンにおいては誰も舞踏会に行く気にはなれなかったが、ばらくしてから再び人生の楽しみが求められるようになると、ウィーン様式による舞踏会が開かれるようになった。1862年になるとテアター・アン・デア・ウィーンTheater an der Wienが、舞踏会を開く許可を得ている。その際に、当時有名であったパルのオペラ座舞踏会をモデルにしている。そして、1869年に、宮廷オペラ座は、現在の位置に新たに作られたオペラ座に移動するが、皇帝フランツ・ヨーゼフはその宮廷オペラ座で舞踏会を開く許可をなかなか与えなかった。それゆえ、「宮廷オペラ座舞踏会」という名称は、リングに出来たオペラ座においてではなく、同時期に新たに豪華に作られた「楽友協会」の建物での舞踏会において使われたのである。その後1877年になってようやく皇帝フランツ・ヨーゼフも宮廷オペラ座で「オペラ座舞踏会」を開くことに同意した。 オペラハウスの会場は、全体がバラやチューリップなど赤い花を主に(オーストリアのナショナルカラー)6万本ほどで飾られる。舞踏会の幕開けは、ファンファーレ、オーストリア国歌、EU賛歌が演奏され、その後ツィーラーのポロネーズに演奏に合わせて若いデビュタント(社交界にデビューする人たち)たちが登場してする。次いでヨハン・シュトラウスの「祭典ポロネーズ」でゲストが登場し舞踏会に花を添える。それからエドゥアルト・シュトラウスの「カルメン・カドリル」でバレエが舞い、ミヒャエル・ヘルタウがレハールやシュトルツを歌うなどのプログラムが組まれている。オープニングワルツはもちろんヨハン・シュトラウス2世「美しき青きドナウ」である。 毎年話題になるのが、ルグナーという地下鉄U-6のBurggasse近くのショッピングセンターを経営している人物が、(たぶんポケットマネーで)ハリウッドから有名なゲスト呼ぶのであるが、今年はアンディ・マクドウェルである。だいたいこのゲストは、別に舞踏会とは何の関係もないのであるが、1995年にはソフィア・ローレン、1998年にはラクウェル・ウェルチ、彼女は150kgものカバンをオペラ座に持ち込みながら、舞踏会に退屈したことで話題になったが・・あと皇帝ベッケンバウアーなども顔を見せている)イメージとしては知的で美しい女優ということになるが、かつては南部訛りがひどく、長年売れなかったが、カンヌ映画祭でグランプリを受賞した『セックスと嘘とビデオテープ』のヒロインとして有名になり、『グリーン・カード』や『フォー・ウェディング』など個性的な役をこなしている女優である。 ところでこの舞踏会が並の舞踏会でないのは、ORFテレビが、夜8時から12時過ぎまで生中継するので、すごい力の入れようである。今年は7000人の客が来ているそうである。日本でいるとさしずめ大晦日の紅白だろうか?(だいたいこんな長時間生中継するものは、この国ではそれほど多くはないので・・・) しかし一見平和な舞踏会であるが、それとは対照的に、その外は物々しい厳戒態勢が敷かれているのである。 <警察のバリケード 劇場からの帰り午後10時頃撮影 向こう側がオペラ座> 「階級社会のシンボル」「貧しいひとたちにもっと目を向けろ」と舞踏会反対者が例年会場の周辺でデモを行い、周辺交通もリングを中心に市電やバスも大幅な規制が行われているのである。着飾った貴族のような人たちとデモに参加する労働者、このような階級間軋轢を目の当たりにすると、まるでフランス革命前夜を思わせるものであり、何か時代を間違えたような錯覚に襲われる気がした。
2006年04月10日
-

オーストリアのワインを調べるには。。。。
オーストリアのワインは、最近徐々に知られつつある。特にドナウ河の川岸に広がるヴァッハウ地方の白ワイン(グリューナー・ヴァルトリーナーやリースリング)は特に評価が高い。 グリューナー・ヴァルトリーナーは、オーストリアの固有種で、DNA鑑定によるとトラミナー種の派生種のようだが、古くはローマ帝政時代からオーストリアに存在していたと言われている。これは低オーストリア地方で最も上質な白ワインとなり、ホイリゲでも多く供される。このワインを飲むとオーストリアのあのワイン畑が目に浮かんでくる。甘い柑橘系とトラミナー種に似たコショウ系の混じり合う風味となるが、収量を減らせば非常に複雑な風味を持つ熟成に耐えうるワインとなる。 これから赤ワインの評価も上がると思う。特にブルゲンラントの赤ワインは、近年90年代以降、若手ワイナリー経営者たちによって急速に質を上げてきている。ただ最近クヴェなる混合酒が流行し、高価な価格で取引されているが、しかしやはり単品のほうが断然素晴らしい味わいを持っている。とくにオーストリアの赤ワインの固有種であるブラウフレンキッシュは、いつ飲んでもオーストリアのあの大地を思い出させてくれる素敵な香りを味わうことができる。フレンキッシュという名前からすでにカール大帝の時代には存在していたと言われているが、石灰質土壌では絶妙な気品のある味わい、ブラックベリーのような肉厚な味わいとなる。オーストリアにはもう一つツヴァイゲルトという赤ワインの品種があるが、残念ながらブラウフレンキッシュには遠く及ばない。 個人的に好きなオーストリア赤ワインのワイナリーを紹介しておく。ただ残念ながらなかなか日本では手に入らないのが実情である。 赤ワインのワイナリー 1 Rosi Schuster2 Prieler 3 Weninger 4 Iby 5 Arachon 6 Heinrich 7 Umathum 8 Gesellmann 9 Kollwentz 10 Grassl オーストリアワインを扱う日本の通販業者五枚橋ワイナリー http://www.gomaibashi.com/scb/shop/shop.cgi AWAhttp://www.awa-inc.com/main/winenary.htmlヴィノテーク・オーストリアhttp://www.edelwein.co.jp/cgi-bin/shopping_list.cgi和泉屋http://item.rakuten.co.jp/wine/c/0000000253/オーストリアのワイン検索http://www.wein.cc/http://www.weinco.at/ireds/P-19.htmlhttp://www.pfanner-weine.com/index.php?artikel=6325http://www.weinco.at/ireds/P-127-ID-63931017.2003.htmlhttp://www.dinstlgut.at/http://www.dinstlgut.at/GVLBB05_S.htmlhttp://www.prieler.at/http://www.wein.cc/wein/weinsuche.php?q=Weninger&index=0
2006年04月09日
-
ソフィア・コッポラのLost in Translation
2005年1月には、ウィーンでは2本の日本を舞台にしたアメリカ映画が上映された。一つが「ラスト・サムライ」でありもう一つがこの「Lost in Translation」である。日本でどのように訳されているかわからないけれど、ウィーンでは英語の題のままであった。ただ「ラスト・サムライ」は大々的に宣伝して上映されていたが、「Lost in Translation」は細々とウィーンではわずかに3館(たぶん?)で上映されていたに過ぎなかった。ただこの作品は後にアカデミー賞にノミネートされたので、注目されてあとから上映が増えたかもしれないけど・・・。 ストーリーはまあきわめてありふれたもの。ピークを過ぎた映画スター、ボブ・ハリス(ビル・マーレイ 「ゴーストバスターズ」でお馴染みですね。)は、サントリーのCMを高額で契約し、日本にやってくる。日本人スタッフとの意志疎通の困難さ、時差ボケ、自分の俳優としての限界の意識、様々な悩みが彼の意識に浮かびながら、異文化の中で暮らさなければならないことは、彼に大きなストレスをかけていた。そこで、宿泊している新宿のパーク・ハイアットのバーへ出かけるのであった。また夫とともに日本へやってきたものの、カメラマンの夫は仕事で忙しく、相手もできず、孤独な時間を送っていた妻シャーロット(スカーレット・ヨハンソン)。そして偶然(宿命的?)そのバーで二人は出会う。年齢差はあるものの、お互い異邦人として見知らぬ地で、二人は急速に接近していく。 この作品の良さは、軽妙なタッチで二人のコミュニケーションを描いていくところで、そこに二人の微妙で危うい関係がよく表現されている。決定的な関係というのが無いところが、心地よいのかもしれない。彼ら二人の異邦人としての結びつきを成立させているのが、彼らにとての日本文化という異文化なのである。うーん、これはまたこれで日本人から見ると複雑で、日本人から見るとこの主人公に感情移入できない一点がそこにあるわけで、そこにヨーロッパの観客と日本人である自分との超えられない観点が厳然として存在するのに気づきますね。 印象に残った異文化経験の場面としては、例えば、冒頭のCMの撮影取りの場面では、ディレクターがいろいろ訳のわからない注文をするのであるが、それを通訳が故意に、あるいは訳すことの限界を感じてか、それを正確に訳さないので、ボブは全く状況がわからない。「カット・カット!!」を連発するディレクターと、その状況に取り残されているボブの対照が笑いを誘う。(この場面は確かにおもしろかった・・) 次にいきなり部屋に出張の「サービス嬢」(??? これは私にも何だかよくわからなかったので、ボブの当惑した感じはよくわかったが・・・)がやってきて、いきなりボブに迫ってきた。まあこういう場合自分ではどうするんだろう?この「サービス嬢」の目が妙に印象に残った。 カラオケはおきまりですが、ようやくボブの調子が上がってきたときには、一緒にいたはずの人たちが断りも無く消えている。まあコミュニケーションツールのはずのカラオケでのコミュニケーションロスをおもしろく描いている。 ボブがホテルのプールで泳いでいると、太ったオバさんたちが大勢でダイエットのスイミング。高級ホテルのイメージが台無し。そして、ゲームセンターでは、若者たちが奇妙なゲーム(ギターや和太鼓などの演奏ゲーム)に興じている。オリジナルではなくゲームで楽器を演奏する感覚が、ズレて見えるんでしょうね。そして、藤井隆の番組に出演したボブが、その藤井の奇妙なテンポに戸惑い、途方に暮れているといったところ。やはり日本のポップカルチャは、外国人にとっては、驚きなんでしょう。少なくともオーストリア人は日本については若干の情報は持っているが、しかし実際に訪れている人はわずかだし、「自動車」「電気製品」「寿司」(最近だと)「ラーメン」といったぐらいのイメージしかない。 監督のコッポラ嬢(フランシス・コッポラの娘)が1ヶ月ほどのロケで、すごい低予算(400万ドル?? サントリーとハイアットはもちろん協賛だろうが・・)で撮ったらしい。そしてアメリカではかなり好評だったようで、しかもアカデミー賞にノミネートされるとは、それは快挙でしょう。今年のアカデミー賞は、渡辺謙と「たそがれ清兵衛」といい日本勢も健闘しているので、期待したい。 でもビル・マーレイのサントリーのCMは妙にはまっていたなあ。実際に日本でCM流したら、二重効果でかなり受けるとおもうが・・・。著作権的にどうなんだろう? 日本の描かれ方としては、ああ現実に近い形だったので、まあ良しとしましょうか。カラオケ・パチンコ・ゲームセンター・ネオンサイン・歌舞伎町などは、現代日本を強調する場合のややお決まりのコースですが、でもウィーン人には日本のイメージに近いもので、それほど違和感無く受け入れられたようです。ただ残念ながら映画館にはそれほど多くの客はいませんでしたが。 映画館について一言。今回行ったところは、”Urania”にある映画館だったけど、私は始めて入りました。ここはちょうどウィーン川がドナウ運河に注ぐところに位置していて、1909 年にOtto Wagnerの弟子であったMax Fabianiが設計したもので、1910年に Franz Josephの臨席のもと天文台のついた(それゆえUraniaと呼ばれる)国民教育センターとしてオープンした。 第二次世界大戦時にUraniaは爆撃でひどいダメージを受け、天文台はほぼ壊滅的な状況であったが、1957年に再建された。現在では映画館やVHS(カルチャーセンター)が入るなど、総合文化施設として利用されている。 http://www.mapletown.ca/entertainment/column/detail.mt?column_id=10197
2006年04月07日
-
サウンド・オブ・ミュージック
オーストリアを舞台に、ジュリー・アンドリュース主演の映画で有名となった米ミュージカル 「サウンド・オブ・ミュージック」が昨年の2月26日、ウィーンで初めて上演された。実はこのミュージカル、オーストリアではこれまで知る人も少なく、不人気だった。 今度は成功を収められるか、注目を集めていたが、そこそこの評価にとどまったようだ。公演場所はオペレッタの殿堂「フォルクスオーパー」である。 ミュージカルには、古都ザルツブルクを舞台に、妻を失った軍人の父親と7人の子供がいるトラップ家、 そこに家庭教師として雇われた主人公マリアとの音楽を通じた温かい交流が描かれている。 65年の映画化で、美しいアルプスの映像に「エーデルワイス」「ドレミの歌」などの名曲の魅力が加わり、 外国でのオーストリアのイメージに大きな影響を与えた。 だが、伝統重視で、クラシック音楽の本家を自任するオーストリアやドイツでは、 ニューヨークのブロードウェー風の演出や、地元の人々には不自然と思われる 登場人物の振る舞いへの反発が募り、当時の映画上映は数日でうち切られた。 ミュージカル上演も何度か試みられたが、受けはよくなかったのだ。 引用元:asahi.com(02/18 14:53) http://www.asahi.com/culture/update/0218/006.html フォルクスオーパーのサイト(画像あり) http://www.volksoper.at/http://www.volksoper.at/Content.Node2/en/spielplan/spielplan_detail_werkbeschreibung.php?eventid=378859
2006年04月07日
-

ウィーン行き
4月某日、成田発ウィーン行きのオーストリア航空OS052便の飛行機は、定刻の10:40よりも10分ほど早く出発し、予定よりも1時間早く、現地時刻15時5分に到着した。 家を6時前に出て、最寄り駅まで荷物を車で運び、荷物を駅に置いた後、一旦家に車で帰ってたのち、徒歩で駅に向かった。荷物は、スーツケース一つと手荷物用の大きめのバック、それにポーチであった。スーツケースは24kg,手荷物用バックは重さを計っていないが、おおよそ12kgぐらいあったように思われる。荷物の重さのゆえか、右手が異様に非常に疲れ、また右足のふくろはぎもウィーンでの最初の夜で、寝ている時につってしまった。痛かった。 成田に着き、集合場所(集合時間8:40分)であるJTBの団体旅行用の早めにいってみると、すでにチケットは用意されており、すぐに受け取ることができた。問題は荷物の重量オーバーであったが、荷物を預けるカウンターは、JTBのカウンターとは別のところで、空港の一番奥のところにあった。スーツケースを計られた時はちょっと緊張したが、24kgで4キロオーバーでなんとかOKであった。成田(他の空港もそうだが)は基本的に手荷物の重さをチェックするシステムはなく、たとえば手荷物を誰か付き添いの人に預けてから、スーツケースなどの大型の荷物のチェックインを行い、それからいったんチェックインエリアの外に出て、そこで付き添いの人から手荷物を受け取れば、手荷物について言えば後はセキュリティチェックのみである。つまり大きささえ問題なければ、手荷物の重さは問題ないのである。確かに荷物の預け入れのところに、大きさを測るベンチみたいなものがおいてあるが、あれはそこに荷物を置いて、大きさを確認するのである。最近航空会社も余裕が無くなったせいか、いろんなところでお金を取ろうとしているので、(特に成田は)荷物などにもうるさくなってきている。知りあいは大きな手荷物を持っていたため、チェックインカウンターでちょっと測らせてくれと言われて、スーツケースと合計で38キロあったために、10キロ分の追加料金8万円(通常エコノミーはスーツケース20キロ、手荷物8キロまで)を徴収されたらしい。普通なら、そこで、荷物を開けて付き添いに余計なものを渡して、後から航空便で送ったほうがよほど安いと思うのであるが、運悪く単身で来てしまった人は、出発が迫っているので、自分で宅急便のカウンターまで行って自宅に送り返すか、あるいは素直に料金を払わざるをえないのである。でも、4月の航空料金は結構安く、せいぜい8,9万円といったところで、航空料金と同じ金額を取られるのは考えただけでも馬鹿らしいのである。まあ、人の弱みにつけ込むのが商売だから致し方あるまい。 出発前に最後の日本食を食べることにし、うなぎとそばのセットを食べた。おいしかった。その後すぐに出発ロビーに向かった。一番端のB75というゲートであったが、端のところで下に降りていくエスカレータに乗ると、すでに団体客がカウンターの近くに多数座っていた。その団体客の間の開いている席のひとつに座った。団体客は胸にバッチをつけているのでわかる。どうやら私もその団体の一人という感じになっているようだ。やっぱり団体は年寄りとご婦人方が多い。10時10分にもなると搭乗手続きを始めた。私は荷物が大きいので置き場を確保するために早めに乗りたいと思ったので、小走りに走って列に並び、ゲートを通過した。機内に乗り込むと、座席は向こう側の列の通路側であった。通路側はなにかと便利なので、都合がよかった。まあここからなら外も少しは見れるし。隣にはしばらく客が来なかったので、ここだけ客がいないのかと思ったが、残念なことに、団体のおばさん3人組が最後にやってきた。でも荷物は座席の下に置いたらしく、私のところのスペースには、私だけの荷物があるだけだった。 オーストリア航空の機内はなかなかきれいであった。隣のおばさんたちは、「狭いね」といっていたが、私にはジャンボよりも少しゆったりしているように思えた。基調は緑と赤らしく、座席は緑、スチュワーデスは赤い制服を着ていた。オーストリア航空のスチュワーデスはオーストリア的骨格であった。日本人のスタッフが1人いたが、あとは全員オーストリアのスタッフであった。赤い制服でなかなかよかったが、どうも途中からサンタクロースにように見えてきたのは私だけだろうか?ヨーロッパの女性にありがちで、太っていても平気で身体にぴったりの服を着るのである。 機内食はメインが2回と1回のおにぎり、それに飲み物サービスであった。最近はエコノミー症候群の話がいきわたっているので、しきりに飲み物を出してくれる。特に水はよくでてきたように思う。ただ機内食は年々悪くなっているような気がする。(すでに伝説となっているが、私が最初にヨーロッパに行った時は、大韓航空の南回り20時間かかったチューリッヒ行きであったが、そこではまるでブロイラーのように、5回ぐらいメインの食事が出た記憶が残っている。あれはあれで食べるのが大変だったが、これからのヨーロッパでの生活を考えると食べなければと一所懸命食べたなあ・・)OSのEUの域内便ではすでにコーヒーなどのサービスは有料になってきている。まあそのほうが合理的ではあるが、飛行機が何か特別な乗り物という共同幻想が薄れてきて、単なる乗り物であることが認識されるようになるのは、まあ時代の趨勢であるから仕方ないだろう。とにかく、無事にウィーンに着いた。
2006年04月06日
-
中欧の春の洪水
日本ではあまり報道されていないが、中央ヨーロッパは、雪解け水による洪水に見舞われている。オーストリアでは、ウィーンの北にあるMarchではドナウ河の支流Thaja川(これはブラチスラヴァでドナウ河に合流)の堤防が決壊し、街に深刻な被害をだしていることを、連日報道している。軍隊も投入され、ヘリコプターから土嚢を投げ入れるなど、被害の拡大を食い止める努力が行われているが、根本的には水が引かない限り打つ手がない状況である。http://kurier.at/bilderdestages/1328918.php/picture/3 特にヨーロッパの家屋は地下室(ワイン蔵、洗濯場、物置)を備えていることが多いので、水が出ると被害は深刻なものとなる。 今回の洪水の被害は、オーストリアだけでなく中部ヨーロッパ一帯において同様で、ドナウ河の下流にあたるハンガリーのブダペストでもドナウの増水が懸念されており、またドイツではエルベ川沿いのドレスデン、陶磁器で有名なマイセンなどもまた被害が出ている。ドレスデンは最近聖母教会が再建され、数年前の洪水の被害から立ち直りつつあったばかりで、再度この洪水によって被害が出ることが懸念されている。またチェコも前回同様に被害を出しているようだ。 そもそもこの初春の雪解け水による洪水というのは多かれ少なかれこの地域にはつきもので、オーストリアの山沿いの谷あいの村などはしばしば洪水の被害にあう。また今年は特に雪が多かったので、暖かくなり一気に雪が溶けたのである。そのような雪の量や、さらに地形による要因が強いと言えるが、他方で、日本のようなコンクリート剥き出しの堤防を作らないヨーロッパの治水に対する考え方も一つの要因となっている。オーストリアのヴァッハウ渓谷などを歩くとわかるが、ドナウ河の水位と堤防の高さの差があまりになく、4-5メートルの増水で水が溢れそうなところをよく見かける。もちろん全ての流域にわたってそうなっているわけではないが、しかし河川の景観を保持するためにも、また日本の台風時のような集中豪雨なども稀であることなどからも、趣味の悪いコンクリート堤防を作らないで、自然な形での治水能力の確保が方針になっているようである。 しかし近年ヨーロッパでも、かつては見られなかったような天候不順が起こるようになってきた。頻発する洪水に対して、どのような対応を取るのか注目されるところだ。
2006年04月06日
-
ウィーン アカデミー劇場 ワイルド 「サロメ」
Salome オスカー・ワイルド作 Gerhard Ruhm 改作 Salome, Caroline Peters Herodes Antipas, Wolfgang Michael Herodias, Maria Happel Jochanaan, Johannes Krisch ワイルドの「サロメ」は今ではR・シュトラウスのオペラとして有名になっているが、もともとはもちろん舞台用の作品である。ただ現代の上演は、多かれ少なかれR・シュトラウスの作品に影響を受けていることは明らかであろう。今回の上演では、サロメのヨカナンに対する「愛情」というよりも、むしろその愛情は宙づりにされた形で(それは演出においてヨカナンが水槽の中に漂っていることに象徴されているように思えたが・・・)むしろ彼女の母親Herodesや、父親を殺した現在の王Herodiasへの憎悪、Herodiasのヨカナンに対する恐れ、母親Herodesのサロメへの嫉妬、そのような負の感情が強調されていたように思える。もちろんここでの「愛情」というのも結局は、かなり倒錯しているもので、結局ヨカナンの血によって静められるものとなる。 原作では色(白・黒・赤)などが強調されていたが、演出ではそれほど目立った色に関する演出はなかった。ただ血のイメージを強調するために、舞台の床に血を滴らせたり、サロメは自分の身体に自殺した大尉の血を塗りたくったり、ヨカナンの首を血塗れにしたりしていた。しかしそれはややグロテスクな演出に過ぎないように思えた。(4.6.2005)
2006年04月05日
-
小沢のフィガロ
小沢征爾は、現在病気療養で日本に帰国したそうで、今年1年はウィーンでの仕事はすべてキャンセルしたようだ。モーツアルト生誕250年で、ザルツブルク音楽祭ではすべてのモーツアルトのオペラ作品が上演されるということで話題になっているが、非常に残念である。病状が感じられる。 小沢のフィガロを見たときのことを書こう。 そのは朝から雪まじりの天気で、気温はそれほど下がらなかったが、一日あまりよい天気ではなかった。雪はすぐやんだのでそれほど積もらなかったが、しかし一度降るとなかなか解けない。歩く時には特に注意が必要である。 昼から友人が来て、彼のために履歴書をパソコンで打ち込んであげた。その彼は日本のヤマハで働いていた経験を持つ調律師であるが、ヨーロッパでさらに自分のキャリアを積むために語学留学も兼ねて、昨年の4月からウィーンに滞在している。30歳過ぎの知りあいである。すでに履歴書と手紙の原稿はできているのですが、あいにく彼はこちらにパソコンとプリンターを持ってきていないため、代わりに私が入力を手伝ってあげたのである。特にドイツ語の場合、ウムラウトが厄介であるが、その入力の仕方も最初習わないとなかなかうまく行かないようで、それも教わるのを兼ねて家にやってきたのである。ウィーンには有名なピアノメーカーBoesendorferがあるが、どうも景気が悪いようで、彼も最初はそこに入ることを希望してウィーンにやってきたのであるが、情報を収集するうちに、無理であることがわかってきたようである。そのため就職運動の方向は今度はドイツに向かい、今回調律師の公募がライプツィヒとシュトゥットゥガルトであるとの情報を友人から手にいれたらしく、そこに応募するために手紙と履歴書が必要なのである。いずれもほぼ日本で書くようなものと同じであるが、やはりこちらでは実習・職歴が重要視されるので、そのあたりを詳しく(中にはやや誇張したような表現もあるが・・)ことを求められる。 彼は4月からこちらに滞在しているが、ビザは取得していない。オーストリアには日本人は観光で6ヶ月滞在できるのであるが、これは他の外国人に比べるとかなり優遇されている。(通常は3ヶ月である)そして彼の解釈によれば、日本でDビザ(滞在ビザを取得するまでのつなぎの仮ビザ)を取得してきたので、2003年度は、そのDビザの6ヶ月と観光ビザ分で9ヶ月滞在でき、2004年は、さらに年度が替わったので、観光ビザ分で6月まで滞在できるということである。この解釈がオーストリアの移民局に通用するのかどうかは不明ではあるが、彼は自信をもっているようであった。ちなみに私はDビザを取得した上で、4月にきてから、8月にようやく滞在ビザがおり、来年2004年8月までは合法的にオーストリアに滞在できることになっている。ということで、彼の就職を祈るばかりである。 今晩はStaatsoperで、小沢征爾の「フィガロ」があった。演出はかの有名なJean-Pierre Ponnelleで、カール・ベームが指揮したビデオ版で知られている。Almaviva伯爵は、Boaz Daniel,Almaviva伯爵夫人はKrassimira Stoyanova,スザンナはIldiko Raimondi,Figaroは、Ildebrando D'Arcangelo, ケルビーノはAngelika Kirchschlagerであった。出来からするとなかなかよかったと思う。特にAlmaviva伯爵夫人のStoyanovaは、なかなか気品があり2幕冒頭のアリアは上出来であった。この役はどうもビデオを見すぎたせいかキリテ・カナワの伯爵夫人がはまり役に思えてしまうのあるが、Stoyanovaの艶のある演技も良いように思う。ケルビーノのKirchschlagerもよく歌っていたように思う。この役独特の幼さと無邪気さの中に、男の願望をそれとなく紛れ込ませるような歌が似合う歌手であった。容姿も役によく合っていた。Figaroの D'Arcangeloはいかにもイタリア人といった風貌で、ヘルマン・プライのフィガロとは全く違った、まさに軽快なフィガロであった。ただ歌の方はややばらつきがあり、良いときもあれば悪いときもあるといった感じで、やや不安定な印象を受けた。でも演技は好演していた。Almaviva伯爵のDanielも良かったように思う。彼は全く余談だが「スタートレック2」の副官に風貌が似ている人間で、まさに好色漢といったところで、その「いやらしさ」がよくでていた。Ponnelleの演出は今となってみるともはや古典であるので、現代の演出であれば、もっと露骨に演技させることも可能であると思う。 演奏は素晴らしかった。小沢征爾の演奏はいつもオーソドックスでもう少し小沢色を出していいと思うのであるが、やはりやや格式が高いためか、ウィーン国立歌劇場の演奏スタイルが全面に出ているような気がしないでもない。カーテンコールでも小沢は目立たないようにいつも控えめにしている。たぶんそれは彼の処世術なんだと思うが。ここウィーンでは余り目立ち過ぎるとやっかむ人間が必ず出てきて、影でいろいろ陰謀を張り巡らすことになる。とりあえず、周りを立てておいて、次第に自分のカラーを出すという戦略なのかもしれないが、ただミイラ取りがミイラになるということもあり得るので、もう少し大胆に個性を出しても良いように思われる。ただ小沢の個性って何だ?と言われると、私はまだそれに対する言葉を持ち合わせていない。まだしばらく演奏を聴く機会があるので、考えてみたいとは思う。 演出はおなじみの物なので、あまり言及すべきものはないが、やはりウィーン国立歌劇場の水準からいうと良い方だと思う。1,2幕目はお馴染みのものであったが、3幕目は伯爵の執務室のようであったが、やや目新しいように思われた。(確かでは無いが・・)4幕目もお馴染みのものであった。 オペラ座で偶然友人にあった。彼も日本から研究でウィーンの国連機関に滞在しているのであるが、開演前にロビーで出くわした。幕間は一緒にワインを飲み楽しいひとときを過ごした。オペラのビュッフェは良い値段であるが、個人的にはワインはなかなかおいしいし、3ユーロぐらい(1/8リットル)なので、悪くないと思う。私はいつも赤を飲んでいるが、白やビールもいい。 (21.1.2004)
2006年04月04日
-
飼い主に「犬の免許証」を発行?
ときどきウィーンからはおかしなニュースが舞い込んでくる。この前の鶏インフルエンザのときは、病死したらしい鶏が道路にころがっていたところ、かけつけたゴミ回収者(公務員)が鶏の回収を拒否し、そのためその道路が大渋滞したというニュースがあった。さて今回は時事通信が伝えたところでは、今度はどれぐらい本気であるかわからないが、ウィーンでは飼い主に「犬免許証」なるものを発行するらしい。確かにウィーン人の犬好きは日本人に比べてもすごいものであるが、しかしそれに伴い道路での糞の不始末もすごいものがある。これまでモラルが低下した日本人だが、犬の糞についてはまだモラルが高いと関心するほど、ウィーンの糞公害はひどい。かつてハイヒールが人糞避けるために発明したというお国柄だけに、道路に糞が落ちていてもあまり気にしないのかもしれない。でもさすがに忍耐の限度の越えたのか、今回の「犬免許証」なるものの登場となったようである。市の担当者は「ウィーン市民は本当に犬好きなので、 人間と犬が共存するには厳格な手段が必要と考えている。これは飼い主が愛犬、他人への責任を真剣に考えている証明」と話しているとのこと。 ただウィーンではこのニュースはあまり知られていないようなので、どれだけ実効性があるかは疑問符がつくところである。
2006年04月04日
-
アパート 探索記(1)
ウィーンに着いてからしばらく住んでいた部屋(大家との2世帯住宅のようなところ)を脱するべく新たにアパート(日本のアパートとはだいぶイメージは違うが・・・)を探すことにしましたが、これがなかなか大変でした。いくつかその経験をご紹介したいと思います。 まず物件を探すにあたって、業者を使うにしても、できるだけ手数料の少ないところがもちろんよいので、外国人向けの物件(短期でも可)を多く扱っているOdysseeというところで希望を登録して、連絡を待ちました。ここは物件が見つかるまで、一定の間隔で物件情報をファックスで連絡してくれ、気に入った物件があればこちらから直接その物件の持ち主に連絡し、アポイントを取って実際に家を見た後、契約が成立すれば、後でこの業者に手数料(契約期間によって異なる)を支払うというシステムになっています。外国人向けが主なので比較的契約期間が限定され(例えば何年何月からいつまでという風に)また短期のもの(例えば6ヶ月とか1年とか)が多いように思われます。また若干相場よりも高い物が多いようです。 こちらの希望としては、電話・ケーブルテレビ・風呂・トイレを挙げ、家賃は6OOユーロまでを提示しました。そして数日してからその業者からファックスが届きました。必ずしもこちらの条件に合わない物もありましたが、家賃の希望はおおよそ満たしていました。その中から良さそうな物件を一つ見つけだし、連絡して見せてもらうことにしました。 その一つ目のアパートは西駅から市電で3つ目の停留所から、歩いて5分ぐらいのところにある物件でした。(場所が特定されないように地名は省略させていただきます。)ここはバスでも行けるのですが、本数が少ないので、バスで行くのはやや不便そうでありました。それから行ってみてわかったのですが、この物件はいわゆるウィーン市の公共住宅(Gemeinde Wohnung)で、住宅棟が5つほどあり、その1つの棟の4階の部屋でした。公共住宅になぜ日本人が住めるのか?と疑問に思いましたが、とりあえず行って話を聞くことにしました。 ここの住人は、小さな赤ん坊のいる25歳ぐらいの夫婦で、旦那さんはすでにベルリンで住んでいるので、今日会ったのは奥さんだけでしたが、とても感じのよい人でした。年齢は聞きませんでしたが、25歳ぐらいでしょうか。昔日本に来たことがあって、今あるかどうか確かではありませんが、北海道の「グリュック王国」で子供の相手をするバイトをしていたと教えてくれました。夫婦で住むために12月1日にベルリンに引っ越すが、1年後に戻ってくるので、その間1年間貸すということです。どうも家庭の事情はいろいろ複雑なようで、現在旦那さんはベルリンで働いているが、夫婦としてはできればウィーンに住むことを希望している(というより奥さんの希望かな?奥さんはウィーン人)ので、1年以内に旦那さんはオーストリアで職場を探すつもりだということです。ドイツよりオーストリアのほうが失業率が低い(所得も低いが)ので見つかる確率は高いのかもしれません。(オーストリア人に言わせるとやはり景気は悪いと言ってますが。)ですので、貸し主は1年間ベルリンに住むが、市内には貸し主の奥さんのお母さんがいるので、なにかあったら助けてくれると言っていました。 ここの部屋は46m2で、基本的には2部屋で、1部屋は寝室(ベッドと書棚、タンス、衣服のロッカー、植物)で8畳ぐらい、それからリビングルームは、台所と兼用で机と大きなテーブル(4人掛け)がありました。基本的には東と西に窓があるので、そんなに暗くはないと思います。少なくともその当時住んでいたところ(北向き)よりは良い印象でした。お風呂にはバスタブがあり、ホテルに時々あるガラスのガードが半分まであるタイプで、さらに洗面台がついていました。トイレは別になっていて、玄関の脇のところにありました。暖房兼湯沸かし器は、昨年新しくしたらしく、大きいものが一つありました。あと7,8年使っている洗濯機があり、これはいつ壊れても仕方がないので、壊れたときは許して下さいと行っていました。でもそれでも後で訪れた別のアパートにあったやつよりも新しそうでした。あとオーブンと、3つ口のガスレンジがありました。お湯は洗面所、台所でも使えるとのことでした。あとCabel―TVは現在契約しているので、そのまま使えるとのことでした。電話器や掃除機もそのまま貸してくれるそうで、あと食器類もそのまま置いておいてくれるそうです。 条件ですが、月410ユーロ、保証金は1ヶ月で基本的には保証金は返してくれると言っていました。ただ最後電話料金の請求が私が1年後に引っ越した後にくるので、その精算をしてから返すと言ってました。電気代は家賃に込みになっていました。 あと部屋の使用の際の留意事項などを聞きましたが、シャワーは夜何時まででも浴びていいといってました。ただ洗濯機はうるさいので夜10時までにしてほしいと言ってました。隣の家とかの音はうるさくないかと聞いたら、上の階の人の靴の音がちょっと聞こえることはあるとは言ってました。 ただ問題は、ここがウィーンの公共住宅であるということです。本来であれば借り主は又貸しができない契約になっているようです。これは多くの人から聞きましたが、ウィーンの公共住宅は家賃が大変安く(月410ユーロ要求するぐらいですから、本当は300ユーロ程度ではないかと推測されますが・・・)ので、入居希望者はかなりいて、希望者リストに登録してからも相当待たされるそうです。もちろん所得制限が厳しく、母子家庭や身障者などは優先されるようです。だから、ここの借り主も一旦家を手放すと、また借り直すのは大変なようなようですので、本来住まなければ退去しなければならないんでしょうが、その期間又貸しを考えたようです。念のため「日本人が公共住宅に住んでもいいのか?」と聞きましたが、この公共住宅にもトルコ系やアフリカ系などが多く住んでいるので、問題はないという答えでした。そのような契約の条件であれば、私はここで住民登録ができないことは明らかです。ですので、貸し主の提案としては、私の住民は彼女の母親のところでして欲しいということでした。 広さは普通だけど、とにかく安いし、大家もうるさそうでないので、いいのではないかと一瞬思いましたが、でもやはり後々面倒なことが起こって、結局出ていかなければならなくなると、引っ越しが二度手間になるわけで、また一から部屋探しをしなければなりません。また常にここの住民の視線を感じながら住まなければならないというのは、相当ストレスです。ただでさえ、日本人は好奇の目で見られていますから。場所的にはまあまあ便利で、バス停までは歩いて2分ぐらい(本数は10分に1本ぐらい)、また歩いて5分ぐらいの所の市電を使えば西駅まですぐ行けるし、歩いてもU4の地下鉄の駅まで歩いて5分ぐらいです。でもそうは思いつつも、日本での立場もあるので、やはりここは常識的にウィーンの公共住宅の入居は断念することにしました。2004年の12月までという契約期間もちょっとひっかかったのも事実ですが。 ウィーンでは、日本人の感覚からすると驚くことにシェーンブルン宮殿やアーセナル(武器庫)の一部に公共住宅として一般の住民が住んでいるし、また世界の住宅公団の原型と言われているカール・マルクスホーフもいまだに公共住宅として使われています。そして真偽は定かではありませんが、住民の多くがSPOe支持者だと言われています。日本の都心の1等地にある公務員住宅の家賃などもそうですが、ここの国も公共住宅に関して、いろいろ問題があるようです。
2006年04月03日
-
ちょっと早いがメーデーの話
メーデーは、オーストリアでは祝日です。9時に起き、朝のうちは天気がはっきりしませんでしたが、午後から晴れてきました。メーデーでは、朝10時から市庁舎の前で集会があると聞いていたので、時間通りに行くつもりでしたが、実際に着いたのは11時過ぎだったので、すでに市庁舎の前の集会は終わっていました。(鬱・・・)そこで国会議事堂の方に移動すると、その前で引き続き集会をやっていました。そこでしばらく演説を聞いていましたが、代わる代わる弁者が交替し、そろって年金改革への反対を訴えていました。どうやら社会民主党系の会合で、労働組合関係者たちが集まっていたようでした。そしてそのあちこちに赤い羽根や機関誌などを売る机が置かれていて、カンパをしているようでした。私もそこに立っていると労働組合の新聞を売りにきたので、記念に1部買いました。ただ極右らしい黒い服をきた人たちも回りを取り巻いたりしていて、やや緊張した雰囲気も感じられました。国会議事堂はリンクに面していますが、この時間帯はリングの市電も止まっていて、リングは歩行者天国になっていました。その演説を聞いたあと、12時ぐらいにプラーター公園に移動しました。そこではメーデーの日にMaifest(5月祭)が開かれると聞いていたからです。しかし1時から開始だったので、まだ人出はそれほどではありませんでした。久しぶりにプラーターに行きましたが、アトラクションは相変わらず古く、浅草の花屋敷を思わせました。でも今日は料金を安くしていたので、子供たちがたくさん並んで順番を待っていました。もともと場所も狭いこともあり、結構にぎわっている感じでした。このMaifestというのは昔から名前は有名ですが、今ではどうやら社会民主党の主催らしく、プログラムを見るとプラーター公園一帯でいろいろな出し物をやるようです。でも実際に出し物を見ても、こちらのものはなんかどことなくのんびりしているというか、適当というか、素人に毛がはえたような芸人がやっています。1時過ぎにはロックのコンサートのようなものをやっていましたが、途中で間違えて演奏が止まっていたりして、なんともほほえましい感じでした。ということで、まあ2時間ぐらいうろついてから帰りました。ただ私が帰るころになると、これからプラーターに行く人並みがかなり増えてきました。すぐ帰るのものなんなので、U-1でシュテファンスドームで降りて、そのあたりを散歩しました。祝日は街の中心部は観光客しかいない状態になります。地元の人は店もほとんど休みになる祝日にわざわざ街の中心部に出てくるようなことはしないようです。こちらに来て初めてシュテファンスドームに入って見学しましたが、さすがに観光客で溢れていました。祭壇に続く椅子のところにしばらく座っていると、祭壇のところから音楽が聞こえてきました。今日ベートーヴェンのミサ曲の演奏会がここでやるので、そのリハーサルのようです。なかなかいい音でした。そこで思わず入り口のところで15ユーロ(一番安い席)のチケットを買ってしまいました。今日8時からでした。 シュテファンスドームでのコンサートですが、15ユーロの安い席だから仕方がないのですが、かなり後ろのほうの一番左の席でした。だから演奏が始まっても直接見えないし、モニターが一応申し訳程度にあるんだけれども、音楽はかなり遠くから響いてくる感じでした。でも音はドームのなかを柔らかく響きあい、調和のあるまろやかな音になっていました。ちょっと音量が小さかったですが。曲目はベートーヴェンのミサ ハ長調を中心に、ハイドンのテデウム、モーツアルトのAve Verumでした。最後にヘンデルのハレルヤをアンコールでやってくれました。そうだなあ、まあもう一度行くかというとちょっともういいって感じですが、シュテファンスドームでの音の響きを一度楽しめたのは良かったですね。ただ時間も8時半に始まって、9時半過ぎには終わっていたから、かなり短い演奏会でした。きっとシュテファンスドームへの喜捨ということでしょう。
2006年04月02日
-
欧米人が見る日本人
Landstarasseの駅前のシネコンで19:45分より「ラストサムライ」(上演時間2時間程度)を見た。ウィーンではあちこちで宣伝しているので、どのくらい人が来ているか興味があったが、思ったほどの入りではなく、大きなホールに30人ほどがいた程度であった。ここのシネコンはアマデウス書店の上にあるところで、10スクリーンあるウィーンでも大きな映画館である。そのなかで、「ラストサムライ」は一番大きなホールで上演されていた。映画館の入り口は建物の2Fにあるのだが、そこのそばにあるアジアンレストランで酢豚(ほんとうはチャーハンを頼んだのに間違って男が持ってきた・・・)で腹ごしらえをしてから、映画をみた。 内容については「西南戦争」の西郷隆盛をモデルに原作が書かれていることは知っていたので、おおよその予想はついたが、やはり異国の地で自国に関する歴史がまたさらに他国の人たちの視線から描かれるというのは、かなり奇妙な感じであった。 映画の中では、滅び行く日本の侍がアメリカのインディアンに重ね合わせられており、それによって果たしてきちんと日本の歴史が描かれるのかどうか疑問であったが、やはり描き方はかなり浅く、またストーリーの展開もやや単純であった。トムクルーズ演じる南北戦争の英雄・アメリカ騎兵隊のオールグレン大尉は、近代化を目指す日本政府に軍隊の教官として招かれるが、初めて侍と戦いを交えた日に捕虜となり、ラストサムライである勝元に助けられ、彼との交流の中で、サムライの魂に触れ、その武士道に共感していくのである。 まず日本人が外国映画で描かれる自画像を見るとき、常に違和感を感じてきた。それは同時に外国人が日本に対して感じている違和感の表現でもあるのだ。しかしこの映画では映像の美しさの中に、日本の生活習慣がよく描かれていたように思う。茶道や能、忍者、農村、桜、天皇、お寺などかなり観光用映画という印象も一方で受けたが、しかし比較的日本人の視線に近いところで日本人を描いていたように思う。 ウィーンの観客の関心は、もちろん異文化としての日本である。彼らはトムクルーズと同じ視線からこの映画を興味深く見ていたはずである。時々あちこちから映画館で笑いが起こったが、例えばトムクルーズが日本の着物を初めて着て、ぎこちなく歩く場面であったが、おそらくヨーロッパ人の多くが経験するであろうことを、トムクルーズが体現して見せたため、その滑稽さ・ぎこちなさ・こわばりに対して笑いが起きたのである。また映画の中ではかなり日本語のせりふがあったが、ドイツ語(字幕)ではきちんと訳されておらず、そのニュアンスはあまりうまく伝わっていないような気がした。 確かに勝元を演じた渡辺謙はなかなか好演であり、トムクルーズをも凌ぐほどの存在感を示していた。というか、トムクルーズの演技が今一歩陰影に欠けるところがあった。やはりアメリカ的な物語の中では別に違和感はないのであるが、日本文化に触れたとき、単なる異人さんになってしまい、何か彼の持つ内面が見えてこないところが、残念であった。つまりお決まりストーリーを越える何かが彼によって表現されなかったことが残念である。ただ噂通りさすがに格闘シーンはよく練られており、見応えはあった。最後一人だけトムクルーズが生き残るのはどうかとは思ったが。ちょっとリアリティを考えて欲しい・・。それに最後の戦闘シーンであるが、外国人には敵の人間(勝元)に礼を尽くすのは、やはり時代背景抜きには理解できないと思う。時代背景の説明というか説得力が薄っぺらで、ちょうど横浜のコンピュータグラフィックがややちかったのと同様に、映画の厚みの無さをどうしても感じてしまう映画ではあった。 真田広之はなかなか精悍であったが、先日見たLost in Translation同様に、最近の日本を描いた映画は、それほど違和感なく見られるようになったのが、救いである。入場料7.5ユーロ。(22.1.2004)
2006年04月01日
-
ORFのニュース
ORF(オーストリア放送協会)のニュースがVideo on demandで見ることができるのを見つけた。今までもあったのかもしれないが、ただ気づかなかったのかもしれない。というのもORFのHPはひどく入り組んでいて、ひと目ではわからないからである。ZIB2というニュースなのだが、オーストリアらしくいいかげんで、ニュースの後の映画番組もいっしょに映っていたりする。こんなのは著作権から見て問題だと思うが、そんなところがお構いなしなのが、オーストリアのいいところ。最近はVideo on demandで見られるTV番組が増えつつある。ドイツのDWやARDのニュースなども見ることができる。特にPOstcastを用いるととても便利である。近い将来TVがそのままネットで流れるのは間違いないであろう。問題は単に通信スピードだけである。http://tv.orf.at/zib2
2006年04月01日
-
ウィーン国立歌劇場 プロコフィエフ バレイ 「ロミオとジュリエット」
プロコフィエフ バレイ 「ロミオとジュリエット」Romeo und Julia振り付け:John Cranko指揮: Kevin Rhodes配役: Julia Maria Kousouni Romeo Tamas Solymosi Mercutio Gregor Hatala Tybalt Christian Musil Crankoの振り付けでは128回目の公演となる。プロコフィエフはこの「ロミオとジュリエット」を最初はキーロフ・バレイとの間で作ろうとしたが、キーロフ側が拒否したため、次のボリショイ・バレイでの上演を前提にこの作品を作曲した。1935年夏にはこの作品はほぼ完成したが、しかし今度はボリショイ・バレイ側が、この音楽に合わせて踊ることは不可能であるという見解を示して、プロコフィエフと上演契約をすることを拒否したのである。結局このバイレの初演は、チェコのBruennにおいて1938年12月30日にPsota(ロミオ:Psota自身 ジュリエット:Semberova)の振り付けによって行われている。ただ政治的な関係から、この公演は長くは続かなかった。 確かにプロコフィエフの音楽は、それだけ聴いても十分鑑賞に耐えるほど厚みのある音楽になっている。そのため当初バレイ関係者がこの音楽をバレイに不向きであると考え事は容易に推定できるように思われれる。 6月にウィーン国立歌劇場ではさらに数回この公演があるが、Romeo Tamas Solymosi、Julia Maria Kousouni のペアはこれで終わりのようである。JuliaのMaria Kousouniの踊りはなかなかチャーミングで好感が持てた。(1.6.2005)
2006年03月31日
-
年度末・・・・・
すっかりこのブログを放置して、1年経ってしまった。 その間オーストリアの状況もいろいろ変わってきている。今は社会民主党系の銀行BAWAGの問題が世間を騒がせている。投機で巨額の損失を出したようだが、誰一人その損害額を把握していないようで、深刻な問題となっている。特に労組の支持基盤の預金者が多いので、この国特有の政治と経済との歪んだ関係がかいま見えるところである。 またTheater an der Wienがオペラハウスに生まれ変わり盛況であるが、一方でVolksoperの経営状態が心配されている。Volksoperにはがんばってもらいたいところであるが。 来年度からは少しずつ書いて行きたいと思っている。。。
2006年03月30日
-
オーストリア ワインの頒布会を結成したいが・・・
オーストリアの音楽、文学、演劇は、まあそこそこ日本では評価されていると思うが、唯一ワインだけは本当に見事なまでに無視されている。これは美術と全く同じであるが、日本人の頑ななまでのフランス信仰がその害悪の源である。人間の味覚は3歳までに決まるというと、まったくワインの味などわからないのに、馬鹿の一つ覚えのように「フランスワイン」「フランスワイン」と呪文を唱えているやからが多すぎる。その端的な例が「ボジョレー」ブームで、フランスの次ぎにボジョレーを飲んでいるのが日本人であるというのは、驚くべきことである。 ということで、日頃からフランスワインには反感を持っているのであるが、今年から(?)日本でもオーストリアの新酒ワインが結構の量で輸入されて、まあまあの価格で販売されている。私も早速6本ほど買ってみたが、この新酒はグリンツィンクのザーヘルというホイリゲのものだそうだ。 http://www.tanakaya3.com/Austria/Au015.htm HPなどの解説では、「ザーヘルは1930年代以降ホイリゲ(居酒屋)を営み、またホイリゲワインを造ってきた歴史あるワイナリーで、ホイリゲの本場ウィーンのグリンツィングを代表するワイナリーです。「ホイリゲと言えばザーヘル」と言われるほど、いわゆるホイリゲの代名詞となるほど定評のあるワイナリーなのです。また、ザーヘルのホイリゲは毎年オーストリアエアラインのビジネスクラスでサービスされることでも知られています。」 飲んだことはないが、一応このザーヘルというホイリゲのものは悪くないらしい。11月11日が解禁日で、その日あたりに空輸してくれるそうなので、楽しみにしている。 あと日頃から考えているのは、このオーストリアワインの冷遇ぶりは、まったく嘆かわしい限りであるが、それは輸入業者の怠慢のたまものでもある。つまりろくなワインを輸入していないのである。あの例の音楽家の顔が描かれた不味い白ワインを飲めば、だれだって「こんなもんか!」と言いたくなるところである。 だから私の野望としては、「オーストリア 銘酒ワインの頒布会」を結成して、日本でのオーストリアワインの普及に努めたいと思っている。取りあえず、私の好きなRosi SchusterやWeningerあたりをまとめて輸入したいのであるが、賛同していただける方は是非このHPに書き込みをお願いしたい。(まとめて輸入したほうが、単価も安いし、郵送料も安くなる)いつ実現するか未定だが、なんとかオーストリアファンを増やし、味のわからない輸入業者を通さないでおいしいオーストリアワインを味わうというのが、私の目論見である。これを見ていただけるみなさんにお願いする次第であります。 オーストリアワインのランキングhttp://www.austrian.wine.co.at/archiv/ma_050211.htm
2005年10月12日
-
ひさしぶりの日記
ひさしぶりの日記である。実に半年ぶり以上(実は日記を一部削除してしまっているので)であるが、その間いろいろ忙しく、書きたいことも多かったのだが、なにせ時間がなく書き込みができなかった。 その間の大きな出来事は、2年間の留学を終えて日本に帰国したことである。一応遊びにオーストリアに行っていたわけではなく、勉強しにいっていたのであるが、あっという間の2年間である。そして留学以前の日常の生活に戻った訳であるが、あっというまに日本の生活に馴染めてしまうことが悲しかった。 まあ2年間の勉強をこれからの仕事に生かしていきたいと思う。ただこれまでのように気楽にオペラや劇場に足を運べないのは真に残念である。 これからは以前ほど頻繁には書けないと思うが、オーストリアやウィーンに関する話題を少しずつ書いていきたいと思う。また以前の日記を再構成したり、書いていなかったものをまとめていきたいと思う。半年以上放置していたのだが、その間結構多くの方に閲覧していただいて、感謝を申し上げる次第である。
2005年09月26日
-
サイモン・ラトル ウィーン国立歌劇場初登場 ワーグナー「パルジファル」
サイモン・ラトル ウィーン国立歌劇場初登場 ワーグナー「パルジファル」 いよいよ今シーズンの目玉ともいうべきサイモン・ラトルのウィーン国立歌劇場初登場である。すでにラトルはウィーンでは常連であり、昨年の5月のウィーン芸術週間にはベルリンフィルを率いて来たし、すでにウィーンフィルもたびたび客演している。(この1月も振ることになっている)また今年は何とベルリンフィルとウィーンフィルの合同コンサートも指揮するというから驚きである。 ベルリンフィルの常任である彼は、同時にザルツブルク復活祭の芸術監督でもあり、そこで彼は話題になった「フィデリオ」を取り上げている。その上演では「レオノーレ」序曲第3番を演奏せず(これはあればあったで全体の調和を崩しているが、無ければなんか寂しいところである。。)、不必要な台詞を恣意的に省いたため、演出のレンホフに対してかなりブーイングがあったようだが、私には退屈きわまりない作品である「フィデリオ」に対する意欲的な解釈として評価もできるである。 ラトルは意外と知られていないがオペラ活動をかなり昔からスタートさせている。1985年の英国国立オペラのヤナーチェク「カーチャ・カヴァノヴァ」、ベルク「ヴォツェック」(1988年ロス・アンゼルス)「トリスタン」(1997年アムステルダム)、「パルシファル」(1997年アムステルダム)、ヤナーチェク「イエヌーファ」(1996年パリ・シャトレ座)、ドビュッシー「ペレアスとメリザンド」(1996年アムステルダム)などを挙げることができる。ただコンサート指揮者としての評価にはまだ及ばないのが実状であり、これからの成長が期待されているところである。 ということで、結論はどうであったかと言えば、結局悪くは無く、無難に音作りをしていたものの、しかし全体的には新機軸を打ち出せたと言えるほどでは無かった。もともとラトルは演奏中にあまり細かい指示を与える指揮はしない。左右の手を同じように動かしながら、(私のイメージなのだが・・)ヒヨコのようにピョコピョコ飛び上がりながらかわいらしく指揮をするのである。だから十分な練習が必要なのであろうが、この公演のためにあまり時間が取れなかったようだ。オケも最初はややおっかなびっくりといったところで、序曲は全般にゆっくりのテンポを取り、弦の響きもいつもの渋い艶やかな音なのだが、所々テンポを動かすところでは細かい処理がアンサンブルのまとまりがやや悪かったが、次第に調子を上げていった。 ただ何と言っても押しも押されもしない世界の頂点に上り詰めたラトルである。どんな演奏をしようと初めから拍手喝采は間違いないのだが、第一幕などは終わっても聴衆も戸惑ったのか、あまり拍手も無くそのまま休憩になってしまったのは、今日の雰囲気を物語っているように思えた。 (写りが悪いが、一番左がラトル)
2005年01月13日
-
ジルベスターとスマトラ沖地震
今年のジルベスターはベルリンで迎えた。ブランデンブルク門からSiegessaeuleに続く「6月17日通り」には数キロに渡って屋台が並び、ヨーロッパでもっともにぎやかなジルベスターの祝宴が見られるはずであった。 しかし年末年始にかけてヨーロッパは重苦しい雰囲気に包まれた。もちろんスマトラ沖大地震による被害によってである。日本人が考えるよりも多くのオーストリア人とドイツ人がこの地域に出かけており、正確な数字は全く掴めていないが、オーストリア人の10人の死亡が確認され、依然600人程度の行方不明者がおり、ドイツ人は60人の死亡が確認され、1000人の行方不明者がいる。特に今回の報道でタイのカオラックにドイツ人が好んで旅行していたことが知られることになった。この地震が12月26日ではなく、もっと前か後であったら日本人の被害ももっと大きく出ていたことであろう。 ドイツ人やオーストリア人がこの地域に行く理由は非常に明快である。それは旅行代金が非常に安いこと(1週間オーストリア国内にスキー滞在するよりも安い)、そして南国の海が楽しめることの2点である。最近はオーストリアでも肌を焼くことは、金持ちに見せるための必須条件となっている。 今回の被害に関する報道についてだが、地理的に近い日本ではそれほど大々的にではなかったが、ヨーロッパでは連日ニュース・特番でむしろ大きく取り上げられたという現象が見られた。特にニュース専門番組(N24等)では(1月6日現在でも)ほとんどがこれに関する報道であった。 それに対して日本では、年末の恒例番組を予定通り流すため、あるいは紀宮の婚約披露に水を差さないためか、テレビ・新聞はほとんどこの災害報道はスルーで、自粛ムードは無きに等しかったようである。NHKは、この災害に関する特番を組むことはなく紅白歌合戦をやっていたようだし、外務省は今回総額5億ドルになる復興支援の取りまとめは確かに要領よく効果的にやったが、しかし実際の救援活動では、自分の役人の捜索を優先させてやった印象は拭えず、日本人行方不明者数の確定作業などは後回し、ようやく年明けに行方不明者の具体的な数が出てくる始末であった。さらに報道の自由度世界40位にランキングされる日本のマスコミは、正月休みをエンジョイするために、あまりこの被害を強調することはせず、世論を刺激する行方不明者の具体的な数については報道規制だったようで、ようやく正月休みも終わる1月3日になってようやくそれらしい控えめな数字がでてくるようになった。災害地への募金活動などもそれほど活発ではなかったように見える。そのため年明けの経団連の奥田会長の年頭挨拶でも特にこの災害に関する政府の対応の不十分さを指摘していた。奥田会長の最近の中国寄りの発言はいただけないが、しかし海外の視点から日本を見ている人間の感じる共通の認識を表明していたように思う。ただ批判は政府だけでなく、当然この災害に関する報道において怠慢であったマスコミにも向けられるべきであろう。依然日本でも行方不明者が100名いるという事実に関して、ほとんどその数字以上何も報道されていないことはマスコミの見識を疑うところである。 各国ではこの災害に対して問題のあった対応が議論されている。例えばヨーロッパで最大の被害を出しているスウェーデンでは政府の対応の遅れに国民の批判が集中しており、オランダでは被災地に滞在していた内務大臣が災害後も休暇を続行して何もしていなかったことが明らかになり問題となり、オーストリアでも財務大臣のグラッサーが滞在先のモルジブで同じく災害後も休暇を続行していたのだが、帰国が遅れた理由を「帰国便が無かった」とか「モルジブ政府の要請で滞在を続行した」などと言っていたのが、それが嘘だとわかってしまい、現在マスコミで叩かれている。それを考えるとこの災害に関する日本政府の対応も批判されるべき点が多いと思うのだが、幸運なことに正月と重なったために、正月の祝賀ムードを他人の災害によって自粛する気になれない国民と思惑が一致し、政府への批判もほとんど無く、これだけの規模の災害であっても報道は最小限の扱いとなったのであろう。
2005年01月07日
-

本年最後の日記
本年最後の日記 ちょっと早いですが、今日が本年最後の日記になります。旅行に出かけるため残念ながらしばらく書けません。よりによってさらに寒いドイツに行くというのも何なのですが、まあいいでしょう。中途半端になっている日記も多いですが、なんとか来年はそれを補筆したいと思っています。 現地の人は、クリスマスの期間は当然休みですが、その後も休暇を取って1月10日あたりまで連続して休みを取るという人も少なくないでしょう。合計で2週間以上の休暇ということになりますが、スキーに行ったり、南の海に行ったりと、クリスマスに引き続きみな旅行でも忙しいようです。最近はオーストリア人でも遠くタイ(プーケット)やインドネシア(バリ)あたりまで足を延ばす人も多いようです。知人が年に数回バリに行くのですが、当地でドイツ人に良く会うと言っています。まあその中にはオーストリア人も含まれているのでしょう。地理的遠いのですが比較的料金的にはお手軽なので、人気が高いスポットになっているようです。とにかくオーストリアには海が無いだけあって、海に対する憧れは非常に強いようです。国営放送でよく放映されるドラマなども、イタリアの海辺のリゾート地での殺人事件といった設定がよく登場することになります。 ウィーンにこのまま残って、年末マゼールの指揮のウィーンフィルでも聴きに行ってもいいかなとは思っていたのですが(もちろんニューイヤーコンサートではなく、同じプログラムで行われる年末のコンサートの方ですが。)昨年もウィーンに居たので、やはりジルベスターは別の街で迎えたいですね。たぶん伯林になりそうです。ラトル指揮のベルリンフィルの年末のコンサートが3日連続であったのですが、1ヶ月前のチケットの売り出しの当日、あっという間に売れ切れてしまいました。悔しい思いをしました。まあチケット販売店に行けば手に入るかもしれませんが。 また今年も金満日本人がニューイヤーコンサートのチケットを買って、ウィーンに押し掛けてくるのではないかと思います。昨年は右手枡席の一番前あたりの和服の日本人がやけに目立っていました。金さえ出せばニューイヤーコンサートのチケットはいくらでも手に入ります。昨年の相場では、席にもよりますが1000ユーロぐらいでしたが、テレビに良く映る枡席などはその5,6倍はすると言われています。このニューイヤーコンサートのチケットはほとんどが定期会員に販売されますが、その会員たちは代理店を通してチケットを転売することで儲けているわけです。ただ正規チケットは若干ですが一般客にも販売されています。それが確か1月の楽友協会(ウィーンフィルの方だったかな?)のHPで購入申し込みができたと思います。もちろん全員が買えるわけではなく抽選になり、昨年私も申し込みましたが残念ながら外れました。どのくらい一般販売されているかわかりませんが、競争率はきっと相当なものでしょう。でも一応来年また申し込みたいとは思いますが。新年を迎えるとまたザルツブルク音楽祭のチケットの申し込みも始まると思います。先日手元に来年の申し込み用紙とパンフレットが送られてきていました。 ウィーンではもうすっかりクリスマスといったところで、24日の午前まで店が開いていますが、24日の午後と25,26日はお店は完全に休みです。ですので、それまでに食料を買い込んでおかないと、かなりひもじい思いをすることになります。 地方によっても違いますが、中欧ではクリスマスには鯉や鱒をよく食べます。 (Karpfen 鯉) 鯉はもうだいぶ前からスーパーなどにたくさん並んでいるのを見かけます。日本の鯉よりもおおぶりでややグロテスクな印象ですが、フライにして食べることが多いようです。しかし鯉の脂とフライの衣の油で結構しつこい味になるのは仕方がないでしょう。鱒の方は、ホイル焼きにしてレモン汁で食べたり、小麦粉でまぶして油で揚げたり、煮込み料理などにしますが、私はいつもオーブンで塩焼きにして食べています。だいたい中欧の人間は魚料理に関してセンスが無いので、美味しい素材をわざわざ変なふうにして台無しにしてしまいますが、こちらの鱒は日本の虹鱒などよりもよっぽど臭みがないので、自然の味がそのまま引き立つ塩焼きが一番だと思います。食感は鮭に似ています。 Saiblingと呼ばれるイワナもなかなかいけます。これも塩焼きが一番ですが、鱒よりも味は淡泊で、上品です。個人的には鱒よりも好きな魚です。 塩焼きですが、最初に魚の表面と内部に塩をたっぷりつけておきます。30分ぐらいおいておくと水分が抜けますので水を捨て、流れた塩を補うためにもう少し塩をつけます。オーブンでは200度で片面15分から20分程度焼きます。焼き加減はお好みでしょう。ぱりっと焼き上げると皮がきれいに剥がれ、中味を堪能することができます。 そうは言うものの、私はキリスト教徒でも無いし、鯉を美味しいとも思わないので、やはりクリスマスには鶏の丸焼きを食べたいですね。できれば七面鳥のほうがいいかな。 (Forelle 鱒) (Saibling イワナ ) しかしこの時期は本当に鯉にとっては受難の時期です。受難劇は鯉のために捧げられるべきものでしょう。 (昨年の雪のホーフブルク) ウィーンのジルベスターは、まあ特筆すべき行事はありませんが、めいめいが好きなように楽しみながら新年を迎えるといった趣です。当時は仲間と集まってパーティという人も多いとは思いますが、新年のカウントダウンの時間になると、シュテファンス寺院を中心に旧市街に人々が集まりはじめ、手にはシャンパンとグラスを持ち、花火(爆竹がほとんどですが)を打ち上げ、あるいはワルツを踊り、また奇声を発しながら、新年を迎えるということになります。ただ所構わず爆竹を鳴らす若者が多いので、やや危険な感じもしないではありませんが、昨年は特に混乱はありませんでした。 昨年はあいにく雨が降っていたので、全体的に盛り上がりもややしめった感じでありましたが、シュテファンス寺院にはそれなりの数の人が集まっていました。ラジオでは、新年にあわせて鳴らされるシュテファンス寺院の北塔の鐘「プリムメン」の音が全国に生中継されます。日本の除夜の鐘といったところです。 今年はブランデンブルク門で新年を迎えたいですが、果たしてそこまで辿りつけるかどうか。 どうかよいお年をお迎えください。新年は6日あたりからまた復活したいと思っております。
2004年12月22日
-
ウィーン 楽友協会 アルノンクール指揮 ヘンデル 「メサイア」
ウィーン 楽友協会 アルノンクール指揮 ヘンデル 「メサイア」 ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス 今日は楽友協会でアルノンクール指揮ウィーン・コンツェントゥス・ムジクスでヘンデル「メサイア」(全曲)を聞いた。 最も有名なオラトリオといえば、このヘンデルの「メサイア」ということになるだろう。「ハレルヤ」コーラスを聴けば誰もが馴染みの曲ということになる。 三時間にも渡る大曲「メサイア」の第二部の最後に置かれている「ハレルヤ」コーラスは、明るいニ長調を基調に特に印象的な”ハ・レ・ル・ヤ Ha-lle-lu-jah”(”Praise the Lord”主を褒め称えよ が原意)の4つの音節とともにそれぞれ異なる旋律が割り当てられた4声が絡み合う。”ハ・レ・ル・ヤ ”が10回ほど繰り返されると、合唱がユニゾンになり、 "for the Lord God Omnipotent reigneth"(denn Gott, der Herr, regieret allmaechtig 神、主が全能に統治されるがゆえに)を高らかに歌い上げる。単純なフレーズが反復しながら複雑なフーガを形成することで、聴く者の前にめくるめく多様な神の世界を現出させる。 アルノンクール、ウィーン・コンツェントゥス・ムジクスの演奏は、過度な感情表現を抑えた、いつもながらの端正で厳密で禁欲的な演奏でありながら、しかしその禁欲さの中にむしろきわめて人間的な強い表現・欲求・感情を感じさせる見事な演奏である。もちろんそれはアルノンクールその人から由来するところが大きい。アルノンクールは数年前ニューイヤーコンサートに登場し、独特のヨハン・シュトラウス解釈で評判になったが、彼は元々ベルリン生まれでありながら、ウィーンとの繋がりが強く、ウィーンで音楽教育を受けた後、長らくウィーン交響楽団でチェロ奏者を勤めていた。しかしそれにもかかわらず彼は、ウィーンでは永遠の異邦人といった風貌で、ウィーンの中にありながら頑なに自分の演奏理念、スタイルを守り続けている。往年のハンス・リヒターを思わせるところがある。 アルノンクールは名前からして恐らく17世紀にドイツに亡命したフランスのユグノー系の末裔だと思われるが、もしそうであれば、その生い立ちが演奏スタイルにも影響を与えている可能性もあるだろう。例えばドイツのユグノーと言えば、プロイセンの社交界の花であり女流作家であったラ・ロッシュ夫人、法学者のサヴィニー、作家のレマルクなどを挙げることができるだろう。ユグノーはフランスで迫害されるが、オランダ、イギリス、スイスなどでも彼らはプロテスタンティズム倫理の体現者として西欧の資本主義の発展に多大な貢献をした。またグリム兄弟の童話の中にもユグノー経由でペロー由来の童話が入り込んでいる(例えば有名な「灰かぶり」など)ところを見ても、ドイツ文化にも大きな影響を与えているのは確かである。ユグノー教徒は、もちろんユダヤ人とは異なり異国にあって迫害を受けたわけではないが(むしろ融和的であった)、しかし高い文化の担い手として自分たちの文化を実践した人々でもあった。 「メサイア」、ユグノー、クリスマスとなるともちろん非常に宗教的な気分になるのであるが、しかし今週のProfilにキリスト教関係の記事が出ていたが、ヨーロッパでキリスト教徒は全体の68%であり、また毎週教会に通う敬虔な信者は全体の24%である。この数字を高いと見るか低いと見るかは意見が分かれるが、「毎週教会に通う」キリスト教徒が24%もいるというのは、今の日本人から見るとやや驚きであった。またキリスト教徒の割合が高いのは、ルーマニア(93%),ポーランド(88%) ギリシャ(87%)イタリア(82%)の順である。オーストリアはちなみに72%で平均よりちょっと上、ドイツは51%といった程度である。逆に低いのはチェコ(27%) オランダ(38%) イギリス(49%)である。そして一緒に無神論者の数字も挙げられていて、一番多いのがチェコ49% オランダ38% デンマーク37%である。特にデンマークはおもしろく、キリスト教徒は61%いるが、キリスト教徒以外はほとんど無神論者ということらしい。これはほとんど外国人労働者が居ないということであろう。ドイツなどはキリスト教徒と無神論者をあわせると89%なので、11%あまりが一応別の宗教の信者ということになる。 ただこのような統計は取り方によって数値の出方がだいぶ違う。例えばオーストリアなどは、住民票の申告の時にキリスト教と申告すると教会から教会税の徴収が来るので、それを嫌ってキリスト教徒と申告していない人もいるようだ。知人は最近結婚して経済的に苦しいので、教会に手紙を送って窮状を訴え、教会税を免除してもらったと言っていた。
2004年12月21日
-
ウィーンの老舗食料品店ー ユリウス・マインルでの不愉快な経験 (5)
ウィーンの老舗食料品店ー ユリウス・マインルでの不愉快な経験 (5) ユリウス・マインルでの不愉快な経験の件であるが、その後私とマインルとのやりとりのコピーを送っていたVISA-AUSTRIAから反応があった。次のようなものであった。 Sehr geehrter Herr ××,aufgrund der Tatsache, dass mit Ihrem zuletzt gesandten Email auch eine Kopie an die "Office"-Adresse von VISA-AUSTRIA geschickt wurde, erlauben wir uns, Folgendes darzulegen.Die in der bisherigen Kommunikation geschilderte Vorgangweise durch Mitarbeiter der Firma Meinl in Bezug auf Art und Weise der Unterschriftskontrolle entspricht voll und ganz sowohl den direkten, vertraglich geregelten Pflichten als auch den im internationalen VISA Geschäft üblichen Gepflogenheiten. Die für eine sichere Abwicklung einer bargeldlosen Zahlungstransaktion notwendige Sorgfalt dient dabei immer auch der Sicherheit des rechtmäßigen Karteninhabers.Seitens VISA-AUSTRIA wird aufrichtig bedauert, dass die dargelegte, korrekte Vorgangsweise der Firma Meinl aus Ihrer Sicht eine Verletzung Ihrer persönlichen Gefühle darstellt. Wir können Ihnen versichern, dass dies weder im Sinne des weltweit renommierten Unternehmens Meinl ist - noch im Interesse von VISA-AUSTRIA liegt.Für etwaige Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und verbleibe mitmit freundlichen Grüßen 長いので要約するが、 「今までのあなたとマインルとのやりとりを拝見すると、マインルの従業員が署名のチェックについて行った行為は、クレジットカードの利用に関して当社との契約上マインルに課された義務に全く即しているものであり、同時にVISAインターナショナルにおける慣習において何ら違反しているものではない。カードの厳しいチェックは、カードの利用者の安全にも寄与するものでもある。 しかし一方で、マインルによる取り扱いがあなたの観点からすればあなたの感情を著しく害したということは、VISAにとっても非常に残念である。私たちは、この発言が”世界的に有名な企業であるマインルの利益のためでも、VISA-AUSTRIAの利益のために言っている訳ではないことをあなたに保証することができる。質問があればなんなりとどうぞ。」 こういう内容である。まあ手数料を直接徴収しているマインルに対してVISAが批判的な発言をする訳がない。ここで興味深いのは、単にコピーを送っていたVISAが、この段になって私にメールを送ってきた真意である。考えられるのはマインルが手を回したのか、あるいはVISAがこれまでの経緯を見てたまりかねてメールを送ってきたのか、いずれかのような気がする。VISAに対して直接マインルと私の問題を仲裁するように私が頼んだ訳ではないので、わざわざここでマインルと私のもつれた交渉に割って入ってくるVISAは、何らかの意図があると言わざるを得ない。こんなところで割って入ってきても面倒を背負い込むだけだからである。 それを探るために、私はVISAに次のような内容のメールを送った。「私は私がマインルに対して要求した質問にマインルが不誠実にも全く回答していないにも関わらず、あなた方が私たちのやりとりから何らかの判断を下すことができたということは信じられないことである。VISAは、この件に関してどのような事実認定を行って私に対して上記のような意見を送ってきたのか、説明していただきたい。そして次のことは、VISAの規約に適合しているのかどうかお知らせいただきたい。1)店舗の従業員は、顧客を公衆の面前で犯罪者扱いすることが許されているのか?2)店舗の従業員は、顧客の許可無しにクレジットカードを顧客が関知しない所に持っていくことが許されているのか?」 こんな質問にVISAはまともに答えてこないかもしれない。というのも、こんなことが規約に当てはまらないことは当然であり、いちいちこんな当然の答えに答える必要があるとは思わないかもしれないからである。しかしあえて私がそのような質問をしたのは、VISAときちんと論理的な話ができるかどうかを判断するためである。答えがあまりにも当然であるかどうかは別として、こちらの質問に対して論理的な回答をする誠意を持っているかどうかを見たいのである。少なくともマインルはその誠意は持っていない。彼らに都合の悪いことは、一切回答しないから明らかである。 都合の悪いことに一切答えないことは、ヨーロッパ人の常套手段である。本当に昔から言い古されているが、彼らが謝罪する時は、謝罪しても取るに足りない時か、本当に自己の敗北を認めそれに対して責任を取る覚悟ができた場合である。特に後者については、実際はほとんど日本人がお目にかかることはない。もしマインルの店長が私に謝罪した場合、それは自分の無能さを認めた時であり、その後店内で昇進できなくとも文句は言えなくなるからである。このような環境の中で、ヨーロッパ人に誠実さを要求することなどは無理であり、誠実さなどよりも自己の利益が優先されるのである。例え自分が間違っているとわかっていても、絶対にそれは口にせず、相手からそこを突かれても徹底的にはぐらかすのが常套手段である。だからマインルの店長は、私のメールにのらりくらりと応じながらも、一切私の質問に答えようとはしない。自分の都合の良いこと、発言しても支障の無いことだけをこちらに伝えてくる。そこで思い出すのが、オーストリアの美術史美術館などに所蔵されているナチス時代に没収されたユダヤ人の所蔵であった美術品の扱いである。ナチス政権の成立以前、ウィーンに住んでいたアメリカ在住のユダヤ人は今なおオーストリア(当時はナチスドイツに併合されてはいたが)に没収された美術品の返還を要求しているが、しかしオーストリアはのらりくらいと回答を引き延ばしにして誠実に答えようとはしない。それについてあるオーストリア人は次のように私に言っていた。「それは小国になったオーストリアの知恵なんです。時間が過ぎれば年寄りはみんな死んでしまい、みな美しい過去になるでしょう。」と。それがオーストリア人であり、ヨーロッパ人である。彼らに誠実さを求めるのは私の他の経験からしても非常に難しいと思う。 VISAの担当者の文面は、ドイツ語のレベルから考えてもマインルの店長よりも数段教養のある人間の文章である。だからきちんと答えてくるかどうかは五分五分のところであろう。ただ当然マインルに肩入れして私を宥めるためにメールを送ってきたのであるから、こちらとしてもその部分については油断はできないところである。とりあえず、VISAの担当者からの回答を待つことにしたい。 ただ最近気になるのは、再びオーストリアは民族主義的な傾向が見え隠れしているところである。まずオーストリア国内の難民を強制的に軍隊の兵舎に収容する案が出ていることから始まり、トルコのEU加入を巡って先週、首相シュッセルがオーストリア国内で国民投票をする提案を行った。これはトルコのEU加入について国内では反対世論が強いことを見越して、EU内での一定の発言権を確保しようとする狙いとさらとスケープゴートを作ることによって国内での求心力の回復を狙ったものであるという観測も流れている。とにかく国民投票を行った場合、トルコ人への差別的な意識が嫌がおうでも強まることは間違いない。
2004年12月20日
-
日本人初出演!? ウィーン・ブルク劇場 ゲルハルト・ハウプトマン「夜明け前」(プレミエ)
日本人初出演?! ウィーン・ブルク劇場 ゲルハルト・ハウプトマン「夜明け前」(プレミエ) ドイツの自然主義を代表する作家ハウプトマン「夜明け前」のプレミエをブルク劇場で見た。当日にブルク劇場から一度上演キャンセルのメールが来たのだが、その後数十分後に再度上演する旨のメールが来るなど、現場はかなり混乱しているようで、やや上演が危ぶまれる状況であった。 ハウプトマンの「夜明け前」はドイツ自然主義の代表作で、レスピーギが「沈鐘」としてオペラ化し、また明治の文豪・泉鏡花などにも影響を受けているが、1889年の初演は、当時のドイツ文学界においては一つのスキャンダルとなったほどである。 この作品は、ドイツの炭坑町を舞台に、地主で複雑な家庭環境にあるクラウゼ家の人々の生き様を、ありのままに描いている。話は社会改革者であるロートが友人のホフマンHofmannがその長女と結婚しているクラウゼ家を訪れるところから始まる。そこでロートは彼は過酷な労働条件の働く労働者たちを取材するつもりであったが、同時に滞在するクラウゼ家の人々のアルコール依存症、父親と娘の近親相姦を暗示させる関係、退廃した雰囲気に沈潜する人間関係を目撃する。ロートは次第にクラウゼ家の次女ヘレーネと親しくなるが、ここで唯一健全の精神を持っている旧知の医者シンメルプフェニッヒSchimmelpfennigからヘレーネとの関係を警告される。そして長女マルタMarthaとホフマンHofmannの子供が生まれるが、それは死産で終わり、決してクラウゼ家の新たな「夜明け」にはほど遠く、次女ヘレーネにもクラウゼ家の刻印を見たロートは、結局この地から一人去っていくのである。 当時の初演の記録では、第2幕の初めあたりから、つまりこの家の主人クラウゼKrauseが酔っ払って帰ってきて自分の娘に性的暴力を暗示する行動をするあたりから、観客が騒ぎ始めた。一部の観客が「俺たちは売春宿にいるのか!」と叫び始めたのである。そして第2幕は、クラウゼの最初の妻から生まれた娘ヘレーネが、クラウゼ夫人の小間使いMieleがこの家にいることを許されなければ、彼女の義理の母クラウゼ夫人と彼女の甥でヘレーネの婚約者でもあるヴィルヘルム・カールWilhelm Kahlの不倫関係をばらすと脅迫する場面で終わるが、その場面でも場内が騒然となった。第3幕以降も観客の怒号が絶え間なく飛び交い、もはや上演を続けることが不可能であると思われるほどであった。そして第4幕で舞台裏でマルタMarthaとホフマンHofmannの子供が生まれる一方で、舞台では医者のシンメルプフェニッヒSchimmelpfennigと社会改革者ロートLothが皮肉な会話を交わす場面があるが、そこでこの騒乱が頂点を迎えた。最後のカーテンコールではハウプトマン自身が舞台に現れたようだが、観客からは複雑な反応であったようだ。翌日の新聞の批評も賛否両論に分かれたが、この騒動によってハウプトマンはドイツで最も有名な問題作家となったのである。ニコラス・シュテーマン演出 この作品は「豊かさの中にある危機」という一連のシリーズの一つの作品としての上演である。 (日本人? Sachiko Hara ) たぶん日本人だと思うが、クラウゼ夫人の小間使いMiele役で日本人のSachiko Haraという女優が出ていた。何回か歌を歌っていたので声楽出身の女優なのかもしれない。歌は女優の歌としては悪くはないのだが、演技はうーん、何とも評価できないレベルであった。故意にぎこちなく演じているようにも見えないのであるが。。。「うる星やつら」のラムちゃんのような衣装だった。
2004年12月19日
全155件 (155件中 1-50件目)
-
-
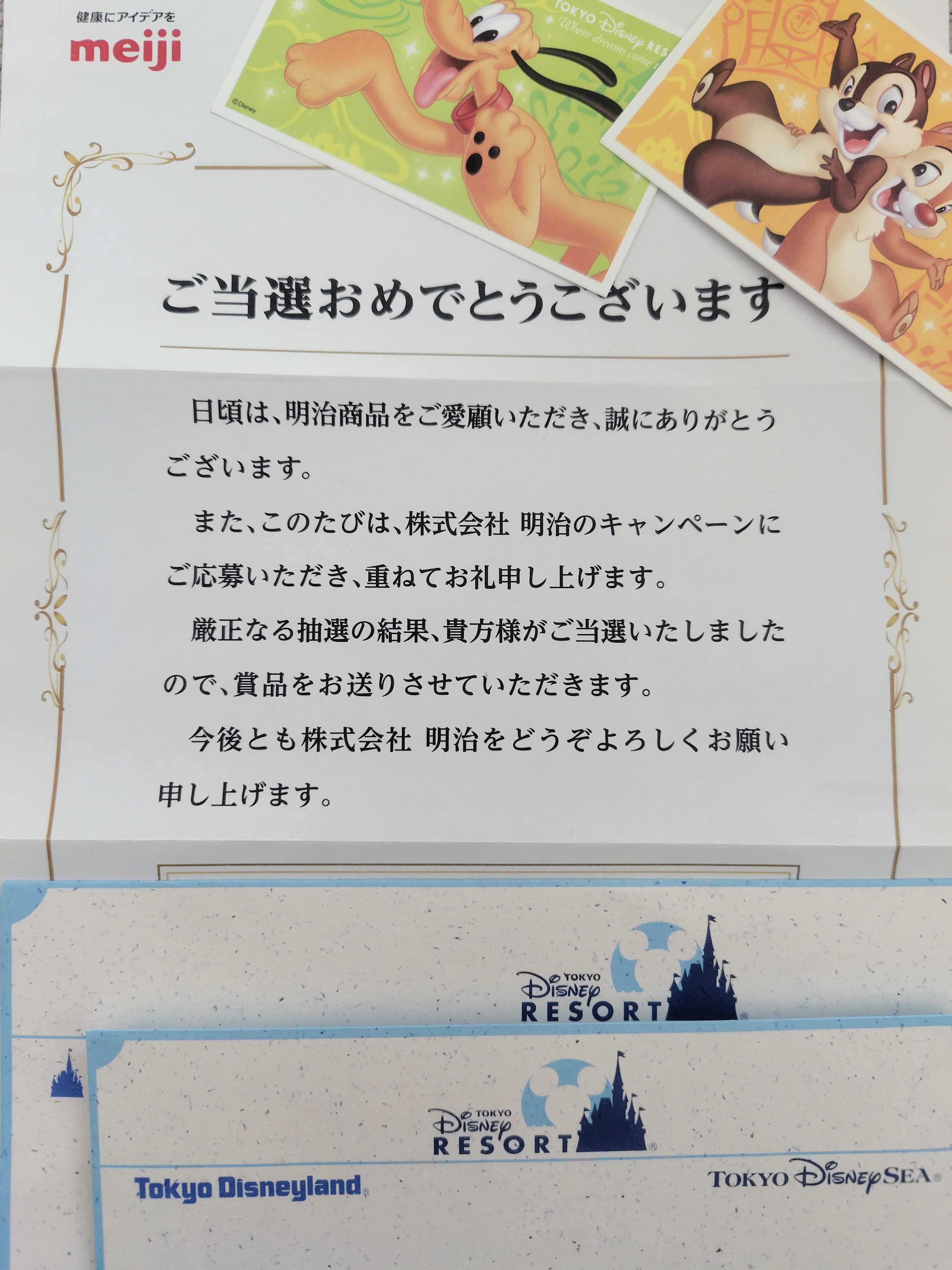
- ディズニーリゾート大好っき!
- 当選☆相鉄ローゼン★ディズニーチケッ…
- (2025-11-30 15:40:56)
-
-
-

- 日本各地の神社仏閣の御朱印
- 秋の京都旅行 おもかる石と伏見稲荷…
- (2025-11-29 13:52:53)
-
-
-
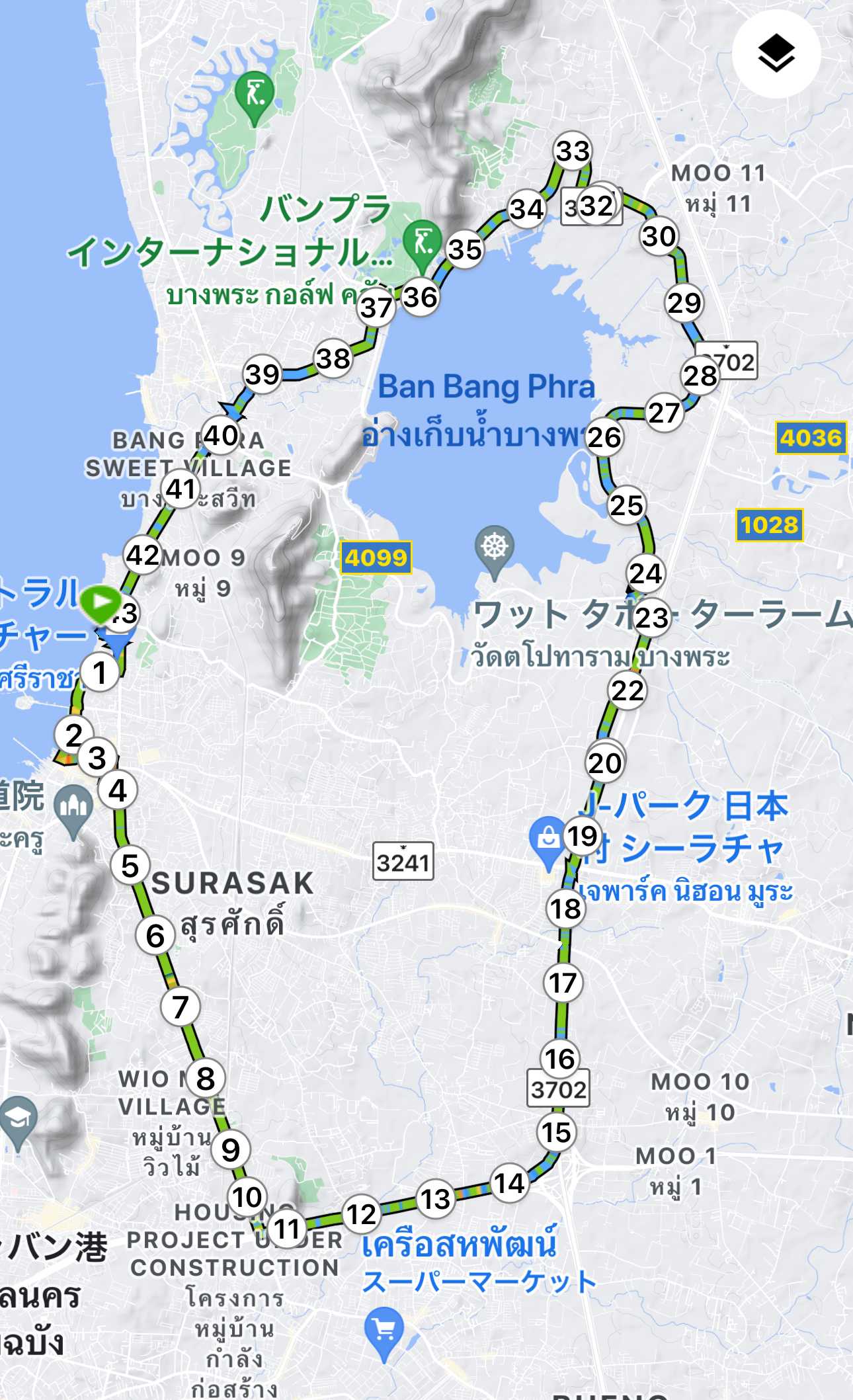
- タイ
- タイ駐在10年の軌跡 ~シラチャ43㎞…
- (2025-11-26 21:18:33)
-








