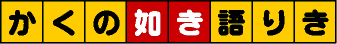2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年12月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
●●●亀も空を飛ぶ
トルコとの国境も近い、イラク北部クルディスタン地方の小さな村。2003年である、まさにアメリカ軍の動向が、この地方の大人の最大の気がかりな頃、子どもたちは元気に駆け回り働いていた。リーダーの少年はサテライト、近郊の村を回り子どもたちを率いながら、便利屋として大人たちに重宝されていた。その日はバラボラ・アンテナを買い求め、村に設置してテレビの取り付けを行っていた。ほんの少し英語を知っている彼だが、アメリカのニュース番組を訳せるほどの力はない。適当に言いくるめ大人たちを煙に巻く。しかしながら誰もが皆、「ニュース」が必要なのは確かである。足のない子が器用に松葉杖をついて、サテライトの回りにいる。地雷がそこら中に埋まっているのだ。そして子どもたちは地雷を掘り出し、サテライトの手配で国連の出先機関に売るのだ。ある少年は口で信管を取り外していた。誰よりも地雷を取り出した彼には、両腕がなかったのである。隣にはいとけない少女がいて、二人は兄妹のようである。もうひとり、幼い幼児を連れていた。サテライトがその妹に恋心をを抱くのも、サテライトの周囲の子どもたちがにやついてその様子を見てるのも微笑ましい。彼らは危険と隣り合わせの中で、無邪気さと明るさは失わないでいた。だが、両腕のない子とその妹には、辛く狂おしい暗闇があった。マジックリアリズムと呼ばれる手法で、ドキュメンタリーのようなニュアンスに、少年たちの物語をない交ぜにしてゆく。バフマン・ゴバディ監督作品。戦禍にも元気で明るい子どもたちに焦点をあて、暖かいまなざしで包みながらも、しっかりと見据えられているのは、「未来」のようである。大人たちは「ニュース」を欲しがり、両腕のない少年は「未来」を「予言」する。だが彼は妹と妹の産んだ子どもに起こる悲劇を、防ぐことはできなかったのである。自分の力で必死に生きようとする子どもたち、サテライトもまた、彼なりに必死である。恋した少女の子どもを救うため、足に怪我をしたというのに、少女もその子どもも世界からいなくなった。その代わりのように、フセインの銅像の腕と染められた金魚が彼にもたらされる。どれだけ懸命に生きようとも、戦争は人の命をもてあそび運命を変える。サテライト少年のもとに、両腕のない少年から「予言」が届けられた。だが今は通り過ぎる戦車の列を観るのが精一杯のようであった。
2005.12.05
コメント(2)
-
●●●義経~生々流転、万物は流れていく
源義経の人生も終盤となる。逃亡の旅の果てに迎えられた北の地、奥州の王者は快く義経主従を迎え入れる。藤原秀衡、全てを受け入れた上での偽りのない歓待、暖かい。泰衡ら子たちも変わらぬ姿である。穏やかな日々を過ごしたかつての館に戻り、郎党が観るのは金色の屏風である。平清盛が夢見た福原の都、新しき国の夢それは今、義経の胸にある。京より吉次が知らせたのは、静御前の話である。しずやしず、鶴岡八幡宮の祝いの席で、頼朝ではなく、義経を想って舞ったという、生まれたのは女子、その子とともに京にいると、吉次は言うが顔は曇っていいる。真実は義経にも明らかであった。新しき国、それは。清盛入道と語った夢の都、異国との商いで栄え、人々は皆豊かで、親兄弟が争わず安寧に暮らす国。秀衡には全てが見えていた。源義経の夢は鎌倉にはなかっただろう。ならばここで作るがいい、と奥州の王者は快く義経を受け入れる。奥州の王者はなおもこの国を、豊かにしようと夢を見ているようでもある。誰の目も豊かな北の王国である。だが、まだ彼は先を見ているようである。だが生々流転。万物は全て流れていく。かつて義経に継ぎ従い、奥州を出た佐藤継信、忠信兄弟は死に、鷲尾三郎義久が初めて奥州の地を踏んだ。時は流れていく、北に王国を作り上げた王者は、義経よりも誰よりも、源頼朝との決着に気づいていた。藤原秀衡は知っていたのだ、何か理由があれば鎌倉は北にやってくる。こちらからは攻め込まぬ、だが白川の関を越えるならば、戦う覚悟を秘めていた。白川の関を越えたならば。頼朝は奥州の王者の格を感じていた。どっしりと立つ王者の姿を感じていた。だが、藤原泰衡は違う。息子に四代目継承を宣言した後、秀衡は病の床につく。そして巨星墜つ。頼朝には奥州が見えていた。そこにいる義経の姿も、きっと。若きもののふの人生はそうして遂に、終盤へと差しかかることとなる。誰も伝えてはくれぬ、誰も教えてはくれぬ、偉大な人物も未来に夢を託そうとも叶わぬまま、終焉へと向かっていくのである、終焉へと。だが命は消えるまである。
2005.12.04
コメント(6)
-
●●●終わりに見た街
歴史にもしも、はないけれど。それでも、敢えて、もしも、である。一つの家族と一つと父子が昭和19年にタイムスリップした。もしも、そんな不可思議なことがなければ。200×年の「東京」は、今のままであっただろうか。携帯電話。テレビ、パソコン、ゲーム。ハンバーガー、チョコレート。冷蔵庫にはいつも卵とミルクが入っている。この作品に描かれたことが、別の歴史を生み出したと言えるだろうか。山田太一の原作・脚本、1982年にドラマ化された作品のリメイク。ところどころ過去の記憶も蘇ってくる。家族の物語、と印象があったが、終戦60年として企画されたこの作品は、「警告」としての色彩が強い。歴史にもしも、はないけれど。浅草生まれの清水要治、システムエンジニアである。マイホームがあり、妻と中学生の女の子、小学生の男の子の四人家族。タイムスリップしたのは、久しぶりに再会した小学校時代の旧友、宮島敏夫と息子の二人の二組だった。口の達者な宮島の活躍もあり、二組は疑いの目を避けながらも、昭和19年の生活に溶け込んでいく。国民登録、配給、竹槍訓練、軍需工場での労働、農家への買い出し、男たちは髪を切り、英語の服はもう着られない。ただ持ち込んだ昭和史を記す資料が、この困難な状況を生き抜く武器になっていた。だからこそ清水たちは、東京に起こる大空襲で起こる悲劇を少しでも減らせないかと一計を巡らせた。噂話の体裁をとり、3月9日深夜の空襲を東京の下町の人たちに警告できないかと。だが歴史は彼らの試みを踏みつぶす。しかも思わぬ形となって。近づく爆撃機。空襲のないはずの場所にいる清水たち。だが、爆撃機の音は大きくなる。炎が彼らを包もうとしていた。中学、高校の世代の若者たちは、今を生きようとしていた。皆が戦っているのだから戦うのだ。父親たちはもうすぐ終わるこの戦争は終わる、これは愚かな戦争だと言う大人に対し、若者たちは時代の熱に囚われようとしていた。戦わなければならない。戦うことが、この時代を生きること。この物語は40代の大人たちと子どもたちが話し合う場面が少ない。膝をつき合わし語り合うことのないままに、昭和19年の中で若者たちは、時代に熱に囚われようとしていた。歴史にもしもはないけれども。「歴史と違う!」清水要治は東京都心を見た。くずれたビルを見た、くずれた東京タワー。左腕の無くなった彼が最後に見た町。瓦礫に埋もれた世界に、死体が無数に転がっている。そして死に際の男に遭遇する。水を欲しがっていることから、何がその地に起こったのか容易に想像できる。清水は確認しようと男に聞いた。男は途切れ途切れに答える。「ニセン・・・×年」新たに清水が飛ばされたのは、携帯電話やハンバーガーのある時代である。二度目の「終わりに見た街」荒唐無稽な物語だと思うこともある。だがこの作品の衝撃のラストは時代を経ることに、信憑性を帯びてくる。エンディングに流れるのは、私たちの知る「現代」の姿である。人の溢れる大都会、小泉首相が手を振っている。歴史にもしもはないけれども。もし何が出来るとしたら何が出来るというのか。このラストシーンを私たちが迎えることのないように。そう切に「願う」しかないのか。「終わりに見た街」オフィシャルサイト「終わりに見た街」(←以前の日記です)
2005.12.03
コメント(7)
-

●●●ボーイズ ドント クライ
華奢な身体に細い首、ベリーショートの髪を、器用に手で整えていつもの髪型に。角張った顔に浮かぶはにかんだ微笑み。21歳のブランドン・ティーナ。彼はいつも優しい。男は女に優しくなれるのだ。惚れた女なら尚更だろう。もし女が嬉しそうに笑ってくれれば、その笑顔は男の戦利品になるのだ、と、ブランドンを観ていて思った。性同一性障害。心の病として名前を付けられても、病気、というのは彼に相応しくない。1993年、21歳でティーナ・ブランドンは殺された。華奢な身体に細い首、ベリーショートの髪、角張った顔に浮かぶはにかんだ微笑み。胸にきつく布を巻いている。股間には丸めたソックスを入れて、男物のパンツを穿いているけれども、足は白く細くか弱かった。ヒラリー・スワンクの演技と、鮮烈で清冽な映像が見る者を巻き込む。ネブラスカ州フォールズ・シティ。都会とは程遠い町のバーでブランドンは、ラナという女性と出会った。彼女に恋をしてその気持ちは通じて、やがて二人は愛し合うようになる。ブランドンの愛撫を受け入れるラナ。強い愛情で結ばれながらも、やがてブランドンの正体がばれ悲劇が訪れる。複雑な家庭で育ったラナ、もちろん家族はこの恋を許さない。ティーナ・ブランドンは女としてレイプされ、警察にも女として訊問される。男は女に優しくなれるのに。ブランドンを見れば見るほど思う。作ってもらった食事はおいしい、といい、プレゼントを貰えば、心底よろこんだ。殺される間際まで世話になった女性を庇っていたのだ。しかもどこかで強くなろうと必死である。彼が成りたかったのはタダの男性ではないのだ、きっと。惚れた「女」を幸せにしたい。そのためには「男」になるしかなかったのだ。華奢な身体に細い首、ベリーショートの髪、角張った顔に浮かぶはにかんだ微笑み。鏡を見て笑っているブランドン。ヒラリー・スワンクは少年の姿をしていた。そして彼女はティーナ・ブランドンにもなる。男の暴力に屈しざるを得ない女になる。キンバリー・ピアース監督は、ティーナ・ブランドンの軌跡を描いている。事件が抱える社会的な問題ではなく、彼女が何を思い何を考えたか、に。視点に偏りを見せぬよう、しっかりと彼女に支点を据え、この痛ましい実話に命を吹き込んでいる。ブランドン・ティーナネブラスカ州をでたことがないと言っていた。本当に出たかったのだろう。その町から、その場所から。愛するラナと一緒に。「ボーイズ ドント クライ」オフィシャルサイト
2005.12.02
コメント(4)
-
●●●コーラス
「池の底」と呼ばれる寄宿舎、固く閉ざされた門の前で土曜日に迎えに来ると言った父親をペピノはずっと待っていたのである。丁度そんな時、マチュー先生は赴任してきた。1949年、フランスの片田舎。丸い顔に丸い身体をしたクレマン・マチューは、鞄の中に大切に譜面を隠していた。まだ世界は戦禍の闇を色濃く残している。音楽への夢を志していたなら、さぞ辛い時代を過ごしたことだろう。しかも挫折の果てに赴任した寄宿舎は、問題児たちの巣窟だったのだ。その上に校長先生の方針は体罰である。悪戯と体罰が繰り返され悪循環が続いていた。それを解きほぐしたのは、丸い顔に丸い身体のマチュー先生の振る、柔らかな腕のタクトである。彼の腕に合わせて、子供たちは声を合わせて歌っている。コーラス。最初はぎこちなく。だが、次第に声が重なっていく。それはいつしか奇跡のように紡がれて高らかに歌声は音楽になる。誰も彼も皆、全てが、何かを持って生まれて来る。それは唯一とゆうべきもので、他と比べるものではなく、だからこそ強く、美しくさえある。子どもたちの声は子どもたちだけのもの。マチュー先生の音楽もそう。自分だけが持つ宝物を認識できてこそ、やっと人は手を伸ばすことが出来る、そうして「世界」を知るのである。物語は50年を過ぎた現代から始まる。ペピノが訪れたのは、世界的指揮者のピエール。その指揮者が世界に羽ばたいたのも、クレマン・マチューのタクトがきっかけだった。天使の声を持っていながら「池の底」で一二を争うピエール少年は、長い間悪戯を重ね、母親に苦労をかけていた。その彼が歌う喜びとマチューの心を知ったとき、彼の手はやっと「世界」に手が届いた。クレマン・マチュー演じる、ジェラール・ジュニョの軽妙な演技、ジャン=バティスト・モニエのソプラノボイスは、この作品の大きな要素ではある。だが子供たち一人一人の「個性」も、丁寧にかつ、素朴に写し出されている。ソリストの歌声に聞き惚れながらも、コーラスという題材に「個性」の輝きも見える。丸い顔に丸い身体のマチュー先生の振る、柔らかな腕のタクト。だが数少ないテノールのはずだった一人の少年は声を出す機会のないまま復讐の罪を犯す。まるで、マチューが来るまでの「池の底」のように。逆に、用務員に重傷を負わせた少年は、マチューによって罪を知り、罪を償う機会を得る。土曜日に迎えに来るそういった父親は既に死んでいるのにずっと待ち続けてたペピノ少年だった。だが、彼は学校を去るマチューについていった。小さな手は「世界」に触れようと、必死で走っているかのように。「コーラス」オフィシャルサイト
2005.12.01
コメント(10)
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
-

- 台湾ドラマ☆タレント
- 涙をこらえて歌う「愛轉角」
- (2025-02-16 19:53:58)
-
-
-

- 宝塚好きな人いませんか?
- 2/9 退職祝いパーティ(推しを推す会…
- (2025-02-16 13:32:23)
-
-
-

- どんなテレビを見ました?
- 【夜ドラ】バニラな毎日(17)感想
- (2025-02-18 11:54:25)
-