2025年02月の記事
全46件 (46件中 1-46件目)
1
-

侍女の物語 マーガレット・アトウッド 斎藤英治 早川書房
日常とは、あなた方が慣れているもののことです今はまだこの状態が日常には思えないかもしれません。でも、しばらくすればきっとそう思えるようになるはずです。これが日常になるのです。侍女の物語 (ハヤカワepi文庫) [ マーガレット・アトウッド ]価格:1,320円(税込、送料無料) (2025/2/26時点)楽天で購入
2025.02.26
コメント(0)
-

自然は脈動する 再々々々々 アリック・バーソロミュー 野口正雄 日本教文社
H2Oという記号は純水、つまり蒸留された水を表している。この種の水は発達した特徴や性質をもたないため、ヴィクトルはこの水を「幼い」水と呼んだ。この水は生硬で飢えているのだ。赤ん坊のように手の届くところにあるものを何でもつかんでしまう。この幼い水だけを飲んでいれば、人は衰弱し、やがて死んでしまう。この水が体内からミネラルと微量元素をしぼり取るからだ。水は、他の生物がエネルギーと生存のために必要としている物質、いわゆる「不純物」を適度に含んだ状態になると成熟する。自然は脈動する ヴィクトル・シャウベルガーの驚くべき洞察 [ アリック・バーソロミュー ]価格:2,860円(税込、送料無料) (2025/2/25時点)楽天で購入
2025.02.25
コメント(0)
-

鳥部野や鷲の高嶺の末ならんけぶりを分て出づる月影 西行
鳥部山にてとかくのわざしける煙中より夜更けて出でける月のあはれに見えければGeminiさんによる解説この歌は西行の『山家集』に収められていますこの歌は鳥部山で葬送の儀式が行われている煙の中から夜更けに出てきた月を見てその月の光を死者の魂の導き手のように感じた心情を詠んでいます現代語訳と解説は以下のとおりです現代語訳鳥部山で葬送の儀式が行われ煙が立ち込める中夜更けに出てきた月がなんとも哀れ深く見えたので詠んだ歌鳥部野や鷲の高嶺の末から立ち上る煙を分けて出てくる月の光よ解説この歌は死者の魂を弔う情景と月の光を重ね合わせることで死者への鎮魂の思いを表現しています「鳥部山」は京都の葬送の地として知られていました「とかくのわざ」は葬送の儀式を意味します「煙中より」は煙の中からという意味で葬送の儀式で立ち上る煙を表しています「夜更けて出でける月」は夜遅くに出てきた月のことで死者の魂を導く光のように感じられます「鷲の高嶺」は鳥部山にある鷲峰(じゅうぶ)という山のことで葬送の地として知られています「けぶりを分て出づる月影」は煙を分けて出てくる月の光という意味で月の光が死者の魂を導く光のように感じられますこの歌から読み取れるのは死者への鎮魂の思いと月の光を死者の魂の導き手のように感じる西行の優しい心情ですChatGPTさんによる解説現代語訳鳥部野よあの煙は鷲が舞うような高嶺の頂から立ち昇るものなのかその煙を押し分けて夜更けに浮かび出た月の光のなんとあわれなことよ解釈と鑑賞1. 「鳥部野」 と 「煙」「鳥部野(とりべの)」京都の鳥部野は葬送の地として知られる場所「煙」 火葬の煙を指すと考えられる→ 「夜更けに立ち昇る煙」 は人の死を思わせる情景 そこに月が昇ることでさらに深い余情が生まれる2. 「鷲の高嶺の末ならん」「鷲の高嶺」霊山や高山を指し鷲が天高く舞うような場所「末ならん」その頂の端(すえ)から昇るのだろうか→ 鷲が天に向かうように煙も高く昇る 死者の魂が天に帰るようなイメージも感じられる3. 「煙を分けて出づる月影」「煙を分けて出づる」立ちこめる煙の間から月が現れる「月影」ただの月ではなく「影」として捉えられることでもの悲しさや幽玄さが加わる→ 煙と月の対比 が美しい - 煙は地上のもの(人の営み・死の象徴) - 月は天上のもの(永遠・浄化) → この対比が世の無常を際立たせる全体の趣葬送の地・鳥部野の静寂の中夜更けに煙が立ち昇る情景その煙を押し分けるように現れる月に「あはれ」を感じる死と月光儚さと永遠を対比させながら深い余情を生み出している→ 西行の無常観と美意識が込められた歌 ですねClaudeさんによる解説この和歌は鳥部山(とりべやま)での実体験に基づいた歌です題詞からは火葬場の煙の中から月が出てきた時の感動が詠まれていることが分かります「鳥部野や」鳥部野は京都の東山にある火葬場のあった場所です「や」は詠嘆を表す助詞です「鷲の高嶺の末ならん」「鷲の高嶺」は鷲が住むような高い山の頂を指します「末」は山の端を意味します「ならん」は推量を表す助動詞です「けぶりを分て」火葬の煙を分けるようにという意味です煙の中から月が姿を現す様子を動的に表現しています「出づる月影」煙の中から現れ出る月の姿を表現していますこの月の出現に深い感動を覚えていますこの歌の特徴は火葬場という死と直接向き合う場所で煙を分けて出てくる月に深い感動を見出している点です火葬の煙という無常を象徴するものと清らかな月光という永遠性を象徴するものが対比され深い仏教的な洞察が感じられます題詞の「あはれに見えければ」という言葉からも分かるようにこの情景に西行が深い感動を覚えたことが伝わってきます死と向き合う場所での月との出会いという西行らしい死生観が表れた秀歌といえるでしょうGrokさんによる解説この歌も西行の作品で鳥部山での情景と月の美しさを詠んでいます以下に詳しく解説します鳥部山にて「鳥部山」は実在の山で奈良県にある山を指します「にて」は「で」の意味で「鳥部山で」と解釈できますとかくのわざしける「とかくのわざ」は「さまざまな仕事」や「いろいろなこと」「しける」は「していた」の意味です「とかくのわざしける」は「いろいろなことをしていた」という意味です煙中より「煙中」は「煙の中」の意味で「より」は「から」の意味です「煙中より」は「煙の中から」のことです夜更けて出でける月の「夜更けて」は「夜が更けて」「夜が深まって」「出でける」は「出た」の意味で「月の」は「月が」のことです「夜更けて出でける月の」は「夜が更けて出てきた月が」の意味ですあはれに見えければ「あはれ」は「美しい」「哀れ」の意味で「見えければ」は「見えたならば」の意味です「あはれに見えければ」は「美しく見えたので」の意味です鳥部野や「鳥部野」は鳥部山の周辺の野原を指し「や」は感嘆や呼びかけの助詞です「鳥部野や」は「鳥部野よ」と解釈できます鷲の高嶺の末ならん「鷲の高嶺」は「鷲の高い峰」「末ならん」は「末であるだろう」の意味です「鷲の高嶺の末ならん」は「鷲の高い峰の末であるだろう」のことですけぶりを分て「けぶり」は「煙」の意味で「分て」は「分けて」の意味です「けぶりを分て」は「煙を分けて」のことです出づる月影「出づる」は「出る」の意味で「月影」は「月の光」や「月の姿」のことです「出づる月影」は「出てくる月の光」の意味ですこの歌は鳥部山でいろいろなことが行われていた煙の中から夜が更けて月が出てきた情景を詠んでいます西行はその美しさに感動し鳥部野や鷲の高嶺の煙を分けて現れる月の光を詩的に表現していますここには自然の美しさとその一時性が煙という日常的な情景から浮かび上がる月の姿によって強調されています月の光が煙を抜けて現れる様子は自然の静寂や純粋さを象徴し西行の感動を呼び起こしていますこの歌からは自然の中での一瞬の美しさに対する敏感さとそれが人間の心に与える深い影響が感じられますPerplexityさんによる解説この歌は西行の有名な和歌の一つで鳥部山(とりべやま)での情景を詠んだものです以下にその意味と解釈を示します歌の意味「鳥部野や鷲の高嶺の端であろうか。煙を分けて出てくる月の姿が哀れに美しい。」解釈この歌には西行の繊細な感性と自然観察力が表れています背景鳥部山は京都の東山にある火葬場があった場所です西行がここで何らかの仕事(おそらく火葬に関連する)をしていたことが示唆されています情景描写煙の立ち込める中から月が姿を現す様子を描写していますこれは火葬の煙を通して見える月を表現しているのでしょう鷲の高嶺鳥部山の頂上を鷲の高嶺に喩えていますこれは山の高さと尖った形状を表現するとともに神聖さや崇高さを暗示しています月の象徴性煙を分けて出てくる月は死と再生のサイクルあるいは浄化や解脱を象徴しているとも解釈できます「あはれ」の感覚西行が好んで用いた「あはれ」という言葉はここでは月の美しさと同時に人生の無常さや儚さへの感慨を表現していますこの歌は死と美俗世と聖なるものの対比を通じて西行の仏教的世界観と美意識を巧みに表現しています煙の中から現れる月の姿に西行は人生の真理や美を見出し深い感動を覚えたのでしょうこの歌は西行の代表作の一つとしてその後の和歌や日本文学に大きな影響を与えましたFeloさんによる解説西行の歌「鳥部山にてとかくのわざしける煙中より、夜更けて出でける月のあはれに見えければ」は彼の詩的な感受性と自然との深い結びつきを表現していますこの歌は鳥部山の煙の中から夜遅くに現れる月の美しさを描写しています歌の解釈情景描写歌の冒頭では鳥部山での煙が描かれていますこの煙は自然の中での生活や行為を象徴しておりそこから夜更けに現れる月の光が静けさや神秘的な美しさをもたらします月が煙を分けて出てくる様子は自然の調和を感じさせます感情の表現西行は月の光を通じて感情を表現しています月はしばしば人の心情を映し出す存在として描かれ彼の歌においても月を見ることで感じる感慨や孤独感が表現されていますこの歌では月の美しさが心に深く響く様子が描かれています無常のテーマ西行の作品には無常観がしばしば表れますこの歌もその一例で煙の中から現れる月は時間の流れや儚さを暗示しています彼の作品は自然の美しさと同時にその背後にある悲しみや孤独を感じさせるものです西行全歌集 (岩波文庫 黄23-2) [ 西行 ]価格:1,507円(税込、送料無料) (2025/2/22時点)楽天で購入
2025.02.24
コメント(0)
-

白妙の衣重ぬる月影のさゆる真袖にかゝる白露 西行
月Geminiさんによる解説この歌は西行の『山家集』に収録されていますこの歌は月の光が降り注ぐ中袖にかかる白露の美しさを詠んだ歌です現代語訳と解説は以下のとおりです現代語訳白い衣を重ね着ているような月の光が清く澄み渡る私の袖に白露が降りかかることだ解説この歌は月の光と白露の白さを重ね合わせることで幻想的な美しさを表現しています「白妙の衣重ぬる」は月の光が白い衣を重ね着ているように見える様子を表しています「月影のさゆる」は月の光が清く澄み渡っている様子を表しています「真袖」はまっすぐな袖ここでは清らかな袖を意味します「かゝる白露」は袖にかかる白露を表していますこの歌から読み取れるのは月の光と白露の白さが織りなす幻想的な美しさですChatGPTさんによる解説現代語訳白く澄んだ衣を重ねるように月の光が幾重にも降り注ぐ夜その冷ややかな光の袖にひとしずくの白露がかかることよ解説1. 「白妙の衣重ぬる」「白妙(しろたへ)の衣」白い衣(特に清らかで美しい衣を指す)「重ぬる」重ねる幾重にもまとわせる→ 「白妙の衣」が月光の比喩にもなっている まるで**「月の光が何層にも重なるように降り注ぐ」** かのような情景2. 「月影のさゆる真袖にかゝる白露」「月影のさゆる」月の光が澄み渡る冷たく冴える「真袖(まそで)」(着物の)袖「かゝる白露」袖に降りかかる白露(夜露)→ 冷たく澄んだ月の光が衣を通して袖にまとわりつき そこにさらに夜露がかかる様子 「月の光」と「白露」の重なり が繊細な美しさを醸し出している歌の趣と解釈1. 清らかな月夜の情景白い衣と月の光白露という純白のイメージの重なり月光が冷たく冴え夜露がしっとりと袖を濡らす 静寂の美視覚(白妙の衣・月の光)と触覚(冷たい夜露)の組み合わせが鮮やか2. 移ろいゆくものの儚さ月の光は清らかでありながらどこか冷たく儚いそこに落ちる夜露は一瞬で消え去るものの象徴「美しくも、すぐに失われるもの」 への繊細な感受性が表れている3. 「月」と「袖」に託された感情古典では「袖」は涙や感情を映す場所 としてよく使われる月光が袖に降りかかる → 月を眺める人の心情が袖に映るそこにさらに夜露が加わることで月に寄せる思いが涙のように静かに積もる様子が浮かぶまとめこの歌は白妙の衣・月光・白露という白の重なりを用いて月夜の静かな美しさと儚さを詠んだ一首清冽な月光と夜露が袖に降りかかる純白の美しさと消えゆくものの儚さが対照的に描かれる袖にかかる月光と夜露が涙のようにも感じられる西行らしい静けさと余情に満ちた一首 ですねClaudeさんによる解説この和歌は月光と露を白い衣に重ね合わせた繊細な光の表現が特徴的な歌です「白妙の」「白妙」は真っ白で美しいさまを表す枕詞です「衣」にかかる枕詞として使われています「衣重ぬる」衣を重ね着るという意味ですここでは月光が層になって降り注ぐさまを衣を重ねることに譬えています「月影の」月の光を指しますこの月光が次の「さゆる真袖」に白い露とともに降り注ぐイメージです「さゆる真袖に」「さゆる」は冷たくなる寒さで凍えるという意味です「真袖」は着物の袖を指します夜の冷気で冷たくなった袖を表現しています「かゝる白露」袖に置く白い露を指します月光とともに袖に宿る露を表現していますこの歌の特徴は月光と露という二つの白い光を重ね着た衣に譬えて表現している点です夜の静けさの中で月の光と露が袖に重なり合う様子を繊細な感性で捉えていますまた「さゆる」という言葉で寒さを表現することで秋の夜の冷気も伝わってきます視覚的なイメージと触覚的な感覚が見事に結びついた秀歌といえるでしょう西行らしい繊細な自然観察とそれを美しい比喩で表現する技巧が光る歌ですGrokさんによる解説この歌も西行の作品で月の光と白露の美しさを詠んでいます以下に詳しく解説します白妙の衣「白妙」は「白く美しい」の意味で「衣」は「衣服」のことです「白妙の衣」は「白く美しい衣服」を指します重ぬる「重ぬる」は「重ねる」の意味でここでは「重なっている」様子を示しています月影の「月影」は「月の光」や「月の影」の意味で「月影の」は「月の光の」となりますさゆる真袖に「さゆる」は「冷える」「寒くなる」の意味で「真袖」は「本当の袖」「純粋な袖」の意味です「さゆる真袖に」は「冷える純粋な袖に」の意味ですかゝる白露「かゝる」は「かかる」「乗る」「付く」の意味で「白露」は「白い露」のことです「かゝる白露」は「付いている白い露」の意味ですこの歌は白く美しい衣服に月の光が重なりその冷たい袖に白い露が付いている情景を詠んでいます西行は月の光が衣服に映り込みさらにその上に露が宿るという自然の美しさとその一時的な美を詩的に表現していますここには月の光と露という自然の要素が人間の衣服に重なることで生まれる美しさとその冷たさや儚さが描かれています白妙の衣や真袖という言葉は純粋さや清らかさを象徴し自然と人間の調和を表しているとも言えますこの歌からは自然の美しさが人間の感覚や感情にどのように影響を与えその一過性の中にある詩的な美意識が感じられますPerplexityさんによる解説この和歌は冬の月光と白露を美しく描写した歌です以下にその意味と解釈を示します歌の意味「白妙の衣を幾重にも重ねて着ているかのような月の光が、冷え冷えとした袖に白露となって宿っている」解釈この歌は冬の夜の情景を繊細に表現しています白妙の衣「白妙」は真っ白で美しいさまを表す言葉です月光を白い衣に喩えています重ぬる月影月の光が幾重にも重なっているように見える様子を表現していますこれは月光の強さと美しさを強調していますさゆる真袖「さゆる」は寒さで冷え冷えとしている状態を表します「真袖」は袖の内側を指し寒さを直接感じる部分ですかかる白露冷えた袖に宿る露を表現していますここでは月光が白露のように見えることを巧みに詠んでいますこの歌は冬の夜の冷たさと月光の美しさを対比させながら視覚的にも触覚的にも豊かな情景を描き出しています月光の白さと冷たさそして露の儚さが見事に表現されており和歌の伝統的な美意識が感じられる作品ですFeloさんによる解説西行の歌「白妙の衣重ぬる月影のさゆる真袖にかゝる白露」は彼の詩的な感受性と自然との深い結びつきを表現した作品ですこの歌は月の光が白い衣に映りその上に白露がかかる様子を描写しています歌の解釈情景描写歌の中で西行は月の光が白い衣に重なりその衣にかかる白露を描写しています「白妙の衣」は清らかさや美しさを象徴し月影はその美しさを引き立てる役割を果たしていますこのように自然の美しさと人間の感情が交錯する情景が浮かび上がります感情の表現この歌は月の光と白露を通じて孤独感や切なさを表現しています月はしばしば人の心情を映し出す存在として描かれ白露はその儚さを象徴しています西行は自然の美しさを通じて自らの内面的な感情を表現しているのです無常のテーマ西行の歌には無常観がしばしば表れますこの歌もその一例で白露が衣にかかる様子は時間の流れや儚さを暗示しています彼の作品は自然の美しさと同時にその背後にある悲しみや孤独を感じさせるものです西行全歌集 (岩波文庫 黄23-2) [ 西行 ]価格:1,507円(税込、送料無料) (2025/2/22時点)楽天で購入
2025.02.22
コメント(0)
-

訪へな君夕暮になる庭の雪を跡なきよりはあはれならまし 西行
雪歌よみけるにGeminiさんによる解説この歌は、西行の『山家集』に収められています。この歌は夕暮れ時に雪が降る庭を訪れてほしい足跡のない雪よりもあなたの足跡がある方がより一層趣深いだろうという心情を詠んでいます現代語訳と解説は以下のとおりです現代語訳あなたは私を訪ねてきてください夕暮れ時になる庭の雪を足跡のない状態よりもあなたの足跡がある方がより一層趣深いでしょうから解説この歌は恋しい人に会いたいという気持ちを雪景色に託して表現しています「訪へな君」は「あなたは私を訪ねてきてください」という意味で恋しい人に直接語りかけるような表現です「夕暮になる庭の雪」は夕暮れ時に雪が降る庭の情景を表しています夕暮れ時の雪景色は、寂しさや哀愁を感じさせます「跡なきよりはあはれならまし」は「足跡のない状態よりも、あなたの足跡がある方が、より一層趣深いでしょう」という意味です雪の上に足跡が残ることでそこに人の気配が感じられより一層趣深い情景になるという作者の思いが込められていますこの歌から読み取れるのは恋しい人に会いたいという切実な願いと雪景色に託した繊細な感情ですChatGPTさんによる解説現代語訳訪ねてくれるな君よ夕暮れになれば庭に積もった雪も足跡が消えてしまうそれならば最初から足跡のないままのほうがかえって切なくしみじみとした思いになるだろうに解説1. 「訪へな君」「訪へな」「訪ねてくれるな」「君」「あなた」(親しい間柄の人への呼びかけ)→ 誰かに「来ないでほしい」と言っている ただし拒絶というよりも心の揺れがにじむ表現2. 「夕暮になる庭の雪を」「夕暮になる」時間が経つにつれて「庭の雪を」庭に積もった雪。→ 夕暮れの静かな雪景色が描かれている 訪ねてきた人の足跡が雪の上に残る状況を暗示 する3. 「跡なきよりはあはれならまし」「跡なきよりは」足跡が残らないよりも「あはれならまし」しみじみとした思いが深まるだろう→ 「足跡が消えてしまうなら、最初からないほうがよかったのに」と感じている 訪れた痕跡が残らないことに切なさを覚える心情 が表れている歌の趣と解釈1. 訪れを待つ心の矛盾「訪ねてくれるな」と言いながら本当は訪れを待つ心情 がにじむもし来てくれたならその足跡が消えてしまうことが切なさを生む「ならば、最初から来ないほうがよかった」 という逆説的な思い2. 雪と足跡の儚さ雪は「積もる」ことで足跡を残しまた「降る」ことで消してしまう人の訪れも来たときは温もりを感じさせるが去った後には寂しさが残る消えゆくものの象徴としての雪 を用いた繊細な表現3. 「あはれ」の感覚「あはれ」 は単なる寂しさではなく「しみじみとした風情」「物の哀れを感じる心」ただ「寂しい」ではなく美しくも儚い感情の揺らぎを表現 しているまとめこの歌は訪れを待つ人の切なさを雪の情景に託した一首夕暮れに雪が積もる庭の風景訪れてくれた人の足跡が雪に刻まれるがやがて消えてしまうそれならば初めから足跡のないほうがかえって心に残るのではないか「人の訪れ」と「雪の足跡」の儚さを重ねることで失われるものの美しさを詠んでいる西行らしい繊細な情感 が漂う一首Claudeさんによる解説この和歌は雪の庭に人の訪れを願う西行の繊細な心情を詠んだ歌です「訪へな君」「訪ふ」は訪れるという意味です「な」は願望や依頼を表す助詞です誰かに訪れてほしいという切実な思いが表現されています「夕暮になる」夕方に移りゆく時間帯を示しています寂寥感が深まる時間であることを暗示しています「庭の雪を」庭に積もった雪を指します純白で何も印されていない雪の状態を表現しています「跡なきよりは」誰の足跡もないよりはという意味です人の気配が全くない状態への物悲しさが込められています「あはれならまし」「あはれ」は情趣や感動を表す言葉です「まし」は願望を表す助動詞です人の足跡があった方が趣深いだろうという思いを表現していますこの歌の魅力は純白の雪に足跡が付くことを通じて人との交わりを願う心情を繊細に表現している点にあります誰の訪れもない完璧な雪景色よりも人の足跡がある方が「あはれ」(趣深い)という逆説的な表現が印象的ですまた「夕暮」という時間設定も効果的で暮れゆく夕方の寂しさと誰もが訪れない雪の庭という空間が重なり深い情感を生み出しています西行らしい孤独と人恋しさが見事に表現された秀歌といえるでしょうGrokさんによる解説この歌も西行の作品で訪れない人への思いと雪の情景を詠んでいます以下に詳しく解説します訪へな君「訪へな」は「訪ねない」の意味で「君」は「あなた」を指します「訪へな君」は「訪ねてこないあなた」の意味です夕暮になる「夕暮」は「夕方」や「日が暮れる時」の意味で「になる」は「~になる」の意味です「夕暮になる」は「夕暮れになる」のことです庭の雪を「庭の雪」は「庭に積もった雪」の意味です跡なきよりは「跡なき」は「足跡がない」の意味で「よりは」は「~よりも」の意味です「跡なきよりは」は「足跡がないことよりも」の意味ですあはれならまし「あはれ」は「美しい」「哀れ」の意味で「ならまし」は「であったら」「であるだろう」の意味です「あはれならまし」は「美しいものであっただろう」の意味ですこの歌は訪ねてこないあなたを待つ間に夕暮れになり庭の雪にあなたの足跡がないよりも訪ねてきてくれればその情景がもっと美しいものであっただろうという思いを詠んでいます西行は雪の静寂と美しさに重ねて人との出会いや訪れへの期待を詩的に表現していますここには雪の美しさとその静けさが訪れを待つ心の孤独感や切なさと対比されつつもそれが訪れがあればさらに美しくなるという希望が描かれています自然の風景と人間の感情が密接に結びついていることが感じられますこの歌からは期待と失望の間で揺れる心と自然の美しさがその感情をどう増幅するかそしてその中での切ない美意識が伝わってきますPerplexityさんによる解説この歌は雪が積もった庭の情景を詠んだ西行の和歌です以下にその意味と解釈を示します歌の意味「どうか訪ねてきてください。夕暮れ時の庭に積もった雪を、誰の足跡もないままよりは、あなたの足跡がついている方が情趣があるでしょう。」解釈この歌には西行の繊細な感性と孤独感が表現されています情景描写夕暮れ時の雪景色を背景に静寂と孤独感を醸し出しています人の訪れへの願い「訪へな君」という呼びかけは誰かの来訪を切望する気持ちを表しています足跡の意味雪原に残る足跡は人の存在の痕跡であり孤独な風景に人の温もりを加える象徴となっています「あはれ」の感覚西行が好んで用いた「あはれ」という言葉はこの歌では人の気配がする風景の方が情趣深いという思いを表現しています西行は自然の美しさと人間の感情を巧みに結びつけ孤独でありながらも人との繋がりを求める心情を表現していますこの歌は西行の代表的な特徴である自然への深い洞察と人間の感情の機微を捉えた作品といえるでしょうFeloさんによる解説西行の歌「訪へな君夕暮になる庭の雪を跡なきよりはあはれならまし」は彼の感情や孤独感を表現した非常に印象的な和歌ですこの歌は夕暮れ時に訪れない君を思い庭に積もった雪が跡形もなく消えてしまうことを惜しむ内容になっています歌の解釈情景描写歌の中で西行は夕暮れの静けさと庭に積もった雪を描写しています雪は通常訪れた人の足跡を残すものですがここでは「跡なき」と表現されており君が訪れないことでその跡が残らないことを悲しんでいます感情の表現「あはれならまし」という言葉は感情の深さを示しています君が訪れてくれたなら雪の跡が残ることで何らかの形でその存在を感じることができたかもしれないという切ない思いが込められていますこのように雪の消失は孤独感や無常を象徴しており訪れない君への思いが強調されています無常のテーマ西行の歌には無常観がしばしば表れますこの歌もその一例で雪が消えてしまう様子は人生の儚さや人との関係の儚さを暗示しています彼の歌は自然の美しさと同時にその背後にある悲しみや孤独を感じさせるものです西行全歌集 (岩波文庫 黄23-2) [ 西行 ]価格:1,507円(税込、送料無料) (2025/2/22時点)楽天で購入
2025.02.22
コメント(0)
-

ねずさんの日本の心で読み解く百人一首 五十四番歌 小名木善行 彩雲出版
忘れじのゆく末まではかたかれば今日を限りの命ともがな儀同三司母可憐な愛と純粋な子供たち【POD】ねずさんの 日本の心で読み解く「百人一首」 [ 小名木善行 ]価格:3,806円(税込、送料無料) (2025/2/21時点)楽天で購入
2025.02.21
コメント(0)
-

嗤う伊右衛門 京極夏彦 中公文庫
誰がどのような思惑で語れども、言葉というものはそもそも半分は嘘なのだ。語り手が幾ら真実を語ったつもりでいても、語りは真実そのものではない。逆に出鱈目な言葉を並べても、半分は本当になる。一から十まで拵えるのは至難の業だし、普く逆様に述べたとて、底が知れれば却って道理が汲めるからだ。一方で、もしも騙し通して貰えたならば、嘘は丸ごと実となる。嗤う伊右衛門 (中公文庫) [ 京極夏彦 ]価格:607円(税込、送料無料) (2025/2/19時点)楽天で購入
2025.02.19
コメント(0)
-

自然に還る 再々々々 福岡正信 春秋社
日本の百姓は、どんな食物を作り、摂るかという姿勢でなく、四季春秋、自然に畑に出来た旬の作物をその秋、その時摂っていただけです。そして、自然の理に従って料理したのです。人がまずあって、人知で食物を作るのでなく、自然の食がまずあって、人が無為自然に生きる。それが、日本の本来の生き方であり、食事の作法(神事)だったのです。福岡正信の自然に還る (福岡正信の本) [ 福岡 正信 ]価格:3,960円(税込、送料無料) (2025/2/19時点)楽天で購入
2025.02.19
コメント(0)
-

自然に還る 再々々 福岡正信 春秋社
日本の国では多種多様の食物がありました。私の村のその周辺から採れる穀物、野菜、果物、山菜を加えると、四季別に集めてみると全く食のマンダラ図ができます。毎月新しい三十種類もの食べ物が発生しているのです。ということは、家の周りを走り回れば、毎日一つは旬の初ものが食べられるということです。昔の百姓は貧しく、麦飯、香物、梅干だったように言われますが、実態は御馳走を食べていたともいえるのです。スーパー・マーケットの季節はずれの七色の食品をいくら集めても、本物の御馳走はできません。福岡正信の自然に還る (福岡正信の本) [ 福岡 正信 ]価格:3,960円(税込、送料無料) (2025/2/19時点)楽天で購入
2025.02.19
コメント(0)
-

その折のよもぎがもとの枕にもかくこそ虫の音にはむつれめ 西行
物心ぼそくあはれなりける折しもきりぎりすの声の枕に近く聞えければGeminiさんによる解説西行の『山家集』に収められていますこの歌は心細く寂しい気持ちでいた時に枕元でコオロギの声が聞こえたのを聞いて昔住んでいたよもぎが茂る家のことを思い出したという内容です現代語訳と解説は以下のとおりです現代語訳心細く寂しい気持ちでいた時にちょうどコオロギの声が枕元近くで聞こえたのでその時(昔)のよもぎが茂っていた家の枕元でもこのように虫の音に心惹かれたのだろうかと思い出されることだ解説この歌はコオロギの鳴き声を聞いたことで過去の記憶が呼び起こされた様子を詠んでいます「物心ぼそくあはれなりける折しも」は「心細く寂しい気持ちでいた時に、ちょうど」という意味です「きりぎりすの声」はコオロギの鳴き声を指しています「枕に近く聞えければ」は「枕元近くで聞こえたので」という意味です「その折のよもぎがもとの枕にも」は「その時(昔)の、よもぎが茂っていた家の枕元でも」という意味です「かくこそ虫の音にはむつれめ」は「このように虫の音に心惹かれたのだろうか」という意味です「むつれ」は「親しむ、心を惹かれる」という意味ですこの歌から読み取れるのはコオロギの鳴き声を聞いたことで過去の寂しかった頃の記憶が呼び起こされたという心情です同時に昔の家で聞いた虫の音も思い出し懐かしさを感じている様子が伝わってきますChatGPTさんによる解説現代語訳物寂しく心細い思いに沈んでいた折にちょうど枕元近くでキリギリスの声が聞こえたそのときふとあの蓬の下での枕もこうして虫の音と共にあったのだろう と思い出された解説1. 「物心ぼそくあはれなりける折しも」「物心ぼそく」物寂しく心細く「あはれなりける」 しみじみとした感慨にふける「折しも」ちょうどその時→ 寂しさや心細さに包まれた瞬間 であることが分かる2. 「きりぎりすの声の枕に近く聞えければ」「きりぎりす」キリギリス(またはコオロギ)「声の枕に近く聞えければ」その鳴き声が枕元近くで聞こえたので→ 秋の夜に響く虫の音が寂しさをより深める ような情景 孤独感と共にどこか風情のある雰囲気もある3. 「その折のよもぎがもとの枕にも」「その折の」かつてのあの時「よもぎがもと」蓬(よもぎ)の下粗末な草の寝床「枕にも」(そこでの)枕にも→ 過去のある出来事を回想している ことが分かる 「よもぎがもと」という表現から僧としての野宿や旅の寂しさが想起される4. 「かくこそ虫の音にはむつれめ」「かくこそ」まさにこのように「虫の音にはむつれめ」虫の音と親しんでいたことだろう→ 過去の記憶と現在の情景が重なり合い虫の音に寄り添うような心境 が表現されている歌の趣と解釈1. 虫の声と寂寥感枕元で鳴く虫の音が寂しさをより深める孤独な心情 とそれを和らげるような自然の情景 の対比が美しい2. 過去と現在の重なりかつての「よもぎの下」での寝床と今の状況が重なり「昔も今も変わらず、虫の音と共にある」 ことを感じる時間を超えた静かな共鳴 がある3. 西行らしい風流な感性孤独を詠いながらも虫の声に寄り添うような温かみ がある「寂しい」とだけ嘆くのではなくその寂しさを風情として受け止める のが西行の特徴まとめこの歌は寂しさと回想が織り交ざった叙情的な一首心細さに包まれた夜枕元で虫の音が響く過去の旅の記憶がよみがえりあのときも虫の音と共にあったのだろうと感じる「変わらぬもの」としての自然の存在 を感じながら静かに心を寄せる西行らしい寂しさの中にある穏やかな受容の心 が伝わる一首Claudeさんによる解説この和歌は寂しい心境の中で聞こえたきりぎりすの声から過去の思い出を詠んだ歌ですまず題詞「物心ぼそくあはれなりける折しも、きりぎりすの声の枕に近く聞えければ」から心細く感傷的な気持ちでいた時に枕元でキリギリスの声が聞こえてきたという情景が分かります「その折の」かつてのあの時のという意味です過去のある特定の時点を回想しています「よもぎがもとの」「よもぎ」は野草の蓬(よもぎ)を指します質素な寝床を象徴的に表現しています「枕にも」過去の枕と現在の枕を重ね合わせる表現です「かくこそ虫の音にはむつれめ」「むつれめ」は親しむ寄り添うという意味です虫の声に心を慰められるという心情を表現していますこの歌の特徴は現在の寂しい心境と過去の思い出を虫の声を通じて重ね合わせている点です質素な寝床で聞く虫の声は変わらないもののその時々の心情によって異なる感慨を呼び起こすという繊細な心理描写が印象的ですまた「よもぎがもと」という表現からは西行の質素な生活と出家者としての在り方も感じられますGrokさんによる解説この歌も西行の作品で自然の音と心の静けさを詠んでいます以下に詳しく解説します物心ぼそく「物心」は「心」や「感覚」の意味で「ぼそく」は「細かく」「微細に」の意味です「物心ぼそく」は「心細く」「感覚が微細に」の意味ですあはれなりける「あはれ」は「美しい」「哀れな」などの意味で「なりける」は過去の感想を表します「あはれなりける」は「美しく感じられた」の意味です折しも「折しも」は「その時」「その頃」の意味ですきりぎりすの声の「きりぎりす」は「キリギリス」のことで「声」は「音」「鳴き声」の意味です「きりぎりすの声」は「キリギリスの鳴き声」のことです枕に近く聞えければ「枕に」は「枕の近くに」「近く」は「近くで」「聞えければ」は「聞こえるならば」の意味です「枕に近く聞えければ」は「枕の近くで聞こえるならば」の意味ですその折のよもぎがもとの枕にも「その折の」は「その時の」「よもぎ」は「ヨモギ」のことで「もとの枕に」は「元の枕に」「も」は「も」の意味です「その折のよもぎがもとの枕にも」は「その時のヨモギが元の枕にも」の意味ですかくこそ「かく」は「このように」「こうして」「こそ」は強調の助詞です「かくこそ」は「このようにしてこそ」の意味です虫の音にはむつれめ「虫の音」は「虫の鳴き声」「には」は「に対して」「むつれめ」は「むつれるだろう」「悩むだろう」の意味です「虫の音にはむつれめ」は「虫の声に対して悩むだろう」の意味ですこの歌は心細く美しいと感じていた時にキリギリスの声が枕元で聞こえてきた情景を詠んでいますそしてその時のヨモギの枕でも同じように虫の声に心が悩まされるだろうという思いを表現していますここには自然の静けさとその中で聞こえる虫の声が心の微細な動きや感覚を引き立たせるという詩的な情景が描かれています虫の声が心地よい一方で心細さを増すこともあるという自然と人間の心の関係性が示されていますこの歌からは自然の美しさやその音が人間の感情や静寂の深さをどのように反映するかそしてその中での孤独感や美しさへの共感が感じられます西行全歌集 (岩波文庫 黄23-2) [ 西行 ]価格:1,507円(税込、送料無料) (2025/2/19時点)楽天で購入
2025.02.19
コメント(0)
-

君にいかで月にあらそふ程ばかりめぐり逢ひつゝ影を並べん 西行
月Geminiさんによる解説この歌は西行の『山家集』に収められていますこの歌はあなた(恋しい人)と月が美しい光を競い合うほどに何度も巡り会って影を並べたいという切ない願いを詠んでいます現代語訳と解説は以下のとおりです現代語訳あなたと月がその美しさを競い合うほどに何度も巡り会って寄り添い影を並べたいものだ解説この歌は恋しい人に会いたいという切実な願いを美しい月と重ね合わせて表現しています「君にいかで」は「あなたとどうして」という意味で会うことが難しい状況を表しています「月にあらそふ程ばかり」は「月がその美しさを競い合うほどに」という意味で月が非常に美しいことを強調しています「めぐり逢ひつゝ」は「何度も巡り会って」という意味で恋しい人に何度も会いたいという願いを表しています「影を並べん」は「(あなたと)寄り添い、影を並べたい」という意味で恋しい人と一緒にいたいという切実な願いを表していますこの歌から読み取れるのは恋しい人に会いたいという切実な願いとそれが叶わないもどかしさです美しい月を見れば見るほど恋しい人への思いが募り会いたい気持ちが強くなるしかし現実にはなかなか会うことができないそのもどかしさがこの歌には込められていますChatGPTさんによる解説現代語訳どうにかしてあなたと月と争うほどの長い時を巡り逢いながら影を並べて歩みたいものです解説1. 「君にいかで」「君」親しい人愛しい人を指す「いかで」「どうにかして」「なんとかして」→ 「どうにかしてあなたと」 という願望の表現2. 「月にあらそふ程ばかり」「月にあらそう」月と競い合うほど「程ばかり」それほどの長さ(=長い時間)→ ここでの「月」は 「長く輝き続けるもの」 の象徴つまり「月のように長く続く時間」 を表している「月に争うほど」というのは「月と競うくらい長くあなたと共にありたい」 という願い3. 「めぐり逢ひつゝ影を並べん」「めぐり逢ひつゝ」 繰り返し巡り逢いながら「影を並べん」影を並べる=一緒に歩むこと→ 「影を並べる」は「共に過ごし、一緒に歩む」 ことの比喩つまり何度も巡り逢いながら共に歩む人生を願う という意味この歌の魅力時間の永続性を願う「月と競うほど長く」 という表現がロマンチック「巡り逢い」 という言葉に一度ではなく何度も再会したい という想いが込められている「影を並べる」という優雅な表現影人の存在の象徴「あなたと共に歩む未来を願う」 という情感が美しい仏教的な輪廻観ともつながる可能性西行の歌には 「生まれ変わってもまた会いたい」 という願いを込めたものもある「巡り逢い」 という言葉にはただの再会ではなく何度生まれ変わっても共にありたい という深い意味も感じられるまとめこの歌は「あなたと長い時を共にし、巡り逢いながら影を並べて歩みたい」 という願いを詠んだもの恋の歌 としても読めるし親しい人との絆の歌 としても解釈できるまた単なる一生の時間ではなく「輪廻を超えて、何度でも共にありたい」 という深い思いが込められている点が西行らしい繊細な感性を感じさせるClaudeさんによる解説この和歌は西行の恋情と月への思いが見事に融合した歌です「君にいかで」「いかで」は「どうにかして」という願望を表す言葉です「君」は慕う相手を指しています「月にあらそふ程ばかり」「月と競えるほどの」という意味です月の美しさと比べられるような出会いを願う表現です「あらそふ」は競う、匹敵するという意味です「めぐり逢ひつゝ」めぐり会う偶然の出会いを重ねるという意味です「つつ」は継続や繰り返しを表す助詞です「影を並べん」共に寄り添って歩きたいという願いを表現しています「影を並べる」は親しく寄り添う様子を表す優美な表現ですこの歌は人への思いと月への憧れを巧みに結びつけています月のように清らかで美しい逢瀬を願う心情が繊細に表現されていますまた「めぐり逢ひ」という言葉には仏教的な因縁や運命の巡り合わせというニュアンスも感じられ西行の僧侶としての側面も垣間見えます人への思いを月に重ね合わせる表現は直接的な恋の表現を避けながらも深い情感を伝える西行らしい技法といえるでしょうGrokさんによる解説この歌も西行の作品で恋心と月の美しさを詠んでいます以下に詳しく解説します君に「君」は「あなた」の意味で「に」は相手を示す助詞です「君に」は「あなたと共に」の意味ですいかで「いかで」は「いかにして」「どうやって」の意味で問いかけや驚嘆を表します月にあらそふ程ばかり「月に」は「月に対して」「あらそふ」は「競う」「比べる」の意味で「程ばかり」は「ほど」「くらい」の意味です「月にあらそふ程ばかり」は「月と比べるほどに」の意味ですめぐり逢ひつゝ「めぐり逢ひ」は「めぐり合う」の意味で「つゝ」は「つつ」「しながら」の意味です「めぐり逢ひつゝ」は「めぐり合いながら」の意味です影を並べん「影」は「影」の意味で「並べん」は「並べる」の意志形で「影を並べん」は「影を並べよう」という意味ですこの歌はどうやってあなたと一緒に月と競うほどに美しい時間を過ごしその影を並べることができるかと詠んでいます西行は恋愛感情を自然の美しさ(特に月)に引き寄せその中で自分と恋人との時間を比喩的に表現していますここには自然の美しさと人間関係の深い結びつきそしてその中に見出す愛や美の追求が詩的に表現されています月と競うほどに美しい時間を過ごすことは恋愛の高揚感や純粋さを象徴していますこの歌からは恋愛の喜びや美しさを自然と一体化させて感じる西行の感性そしてその感情を詩的な言葉で表現する能力が伝わってきます西行全歌集 (岩波文庫 黄23-2) [ 西行 ]価格:1,507円(税込、送料無料) (2025/2/19時点)楽天で購入
2025.02.19
コメント(0)
-

折ならぬめぐりの垣の卯の花をうれしく雪の咲かせつるかな 西行
雪歌よみけるにGeminiさんによる解説この歌は西行の『山家集』に収められていますこの歌は雪が降って卯の花(ウツギの花)が咲いたように見える風景を素直に美しいと感じた心情を詠んでいます現代語訳と解説は以下のとおりです現代語訳曲がりくねった垣根の卯の花が(雪によって)咲いたように見えるのがとても嬉しいことだ解説この歌は雪が降って白い雪が垣根に積もっている様子を卯の花が咲いたように見立てています「折ならぬめぐりの垣」はまっすぐではない曲がりくねった垣根を意味します「卯の花」は初夏に白い花を咲かせるウツギの花のことです雪の白さと卯の花の白さを重ね合わせることで雪景色の清らかさ美しさを強調しています「うれしく雪の咲かせつるかな」は雪が降ってまるで卯の花が咲いたように見えるのがとても嬉しいという素直な感情を表していますこの歌から読み取れるのは雪景色の美しさそしてそれを花に見立てることで自然の造形美に対する素直な感動ですChatGPTさんによる解説現代語訳思いがけず巡り合った垣根の卯の花よまるで雪が咲かせたかのように美しい解説1. 「折ならぬめぐりの垣の卯の花を」「折ならぬ」時節に合わない思いがけない「めぐりの垣」巡り合った垣根(偶然に出会った場所)「卯の花」ウツギの花(初夏に白く咲く)→ 「思いがけず巡り合った垣根に咲く卯の花」 という意味「めぐりの垣」とは単に垣根のことだけでなく「巡り合わせ」という縁のニュアンスも含んでいる2. 「うれしく雪の咲かせつるかな」「うれしく」喜ばしく、美しく「雪の咲かせつるかな」まるで雪が咲かせたようだ→ 「まるで雪が咲かせたかのように、白く美しく咲いている」 という表現卯の花の白さを雪に例えている歌の背景と解釈1. 季節のズレ(「折ならぬ」)「卯の花」は通常 旧暦の4〜5月頃(現在の5〜6月) に咲くしかし「雪」との対比があることから「季節外れの卯の花」 を見ている可能性があるつまり 「冬なのに卯の花が咲いている」 という驚きの情景とも読める2. 「雪」と「卯の花」の取り合わせ「卯の花」は「夏の雪」とも呼ばれ白い小花が雪に似ている「雪が咲かせた」 という擬人化によって花と雪の美しさを一体化 させる発想が見られる3. 巡り合わせの喜び「めぐりの垣」とは単なる垣根ではなく「思いがけない出会い」 という意味が含まれているそれを「うれしく」と詠んでいることから偶然の美しい出会いを喜ぶ心情 がうかがえるこの歌の魅力「雪と花の融合」卯の花の白さを「雪」と重ねる 発想が美しい「雪が花を咲かせる」という 幻想的な表現 が魅力的偶然の喜びを詠むふとした巡り合わせで見つけた美しい花「思いがけない幸運」 を感じさせる歌でもある視覚的な美しさ白い花と雪が混ざる光景が目に浮かぶシンプルながら、風景の清らかさと感動が凝縮されているまとめこの歌は季節外れに咲く卯の花を雪が咲かせたかのように感じた驚きと喜び を詠んだもの偶然の美しい出会いを愛でる心と花と雪の対比が織りなす幻想的な世界観が西行らしい繊細な感性を表している名歌 といえるClaudeさんによる解説この和歌は西行が卯の花と雪を重ね合わせた趣向の和歌です「折ならぬ」季節外れの時期ではないという意味ですここでは冬の季節に卯の花が咲いているかのような錯覚を詠んでいます「めぐりの垣の」家の周りを囲む垣根のことを指します「めぐり」は周囲を巡るという意味です「卯の花を」卯の花は初夏に咲く白い花ですここでは実際の卯の花ではなく雪の比喩として用いられています「うれしく雪の咲かせつるかな」雪が積もった様子をまるで花が咲いたかのように表現しています「咲かせつる」という表現で雪を花に見立てる巧みな技法が使われています「かな」は詠嘆の意を表す助詞ですこの歌の特徴は季節外れの時期に雪が卯の花のように見えるという見立ての妙にあります冬の厳しい雪景色を春の温かな卯の花に見立てることで意外な美しさを見出しています「うれしく」という言葉からはこの意外な景色に対する西行の素直な感動が伝わってきます厳しい冬の景色の中に温かな春の花のイメージを重ね合わせる西行らしい繊細な感性が光る歌といえるでしょうGrokさんによる解説この歌も西行の作品で自然の美しさとその一時性を詠んでいます以下に詳しく解説します折ならぬめぐりの垣の「折ならぬ」は「折れない」「壊れない」の意味で「めぐり」は「めぐらす」「囲む」の意味です「めぐりの垣」は「囲いの垣」や「塀」のことです「折ならぬめぐりの垣」は「壊れない囲いの垣」の意味です卯の花を「卯の花」は「デイゴの花」や「アンズの花」といった春に咲く花のことを指しますうれしく「うれしく」は「嬉しく」「喜ばしく」の意味でここでは「喜ばしいことに」「嬉しいことに」の意味です雪の咲かせつる「雪の咲かせつる」は「雪が咲かせた」の意味で「つる」は過去の表現です「雪が咲かせた」は「雪が花のように見せた」という意味ですかな「かな」は感嘆や感想を表す終助詞でここでは「なんて」「さては」と感嘆の意味を持ちますこの歌は壊れない塀の上に卯の花のように雪が咲いていることを喜んで詠んでいます西行は雪が降ることでまるで春の花が咲いているかのような美しさが生まれることを詩的に表現していますここには自然の美しさとその季節を超えた一時的な風景の魅力が描かれています冬の雪が春の花の美しさを再現することで季節の移ろいや自然の無常観に対する感動が込められていますこの歌からは自然の変化がどのように人間の心を動かし季節を超えても美しさを見つけ出すことができるかという西行の詩的な視点が感じられます西行全歌集 (岩波文庫 黄23-2) [ 西行 ]価格:1,507円(税込、送料無料) (2025/2/19時点)楽天で購入
2025.02.19
コメント(0)
-

数学ガール 乱択アルゴリズム 再 結城浩 SoftBank Creative
「武器を磨こう」「宝の持ちぐされにならないように、持っている剣を磨く。 持っているだけではさびついていく。 なにしろー記憶するだけでは、いけないのだから」数学ガール(乱択アルゴリズム) [ 結城浩 ]価格:2,090円(税込、送料無料) (2025/2/18時点)楽天で購入
2025.02.18
コメント(0)
-

7つの習慣 再 スティーブン・R・コヴィー ジェームス・J・スキナー 川西茂 キングベアー出版
農場で場当たり的な詰め込み主義で作業することの愚かさを考えたことがあるだろうか農場は自然のシステムである。必要な務めを果たし、作業を行わなければならない。蒔いたものしか刈り取ることはできない。そこに近道はない。人の成長や人間関係においても、最終的にはこの原則が必ず作用することになる。つまり、人の成長も人間関係も自然のシステムであり、農場の法則が支配しているのである。完訳7つの習慣 30周年記念版 [ スティーブ・R.コヴィー ]価格:2,420円(税込、送料無料) (2025/2/18時点)楽天で購入
2025.02.18
コメント(0)
-

ねずさんの日本の心で読み解く百人一首 五十三番歌 小名木善行 彩雲出版
嘆きつつひとり寝る夜の明くる間はいかに久しきものとかは知る右大将道綱母母として人としての美しさ【POD】ねずさんの 日本の心で読み解く「百人一首」 [ 小名木善行 ]価格:3,806円(税込、送料無料) (2025/2/18時点)楽天で購入
2025.02.18
コメント(0)
-

自然に還る 再々 福岡正信 春秋社
自然食が叫ばれ、有機農法ができてきて、多少でも科学農法のブレーキを果たすと安易に思っていたところに、問題があると思うんです。そういうことを盛んに言えば言うほど、みんな平気で壊してしまうのが現在なんです。福岡正信の自然に還る (福岡正信の本) [ 福岡 正信 ]価格:3,960円(税込、送料無料) (2025/2/14時点)楽天で購入
2025.02.14
コメント(0)
-

自然に還る 再 福岡正信 春秋社
「あんた、怪我をしたら医者がいませんよ。 この島には、医者がいないのですよ」と言ったら、体に気をつけるでしょう。「この島には外科もおります。 内科の医者もおります。 安心しなさい」と言われたら、人間は、やっぱり体に気をつけない。福岡正信の自然に還る (福岡正信の本) [ 福岡 正信 ]価格:3,960円(税込、送料無料) (2025/2/14時点)楽天で購入
2025.02.14
コメント(0)
-

自然に還る 福岡正信 春秋社
期待された有機農法というのも、科学農法と、右手と左手ぐらいの違いしかなく、今のままでは昔の有蓄農法、堆肥農法に帰るだけだから、かつて来た道にすぎず、これでは真の自然を回復することに役立たないばかりではなくて、自然破壊に肩をかすことになってしまいます。もちろん有機農法は、ブレーキ役は務めているけれど、ブレーキと破壊する車輪とが一緒になって走り回るから、結果的には科学農法の一翼を荷うことになり、ブレーキがブレーキにならず、なお危険だということです。福岡正信の自然に還る (福岡正信の本) [ 福岡 正信 ]価格:3,960円(税込、送料無料) (2025/2/14時点)楽天で購入
2025.02.14
コメント(0)
-

いかでわれ今宵の月を身に添へて死出の山路の人を照さん 西行
七月十五夜月明かりけるに舟岡にまかりてGeminiさんによる解説この歌は西行が七月十五夜の満月の夜に舟岡という場所で詠んだとされています現代語訳と解説は以下のとおりです現代語訳七月十五夜月が明るく照っている時に舟岡に行って(この月を見て思った)どうして私は今宵の月を身に添えて死出の山路を行く人々の道しるべとすることができないのだろうか解説この歌は美しい満月を見ながら死後の世界へ旅立つ人々のことを思いせめて自分の魂だけでも彼らの道しるべとなって照らしてあげたいという西行の優しい心情を表しています「舟岡」は京都の北にある葬送の地として知られていました西行はそこで美しい月を見ながら亡くなった人々への供養の気持ちを抱いたのでしょう「死出の山路」は死後に行くと言われている道のことです「今宵の月を身に添へて」という表現は月を自分の魂に見立てていることを示唆していますChatGPTさんによる解説現代語訳どうにかしてこの今宵の美しい月を身にまといあの世へ旅立つ人の道を照らしてあげられたら——解説1. 「いかでわれ今宵の月を身に添へて」「いかで」何とかしてどうにかして「われ」私「今宵の月」七月十五夜の明るい月「身に添へて」自分の身と一緒にする→ 「どうにかして、今宵の月を自分の身にまとえたら」 という願いを表している2. 「死出の山路の人を照さん」「死出の山路」死後の世界へと向かう道(黄泉路)「人を照さん」旅立つ人の道を照らしたい→ 「あの世へ向かう人の道を、この月の光で照らしてあげたい」 という思い歌の背景と解釈1. 七月十五夜の月七月十五夜は「旧暦の盂蘭盆(お盆)」にあたる日亡き人の魂を供養する夜 であり月の光は霊を導く象徴にもなる2. 亡き人への思い西行はしばしば 「亡き人の行方」 を歌にしているこの歌も 死者を想う気持ち が込められている「死後の旅路に少しでも光を」 という願いは仏教的な供養の心とも通じる3. 「月と共にありたい」という願望ただ「死者を照らしたい」というだけでなく「自分も月と一体になりたい」 という願いが見えるこれは西行がしばしば持つ 「自然との一体化」 という思想と重なるこの歌の魅力1. 「月を身にまとう」という幻想的な発想普通月は「見るもの」だが「月を身に添えて」 という表現が幻想的で美しい光そのものになって死者を導く という発想が独特2. 生と死をつなぐ月の存在生者(西行)と死者をつなぐのが月 という視点「月に寄せる祈り」 がより深い余韻を生む3. 余白の美「死出の山路の人」が 具体的に誰なのか言及していない読み手がそれぞれの「亡き人」を思い浮かべられる余白があるそのため個人的な供養の歌でありながら普遍的な死者への祈り になっているまとめこの歌はお盆の夜に月を眺め亡き人を偲ぶ という切ない祈りの歌「月を身に添えて、死出の旅路を照らしたい」という幻想的な表現が西行らしい仏教的な死生観と自然への憧れ をよく表している儚くも美しい供養の心が込められた名歌西行全歌集 (岩波文庫 黄23-2) [ 西行 ]価格:1,507円(税込、送料無料) (2025/2/13時点)楽天で購入
2025.02.14
コメント(0)
-

嘆けとて月やは物を思はするかこちがほなるわが涙かな 西行
月Geminiさんによる解説この歌は西行の『山家集』に収められていますこの歌は美しい月を見ても心が晴れず物思いに沈んで涙がこぼれる様子を詠んでいます現代語訳と解説は以下のとおりです現代語訳月が私に「嘆け」と言っているのだろうかいやそんなはずはないそれなのにどうしてこんなに物思いに沈んで涙がこぼれるのだろうか解説この歌は美しい月を見ても心が晴れず物思いに沈んで涙がこぼれる様子を詠んでいます「嘆けとて月やは物を思はするか」は「月が私に『嘆け』と言っているのだろうか」という疑問の表現です実際には月が何かを言っているわけではありませんが物思いに沈んでいる自分の心を月のせいにしているような少しユーモラスな表現です「こちがほなるわが涙かな」は「どうしてこんなに物思いに沈んで涙がこぼれるのだろうか」という自問自答の表現です「こちがほ」は「恨みがましい様子」という意味でここでは涙がこぼれることを少し恨めしく思っているようなニュアンスがありますこの歌から読み取れるのは美しい月を見ても心が晴れず物思いに沈んで涙がこぼれるという複雑な心情ですChatGPTさんによる解説現代語訳月が「嘆け」と言っているわけではないのにそれでも涙が流れてしまうまるで月のせいで泣いているかのように——解説1. 「嘆けとて月やは物を思はする」「嘆けとて」「嘆け」と命じているのか(いや、そんなことはない)「月やは」月が~するというのか(いや、そんなことはない)「物を思はする」物思いをさせるつまり「月が私に嘆けと言っているわけではない」 という意味しかし月を見ていると自然と涙があふれてくる2. 「かこちがほなるわが涙かな」「かこちがほ」人のせいにするような顔つき「わが涙かな」私の涙よつまり「あたかも月のせいで泣いているかのような私の涙よ」 ということ涙が止まらないのは月のせいではないのにまるで「月のせいだ」と言い訳しているような状態を嘆いている歌のテーマと味わい1. 「月」と「涙」の関係西行にとって「月」は無常・憧れ・孤独・悟りなどさまざまな象徴を持つしかしこの歌では「月そのものは何もしていない」と強調されるにもかかわらず月を見ていると涙があふれる2. 「理由のない悲しみ」「涙が流れるのは月のせいではない」としながらも月を見つめることで悲しみが増す という逆説的な構造自分でも理由のわからない涙言葉にできない切なさを表しているこの歌の魅力「月に理由を求める心の動き」 に焦点を当てた西行らしい繊細な感情表現 の歌月の静けさと涙の動きが対比 されることで→ 「静かなのに胸が締めつけられる」 という感覚を生む涙の理由を明言しないことで読者にさまざまな解釈の余地を残す→ 失恋の嘆き? 人生の無常? 仏道への思索?この曖昧さが「理由のない悲しみ」 をよりリアルに感じさせる非常に奥深い歌となっているClaudeさんによる解説この和歌は月への思いと自身の感情を複雑に絡め合わせた西行らしい深い情感のある歌です「嘆けとて月やは物を思はする」「月が私に嘆けと言っているわけではないのに」という意味です「や」は反語を表す助詞で月は実際には何も命じていないことを強調しています月を擬人化しながら自分の感情を客観的に見つめる視点が表れています「かこちがほなる」「かこつ」は不平や不満を言う愚痴をこぼすという意味です「がほ」は様子や態度を表す接尾語ですつまり不平を言いたげな様子を表現しています「わが涙かな」結局は自分の感情を抑えきれず涙を流してしまう様子を詠んでいます「かな」という詠嘆の助詞でその状況への諦めや自嘲的な思いも感じられますこの歌の魅力は月と自分の感情の関係を複雑に描き出している点にあります月は何も命じていないのに見る者の心を揺さぶり感情を喚起させる存在として描かれていますまた自分の感情を客観的に見つめながらも結局は涙を流してしまうという人間の弱さや感情の制御できない様を繊細に表現しています西行の他の月の歌にも共通する月への深い思い入れとそれを見つめる自己の内面への洞察が見事に表現された秀歌といえるでしょうGrokさんによる解説この歌も西行の作品で月の美しさとそれが引き起こす感情を詠んでいます以下に詳しく解説します嘆けとて「嘆け」は「嘆く」「嘆息する」の意味で「とて」は「というからには」「ということで」の意味です「嘆けとて」は「嘆くように言われて」の意味です月やは物を思はするか「月やは」は「月が」「月は」の意味で「物を思はする」は「物思いにさせる」「考えさせる」の意味です「月やは物を思はするか」は「月が物思いにさせるのか」と解釈できますこちがほなる「こちがほ」は「こちら側の顔」や「こちらのほほえみ」の意味で「なる」は「なって」の意味です「こちがほなる」は「こちらのほほえみになる」の意味ですわが涙かな「わが涙」は「私の涙」の意味で「かな」は感嘆や感想の終助詞です「わが涙かな」は「私の涙よ」と感嘆する意味ですこの歌は嘆くように言われているのに月を見ると物思いにさせられその結果涙がこちらのほほえみのように流れ落ちるという情景を詠んでいます西行は月の美しさが持つ力が悲しみや思索を引き起こしそれが涙という形で現れることを表現していますここには自然の美しさ(特に月)が人間の感情をどのように揺さぶるかその複雑さと美しさが描かれています涙は通常は悲しみや苦しみを象徴しますがこの歌ではそれが「こちがほなる」つまり何か美しいものや穏やかなものへの反応としても描かれていますこの歌からは自然の美しさと人間感情の深い結びつきそしてその感動がどれほど詩的で複雑なものであるかが感じられます西行全歌集 (岩波文庫 黄23-2) [ 西行 ]価格:1,507円(税込、送料無料) (2025/2/13時点)楽天で購入
2025.02.14
コメント(0)
-

卯の花の心地こそすれ山里の垣根の柴を埋む白雪 西行
雪歌よみけるにGeminiさんによる解説この歌は西行の『山家集』に収められていますこの歌は山里の垣根に積もった雪が卯の花(ウツギの花)のように真っ白で美しい様子を詠んでいます現代語訳と解説は以下のとおりです現代語訳山里の垣根の柴を埋め尽くす白雪はまるで卯の花が咲き乱れているかのようだ解説この歌は雪景色を白い花に見立てることでその美しさを表現しています「卯の花」は初夏に白い花を咲かせるウツギの花のことです雪の白さと卯の花の白さを重ね合わせることで雪景色の清らかさ美しさを強調しています「山里の垣根の柴を埋む」という表現は雪が深く積もっている様子を表していますこの歌から読み取れるのは雪景色の美しさそしてそれを花に見立てることで自然の造形美に対する感動ですChatGPTさんによる解説現代語訳山里の垣根に積もる白雪を見ているとまるで卯の花が咲いているような気がする解説1. 「卯の花の心地こそすれ」「卯の花」ウツギの花白く小さな花をたくさん咲かせる「心地こそすれ」(まるで)~のように感じるつまり「まるで卯の花のようだ」 という比喩表現2. 「山里の垣根の柴を埋む白雪」「山里」人里離れた静かな場所「垣根の柴」粗末な垣根(木の枝などで作ったもの)「埋む白雪」降り積もる雪が垣根を覆い隠す冬の山里柴垣が雪にすっぽり覆われている情景を描写している歌の情景と味わいこの歌は冬の静かな山里の風景を詠んだ叙景歌白雪が降り積もるとまるで春の「卯の花」が咲いたように見える雪と花の白さを重ね合わせ冬の冷たさよりもどこか柔らかく幻想的な雰囲気を感じさせる西行は出家後自然の風景を通じて心の静けさや美しさを詠むことが多かったこの歌もそのような心境を映しているといえるClaudeさんによる解説この和歌は雪景色を卯の花に見立てた西行らしい繊細な感性が光る歌です「卯の花の心地こそすれ」「卯の花」は初夏に咲く白い花で垣根などによく見られます「心地」は様子や感じの意味で雪景色が卯の花のように見えるという見立てを表現しています「山里の垣根の柴を」「山里」は山間の集落を指し西行がよく詠んだ場所です「垣根の柴」は垣根として使われている雑木や小枝を指します「埋む白雪」白い雪が柴を覆い尽くす様子を表現しています「埋む」という動詞で雪の深さを印象づけていますこの歌の特徴は冬の雪景色を初夏の卯の花に見立てるという季節を超えた発想にあります山里の素朴な風景(垣根の柴)に積もった雪を白い卯の花に見立てることで厳しい冬の景色に優美さを見出していますまた「山里」という空間設定は西行の隠遁生活や僧侶としての生き方とも深く関連しておりその実体験に基づいた観察眼が感じられます自然の中に美を見出しそれを季節を超えた連想で表現する西行らしい繊細な歌といえるでしょうGrokさんによる解説この歌も西行の作品で自然の美しさとその一過性を詠んでいます以下に詳しく解説します卯の花の心地こそすれ「卯の花」は「デイゴの花」や「アンズの花」といった春に咲く花を指すことがあります「心地こそすれ」は「感じさせる」「思わせる」の意味で「卯の花の心地こそすれ」は「まるで卯の花のような感じがする」の意味です山里の垣根の柴を「山里」は「山奥の村」や「山間の地」の意味で「垣根」は「塀」「柵」の意味「柴」は「小枝」「薪」の意味です「山里の垣根の柴」は「山里の垣根に使われている小枝」のことです埋む白雪「埋む」は「埋もれる」「覆われる」の意味で「白雪」は「白い雪」のことです「埋む白雪」は「白い雪に覆われる」という意味ですこの歌は雪が積もることで垣根の小枝がまるで卯の花のように見える様子を詠んでいます西行は雪の白さとその美しさが春の卯の花の美しさを想起させるという詩的な情景を描いていますここには自然の変化がどのように新たな美しさを生み出すかその一過性と美しさの両方を感じさせる力が表現されています雪が降ることで通常は見えない美や色彩が現れそれが春の花の美しさに匹敵するという感覚が詩的に表現されていますこの歌からは自然の美しさの多層性とその季節ごとの移ろいがもたらす無常観が感じられます自然の美しさを観察しそれを詩的な言葉で捉える西行の感性が伝わってきます西行全歌集 (岩波文庫 黄23-2) [ 西行 ]価格:1,507円(税込、送料無料) (2025/2/13時点)楽天で購入
2025.02.13
コメント(0)
-

自然は脈動する 再々々々 アリック・バーソロミュー 野口正雄 日本教文社
コーカサス出身の神秘主義者で教育者でもあるゲオルギー・グルジェフは、ふつうの人間は、気づきや意識をもたない盲目的な機械のように生きているとよく述べた。ヴィクトルは、現代の人間は物を見ることはあっても、本質を見ない表層的な生き物だと考えた。私たちの視覚は認識するのみに限定されており、深い考察とは関係がない。私たちは外見を全体と、結果を原因と取り違えてしまっているのだ。実際に目にしているものは発現したものの外側の殻であり、形成的エネルギーが遺していったものにすぎない。私たちには、生物を創ったエネルギーが見えないのである。自然は脈動する ヴィクトル・シャウベルガーの驚くべき洞察 [ アリック・バーソロミュー ]価格:2,860円(税込、送料無料) (2025/2/13時点)楽天で購入
2025.02.13
コメント(0)
-

自然は脈動する 再々々 アリック・バーソロミュー 野口正雄 日本教文社
自然界ではあらゆるプロセスがたえまない変化と変形によって働いており、一つとして同じものはありえない。量的科学では一+一=二だとするが、自然のシステムでは等式は成り立たないのだ。自然は脈動する ヴィクトル・シャウベルガーの驚くべき洞察 [ アリック・バーソロミュー ]価格:2,860円(税込、送料無料) (2025/2/13時点)楽天で購入
2025.02.13
コメント(0)
-

自然は脈動する 再々 アリック・バーソロミュー 野口正雄 日本教文社
従来の科学では質の重要性は問われない。還元主義的科学者にとっては水は水であり、遺伝子組み換え作物は従来の作物と「実質的に同等」なものである。自然は脈動する ヴィクトル・シャウベルガーの驚くべき洞察 [ アリック・バーソロミュー ]価格:2,860円(税込、送料無料) (2025/2/13時点)楽天で購入
2025.02.13
コメント(0)
-

自然は脈動する 再 アリック・バーソロミュー 野口正雄 日本教文社
低い水質の水の中でも生きられるのは下等な魚だけであることは誰でも知っている。人間についても事情は変わらない。環境中の天然資源の価値が下がってしまうことで、人類の潜在力の質は避けがたく悪影響を被る。自然は脈動する ヴィクトル・シャウベルガーの驚くべき洞察 [ アリック・バーソロミュー ]価格:2,860円(税込、送料無料) (2025/2/13時点)楽天で購入
2025.02.13
コメント(0)
-

ねずさんの日本の心で読み解く百人一首 五十二番歌 小名木善行 彩雲出版
明けぬれば暮るるものとは知りながらなほ恨めしき朝ぼらけかな藤原道信朝臣愛する人と同じ思いで【POD】ねずさんの 日本の心で読み解く「百人一首」 [ 小名木善行 ]価格:3,806円(税込、送料無料) (2025/2/12時点)楽天で購入
2025.02.12
コメント(0)
-

月を見ていづれの年の秋までかこの世にわれが契りあるらん 西行
月前述懐Geminiさんによる解説この歌は西行の『山家集』に収められていますこの歌は美しい月を眺めながらこの世にいられるのもあとわずかなのかもしれないという西行の無常観を表した歌です現代語訳と解説は以下のとおりです現代語訳月を見ているとあとどれくらいの秋まで私はこの世に生きていることができるのだろうかと考えてしまう解説この歌は美しい月を眺めながら自分の寿命について考えさせられるという心情を詠んでいます「月を見て」は月を眺めているという意味です「いづれの年の秋までか」は「どの年の秋までだろうか」という疑問の表現です「この世にわれが契りあるらん」は「この世に私が生きていることができるのだろうか」という意味です「契り」はここでは「命」という意味で使われていますこの歌から読み取れるのは美しい月を眺めながら自分の寿命について考えさせられるという西行の無常観ですこの歌は短い言葉の中に人生の儚さそしてそれを受け入れる覚悟のようなものが込められた印象的な歌ですChatGPTさんによる解説現代語訳月を見ながら思う私はいったいいつの年の秋までこの世に生きる契りがあるのだろうか解説1. 「月を見て」西行にとって「月」は特別な存在であり多くの歌に登場する「月」無常・永遠・憧れ・悟りなどさまざまな象徴を持つこの歌では「変わらず照り続ける月」と「限りある人の命」の対比が意識されている2. 「いづれの年の秋までか」「いづれの年」どの年「秋までか」どの年の秋まで生きるのか西行は人生の無常を強く意識する歌を多く詠んでいる「秋」という季節には「実り」「成熟」のイメージがある一方で「ものの終わり」や「寂しさ」 も象徴する→ 「自分はあと何回、この秋を迎えるのだろうか」 という思いが込められている3. 「この世にわれが契りあるらん」「契り」前世・来世を含めた因縁または寿命の約束「あるらん」あるのだろうか(推量)つまり「自分はこの世にあとどれほど生きることになっているのだろうか」という問いかけ西行は出家しているため「生の執着」を捨てようとしているしかしこの歌にはどこか 「まだこの世にいるのか」という迷い が感じられる→ まだ「死を覚悟しきれていない」ような心境がにじむこの歌のテーマこの歌は西行の「無常観」と「自分の命の行方」に対する思索を表している「月」は変わらずにあるが人の命には限りがある「あとどの秋まで生きるのか」 という疑問は→ 「人生の先が見えない不安」でもあり→ 「死が近づく自覚」でもある西行は晩年亡くなる前年にも「願わくは花の下にて春死なん」という有名な歌を詠んでいるこの歌もまた同じように「自分の命がどこまで続くのか」を静かに見つめるものといえるClaudeさんによる解説この和歌は西行の無常観と月への深い思いが結びついた非常に深い意味を持つ歌です「月を見て」月を見上げながらという状況設定です西行にとって月は特別な存在で多くの歌に詠まれています「いづれの年の秋までか」どの年の秋までという問いかけの形を取っています自分の命がいつまで続くのかという無常の思いが込められています「この世にわれが契りあるらん」「契り」は約束、縁、運命などを意味しますこの世との関わりつまり生きている時間がどれほど残されているのかという思いを表現しています「らん」は推量の助動詞で不確かさを表現していますこの歌の深さは月を見る行為を通じて自身の生命の有限性を静かに見つめている点にあります毎年変わらず見える月に対して自分の生命は限られているという対比が印象的ですまた「契り」という仏教的な概念を用いながらこの世との関わりを問う姿勢には僧侶としての西行の思索が表れていますしかしそれは厭世的なものではなく静かな諦観とも言える心境で詠まれています月の不変性と人間の生命の儚さという対比そして仏教的な無常観が見事に調和した秀歌といえるでしょうGrokさんによる解説この歌も西行の作品で人生の無常観と月の美しさを通じた思索を詠んでいます以下に詳しく解説します月を見て「月を見て」は「月を見ることで」の意味で月の美しさやその一時性に思いを馳せるきっかけを示していますいづれの年の秋までか「いづれの年」は「どの年」の意味で「秋までか」は「秋までだろうか」の意味です「いづれの年の秋までか」は「どの年の秋までだろうか」という問いかけですこの世に「この世に」は「この世の中に」「この現世に」の意味ですわれが契りあるらん「われが」は「私が」「契り」は「縁」「約束」の意味で「あるらん」は「あるだろう」「存在するだろう」の意味です「われが契りあるらん」は「私がこの世と縁があるだろうか」という意味になりますこの歌は月を見ることで自分がこの世にどれだけの期間存在できるのかつまり自分の命がいつまで続くのかという深い問いを投げかけています西行は月の美しさとその一時性から人生の無常さを感じその中で自分がどれほどの時間をこの世で生きられるのかという思索を詩的に表現していますここには自然の美しさとその背後にある時間の流れや存在の儚さに対する感慨が込められています月の満ち欠けは季節の移り変わりや一年の終わりと始まりを象徴しそれを人生の終わりに重ね合わせることで西行は自分の存在の意味や限界について考えていますこの歌からは人生の短さとその無常さに対する深い思索そして自然の中に見出す生命の美しさと儚さが感じられます西行全歌集 (岩波文庫 黄23-2) [ 西行 ]価格:1,507円(税込、送料無料) (2025/2/10時点)楽天で購入
2025.02.10
コメント(0)
-

足引の山のあなたに君住まば入るとも月を惜しまざらまし 西行
月Geminiさんによる解説この歌は西行の『山家集』に収められていますこの歌はもしもあなたが遠い山奥に住んでいるのなら月がなくてもあなたに会いに行けるのにという切ない心情を詠んでいます現代語訳と解説は以下のとおりです現代語訳もしあなたが足を踏み入れても引き返すような遠い山の向こうに住んでいるのならたとえ月が出ていなくてもあなたに会いに行くでしょう解説この歌は恋しい人が遠い場所に住んでいるためなかなか会うことができないもどかしさを詠んでいます「足引の山」は険しい山足を踏み入れても引き返してしまうような遠い山を意味します「あなた」は山の向こう側遠い場所を指します「君住まば」は「君が住んでいるならば」という仮定の表現です「入るとも」は「たとえ(月が)出ていなくても」という意味です「月を惜しまざらまし」は「月を惜しむ必要はないだろう」という反実仮想の表現で月がなくてもあなたに会いに行くという強い意志を表していますこの歌から読み取れるのは恋しい人に会いたいという切実な願いとそれが叶わないもどかしさです月が出ていなくてもあなたに会いに行くという表現は恋しい人への強い思いを表していますChatGPTさんによる解説現代語訳あなたが山の向こうに住んでいるのならたとえこの月が山に沈んでしまっても惜しいとは思わなかっただろうに解説1. 「足引の山のあなたに君住まば」「足引の山」「山」を枕詞として導く表現「足引きの山」は和歌でよく使われる慣用的な表現で具体的な山ではなく山一般を指す「あなたに君住まば」「あなた」は「彼方」つまり山の向こう側のこと「君が住んでいるのなら」 という意味になるここでは恋しい相手が山の向こうに住んでいるという設定があり「遠く離れていて会えない」という状況を表している2. 「入るとも月を惜しまざらまし」「入る」月が沈むこと「月を惜しまざらまし」「月が沈むのを惜しく思わないだろうに」= 「たとえ月が沈んでも気にならないはずだ」和歌では**「月」=「思慕」「未練」**を表すことが多いこの部分の意味としては「もし君が山の向こうにいるのなら、月が沈んでも(=夜が終わっても)惜しくはない」つまり月が沈んでも「会える」ならそれでいいのに という気持ちが込められているこの歌のテーマこの歌は**「会えない恋」「遠く離れた想い人」**をテーマにしたもの「山」 は物理的な距離だけでなく「会えない障害」を象徴している「月」 は西行の歌では特に「思慕」「未練」「憧れ」の象徴「月が沈む=夜が終わる」のを惜しむのはふつうは「もう少し月を見ていたい」という思いでもこの歌では**「月が沈んでも惜しくない」**と言っている→ それは「君に会えるなら」という前提があるから🌿 ポイント「月を惜しまない」という逆説的表現 が切なさを際立たせる実際には「君」は遠くにいて会うことはできないだからこそこの歌の「叶わぬ思い」がより強く伝わる西行の歌にはこうした「叶わぬ恋」「届かぬ想い」を詠んだものが多いですがこの歌もその一つで夜が終わることを惜しむのではなく「会えぬ切なさ」を際立たせる構成になっていますClaudeさんによる解説この和歌は西行の月への深い思いと人間関係における繊細な感情を組み合わせた印象的な歌です「足引の」「足引の山」は山が低く連なっている様子を表す枕詞です「足」を「引く」ように低く続く山という意味から来ています「山のあなたに君住まば」「あなた」は山の向こう側を指します「君」は特定の人物を指していると考えられますもし大切な人が山の向こうに住んでいるならばという仮定を示しています「入るとも月を惜しまざらまし」「入る」は月が山の向こうに沈むことを指します通常なら惜しむべき月の入りもその方向に大切な人がいるのなら惜しまないという心情を表現しています「まし」は仮定を表す助動詞で願望の念も含まれていますこの歌の特徴は西行が頻繁に詠んだ月への愛着と人への思いを見事に結びつけている点です普段なら月が山の向こうに沈むのを惜しむ西行がその方向に大切な人がいるならば月の入りさえも心満ちたものとして受け入れられるという繊細な心情の変化を描いていますまた実景と心情が見事に融合している点も西行らしい表現といえます月、山、そして人への思いが自然な形で結びつき深い情感を生み出していますGrokさんによる解説この歌も西行の作品で恋心や自然への思いを詠んでいます以下に詳しく解説します足引の山のあなたに「足引の山」は実在の山で現在の京都市右京区に位置する山です「あなたに」は「向こう側に」の意味です「足引の山の向こう側に」と解釈できます君住まば「君」は「あなた」を指し「住まば」は「住んでいるならば」の意味で「君住まば」は「あなたが住んでいるならば」の意味です入るとも「入る」は「入る」「訪れる」の意味で「とも」は仮定形の助詞です「入るとも」は「訪れるならば」という意味です月を惜しまざらまし「月を惜しむ」は「美しい月を惜しむ」「月を大切に思う」の意味で「ざらまし」は「しないであろう」「しないだろう」の意味です「月を惜しまざらまし」は「月を惜しむことはしなかっただろう」の意味ですこの歌はもしあなたが足引の山の向こう側に住んでいるならば月を見ることを惜しむことなくその美しさを共有するためにあなたのもとへ訪れていただろうという思いを詠んでいます西行は自然の美しさ(特に月)を通じて恋心や親愛の情を表現していますここには自然と人間との関係そしてその中での人間関係(特に恋愛感情)の美しさや純粋さが描かれています月を見ることの喜びが愛する人と分かち合うことでさらに深まるという詩的な情景が感じられますこの歌からは自然の美しさが人間の感情や行動をどのように高めるかまたそれがどれほど深い愛情を表現する手段となり得るかについての西行の感性が伝わってきます西行全歌集 (岩波文庫 黄23-2) [ 西行 ]価格:1,507円(税込、送料無料) (2025/2/10時点)楽天で購入
2025.02.10
コメント(0)
-

青根山苔の筵の上に敷く雪は白根の心地こそすれ 西行
雪歌よみけるにGeminiさんによる解説この歌は雪の降り積もる青根山の情景を詠んだ歌です青根山は神奈川県と山梨県の県境にある山で標高は930mほどです苔の生えた岩の上に雪が降り積もる様子を白い根が広がっているように見立てていますこの歌を現代語訳と解説を以下に示します現代語訳青根山の苔が生えた岩の上に降り積もる雪はまるで白い根が広がっているように感じられることだ解説この歌は雪景色を白い根に見立てることで自然の造形美を表現しています「青根山」は神奈川県と山梨県の県境にある山で苔が多いことで知られています「苔の筵」は苔が生えた岩の表面を筵(むしろ)に見立てた表現です「白根」は白い根ここでは雪の白い様子を指しています「心地こそすれ」は「~のように感じられる」という表現で雪が白い根のように見える様子を表していますこの歌から読み取れるのは雪景色の美しさそして自然の造形に対する作者の繊細な感性です苔の緑と雪の白のコントラストそして雪が根のように見えるという表現が青根山の雪景色を鮮やかに描き出していますChatGPTさんによる解説現代語訳青根山の苔の上に敷かれた雪はまるで白根のような心地がすることだ解説1. 「青根山苔の筵の上に敷く」「青根山」青々とした木々が茂る山「苔の筵の上に敷く」「苔の筵(むしろ)」苔をまるで敷物のように見立てている「上に敷く」その苔の上に雪が降り積もっている情景西行の感性が光る表現で青々とした苔の上に白い雪が降り積もりまるで緑の絨毯の上に白い布がかぶさったような光景が想像できます2. 「雪は白根の心地こそすれ」「雪は」降り積もった雪は「白根の心地こそすれ」「白根」白い根または白いもの全般を指すここでは「真っ白な心地」つまり澄み切った感覚清浄な印象を表しているこの部分は単なる視覚的な描写ではなく「白」=清浄、純粋さを象徴していると考えられますつまり苔の上の雪が清らかで神聖な雰囲気をかもし出しているということこの歌のテーマこの歌は苔の上に降り積もる雪の情景を詠みながらその神聖な美しさや清らかさを感じ取るものです🌿 ポイント「青根山」「苔」「雪」と色彩の対比が美しい→ 深い緑の苔 × 白い雪 のコントラスト「白根の心地」と自然の美しさを超えた精神的な清浄さに触れている→ 修行者としての西行の感覚が表れている雪をただの風景としてではなく精神の純粋さや静寂と重ねるのは西行らしい感性と言えるでしょうClaudeさんによる解説この和歌は地名の「青根山」と「白根」を巧みに用いた言葉遊びの要素を含みながら山の風景を鮮やかに描写した歌です「青根山」現在の静岡県にある山の名前です「青」という色彩語が印象的です「苔の筵の上に敷く」「筵(むしろ)」は敷物のことを指します苔を敷物に見立てた表現で山の自然な風景を巧みに表現しています「雪は白根の心地こそすれ」「白根」は白根山(しらねやま)を想起させる表現です「心地」は感じや様子を表します青々とした苔の上に積もった雪がまるで白根山のようだという趣向ですこの歌の魅力は「青根」と「白根」という対照的な色彩を用いながら苔の緑の上に白い雪が積もる様子を鮮やかに描き出している点にありますまた実在の地名を詠み込みながらそれを自然の色彩描写と重ね合わせる技巧も見事です山の風景を詠むことの多かった西行らしい実景に基づいた表現力が感じられますさらに「筵」という日常的な物を苔に見立てることで荘厳な山の風景をより身近なものとして感じさせる効果も生んでいますGrokさんによる解説この歌も西行の作品で自然の美しさとその一過性を詠んでいます以下に詳しく解説します青根山「青根山」は実在の山の名前でありここでは自然の風景の一部分として用いられています苔の筵の上に「苔」は「こけ」のことで「筵」は「むしろ」や「敷物」の意味です「苔の筵」は「苔が敷き詰められたかのような地面」のイメージです敷く雪は「敷く」は「敷き詰める」「広げる」の意味で「敷く雪」は「雪が広がっている」ことを指します白根の心地こそすれ「白根」は「白い根」や「白いもの」の意味でここでは「真っ白な雪」を指すと解釈できます「心地こそすれ」は「感じさせる」「思わせる」の意味で「白根の心地こそすれ」は「まるで白い根のような感じがする」という意味ですこの歌は青根山の苔の上に降り積もった雪がまるで白い根のように見える様子を詠んでいます西行は自然の風景の中で雪がどのように美しくそして一時的に存在するかを表現していますここには自然の美しさとその一時性に対する感動が込められています雪が苔の上に敷かれることで通常は緑豊かな風景が白一色に変わりその変化が新たな美しさや感動を生むという詩的表現が見られますこの歌からは自然の変化とその美しさに対する西行の深い観察眼と自然の無常観を感じることができるでしょう西行全歌集 (岩波文庫 黄23-2) [ 西行 ]価格:1,507円(税込、送料無料) (2025/2/10時点)楽天で購入
2025.02.10
コメント(0)
-

ミダスタッチ 再々々 ドナルド・トランプ ロバート・キヨサキ 筑摩書房
創造主は私たちに二つの目と二つの耳を与え、口は一つしか与えなかった。そこに込められたメッセージはこうだーよく聴き、よく観察し、控えめに話せ。話はするが耳を傾けることができないリーダーはいいリーダーではない。しっかり覚えておいてほしい。一番多く話した人間が負けだ。一番よく耳を傾けた人が勝つ。耳を傾けることは尊敬の印だ。自分が興味の対象であろうとするより、こちらから相手に興味を持つのも尊敬の印だ。相手に敬意を払おう。そうすればあなたは勝つ。ビジネスにおいてだけでなく、人生においても同じだ。黄金を生み出すミダスタッチ 成功する起業家になるための5つの教え [ ドナルド・J.トランプ ]価格:2,090円(税込、送料無料) (2025/2/10時点)楽天で購入
2025.02.10
コメント(0)
-

ミダスタッチ 再々 ドナルド・トランプ ロバート・キヨサキ 筑摩書房
人間関係には意見の相違がつきものだ。いいパートナー同士であれば、そのような違いは生産的なものになり得る。多くの場合、よりよいアイディアは白熱した議論から生まれる。黄金を生み出すミダスタッチ 成功する起業家になるための5つの教え [ ドナルド・J.トランプ ]価格:2,090円(税込、送料無料) (2025/2/10時点)楽天で購入
2025.02.10
コメント(0)
-

ねずさんの日本の心で読み解く百人一首 五十一番歌 小名木善行 彩雲出版
かくとだにえやはいぶきのさしも草さしも知らじな燃ゆる思ひを藤原実方朝臣【POD】ねずさんの 日本の心で読み解く「百人一首」 [ 小名木善行 ]価格:3,806円(税込、送料無料) (2025/2/8時点)楽天で購入
2025.02.08
コメント(0)
-

自然は脈動する アリック・バーソロミュー 野口正雄 日本教文社
自然の世界は本来分割できないものなのだが、人間は自然を二つの異なる方向から理解することを運命づけられている。つまり五感(知覚)を通した理解と、頭脳(概念)を通した理解である。子供ならただ見て驚嘆するところを、私たちは理性的判断を躾けられるにつれて、感覚的経験の「意味を理解する」ために、目にするものを解釈する方法を、たいていは他人の発想を通じて教えられる。どちらも現実の一つの形ではあるが、この二つの面を意味をなすように合わせることができなければ、世界は私たちの目には理解しがたい謎にしか映らないことだろう。これはまさに、現在の人類社会の根本的な欠点なのであり、現在支配的な主流科学の大きな弱点なのである。自然は脈動する ヴィクトル・シャウベルガーの驚くべき洞察/アリック・バーソロミュー/野口正雄【1000円以上送料無料】価格:2,860円(税込、送料無料) (2025/2/7時点)楽天で購入
2025.02.07
コメント(0)
-

心の病に薬はいらない! 再々々々 内海聡 かんき出版
この最も基本的な、動物から人間に成長するための教育をおろそかにしたまま、現代教育は成績だけを重視してきました。心の病に薬はいらない!【電子書籍】[ 内海聡 ]価格:1,584円 (2025/2/7時点)楽天で購入
2025.02.07
コメント(0)
-

心の病に薬はいらない! 再々々 内海聡 かんき出版
現在多くの子どもが発達障害だと何の根拠もなく扱われていますが、この子どもたちの多くが、発達障害というより別の要因から問題行動を起こしていることがわかります。心の病に薬はいらない!【電子書籍】[ 内海聡 ]価格:1,584円 (2025/2/7時点)楽天で購入
2025.02.07
コメント(0)
-

散ると見ればまた咲く花のにほひにも遅れ先立つためしありけり 西行
花の散りたりけるに並びて咲き始めける桜を見てGeminiさんによる解説現代語訳花が散ってしまったのを見て遅れて咲き始めた桜を見ると散ると思えばまた咲く花の香にも遅れて咲いたり先に散ったりという例があるのだなあと改めて気づかされる解説この歌は散った花とこれから咲く桜を見て花の散る時期咲く時期もそれぞれであることに改めて気づいたことを詠んでいます「散ると見ればまた咲く花のにほひにも」は散ったと思えばまた別の花が咲き始めるのを見てということを表しています「遅れ先立つためしありけり」は花にも咲くのが遅れたり先に散ったりするものがあるという例があるのだなあと改めて気づかされたということを表していますこの歌から読み取れるのは花の命の儚さとそれでもまた新しい花が咲くという自然の循環に対する感慨です散った花を見てその儚さを感じると同時に遅れて咲き始めた桜を見てまた新しい命が生まれることを知るその繰り返しの中で自然の力強さそして儚さを感じている様子が伝わってきますChatGPTさんによる解説現代語訳散るのを見ればまた咲く花があるその美しい姿も遅れるものや先立つものがあるというまるで人の世のようだなあ解説1. 「散ると見ればまた咲く花のにほひにも」「散ると見れば」花が散るのを見ていると「また咲く花の」また新たに咲き始める花がある「にほひにも」美しく咲き誇るその姿にも「にほひ(匂ひ)」はもともと「色や香りの美しさ」を指す言葉ここでは咲き誇る桜の美しさを表している2. 「遅れ先立つためしありけり」「遅れ先立つ」後から咲くもの先に散るもの一斉に咲き散るのではなく早く散る花もあれば遅れて咲く花もある「ためしありけり」そんな例があるものだなあ「ためし」前例世の常のことという意味を持つつまり「花の世界でも、先に散るもの・遅れて咲くものがある」というのはまるで人の世のようだと暗に言っているこの歌のテーマこの歌は桜の咲き散る様子を通して人の生死の無常を詠んだものと考えられます🌿 ポイント花は散ってもまた咲くがそれぞれに咲く時・散る時が異なる→ 人生にも「先に去る者」「後に生まれる者」がいる「ためしありけり(そういう例があるものだ)」とどこか達観したような表現→ まるで人生の理(ことわり)を見つめる僧侶の視点にも通じる西行は桜を詠んだ歌を多く残していますがこの歌もまた桜の美しさと儚さを通して人の世の無常を映し出した一首と言えるでしょうClaudeさんによる解説この和歌は西行の優れた観察眼と深い洞察が表れた歌です題詞からわかるように散った桜と新しく咲き始めた桜を同時に目にした時の感慨を詠んでいます「散ると見れば」すでに散りゆく桜を見ている状況を示しています「と見れば」という表現にはその瞬間的な発見のニュアンスが込められています「また咲く花のにほひにも」新たに咲き始めた桜の様子を「にほひ」(美しい姿)という言葉で表現しています「また」という言葉で桜の生命の循環を強調しています「遅れ先立つためしありけり」「遅れ先立つ」はあとから咲く花と先に散る花という時間的な前後関係を表現しています「ためしありけり」はそのような例が実際にあったという発見や気づきを示していますこの歌の特徴は同じ場所で散る桜と咲く桜を同時に目にするという珍しい情景を捉えそこから人生の真理を見出している点です桜の開花と散花の一瞬の重なりの中に生命の循環や無常の理を見出していますまた「遅れ先立つ」という表現には人生における様々な出会いと別れ世代交代なども暗示されており単なる自然描写を超えた深い洞察が感じられます西行らしい観察の鋭さとそこから導き出される哲学的な思索が見事に調和した秀歌といえるでしょうGrokさんによる解説この歌も西行の作品で桜の散り際と咲き始めの美しさを詠んでいます以下に詳しく解説します花の散りたりけるに「花の散りたりける」は「花が散った」の意味で「に」は状況を示す接続助詞です「花が散ったという状況で」と解釈できます並びて咲き始めける「並びて」は「並んで」「共に」の意味で「咲き始めける」は「咲き始めた」の意味です「並びて咲き始めける」は「共に咲き始めた」という意味です桜を見て「桜を見て」はその桜の風景を見たという状況を示しています散ると見れば「散ると見れば」は「散るのが見えれば」の意味で「見れば」は仮定の意味を含みます「花が散るのを見れば」という意味ですまた咲く花のにほひにも「また咲く花」は「また新たに咲く花」の意味で「にほひ」は「香り」のことです「また咲く花のにほひにも」は「また咲く花の香りにも」の意味です遅れ先立つためしありけり「遅れ」は「遅れる」「先立つ」は「先に立つ」「先に進む」の意味で「ためし」は「例」「場合」の意味です「遅れ先立つためしありけり」は「遅れたり先に立ったりする例があるのだ」という意味ですこの歌はある桜の花が散るのを見る一方で別の桜が咲き始めるという情景を詠んでいます西行は花が散る時と新たに咲く時が重なり合うことで自然の循環性や無常観を表現しています特に「遅れ先立つためしありけり」という表現は自然の中での時間の流れや生命のリズムが必ずしも一貫していないことつまり一つの生命の終わりが別の生命の始まりと重なることがあるということを示していますこの歌からは自然の美しさとその一時性そしてそれがもたらす生命の連続性に対する深い感慨が感じられます西行は桜の散り際と咲き始めを通じて人生や自然の循環についての思索を詩的に表現しています西行全歌集 (岩波文庫 黄23-2) [ 西行 ]価格:1,507円(税込、送料無料) (2025/2/6時点)楽天で購入
2025.02.06
コメント(0)
-

思ひ出づることはいつともいひながら月には堪へぬ心なりけり 西行
月Geminiさんによる解説この歌は西行の『山家集』に収録されていますこの歌は月を見ることで様々なことを思い出し心が揺り動かされる様子を詠んでいます現代語訳と解説は以下のとおりです現代語訳いつのことを思い出しているのかと(人に)言われるかもしれないが(それほどに様々な思いが去来して)月を見ていると耐えきれない気持ちになるのだった解説この歌は月を見ることで様々な感情が湧き上がり心が揺り動かされる様子を詠んでいます「思ひ出づることはいつともいひながら」は具体的に何について思いを巡らせているのかは明確に示されていませんしかし様々な思いが去来し感情が揺れ動いている様子が伝わってきます「月には堪へぬ心なりけり」は月を見ることで感情が抑えきれなくなるという意味です月は古くから人の心を惑わすものとして和歌に詠まれてきました西行もまた月の力に翻弄される心情を率直に表現していますこの歌から読み取れるのは月を見ることで様々な感情が湧き上がり心が揺り動かされるという複雑な心情ですChatGPTさんによる解説現代語訳思い出すことはいつでもあるけれど月を見るとどうしても耐えきれなくなってしまう心なのだなあ解説1. 「思ひ出づることはいつともいひながら」「思ひ出づる」思い出す「ことはいつともいひながら」(特定の時というわけではなく)いつも思い出すけれどもここでの「こと」は過去の記憶や恋しい人大切な思い出を指すと考えられる「いつともいひながら」とすることで四六時中思い出していることを示唆している2. 「月には堪へぬ心なりけり」「月には」月を見ていると「堪へぬ心なりけり」心が耐えられなくなってしまう「堪へぬ」は耐えきれずに溢れ出す感情を表している月は昔から物思いを誘う象徴でありこの場面でも月の光を見ていると抑えていた感情がこみ上げてくる様子が描かれているこの歌のテーマこの歌は普段から思い出してはいるものの月を見たときにだけはどうしても耐えきれなくなるという繊細な心の動きを詠んでいます🌿 ポイント「いつも思い出しているが、月を見ると特に耐えられなくなる」→ 月の光が心の奥底にある思いを強く浮かび上がらせる「月には堪へぬ」→ 月の持つ静寂と美しさが抑えていた感情を刺激する西行は月を詠んだ歌を多く残しておりしばしば月を過去の記憶や思いの象徴として扱っていますこの歌もまた月を通して抑えきれない心の揺らぎを描いた一首といえるでしょうClaudeさんによる解説この和歌は西行の代表的な月の歌の一つで「月」に対する深い感動と内面の感情を巧みに表現しています「思ひ出づることはいつともいひながら」「いつも月を見ると心が動かされる」という思いを常々感じているということを表現しています「いひながら」はそのことを自分でも認識しているという意味を含みます「月には堪へぬ心なりけり」どれだけ心構えをしていても月を見ると感動を抑えきれない心情を詠んでいます「堪へぬ」は耐えられない抑えきれないという意味です「なりけり」はその事実に改めて気づいたという発見や感慨を表現していますこの歌の魅力は月を見る度に感動する自分の心をあたかも他人事のように客観的に見つめながらそれでもなお抑えきれない感動を素直に認めている点にあります西行は多くの月の歌を残していますがこの歌では月そのものの描写ではなく月を見る人間の心の動きに焦点を当てています「分かっているはずなのに、やはり感動してしまう」という人間の心の機微を見事に捉えた歌といえるでしょうまたこの歌には仏道修行者としての西行の一面も垣間見えます感情を制御しようとしながらも美しいものに心を動かされる人間としての正直な感情が表現されているのですGrokさんによる解説この歌も西行の作品で思い出と月の美しさの関係を詠んでいます以下に詳しく解説します思ひ出づることは「思ひ出づる」は「思い出す」の意味で「思ひ出づることは」は「思い出すことは」の意味ですいつともいひながら「いつとも」は「いつでも」の意味で「いひながら」は「言いながら」「言うけれども」の意味です「いつともいひながら」は「いつでもと言いながら」という意味になります月には堪へぬ「月には」は「月に対して」「堪へぬ」は「堪えられない」「耐えられない」の意味です「月には堪へぬ」は「月に対しては堪えられない」の意味です心なりけり「心」は「心情」「心の状態」を指し「なりけり」は過去形の表現で「心なりけり」は「そのような心であった」の意味ですこの歌はいつでも思い出すと言いながらも実際には月の美しさに対して心が堪えられないつまり月を見ると特別な感情が溢れてしまうということを詠んでいます西行は月が引き起こす感情の強さや思い出との結びつきの深さを表現していますここには月の光景が持つ詩的で感傷的な力が人間が過去を思い出すきっかけとなりその感情をコントロールできないほど強くさせるというテーマが含まれています月は西行の詩世界でしばしば無常観や美の象徴として使われこの歌もその一例ですこの歌からは自然の美しさと人間が持つ記憶や感情の深い結びつきそしてそれらがどのように私たちの心を動かすかに対する西行の深い洞察が感じられます西行全歌集 (岩波文庫 黄23-2) [ 西行 ]価格:1,507円(税込、送料無料) (2025/2/6時点)楽天で購入
2025.02.06
コメント(0)
-

雪降れば野路も山路も埋もれてをちこち知らぬ旅の空かな 西行
雪歌よみけるにGeminiさんによる解説この歌は西行の作と伝えられ『山家集』に収録されています雪が降ると野道も山道も雪に埋もれてどちらへ向かえばいいか分からなくなるそんな旅の空の心細さを詠んだ歌ですこの歌を現代語訳と解説を以下に示します現代語訳雪が降ると野道も山道も雪に埋もれてどちらへ行けばいいのか全く分からなくなってしまうああ旅の空は心細いものだなあ解説この歌は雪が降ると道が分からなくなるという旅先での不安な気持ちを詠んでいます「野路も山路も埋もれて」は雪が降って野道も山道も雪に埋もれてしまった様子を表しています「をちこち知らぬ」は「彼方此方(おちこち)」つまり「あちらこちら」が分からなくなる道に迷ってしまうという意味です「旅の空かな」は旅の空は心細いものだなあという詠嘆の表現ですこの歌から読み取れるのは旅先での不安心細さです雪が降ると道が分からなくなり旅人は不安になります特に山道などでは遭難の危険性もありますこの歌はそのような旅の不安な気持ちを率直に表現していますChatGPTさんによる解説現代語訳雪が降ると野の道も山の道もすっかり埋もれてしまいどこがどこだか分からないまま旅の空にいるのだなあ解説1. 「雪降れば野路も山路も埋もれて」「雪降れば」雪が降ると「野路も山路も埋もれて」野の道も山の道も雪に覆われどこが道か分からなくなるここでの「埋もれる」は単に雪が積もることを指すだけでなく進むべき道が見えなくなることを象徴している野の道も山の道も自然の中に溶け込み境界が消える光景が思い浮かぶ2. 「をちこち知らぬ旅の空かな」「をちこち知らぬ」どこがどこだか分からない「をちこち」は「遠く近く」や「あちらこちら」の意雪によって景色が一様になり方角が分からなくなってしまう様子を表す「旅の空かな」旅先でのことよ「空」には「旅の空(=旅の途中の空模様)」という意味と**「心の空虚さ」や「無常観」**も重ねられている旅にある孤独感や不安が道が分からなくなることでさらに強調されるこの歌のテーマこの歌は旅の心細さと無常感を雪に覆われた道の情景と重ねて詠んでいます🌿 ポイント雪で道が消える=進むべき方向を見失う不安旅の空物理的な旅と人生の旅の二重の意味無常感すべてが白く覆われ境界が曖昧になる感覚西行の旅の歌にはこうした「自然の変化による心境の反映」がよく見られますこの歌もまた自然と心情が共鳴し旅の孤独と人生のはかなさを映し出す一首と言えるでしょうClaudeさんによる解説この和歌は西行の『山家集』に収められた旅の情景を詠んだ歌です「雪降れば」雪が降ることで一気に景色が変わる様子を切り取る出だしです季節は冬そして歌の場面設定として雪が激しく降っていることがわかります「野路も山路も埋もれて」平地の道も山道もすべて雪に埋もれてしまう様子を描写しています「も...も」という表現であらゆる道が見分けがつかなくなる状況を強調しています「をちこち知らぬ旅の空かな」「をちこち」は「あちこち」の古語で方向や場所を示します方向感覚を失った旅人の不安と途方に暮れた心情が表現されていますこの歌の特徴は単なる雪景色の描写を超えて旅人としての実体験に基づく心情を見事に表現している点です西行は生涯多くの旅を重ねた歌人として知られていますがこの歌からは実際に雪道で道に迷った経験が感じられますまた「旅の空」という表現には物理的な空間としての空だけでなく旅人としての心の状態や運命なども含意されており西行らしい重層的な意味を持たせています目の前の光景(雪に埋もれた道)と旅人としての心情(方向感覚の喪失、不安)が見事に結びついた秀歌といえるでしょうGrokさんによる解説この歌も西行の作品で雪が降ることによる風景の変化と旅の感覚を詠んでいます以下に詳しく解説します雪降れば「雪降れば」は「雪が降ると」の意味で雪が降ることが歌の主題となります野路も山路も「野路」は「田舎の道」や「野原の道」「山路」は「山道」のことです「野路も山路も」は「野の道も山の道も」の意味です埋もれて「埋もれて」は「覆い隠されて」「見えなくなって」の意味でここでは「雪に埋もれてしまう」ことを指しますをちこち知らぬ「をちこち」は「あちこち」「所々」の意味で「知らぬ」は「知らない」「分からない」の意味です「をちこち知らぬ」は「あちこちが分からなくなる」の意味です旅の空かな「旅の空」は「旅の途上の風景」や「旅する中での空」のことです「かな」は感嘆や感想を表す終助詞で「旅の空かな」は「旅の空よ」という感嘆の意味ですこの歌は雪が降ると野の道も山の道もすべて雪に覆われてしまいどこがどこだか分からなくなってしまう旅の風景を詠んでいます西行は雪の力によって通常の道筋が失われ旅の目的地や方向感覚が曖昧になる状況を描いていますここには自然の力が人間の生活や行動に与える影響そしてその中で感じる孤独感や自由さあるいは無常感が詩的に表現されています雪によって通常の風景が変わり新たな旅の空間が創出されることへの驚きや美しさが感じられますこの歌からは自然の変化と共に旅の意味や感じ方がどのように変わるかそしてそれが旅人(特に西行自身)の心象風景にどのように影響を与えるかという深い洞察が伝わってきます西行全歌集 (岩波文庫 黄23-2) [ 西行 ]価格:1,507円(税込、送料無料) (2025/2/6時点)楽天で購入
2025.02.06
コメント(0)
-

TREE C.W.ニコル 宮崎駿 竹内和世 徳間書店
日本という国を、世界でも有数の豊かな国におしあげたもの。それはこの国の森であり、山であり、清浄な水であった。広大な緑の森と、豊かな水資源のおかげで、日本は健康な国、力強い国となった。おびただしい上質の食べ物、山の幸、海の幸に恵まれた自然こそ、この国の財産なのだ。 いま、日本はうぬぼれを汚染に満ちた国になってしまった。なるほど、国民はたっぷり食べている・・・けれどもその食べ物は昔のような健康なものではない。 日本がいまのように金持ちの国になったのは、国民が勤勉で、よく働くからだというのは、単純すぎる考え方だし、うぬぼれもはなはだしい。 このうえなく繊細で変化に満ちた文化を持つ日本。力強く、順応性に満ちた日本。こうした日本を作り上げたのは、他ならぬ日本の自然なのだ・・・日本の水、日本の森、日本の海、日本の気候。そのほか、神が授けたもうたすべての自然の恵みなのだ。 だが、それも消滅しつつある。しかも、急速に。【中古】 TREE / 竹内 和世, 宮崎 駿, C・W・ニコル / 徳間書店 [文庫]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】価格:448円(税込、送料別) (2025/2/4時点)楽天で購入
2025.02.04
コメント(0)
-

なき人を霞める空にまがふるは道を隔つる心なるべし 西行
寄霞無常Geminiさんによる解説この歌も西行の作と伝えられています亡き人を偲ぶ心情を霞にかすむ空にたとえて詠んだ歌ですこの歌を現代語訳と解説を以下に示します現代語訳亡き人を霞がかかった空に見間違えるのはもう(会うことのできない)道が隔てられているからなのだろうか解説この歌は亡き人を偲ぶ切ない心情を美しい自然描写の中に表現しています「なき人」は亡くなった人を指し「霞める空」は霞がかかった空を指しています「まがふる」は「見間違える」という意味で亡き人の面影を霞にかすむ空に見ている様子を表しています「道を隔つる心なるべし」は「(もう会うことのできない)道が隔てられているからなのだろうか」という意味で会うことのできない悲しみを婉曲的に表現していますこの歌から読み取れるのは亡き人への切ない思慕の情です霞にかすむ空に亡き人の面影を重ねてしまうのはもう会うことのできない現実を受け入れられないからそれでも「道を隔つる心なるべし」と別れの現実を認めようとしている様子がより一層悲しみを深めているように感じられますこの歌は短い言葉の中に亡き人への切ない思いを凝縮した美しい歌ですChatGPTさんによる解説現代語訳亡き人を思うと霞のたなびく空にその姿が紛れて見えるけれどもそれは単に距離が隔たっているのではなく生と死の道が分かれてしまったためなのだろう解説1. 「なき人を霞める空にまがふるは」「なき人」=亡くなった人具体的な相手は不明ですが親しい人あるいは敬愛する人を指していると考えられます「霞める空にまがふる」霞がかった空の中にその姿があるように思われる「まがふる」は「紛れる」「見間違える」意春の霞の中に亡き人の姿が見えるような気がするという情景が浮かびます霞は向こう側がはっきりと見えないものの象徴であり「死後の世界と現世の境界」を暗示しているとも取れます2. 「道を隔つる心なるべし」「道を隔つる」道が隔たる生と死の境界がある「道」は単なる物理的な道ではなく生者と死者の歩む道の違いを指しています生者は現世を死者は彼岸の道を行くという仏教的な考え方が背景にある「心なるべし」その隔たりは心の持ちようによるのだろう「霞に亡き人の姿が見える」のは単なる幻想ではなく「心が隔たっている(=生と死が別の世界にある)」からなのだと気づく亡き人に会いたいという思いがある一方で「もう会えないという現実を受け入れざるを得ない心境」 も感じられますこの歌のテーマこの歌は亡き人への追慕の情を霞のイメージに重ねながら生者と死者の隔たりを静かに見つめる心境を詠んでいます🌿 ポイント「霞」死者の姿を幻視するほどの切ない思い「道を隔つる」生と死の道が違うことの自覚亡き人を思いながらも「もう会えない」現実を悟る境地西行の歌にはしばしば「霞」「空」「月」といった遠いものに亡き人の面影を重ねる表現が見られますこの歌も亡き人を思う心と悟りの境地との間で揺れる感情が滲んでいるように思えますClaudeさんによる解説この和歌も西行の深い感情と哲学的な思索が感じられる秀歌です「なき人を」亡くなった人または会えない人を意味します西行は僧侶でありながら世俗の感情や人間的な情感を深く詠む歌人として知られています「霞める空にまがふるは」霞で覆われた空つまり曖昧で不明瞭な景色に似ているという表現「まがふ」は紛れるまぎれるという意味で境界が曖昧になることを示しています「道を隔つる心なるべし」生者と死者または会えない人との間の隔たりを心の問題として捉えています「道を隔つ」は物理的な距離だけでなく精神的な隔たりも意味していますこの歌には西行独特の無常観や人生観が表れています亡くなった人や会えない人との距離を単なる物理的な距離ではなく霞のように曖昧で理解しがたい心の問題として昇華させています仏教的な無常の思想と人間的な情感が見事に融合した歌で故人への思いや人間存在の儚さを深く静かに表現しています西行らしい静謐で哲学的な感性が感じられる秀歌と言えるでしょうGrokさんによる解説この歌も西行の作品で亡くなった人に対する思いを詠んでいます以下に詳しく解説しますなき人を「なき人」は「亡くなった人」の意味でここでは「亡くなった愛する人」を指します霞める空に「霞める」は「霞む」の意味で「霞める空」は「霞んだ空」「霞がかかった空」のことですまがふるは「まがふる」は「まぎれる」「混ざる」の意味で「まがふるは」は「まぎれるのは」の意味です道を隔つる「道を隔つる」は「道が隔てられる」「道が分かれる」の意味でここでは比喩的に「生と死の道が分かれる」ことを指しています心なるべし「心」は「心情」「心の状態」を指し「なるべし」は「そうであるべきだ」「そうだろう」という推量の意味です「心なるべし」は「それが心の状態であるべきだ」「それは心の問題だろう」という意味ですこの歌は亡くなった人を想う気持ちが霞んだ空にその人の存在が混ざり込むかのように感じられることを詠んでいますそしてそのような錯覚や感覚は生と死が分かれているという現実と自分の心の距離感つまり「道を隔つる心」から来るものであると考えることを示していますここには亡くなった人に対する切ない思いとその思いが自然現象や風景に投影される心象風景が描かれています西行は亡くなった人への想いが現実と幻想のはざまで揺れ動く複雑な感情を詩的に表現していますこの歌からは愛する者を失う悲しみとその悲しみが自然や時間とどのように交差するかという深い思索が感じられます西行全歌集 (岩波文庫 黄23-2) [ 西行 ]価格:1,507円(税込、送料無料) (2025/2/4時点)楽天で購入
2025.02.04
コメント(0)
-

月を見る心のふしを咎にして便りえがほに濡るゝ袖哉 西行
月Geminiさんによる解説この歌は西行の『山家集』に収録されています月を見ることで心が乱れることを嘆きその涙で袖を濡らしている様子を詠んだ歌ですこの歌を現代語訳と解説を以下に示します現代語訳月を見ることで心が乱れることを咎めて(悲しんでいると)手紙の返事を期待する気持ちで袖が濡れてしまうことだ解説この歌は月を見ることで心が乱れることを悲しみその悲しみから手紙の返事を期待する気持ちが生まれる様子を詠んでいます「心のふし」は心の節心の奥底にある感情を指しています「咎にして」は「咎めて」と解釈できここでは月を見ることで心が乱れることを悲しんでいることを表しています「便りえがほ」は手紙の返事を期待する気持ちを指しています「濡るゝ袖」は涙で濡れた袖を表していますこの歌から読み取れるのは月を見ることで心が乱れることへの悲しみとそこから生まれる手紙への期待という複雑な感情です月は古くから人の心を惑わす存在として和歌に詠まれてきましたこの歌も月を見ることで心が乱れる様子を描写しその感情を手紙への期待という形で表現していますこの歌は短い言葉の中に複雑な感情を繊細に表現した美しい歌ですChatGPTさんによる解説現代語訳月を見つめる自分の心のありようをとがめるように思われてしまいその誤解を解くすべもなくわずかなつながりを頼りにしていたのにそれも叶わず涙に袖を濡らしていることだ解説1. 「月を見る心のふしを咎にして」「月を見る心のふし」月を眺めながら思いにふける心のありよう「ふし」は「節」のことで心の傾き思いのありようを指しますここでは月を見て恋しい人を思う気持ちとも取れますし何か深い物思いに沈む様子とも解釈できます「咎にして」罪のように見なされる月を眺めているだけなのにそれがとがめられてしまうというニュアンスがありますこれは「月を見ている=他の誰か(あるいは過去)を思っている」と誤解された可能性も考えられます2. 「便りえがほに濡るゝ袖哉」「便りえがほ」頼みにしていたわずかな縁やつながり「便り」は文字通り「手紙」や「訪れ」の意味もありますがここでは広く「相手とのつながり」を指していると考えられます「えがほ」「得顔(えがお)」のことで何かを得たような気持ちになることつまり「かすかな頼りを得られそうだと思っていたのに」という意味になります「濡るゝ袖哉」涙で袖が濡れてしまう期待していた「便り」や「つながり」が叶わなかったため涙にくれる様子「月を見る心のふし」が「咎められた」ことで誤解され関係が悪くなったのかもしれません歌のテーマと解釈この歌は西行が月を眺めることで何らかの誤解を招き大切なつながりが絶たれてしまい悲しみに沈む様子を詠んでいると考えられます💡 解釈のポイント「月を見る心のふし」物思いに沈む心(恋愛かもしれないし、深い哲学的思索かもしれない)それが「咎められた」周囲の人に誤解された(恋人か、あるいは社会との関係か)「便りえがほ」わずかな望みを持っていたが、それが叶わなかった結果として「袖を濡らす」涙に暮れる→ 無実の罪や誤解によるすれ違い孤独を感じる歌とも読める仏教的な無常観との関係西行は世の中の誤解や人間関係の儚さを仏教的な視点からも見ていたはずですこの歌も単なる恋の歌ではなく**「人は分かり合えない」**という無常観を含んでいるのではないでしょうか「月」はしばしば真理の象徴とされるため西行が「月を見ているだけ」で誤解されるのは「自分が何を思おうと、他人は勝手に解釈し、誤解する」という人間の世の常 を示しているようにも感じられますまとめ🌙 月を見つめることが誤解を招き頼みとしていたつながりも断たれ涙に暮れる という切ない歌💔 誤解される悲しみ と思いが届かないことへの諦め が込められている🪷 仏教的な無常観 にも通じる世の中のままならなさを詠んだ一首とても西行らしい静かな悲しみが滲む歌ですねClaudeさんによる解説この和歌も西行法師の名歌の一つですね恋心や情感を繊細に詠んだ歌です一句ずつ解説します「月を見る心のふしを咎にして」月を見つめる自分の心の動きや気持ちをまるで罪のように責められているような表現です「心のふし」は心の中の微妙な感情の揺れや機微を意味します「咎(とが)」は非難、罪、とがめるという意味です「便りえがほに濡るゝ袖哉」「便り」は手紙や消息情報という意味「えがほ」は笑顔嬉しそうな表情を指します「濡るゝ袖」は涙で濡れた袖を意味します全体として恋心を抱きながらもその感情を笑顔で隠そうとするものの結局は涙で袖を濡らしてしまう心情を詠んでいます月を見ることで呼び起こされる恋心やその感情を抑えきれない微妙な心の揺れが見事に表現されています表面的には笑顔を作りながらも内心は深い感情に揺さぶられている様子が濡れた袖というイメージによって象徴的に描かれています西行特有の繊細で奥深い心情表現が光る秀歌と言えるでしょう恋や思いを直接的に述べるのではなく月や袖という間接的な表現を通じて深い感情を見事に詠み込んでいますGrokさんによる解説この歌も西行の作品で月の美しさを見ることとそれに伴う感情の動きを詠んでいます以下に詳しく解説します月を見る心のふしを「月を見る」は「月を見る行為」「心のふし」は「心の節」や「心の複雑さ」を指します「ふし」は「節」「節目」「複雑な部分」の意味でここでは「心の深いところ」や「心の微妙な動き」を示していると考えられます咎にして「咎に」は「罪に」「非難する」の意味で「して」は「する」の連用形です「咎にして」は「それを非難して」「それを罪に感じて」という意味になります便りえがほに「便り」は「便り」「知らせ」の意味で「えがほ」は「笑顔」や「微笑み」を指します「便りえがほに」は「便り(知らせ)があるときの笑顔」を示しますがここでは比喩的に「何かを知り喜ぶ心の状態」を指している可能性があります濡るゝ袖哉「濡るゝ」は「濡れる」の意味で「袖」は「袖口」を指します「濡るゝ袖」は「袖が濡れる」つまり「涙を流す」ことを表しています「哉」は感嘆の終助詞で「濡るゝ袖哉」は「袖が濡れることを感嘆する」という意味ですこの歌は月を見ることで起こる心の微妙な動きや複雑さをまるでそれが非難されるようなものとして詠んでいますしかしその深い感情の揺れ動きは知らせを受けた時のような笑顔に繋がり最終的には感動や涙によって袖が濡れるという美しい情景へと展開しますここには自然の美しさ(特に月)が人間の感情や内面に与える影響そしてその感情の豊かさや複雑さに対する西行の深い理解と共感が描かれています自然の美しさに触れることで人間がどう感動し涙するのかというテーマが詩的に表現されていますこの歌からは自然と人間の感情の深い結びつきそして自然から得られる感動や哀しみ喜びの複雑な感情が感じられます西行全歌集 (岩波文庫 黄23-2) [ 西行 ]価格:1,507円(税込、送料無料) (2025/2/4時点)楽天で購入
2025.02.04
コメント(0)
-

7つの習慣 スティーブン・R・コヴィー ジェームス・J・スキナー 川西茂 キングベアー出版
歴史から学べる最も大切な教訓のひとつは、個人にしても、組織にしても、また文明そのものにしても、「効果性」を司る不変の原則または自然の法則と調和した行動をとるとき、必ず長期において繁栄しているということです。完訳7つの習慣 30周年記念版 [ スティーブ・R.コヴィー ]価格:2,420円(税込、送料無料) (2025/2/2時点)楽天で購入
2025.02.02
コメント(0)
-

ねずさんの日本の心で読み解く百人一首 五十番歌 小名木善行 彩雲出版
君がため惜しからざりし命さへ長くもがなと思ひけるかな藤原義孝愛する人のために【POD】ねずさんの 日本の心で読み解く「百人一首」 [ 小名木善行 ]価格:3,806円(税込、送料無料) (2025/2/2時点)楽天で購入
2025.02.02
コメント(0)
-

日本霊性論 内田樹 釈徹宗 NHK出版新書
数値として検知されるのは、ある種の計測機器の測定できる変化だけです。計測機器の精度では感知できない変化は機械ではなく人間が感知するしかない。当たり前のことです。人間というのは実にいろいろなことがわかるんです。重大な危機を予知することくらいできる。機械にはできないことが人間にはできる。日本霊性論 (NHK出版新書) [ 内田樹 ]価格:946円(税込、送料無料) (2025/2/2時点)楽天で購入
2025.02.02
コメント(0)
-

心の病に薬はいらない! 再々 内海聡 かんき出版
人間は「知る」という能力に限界がありません。記憶力に限界があったとしても、好奇心や理解力に限界はないのです。しかし人間ほどに自分が信じてしまったものを捨て去るのが難しい生物は他にいないでしょう。本能や生存心よりも刷り込まれたものにすがるのが人間なのです。 教育、勉強というのは最大の修行です。誤解を恐れず言えば、幼少期に自ら学ぶことの重要性がどれだけ身につけられたかで、勝負が決まっているといっても過言ではありません。厳しすぎても優しすぎてもダメであり、近年の教育はまったく人間を強くするための教育とは言えないようです。心の病に薬はいらない!【電子書籍】[ 内海聡 ]価格:1,584円 (2025/2/2時点)楽天で購入
2025.02.02
コメント(0)
-

777 再々 伊坂幸太郎 角川書店
良くも悪くも、日本の政治家はみんないい人です。中途半端に、いい人なんですよ。敵か味方かに分類して、味方には利益を還元する。敵の揚げ足を取り、敵の追求をあしらう。同じようなことを延々と繰り返すだけです。本当につまらないことしか考えていないんです。777 トリプルセブン [ 伊坂 幸太郎 ]価格:1,870円(税込、送料無料) (2025/2/2時点)楽天で購入
2025.02.02
コメント(0)
全46件 (46件中 1-46件目)
1
-
-

- 入浴後の体重
- 2025/06/30(月)・06月「0・7増」…
- (2025-06-30 17:00:00)
-
-
-
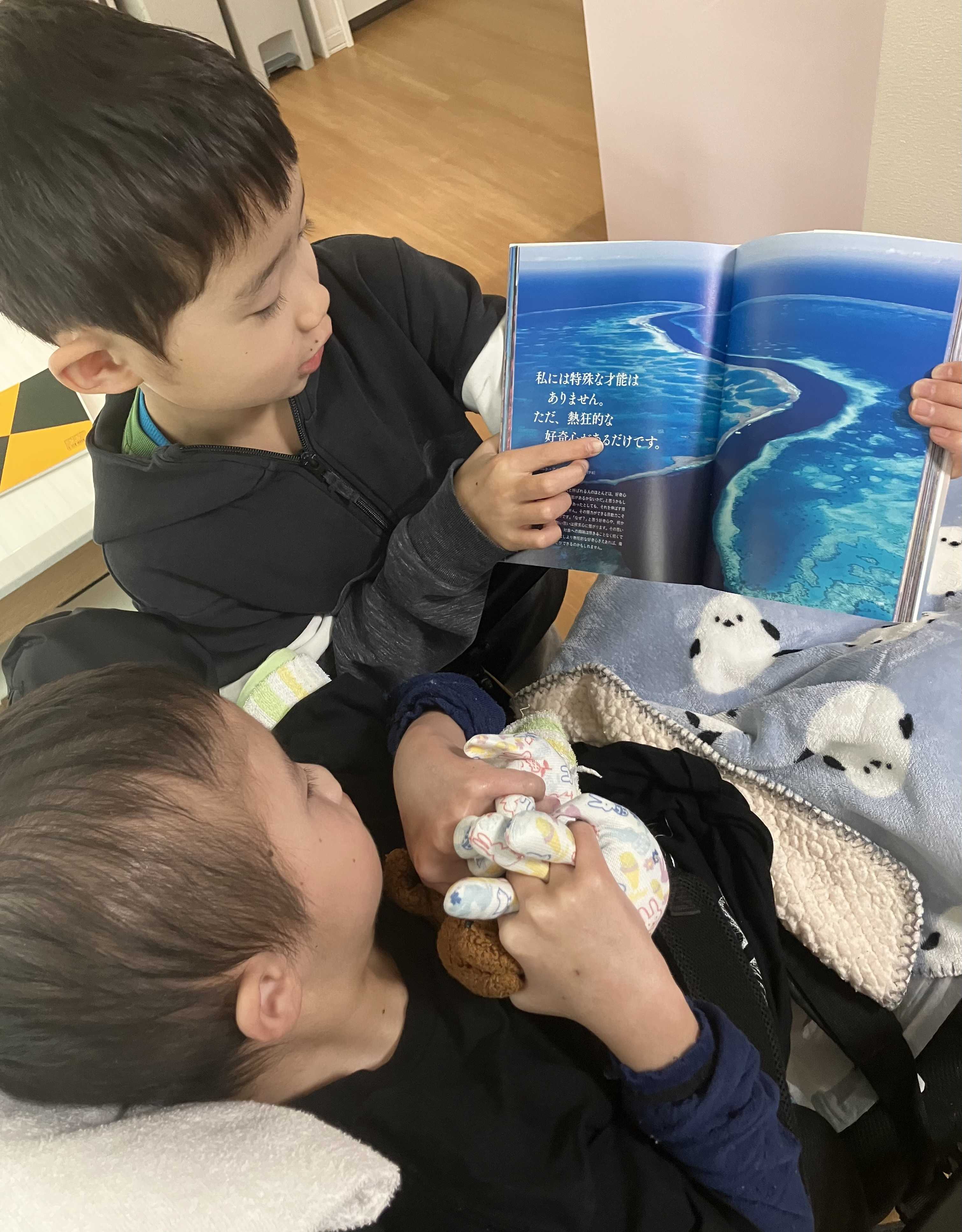
- 闘病記
- 長男🐻おうちでゆっくり😌(在宅2日目)
- (2025-11-23 12:00:06)
-
-
-

- 今日の体重
- 2025/11/23(日・祝)・=勤労感謝の…
- (2025-11-23 12:00:01)
-







