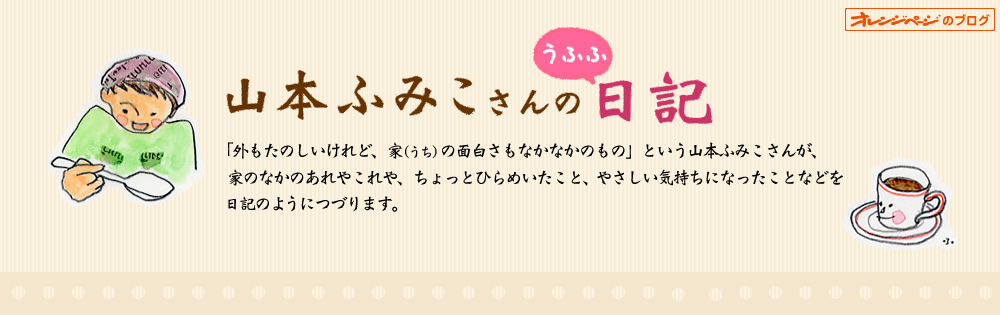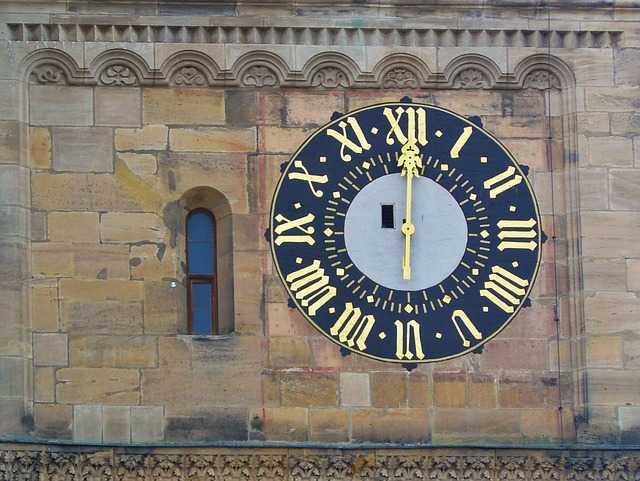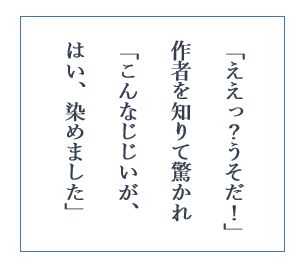2007年09月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-

「細部」の改善が、ちょっとしたテーマです。
「いいじゃない、そんな小さいことにこだわらなくってさ」 と、思うことがある。 ひとがひとを許せない、という話のとき、そんなふうに感じることがある。「めくじらを立てる」ということばもあって、それは、他人の欠点をさがしだす、という意味だけれど、同じことなら、欠点よりイイトコをさがしたほうが気持ちがいいだろう、と思う。 しかし。 これが家のなかのこととなると、話がちょっと変わる。 家のなかに、ちょっと気になるところ——欠点といえば、欠点かな——というのが、ある。誰にでも、あるのじゃないだろうか。 畳を板の間にかえたい、とか、キッチンをとり換えたい、とか、そういう話じゃない。うちの「あれ」、ちょっと使いにくい、とか。「あそこ」がこうなってたらいいのにというくらいのこと。 ひととひとの関係には、あんまり「めくじら」立てないほうがいいと考えるわたしだけど、家のなかのこととなると、細部が大事だなあと思わされる。 日日そこに暮らし、そこで働くわけなので、小さい部分の不具合が身にこたえる。 先日、こんなことがあった。 冷蔵庫の扉の内ポケットから、煎りゴマの入った瓶をとり出そうとして、おとなりの七味唐辛子の筒をひっかけ、床に落としてしまった。落としたのは、このときが初めてだったが、これまでも、煎りゴマ氏を呼びだすたび、七味唐辛子、一味唐辛子、山椒諸氏をなぎ倒し迷惑をかけてきた。 煎りゴマ氏は出番も多いので、呼びだすたび、なんとかならないものかなあ、と思っていた。 その日はめずらしく、頭が澄んでいたようだ。 ふと、煎りゴマ氏をもうひとまわり大きい瓶に入れておけば、煎りゴマ氏が働きに出たあと、七味、一味、山椒さんたちに迷惑をかけることもないわけだ、と心づく。空き瓶をためておく棚をさがすと、調度よさそうなのが、あった、あった。 瓶をもうひとつ瓶に収め、「いままで、すみませんでしたね。これからは、煎りゴマ氏不在のときにも、すっきり立っていていただけますから」と七味、一味、山椒各氏に、挨拶。 うふふ、なかなか、いい具合。 こんなことが、どうしてこうもうれしいんだろう、と思う。 持ち上げているのが、煎りゴマ。となりの「七」:七味唐辛子、「一」:一味唐辛子、「山」:山椒です。
2007/09/28
コメント(1)
-

けんちゃんは、はたらき者です。
けんちゃんがうちにやってきたのは、5年前のクリスマスだった。 サンタクロースに手をひかれて、きた。 けんちゃんってのは、食器洗い乾燥機。 夫が、クリスマスにプレゼントしてくれたのだ。あと片づけを手伝ってくれる手をひとつ贈られたようで、とてもうれしかったが、「またか」とみじかくため息もつく。 夫から、初めて贈られた誕生日プレゼントは、「かつおぶしけずり」だった。木屋製の、じつにいい「かつおぶしけずり」だったが、わたしはおおいに面食らった。なにせ、初めての誕生日プレゼントだ。小さなアクセサリーとか、ハンドバックとか、なんというかもうちょっと甘美なものでもいいんじゃないか、とね。 つぎの誕生日には、前からほしかった風変わりな植木鉢をもらった。 そのつぎの年は……、まあ、いいや。 この話を友だちにうち明けると、「そりゃ、ちょっとやだね」というひとと、「いいじゃない、実直な品。へんてこなアクセサリーやスカーフもらったりしたら、目も当てられないわよ」というひとと、意見はふたつに割れる。 けんちゃん。 家につくなり、彼は、どんどんはたらいてくれた。 食事のあとにゆとりが生まれたような気がして、うれしかった。しかし、それにも慣れると、「洗い上がったら、それぞれ、自分でけんちゃんから出て、食器棚の定位置にもどってくれるといいんだけどな、と思うようになったりする。いやはや感謝知らずの女である。 けんちゃんの仕事がすみ、わたしが洗い上がった食器をとり出して片づけるまでは、けんちゃんには何も入れられない。ここのところが、不都合といえば、ちょっと不都合だ。 あるとき。 システムキッチンのパンフレットを見るともなく見ていた。すると、食器洗い乾燥機が上下に2台ついたキッチンの写真があるではないか。いつでも洗い物を引き受けられるシステムなんだそうだ。貧乏性のわたしは、ちょっと、ぜいたく過ぎやしないか、と思う。 とにかく、けんちゃんのおかげで、わたしはやっぱりずいぶん楽をさせてもらっている。 どうしてけんちゃんという名前か、って? まだけんちゃんの影もないころ、そうして、娘たちがいまより5、6歳若かったころのこと。 晩ごはんのあと、食器を洗いながら、ふと、(娘たちのうちの誰かに彼氏ができたら、食器洗いを手伝ってくれたりするだろうか) と思いつき、それを入口に、妄想の森へと歩みだす。(食器は洗わないけど、食器を洗うおかあさんのそばで、歌をうたいますよ、なんていうのもいいねえ。くくくくく) そこで、ラジオから流れてきたのが、「平井堅」うたう「大きな古時計」。(ああ。手伝ってくれなくっても、こんなふうに近くで歌ってくれたら、うれしいかも……) しかし、あと片づけを手伝ってくれそうな彼氏も、わたしの横で歌ってくれそうな彼氏もなかなか登場しないうちに、食器洗い乾燥機がやってきた。 かの日、食器を洗いながらうっとり聴きほれた「平井堅」の歌声にちなんで、「けんちゃん」と命名。 けんちゃん、毎日、ありがとうね。きょうは、わたしが何か、歌ってあげるよ。 けんちゃんです。けんちゃんの前には、けんちゃん稼働中に出た「使用済み食器」を、手で洗ってのせておく小さな棚があります。何もかも、けんちゃんに洗てもらおうしないで、このごろは、わたしも洗うんです。 けんちゃんの下(流しの奥)には、手を洗うせっけん、金だわし、スポンジがいます。
2007/09/21
コメント(2)
-

絵はがきを、つくりました。
ちょっと忙しいことが重なっても、「食べる」と「眠る」に関する時間だけは、確保(死守かな)しようとする。忙しいぞ、というとき、仕事をがんばろう!という気概よりも、よく食べ、よくよく眠るぞ、という決心のほうが幅を利かせているような。 少しくらい忙しくっても、じゅうぶんに食べ、じゅうにぶんに眠っているから、日日の暮らしにはあんまりしわ寄せがこない。ような気がしている。 しかし、先日。 ついに、しわ寄せ=しわのたまり場を発見。 それは、書棚にかけた小さな黒板の隅っこの、いただいたお手紙返事や、便りを書きたい、または書かないといけない方方のお名前のつらなり。 これこそは、日日のしわ寄せだわ、と思わされ、深深とため息をつく。 もともと、ペンをもって字を書いたり、下手な絵を描くのは好きなのだ。はがきを書きだせば、どんどん書ける。書いているうちに、だんだん楽しくなってきて、「メールなんかより、ずっといいなあ、はがきはね」と、ひとりごとを言ったりする。 けれども、ひとたび余裕をなくすると、だ。はがきに手がのびない。はがきを書くためのペンや色鉛筆を、見て見ぬふり。いただいて、梨のつぶての書状にいたっては、視界に入らなくなる。 仕事をして、家のことをして、家族にむかってにっこりして、料理して、食べて、眠って、日が過ぎていく……。ああ、きょうもまた、はがき1枚書けなかった。やれやれ。 わたしね、便せんはあんまり使わない。 和紙や、昔ながらのうつくしい紙の便せんも、少しは持っている。いちばん最近、便せんをひきだしの奥からひっぱり出したののは、半年ほど前。 娘の大学の教授に宛てて、家の用事で試験日に東京にいられず、できれば再試験を受けさせてやっていただきたい、という嘆願の書状をしたためたときだった——教授から、保護者からの手紙が必要だとお達しがある——。こうしてみると、便せんの登場は、あんまりよく知らないえらいひとに、慇懃な手紙を書くときになるようだ。 たいていは、はがきサイズの紙に、書く。 目上の方に書く場合と、書ききれないときには、裏表に書き、封筒におさめて投函する。はがき1枚書き上がると、玄関のげた箱の上に、置きにいく。ここが、家のポスト=「出がけに、ポストの投函してくださいね」のコーナーだからなのだが、このときの気持ちは、達成感と呼んでもいいと思う。 はがきを書くのはきらいではないのに。 いや、むしろ楽しみと言ってしまってもいいほどなのに、取っつきがわるいのはなぜだろう。 もしかしたら……。 はがきを書くとき、字も書いて、絵も描く、という両方をするのことが、かさ張っているのかもしれない。それなら、時間のあるとき、絵ばかりを描いておこう。 そういうわけで、きょうは、どしどし、絵はがきをつくった。愉快。 こんなことせずに、かわいいポストカードを買いだめしたりすればいいのにね。そう思いつつ、絵も描きたくなってしまうのです。色紙や新聞紙をちぎったりして、貼り絵にすることもあります。相手の贔屓の役者や、タレントの写真を切り抜いておき、貼りつけると、喜ばれること請け合い。
2007/09/14
コメント(1)
-

石が、活躍しています。
山や川に行くと、石が気になる。 気になって眺めているうち、たくさんの石のなかから、とっても気になる石がみつかって、またじっと見る。拾って、てのひらにのせ、感触をたしかめる。 そんな自分を、このごろ「石泥棒」かもしれないと、思いはじめている。 自然界の石には、ひとつひとつ存在理由があり、それより前に石が生じた理由もあるのだと思う。こういう石を、持ってきてしまうのは、いけないじゃないだろうか。「ね、石って、山や川から持って来ちゃっても、いいもの?」 そう友だちに尋ねると、たいてい、「少しならいいんじゃない?」 という答え。「石、拾うとき、罪の意識におののかない?」 の質問には、「おののかないよ。拾わないもの」 という答え。 そうか、みんなはあんまり拾わないのね。そこで、1つめの質問の答え:「少しならいいんじゃない?」を頼みとし、このごろは、いちどきに1個だけいただくようにしている。 玄関の火打ち石。 正確には、火打ち石のはたらきをする石ころだ。これは、もう15年ほど前に伊豆・今井浜の海岸で拾ったもの。 玄関から、家の者たちが出かけるとき——訪ねてきてくれたひとが帰るときにも、つい——「いってらっしゃい」と言いながら、肩先でふたつの石を打ち合わせる。夫も子どもも、これを「かちかち」と呼び、誰かが出かけようとするとき、「わたしが、かちかちするね」などとと言ったりする。 かちかちだなんて。かちかち山みたいだ。 いまでも、職人、芸人、あるいは危険な仕事に就くひとびとのおかみさんが、火打ち石の切り火で送りだす習慣が生きているという。相手の無事は、祈るほか手だてはないが、出がけに、火打ち石で威勢よく送りだすというのは、そこから1歩、前に踏みだす行為のような気がする。相手のためにできることの、ぎりぎりの線まで。 さて、約1年前、3階建ての、縦にひょろ長いこの家に越してきたとき、この「かちかち」に変化が生じた。誰かが出かける気配を追って、2階(台所も居間も、わたしの部屋も、みんな2階にある)から駆け降りても、「まだ行かない、ちょっと髪とかしてから」「電話、1本かけてから」など、タイミングがずれるのだ。そのたび、2階に戻り、また駆け降りて……。運動にはなるかもしれないが、わたしには、途切れさせたくない仕事だってある。 そこで、昨年、千葉県を旅したとき、拾った石を2階用の火打ち石とすることにした。2階の居間のあたりで「いってらっしゃい」と言い、かちかちする。インチキのようだが、インチキでもなんでも、かちかちやらないことには落ち着かなくなってしまったのだから、仕方ない。 玄関で、子どもを送りだす。かちかち。 これが、玄関の火打ち石です。長年、かちかちやってたら、少し、やせてきました。 2階の、火打ち石。居間の入口の、ピアノの上に置いてあります。 レースのカーテンが、風でめくれないように、重石としてカーテンの裾に石ころを入れています。
2007/09/11
コメント(0)
-

「これ、ちょっといいねえ」と、評判のいい鍋ラックです。
この夏は、お客さんが多かった。 とくに、女のお客さん。 なんだかんだと食べるもの、飲むものを持ちよって、おおいに飲み、食べて、うんとこさ話をする。 「友だちの家に遊びに行くより、友だちが遊びに来てくれるほうが、ずっと多いな」 と、末の子が言う。「へえ。わたしも、そうだよ。来てくれるのを迎えるほうがずっと多い」 そう言うと、末の子があはは、と笑う。「お母さんが、誰かが家に来るの、好きだから、友だちが来てくれるんだよ。うちの友だちも、お母さんの友だちも」「好きなのかな、わたし」「きらいじゃないでしょう」 そうか、と思う。 だけどね、これでも、おひとが来てくれるということになると、やっぱり、ちょっとは身構えるのよ。と、言いたくなる。 身構えて……、まず何をするかというと、掃除(大掃除なんかはしない、ちょっと、するだけ)。そのつぎは……。食べてもらうもの(=つくるもの)を決める。 あれー? これだけで、もう「これで、みんなを待つばかり」という気持ちになっているみたい。 掃除、も、ちょっと。 食べてもらう、も、ふだんうちで食べているものを、いつもより多めにこしらえるだけ。 おひとを迎えるときの心がけは、きどらないこと。きどっても、すぐ底が割れる。 話は脱線したが、この夏のお客さんたちに、評判がよかったのが、食卓の脇にある鍋ラック。ほんとうなら、台所に納めたいところだが、納まらなかった。 この、言ってみれば、はぐれ者たちが、なぜか目を引く。「これ、いいねえ。どこで買ったの? もうちょっと背の低いのも、あった?」 とか。「道具が陳列してあるっていうの、いいわよ」 とかね。 わたしは、実直でうつくしい道具が好きだ。 なるべく、そういうものを選びたい、と思っている。現に、収納せずに見せちゃおう、という置き方(密かに、「飾り置き」と呼んでいる)をしている道具もある。 そうは言っても、飾るにはふさわしくないモノも少なくはない。そういうモノたちは、「隠し置き」にする。「隠し置き」と「飾り置き」を使いわけると、収納は、案外うまくいく。 「飾り置き」。これが、うわさの鍋ラックです。ラック下に、いちご(うちの黒猫)に午後4時に出してやる、缶詰めのごはんの容器があります。ちょっと時間が過ぎると、この容器を、指さすような仕草。そんなときは、「いま、あげようと、思ってたのよ」と言いわけしながら、よそいます。水も、いちごの飲み水。 「隠し置き」。義母が、嫁入り道具として持ってきたという火鉢。このなかには、ごちゃごちゃとモノ(イヤホン。ちょっとのあいだ、とっておきたいチラシ。へんな色のメトロノーム。へんな色のえんぴつ削り器)が隠してあります。
2007/09/04
コメント(4)
全5件 (5件中 1-5件目)
1