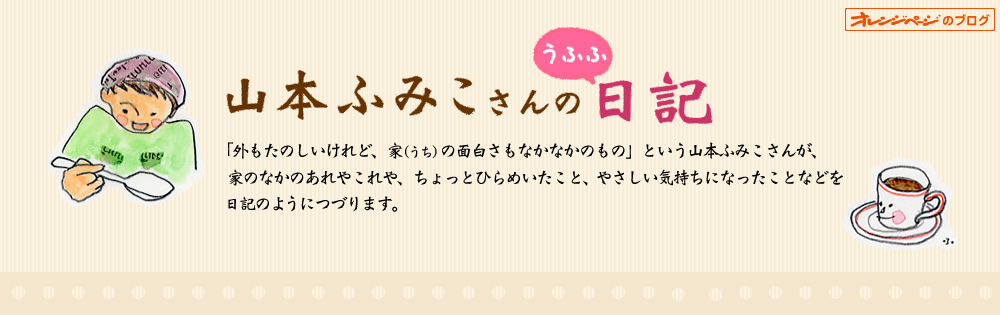2007年12月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-

結局、大掃除はしないのでした。
大掃除、大掃除、と、うかれるように言うひとが多いのには、驚かされる。 「お祭りみたいだね。大掃除、好きなの?」 と、友だちに尋ねたことがある。「掃除はきらいだけどね、大掃除は、好きかな。家の者たちもみーんな働かせて、1年分の掃除をするつもりでやるの」 掃除はきらい。 大掃除は好き。 家の者たちを働かせる。 1年分の掃除をする。 というコトバが、頭のなかでぐるぐるまわる。 掃除がきらい、というのはわかる。わたしもきらいだからさ、共感する。「大掃除は、好きかな」ってね、アナタ。それ、なによ。掃除がきらいなのに、いっぺんにいっぱい掃除するのが好きというの、ひどく矛盾しないか? 自棄(やけ)ですか? 家の者たちを働かせる——みんな、アナタの計画する大掃除の1から10につきあうんだろうか。 1年分の掃除をする——それは、無理だー。 祭り気分で燃えてるひとに向かって、身も蓋もないことを書きつらねてしまったが……どんなに誘われたって、わたしは、大掃除はしたくない。 ひねくれているので、大勢のひとたちがせっせと働いている時期に、へらへらしていたい、という気持ちもある。けれど、それだけじゃ、ない。 そろそろ今年の仕事に限(きり)のつきそうないまになって、わたしは、はたきにも手をのばさず、雑巾もしぼらず。やおら本棚から、時間ができたら読もうと決めていた本をとり出した。『モモ』。——時間どろぼうとぬすまれた時間を人間にとりかえしてくれた女の子のふしぎな物語。 いま現在、3分の1ほどまで読んだ。何度も読みたい本というのは、共通して、読むたびに初めて読むような気持ちにさせられる。『モモ』の場合は、読むたび、自分と時間とのかかわり方が変化しているからでもあるだろう。 この本にでてくる、モモの親友・道路掃除夫ベッポがこんなことを言う場面がある。 「なあ、モモ、」と彼はたとえばこんなふうに始めます。「とっても長い道 路を受けもつことがよくあるんだ。おっそろしく長くて、これじゃとても やりきれない、こう思ってしまう。」 彼はしばらく口をつぐんで、じっとまえのほうを見ていますが、やがて またつづけます。 「そこでせかせかと働きだす。どんどんスピードをあげてゆく。ときどき 目をあげて見るんだが、いつ見てものこりの道路はちっともへっていない。 だからもっとすごいいきおいで働きまくる。心配でたまらないんだ。そし てしまいには息が切れて、動けなくなってしまう。こういうやりかたは、 いかんのだ。」 ここで彼はしばらく考えこみます。それからやおらさきをつづけます。 「いちどに道路ぜんぶのことを考えてはいかん、わかるかな? つぎの一 歩のことだけ、つぎのひと呼吸(いき)のことだけ、つぎのひとはきのこ とだけを考えるんだ。いつもただつぎのことだけをな。」 わたしが、大掃除をしない理由はこれだー!と、叫んでしまった。 わたしは、つぎの1歩、つぎのひと片づけ、つぎのひと拭きだけを考えながら、毎日きらいな掃除をするのが性に合ってる。 どうも、そういうことらしいのだ。 結局、きょう、ガラス拭きをすることにした。これは大掃除じゃ、ない。毎日のひと拭き。娘たちの部屋に、ボロ布とガラス拭きの洗剤をじゅんぐりに置く。こうしておくと、なんとはなしにガラス拭きをしてしまう、という具合なのだ。わたしがこうなんだから、家の者たちにも「つぎの1歩」、「つぎのひと片づけ」、「つぎのひと拭き」以上のことは、期待できない。 ※ 『モモ』(ミヒャエル・エンデ作 大島かおり訳/岩波書店) * 皆さん、佳い年をお迎えください。 つぎのブログの更新は、1月7日(月)です。お休みのあいだは「コメント欄」で、遊びたいと思います。よろしくお願いします。 おじぎ。 きょう最初の1歩。居間・東側の小窓を拭きました。置いてあるのは、友だちが韓国土産にくれた、織物に使う道具。「わあ〜」ひと目で気に入りました。こういういびつなモノが、好みです。大きな声ではいえませんが、もらった瞬間、「喧嘩したとき、これで、夫になぐりかからないようにしよう」と、密かにつよく誓ったことです。
2007/12/28
コメント(4)
-

「モノ」が「時間」を、誘惑!
することがたくさんあって、せっせと働く自分を、想像する(皆さんも!)。 そんなとき、決まって、「ああ、約束の時間までに、もう1時間多く時間があれば……」 と、思う。 最近わたしがこんなふうに思ったのは3日前。 突発の予定が入り、それに向かってひた走った(時間と競争)。机に向かいながら。洗濯ものをとりこみ、たたみながら。台所でごはんをつくりながら。「あ!」と気づいてふたたび机に向かいながら。「風呂掃除、たのむー」と、末娘を拝みながら。 とにかく、あせる・あせる。 あせっているこんなとき、モノがくゎっと、その存在を主張する。 それは道具の場合もあるし、器や器具のようなもの、装飾品、小物、消耗品という具合に、いろいろ、ある。つまり、わたしたちの持ちものを総称した、モノたち。 モノたちは、ときに、とっても助けになる。 モノたちは、ときに、わたしの邪魔をする。 つまり、モノに値打ちを吹き込むのは、わたし自身だということだ……。 助けになるモノは、・ 定位置で出番を待っているモノ。・ 手に馴染んだ(あるいは、目に馴染んだ)モノ。 邪魔をするモノは、・ しまい場所がわからなくなったモノ。・ やたらと数があって、みつけだせない目当てのモノ。・ 壊れたモノ。すでに寿命を終えたモノ。 邪魔をするモノは、わたしたちの時間を食べる。わしわしわしと、食べるのだ。探す時間。ちがうものを調達する時間。直す時間。「だめだー」とがっかりする時間。 モノは、ときどき悪女のようになって、時間を誘惑する。「たまには、ゆっくり遊んでいきなさいよ」 とか言って。 いや、無駄な時間がわるいばかりではない、わるくはないけれど、いまは大急ぎなんだ!という場面で、誘惑するのはやめてほしい。 モノをおかしな悪女にしないために、わたしたちがしたほうがいいこと。 それは——。 ・ モノの置き場所、しまい場所、つまり定位置を決める。・ たくさん持たない。・ たまには、手入れをする。 へんてこ棚をご紹介します。へんてこ棚は、居間の東南に、超厚型テレビをのせてすまして、坐っています。なかは、ほんとに雑多。「雑多だっていいんだー」と思っています。使う者たちさえ、わかっていれば……ね。 どう「へんてこ」で、何が「雑多」かと申しますと。正面7つのひきだし、上から——。1)皆がちょこちょこ使う文具 2)客用の箸(誰それさん専用の箸、というのもかなりある) 3)クスリ(内用) 4)クスリ(外用)5)髪関係(櫛、ピン、ゴム) 6)弁当包み 7)巾着袋、ミニタオル(おしぼり用)。 ね、取留めのない収納でしょう? この取留めのなさがへんてこな由縁、そして、収納を気楽にさせてくれます。 上から5番めのひきだしは、髪の小物のキーステーション。髪の小物は、家じゅうに散らばる、ちょっとイヤなモノたち。ひきだし下に写っているのは、浴室となりの脱衣所に置いてある、ピンとゴムの容れもの。そのほか、こんな箱(それぞれピン用、ゴム用あり)が、髪の長い上ふたりの子どもの部屋にもあります。この箱のおかげで、髪の小物にわずらわされなくなりました。 へんてこ棚、向かって左側は、こんなふうに開きになっています。ここは、もうほんとうにあれやこれやです。香辛料、黒粒こしょう・白粒こしょうがあるかと思うと、救急絆創膏、フウセンカズラの種あり……。小さな空き瓶や、爪楊枝の在庫も置いてあります。 へんてこ棚、うしろ側です。上段にあるのは、升(ます/これで日本酒を飲むのが趣味)。下段左から、小豆、白ごま、黒ごま、「ジェンガ」(木製のゲーム)です。ハエたたきや「S字」も、こんなところで出番を待っています。
2007/12/25
コメント(3)
-

これが、皿まわし——山本の、ある1日です。
きょうは、ちょいと忙しかった……。 気分は、すっかり「皿まわし」。 長い軸のようなものに、つぎつぎ皿をまわしながらのせていく。皿を落として割らずに、まわしつづけられたら、拍手ご喝采! ほんとにやってみたら、1枚としてまわせはしないとわかってはいても、イメージは、すっかりね。皿まわし——山本。 本日、 1枚めの皿——2人分の弁当づくり。 2枚めの皿——5人分の朝ごはんづくり。 3枚めの皿——洗濯。 4枚めの皿——アイロンかけ。 5枚めの皿——ブログのための撮影(共有の衣類の戸棚の写真を撮る)。 6枚めの皿——本日〆切のエッセイ(新聞)を書く。 7枚めの皿——夫の昼ごはんをつくる。 (ブログの撮影で世話になったので、ちょっとがんばる/ご 飯、ビーフン、かぶと生ハムのサラダ、ほうれんそうのか らし和え、だし巻き卵、柿、玄米茶) 8枚めの皿——本日〆切のエッセイ(月刊誌)を書く。 9枚めの皿——掃除機をかける。10枚めの皿——小さなさし絵を1枚描いて、郵送。11枚めの皿——メールを3本書いて、送る。12枚めの皿——末の子とその友だち4人の宿題を監視(?)+おやつ。 (おやつ/海苔もち、安倍川もち、柿、玄米茶)13枚めの皿——単行本の原稿を書く。14枚めの皿——洗濯ものをとり込み、たたんで、仕舞う。 15枚めの皿——このブログを書く。 こう書くと、すべてが順調みたいにみえるけれど、8枚めの皿のところでは、頭をかきむしった。「ああ、何、書こうー。う・う・う・うー」 頭が空っぽだったので、よろよろと台所に逃げだし、自分を励ます意味でラーメンをつくって、食べたりした。〆切の日に原稿を書くのはよそう、と約250回めの誓いを立てる。 さて、このあと——。 16枚めの皿は、きっと晩ごはんづくりになり、17枚めで洗濯と入浴、18枚で晩ごはん。19枚め、洗濯もの干しと後かたづけ。20枚めあたりで、もう寝ちゃっていると思う。 あれ、なんの話だったけ。 そうそう。 ちょっとせわしない、きょうのような日、ふと、自分のなかにシンプルで、究極的な問いが生まれることがある。そんなこと、時間があるときに思いつこうよ、というような問いだ。 ヒトが等しく与えられているもちもののなかで……、 わたしが、いちばん大事にしているものは、何か。 「時間かな」。 わたしの時間は、ほとんど毎日、ご覧のように細切れになる。 ものを書く人間としたら、時間を細切れにせずにできるだけ長いこと集中して机に向かっているのが望ましい。と、いう考え方もあるだろう。 母ちゃんとしたって、学校から帰ってくる子どもを迎えられるのはいい、だけど、おやつを出して、ちょっと宿題に口をだしたかと思うと、また仕事部屋にこもってしまうのなんかは、ちょっとへんてこなのかもしれない。 しかし、時間が細切れになることには慣れた。 はじめから、細切れを望んで、居職の生活を選んだといってもいいと思う。 時間と、わたし。 ときには、「さて、どう折り合いをつけるか」というほど抜き差しならぬ場面もめぐってくる。 どんな日も、このことだけは、大まじめに考えている。 きょうひとひ、時間とどうつきあうか。 皿まわしのお仲間の皆さんへ。 この話のつづきは、来週火曜日に。 「皿まわし」に因んで、ちょっと重宝している皿をご紹介します。この四角いのは、「置いとくごはん」用の皿です(全6セット)。一緒にごはんの食卓につけないひとのための……。定食のように、盛りつけて、別に、ご飯と汁ものを置いておきます。こういう区切りがあると、ごはんの準備がしやすいし、ままごとのようで、楽しい、です。——ままごとだなんてね、変かな。 これは、朝ごはん用の皿です(全5セット)。純和食のときには、使いませんが、ここにご飯を盛りつけて、おかずを添えたり。まんなかに野菜と、ベーコンエッグを盛りつけて、パンを添えたり。目先を変えながら、朝ごはんを準備しています。とにかく、ここに味噌汁がつくのが、約束です。いいんだそうですね。この皿たちは、食器棚とは別の、台所のひきだしが置き場所です。そこが、いちばんとり出しやすい場所なのです。
2007/12/18
コメント(4)
-

「衣」も、一部「共有」しています。
寒くなってきたので、あたたかい下着を買い足すことにする。 いわゆる「婆(ババ)シャツ」。長そでで、伸縮率が高く、裾がながーいもの。あれは、あったかい。 わたしは暑さには弱いが、寒さには強く、冬は意気揚揚と(!)薄着である。それでも数年前、たまには婆シャツを着ようかと、思いなおし、自分用にと買って使いはじめた。薄着でもぜんぜん平気なのだが、寒い日には気をつけて、少しはあったかくしないといけないという目に遭ったのだ。 その年の冬、ボウコウエンになってしまった。 病院に行って、主治医のせんせいとああでもない、こうでもない、と話すうち、どうやら薄着が過ぎることが、病気の原因のひとつかもしれない、というところに突きあたった。 そういうわけで、婆シャツを、買いに出た。 婆シャツってのは、町の洋品店で買うんだなと、当たりをつける。隣り町の吉祥寺にだって、婆シャツを置いていそうな店はあるのだ。 あそこだ!という店に、ねらい定めて、出かける。 ——うかれました。 婆シャツのほか、遠赤外線をどうにかしたとかいうガードルももとめる。 「お母さん、いくらなんでも、これは完全無欠な婆シャツじゃないの」 と、上ふたりの年増の(失礼! しかし江戸時代には20歳を過ぎれば、年増と呼ばれたそうな)娘たちが言う。 完全無欠な婆シャツときたか……。「文句があるなら、着なくていいよ」 このやりとりからわかっていただけるかどうか、わたしは、下着や衣類の一部を、娘たちと共有している。とくに、ほとんどいろんな寸法がそっくりな長女とわたしは——ちがいは、彼女のほうが全体に少し細く、わたしのほうが5センチほど脚が長いところ——共有率が高い。 まったく油断も隙もないんである。 出かける前に、さあ着替えよう、とワードローブを覗くと、目当てのものが見えない。「やられたー」 目当てがあるときにかぎって、先に着られてしまうのだ。 靴になるともっと質(たち)がわるい。靴が、その日の装いを決定づけるというのに、靴箱をあけてはじめて、すでに履いて出かけた者がいることを知ったりすると、めげる。さいごの靴めざして選んだつもりの上のほうの服装をとり換える時間がなかったりすると、外出のあいだ、なんとはなしにちぐはぐな気分で過すことになる。 それでも。 なぜか、共有ってのが、好きなのだ。 なんとなく、相手と気持ちが寄りそう。 わたしが買った婆シャツに文句を言うのも然り。「ね、この服買おうと思うんだけど、色、どうする?」と、通信販売のカタログを見せられるときも然り。「あした、ブーツ黒、履きます、よろしく」と、宣言されるときも然り。 さて。 婆シャツはどうなったか。 文句を言っていた娘たちは、いちど身につけると、そのあったかさの虜(とりこ)になり、なんのことはない、毎日婆シャツを着ている。 わたしはわたしで、娘の買ったお尻にサクランボの模様入りの毛糸のパ○○履いて出かける日には、誰かにみせびらかしたくなる。ふふっ。 3階へ上がる階段のつきあたりにある戸棚のなかにに、共有の下着と衣類のひきだしが入っています。6段のひきだし——。上から、「半そでTシャツ(ポロシャツ)」、「ブラ/スパッツ、2枚めパ○○」、「長そでTシャツ」、「くつした」、「半そでシャツ/毛パ○○、ハラ巻」、「キャミソール/長そでシャツ」。冬期と夏季で、「半そでTシャツ」と「長そでTシャツ」のひきだしの位置をかえます(活躍するほうを、とり出しやすい位置に)。また、ひとつひきだしのなかに同居している「キャミソール」と「長そでシャツ」も、冬期と夏季で、前後入れかえます。
2007/12/14
コメント(1)
-

ついに、ゼラニウムを植えました!
たしか、この「家事手帖」のブログをはじめたころだったと思う。ゼラニウムにあこがれている話を書いたのは。 ——ついに、うちにゼラニウムの白花が、やってきました。 花がやってくる、それも、住み込みにきてくれるなど、ちょっとやそっとの縁ではない、という気がする。 植え込みながら、思わずと声をかける。「よく来てくれたねー」 早速、水(米のとぎ汁)をそっと与える。 そのときだ。 なつかしい感じに包まれた。 ああ、どこかで嗅いだにおいだ、と思う。 この、青臭くて、かすかに金属的な葉のにおい……。目をとじて、記憶をたどっていくと、小学生のわたしがあらわれた。そこは、大好きな祖父母の、庭。あそこに、ゼラニウムがあったのだ。 家の南北にあるふたつの庭をつなぐ、東側の通路——そこは、隣りのお寺の墓地に面していた——には、塀に添って台が設(しつら)えてあり、たしかに植木鉢がならんでいた。そこで始終遊んでいた幼いころの匂いの記憶が、そこに植えられていたのが、ゼラニウムだったことを伝えた。およそ40年の歳月を経て。 ふり返れば、菊の手入れをする祖父と、洗濯ものをとりこむ祖母に、会えるかもしれない。 目をとじたまま、ふり返る。 匂いの記憶というのは、な、なんて……。 過去、名も名乗りあわず、ふれあっていたものの正体を、いまに伝える。 きょう。 自分がなぜ、これほどゼラニウムにあこがれ、なつかしんでいたか、ということに気づいた日。 ちょっとだけ、幼い自分に戻らせてもらう……。 おじいちゃん。 おばあちゃん。 2階のベランダ、西のはずれです。まだ若いゼラニウムを2本、植えました。1本、158円也。安過ぎやしないかなあ。そうそう。先に書いた「からからに干した茶がら」をたっぷり混ぜこんだ土に植えました。 下の道から写してみました。こんなふうに、見えます。
2007/12/11
コメント(3)
-

ボロ布と、タオル、standby(スタン・バイ)!
出版社に勤めていた20代の数年間、高齢者向けの総合雑誌の編集に携わっていた。 当時はまだ、年を重ねたひとの健康(および高齢者のかかりやすい病気)、生活などに、世間の関心はうすかったな。 高齢者の生活を取材し、実際にわたしの3倍以上も年のはなれたひとにお会いし、さまざまな老人施設を見学していたわたしは、20歳代でありながら「高齢世界」にどっぷり漬かった。 おもしろかったのなんのって。 活きのいいお年寄りは、無気力な若者の数倍も若若しい! かわいいおばあちゃんになりたいって? いま全然かわいくないのに、年とっていきなりかわいくなるのは無理だ! 高齢者、高齢者って言うけれど、誰も以前は壮年で、もっと以前は子どもだったんだ……。 というようなことを、毎日つきつけられていたのだった。 なんてありがたい20代を過していたことだろう。 結果、年をとることが怖くないばかりか、おもしろくて仕方ないわたしになることができた。あやかりたいようなカッコイイひとに、いっぱいお会いしたおかげだろう。 さて。 高齢者向き雑誌をつくる仕事はたのしかったし、やり甲斐もあったが、わたし自身に、医療、とくに介護の知識が無いのに等しいことには不安を感じていた。そういうこともあって、わたしは、長く訪問看護の仕事をしてきたKさんという女性を頼りにしていた。 Kさんからは、いろいろおそわった。病気の告知を受けたときの患者の心理。闘病を支える家族の緊張。そうして、日常のちょっとした備えといったことも。 「介護、応急処置、救急医療には、タオルやボロ布が必要になるんです。傷みのある背中や腰に当てたり。まくらの高さを調節するのに使ったり。身体を拭いたり。汚れを拭ったり。大急ぎの処置のために、『タオルとボロ布をお願いします』とお願いして、すぐ出てくるお宅って少ないんですよ」 とKさんは、よく言っていた。 この場合のタオルは、使い古しがいいそうだ。ビニール袋に入ったままの新品タオルや、上等な分厚いバスタオルなんかが出てくると、もうお手上げなんだとか。また、ボロ布はボロ布でも、まだ服のかたちをしたボロ布も困る。裁ちばさみを出してきて、切ったりしているあいだに、タイミングを逸して、ついには役に立たない、なんてことになったりする。 以来、わたしは、Kさんのおしえを守って、ボロ布は程よい大きさに切ってひきだしにしまっている。別に、タオルと布のひきだしというのもあって、そこには下ろすまえのタオルもしまってあるが、雑巾になるのを待っている使い古しのタオルと、縫ったばかりの新しい雑巾もしまってある。 持っているというだけでは、いけない。 Standby(スタン・バイ)! ボロ布スタン・バイです。くつ下は、そのまま待機。 ボロ布たちといっしょに、使用済みの歯ブラシも、スタン・バイ。掃除に、いろいろ磨きに、重宝します。 別のひきだしに、雑巾と、古タオルをしまっています。
2007/12/07
コメント(2)
-

わたしは「ホシタガリ」です。
お茶を飲んだあとの茶がら。 食べたあとの、みかんの皮。 包丁で剥(む)いた野菜の皮。 いちどにたくさん手に入ったきのこ類。 このごろ、わたしは、こうしたものを片端から干すことに凝っている。 ホシタガリ。 そう、わたしは、干したがり屋なんである。 茶がらは、干して肥料や、げた箱、冷蔵庫内の脱臭剤(抗菌作用も期待できるらしい)にする。「茶がらならさ、水気をきるだけで、佃煮や揚げものの衣、チャーハンに入れられる。美味しいわよ」 と、友だちにおそわったが、なにせ、わたしはホシタガリなので、それはまだ試していない。たしかに美味しそうだけど……。 そうそう。 茶がら枕というのもいつか、つくりたい、と夢みている。 みかんの皮は、干して、布の袋に入れて湯船に。 入浴のときの、たのしみになっている。干しみかんの皮のおかげで、身体があったまるような気がする。 大根やにんじんは、皮を剥かずに使うこともあるけれど、皮を剥くほうがいい料理も少なくない。そういうときは、あとで皮をせん切りにして、干す。干したいあまりに、皮を剥いてしまうこともある。 そうして煮ものや、甘酢漬けに。 友だちがしいたけを届けてくれた。「でたでた、でたー」と言いながら。 なんでも、しいたけの種菌を植えつけた榾木(ほだぎ)をもとめて、1年、やっとしいたけが出てきたのだそうだ。 いいなあ、素敵だなあ。 ひとり1枚あて、網で焼き、しょうゆをたらして大事にごちそうになる。 あとは、干そう、とまた思う。 ホシタガリの気持ちが、半年つづいたので、干し専用のネットのようなものを買っていいことにする。仕事部屋の本棚の上に、干している途上の茶がらやら野菜の皮がならんでいるのもわるくはないが、どこかにまとめて置けるといいなあ、と思うようになってきた。キャンプ用品の、食器を干したりするのに使うらしい「ドライネット」というのを、買うことを思いつく。 さがしにさがして990円也。 ますます、ホシタガリが昴じている。 はじめのうちは、こんなふうに干していました。乾きはいいのですが、風に飛ばされてなくなってしまうことがあるんです。いちご(うちの猫です)も、このお気に入りの椅子を茶がらに奪われて、不満顔。 これです! ドライネット。通信販売で買いました。このときは、新聞の折り込み広告で折った箱に(中敷きに新聞紙を)入れて干していますが、ざるで干すこともできます。細かいものが多いし、茶殻などは最初、相当湿っているので、直(じか)置きにはしません。このドライネットを、洗濯ものといっしょに干して、夕方取りこみ、納戸に吊るしておきます。※プラスチック資源(プラ)を洗ったあと、このネットで干すと具合がいいです。 こうして、茶がらをためています。ほんとうにカラカラで、またこれでお茶をいれられるんじゃないか、と思ってしまうほどです。 みかんの皮。大根とにんじんの皮。干ししいたけと、干ししめじちょっと。
2007/12/04
コメント(6)
全7件 (7件中 1-7件目)
1