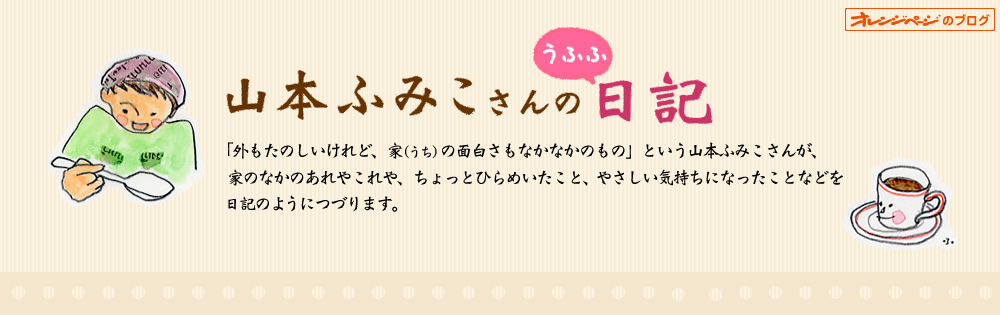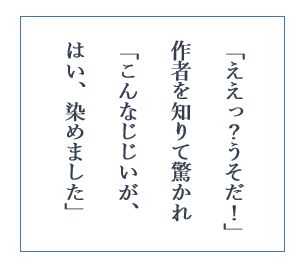2007年10月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-

ボタンが、大好きです。
衣替えというのは、なかなか骨の折れる仕事だ。 暑さに弱く、寒さにはつよい質(たち)だからだろうか、わたしは、秋冬ものから春夏ものへの衣替えは、すぐしたくなる。早い時期から、半袖・薄ものを着て過したくなるからだ。 「ちょっと早過ぎやしない?」 と、家の者たちにあきれられる。 その反対に、春夏ものから、秋冬ものへの衣替えは、ちょっとぐずぐず。 まだ、もうちょっと半袖・薄ものでいたい、という抵抗が、衣替えをおくらせるらしい。 そう。わたしは衣替えは年に2回しかしない。 そのかわり、合着のケースというのをつくっている。 ・秋冬ものから春夏ものへという衣替えのときは、秋寄りの合着を、合着のケ ースにしまう。・春夏ものから秋冬ものへという衣替えのときは、春寄りの合着を、合着のケ ースにしまう。 ——合着のケースは、比較的とり出しやすい場所に納める。 10月のはじめ、衣替えをした。 半年あまり世話になった服に傷みやほころびがみつかる。手直ししてから仕舞いたいが、ついその作業があとまわしになる。 思い立って、きょう、やっと、それを取りだし、ボタンをつけたり、つくろったりした。はじめてみると、なかなかたのしい仕事なのに、どうしてあとまわしにするんだろう、などと思いながら……。 末娘の袖なしのシャツにシミを、発見。 古い歯ブラシに、歯磨き粉をつけ、とんとんと叩いてシミヌキするも、とれない。色柄ものOK の漂白剤でも、ダメ。ままよ、とばかりに、白もののみという条件の塩素系漂白剤を、つけて歯ブラシでとんとんしても、ダメ。 シミに気づかず、長いあいだ置いてしまったものとみえる。 あの手しか、ないな。 そう思って、ボタンの瓶をとり出す。 これは、ボタンを貯めておく瓶なのだ。あたりまえのボタンも収めてあるが、風変わりでわたし好みのボタンをみつけたときにも、買って、ここに入れておく。 このたびのシミは、わたしにはお手上げだったので、この瓶のなかから、サカナのかたちのボタンをシミの上に縫い付けることにする。 これが、さいごのあの手。 ボタンで、シミを隠そう、というわけ。 パンチに欠ける洋服も、ボタンを替えるだけで生き返ることがある。 アップリケのかわりにボタンをつけるという手も、たびたび使う。ほんとうは縫ってやりたかった子どものかばんを、時間がなくて買った、というような場面でも、ボタン。大事にしていたボタンを1個つけてやるだけで、気がすんだりする。 ああ、ボタン、大好き。 シミの上に、ボタンをつけました。ほんとうは赤いボタンがかわいいと思うけど、わざわざ買わない、というのも、ちょっとした信条。ポケットの上についていたボタンシャツの右)ははずし、ここにも同じサカナのボタンをつけました。 これが、ボタンの瓶です。ただいま、涸れ気味なので、近いうちにボタン狩りに出かけるとしましょう。たのしみ。
2007/10/26
コメント(0)
-

皮むきの練習を、しています。
果物のおいしい季節。 わたしは柿に目がない。店先に柿をみつけると、つい顔がほころび、ほころびついでに、ふらふらと買ってしまう。 このごろは、柿も種なしがふえた。食べやすいから、そういうふうに品種改良するのか、こうなると、「さるかに合戦」のおとぎ話も、あのぴりりと辛い「柿の種」も、話のはじまりがみえなくなるね。 自己紹介なんかをするとき、「わたし、じつは臍(へそ)なしなんですよ」 と、言っている自分を連想したりする。 柿は、種のまわりのどよよんとしたところも、美味しかったのにな。 さて。 この秋、末の子どもが、果物の皮むきの練習をはじめた。 ものをおしえるとき、わたしはすごく乱暴で、「ほらね、見てて。こんなふうにむくのよ。親指の使い方が、ポイント」 とか言いながら、目の前でむいて見せる。それだけ。 あとは、ひたすら見守る。口も出さない。 口を出すと、怪我をする。 子どもって、大人の期待に応えようとするようなところがあるから、「そうじゃなくて、ナイフをこう引き寄せるようにむくのよ」と言っただけで、考えと、動きが、ばらばらになる。 また、考え考えむこうとしているところに、うるさく言われれば、子どもだって、いらいらする。 と、思うのだ。 だから、黙っている。 はじめのうちは、はらはらするし、柿が口に入るまでに20分ほどもかかってしまう。が、かならず、皮むきのコツのようなものを自分でつかむ。「あなたがむいてくれた柿は、おいしい」 皮むきの練習は、梨の季節にはじめ、りんご、柿にも挑戦。 りんごは、4ツ割りにしてむくのより、くるくるとお尻のほうからむくほうが、おもしろいし、むきやすいようだ。はじめは、それを練習するのがよさそうだ。 ついに、きのう、皮をつづけてむききった。こういうことは、喜んでやりたい、大げさなほどに、と思いつく。 そうして1本つながりのりんごの皮を、飾った。 わたし、さり気なさを装い、見守ってます。梨、りんごで少し練習を積んだので、だいぶ上達してきました。 子どもたち用に、こんなナイフを買いました。これで、野菜を刻んでいる姿が、なつかしい……。 わたしは、ペティナイフが好きです。台所で、いちばん活躍するのが、これ。1代目は、研いで研いで、こんなに痩せて小さくなりました。子どもにも、これを使わせています。研いで、よく切れるのを使ってもらいます。切れがわるいと、かえって怪我につながる……それは、大人も、同じですね。 これを、飾りました。
2007/10/23
コメント(1)
-

カレンダーを、持ち歩いています。
来年のカレンダー、手帖が出まわる季節になった。 それはもちろん、こういうものは、早めに出てくるものだろうけれど、かなり、あせる。ついこのあいだ、2006年から2007年のカレンダーにかけかえたばかりだというのに。 わたしね、じつは手帖は持っていない。 カレンダーを、持ち歩いている。「つぎの打ち合わせの日にちですけど……」という話になるとき。「つぎの予約、いつおとりしましょう」という話になるとき。 相手は、へえっという顔になる。まさかカレンダーが出てくるとは、思わなかった、という表情。 そうだ。 革製のシステム手帖なんかを広げて、「そうですねえ」なんて首をかしげて見せたりすれば、いかにもキャリアを積んだウーマン風だ。 格好だけ、そんな風だったことは、ある。 手帖に仕事の予定を書きこみ、台所のカレンダーに家の予定——子どもの学校行事。レッスン。山歩き。水道工事で、午後1時から断水。など——を書きこみ、自分の部屋のカレンダーに、友だちとの約束、観劇の予定を書きこんでいた。 これを、いつどこでつき合わせるか、だ。 すぐつき合わせても、予定が1日の枠のなかで、重複する。 ・家に編集者が来てくれる日に、ガス工事があって火が使えない。・仕事と、学校行事が重なる。・打ち合わせの時間と、美容院の時間が重なる。 という具合に。 進歩なく、こんなことをしばらくつづけていた。ある日、とうとう、すべての予定を同じところに書きださなくちゃ、と気づく。 思いつくのが、おそい。 たしかに。 でも、どこに集約するか、というところで、迷っていた。手帖ではない、という気がした。それだと、きっと家の関係の予定が、こぼれる。 1つのカレンダーという結論に達したとき、やれやれ、と思った。 格好よくない、とね。 でも、まあ、わたしらしいか、と思いなおす。 それから5年、カレンダーを持ち歩いている。大きな声では言えないが、いまでもときどき、ダブルブッキングのポカをやる。これは、カレンダーのせいではなく、自分の……、言いにくいがわたしの、そそっかしさが原因だ。 とはいえ、以前よりずっと、そんな失敗は減っている。 カレンダーの寸法は、左右20×天地18cm。家にいるときの居場所は、2箇所。仕事ちゅうは、仕事部屋・机横の書棚にかけています。 もうひとつの居場所は、台所・冷蔵庫の扉。朝と夕方は、ここにいます。
2007/10/19
コメント(0)
-

とうとう、買いものかごをみつけました。
先週、静岡県藤枝市に出かけた。「大井川の木で家をつくる会」(ハイホームス)のひとたちとお会いするのが目的だった。 講演の依頼があったとき、気がつくと、ふたつ返事で「はい、行きます」と答えていた。 わたしは、話が下手くそだし、日ごろ、講演という話からは逃げよう、と考えているというのに。 なぜだろう……。 依頼のお手紙と、わざわざ会いに来てくださった会の方たちから、ゆらゆらとたちのぼっていた何かが、作用したのか。 何だろう、これ。 静岡に降り立つや車に積みこまれ、川根の山をめざした。 途中、茶畑や大井川と縁を結んだ川を褒めながら、ゆっくり、日ごろ身につけている鎧(よろい)をはずしにかかる。その鎧は、たやすくこころを許さない、簡単には感動しない、という自分との約束、ま、警戒心だ。 雨上がりの川根の山には、もやがかかり、幻想的な佇まいを見せている。 山をしばらく歩くうち、胸がしん、とするのがわかる。 杉が、ある間隔をおいて立っている。 案内してくださる「大井川の木で家をつくる会」の代表の三浦さんが、「ここは、理想的な状態ですが、ほら、あそこ。あそこは、もう少し、木同士、間隔をあけなければなりません」と、言う。 杉は、欲望もなく、ただあるがままにすっくと立っている。 ああ、1本の木のように生きたい。 ひと同士も、いい具合の間隔をとって暮らしたい。礼儀知らずにならぬよう、また、ひとりの胸でしん、と感じたり、考えたりできるように。 そんなことを、感じていた。 この2日間、山を、木を、川を守りたいと希ってやまない人びとのなかで過した。山、木、川を守るため、手に技もとうとしている彼らには、詩ごころが宿っていた。 わたしが、最初に感じたあれ——会の方たちからゆらゆらとたちのぼっていた——は、詩ごころ……。 川根の山に向かう途中、この町の人びとの手になる工芸品、食べものを売る小さな店に立ち寄る。 ここで、買いものかごをみつけた。 長いあいだ、探していた買いものかごを、とうとう、みつけた。 町の女性たちが編み上げたという、竹のかごだ。 これを持つたび、わたし自身の、手に技をもつ目当てをたしかめるとしよう、と誓う。 エコロジーの意味も、そこから探ることにしよう。 いつしか、暮らしに詩ごころが湧く日をめざして。 探しつづけるものは、ある不思議な縁のなかでみつかるものかもしれません。この買いものかごも、そうでした。気がついて、よかった……。ここで合えて、よかった、です。大事にします。
2007/10/12
コメント(2)
-

ここは、わたしの「拠所(よりどころ)」です。
あわてん坊だし、おっちょこちょいだし、せっかちだし、およそ大人らしい落ち着きの不足がちなわたし……。 一度動きだすと、拍車がかかり、どんどんスピードが増していく。 減速しよう、止まらなくちゃ、と思う。 そういうときは、つまり自分にブレーキをかけるときに効くのは、煎茶だ。 居間にある、小さなつくり付けの棚から、茶筒と急須をおろして、お茶をいれる。朝沸かして、ポットに入れておいた湯を、湯冷ましに注ぎ、しばらく待つ。お茶どころ静岡県の川根町(島田市だろうか、大井川沿いの町)のお茶屋の若奥さんにおしえてもらった手順を、思い返し思い返しお茶と向きあっているうち、逸(はや)るこころが、ほぐれ、のびていくのがわかる。 湯冷ましの湯を急須に注ぐ。 このときの湯の温度? 急須の底をてのひらにのせたとき、熱いけれど、持てないことはない、というほどの温度——とのことだ。 葉がひらくのを待って、ゆっくり湯冷ましにお茶を注ぐ。湯呑みにではなく、湯冷ましに、だ。 これを小振りの湯呑みに注ぐ。 そっと、湯呑みに口をつける。 熱くもない、ぬるくもない、香り引きたつ煎茶が、沁みる。身にも、こころにも……。 ふだん使いの急須(茶葉には、ふだんも客用もない。これには、ほんの少しぜいたくをしている)ののった小さな棚には、ほかに、絵はがきの入った小さな額、子どもと散歩の途中で拾った木の枝、ロウソク立てが置いてある。 絵はがきの額のことだけど、それは、「熊谷守一(くまがい・もりかず)」(1880-1977 没年97歳。東京豊島区の自宅跡に「熊谷守一美術館」がある)の「仏前」という絵。ご長女の萬さんが亡くなったとき、供えたという鶏の卵を描いたものだ。 熊谷守一というひとの、誰が相手にしてくれなくとも、石ころひとつとでも、じゅうぶん暮らせる、というような生き方が好きだ。「石ころをじっとながめているだけで、何日も何月も暮らせます」と熊谷守一氏は述べている。 ほんとうに、ただ自由に自分の時間を生きることだけを望んだ生涯だった。 話は、かなりはしょることになるが、そういうわけなので、この世から旅立った親しいひとたち、あるいは面識こそなかったけれど尊敬するひとびとへの気持ちを、そこに集める意味で、この「仏前」という絵はがきを飾ることにした。 毎日、子どもたちが「ね、もう、誰か、お水、あげた?」と言いながら、お水を供えている。酒や茶、新米やめずらしい茶菓を供える日もある。 ここは、そういう棚なのだ。 この棚は、急ぎたがるこころを引きとめ、静かに立ち止まらせてくれる。 わたしの、たより。 拠所(よりどころ)……。 これが、その、棚です。 愛用のポット。おそらく40年近く使っている「アラジン」です。もっと保温性の高いのとか、注ぎやすいのとかあるかもしれないけれど、ここまでつきあったら、「共白髪」です。 急須、湯冷まし、湯呑み。湯冷ましが2度働く(1回め—湯をさます。2回め—湯冷ましに茶を注ぎ、湯呑みへ)ことを知ってから、お茶をいれるのが楽になりました。急須のなかのお茶を、湯冷ましに移すことによって、1煎ごとに決着するからでしょうか。こうして、4煎までたのしめます。湯呑みが小さいのも、なかなか具合がいいです。酒坏(さかつき)も、使えそうです。
2007/10/05
コメント(2)
-

鍋に「柄」を、つけました。
台所で、毎日活躍している鍋は、7個。 ・ 文化鍋→ ご飯を炊く。・ ル・クルーゼの鍋(18センチ)→ 味噌汁、清汁をつくる。・ 行平鍋(15、18、21、24センチ)→ あらゆる茹でもの、煮炊きに。・ フライパン(銅製)→ 焼きもの、炒めものに。 このなかで、いちばんの古参といったら、行平鍋4人衆だ。 もう、24年のつきあいになる。初めて自分の台所をもったときから、ほんとうにずいぶん、世話になった。 台所の恩人といってもいいほどなのに、わたしはときどき、ひどい扱いをする。柄を、焦がすのだ。それが1度や2度でない証拠に、これまで、何度か、柄が焼けて、とれてしまった。 ときどき、安いすりこぎを買ってきてそれを柄として、木螺子(もくねじ)をねじ込んで、とり付ける。 そんなことをくり返すたび、どうして焦がしちゃうんだろうなあ、わたしは……と、さびしく反省。 が、あるとき、柄無しでもいいんじゃないか——木製の柄がなければ、オーブンに入れて調理できるし、と言いわけめいたことをつぶやき、つぶやき——と、思うに到り、ここ7年ほど、柄無しで働いてもらった。 ただし……。 いちばん大きい24センチのは、なかみが入るとさすがに重くて、柄の力を借りないと使いにくいという理由で、柄をつけて使った。 「自分が、たのしむ」「いやになってしまわないように、なまける、休む」「ときどき変化させる」 これが、わたしの台所仕事3箇条。 なんだか、わたしというひとのわがままが露呈するようで、気が引けるが、そういうことで、やってきた。 で、鍋の柄を、7年ぶりにくっつけようというのなんかは、「ときどき変化させる」に、該当する。そのくらいのことで、変化なんかするの?と、お疑いのあなた、これが、もう、うれしくなっちゃうほどの変化なのだ。 まず、100円ショップに出かけていき(これだけで、かなりうれしくなっちゃう)、鍋の柄になるすりこぎを2本もとめる。 この2本から、3本の柄をつくるのに、のこぎりと愛用の「肥後守」をとりだす(工作だ、工作だ、というので、また、うれしくなる)。柄が長すぎると、あぶないし、使いにくいので、ほどよい長さにぎこぎこやる。 うふふ、たのし。 1本のすりこぎで、21センチの鍋の柄が1本つくれ、もう1本のすりこぎから、18センチと15センチの鍋の柄がとれるのだ。 鍋の柄をさしこむ部分の大きさに合わせて、「肥後守」ですりこぎを削る。ここまでくると、もう気持ちはすっかり職人だ。 最後に、柄をさし込み、錐(きり)で穴をあけて、木螺子で固定する。 こうして、手をかけてとりつけた鍋の柄は、台所に大きな変化をもたらす、というわけ。 おおっ、新しい風。 変化の香り。 柄のない行平鍋4人衆。 愛用の、「肥後守」(ひごのかみ)です。これ、1本持っていたらいいと思うんです。 柄を削っています。ちょっと職人をきどっています。この作業には、肥後守と軍手は不可欠。 鍋に柄が、つきました。うれしいっ。
2007/10/02
コメント(0)
全6件 (6件中 1-6件目)
1