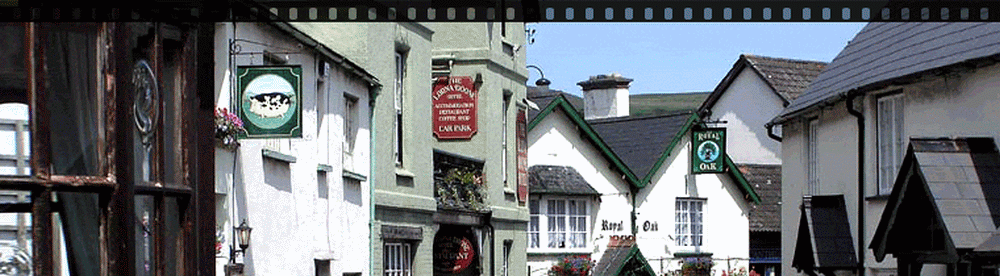2009年05月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
METライブビューイング~ラ・チェネレントラ(シンデレラ)
エリーナ・ガランチャのチェネレントラ、ノーブルさを備えた容姿と意志の強さみなぎる演技、それでいて歌が全く乱れないのですから、本当にすばらしいです。 私は、ドン・マニフィコのアレッサンドロ・コルベッリが今回一番のお気に入りです。本人もインタビューで、一緒に笑ってしまうのではなく、自分は真面目に役になりきることで、見てる人はギャップにおかしさを感じるのだと言ってました。さすがベテランの役作りです、醸し出される雰囲気がとてもいいスパイスになります。 最近のMET演出にはミュージカル的な要素が入って、時代設定もできるだけ近世にかえてきていて、楽しく受け入れやすいようにしているように感じます。ブロードウェイという下地があるからこそできるヴァリエーションなんでしょうね~ ガランチャは、高音も中低音も全く同じような違和感ない響きで、とくに中低音のふくよかでやさしく包み込むような美しい声は本当に魅せられます。私的には、今回彼女には若い娘らしさというより、いつかチャンスがあったらと虎視眈々として、機会逃さず作戦練って・・というしたたかさをものすごく感じました。だからこそフィナーレは勝利宣言を端的に感じて、上品でありながら力強さにものすごく圧倒されました。 「お姫様はお城で王子様と幸せに暮らしました、めでたしめでたし」なんていうのではない、現実はこういうシビアなものなんだよ~~というロッシーニの皮肉さがみごとに出ている感じで、そういう目線から見ると、とても彼女のチェネレントラ適役に感じます。 ガランチャはこの役にはもう決別を決心しているそうです。コロラトゥーラよりメロディーラインで訴えかける歌や役のほうが自分には合っていると、中途のトーマス・ハンプソンのインタビューに答えていました。実は最初から、うまいけどなんか冷めてやってるみたいだなぁ、そういう役作りなのかなぁと感じていたのですが、その辺の事情がひょっとすると歌や演技に表れていたのかもしれません。 ロッシーニから始まった彼女のスターのキャリア、豊潤な美声としたたかな演技は今後どんな方向に行くのでしょうか、とても楽しみです。 2009年5月9日 メトロポリタン歌劇場上演 指揮 マウリツィオ・ベニーニ演出 チェーザレ・リエーヴィ チェネレントラ エリーナ・ガランチャドン・ラミーロ王子 ローレンス・ブラウンリードン・マニフィコ男爵(チェネレントラの義父) アレッサンドロ・コルベッリダンディーニ(王子の従者) シモーネ・アルベルギーニアリドーロ(王子の師) ジョン・レリエ ちなみにCenerentola チェネレントラはイタリア語読み、フランス語だとCendrillon サンドリヨン、英語でCinderella シンデレラだそうです。
2009年05月31日
コメント(0)
-
フジコ・ヘミング ピアノ・ソロ・リサイタル
相変らず癒しの音色です。私が彼女のソロ・リサイタルに毎回来る一番の理由は、内に秘めた希望と情熱を感じること、そして重い楽曲に深刻さや悲壮感がないこと。彼女の奏でる音は、私に希望を与え、心を癒してくれます。若者のような情熱と心地よい甘さを感じるベートーヴェンの月光に、まず引き込まれました。そして、アンコールで、前回リサイタルで大衝撃を受けたテンペストの第3楽章が!私は今回これに最も感銘受けました。なんと表現したらいいのか、押し付けがましくない演奏が、適度な緊張と適度なリラックスをバランスよく感じさせてくれて、聞かずにはいられないという奏でなのです。もちろん、ショパンやリストはずっと前からそんな印象で、今回も引き込まれました。独特のテンポや間が、技術に走りがちな楽曲に温かみを与えてくれます。やっぱラストのリストのパガニーニ大練習曲2曲がすばらしかったです。私個人的には、どうしても構えて聞いてしまうベートーヴェンを、リラックスしながら聞けることに、いろいろ感じることがありました。やっぱ生の音には何かしらの発見があるのですね。ドビュッシー 「ベルガマスク組曲」より第3曲「月の光」ドビュッシー 組曲「版画」より第3曲「雨の庭」ベートーヴェン ピアノソナタ第14番 嬰ハ短調作品27‐2「月光」ショパン 3つの夜想曲 作品9 第2番 変ホ長調ショパン ワルツ第1番 変ホ長調「華麗なる大円舞曲」作品18ショパン 12の練習曲 作品10 第3番 ホ長調「別れの曲」ショパン 12の練習曲 作品10 第5番 変ト長調「黒鍵」ショパン 12の練習曲 作品10 第12番 ハ短調「革命」‐休憩‐J.S.バッハ カンタータBMV147より「主よ、人の望みの喜びよ」J.S.バッハ ゴルドベルグ変奏曲BMV988より「アリア」 リスト 「三つの演奏会用練習曲」作品144より 第3番「ため息」リスト 春の宵(R.シューマンによる)リスト パガニーニ大練習曲 第6番「主題と変奏」リスト パガニーニ大練習曲 第3番「ラ・カンパネラ」‐アンコール‐ショパン ノクターン第1番 変ロ短調ベートーヴェン テンペストより第3楽章 平成20年5月9日 東京芸術劇場大ホールにて
2009年05月09日
コメント(2)
-
バロック余韻~シュ・シャオメイ 平均律クラヴィーア第2巻CD
昨日買ったシュ・シャオメイのクラヴィーア第2巻聞いてます。なんというのでしょうか、目の前に希望の光が見えて、それに慈しまれて、力強さがわいてくるという演奏です。 音楽って本当に自己主張なんだ、言葉では全部表せないことも、思いとして伝えることができるんだ、改めてそんな風に感じました。 ブルゴーニュワインでバロック余韻盛り上げてます。
2009年05月05日
コメント(0)
-
ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2009 その2
休憩はさんで、私の夕方(5月4日)の部開始です。児玉麻里児玉桃小曽根真(以上ピアノ)シンフォニア・ヴァルソヴィアジャン=ジャック・カントロフ(指揮)J.S.バッハ 2台のチェンバロ(ピアノ)のための協奏曲第1番ハ短調BWV1060J.S.バッハ 2台のチェンバロ(ピアノ)のための協奏曲第2番ハ長調BWV1061J.S.バッハ 3台のチェンバロ(ピアノ)のための協奏曲第1番二短調BWV1063 2台の・・・は児玉姉妹が演奏して、3台の・・・に小曽根氏が加わりました。ピアノが2台で、オケより優位な響きかなと思ったらそんなことなく、片方がシンフォニアと同化して、なるほどねぇ、という感じです。第2番二楽章のピアノソロはさすがです。3台の・・・は小曽根氏のパートが完全主導。さすが小曽根、圧巻でした!!特に二楽章のジャズのアドリブとも感じられるソロは、小曽根の世界ですね!ひさびさ堪能しました。いよいよ、私のメインです。演奏曲目が変更になってました。シュ・シャオメイ ピアノJ.S.バッハ「平均律クラヴィーア第1巻」より前奏曲とフーガ第1番ハ長調BWV846第6番二短調BWV851第7番変ホ長調BWV852第8番変ホ短調BWV853第12番ヘ短調BWV857第13番嬰ヘ長調BWV858第14番嬰ヘ短調BWV859第15番ト長調BWV860第16番ト短調BWV861第4番嬰ハ短調BWV849第1番が曲目変更で追加され、しかも冒頭に!あのメロディー始まった瞬間、あまりのやさしく流れる感じに衝撃受けました。なんて、慈しむような音色なのでしょうか!そしてそのあと、8番12番と短調が続いた際に、とても暗く抑圧された印象で、ギャップに逆に驚いてしまいました。15番ト長調で爆発、そのあとはやさしさと力強さを融合する音色に圧巻です。こんな短時間に人生感じます。彼女の波乱の人生が反映しているのでしょうか。慈愛と強固な意志を、美しいメロディーにのせ、本当に感動しました。バッハの平均律クラヴィーアで、こんな表現をするなんて、すばらしいの一言につきます。ラストはオール・ヘンデル・プログラム。古部賢一(オーボエ)香港シンフォニエッタイプ・ウィンシー(指揮)合奏協奏曲ト長調作品3‐3 HWV314オーボエ協奏曲第3番ト短調 HWV287管弦楽組曲「水上の音楽」より抜粋第1組曲ヘ長調HWV348より序曲:ラルゴ‐アレグロ、アダージョ・エ・スタッカート、アレグロ‐アンダンテ‐アレグロ、エア(アリア)、ブーレ、ホーンパイプ第3組曲ト長調HWV350よりメヌエット、カントリー・ダンス第2組曲ニ長調HWV349よりアラ・ホーンパイプオーボエ協奏曲の古部さん、本当に甘い音色です。オーボエの魅力余すことなくだしてくれます。そして、フィナーレのアラ・ホーンパイプは圧巻です!!トランペットとホルンの掛け合いが気持ちイイ~きびきびした迫力で、これ聞いて、ああ今日来て良かったぁと、本当に感じました。それくらいのインパクトです。ウィンシー女史ブラヴァです!4日一日バロック三昧、ワイン飲んでハイネケン飲んで、至福の一日でした。写真はNHKのサテライトスタジオです。
2009年05月04日
コメント(0)
-
ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2009 その1
今年はバッハをはじめ、バロックの祭典、なかなか生で聞く機会がないジャンルだけに、今日は一日東京国際フォーラムです。まずは、スキップ・センペ(チェンバロ奏者)率いる、古楽アンサンブル「カプリッチョ・ストラヴァガンテ」の演奏です。F・クープラン 4声のソナタ「スルタン妃」テレマン リコーダー、弦楽、通奏低音のための組曲イ短調いきなり、「あぁ、バロックだぁ~!」と痺れてしまいました(笑)バロックでは有名な作曲家でも、日本ではまず聞くチャンスの少ない演目。クープランの方はウキウキと、テレマンの方は目まぐるしい変遷にワクワクしながら聞いてしまいました。テレマンの方は、「リコーダー協奏曲」ですね。リコーダー取り替えず同じもので続けていて、なんであんなに音域がでるんだろう。テンポ速い音階、全くブレスがわからないのです。いきなりバロック全開、満足の朝です。続いて、ベルギーのフィリップ・ピエルロ指揮、古楽アンサンブル、リチェルカール・コンソート演奏のミサ曲です。マリア・ケオハネ(ソプラノ)サロメ・アレール(ソプラノ)カルロス・メナ(カウンターテナー)ハンス=イェルク・マンメル(テノール)ステファン・マクラウド(バス)J.S.バッハ ミサ曲ト短調BWV235(抜粋)J.S.バッハ マニフィカト ニ長調BWV243マニィフィカトはトランペットが鳴り響き、ふつうにイメージするミサ曲よりも祝典要素満載で、飽きずに楽しめます。なんといっても、(ワケわからない)ラテン語歌詞に日本語訳もついて、今歌ってるとこがなんとなくわかることが、(声楽聞く際よくおこる)ストレスたまらなくてイイですね!マリア・ケオハネは本当に天に届くソプラノです。心が洗われます。カウンターテナーのカルロス・メナが、中低音域に声量小さくなることなく響き渡り、そして高音の厚みのある響きに、とても心打たれました。バスのステファン・マクラウドは精悍な響きでいいですね~決して声楽向きホールじゃないのに、ノーブルな響きに感動してしてしまいました。スペースでアウラという女性五人組のユニットが、アカペラ演奏してました。最低音担当の方の響きが最高でした!
2009年05月04日
コメント(0)
-
バッハ 平均律クラヴィーア
ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポンの『勝手に』前夜祭で(といっても、私は4日のみに集中させて行くだけですが)、今回私にとっては楽しみの一つ、平均律クラヴィーアを聞いてます。昔々、初めて自分で弾いた時、ハノンみたいな感じになってしまい、全然良さがわかりませんでした。こうして¨ちゃんとした人¨が弾くのを聞くと、バロックの躍動を感じます!私は一日しかきかないけど、シュ・シャオメイの演奏が楽しみです!バッハ聞きながらに旬のアサリで、またまた酒が進みます
2009年05月02日
コメント(0)
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
-

- プログレッシヴ・ロック
- Yes【イエス】ロンリーハート~ビッ…
- (2025-11-25 21:23:42)
-
-
-

- UK~エイジア~ジョン・ウェットン
- Roxy Music - Out Of The Blue Midni…
- (2025-11-12 00:00:13)
-
-
-

- 好きなクラシック
- ベートーヴェン交響曲第6番「田園」。
- (2025-11-19 17:55:25)
-