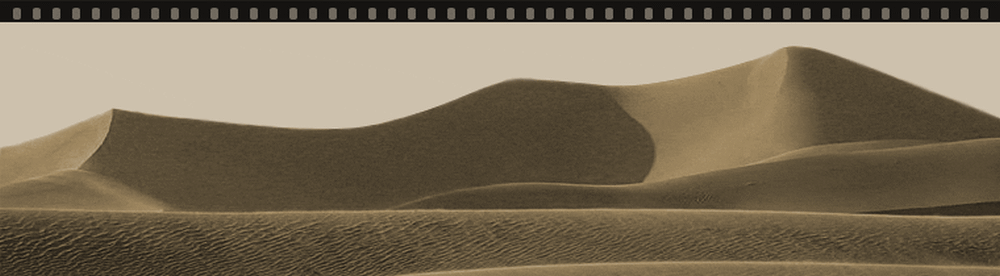2008年01月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-

1/27(日)は、第19回菊之丞独演会でした。
この日は、午後には飯能市市民会館主催の「新春落語会」を奥さんと聴きに行っていましたが、途中で、私の携帯が振動したのですが正蔵さんの高座の最中だったので、出られませんでした。落語会終了後にすぐ携帯の着信記録をみたら、発信者は菊之丞さんでした。(何だろう!)開催直前に、出演者からかかってくる電話の用件は「緊張」します。それは「遅れる」か「行けなくなった」という連絡であることが多いからです。しかし、菊之丞さんの電話は留守電になっていました。(ということは、あまり緊急な用件ではないようです)「さっきは電話に出られませんでしたが、これからはいつでもOKです」と留守電に吹き込んでおきました。会場で準備を始めた時、同じ世話人仲間のKさんが「さっき菊之丞さんから私に電話が有って、きょう一人飛び入りのゲストを連れて来るって!」(私)「たぶん前の会場で一緒に仕事して、そのまま一緒に来るんでしょうね?」以前にも、三三さんの時にそういうことが有ったのです。(私)「誰って言ってました?」(K)「はっきり聞こえなかったけど いちば って言ってたような・・・」市馬師匠が、飛び入りゲストならこんな嬉しいことはありません。・・・・・・と喜んだのも束の間、菊之丞さんと一緒に来たのは一左さんでした。 ご存じの通り、柳朝さんの弟弟子です。いずれは、菊之丞さんの弟子が一緒に来てくれるようになることをいまからもう楽しみにしています。左から、私 菊之丞さん 一左さん Kさん壁にある「謹賀新年」は町内会で掛けたものです。そんな訳できょうの演目は下記の通りです。一左 「つる」菊之丞 「転失気」 「五人廻し」 来場者95人打ち上げのとき、カメラを向けたらこんな「サービスポーズ」をしてくれました。
2008.01.31
コメント(0)
-
昨日(1/27)の午後は、地元・飯能市民会館の「新春落語会」でした。
この日の夜は、「有望若手応援寄席・菊之丞独演会」もあります。地域も客層も重なっているので、出来れば同じ日にはなりたくなかったのですが、市民会館のきょうの落語会の日程を知ったのは、すでに、菊之丞独演会の日程をチラシやwebサイトで公表した後だったので変更できませんでした。時間帯が昼と夜で重なっていないことがせめてもの慰めです。市民会館が主催する落語会に来るお客さんは、「地域寄席」にとっても、絶好のPR対象なのですが、飯能市民会館では主催するイベントでは、市民グループのチラシの「挟み込み」はさせてくれないのです。(隣接の入間市や所沢市の公共施設ではOKなのですが・・・・)そこで、いつも、市民会館の入り口で来場者一人一人に「有望若手応援寄席」のチラシを手渡しで配布することにしています。この日(1/27)も開場の20分前から奥さんと「有望若手応援寄席」のチラシを配布しました。この時の来場者の中には有望若手応援寄席で顔見知りの常連さんが何人もいましたが、みなさん「夜も伺いますので宜しくね!」と声をかけてくれました。きょうの出演者と演目は下記の通りです。 林家たこ平 空き巣ねらい 桂小文治 七段目 中入り 翁家勝丸 太神楽 林家正蔵 読書の時間
2008.01.28
コメント(0)
-
1月24日(木)は、「第109回・練馬区民寄席」に行って来ました。
会場は練馬文化センター。この会場は、奥さんのいまの職場に近いし、西武池袋線で飯能から乗り換え無しで行けて、しかも駅前なので、ここで開催される落語会は結構聴きに行っています。きょうの出演者と演目は下記の通りです。 三遊亭歌五 子ほめ 三遊亭きん歌 紙入れ 三遊亭歌之介 龍馬伝 中入り 三遊亭小円歌 三味線漫談 三遊亭円歌 中沢家の人々前売り券は完売。場内は満員でした。歌之介さんは、寄席で聴くだけで、今日で5回目ですがいつも「爆笑」です。なんとしても「独演会」に行きたいと思いました。
2008.01.27
コメント(0)
-
きょう(01/20)は、俗曲の「うめ吉コンサート」に奥さんと行ってきました。
会場は入間市産業文化センターです。「うめ吉」は、新聞雑誌の記事では知っていましたが、寄席ではまだ一度も聴く機会がありませんでした。俗曲でライブを構成するのは、着眼点がいいと思っていましたし、何よりも美人です。それでも、まだ知名度は低いのでしょう、会場の入りは半分でした。きょうの座席は最前列の真ん中。いわゆる「かぶりつき」だったので間近でたっぷり顔を見られたのは満足でした。しかし、ヘッドフォンマイクの音量調整がうまくいかなかったのか、トークの時は内容を聞き取れるのですが、バックバンド「おてもと社中」の演奏と重なると、歌詞がよく聞き取れなかったのです。休憩を含んで1時間40分の舞台では、ちょっと物足りない気がしました。「三味線ブギ」などのブギシリーズは悪くなかったのですが、「うめ吉」のためのオリジナルのブギが早急に待たれます。例えば、「平成ブギ」とか「寄席よせブキ」、「お囃子ブギ」というようなタイトルで、当人が作詞作曲できればいいのですが・・・・
2008.01.20
コメント(0)
-

01/11は、毎年恒例の渋谷パルコ劇場「志の輔らくご」に奥さんと行ってきました。
きょうの演目は下記の通りです。 (立川志の輔サイト)エレベーター前に有ったので、帰りに乗り込む人たちの混雑で、かなりピンボケになってしまいました。(奥さんは小さいので雑踏ではどうしても押されてしまいます)昨年の「志の輔らくご」は、公演日によって「演目」を選ぶことができましたが、今年は映画『歓喜の歌』の公開直前なので、それが予め毎日の演目の一つに決められていました。私たち夫婦にとっては2004年11月以来、二度目です。今回もラストはご存じの通り、実際の「ママさんコーラス」の約80人が舞台で「歓喜の歌」を合唱しました。初演の2004年11月に初めて、この「演出」に触れたとき、「驚きと感動」の中で、私の頭の中をよぎったのは「観客動員の方法としては最高の手段だなぁ」ということでした。舞台に上がった80人のママさんたちは、当然、自分の家族や知人に「パルコ劇場での志の輔らくごを聴きに来てね」と誘うでしょうから、1人平均4人としたら80×4で320人にもなります。定員458席の劇場で320人を「自動的に集客できる」としたら、1ヶ月連続公演も、志の輔独演会なら、そんなに難しいことではないな、と思ったものです。この日の「80人」は、「ママさん」ですから、同じコーラスグループが毎日出演することはできないでしょう。当然、何組ものグループが交代で出演しているのでしょう(たぶん)から、この出演者総数からの集客数は、かなりの数になるはずです。たしか、2004年の初演の時が、パルコ劇場「志の輔らくご」としては、「初めての一ヶ月連続公演」だったと記憶しています。<大合唱団の定番 → 第九の「歓喜の歌」→ 年末公演>という図式が、殆どの日本人の頭の中に刻み込まれています。「全公演日程を確実に満席にするにはどうすればいいか?」というプロデューサー感覚で、この「ママさんコーラスグループを登場させる」というアイデアを考え出した人は(誰か知りませんが)、凄い人だと思います。もちろん、映画も公開早々に観に行こうと決めています。上映館のシネカノンは「水曜日は男女共1000円デー」なので、早ければ2/6(水)に行くつもりです。
2008.01.11
コメント(0)
-
今年の夢は講談の新作台本を書いて、講談師か噺家さんに演じてもらうことです。
タイトルだけは決めています。『渋沢栄一物語』です。いま、なぜ、渋沢栄一なのか?ここがポイントです。日本の資本主義の誕生とともに数百社の創業と発展に関わってきた渋沢栄一を「起業家の先駆け」として、現代に蘇らせたいのです。明治の時代には、多くの起業家が誕生しましたが、1社か2社を起業したというだけの人を題材にしたら、「単なる創業者伝」に過ぎません。500社以上の立ち上げや成長に関わってきた渋沢栄一を主人公にすることで、下記のようなテーマに恵まれると思っているからです。 1.「百姓から武士への転身」は現代では「人生の進路選択」 2.「徳川慶喜の家臣になった」ことは「最初の就職」 3.「欧州使節団の随員」は「海外留学の功罪」 4.「新政府への参加」は「最初の仕事が人生を決める」
2008.01.01
コメント(0)
全6件 (6件中 1-6件目)
1