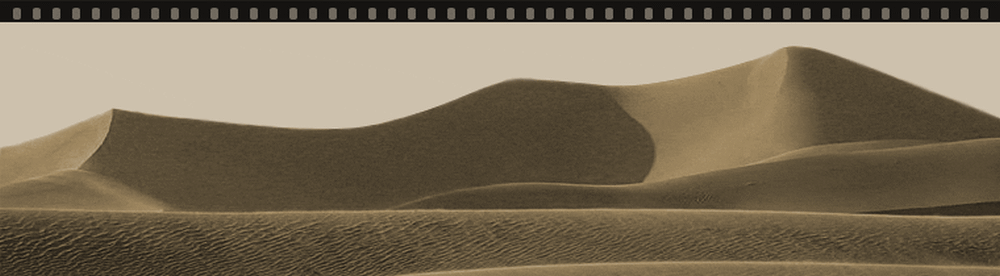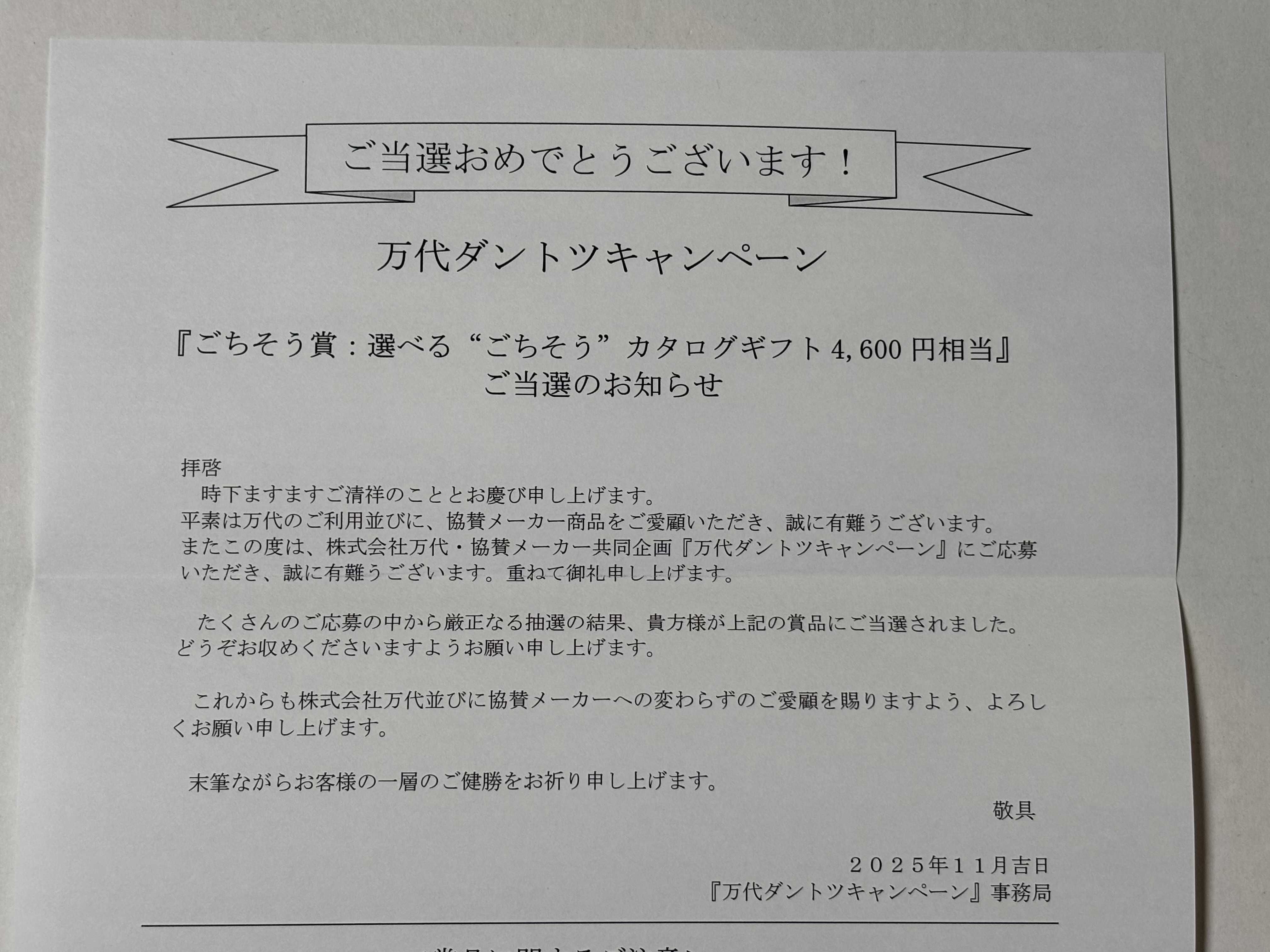2007年01月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
「続けられる」→「満員になる」→「前売りで完売」→「毎週開催から毎週開催へ」→ ?
私がいま埼玉県飯能市で毎月開催している<有望若手応援寄席>の来場者は毎回50~70人くらいです。 しかし、いまの会場は広いので「満員」になったことがありません。 私が地域寄席を開催していて、現時点で描いている夢は下記のようなささいなことです。まず「続けていくこと」です。そうしなければ、地域の人たちに知られていきません。 ↓次は「いつも満員になること」です。累積赤字の金額が増える一方だと続けられなくなります。 ↓その次は「満員につき入場できないお客が出てくる」ことです。さらに前売りの段階で売切になれば「値上げ」も可能になります。 ↓その次は「開催の頻度が増える」ことです。「3ヶ月に一度」や「隔月開催」が「毎月開催」になります。「毎月開催だった地域寄席」は「週一開催」も不可能ではなくなります。 私も、現時点では「有望若手応援寄席」が、現在の「毎月開催」から「毎週開催」になることを目指しています。そうなれば「有望若手応援寄席・飯能」とか「有望若手応援寄席・入間」「有望若手応援寄席・日高」「有望若手応援寄席・所沢」くらいはやってみたいですね。
2007.01.28
コメント(0)
-
1月21日は、私が7年前から主催している<有望若手応援寄席>の第74回目がありました。出演者は古今亭菊之丞さん。飯能独演会としては16回目です。
出し物は「棒たら」と「子別れの序」の二席。来場者はスタッフも含めて計64人でした。 会場の「一丁目倶楽部」は、飯能駅徒歩2分の久下稲荷神社の境内にある木造の新しくて大きな建物ですが、地域の町内会の集会場です。 駅からの距離、わかりやすさ、雰囲気、面積、設備、予約システム、使用料など、どれも地域寄席の会場としては申し分ありません。 しかし、たった一つだけ大きな(?)な欠点があります。 それは、隣が消防署だということです。つまり、消防車や救急車が出動するときは、サイレンの音がまともに聞こえてくるのです。 今回(1/21)も中入りを挟んで、2度、救急車のサイレンが聞こえてしまいました。 有望若手応援寄席は、会場が駅から近くて便利がいいため、毎回、遠方からの来られるお客さんが少なくないのです。 そこで、毎回、冒頭の主催者挨拶では「初めての方に予めお知らせしておきますが、隣が消防署ですので・・・・」と言うことにしています。 それでも、実は、まだ、地元以外のお客さんには隠していることがあります。 それは、北隣は消防署ですが、西隣は救急病院なのです。しかも、飯能市内では一番大きい救急病院なのです。 他にも、小さい(?)ことですが、みなさんが、たぶん驚くような欠点が有るのですが、それはまたの機会に・・・・・・<お知らせ> 次回の有望若手応援寄席は、2月18日(日)柳家三三さんの独演会です。いつも、たっぷり3席やって頂けます。
2007.01.23
コメント(0)
-
「地域寄席」を定義づける「7つの項目」・その2<出演者><会場><来場者><入場料><開催回数>
今回は「地域寄席を定義する7つのチェックポイント」の5つについて書いてみました。<出演者>・4団体のいずれかに所属しているプロの本物の落語家が出演している落語会でなければ地域寄席とは言いません。・つまり、素人だけの落語会は、地域の人たちによって開催されていても地域寄席とは言いません。・主な出演者が素人であっても、一人でもプロの噺家が出演していれば、それは地域寄席と言えます。<会場>・地域の集会場や事業所内の施設、お寺、神社、個人宅などで開催される落語会が地域寄席です。・市民会館大ホールや、ホテルの宴会場で開催される落語会は、主催者が一般の個人であっても、それを地域寄席とは言いません。・学校寄席も地域寄席とは違います。<来場者>・会場の周辺に住んでいる人たちが主なお客さんです。・情報誌やインターネットを見て遠方から聴きに来る人のほうが多くても、地域の人も来ている落語会であれば、それは地域寄席です。<入場料>・無料でも有料でもどちらでもOKです。・ただし、高額な入場料を取る落語会は地域寄席とは言えません。 (私見ですが、3000円以上は対象外ではないでしょうか・・・・)<開催回数>・連続して開催されているのが地域寄席です。・結果的に短期間しか続かなかったとしても、「長く開催していこう」という意図の下で開催されている落語会なら、それは地域寄席です。・当初から「1回こっきり」「単発開催」であるなら、それは地域寄席とは言いません。・地域の人たちから「定着しているね」「楽しみにしているよ」と言われなければ地域寄席ではない、という厳しい意見の人もいます。(私です)
2007.01.19
コメント(0)
-
「地域寄席」を定義づける「7つの項目」・その1<主催者><目的>
「地域寄席って何?」 これは必ず質問されることです。 「そもそも地域寄席とは・・・・」と、その定義の説明から始まる話はどうも理屈っぽくなっていけません。 でも、必要不可欠な話題なので、当ブログもやはりその定義から入ります。 定義づけるときに重要なのは、その<項目>です。 私は、地域寄席の定義に必要な項目は、<主催者><目的><出演者><会場><来場者><入場料><開催回数>の7つだと考えています。 これを「地域寄席を定義する7つのチェックポイント」と言います(ウソです)<主催者>・落語好きの一般人が主催している落語会に限定されます。・事業所(企業・病院・福祉施設)が主催であっても、地域の人が自由に入場できるのであれば、それは地域寄席と言えます。・噺家当人やその家族、プロの興業会社などが主催している落語会は、少人数の開催でも地域寄席とは言いません。<目的>・「自分の好きな噺家を呼びたい」「地域の人に落語と噺家を知って欲しい」ということが主な目的である落語会に限定されます。・主催者だけの利益(入場料で儲けたい)や、自己PR(商売・選挙)のために開催されている落語会は地域寄席とは言えません。・飲食店の経営者が、自分の店で開催しても「落語だけを聞く会」であれば地域寄席ですが、売り上げ増のために飲食を伴うことを求めたら、それは地域寄席ではありません。・お寺や神社が檀家や氏子のために開催する落語会は、「自分(住職・神主)の利益のため」とも言えますが、地域の人が自由に入場できる落語会であれば、それは地域寄席です。・「檀家だけ」「氏子だけ」と限定されていれば、それは「宗教団体による落語会」であって、地域寄席ではありません。 残りの5つは次回にします。
2007.01.18
コメント(2)
-
もうGoogle検索で 地域寄席研究所 が表示されるようになりました。
このBlog「地域寄席研究所」を開設した直後にGoogleで 地域寄席研究所 を検索しても、まだ当Blogは表示されませんでした。 ところが、さっき(1/17/19:10)“地域寄席研究所”でGoogle検索してみたら、みごと、私の個人サイトと当Blogの2件だけが表示されました。 つまり、ここからインターネット上での「地域寄席研究所」の歩みが始まったわけです。 ちなみに“地域寄席サミット”で検索すると12件表示されました。 当然、まだまだ<地域寄席サミット>のほうが、言葉としては広く認知されています。 ちなみに“地域寄席”で検索すると857件表示されますが、当Blogは34番目に表示されていました。 1年後に、それぞれの言葉の「検索結果の件数」が、どのように増えているかがいまから楽しみです。(もちろん、それまでは当Blogは続けます)
2007.01.17
コメント(4)
-
当Blog「地域寄席研究所」のカテゴリーとして、現時点では下記の21項目を考えています。
「地域寄席」って何? → 定義のようなことを書いていきます地域寄席のスタイル → 主催者や会場、運営の特徴を「続けられる」地域寄席 → 「続けられている」成功要因を「続かない」地域寄席 → 「続けられなかった」失敗要因を地域寄席の始め方 → 自分や友人の体験を踏まえて書きます地域寄席の続け方 → これも体験が主になります地域寄席の終わらせ方 → 一応いまから考えてはいます地域寄席を訪ねて → 首都圏に限られると思いますが・・・「世話人さん」インタビュー → 動機や経緯に興味があります噺家さんの意見 → 噺家さん地域寄席をどうみているのか?地域寄席に望むこと → お客さんだけではなく噺家さんの要望も若手噺家との接し方 → 鍛え方・育て方・煽て方・虐め方・・・・・・有望若手応援寄席のこと → 私が主催している地域寄席です世話人の本音 → これが書きたかったのです地域寄席の現状 → 告知、集客、赤字、マンネリ、内紛・・・・・・もっと「ご当地落語」を! → 「目黒のサンマ」のような地名入り落語の近未来 → 10年後か20後の予想(というか願望)を落語フアン用語の基礎知識 → 落語用語ではありません噺家になりたかった人々 → 実は私もそうでした・・・・・・・・噺家になりたい人へ → これから目指す人は居ませんか?この人を噺家に! → 有名人で誰に落語をやって欲しいか? ところで、みなさんへ確認のお願いです。私のパソコン画面では「カテゴリーの一覧表」が表示されるときと、表示されないときがあります。みなさんには、この「カテゴリーの一覧表」が表示されているのでしょうか?
2007.01.16
コメント(2)
-
きょう(2007/01/15)は「地域寄席研究所」というサイトが日本で初めて開設された記念すべき(?)日です。
Googleで “地域寄席研究所” を検索してみて下さい。 現時点では、私の個人サイトしか表示されません。(もちろん、当Blogもまだ表示されません) 私は、埼玉県飯能市で〈有望若手応援寄席・飯能〉という地域寄席を2000年10月から毎月主催してきました。「地域寄席は始めるのは簡単だが続けるのが難しい」と言われていますが、何とか現在も続いています。たぶん、これからも続けられると思います(自信ありませんが・・・・・・) 最近は、新聞や雑誌で〈地域寄席〉が取り上げられることも増えてきました。しかし、落語家を主人公にした映画やテレビドラマも続々と製作されていますが、〈地域寄席〉を舞台にしたものはまだのようです。(そのうち作られるかもしれませんね・・・・・) 考えてみれば、〈地域寄席〉というのは不思議な存在ですね。 いや、〈落語という世界〉そのものが不思議で笑っちゃうくらい自由な存在なのでしょう。 上野、浅草、新宿、池袋のような、席亭と言われるプロ興行主が経営する〈定席〉という、昔からの伝統を引き継いでいる寄席もあれば、落語家自身が興業主になることが多い〈ホール落語〉も全盛を極めています。 ここまでは、他の〈歌舞音曲〉の世界の興業形態と同様です。 しかし、〈地域寄席〉というのは、興業の世界とは無縁の素人が、勝手に芸人さんと交渉して、開催日と会場とギャラを決め、入場料も自由に設定して、興行してしまうのです。(しかも、大部分は赤字を続けながら) お客さんも、「通」の人は、定席の寄席や、ホール落語と地域寄席の違いを判ったうえで、それぞれの会場に聞きに行っています。 私自身は、自分で〈地域寄席〉を主催するようになってからは、定席の寄席やホール落語よりも、〈地域寄席〉そのもののほうに興味がいくようになりました。 そこで、ちょっと、〈地域寄席〉についてじっくり考えを巡らせてみたくなって、このBlogを開設して、思い付くことを書き続けていくことにしました。 いつまで、どの程度のレベルまで続けられるか判りませんが、とりあえず1年は続けますので宜しくお願いします。
2007.01.15
コメント(2)
全7件 (7件中 1-7件目)
1