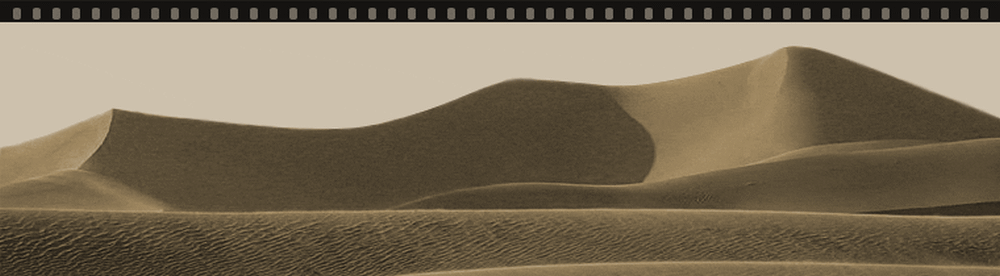2008年06月の記事
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-
今夜は、奥さんと「東西若手落語家コンペティション2008」第2回に行ってきました。
会場は第1回目と同じ内幸町ホール。今回も完売で満員。お客さん全員が審査員なので入り口で「投票用紙」を渡されます。審査と投票のルールについては、第1回目の書き込み(4/21)に書いてありますので、そちらをお読み下さい。2008年度・第2回の出演者と、その演目は下記の通りです。 立川志らら 宮戸川 三遊亭司 七段目 林家笑丸 余興屋(新作) 古今亭菊六 やかん 桂よね吉 七段目コンテストなので、普段の落語会では絶対に無い「同じ演目」が重なりました。私も初めての体験ですが、比較ができるので「さっき聴いた話」でも飽きることは有りませんでした。「同じネタ」の後で演じるほうが不利だと思うのですが、最後に登場したよね吉さんは「力量の違い」を見せつけてくれました。これだけの噺家さんも「出場資格ギリギリ」とはいえ「入門13年未満」の若手なのです。きょうの優勝者はその桂よね吉。今回も私と奥さんの投票した噺家は同じで、その人が優勝しました。第3回目(8/26)も前売り券を買う予定です。
2008.06.17
コメント(0)
-

昨夜(6・15)は柳家三三独演会の第30回でした。
まだ足が完治しないので会場準備のような「肉体労働」ができないのですが、幸いなことに、9月に予定している<ふるきゃら飯能公演実行委員会>のPRのために来た人たち(女性2名)が手伝ってくれました。きょうの来場者は121名。演目は「たらちね」「猫の災難」(中入り)「万両婿」でした。暑くて会場の窓を解放していたので、隣の家の飼い犬の吠えた声が聞こえてしまったのですが、三三さんはタイミングよく「犬だって吠えてるじゃねか」と話の中に取り込んで笑いを取っていました。「万両婿」は、有望若手応援寄席の第1回(したがって三三飯能独演会第1回)の時にも演ったネタなので実に8年ぶりの演目でした。いつもの中華料理店での打ち上げでは「万両婿(小間物屋政談)」のことをきっかけに「講談調の落語と講談との違い」について話しが弾みました。「講談のほうが落語よりも演者の自由度が高い」という指摘には納得がいきました。だからこそ私は「素人芸では落語よりも講談のほうが様になる」のではないかと感じていたのでしょう。
2008.06.16
コメント(1)
-
「地域寄席は儲けていいのか?」それとも「儲けてはいけないのか?」
1年ほど前からようやく<有望若手応援寄席>は、ほぼ毎回黒字になるようになりました。もちろんその内訳は下記のようなものです。 噺家さんへの出演料 + 会場費 ≦ 当日の売り上げポスターやチラシの制作費、印刷代、それらの配布や掲示の手間、備品代(提灯・幟旗・座布団・毛氈など)は含んでいません。スタートさせた当初は「最初から黒字になる」という甘い予想を立てていたのですが、現実には「黒字になる」まで7年(通算で80回以上)もかかってしまいました。その最大の原因は「定期券制や回数券制によって入場料を大幅に下げた」ことでしょう。しかし、私は「地域寄席」の課題の一つは「赤字が続くことは避けたいがそれでもできるだけ低料金で開催する」ことだと思っています。例えば、毎回達成したい1回の入場料総計が10万円だとしたら「2000円で50人の入場者」よりも「1000円にして100人入場してくれる」ほうが地域イベントとしては嬉しいのです。もちろん可能であれば「500円にして200人入場してくれる」ようになることを望んでいます。最高で50万円まで膨らんだ累積赤字も、現時点での予測では一掃できる日はそんなに遠くないでしょう。黒字が溜まって、いわゆる「儲かる」ようになったら、どうするか?この件に関しては、有望若手応援寄席をスタートさせる時に、世話人同士で方針を決めていました。 1.噺家さんの出演料を上げる 2.出演者を増やす(弟子を取ったら連れてきてもらう) 3.真打昇進や襲名披露や寿の時にお祝いを奮発する 4.着物を贈呈する(地域には呉服屋さんがありますので)しかし、このような「心積もり」は、世話人の「胸の中」に秘めているだけですから誰も知りません。(出演してくれる噺家さんには話しています)こんなことはお客さんは知りませんから、「大勢の入場者」を見て「ずいぶん儲かってるだろうなぁ」と思う人もいるでしょう。<有望若手応援寄席>に限らず、地域寄席ではお客さんの中に、冗談で世話人に対して「儲かるでしょう!?」と言う人が必ずいるものですが、その言葉を言われる度に「カチン!!」とくる世話人は多いでしょう。「地域寄席で儲けていいのか?いけないのか?」という問題は、地域寄席では永遠に続く「悩み」ではないでしょうか。
2008.06.14
コメント(2)
-
その地域の在住者か在勤者の主催によることが「地域寄席たる最大の条件」だと思います。
個人(グループ)が趣味で運営する落語会であっても、会場がその人たちが住んでいる地元ではないと、それは地域寄席とは言えないと思います。例えば、私や同じ世話人のKさんは、<有望若手応援寄席・飯能>をそれぞれの自宅から徒歩5分の所に在る地元の会場で開催しているから<地域寄席>と言えるのです。もしも、同じ出演者の顔ぶれ、同額の出演料と入場料、同じような規模であっても、隣接の入間市や日高市、狭山市、東京都青梅市で開催したら、それは、その地域での<地域寄席>とは言えないのではないでしょうか?第一、自分が住んでもいない地域で、赤字覚悟で落語会を開く人はいないだろうと思います。世話人が赤字を負担しながら地域寄席を続けているのは、会場が自分たちが住んでいる地元だからです。自分たちの友人、知人、仕事関係者だけでなく、見ず知らずの人であっても、同じ地域に住んでいる人が来場してくれるのが嬉しいからこそ、赤字でも続けていられるのです。(もちろん、続けているからにはいつかは累積赤字を一掃しようと思ってはいますが・・・・)私たちが住んでいる埼玉県飯能市は面積が広いうえに、山林が多くしかも東西に細長いので、東部に偏っている市の中心部から西端の山間部までは車で30分~40分はかかります。例えば、同じ飯能市内でも名栗地区や吾野地区で、私やKさんが<有望若手応援寄席・名栗>とか<有望若手応援寄席・吾野>を開催しても、その地域の人たちからは「地元の人が主催する地域寄席」とは認識されないのではないかと思います。もしも、私やKさんが、この地区で<有望若手応援寄席>を定期的に開催したら、たぶん地域の人たちの中には「地域寄席と言っているが結局は自分たちが儲けるためではないか」と思う人も出てくるでしょう。だから、私たちはPRチラシやwebサイトで「吾野や名栗で地域寄席を主催しませんか? 開催までは応援しますから」と呼びかけています。(検討した人はいましたが開催には至りませんでした)
2008.06.13
コメント(0)
-
地域寄席主催者の動機や目的は様々です
地域寄席の主催者としては、最も多い(と思われる)<個人・家族・グループ>も、その動機や目的に焦点を当てると下記のように分類されることがわかります。 A・落語そのものが好きだから主催している人たち B・特定の落語家が好きだから主催している人たち C・イベント企画が好きでその形態の一つとして主催している人たち D・その会場を盛り立てる手段の一つとして主催している人たち私自身はBでありCでもあります。私がAではないと言い切れるのは、落語と同じくらい他の舞台演芸(漫才、コント)や演劇、朗読、コンサートも大好きだからです。事実、松元ヒロ、太田寸世里や無名のシンガーソングライターのライブを主催してきましたが、地域寄席が一番「楽だった」から続いているのだと自覚しています。Dでもないと言い切れるのは、いま使用している会場(地域の自治会の集会場)は、現時点で「面積、使いやすさ、駅からの距離、使用料」などを総合して最も良い会場だからであって、その会場を「盛り立てなけれならない」からではありません。他にもっと良い会場ができればすぐにでもそちらに変わるつもりです。Bの人たちは、他の噺家さんの落語会を主催しようとは思わないでしょう。仮に来場者から「他の噺家さんも呼んでくれ!」とリクエストされても応じないでしょう。「あなたがお呼びになって主催したらどうでしょうか?」と切り返すかもしれません。実は、私はそのように対応することもあります。地域寄席で意外と多いのはDでしょう。飲食店や大きなお屋敷、会社の施設で開催される地域寄席の主催者にはこのケースが多いようです。飯能市には、落語会の会場として趣の有る蔵造りの貸し会場や店舗が多いのですが、そのオーナーに私は「地域寄席を主催しませんか?」と提案し続けています。最近、自社ビルの中にあるサロン(会議室)で毎月定期的にクラシックコンサートを開催している新聞専売店の社長に「新たな地域寄席の開催」を打診してみたら、意欲を示して、8月にとりあえずテスト的に開催することになりました。(出演者は春風亭一之輔さんの予定です)私としては、「自分の金銭的な利益」のために地域寄席を主催しているわけではないので、同じ飯能市内に、他にも地域寄席が増えて欲しいと本心から思っています。とりあえず、「毎月1回開催している地域寄席」が4ヶ所あったら、地元の人たちにとっては「毎週1回は地域寄席が開催されている」という状況になります。それが、私の当面の目標かもしれません。
2008.06.11
コメント(0)
-
やっぱり地域寄席は「主催者に興味が向かう」のではないでしょうか?
いままで、地域寄席を考えるうで欠かせない7つの項目(主催者・目的・出演者・会場・来場者・入場料・開催回数)を提示してみましたが、その<考える順番>も重要です。地域寄席を考える時に、最初に思い浮かぶ項目は、やはり<主催者>ではないでしょうか?それは、私自身が地域寄席を主催し、他の地域寄席にも興味が有るからなのかもしれません。私は地域寄席に行くと次のようなことに興味が湧いていきます。「どんなグループがやっているのか?」「その中では誰がキーマンになっているのか?」「その人たちの家族はどのように関わっているのか?」「友人知人、ご近所、町内会などは関わっているのか?」「自治体や公共施設の職員は関わっているのか?」・・・・実際にその地域寄席を聴くために出かける場合は「どこで開催しているのか?」と「いつ開催するのか?」ということも当然重要ですが、「地域寄席とは何か?」ということを考えるときには、最初に思い浮かぶのは「誰が(どういう人たちが主催しているのか?)という項目ではないでしょうか?会場が市民会館だったり公民館だったりする地域寄席は多いのですが、だからと言って、その全てが自治体の<支援>とか<監督>や<制約>を受けている訳ではありません。地域寄席の主催者としては、最も多い(と思われる)<個人・家族・グループ>も、その動機や目的に焦点を当てると下記のように分類されることがわかります。 A・落語そのものが好きだから主催している人たち B・特定の落語家が好きだから主催している人たち C・イベント企画が好きでその一つとして主催している人たち D・その会場を盛り立てる手段の一つとして主催している人たち私自身はBでありCでもあります。
2008.06.11
コメント(0)
-
「人様からお金を戴いている時点でそれはもう立派なビジネス」と言う人も居るようですが・・・・
2008.06.08 10:24:16に書き込まれたトーリ・スガリーさんのコメントへの返信です。>私個人的には人様からお金を戴いている時点でもう立派なビジネスなんですよ。●上記が「お金を頂くからにはその金額に値するだけの内容でなければならない」という意味で「ビジネス」と書かれているのであれば同感です。●もし、単純に「お金を頂く=もうそれはビジネスだ」というのであれば、その個人的な認識は正しくないと思います。(あくまでもこれは私の見解ですが・・・・)例えば、有望若手応援寄席が会場にしている一丁目倶楽部は地域の自治会の会館ですが、貸し出す部屋の使用料を徴収していて、年間かなりの金額になりますし、自治会の会計では「事業収入」という項目にはなっていますが、自治会の役員も、自治会費を納めている人たちも、誰も「会場を貸して使用料を戴くこと」を自治会のビジネスとは思っていません。>しかもいつかは黒字にしたいと考えていらっしゃる。●はい。「累積赤字」は解消したいと思っています。しかし、その赤字は「第三者の領収書」で計上できるだけの金額に限られています。もし、私たち世話人の「お客さんとして入場する人には想像もつかない膨大な時間の人件費」まで計上したら、正確な意味での黒字には絶対にならないでしょう。>もし小久保様が本当に地域寄席を趣味道楽でおやりになっているのなら、ご自分の好きなようにおやりになりたいのなら木戸銭無料にして●私が趣味道楽で落語を演って、それをお客さんに聴いてもらおうという場合は、おっしゃる通り木戸銭無料にします。しかし、「有望若手応援寄席飯能」はプロの噺家さんに出演して貰っているのですから、出演料をお支払いするために入場料を頂いています。>ボランティアとして運営するのが理想かと。●はい。おっしゃる通り「運営」は世話人たちのボランティアでやっています。>ふつう自分の趣味道楽に他人のお金を戴きますか?●趣味道楽で芝居やコンサートをやっている人たちも、入場料は頂いていると思うのですが・・・・趣味で陶芸を絵画などをやっている人が作品を売ることはよくあることですが、税法上も「雑収入」であって、誰もそれをビジネス・事業とは言いません。趣味道楽で他人からお金を頂いています。>他人からお金を戴くのなら地域寄席の運営をビジネス・事業として考えて下さい。●上記が「お金を戴いているからにはお客さんから苦情の無いように地域寄席を運営しなければならない」という意味であれば同感です。●しかし、「お金を頂くからにはビジネス・事業にしなければならない」というのが私には理解できません。>かつてビジネス書を書かれていたという小久保様は●すみません、いまも仕事はまだ現役なのですが・・・>そのくらいはご存知かとおもっていましたが・・・●「他人からお金を頂くことをすべてビジネスだ」という認識は私にはありません。●「お金を頂くからにはビジネス・事業として考えろ」と他人に意見する人は、私の経験値の範囲では「自分でビジネス・事業をしたことがない人」だと思うのですが・・・・ハズレたでしょうか?
2008.06.09
コメント(0)
-
個人ブログは「本音」じゃないと面白くない。プロはお客の「独断と偏見による評価」は気にしないでしょう。
2008.06.07 15:48:49に書き込まれた<ピーチ師匠>さんのコメントへの返信です。>ただ、小久保さんの表現で気になるところがあるので、意見させてください。●ありがとうございます。今後の参考になりますので、ご意見やご指摘は大いに歓迎しています。 >不特定多数の人が見ることが出来るとこで、「期待ハズレ」や「次回のチケットは買わなかった」などの表現は、いかがなものかと思いました。せいぜい「自分の趣味とは会わなかった」程度の表現の方が良いと思いますが、いかがでしょうか?●<インターネットの書込>に対してピーチ師匠さんのように言われる方は少なくありませんが、私はそうは思わないのです。「自分の趣味とは会わなかった程度の表現」で終わったら、書く方は徒労感しか残りませんし、読んだ方も参考にはならないと思っています。「プロ」は、お客からどのような評価をされても耐えられるものです。●私はインターネット上でも「本名と住所」を明かして書き込んでいるのは、自分が本気で書いているということの証であり、自分が書き込んだ内容に責任を持つ覚悟が有るという宣言でもあるからです。私以外でも「インターネットで本名(もしくは身分を明かして)」書かれている方は、「自分の本音の書き込み」に責任を持つ覚悟が有るからなのです。>これから落語を見ようとしてる人や、落語に興味を持ちはじめて、次はどんな人を見ようと考えてる人も見る可能性があるのですから。●はい。そういう人のためにも「自分の趣味とは会わなかった程度の表現」で終わらせたくないと思っています。>志ん生も圓生も落語。三平も志ん朝も談志も落語。川柳も円丈も落語。談春も白鳥も、みんな落語なんですから。●はい、そうだと私も思っています。(そういうことを否定しているような書き込みが私のブログの中に有るのでしょうか?・・・・)個人のブログは「建前」ではなく「本音」を書かなければ意味がないと思っていますが、だからと言って、私がブログで書いていることのすべてが「本音」であるとは限りません。だから、このブログでも、ピーチ師匠が読まれていない(気づかれていない)部分では「自分の趣味とは会わなかった程度の表現」はけっこう有ると思います。
2008.06.08
コメント(0)
-
「優等生の落語」? 「数学の方程式を解くように落語を語る噺家さん」? 「地域寄席の主催者の役目」?
2008.06.07 13:09:56に書き込まれた<トーリ・スガリーさん>のコメントへの反応です。>というか、小久保さんをはじめ今の地域寄席を運営する人が優等生の落語しか聴いていないのでしょうね。●「優等生の落語」の意味が明確にされていませんが、たぶん「既に評価が定まっている古典落語しかやらない」とか「師匠に教わった通りのことをやるだけ」とか「独創性が無い」という意味なのでしょうか?私としては「新作しかやらない人」「はちゃめちゃな人(誰とはいいませんが)」も聴いているのですが・・・・●私としては別に落語協会の噺家さんだけでなく、落語芸術協会や立川流、円楽党、上方落語、素人落語など幅広く聴いているつもりなのですが・・・・>言葉が悪いかもしれませんが、落語協会のは大学進学率100%の公立高校の、芸協は中退率50%の工業高校の落語の落語といえるかもしれない。●面白い喩えですが、「日本の大学のお粗末さ」や「日本の学校歴偏重社会の馬鹿らしさ」を痛感してきた私としては、面白くても「使いたくない喩え」です。>優等生の落語が好きな小久保さんにはこれは理解出来ないかもですね。●「優等生の落語が好きな小久保さん」とか「小久保さんにはこれは理解出来ないかもですね」と断定できる根拠が私にはわかりません。>例えば寿輔師の落語なんかはねぇ。●「落語鑑賞」のすべてを記録しているわけではないので年月日は正確ではありませんが、たぶん、無いと思います。>私なんかにしてみれば三三師や柳朝師のようなまるで数学の方程式を解くように落語を語る噺家さんに魅力は感じません。●それは個人の好き嫌いですから自由です。私が主催している有望若手応援寄席に出演してもらっている4人の噺家さんについても、私の周囲にも「あの噺家さんはあまり好きじゃない」という人はいますので・・・>そういうのだけを地域のみなさんに落語家として見せるより、●個人が主催している「地域寄席」は自分の好きな噺家さんを主体にしているからこそ続くのです。「自分の好きな噺家さんを地域の人たちにも知って欲しいから地域寄席を続けている」のです。>香具師的に落語にもこんなのもあるんだよ、こんなのもあるんだよと、いろんな落語を見せるのが地域寄席主催者の役目であってほしいと思いますね。●そういう地域寄席もあるでしょうが、それが「地域寄席の主催者の役目」とは思っていません。私自身の狭い見聞の範囲では「毎回違う噺家さんを出演させることにしている地域寄席は続けない」のが多いように思えるのですが・・・・★何度も言わせていただきますが、「地域寄席の主催者」にとっては「続ける」ことが最大の課題です。「好きな噺家さんをよぶ」のも「赤字を解消できるくらいの入場料は頂く」のもすべて「続ける」ための重要な要因なのです。
2008.06.08
コメント(0)
-
普段はまったくコメントが無いのに、昨日の書込には珍しくコメントがありましたので、それへの「反応」を書くことにしました。
2008.06.07 10:33:20に書き込まれた<トーリ・スガリーさん>のコメントへの反応です。 >昔昔亭桃太郎さんも私も奥さんも初めてだったのですが期待ハズレ。なにがどう期待はずれだったのか書かないから、ちっともその失望感がこっちにつたわってこないのだけれど。●済みません。「その失望感までも伝えよう」とは思わなかったのです。一落語ファンとしてこのブログを読むと寄席運営者として顔しか見えず、落語ファンとしての顔が全く見えないんです。●それは鋭い指摘だと思います。そもそも、このブログを開設した当初も、現在も「地域寄席運営者」として考えたこと、感じたことを書こうと思っているのであって、「落語ファンとしての顔」を見せようとは考えていないのです。もし落語ファンを自認するなら、●落語ファンとしてこのブログを開設したわけではありませんので、「落語ファンを自認したこと」は無いと思います。何しろ「20代前半から40代後半までの30年間も「落語が嫌い」という時期があったのです。もうちょっとまともな感想を書いてほしい。●別に開き直るわけではありませんが、「感想文を書く」というのは、子供の頃から現在まで「嫌いなことの一つ」なのです。それと地域寄席運営者に対しての要望を一つ。羽村のゆとろぎ寄席もそうだけど、よぶ噺家さんが偏り過ぎ。●市民会館や公民館などが主催者になっている地域寄席は、「出演する噺家さんが偏り過ぎる」のは良くないと思いますが、個人が自分の趣味・道楽として主催している地域寄席は「主催者の好き嫌いで偏っていてもそれでいい」と思っています。むしろ、「主催者が好きな噺家さんだけに出演してもらっている地域寄席」のほうが長続きしています。もっと時間があるかぎり色々な落語会、二つ目さんの勉強会、早朝・深夜寄席に足を運んでほしい。●これはおっしゃる通りです。できるだけ「まだ聴いたことのない二つ目さんの落語を聴きにいこう」と思っています。たとえば芸協の真打さん、二つ目さんにも才能がある人いっぱいいる。ただあなた方が知らないだけ。●これもおっしゃる通りです。しかし、地域寄席は趣味でやっているのであって、興業会社のようにビジネスでやっているのではないのですから「二つ目全員の話を聴いてから出演者を選ばなければならない」とは思っていません。なぜなら「あの二つ目さんもいいなぁ」ということが判っていても、そういう噺家さんの全員を自分の地域寄席に出演してもらうわけにはいかないからです。地域寄席には地域の人たちに本物の落語に親しんでもらうという目的もあるけれど、噺家さん本人の勉強、修業という目的もあると思いますよ。●これもおっしゃる通りです。私の目的は当初も現在もこれからも後者のほうです。「地域の人たちに本物の落語に親しんでもらう」という目的を建前にするのは市民会館や公民館が主催する落語会だと思っています。地域寄席の主催者は「呼べる噺家さんが限られている」のです。地域の人が求める有名な噺家さんは集客力と支払う出演料との兼ね合いで呼べないのです。権太楼師やさん喬師、一朝師のところの方がダメというわけではけっしてないけれど。なんでそこに偏るのか。わからない。●正確に表現すると「偏っている」のではなく、「限られた噺家さんだけしか呼べない」のが現実なのです。どうか、個人が赤字負担で運営している地域寄席と、市民会館などが収益事業として開催している落語会とを一緒にしないで下さい。雲助一門、鯉昇一門にも目を向けて下さい。●はい。そうします。
2008.06.07
コメント(2)
-
きょう(6・6)は、「昔昔亭桃太郎・立川藤志楼(高田文夫)二人会」に奥さんと行ってきました。
会場は、西武池袋線練馬駅前にある練馬文化センター小ホール。前にも書きましたが、ここは奥さんの職場の<縄張り>の中にあるので、ここで開催される落語会はけっこう聴きに来ています。きょうの前売り券を買った時点では、まさか足が悪くなるとは思っても見なかったのですが、きょうも松葉杖だったのでかなり疲れました。 <きょうの演目> 春風亭昇々「雑俳」 昔々亭慎太郎「壺算」 立川藤志楼 中入り 高田文夫と昔昔亭桃太郎のトーク 昔昔亭桃太郎「春雨宿」きょうの出演者の中では立川藤志楼がマクラも話も一番。場内も爆笑の連続でした。直前に話した二人について、冗談めかしながら「昔々亭一門は人材不足だね・・」とか「きょうはシロウト演芸会かよ!」と言って、場内の笑いを取りましたが、私としては「本音」として受け取りました。昔昔亭桃太郎さんも私も奥さんも初めてだったのですが期待ハズレ。場内では、次回の「笑福亭鶴瓶・昔昔亭桃太郎二人会」の前売り券を発売していましたが、奥さんは「面白かったら次回の前売りを買っておこう」と言っていましたが、結局は買いませんでした。
2008.06.06
コメント(5)
-
きょう(6・04)は、「三三、三十三才、三夜、三席、三宅坂」の三日目(最終日)に奥さんと行ってきました。
まだ遠出の外出には松葉杖が必要です。有楽町線永田町駅は、改札口を出てから、地上に出るまでが長く、会場の国立演芸場までえっちらほっちらと30分もかかってしまいました。(かといってタクシーに乗れる場所ではありません)今月の有望若手応援寄席飯能は三三独演会なので、チラシを会場の入り口で配布させてもらおうと、開場前に主催者(ショーキャンプ)の方に打診したら、「まだ間に合うから挟み込みしてもいいですよ」と言ってくれたので、すぐに、きょうのプログラムへの挟み込み作業に取りかかりました。しかも、その女性スタッフの方も作業を手伝ってくれたのです。「きょうの主な演目」は予めプログラムに時刻まで印刷されていました。 「だくだく」 「三味線膝栗毛」 中入り 「笠碁」三三さんも開口一番で「笠碁は50分かけてみっちりやりますから・・・」と言っていたのですが、中入り後の幕が開いて、メクリに下がっていた出演者名は「立川談春」。私は一瞬(三三さんの冗談だろう!)と思ったのですが、談春さん本人が出囃子とともに現れたときは、場内は大拍手。演目は「三人旅」でした。きょうの談春さんの話によると「三三という名前で三十三才になるなら、三席の独演会を三日間やれば面白いのに」と三三さんに提案したのでは談春さんだったのです。その「流れ」でゲスト出演ということになったとのことでした。三三さんが談春さんにゲスト出演を依頼したときに「絶対、当日まで誰にも言わないでね」と釘を刺していたそうです。当然『東京かわら版』6月号の「演芸会情報欄」<掲載日別出演者索引>の「立川談春欄」にも載っていませんでした。会場でばったり会った私の知人が「初日も聴きに来た」というので、終演後すぐに「初日も談春さんはゲストで出演したの?」と訊きましたが「出なかった」という答えでした。三三さんは、ゲストを秘密にした理由を「当日のお客さんの驚く様子を見たかったから」と言っていましたが、本当に驚きましたよ!
2008.06.04
コメント(0)
-
Webサイトを全面的に変更してみました。
<HP有望若手応援寄席>を全面的に一新してみました。変えたのは主に下記の3点です。1.いままではwebサイト製作ソフトのDREAMWEAVERを使って自分のデザインで作成していましたが、無料で誰でも使えるオープンソースのポータルサイト作成ソフト<xoops>で作成することにしました。(だからURL変わりました)2.いままでの予約メールは、「管理人との個人メールとしてのヤリトリ」でしたが、来場したい人が自分で「予約登録」し、その予約数が自動的に表示されるようになりました。3.リンク集の編集が容易になったので、これからは「落語関連サイトのリンク」を充実させていく予定です。(現時点ではゼロですが・・・)このxoopsというポータルサイト作成ソフトを教えてくれたのは、もう5年も私のパソコン家庭教師をしてもらっているK君です。だから、まだ、私自身がこのxoopsの機能を知らないので、どのような便利なコト、面白いコトが出来るのかを判っていません。これから<落語関連サイト>の一つとして徐々に、充実させていきたいと思っています。
2008.06.01
コメント(0)
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-
-

- 楽天市場
- 楽天ブラックフライデーセール!
- (2025-11-22 01:03:03)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 「インスタグラビアの女王」似鳥沙也…
- (2025-11-22 00:30:05)
-
-
-

- 自分らしい生き方・お仕事
- ^-^◆ 嵐の後の光 …… について
- (2025-11-21 12:32:11)
-